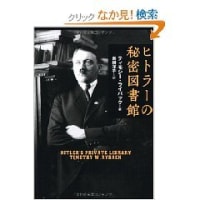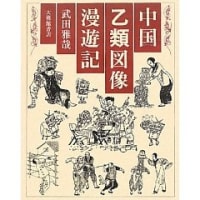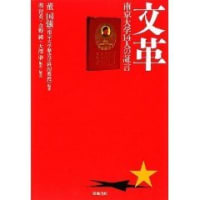白暗淵(しろわだ) 古井由吉 講談社
「群像」連載の十二の短編を集めたもの。前作「野川」と同様、古井の晩年の到達点を堪能できる。印象批評風に言えば、ベートーベンの後期ピアノソナタを聞いている感じ。晩年から振り返る過去。死を意識した人間の研ぎ澄まされた感覚を言葉によって描き出そうとする。作品を通じて感得されるのは、62年前の東京大空襲の体験が核になっているということだ。意識と無意識、生と死のあわいでさまよう人間が次々登場する。それぞれが時間の流れの中で浮かんでは消えてゆく。
小説の基本であるドラマ性が敢えて水面下に放擲されているがゆえに、一切の解釈を拒絶する。そこに美があるのだ。小林秀雄が言った歴史の美の議論に通じるものがあると思う。高校の現代文の授業では扱えない気がする。だって解釈できないのだから。よってこの作品は、文学を教えることの限界をはっきり指摘したものと言えるだろう。