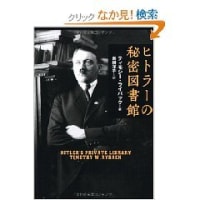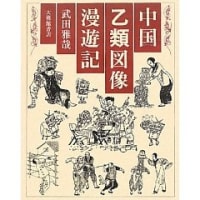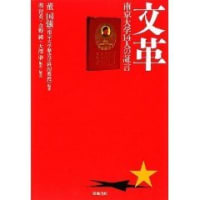1000ページを超す大部の小説は新撰組副長・土方歳三の物語である。タイトルの「ヒトごろし」は土方のことで、彼は自分のことを人殺しが好きで、人を殺しても罪の重さなど微塵も感じず、後悔もしない、化け物だと思っている。彼は人を斬りたいがために新撰組を作り、幕府の権力のもとに勤王の志士を斬りまくったという異色の新撰組物語である。司馬遼太郎の『燃えよ剣』や『新撰組血風録』とは無縁の世界が描かれており、新撰組フアンは衝撃を受けたのではないか。
土方が殺人に魅せられたのは、七歳の時、武家の妻が中間奴と不義密通を犯し、逐電の途中に夫の武士に惨殺される場面を見たことによる。切られた女の碧天に噴き上がる鮮血、これを甘美な死の景色として心に刻み込まれたと書いてある。刀で人を殺すという人倫にもとる衝動に取り憑かれたのだ。異様な人物設定である。この土方が新撰組結成前に、見廻り組の佐々木只三郎と会った時、佐々木は言う、「お前、人殺しが好きだな。人殺しという行ないは、どんな時も、何であろうとしてはいけねえことだろうよ。大罪だ。人を殺したら必ず罰せられるのだ。どんな形であれ罰せられるのだ。獄門になるか遠島になるか入牢するか、どんな形であっても罪は必ず償わねばならんのだ。どんなに乱れた世の中であっても、どんなに人心が狂うておっても、そこだけはきっちりしておかなくてはならんのだ。国の箍が緩んでも、そこだけは変らねえのだ。ただな、罰するのはお上だ。親方は幕府だ。人殺ししてえならそういう身分になるしかねえな」と。
これは国家権力というものをわかりやすく述べたもので、土方の殺人衝動は国家権力そのものに抑制されるべきもの、逆に権力側に立てば戦争などの名のもとに殺人が正当化されるといことだ。
でも、刀での切り合いが、戊辰戦争になると、大砲や鉄砲の戦闘に変わる。土方はこの戦いについて次のように言う、「これらの戦いはな、立ち合いもねえ。名乗りもしねえ。誰が誰を殺したのかもわからねえ。ただ大勢が一度に死ぬだけのもんだ。殺した方も人を殺したって気持ちは持てねえ。大砲だの鉄砲だの撃ったてだけだ。それで皆死ぬ。沢山死人がでた方が負けだ。兵隊はただの将棋の駒だよ。武勲も武功もねえ。全部が全部、成ることのねえ歩だよ」と。
近代戦が殺人のタブーを簡単に破ってしまうことを言い当てている。死の「無名化」というべきもので、第二次世界大戦のホロコースト、最近の民族浄化に繋がるものだ。人殺しは悪だが、それを倫理だけで抑制することはいささか困難であるということを土方を通して知らしめているのではないか。本編は以上のテーマを含みつつも小説としての面白さを存分に味わわせてくれる。近藤勇は出世にしか興味のない人間として、沖田総司はなぶり殺しが好きな変質狂として描き、ディストピア小説としての面目躍如たるものがある。芹沢鴨の暗殺、古高俊太郎の拷問、池田屋事件、伊東甲子太郎暗殺と時系列で展開される新撰組の事件が会話を中心に描かれる。それが血なまぐさいリアリティーを増幅して読者を京極ワールドに引きずり込む。久しぶりに面白い小説を読んだ。
土方が殺人に魅せられたのは、七歳の時、武家の妻が中間奴と不義密通を犯し、逐電の途中に夫の武士に惨殺される場面を見たことによる。切られた女の碧天に噴き上がる鮮血、これを甘美な死の景色として心に刻み込まれたと書いてある。刀で人を殺すという人倫にもとる衝動に取り憑かれたのだ。異様な人物設定である。この土方が新撰組結成前に、見廻り組の佐々木只三郎と会った時、佐々木は言う、「お前、人殺しが好きだな。人殺しという行ないは、どんな時も、何であろうとしてはいけねえことだろうよ。大罪だ。人を殺したら必ず罰せられるのだ。どんな形であれ罰せられるのだ。獄門になるか遠島になるか入牢するか、どんな形であっても罪は必ず償わねばならんのだ。どんなに乱れた世の中であっても、どんなに人心が狂うておっても、そこだけはきっちりしておかなくてはならんのだ。国の箍が緩んでも、そこだけは変らねえのだ。ただな、罰するのはお上だ。親方は幕府だ。人殺ししてえならそういう身分になるしかねえな」と。
これは国家権力というものをわかりやすく述べたもので、土方の殺人衝動は国家権力そのものに抑制されるべきもの、逆に権力側に立てば戦争などの名のもとに殺人が正当化されるといことだ。
でも、刀での切り合いが、戊辰戦争になると、大砲や鉄砲の戦闘に変わる。土方はこの戦いについて次のように言う、「これらの戦いはな、立ち合いもねえ。名乗りもしねえ。誰が誰を殺したのかもわからねえ。ただ大勢が一度に死ぬだけのもんだ。殺した方も人を殺したって気持ちは持てねえ。大砲だの鉄砲だの撃ったてだけだ。それで皆死ぬ。沢山死人がでた方が負けだ。兵隊はただの将棋の駒だよ。武勲も武功もねえ。全部が全部、成ることのねえ歩だよ」と。
近代戦が殺人のタブーを簡単に破ってしまうことを言い当てている。死の「無名化」というべきもので、第二次世界大戦のホロコースト、最近の民族浄化に繋がるものだ。人殺しは悪だが、それを倫理だけで抑制することはいささか困難であるということを土方を通して知らしめているのではないか。本編は以上のテーマを含みつつも小説としての面白さを存分に味わわせてくれる。近藤勇は出世にしか興味のない人間として、沖田総司はなぶり殺しが好きな変質狂として描き、ディストピア小説としての面目躍如たるものがある。芹沢鴨の暗殺、古高俊太郎の拷問、池田屋事件、伊東甲子太郎暗殺と時系列で展開される新撰組の事件が会話を中心に描かれる。それが血なまぐさいリアリティーを増幅して読者を京極ワールドに引きずり込む。久しぶりに面白い小説を読んだ。