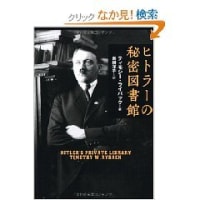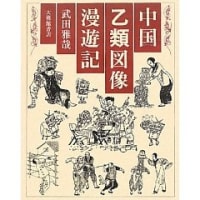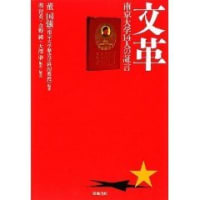文庫としては昭和42年以来63刷改版で、活字が大きく読みやすくなった。終戦(敗戦)記念日に合わせての発刊である。著者は昭和20年1月25日フイリッピンのミンドロ島南方山中で米軍の捕虜となり、終戦後帰還した。その間捕虜となった日本兵(終戦前の招集兵が多かった)の姿を冷徹に観察し批評しているが、その人間観察力に裏打ちされた記述は哲学者のレベルまで到達している。
まず、「捉まるまで」の項では、マラリアにかかりジャングルで置いてきぼりになり、藪の中で身を屈め、もし米兵に遭遇したら射つか、射たないかで思索が展開される。結局、若い米兵を目の前にして射たなかったのであるが、その理由をこう書いている、あの時私が敵を射つまいと思ったのは私が「神の声」を聞いたのであり、米兵が迫って、私がその声に従うことが出来るか出来ないか不明に立ち至った時、別の方面で銃声を起こらせ、米兵をその方へ立ち去らせたのは「神の摂理」ではなかったか、という観念であると。著者は東京のあるミッションスクールの中学生であった13歳の時、聖書の真理に打たれ神を信じたと書いている事を考えると、汝の敵を愛せというキリスト者の本分を実践したのかも知れない。しかし、私の感じでは、射つのが面倒くさかったのではないかと思う。敵を射ち殺す慙愧の念と射ち殺される無念とを秤にかけたら、射たれる方が楽だというのは大いにありうると思う。ことほど左様に33歳のインテリ補充兵の厭戦気分は小説全般に横溢している。
捕虜収容所で同胞の捕虜を見た時の印象を「私が彼等に会うのを欲しなかったということは考えられない。いかにも私は昭和初期に大人になったインテリの一人として、所謂大衆に対する嫌悪を隠そうとは思わないし、軍隊にだまされた愛国者と強いられた偽善者に満ちていたが、しかし比島の敗軍にあっては、私達の間に一種の奴隷の友情が生じていたのを私は知っている。私は自分を憐れむと同じ程度に彼らを憐れんでいた。どうして私にレイテの傷兵にまみえるのを喜ばぬ理由があろう」と書く。インテリの矜持と捕虜としての奴隷根性の自覚、これらは日本人の特性として戦後いろいろ議論になった。また「戦友」の項では、詐欺師同然の兵を目の当たりにして、「こう書いてくると、遺憾ながらわがミンドロの将校や補充兵がただ軍人として劣るばかりでなく、人間としても甚だ愛すべき存在でなかったことを認めざるを得ない。そしてもしこうした世に摺れた中年男の醜さが、戦場という異常の舞台に氾濫するに至ったのが、専ら彼等に戦意が足りなかったという事実に拠るとすると、国家が彼等を戦場へ送ったのは、国家にとっても、彼等自身にとっても、遺憾なことであった。無論機会を送るのが最上であったが、機会を持たない日本は、そのかわり訓練によって戦意を持たされた人間を送った。しかし教えられた戦意が事実の前に脆いのは、補充兵でも現役兵でも似たようなものである」と書く。こういう人間たちが戦争に関わったのであるから、結果は火を見るより明らかだったろう。戦争末期の実相を端的に捉えている。
政治学者の丸山真男は『超国家主義の論理と心理』で、太平洋戦争に組み込まれて行ったメカニズムを分析して、大衆がその役割を担ったと言っているが、大岡の立場もこれに近いものがある。『俘虜記』はいわばインテリから見た大衆の愚かさということになるのかも知れない。しかし最近はこの大衆の愚かさを批判する文化人がめっきり少なくなった。新聞・テレビ等のメディアが大衆の側に埋没しているので、これに同調する文化人・インテリが批判の視座に立てないのだ。
まず、「捉まるまで」の項では、マラリアにかかりジャングルで置いてきぼりになり、藪の中で身を屈め、もし米兵に遭遇したら射つか、射たないかで思索が展開される。結局、若い米兵を目の前にして射たなかったのであるが、その理由をこう書いている、あの時私が敵を射つまいと思ったのは私が「神の声」を聞いたのであり、米兵が迫って、私がその声に従うことが出来るか出来ないか不明に立ち至った時、別の方面で銃声を起こらせ、米兵をその方へ立ち去らせたのは「神の摂理」ではなかったか、という観念であると。著者は東京のあるミッションスクールの中学生であった13歳の時、聖書の真理に打たれ神を信じたと書いている事を考えると、汝の敵を愛せというキリスト者の本分を実践したのかも知れない。しかし、私の感じでは、射つのが面倒くさかったのではないかと思う。敵を射ち殺す慙愧の念と射ち殺される無念とを秤にかけたら、射たれる方が楽だというのは大いにありうると思う。ことほど左様に33歳のインテリ補充兵の厭戦気分は小説全般に横溢している。
捕虜収容所で同胞の捕虜を見た時の印象を「私が彼等に会うのを欲しなかったということは考えられない。いかにも私は昭和初期に大人になったインテリの一人として、所謂大衆に対する嫌悪を隠そうとは思わないし、軍隊にだまされた愛国者と強いられた偽善者に満ちていたが、しかし比島の敗軍にあっては、私達の間に一種の奴隷の友情が生じていたのを私は知っている。私は自分を憐れむと同じ程度に彼らを憐れんでいた。どうして私にレイテの傷兵にまみえるのを喜ばぬ理由があろう」と書く。インテリの矜持と捕虜としての奴隷根性の自覚、これらは日本人の特性として戦後いろいろ議論になった。また「戦友」の項では、詐欺師同然の兵を目の当たりにして、「こう書いてくると、遺憾ながらわがミンドロの将校や補充兵がただ軍人として劣るばかりでなく、人間としても甚だ愛すべき存在でなかったことを認めざるを得ない。そしてもしこうした世に摺れた中年男の醜さが、戦場という異常の舞台に氾濫するに至ったのが、専ら彼等に戦意が足りなかったという事実に拠るとすると、国家が彼等を戦場へ送ったのは、国家にとっても、彼等自身にとっても、遺憾なことであった。無論機会を送るのが最上であったが、機会を持たない日本は、そのかわり訓練によって戦意を持たされた人間を送った。しかし教えられた戦意が事実の前に脆いのは、補充兵でも現役兵でも似たようなものである」と書く。こういう人間たちが戦争に関わったのであるから、結果は火を見るより明らかだったろう。戦争末期の実相を端的に捉えている。
政治学者の丸山真男は『超国家主義の論理と心理』で、太平洋戦争に組み込まれて行ったメカニズムを分析して、大衆がその役割を担ったと言っているが、大岡の立場もこれに近いものがある。『俘虜記』はいわばインテリから見た大衆の愚かさということになるのかも知れない。しかし最近はこの大衆の愚かさを批判する文化人がめっきり少なくなった。新聞・テレビ等のメディアが大衆の側に埋没しているので、これに同調する文化人・インテリが批判の視座に立てないのだ。