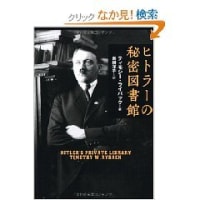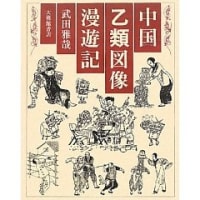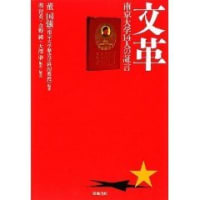アメリカの終わり フランシス・フクヤマ 講談社
フクヤマはかつてウオルホオウイッツ前国防副長官らとともにネオコンの主流を歩み、クリントン政権時代は「対イラク強硬策」を主張した論客だ。「歴史の終わり」はベストセラーになったが、これもそれにあやかったものだ。民主主義が世界の各国に広がって行けば、それが世界のありようの最終段階になり、そこで歴史的発展は終わるというものだが、アメリカの世界民主主義移植作戦は実現の可能性はない。ネオコンの「善意による覇権」はイラクの状況一つを見ても失敗に終わったことは確かだ。この状況下でフクヤマはネオコンと決別し、「転向」を表明したのが本書である。ブッシュ政権は外交政策において「レジームチェンジ(体制転換)」を前面に打ち出し、中心にすえた。具体的には軍事力を用いて、アフガニスタンとイラクの従来のレジームを排斥した。この政策を思想的に支えたのがネオコンである。
ネオコンの源流は、ニューヨーク市立大学(CUNY)に1930年代半ばから後半にかけてと、40年代初頭に通っていたユダヤ人を中心とする一群の優秀な学生たちにある。彼らはみな移民の労働者階級出身で、コロンビアやハーバードといったエリート大学に入ることができずにCUNYに進んだ。彼らの政治意識は高く、左翼政治運動にのめりこんでいった。しかし彼らのは「反共産主義左翼」というべきもので、1930~40年代のスターリニズムとの対決、60年代の新左翼とそれが生んだ対抗文化との戦いを契機として、左派から右派への転換が行われた。彼らの思想的支柱は哲学者のレオ・シュトラウスだが、ネオコンは彼の思想を誤解しているとフクヤマは指摘する。本書の第二章「ネオコンの来歴は」上記の内容を詳細に分析しており、読み応えがある。
アフガニスタン・イラク問題を今後アメリカはどう解決するのか。ポスト・ブッシュ政権はネオコンの外交政策とひとまず決別して出直すしかないだろう。