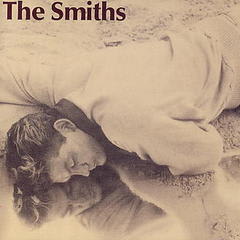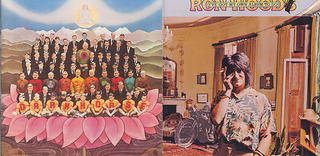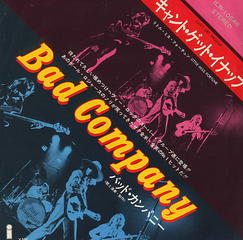いよいよ、ワールド・カップ。日本代表を応援するのはもちろんだが
日本以外の対戦カードもチェックせねばならない。
日韓ワールド・カップからもう4年経つのか・・・。
2回も転勤させられたんだなあ。(笑)
エンケンにはサッカー日本代表を応援する曲がある。
というわけで半ば強引に結びつけたが、今回の選曲はエンケンである。
遠藤賢司にはおよそ駄作というものはない。突き抜け方が凄いだけに
「ああ、平均点だな」と思う曲やアルバムもあるが、エンケンの平均点は
その設定値が高いのだ。エンケンという枠で60点くらいかなぁと思うものは
日本のフォークやロックという枠に放り込むと軽く80点以上はクリアしている。
普段、「裸の大宇宙」や「東京ワッショイ」を聴くとむやみに燃えてくるのだが
実のところ「またいつか会いましょう」とか「外は雨だよ」とかの
ちょっと地味目の曲に執着していたりする。
選んだのは「雨あがりのビル街」。70年発表のエンケンのデビュー作である
「NIYAGO」に収録されている。大瀧詠一を除くはっぴいえんどの
秀逸な演奏がアルバムの中でも抜きん出ている曲だ。
歌詞の中に「ビル街」は出てこないが、なんとなく歌詞の風景が私の頭の中に
浮かんでくる。
例えば・・・。
都庁近辺でも新大阪駅近辺でもいいのだが、日曜日の夕方。
普段は人の行き来が多いのだが休日で閑散としている通り。
それでも人の往来はある。
女の子と待ち合わせをしているのだが、どうも来そうにない。
夕立にもふられ、2時間ほどぼんやり。気がつくと日が暮れていく。
孤独感と虚無感を抱えて、もたれていたビルの壁から離れる・・・。
もちろん歌詞の中では「誰を」「何のために」待っているとは明言していない。
あくまで、私が頭の中に描いた風景の1断片である。
私はいつも何かを待っている。誰かを待っているのかもしれない。
急激な変革や日常の変化を全く望んでいないのに、それでも何かを待っている。
できれば待たせる側になりたいのだが、いつも待つ側である。
何を待っているかわからないので、何が来たのかもわからない。
日常はかくもやるせない。
ずっとそれは変わらないだろう・・・。
雨あがりのビル街《僕は待ちすぎてとても疲れてしまった》
(作詞・作曲 遠藤賢司)
水溜りの中で 大きくゆれた街
しびれを切らした人々は
ゆっくりと歩き始めた
しびれを切らした自動車は
急ブレーキを踏む
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
ちっちゃな ちっちゃな女の子が
ちっちゃな ちっちゃな足音を立てていった
それはほんとに ちっちゃな足音だったけど
僕にはとても大きくひびいたんだ
だからもう帰ろうと思った
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
日本以外の対戦カードもチェックせねばならない。
日韓ワールド・カップからもう4年経つのか・・・。
2回も転勤させられたんだなあ。(笑)
エンケンにはサッカー日本代表を応援する曲がある。
というわけで半ば強引に結びつけたが、今回の選曲はエンケンである。
遠藤賢司にはおよそ駄作というものはない。突き抜け方が凄いだけに
「ああ、平均点だな」と思う曲やアルバムもあるが、エンケンの平均点は
その設定値が高いのだ。エンケンという枠で60点くらいかなぁと思うものは
日本のフォークやロックという枠に放り込むと軽く80点以上はクリアしている。
普段、「裸の大宇宙」や「東京ワッショイ」を聴くとむやみに燃えてくるのだが
実のところ「またいつか会いましょう」とか「外は雨だよ」とかの
ちょっと地味目の曲に執着していたりする。
選んだのは「雨あがりのビル街」。70年発表のエンケンのデビュー作である
「NIYAGO」に収録されている。大瀧詠一を除くはっぴいえんどの
秀逸な演奏がアルバムの中でも抜きん出ている曲だ。
歌詞の中に「ビル街」は出てこないが、なんとなく歌詞の風景が私の頭の中に
浮かんでくる。
例えば・・・。
都庁近辺でも新大阪駅近辺でもいいのだが、日曜日の夕方。
普段は人の行き来が多いのだが休日で閑散としている通り。
それでも人の往来はある。
女の子と待ち合わせをしているのだが、どうも来そうにない。
夕立にもふられ、2時間ほどぼんやり。気がつくと日が暮れていく。
孤独感と虚無感を抱えて、もたれていたビルの壁から離れる・・・。
もちろん歌詞の中では「誰を」「何のために」待っているとは明言していない。
あくまで、私が頭の中に描いた風景の1断片である。
私はいつも何かを待っている。誰かを待っているのかもしれない。
急激な変革や日常の変化を全く望んでいないのに、それでも何かを待っている。
できれば待たせる側になりたいのだが、いつも待つ側である。
何を待っているかわからないので、何が来たのかもわからない。
日常はかくもやるせない。
ずっとそれは変わらないだろう・・・。
雨あがりのビル街《僕は待ちすぎてとても疲れてしまった》
(作詞・作曲 遠藤賢司)
水溜りの中で 大きくゆれた街
しびれを切らした人々は
ゆっくりと歩き始めた
しびれを切らした自動車は
急ブレーキを踏む
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
ちっちゃな ちっちゃな女の子が
ちっちゃな ちっちゃな足音を立てていった
それはほんとに ちっちゃな足音だったけど
僕にはとても大きくひびいたんだ
だからもう帰ろうと思った
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から
僕は人を待ってたんだ もうずっと前から