
こんにちは。
先週に引きつづき台風の影響で関東地方は雨が降っています。週末の雨ばかりで出かけるにも出足をくじかられてしまう雨になっています。そして、ニュースでは被害を伝えることが多い台風のようです。雨だからのんびりと、家にこもって…という気になれない台風です。
季節は雨がふるごとに寒さが増しているように見えます。職場ではカゼをひてマスクをしているひともみました。これからは、寒さに対応した体が求められるのでしょうか。ちょっとした工夫が大切な季節です。
さて、今週は衆院選の開票結果がでました。
あいかわらず与党の勢力は衰えようとしませんね。どうしてなのでしょうかねえ。自民党、公明党を合わせて過半数以上になってますますやりたいことをやろうという意気込みが伝わってきます。まさに今後も「一強多弱」の色あいが濃く出てくる政治が転回されるのでしょうか。困ったことですねえ…。
さらには、これまで日本は「ものづくり日本」ということがいわれてきました。それが危うくなってくる企業の不祥事が相次いでいました。
神戸製鋼の品質検査の偽装、日産、スバル両自動車会社の検査偽装。どれもが一流企業、いわばを日本のモノづくりをリードしてきた会社だけに大変なように思えます。
それにしても、なぜこのタイミングなのだろう…とも思います。きっと内部告発かで発覚したものではないかと思います。どれも、「氷山の一角」にも見えます。なぜなら、大小あるもののブラック企業という言葉があるようにいま、日本の働く現場が偽装があるのではないのでしょうか。重箱の隅をつつくようですが、私の身の周りにもあります。「なんでこうなるの?」と思える出来事が多いのではないのであようか。それにつけても、この企業の労働組合はいったいどうなっているのかのかという疑問がでてきるのではないのであようか。(労働者を守るはずの組合がどう対処していくのか、今後の組織の在り方も問われていると思いますが)
それにしても、「希望の党」はいったい何者だったのでしょうか。まさに、政治家の野心やもろさを見たような気がしました。


たいへんご無沙汰していました。8~9月と2か月間のお休みをもらっていました。2か月間の間には紹介している本意外にもありました。しかし、私の怠慢で記録していないことが多く月末にまとめることもできずにいました。
今月は…と思いがんばってみました。読み返すうちにどれも中途半端の反省はゆがめません。それでも、一つの記録として残すために、今月は載せました。
世の中には星の数ほどの本があります。その中から何らかのご縁であるいは必要にせまられて読んでいるのが本です。どれも、興味深い内容であることは読み終えて感じます。その中で「これはも一度読んでみたい」というものも出てきます。図書館で借りたり、絶版はアマゾンで探したり、と気がつけばこれから何年生きられるかわからないのにたまる一方です。そんなことを思いつつ手元にとっておきたい本はいっぱいあります。なんかバカなのでしょうねえ。

p151 ところが、入院が三週間あまり七月三十日、人のうめき声が聞こえないところで眠りたいと思い始めたら、もう矢もたてもたまらなくなって、いきなり、明日退院したいと申し入れた。
p176 しかしこの世の出来事には必ず”因”があって”果”があるのであって、あらゆる物理的な、心理的、生理的、そして社会的因果関係も予測する力もあれば、多くの不運は避けられるはずである。
p176 いや現実には人の世は私利私欲、不注意、怠情などが渦巻き、一人の人間では防ぎきれぬ悪しきものの種子が尽きるとはないのだろう。だから個々の人間は運命としてあきらめるより仕方のない、自分の力を完全に出し切ってなお避けることのできない不運というものは、いつの世になってもつきまとうことだろう。
p389 また一方、発見と同時に既に手遅れも手遅れ、今日死ぬか、明日死ぬかというような状況の中にあって、彼の死生観、患者としての生きかたと、医師たちやナースたちの姿勢が緊張感ある調和を保って、彼はある平安のうちに死に得た、と推測されるからである。彼の死について書くことの意味を納得するまでに、かなりの時間がかかったが、それは対がん運動への私の中の虚しさのためでもあった。…その度に私は、「家の中の恥をさらして書いても、所詮、がんなんて他人事でしかないのね」と嘆いたものである。

しょせん「がん」という病気とは縁がないだろうと思っていた。若い時にはとくに考えてもいなかった病名だ。
ところが最近のこと、会社の同僚や友達のようすを聞いたら以外と多いことに驚いてしまった。
そして、とうとう身内にまでその病名がうかんできた。がんは遺伝子するようなものだと考えていたがちがったことを目の当たりにしておどろいている。
「なぜ…? ぼくの身内に…」という疑問はいまも消えない。
「なんという無知!!」それでも信じたくないことだった。
それからというもの、少しずつ落ち着いて「がん」についての本を読んでみようと思って一冊選らんだのが『がんと闘う、がんに学ぶ、がんと生きる』(中島みち・文春文庫)であった。
読めばよむほどに、それほど遠い病気でもないように思えた。「がんは病気の王様か」という気さえ起きてきた。それにしても、これほど長い間研究され薬も多くできているだろうに、いまだにそれができていないのはなぜだろうと考えてしまう。そんなことを思った。
さて本は、作家・中島みちさんが乳がんにかかってから、その対応をドキュメントした記録である。発症から手術、そして治療 しょせん「がん」という病気とは縁がないだろうと思っていた。若い時にはとくに考えてもいなかった病名だ。
けっきょく、この病気との関係は生きていくためには永遠の付き合いがよぎなくされる。しかも、その過程においては死をもつれてくる病気であることはだれでも分かっていることだろう。うらをかえせば、それだけ人に「人間とは…」という大きなテーマを与えてくれる病気であることがわかる。
……………………………………………………………………………………………………………………
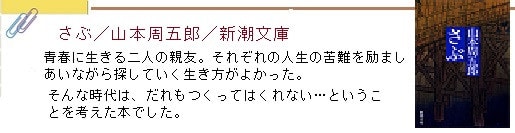
p45 「…おめえはな、さぶ、pれにとっては厄介者dころか、いつも気持ちを支えてくれる大事な友だちなんだ、正直にいうから怒らねえでくれよ。おめえはみんなからぐずと云われ、ぬけていると云われながら、辛抱づよく、黙って、石についた苔みてえにしっかり自分の仕事についてきた。おらあその姿を見るたび、心の中で自分に云いきかせたもんだ…。
p114 世間ぜんたいが敵だ。これを忘れてはいけない。金持ちは金の力で、役人は権力で、罪のない者を罪人にすることができる。自分のように金もなく権力もない者にはかれらに対抗することはできない。
p103 心の中で唾を吐いた。
p210 一枚の布切れのため、右から左からも無法に痛めつけられ、一生をめちゃくちゃにされてみれば、人を憎み世間を憎むのは当然なことだ。いまはその憎む心でいっぱいなのだ。無事平穏にしている者を見れば、その憎悪をかきたてられるだろう。
p275 うまい字を書こうとすると嘘になる。字というやつはその人の本性をあらわすものだ。いくらうまい字を書いても、その人間の本性が出ていないものは字ではない。上手へたは問題ではない。自分を偽らず正直に書け…。
p310 「…人間てやつは欲に弱いもんだ。いるかわからないが、おめえが訴え出ても、その役人たちは自分の欲と面目のためにどんな手を使っても揉み消そうするだろう。
p317 この世を生きてゆくということは、損得勘定じゃない。短い一生なんだ。自分の生きたいように生きるほうがいい。しっかりやってくれ清さん。

『さぶ』という作品は、40年ほど前(20歳台)に友達に紹介された小説だったと思う。今では、その友達は結婚ししてゆくえ知れずとなっている。どこでどんな生活をしているのか思い出すことがある。その時代は、「この親友とは一生つきあってゆくのかな…」と思っていた。
その昔、靖国神社を歩きながらこの人と一緒に一生を送っていけたらなんと幸せなことかとも思っていたが…、世の中思うほどに進まないと思う。青春時代とは多感でもあったのだと思う。そんなことを思い出させてくれる小説だと思う。
山本周五郎の大事な人間の心あり方を問う作品があるように思う。
その一部を紹介するかのように小説にしていることに気がつく。
いなみに、神奈川近代文学館で2017年(平成29)9月30日(土)~11月26日(日)の期間「周五郎展」をやっています。終わる前に一度行ってみたいと思う。
※興味のある方はこちらも
 山本周五郎展
山本周五郎展……………………………………………………………………………………………………………………

p21 森林というコミュニティは、高い樹木だkでなく、低木や草なども含めたすべての植物が同じような方法で会話をしているのかもしれない。
p24 …同じ種類の樹木同士ではそうはならないのだ。…ブナなどの木は仲間意識が強く、栄養を分け合う。弱った仲間を見捨てない。仲間がいなくなると、木と木のあいだに隙間ができ、森にとって好ましい薄暗さや湿度の高さを保てなくなってしまうからだ。
p63 樹木のとっては、菌類がいちばん大切なパートナーだが、それ以外にもたくさんの協力者がいる。たとえばキツツキ。「協力者」は言いすぎかもしれないが、少なくともキツツキは樹木の役に立っている。
p108 「森は自分の居場所を自分で理想に近づける」
p144 クマは食べれば食べるだけどんどん太るが、木の場合は、満たされてしまえばそれで終わりになる。たとえば野生のサクラやナナカマドなどは、まだまだ日差しの強い時期が続いているというのに、八月になると早くも赤く染まりはじめる。今年の活動はもう終わり、といわんばかりに。樹皮の下と根っこのタンクが満たされたので、それ以上糖分をつくっても蓄える場所がないからだ。
p145 健康な木は葉の黄色をきれいに輝かせることで、自分には翌年も抵抗力があるぞ、と合図している。これは、その木の免疫力があって充分な防御物質が分泌できているということを意味しているので、アブラムシの子孫などの目には脅威に映るだろう。
p160 樹木の運命も、あるひ突然、何らかの理由で大きく変わることがる。樹木の健康は、森林の生態系が安定しているどうかで決まる。

これから紅葉の季節。
木々の生活を読むことは、その意味がわかること。森を歩くとき、再読していくとさらに主人公たちの音が身近に感じることだろうと思う。
一人で歩く森の中で「知られざる樹木たちの生活」をきっと思い出すことだろう。(ちなみに出版社は「早川書房」でした)。

p133 働くことのあり様はさまざまな形がある。人の数だけ働くこともある。それは「私」という個人がこの世界に二人といないことと同じだ。「私」が働きことをどのように選択し、どう関係を持つかによって、働くことの在り方、意味が決まる。それは働くことと「私」の関係を問うていくことでもある。そして、問うということができるということ自体、自由であることの証なのだ。

それぞれの景色のなかに自分がいる。ある作家の小説が似ているものがあることに気がつくこともあると思う。
林芙美子の『放浪記』は就活をしている人に良く似ている。それは、職を求めてさまよう主人公のように求めるものを得るためにさまよう景色なのだろうと思うからだ。さらに、派遣狩りという言葉が世の中を席巻したとき読まれたいた小林多喜二の『蟹工船』という小説を思い出す。そのなかに、登場する人々が時代と場所は違うが境遇がまりにもよく似ている…という小説が話題になったことは記憶に新しいことだろう。
とくにそんなことを意識して小説を読んでみたら…という本だった思う。
ただそんなことを気にしなくとも、手に取った本はなんらかのテーマがあるようだ。大事なことは、最後に読みえ終えて手に取った本の内容のテーマと今置かれいる自分の立っている場所を考えることが最も大事なことだと思う。
◆◆ほかにこんな本も読んでいました。

……………………………………………………………………………………………………………………



早いものです。
一年が終わろうとしています。一年のマンションの締めくくりとして管理組合の総会に行ってきました。近所の図書館分館を借りての総会でした。
メインテーマは「今年の会計報告」と来年の「大規模修繕」についてでした。とくに「大規模修繕」については、質疑が多数でた総会でもありました。
最近、建築物の偽装事件などはききませんそ。横浜の「傾斜マンション」、「杭打ちデータ偽装事件」などと呼ばれた、横浜市都筑区の大規模マンションの問題が記憶に新しいでしょうか。そんなことが頭をよぎった総会でした。
この事件は元請けが工事を下請けに丸投げして発注したものでした。その仕組みは、いまでも下請けが工事を請け負う構図はかわってはいないのでしょう。今回の修繕工事でも管理会社から下請けに工事の発注するそうです。
ただ、それが他人のことから現実自分の身の周りに関わってきたということでしょう。元請けが下請けに発注することは問題ではなく、そのなかで元請けが予算内で利益を多く得ようとして、下請けに注文をつけ、下請けは自分の利益と元請けへの利益をつくるために、手抜き工事をしていた…ということでした。そのため、マンションは欠陥になっていることを偽装したものでした。
最近、NHKの「クローズアップ現代」でこの内容の放送がありました。
私は失礼と思いつつ質問にこのクローズアップ現代の内容と「そんなことのないように修繕後の検査を的確にやってほしい」との注文をつけていました。業者は「管理会社も立ち会って『打診検査』なども含めてちゃんとやるとの回答でした。私も管理組合の理事の人もぜんぶしろうとですから、と理由で工事の細かい内容にはよくわからない…ことが多いものです。それでも、少なくとも自分たちのお金で修繕することになるわけですから、もっと注文をたくさんあ出して質問が必要になってくるように思えました。質問が偽装への「予防効果」があるだと思います。質問をして恥をかくくらいならまだいいのです。それより重大な問題になる前にたくさんの「恥」でもかいておくのも必要なのではないのかな、と思いました。


とうとう10月も終わる。
思えば先週と今週はとても忙しかった。それが証拠に歯ぐきが腫れて、腰痛が戻ってきた。季節の変わり目にはこんな症状が多く出てくることは知ってはいるが…、体が痛みに悲鳴をあげている。とうとう、腰痛にはコルセットを着けて仕事をしていた。散歩をしるのもおっくうになって体が重くなっている。
まさに「負の連鎖」で体調がわるくなっていくだろうと日々感じるようになった。
気分転換!!と思い、散髪屋さんに行ったり、11月には体が軽くなるようなスケジュールを手帳に書きこんでいた。まさに、天気次第とならないようにしたいが、貧乏人の私は天気は貴重な情報だ。
これだけ雨も降れば、季節は一気に寒くなって山は紅葉が見ごろになってくるだろうと思う。11月はそれをのんびり『樹木たち…』を思い浮かべながら歩いてみようと思う。
それも、日々の計画の一つ一つの実行から。忘れたようにしてきたものを片づけていかないとパニックになるのは私だ。
「負の連鎖」で心がこんがらないようになる前に一歩づつ行きたいものである。「今月の本棚」をまとめていたら、子どもの頃、夏休みも終わりに近づいた宿題を思い出した。なかなか怠けぐせはなおらないものである。
大人になって「スケジュール」を手帳に付けることを覚えたが、性根はそんなにかわっていまのだなあと思う。<反省の日々>日々是毎日ということだろう。
さて、11月はすぐそこに来ています。
どんな11月になるのでしょうか。そんななかでも、「これだけは」と思うものを実践しようという予定が大事なのだなあ…と思います。
「今月の本棚」はいかがでしたでしょうか。8月から10月の本を紹介しました。もっと感想があったのでしょう。それを記録していないと全部忘れています。大事なことはノートをとること、と。
来月のメインテーマは「年金」についてです。どんな本を読んでいるのでしょうか…。10月も終わります。おつかれさまでした。
11月の連休にでも整理していこうと思います。
台風の去った後、近所の公園にいくと木々も少しずつ紅葉し始めていましたよ。(写真)そして、北風が強くなってきていました。うっかりするとカゼをひいてしまいます。風の戸に木々が音をたてていました。ご注意を!!
プリ野球日本シリーズも始まっています。私は、関東なので横浜ベースターズを応援しています。ガンバレーと…。でも、工藤監督のファンでもあります。今回はカンベンしてもらいましょう。(ちなみに、工藤監督の選手を大切にする持論に感心しています)
それでは長くなりましたが、今回はこの辺で失礼します。
読んでくれた人、ありがとうございました。










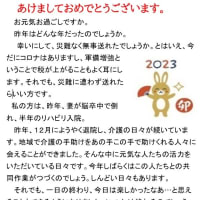









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます