『国家はなぜ衰退するのか』
ダロン・アセモグル ジェイムズ・A・ロビンソン 著 鬼澤 忍訳
http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec49/ard49-bookinfo.html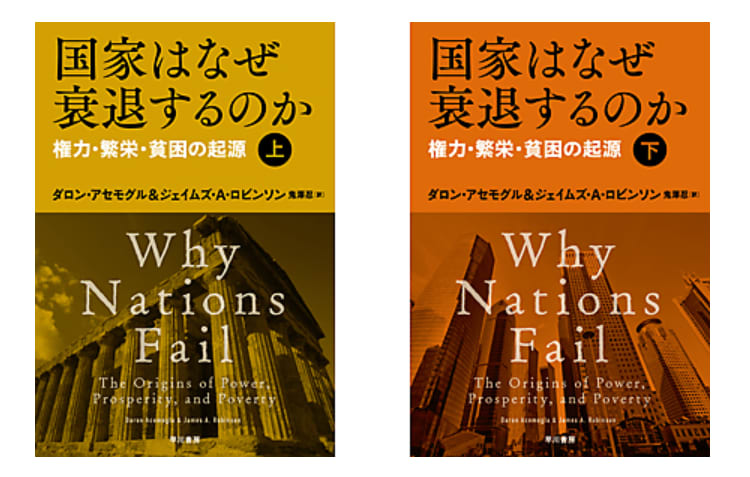
毎日新聞社 新聞研究本部 位川一郎 氏の論評より。
●繁栄と貧困を分けるのは政治と経済における「制度」
●国家の制度は、権力が社会に広く配分され大多数の人々が経済活動に参加できる「包括的制度」と、限られたエリートに権力と富が集中する「収奪的制度」に分けることができる(「包括的」という言葉はやや分かりにくいが、一般的な感覚では「民主主義的」に近いだろう)。
包括的制度のもとでは、法の支配が確立し、所有権が保護され、イノベーションが起こりやすい。
収奪的な政治制度と経済制度のもとでは、その反対のことが起きる。
そして、「経済的な成長や繁栄は包括的な経済制度および政治制度と結びついていて、収奪的制度は概して停滞と貧困につながる」と著者は主張する。
●1346年のペスト襲来という「決定的な岐路」
●産業革命がイングランドで始まり大きく前進したのは、1688年の名誉革命が包括的政治制度をもたらしたためだった。
●現代においても、ジンバブエ、コロンビア、北朝鮮、ウズベキスタンなど多くの国で収奪的制度の悪循環が繰り返されている。(第11章~第13章)
●収奪的な政治制度から包括的政治制度への移行がなければ、中国の成長はいずれ活力を失うだろう。(第15章)
●収奪的制度から包括的制度に移行するにはどうすればよいか。著者は「移行をたやすく達成する処方はない」と言い切る。
●第15章の最終節で、包括的制度の強化に成功した国に共通するのは「社会のきわめて広範かつ多様な集団への権限移譲に成功したことだ」と指摘している。困難ではあっても、各国の内側で政治的な多元主義が育つのを期待するしかないということだろう。納得できる見解といえる。
●本書は主に一国内の収奪的制度に着目しているが、国際的な収奪構造も無視するわけにいかない。だとしたら、先進国の側も貧困の克服のために、従来とは異なる関与の仕方を探るべきではないだろうか。
最新の画像[もっと見る]
-
 髙橋まきこ氏と『政策協定』
2ヶ月前
髙橋まきこ氏と『政策協定』
2ヶ月前
-
 晴海西小中学校の校庭への仮設校舎設営(第二校舎始動までの間の令和9〜10年)、令和7年6月4日開催教育委員会定例会で議論
2ヶ月前
晴海西小中学校の校庭への仮設校舎設営(第二校舎始動までの間の令和9〜10年)、令和7年6月4日開催教育委員会定例会で議論
2ヶ月前
-
 同じ会派「かがやき中央」で活動した髙橋まきこ氏を、完全無所属の立場から、応援します。
2ヶ月前
同じ会派「かがやき中央」で活動した髙橋まきこ氏を、完全無所属の立場から、応援します。
2ヶ月前
-
 有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
4ヶ月前
有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
4ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4ヶ月前
-
 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4ヶ月前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4ヶ月前
-
 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4ヶ月前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4ヶ月前
「書評」カテゴリの最新記事
 『日本政治学史』酒井大輔著
『日本政治学史』酒井大輔著 自身の活動の根底にあるものの一つ『苦海浄土』、医師として反省し、決して繰り返...
自身の活動の根底にあるものの一つ『苦海浄土』、医師として反省し、決して繰り返... 世界一わかりやすく書かれた哲学の本。この本が、日本の民主主義を守る力も持って...
世界一わかりやすく書かれた哲学の本。この本が、日本の民主主義を守る力も持って...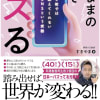 元教師が語る最もわかりやすい「情報リテラシー」指南書。これ一冊で、誰もが、バ...
元教師が語る最もわかりやすい「情報リテラシー」指南書。これ一冊で、誰もが、バ...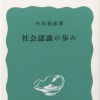 「世の中を読む手法を教えてください」と問われたら、どう答えるか。過去の若輩小...
「世の中を読む手法を教えてください」と問われたら、どう答えるか。過去の若輩小...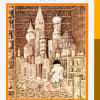 ミヒャエル・エンデ『モモ』、読んでおきたい名作。
ミヒャエル・エンデ『モモ』、読んでおきたい名作。 『白いハンカチ』中桐雅夫詩集より。
『白いハンカチ』中桐雅夫詩集より。 「本を読んだ方がいいと思いますか?」と小学生に質問されたら、何と答えますか。
「本を読んだ方がいいと思いますか?」と小学生に質問されたら、何と答えますか。 絵本の読み聞かせで、最も大切なことの一つ。
絵本の読み聞かせで、最も大切なことの一つ。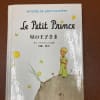 『星の王子さま』 サン・テグジュペリ 作、内藤 濯(ないとうあろう)訳 岩波...
『星の王子さま』 サン・テグジュペリ 作、内藤 濯(ないとうあろう)訳 岩波...















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます