小児は、免疫が未発達であり、感染防御能が低い状態です。
予防接種により、小児に十分な感染防御能を付けることができ、子ども達を守ることができます。
しかし、現在の日本は、ワクチン後進国と言われ、欧米をはじめ多くの国においてすでに過去の感染症となっているVPD(Vaccine Preventable Diseases)に苦しめられるこども達がいまでも後を絶ちません。
<予防接種が自然感染より優れている理由>
一部で、自然感染の方が予防接種より強い免疫が出来ると信じている方々がいますが、この考え方は誤っています。
なぜならば、
・自然感染より予防接種の方が強い免疫を誘導できる場合もある(結合型肺炎球菌ワクチン、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)など)
・自然感染は、重症化(はしかの脳炎など)、遷延化、持続感染(みずぼうそうの帯状疱疹など)を起こす。
・発病者は、他人への感染源(百日咳の乳児への感染、みずぼうそうの新生児への感染など)になる。
よって、自分にも良くなく、他人にも悪さをする自然感染は、決して起こしてはなりません。
保護者の皆様へ
定期予防接種のBCG、三種混合&二種混合、MR、日本脳炎は当然のことですが、
中央区では公費負担となり保護者負担がゼロの7価肺炎球菌ワクチン:『プレベナー』、ヒブワクチン『アクトヒブ』そしてHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)
任意接種の水痘ワクチン、おたふくワクチン、B型肝炎ワクチンなど接種をお願いします。
なおポリオワクチンは、経口生ワクチンでなく、不活化ポリオワクチン(当院でも接種開始)が日本にも早期導入されることをまち望んでいます。
実は、ワクチン行政を世界レベルにするには、以下の課題の解決をせねばなりません。
<小児科学の観点からの今後のワクチン行政の課題>
*筋肉注射の導入(免疫原性が高い、局所反応が少ない)
*7価肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、水痘ワクチン、おたふくワクチン、B型肝炎ワクチンなどの定期接種化
*二期DTワクチンの三種DTP化
*インフルエンザワクチンの接種量の改訂(小児0.3ml 大人0.5ml)
*ロタウイルスワクチン、13価肺炎球菌ワクチン、髄膜炎菌ワクチン、不活化ポリオワクチンの導入
*日本版ACIPの設立(今は、日本小児科学会をはじめ学術13団体が横断的にワクチン検討委員会を手弁当で設置しているところ)
東京都の課題としては、
*同じ都内自治体でも、7価肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの助成額が異なります。中央区は保護者負担ゼロですが、保護者負担が5000円近くの自治体もあると聞いています。この不均衡をなくすためにも、都が財政負担を行うべきだと考えます。
など
<ワクチンの最新知識> The Pink Book 12th Edition(April 2011)
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/default.htm
上記記事は、防衛医科大学小児科学講座 野々山恵章教授のご講演も参照し記載致しました。
**以下、参考までに、中央区議会が厚生労働大臣及び内閣総理大臣あてに出した意見書*****
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/seigan/iken/iken65.pdf
日本国内での不活化ポリオワクチンの早期導入を求める意見書
わが国におけるポリオの予防は、「経口生ポリオワクチン」を用いた予防接種により行われていますが、今、世界では欧米諸国をはじめ多くの国々が「不活化ポリオワクチン」を使用しています。これは、国立感染症研究所が昨年七月に発表した「ポリオワクチンに関するファクトシート(報告書)」においても述べられているとおり、「不活化ワクチン」は「生ワクチン」と比較し、安全性と優位性が認められているからにほかなりません。
現在、国内で使用されている「生ワクチン」については、厚生労働省が昨年八月に発表した「予防接種後副反応報告書」によると、接種者二百十二万八千八百四十八人中、四肢の麻痺六件、その他の副反応症例九件、計十五件の事例が認められたと報告されています。一方、「不活化ワクチン」については、既に導入した各国において麻痺の副反応の比率が極めて少ないことが明らかになっています。こうした状況から見ても、わが国も早急に「不活化ワクチン」の導入を図る必要があります。
これまでも「不活化ワクチン」については、日本医師会、患者家族会などが国に対し予防接種への導入を強く要望してまいりましたが、ワクチンの承認は未だ、実現されておりません。そこで、国が承認するまでの間、当面、「不活化ワクチン」を輸入して対応することを認め、重症な副反応による被害者をこれ以上出さないようにすべきと考えます。
よって、本区議会は、国に対し早急に予防接種法を抜本的に改正し、「不活化ワクチン」を導入するよう強く要望します。
右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。
平成二十三年三月十七日
厚生労働大臣
内閣総理大臣 あて
最新の画像[もっと見る]
-
 連携している子育てひろば「あすなろの木」さんが、今年度も企画、第20回 学びの宝箱。参加者募集中(先着順)
2週間前
連携している子育てひろば「あすなろの木」さんが、今年度も企画、第20回 学びの宝箱。参加者募集中(先着順)
2週間前
-
 連携している子育てひろば「あすなろの木」さんが、今年度も企画、第20回 学びの宝箱。参加者募集中(先着順)
2週間前
連携している子育てひろば「あすなろの木」さんが、今年度も企画、第20回 学びの宝箱。参加者募集中(先着順)
2週間前
-
 髙橋まきこ氏と『政策協定』
2ヶ月前
髙橋まきこ氏と『政策協定』
2ヶ月前
-
 晴海西小中学校の校庭への仮設校舎設営(第二校舎始動までの間の令和9〜10年)、令和7年6月4日開催教育委員会定例会で議論
3ヶ月前
晴海西小中学校の校庭への仮設校舎設営(第二校舎始動までの間の令和9〜10年)、令和7年6月4日開催教育委員会定例会で議論
3ヶ月前
-
 同じ会派「かがやき中央」で活動した髙橋まきこ氏を、完全無所属の立場から、応援します。
3ヶ月前
同じ会派「かがやき中央」で活動した髙橋まきこ氏を、完全無所属の立場から、応援します。
3ヶ月前
-
 有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
5ヶ月前
有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
5ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
5ヶ月前
「小児医療」カテゴリの最新記事
 障がい学における「個人モデル」と「社会モデル」の違いとは。
障がい学における「個人モデル」と「社会モデル」の違いとは。 AYA世代のがんのサポートについて
AYA世代のがんのサポートについて 福祉保健費:自治体での5歳児健診実施に向け、一緒に考えましょう!その子のさらに...
福祉保健費:自治体での5歳児健診実施に向け、一緒に考えましょう!その子のさらに... 中央区政の大きな進展のひとつ。念願だった、小児インフルワクチンにも補助が付き...
中央区政の大きな進展のひとつ。念願だった、小児インフルワクチンにも補助が付き...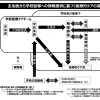 問い:学校医とは、何ですか。どんな役割がありますか?
問い:学校医とは、何ですか。どんな役割がありますか? 2024年度の募集に、中央区も参加できないだろうか。新生児マススクリーニングへ2つ...
2024年度の募集に、中央区も参加できないだろうか。新生児マススクリーニングへ2つ... 本日4/20、とてもうれしかったこと。小児科学会でアドヴォカシーを取り組まれてい...
本日4/20、とてもうれしかったこと。小児科学会でアドヴォカシーを取り組まれてい... 『入院しているこどもの家族の付き添いに関する課題に対して小児科学会はどう取り...
『入院しているこどもの家族の付き添いに関する課題に対して小児科学会はどう取り...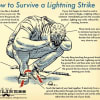 落雷対策、再確認願います。1,広場から離れる・木から4m離れる、2,建物・車に避...
落雷対策、再確認願います。1,広場から離れる・木から4m離れる、2,建物・車に避... 週末の小児科関連の学術集会、学校との連携のありかた、他地域ではどのようにして...
週末の小児科関連の学術集会、学校との連携のありかた、他地域ではどのようにして...















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます