該当する学校の皆様は、すでにご存じかとは思いますが、胃腸炎が、たいへん流行っています。
学年閉鎖となった学校があります。
アルコールでは消毒できないこともあり、手洗いをお願いします。
吐いたら、飲食止めてお腹を休めて下さい。OS-1ゼリー等で水分補給を。
******中央区感染状況*******
第13週 3/27-4/2 (三月下旬の状況で、現状の反映はできません。)
この度の2月補正予算で、妊娠出産支援の充実を図るところです。
あくまでも、うまく行政とつながった方々への支援は充実できます。
母子手帳の交付を受けることができていないかたがたへの支援をどうするか、大きな課題があると考えています。
すなわち、ひとりで抱えこまずに、相談できる先とつながれますように、体制を整備していくこと、そして、多職種・多機関の連携体制を強化することが求められています。
ひとりで抱え込んだまま、0カ月0日を迎えることのないように。
小さかったころを思い出して、どうか、かかりつけであった小児科医にもご相談いただければと考えます。
********中央区令和4年度2月補正予算資料************
https://www.city.chuo.lg.jp/documents/13518/r4-2hoseiann.pdf

「コウノトリ」ではなくて、精子と卵子が一緒になって受精卵となり子宮の中で大きくなっていくことを、子どもの問いに向き合いながら、理解できる形で伝えることが大切です。早い子では初経を迎え妊娠につながる体となる小学四年生(10歳)までには、性交・妊娠の仕組みを知っておくべきと考えます。ユネスコの『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』では、5歳から伝える内容が整理され、日本でも包括的性教育として広がりを見せています。
今年の4月から「生命(いのち)の安全教育」が始まり、プライベートゾーン、デートDV、性的同意などについて学校でも教えられます。プライベートゾーンは、顔・口と水着で隠れるところ(胸、おしり、性器)です。赤ちゃんのころから体を清潔にしながら、大事にしようねと語りかけて下さい。自分を大切にすること、思春期の体の変化を知ること、困ったときに相談できる大人を持つこと(かかりつけの小児科医にもご相談下さい)が、ご家庭と学校・地域での教育を通じ子ども達にしっかりと伝わりますように。子どもの問いに、科学的な知識を基盤にきちんと伝えていく積み重ねで、自分の体を自分で守れる子、自分の体の自己決定ができる子に育つことを願っています。
#つながるBOOK、産婦人科医高橋幸子先生のHP『サッコ先生の性教育研究所』、集英社りぼん別冊『生理カンペキBOOK』など参考になります(本稿でも参照)。
*******包括的性教育に役立つ書籍や教材********
●サッコ先生の性教育研究所
https://sakko0607.wixsite.com/sakko/about
●自分の体の自己決定、性的同意とは?
動画解説 https://youtu.be/xxlwgv-jVI8)
●世界の性教育 国際セクシュアリティ教育ガイダンス
https://sexology.life/
https://sexology.life/world/
●#つながるBOOK
https://www.jfpa.or.jp/
●女性の健康教育プログラム まるっと
https://marutto-woman.jp/
https://marutto-woman.jp/
●集英社りぼん別冊『生理カンペキBOOK』
http://ribon.shueisha.co.jp/
<書籍>
●性をめぐる子育て支援
●
スクリーンタイムに関しては、注意していく必要があります。
以下、新年のご挨拶でも、2023年の子ども関連施策の充実すべき点で取り上げました。
毎日新聞記事において、ゲーム依存について取り上げられしましたので、共有いたします。
どうか、ご関心をお持ちいただければと思います。
気がかりなことがございましたら、お早めにご相談ください。
***********************
2021年度から一人一台タブレットが配備され文房具が一つ増えました。有効活用に期待する一方で、デジタル機器の長時間の使用が脳や体へ与える悪影響を注意深くフォローする必要性があると考えます。国際的な疾患分類ICD-11では、「ゲーム行動症」なる疾患名も新しく採用されています。電子スクリーン症候群(ESS)という疾患名も出てきています。スマホ、タブレット、テレビなどのスクリーンタイムの増加は、発達への影響が懸念されており、実際に長時間のスクリーンタイムに曝露した1歳半の幼児は、3歳時点において自閉傾向が見られたという国内の論文も出ました。
スマホに一時的に子守りをさせねばならないやむを得ない状況が日常生活で多々あることは理解するものの、小児科医らは日本小児科医会を中心に、2歳までテレビ・ビデオ視聴は控えること、スクリーンタイムを2時間以内、ゲームは30分までにすることを2000年半ばより発信してきました。乳幼児期から、電子スクリーン症候群(ESS)の影響を考え、スクリーンタイムを減らす努力をすることを、母子保健活動で、情報提供されていくべきと考えます。
教育現場においても、スマホ・ゲーム依存への啓発活動や、電子スクリーン症候群(ESS)を予防する取り組みもまた重要です。教育現場において、スマホ・ゲーム依存などが原因となり、実際に脳や体への悪影響が出てきているような事例はないか、注意深く健康を観察していく必要もあると考えます。
*********毎日新聞2023.1.13****************


わかりやすく、医学的に正しい情報が、子ども達に伝わること、生と性の情報についてもしかりです。
多くの若者たちが、義務教育で十分な性教育を受けられないまま、インターネットやアダルトビデオから歪んだ情報を取り込んでしまっているのが現状です。
「赤ちゃんってどうやってできるの?」と聞かれたら、しっかりと子どもに伝えてあげてください。
世界の性教育の基準が書かれている、ユネスコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」では、性教育は5才から始まっています。
もちろん、伝えるには、それ相応の準備が必要です。
その場でわからないときは、「ちょっとまってね、調べてから伝えるね」といって、後ほど伝えてあげてください。
包括的性教育に精力的に取り組まれておられる埼玉医科大学産婦人科高橋幸子先生が、ご講演の際にご紹介されていた生と性の情報に関するサイトをこちらでも共有します。
それぞれに、伝える内容が、うまく整理されています。
(今後、書籍を入荷できたら、あすなろの木の前の「まちかど図書館」に貸出本として配備します。しばし、お待ちを。)
きちんと伝えていく積み重ねで、自分の体を自分で守れる子、自分の体の自己決定ができる子に育ちます。
(参考:自分の体の自己決定、性的同意とは?動画解説 https://youtu.be/xxlwgv-jVI8)
●世界の性教育 国際セクシュアリティ教育ガイダンス
https://sexology.life/
https://sexology.life/world/
●#つながるBOOK
https://www.jfpa.or.jp/
●女性の健康教育プログラム まるっと
https://marutto-woman.jp/
https://marutto-woman.jp/
●生理かんぺきブック
http://ribon.shueisha.co.jp/
<書籍>
●
年末年始、いつもより忙しいと感じています。
救急の手法について、紙上で整理されていたため、共有いたします。
最後に書かれていますが、元気のある発熱は、家で様子が見れます。
***********朝日新聞2022.12.30*******************

************毎日新聞2022.12.30*******
*********毎日新聞2022.12.29******
********国立感染症研究所*******
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2559-cfeir/11727-20.html
小児科医が待ち望んだ成育基本法。
法律ができたあとは、その法律を育てていかねばなりません。
育てるためには、声を水のように届けねば…
*****園田先生SNS******
小児科のひとつの大きな課題が、本日11/30、朝のNHKで取り上げられていました。
「移行期医療」
成人分野・地域の医師と小児科専門分野がうまく連携をして、クリアしていきたい課題です。
NHK:小児科にかかり続ける大人の患者 成人診療とのはざまで何が | NHK | 医療・健康
https://www3.nhk.or.jp/news/
ご家庭、学校、かかりつけ医、それぞれができるところで、学びの機会をつくっていきたいものです。
●中学生、高校生自身が、「#つながるBOOK」で学べます。
Web版 https://www.jfpa.or.jp/tsunagarubook/
PDF版 https://www.jfpa.or.jp/tsunagarubook/tsunagarubook.pdf
●産婦人科医 高橋幸子先生 サイト
https://sakko0607.wixsite.com/sakko/about
参考本:
【問い】ゲーム行動症について教えて下さい。
【回答】
スマホやゲーム依存が、小学生をはじめ若い世代を中心に問題となっています。コロナの影響でテレビ・DVD・スマホなど見続けるスクリーンタイムが増えさらに依存が悪化しています。ニコチンよりもスマホの依存性が強いことや、スマホやゲームはテレビの4倍の刺激があるとも言われています。それら依存により感情コントロールができず、怒りやすくなり、暴力に発展もします。アルコールや薬物と同様に脳の報酬回路に変化が起きています。
ゲーム行動症は、今般新しい疾患のカテゴリーとしてできました。ゲームのコントロールができず、生活の中で何よりも優先され、問題があってもし続ける状態をいいます。ADHD、自閉症、うつなどとの合併も多いです。
電子スクリーンよりも睡眠や運動、リアルな体験がとても大切です。スマホを所持するのは遅い方がよいし、寝る1〜2時間前は画面を見ないで目を休めましょう。小児科医らは、2歳までテレビ・ビデオを控えること、スクリーンタイムを2時間以内、ゲームは30分以内などの提言を出してきました。香川県では、ネット・ゲーム依存症対策条例も制定されています。
『学校現場におけるネット・ゲーム依存予防対策マニュアル』(同県)や『ゲーム依存相談対応マニュアル』(厚労省)、スマホ依存防止学会からの情報が参考になります。
子どもの心の発達、体の発達そして学力の向上に最も大事なものの一つは、睡眠です。
小学生9-10時間、中学生8-9時間。
必ず、とってほしいところです。
小児科学会の学術集会でも睡眠の大切さがテーマに上がります。
公衆衛生の学会でも、睡眠がテーマで、シンポジウムが開催されています。
朝日新聞の記事で内村直尚氏は、夜型社会を変えるべきと述べられています。
小中学生に睡眠をとるようにいうよりもなによりも、実は、子ども達に夜遅くまで起きることを強要する社会自体が変わらなければならないことに同感です。
******朝日新聞2022.10.30******


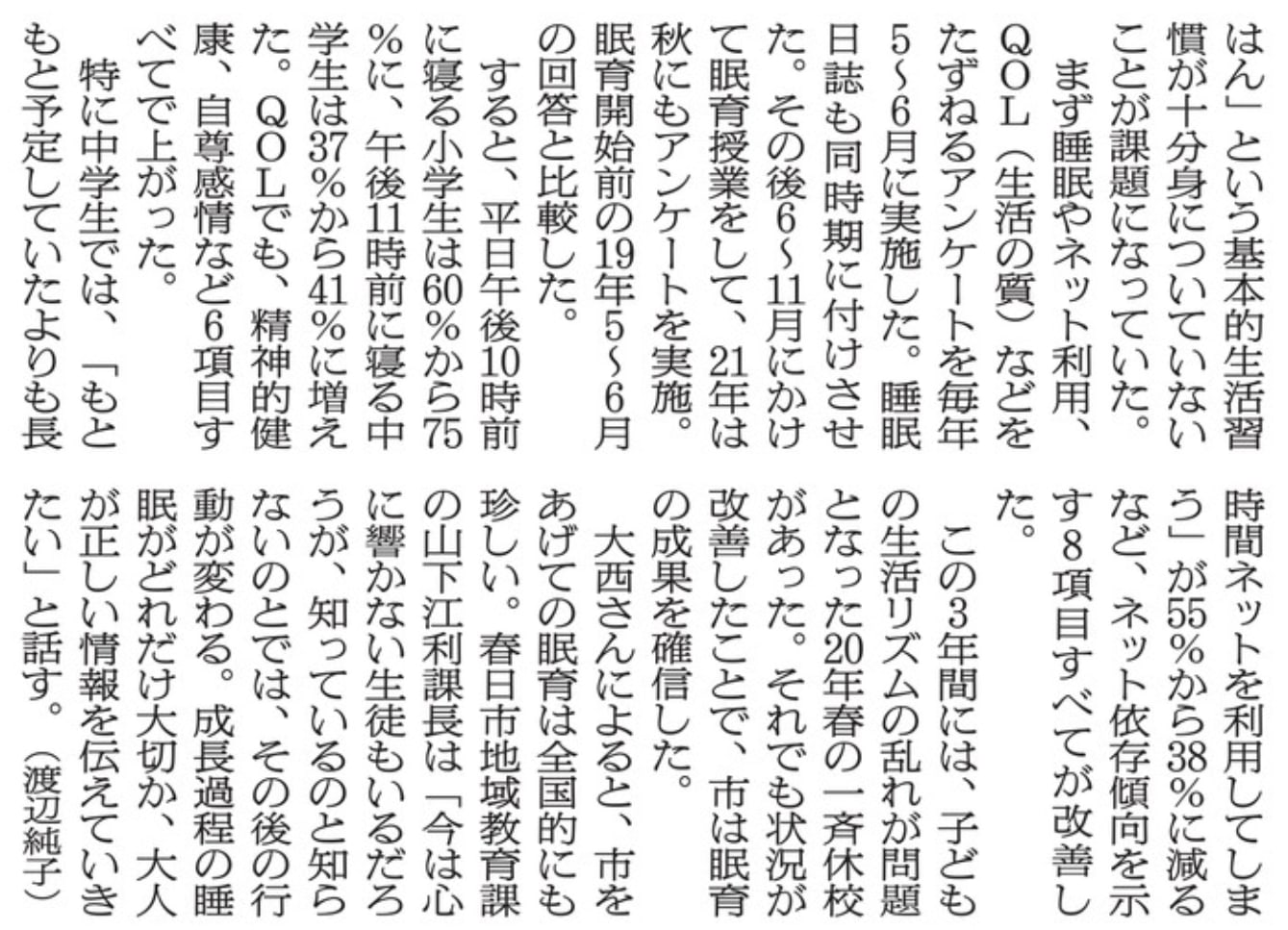
小児科医 豊川先生からの情報。
子どもの自傷行為 叱らないで
(20221013朝日新聞27面)
子どもの自傷行為 叱らないで。
7人に1人、誰にでも起こりうる。
何か意味がある。観察して、心の内に思いをはせて。
しんどいって言えない。
シェアさせていただきます。
子宮頸がんワクチンは、現在、2価と4価が、定期接種の対象として実施しています。
自費で実施してきました9価が、来年度から定期接種の対象になります。
カバーする範囲が広がり、朗報です。
*****朝日新聞2022.10.5******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15436245.html
後部座席窓からの転落事故。偶然、SNSで見つけました。
映像の子どもは大丈夫だったようですが、お気を付けください。
子どもは、頭が相対的に大きく(重心の位置が大人と異なります。)、身を乗り出すと、バランスを崩し、頭から落ちます。
*******ヒロクライム様 SNS**************
https://twitter.com/tannokasa4/status/1576108401540493313





















