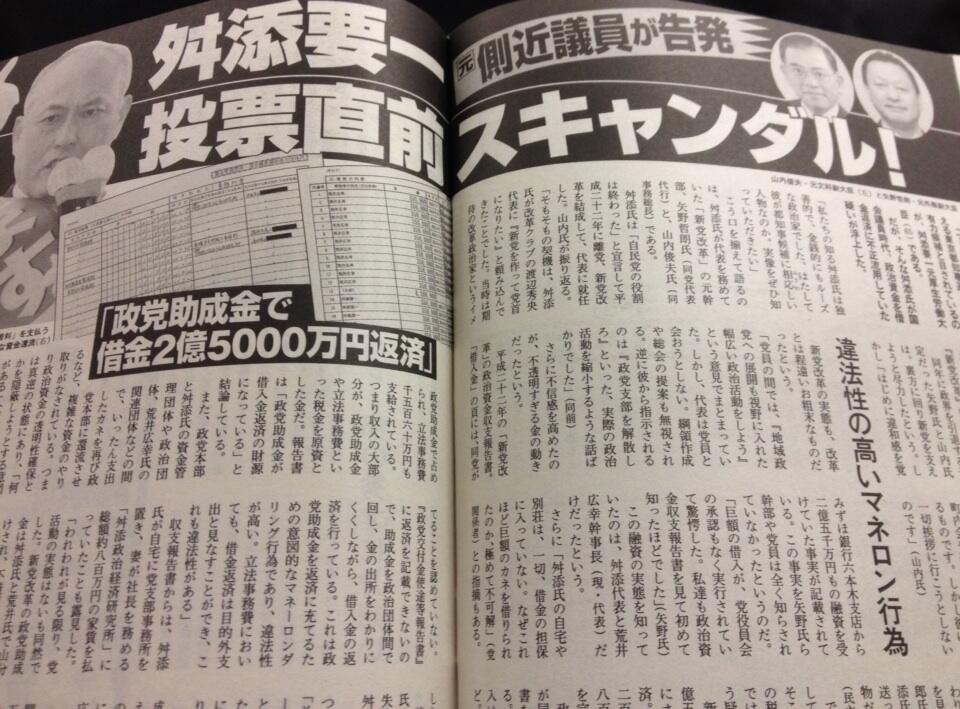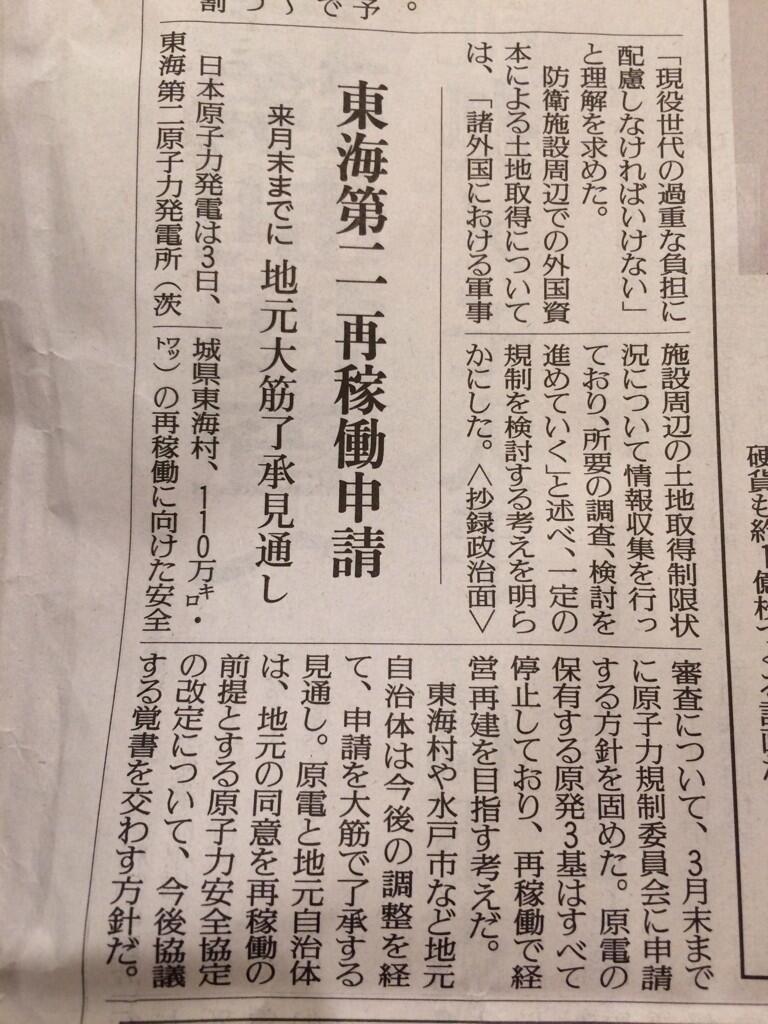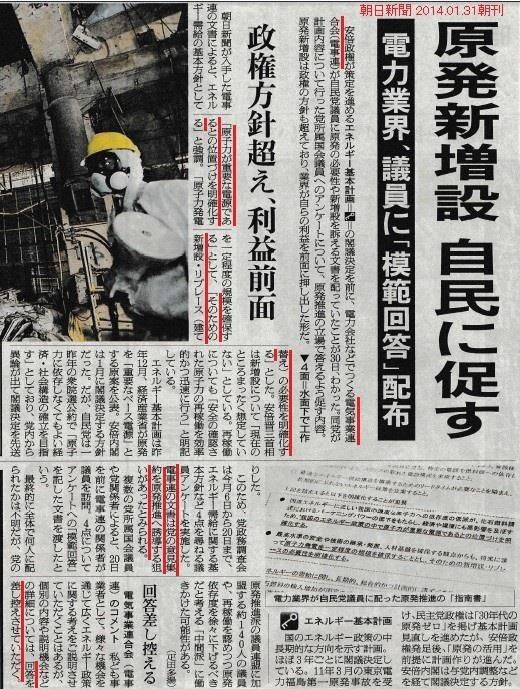参考になる考え方故、こちらでも、該当箇所を掲載します(自分の考察を深める、メモとしても)。
問題となる民法条文、現行の条文です。
(法定地上権)
第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
〜法定地上権の成立要件〜
1、抵当権設定時の土地と建物が存在していること。
2、抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属していること。
3、土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること。
4、競売が行われて土地と建物が別異の者に帰属すること。
******最高裁ホームページ*******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120845115650.pdf
裁判官千種秀夫の補足意見は、次のとおりである。
私は、本件において、法定地上権の成立を認めない法廷意見に賛成するものであ
るが、その理由について若干補足しておきたい。
一 我が国の民法は、土地と建物を別個独立の不動産としているため、同一所有者
に属する土地とその地上建物のいずれかに抵当権が設定されそれが競売された場合
には、土地と建物が別個の所有者に帰属するに至る結果、建物所有者がその敷地の
所有者に対し敷地の利用権を主張することができず、建物を収去せざるを得なくな
るおそれがある。法定地上権の制度は、このような事態に伴う社会経済的な損失を
防止する目的から、そのような場合には、「抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付キ地上
権ヲ設定シタルモノト看做ス」こととし(民法三八八条)、建物所有者に敷地利用
権を保証し、建物を収去しなくてもすむように配慮したものである。
二 そのような制度の目的からすれば、土地が数人の共有に属する場合においても、
同様な事態にあっては、同様な結果になることが好ましいともいえる。しかし、土
地の共有者は、その共有持分自体を担保に供することはできても、当該共有地上に
単独で地上権を設定することはできない。そのため、土地の共有持分が競売された
場合においては、共有者全員について建物所有者のために地上権を設定したとみな
- 4 -
し得るような特段の事情がある場合でない限り、建物所有者は法定地上権を取得す
ることができないことになる。すなわち、たとえば甲、乙共有の土地上に甲所有の
建物があり、甲が自己の土地共有持分に抵当権を設定しこれが競売された場合を考
えると、甲については法定地上権を設定したものとみなし得る事情が存在するとし
ても、乙としては、共有地上に地上権が設定されることは予期しないところであり、
もしこれが認められることになれば、自己の意思に反して不当な負担を課せられる
結果となりかねない。そのため、判例は、かかる事案においては、法定地上権の成
立を否定してきたのである(最高裁昭和二六年(オ)第二八五号同二九年一二月二
三日第一小法廷判決・民集八巻一二号二二三五頁参照)。
三 それならば、右の事例で、乙に甲のため地上権を設定する意思があったなら法
定地上権を認めてもよいか。これは、解釈論として当然に予想される問題である。
殊に、甲外数名が敷地を共有するとともに地上建物をも共有する場合に、全員が全
員の共同の債務を担保するため同一債権者に対して共同で各持分について抵当権を
設定した場合を想定すると、他に特段の事情のない限りは共有者全員を束ねて一人
とみることも可能であり、その結果は、民法三八八条をそのまま適用することもで
きることになるのではないか、それならば、更に一歩を進めて、土地共有者全員が、
そのうちの一人の債務を担保するため、共同で各自の共有持分に抵当権を設定した
場合にも同様なことがいえるのではないか。そうした疑問が起こるのも当然である。
四 原審の確定するところによれば、前記のとおり、本件土地は被上告人B1とそ
の妻子の三名の共有に属していたところ、右共有者らは、本件土地につき、B1を
債務者として国民金融公庫のために抵当権を設定しその旨の登記を経ており、公庫
は、右抵当権に基づいて本件土地全体につき競売手続を申し立て、上告人が本件土
地全部を競落し、その所有権を取得したというのである。しかも、本件土地建物は、
もともとB1の父DがB1に贈与する意向であったが、土地については、B1に単
- 5 -
独で贈与税を支払う資力がないことから同人とその妻子に贈与し、建物については、
B1が事業に失敗しその債権者から差押えを受けるおそれがあったため、Dの所有
名義にしておいたところ、同人の死亡によりB1を含む九名の相続人の共有になっ
たというのである。したがって、このような事実関係を内部的にみれば、被上告人
B1ら三名は、ほとんどB1一人と同視し得る実情にあり、B1の妻子らとしても、
地上建物所有者らのために法定地上権が発生することは当然予想していたとみるこ
とも可能であろう。
五 しかしながら、法定地上権は競売によって生ずるものであるから、その成否の
解釈に当たっては、競売手続の適正迅速な進行とその結果として形成される法律関
係の確実性の確保という観点を看過することはできない。そうでなければ、取引の
安全と競売手続への信頼を確保することができないからである。従来、法定地上権
の解釈論は、先に掲げた民法の趣旨、目的のゆえに、実体法学者から、なるべく建
物所有者の土地利用権を確保する方向で論じられてきたかに思われる。しかし、そ
の結果の妥当性もさることながら、競売手続が終了した後になって法定地上権の有
無が訴訟で争われること自体にも問題のあることを指摘しなければならない。
六 今日、このような問題が実務上注目されるようになったゆえんは、一に土地利
用権が一個独立の価値権として評価され、ひいては課税あるいは取引の対象とされ
るに至ったことにある。その上、地価の上昇に伴い、課税その他の理由から土地を
単独で所有することができず、そのために土地共有関係が増加しつつあるという社
会経済的事情があり、これが背景となって、問題の解決を更に困難にしている。
地上権はもとより土地賃借権が法的に手厚い保護を受け、それ自体が財産権とみ
なされるということは、反面、こうした用益権の付着した土地の底地価格が低下す
ることを意味する。その結果、土地の競売手続においては、その地上に建物が存す
るか否か、また、その建物の所有者がいかなる土地利用権を有するかが大きな問題
- 6 -
となり、競落後法定地上権が生ずるか否かも売却価額に大きな影響を与えるに至る。
競売の対象とされた土地の売却代金によりどれだけの被担保債権の弁済が受けられ
るか、はたまた、競売後地上建物の所有者又はその居住者はその建物をそのまま保
持し又はこれに居住し続けることができるかどうか、こうした問題は、関係者とし
ては無視できない大きな利害関係のある問題である。その結果、競売手続を進行さ
せる執行裁判所としては、競売物件の評価に当たって、これらの権利の有無を適確
に判断しなければならないこととなる。
通常、競売不動産については、執行裁判所の執行官が不動産の現況を調査し、土
地利用関係を確認し、この報告を基礎として評価人が右不動産の評価をし、しかる
後裁判所により物件明細書が作成され、最低売却価額が決定されるのであるが、も
しこの段階で複雑な事実認定と困難な法律判断を要することになると、競売手続を
適正迅速に処理することは困難とならざるを得ない。したがって、この段階におい
て判断の資料に供しうるのは、登記簿の記載等公示されだれにでも分かる客観的資
料のみに限る必要がある。先にも触れたとおり、本件においては、土地共有者らは
主債務者とその妻子であって、対債権者の関係のみに限ってみれば、主債務者の妻
子はこれと同一視し得ないではない。しかし、そのような内部事情は登記簿上だれ
でも確知できるものではなく、多くの場合訴訟手続ないしはそれに準ずる事実認定
手続を経なければ明確にし得ない事情である。そのような事情を競売手続において
考慮することは適当とはいえない。
それならば、こうした主観的事情を捨象し、ただ土地の共有者三名がその一人の
債務のため同一債権者に対し各共有持分について共同して抵当権を設定したという
事実(これは登記簿上確認できる。)だけで他の土地共有者らの地上権設定の意思
を認め、法定地上権の成立を肯定してよいかが問題となる。しかし、これまた、直
ちに積極の結論を導くことは容易ではない。三名の各共有持分は、それぞれの共有
- 7 -
者の資産であるから、一般論としていえば、各人はそれぞれの持分を他に処分しあ
るいはそれに自己の債務のため抵当権を設定することも可能であり、また逆に、そ
れぞれの債権者からそれぞれの持分を差し押さえられた結果これらが各個に競売さ
れ、他の者がその共有持分を取得することも考えられる。このように、現実の競売
の時点においては、三名が共同して抵当権を設定した時と異なった状況の生じてい
る場合もあり得るのであって、そのような場合に、どの時点のどのような事情をも
って法定地上権の発生を確定しうるかは一律に決し難く、立法等による明確な基準
の設定をまたない限り、統一的な処理は困難である(また、本件にあっては、被上
告人B1は九名の建物共有者のうちの一人にすぎないという事情も考慮されなけれ
ばならないであろう。)。
以上のように考えると、先に述べたように他の土地共有者らについても建物所有
者のために地上権を設定したとみなし得るような特段の事情がある場合(最高裁昭
和四一年(オ)第五二九号同四四年一一月四日第三小法廷判決・民集二三巻一一号
一九六八頁参照)を除いて、土地共有持分の競売に当たっては、当然には法定地上
権は発生しないものとし、なるべく画一的に処理することが相当であるといわなけ
ればならない。
七 なお付言するに、立法論としていうならば、法定地上権の目指す目的は、必ず
しも地上権という用益物権の成立を認めなくとも、賃借権あるいは使用借権その他
何らかの敷地利用権を確保してやれば足りるといえる。
ただ、民法制定当初は、他人の土地を利用して建物を建築所有する方法としては
地上権の設定が予想されていたためこのような制度が設けられたにすぎない。しか
し、その後の土地利用の実態をみると、建物敷地として他人の土地を利用する場合
には、賃貸借又は使用貸借契約を利用する場合が多く、かつまた、その後の立法に
よって、土地の賃借権は地上権と同様に手厚く保護され、物権に劣らぬ強力な権利
- 8 -
とされるに至ったため、今日では、建物所有のために地上権が設定されることはま
れであり、専ら賃借権が利用されるに至っている。加えて、借地権に関しては、累
次の法改正により、今日では、共有の建物に関しては、他の者と共に有することと
なるときに限り、自己借地権の設定も認められ(借地借家法一五条)、また、借地
権をめぐる問題の処理のためには非訟手続も整備されるに至っている。そのような
状況の下においては、現行の法定地上権の制度は陳腐化し、解釈によって今日の複
雑な事態に適応させていくことは困難であるばかりでなく、土地利用権の確保に偏
重することは競売手続への信頼をおびやかすおそれなしとしない。そのような意味
からすれば、法定地上権の制度は、法定借地権等今日通常行われている土地利用権
を内容とするものに改め、かつ、その内容を法定し、あるいは借地非訟事件手続に
より一定の範囲内でその条件を確定する道を開く(現在でも、法定地上権成立後そ
の地代は裁判所が定めなければならないこととされている(民法三八八条但書)。)
等今日の社会経済の実情に合致した制度とすることが望ましいと考える。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
裁判官 尾 崎 行 信
-