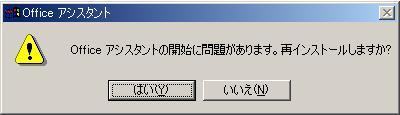kan-haru blog 2007
< 総合INDEX へ
排熱回収ボイラー俯瞰
横浜火力発電所のACC発電設備の航空写真を見ると、巨大なタービン本館から7、8号系列各4基の排熱回収ボイラーの配列配置と、そこから高さ200mの排気塔まで導かれている排気道のレイアウトがよく分かります。

左:タービン本館からの排熱を処理する排熱回収ボイラー(クリックで拡大)
中:7号系列排熱回収ボイラーから排気筒への排気導管(クリックで拡大)
右:排熱回収ボイラーからの排気を放出する7号系列排気塔口(クリックで拡大)
ACC発電設備見学
展望塔の見学を終え、貸切バスでタービン本館、排熱回収ボイラーとツインタワーを一周する形でトウィニー・シアターに隣接した中央操作室に行きました。
中央操作室では、見学説明員の案内により見学を行い、先ず最初にACC発電の仕組みの説明を聞きました。
発電原理は、ジェット機エンジンと同じ構造のガスタービン内で、圧縮空気とともに天然ガスを燃やして発電機を回転させ、さらにその排気ガスを排熱回収ボイラーに送り、その熱で蒸気をつくります。作った蒸気でさらにタービンを回転させ、ガスタービンの回転と合わせて発電機を回して発電します。
蒸気タービンは、高圧、中圧、低圧の3種類のタービンで構成されており、ACC発電機の熱効率は49%もあり、在来の汽力発電の40%と比較するとかなりの効率です。このうち熱再利用の蒸気による熱効率は1%が寄与しているとのことです。

左:ACC発電の仕組みの説明パネル(クリックで拡大)
中:タービン本館の発電設備模型(クリックで拡大)
右:ガスタービン、蒸気タービン、発電機模型(クリックで拡大)
タービン本館見学
ACC発電の仕組みや発電設備の構造を理解した後、タービン本館で発電設備の中枢機能のガスタービン、排熱の再利用で回転する蒸気タービンと発電機を見学しました。7、8号系列の8基の発電設備が稼動している、戦艦大和がすっぽりと入る建屋はさすが大きく壮観でした。

左:8号系列の発電設備(クリックで拡大)
中:7号系列の発電設備(クリックで拡大)
右:発電設備の左方から発電機、中央円筒系は高圧・中圧・低圧蒸気タービン、右方箱状はガスタービン(クリックで拡大)
中央操作室見学
タービン本館とT字状につながっている中央操作室は、横浜火力設備を集中監視制御を行う中枢設備で、24時間体制で運用しております。中央監視室の映像は、撮影禁止のため横浜火力発電所ホームページから引用しました。
火力発電所の目的は、電力の供給がピーク需要時間に限られ日中のみの発電となります。見学時間は、ちょうど15時頃で8号系列の1、3、4号機の3基が稼働しておりました。電力の需要の年間のピークは、横浜火力発電所管内では7、8月の夏季が最大となります。

左・中:ACC発電設備の発電量表示盤
右:中央監視室(東電から引用)
キリン横浜ビアビレッジ見学
火力発電所の見学を終え、貸切バスにてキリン横浜ビアビレッジを見学しました。
キリン横浜ビアビレッジは、昨年10月22日に異業種交流会分科会の有志で見学(「イベント(9) キリン横浜ビアビレッジ見学」参照)をしたところで、今回2回目の見学です。
横浜で生まれたキリンビールは、2007年2月23日に創立100周年を迎え工場見学施設をリニューアルし、ブルワリーツアーガイドがビールの製造工程(原料、仕込み、発酵・貯蔵、ろ過、パッケージング)の案内で見学します。工場内は、撮影禁止のため写真掲載はありません。

前回の見学は、休日に行ったので工場ラインは停止してましたので、平日の今回は期待してたのですが、またも停止でガッカリしました。
麦芽やホップに触れたり、まだアルコールになっていない麦汁を試飲し、工場の環境への取り組みなどを聞いたりして、1人2毎渡された券で出来たてのビールを試飲して見学が終了です。
見学後、希望者による構内レストランのビアポートで折紙付き、最高レベルの状態
のビールで懇親しました。
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております。(5月分掲載Indexへ)
カテゴリー別Index ITと技術 カテゴリー別総目次 へ
<前回 ITと技術 横浜火力発電所とキリン横浜ビアレッジ見学 その2 へ
次回 ITと技術 Web 2.0時代のパソコン活用のヒント へ>
< 総合INDEX へ
排熱回収ボイラー俯瞰
横浜火力発電所のACC発電設備の航空写真を見ると、巨大なタービン本館から7、8号系列各4基の排熱回収ボイラーの配列配置と、そこから高さ200mの排気塔まで導かれている排気道のレイアウトがよく分かります。

左:タービン本館からの排熱を処理する排熱回収ボイラー(クリックで拡大)
中:7号系列排熱回収ボイラーから排気筒への排気導管(クリックで拡大)
右:排熱回収ボイラーからの排気を放出する7号系列排気塔口(クリックで拡大)
ACC発電設備見学
展望塔の見学を終え、貸切バスでタービン本館、排熱回収ボイラーとツインタワーを一周する形でトウィニー・シアターに隣接した中央操作室に行きました。
中央操作室では、見学説明員の案内により見学を行い、先ず最初にACC発電の仕組みの説明を聞きました。
発電原理は、ジェット機エンジンと同じ構造のガスタービン内で、圧縮空気とともに天然ガスを燃やして発電機を回転させ、さらにその排気ガスを排熱回収ボイラーに送り、その熱で蒸気をつくります。作った蒸気でさらにタービンを回転させ、ガスタービンの回転と合わせて発電機を回して発電します。
蒸気タービンは、高圧、中圧、低圧の3種類のタービンで構成されており、ACC発電機の熱効率は49%もあり、在来の汽力発電の40%と比較するとかなりの効率です。このうち熱再利用の蒸気による熱効率は1%が寄与しているとのことです。

左:ACC発電の仕組みの説明パネル(クリックで拡大)
中:タービン本館の発電設備模型(クリックで拡大)
右:ガスタービン、蒸気タービン、発電機模型(クリックで拡大)
タービン本館見学
ACC発電の仕組みや発電設備の構造を理解した後、タービン本館で発電設備の中枢機能のガスタービン、排熱の再利用で回転する蒸気タービンと発電機を見学しました。7、8号系列の8基の発電設備が稼動している、戦艦大和がすっぽりと入る建屋はさすが大きく壮観でした。

左:8号系列の発電設備(クリックで拡大)
中:7号系列の発電設備(クリックで拡大)
右:発電設備の左方から発電機、中央円筒系は高圧・中圧・低圧蒸気タービン、右方箱状はガスタービン(クリックで拡大)
中央操作室見学
タービン本館とT字状につながっている中央操作室は、横浜火力設備を集中監視制御を行う中枢設備で、24時間体制で運用しております。中央監視室の映像は、撮影禁止のため横浜火力発電所ホームページから引用しました。
火力発電所の目的は、電力の供給がピーク需要時間に限られ日中のみの発電となります。見学時間は、ちょうど15時頃で8号系列の1、3、4号機の3基が稼働しておりました。電力の需要の年間のピークは、横浜火力発電所管内では7、8月の夏季が最大となります。

左・中:ACC発電設備の発電量表示盤
右:中央監視室(東電から引用)
キリン横浜ビアビレッジ見学
火力発電所の見学を終え、貸切バスにてキリン横浜ビアビレッジを見学しました。
キリン横浜ビアビレッジは、昨年10月22日に異業種交流会分科会の有志で見学(「イベント(9) キリン横浜ビアビレッジ見学」参照)をしたところで、今回2回目の見学です。
横浜で生まれたキリンビールは、2007年2月23日に創立100周年を迎え工場見学施設をリニューアルし、ブルワリーツアーガイドがビールの製造工程(原料、仕込み、発酵・貯蔵、ろ過、パッケージング)の案内で見学します。工場内は、撮影禁止のため写真掲載はありません。

前回の見学は、休日に行ったので工場ラインは停止してましたので、平日の今回は期待してたのですが、またも停止でガッカリしました。
麦芽やホップに触れたり、まだアルコールになっていない麦汁を試飲し、工場の環境への取り組みなどを聞いたりして、1人2毎渡された券で出来たてのビールを試飲して見学が終了です。
見学後、希望者による構内レストランのビアポートで折紙付き、最高レベルの状態
のビールで懇親しました。
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております。(5月分掲載Indexへ)
カテゴリー別Index ITと技術 カテゴリー別総目次 へ
<前回 ITと技術 横浜火力発電所とキリン横浜ビアレッジ見学 その2 へ
次回 ITと技術 Web 2.0時代のパソコン活用のヒント へ>