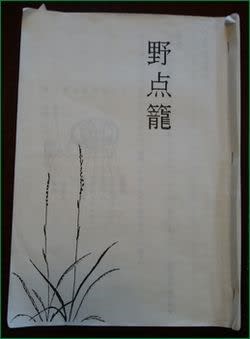「昨日○○さんさんからご招待のお手紙を頂きました。
参加のお返事が必要との事でしたが・・・・
楽しみな反面、初めてのことで戸惑っています。」
と初めてお茶事のお客様として参加する方。
早速参考になるお返事をお見せして、こんな風にとお話ししました。
何しろ、聞いてはいたものの巻紙初体験ですから、ちょっと慌てますね。
ご招待をしたご亭主役の方も、当日のお客様四名に巻紙で招待状です。
これもまた初めてですから、さぞかし大変だったのでは。
稽古茶事とはいえ亭主さんは初陣です。
皆さんで協力して助け合わなくては無事に終えることはできないでしょう。
ご亭主に名乗り出で、茶事の勉強の機会を作ってくださったことに感謝しながら、
客も亭主も全力で(と私は発破をかけ)頑張ってください。
このように茶事に向かって、それぞれの役割で準備も進んでいます。
さて私のしなければならない準備はと、できることから始めました。
まず御茶席用の座布団をきれいにしましょうと。
新しい生地でカバーを変えようかと思ったのですが、
まだまだ使えますから洗って掛け直すことにし、四枚仕上げました。
これとお尻の下に敷く枕を点検して、完了です。
さて次はガラスもそろそろきれいにしておかなくてはと思っていたら、
お稽古の後で社中の方が、
「私得意なんです。早いんですよ。」
とベランダに面した三部屋分六枚のガラス戸を、
あっという間にきれいにしてくださいました。


ほら、ガラス戸がないと思えるくらいきれいになりました。
しゃがむ姿勢がまだ怖くてできないので、助かりました。
それではそろそろ当日使う風炉に灰を入れて、
灰形造りの準備をと思っていたら、当日水屋担当の方が、
「灰形のお勉強をしたいので、させてください。」と。
初めのころはお料理から何からすべて頑張っていたことを思うと、
今は、気が付いた方がどんどん申し出てくださるので、夢のようです。
それだけ皆さんが経験を積まれて、
役割分担ができるようになったということですね。
体力のいる仕事は何とかしていただけるので、
私は細かい事と、頭と口だけ働かせばよいようです。
"頭"は最近ちょっと危ないのですが、"口"は大丈夫です。