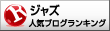昨年6月に書いたブログ記事【私の地下ジャズ愛好癖】偶想破壊ピアニスト、バートン・グリーンを論ずる~第1回:ESPの2作『Burton Greene Quartet』『On Tour』、そしてマイナスからのスタート。を英訳してバートン・グリーン本人に送ったところ、すぐに届いた返事には『バートン・グリーン事件』についての説明が書かれていた。アメリカ人が書いた追悼記事の中でも触れられているように、リロイ・ジョーンズ(のちにアミリ・バラカ)による批判的(嘲笑的)な記事は、本国でも物議を醸し、バートン・グリーン本人の活動にも大きな影響を及ぼした。それがアメリカを離れヨーロッパへ移住するきっかけだったという。しかしながら、音楽シーンの革命のひとつとされる60年代半ばのフリージャズの爆発にもかかわらず、ニューヨークで音楽だけで経済的に身を立てることは難しく、60年代後半に多くのフリージャズ・ミュージシャンが自由の天地(聴衆と仕事)を求めてヨーロッパへ渡った事実を考えると、リロイの記事がなかったとしてもバートン・グリーンは渡欧したに違いない。しかしアメリカへ戻ることなく死ぬまでアムステルダムに永住することになった背景には差別体質が残る母国への忸怩たる想いがあるようだ。
今回はバートン・グリーン本人の発言から『バートン・グリーン事件』の真実を探ることにしよう。
Q:60年代半ば、フリージャズはブラックパワーとの関連が強まっていました。それは問題になりましたか?
フリージャズのイノベーターたちから人種差別を受けたことはありません。オーネット・コールマン、アルバート・アイラー、ジュゼッピ・ローガン、セシル・テイラーやサニー・マレイは私に対してそんな雰囲気を感じさせたことはありません。アーチー・シェップも同様で、『ダウンビート』誌で私をシーンのトップ・ピアノプレーヤーの一人だと言ってくれました。問題はリロイ・ジョーンズです。彼はユダヤ系白人の妻と離婚して子供と一緒に置き去りにして、ダシキ(西アフリカの衣装)とサングラスを身につけてニューアークのゲットーに移り住んだのです。彼はどうやら中流階級のいい身分の黒人で、白人の大学で学んだようです。しかし、ある日突然、白いものはすべて嫌悪の対象になり、リロイはサングラスをかけてすべてが黒く見えるようになってしまったのです。
Q:彼は、1966年の『ダウンビート』のコラム「アップル・コア」で、かなり堂々とあなたを攻撃していますね。
「バートン・グリーン事件」ですね(訳注:のちに著書『ブラック・ミュージック』に収録)。本当の話は、ファロア・サンダースとマリオン・ブラウンがニューアークで一緒に演奏しようと誘ってくれたのです。しかし会場にあったのは、鍵盤が少なくとも25個もない(しかもピアノの真ん中の!)めちゃくちゃなピアノで、音を出すためには上も前も下も外して、内部をマレットとドラムスティックで弦を擦ったり叩いたりしなければなりませんでした。それを見たリロイは「バートン・グリーンはピアノを弾くのではなく、拳や棒で叩くだけだ。これがシーンでヒップな若い白人ピアノ奏者と呼ばれる男だ」などと貶したのです。まるで私が第2のビックス・バイダーベックかベニー・グッドマンのように盗みを働いているかのように。私は頭にきて反論を書き始めたのですが、バイアード・ランカスターとサニー・マレイに出会って「代わりに音楽で勝負しろよ」と言われてやめました。
Q:一度は『ダウンビート』のオフィスに火を付けようとしたサニーがそう言うとよほどのことですね。
本当ですか?(笑)まあ、その頃はみんなが、短い導火線と長い爆発(かんしゃく玉)を持っていました。サニー、ミルフォード(グレイブス)、ラシッド(アリ)の3人は、すべてはヴァイブレーション次第だと分かっていたんです。サニーは特に強烈で、私によく言ったものです。「バートン、あそこに壁があるだろう。俺はあの壁に取り組んでるんだ。いつかあのクソッタレ野郎は倒れるだろう」とね。彼は本気でした!とにかく、私は『ダウンビート』に対して何を書けばよかったのでしょうか?白人にも金玉があるとでも?私は苛立っていて、こうした箱庭的な考え方にうんざりしました。私がアメリカを離れた理由の1つはそこにあります。ロウアー・イーストサイドの緊張の高まりが私の神経に障りはじめました。ジャンキーに3回も騙され、大家には家賃を値上げされました。死後硬直が始まったら、移動した方がいい、と歌手のバブス・ゴンザレスがよく言っていました!そういうわけで、1969年に我々は大挙してパリに行ったのです。
(以上、2003年12月22日アムステルダムでのBurton Greene Interview by Dan Warburtonより)
その何年か後に、リロイの人種差別な描写は、本人から私に対して直接撤回されました。私が住んでいるアムステルダムで行われたポエトリー・フェスティバルに彼が出演した後、一緒に飲みに行ったのです。そこで彼は、当時ブラックナショナリズムに傾倒していたからそう言っただけだったと話してくれました。後にそれを諦めて仏教に傾倒し、その後は他の「イズム」に傾倒していったそうです。(*)
当時、攻撃を受けた白人のミュージシャンは私だけではありませんでした。例えば、素晴らしいサックス奏者で前衛画家のフランク・スミスは、同じく黒人作家のA・B・スペルマンから同じように攻撃されました。その時私が感じたのは、 60年代半ばから後半にかけての(白人だけでなく黒人の)意識の爆発的な高まりの中で、特に黒人作家たちは、黒人ミュージシャンが正当に評価されることを確実にしたかったのではないか、ということです。
リロイが批評の中で言わなかったのは、私がファロア・サンダースとマリオン・ブラウンに誘われて出演したということです。まるで私がライブに侵入したかのような言い方をしたのです!
誰もが知っている通り、アメリカ(アモリカ)では今も昔も人種差別が行われています。私がうんざりしてヨーロッパ、アムステルダムに移った理由はここにあります。
(以上、2020年6月3日Burton Greeneから筆者への私信)
*詳細はバートン・グリーンの自伝『Memoirs of a musical " pesty mystic " : Or, from the ashcan to the ashram and back again Unknown Binding』(2001 / Cadence Jazz Books)に詳しいとのことだが未読である。

結果的にヨーロッパで生活し活動することにより、自分の好きな音楽を84歳で亡くなるまで続けられたのだから、バートン・グリーンの人生は幸福だったに違いない。本国で活動していたらもしかしたらメジャーな成功もありえたかもしれないが、それにより失うものも大きかったかもしれない。そう考えると、もう一人筆者の敬愛するミュージシャンが頭に浮かぶ。ロック詩人のエリオット・マーフィーである。70年代前半にブルース・スプリングスティーンなどと共に第2のボブ・ディランとして大々的にデビューし、メジャー・レーベルから4枚のアルバムをリリースしたのちパリに移住しヨーロッパのインディレーベルから40作近いアルバムをリリースし現在もマイペースに活動するエリオットも誰に媚びることなく我が道を行く理想のミュージシャン像である。
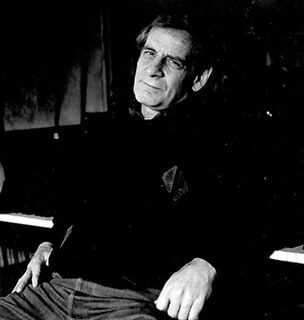

バートンと
エリオット
共演したらよかったな
なんと、エリオット・マーフィーは80年に『Elliott Murphy / Affairs(エリオット・マーフィー事件)』というミニアルバムをリリースしている。

Elliott Murphy - Extended Affairs 1980 (Full Vinyl 1989)