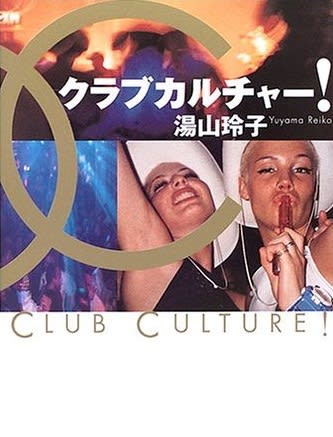サンスター オーラツー presents
25th ANNIVERSARY J-WAVE LIVE 2000+13
三代目 J Soul Brothers from EXILE/加藤ミリヤ/きゃりーぱみゅぱみゅ/三浦大知/RIP SLYME/家入レオ
国立代々木競技場第一体育館
J-WAVEは今年、開局25周年を迎えます。
J-WAVEと縁の深い、日本を代表するアーティスト達が今年も集まってくれます。
真夏の週末を素晴らしい音楽と共に、東京のど真ん中・代々木第一体育館で一緒に過ごしましょう!さまざまな企画盛りだくさんでお待ちしています。
(ちなみに「2000+13」は「ニセンジュウサン」と読んでください)
(公式サイトより)

「真夏のど真ん中、灼熱の太陽に負けず、熱いライヴ現場で汗を流そう」企画・第2日目。1.4万人と一緒にJ-POP王道体験。
「なんだこれくしょん」リリース後初のきゃりーぱみゅぱみゅなので、対バンが誰かも確認せず迷うことなくチケット購入。改めてチェックして、2008年から続くJ-WAVE主催の一大イベントで、超人気都市型夏フェスであることを知る。J-WAVEはクラブチッタとクラブクアトロと同じく今年25周年。そもそも「J-POP」という名称自体、1988年に開局したばかりのJ-WAVEとレコード会社の合議で誕生したと言うから、このイベントこそJ-POPの頂上決戦であることが頷ける。ラインナップを眺めると、個人的にはあまり縁のないアーティスト名が並んでいる。ライヴを観たことがあるのはきゃりーとTHE BAWDIESだけだが、世間一般では誰でも知っている超メジャーな顔ぶれに違いない。
ジリジリ焼ける太陽の下、代々木体育館へ向かう。道行く人の列は異常に女性の姿が多い。母娘連れも目立つ。これは一体何事?と思っていたら、ほぼ全員がJSB(J Soul Brothers)のタオル、T-シャツ、フラッグなどを着用・持参している。確かに昨夜から「三代目とRIPが楽しみ♡」というツイートが多かった。座席に着くと周囲はほぼ♀♀♀♀♀♀♀♀。。。。かつて経験したORANGE RANGEの悪夢が頭をよぎる。10日前はモノノフに取り囲まれたし、アリーナではいつもアウェー&ぼっち状態である。とはいってもきゃりーちゃんを応援せねば、と気を引き締める。
出演順は明らかにされず、本番前にスクリーンで発表される趣向。次は誰かな、といワクワク感に会場が満たされる。アーティストのパフォーマンスも、イベント進行も、ステージの演出も、会場内外のサービス・物販・屋台も、とにかく盛り上げ客を楽しませることが至上命令として徹底されている。アーティストは常に「楽しんでますかー?」「盛り上がりましょう!」「ついてきてくれますか?」と呼びかけ、オーディエンスが「ウォーーーッ!」と大歓声で応えるのがお約束。J-POPとは大多数を盛り上げ楽しませることが使命なのだ。元気をもらうことを音楽に求めている人がこれほど多いことに驚愕する。特にRIP SLYMEと三代目 J Soul Brothersへの女子軍団の盛り上がりはハンパなく凄かった。ある意味、アイドル現場に於けるヲタの女子版といえるが、1万人以上の♀が一斉にキャーッ!と雄叫びを上げる迫力は、自然の脅威と同様に、人知を超えた超常現象である。王道J-POPの多数決パワーの前では、マイナーなアングラヲタは黙ってスマホを弄るしか術がなかろう。所詮日陰にしか咲くことが許されない悪の華である。
●家入レオ

今年高校を卒業したばかりとは思えぬ堂々としたステージングに感服。メロディがしっかりした歌はパワフルでいい。
●三浦大知

何かで当たったタダ券で観に行き、余りにノリが違い当惑させられた男性シンガー&ダンサー。想定外の人気にまたしても当惑。
●きゃりーぱみゅぱみゅ




我らがきゃりーちゃんが前半のトリ。会場にコアなファンは少ないが、みんなが知ってる曲ばかりなので大いに盛り上がる。前日の野外フェスで熱中症でビビったとネットニュースに出て心配させたが、もったく問題なく元気な歌と踊りを披露。初めて生で聴く「み」の破壊力と呪術性にクラクラ。9月からスタートするホールツアーが楽しみでならない。
Set List
1.なんだこれくしょん
2.インベーダーインベーダー
3.きゃりーANAN
4.にんじゃりばんばん
5.み
6.CANDY CANDY
7.つけまつける
8.ファッションモンスター
●RIP SLYME

ヒップホップやラップやDJがJ-POPのセンターであることに改めて驚く。盛り上げ役には絶好のお祭りバンド。知っている曲多し。
●加藤ミリヤ

木村カエラは好きだが、西野カナやこの加藤ミリヤは余りイメージが湧かない。ロック風の幕開けだったので、おっと思ったが、「本当の自分を信じて頑張ろう!」という前向きなメッセージと16ビートに乗せたディーヴァな歌は120% J-POPとしか表現できない。
●三代目 J Soul Brothers

人数が多すぎてAKB関係には近寄れない似非アイヲタにとっては、同様に大人数のEXILE周辺は鬱蒼と生い茂る樹海さながら。三代目ってことは初代や二代目もいるのか?調べる気はないが、盛り上げ方の妙と見事なダンスは一見の価値がある。1万人の女子の狂乱状態は滅多に体験できるものではない。
J-POP
J-LEAGUE
JeJeJet!
「J」は魔法の合言葉。