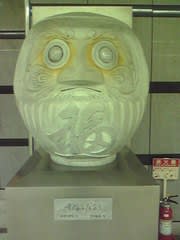いやー驚いた、驚いた。JR錦糸町駅前の錦糸公園にある、墨田区総合体育館に用事があって
でかけたら、ものすごいものが吊るしてあった。

こっ、これは……!?
王貞治の選手時代のユニフォーム(本物)。どうして墨田区の体育館に? と思ってキョロキョロ
あたりを見回すと、王さんが2009年に墨田区名誉区民になったお知らせが目に入った。

写真パネルがいっぱい。
王さんは、昭和15年(1940年)5月20日に東京市向島区吾嬬町西(現・墨田区八広西4丁目)の
中華料理店「五十番」で、中国出身の父・王仕福さんと、富山県出身の母・登美さんの間に誕生。
そして20歳まで墨田区で暮らしたというから、50年も前のことだ。

王さんからのコメント:
「小さい頃を過ごした墨田区は、私にとって野球人生の原点でもあります。今の私があるのも、
その頃の友人や地域の方々のおかげだと思っています。中でも、早稲田実業学校高等部在学
中に春の甲子園大会で優勝した際、町内でお祝いの提灯行列をしてくださったことが大変嬉しく
思い出に残っています。離れて50年になるにもかかわらず、あたたかい目で見守り続けていただ
いた故郷の皆さまに心から感謝しております」

渋いコメントだなぁ~!
巨人軍入団以後の3年間は、成績がふるわなかった王さん。昭和37年(1962年)に荒川博氏が
打撃コーチとして巨人軍に入団し、一本足打法をはじめてから数々のホームラン記録を打ち立て、
“世界の王”として花開いた。
「墨田区出身」のイメージが薄いのは、「荒川コーチ」に指導を受けたイメージが強いからだよって
うまいこというFacebookの友達がいたことを書き添えて、今回はおしまい。
でかけたら、ものすごいものが吊るしてあった。

こっ、これは……!?
王貞治の選手時代のユニフォーム(本物)。どうして墨田区の体育館に? と思ってキョロキョロ
あたりを見回すと、王さんが2009年に墨田区名誉区民になったお知らせが目に入った。

写真パネルがいっぱい。
王さんは、昭和15年(1940年)5月20日に東京市向島区吾嬬町西(現・墨田区八広西4丁目)の
中華料理店「五十番」で、中国出身の父・王仕福さんと、富山県出身の母・登美さんの間に誕生。
そして20歳まで墨田区で暮らしたというから、50年も前のことだ。

王さんからのコメント:
「小さい頃を過ごした墨田区は、私にとって野球人生の原点でもあります。今の私があるのも、
その頃の友人や地域の方々のおかげだと思っています。中でも、早稲田実業学校高等部在学
中に春の甲子園大会で優勝した際、町内でお祝いの提灯行列をしてくださったことが大変嬉しく
思い出に残っています。離れて50年になるにもかかわらず、あたたかい目で見守り続けていただ
いた故郷の皆さまに心から感謝しております」

渋いコメントだなぁ~!
巨人軍入団以後の3年間は、成績がふるわなかった王さん。昭和37年(1962年)に荒川博氏が
打撃コーチとして巨人軍に入団し、一本足打法をはじめてから数々のホームラン記録を打ち立て、
“世界の王”として花開いた。
「墨田区出身」のイメージが薄いのは、「荒川コーチ」に指導を受けたイメージが強いからだよって
うまいこというFacebookの友達がいたことを書き添えて、今回はおしまい。