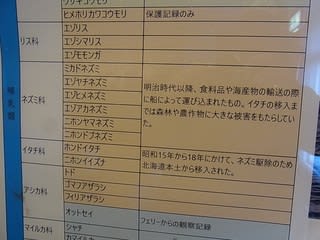こんにゃくえんまってなんだろう。ちょっといってみよう。後楽園駅に掲示してある地図をみて、千川通りを歩いていく。
5月なのに真夏日! 日本に四季があるというのは昔の話で、いまは冬と夏しかない。

ふりむくとドームがあんなふうに
白いから光をはじいてカメラに写りにくいけど、道路のつきあたりに巨大なエアバッグが開いてるようにみえる。
それにしても暑い。

えんま通り商店街がみえてきた
フォーカス(新潮社)、フライデー(講談社)、フラッシュ(光文社)といった写真週刊誌のひとつで、エンマ(文春)
というのが昔あった。当時はいまと違って文春砲が当たらず、すぐ消えた。えんま通り商店街で思い出した。

ふりかえったらこんにゃくえんま
ゑんま、って書くのね。こんにゃくゑんまは、婚約ゑんま? 困厄ゑんま? 縁結びか厄除けか、どっちだろう?
お坊さんが卒塔婆をたくさん立てかけて葉っぱでなでている。あいうえお順に並べて。

お寺だけどちょっと神社っぽい
ふりむくと絵馬掛けがあって、目の病気が治るように祈願したものが多い。てことは婚約じゃなくて困厄ゑんま
の意味での、こんにゃく?

こんにゃくが山積みに
お供えのこんにゃくが、こんなにたくさん。毎日こんにゃくが供えられたら、毎日お坊さんがこんにゃく食べる?
こんにゃく食べきれる?

塩漬け状態の塩地蔵尊
西新井大師とかでも塩地蔵みたあるけど、これはまたずいぶん塩だらけな……書いてなければ地蔵なのか
何なのかわからないくらいだ。

鐘に老人が群がってる
なんだろうと思って近寄ってみると、支那事変から太平洋戦争に日本が向かいだす1937年にこの鐘はこの寺
からサイパンの南洋寺に寄贈され、1944年にサイパンが玉砕するまで鳴らされていたという。

銃弾の痕とかあるし…
米軍が上陸してサイパンの日本人が全滅したあと、鐘は行方不明だったが、1965年にテキサスで発見されて
1974年、こんにゃくゑんまに返された。

あの穴は貫通してそう
アメリカでは仏像とおなじように鐘も金色に輝いていると思われているので、この鐘もテキサスにあるときは
金色に塗られていた。だから、ところどころ金色がまだ残ってる。誤解ってすごい……!

関連記事: 江北六丁目団地 (西新井大師の塩地蔵が出てくる)
5月なのに真夏日! 日本に四季があるというのは昔の話で、いまは冬と夏しかない。

ふりむくとドームがあんなふうに
白いから光をはじいてカメラに写りにくいけど、道路のつきあたりに巨大なエアバッグが開いてるようにみえる。
それにしても暑い。

えんま通り商店街がみえてきた
フォーカス(新潮社)、フライデー(講談社)、フラッシュ(光文社)といった写真週刊誌のひとつで、エンマ(文春)
というのが昔あった。当時はいまと違って文春砲が当たらず、すぐ消えた。えんま通り商店街で思い出した。

ふりかえったらこんにゃくえんま
ゑんま、って書くのね。こんにゃくゑんまは、婚約ゑんま? 困厄ゑんま? 縁結びか厄除けか、どっちだろう?
お坊さんが卒塔婆をたくさん立てかけて葉っぱでなでている。あいうえお順に並べて。

お寺だけどちょっと神社っぽい
ふりむくと絵馬掛けがあって、目の病気が治るように祈願したものが多い。てことは婚約じゃなくて困厄ゑんま
の意味での、こんにゃく?

こんにゃくが山積みに
お供えのこんにゃくが、こんなにたくさん。毎日こんにゃくが供えられたら、毎日お坊さんがこんにゃく食べる?
こんにゃく食べきれる?

塩漬け状態の塩地蔵尊
西新井大師とかでも塩地蔵みたあるけど、これはまたずいぶん塩だらけな……書いてなければ地蔵なのか
何なのかわからないくらいだ。

鐘に老人が群がってる
なんだろうと思って近寄ってみると、支那事変から太平洋戦争に日本が向かいだす1937年にこの鐘はこの寺
からサイパンの南洋寺に寄贈され、1944年にサイパンが玉砕するまで鳴らされていたという。

銃弾の痕とかあるし…
米軍が上陸してサイパンの日本人が全滅したあと、鐘は行方不明だったが、1965年にテキサスで発見されて
1974年、こんにゃくゑんまに返された。

あの穴は貫通してそう
アメリカでは仏像とおなじように鐘も金色に輝いていると思われているので、この鐘もテキサスにあるときは
金色に塗られていた。だから、ところどころ金色がまだ残ってる。誤解ってすごい……!

関連記事: 江北六丁目団地 (西新井大師の塩地蔵が出てくる)