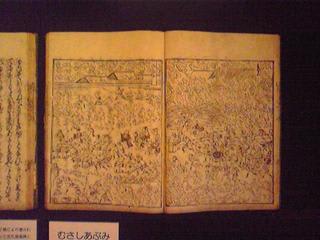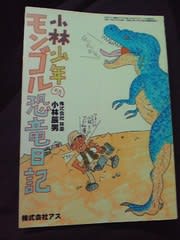仕事で博多に行くことになった。ランニング特集の取材で、大学の先生を訪ねるのだ。
編集長は「なるべく日帰りでね!」といった。取材は3時から。飛行機で日帰りできるが、
たまたま金曜日。いつ帰ろうと交通費は同じ。自主的に泊まってくることに決めた!
ところが、航空券はとれたがホテルがとれない。出発の1週間以上も前から、
旅慣れたぼくが検索技術をつくしても、なぜかホテルの空室が全然ヒットしない。
お盆は過ぎているし、博多の祭は8月じゃないし、なんなんだろう?
やむをえず、旅行代理店の力を借りて金曜の夜だけ天神のビジネスホテルをとる。
あとのことは、いけばどうにかなるだろう。
当日、取材を終えて天神のホテルに転がり込み、ページの構成をしばらく練って、
灯燈し頃に街に出た。居酒屋でイカを食べた。活き作り。それから夜の中洲と天神を
歩き回り、屋台を何軒かハシゴするうちに、ことの真相が明らかになった。
SMAPが木・金・土・日と4日間、福岡ドームでコンサートをやっているから、
県外から泊まりがけでやってくる女性のお客さんがホテルを押さえてしまって、
それでどこも空いてないのだという。女性客たちはコンサートのあと部屋に戻って
コンビニのカップはるさめや蒸しパンで腹を満たして寝てしまうから、博多の屋台は
SMAPのおかげで毎年、大打撃をこうむっているそうだ。去年は草剪くんが逮捕されて
全公演がキャンセルになり、屋台の売り上げが減らなくて助かったたらしい。
実際、10時半にドームでコンサートが終わると、中洲や天神に女性の集団が
通行するようになったけど、屋台に入る人は少なく、コンビニばかり混んでいた。
酔った勢いでブラブラ長浜まで歩く道すがら、酔眼ではっきりチェックできた。
一口餃子とか、明太子の天ぷらとか、おいしいのに、コンサートの開演前に
がっつり豚骨ラーメンか何かで腹ごしらえして、会場でSMAPグッズを買い込み、
たっぷり声援を送って夜食は部屋で済ませ、明日のコンサートに備えるのか?
それはいいとして、なぜ長浜までわざわざ歩いたかというと、会社の近くにある
「やまちゃん」というラーメン屋さんの、ルーツの屋台がそこにあるから。
訪ねてみると写真(上)の通り、おでんも焼きとりもやっている総合屋台で、
ラーメンはその中のメニューのひとつだが、食べてみると東京の店より
スープにパンチがあった。夜中にそんなこと確かめて、どうする?
(吉野ヶ里につづく)
編集長は「なるべく日帰りでね!」といった。取材は3時から。飛行機で日帰りできるが、
たまたま金曜日。いつ帰ろうと交通費は同じ。自主的に泊まってくることに決めた!
ところが、航空券はとれたがホテルがとれない。出発の1週間以上も前から、
旅慣れたぼくが検索技術をつくしても、なぜかホテルの空室が全然ヒットしない。
お盆は過ぎているし、博多の祭は8月じゃないし、なんなんだろう?
やむをえず、旅行代理店の力を借りて金曜の夜だけ天神のビジネスホテルをとる。
あとのことは、いけばどうにかなるだろう。
当日、取材を終えて天神のホテルに転がり込み、ページの構成をしばらく練って、
灯燈し頃に街に出た。居酒屋でイカを食べた。活き作り。それから夜の中洲と天神を
歩き回り、屋台を何軒かハシゴするうちに、ことの真相が明らかになった。
SMAPが木・金・土・日と4日間、福岡ドームでコンサートをやっているから、
県外から泊まりがけでやってくる女性のお客さんがホテルを押さえてしまって、
それでどこも空いてないのだという。女性客たちはコンサートのあと部屋に戻って
コンビニのカップはるさめや蒸しパンで腹を満たして寝てしまうから、博多の屋台は
SMAPのおかげで毎年、大打撃をこうむっているそうだ。去年は草剪くんが逮捕されて
全公演がキャンセルになり、屋台の売り上げが減らなくて助かったたらしい。
実際、10時半にドームでコンサートが終わると、中洲や天神に女性の集団が
通行するようになったけど、屋台に入る人は少なく、コンビニばかり混んでいた。
酔った勢いでブラブラ長浜まで歩く道すがら、酔眼ではっきりチェックできた。
一口餃子とか、明太子の天ぷらとか、おいしいのに、コンサートの開演前に
がっつり豚骨ラーメンか何かで腹ごしらえして、会場でSMAPグッズを買い込み、
たっぷり声援を送って夜食は部屋で済ませ、明日のコンサートに備えるのか?
それはいいとして、なぜ長浜までわざわざ歩いたかというと、会社の近くにある
「やまちゃん」というラーメン屋さんの、ルーツの屋台がそこにあるから。
訪ねてみると写真(上)の通り、おでんも焼きとりもやっている総合屋台で、
ラーメンはその中のメニューのひとつだが、食べてみると東京の店より
スープにパンチがあった。夜中にそんなこと確かめて、どうする?
(吉野ヶ里につづく)