
GoToトラベルキャンペーンが裏目に出て新型コロナの感染爆発がおこり、今年ずっと死んでいた
旅行業界がこの10月に自粛要請を解除された結果、どれくらい賑わいを取り戻したか興味があり
ツアー情報をサイトで調べてみた。すると、数日間しか催行されない「工事中の高速道路に潜入」
という日帰りツアーがあって、面白そうだから申し込んだ。

8:15
上野駅の公園口に集合出発で観光バスがすべりだす。以前は駅の反対側から観光バスが出ていた。
コロナが感染爆発してるあいだ(第3波・第4波)に公園口のロータリーが整備されてバスの発着
場所がわかりやすく変化していた。添乗員さんの挨拶では、昨年GoToキャンペーンが中断されて
以来これが4回目の乗務で、ずっと仕事がなくてドラッグストアのアルバイトをしていたけれど、
つらくて痩せたからジャケットがブカブカですみません。

9:12
うとうとしていると海老名のサービスエリアについた。東名高速道路が空いてるので休憩が長く、
のんびりサーティワンアイスクリームに着席してジャモカアーモンドファッジのスモールサイズ
など食べる。9:40出発。再度うとうとすると1時間弱で「沼津ぐるめ街道の駅竜宮海鮮市場」
にバスが着いて、あまりお腹すいてないけどお昼ごはんになった。

10:35
いま食べないと後できっと飢えるから、がんばって金目鯛釜飯御前たいらげる。箸袋に万葉の湯
と書いてあるので、完食後ぶらぶら施設を徘徊したら2階に温泉施設があった。沼津駅や三島駅
から竜宮海鮮市場までシャトルバスが朝2本、夕方2本ぐらい出ている。地元の人ならいいけど
自分がシャトルバスで万葉の湯に入りにくるチャンスはなさそうだ。11:45出発。

13:00
新東名に入り、今年4月に開通した新区間(新御殿場ー御殿場)を通行して、道の駅ふじおがわ
でNEXCO中日本の先導車と合流して本日最初の見学地、湯船原トンネルの工事現場へ。1.6km
ほどのトンネルは岩盤を掘削するなら2年ほどで貫通できるそうだが、富士の噴火の堆積物から
なる地層を掘り進む湯船原トンネルは2017年に掘り始めてまだ途中……岩盤に穴を開けるよりも
柔らかい土を固めながら掘るほうが大変なのだ。

13:10
ヘルメットとベストと軍手を借りて入坑し、600mほどゆっくり穴の中を歩きながら説明を聞く。
事故などがあったとき並行する上りと下りのトンネルを往来するための避難連絡坑(普段は扉が
閉まっているので自動車から気づかれにくい)を通り、工事の手順の解説動画など見せてもらう。
固めながら掘るなんて、矛盾のようなもの。岩盤掘削であれば1日4mぐらい進むこともあるけど
湯船原トンネルは1日1mずつ、着実に固めながら掘っている。

14:10
あんまり中の写真を撮らない(というか載せない)ほうがいいみたいなので、坑内の様子や工法の
ことはこれぐらいにして、雨ガッパのまま観光バスに戻って次の見学場所に移動する。トンネルの
つぎは高架橋、ユニークな作り方をしている柳島高架橋だ。ダムを作るときに使うインクラインを
設置して道路工事をしている。なぜなら作業用の道路を作れない場所だから。

14:25
2tトラックやタンクローリーが上がっていくには急すぎる道しか作れないので、エレベーターと
エスカレーターとケーブルカーを足して3で割ったようなインクラインを作業のために築き上げ、
上まで工事車両を上げちゃう。工事が休みの日を利用して、特別に見学の人を上まで上げちゃう。
工事現場では傘が使えないので、雨ガッパは主にこの見物のために着用している。

あの水色っぽい台座に2t車やタンクローリーを乗せて、1日40往復ぐらいしている。工事完成
が見えてきた現在までに、3万往復ぐらいしている。工事が終わったら大型車を上げ下げする必要
なくなるので、インクラインは解体して小型車が上り下りする作業道を敷設する。本日見学してる
新東名の区間は2023年度に開通予定ということで、本道のほかにも作業道を作ったりバラしたり
見えないところで手間がかかる。

65mぐらいの斜面をゆっくり3分半ほどかけて上がる。これは高所恐怖症の人にはたまらない。
上に着いてインクラインから現場に渡るとき、一瞬、下が見えて鳥肌が立ちそうになった。下を
見なければどうということはない。人は隙間をまたぐけど、大型車は下でインクラインに乗った
向きのまま3分半クラッチを切り、上でクラッチをつなげればタイヤで現場に渡ることができる。
とても便利である。

そのまま前進して右にハンドルを切れば作業道を上って高速道路の工事現場に行くことが可能。
合理的にできている。人間たちは作業道よりも見晴らしに興味をもち、案内の方にお願いして
記念写真を撮っている。確かに、こんなところ滅多なことでは上がれないし、開通までに解体
されちゃう現場だから恥を忍んで記念写真を撮ってもらう。背中を向けて。

あの橋脚も作りかけのときは人が上り下りするエレベーターがついていたそうだ。それを見た
地元の人はマンション建設の工事かと思ったという。この橋も時速100キロとかで走行すれば
2秒もかからずに渡り切ってしまう。果たして自分がクルマで通ってインクラインで上ったと
思い出す機会が一生のうちにあるだろうか?

見下ろせば、乗ってきた観光バスがあんなに小さくうずくまっている。高所恐怖症の人には、
きっとたまらない眺めだろう。これからインクラインで3分半かけて下まで移動して、バスに
15:20に戻って最後の見学地、中嶋高架橋まで移動する。10分ぐらいで着くらしいので、
やはり雨ガッパ着たまま。

15:30
完成した中嶋高架橋を自由に歩かせてもらう。その前にトンネルの上に歩いて登り記念写真。
もしも天気がよかったら、ここから富士山がバッチリ見晴らせるということでパネルを持つ。
東京から名古屋方面へ新東名高速道路を走り、中嶋高架橋を渡るとき、このような富士山が
見えたら「そういえば開通前にここへ来たとき雨降りだったなあ」と思い出す機会あるかも。
2023年以降だけど。

見下ろせば、もうあんなに人が歩いている。あっちは下りの車線で、名古屋のほうから東京へ
向かうクルマが通る。真ん中しか舗装してないのはどうしてだろう。質問してみたら、あれは
作業用の舗装路だから開通する前にすべて剥がし、ハイブリッドという水はけのいいアスファ
ルトをいまの路面より高く舗装するそうだ。なるほど、作業用だから真ん中だけ舗装してある
のか。公共事業って丹念に手間かけるんだなあ。

実際に歩いてみると進行方向に若干の傾斜があり、それだけでなく左右にも若干の傾斜がある。
左右の傾斜はクルマがカーブするとき走りやすいようにつけてあるのと、排水のための傾斜で
片側に水を集めて排水溝を流すようにしてあるという。古代ローマの馬車道も排水については
気を配ってあったらしいけど、左右の傾斜をつけてあったかどうか。気にしながら帰途につく
バスが16:05に中嶋高架橋を発車した。上野に19時ごろ着いた。
旅行業界がこの10月に自粛要請を解除された結果、どれくらい賑わいを取り戻したか興味があり
ツアー情報をサイトで調べてみた。すると、数日間しか催行されない「工事中の高速道路に潜入」
という日帰りツアーがあって、面白そうだから申し込んだ。

8:15
上野駅の公園口に集合出発で観光バスがすべりだす。以前は駅の反対側から観光バスが出ていた。
コロナが感染爆発してるあいだ(第3波・第4波)に公園口のロータリーが整備されてバスの発着
場所がわかりやすく変化していた。添乗員さんの挨拶では、昨年GoToキャンペーンが中断されて
以来これが4回目の乗務で、ずっと仕事がなくてドラッグストアのアルバイトをしていたけれど、
つらくて痩せたからジャケットがブカブカですみません。

9:12
うとうとしていると海老名のサービスエリアについた。東名高速道路が空いてるので休憩が長く、
のんびりサーティワンアイスクリームに着席してジャモカアーモンドファッジのスモールサイズ
など食べる。9:40出発。再度うとうとすると1時間弱で「沼津ぐるめ街道の駅竜宮海鮮市場」
にバスが着いて、あまりお腹すいてないけどお昼ごはんになった。

10:35
いま食べないと後できっと飢えるから、がんばって金目鯛釜飯御前たいらげる。箸袋に万葉の湯
と書いてあるので、完食後ぶらぶら施設を徘徊したら2階に温泉施設があった。沼津駅や三島駅
から竜宮海鮮市場までシャトルバスが朝2本、夕方2本ぐらい出ている。地元の人ならいいけど
自分がシャトルバスで万葉の湯に入りにくるチャンスはなさそうだ。11:45出発。

13:00
新東名に入り、今年4月に開通した新区間(新御殿場ー御殿場)を通行して、道の駅ふじおがわ
でNEXCO中日本の先導車と合流して本日最初の見学地、湯船原トンネルの工事現場へ。1.6km
ほどのトンネルは岩盤を掘削するなら2年ほどで貫通できるそうだが、富士の噴火の堆積物から
なる地層を掘り進む湯船原トンネルは2017年に掘り始めてまだ途中……岩盤に穴を開けるよりも
柔らかい土を固めながら掘るほうが大変なのだ。

13:10
ヘルメットとベストと軍手を借りて入坑し、600mほどゆっくり穴の中を歩きながら説明を聞く。
事故などがあったとき並行する上りと下りのトンネルを往来するための避難連絡坑(普段は扉が
閉まっているので自動車から気づかれにくい)を通り、工事の手順の解説動画など見せてもらう。
固めながら掘るなんて、矛盾のようなもの。岩盤掘削であれば1日4mぐらい進むこともあるけど
湯船原トンネルは1日1mずつ、着実に固めながら掘っている。

14:10
あんまり中の写真を撮らない(というか載せない)ほうがいいみたいなので、坑内の様子や工法の
ことはこれぐらいにして、雨ガッパのまま観光バスに戻って次の見学場所に移動する。トンネルの
つぎは高架橋、ユニークな作り方をしている柳島高架橋だ。ダムを作るときに使うインクラインを
設置して道路工事をしている。なぜなら作業用の道路を作れない場所だから。

14:25
2tトラックやタンクローリーが上がっていくには急すぎる道しか作れないので、エレベーターと
エスカレーターとケーブルカーを足して3で割ったようなインクラインを作業のために築き上げ、
上まで工事車両を上げちゃう。工事が休みの日を利用して、特別に見学の人を上まで上げちゃう。
工事現場では傘が使えないので、雨ガッパは主にこの見物のために着用している。

あの水色っぽい台座に2t車やタンクローリーを乗せて、1日40往復ぐらいしている。工事完成
が見えてきた現在までに、3万往復ぐらいしている。工事が終わったら大型車を上げ下げする必要
なくなるので、インクラインは解体して小型車が上り下りする作業道を敷設する。本日見学してる
新東名の区間は2023年度に開通予定ということで、本道のほかにも作業道を作ったりバラしたり
見えないところで手間がかかる。

65mぐらいの斜面をゆっくり3分半ほどかけて上がる。これは高所恐怖症の人にはたまらない。
上に着いてインクラインから現場に渡るとき、一瞬、下が見えて鳥肌が立ちそうになった。下を
見なければどうということはない。人は隙間をまたぐけど、大型車は下でインクラインに乗った
向きのまま3分半クラッチを切り、上でクラッチをつなげればタイヤで現場に渡ることができる。
とても便利である。

そのまま前進して右にハンドルを切れば作業道を上って高速道路の工事現場に行くことが可能。
合理的にできている。人間たちは作業道よりも見晴らしに興味をもち、案内の方にお願いして
記念写真を撮っている。確かに、こんなところ滅多なことでは上がれないし、開通までに解体
されちゃう現場だから恥を忍んで記念写真を撮ってもらう。背中を向けて。

あの橋脚も作りかけのときは人が上り下りするエレベーターがついていたそうだ。それを見た
地元の人はマンション建設の工事かと思ったという。この橋も時速100キロとかで走行すれば
2秒もかからずに渡り切ってしまう。果たして自分がクルマで通ってインクラインで上ったと
思い出す機会が一生のうちにあるだろうか?

見下ろせば、乗ってきた観光バスがあんなに小さくうずくまっている。高所恐怖症の人には、
きっとたまらない眺めだろう。これからインクラインで3分半かけて下まで移動して、バスに
15:20に戻って最後の見学地、中嶋高架橋まで移動する。10分ぐらいで着くらしいので、
やはり雨ガッパ着たまま。

15:30
完成した中嶋高架橋を自由に歩かせてもらう。その前にトンネルの上に歩いて登り記念写真。
もしも天気がよかったら、ここから富士山がバッチリ見晴らせるということでパネルを持つ。
東京から名古屋方面へ新東名高速道路を走り、中嶋高架橋を渡るとき、このような富士山が
見えたら「そういえば開通前にここへ来たとき雨降りだったなあ」と思い出す機会あるかも。
2023年以降だけど。

見下ろせば、もうあんなに人が歩いている。あっちは下りの車線で、名古屋のほうから東京へ
向かうクルマが通る。真ん中しか舗装してないのはどうしてだろう。質問してみたら、あれは
作業用の舗装路だから開通する前にすべて剥がし、ハイブリッドという水はけのいいアスファ
ルトをいまの路面より高く舗装するそうだ。なるほど、作業用だから真ん中だけ舗装してある
のか。公共事業って丹念に手間かけるんだなあ。

実際に歩いてみると進行方向に若干の傾斜があり、それだけでなく左右にも若干の傾斜がある。
左右の傾斜はクルマがカーブするとき走りやすいようにつけてあるのと、排水のための傾斜で
片側に水を集めて排水溝を流すようにしてあるという。古代ローマの馬車道も排水については
気を配ってあったらしいけど、左右の傾斜をつけてあったかどうか。気にしながら帰途につく
バスが16:05に中嶋高架橋を発車した。上野に19時ごろ着いた。










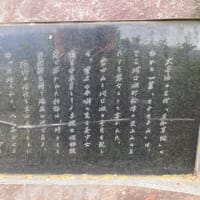















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます