
戦国乱世の頃、古田織部という茶人武将が「数寄を以って天下を獲らん」と活躍しました。信長→秀吉→家康に仕え、利休に師事し、弟子には小堀遠州、上田宗箇などがいます。活躍の結果、現代において尚ひとつの様式として『織部』があります。我々が非対称さに美意識を見出す事が出来るのもその辺りも要因のひとつでしょう。
その人生は、歴史大河ギャグ漫画『へうげもの』として長期連載中です。(まもなく21巻が出ます)
『へうげもの』は剽軽者とでも書くのでしょうが、隙あらば命のやり取りをする日本全国任侠時代において、命掛けで趣味趣向を貫く豪胆さ、それに対して表現の軽さが主題でもあります。そして、一世風靡し、ある時を境に灰燼に帰して忘れられる人生。あくまでも体制側に居ながら新しき事をなすという存在でした。
まさに『桃山に散った』というべき人生で、このあたりに現代人は感化されるのでしょうか。
さて、そんな事を思っていると、ふと疑問が。
「音楽(クラシック)の歴史において、古田織部に当たるのは誰だろう?」
ボンヤリと考えていましたが、答えはすぐに出る。
つまり、いない。
権力者(王、貴族、武家、教会など)があり、かつ体制側の人から探さねばならない。つまり時代としては古典派ぐらいまでである。
しかし、西洋では権力者自らが表現した芸術はほぼ無い。あちらの芸術は発注側と受注側の階層がはっきりとあるので存在しないのである。
織部も発注者側であるが、陣頭指揮をして形式、様式を牽引したという意味では表現者ともいえます。
オペラにおけるバレエ導入を国王が許すとか、そういう程度ではない。価値観やその後の美意識に影響を創出した人……。
となると、思いつかないなぁ。( ← 不勉強は棚に上げて)
ちなみにザックリとした音楽のメインストリームを書いておくと……、(西洋美術史や現代アートは、音楽史に置き換えて覚えました)
●黎明期
民衆の生活で伝わったもので楽譜はない。吟遊詩人やお祈りの歌など。
●ルネサンス
スポンサーは教会。
ミサ曲、合唱曲や世俗曲など。現代とは異なる記譜方法。教会旋法(チャーチモード)など現代と音の配列が異なる。
●バロック
スポンサーは教会、貴族。
現代の調性や和音進行など基礎が出来る。延々と繰り返される通奏低音に主旋律が乗る形式。伴奏と旋律など楽器が分業化。
バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディなど。
●古典派
スポンサーは貴族から富裕層市民へ。
室内楽メイン。整然とした『起承(転)結』の形式が出来る。現代楽器の基礎が出来る。ピアノの発明により婦女子向けの曲が楽譜として出版される。
ハイドン、モーツァルト、ベートーベンなど
●ロマン派
スポンサーは市民。
主題に対して物語性をもって表現する。作者の主観が強く「俺の話を聴け」的な曲も多い。
楽器がコントロールしやすくなり、奏法が確立するにつれて楽器編成が大きくなる。オペラやフルオーケストラが誕生。
・前期:メンデルスゾーン、シューマン、ショパン、ブラームスなど
・後期:ワーグナー、ブルックナー、チャイコフスキー、マーラー、シュトラウス(R)、シベリウス、ラフマニノフなど
●近代 (ロマン派末期と被っている)
肥大化するロマン派に対してアンチな立場。印象派、新ロマン主義など。調性の有無、拍子、旋律数、破調した和声進行などの作曲、編成の多様性など、主義主張が乱立する。
ドビュッシー、シェーンベルク、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチなど
●現代
やったもんがち。現代アートとの連動でコンセプチュアルなものもある。「音楽なのに楽器を弾かない」などは有名すぎる。
ジョン・ケージ、アルバン・ベルク、武満徹など
という事で、権力者かつ表現者は……、いない。
しかし、それではつまらないので作曲技法だけで考えてみると、『エリック・サティ』かな? 時代は古織様からずれて19世紀末から20世紀に達するが。
サティーは奇行が多い変人であったけれど、『家具の音楽』を自認する作風でBGM業界の創始者である。
伝統的な規則性や規律から生まれる安定した心地良さを根底からひっくり返し、調性、リズム、和声進行を崩壊させた。いわば『歪みの心地良さ』である。
印象派といえばドビュッシーが有名だが、その人に影響を与えた意味では印象派プロトタイプを生み出した人である。
その後は、記譜も独自のものになり、調性記号、拍子記号、小節線が放棄され、『そこにあるなら、あるんじゃね?』というありのままな形となる。
百花斉放、百家争鳴なロマン主義の中で、伝統を破壊し、新しい表現を創造し、やがて様式となる。
超人的作為を通して無作為を装う技巧。流れていく旋律に対する和音の諧謔性。
『破調の美』であり『乙』であります。
あと、曲のタイトルも一興。
タイトルと曲の関連性を持たせない為にあえて言を弄するスタイル。『無題』という風にテキトーに投げていないのが乙です。
な~~~んて事を思いながら、本日は『Préludes flasques <pour un chien> =(犬のための)ぶよぶよしたした前奏曲』から始まりました。













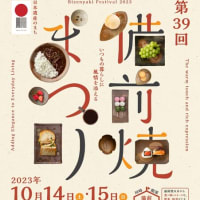
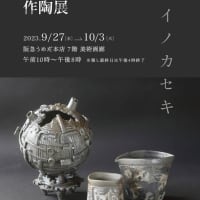



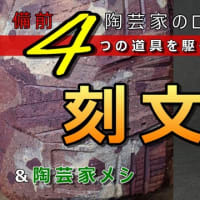





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます