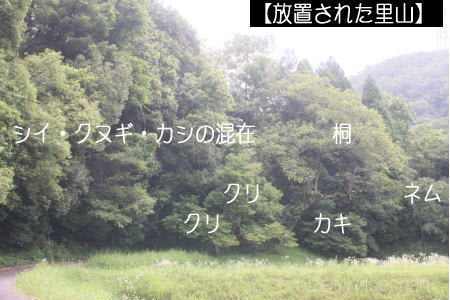製作のキーワードを訊かれる事がある。その場合、大体は「現代性です」と答える。今の生活に使うモノという趣旨で。
そして「何かを参考にする場合、そのものズバリは作らず、そのエッセンスを表現します」とも。
つまり「シリアの古代ガラスの形を作りたい」と思っても、形そのものではなくてエッセンスを組み合わせて雰囲気を作るという意味。
エッセンスの抽出は記号化とも言えるかな。このエッセンスのジャンル別で複数のシリーズが出来ている。現在継続中は5系統ぐらいか。
今の生活で使っていてお気に入りのグラスがある。持たない取っ手の付いたグラス自体は、ままあるけれど、これは自分にはない緩やかなラインのモノ。
作家さんにお伺いすると「もともとは、キャンドルホルダーとして作った」との事。
しかし、ブランデーを呑むのに丁度良くて、手で包み込むようにして持つと葡萄の芳香がほんのりと立つ。葡萄を手のひらで受けているみたいな感覚。
この形状で「自分なりのカップを作りたいなぁ」と思って試作した。現在は使い勝手を検証中。
エッセンスとしては、取っ手の在り様であるな。
さてさて、これはコピーか?
素材が違うとはいえ、現段階ではコピーの色合いが濃い。このままでは『何処かで見た形』であるな。
『何処かで見た形≒コピー』に対する考え方は、人それぞれだろう。
小生の場合、モノの製作では判りにくいので、音楽(作曲)に置き換えて考えている。
つまり作曲においては、ひとつの音から次の音への進み方とその長さは『順列組み合わせ』の問題であるので、現代では既に何小節かは作曲され尽くしていると判断できる。
それが4小節なのか、6小節なのかという長さは年数を重ねる程増して行くので、同じフレーズは必ず存在するし、似たものなら尚更の事である。
これが美術工芸においては、順列組み合わせの選択肢が格段に多いけれど、似たモノが同時に存在していても不思議ではない。
つまり、本人の意図に関わらず似たモノは確率的に存在する。なので、作家は『何処かで見た形≒コピー』を回避する事に思索を巡らしても仕方がないのである。
仕方はないが「自信を持って自身の作である(≒コピーではない)」と証を立てる為には、どうするべきか?
それは自分に対する裏付け=『モノの説得力』を持つ事である。順列組み合わせで同じものがあったとしても「オリジナル」と認知され次々と『新作』が出てくるのはそのあたりに起因するはずだ。
その意味で拙作の各シリーズのバリエーション展開の手法は説得性の要素になっている。逆に『脈絡なく突然出てくるモノは説得力が弱い』とも取れるので、新しいシリーズを作る場合は慎重になる。
そういう脈絡の無いヒラメキは突然来るけれど、作る事と発表方法は要検討である。
今後、このカップを自作の形としていくには説得力を加味していく事になる。
まず簡単に思いつくのは、自分のシリーズに落とし込むとすると『アフリカン』か『紀元前』あたりで、器種としてはカフェ・オ・レ・ボウルか。エッセンスとしては瓢の民芸品とか耳盃かな。
こういう発想や参考参照の方法論については、ビジネス書のタイトルに喧伝されている。いわゆる自己啓発系など。
それは会社の企画書だけでなく、我々モノ作りにも通じる内容でもあるのだろう。(読んだ事ないけど)
ところで、いつも思うんだけど、この手の本って『なぜ、〇〇は□□なのか?』という『なぜ、のか?』パターンが多いのだろう。
本のタイトル自体が既に『何処かで見た形』なんだけどねぇ。作家さんが表現したい動機から本になっているはずなので、きっと中身に説得力があるんだろうなぁ。
あと、就職活動の服装、髪型、化粧も疑問。
悪目立ちを避けたいのは判るが、面接は自己表現の場である。なのに「なぜ、就活生は非個性化を目指すのか?」と。 (あっ、使っちゃったわ)
コピー、写し、スタイル、伝統……言い方は多いけれど、オリジナルと認められるには最後は説得力である。モノも本も面接も。
コピーから始まっても最後にはオリジナルを目指す。それが流儀。
(あ~~、粘土さわりてぇ~~~。 ←事務作業中)