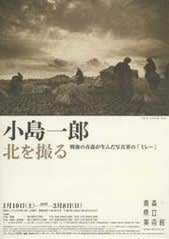
青森県立美術館で開催中の企画展「小島一郎 北を撮る」。
サブタイトル「戦後の青森が生んだ写真界の「ミレー」」。ミレーとは、もちろん、「晩鐘」、「落穂拾い」、「種まく人」を描いた19世紀フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーのことです。小島一郎(1924-1964)が津軽の農民を撮った写真は、確かに、ミレーの描いた農民たちの絵と雰囲気が似ています。チラシに載っている写真なんか、稲わらを麦に代えたらそのままバルビゾンの農村になりそうだし。小島一郎自身も、津軽の農夫達の姿は、ミレーの「晩鐘」をほうふつとさせる、と書き残しているらしい。まあ、なんでもかでもヨーロッパの画家を引き合いに出すことはないだろう、という気もちょっとしますけどネ。

青森市生まれの写真家・小島一郎は、1950年代後半、津軽や下北の農村や漁村を歩き、そこに住む人々の姿をカメラに収めてきました。特に、冬の情景が多いのが特徴です。彼自身、あまりの寒さに指が凍えながらもシャッターを押したと撮影記に書いています。地吹雪を体験したことのある人なら、それがどんなに苦しいことか、とてもよくわかります。
「津軽シリーズ」は、遠景に、たれ込める雲の切れ間から太陽がのぞく空を配置している写真が印象的です。ああいう空も、冬の青森ではおなじみですね。毎日のように降り続く雪の中で、時折顔をのぞかせる太陽がとてもいとおしく思える時があります。弱々しい太陽の光を真正面からとらえ、前景には、たいてい後ろ姿の人々が描かれる。そのコントラストがたまらない。

何でも、彼はそうやって逆光で撮ったフィルムを、現像の際にテクニックをフル活用して、黒と白の複雑なグラデーションをつくり出したのだとか。戦場カメラマンのロバート・キャパは、ノルマンディー上陸作戦の写真を撮るとき、臨場感を出すためにわざとブレるように撮影したといいますが、それもプロの写真家の華麗なるテクニックなのですな。
戦場カメラマンといえば、青森の生んだフォト・ジャーナリスト沢田教一(1936-1970)は、小島一郎の12歳ほど年下ですが、彼が一時、小島の生家である写真機店で働いていたという話には驚きました。「安全への逃避」でピューリッツァ賞を受賞した沢田教一は、1970年、ベトナム戦争取材中に銃弾に倒れ、34歳の若さで亡くなっています。小島一郎も、亡くなったのは39歳(1964年)と、いずれも30代の若さでこの世を去っています。不思議な因縁を感じます。
「津軽シリーズ」では、竜飛の風景を撮った写真が印象に残りました。高台にポツンと立つ墓石を撮っているのですが、それが見事に傾いているのです。墓石だけではありません。卒塔婆も、お地蔵様も、みんな一斉に20°ほど左に傾いている。年中竜飛を吹き抜ける強い風があんな造形をつくり出したのでしょうか…。見れば見るほど不思議な写真でした。
小島一郎のもう一つの大きなシリーズが「下北シリーズ」。下北半島の西海岸を中心に撮影旅行をして撮りためた一連の写真は、「下北の荒野」と名付けられ、「カメラ芸術新人賞」を受賞し、彼の名前を一躍有名にしています。このシリーズは、「津軽」と違って、白から黒へのグラデーションは一切ありません。ひたすら、黒か白か。これもまた彼のテクニックのなせる技。津軽とはまた違った下北半島の冬の荒涼を描くために用いられた手法なのでしょう。
同じ部屋に展示されていた写真雑誌をよく読んでみたら、木村伊兵衛氏が、この下北の写真を展示した写真展をについてこき下ろしていたことがわかりました。座談会で、「新人だからあえて言う」として、「全体的にバランスが悪い、もっと勉強せよ」みたいな話をしています。いくら被写体に恵まれても、プロを目指すには、まだまだ修行が足りんということなのでしょうね。
彼は、この下北シリーズの撮影後、プロのカメラマンを目指し、意を決して上京。しかし、やはり彼の居場所は青森しかなかったようです。東京時代の彼の作品もいくつか展示してありましたが、青森での写真と比べると、全くといっていいほど精彩に欠けることは、素人目にもわかります。東京近郊の農村の写真など、何も訴えてこない。東京の夕日を背景に撮った街並みの写真は、小島一郎らしい写真と言えば言えるのですが、彼が撮りたかったのは、こういう「街」ではなかったと思います。
小島一郎がこだわった津軽の冬、下北の冬。そこにこだわり続けていたら、彼も北海道への撮影旅行もしなかっただろうし、そこで体調を崩して夭折することもなかったかもしれません。風景自体は、彼が撮影した50年前とそれほど変わらないかもしれませんが、そこに住む人々の生活は大きく変わったのではないでしょうか。小島一郎がもし生きていれば、もう80歳を超えていることになりますが、「今」の風景を、彼がどんなふうに撮ってくれるのか、見たかったなあと思います。
サブタイトル「戦後の青森が生んだ写真界の「ミレー」」。ミレーとは、もちろん、「晩鐘」、「落穂拾い」、「種まく人」を描いた19世紀フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーのことです。小島一郎(1924-1964)が津軽の農民を撮った写真は、確かに、ミレーの描いた農民たちの絵と雰囲気が似ています。チラシに載っている写真なんか、稲わらを麦に代えたらそのままバルビゾンの農村になりそうだし。小島一郎自身も、津軽の農夫達の姿は、ミレーの「晩鐘」をほうふつとさせる、と書き残しているらしい。まあ、なんでもかでもヨーロッパの画家を引き合いに出すことはないだろう、という気もちょっとしますけどネ。

青森市生まれの写真家・小島一郎は、1950年代後半、津軽や下北の農村や漁村を歩き、そこに住む人々の姿をカメラに収めてきました。特に、冬の情景が多いのが特徴です。彼自身、あまりの寒さに指が凍えながらもシャッターを押したと撮影記に書いています。地吹雪を体験したことのある人なら、それがどんなに苦しいことか、とてもよくわかります。
「津軽シリーズ」は、遠景に、たれ込める雲の切れ間から太陽がのぞく空を配置している写真が印象的です。ああいう空も、冬の青森ではおなじみですね。毎日のように降り続く雪の中で、時折顔をのぞかせる太陽がとてもいとおしく思える時があります。弱々しい太陽の光を真正面からとらえ、前景には、たいてい後ろ姿の人々が描かれる。そのコントラストがたまらない。

何でも、彼はそうやって逆光で撮ったフィルムを、現像の際にテクニックをフル活用して、黒と白の複雑なグラデーションをつくり出したのだとか。戦場カメラマンのロバート・キャパは、ノルマンディー上陸作戦の写真を撮るとき、臨場感を出すためにわざとブレるように撮影したといいますが、それもプロの写真家の華麗なるテクニックなのですな。
戦場カメラマンといえば、青森の生んだフォト・ジャーナリスト沢田教一(1936-1970)は、小島一郎の12歳ほど年下ですが、彼が一時、小島の生家である写真機店で働いていたという話には驚きました。「安全への逃避」でピューリッツァ賞を受賞した沢田教一は、1970年、ベトナム戦争取材中に銃弾に倒れ、34歳の若さで亡くなっています。小島一郎も、亡くなったのは39歳(1964年)と、いずれも30代の若さでこの世を去っています。不思議な因縁を感じます。
「津軽シリーズ」では、竜飛の風景を撮った写真が印象に残りました。高台にポツンと立つ墓石を撮っているのですが、それが見事に傾いているのです。墓石だけではありません。卒塔婆も、お地蔵様も、みんな一斉に20°ほど左に傾いている。年中竜飛を吹き抜ける強い風があんな造形をつくり出したのでしょうか…。見れば見るほど不思議な写真でした。
小島一郎のもう一つの大きなシリーズが「下北シリーズ」。下北半島の西海岸を中心に撮影旅行をして撮りためた一連の写真は、「下北の荒野」と名付けられ、「カメラ芸術新人賞」を受賞し、彼の名前を一躍有名にしています。このシリーズは、「津軽」と違って、白から黒へのグラデーションは一切ありません。ひたすら、黒か白か。これもまた彼のテクニックのなせる技。津軽とはまた違った下北半島の冬の荒涼を描くために用いられた手法なのでしょう。
同じ部屋に展示されていた写真雑誌をよく読んでみたら、木村伊兵衛氏が、この下北の写真を展示した写真展をについてこき下ろしていたことがわかりました。座談会で、「新人だからあえて言う」として、「全体的にバランスが悪い、もっと勉強せよ」みたいな話をしています。いくら被写体に恵まれても、プロを目指すには、まだまだ修行が足りんということなのでしょうね。
彼は、この下北シリーズの撮影後、プロのカメラマンを目指し、意を決して上京。しかし、やはり彼の居場所は青森しかなかったようです。東京時代の彼の作品もいくつか展示してありましたが、青森での写真と比べると、全くといっていいほど精彩に欠けることは、素人目にもわかります。東京近郊の農村の写真など、何も訴えてこない。東京の夕日を背景に撮った街並みの写真は、小島一郎らしい写真と言えば言えるのですが、彼が撮りたかったのは、こういう「街」ではなかったと思います。
小島一郎がこだわった津軽の冬、下北の冬。そこにこだわり続けていたら、彼も北海道への撮影旅行もしなかっただろうし、そこで体調を崩して夭折することもなかったかもしれません。風景自体は、彼が撮影した50年前とそれほど変わらないかもしれませんが、そこに住む人々の生活は大きく変わったのではないでしょうか。小島一郎がもし生きていれば、もう80歳を超えていることになりますが、「今」の風景を、彼がどんなふうに撮ってくれるのか、見たかったなあと思います。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます