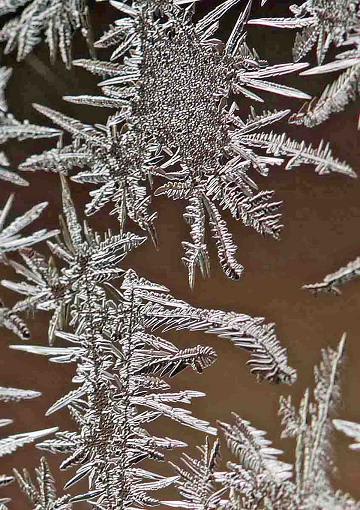我ながら感心しているのですが、今月はブログ開設以来、初めて半月間ブログ皆勤です。
ここまで来たら、1ヶ月続けたいと思っていますがどうなりますか。
昨日は、東京で同期会が行われていましたが、私は地元で写真展「寿齢讃歌Ⅶ」の開展式に出席していました。
私のブログも、ここにお並びの被写体の方の年まで続けられますかどうか。。。
「寿齢讃歌」は、概ね80才以上の方が被写体となった写真展です。

10時、開会。
ご来賓の方々の挨拶の後、テープカットで開場です。
後ろが、展覧会会場。

真ん中が、写真展「寿齢讃歌」の、プロデューサー木之下晃先生。
右は、木之下先生が、客員教授をしていらっしゃる日本福祉大学学長、他は茅野市美術館館長など茅野市関係者。

木之下先生、ご挨拶文。

茅野市民館会場内部。
カラー写真で応募した写真が、白黒に変換されての展示です。
今年は、ワークショップの時に、日本カメラの方から「最初から白黒で撮ってみてはいかがでしょうか」という提案もありました。
被写体の方にさし上げる時は、カラーのほうが嬉しいでしょうから、両方で写しておくということでしょうか。

木之下先生と来賓者で、毎年9月号に寿齢讃歌を掲載している「日本カメラ」を前に、お話が弾んでいます。

こちらに展示されている写真は、ガラス越しに茅野市民館の外から見られます。

今年の、私と主人の出品作品。
出品は、一人2点までです。

東京のケァ・ホーム従業員駐車場に停めてあったオートバイと母。

木之下先生から、母がオートバイの手前に立ち両手でハンドルを持ち93歳がオートバイに乗るのかと思わせる写し方をすれば面白かったとアドバイスがありました。
このあと、自立ルームから介護ルームに移った母には、両方のハンドルに手を伸ばす事自体危なっかしくて無理。
足元もおぼつかなくなってきています。
オートバイはフェンスぎりぎりに停めてあり、写し手はこれより右に寄れません。
でも、おっしゃるとおりに、写せたら面白い写真になったでしょうね。
頭の片隅に。
デジカメクラブのプロもそうですが、プロというのは、素人には不可能な状況を要求します。
不可能を可能にして、プロの厳しい道を進んでこられたのでしょうね。
今年のポスターに載った、昨年の応募写真の母(左下)。

地元米沢の83才のおばあさまが、トラクターを運転しているところ。
後ろは、蓼科山と北横岳。

木之下先生も「83才でトラクター運転するの。すごいなぁ」と、感心していらっしゃいました。
春先に、塩壺の湯でお会いした時に「私がトラクターを運転しているところを写して、寿齢讃歌に出して欲しいの」と頼まれました。
別荘地、三井の森の定住者懇親パソコンサークル「八ヶ岳サロン」の講師80才。

この日が講師引退で、これからは、生徒に回られるそうです。
その、ご挨拶をしているところを引退の記念にと写し応募しました。
木之下先生からは、「80才の人が、パソコンをするということ自体すごいことなのだから、パソコンをしているところを写せば良かった」とのことでした。
そんなことも思い、左下にパソコン画面を入れたのですが。。。
「寿齢讃歌」来年度用のプロモーションビデオの制作ということで、トラクターのおばさまと先日、取材を受けた時にスタッフが写した写真も展示されていました。
木之下先生から、被写体と写し手との関係を取材するようにとお話があったそうです。

83才で軽トラを運転し、草刈器を操っています。
右下から2番目の写真は、スタッフの皆様にお振る舞いする自家製の西瓜を用水路を石でせき止め冷やしていたのを取り出すところです。
先人の知恵ですね。
もう1組は、被写体が100才の画家と、応募のご家族です。
この応募者の方が、高校の先生で写真クラブの顧問をしていらして、その生徒さんたちからの応募もありました。
高校生から、応募者自身が寿齢讃歌の被写体の年齢に達している方まで、応募者の年齢層も広がっています。
会場には、今年のプロモーションビデオが流れています。
招待客には、応募作品すべて掲載の寿齢讃歌Ⅶのアルバムをくださいました。
年々、応募作品が増え、今年は特に厚くなリ、ずしりと重い感じがします。