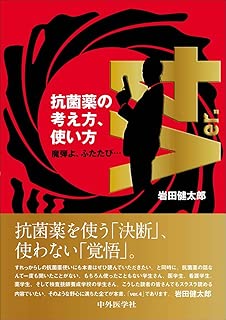現在90歳代の女性に高カロリー輸液を行っている。
93歳女性は地域の基幹病院外科から腸閉塞を繰り返すことと嚥下障害があることから、末梢静脈からの点滴でお看取りの方針で転院してきた。家族(娘さん)はできるだけ長く生きてほしいと希望された。起きている時は顔を見ると笑いかけてくる。会話は話しかけると小さな声で一言発するくらいだが。
99歳女性は誤嚥性肺炎で入院した。嚥下訓練をして経口摂取は不可能と判断された。入院時に付き添ってきた、実際に自宅で介護していた長男のお嫁さん(といっても高齢者)は、だめならだめでという感じだった。今後のことを相談することになって、息子2名が来て(直接介護はしていない)、できるだけ生きていてほしいと強く希望した。患者さんはほとんど寝ているだけで、発語もない。
96歳女性は急性腎盂腎炎・敗血症性ショックで入院した。抗菌薬と昇圧薬(ノルアドレナリン)で何度か軽快した。息子さんと相談して、高カロリー輸液を開始した。こちらはベット上でけっこう動くので、処置の時は看護師数名が参加する。気に入らないと看護師さんを叩いてくるくらい元気?だ。
いずれも療養型病床のある病院への転院待ちの状態だ。早くて1か月だが、2~3か月かかる時もある。
金曜日も、食事摂取できそうなのにしない95歳女性の家族と相談した。以前息子さんに電話すると、「病院にまかせる。本人も死ぬ気でいるようだからそれでいい。」とあっさり言っていた。ただこの患者さんは薬は飲むし、会話可能で同室者のことを言ったりする。嚥下障害というよりは拒食のように思われる。
すでに中途半端な状態で2か月以上経過していて、病棟では方針を決めてほしい。高カロリー輸液に切り替えて、療養型病床の受け入れ待ちにすることを提案した。息子さんは特に反対はしなかった(話が終わると、いっしょに来た姪を残してさっと帰って行った)。幸い療養型病棟のある病院の一般病床に入院したことがあり、なじみがあった。
こういう医療は日本全国で行われているのだろう(たぶん欧米ではありえない形?)。いわゆる老人病院は、このような患者さんたちで満床経営なので経済的に潤っていると思われる。(当院も、経営的に存続できれば将来的にはそうなる予定)
大学病院老人科の先生が、バイトに行っている老人病院で、高カロリー輸液の高齢者と経管栄養の高齢者でどちらが長生きするかという研究をしていた。結果は経管栄養の方が長生き(数か月の単位だが)ということだった(カテーテル関連血流感染を来しても、抜去しないのが影響している?)。看護師さんの手間は高カロリー輸液の方が1日1回点滴交換するだけなのではるかに楽だ。
初版から購入している岩田健太郎先生の「抗菌薬の考え方、使い方ver4」(中外医学社)をやっと読んだ。さらに岩田節になっていて面白い。ただ、びっくりするくらい誤植があり、中外医学社のホームページに長い長い正誤表がある。
「今日は天気もいいし、布団も干してきたから、セフトリアキソン」と俵万智の俳句のような、ポエティックな理路を立ててはいけません、という記載がある。これは当然俳句ではなくて和歌で、校正者も気づいているはずだが、あえて直さなかったのだろうか。