(前回の続き⇒)
…と行きたいところだけど。
ちょっと時代を進めて、第二次世界大戦後の話となる。
学校教育では…、
「日本は、ポツダム宣言を受け、無条件降伏した」と教わった気がする。
“戦争の敗戦国が「無条件」の降伏をした!“
それなのに、何故、竹島や北方領土などの領土問題が残ったのだろうか?
その疑問は、子供の頃からあったもの、
誰に聞けばいいのかも分からなかった。
あるテレビ番組によれば…、
第二次世界大戦の終盤、ソヴィエト連邦は、連合国の一翼として、
対日参戦しており。
このことは、ロシアでの、近現代史の教科書にも記述されている…とあり。
この「連合国」についても、説明があった。

1941年、アメリカのルーズベルト大統領の主導による大西洋憲章では、
「第二次世界大戦が終了したとき、勝った国は、領土を拡大させることはない」
(戦勝国が、敗戦国の領土を奪わない)という方針を打ち出しており。
その上で…、
1942年、連合国共同宣言が、26ヶ国で行われている。

日本では「国際連合」と扱われているUnitedNationsは、
国家を超えた「世界連邦」のような存在ではなく。
すでに記したように「連合国」を意味している。
戦争による領土拡大を抑えることを、目的としていたものであり。
日本は、1951年、サンフランシスコ平和条約によって、
「樺太の一部」と「千島列島」に対する、
すべての権利を放棄することになった。
(ただし、ソビエト連邦は調印せず、帰属先は明記なし)
ソビエト連邦は、この国際連合として参戦していながら実効支配し、
ソビエト連邦の解体後(1991年12月)は、
ロシアによって、30年以上も実効支配されているのだから、
“そろそろ返してくれ!”ともなってくる。
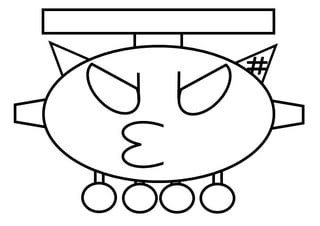
この第二次世界大戦後、世界は、西側の資本主義陣営と、
東側の社会主義陣営とで分かれ、対立状態となっていく。
いわゆる(直接的な戦争のない)冷戦の時代となり。
西側のアメリカ合衆国と東側のソヴィエト連邦とによる、
直接的な戦争こそなかったもの。
朝鮮戦争、ベトナム戦争、キューバ危機などがあり。
1979年、ソヴィエト連邦は、アフガニスタンにも侵攻している。
そして…。
1985年、ソヴィエト連邦、共産党書記長に、ゴルバチョフが就任、
彼が主導した、ソビエト連邦のペレストロイカ(立て直し)によって、
東側諸国も変化していく。
1989年、11月9日、東西ドイツ、ベルリンの壁を開放され、
1989年12月、米ソ首脳により、冷戦終結宣言(マルタ会談)となる。
この冷戦終結によって、
ソヴィエト連邦の構成国は、それぞれ独立していくこととなり。
1990年、東西ドイツは、ドイツ連邦共和国に統一
1991年、12月、ソヴィエト連邦は解体する。
現在、交戦状態にあるロシアとウクライナは、
このとき独立国家となっている。
西側の超大国、アメリカの軍産複合体は、
アメリカの敵となる存在(仮想敵国)を、常に必要としており。
それによって、莫大な予算枠を得ていたこともあり。
西側諸国は、東西冷戦後のロシアを民主化していくことへの熱意は、
あまりなかったとも聞く。
1994年、ウクライナは、ブカレストにおいて核放棄しており。
アメリカとロシアは、ウクライナが核放棄するとき、
安全保障の条件を話合いながらも、
今、ロシアが侵攻している状況には、強い憤りを感じてしまう。
蛇足:
今まで聞いていなかったようなことを、
一度に言われても、何が正しいことなのか分からない。
争いごとなんて、やりたいヤツだけが、
こちらの知らないところで勝手にやっていればいいんだ!
…とも言いたくなるけど。
それは、物事を単純化した見方。
このような反応は、見捨てられたような気分になるかも知れない。
ロシア軍によるウクライナ侵攻の中、
ロシア軍から脱走兵が出たというニュースを聞いたとき
あまり素直に喜べなかった。
例え、職業軍人でなくても、戦場に兵士として送られれば、
自己判断で、戦地から抜け出せるハズもなく。
上官の命令を無視したり、反対意見をすれば、タダ事では済まない。
彼らの(ロシア社会での)キャリアは、そこで終わっただけでなく。
下手をすれば、永久に、故郷に帰ることもできなくなる。
…それでも“殺し合いの場から、抜け出せた人がいることは、
喜ぶべきなのかも知れない。
今、分かっているのは、これくらいのところ。
数年後、このレポートを見たとき、
どのように感じるのかなど、予想もつかないところです。
…と行きたいところだけど。
ちょっと時代を進めて、第二次世界大戦後の話となる。
学校教育では…、
「日本は、ポツダム宣言を受け、無条件降伏した」と教わった気がする。
“戦争の敗戦国が「無条件」の降伏をした!“
それなのに、何故、竹島や北方領土などの領土問題が残ったのだろうか?
その疑問は、子供の頃からあったもの、
誰に聞けばいいのかも分からなかった。
あるテレビ番組によれば…、
第二次世界大戦の終盤、ソヴィエト連邦は、連合国の一翼として、
対日参戦しており。
このことは、ロシアでの、近現代史の教科書にも記述されている…とあり。
この「連合国」についても、説明があった。

1941年、アメリカのルーズベルト大統領の主導による大西洋憲章では、
「第二次世界大戦が終了したとき、勝った国は、領土を拡大させることはない」
(戦勝国が、敗戦国の領土を奪わない)という方針を打ち出しており。
その上で…、
1942年、連合国共同宣言が、26ヶ国で行われている。

日本では「国際連合」と扱われているUnitedNationsは、
国家を超えた「世界連邦」のような存在ではなく。
すでに記したように「連合国」を意味している。
戦争による領土拡大を抑えることを、目的としていたものであり。
日本は、1951年、サンフランシスコ平和条約によって、
「樺太の一部」と「千島列島」に対する、
すべての権利を放棄することになった。
(ただし、ソビエト連邦は調印せず、帰属先は明記なし)
ソビエト連邦は、この国際連合として参戦していながら実効支配し、
ソビエト連邦の解体後(1991年12月)は、
ロシアによって、30年以上も実効支配されているのだから、
“そろそろ返してくれ!”ともなってくる。
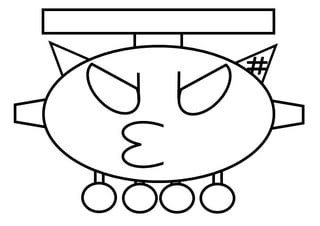
この第二次世界大戦後、世界は、西側の資本主義陣営と、
東側の社会主義陣営とで分かれ、対立状態となっていく。
いわゆる(直接的な戦争のない)冷戦の時代となり。
西側のアメリカ合衆国と東側のソヴィエト連邦とによる、
直接的な戦争こそなかったもの。
朝鮮戦争、ベトナム戦争、キューバ危機などがあり。
1979年、ソヴィエト連邦は、アフガニスタンにも侵攻している。
そして…。
1985年、ソヴィエト連邦、共産党書記長に、ゴルバチョフが就任、
彼が主導した、ソビエト連邦のペレストロイカ(立て直し)によって、
東側諸国も変化していく。
1989年、11月9日、東西ドイツ、ベルリンの壁を開放され、
1989年12月、米ソ首脳により、冷戦終結宣言(マルタ会談)となる。
この冷戦終結によって、
ソヴィエト連邦の構成国は、それぞれ独立していくこととなり。
1990年、東西ドイツは、ドイツ連邦共和国に統一
1991年、12月、ソヴィエト連邦は解体する。
現在、交戦状態にあるロシアとウクライナは、
このとき独立国家となっている。
西側の超大国、アメリカの軍産複合体は、
アメリカの敵となる存在(仮想敵国)を、常に必要としており。
それによって、莫大な予算枠を得ていたこともあり。
西側諸国は、東西冷戦後のロシアを民主化していくことへの熱意は、
あまりなかったとも聞く。
1994年、ウクライナは、ブカレストにおいて核放棄しており。
アメリカとロシアは、ウクライナが核放棄するとき、
安全保障の条件を話合いながらも、
今、ロシアが侵攻している状況には、強い憤りを感じてしまう。
蛇足:
今まで聞いていなかったようなことを、
一度に言われても、何が正しいことなのか分からない。
争いごとなんて、やりたいヤツだけが、
こちらの知らないところで勝手にやっていればいいんだ!
…とも言いたくなるけど。
それは、物事を単純化した見方。
このような反応は、見捨てられたような気分になるかも知れない。
ロシア軍によるウクライナ侵攻の中、
ロシア軍から脱走兵が出たというニュースを聞いたとき
あまり素直に喜べなかった。
例え、職業軍人でなくても、戦場に兵士として送られれば、
自己判断で、戦地から抜け出せるハズもなく。
上官の命令を無視したり、反対意見をすれば、タダ事では済まない。
彼らの(ロシア社会での)キャリアは、そこで終わっただけでなく。
下手をすれば、永久に、故郷に帰ることもできなくなる。
…それでも“殺し合いの場から、抜け出せた人がいることは、
喜ぶべきなのかも知れない。
今、分かっているのは、これくらいのところ。
数年後、このレポートを見たとき、
どのように感じるのかなど、予想もつかないところです。










