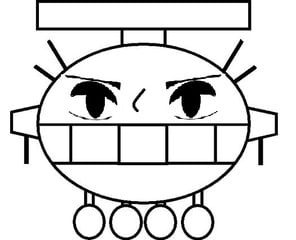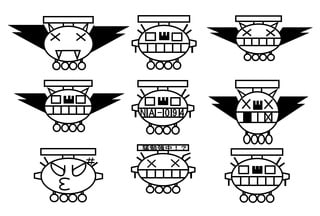新社会人の頃、電話の取り方を徹底的に指導されたことがある。
社内の電話が鳴ったら、
まず(右手が利き腕の場合は)左手で電話機の受話器をとり。
必ずメモを取るように徹底された。
左右のどちらの手で、とっても同じだろう…などと言うものに限って、
受話器を持ち換えようとしながら、
机(デスク)のまわりから、メモとボールペンを探して、
受話器もろとも電話機を落としたヤツまでいたけど。
相手は、用事があって職場の電話にかけてきているのだから、
伝達漏れや未報告が許されるハズもなく。
用件を書き留めておけるように準備するのは、当たり前だとも言える。
“これ”ができない人は、意外なほど多く。
ロクすっぽに用件を聞いていなかったりもする。
ヒドいものになると、相手の名前すら覚えていないことまである。
“あーっ、名前なんて言ってなかったすっよ”
“ウソつけ!張り倒すぞ”となり。
かなり怒られることとなった(ダメじゃん!)。

こんな話も、もう大昔のこと。
職場の新人研修では、色々と指導されたものです。
今でも、あまり頭の良い大人ではないけど。
一般常識もロクに分かってもいなかっただけに、
傍若無人にも思える行動(マネ)をしては、迷惑をかけていました。