憲法学における内閣についてのQ君とA先生とのやりとりです。
一 行政権と内閣
Q君
憲法 「第六十五条 行政権は、内閣に属する。 」とありあす。
65条にいう行政権の概念を説明してください。
A先生 全ての国家作用から、立法作用と司法作用を取り除いた残りの作用を行政権と定義します。
この説を、控除説といいます。
Q君 控除説の長所と問題点は、何ですか?
A先生
長所は、現実の行政活動を包括的にとらえることができる点です。
問題点は、行政権を限定していないために、行政国家現象を助長するのではないか、という疑いがある点です。
Q君 独立行政委員会とは何ですか。
とくに、準立法作用・準司法作用を行う独立行政委員会とは。
A先生
内閣から、一定程度独立して活動を行う行政機関を独立行政委員会といいます。
人事院は、人事院規則の制定などの準立法作用を行います。
公正取引委員会は、政治権力から独立して、独禁法違反の調査と裁決を行うので、準司法作用を営んでいます。
Q君 独立行政委員会が65条に反しないというには、どのような理由付けを行っているのですか。
A先生
1)65条は、41条や76条のように、「全て」「唯一の」という文言を用いていないことから、65条は全ての行政機関について、直接指揮監督することまでを要求していないことがひとつ目の理由です。(形式的理由)
2)政治的に中立性を保つ必要のある機関が存在することが二つ目の理由です。
3)人事や予算について、国会のコントロールが及んでいることが三つ目の理由です。
二 内閣の組織と権能
総理大臣
Q君 内閣総理大臣の職務権限は、どういうものですか?
A先生
判例(ロッキード事件 平成7年2月22日判決)では、次のように述べています。
「内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として(六六条)、国務大臣の任免権(六八条)、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあるものである。そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(四条)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(六条)、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。このように、内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。したがって、内閣総理大臣の運輸大臣に対する前記働き掛けは、一般的には、内閣総理大臣の指示として、その職務権限に属することは否定できない。」
Q君 内閣の責任のうち、法的責任と政治的責任について説明してください。
A先生
「内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う(66条3項)」と規定されていますが、これは、政治責任を指します。
ここでの責任は、違法な行為だけではなく、不当もしくは国民が納得しない政府の行為を含んでいる。
一方、法的責任は、その要件と効果が法定される必要があるところ、明文で定められている内閣の法的な責任の取り方は、不信任案の可決の場合です。
議院内閣制
Q君 立法権と行政権の関係についての4つのタイプがあるといいますが、それぞれ、説明してください。
A先生
1)アメリカ型 議会と政府を完全に分離して、それぞれに民意を反映させます。
2)旧ドイツ型 君主制の下で、政府は君主に対して責任を負い、議会に対しては何の責任も負いません。
3)スイス型 政府がもっぱら議会によって選任され、その指揮に属します。
4)イギリス型 議院内閣制です。
Q君
議院内閣制の本質についての二つの学説の対立があるといいます。
一元論(責任本質説)対二元論(均衡本質説)ということですが、それぞれ、説明してください。
A先生
責任本質説~議院内閣の本質を内閣の存在が議会の信任にあることに求めます。議会と内閣の一体性を強調します。そういう意味で一元論であります。
均衡本質説~議会と内閣の対等性を重視し、議会の不信任決議に対して、内閣が解散権で対抗することに議院内閣制の本質をみます。
議会と内閣を対立するという意味で、二元論であります。
議院内閣制をいろいろな角度で説明しているというようなレベルで理解しておくとよいでしょう。
Q君 衆議院の解散が行われる場合とは?
A先生
7条と69条 ここも大きな論争があったが、現在は、7条解散ができるということで実務的に確定しているので、それほど重要な論点ではありません。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
Q君 解散権の機能を説明してください。
A先生
解散権の機能は、以下、3つあります。
1)国民投票としての機能~重要論点を国民に問うことです。例えば、「郵政民営化」の論点を問う形で、過去に解散がなされました。
2)民意の反映が二つ目の機能です。
3)内閣に対する国民の信任が三つ目の機能です。
以上
最新の画像[もっと見る]
-
 有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
4週間前
有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
4週間前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
4週間前
-
 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4週間前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4週間前
-
 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4週間前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4週間前
-
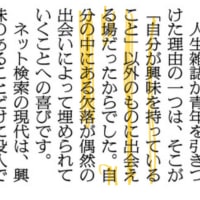 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4週間前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
4週間前
-
 自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。
4週間前
自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。
4週間前
-
 千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。
1ヶ月前
千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。
1ヶ月前
「シチズンシップ教育」カテゴリの最新記事
 勉強会開催します。4月11日(金)19時〜21時。テーマ;『あるべき会計と現行の会計...
勉強会開催します。4月11日(金)19時〜21時。テーマ;『あるべき会計と現行の会計... 子ども達、オンラインゲームでオンラインゲームで、怖い大人に、捕まらないで!
子ども達、オンラインゲームでオンラインゲームで、怖い大人に、捕まらないで! デジタルシチズンシップ教育、真実を知る最も確実な方法は、生身の人間の言葉。
デジタルシチズンシップ教育、真実を知る最も確実な方法は、生身の人間の言葉。 デジタルシチズンシップ教育、ここ中央区でも、実践してまいりましょう。まいりま...
デジタルシチズンシップ教育、ここ中央区でも、実践してまいりましょう。まいりま... 子どもの権利条約を知る。最も大事な権利のひとつ、意見表明権
子どもの権利条約を知る。最も大事な権利のひとつ、意見表明権 今回の非常戒厳の轍を、日本は、絶対に踏まないようにしなくてはなりません。
今回の非常戒厳の轍を、日本は、絶対に踏まないようにしなくてはなりません。 若者の声の反映、活動の場の創出、『こども計画』でも織り込む必要性。その際の大...
若者の声の反映、活動の場の創出、『こども計画』でも織り込む必要性。その際の大... 子どもアドボカシーの視点、権利侵害とアドボカシー
子どもアドボカシーの視点、権利侵害とアドボカシー 子どもの意見表明支援(子どもアドボケイト)について都の考え方のひとつ
子どもの意見表明支援(子どもアドボケイト)について都の考え方のひとつ 子ども達の中央区議会、見学会。子ども達自身から、たくさんのご意見、ありがとう...
子ども達の中央区議会、見学会。子ども達自身から、たくさんのご意見、ありがとう...
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます