事案:
Xは、Yに賃貸していた貸室(以下、「本件物件」という。)について、所有者と称する訴外Aから明渡しを求める訴訟が提起され(前訴)、Yに訴訟告知した。
YはXのために補助参加。本件物件の所有権は賃貸借締結当時からAに帰属していたと認定され、Xの全部敗訴の判決が確定。
前訴が提起された後、Yは賃料をXに支払っていなかったため、上記判決確定後に、Xは、本件物件の所有権が自己にあることを前提として、Yに対して延滞賃料等の支払いを求める訴訟を提起した(後訴)。
前訴に補助参加したYとして、前訴の判決の効力を、後訴においてどこまで主張できるかが法的問題点である。
問題となる条文:
民訴法46条
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
条文のどの文言解釈が問題か
「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対しても効力を有する。」(民訴法46条)というその「効力」の及ぶ範囲の解釈が問題となっている。
自分と反対の考え方:
被参加人・相手方間の判決の既判力を参加人に拡張することを定めた規定と位置づける既判力説。
上記考え方の問題点:
既判力の一般原則通り、主文中の判断だけが効力を生じるとすると、後訴裁判所は所有権の帰属についての判断に拘束されないから、後訴において、前訴とは矛盾する判断である所有権はXに属する旨の判断がなされる可能性があり問題である。
→46条各号のような制約は、既判力の本質と相容れない。
自分の考え方:
民訴法46条に定める判決の補助参加人に対する効力は、既判力とは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後、補助参加人・被参加人相互間で、その判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。
なぜならば、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者(補助参加人)が、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るために、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、協力しえたにもかかわらず、敗訴した場合の敗訴の責任もまた補助参加人に分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法46条が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、民訴法53条が単に訴訟告知を受けたに過ぎないものについても同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法46条は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものとするのが合理的であるからである。
本件では、前訴の確定判決の効力は、その訴訟の被参加人たるXと補助参加人たるYとの間においては、その判決の理由中でなされた判断である本件物件の所有権が賃貸当時Xには属していなかったとの判断にも及ぶものというべきであり、したがって、Xは、前訴の判決の効力により、本訴においても、Yに対し、本件物件の所有権が賃貸当時Xに属していたと主張することは許されないと解すべきである。
最判45年10月22日民集24巻11号1583頁(主要判例137、百選4-104)
Xは、Yに賃貸していた貸室(以下、「本件物件」という。)について、所有者と称する訴外Aから明渡しを求める訴訟が提起され(前訴)、Yに訴訟告知した。
YはXのために補助参加。本件物件の所有権は賃貸借締結当時からAに帰属していたと認定され、Xの全部敗訴の判決が確定。
前訴が提起された後、Yは賃料をXに支払っていなかったため、上記判決確定後に、Xは、本件物件の所有権が自己にあることを前提として、Yに対して延滞賃料等の支払いを求める訴訟を提起した(後訴)。
前訴に補助参加したYとして、前訴の判決の効力を、後訴においてどこまで主張できるかが法的問題点である。
問題となる条文:
民訴法46条
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
条文のどの文言解釈が問題か
「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対しても効力を有する。」(民訴法46条)というその「効力」の及ぶ範囲の解釈が問題となっている。
自分と反対の考え方:
被参加人・相手方間の判決の既判力を参加人に拡張することを定めた規定と位置づける既判力説。
上記考え方の問題点:
既判力の一般原則通り、主文中の判断だけが効力を生じるとすると、後訴裁判所は所有権の帰属についての判断に拘束されないから、後訴において、前訴とは矛盾する判断である所有権はXに属する旨の判断がなされる可能性があり問題である。
→46条各号のような制約は、既判力の本質と相容れない。
自分の考え方:
民訴法46条に定める判決の補助参加人に対する効力は、既判力とは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後、補助参加人・被参加人相互間で、その判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。
なぜならば、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者(補助参加人)が、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るために、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、協力しえたにもかかわらず、敗訴した場合の敗訴の責任もまた補助参加人に分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法46条が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、民訴法53条が単に訴訟告知を受けたに過ぎないものについても同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法46条は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものとするのが合理的であるからである。
本件では、前訴の確定判決の効力は、その訴訟の被参加人たるXと補助参加人たるYとの間においては、その判決の理由中でなされた判断である本件物件の所有権が賃貸当時Xには属していなかったとの判断にも及ぶものというべきであり、したがって、Xは、前訴の判決の効力により、本訴においても、Yに対し、本件物件の所有権が賃貸当時Xに属していたと主張することは許されないと解すべきである。
最判45年10月22日民集24巻11号1583頁(主要判例137、百選4-104)

















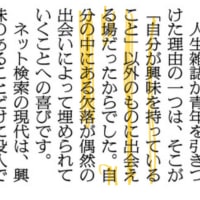









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます