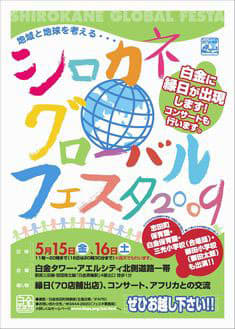3日間の熊本・阿蘇~菊池の旅から帰ってくる。
阿蘇の圧倒的なスケールの中で大地の上にしっかりと立ち、
いのちと向き合いながら生きる阿蘇百姓村の山口力男さん。
山口力男さんの管理する大草原で、自然と共に牛と語りつつ、
生命とか、宇宙とか、普段考えないことを考えてきました。
原に風が吹き、里に桜が満開でした。

百姓村につくと研修生が子牛の餌やりにいくというので、連れていってもらう。
10数頭の子牛がいて、彼らに餌をやる。
彼らは1年近く育てられた後、肥育農家に手に渡る。
自然の餌をあげるので、出荷までは、他の牛飼いの時間よりも長い。
彼らのつぶらな瞳をみつつ、鼻をなでつつ、言葉にならないことを想う。
後に力男さんが発した「食べ物は生命に直結する」という言葉が響く。
そう。食べる自分の生命にも、食べられる牛の生命にも。

百姓村に戻って、温泉でも行こうかと外に出ようとしたところで、
力男さんがやってくる。
そのまま、温泉に向かう。
途中、近所の牛飼いのところによる。
温泉場でも、力男さんはたくさんの人に声をかけ、かけられていた。
時計の時間を意識していないだけで、
目の前にいる人と共にいる時間は意識している。
時計を気にしてカリカリするよりも、
そちらのほうがよっぽど誠実な態度なのかもしれないと、
阿蘇の大地では思えるようになる。

風呂に入った後、飯を食い、その後百姓村で、夜が更けるまで語る。
話しは、マサイ族の話から、中国のトイレのことから、
村と障害者の関係から、縦横無尽に広がる。
でも、何か根源的なところでつながっているように感じられ、
気は引き締まっていく。そして、阿蘇の夜が更ける。
この日、満月の一日前。byこっぺ

晴耕雨読人類往来記







































































































 本日午後に、
本日午後に、