昨日、テレビでジャック・ニコルソン(Jack Nicholson、1937‐)が主演の『ボーダー(The Border)』(1982)を観た。ジャック・ニコルソンといえば、学生時代に『カッコーの巣の上で( One Flew Over the Cuckoo's Nest)』(1975、監督Miloš Forman)を観て、間違いなく衝撃を受けたことが第一の思い出だ。『カッコーの巣の上で』のニコルソンの演技もそうだったが、大体、彼が演じる主人公はけっして表立(おもてだ)った正義の味方などではない。しかし、あり余る感情(芸術的な感性の表出といってもいい)を持て余すほど持っており、その感情をときに立場もわきまえず不都合な状況下(精神病棟や国境のボーダーライン)で弱者(患者や移民希望者)への思いやりに使ってみるような訳(わけ)の分からない男だ。格好(かっこう)いい役者が演じるヒーローや正義漢が全身から滲(にじ)ませる理路整然や首尾一貫性がないから、観ている者は、ニコルソンの演じるアクの強い捻(ひね)くれたアウトサイダー役を多少やきもきしながら半信半疑で見つめている。それでも見続けるのは、悪人相なニコルソンが時折、垣間見せる照れて恥ずかしそうな笑みである。あれは得(え)も言われぬ笑みだ。何かを思い出したように内面からひょいっと浮かび上がってくるシャイで無垢(むく)な笑みに、観客は惹(ひ)かれるし、もしかしてこの男は本気かしらと真心(まごころ)を信用したくなるのである。美男系の男優よりは醜(ぶ)男系に、そんな笑い方をする役者が居る。アメリカの俳優では、ほかに『タクシードライバー(Taxi Driver)』(1976、監督Martin Scorsese)のロバート・デ・ニーロ(Robert De Niro、1943‐)もそんな笑みを持っている。日本の俳優では、含羞(がんしゅう)派の笑みを発現する役者は、演技力はいささか劣るかもしれないが、『男はつらいよ』(1969‐95、全49作)の渥美清(1928-96)、そして同じく寅さんに子役時代から出ていた吉岡秀隆(1970‐)ではないか。吉岡がやはり子役時代から出演したテレビドラマ『北の国から』(1981‐82、ドラマスペシャル83‐2002)は、放映が始まるその少し前まで学生時代を北海道で過ごした直近の記憶も相俟(あいま)って、小生にとって忘れがたい作品になっている。
 嫌々ながら国境警備隊員になった内気な主人公
嫌々ながら国境警備隊員になった内気な主人公
 気はいいが浪費家の妻とはどこか合わない
気はいいが浪費家の妻とはどこか合わない
 アメリカへ国境を越えたい娘を命がけで助ける
アメリカへ国境を越えたい娘を命がけで助ける
 『カッコーの巣の上で』のニコルソン
『カッコーの巣の上で』のニコルソン
 『タクシードライバー』のデ・ニーロ
『タクシードライバー』のデ・ニーロ
 『男はつらいよ』
『男はつらいよ』
 『北の国から』の吉岡
『北の国から』の吉岡
今日の日経を読んでいたら、最終面にレンブラント「笑う自画像(ゼウクシスとしての自画像)」が紹介されていた。レンブラント63歳(小生と同い年)、最晩年の自画像だそうだ。ジャック・ニコルソンやロバート・デ・ニーロ、渥美清、吉岡秀隆の件(くだん)の笑みは、このレンブラント(Rembrandt、1606‐69)の「笑う自画像」を想起させる。生活にも困窮するオランダ人画家が、人生の最期(さいご)に鏡の中に見詰めた、内面からの光にぽっと照らし出されたような、リクエストに仕方なく応えてにそにそと力もなくじんわりと笑ってみせる、どうにでもとれる情(なさ)けないような自分の顔を描いたのである。
 Rembrandt
Rembrandt
 Jack Nicholson
Jack Nicholson
 Robert De Niro
Robert De Niro
 渥美清
渥美清
 吉岡秀隆
吉岡秀隆
『ボーダー』という映画は、上に掲載したスチール写真からも想像がつくように低予算の「B級映画」ぽい感じがするが、内容は、ジャック・ニコルソンの演技力によってぐっと彫りが深いものになっている。監督はイギリス人のトニー・リチャードソン(Tony Richardson、1928‐91)。映画界には珍しいオックスフォード大学出身の奇才で、最期は彼が監督した『マドモアゼル(Mademoiselle)』(1966、ジャン・ジュネ原案)で主演したあのフランスの大女優ジャンヌ・モロー(Jeanne Moreau、1928-2017)に看取(みと)られて、レンブラントと同じ63歳という年齢でエイズで亡くなった。同監督の遺作となった『ブルースカイ(Blue Sky)』(1994)は、以前、このブログでも取り上げた。『トッツィー(Tootsie)』(1982)でアカデミー助演女優賞を受賞したジェシカ・ラング(Jessica Lange、1949‐)は、この『ブルースカイ』で同主演女優賞を受賞している。『ボーダー』と『ブルースカイ』のこの2作だけの印象からすると、同監督は、正義を律義に心の奥に秘めて行動力がある並外れて心優しい夫とその夫のことを理解しない性的で自由奔放(ほんぽう)な妻というパターンの夫婦(しかも別れない)を描いて優れている。そこには、バイセクシュアルという彼の性的傾向と両性への理想主義が色濃く出ていたのかもしれない。
 Tony Richardson
Tony Richardson
 Jeanne Moreau
Jeanne Moreau
 『Mademoiselle』
『Mademoiselle』
 『Blue Sky』
『Blue Sky』
 『Tootsie』のラング
『Tootsie』のラング
リチャードソン監督は、ジョン・アーヴィング(John Irving、1942‐)原作の映画『ホテル・ニューハンプシャー(The Hotel New Hampshire)』(1984)を撮っているが、そこで主役に抜擢したのが、Yale大学卒の才媛ジョディ・フォスター(Jodie Foster、1962‐)であった。ジョディは13歳で『タクシー・ドライバー』の少女娼婦役を演じて高い評価を得たそうだが、あれがジョディー・フォスターだったとは今になって知った。つい最近、『告発の行方(The Accused)』(1988)という、ジョディがアカデミー主演女優賞を受賞したレイプを扱った映画(レイプを煽ったり黙って傍観していた者の罪をも問うている問題作)を観たばかりなので、何かの因縁、関連を感じている。ただし残念ながら、『マドモアゼル』も『ホテル・ニューハンプシャー』も観ていないので、大した根拠のある話にもならないのだが、ただ、リチャードソン氏は、ニコルソンや『ブルースカイ』で主演したトミー・リー・ジョーンズ(Tommy Lee Jones、1946‐)のような男優もそうだが、女優中の女優、モロー、ジョディやラングのような賢く演技も達者な女優が好きだったし、個性を存分に引き出すことに長(た)けていた思う。生半可(なまはんか)な役者では、とても彼の文芸的世界を十分に演じ切れないと感じていたのではないか。
 『The Hotel New Hampshire』
『The Hotel New Hampshire』
 『タクシードライバー』のジョディ
『タクシードライバー』のジョディ
 『告発の行方』のレイプシーン
『告発の行方』のレイプシーン
 若き日のジョディ・フォスター
若き日のジョディ・フォスター
こうして映画の世界を巡っていると、あれもこれも次から次へ連想が止まらなくなってしまう。大学時代に淀川長治の「ラジオ名画劇場」を毎週楽しみに聴いていた影響があるのかもしれない。自分でもそれほどとは思っていなくても、小生、映画もしくはそこに出演している役者個人のことがかなり好きらしい。その流れで最後に、今回、調べていて知ったことだが、Yale大学の演劇大学院を卒業し、ニューヨークで舞台女優として活動を始めていたメリル・ストリープ(Meryl Streep、1949‐)は、『タクシードライバー』のデ・ニーロの演技に衝撃を受け、以後、映画のオーディションを受けるようになった。奇しくも、デ・ニーロがチェーホフの芝居『桜の園』に出演していたストリープの演技に目を止め、『ディア・ハンター(The Deer Hunter)』(1978、監督Michael Cimino)の出演者に推挙したという。ストリープは、特に好きな女優でもなかったが、最近、二度目の視聴になる『マーガレット・サッチャー 鉄の女(The Iron Lady)』(2011)を観て、成程(なるほど)コクのある演技だなと思った。ストリープは、この堂々たる演技でアカデミー主演女優賞を受賞。『Kramer vs. Kramer(クレイマー、クレイマー)』(1979)や『The Bridges of Madison County(マディソン郡の橋)』(1995)の例もあるが、こういうただ者ならぬ立派な風貌の女性を妻に持つと旦那と言うのは一体どういう心境になるのかな、とふと思う。そういえば、大分前になるが、『31年目の夫婦げんか(Hope Springs)』(2012)というストリープとトミー・リー・ジョーンズで倦怠期にさしかかった夫婦がカウンセリングを受けるコメディー映画も観たな。ああした円熟した柔らかい味も出せる女優である。イエールとハーバード出身の競演だからずいぶん高学歴なコンビだ。『ディア・ハンター』については、ベトナム戦争におけるあのロシアンルーレットの恐怖とともに、小生にとって学生時代に観たやはり忘れようとしても忘れられない衝撃の作品だった。あの忍び泣かせるギターの音色が特徴のテーマ曲「Cavatina」(作曲Stanley Myers)が聴こえてくると、寒々と寂しいアメリカの田舎町、ピッツバーグ郊外にある製鉄の町Clairton(Rust Belt地帯にあるこの町の名を使っただけで、実際の映画は、ここで撮られたわけではなかったようだが)の情景がまるで行ったことがあるかのように今でも彷彿(ほうふつ)と眼(まなこ)に浮かび来て居たたまれないほど切なく、胸キュンとなる。
 『タクシードライバー』のデ・ニーロの演技
『タクシードライバー』のデ・ニーロの演技
 『The Deer Hunter』
『The Deer Hunter』
 ロシアンルーレットで思い出すシーン
ロシアンルーレットで思い出すシーン
 『The Iron Lady』
『The Iron Lady』
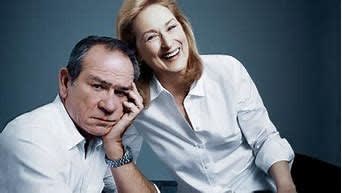 『Hope Springs』
『Hope Springs』
 Clairton in 1973
Clairton in 1973
◆追記:YouTubeの「Cavatina」にこんなコメントがあった。「My dad was an army doctor in Vietnam. I remember the night he came home from seeing this movie with my mother. He had an expression and look on his face that I had never seen before or since.Years later I asked him what he thought of the Dear Hunter. He said that it was the most accurate movie on Vietnam that he had ever seen. The depiction of the times and the entire recapturing of the experience in Vietnam American soldier was unbelievable and it brought him right back to Vietnam .」切ない気分になるのは、単なる感傷からだけではないのかもしれない。それだけ心象におけるリアルな映画だったのだ。
 嫌々ながら国境警備隊員になった内気な主人公
嫌々ながら国境警備隊員になった内気な主人公 気はいいが浪費家の妻とはどこか合わない
気はいいが浪費家の妻とはどこか合わない アメリカへ国境を越えたい娘を命がけで助ける
アメリカへ国境を越えたい娘を命がけで助ける 『カッコーの巣の上で』のニコルソン
『カッコーの巣の上で』のニコルソン 『タクシードライバー』のデ・ニーロ
『タクシードライバー』のデ・ニーロ 『男はつらいよ』
『男はつらいよ』 『北の国から』の吉岡
『北の国から』の吉岡今日の日経を読んでいたら、最終面にレンブラント「笑う自画像(ゼウクシスとしての自画像)」が紹介されていた。レンブラント63歳(小生と同い年)、最晩年の自画像だそうだ。ジャック・ニコルソンやロバート・デ・ニーロ、渥美清、吉岡秀隆の件(くだん)の笑みは、このレンブラント(Rembrandt、1606‐69)の「笑う自画像」を想起させる。生活にも困窮するオランダ人画家が、人生の最期(さいご)に鏡の中に見詰めた、内面からの光にぽっと照らし出されたような、リクエストに仕方なく応えてにそにそと力もなくじんわりと笑ってみせる、どうにでもとれる情(なさ)けないような自分の顔を描いたのである。
 Rembrandt
Rembrandt Jack Nicholson
Jack Nicholson Robert De Niro
Robert De Niro 渥美清
渥美清 吉岡秀隆
吉岡秀隆『ボーダー』という映画は、上に掲載したスチール写真からも想像がつくように低予算の「B級映画」ぽい感じがするが、内容は、ジャック・ニコルソンの演技力によってぐっと彫りが深いものになっている。監督はイギリス人のトニー・リチャードソン(Tony Richardson、1928‐91)。映画界には珍しいオックスフォード大学出身の奇才で、最期は彼が監督した『マドモアゼル(Mademoiselle)』(1966、ジャン・ジュネ原案)で主演したあのフランスの大女優ジャンヌ・モロー(Jeanne Moreau、1928-2017)に看取(みと)られて、レンブラントと同じ63歳という年齢でエイズで亡くなった。同監督の遺作となった『ブルースカイ(Blue Sky)』(1994)は、以前、このブログでも取り上げた。『トッツィー(Tootsie)』(1982)でアカデミー助演女優賞を受賞したジェシカ・ラング(Jessica Lange、1949‐)は、この『ブルースカイ』で同主演女優賞を受賞している。『ボーダー』と『ブルースカイ』のこの2作だけの印象からすると、同監督は、正義を律義に心の奥に秘めて行動力がある並外れて心優しい夫とその夫のことを理解しない性的で自由奔放(ほんぽう)な妻というパターンの夫婦(しかも別れない)を描いて優れている。そこには、バイセクシュアルという彼の性的傾向と両性への理想主義が色濃く出ていたのかもしれない。
 Tony Richardson
Tony Richardson Jeanne Moreau
Jeanne Moreau 『Mademoiselle』
『Mademoiselle』 『Blue Sky』
『Blue Sky』 『Tootsie』のラング
『Tootsie』のラングリチャードソン監督は、ジョン・アーヴィング(John Irving、1942‐)原作の映画『ホテル・ニューハンプシャー(The Hotel New Hampshire)』(1984)を撮っているが、そこで主役に抜擢したのが、Yale大学卒の才媛ジョディ・フォスター(Jodie Foster、1962‐)であった。ジョディは13歳で『タクシー・ドライバー』の少女娼婦役を演じて高い評価を得たそうだが、あれがジョディー・フォスターだったとは今になって知った。つい最近、『告発の行方(The Accused)』(1988)という、ジョディがアカデミー主演女優賞を受賞したレイプを扱った映画(レイプを煽ったり黙って傍観していた者の罪をも問うている問題作)を観たばかりなので、何かの因縁、関連を感じている。ただし残念ながら、『マドモアゼル』も『ホテル・ニューハンプシャー』も観ていないので、大した根拠のある話にもならないのだが、ただ、リチャードソン氏は、ニコルソンや『ブルースカイ』で主演したトミー・リー・ジョーンズ(Tommy Lee Jones、1946‐)のような男優もそうだが、女優中の女優、モロー、ジョディやラングのような賢く演技も達者な女優が好きだったし、個性を存分に引き出すことに長(た)けていた思う。生半可(なまはんか)な役者では、とても彼の文芸的世界を十分に演じ切れないと感じていたのではないか。
 『The Hotel New Hampshire』
『The Hotel New Hampshire』 『タクシードライバー』のジョディ
『タクシードライバー』のジョディ 『告発の行方』のレイプシーン
『告発の行方』のレイプシーン 若き日のジョディ・フォスター
若き日のジョディ・フォスターこうして映画の世界を巡っていると、あれもこれも次から次へ連想が止まらなくなってしまう。大学時代に淀川長治の「ラジオ名画劇場」を毎週楽しみに聴いていた影響があるのかもしれない。自分でもそれほどとは思っていなくても、小生、映画もしくはそこに出演している役者個人のことがかなり好きらしい。その流れで最後に、今回、調べていて知ったことだが、Yale大学の演劇大学院を卒業し、ニューヨークで舞台女優として活動を始めていたメリル・ストリープ(Meryl Streep、1949‐)は、『タクシードライバー』のデ・ニーロの演技に衝撃を受け、以後、映画のオーディションを受けるようになった。奇しくも、デ・ニーロがチェーホフの芝居『桜の園』に出演していたストリープの演技に目を止め、『ディア・ハンター(The Deer Hunter)』(1978、監督Michael Cimino)の出演者に推挙したという。ストリープは、特に好きな女優でもなかったが、最近、二度目の視聴になる『マーガレット・サッチャー 鉄の女(The Iron Lady)』(2011)を観て、成程(なるほど)コクのある演技だなと思った。ストリープは、この堂々たる演技でアカデミー主演女優賞を受賞。『Kramer vs. Kramer(クレイマー、クレイマー)』(1979)や『The Bridges of Madison County(マディソン郡の橋)』(1995)の例もあるが、こういうただ者ならぬ立派な風貌の女性を妻に持つと旦那と言うのは一体どういう心境になるのかな、とふと思う。そういえば、大分前になるが、『31年目の夫婦げんか(Hope Springs)』(2012)というストリープとトミー・リー・ジョーンズで倦怠期にさしかかった夫婦がカウンセリングを受けるコメディー映画も観たな。ああした円熟した柔らかい味も出せる女優である。イエールとハーバード出身の競演だからずいぶん高学歴なコンビだ。『ディア・ハンター』については、ベトナム戦争におけるあのロシアンルーレットの恐怖とともに、小生にとって学生時代に観たやはり忘れようとしても忘れられない衝撃の作品だった。あの忍び泣かせるギターの音色が特徴のテーマ曲「Cavatina」(作曲Stanley Myers)が聴こえてくると、寒々と寂しいアメリカの田舎町、ピッツバーグ郊外にある製鉄の町Clairton(Rust Belt地帯にあるこの町の名を使っただけで、実際の映画は、ここで撮られたわけではなかったようだが)の情景がまるで行ったことがあるかのように今でも彷彿(ほうふつ)と眼(まなこ)に浮かび来て居たたまれないほど切なく、胸キュンとなる。
 『タクシードライバー』のデ・ニーロの演技
『タクシードライバー』のデ・ニーロの演技 『The Deer Hunter』
『The Deer Hunter』 ロシアンルーレットで思い出すシーン
ロシアンルーレットで思い出すシーン 『The Iron Lady』
『The Iron Lady』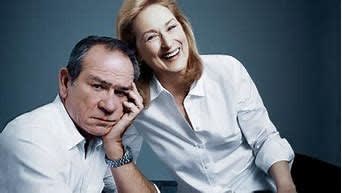 『Hope Springs』
『Hope Springs』 Clairton in 1973
Clairton in 1973◆追記:YouTubeの「Cavatina」にこんなコメントがあった。「My dad was an army doctor in Vietnam. I remember the night he came home from seeing this movie with my mother. He had an expression and look on his face that I had never seen before or since.Years later I asked him what he thought of the Dear Hunter. He said that it was the most accurate movie on Vietnam that he had ever seen. The depiction of the times and the entire recapturing of the experience in Vietnam American soldier was unbelievable and it brought him right back to Vietnam .」切ない気分になるのは、単なる感傷からだけではないのかもしれない。それだけ心象におけるリアルな映画だったのだ。












 Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk












