
※結末に触れる部分もあります。ご覧になってから読まれることをおススメします。
----このタイトル、宮崎駿のアニメそっくりだよね。
ファンタジーかなにかなの?
「原題は『The Cave of the Yellow Dog』。
あの驚愕のドキュメンタリー『らくだの涙』を手がけた
女性監督ビャンバスレン・ダバー監督の新作だ」
----驚愕のドキュメンタリーってどういうこと?
「難産の母らくだがその後遺症から子育てを拒否。
そこでらくだの飼い主は音楽家を呼んで、
らくだの前で演奏をしてもらう。
馬頭琴から流れるその音色を聞いた母らくだの目には涙が…。
そして彼女は子らくだにやさしくなる」
----うわあ、信じられない話だね。でも今度はドラマだよね。
「そうなんだけど、タッチがほとんど前作と同じ。
この映画を観ていると、
いままでの概念のドラマ、ドキュメンタリーの壁が取り払われてゆく」
----物語はどういうものなの?
「これと言った物語はないんだ。
羊の放牧をする父親と母親、そして娘ふたり、小さな男の子の4人家族。
ある日、6歳になる長女ナンサはお手伝いの途中、
寄り道をしたほら穴で子犬のツォーホルと出会う。
犬を飼うことを許してくれない父親に隠れて、ナンサはツォーホルを飼う。
この話の中に、おばあさんが語る<黄色い犬の伝説>が挟み込まれる」
----ほんと、なんてことない話だ。
「ところが、この家族がぼくらの日常感覚からはあまりに遠く離れている。
一番下の1歳の息子なんて、
母親がこんなに目を離していいのかなという感じで、見ていてハラハラ。
監督によれば、モンゴルではあまり甘やかせて育てるとガラスの子供になると、
小さい頃から危険なことをしても決して反対しないらしい。
この映画は、その放任が一つの<スリル>を生み、
ぼくらの目をスクリーンに強く引きつける」
----そうか、珍しい風物が見られるというだけじゃないんだ。
「もちろん、それはたくさん出てくるけどね。
牛のフンで肉が燻され、同じそのフンで子供たちは遊ぶ。
そのときの子供の無邪気な笑顔。
こんなすてきな笑顔を僕はいままで見たことない。
また一方では、お父さんが羊の皮を剥ぎ、
その残った肉はハゲワシがつつくなんて、
ショッキングな映像もあれば、
羊の乳からチーズができるまでや、
草原を移動するためにゲルを解体する過程も見られる」
----ゲルって?
「中国語読みの<パオ>のことだよ」
---あっ、昨年、瀬戸内海の直島で泊まったあれだね。
 ※直島のパオ
※直島のパオ
「そう。実際に泊まったことがあるだけに親近感が沸いたね。
それはともかくとして、そんな彼らにも文明が入り込んでくる。
町に皮を売りにいったお父さんがお土産に
緑のプラスチック容器やピンクのぬいぐるみを買ってくる。
この<文明>がモンゴルの自然やゲルの中に入ってきたときに感じる
一種の違和感もこの映画の特徴だ。
それまでに徐々に慣れ親しんできたこのすばらしい風景が
汚されてしまったように感じるんだね」
----でも、それって文明先進国に住む人の勝手な思いじゃ?
「うん。そこがこの映画の重要なポイントだろうね。
安息や無垢など、
<よその>ぼくたちが残しておきたいと思う伝統的な価値観。
便利さや教育など、
<そこの>遊牧民たちが取り入れることに利点を見出す近代的価値観」
----う~ん、分かるような分からないような。
物語の方は、このあとどうなるの?
「移動の途中、一番下の子が車から落ちてしまうんだ。
馬で探しに戻るお父さん。
彼が目にしたのは、ハゲワシからその子を守った犬のツォーホル。
これで一件落着と、次の放牧地に向かう家族と羊たちの前に
突然、選挙広報車が現れ、スピーカーで叫ぶ。
「正しい決断をしよう」。
群れていた羊たちは車に道を譲り、またひとつになる。
雄大な緑の草原を背景としたこのエンディングに、
なぜか涙があふれて止まらなくなった。
あとで、その理由を考えてもよく分からない。
プレスで絵本作家の佐野洋子さんのコラム
『空と草原と風だけなのに』を読んで、またまた涙」
----佐野洋子さんなら僕も知っているよ。
「100万回生きたねこ」を書いた人でしょ?
「うん。
そこには、自分がこの映画に涙した理由を解く鍵が隠されていたんだ。
オフィシャルに載ったらリンクを張るけど
おそらくこの佐野さんのコラムを超えるレビューは誰にも書けないと思うね」
(byえいwithフォーン)
※笑顔がすてきだ度


※ドイツでのこの映画のサイト(予告編も観られます)
人気blogランキングもよろしく
☆「CINEMA INDEX」☆「ラムの大通り」タイトル索引
(他のタイトルはこちらをクリック→)

----このタイトル、宮崎駿のアニメそっくりだよね。
ファンタジーかなにかなの?
「原題は『The Cave of the Yellow Dog』。
あの驚愕のドキュメンタリー『らくだの涙』を手がけた
女性監督ビャンバスレン・ダバー監督の新作だ」
----驚愕のドキュメンタリーってどういうこと?
「難産の母らくだがその後遺症から子育てを拒否。
そこでらくだの飼い主は音楽家を呼んで、
らくだの前で演奏をしてもらう。
馬頭琴から流れるその音色を聞いた母らくだの目には涙が…。
そして彼女は子らくだにやさしくなる」
----うわあ、信じられない話だね。でも今度はドラマだよね。
「そうなんだけど、タッチがほとんど前作と同じ。
この映画を観ていると、
いままでの概念のドラマ、ドキュメンタリーの壁が取り払われてゆく」
----物語はどういうものなの?
「これと言った物語はないんだ。
羊の放牧をする父親と母親、そして娘ふたり、小さな男の子の4人家族。
ある日、6歳になる長女ナンサはお手伝いの途中、
寄り道をしたほら穴で子犬のツォーホルと出会う。
犬を飼うことを許してくれない父親に隠れて、ナンサはツォーホルを飼う。
この話の中に、おばあさんが語る<黄色い犬の伝説>が挟み込まれる」
----ほんと、なんてことない話だ。
「ところが、この家族がぼくらの日常感覚からはあまりに遠く離れている。
一番下の1歳の息子なんて、
母親がこんなに目を離していいのかなという感じで、見ていてハラハラ。
監督によれば、モンゴルではあまり甘やかせて育てるとガラスの子供になると、
小さい頃から危険なことをしても決して反対しないらしい。
この映画は、その放任が一つの<スリル>を生み、
ぼくらの目をスクリーンに強く引きつける」
----そうか、珍しい風物が見られるというだけじゃないんだ。
「もちろん、それはたくさん出てくるけどね。
牛のフンで肉が燻され、同じそのフンで子供たちは遊ぶ。
そのときの子供の無邪気な笑顔。
こんなすてきな笑顔を僕はいままで見たことない。
また一方では、お父さんが羊の皮を剥ぎ、
その残った肉はハゲワシがつつくなんて、
ショッキングな映像もあれば、
羊の乳からチーズができるまでや、
草原を移動するためにゲルを解体する過程も見られる」
----ゲルって?
「中国語読みの<パオ>のことだよ」
---あっ、昨年、瀬戸内海の直島で泊まったあれだね。
 ※直島のパオ
※直島のパオ「そう。実際に泊まったことがあるだけに親近感が沸いたね。
それはともかくとして、そんな彼らにも文明が入り込んでくる。
町に皮を売りにいったお父さんがお土産に
緑のプラスチック容器やピンクのぬいぐるみを買ってくる。
この<文明>がモンゴルの自然やゲルの中に入ってきたときに感じる
一種の違和感もこの映画の特徴だ。
それまでに徐々に慣れ親しんできたこのすばらしい風景が
汚されてしまったように感じるんだね」
----でも、それって文明先進国に住む人の勝手な思いじゃ?
「うん。そこがこの映画の重要なポイントだろうね。
安息や無垢など、
<よその>ぼくたちが残しておきたいと思う伝統的な価値観。
便利さや教育など、
<そこの>遊牧民たちが取り入れることに利点を見出す近代的価値観」
----う~ん、分かるような分からないような。
物語の方は、このあとどうなるの?
「移動の途中、一番下の子が車から落ちてしまうんだ。
馬で探しに戻るお父さん。
彼が目にしたのは、ハゲワシからその子を守った犬のツォーホル。
これで一件落着と、次の放牧地に向かう家族と羊たちの前に
突然、選挙広報車が現れ、スピーカーで叫ぶ。
「正しい決断をしよう」。
群れていた羊たちは車に道を譲り、またひとつになる。
雄大な緑の草原を背景としたこのエンディングに、
なぜか涙があふれて止まらなくなった。
あとで、その理由を考えてもよく分からない。
プレスで絵本作家の佐野洋子さんのコラム
『空と草原と風だけなのに』を読んで、またまた涙」
----佐野洋子さんなら僕も知っているよ。
「100万回生きたねこ」を書いた人でしょ?
「うん。
そこには、自分がこの映画に涙した理由を解く鍵が隠されていたんだ。
オフィシャルに載ったらリンクを張るけど
おそらくこの佐野さんのコラムを超えるレビューは誰にも書けないと思うね」
(byえいwithフォーン)
※笑顔がすてきだ度



※ドイツでのこの映画のサイト(予告編も観られます)
人気blogランキングもよろしく

☆「CINEMA INDEX」☆「ラムの大通り」タイトル索引
(他のタイトルはこちらをクリック→)










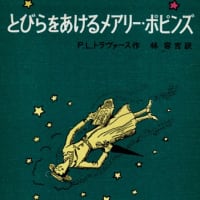

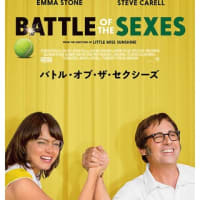



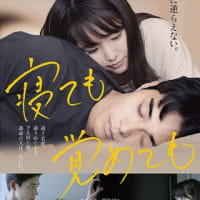



近代化との関わり、変化していく生活の描かれ方がとても自然で、それが言葉にならない深い想い、問題を心に残すような気がします。緑の草原、青い空と白い雲と共に、プラスチックやぬいぐるみの人工的な色が強烈に印象に残りました。観て良かったです!
ず~っと続く緑の海に、羊と人がぽつぽつ。
モンゴルってすごいところですね。
この監督は前作『らくだの涙』がフロックではなかったことを
見事に証明してくれました。
ラストはなぜだか涙が流れてなりませんでした。
■Renさん
私の知人に、ここ15年ほど毎年モンゴルに行っている人がいます。
星空など、ほんとうに筆舌につくしがたいようです。
この自然、いつまでも残ってほしいものですね。
この映画、すごく良かったですね。
まずキャストが「モンゴルで暮らす遊牧民の家族と子犬」
と書いてあったところに強く惹かれました。笑
モンゴルだからこうな訳ではなくて、昔はどこの国も
似たような生活を送っていたのでしょうね。
“文明”は確かにすごいインパクトでした。
いつか彼らも今の私たちのような生活を送る日が
来るのでしょうか。。。
コメント、面白かったです☆
また来ます!
この映画のすてきなところは、
アート、アートしていないところです。
全然お高く止まっていない。
ある家族の生活を写しただけでこれだけ感動できると言うのは、
やはりその生活がシンプルにも関わらず
中身がとても豊穣だからでしょうね。
芸術性を求めすぎた作品は、一般にはウケないのの
逆で、自然さを求めた作品は観客の心に
自然と入ってくるのでしょうね。
この監督の「生活観」の描き方が好きです。
私は、あまりTBやコメント残しなどしないのですが、
次のGWに、直島か小豆島で一泊しようと思っているのです。
実家が香川なんですが、身近なようで遠い、その島に泊まってみようかと。
安藤忠雄さんの作品もあるとか聞きますし。(まだ調べてないけど)
私も、あのゲルがいつも不思議だったので、そういう風景を見れて嬉しかったです。
コメントありがとうございます。
直島は、画家の知人から聞いていったのですが、
ぜひもう一度行きたいと思っています。
行った時の日記が出てきましたので、
恥ずかしながらURLを記しておきます。
また、来てくださいね。
http://plaza.rakuten.co.jp/durhum/diary/200411140000/
僕も、佐野よう子さんの感想には、この人らしいたしかな視点だなあ、と思わせられました。パオ(ゲル)を、近頃は、子供部屋とか、遊び部屋に、買い求める人が、日本でも、増えてきつつあるみたいですね。
パオを子供部屋にですか?
それは敷地が相当ないと難しいですね。
うらやましい話ではあります。