
寒さが厳しい地域では、樹木は落葉によって体力を維持する。寒さがそれほどでもない地域では落葉せず、常緑の広葉樹林となる。
葉を維持し続けるために、寒さ対策として、熱帯多雨林のものより、葉を小さく、厚くする傾向がある。カシ、クス、シイ、ツバキなどがその例。
極相林としては、『もののけ姫』の森が近い。日が地面まで差し込まず、シダ、コケがひしめき合う。
照葉樹林帯は 東は日本から 中国沿岸を抜けて 西はヒマラヤ山麓まで連なる。要は寒過ぎず、暑過ぎずの地域。
かつて一斉を風靡した『照葉樹林文化』という考え方があった。照葉樹林帯の各地において、同時多発的にある類似した食文化、農業、風習、宗教、伝説を指す。
原生植物の種類と文明・文化の関連傾向についての論。
例えば、
焼畑農業と雑穀栽培。お茶。儀礼食としての餅。なれ寿司。水にさらしてアクを抜く技術。漆器。養蚕。麹からつくる醸造酒。豆の発酵食品。柑橘とシソ類の栽培。
食物、環境が思想にも影響するのは確か。当然似てくる。
月の信仰。山上他界の観念。精霊信仰。異形の神。羽衣伝説。鳥居と注連縄。
ユングが、『普遍的無意識』という考え方をしていたけれど、フィールドワークをしていれば、もう少し違った見方が出ていたかも知れないな。
照葉樹林は、伐採など人が手を加えると、落葉広葉樹に遷移してしまう。スギ、ヒノキの人工林もある。現在、比較的まとまっているのは 『鎮守の森』など。
ウチの周りでもマツが枯れて、その後に照葉樹が生え、雑木林になりつつある。
ドングリが実る種類が増えれば、山ももっと賑やかになるだろうが、竹ヤブが脅威。雑木林ものみ込んで繁殖していき、木々を枯らす。
方々で、竹害となっているが、ウチの周りにしても同じこと。高齢者が増え、放棄された農地が竹ヤブになっているところが増えている。
中国には、『无肉使人痩 无竹使人俗(肉がないと人は太らず、竹がないと人は俗になる)』という言葉があるが、ほどほどにして頂きたいなぁ
環境が文化・思想を生み出す。
荒れた藪では……。
身の回りの環境整備をしないとなぁ。いよいよ今年もあと少し。













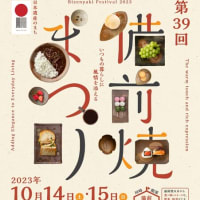
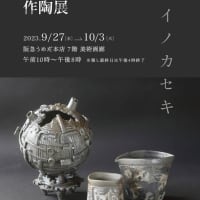



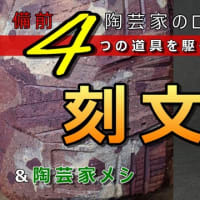





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます