関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPします。
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)から。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
--------------------------------------
ここからは、いよいよ忍秩父観音霊場、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の核心部に入っていきます。小規模で無住の寺も多く、御朱印拝受難易度は高いです。
■ 光明山 地蔵院 観音寺
熊谷市上中条2018
高野山真言宗
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第10番
・こちらも無住で情報が少ないです。
『新編武蔵風土記稿』の上中條村(埼玉郡忍領)の項に「邑楽郡赤岩村光恩寺末(略)慶安二年(1649年)観音堂領トシテ十六石六斗ノ御朱印ヲ附セラル 開山了空明應五年(1496年)寂セリ 本尊不動ヲ安ス 観音堂」とあります。
・現在の御本尊は聖観世音菩薩のようで、地元では「中条観音様」と呼ばれ、信仰を集めている模様です。
・境内入口の石碑に「聖観世音安産守護」、本堂扉に「腹帯子宝祈願」「安産祈願」の案内があるので、子宝・安産に霊験あらたかな観音様のようです。
・入母屋造銅板葺で切妻様の向拝を付設しています。照りの強い本棟の屋根と起り気味の向拝屋根が独特のコントラストを見せています。
・大棟と鬼板に聖観世音菩薩の種子「サ」が掲げられているので、やはり御本尊は聖観世音菩薩とみられます。向拝正面には「観世音」の扁額が掲げられています。
・木鼻側面貘と正面獅子の彩色が異なるなど芸が細かいです。
・現在無住で、御朱印は浄瑠璃山 長慶寺(熊谷市西城93-1)で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第10番 聖観世音菩薩


■ 福聚山 阿弥陀院 利永寺
熊谷市下奈良796
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第12番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番
・こちらは、今回の記事のなかでもっともマニアックな札所かと思われます。記事UPは迷いましたが、確かに忍観音霊場の札所なのでご紹介します。
・参拝情報がほとんどなく、Googleマップで位置検索するととある企業の敷地を示すので、意を決してこちらの事務所にお伺いすると、こちらの敷地内に御座とのこと。
・ご丁寧にもご案内いただき、ようやく参拝が叶いました。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 本尊前(十一面観音)ニ同シ 観音堂 利永寺持」とあり、本堂(御本尊:十一面観世音菩薩)のほか、観音堂を擁していたかもしれません。
・整った宝形造で向拝を付設し、向拝見上げにはしっかり御詠歌の木板が掛かっていました。ただし、この木板の札番は「第七番」。こちらは忍観音霊場で第11番、幡羅郡新四国霊場で第43番のはずなので、この「第七番」というのはナゾです。
・こちらの御朱印はなかばあきらめていたのですが、一乗院様にお伺いすると、第11番観音寺のほか、こちらの御朱印(規定用紙)も授与されているとのことで、ありがたく拝受しました。
・ご紹介はしましたが、参拝時に一般企業さんのお手間をいただくこともあり、忍観音霊場巡拝者に限ってお伺いした方がよろしいかと思います。また、休業日や営業時間外の参拝も不可だと思います。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第12番 十一面観世音菩薩(大悲殿)

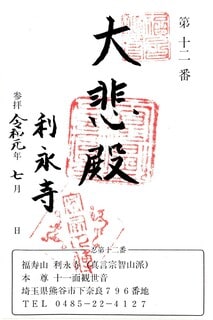
■ 大慈山 薬師院 観音寺
熊谷市下奈良913
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第11番
・この寺社巡りも、下奈良エリアに至ってますますディープな世界に入っていきます(笑)
・忍秩父三十四観音霊場第11番のこの札所寺院は、現在無住のお堂で、境内掲示はなくWebでも情報がとれないので、『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項の記載を引用します。
「埼玉郡羽生村正覺院ノ末ナリ 本尊十一面観音安セリ 薬師堂」。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番の札所は福聚山 利永寺とされていますが、別の資料によると、もともとはこちらが第43番の札所であった可能性もあります。
・まわりにランドマークがないので説明しにくいですが、Googleマップの住所検索でヒットします。
・竹林を背にした奥まったところにあり、向拝柱はあるものの、切妻造妻入で一見お堂らしくないので、参道入口の如意輪観世音菩薩と地蔵菩薩の石仏がなければそれとわからないかもしれません。
・御朱印は、真言宗智山派関東十一談林の名刹、光明山 一乗院(熊谷市上之2891-1)で規定用紙のものを拝受できます。(一乗院の御朱印は授与されておりません。)
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第11番 十一面観世音菩薩(大悲閣)


■ 萬頂山 集福寺
熊谷市下奈良551
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第13番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番
・山内掲示によると、永仁年間(1293-1299年)、由良法燈圓明國師によって臨済宗法燈派の本山として開かれ、天文年間(1532-1555年)、永平道元孫桂室秀芳大和尚によって曹洞宗に改められたという名刹です。
・同掲示には、(当寺)五世扶嶽太助大和尚は、後に「とげぬき地蔵」(江戸・巣鴨(当時は神田明神下)の萬頂山 高岩寺を開いたことで知られています、との記載があります。
・境内の諸堂は江戸時代後期の建立で、法堂、庫裡、仏殿、開山堂を回廊で結び、内部に鐘楼を設けた七堂伽藍の配置をとっているようです。
・幡羅郡新四国霊場の初番発願所を務められ、このことからも当地屈指の名刹であることがわかります。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項にも大きく記載され「相傳フ往昔ハ臨済派ニテ開山圓明國師(略)其後永正年中桂室秀芳ト云僧、曹洞派ニ改メシヨリ今開山トス(略)開基ハ式部大輔助高十代成田下総守親泰法名貞岡宗蓮菴主ト号ス 入道シテ当村ニ隠棲ヲ営ミ 即当寺ヲ造建シ大永四年六月八日卒ス 御打入ノ後 東照宮忍城ヨリ此辺御放鷹ノ時、当寺ヘ成ラセラレ住僧桂岩ヘ御目見仰付ラレ 其後慶長年中江戸ヘ召セレシ時 元神田蔵王権現ノ舊(旧)蹟ニ於テ寺地ヲ賜ハリ一寺ヲ草創シテ金峯山高林寺ト号シ蔵王権現ヲ鎮守トセリ 後替地ヲ給ヒ本郷ヘ遷リ 又駒込ヘ遷リテ 今ハ当寺ノ末トナレリ 本尊三尊ノ釋迦ヲ安セリ(以下略)」とあります。
・「金峯山 高林寺」とは、文京区向丘の金峰山 高林寺をさすとみられ、本郷区史のP.1247には、たしかに「高林寺 武州幡羅郡下奈良村集福寺末、金峰山と号ス」との記載があります。
・「七堂伽藍の名刹」だけあって、さすがに伽藍は整っています。
・庫裡にて拝受した御朱印は。忍観音霊場と幡羅郡新四国霊場のふたつの札所印が捺されていました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第13番 札所本尊不明 御朱印尊格は釋迦牟尼佛
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番 釋迦牟尼佛
1通で兼用。




■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺
熊谷市柿沼499
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。
・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。
・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。
・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。
・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)


※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり
■ 天神山 観音院 吉祥寺
熊谷市原島682
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第33番
・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。
・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。
・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩


■ 有應山 浄圓院 養平寺
熊谷市原島1192
真言宗霊雲寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所:-
こちらは非札所で存じ上げませんでしたが、公式Webによると、
養平寺本尊「歓喜地蔵菩薩」
薬師堂「薬師如来」
愛染堂「愛染明王」
毘沙門堂「毘沙門天」
の4種の御朱印を授与されている模様です。
拝受次第、掲載します。
■ 永昌山 常楽寺
熊谷市中奈良1956
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項には「奈良村集福寺末 開山ハ本尊(ママ)七世ノ僧宗察慶長年中(1596-1615年)創建ト云 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・おそらく本寺であった集福寺第七世の僧宗察が慶長年中(1596-1615年)に創建とみられます。
・また、山内の石碑には「当常楽寺ノ境内地ハ創立当時南ハ新井北ハ堀内東ハ後原ヲ境ニ凡ソ五千三百余坪アッタ」とあり、相当の大寺であったことが伺われます。
・参拝時ご不在でしたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番で、曹洞禅ナビで「御朱印対応あり」となっているので、郵送をお願いするとお送りいただけました。
・こちらの御朱印にも幡羅郡新四国霊場の札所印が捺されていました。「幻の霊場」ともいわれる幡羅郡新四国霊場ですが、意外に札所印が残っているようです。
・御本尊は釈迦如来のようですが、御朱印尊格は観世音菩薩となっています。禅宗寺院の観音様は聖観世音菩薩が多いですが、御朱印の主印に種子は確認できず聖観世音菩薩かどうかはわかりません。(観世音菩薩、大悲殿などの揮毫でも、朱印に種子があれば(=御寶印)、こちらで観音様の個別の尊格はわかります。)
・新四国霊場の札所本尊は御本尊の例が多いのですが、こちらはなんらかの由縁で観音様が札所本尊となられているのかもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番 釈迦如来


■ 奈良神社
熊谷市中奈良1969
御祭神:奈良別命
旧社格:延喜式内社(論社)、奈良四村の総鎮守
元別当:摩尼山 熊山院 長慶寺(中奈良/高野山真言宗)
授与所:境内拝殿前
・中奈良に御鎮座の古社で、『延喜式神名帳』の幡羅郡小社四座の一社(論社)とされます。
・『埼玉の神社』には、仁徳天皇の御世、下毛野君の祖で豊城入彦命の子孫とされる奈良別命が、下野国国造の任を終えたのち当地を開拓したことから、郷民がその徳を偲んで創祀とあります。
・また、当地に拠った奈良氏は、成田・別府・玉井氏などとならぶ名族で、当社を奉斎していたとみられています。
・中世、当社は熊野信仰の影響を受けて奈良神社から熊野神社に号を改めました。
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項の熊野社には「奈良四村ノ惣鎮守ナリ 本地彌陀・薬師・観音を安ス 古は修験圓蔵坊カ持ナリシガ 成田氏下野國烏山ニ移ル時圓蔵坊モ随テ移リ(略)今ハ長慶寺ノ持トナル 社内ニ奈良神社ヲ合セ祀ル 奈良神社ハ神名帳当郡四座ノ一ナリ想ニ舊章衰廃ノ後、熊野三社ヲ合祀シ」とあります。
・『埼玉の神社』では、「恐らく、古代に創建された奈良神社は廃絶したのではなく、中世、その時流に合った熊野信仰を収容することにより社名を変えて存続したのであろう。」とみなしています。
・また、「江戸後期になると、中世以来永く熊野神社としてきた当社は、復古の思想興隆により、社名を古代の奈良神社に復した。」とも記されています。
・古社の落ち着きを感じる境内。本殿の意匠も見事なものです。
・拝殿前に御朱印が置かれていたので、お代を賽銭箱に納めて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:奈良神社 書置(筆書)


■ 摩尼山 熊山院 長慶寺
熊谷市中奈良1995
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第25番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項に「紀伊國高野山清浄心院末(略)相傳フ当寺は古修験地ナリシガ 天正十八年(1590年)圓蔵坊ト云僧、成田氏ニ従ヒ下野國ニ移リシ後 長慶ト云僧今ノ宗ニ改メ造立セリト云(略)元空坊号ヲ継テ其頃当村ニ住シ後黒田村ヘ移シニヨリ 坊宇以下其ママ長慶(延寶四年(1676年)寂)譲受テ今ノ宗ノ一寺トセシニヤ 本尊地蔵ヲ安セリ」とあります。
・当初は(天台系)修験の圓蔵坊・元空坊が護持し、後に長慶が跡を継いで紀伊国の真言宗高野山浄心院の末寺となり、江戸期には奈良神社(熊野社)の別当を司りました
・『埼玉の神社』には「明治期に入ると、当社(奈良神社/熊野社)本殿の熊野神の本地である弥陀・薬師・観音の三尊は、長慶寺に移され、代わって神鏡が奉安された。」とあるので、熊野神は本地(弥陀・薬師・観音の三尊)として長慶寺に遷られたことになります。
・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂。忍観音霊場の札所本尊、如意輪観世音菩薩も本堂に御座とのことです。
・御朱印はご住職がいらっしゃれば庫裡にて拝受できるかと思いますが、ご不在がちのようで、書置もないので拝受はなかなかむずかしい札所です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第25番 如意輪観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番 地蔵菩薩


■ 開敷山 観音院 妙音寺
熊谷市上奈良702
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第24番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
・『新編武蔵風土記稿』によると、開山の頼尊は奈良三郎と伝わり、成田大夫助高の三男奈良三郎高長とみなしています。高長は入道して頼尊と号し当寺を開山されたとの由。
・境内の「奈良三郎の墓」は市指定記念物(史跡)に指定されています。
・如意輪観世音菩薩は行基の作と伝わります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第33番の吉祥寺(熊谷市原島682)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第24番 聖観世音菩薩


■ 瑠璃光山 真蔵院 東光寺
熊谷市上奈良953
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番
・山内石碑によると、創立は慶長年間(1596-1615年)。延宝年間滎伝阿闍梨により中興するも、文化八年(1811年)火災により古文書を焼失し由緒詳細は不明とのこと。
・『新編武蔵風土記稿』によると、慶安年間(1648-1652年)以前は「東ノ坊」と称し、妙音寺を「西ノ坊」と称していたようです。
・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂です。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番 薬師如来


■ 豊布都神社
熊谷市上奈良1286
御祭神:武甕槌命、(旧)鎌倉権五郎景政公
旧社格:旧上奈良村鎮守
元別当:瑠璃光山 真蔵院 東光寺(上奈良/高野山真言宗)
授与所:境内拝殿前
・旧上奈良村の鎮守で、かつては御霊社と号し、御祭神は鎌倉権五郎景政公と伝わります。(『新編武蔵風土記稿』)
・『埼玉の神社』には、明治5年に御祭神と社号を改めたとありますが、「豊布都とは、武甕槌命の別称で、鎌倉権五郎の武勇にちなんだものと思われる」とあり、旧御祭神のゆかりを示唆しています。
・上奈良はかつて荒川の川筋に当たっていた地で、境内掲示には「往時の人々は、河川の氾濫によって生じる疫病などの厄災を怨霊の祟り・御霊によるものとの考えから御霊という音に近い鎌倉権五郎の怨霊を祀ってその祟りを鎮めようとした。」とありました。
・本地の愛染明王は、明治の神仏分離時に元別当の東光寺に遷されています。
・こぢんまりとした境内ですが、すっきりと整って清冽な気が流れているような感じがしました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:豊布都神社 書置(筆書)

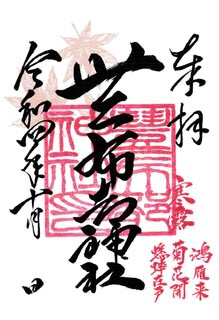
■ 増田山 観音堂
熊谷市下増田841
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第20番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
〔拝受御朱印〕
・第19番下増田観音寺からほど近く、県道263号弁財深谷線沿いにあるのでわかりやすいです。
・寺号標は「増田山観音堂」、門柱には「旧宝蔵院」と「牛頭天王分社」、観音堂扁額には「十一面観世音」「牛頭天王宮」。
・忍観音二十番霊場の立派な札所碑。宝形造の端正な観音堂には真如親王様のお大師さまが描かれた幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番の札所板も掲げられ、霊場札所の趣きがあります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第19番の下増田観音寺(熊谷市下増田866)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第20番 十一面観世音菩薩


■ 大悲山 慈眼院 観音寺
熊谷市下増田866
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第19番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第69番
・忍秩父三十四観音霊場には「観音寺」「観音堂」と号する札所がじつに5つ(6番行田市持田、10番上中条、11番下奈良、19番下増田、20番下増田(観音堂)、26番玉井(廃寺))もあり、場所が近いこともあって混乱します。
・こちらは第19番下増田の観音寺で、第20番下増田観音堂も護持されています。
・御朱印は忍秩父第19番、第20番(増田山観音堂)を拝受しました。本堂にあげていただき、たいへんご親切なご対応をいただきました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第19番 聖観世音菩薩


■ 福聚山 香林寺
熊谷市東別府799
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第23番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第61番、第6番(旧福泉寺・薬師如来)
・別府小太郎清重が父入道義重(法名香林寺義重道薫居士)追福のため建立と(開基は義重)いう寺伝があり、集福寺第二世要岩(弘治三年(1557年)十六日示寂)が開山という伝もあります。
・別府小太郎清重は平家物語に登場し、平家物語は延慶二年(1309年)以前に成立とみられているので、開基開山の年代が合いません。
・これについては、『新編武蔵風土記稿』も「清重の開基といはんには年代相あたらず、若くは天文(1532年-1555年)の頃、別府尾張守長清など、己が遠祖義重のために造立せしにや、さあれば開山開基の年代合へり」と指摘しています。
・香林寺は(東)別府城の城址とされる東別府神社のすぐそばにあり、香林寺を別府氏館跡とする史料もあるようです。
・別府城跡(県指定記念物(史跡))の掲示には「成田助高の二男次郎行高が別府に住み、その子太郎能幸は東別府に、二郎行助が西別府に数代相対して領知」とあるので、小太郎清重は能幸の流れの東別府氏とみられ、同掲示には「太郎能幸に初まった東別府家は、それから十一代目の尾張守長清まで続いたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の北条氏攻略に際し、敗軍側についたため家禄を失ってしまった。」ともあります。
・御朱印は、庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

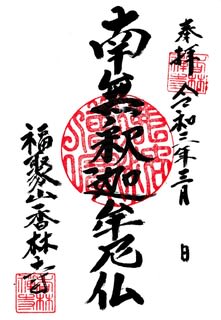
■ 吉祥山 丈六院 安楽寺
熊谷市西別府2044
臨済宗円覚寺派
御本尊:釈迦如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第22番
・養老年間(717-24年)、藤原不比等淡海による草創と伝わる古刹。
・草創時に丈六の釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来の三尊を安置、後に武蔵国国司(藤原)式部大輔任助の二男別府左衛門行隆が、六阿弥陀を加えて九品の本尊とし、その子孫の別府甲斐守頼重が再興したといいます。
・繁室玄茂和尚(文和二年(1353年)寂)の開山という伝もあります。
・『新編武蔵風土記稿』および『埼玉の神社(西別府湯殿神社の項)』によると、康暦二年(1380年)九月、乱を起こした下野守護小山義政征討のため足利左馬頭氏満が鎌倉を出立。別府の地に陣を構えて小山攻めの軍勢を催促するとともに丈六(院)に参詣念誦したところ、小山義政みずから当所に赴き降参したことは、ひとえに丈六の尊像の感應によるものと称揚されました。
・御朱印は庫裡にて授与いただけましたが、新型コロナ禍のなかでは原則授与を中止されているようです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第22番 九品佛
※御本尊の御朱印不授与


■ 瑠璃光山 薬師院 玉井寺
熊谷市玉井1888
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
司別当:玉井大神社:境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)
・埼玉県神社庁『埼玉の神社』の「玉井大神社」の項に、「玉井」および「玉井寺」についての記載もあるので抜粋引用します。
・桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧賢璟は、巡視の足を東国までのばしました。
・賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。
・この井戸「玉の井」は玉井寺の境内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。
・『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。
・玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。
・「玉の井」の脇には市指定記念物(史跡)の「玉井四朗の墓」があり、玉井寺は玉井四朗の屋敷跡と伝わります。
・玉井氏は、成田助高の子助実が玉井四郎と称したのをはじめとし、『保元物語』の白河殿夜討ちの条には、源義朝公に従った玉井四郎が軍功を立てたことが記されています。また、『郡村誌』には「往古元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な札所の御朱印を授与されています。
・布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番 阿弥陀如来

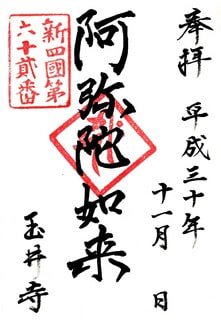
2.熊谷七福神 布袋尊


■ 赤城久伊豆神社
熊谷市石原1007
御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命
旧社格:旧石原村鎮守
元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(石原/真言宗智山派)
授与所:境内授与所
・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。
・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。
・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。
・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。
秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。
・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。
・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)


■ (小島)春日神社
熊谷市小島142
御祭神:天児屋根命、武甕槌命、経津主命、比売神
旧社格:旧小島村鎮守
元別当:小嶋山 無量院 西光寺(小島/天台宗)
授与所:拝殿前
・旧小島村の鎮守社と伝わり、明治42年、地内の稲荷社・天神社・八坂社および飛地境内社道祖社を合祀しています。
・『埼玉の神社』には「鎌倉時代に源家が滅亡し、北条氏が執権政治を始めた年に当たる承久元年(1219年)三月、奈良の春日神社から神霊を遷した」とあります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:春日神社 書置(筆書)


■ 青野山 清浄院 大正寺
熊谷市籠原南1-252
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番
・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。
・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。
奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。
・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。
・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。
・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。
・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

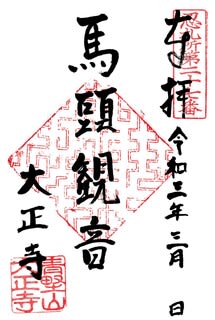
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王
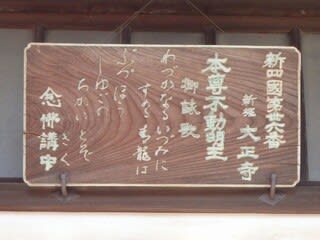
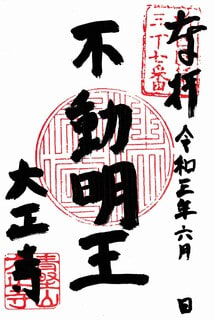

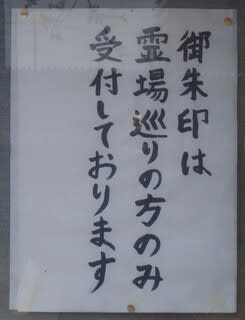
※霊場巡拝者にのみ授与
■ 狗門寺
熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)
真言宗豊山派?
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番
・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。
・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。
・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩
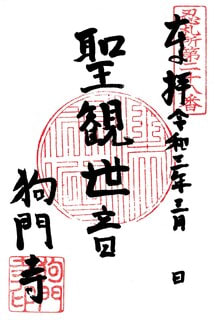
※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)
■ 田中神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命
旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)
元別当:寶珠山 延命寺(三ケ尻/真言宗豊山派)
授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所
・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。
・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。
・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。
・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)


■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)


公式Web
熊谷市三ケ尻3712
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番
・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。
・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。
・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。
・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。
・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。
〔拝受御朱印〕
1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

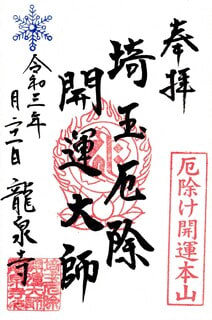
2.関東八十八箇所第83番 不動明王

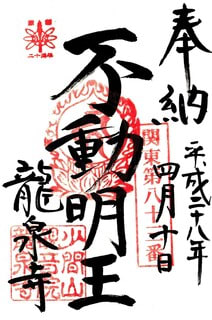
3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩
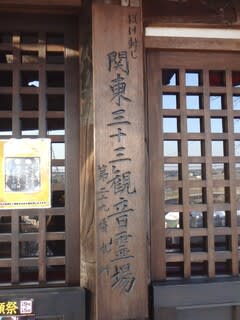
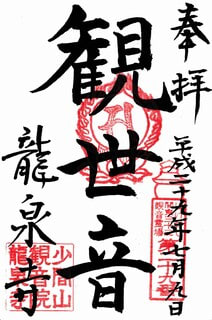
尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。
4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩
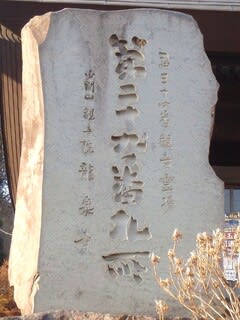
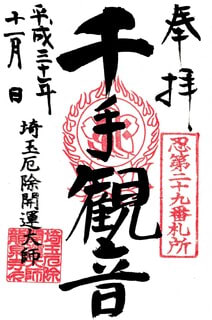
5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩
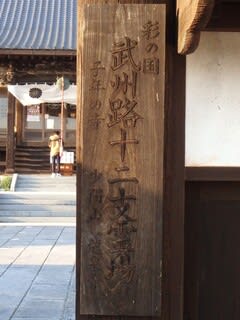

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。
6.「如月 花手水」の御朱印


7.切り絵御朱印

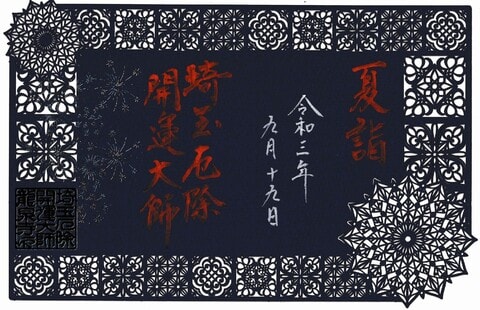
※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。
■ (三ケ尻)八幡神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公
旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守
元別当:
授与所:境内社務所
・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。
・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。
・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

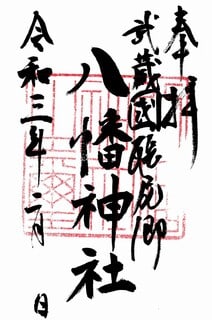
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。
【 BGM 】
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里
■ 約束 (Yakusoku) - 如月千早(今井麻美) // covered by 凪原涼菜
■ Mirai 未来 - kalafina
1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!
さすがに梶浦由記さん
→ コード
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)から。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
--------------------------------------
ここからは、いよいよ忍秩父観音霊場、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の核心部に入っていきます。小規模で無住の寺も多く、御朱印拝受難易度は高いです。
■ 光明山 地蔵院 観音寺
熊谷市上中条2018
高野山真言宗
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第10番
・こちらも無住で情報が少ないです。
『新編武蔵風土記稿』の上中條村(埼玉郡忍領)の項に「邑楽郡赤岩村光恩寺末(略)慶安二年(1649年)観音堂領トシテ十六石六斗ノ御朱印ヲ附セラル 開山了空明應五年(1496年)寂セリ 本尊不動ヲ安ス 観音堂」とあります。
・現在の御本尊は聖観世音菩薩のようで、地元では「中条観音様」と呼ばれ、信仰を集めている模様です。
・境内入口の石碑に「聖観世音安産守護」、本堂扉に「腹帯子宝祈願」「安産祈願」の案内があるので、子宝・安産に霊験あらたかな観音様のようです。
・入母屋造銅板葺で切妻様の向拝を付設しています。照りの強い本棟の屋根と起り気味の向拝屋根が独特のコントラストを見せています。
・大棟と鬼板に聖観世音菩薩の種子「サ」が掲げられているので、やはり御本尊は聖観世音菩薩とみられます。向拝正面には「観世音」の扁額が掲げられています。
・木鼻側面貘と正面獅子の彩色が異なるなど芸が細かいです。
・現在無住で、御朱印は浄瑠璃山 長慶寺(熊谷市西城93-1)で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第10番 聖観世音菩薩


■ 福聚山 阿弥陀院 利永寺
熊谷市下奈良796
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第12番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番
・こちらは、今回の記事のなかでもっともマニアックな札所かと思われます。記事UPは迷いましたが、確かに忍観音霊場の札所なのでご紹介します。
・参拝情報がほとんどなく、Googleマップで位置検索するととある企業の敷地を示すので、意を決してこちらの事務所にお伺いすると、こちらの敷地内に御座とのこと。
・ご丁寧にもご案内いただき、ようやく参拝が叶いました。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 本尊前(十一面観音)ニ同シ 観音堂 利永寺持」とあり、本堂(御本尊:十一面観世音菩薩)のほか、観音堂を擁していたかもしれません。
・整った宝形造で向拝を付設し、向拝見上げにはしっかり御詠歌の木板が掛かっていました。ただし、この木板の札番は「第七番」。こちらは忍観音霊場で第11番、幡羅郡新四国霊場で第43番のはずなので、この「第七番」というのはナゾです。
・こちらの御朱印はなかばあきらめていたのですが、一乗院様にお伺いすると、第11番観音寺のほか、こちらの御朱印(規定用紙)も授与されているとのことで、ありがたく拝受しました。
・ご紹介はしましたが、参拝時に一般企業さんのお手間をいただくこともあり、忍観音霊場巡拝者に限ってお伺いした方がよろしいかと思います。また、休業日や営業時間外の参拝も不可だと思います。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第12番 十一面観世音菩薩(大悲殿)

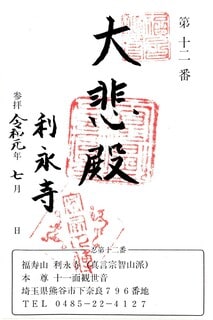
■ 大慈山 薬師院 観音寺
熊谷市下奈良913
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第11番
・この寺社巡りも、下奈良エリアに至ってますますディープな世界に入っていきます(笑)
・忍秩父三十四観音霊場第11番のこの札所寺院は、現在無住のお堂で、境内掲示はなくWebでも情報がとれないので、『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項の記載を引用します。
「埼玉郡羽生村正覺院ノ末ナリ 本尊十一面観音安セリ 薬師堂」。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番の札所は福聚山 利永寺とされていますが、別の資料によると、もともとはこちらが第43番の札所であった可能性もあります。
・まわりにランドマークがないので説明しにくいですが、Googleマップの住所検索でヒットします。
・竹林を背にした奥まったところにあり、向拝柱はあるものの、切妻造妻入で一見お堂らしくないので、参道入口の如意輪観世音菩薩と地蔵菩薩の石仏がなければそれとわからないかもしれません。
・御朱印は、真言宗智山派関東十一談林の名刹、光明山 一乗院(熊谷市上之2891-1)で規定用紙のものを拝受できます。(一乗院の御朱印は授与されておりません。)
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第11番 十一面観世音菩薩(大悲閣)


■ 萬頂山 集福寺
熊谷市下奈良551
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第13番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番
・山内掲示によると、永仁年間(1293-1299年)、由良法燈圓明國師によって臨済宗法燈派の本山として開かれ、天文年間(1532-1555年)、永平道元孫桂室秀芳大和尚によって曹洞宗に改められたという名刹です。
・同掲示には、(当寺)五世扶嶽太助大和尚は、後に「とげぬき地蔵」(江戸・巣鴨(当時は神田明神下)の萬頂山 高岩寺を開いたことで知られています、との記載があります。
・境内の諸堂は江戸時代後期の建立で、法堂、庫裡、仏殿、開山堂を回廊で結び、内部に鐘楼を設けた七堂伽藍の配置をとっているようです。
・幡羅郡新四国霊場の初番発願所を務められ、このことからも当地屈指の名刹であることがわかります。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項にも大きく記載され「相傳フ往昔ハ臨済派ニテ開山圓明國師(略)其後永正年中桂室秀芳ト云僧、曹洞派ニ改メシヨリ今開山トス(略)開基ハ式部大輔助高十代成田下総守親泰法名貞岡宗蓮菴主ト号ス 入道シテ当村ニ隠棲ヲ営ミ 即当寺ヲ造建シ大永四年六月八日卒ス 御打入ノ後 東照宮忍城ヨリ此辺御放鷹ノ時、当寺ヘ成ラセラレ住僧桂岩ヘ御目見仰付ラレ 其後慶長年中江戸ヘ召セレシ時 元神田蔵王権現ノ舊(旧)蹟ニ於テ寺地ヲ賜ハリ一寺ヲ草創シテ金峯山高林寺ト号シ蔵王権現ヲ鎮守トセリ 後替地ヲ給ヒ本郷ヘ遷リ 又駒込ヘ遷リテ 今ハ当寺ノ末トナレリ 本尊三尊ノ釋迦ヲ安セリ(以下略)」とあります。
・「金峯山 高林寺」とは、文京区向丘の金峰山 高林寺をさすとみられ、本郷区史のP.1247には、たしかに「高林寺 武州幡羅郡下奈良村集福寺末、金峰山と号ス」との記載があります。
・「七堂伽藍の名刹」だけあって、さすがに伽藍は整っています。
・庫裡にて拝受した御朱印は。忍観音霊場と幡羅郡新四国霊場のふたつの札所印が捺されていました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第13番 札所本尊不明 御朱印尊格は釋迦牟尼佛
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番 釋迦牟尼佛
1通で兼用。




■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺
熊谷市柿沼499
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。
・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。
・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。
・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。
・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)


※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり
■ 天神山 観音院 吉祥寺
熊谷市原島682
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第33番
・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。
・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。
・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩


■ 有應山 浄圓院 養平寺
熊谷市原島1192
真言宗霊雲寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所:-
こちらは非札所で存じ上げませんでしたが、公式Webによると、
養平寺本尊「歓喜地蔵菩薩」
薬師堂「薬師如来」
愛染堂「愛染明王」
毘沙門堂「毘沙門天」
の4種の御朱印を授与されている模様です。
拝受次第、掲載します。
■ 永昌山 常楽寺
熊谷市中奈良1956
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項には「奈良村集福寺末 開山ハ本尊(ママ)七世ノ僧宗察慶長年中(1596-1615年)創建ト云 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・おそらく本寺であった集福寺第七世の僧宗察が慶長年中(1596-1615年)に創建とみられます。
・また、山内の石碑には「当常楽寺ノ境内地ハ創立当時南ハ新井北ハ堀内東ハ後原ヲ境ニ凡ソ五千三百余坪アッタ」とあり、相当の大寺であったことが伺われます。
・参拝時ご不在でしたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番で、曹洞禅ナビで「御朱印対応あり」となっているので、郵送をお願いするとお送りいただけました。
・こちらの御朱印にも幡羅郡新四国霊場の札所印が捺されていました。「幻の霊場」ともいわれる幡羅郡新四国霊場ですが、意外に札所印が残っているようです。
・御本尊は釈迦如来のようですが、御朱印尊格は観世音菩薩となっています。禅宗寺院の観音様は聖観世音菩薩が多いですが、御朱印の主印に種子は確認できず聖観世音菩薩かどうかはわかりません。(観世音菩薩、大悲殿などの揮毫でも、朱印に種子があれば(=御寶印)、こちらで観音様の個別の尊格はわかります。)
・新四国霊場の札所本尊は御本尊の例が多いのですが、こちらはなんらかの由縁で観音様が札所本尊となられているのかもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番 釈迦如来


■ 奈良神社
熊谷市中奈良1969
御祭神:奈良別命
旧社格:延喜式内社(論社)、奈良四村の総鎮守
元別当:摩尼山 熊山院 長慶寺(中奈良/高野山真言宗)
授与所:境内拝殿前
・中奈良に御鎮座の古社で、『延喜式神名帳』の幡羅郡小社四座の一社(論社)とされます。
・『埼玉の神社』には、仁徳天皇の御世、下毛野君の祖で豊城入彦命の子孫とされる奈良別命が、下野国国造の任を終えたのち当地を開拓したことから、郷民がその徳を偲んで創祀とあります。
・また、当地に拠った奈良氏は、成田・別府・玉井氏などとならぶ名族で、当社を奉斎していたとみられています。
・中世、当社は熊野信仰の影響を受けて奈良神社から熊野神社に号を改めました。
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項の熊野社には「奈良四村ノ惣鎮守ナリ 本地彌陀・薬師・観音を安ス 古は修験圓蔵坊カ持ナリシガ 成田氏下野國烏山ニ移ル時圓蔵坊モ随テ移リ(略)今ハ長慶寺ノ持トナル 社内ニ奈良神社ヲ合セ祀ル 奈良神社ハ神名帳当郡四座ノ一ナリ想ニ舊章衰廃ノ後、熊野三社ヲ合祀シ」とあります。
・『埼玉の神社』では、「恐らく、古代に創建された奈良神社は廃絶したのではなく、中世、その時流に合った熊野信仰を収容することにより社名を変えて存続したのであろう。」とみなしています。
・また、「江戸後期になると、中世以来永く熊野神社としてきた当社は、復古の思想興隆により、社名を古代の奈良神社に復した。」とも記されています。
・古社の落ち着きを感じる境内。本殿の意匠も見事なものです。
・拝殿前に御朱印が置かれていたので、お代を賽銭箱に納めて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:奈良神社 書置(筆書)


■ 摩尼山 熊山院 長慶寺
熊谷市中奈良1995
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第25番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項に「紀伊國高野山清浄心院末(略)相傳フ当寺は古修験地ナリシガ 天正十八年(1590年)圓蔵坊ト云僧、成田氏ニ従ヒ下野國ニ移リシ後 長慶ト云僧今ノ宗ニ改メ造立セリト云(略)元空坊号ヲ継テ其頃当村ニ住シ後黒田村ヘ移シニヨリ 坊宇以下其ママ長慶(延寶四年(1676年)寂)譲受テ今ノ宗ノ一寺トセシニヤ 本尊地蔵ヲ安セリ」とあります。
・当初は(天台系)修験の圓蔵坊・元空坊が護持し、後に長慶が跡を継いで紀伊国の真言宗高野山浄心院の末寺となり、江戸期には奈良神社(熊野社)の別当を司りました
・『埼玉の神社』には「明治期に入ると、当社(奈良神社/熊野社)本殿の熊野神の本地である弥陀・薬師・観音の三尊は、長慶寺に移され、代わって神鏡が奉安された。」とあるので、熊野神は本地(弥陀・薬師・観音の三尊)として長慶寺に遷られたことになります。
・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂。忍観音霊場の札所本尊、如意輪観世音菩薩も本堂に御座とのことです。
・御朱印はご住職がいらっしゃれば庫裡にて拝受できるかと思いますが、ご不在がちのようで、書置もないので拝受はなかなかむずかしい札所です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第25番 如意輪観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番 地蔵菩薩


■ 開敷山 観音院 妙音寺
熊谷市上奈良702
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第24番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
・『新編武蔵風土記稿』によると、開山の頼尊は奈良三郎と伝わり、成田大夫助高の三男奈良三郎高長とみなしています。高長は入道して頼尊と号し当寺を開山されたとの由。
・境内の「奈良三郎の墓」は市指定記念物(史跡)に指定されています。
・如意輪観世音菩薩は行基の作と伝わります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第33番の吉祥寺(熊谷市原島682)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第24番 聖観世音菩薩


■ 瑠璃光山 真蔵院 東光寺
熊谷市上奈良953
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番
・山内石碑によると、創立は慶長年間(1596-1615年)。延宝年間滎伝阿闍梨により中興するも、文化八年(1811年)火災により古文書を焼失し由緒詳細は不明とのこと。
・『新編武蔵風土記稿』によると、慶安年間(1648-1652年)以前は「東ノ坊」と称し、妙音寺を「西ノ坊」と称していたようです。
・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂です。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番 薬師如来


■ 豊布都神社
熊谷市上奈良1286
御祭神:武甕槌命、(旧)鎌倉権五郎景政公
旧社格:旧上奈良村鎮守
元別当:瑠璃光山 真蔵院 東光寺(上奈良/高野山真言宗)
授与所:境内拝殿前
・旧上奈良村の鎮守で、かつては御霊社と号し、御祭神は鎌倉権五郎景政公と伝わります。(『新編武蔵風土記稿』)
・『埼玉の神社』には、明治5年に御祭神と社号を改めたとありますが、「豊布都とは、武甕槌命の別称で、鎌倉権五郎の武勇にちなんだものと思われる」とあり、旧御祭神のゆかりを示唆しています。
・上奈良はかつて荒川の川筋に当たっていた地で、境内掲示には「往時の人々は、河川の氾濫によって生じる疫病などの厄災を怨霊の祟り・御霊によるものとの考えから御霊という音に近い鎌倉権五郎の怨霊を祀ってその祟りを鎮めようとした。」とありました。
・本地の愛染明王は、明治の神仏分離時に元別当の東光寺に遷されています。
・こぢんまりとした境内ですが、すっきりと整って清冽な気が流れているような感じがしました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:豊布都神社 書置(筆書)

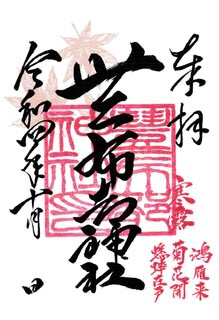
■ 増田山 観音堂
熊谷市下増田841
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第20番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
〔拝受御朱印〕
・第19番下増田観音寺からほど近く、県道263号弁財深谷線沿いにあるのでわかりやすいです。
・寺号標は「増田山観音堂」、門柱には「旧宝蔵院」と「牛頭天王分社」、観音堂扁額には「十一面観世音」「牛頭天王宮」。
・忍観音二十番霊場の立派な札所碑。宝形造の端正な観音堂には真如親王様のお大師さまが描かれた幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番の札所板も掲げられ、霊場札所の趣きがあります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第19番の下増田観音寺(熊谷市下増田866)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第20番 十一面観世音菩薩


■ 大悲山 慈眼院 観音寺
熊谷市下増田866
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第19番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第69番
・忍秩父三十四観音霊場には「観音寺」「観音堂」と号する札所がじつに5つ(6番行田市持田、10番上中条、11番下奈良、19番下増田、20番下増田(観音堂)、26番玉井(廃寺))もあり、場所が近いこともあって混乱します。
・こちらは第19番下増田の観音寺で、第20番下増田観音堂も護持されています。
・御朱印は忍秩父第19番、第20番(増田山観音堂)を拝受しました。本堂にあげていただき、たいへんご親切なご対応をいただきました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第19番 聖観世音菩薩


■ 福聚山 香林寺
熊谷市東別府799
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第23番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第61番、第6番(旧福泉寺・薬師如来)
・別府小太郎清重が父入道義重(法名香林寺義重道薫居士)追福のため建立と(開基は義重)いう寺伝があり、集福寺第二世要岩(弘治三年(1557年)十六日示寂)が開山という伝もあります。
・別府小太郎清重は平家物語に登場し、平家物語は延慶二年(1309年)以前に成立とみられているので、開基開山の年代が合いません。
・これについては、『新編武蔵風土記稿』も「清重の開基といはんには年代相あたらず、若くは天文(1532年-1555年)の頃、別府尾張守長清など、己が遠祖義重のために造立せしにや、さあれば開山開基の年代合へり」と指摘しています。
・香林寺は(東)別府城の城址とされる東別府神社のすぐそばにあり、香林寺を別府氏館跡とする史料もあるようです。
・別府城跡(県指定記念物(史跡))の掲示には「成田助高の二男次郎行高が別府に住み、その子太郎能幸は東別府に、二郎行助が西別府に数代相対して領知」とあるので、小太郎清重は能幸の流れの東別府氏とみられ、同掲示には「太郎能幸に初まった東別府家は、それから十一代目の尾張守長清まで続いたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の北条氏攻略に際し、敗軍側についたため家禄を失ってしまった。」ともあります。
・御朱印は、庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

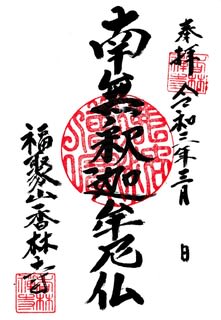
■ 吉祥山 丈六院 安楽寺
熊谷市西別府2044
臨済宗円覚寺派
御本尊:釈迦如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第22番
・養老年間(717-24年)、藤原不比等淡海による草創と伝わる古刹。
・草創時に丈六の釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来の三尊を安置、後に武蔵国国司(藤原)式部大輔任助の二男別府左衛門行隆が、六阿弥陀を加えて九品の本尊とし、その子孫の別府甲斐守頼重が再興したといいます。
・繁室玄茂和尚(文和二年(1353年)寂)の開山という伝もあります。
・『新編武蔵風土記稿』および『埼玉の神社(西別府湯殿神社の項)』によると、康暦二年(1380年)九月、乱を起こした下野守護小山義政征討のため足利左馬頭氏満が鎌倉を出立。別府の地に陣を構えて小山攻めの軍勢を催促するとともに丈六(院)に参詣念誦したところ、小山義政みずから当所に赴き降参したことは、ひとえに丈六の尊像の感應によるものと称揚されました。
・御朱印は庫裡にて授与いただけましたが、新型コロナ禍のなかでは原則授与を中止されているようです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第22番 九品佛
※御本尊の御朱印不授与


■ 瑠璃光山 薬師院 玉井寺
熊谷市玉井1888
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
司別当:玉井大神社:境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)
・埼玉県神社庁『埼玉の神社』の「玉井大神社」の項に、「玉井」および「玉井寺」についての記載もあるので抜粋引用します。
・桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧賢璟は、巡視の足を東国までのばしました。
・賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。
・この井戸「玉の井」は玉井寺の境内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。
・『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。
・玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。
・「玉の井」の脇には市指定記念物(史跡)の「玉井四朗の墓」があり、玉井寺は玉井四朗の屋敷跡と伝わります。
・玉井氏は、成田助高の子助実が玉井四郎と称したのをはじめとし、『保元物語』の白河殿夜討ちの条には、源義朝公に従った玉井四郎が軍功を立てたことが記されています。また、『郡村誌』には「往古元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な札所の御朱印を授与されています。
・布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番 阿弥陀如来

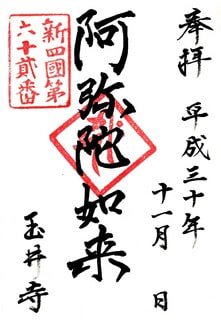
2.熊谷七福神 布袋尊


■ 赤城久伊豆神社
熊谷市石原1007
御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命
旧社格:旧石原村鎮守
元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(石原/真言宗智山派)
授与所:境内授与所
・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。
・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。
・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。
・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。
秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。
・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。
・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)


■ (小島)春日神社
熊谷市小島142
御祭神:天児屋根命、武甕槌命、経津主命、比売神
旧社格:旧小島村鎮守
元別当:小嶋山 無量院 西光寺(小島/天台宗)
授与所:拝殿前
・旧小島村の鎮守社と伝わり、明治42年、地内の稲荷社・天神社・八坂社および飛地境内社道祖社を合祀しています。
・『埼玉の神社』には「鎌倉時代に源家が滅亡し、北条氏が執権政治を始めた年に当たる承久元年(1219年)三月、奈良の春日神社から神霊を遷した」とあります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:春日神社 書置(筆書)


■ 青野山 清浄院 大正寺
熊谷市籠原南1-252
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番
・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。
・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。
奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。
・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。
・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。
・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。
・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

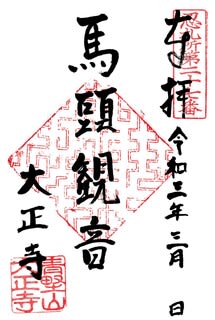
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王
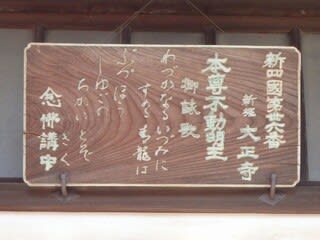
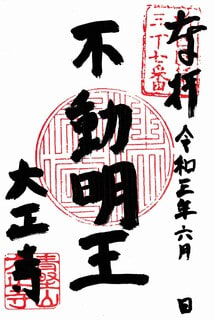

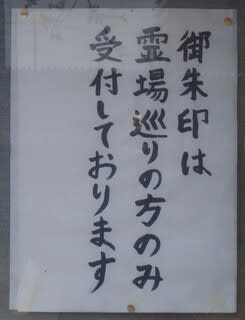
※霊場巡拝者にのみ授与
■ 狗門寺
熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)
真言宗豊山派?
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番
・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。
・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。
・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩
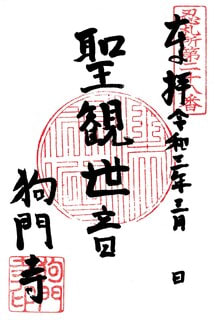
※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)
■ 田中神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命
旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)
元別当:寶珠山 延命寺(三ケ尻/真言宗豊山派)
授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所
・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。
・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。
・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。
・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)


■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)


公式Web
熊谷市三ケ尻3712
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番
・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。
・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。
・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。
・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。
・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。
〔拝受御朱印〕
1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

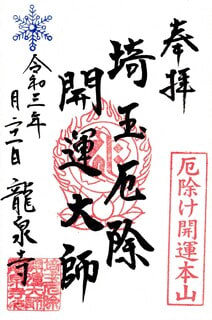
2.関東八十八箇所第83番 不動明王

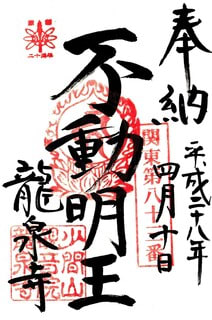
3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩
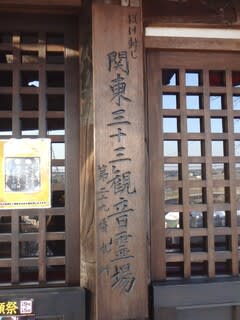
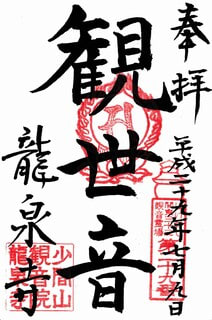
尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。
4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩
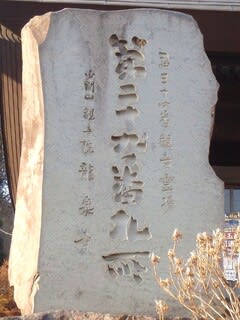
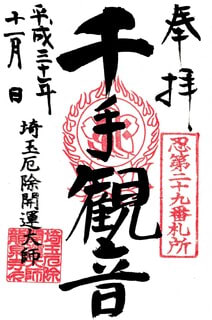
5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩
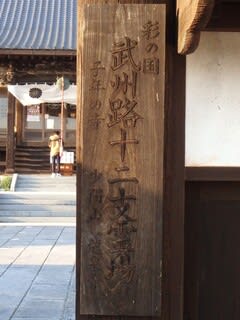

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。
6.「如月 花手水」の御朱印


7.切り絵御朱印

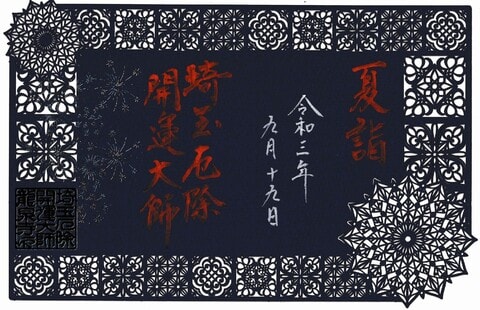
※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。
■ (三ケ尻)八幡神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公
旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守
元別当:
授与所:境内社務所
・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。
・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。
・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

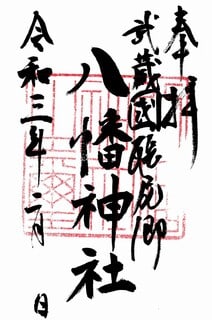
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。
【 BGM 】
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里
■ 約束 (Yakusoku) - 如月千早(今井麻美) // covered by 凪原涼菜
■ Mirai 未来 - kalafina
1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!
さすがに梶浦由記さん
→ コード
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPします。
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
1.旧 大里町エリア
■ 吉見神社
熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)
御祭神:天照大神
旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守
授与所:神社そばのご神職宅
・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。
・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。
・古社らしい厳かな境内。御朱印は境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)


■ (高本)高城神社
熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)
御祭神:高皇産霊命
旧社格:村社、延喜式内社(小)論社
元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)
授与所:神社そばのご神職宅
『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。
・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。
・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。
・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。
・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)


2.旧 江南町エリア
■ 東方山 保泉寺
熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。
・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。
・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。
・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内です。
・こちらはご縁をいただいて期せずして御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 東方山 保泉寺
熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。
・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。
・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。
・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。
・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 高根山 満讃寺
武州路十二支霊場Web
熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)
・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。
・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.武州路十二支霊場 普賢菩薩


■ 五台山 文殊寺
公式Web
熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:文殊師利大菩薩
・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。
・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。
・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。
・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。
・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。
・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。
・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)


■ 龍谷山 静簡院
熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番
・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。
・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。
・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。
・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。
・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。
・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。
・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釋迦如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音


3A.旧 熊谷市エリア-1
■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社
熊谷市鎌倉町44
御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命
旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)
元別当:大善院
授与所:古宮神社(池上)授与所
・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。
・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。
・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。
・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。
・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。
・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。
・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。
・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。
〔うちわ祭について〕
・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。
・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。
・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。
・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)


2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)


■ 星河山 千手院 石上寺
熊谷市鎌倉町36
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)
司元別当:(宮町)高城神社(熊谷市宮町)
・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。
・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。
・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。
・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。
・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。
・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)


2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

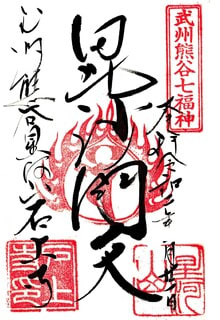
■ 熊野山 千形院 圓照寺
公式Web
熊谷市星川1-1
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)
・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。
・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。
・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。
・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。
・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.不動明王の御朱印


2.聖徳皇太子の御朱印


■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)
公式Web
熊谷市本石1-102
臨済宗妙心寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第2番
・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。
・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。
・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩


■ (宮町)高城神社
公式Web
熊谷市宮町2-93
御祭神:高皇産霊神
旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守
元別当:星河山 千手院 石上寺(鎌倉町/真言宗智山派)
授与所:境内授与所
・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。
・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。
・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:高城神社 直書(筆書)


髙城神社の御朱印帳

■ 肥塚山 成就院
熊谷市資料(PDF)
熊谷市肥塚2-6-1
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:-
司元別当:肥塚伊奈利神社(熊谷市肥塚)
・永正元年(1504年)以前に僧欽照による開山(ないし中興)と伝わり、古くは鎌倉胡桃大楽寺末であったといいます。
・「肥塚氏供養板石塔婆」があることから、肥塚氏ゆかりの寺院とみられます。「熊谷市文化財ガイドブック」(PDF)によると、熊谷氏の祖となった直季の弟直長が肥塚に住んで肥塚氏の始祖となったとのことです。
・御本尊は阿弥陀如来。脇本尊に「一光三尊(弥陀、勢至、観音)燈籠佛」(とても小さいそうです)を奉安され、こちらの御朱印も授与されています。
・燈籠佛は各種の霊験で知られ、江戸中期の忍藩主・阿部豊後守正充公も信仰したといいます。
・墓地は肥塚殿(山)と呼ばれた古墳跡とされます。
・御朱印は本堂にて拝受しましたが、1回目はご不在でした。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 阿弥陀如来


2.脇本尊 燈籠佛


■ 熊谷山 報恩寺
公式Web
熊谷市円光2-8-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。
・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。
熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。
そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。
姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。
その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。
寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。
・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。
・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。
・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。
・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。
・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。
・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。
・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。
・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。
・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


■ 梅籠山 久松寺 東竹院
熊谷市久下1834
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)
・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。
・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。
・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。
・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。
・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛


■ 佐谷田神社
熊谷市佐谷田310
御祭神:誉田別命
旧社格:旧佐谷田村鎮守
元別当:
旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(佐谷田村/新義真言宗)
旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(戸出村/新義真言宗)
旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(平戸村/真言宗新義)
・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)
・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。
・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。
・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書


■ 藤井山 源宗寺
熊谷市平戸611
曹洞宗
御本尊:薬師如来 観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第5番
・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。
・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。
・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。
・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。
・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。
■ 上之村神社
公式Web
熊谷市上之16
御祭神:事代主命、大山祇命、大己貴命
旧社格:郷社、上之村・箱田村・池上村三村の鎮守社
元別当:伊豆国 浄慶院 久見寺(上村/新義真言宗)
授与所:境内授与所
・公式Web、境内掲示、『埼玉の神社』などによると、創祀は平安時代以前とみられ、応永年間(1394-1428年)、成田五郎家時により再興とされます。
・明治2年に現在の上之村神社に改められるまでは、「久伊豆神社」ないし「久伊豆明神社」と号し、『新編武蔵風土記稿』の上村の項には「久伊豆社」として記載されています。
・『新編武蔵風土記稿』に「祭神ハ大山祇命ニテ 伊豆國三嶋社ヲ写シ祀ルトイヘト疑フヘシ 此久伊豆社ト云ハ騎西町塙ニ大社アリテ近郷往々是ヲ勧請スレハ 当社モ恐クハ彼ヲ写セシナラン」とあり、騎西ご鎮座の久伊豆神社の総社、玉敷神社からの勧請を示唆しています。
・御祭神は、江戸期は大山祇命でしたが、明治2年、主祭神を事代主命、相殿の神を大己貴命と大山祇命に改めています。
・また、別当の久見寺客殿に久伊豆の本地十一面観音が安置されていたとあり、神仏混淆の歴史が伺われます。
・当社ご鎮座の旧上(之)村は成田郷ともいわれた名族、成田氏の本貫で、当社は成田氏の尊崇篤く、後に徳川氏の尊崇を受けたと伝わります。なお、成田・別府・奈良・玉井氏は「武州四家」と呼ばれ、いずれも中世にこの地に勢力を張った名族とされています。
・当地有数の古社だけあって厳かな境内。木造の両部鳥居は寛文四年(1664年)建造の墨書が残り、市内最古の木造鳥居として市指定有形文化財に指定されています。
・応永年間(1394-1428年)、成田左京亮家時再建の本殿は一間社流造銅板葺で県指定文化財に指定されています。
・御朱印は参拝時たまたまご神職がいらしたのでいただけましたが、常駐ではありません。(公式Webにご在社予定が出ています。)
・熊谷七福神(恵比寿天)の御朱印は通常不授与かもしれませんが、御朱印には恵比寿様のお姿印が捺されていました。
・なお、兼務社として佐谷田神社、奈良神社(中奈良)、豊布都(とよふつ)神社(上奈良)、春日神社(小島)があり、それぞれWeb上で御朱印がみつかりますが、こちらで拝受できるかは不明です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:上之村神社 直書(筆書)


■ 大雷神社
熊谷市上之16
御祭神:大雷神
旧社格:上之村神社の境内社
元別当:
授与所:上之村神社境内授与所
・『新編武蔵風土記稿』に「末社 雷電 但馬国木田郡雷電社を勧請スト云伝フ(略)別当久見寺 客殿ニ雷電ノ本地馬頭観音を蔵ス」とあります。この地は雷の名所(?)ですが、どうしてわざわざ大雷神を但馬国(現・兵庫県)から勧請したのかはナゾです。
・上之村神社の摂社ですが、社号標、鳥居扁額ともに上之村神社と併記され、拝殿扁額も併記となっています。
・本殿は別で、こちらの本殿も県指定文化財に指定されています。
・この様な祭祀形態を配祀というか相殿というのかわかりませんが、本殿は分かれているので配祀なのかもしれません。
・「上之の雷電さま」と呼ばれ周辺住民の尊崇を集めています。利根川沿いのこのエリアはとくに雷が多く、随所で大雷神が祀られています。
・御朱印は、上之村神社境内授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大雷神社 直書(筆書)

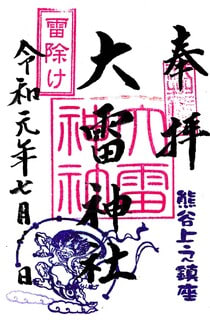
■ 太平山 龍淵寺
熊谷市上之336
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第8番
・名族成田家の菩提寺とされる名刹。
・境内掲示の寺伝・新編武蔵風土記稿などによると、開基は成田左京亮家時。応永十八年(1411年)和庵清順(わなんせいじゅん)大和尚により開創・開山。
・天正十九年(1591)、徳川家康公が遊猟の折に当寺へ立ち寄られ、時の住職呑雪和尚が家康公の三河時代の御乎習の御相手であったことがわかり、これを奇瑞として当寺に曹洞派の総録を許されましたが、呑雪和尚はあえてこの申し出を辞したと伝わります。
・本堂の後にあった小池は「龍ヶ淵」と呼ばれ、かつて龍が潜んでいましたが、開山の和尚清順が法力をもってこれを退けてこの地に当寺を建立したため「龍淵」を寺号としたと伝わります。
・成田氏系図をはじめ多くの文化財を蔵します。高浜虚子が当寺で詠んだ句碑も残されています。
・御朱印は庫裡にて御本尊のものを授与されています。忍観音霊場の御朱印は不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 伊弉諾神社 (いざなぎじんじゃ)
熊谷市上川上36
御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、大日孁貴命、猿田彦命、菅原道真公
旧社格:村社、旧上川上村鎮守
元別当:
授与所:古宮神社(池上)授与所
・社伝、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)などによると、中世、紀伊国熊野三所権現の勧請が創建で、当社、下川上の熊野社、大塚の熊野社の三社を総称して「熊野三所権現」と呼ぶとのこと。また、当社は「十二所権現」とも称されるようです。
・鎌倉期、征夷大将軍・宗尊親王が帰京した際、親王の供の平家ゆかりの宮田太郎貞明は北条氏の追及をおそれてこの地に逃れ当社の宮守りになった(『宮田氏家系図』)とされます。
・安政二年(1855)には、神祇管領から「伊弉諾神社熊野大権現」の幣帛を受けています。
・所蔵の黒馬図、相撲絵馬は市指定文化財に指定されています。
・古社にふさわしい厳かな境内。入母屋造桟瓦葺流れ向拝の端正な拝殿で、向拝には「伊弉諾神社」の扁額が掲げられています。
・御朱印は、古宮神社(熊谷市池上606)にて拝受しました。
・こちらは以前参拝し、その時は御朱印はないものと思っていましたが、いまは拝殿前に御朱印の案内が貼り出されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊弉諾神社 直書(筆書)


■ 古宮神社(こみやじんじゃ)
公式Web
熊谷市池上606
御祭神:石凝姥命、少彦名命、武甕槌命
旧社格:旧池上郷総鎮守
元別当:
授与所:境内授与所
・公式Web、境内由緒書、『埼玉の神社』などによると、古代、紀伊国秋月に御鎮座の旧宮幣大社、日前国懸神宮(ひのくま・くにかかすじんぐう)を勧請して創祀と伝わり、当初は社殿はなくいわゆる「磐座(いわくら)信仰」だったとみられています。
・社殿造立は、平安末期の長寛二年(1164年)。
・祭神の石凝姥命(いしこりどめのみこと)は、天孫降臨の際に邇邇芸命に随伴し、天児屋命、太玉命、天宇受売命、玉祖命と共に天降った五伴緒の一柱とされ、天照御大神が天岩戸にお隠れになったとき、日像鏡・日矛鏡を造られた神といわれています。
・西日本で祀られる例が多く、『埼玉の神社』には「なぜ、和歌山に祀られ鏡作部の遠祖とされる同神が、この地に勧請されたか不明であるが、埼玉地方は、武蔵国の古代文化の中心地の一つであり、近くには金錯銘鉄剣で有名な埼玉古墳群があることなどを考え合わせると、当地に神部(鏡作)ゆかりの人たちが住み、当社を祀ったとも考えられる。」とあります。
・室町期の文安二年(1445年)、相殿の神として少彦名命と武甕槌命を勧請したとされるので、創祀時の主祭神は石凝姥命とみられます。
・古くは岩倉社、又は岩倉大明神とも称し、『新編武蔵風土記稿』の池上村の項には「岩倉社」として記載されています。
・境内はよく整備され、明るい雰囲気のお社です。本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で多彩な棟飾りを配し、寺院建築のエッセンスが入っているかも。
・御朱印は境内の授与所にて拝受でき、親切なご神職が兼務社の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:古宮神社 直書(筆書)


■ 龍智山 毘廬遮那寺 常光院
公式Web
熊谷市上中条1160
天台宗
御本尊:釈迦如来(三尊佛)
札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番
・公式Webの縁起より抜粋引用させていただきます。
「長承元年(1132年)、藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光公が武蔵国司として下向し、当地に館(中條館)を構え豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、16歳で既に頼朝公の石橋山の合戦に扈従し信任が厚く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画、評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺院とし、比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年(1192年)開基」「文禄三年(1594年)には忍城主松平忠吉(家康公四男)が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併」「開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章『梶竪一葉紋』を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇」
・山門には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。
・境内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。
・本堂は元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺きのどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。
・「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種以上もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度の参拝の方がいいかもしれません。
なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)
本堂に御座します。

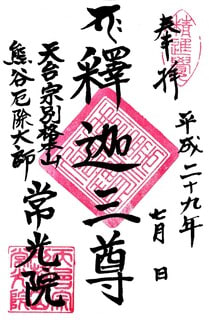
2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)
本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

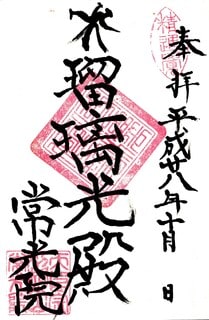
3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)
本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

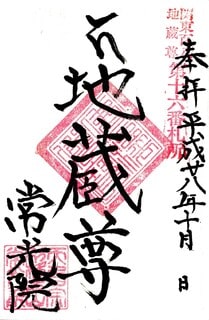
4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)
境内に露仏として奉安されています。

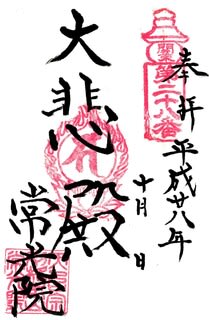
5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)
境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

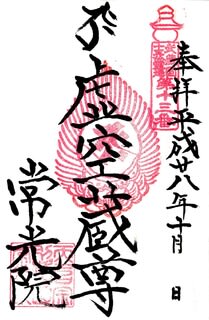
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
【 BGM 】
■ 夏影~Airness~ - 茶太ver
■ 春風 - Rihwa(カバー)
■ Hero - 安室奈美恵 // covered by 皇 美緒奈
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
1.旧 大里町エリア
■ 吉見神社
熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)
御祭神:天照大神
旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守
授与所:神社そばのご神職宅
・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。
・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。
・古社らしい厳かな境内。御朱印は境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)


■ (高本)高城神社
熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)
御祭神:高皇産霊命
旧社格:村社、延喜式内社(小)論社
元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)
授与所:神社そばのご神職宅
『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。
・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。
・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。
・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。
・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)


2.旧 江南町エリア
■ 東方山 保泉寺
熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。
・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。
・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。
・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内です。
・こちらはご縁をいただいて期せずして御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 東方山 保泉寺
熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。
・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。
・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。
・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。
・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 高根山 満讃寺
武州路十二支霊場Web
熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)
・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。
・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.武州路十二支霊場 普賢菩薩


■ 五台山 文殊寺
公式Web
熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:文殊師利大菩薩
・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。
・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。
・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。
・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。
・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。
・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。
・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)


■ 龍谷山 静簡院
熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番
・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。
・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。
・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。
・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。
・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。
・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。
・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釋迦如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音


3A.旧 熊谷市エリア-1
■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社
熊谷市鎌倉町44
御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命
旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)
元別当:大善院
授与所:古宮神社(池上)授与所
・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。
・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。
・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。
・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。
・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。
・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。
・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。
・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。
〔うちわ祭について〕
・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。
・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。
・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。
・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)


2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)


■ 星河山 千手院 石上寺
熊谷市鎌倉町36
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)
司元別当:(宮町)高城神社(熊谷市宮町)
・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。
・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。
・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。
・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。
・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。
・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)


2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

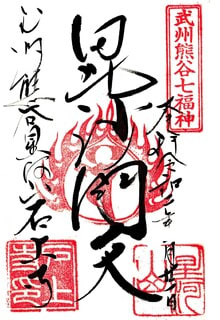
■ 熊野山 千形院 圓照寺
公式Web
熊谷市星川1-1
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)
・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。
・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。
・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。
・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。
・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.不動明王の御朱印


2.聖徳皇太子の御朱印


■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)
公式Web
熊谷市本石1-102
臨済宗妙心寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第2番
・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。
・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。
・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩


■ (宮町)高城神社
公式Web
熊谷市宮町2-93
御祭神:高皇産霊神
旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守
元別当:星河山 千手院 石上寺(鎌倉町/真言宗智山派)
授与所:境内授与所
・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。
・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。
・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:高城神社 直書(筆書)


髙城神社の御朱印帳

■ 肥塚山 成就院
熊谷市資料(PDF)
熊谷市肥塚2-6-1
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:-
司元別当:肥塚伊奈利神社(熊谷市肥塚)
・永正元年(1504年)以前に僧欽照による開山(ないし中興)と伝わり、古くは鎌倉胡桃大楽寺末であったといいます。
・「肥塚氏供養板石塔婆」があることから、肥塚氏ゆかりの寺院とみられます。「熊谷市文化財ガイドブック」(PDF)によると、熊谷氏の祖となった直季の弟直長が肥塚に住んで肥塚氏の始祖となったとのことです。
・御本尊は阿弥陀如来。脇本尊に「一光三尊(弥陀、勢至、観音)燈籠佛」(とても小さいそうです)を奉安され、こちらの御朱印も授与されています。
・燈籠佛は各種の霊験で知られ、江戸中期の忍藩主・阿部豊後守正充公も信仰したといいます。
・墓地は肥塚殿(山)と呼ばれた古墳跡とされます。
・御朱印は本堂にて拝受しましたが、1回目はご不在でした。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 阿弥陀如来


2.脇本尊 燈籠佛


■ 熊谷山 報恩寺
公式Web
熊谷市円光2-8-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。
・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。
熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。
そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。
姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。
その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。
寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。
・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。
・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。
・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。
・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。
・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。
・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。
・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。
・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。
・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


■ 梅籠山 久松寺 東竹院
熊谷市久下1834
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)
・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。
・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。
・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。
・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。
・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛


■ 佐谷田神社
熊谷市佐谷田310
御祭神:誉田別命
旧社格:旧佐谷田村鎮守
元別当:
旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(佐谷田村/新義真言宗)
旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(戸出村/新義真言宗)
旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(平戸村/真言宗新義)
・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)
・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。
・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。
・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書


■ 藤井山 源宗寺
熊谷市平戸611
曹洞宗
御本尊:薬師如来 観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第5番
・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。
・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。
・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。
・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。
・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。
■ 上之村神社
公式Web
熊谷市上之16
御祭神:事代主命、大山祇命、大己貴命
旧社格:郷社、上之村・箱田村・池上村三村の鎮守社
元別当:伊豆国 浄慶院 久見寺(上村/新義真言宗)
授与所:境内授与所
・公式Web、境内掲示、『埼玉の神社』などによると、創祀は平安時代以前とみられ、応永年間(1394-1428年)、成田五郎家時により再興とされます。
・明治2年に現在の上之村神社に改められるまでは、「久伊豆神社」ないし「久伊豆明神社」と号し、『新編武蔵風土記稿』の上村の項には「久伊豆社」として記載されています。
・『新編武蔵風土記稿』に「祭神ハ大山祇命ニテ 伊豆國三嶋社ヲ写シ祀ルトイヘト疑フヘシ 此久伊豆社ト云ハ騎西町塙ニ大社アリテ近郷往々是ヲ勧請スレハ 当社モ恐クハ彼ヲ写セシナラン」とあり、騎西ご鎮座の久伊豆神社の総社、玉敷神社からの勧請を示唆しています。
・御祭神は、江戸期は大山祇命でしたが、明治2年、主祭神を事代主命、相殿の神を大己貴命と大山祇命に改めています。
・また、別当の久見寺客殿に久伊豆の本地十一面観音が安置されていたとあり、神仏混淆の歴史が伺われます。
・当社ご鎮座の旧上(之)村は成田郷ともいわれた名族、成田氏の本貫で、当社は成田氏の尊崇篤く、後に徳川氏の尊崇を受けたと伝わります。なお、成田・別府・奈良・玉井氏は「武州四家」と呼ばれ、いずれも中世にこの地に勢力を張った名族とされています。
・当地有数の古社だけあって厳かな境内。木造の両部鳥居は寛文四年(1664年)建造の墨書が残り、市内最古の木造鳥居として市指定有形文化財に指定されています。
・応永年間(1394-1428年)、成田左京亮家時再建の本殿は一間社流造銅板葺で県指定文化財に指定されています。
・御朱印は参拝時たまたまご神職がいらしたのでいただけましたが、常駐ではありません。(公式Webにご在社予定が出ています。)
・熊谷七福神(恵比寿天)の御朱印は通常不授与かもしれませんが、御朱印には恵比寿様のお姿印が捺されていました。
・なお、兼務社として佐谷田神社、奈良神社(中奈良)、豊布都(とよふつ)神社(上奈良)、春日神社(小島)があり、それぞれWeb上で御朱印がみつかりますが、こちらで拝受できるかは不明です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:上之村神社 直書(筆書)


■ 大雷神社
熊谷市上之16
御祭神:大雷神
旧社格:上之村神社の境内社
元別当:
授与所:上之村神社境内授与所
・『新編武蔵風土記稿』に「末社 雷電 但馬国木田郡雷電社を勧請スト云伝フ(略)別当久見寺 客殿ニ雷電ノ本地馬頭観音を蔵ス」とあります。この地は雷の名所(?)ですが、どうしてわざわざ大雷神を但馬国(現・兵庫県)から勧請したのかはナゾです。
・上之村神社の摂社ですが、社号標、鳥居扁額ともに上之村神社と併記され、拝殿扁額も併記となっています。
・本殿は別で、こちらの本殿も県指定文化財に指定されています。
・この様な祭祀形態を配祀というか相殿というのかわかりませんが、本殿は分かれているので配祀なのかもしれません。
・「上之の雷電さま」と呼ばれ周辺住民の尊崇を集めています。利根川沿いのこのエリアはとくに雷が多く、随所で大雷神が祀られています。
・御朱印は、上之村神社境内授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大雷神社 直書(筆書)

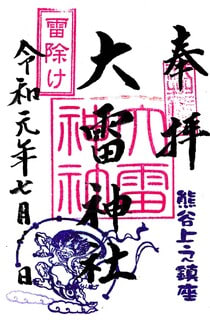
■ 太平山 龍淵寺
熊谷市上之336
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第8番
・名族成田家の菩提寺とされる名刹。
・境内掲示の寺伝・新編武蔵風土記稿などによると、開基は成田左京亮家時。応永十八年(1411年)和庵清順(わなんせいじゅん)大和尚により開創・開山。
・天正十九年(1591)、徳川家康公が遊猟の折に当寺へ立ち寄られ、時の住職呑雪和尚が家康公の三河時代の御乎習の御相手であったことがわかり、これを奇瑞として当寺に曹洞派の総録を許されましたが、呑雪和尚はあえてこの申し出を辞したと伝わります。
・本堂の後にあった小池は「龍ヶ淵」と呼ばれ、かつて龍が潜んでいましたが、開山の和尚清順が法力をもってこれを退けてこの地に当寺を建立したため「龍淵」を寺号としたと伝わります。
・成田氏系図をはじめ多くの文化財を蔵します。高浜虚子が当寺で詠んだ句碑も残されています。
・御朱印は庫裡にて御本尊のものを授与されています。忍観音霊場の御朱印は不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 伊弉諾神社 (いざなぎじんじゃ)
熊谷市上川上36
御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、大日孁貴命、猿田彦命、菅原道真公
旧社格:村社、旧上川上村鎮守
元別当:
授与所:古宮神社(池上)授与所
・社伝、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)などによると、中世、紀伊国熊野三所権現の勧請が創建で、当社、下川上の熊野社、大塚の熊野社の三社を総称して「熊野三所権現」と呼ぶとのこと。また、当社は「十二所権現」とも称されるようです。
・鎌倉期、征夷大将軍・宗尊親王が帰京した際、親王の供の平家ゆかりの宮田太郎貞明は北条氏の追及をおそれてこの地に逃れ当社の宮守りになった(『宮田氏家系図』)とされます。
・安政二年(1855)には、神祇管領から「伊弉諾神社熊野大権現」の幣帛を受けています。
・所蔵の黒馬図、相撲絵馬は市指定文化財に指定されています。
・古社にふさわしい厳かな境内。入母屋造桟瓦葺流れ向拝の端正な拝殿で、向拝には「伊弉諾神社」の扁額が掲げられています。
・御朱印は、古宮神社(熊谷市池上606)にて拝受しました。
・こちらは以前参拝し、その時は御朱印はないものと思っていましたが、いまは拝殿前に御朱印の案内が貼り出されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊弉諾神社 直書(筆書)


■ 古宮神社(こみやじんじゃ)
公式Web
熊谷市池上606
御祭神:石凝姥命、少彦名命、武甕槌命
旧社格:旧池上郷総鎮守
元別当:
授与所:境内授与所
・公式Web、境内由緒書、『埼玉の神社』などによると、古代、紀伊国秋月に御鎮座の旧宮幣大社、日前国懸神宮(ひのくま・くにかかすじんぐう)を勧請して創祀と伝わり、当初は社殿はなくいわゆる「磐座(いわくら)信仰」だったとみられています。
・社殿造立は、平安末期の長寛二年(1164年)。
・祭神の石凝姥命(いしこりどめのみこと)は、天孫降臨の際に邇邇芸命に随伴し、天児屋命、太玉命、天宇受売命、玉祖命と共に天降った五伴緒の一柱とされ、天照御大神が天岩戸にお隠れになったとき、日像鏡・日矛鏡を造られた神といわれています。
・西日本で祀られる例が多く、『埼玉の神社』には「なぜ、和歌山に祀られ鏡作部の遠祖とされる同神が、この地に勧請されたか不明であるが、埼玉地方は、武蔵国の古代文化の中心地の一つであり、近くには金錯銘鉄剣で有名な埼玉古墳群があることなどを考え合わせると、当地に神部(鏡作)ゆかりの人たちが住み、当社を祀ったとも考えられる。」とあります。
・室町期の文安二年(1445年)、相殿の神として少彦名命と武甕槌命を勧請したとされるので、創祀時の主祭神は石凝姥命とみられます。
・古くは岩倉社、又は岩倉大明神とも称し、『新編武蔵風土記稿』の池上村の項には「岩倉社」として記載されています。
・境内はよく整備され、明るい雰囲気のお社です。本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で多彩な棟飾りを配し、寺院建築のエッセンスが入っているかも。
・御朱印は境内の授与所にて拝受でき、親切なご神職が兼務社の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:古宮神社 直書(筆書)


■ 龍智山 毘廬遮那寺 常光院
公式Web
熊谷市上中条1160
天台宗
御本尊:釈迦如来(三尊佛)
札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番
・公式Webの縁起より抜粋引用させていただきます。
「長承元年(1132年)、藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光公が武蔵国司として下向し、当地に館(中條館)を構え豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、16歳で既に頼朝公の石橋山の合戦に扈従し信任が厚く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画、評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺院とし、比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年(1192年)開基」「文禄三年(1594年)には忍城主松平忠吉(家康公四男)が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併」「開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章『梶竪一葉紋』を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇」
・山門には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。
・境内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。
・本堂は元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺きのどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。
・「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種以上もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度の参拝の方がいいかもしれません。
なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)
本堂に御座します。

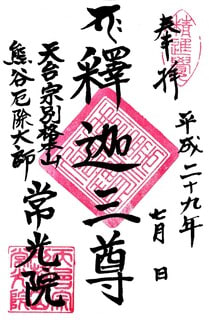
2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)
本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

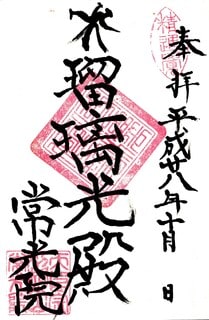
3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)
本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

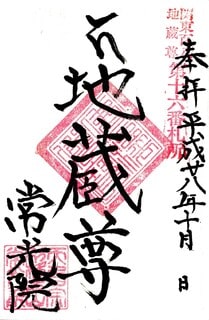
4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)
境内に露仏として奉安されています。

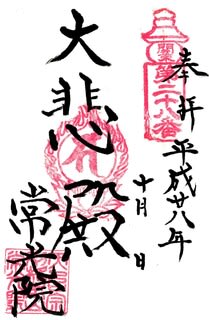
5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)
境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

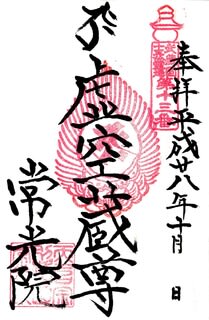
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
【 BGM 】
■ 夏影~Airness~ - 茶太ver
■ 春風 - Rihwa(カバー)
■ Hero - 安室奈美恵 // covered by 皇 美緒奈
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
本日28日は初不動でした。
新規に内容を追加してリニューアルUPします。
歴史あるお寺様が多く、徳川家康公のブレーン?であった天海大僧正が「江戸の守護結界のために五色の不動尊を(江戸をとりまくように)安置した。」という説もあります。
早起きすれば一日結願もできると思います。
興味ある方は一度巡ってみてはいかがでしょうか。
-------------------------
2021/08/13 UP
武州江戸六阿弥陀詣の御朱印がけっこうなアクセスをいただいているので、江戸五色不動についてもまとめてみます。
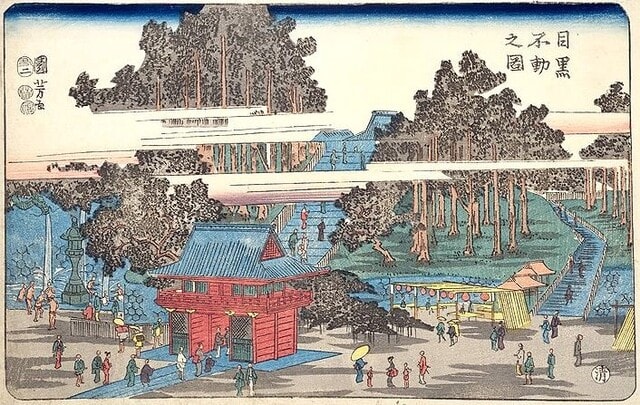
「目黒不動之図 / 源氏絵」 国芳
(国立国会図書館「錦絵で楽しむ江戸の名所」より利用規約にもとづき転載。)

「目白不動堂 / 江戸名所図会. 十二」
(国立国会図書館D.C.より利用規約にもとづき転載。)
江戸五色不動は、都内に御座す五尊のお不動様を巡拝する不動尊詣でです。
江戸五色不動についてはこれまで詳細に調べたことはなく、武州江戸六阿弥陀詣や江戸六地蔵と同様、江戸時代から広く親しまれていたものと思っていました。
ところが今回調べてみると、どうやら江戸時代には”江戸五色不動”というものはなく、不動尊巡拝にかかわる史料も多くないことがわかりました。
それでも”江戸五色不動”が比較的広く知られているのは、「天海大僧正が江戸の守護結界のために五色の不動尊を(江戸をとりまくように)安置した。」というわかりやすい説があるからだと思います
考えてみると、江戸には弘法大師霊場、阿弥陀詣、観音霊場、地蔵霊場、弁天霊場、閻魔巡りなど、とりどりの霊場が揃っていたのに、不動尊霊場については主だった記録がみあたりません。
お不動様はご縁日に一日一尊でお参りするもの、という意識があったのかも。
この点は、主な尊格がたとえば(二十一、八十八)弘法大師霊場、(六)阿弥陀、(三十三、七)観音、(七)薬師など一定の数で尊格・札所構成されるのに対し、不動尊についてはそういうものがあまりみられないことからも裏付けられるかもしれません。
(御府内二十八不動霊場という霊場の情報がありますが、こちらは明治に入ってからの開創のようです。)
なお、近年各地で「三十六不動尊霊場」が開創されていますが、これは不動明王の眷属の三十六童子に由来するものかと思われます。
「江戸五色不動」については比較的多くの資料やWeb資料がみつかりますが、その切り口は大きく2つに分かれます。
1.「江戸五色不動」江戸鎮護結界説
2.「江戸五色不動」は江戸時代にはなかった説(非結界説)
史料から当たっていくと、どうやら2.に落ち着く感じがしますが(結果として結界は張られているのかも)、6箇寺それぞれの由緒をひもといていくと、見えてくるものもあるかもしれません。
なお、下記のWeb記事を参考とさせていただきました。
■ まぼろしの五色不動
■ 日本文化の入り口マガジン
■ 江戸五色不動と武蔵野
〔 江戸五色不動の所在 〕
江戸五色不動に札番は振られていません。
なので参拝順の縛りはないと思いますが、西から順にリストしてみました。
なお、「目黄不動尊」は通常2尊リストされますので、実質は6ヶ寺の巡拝となります。
■ 竹園山 最勝寺 教学院 / 目青不動尊
世田谷区太子堂4-15-1(港区麻布谷町(現・六本木周辺)の勧行寺または正善寺から青山南町を経て移転)
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
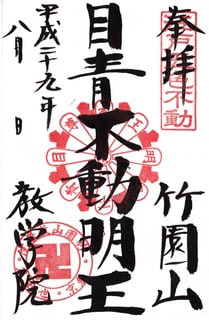
■ 泰叡山 護國院 瀧泉寺 / 目黒不動尊
目黒区下目黒3-20-26
天台宗 御本尊:不動明王
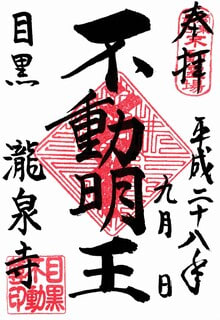
■ 神霊山 慈眼寺 金乗院 / 目白不動尊
豊島区高田2-12-39(新長谷寺(現・文京区関口)から移転)
真言宗豊山派

■ 大聖山 東朝院 南谷寺 / 目赤不動尊
文京区本駒込1-20-20
天台宗 御本尊:不動明王
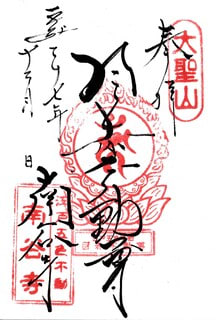
■ 養光山 金碑院 永久寺 / 目黄不動尊
台東区三ノ輪2-14-5
天台宗 御本尊:不動明王

■ 牛宝山 明王院 最勝寺 / 目黄不動尊
江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)
天台宗 御本尊:釈迦如来・不動明王

寺院は山の手・三軒茶屋(世田谷区)から下町・平井(江戸川区)まで、南北13.61km、東西17.81kmの範囲に分散しています。
電車・バスを使えばおそらく1日で廻れるかと思いますが、見どころの多い大寺もあるので、何日かに分けてじっくり廻るのも手かと思います。
〔 江戸五色不動の回り方 〕
目黄不動尊(最勝寺)が離れているので、こちらをラストとするのがベターかと思います。
1日で回れそうな効率的なルートを考えてみました。
1.目黒不動尊(瀧泉寺/目黒)
2.目青不動尊(教学院/三軒茶屋)
3.目白不動尊(金乗院/目白・雑司が谷)
4.目赤不動尊(南谷寺/本駒込)
5.目黄不動尊(永久寺/三ノ輪)
6.目黄不動尊(最勝寺/平井)
鉄道網のつながりが意外に悪く、ルートをミスると1日では結願できない可能性も。
見どころも多いので、できれば9時すぎには目黒不動尊に到着したいところです。
※なお、この乗り継ぎ案は新型コロナ禍前のものです。現時点では変更となっている可能性があります。
1.目黒不動尊(瀧泉寺/目黒)
スタート:目黒駅(正面(中央)口) → 行人坂・太鼓橋・五百羅漢寺前 → 目黒不動尊(目黒駅から1㎞強、散策含みで30分はみておいた方がいいかと。)
目黒不動尊から鉄道駅まではけっこう距離があるので、目青不動尊まではバスルートをご紹介します。
バス停「元競馬場前」(目黒不動尊から1㎞弱)
東急バス「黒06 三軒茶屋駅~目黒駅前線」 →時刻表(15分に1本程度)
※この路線は住宅地を縫うように走り、運転手さんのスーパーテクが味わえる「東京のバス狭隘区間」のひとつとして知られています。
終点:三軒茶屋駅3番バス停で降ります。(乗車33分)
→ 目青不動尊(バス停から徒歩約300m)
2.目青不動尊(教学院/三軒茶屋)
三軒茶屋(東急田園都市線)→ 渋谷(メトロ副都心線) → 雑司が谷 (乗車約25分、3番出口、徒歩5~10分) → 目白不動尊
3.目白不動尊(金乗院/目白・雑司が谷)
目白不動尊から目赤不動尊までは、いろいろなルートがあります。
都電荒川線「学習院下」→メトロ「本駒込」の乗換案内検索結果。
都電荒川線は風情ありますが、のんびり走るので時間がかかります。
※ 目白不動尊 → 甘泉園公園前 (都営バス 飯64系統時刻表、乗車20分) → 飯田橋駅前(メトロ南北線) → 本駒込(2番出口、徒歩2分) → 目赤不動尊
という乗換1回の裏ワザもありますが、甘泉園公園前バス停までけっこう歩きます。
4.目赤不動尊(南谷寺/本駒込)
本駒込から三ノ輪(目黄不動尊(永久寺))までは、
本駒込(メトロ南北線)→後楽園(徒歩)→春日(都営大江戸線)→上野御徒町(徒歩)仲御徒町(メトロ日比谷線)→三ノ輪
が最短ですが、乗継徒歩(2回)の距離がかなりあるのでおすすめできません。(駒込・上野ルートも同様)
ここは、乗り換えなしのバス便をおすすめします。
目赤不動尊 →(徒歩約300m)→東洋大学前 →(都営バス 草63系統)→ 三ノ輪駅前(所要約30分、15分に1本、時刻表)→(徒歩すぐ)目黄不動尊(永久寺)
5.目黄不動尊(永久寺/三ノ輪)
三ノ輪(メトロ日比谷線)→ 秋葉原(JR総武線線)→ 平井(乗換1回、所要約25分)
平井(南口、徒歩約16分(1.3㎞))→ 目黄不動尊(最勝寺)
6.目黄不動尊(最勝寺/平井)
「関東三十六不動霊場」の札所の納経受付止時間はおおむね16時~17時で、季節により変動するところもあります。最勝寺の時間確認は03-3681-7857(寺務所)まで。
御朱印についてはすべての寺院で拝受できますが、すべてで「五色不動」の印判をいただけるかは不明です。
※ 目黄不動尊は上記のとおり2尊リストされていますが、下記の2尊についても「目黄不動尊」とする説があります。
■ 古碧山 龍巌寺 / 目黄不動尊
渋谷区神宮前2-3-8(墨田区東駒形から移転)
臨済宗南禅寺派 御本尊:釈迦如来

孫引きとなりますが、猫の足あと様掲載の『渋谷区史』には「本堂の側に大師堂がある。府内八十八ヶ所九番の札所である。明治七年熊野神社の別当浄性院から移した、堂内に安置せる不動尊を目黄不動という。しかし目黄不動は、江戸川区荒川堤下最勝寺(もと本所表町)にあるのが、古来有名である。」とあり、こちらの不動尊が「目黄不動」として数えられたという説があります。
参拝時、大師堂の手前に、「五色不動」を示す石碑(?)があった記憶もありますが、こちらは山内撮影禁止なので定かではありません。
なお、Web情報では「一般公開されていない」との記述が複数みつかりますが(Wikipediaに「非公開」とある)、こちらは御府内霊場の札所(第9番)なので参拝は可能で御朱印も拝受できます。(敷居はやや高いですが・・・。)
御府内霊場の御朱印の主尊格は釈迦牟尼佛ですが、黄金目不動明王の揮毫もあります。
■ 五大山 不動院 / 目黄不動尊
港区六本木3-15-4
高野山真言宗 御本尊:不動明王
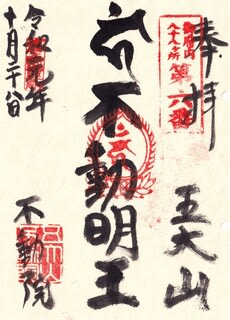
万治元年(1658年)に麹町平河町より当地へ移転したといい、「通称、麻布不動坂の一願不動さん、或は六軒町の目黄不動と呼ばれ、親しまれてきた。」という伝承があるようです。(→参考)
なお、もともとの目青不動尊と伝わる麻布谷町にあった勧行寺(ないし正善寺)に近いため、こちらとの関連を示唆する説もあるようです。
こちらも御府内霊場の札所(第6番)なので参拝可能で御朱印もいただけます。
御本尊、不動明王の御朱印です。
こちらは非常駐のようで通常は閉扉され、御朱印は兼務されている大安楽寺(中央区日本橋小伝馬町)での授与となりますが、タイミングが合えば御本尊前でお参りでき、御朱印も本堂内で拝受することができます。
なお、昭島市の眞覺寺も「目黄不動尊」を護持されていますが、こちらと「江戸五色不動」との関係は確認できておりません。
■ 築当山 眞覺寺 / 目黄不動尊
昭島市玉川町5-9-27
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
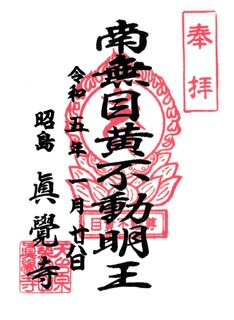
上記のように複数の目黄不動尊が存在することは、「江戸五色不動」の複雑な歴史を物語っています。
〔 江戸五色不動の宗派 〕
不動尊霊場としてはめずらしく、天台宗が多くなっています。
目白不動尊(金乗院)のみが真言宗豊山派で、あとはすべて天台宗寺院です。
大僧正天海の発案ということであれば、天台宗一択ですべて天台宗寺院の方が自然です。
とくに結界が絡むとなると、山王一実神道は避けて通れなくなるはずで、その点からも天台宗寺院で固める必要があったのでは。
実際、目黒不動尊は山王一実神道との関係を表明し、最近、参道に山王鳥居を建立しています。
一寺だけ真言宗寺院が入っていることについては、なにか特段の理由があったのかもしれません。
〔 江戸五色不動の歴史 〕
諸説あり錯綜していますが、手持ちの文献やWeb上で確認できた内容を列挙してみます。
・寛永年間(1624-1645年)、三代将軍家光公が大僧正天海の具申により江戸(王城)鎮護祈願のために、江戸の周囲に五色の不動尊を造立して安置。当初は四神相応の四不動を定め、のちに目黄が追加された。
五色とは陰陽五行説に由来するもので青(東/青龍)・白(西/白虎)・赤(南/朱雀)・黒(北/玄武)・黄(中央/皇帝)をあらわす。
・参考Webによると、寛保元年(1741年)著の小野高尚の『夏山雑談』には「江戸城鎮護のために不動明王像を、鎮護の四神にならい江戸城の四方に配置したのが目黒・目白・日赤・目青の四不動」との記載があるらしく、これが事実だとすると五色不動鎮護結界説が成立するが、多くの人はこれに疑義を呈している。(原典確認中)
というのは、この『夏山雑談』以外に「五色不動」にふれた江戸期の史料がほとんど見当たらないからです。
江戸時代には三大不動「目黒不動尊・目白不動尊・薬研掘不動尊」が広く知られていましたが、薬研掘不動尊は「五色不動」に入らず、色も振られていません。
お不動様の信仰篤かった江戸庶民のこととて、この時期に「五色不動」が成立していれば、当然『江戸名所図会』『東都歳時記』や『江戸砂子』に記載があるはずですが、見当たりません。(個別の不動尊寺院はかなりとりあげられている)
また、陰陽五行説の方位色と実際の寺院の方位が合わないことも疑義の論拠とされています。
文化五年(1808年)の「柳樽四十六篇」に、「五色には二色足らぬ不動の目」との川柳が残されています。
おそらく目青と目黄が「足りなかった」とみられますが、逆にみると文化五年の時点で「五色不動」が意識されていたことがみてとれます。
・八代将軍吉宗公が、享保年間(1716-1736年)に民力休養のための花見の場所の整備とともに5ヶ所(の不動尊)を選定されたという説。
・江戸に入る街道口の守護として置かれたという説。(=江戸六地蔵の縁起に通じる)
東海道/目黒不動尊(龍泉寺)、中山道/目赤不動尊(南谷寺)、川越街道/目白不動尊(新長谷寺)、甲州街道/目青不動尊(教学院)、日光街道(奥州街道)/目黄不動尊(永久寺)、水戸街道/目黄不動尊(最勝寺)。
・古来、それぞれの寺院の所在する場所で産した馬の毛色や目色からきているという説。
目黒の「目」が「駿馬」をあらわすという説から付会されたものかもしれません。
↑ のように多彩な説があることは、裏返すと江戸時代には「江戸五色不動」が確定していなかったことを示すものかもしれません。
こちらの記事では、『江戸砂子』『続江戸砂子』に記された不動霊場をまとめられています。現時点では筆者にて原典の該当箇所が確認できていないので、恐縮ですが孫引きさせていただきます。
( )は筆者の追記。札番は関東三十六不動霊場のもの。☆は筆者が御朱印拝受した寺院。
--------------------------------------------
五 不動霊場 来由前集にあり。
○目黒不動 慈覚作 めぐろ龍泉寺 (目黒、目黒不動尊、五色不動、第18番☆)
○目白不動 弘法作 めじろ長谷寺 (高田金乗院、目白不動尊、五色不動、第14番☆)
○目赤不動 作不知 駒込南谷寺 (駒込南谷寺、目赤不動尊、五色不動、第13番☆)
○砂尾不動 良弁作 はしば不動院 (砂尾山 不動院 橋場不動尊、第23番☆)
〔増〕逆流不動 作不知 立像五尺 湯嶋根生院護摩堂 (金剛賓山 根生院/豊島区高田☆)
〔増〕幸不動 慈覚の作 修験 宝玉院 神田かぢ町二丁目 (不詳)
○三日月不動 深川 心行寺 (雙修山 心行寺☆)
○波切不動 浅草寺町 大乗院 (五剣山 大乗院/台東区元浅草)
○飛不動 下谷 大音寺前正宝院 (龍光山 正寶院/台東区竜泉、第24番☆)
○大山不動 駒込 願行寺 (既成山 願行寺/文京区向丘☆)
○薬研堀不動 よこ山町 明王院 (薬研堀不動院(川崎大師別院)/中央区東日本橋、第21番☆)
〔増〕滝不動 日暮里道灌山より三丁ほど北の方、田端六あみだのひがし、二丁ほどに、一茂りの小山あり。御用やしきと云。此所に少しの滝あり、下に石仏の不動まします。 (不詳)
○は『江戸砂子』にも載っているもの、〔増〕は『続江戸砂子』での追加分である。
--------------------------------------------
上記によると、五色不動のうち目黒、目白、目赤の三不動は記載されていますが、目青、目黄は記載されていません。
また、江戸の不動尊信仰の要となった深川不動堂(成田山 東京別院)が記載されていないのは不思議な感じがします。
深川永代寺で催された成田山の不動明王の第1回目の「出開帳」は元禄十六年(1703年)、以降江戸江戸時代を通じて計12回行われた出開帳のうち11回は深川永代寺が会場となりました。
ただし、あくまでも「出開帳の会場」であったので、↑の『江戸砂子』には載っていないのかもしれません。(深川永代寺のそばに「深川不動堂」が置かれたのは、明治11年(1878年)です。)
なお、江戸時代には「(江戸)三大不動」が知られており、目黒不動尊、目白不動尊、薬研堀不動尊がこれに当たります。
ただし、三つの不動尊を巡拝するというよりは、ご縁日や願掛けに一寺ずつじっくりと参拝するという傾向が強かったのでは。
歌舞伎役者市川團十郎の影響もあり、江戸の庶民のあいだで成田詣りの人気が高かったこと、また、薬研堀には川崎大師の別院「薬研堀不動尊」、目黒には観光地としても知られた目黒不動尊があったことなどからも、「お不動さまはじっくりと願かけ」という意識が強まった可能性があります。
上記の『江戸砂子』の不動霊場には、昭和62年(1987年)に開創された関東三十六不動尊霊場の札所がいくつかみられます。
また、「深川不動堂(尊)」もこの霊場の札所で、江戸期から信仰を集めた不動尊も多くあるため、上記の☆印の寺院のほかに下記の関東三十六不動尊霊場の札所(都区内)もご紹介します。
■ 石神井不動尊(亀頂山 密乗院 三寶寺) 第11番、練馬区石神井台
■ 志村不動尊(寶勝山 蓮光寺 南蔵院) 第12番、板橋区蓮沼町
■ 中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺) 第15番、中野区中央
■ 等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院) 第17番、世田谷区等々力
■ 浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院) 第22番、台東区寿
■ 皿沼不動尊(皿沼山 永昌院) 第25番、足立区皿沼
■ 西新井大師不動明王(五智山 遍照院 總持寺) 第26番、足立区西新井
まずは江戸五色不動の6つの寺院についてご紹介していきます。
01.竹園山 最勝寺 教学院〔目青不動尊 / 江戸五色不動〕
世田谷区太子堂4-15-1(港区麻布谷町(現・六本木周辺)の勧行寺または正善寺から青山南町を経て移転)
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:江戸五色不動(目青不動尊)、関東三十六不動尊霊場第16番、大東京百観音霊場第54番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番、東京三十三所観世音霊場第10番
縁起によると、応長元年(1311年)江戸城内紅葉山に創建。
太田道灌の江戸城築城にともない麹町貝塚~赤坂三分坂と移り、慶長九年(1604年)には青山南町(百人町)に移転。開基は法印玄応大和尚。
百人町居住の同心の帰依を受けて閻魔堂(現在の不動堂)を建立し、「三合山」「青山のお閻魔さま」とも呼ばれて双盤念仏がさかんに行われたといいます。
元禄年間頃までは山王成琳寺(赤坂日枝神社別当)の末寺でしたが、貞享四年(1687年)頃に相州小田原城主・大久保加賀守忠朝の菩提寺となって隆盛。東叡山輪王寺の直末となりました。
明治41年(1909年)から3年を要して現在地に移転し、現在に至ります。
明和九年(1772年)刊の『江戸砂子』(国会図書館DC)にはつぎの記載があります。
「江戸名所図會、熊野権現社の次條に、心見観音、同北に隣る天台宗にして竹園山教學院と號す、本尊は聖徳太子の真作」
目青不動尊は、麻布谷町にあったという源三位頼政ゆかりの古刹、三合山 源理院 正善寺(随縁山 教解院 観行寺とも)の御本尊が明治15年(1882年)経学院に遷し奉られたもの。
慈覚大師円仁の御作と伝わり、天上界と地上界の間にたなびく青雲の色ゆかりの不動尊といわれ、「縁結びの不動尊」としてとくに女性の信仰が篤いとのことです。
江戸時代より五色不動(五眼不動)の一つに数えられ、東西南北中央の五方角と色(五色)を合わせたもので、将軍家光公の時代に成立したといわれています。


【写真 上(左)】 南の山門
【写真 下(右)】 東の山門
東急線「三軒茶屋」駅から徒歩数分。東急世田谷線からも見えるところです。
山門は世田谷線に面した南側と東側の二箇所あり、堂宇に近いのは東側です。
駅近ですが、山内は緑が多く名刹らしい落ち着きが感じられます。


【写真 上(左)】 門柱に「目青不動尊」
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 不動堂
東側山門から入って右側に不動堂。入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁に木鼻と海老虹梁を備え、正面格子戸で左右に大ぶりな花頭窓を拝しています。


【写真 上(左)】 不動堂(斜めから)
【写真 下(右)】 不動堂向拝-1


【写真 上(左)】 不動堂向拝-2
【写真 下(右)】 不動霊場札所板
右手向拝柱に「関東三十六不動霊場」の札所板。身舎上部には向かって右から、「閻王殿」「不動明王」「元三大師」の扁額が掲げられています。
寺宝として閻魔大王、脱衣婆があり、こちらは不動尊両脇侍仏です。
扁額、脇侍仏ともに「青山のお閻魔さま」の流れを伝えるものとみられます。
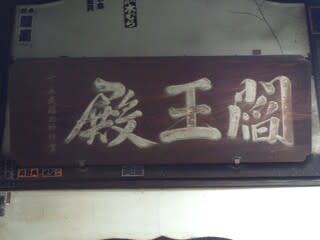

【写真 上(左)】 「閻王殿」の扁額
【写真 下(右)】 「不動明王」の扁額


【写真 上(左)】 「元三大師」の扁額
【写真 下(右)】 寺紋
御本尊の不動明王は秘仏でお厨子内に御座。御前立ちの青銅不動明王坐像も寺宝に定められています。
御前立ちのお不動様は、寛永十九年(1642年)の銘があり、丸いお顔で微笑みを湛えられ「縁結びのお不動さま」として、若い女性の信仰を集めてきたといいます。
恋愛成就の仏様はふつう愛染明王で、お不動さまがこの役を受けもたれる例はめずらしいかもしれません。
樹木に囲まれた参道正面に本堂。
入母屋造銅板葺流れ向拝で水引虹梁、向拝柱、正面桟唐戸、左右に花頭窓。
御本尊は恵心僧都作とされる上品上生阿弥陀如来坐像で、こちらも寺宝です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 納経所
聖徳太子の作と伝わる聖観世音菩薩は本堂に安置され、おそらくこちらが3つの観音霊場の札所本尊かと思われます。
江戸砂子温故名蹟誌 6巻5には「城琳寺末 心見観音、聖徳太子の作、名ある糸さくらあり」(国会図書館DC)とあり、目青不動尊を迎える前は心見観音の霊場として知られていたのかもしれません。
墓所には、小田原大久保家歴代の基、南画家、岡本秋暉の基、明治の書家、岡本碧巌の基などがあります。
御朱印は参道左の納経所にて快く授与いただけます。
目青不動明王、聖観世音菩薩の両尊の御朱印をいただけますが、御本尊・阿弥陀如来の御朱印は授与されていないとのことです。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
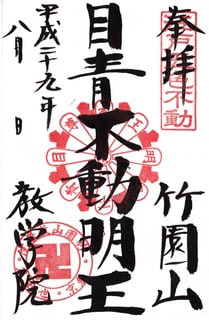
・御朱印尊格:目青不動明王 江戸五色不動尊印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/専用納経帳〕
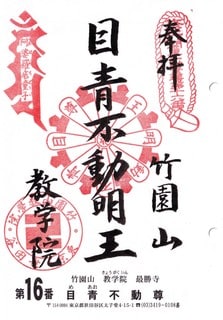
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 書置(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/御朱印帳〕
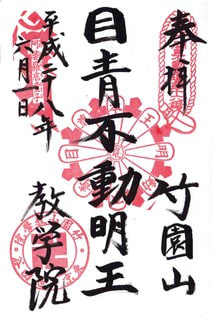
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 直書(筆書)
〔大東京百観音霊場第54番の御朱印〕
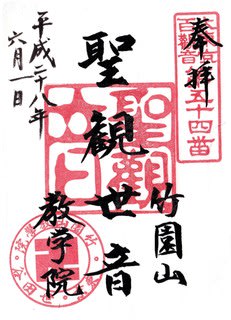
・御朱印尊格:聖観世音 大東京百観音霊場第54番印判 書置(筆書)
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番の御朱印〕
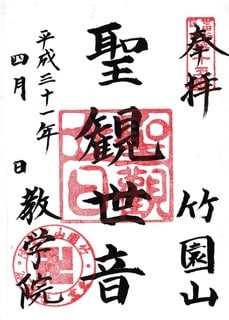
・御朱印尊格:聖観世音 世田谷区内第15番印判 直書(筆書)
こちらへつづく
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 6.目黄不動尊(最勝寺)
新規に内容を追加してリニューアルUPします。
歴史あるお寺様が多く、徳川家康公のブレーン?であった天海大僧正が「江戸の守護結界のために五色の不動尊を(江戸をとりまくように)安置した。」という説もあります。
早起きすれば一日結願もできると思います。
興味ある方は一度巡ってみてはいかがでしょうか。
-------------------------
2021/08/13 UP
武州江戸六阿弥陀詣の御朱印がけっこうなアクセスをいただいているので、江戸五色不動についてもまとめてみます。
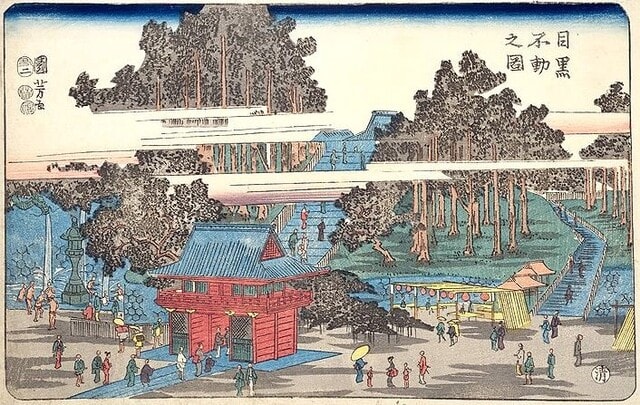
「目黒不動之図 / 源氏絵」 国芳
(国立国会図書館「錦絵で楽しむ江戸の名所」より利用規約にもとづき転載。)

「目白不動堂 / 江戸名所図会. 十二」
(国立国会図書館D.C.より利用規約にもとづき転載。)
江戸五色不動は、都内に御座す五尊のお不動様を巡拝する不動尊詣でです。
江戸五色不動についてはこれまで詳細に調べたことはなく、武州江戸六阿弥陀詣や江戸六地蔵と同様、江戸時代から広く親しまれていたものと思っていました。
ところが今回調べてみると、どうやら江戸時代には”江戸五色不動”というものはなく、不動尊巡拝にかかわる史料も多くないことがわかりました。
それでも”江戸五色不動”が比較的広く知られているのは、「天海大僧正が江戸の守護結界のために五色の不動尊を(江戸をとりまくように)安置した。」というわかりやすい説があるからだと思います
考えてみると、江戸には弘法大師霊場、阿弥陀詣、観音霊場、地蔵霊場、弁天霊場、閻魔巡りなど、とりどりの霊場が揃っていたのに、不動尊霊場については主だった記録がみあたりません。
お不動様はご縁日に一日一尊でお参りするもの、という意識があったのかも。
この点は、主な尊格がたとえば(二十一、八十八)弘法大師霊場、(六)阿弥陀、(三十三、七)観音、(七)薬師など一定の数で尊格・札所構成されるのに対し、不動尊についてはそういうものがあまりみられないことからも裏付けられるかもしれません。
(御府内二十八不動霊場という霊場の情報がありますが、こちらは明治に入ってからの開創のようです。)
なお、近年各地で「三十六不動尊霊場」が開創されていますが、これは不動明王の眷属の三十六童子に由来するものかと思われます。
「江戸五色不動」については比較的多くの資料やWeb資料がみつかりますが、その切り口は大きく2つに分かれます。
1.「江戸五色不動」江戸鎮護結界説
2.「江戸五色不動」は江戸時代にはなかった説(非結界説)
史料から当たっていくと、どうやら2.に落ち着く感じがしますが(結果として結界は張られているのかも)、6箇寺それぞれの由緒をひもといていくと、見えてくるものもあるかもしれません。
なお、下記のWeb記事を参考とさせていただきました。
■ まぼろしの五色不動
■ 日本文化の入り口マガジン
■ 江戸五色不動と武蔵野
〔 江戸五色不動の所在 〕
江戸五色不動に札番は振られていません。
なので参拝順の縛りはないと思いますが、西から順にリストしてみました。
なお、「目黄不動尊」は通常2尊リストされますので、実質は6ヶ寺の巡拝となります。
■ 竹園山 最勝寺 教学院 / 目青不動尊
世田谷区太子堂4-15-1(港区麻布谷町(現・六本木周辺)の勧行寺または正善寺から青山南町を経て移転)
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
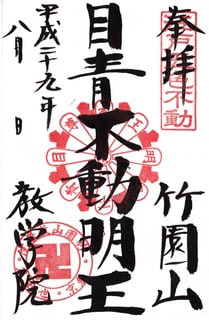
■ 泰叡山 護國院 瀧泉寺 / 目黒不動尊
目黒区下目黒3-20-26
天台宗 御本尊:不動明王
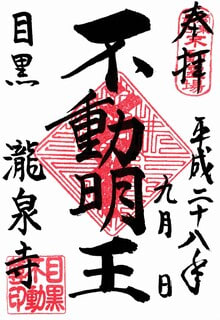
■ 神霊山 慈眼寺 金乗院 / 目白不動尊
豊島区高田2-12-39(新長谷寺(現・文京区関口)から移転)
真言宗豊山派

■ 大聖山 東朝院 南谷寺 / 目赤不動尊
文京区本駒込1-20-20
天台宗 御本尊:不動明王
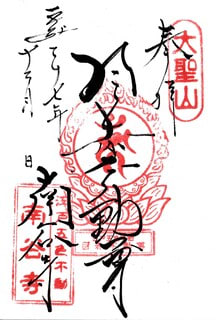
■ 養光山 金碑院 永久寺 / 目黄不動尊
台東区三ノ輪2-14-5
天台宗 御本尊:不動明王

■ 牛宝山 明王院 最勝寺 / 目黄不動尊
江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)
天台宗 御本尊:釈迦如来・不動明王

寺院は山の手・三軒茶屋(世田谷区)から下町・平井(江戸川区)まで、南北13.61km、東西17.81kmの範囲に分散しています。
電車・バスを使えばおそらく1日で廻れるかと思いますが、見どころの多い大寺もあるので、何日かに分けてじっくり廻るのも手かと思います。
〔 江戸五色不動の回り方 〕
目黄不動尊(最勝寺)が離れているので、こちらをラストとするのがベターかと思います。
1日で回れそうな効率的なルートを考えてみました。
1.目黒不動尊(瀧泉寺/目黒)
2.目青不動尊(教学院/三軒茶屋)
3.目白不動尊(金乗院/目白・雑司が谷)
4.目赤不動尊(南谷寺/本駒込)
5.目黄不動尊(永久寺/三ノ輪)
6.目黄不動尊(最勝寺/平井)
鉄道網のつながりが意外に悪く、ルートをミスると1日では結願できない可能性も。
見どころも多いので、できれば9時すぎには目黒不動尊に到着したいところです。
※なお、この乗り継ぎ案は新型コロナ禍前のものです。現時点では変更となっている可能性があります。
1.目黒不動尊(瀧泉寺/目黒)
スタート:目黒駅(正面(中央)口) → 行人坂・太鼓橋・五百羅漢寺前 → 目黒不動尊(目黒駅から1㎞強、散策含みで30分はみておいた方がいいかと。)
目黒不動尊から鉄道駅まではけっこう距離があるので、目青不動尊まではバスルートをご紹介します。
バス停「元競馬場前」(目黒不動尊から1㎞弱)
東急バス「黒06 三軒茶屋駅~目黒駅前線」 →時刻表(15分に1本程度)
※この路線は住宅地を縫うように走り、運転手さんのスーパーテクが味わえる「東京のバス狭隘区間」のひとつとして知られています。
終点:三軒茶屋駅3番バス停で降ります。(乗車33分)
→ 目青不動尊(バス停から徒歩約300m)
2.目青不動尊(教学院/三軒茶屋)
三軒茶屋(東急田園都市線)→ 渋谷(メトロ副都心線) → 雑司が谷 (乗車約25分、3番出口、徒歩5~10分) → 目白不動尊
3.目白不動尊(金乗院/目白・雑司が谷)
目白不動尊から目赤不動尊までは、いろいろなルートがあります。
都電荒川線「学習院下」→メトロ「本駒込」の乗換案内検索結果。
都電荒川線は風情ありますが、のんびり走るので時間がかかります。
※ 目白不動尊 → 甘泉園公園前 (都営バス 飯64系統時刻表、乗車20分) → 飯田橋駅前(メトロ南北線) → 本駒込(2番出口、徒歩2分) → 目赤不動尊
という乗換1回の裏ワザもありますが、甘泉園公園前バス停までけっこう歩きます。
4.目赤不動尊(南谷寺/本駒込)
本駒込から三ノ輪(目黄不動尊(永久寺))までは、
本駒込(メトロ南北線)→後楽園(徒歩)→春日(都営大江戸線)→上野御徒町(徒歩)仲御徒町(メトロ日比谷線)→三ノ輪
が最短ですが、乗継徒歩(2回)の距離がかなりあるのでおすすめできません。(駒込・上野ルートも同様)
ここは、乗り換えなしのバス便をおすすめします。
目赤不動尊 →(徒歩約300m)→東洋大学前 →(都営バス 草63系統)→ 三ノ輪駅前(所要約30分、15分に1本、時刻表)→(徒歩すぐ)目黄不動尊(永久寺)
5.目黄不動尊(永久寺/三ノ輪)
三ノ輪(メトロ日比谷線)→ 秋葉原(JR総武線線)→ 平井(乗換1回、所要約25分)
平井(南口、徒歩約16分(1.3㎞))→ 目黄不動尊(最勝寺)
6.目黄不動尊(最勝寺/平井)
「関東三十六不動霊場」の札所の納経受付止時間はおおむね16時~17時で、季節により変動するところもあります。最勝寺の時間確認は03-3681-7857(寺務所)まで。
御朱印についてはすべての寺院で拝受できますが、すべてで「五色不動」の印判をいただけるかは不明です。
※ 目黄不動尊は上記のとおり2尊リストされていますが、下記の2尊についても「目黄不動尊」とする説があります。
■ 古碧山 龍巌寺 / 目黄不動尊
渋谷区神宮前2-3-8(墨田区東駒形から移転)
臨済宗南禅寺派 御本尊:釈迦如来

孫引きとなりますが、猫の足あと様掲載の『渋谷区史』には「本堂の側に大師堂がある。府内八十八ヶ所九番の札所である。明治七年熊野神社の別当浄性院から移した、堂内に安置せる不動尊を目黄不動という。しかし目黄不動は、江戸川区荒川堤下最勝寺(もと本所表町)にあるのが、古来有名である。」とあり、こちらの不動尊が「目黄不動」として数えられたという説があります。
参拝時、大師堂の手前に、「五色不動」を示す石碑(?)があった記憶もありますが、こちらは山内撮影禁止なので定かではありません。
なお、Web情報では「一般公開されていない」との記述が複数みつかりますが(Wikipediaに「非公開」とある)、こちらは御府内霊場の札所(第9番)なので参拝は可能で御朱印も拝受できます。(敷居はやや高いですが・・・。)
御府内霊場の御朱印の主尊格は釈迦牟尼佛ですが、黄金目不動明王の揮毫もあります。
■ 五大山 不動院 / 目黄不動尊
港区六本木3-15-4
高野山真言宗 御本尊:不動明王
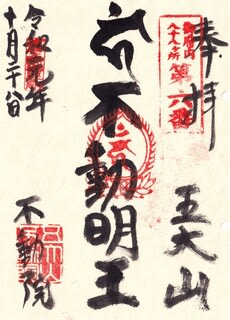
万治元年(1658年)に麹町平河町より当地へ移転したといい、「通称、麻布不動坂の一願不動さん、或は六軒町の目黄不動と呼ばれ、親しまれてきた。」という伝承があるようです。(→参考)
なお、もともとの目青不動尊と伝わる麻布谷町にあった勧行寺(ないし正善寺)に近いため、こちらとの関連を示唆する説もあるようです。
こちらも御府内霊場の札所(第6番)なので参拝可能で御朱印もいただけます。
御本尊、不動明王の御朱印です。
こちらは非常駐のようで通常は閉扉され、御朱印は兼務されている大安楽寺(中央区日本橋小伝馬町)での授与となりますが、タイミングが合えば御本尊前でお参りでき、御朱印も本堂内で拝受することができます。
なお、昭島市の眞覺寺も「目黄不動尊」を護持されていますが、こちらと「江戸五色不動」との関係は確認できておりません。
■ 築当山 眞覺寺 / 目黄不動尊
昭島市玉川町5-9-27
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
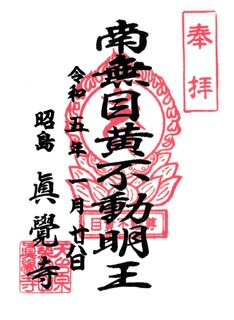
上記のように複数の目黄不動尊が存在することは、「江戸五色不動」の複雑な歴史を物語っています。
〔 江戸五色不動の宗派 〕
不動尊霊場としてはめずらしく、天台宗が多くなっています。
目白不動尊(金乗院)のみが真言宗豊山派で、あとはすべて天台宗寺院です。
大僧正天海の発案ということであれば、天台宗一択ですべて天台宗寺院の方が自然です。
とくに結界が絡むとなると、山王一実神道は避けて通れなくなるはずで、その点からも天台宗寺院で固める必要があったのでは。
実際、目黒不動尊は山王一実神道との関係を表明し、最近、参道に山王鳥居を建立しています。
一寺だけ真言宗寺院が入っていることについては、なにか特段の理由があったのかもしれません。
〔 江戸五色不動の歴史 〕
諸説あり錯綜していますが、手持ちの文献やWeb上で確認できた内容を列挙してみます。
・寛永年間(1624-1645年)、三代将軍家光公が大僧正天海の具申により江戸(王城)鎮護祈願のために、江戸の周囲に五色の不動尊を造立して安置。当初は四神相応の四不動を定め、のちに目黄が追加された。
五色とは陰陽五行説に由来するもので青(東/青龍)・白(西/白虎)・赤(南/朱雀)・黒(北/玄武)・黄(中央/皇帝)をあらわす。
・参考Webによると、寛保元年(1741年)著の小野高尚の『夏山雑談』には「江戸城鎮護のために不動明王像を、鎮護の四神にならい江戸城の四方に配置したのが目黒・目白・日赤・目青の四不動」との記載があるらしく、これが事実だとすると五色不動鎮護結界説が成立するが、多くの人はこれに疑義を呈している。(原典確認中)
というのは、この『夏山雑談』以外に「五色不動」にふれた江戸期の史料がほとんど見当たらないからです。
江戸時代には三大不動「目黒不動尊・目白不動尊・薬研掘不動尊」が広く知られていましたが、薬研掘不動尊は「五色不動」に入らず、色も振られていません。
お不動様の信仰篤かった江戸庶民のこととて、この時期に「五色不動」が成立していれば、当然『江戸名所図会』『東都歳時記』や『江戸砂子』に記載があるはずですが、見当たりません。(個別の不動尊寺院はかなりとりあげられている)
また、陰陽五行説の方位色と実際の寺院の方位が合わないことも疑義の論拠とされています。
文化五年(1808年)の「柳樽四十六篇」に、「五色には二色足らぬ不動の目」との川柳が残されています。
おそらく目青と目黄が「足りなかった」とみられますが、逆にみると文化五年の時点で「五色不動」が意識されていたことがみてとれます。
・八代将軍吉宗公が、享保年間(1716-1736年)に民力休養のための花見の場所の整備とともに5ヶ所(の不動尊)を選定されたという説。
・江戸に入る街道口の守護として置かれたという説。(=江戸六地蔵の縁起に通じる)
東海道/目黒不動尊(龍泉寺)、中山道/目赤不動尊(南谷寺)、川越街道/目白不動尊(新長谷寺)、甲州街道/目青不動尊(教学院)、日光街道(奥州街道)/目黄不動尊(永久寺)、水戸街道/目黄不動尊(最勝寺)。
・古来、それぞれの寺院の所在する場所で産した馬の毛色や目色からきているという説。
目黒の「目」が「駿馬」をあらわすという説から付会されたものかもしれません。
↑ のように多彩な説があることは、裏返すと江戸時代には「江戸五色不動」が確定していなかったことを示すものかもしれません。
こちらの記事では、『江戸砂子』『続江戸砂子』に記された不動霊場をまとめられています。現時点では筆者にて原典の該当箇所が確認できていないので、恐縮ですが孫引きさせていただきます。
( )は筆者の追記。札番は関東三十六不動霊場のもの。☆は筆者が御朱印拝受した寺院。
--------------------------------------------
五 不動霊場 来由前集にあり。
○目黒不動 慈覚作 めぐろ龍泉寺 (目黒、目黒不動尊、五色不動、第18番☆)
○目白不動 弘法作 めじろ長谷寺 (高田金乗院、目白不動尊、五色不動、第14番☆)
○目赤不動 作不知 駒込南谷寺 (駒込南谷寺、目赤不動尊、五色不動、第13番☆)
○砂尾不動 良弁作 はしば不動院 (砂尾山 不動院 橋場不動尊、第23番☆)
〔増〕逆流不動 作不知 立像五尺 湯嶋根生院護摩堂 (金剛賓山 根生院/豊島区高田☆)
〔増〕幸不動 慈覚の作 修験 宝玉院 神田かぢ町二丁目 (不詳)
○三日月不動 深川 心行寺 (雙修山 心行寺☆)
○波切不動 浅草寺町 大乗院 (五剣山 大乗院/台東区元浅草)
○飛不動 下谷 大音寺前正宝院 (龍光山 正寶院/台東区竜泉、第24番☆)
○大山不動 駒込 願行寺 (既成山 願行寺/文京区向丘☆)
○薬研堀不動 よこ山町 明王院 (薬研堀不動院(川崎大師別院)/中央区東日本橋、第21番☆)
〔増〕滝不動 日暮里道灌山より三丁ほど北の方、田端六あみだのひがし、二丁ほどに、一茂りの小山あり。御用やしきと云。此所に少しの滝あり、下に石仏の不動まします。 (不詳)
○は『江戸砂子』にも載っているもの、〔増〕は『続江戸砂子』での追加分である。
--------------------------------------------
上記によると、五色不動のうち目黒、目白、目赤の三不動は記載されていますが、目青、目黄は記載されていません。
また、江戸の不動尊信仰の要となった深川不動堂(成田山 東京別院)が記載されていないのは不思議な感じがします。
深川永代寺で催された成田山の不動明王の第1回目の「出開帳」は元禄十六年(1703年)、以降江戸江戸時代を通じて計12回行われた出開帳のうち11回は深川永代寺が会場となりました。
ただし、あくまでも「出開帳の会場」であったので、↑の『江戸砂子』には載っていないのかもしれません。(深川永代寺のそばに「深川不動堂」が置かれたのは、明治11年(1878年)です。)
なお、江戸時代には「(江戸)三大不動」が知られており、目黒不動尊、目白不動尊、薬研堀不動尊がこれに当たります。
ただし、三つの不動尊を巡拝するというよりは、ご縁日や願掛けに一寺ずつじっくりと参拝するという傾向が強かったのでは。
歌舞伎役者市川團十郎の影響もあり、江戸の庶民のあいだで成田詣りの人気が高かったこと、また、薬研堀には川崎大師の別院「薬研堀不動尊」、目黒には観光地としても知られた目黒不動尊があったことなどからも、「お不動さまはじっくりと願かけ」という意識が強まった可能性があります。
上記の『江戸砂子』の不動霊場には、昭和62年(1987年)に開創された関東三十六不動尊霊場の札所がいくつかみられます。
また、「深川不動堂(尊)」もこの霊場の札所で、江戸期から信仰を集めた不動尊も多くあるため、上記の☆印の寺院のほかに下記の関東三十六不動尊霊場の札所(都区内)もご紹介します。
■ 石神井不動尊(亀頂山 密乗院 三寶寺) 第11番、練馬区石神井台
■ 志村不動尊(寶勝山 蓮光寺 南蔵院) 第12番、板橋区蓮沼町
■ 中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺) 第15番、中野区中央
■ 等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院) 第17番、世田谷区等々力
■ 浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院) 第22番、台東区寿
■ 皿沼不動尊(皿沼山 永昌院) 第25番、足立区皿沼
■ 西新井大師不動明王(五智山 遍照院 總持寺) 第26番、足立区西新井
まずは江戸五色不動の6つの寺院についてご紹介していきます。
01.竹園山 最勝寺 教学院〔目青不動尊 / 江戸五色不動〕
世田谷区太子堂4-15-1(港区麻布谷町(現・六本木周辺)の勧行寺または正善寺から青山南町を経て移転)
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:江戸五色不動(目青不動尊)、関東三十六不動尊霊場第16番、大東京百観音霊場第54番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番、東京三十三所観世音霊場第10番
縁起によると、応長元年(1311年)江戸城内紅葉山に創建。
太田道灌の江戸城築城にともない麹町貝塚~赤坂三分坂と移り、慶長九年(1604年)には青山南町(百人町)に移転。開基は法印玄応大和尚。
百人町居住の同心の帰依を受けて閻魔堂(現在の不動堂)を建立し、「三合山」「青山のお閻魔さま」とも呼ばれて双盤念仏がさかんに行われたといいます。
元禄年間頃までは山王成琳寺(赤坂日枝神社別当)の末寺でしたが、貞享四年(1687年)頃に相州小田原城主・大久保加賀守忠朝の菩提寺となって隆盛。東叡山輪王寺の直末となりました。
明治41年(1909年)から3年を要して現在地に移転し、現在に至ります。
明和九年(1772年)刊の『江戸砂子』(国会図書館DC)にはつぎの記載があります。
「江戸名所図會、熊野権現社の次條に、心見観音、同北に隣る天台宗にして竹園山教學院と號す、本尊は聖徳太子の真作」
目青不動尊は、麻布谷町にあったという源三位頼政ゆかりの古刹、三合山 源理院 正善寺(随縁山 教解院 観行寺とも)の御本尊が明治15年(1882年)経学院に遷し奉られたもの。
慈覚大師円仁の御作と伝わり、天上界と地上界の間にたなびく青雲の色ゆかりの不動尊といわれ、「縁結びの不動尊」としてとくに女性の信仰が篤いとのことです。
江戸時代より五色不動(五眼不動)の一つに数えられ、東西南北中央の五方角と色(五色)を合わせたもので、将軍家光公の時代に成立したといわれています。


【写真 上(左)】 南の山門
【写真 下(右)】 東の山門
東急線「三軒茶屋」駅から徒歩数分。東急世田谷線からも見えるところです。
山門は世田谷線に面した南側と東側の二箇所あり、堂宇に近いのは東側です。
駅近ですが、山内は緑が多く名刹らしい落ち着きが感じられます。


【写真 上(左)】 門柱に「目青不動尊」
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 不動堂
東側山門から入って右側に不動堂。入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁に木鼻と海老虹梁を備え、正面格子戸で左右に大ぶりな花頭窓を拝しています。


【写真 上(左)】 不動堂(斜めから)
【写真 下(右)】 不動堂向拝-1


【写真 上(左)】 不動堂向拝-2
【写真 下(右)】 不動霊場札所板
右手向拝柱に「関東三十六不動霊場」の札所板。身舎上部には向かって右から、「閻王殿」「不動明王」「元三大師」の扁額が掲げられています。
寺宝として閻魔大王、脱衣婆があり、こちらは不動尊両脇侍仏です。
扁額、脇侍仏ともに「青山のお閻魔さま」の流れを伝えるものとみられます。
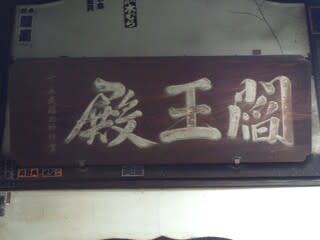

【写真 上(左)】 「閻王殿」の扁額
【写真 下(右)】 「不動明王」の扁額


【写真 上(左)】 「元三大師」の扁額
【写真 下(右)】 寺紋
御本尊の不動明王は秘仏でお厨子内に御座。御前立ちの青銅不動明王坐像も寺宝に定められています。
御前立ちのお不動様は、寛永十九年(1642年)の銘があり、丸いお顔で微笑みを湛えられ「縁結びのお不動さま」として、若い女性の信仰を集めてきたといいます。
恋愛成就の仏様はふつう愛染明王で、お不動さまがこの役を受けもたれる例はめずらしいかもしれません。
樹木に囲まれた参道正面に本堂。
入母屋造銅板葺流れ向拝で水引虹梁、向拝柱、正面桟唐戸、左右に花頭窓。
御本尊は恵心僧都作とされる上品上生阿弥陀如来坐像で、こちらも寺宝です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 納経所
聖徳太子の作と伝わる聖観世音菩薩は本堂に安置され、おそらくこちらが3つの観音霊場の札所本尊かと思われます。
江戸砂子温故名蹟誌 6巻5には「城琳寺末 心見観音、聖徳太子の作、名ある糸さくらあり」(国会図書館DC)とあり、目青不動尊を迎える前は心見観音の霊場として知られていたのかもしれません。
墓所には、小田原大久保家歴代の基、南画家、岡本秋暉の基、明治の書家、岡本碧巌の基などがあります。
御朱印は参道左の納経所にて快く授与いただけます。
目青不動明王、聖観世音菩薩の両尊の御朱印をいただけますが、御本尊・阿弥陀如来の御朱印は授与されていないとのことです。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
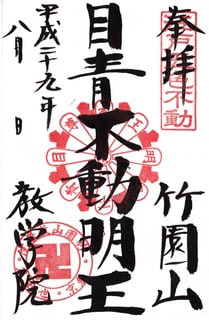
・御朱印尊格:目青不動明王 江戸五色不動尊印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/専用納経帳〕
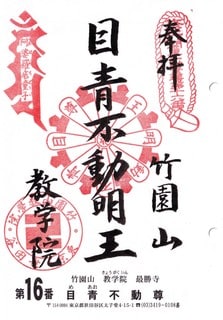
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 書置(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/御朱印帳〕
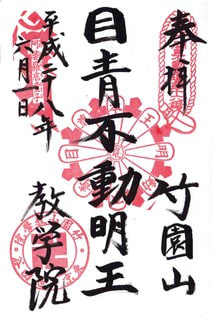
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 直書(筆書)
〔大東京百観音霊場第54番の御朱印〕
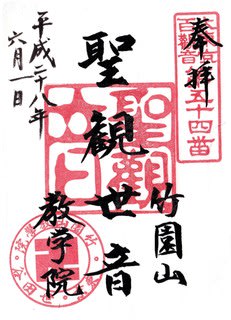
・御朱印尊格:聖観世音 大東京百観音霊場第54番印判 書置(筆書)
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番の御朱印〕
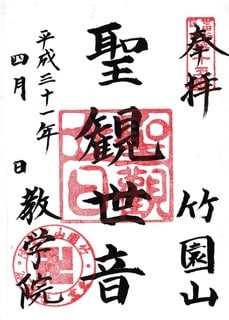
・御朱印尊格:聖観世音 世田谷区内第15番印判 直書(筆書)
こちらへつづく
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 6.目黄不動尊(最勝寺)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1からのつづきです。
↓の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
3.旧 深谷市エリア-2
■ 蓮沼山 地蔵院 惣持寺
公式Web
深谷市蓮沼463
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番、深谷七福神(弁財天/オバナの寺)
・境内の縁起碑に、「當寺墓地の五輪塔(元禄八年(1696年)建立)「當寺廿傳慶基之表」に「夫武蔵國幡羅郡蓮沼山惣持寺者行基菩薩之草創年数978宗澄和尚之中興云々略」と刻記されていることから、草創は奈良時代初期の養老二年(718年)行基菩薩によって創建され、後弘安年間(1278-1288年)顕盛(勅号宗澄)により再興された、深谷市内最古の名刹である。」とあります。
・地蔵堂の御本尊は行基作と伝わりましたが文化四年(1807年)の火災で消失、現在の地蔵尊は”露天の雨乞い地蔵”として村人の信仰を集めているそうです。
・深谷七福神(弁財天)と幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所で、尊格揮毫は「弁財天」、主印は金剛界大日如来の種子「バン」の御寶印と弁財天の持物「琵琶」の印、「新四国第四十二番」の札所印があり、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番と深谷七福神(弁財天)を兼ねたような内容の御朱印となっています。
・新型コロナ禍中は御朱印不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番/深谷七福神(弁財天) 大日如来/弁財天

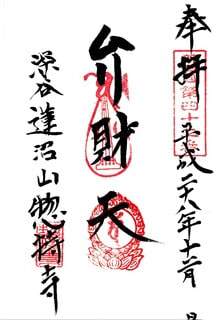
■ 瑠璃光山 浄光寺 摩利支天堂
深谷市江原84−1
高野山真言宗
御本尊:摩利支天尊、弘法大師
札所:-
・武蔵七党・猪俣党の流れの荏原氏の館跡とも伝わります。
・摩利支天尊は武神的な性格ももたれるので、荏原氏が信仰していたのかもしれません。
・通常無住。深谷市江原の浄光寺の管理(境外仏堂?)のようですが、浄光寺も無住らしく、御朱印は毎月1月と15日の祈祷日のみにいただけるようです。
・摩利支天の御朱印は授与例が少なく、その点からも稀少な御朱印です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 摩利支天尊


■ 寛平山 泉光寺
深谷市上敷免473
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀三尊
司別当:諏訪社(旧上鋪免村鎮守)
札所:深谷七福神(恵比寿天/オミナエシの寺)
・石碑によると、平安時代の寛平九年(897年)、良忍上人による開基。『新編武蔵風土記稿』には寛平山 稲荷坊 来迎院と号していたとあります。
・弘法大師とのゆかりがふかく、別尊の薬師如来はお大師さまのご開眼と伝わり、境内には三鈷の松があります。
・市指定文化財の「紙本着色愛宕大権現像」を所蔵されており、以前は愛宕信仰が入っていたのかもしれません。
・立派な鐘楼門、端正な入母屋造流れ向拝の本堂には御本尊の阿弥陀三尊が御座。本堂向かって右手の堂宇には恵比寿天が御座されています。
・深谷七福神の恵比寿天で女郎花(オミナエシ)の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 阿弥陀三尊


2.深谷七福神 恵比寿天


■ 普光山 得蔵院 圓能寺
深谷市高畑379
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:-
・開かれたお寺を目指し、定期的にイベントなどが催されている天台宗のお寺さまです。
・御朱印も快く授与いただけました。
・寄棟造の本堂。本瓦葺で大棟には鴟尾を置く格調高いつくりです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀如来


■ 覚樹山 慶福寺
深谷市矢島744
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:-
・正保二年(1645年)開創の曹洞宗寺院です。
・札所ではないですが、快く御朱印を授与いただけました。
・入母屋造銅板葺流れ向拝、屋根の傾斜が急でどっしりとした意匠の本堂です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼仏


■ 瑠璃山 正伝院
深谷市高島161
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:深谷七福神(毘沙門天/クズの寺)
・弘仁年間(810-824年)、坂上田村麻呂の奥州征伐の際、小野岑守とその子小野篁((おののたかむら)が随行。この地にて篁が薬師如来の尊像を彫刻し、本尊として安置して開基と伝わる古刹です。
・寺宝の「釈迦涅槃図」(市指定文化財)は、幕末の文人、伊丹渓斎(いたみけいさい)の筆によるものです。
・深谷七福神の毘沙門天の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 毘沙門天


■ 長勢山 義光院 吉祥寺
公式Web
深谷市中瀬410
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:-
・鎌倉時代、京・東福寺開山の聖一国師 圓爾辨圓が、上州世良田の長楽寺に滞在されていたときに開いた寺院と伝わります。
・新田氏ゆかりの河田但馬守義光公は、足利氏従属を嫌って当地で帰農し、その子?の 義賢公が堂宇を建立。江戸時代は上州長楽寺の末寺として栄えたそうです。
・山内には数多くの尊格が奉安されています。
・とても親切なご住職で、本堂内を丁寧にご説明いただきました。
・御朱印は数種あり、書置もあって御朱印授与に積極的なようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀如来


2.聖観世音菩薩の御朱印


3.ふれ愛観音の御朱印


■ 瑠璃光山 遍照院 妙光寺
深谷市下手計988-1
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:-
・承應二年(1653年)、福島但馬優婆塞 永照比丘尼の開基、高野山から栄忠僧正を招聘して創立。
・入母屋造桟瓦葺、向拝の唐破風が大がかりで迫力があります。
・渋沢栄一翁の従兄弟、尾高惇忠は当寺で学び、また惇忠の菩提寺のようで、御朱印にもその旨の揮毫があります。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 薬師如来


■ 諏訪神社
埼玉県深谷市血洗島117
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:
授与所:拝殿前
・渋沢栄一翁の郷里の鎮守社です。詳細は、→こちら(血洗島 諏訪神社の御朱印)をご覧ください。
〔拝受御朱印〕

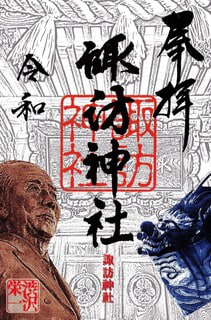
御朱印揮毫:諏訪神社 印刷
■ 能満山 定禅院 能護寺(あじさい寺)
熊谷市Web
熊谷市永井太田1141
高野山真言宗
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第25番(埼玉第13番)
・天平十五年(743年)に国家安穏・万民豊楽と五穀豊穣祈願のため行基上人が開山し、後に弘法大師空海が再建され真言密教の道場として整えられたと伝わります。
・「妻沼のあじさい寺」として知られ、毎年6月には多くの参詣者を迎えます。
・現本堂は文化十一年(1814年)の再建で、内陣に大日如来、外陣に阿弥陀如来を安置した堂内の格天井(十六羅漢図)には、金井烏洲・岩崎榮益・樋口春翠などの彩色の花鳥獣が描かれています。
・虚空蔵堂には虚空蔵菩薩が祀られ、男女13歳厄除け祈願(十三参り)の寺として信仰を集めています。
・鐘楼の鐘は、元禄十四年(1701年)、諸八郎兵衛藤原正綱による鋳造で、乳の間に百字真言の梵字が鋳込まれているもの。市の文化財に指定されています。
・メジャー霊場「東国花の寺百ヶ寺霊場」の札所で、御朱印は庫裡にて拝受。
・御朱印尊格は「十三参り」の虚空蔵尊となっています。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 虚空蔵菩薩


2.東国花の寺百ヶ寺霊場第25番(埼玉第13番)(規定) 虚空蔵菩薩

4.旧 岡部町エリア
■ 教王山 佛母院 弘光寺
深谷市針ヶ谷1324
真言宗豊山派
御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
司元別当:八幡大神社(深谷市針ヶ谷)
札所:-
・天平十七年(745年)、空阿の開基と伝わる古刹で、法院祐尊(応安三年(1370年)寂)を中興開山とします。
・法院祐尊が中興の際、鉢形城主北条氏邦に宛てた書状は貴重な中世文書とされ、深谷市の指定文化財となっています。
・は徳川家光公より三十石の朱印地を得て寺勢興隆し、末寺・配下寺院は75を数えたとされます。
・これほどの名刹で霊場札所となっていないのは不思議な感じもしますが、御本尊・不動明王の御朱印を授与されています。庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 不動明王


■ 八幡大神社
深谷市針ヶ谷258-1
御祭神:品陀和気命、比賣神、神功皇后
旧社格:村社、針ヶ谷鎮守
元別当:教王山 佛母院 弘光寺(深谷市針ヶ谷)
授与所:境内社務所
・社伝によると、天平十七年(745年)で山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請して創建。源頼朝公が伊豆に配流された折、源家再興のため当社を祈願所として定めたと伝わります。
・武蔵風土記等には、「山城国男山八幡宮を移し祀る 文明十一年建営修理」とあります。
・ことに戦時中は武の神として信仰を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡大神社 直書(筆書)


※ 針ヶ谷あたりから少しく足を伸ばすと、近年、人気上昇中の日本神社に参拝できます。
■ 日本神社の御朱印
■ 玉鳳山 千手寺 源勝院
深谷市岡部786
曹洞宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所:-
・岡部藩主安部家の菩提寺。
・天正十八年(1590年)、徳川家康公の関東人国時に安部信勝に岡部が与えられ、信勝は人見の昌福寺八世賢達利尚を招き源勝院の開基としました。
・安部氏は信濃の海野姓の流れとされ、今川家臣から徳川に転じて家臣となり、三河国半原にも所領がありました。譜代大名で幕末期の石高は2万2250石。
・藩主の菩提寺だけあって、端正な本瓦葺、水引虹梁の木鼻など彫刻類も精緻なものです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 千手観世音菩薩


【 BGM 】
■ 夏影~Airness~ - 茶太ver
■ 春風 - Rihwa(カバー)
■ 夢暦 - 川江美奈子
↓の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
3.旧 深谷市エリア-2
■ 蓮沼山 地蔵院 惣持寺
公式Web
深谷市蓮沼463
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番、深谷七福神(弁財天/オバナの寺)
・境内の縁起碑に、「當寺墓地の五輪塔(元禄八年(1696年)建立)「當寺廿傳慶基之表」に「夫武蔵國幡羅郡蓮沼山惣持寺者行基菩薩之草創年数978宗澄和尚之中興云々略」と刻記されていることから、草創は奈良時代初期の養老二年(718年)行基菩薩によって創建され、後弘安年間(1278-1288年)顕盛(勅号宗澄)により再興された、深谷市内最古の名刹である。」とあります。
・地蔵堂の御本尊は行基作と伝わりましたが文化四年(1807年)の火災で消失、現在の地蔵尊は”露天の雨乞い地蔵”として村人の信仰を集めているそうです。
・深谷七福神(弁財天)と幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所で、尊格揮毫は「弁財天」、主印は金剛界大日如来の種子「バン」の御寶印と弁財天の持物「琵琶」の印、「新四国第四十二番」の札所印があり、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番と深谷七福神(弁財天)を兼ねたような内容の御朱印となっています。
・新型コロナ禍中は御朱印不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番/深谷七福神(弁財天) 大日如来/弁財天

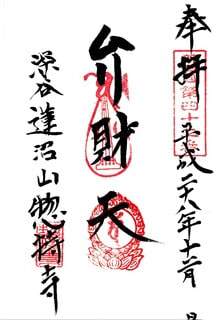
■ 瑠璃光山 浄光寺 摩利支天堂
深谷市江原84−1
高野山真言宗
御本尊:摩利支天尊、弘法大師
札所:-
・武蔵七党・猪俣党の流れの荏原氏の館跡とも伝わります。
・摩利支天尊は武神的な性格ももたれるので、荏原氏が信仰していたのかもしれません。
・通常無住。深谷市江原の浄光寺の管理(境外仏堂?)のようですが、浄光寺も無住らしく、御朱印は毎月1月と15日の祈祷日のみにいただけるようです。
・摩利支天の御朱印は授与例が少なく、その点からも稀少な御朱印です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 摩利支天尊


■ 寛平山 泉光寺
深谷市上敷免473
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀三尊
司別当:諏訪社(旧上鋪免村鎮守)
札所:深谷七福神(恵比寿天/オミナエシの寺)
・石碑によると、平安時代の寛平九年(897年)、良忍上人による開基。『新編武蔵風土記稿』には寛平山 稲荷坊 来迎院と号していたとあります。
・弘法大師とのゆかりがふかく、別尊の薬師如来はお大師さまのご開眼と伝わり、境内には三鈷の松があります。
・市指定文化財の「紙本着色愛宕大権現像」を所蔵されており、以前は愛宕信仰が入っていたのかもしれません。
・立派な鐘楼門、端正な入母屋造流れ向拝の本堂には御本尊の阿弥陀三尊が御座。本堂向かって右手の堂宇には恵比寿天が御座されています。
・深谷七福神の恵比寿天で女郎花(オミナエシ)の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 阿弥陀三尊


2.深谷七福神 恵比寿天


■ 普光山 得蔵院 圓能寺
深谷市高畑379
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:-
・開かれたお寺を目指し、定期的にイベントなどが催されている天台宗のお寺さまです。
・御朱印も快く授与いただけました。
・寄棟造の本堂。本瓦葺で大棟には鴟尾を置く格調高いつくりです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀如来


■ 覚樹山 慶福寺
深谷市矢島744
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:-
・正保二年(1645年)開創の曹洞宗寺院です。
・札所ではないですが、快く御朱印を授与いただけました。
・入母屋造銅板葺流れ向拝、屋根の傾斜が急でどっしりとした意匠の本堂です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼仏


■ 瑠璃山 正伝院
深谷市高島161
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:深谷七福神(毘沙門天/クズの寺)
・弘仁年間(810-824年)、坂上田村麻呂の奥州征伐の際、小野岑守とその子小野篁((おののたかむら)が随行。この地にて篁が薬師如来の尊像を彫刻し、本尊として安置して開基と伝わる古刹です。
・寺宝の「釈迦涅槃図」(市指定文化財)は、幕末の文人、伊丹渓斎(いたみけいさい)の筆によるものです。
・深谷七福神の毘沙門天の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 毘沙門天


■ 長勢山 義光院 吉祥寺
公式Web
深谷市中瀬410
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:-
・鎌倉時代、京・東福寺開山の聖一国師 圓爾辨圓が、上州世良田の長楽寺に滞在されていたときに開いた寺院と伝わります。
・新田氏ゆかりの河田但馬守義光公は、足利氏従属を嫌って当地で帰農し、その子?の 義賢公が堂宇を建立。江戸時代は上州長楽寺の末寺として栄えたそうです。
・山内には数多くの尊格が奉安されています。
・とても親切なご住職で、本堂内を丁寧にご説明いただきました。
・御朱印は数種あり、書置もあって御朱印授与に積極的なようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀如来


2.聖観世音菩薩の御朱印


3.ふれ愛観音の御朱印


■ 瑠璃光山 遍照院 妙光寺
深谷市下手計988-1
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:-
・承應二年(1653年)、福島但馬優婆塞 永照比丘尼の開基、高野山から栄忠僧正を招聘して創立。
・入母屋造桟瓦葺、向拝の唐破風が大がかりで迫力があります。
・渋沢栄一翁の従兄弟、尾高惇忠は当寺で学び、また惇忠の菩提寺のようで、御朱印にもその旨の揮毫があります。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 薬師如来


■ 諏訪神社
埼玉県深谷市血洗島117
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:
授与所:拝殿前
・渋沢栄一翁の郷里の鎮守社です。詳細は、→こちら(血洗島 諏訪神社の御朱印)をご覧ください。
〔拝受御朱印〕

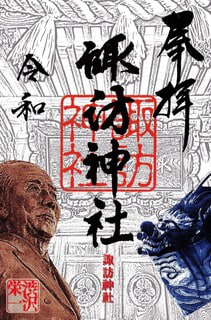
御朱印揮毫:諏訪神社 印刷
■ 能満山 定禅院 能護寺(あじさい寺)
熊谷市Web
熊谷市永井太田1141
高野山真言宗
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第25番(埼玉第13番)
・天平十五年(743年)に国家安穏・万民豊楽と五穀豊穣祈願のため行基上人が開山し、後に弘法大師空海が再建され真言密教の道場として整えられたと伝わります。
・「妻沼のあじさい寺」として知られ、毎年6月には多くの参詣者を迎えます。
・現本堂は文化十一年(1814年)の再建で、内陣に大日如来、外陣に阿弥陀如来を安置した堂内の格天井(十六羅漢図)には、金井烏洲・岩崎榮益・樋口春翠などの彩色の花鳥獣が描かれています。
・虚空蔵堂には虚空蔵菩薩が祀られ、男女13歳厄除け祈願(十三参り)の寺として信仰を集めています。
・鐘楼の鐘は、元禄十四年(1701年)、諸八郎兵衛藤原正綱による鋳造で、乳の間に百字真言の梵字が鋳込まれているもの。市の文化財に指定されています。
・メジャー霊場「東国花の寺百ヶ寺霊場」の札所で、御朱印は庫裡にて拝受。
・御朱印尊格は「十三参り」の虚空蔵尊となっています。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 虚空蔵菩薩


2.東国花の寺百ヶ寺霊場第25番(埼玉第13番)(規定) 虚空蔵菩薩

4.旧 岡部町エリア
■ 教王山 佛母院 弘光寺
深谷市針ヶ谷1324
真言宗豊山派
御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
司元別当:八幡大神社(深谷市針ヶ谷)
札所:-
・天平十七年(745年)、空阿の開基と伝わる古刹で、法院祐尊(応安三年(1370年)寂)を中興開山とします。
・法院祐尊が中興の際、鉢形城主北条氏邦に宛てた書状は貴重な中世文書とされ、深谷市の指定文化財となっています。
・は徳川家光公より三十石の朱印地を得て寺勢興隆し、末寺・配下寺院は75を数えたとされます。
・これほどの名刹で霊場札所となっていないのは不思議な感じもしますが、御本尊・不動明王の御朱印を授与されています。庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 不動明王


■ 八幡大神社
深谷市針ヶ谷258-1
御祭神:品陀和気命、比賣神、神功皇后
旧社格:村社、針ヶ谷鎮守
元別当:教王山 佛母院 弘光寺(深谷市針ヶ谷)
授与所:境内社務所
・社伝によると、天平十七年(745年)で山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請して創建。源頼朝公が伊豆に配流された折、源家再興のため当社を祈願所として定めたと伝わります。
・武蔵風土記等には、「山城国男山八幡宮を移し祀る 文明十一年建営修理」とあります。
・ことに戦時中は武の神として信仰を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡大神社 直書(筆書)


※ 針ヶ谷あたりから少しく足を伸ばすと、近年、人気上昇中の日本神社に参拝できます。
■ 日本神社の御朱印
■ 玉鳳山 千手寺 源勝院
深谷市岡部786
曹洞宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所:-
・岡部藩主安部家の菩提寺。
・天正十八年(1590年)、徳川家康公の関東人国時に安部信勝に岡部が与えられ、信勝は人見の昌福寺八世賢達利尚を招き源勝院の開基としました。
・安部氏は信濃の海野姓の流れとされ、今川家臣から徳川に転じて家臣となり、三河国半原にも所領がありました。譜代大名で幕末期の石高は2万2250石。
・藩主の菩提寺だけあって、端正な本瓦葺、水引虹梁の木鼻など彫刻類も精緻なものです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 千手観世音菩薩


【 BGM 】
■ 夏影~Airness~ - 茶太ver
■ 春風 - Rihwa(カバー)
■ 夢暦 - 川江美奈子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPします。
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
■ 深谷市の御朱印-2へつづきます。
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
1.旧 川本町エリア
■ 吉祥山 應正寺
深谷市田中608-1
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第30番
・由緒は不詳ですが、入母屋造の立派な本堂と、二層の優れた意匠の観音堂があり、忍秩父三十四観音霊場第30番の札所はこちらの観音堂となっています。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。御本尊の御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

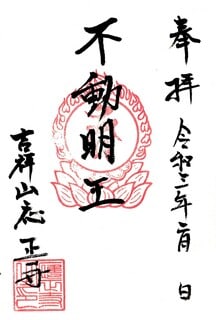
2.忍秩父三十四観音霊場第30番 十一面千手観世音菩薩

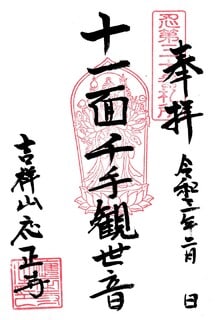
■ 根本山 光明院 正福寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市瀬山141
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東八十八箇所第84番、関東九十一薬師霊場 第35番、武州路十二支霊場 酉(不動明王) ※関東九十一薬師霊場第35番は境外の薬師堂
・永禄年間(1558-1570年)開基、慶長年間(1596-1604年)、重盛法印による開創と伝わる古刹。御本尊の阿弥陀如来は二尺四寸の木彫坐像で、安政二年(1855年)の作と伝わります。
・武州路十二支霊場の札所本尊、不動明王は、板木の記録によると「秀海」という行者が出羽三山へ三十三度尊像を背負って行き来され、霊験あらたかなお不動様として広く信仰され講も組織されたとのこと。
・関東九十一薬師霊場の札所本尊、薬師如来は東側に約600m離れた国道140号パイパス沿いにある境外仏堂の薬師堂(別名:踏鞴堂)に御座。一尺三寸木彫坐像の薬師如来は養老三年(717年)春日仏師一夜作と伝わり、現在の尊像は宝永七年(1710年)造顕とのこと。魔除、厄除、眼病除のお薬師様として広く信仰を集めているそうです。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。3つのメジャー霊場の札所だけに手慣れたご対応です。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第84番 阿弥陀如来

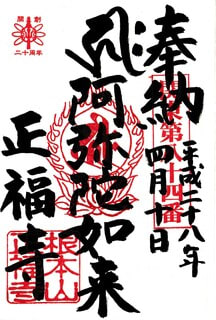
2.武州路十二支霊場(酉) 不動明王


3.関東九十一薬師霊場第35番 薬師如来 〔境外仏堂〕


2.旧 花園町エリア
■ 荒澤山 寿楽院
深谷市荒川983
高野山真言宗
御本尊:不動明王
司元別当:天神社(荒川地内)
・由緒は不詳だが、『風土記稿』には「天神社 寿楽院持」とあります。予想以上に広い境内で、道をはさんで立派な聖天宮が御座します。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。ご住職ご不在時は書置対応となる模様。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

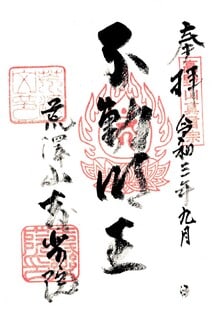
■ 光福山 医王院 長善寺
公式Web
深谷市小前田1452
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所:関東八十八箇所第85番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番
・鉢形城主北条氏邦の三男「光福丸」の菩提寺として知られる古刹で、2つのメジャー霊場の札所として参拝者を集めます。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第85番 大日如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番 聖観世音菩薩

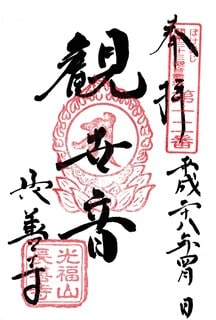
■ (武蔵野)八幡神社
深谷市武蔵野1862
御祭神:誉田別命
旧社格:旧武蔵野村中郷地区鎮守
元別当:常光寺(武蔵野)
授与所:足髙神社(足髙神社社務所に案内あり)
・鎌倉街道(県道小前田・児玉線)沿いに御鎮座の八幡神社。境内社、八坂社の御輿渡御は”暴れ御輿”として知られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

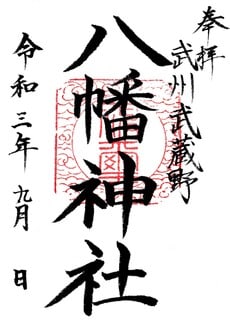
■ 十二社神社
深谷市武蔵野277-3
御祭神:天神七代地神五代の十二柱
旧社格:旧武蔵野村上郷地区鎮守
元別当:寿宝院
授与所:十二社神社(足髙神社社務所に案内あり)
・日本武尊が東征の折、当地にて兵馬・食糧の無事を祈るために創建と伝わります。
・昭和24年、新たな境内を設け旧本殿を移築して御遷座。新しい境内地ながら山林に囲まれ厳かな境内です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:十二社神社 書置(筆書)


■ 足髙神社
深谷市武蔵野3283
御祭神:大物主之大神
旧社格:(氏子区域:旧武蔵野村下郷地区(旧猿喰土村))
元別当:地内観音寺→橋本家→高野家
授与所:境内社務所に案内あり
・既に室町末期には鉢形城主北条氏邦により、領内鬼門鎮護として奉祀されていたとされ、祭礼時、氏邦が神饌を奉るために使った膳が足高であったため、現社号になったと伝わります。
・通常は非駐在のようですが、社務所に掲出の連絡先にTELすると書置の御朱印をお持ちいただけます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:足髙神社 書置(筆書)

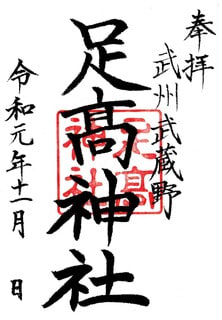
3.旧 深谷市エリア-1
■ 大谷山 地蔵院 宝積寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市大谷114
真言宗豊山派
御本尊:五智如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番、武州路十二支霊場 戌(阿弥陀如来)
・応永年間(1394-1428年)、地蔵菩薩を御本尊として盛谷山地蔵院宝錫寺と号し源照法印が開創。天正十年(1582年)、住職重任和尚が伽藍を整備され、五智如来を奉安されて、大谷山宝積寺と改称して中興と伝わる古刹。
・五智如来とは、大日如来が備えられる5つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智)を象徴する金剛界の五如来(いわゆる金剛界五仏)。
中尊(中央)は法界体性智の大日如来。東方は大円鏡智の阿しゅく如来ないし薬師如来、南方は平等性智の宝生如来、西方は妙観察智の阿弥陀如来、北方は成所作智の不空成就如来でそれぞれ象徴されます。(各尊格は宗派等により異なるようです。)
・関東三十三観音と武州路十二支霊場のふたつの現役霊場の札所を務められ、貴重な五智如来の御朱印も授与いただけます。御朱印は原則書き置きのようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 五智如来

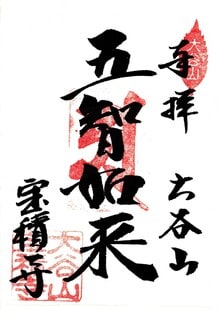
2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番 光明観世音菩薩


3.武州路十二支霊場(戌) 阿弥陀如来

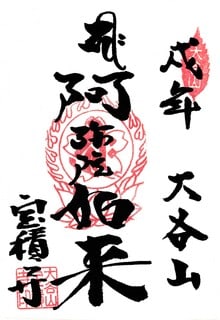
■ 境井山 寶泉寺
深谷市境220-1
曹洞宗
御本尊:
札所:深谷七福神(福禄寿)
・深谷七福神の一寺で福禄寿・キキョウの寺。
・慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いで手柄を立てた旗本吉田与右衛門政景氏は当地境および花園町永田に知行を拝領。人見福昌寺第九世実叟大存大和尚を開山に仰いで当山を建立開基と寺伝にあります。
・深谷七福神の福禄寿は、本堂手前左手に御座。
・七福神の御朱印は本堂内にて直書いただけましたが、御本尊の御朱印は授与されていないそうです。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神(福禄寿)


※御本尊の御朱印は不授与
■ 武蔵國八海山神社
深谷市折之口73
御祭神:大己貴命、國常立尊、少彦名命
旧社格:
元別当:
授与所:境内社務所
・比較的新しい神社で、御朱印も快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八海山神社 直書(筆書)

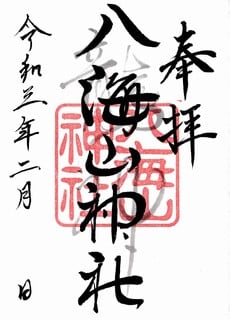
■ 泰国山 人見院 一乗寺
深谷市人見1621-2
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:深谷七福神(布袋尊)
・深谷七福神の一寺で布袋尊・ナデシコの寺。
・正応二年(1289年)、人見四郎泰国による開基、一遍上人の開山とされ、鎌倉時代にこの地に勢力を張った武蔵野七党猪俣党の一族、人見氏の菩提寺です。
・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀三尊(六字御名号)


2.深谷七福神 布袋尊

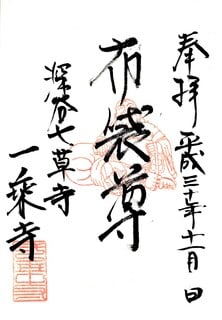
■ 人見山 昌福寺
深谷市人見1391-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
司元別当: 浅間神社(深谷市人見)
札所:
・延文二年(1357年)、深谷城初代城主として山内上杉家の上杉房憲が深谷に入ったのち、父祖の菩提を弔うため仙元山の麓に開基と伝わる曹洞宗の古刹。
・上杉房憲の墓所としても知られています。
・ご住職はお留守でしたが、寺庭さまから書置の御朱印を授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛

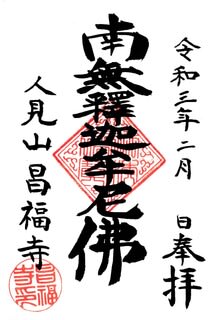
■ 浅間神社
深谷市人見1404
御祭神:木花咲耶姫命
旧社格:郷社
元別当: 人見山 昌福寺(熊谷市人見)
授与所:楡山神社宮司様宅
・標高98mの仙元山の山頂に鎮座する歴史ある浅間神社で、源頼朝が富士の巻狩りの際、その奉賽のために富士本宮から分祀した関八州八社の一社として伝わります。
・また、延文二年(1357年)、深谷城初代城主上杉房憲が昌福寺を開基した折、裏山の仙元山に深谷に入ったのち仙元大菩薩を勧請、後に村内富士講社が富士山本宮より勧請して合祀し、浅間神社と改めたという説もあります。
・深谷城主上杉家、江戸時代の領主・岡田家の篤い尊崇を受けたとされます。
・昭和五年(1930年)、地内の村社・無格社六社を合祀し郷社に列格、戦前には安産の神様として講が組織され、多くの参詣者を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

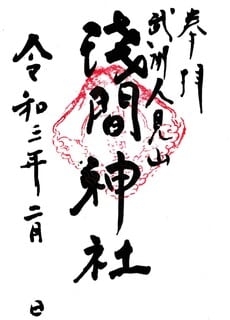
■ 上野台八幡神社
深谷市上野台3168
御祭神:品陀和気命
旧社格:郷社、氏子区域:上野台
元別当:如日山 蓮華院 光厳寺(深谷市上柴町)
授与所:境内
・天文十九年(1550年)、深谷城主上杉氏の家臣、岡谷加賀守清英が、崇敬篤い山城国石清水八幡宮を萱場村に勧請して創祀と伝わります。
・正徳年間(1711-1716年)、時の領主大久保忠義は、村役の嘆願により当地を寄進し萱場村からの御遷座をなしたとされます。
・上野台は、鼠、大台、小台、上宿、中宿、下宿、桜ヶ丘一、同二、泉台の九地区からなり、氏子区域はこの九地区で、多くの境内社はこの氏子区域内からの御遷座とのことです。
・「青天を衝け」にちなんだ御朱印が授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

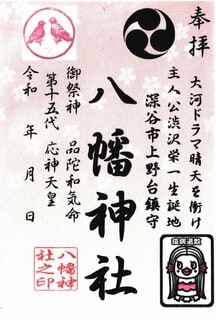


■ (上柴町)諏訪神社
深谷市上柴町東1-18
御祭神:建御名方命、美穂須須美命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、旧大字柴崎地区鎮守
元別当:月笑院
授与所:楡山神社宮司様宅
・文禄元年(1592年)頃、旧柴崎地区の開発者である柴崎淡路守(深谷城主上杉氏の家臣)の一族が氏神として祀ったことが創祀と伝わる柴崎地区の鎮守社。
・境内に御座す双体道祖神は、県内ではめずらしいものとされています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:諏訪神社 直書(筆書)

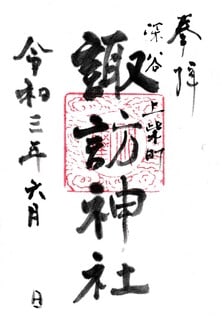
■ 大乗山 正法寺
公式Web
深谷市上柴町東2-2-2
日蓮宗
御本尊:
札所:
・このエリアでは数少ない日蓮宗寺院で、房総・勝浦の松部の地に妙潮寺の末寺として創建、その後、日蓮宗管長、久保田日亀大僧正のお力添えにより深谷に移転されました。
〔拝受御朱印〕
1.御首題

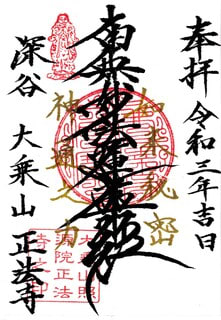
■ (西島)瀧宮神社
公式Web
深谷市西島5-6-1
御祭神:天照大神、豊受大神、彦火火出見命
旧社格:深谷城裏鬼門守護神、旧西島村(内横町仲町)鎮守
元別当:瀧宮山 歓喜院 正覚寺(深谷市深谷町)
授与所:境内社務所
・社伝によると、この地に湧き出る湧水を神として祀り「瀧の宮大明神」と号したのが創祀といいます。
・康正二年(1456年)、上杉氏により深谷城が築かれると、西南に位置する当社を坤門(裏鬼門)の守護神として崇敬し、領国安寧を祈願しました。
・昭和27年(1952年)には深谷宿の守り神・市神様として住民の尊崇篤かった「三社天王」を深谷八坂神社として境内に御遷座。例祭の御輿渡御は「深谷のぎおん」として広く知られています。
・深谷を代表する神社で、御朱印はおおむね社務所にていただけるようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:瀧宮神社 直書(筆書)

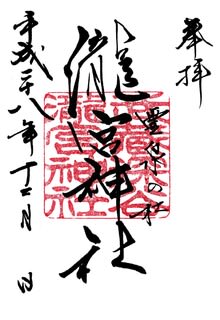
・当社は深谷駅南口のすぐそばに鎮座します。深谷駅の駅舎は、大正時代に竣工の東京駅・丸の内口駅舎が深谷の日本煉瓦製造の煉瓦を使用したことに因み、赤レンガ造をモチーフとしたデザインとなっており、深谷市内のみどころのひとつです。

■ 深谷山 永明寺 高台院
深谷市田谷308
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
・上杉氏の家人、高橋永明が草創。永禄四年(1561年)、深谷城三代目城主上杉憲賢の菩提を弔うため、室の高泰姫によって再興されたと伝わる古刹。
・所蔵の「北亭為直画朱描鎮西八郎為朝像」は市の文化財に指定されています。
・札所ではありませんが、ご住職ご在院時には御朱印を授与いただけるようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

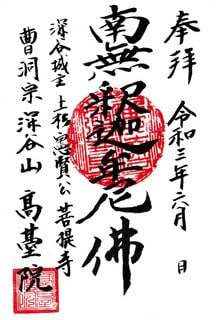
■ 永明稲荷神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市田谷308
御祭神:倉稲魂命、菅原道真公
旧社格:深谷城の戌亥の守護神、田谷地区鎮守
元別当:深谷山 高台院(高泰院) 永明寺(深谷市田谷)
授与所:楡山神社宮司様宅
・康正二年(1456年)、深谷城主上杉氏五代房憲(ないし家臣高橋永明)が築城時に、城の戌亥の守護として創祀と伝わります。
・上杉氏が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、一仏とは瑠璃光寺の寅薬師、三社とは末広稲荷(稲荷町)・永明稲荷・智方明神(本住町)をさすようです。
・明治45年(1912年)、稲荷町の稲荷神社に合祀されたものの社殿は残り、田谷地区の鎮守として独自に祭を催していることから合祀は書類上のものとされています。
・高台院所蔵の「狐開帳図絵馬(きつねかいちょうずえま)」(市指定文化財)は、もともとは永明稲荷神社に奉納されていたものです。
・高台院の奥ふかく、別当というより高台院の地主神的な位置にご鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:永明稲荷神社 直書(筆書)

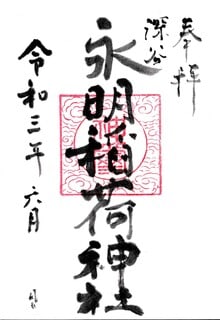
■ 延楽山 福壽院 金胎寺
深谷市本住町9-76
新義真言宗
御本尊:胎蔵界大日如来
司元別当:城内八幡宮・天満宮・管領稲荷社
・慶長九年(1604年)以前に、深谷城主上杉家の祈願寺として法印權大僧都日胤により開基されたという名刹。
・当時の深谷上杉家氏は湯殿山の信仰篤く、御本尊は湯殿山御分身の大日如来であったと伝わります。元禄十一年(1698年)、法印權大僧都快傳による中興開山の折に現在の御本尊大日如来を再鋳安置。
・別尊として奉安される不動明王は、明治22年(1889年)先師秋本一庵法印が下総国成田山より御分身を勧請され、深谷成田山とも称されます。
・札所ではありませんが名刹で、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 大日如来

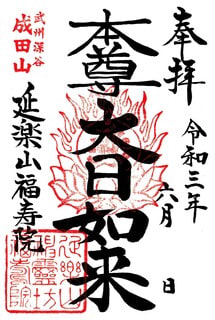
■ (稲荷町)稲荷神社(末広稲荷神社)
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市稲荷町3-2-58
御祭神:倉稲魂命
旧社格:村社、深谷城鬼門鎮護、旧末広村鎮守
元別当:東源寺・宝珠院
授与所:楡山神社宮司様宅
・社伝によると、上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、康正年間(1455-1456年)の城の鬼門守護として創祀とされます。
・「一仏三社」については康応年間(1389-1390)、深谷庁鼻和(こばなわ)に館を構えた上杉憲英が館の鎮護のために勧請という説もみられます。深谷城下の発展に伴い、稲荷町の鎮守として住民から厚く尊崇され今に至ります。
・維新後、無格社であった当社は田谷の稲荷神社(永明稲荷)を合祀し村社に列しましたが、この合祀は書類上のものとみられているようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:稲荷神社 直書(筆書)

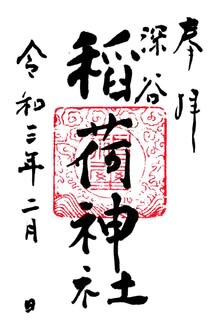
■ 伊勢之宮神社
深谷市西大沼300
御祭神:天照大神、豊受大神
旧社格:- 氏子区域:東大沼、西大沼、栄町、錦町の四か町
元別当:西福院
授与所:(西島)瀧宮神社社務所
・創建は明らかでありませんが、『風土記稿』には「伊勢内宮 村民持、伊勢外宮 西福院持」とあることからかつては二社で、明治初期に一社になったとみられています。
・『埼玉の神社』によると、当地の東部に「田谷」という地があり、これは「旅尾」(御師がお祓大麻を旦那に配るために構えた宿舎)からの転訛とみられ、田谷周辺の村々も伊勢神宮を勧請していることから、当社も伊勢神宮の御師が創建に係わったものとみられています。
・御朱印は(西島)瀧宮神社社務所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊勢之宮神社 直書(筆書)

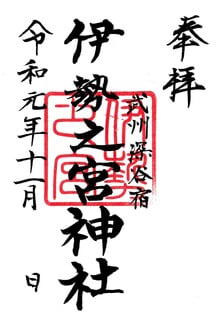
■ 深谷山 光明院 瑠璃光寺
公式Web
深谷市稲荷町北9-25
天台宗
御本尊:釈迦如来、元三大師
札所:関東九十一薬師霊場第39番、武蔵国十三佛霊場第12番、深谷七福神(大黒天/ハギの寺)
・寺伝によると、大同二年(807年)ないし承和二年(835年)、慈覚大師による開山・創建とされる名刹で、鎌倉時代にはすでに七堂伽藍を備えていたといいます。
・康正年間(1455-1456年)、当寺薬師堂の寅薬師を上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」の一仏、鬼門除けのお薬師様として信仰したことでも知られています。
・元和二年(1616年)徳川家康公逝去の後、家康公の遺骨を日光に奉遷する際に天海僧正が当寺で休憩、この縁から慶安二年(1649年)には寺領十石の御朱印状を受領しています。
・複数の現役霊場の札所で、御朱印は庫裡にて印判のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.関東九十一薬師霊場第39番 薬師如来

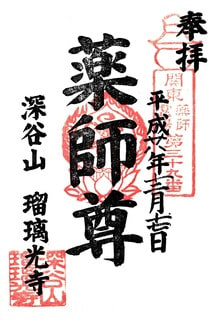
2.武蔵国十三佛霊場第12番 大日如来

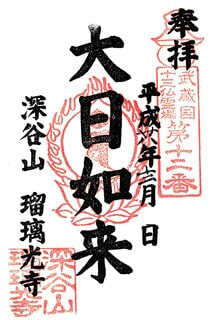
3.深谷七福神 大黒天

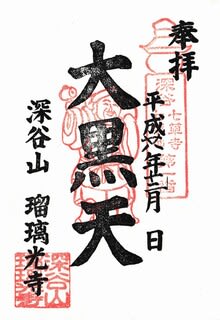
■ 楡山神社
公式Web
深谷市原郷336
御祭神:伊邪那美命
旧社格:県社、延喜式内社
元別当:東学院(本山派修験)・大乗院(本山派修験)・熊野山 能泉寺 正徳院(天台宗)
授与所:楡山神社宮司様宅
・五代孝昭天皇御代の御鎮座と伝わる古社で、延喜式の「武蔵国幡羅郡四座」の一社「楡山神社」に比定されています。
・幡羅郡の総鎮守、幡羅郡總社といわれ、幡羅大神とも称されました。
・旧原ノ郷村は平安時代中期の武将・幡羅太郎道宗が拠った地で、当社南西に史跡「幡羅太郎館趾」があります。
・康平年間(1058-1065年)、源義家公奥州征伐の際、幡羅太郎道宗の長男の成田助高は当社にて戦勝を祈願したといい、後に行田の忍城主となった成田家代々の崇敬篤かったといいます。
・中世には熊野信仰が入り、熊野社、熊野三社大権現などと号したようですが、村民は一貫して楡山神社と称して崇めたといいます。
・社号の由来は一帯に楡の木が多かったことにより、境内の楡の古木は御神木と崇められ、県文化財(天然記念物)に指定されています。
・原郷内の神社を多く境内社としています。また、市内各社の本務社を務められ、複数の御朱印を授与されています。
・御朱印はすこし離れた宮司様宅で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:楡山神社 直書(筆書)

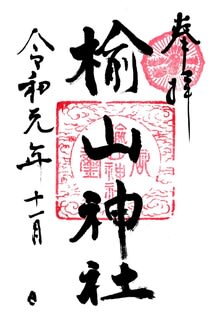
■ (原之郷)愛宕神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市原郷2031
御祭神:火産霊神(ほむすびのみこと)
旧社格:旧原ノ郷村木ノ本の鎮守
元別当:寶珠院 大沼坊(深谷村)
授与所:楡山神社宮司様宅
・旧中山道に面して広大な社地を有していたという愛宕神社で、火防の神様として信仰を集めたといいます。
・境内社として三峯社が鎮座します。
・御朱印は、楡山神社宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:武州原之郷 愛宕神社 直書(筆書)

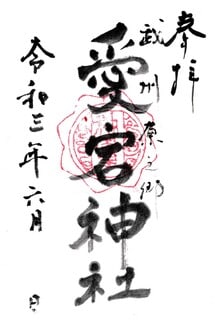
■ 熊野大神社
深谷市東方1709-2
御祭神:伊邪那美命、速玉男命、事解男命
旧社格:郷社、旧東方村鎮守
元別当:熊野山 弥勒院(深谷市東方)
授与所:境内社務所
・延長五年(927年)、この地に枇杷の木を棟木として小祠を建て、上野国碓氷郡熊野本宮より奉遷したのが創建という社伝があり、延喜式神名帳の「白髪神社」(小社)に比定する説もみられます。
・天文年間(1532-1555年)、深谷上杉氏の宿老、皿沼城主岡谷加賀守清英が篤く崇敬し社領を寄進、天正年間(1573-1592年)には深谷上杉氏の家臣秋元景朝・長朝父子が社殿造営とも伝わります。
・江戸期には東方城主として入った松平丹波守康長が崇敬。東方村の鎮守として祀られ、明治42年に地内の五社を合祀、大正13年には郷社に列格しています。
・天正年間 (1573-1592年)の建立と伝えられる本殿は、三間社、入母屋造銅瓦葺の総欅造で、市の文化財(建造物)に指定されています。
・御朱印は、隣接の宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊野大神社 直書(筆書)

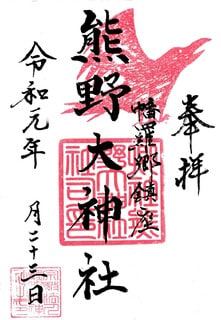
■ 東方山 全久院
深谷市東方2902-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:深谷七福神(寿老人/フジバカマの寺)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第50番(旧 風張寺)
・江戸時代、当地の領主であった松平丹後守康長が祖先戸田弾正左衛門宗光追福のため、三河国牛窪の全久院の寺号を写して草創と伝わります。
・名刹にふさわしく、「紙本着色不動明王三尊像」(室町末期作)、「地蔵尊立像」(室町以前作)などは市の文化財に指定されています。
・深谷七福神の寿老人の札所で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 寿老人
※深谷七福神のみの授与

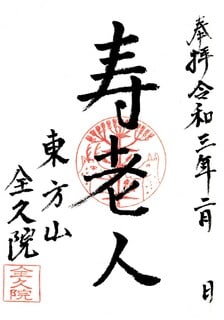
■ 深谷市の御朱印-2へつづきます。
【 BGM 】
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里
■ プラネテス - 黒石ひとみ(Hitomi)
■ Mirai 未来 - kalafina
1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!
さすがに梶浦由記さん
→ コード
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
■ 深谷市の御朱印-2へつづきます。
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
1.旧 川本町エリア
■ 吉祥山 應正寺
深谷市田中608-1
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第30番
・由緒は不詳ですが、入母屋造の立派な本堂と、二層の優れた意匠の観音堂があり、忍秩父三十四観音霊場第30番の札所はこちらの観音堂となっています。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。御本尊の御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

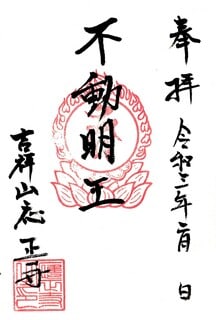
2.忍秩父三十四観音霊場第30番 十一面千手観世音菩薩

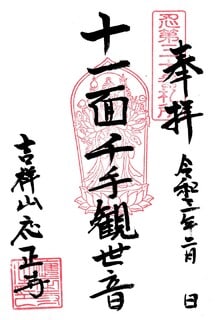
■ 根本山 光明院 正福寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市瀬山141
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東八十八箇所第84番、関東九十一薬師霊場 第35番、武州路十二支霊場 酉(不動明王) ※関東九十一薬師霊場第35番は境外の薬師堂
・永禄年間(1558-1570年)開基、慶長年間(1596-1604年)、重盛法印による開創と伝わる古刹。御本尊の阿弥陀如来は二尺四寸の木彫坐像で、安政二年(1855年)の作と伝わります。
・武州路十二支霊場の札所本尊、不動明王は、板木の記録によると「秀海」という行者が出羽三山へ三十三度尊像を背負って行き来され、霊験あらたかなお不動様として広く信仰され講も組織されたとのこと。
・関東九十一薬師霊場の札所本尊、薬師如来は東側に約600m離れた国道140号パイパス沿いにある境外仏堂の薬師堂(別名:踏鞴堂)に御座。一尺三寸木彫坐像の薬師如来は養老三年(717年)春日仏師一夜作と伝わり、現在の尊像は宝永七年(1710年)造顕とのこと。魔除、厄除、眼病除のお薬師様として広く信仰を集めているそうです。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。3つのメジャー霊場の札所だけに手慣れたご対応です。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第84番 阿弥陀如来

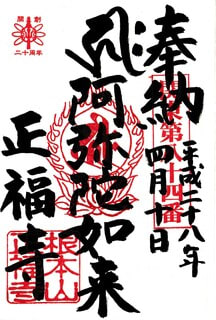
2.武州路十二支霊場(酉) 不動明王


3.関東九十一薬師霊場第35番 薬師如来 〔境外仏堂〕


2.旧 花園町エリア
■ 荒澤山 寿楽院
深谷市荒川983
高野山真言宗
御本尊:不動明王
司元別当:天神社(荒川地内)
・由緒は不詳だが、『風土記稿』には「天神社 寿楽院持」とあります。予想以上に広い境内で、道をはさんで立派な聖天宮が御座します。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。ご住職ご不在時は書置対応となる模様。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

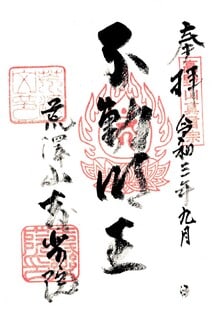
■ 光福山 医王院 長善寺
公式Web
深谷市小前田1452
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所:関東八十八箇所第85番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番
・鉢形城主北条氏邦の三男「光福丸」の菩提寺として知られる古刹で、2つのメジャー霊場の札所として参拝者を集めます。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第85番 大日如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番 聖観世音菩薩

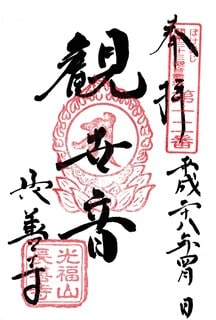
■ (武蔵野)八幡神社
深谷市武蔵野1862
御祭神:誉田別命
旧社格:旧武蔵野村中郷地区鎮守
元別当:常光寺(武蔵野)
授与所:足髙神社(足髙神社社務所に案内あり)
・鎌倉街道(県道小前田・児玉線)沿いに御鎮座の八幡神社。境内社、八坂社の御輿渡御は”暴れ御輿”として知られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

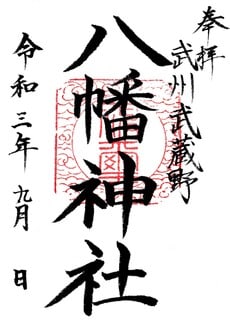
■ 十二社神社
深谷市武蔵野277-3
御祭神:天神七代地神五代の十二柱
旧社格:旧武蔵野村上郷地区鎮守
元別当:寿宝院
授与所:十二社神社(足髙神社社務所に案内あり)
・日本武尊が東征の折、当地にて兵馬・食糧の無事を祈るために創建と伝わります。
・昭和24年、新たな境内を設け旧本殿を移築して御遷座。新しい境内地ながら山林に囲まれ厳かな境内です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:十二社神社 書置(筆書)


■ 足髙神社
深谷市武蔵野3283
御祭神:大物主之大神
旧社格:(氏子区域:旧武蔵野村下郷地区(旧猿喰土村))
元別当:地内観音寺→橋本家→高野家
授与所:境内社務所に案内あり
・既に室町末期には鉢形城主北条氏邦により、領内鬼門鎮護として奉祀されていたとされ、祭礼時、氏邦が神饌を奉るために使った膳が足高であったため、現社号になったと伝わります。
・通常は非駐在のようですが、社務所に掲出の連絡先にTELすると書置の御朱印をお持ちいただけます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:足髙神社 書置(筆書)

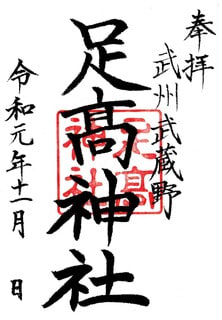
3.旧 深谷市エリア-1
■ 大谷山 地蔵院 宝積寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市大谷114
真言宗豊山派
御本尊:五智如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番、武州路十二支霊場 戌(阿弥陀如来)
・応永年間(1394-1428年)、地蔵菩薩を御本尊として盛谷山地蔵院宝錫寺と号し源照法印が開創。天正十年(1582年)、住職重任和尚が伽藍を整備され、五智如来を奉安されて、大谷山宝積寺と改称して中興と伝わる古刹。
・五智如来とは、大日如来が備えられる5つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智)を象徴する金剛界の五如来(いわゆる金剛界五仏)。
中尊(中央)は法界体性智の大日如来。東方は大円鏡智の阿しゅく如来ないし薬師如来、南方は平等性智の宝生如来、西方は妙観察智の阿弥陀如来、北方は成所作智の不空成就如来でそれぞれ象徴されます。(各尊格は宗派等により異なるようです。)
・関東三十三観音と武州路十二支霊場のふたつの現役霊場の札所を務められ、貴重な五智如来の御朱印も授与いただけます。御朱印は原則書き置きのようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 五智如来

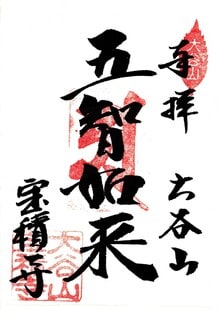
2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番 光明観世音菩薩


3.武州路十二支霊場(戌) 阿弥陀如来

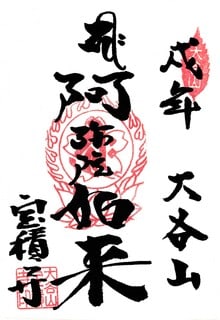
■ 境井山 寶泉寺
深谷市境220-1
曹洞宗
御本尊:
札所:深谷七福神(福禄寿)
・深谷七福神の一寺で福禄寿・キキョウの寺。
・慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いで手柄を立てた旗本吉田与右衛門政景氏は当地境および花園町永田に知行を拝領。人見福昌寺第九世実叟大存大和尚を開山に仰いで当山を建立開基と寺伝にあります。
・深谷七福神の福禄寿は、本堂手前左手に御座。
・七福神の御朱印は本堂内にて直書いただけましたが、御本尊の御朱印は授与されていないそうです。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神(福禄寿)


※御本尊の御朱印は不授与
■ 武蔵國八海山神社
深谷市折之口73
御祭神:大己貴命、國常立尊、少彦名命
旧社格:
元別当:
授与所:境内社務所
・比較的新しい神社で、御朱印も快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八海山神社 直書(筆書)

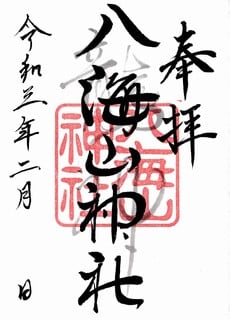
■ 泰国山 人見院 一乗寺
深谷市人見1621-2
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:深谷七福神(布袋尊)
・深谷七福神の一寺で布袋尊・ナデシコの寺。
・正応二年(1289年)、人見四郎泰国による開基、一遍上人の開山とされ、鎌倉時代にこの地に勢力を張った武蔵野七党猪俣党の一族、人見氏の菩提寺です。
・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀三尊(六字御名号)


2.深谷七福神 布袋尊

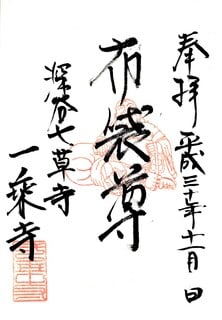
■ 人見山 昌福寺
深谷市人見1391-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
司元別当: 浅間神社(深谷市人見)
札所:
・延文二年(1357年)、深谷城初代城主として山内上杉家の上杉房憲が深谷に入ったのち、父祖の菩提を弔うため仙元山の麓に開基と伝わる曹洞宗の古刹。
・上杉房憲の墓所としても知られています。
・ご住職はお留守でしたが、寺庭さまから書置の御朱印を授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛

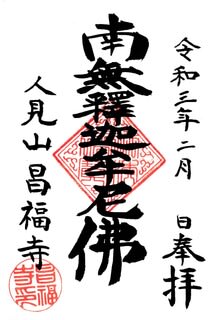
■ 浅間神社
深谷市人見1404
御祭神:木花咲耶姫命
旧社格:郷社
元別当: 人見山 昌福寺(熊谷市人見)
授与所:楡山神社宮司様宅
・標高98mの仙元山の山頂に鎮座する歴史ある浅間神社で、源頼朝が富士の巻狩りの際、その奉賽のために富士本宮から分祀した関八州八社の一社として伝わります。
・また、延文二年(1357年)、深谷城初代城主上杉房憲が昌福寺を開基した折、裏山の仙元山に深谷に入ったのち仙元大菩薩を勧請、後に村内富士講社が富士山本宮より勧請して合祀し、浅間神社と改めたという説もあります。
・深谷城主上杉家、江戸時代の領主・岡田家の篤い尊崇を受けたとされます。
・昭和五年(1930年)、地内の村社・無格社六社を合祀し郷社に列格、戦前には安産の神様として講が組織され、多くの参詣者を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

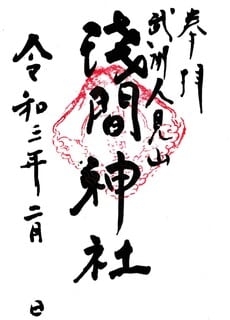
■ 上野台八幡神社
深谷市上野台3168
御祭神:品陀和気命
旧社格:郷社、氏子区域:上野台
元別当:如日山 蓮華院 光厳寺(深谷市上柴町)
授与所:境内
・天文十九年(1550年)、深谷城主上杉氏の家臣、岡谷加賀守清英が、崇敬篤い山城国石清水八幡宮を萱場村に勧請して創祀と伝わります。
・正徳年間(1711-1716年)、時の領主大久保忠義は、村役の嘆願により当地を寄進し萱場村からの御遷座をなしたとされます。
・上野台は、鼠、大台、小台、上宿、中宿、下宿、桜ヶ丘一、同二、泉台の九地区からなり、氏子区域はこの九地区で、多くの境内社はこの氏子区域内からの御遷座とのことです。
・「青天を衝け」にちなんだ御朱印が授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

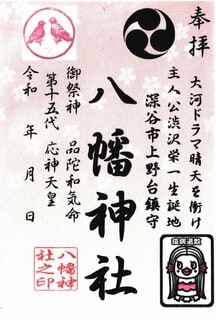


■ (上柴町)諏訪神社
深谷市上柴町東1-18
御祭神:建御名方命、美穂須須美命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、旧大字柴崎地区鎮守
元別当:月笑院
授与所:楡山神社宮司様宅
・文禄元年(1592年)頃、旧柴崎地区の開発者である柴崎淡路守(深谷城主上杉氏の家臣)の一族が氏神として祀ったことが創祀と伝わる柴崎地区の鎮守社。
・境内に御座す双体道祖神は、県内ではめずらしいものとされています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:諏訪神社 直書(筆書)

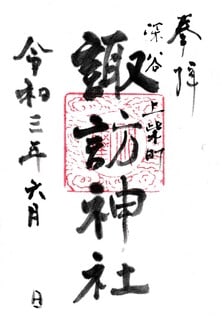
■ 大乗山 正法寺
公式Web
深谷市上柴町東2-2-2
日蓮宗
御本尊:
札所:
・このエリアでは数少ない日蓮宗寺院で、房総・勝浦の松部の地に妙潮寺の末寺として創建、その後、日蓮宗管長、久保田日亀大僧正のお力添えにより深谷に移転されました。
〔拝受御朱印〕
1.御首題

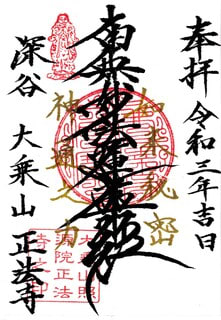
■ (西島)瀧宮神社
公式Web
深谷市西島5-6-1
御祭神:天照大神、豊受大神、彦火火出見命
旧社格:深谷城裏鬼門守護神、旧西島村(内横町仲町)鎮守
元別当:瀧宮山 歓喜院 正覚寺(深谷市深谷町)
授与所:境内社務所
・社伝によると、この地に湧き出る湧水を神として祀り「瀧の宮大明神」と号したのが創祀といいます。
・康正二年(1456年)、上杉氏により深谷城が築かれると、西南に位置する当社を坤門(裏鬼門)の守護神として崇敬し、領国安寧を祈願しました。
・昭和27年(1952年)には深谷宿の守り神・市神様として住民の尊崇篤かった「三社天王」を深谷八坂神社として境内に御遷座。例祭の御輿渡御は「深谷のぎおん」として広く知られています。
・深谷を代表する神社で、御朱印はおおむね社務所にていただけるようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:瀧宮神社 直書(筆書)

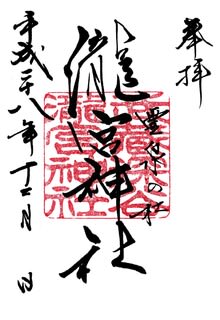
・当社は深谷駅南口のすぐそばに鎮座します。深谷駅の駅舎は、大正時代に竣工の東京駅・丸の内口駅舎が深谷の日本煉瓦製造の煉瓦を使用したことに因み、赤レンガ造をモチーフとしたデザインとなっており、深谷市内のみどころのひとつです。

■ 深谷山 永明寺 高台院
深谷市田谷308
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
・上杉氏の家人、高橋永明が草創。永禄四年(1561年)、深谷城三代目城主上杉憲賢の菩提を弔うため、室の高泰姫によって再興されたと伝わる古刹。
・所蔵の「北亭為直画朱描鎮西八郎為朝像」は市の文化財に指定されています。
・札所ではありませんが、ご住職ご在院時には御朱印を授与いただけるようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

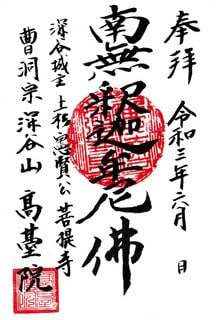
■ 永明稲荷神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市田谷308
御祭神:倉稲魂命、菅原道真公
旧社格:深谷城の戌亥の守護神、田谷地区鎮守
元別当:深谷山 高台院(高泰院) 永明寺(深谷市田谷)
授与所:楡山神社宮司様宅
・康正二年(1456年)、深谷城主上杉氏五代房憲(ないし家臣高橋永明)が築城時に、城の戌亥の守護として創祀と伝わります。
・上杉氏が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、一仏とは瑠璃光寺の寅薬師、三社とは末広稲荷(稲荷町)・永明稲荷・智方明神(本住町)をさすようです。
・明治45年(1912年)、稲荷町の稲荷神社に合祀されたものの社殿は残り、田谷地区の鎮守として独自に祭を催していることから合祀は書類上のものとされています。
・高台院所蔵の「狐開帳図絵馬(きつねかいちょうずえま)」(市指定文化財)は、もともとは永明稲荷神社に奉納されていたものです。
・高台院の奥ふかく、別当というより高台院の地主神的な位置にご鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:永明稲荷神社 直書(筆書)

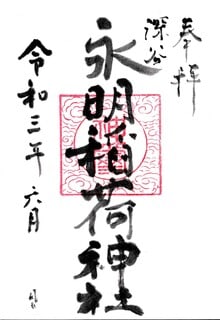
■ 延楽山 福壽院 金胎寺
深谷市本住町9-76
新義真言宗
御本尊:胎蔵界大日如来
司元別当:城内八幡宮・天満宮・管領稲荷社
・慶長九年(1604年)以前に、深谷城主上杉家の祈願寺として法印權大僧都日胤により開基されたという名刹。
・当時の深谷上杉家氏は湯殿山の信仰篤く、御本尊は湯殿山御分身の大日如来であったと伝わります。元禄十一年(1698年)、法印權大僧都快傳による中興開山の折に現在の御本尊大日如来を再鋳安置。
・別尊として奉安される不動明王は、明治22年(1889年)先師秋本一庵法印が下総国成田山より御分身を勧請され、深谷成田山とも称されます。
・札所ではありませんが名刹で、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 大日如来

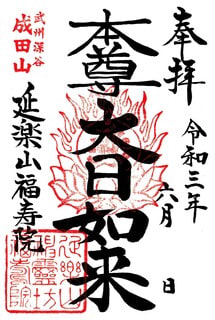
■ (稲荷町)稲荷神社(末広稲荷神社)
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市稲荷町3-2-58
御祭神:倉稲魂命
旧社格:村社、深谷城鬼門鎮護、旧末広村鎮守
元別当:東源寺・宝珠院
授与所:楡山神社宮司様宅
・社伝によると、上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、康正年間(1455-1456年)の城の鬼門守護として創祀とされます。
・「一仏三社」については康応年間(1389-1390)、深谷庁鼻和(こばなわ)に館を構えた上杉憲英が館の鎮護のために勧請という説もみられます。深谷城下の発展に伴い、稲荷町の鎮守として住民から厚く尊崇され今に至ります。
・維新後、無格社であった当社は田谷の稲荷神社(永明稲荷)を合祀し村社に列しましたが、この合祀は書類上のものとみられているようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:稲荷神社 直書(筆書)

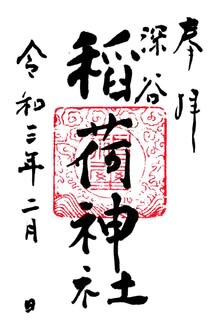
■ 伊勢之宮神社
深谷市西大沼300
御祭神:天照大神、豊受大神
旧社格:- 氏子区域:東大沼、西大沼、栄町、錦町の四か町
元別当:西福院
授与所:(西島)瀧宮神社社務所
・創建は明らかでありませんが、『風土記稿』には「伊勢内宮 村民持、伊勢外宮 西福院持」とあることからかつては二社で、明治初期に一社になったとみられています。
・『埼玉の神社』によると、当地の東部に「田谷」という地があり、これは「旅尾」(御師がお祓大麻を旦那に配るために構えた宿舎)からの転訛とみられ、田谷周辺の村々も伊勢神宮を勧請していることから、当社も伊勢神宮の御師が創建に係わったものとみられています。
・御朱印は(西島)瀧宮神社社務所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊勢之宮神社 直書(筆書)

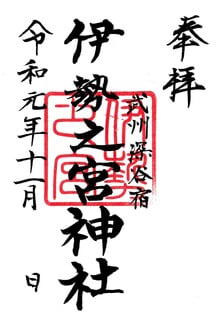
■ 深谷山 光明院 瑠璃光寺
公式Web
深谷市稲荷町北9-25
天台宗
御本尊:釈迦如来、元三大師
札所:関東九十一薬師霊場第39番、武蔵国十三佛霊場第12番、深谷七福神(大黒天/ハギの寺)
・寺伝によると、大同二年(807年)ないし承和二年(835年)、慈覚大師による開山・創建とされる名刹で、鎌倉時代にはすでに七堂伽藍を備えていたといいます。
・康正年間(1455-1456年)、当寺薬師堂の寅薬師を上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」の一仏、鬼門除けのお薬師様として信仰したことでも知られています。
・元和二年(1616年)徳川家康公逝去の後、家康公の遺骨を日光に奉遷する際に天海僧正が当寺で休憩、この縁から慶安二年(1649年)には寺領十石の御朱印状を受領しています。
・複数の現役霊場の札所で、御朱印は庫裡にて印判のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.関東九十一薬師霊場第39番 薬師如来

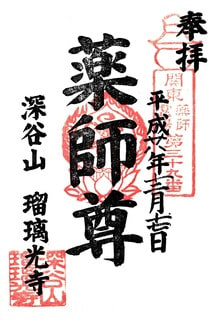
2.武蔵国十三佛霊場第12番 大日如来

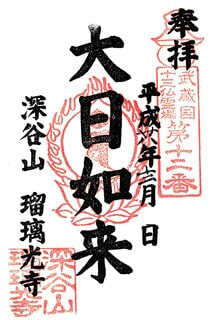
3.深谷七福神 大黒天

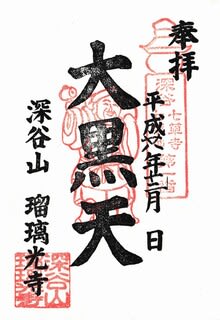
■ 楡山神社
公式Web
深谷市原郷336
御祭神:伊邪那美命
旧社格:県社、延喜式内社
元別当:東学院(本山派修験)・大乗院(本山派修験)・熊野山 能泉寺 正徳院(天台宗)
授与所:楡山神社宮司様宅
・五代孝昭天皇御代の御鎮座と伝わる古社で、延喜式の「武蔵国幡羅郡四座」の一社「楡山神社」に比定されています。
・幡羅郡の総鎮守、幡羅郡總社といわれ、幡羅大神とも称されました。
・旧原ノ郷村は平安時代中期の武将・幡羅太郎道宗が拠った地で、当社南西に史跡「幡羅太郎館趾」があります。
・康平年間(1058-1065年)、源義家公奥州征伐の際、幡羅太郎道宗の長男の成田助高は当社にて戦勝を祈願したといい、後に行田の忍城主となった成田家代々の崇敬篤かったといいます。
・中世には熊野信仰が入り、熊野社、熊野三社大権現などと号したようですが、村民は一貫して楡山神社と称して崇めたといいます。
・社号の由来は一帯に楡の木が多かったことにより、境内の楡の古木は御神木と崇められ、県文化財(天然記念物)に指定されています。
・原郷内の神社を多く境内社としています。また、市内各社の本務社を務められ、複数の御朱印を授与されています。
・御朱印はすこし離れた宮司様宅で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:楡山神社 直書(筆書)

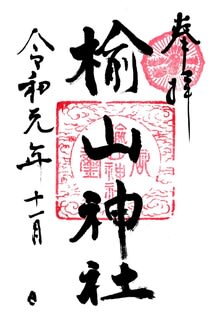
■ (原之郷)愛宕神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市原郷2031
御祭神:火産霊神(ほむすびのみこと)
旧社格:旧原ノ郷村木ノ本の鎮守
元別当:寶珠院 大沼坊(深谷村)
授与所:楡山神社宮司様宅
・旧中山道に面して広大な社地を有していたという愛宕神社で、火防の神様として信仰を集めたといいます。
・境内社として三峯社が鎮座します。
・御朱印は、楡山神社宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:武州原之郷 愛宕神社 直書(筆書)

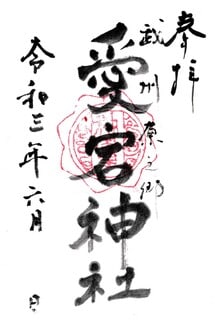
■ 熊野大神社
深谷市東方1709-2
御祭神:伊邪那美命、速玉男命、事解男命
旧社格:郷社、旧東方村鎮守
元別当:熊野山 弥勒院(深谷市東方)
授与所:境内社務所
・延長五年(927年)、この地に枇杷の木を棟木として小祠を建て、上野国碓氷郡熊野本宮より奉遷したのが創建という社伝があり、延喜式神名帳の「白髪神社」(小社)に比定する説もみられます。
・天文年間(1532-1555年)、深谷上杉氏の宿老、皿沼城主岡谷加賀守清英が篤く崇敬し社領を寄進、天正年間(1573-1592年)には深谷上杉氏の家臣秋元景朝・長朝父子が社殿造営とも伝わります。
・江戸期には東方城主として入った松平丹波守康長が崇敬。東方村の鎮守として祀られ、明治42年に地内の五社を合祀、大正13年には郷社に列格しています。
・天正年間 (1573-1592年)の建立と伝えられる本殿は、三間社、入母屋造銅瓦葺の総欅造で、市の文化財(建造物)に指定されています。
・御朱印は、隣接の宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊野大神社 直書(筆書)

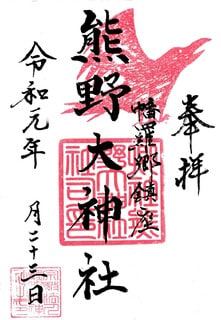
■ 東方山 全久院
深谷市東方2902-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:深谷七福神(寿老人/フジバカマの寺)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第50番(旧 風張寺)
・江戸時代、当地の領主であった松平丹後守康長が祖先戸田弾正左衛門宗光追福のため、三河国牛窪の全久院の寺号を写して草創と伝わります。
・名刹にふさわしく、「紙本着色不動明王三尊像」(室町末期作)、「地蔵尊立像」(室町以前作)などは市の文化財に指定されています。
・深谷七福神の寿老人の札所で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 寿老人
※深谷七福神のみの授与

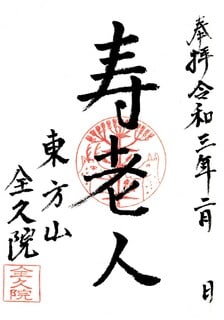
■ 深谷市の御朱印-2へつづきます。
【 BGM 】
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里
■ プラネテス - 黒石ひとみ(Hitomi)
■ Mirai 未来 - kalafina
1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!
さすがに梶浦由記さん
→ コード
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印【補強・追加版】
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印ですが、まだまだ書くべき人物が残っているので、継続して追加していきます。
→ ■ 鎌倉殿の御家人
当初の記事の踏み込みが甘いので、補強も含めて追加していきます。
5.甘縄神明宮 〔源氏・安達盛長〕の補強版です。
5.甘縄神明宮 〔安達藤九郎盛長〕
神奈川県鎌倉市長谷1ー12ー1
主祭神:天照大神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:甘縄院(臨済宗)
鎌倉の御家人のなかでも別格だった存在に安達盛長がいます。
常に頼朝公に寄り添い、数ある政争のなかでも安定した存在感を示して、幕府重鎮の地位を保ったまま往生を遂げています。
頼朝公の逝去は正治元年(1199年)、盛長は翌正治二年(1200年)の没と、頼朝公のあとを追うように世を去っています。
頼朝公逝去後、出家して蓮西と号し十三人の合議制に名を連ねましたが、わずか1年で逝去したため出家後の事績はあまり残っていません。
『吾妻鏡』『源平盛衰記』などには”藤九郎盛長”という武士がしばしば登場しますが、この”藤九郎盛長”が安達盛長です。
”藤九郎”は藤原の九郎を示すとされますが、Wikipediaでは小野田三郎兼広(藤原北家魚名流)の子という説が紹介され、父は藤原忠兼あるいは小野田盛兼としている史料もあり、いずれ東国に移住した藤原氏(小野田氏)の流れとみられます。
兄は藤原遠兼(足立遠元の父)ともいわれ、そうなると安達盛長は足立遠元の叔父ということになります。
ただし史料からすると安達盛長よりも足立遠元の方が年長と推測されるので、この関係を疑う見方もあります。
なお、安達姓は文治五年(1189年)の奥州合戦後に新恩の地となった陸奥国安達荘(福島県二本松市)からという説が有力です。(それ以前は藤原姓、ないし小野田姓を名乗っていたのでは?)
盛長の室は、頼朝公の乳母・比企尼の娘の丹後内侍です。
丹後内侍は京で二条天皇に女房として仕え、和歌にも長じていたため京の公家衆と親交が深かったといいます。
盛長が伊豆配流の頼朝公にいちはやく仕えたのは、妻の母・比企尼の意向を受けたためともみられています。
盛長は伊豆の地で頼朝に仕え、挙兵までの雌伏の日々を支えました。
『曽我物語』には、頼朝公と北条政子の仲を取りもったのは盛長との記載もあります。
治承四年(1180年)夏の頼朝挙兵に従い、下総の千葉常胤を説得して味方につけました。
以降も一貫して頼朝公側近の地位を占め、『吾妻鏡』の公式行事の段には必ずといってよいほど”藤九郎盛長”の名が見られます。
*******
東京都三鷹市の井之頭弁財天は、「頼朝挙兵に際しては、その使者・安達盛長の夢枕に立って大願成就を予言したことから、『勝ち運の銭洗い弁天』として知られる。」(武蔵野市観光機構Web資料から)とされます。
孫引きになりますが、「近世都市周辺の宗教施設の由緒と『名所』化の動向(PDF)」(法政大学多摩論集編集委員会 2020-03)に引用されている『神田御上水源井之頭辨財略縁起』には下記のとおりあります。
「源頼朝公承安年中の頃、伊豆の国に配居し玉ふ時、平家追討の事を謀り玉ひて江戸・笠井・比企・河越の武士召さん迚安達藤九郎盛長使者なりし時、此所の小社に至り暫く休息し頻りに計畧をめくらし思慮未決せさる時、忽然として一人の美人立あらわれ盛長に告て曰、我汝か志願尤大なる事を知る、必本意を達すへし苦思することなかれ、斯謂我ハ源家厚く信仰し玉ふ開運天女の使なりと語り終りて忽に失玉ふ、盛長深く是を感し恐々とし奇異の思ひをなす、是より信心肝に銘し其跡を礼し誓願して謂らく我君速に平氏の一類を追罰し玉ハゝ、此所に一宇の宮殿を建立し奉るへしと一念し、程なく使者の趣を達し帰参の後此事を言上す、頼朝公深く是を感し信心祈誓し玉ひて後建久八年に至り終に宿願を遂玉ひて即此所に宮社を建立し神像を安置し奉れは(以下略)」
伊豆の頼朝公の意向を受け江戸・笠井(葛西)・比企・河越などの武蔵の有力氏族を味方に引き入れるため在所に向かう盛長が当地に休息したとき、御本尊の辨財天女が出現されて本意成就を告げられ、これを聞いた頼朝公は辨財天尊を信心祈誓、宿願成就ののちに宮社を建立し神像を安置したとの由。
頼朝公挙兵前から、盛長が武蔵の有力豪族の懐柔に動いていたことをうかがわせる内容です。
*******

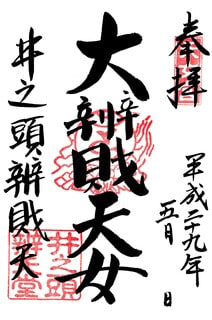
【写真 上(左)】 井之頭辨財天
【写真 下(右)】 井之頭辨財天の御朱印
盛長の邸宅は鎌倉の甘縄(現・甘縄神明神社付近)ないし扇ガ谷の無量寺谷付近とみられます。
当時の「甘縄」は無量寺谷までも含んでいたとされるので、無量寺谷説が有力かも。
(無量寺谷(むりょうじがやつ、現・鎌倉歴史文化交流館周辺)には安達氏の菩提寺とみられる無量寿院や安達氏邸があったと考えられ、発掘調査では鎌倉時代後期の遺跡が見つかり研究が進められています。)
しかし盛長の当初の本拠地については定説がみられません。
埼玉県鴻巣市糠田の糠田山 放光寺にはかつて安達盛長の館だったという伝承があり、南北朝時代制作とされる伝・安達盛長座像を所蔵しています。
鴻巣市糠田は足立氏の本拠に近く、盛長は足立遠元の叔父としてこの地に拠っていたということも考えられます。
放光寺の山内説明板には以下のとおりあります。
「放光寺の開基は、源頼朝の御旗奉行を務めた安達藤九郎盛長とされ、本堂にはこの盛長の坐像が安置されている。(略)安達藤九郎盛長は、治承四年(1180年)源頼朝の挙兵に応じて相模の地で功を挙げ、同国を安堵された。その後、盛長の所領は相模、下総、武蔵にまで及んだ。さらに建久五年(1194年)には頼朝の信任をうけて鶴岡八幡宮の奉公人となった。正治元年(1199年)1月の頼朝の死後出家したが、その後も北条時政や大江広元等とともに重要訴訟の調査・裁決などに係わるなど幕府の要職にあり、三河の守護に就いた。正治二年(1200年)に66歳で没した。」


【写真 上(左)】 放光寺
【写真 下(右)】 放光寺蔵の伝・安達盛長座像(山内説明板より)
放光寺の御朱印は通常不授与ですが、TVドラマ放送を記念し、2022年5月28日(土)14:00~16:00の2時間限定で開催された「安達藤九郎盛長坐像(埼玉県指定有形文化財)」の御開帳イベントでは御住職直筆の御朱印を複写したポストカードが限定配布された模様です。
御朱印イメージは → こちら。
御朱印尊格は大日如来。
主印は金剛界大日如来の種子「バン」(蓮華座+火焔宝珠)のようです。
華々しい逸話は少ないですが、雌伏の頼朝公をはやくから支えて千葉常胤を説得して味方につけ、あまたの合戦でも順調に戦歴を重ねていることから、並みの技倆ではなかったと思われます。
梶原景時の変ではとりまとめ役を果たしたという説があり、頼朝公逝去後、十三人の合議制に名を連ねていることからも相応の実力と人望を有していたのでは。
盛長の嫡男・景盛は宝治元年(1247年)の宝治合戦(北条時頼と三浦氏の抗争)で重要な役割を果たして北条氏の勝利・覇権確立に貢献。
幕閣での地位を高め、景盛は3代将軍実朝公と政子の信頼も厚かったといいます。
景盛の嫡男・義景(秋田城介)、その嫡男・泰盛は、北条氏と姻戚関係を強めたこともあり幕政の中枢を占めましたが、「新御式目」など幕政改革をめぐる御家人の内紛をきっかけに弘安八年(1285年)秋に勃発した「霜月騒動」の旗頭となって敗北し、安達一族はここに失脚しました。
泰盛党として蹶起したのは足利氏、小笠原氏、伊東氏、武藤氏(少弐氏)、宇都宮氏、吉良氏、足立氏などの有力御家人層で、この敗戦によりいずれも幕閣での政治力を失い北条得宗を中心とする専制が強まりました。
安達氏および関連氏族とされる大曾根氏は、江戸時代まで活動の記録がみられますが、最盛期は泰盛の代とされています。
上記のとおり、安達盛長の当初の本拠ははっきりせず、ゆかりの寺社も多くはみられません。
安達盛長の館と伝わる鴻巣・放光寺は御朱印不授与なので、ここでは邸宅跡と伝わる甘縄神明宮をご紹介します。
『新編鎌倉志』の藤九郎盛長屋敷に「甘縄明神の前、東の方を云。【東鏡】に、治承四年(1180年)十二月廿日、武衛御行始めとして、藤九郎盛長が甘縄の家に入御し給ふとあり。其後往々見へたり。」とあります。
頼朝公以来、将軍の来臨もしばしばあったといいます。
この邸址に御鎮座と伝わる甘縄神明宮は和銅三年(710年)行基の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社ともいわれます。
染屋時忠は山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立したといいます。
永保元年(1081年)源義家公が社殿を再建、以降も源頼朝公、政子の方、源実朝公などの崇敬が篤かったとされます。
源頼義公が相模守として下向の折に当宮に祈願して八幡太郎義家公が生まれたとも伝えられ、源家とつよいゆかりをもちます。
------------------------


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 参道-1
江ノ電「長谷」駅から長谷寺、鎌倉大仏へ向かう道は観光客で賑わいますが、長谷寺山門前から鎌倉駅方向へ向かう長谷小路は生活道路で、観光客の姿は少なくなります。
甘縄神明宮はこの長谷小路から参道が伸びていることもあって、人影のすくない落ち着いた神社です。
長谷小路沿いに木柱の社号標があるものの、目立たず見過ごしがちです。
それでも路地正面には石造の神明鳥居が見えています。
ここはちょうど由比ヶ浜の海岸からつづく平地が山手に差しかかるところで、鳥居おくに4つの階段を連ねています。

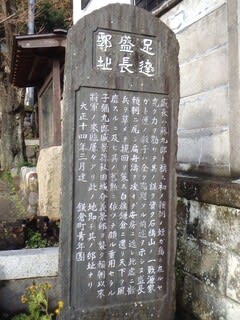
【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 邸址碑
踊り場に建つ「安達盛長邸址」碑には「盛長ハ藤九郎ト称ス 初メ頼朝ノ蛭ヶ島ニ在ルヤ 克ク力ヲ勠セテ其ノ謀ヲ資ク 石橋山ノ一戦源家ガ卜運ノ骰(さい)子ハ全く黯黮タル前途ヲ示シヌ 盛長頼朝ニ尾シ扁舟濤ヲ凌イデ安房ニ逃レ 此処ニ散兵ヲ萃(あつ)メテ挽回ヲ策ス 白旗鎌倉ニ還リ天下ヲ風靡スルニ及ビ 其ノ舊勲ニ拠ツテ頗ル重用セラル子彌九郎盛景 孫秋田城介義景邸ヲ襲グ 頼朝以来将軍ノ来臨屡々アリ 此ノ地即チ 其ノ邸址ナリ」とありました。
石灯籠二対のおくは急な階段となり、のぼりきると正面が銅板葺神明造(ないしは入母屋造流れ向拝)の拝殿です。
周囲はうっそうとした社叢におおわれ神さびて、長谷小路から少し入っただけなのにあたりの空気はまったく異質なものです。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
拝殿前に立派な二対の狛犬。
拝殿向拝の水引虹梁の装飾はシンプルですが、すこぶる均整がとれて風格があります。
向拝正面は板戸で閉扉。その上に「甘縄神明宮」の扁額。


【写真 上(左)】 五社神社
【写真 下(右)】 秋葉神社
境内社として五社神社と秋葉神社が御鎮座です。
境内掲示の略誌には、
御祭神 天照大神
伊邪那岐尊(白山)
倉稲魂命(稲荷)
武甕槌命(春日)
菅原道真公(天神)
とあるので、伊邪那岐尊以下の神々は五社神社祭祀かもしれません。
境内には北条時宗産湯の井があるようですが、超うかつにも写真を撮りわすれました。
北条時宗は鎌倉幕府第8代執権で、室の堀内殿は安達義景の息女。
北条時宗は安達景盛の息女・松下禅尼の邸で産まれ、それがこのあたりといいます。
松下禅尼の子、経時は第4第執権、時頼は第5第執権なので、この時代、安達氏は北条執権の外戚として絶大な権力を握っていたものと思われます。
なお、『徒然草』184段に松下禅尼が障子の切り貼りを手づからしてみせ、時頼に倹約の心を伝えたという逸話がみえ、国語教科書にも取り上げられていたそう。
鎌倉武士の質実剛健の心構えは、安達氏から北条執権家累代にもしっかり伝わっていたようです。
拝殿前には「当宮では御朱印は行っておりません」の掲示がありますが、大町八雲神社にて拝受できました。

甘縄神明宮の御朱印
41.(飯田)足立神社 〔足立右馬允遠元〕
埼玉県さいたま市西区飯田54
御祭神:天神七代尊、地神五代神、日本武尊、市杵島姫命、多岐都比売命、猿田彦命、大国主神、天手力男神、菊理姫命、倉稲御魂命、応神天皇、菅原道真公
旧社格:村社、延喜式内社論社(足立郡足立神社)
元別当:
武蔵国の御家人を代表する一人に足立右馬允遠元がいます。
足立氏は武蔵国足立郡に拠った豪族で、遠元の父・藤原遠兼が当地に土着し遠元の代から足立姓を名乗ったといいます。
『尊卑分脈』では藤原北家魚名流・藤原山蔭の後裔で、安達盛長は遠兼の弟としています。
そうなると安達盛長は足立遠元の叔父になりますが、史料からすると安達盛長よりも足立遠元の方が年長と推測されるので、この関係を疑う見方もあります。
『足立系図』(東大史料編纂所データベース)では、遠元は藤原北家勧修寺流・藤原朝忠の後裔となっています。
Wikipediaによると、武蔵国造家の流れで承平天慶の乱の時代の足立郡司・武蔵武芝の子孫とする説もあるようで、盛長以前の足立氏の系譜は錯綜しています。
諸説いずれも藤原氏ないし天孫系で、足立氏は自らの出自に矜持をもっていたと思われます。
多くの事績を遺しながら、足立遠元の生没年は伝わっておりません。
ゆかりの地の少なさも、鎌倉幕閣重鎮としては異例なほどです。
そのなかでも、桶川市はWebでよくまとまった資料を公開していますので、この資料やその他史料をベースにまとめてみたいと思います。
遠元は平治元年(1160年)の平治の乱で源義朝公に従って右馬允に任ぜられ、源義平率いる17騎の一人として活躍しました。
治承四年(1180年)夏の頼朝公旗揚げでは、頼朝公が下総から武蔵に入った10月2日に豊島清元・葛西清重父子らとともにいち早く参上し、武蔵国足立郡を本領安堵されています。
これは、頼朝公が東国武士に本領所有権を譲渡した最初の事例とみられています。
建久元年(1190年)、頼朝公上洛の際に右近衛大将拝賀の布衣侍7人(三浦義澄、千葉胤正、工藤祐経、後藤基清、葛西清重、八田知重、足立遠元)のうちに任ぜられ供奉。
鎌倉御家人の頂点のポジションを占めています。
頼朝公逝去後には十三人の合議制に名を連ね、晩年も相当の実力と人望を保っていたことがわかります。
母は秩父氏系の豊島康家の息女で、足立郡司職は豊島氏から承継との見方があります。
娘は畠山重忠、北条時房に嫁いで、有力御家人と縁戚関係を築いていました。
なお、畠山重忠に嫁いだ菊の前は、元久二年(1205年)、重忠が北条時政の謀略により討たれたときに自害と伝わります。
別の娘は後白河法皇の近臣の藤原光能に嫁ぎ、京との繋がりも深めています。
光能は永万元年(1165年)下野守に任ぜられているので、そのときに面識をもったのかもしれません。
この時点で院の近臣と縁戚関係をもった東国武士は少ないとされ、これも遠元のオリジナルな強みとなった可能性があります。
後世、どちらかというと文官的な捉え方をされる人物ですが、その武勇は『平治物語』の一幕からひしひしと感じられるので、長くなりますが抜粋引用してみます。
『平治物語/六波羅合戦事』
「金子ノ十郎家忠は(略)真先懸けて戦ひけり。矢種も皆射尽し、弓も引き折り、太刀をも折りければ、折太刀を提げて、あはれ太刀がな、今一合戦せんと思ひて駈け廻る処に、同国の住人足立右馬允遠元馳せ来れば、是れ御覧候へ、足立殿、太刀折れて候。御帯添(戦場で腰につける予備の太刀)候はば、御恩に蒙り候はんと申しければ、折節帯添なかりしかども、御邊が乞ふが優しきにとて、先を打たせたる郎等の太刀を取りて、金子にぞ与へける。家忠大ニ悦びて、又駈け入りて、敵数多討ちてけり。足立が郎党申しけるは(略)是程に見限られ奉りては、(略)既に腹を切らんと、上帯を押し切りければ、遠元馬より飛んで下り、汝が恨むる所尤も理なり。然れども、金子が所望黙止がたさに、御邊が太刀を取りつるなり。軍をするのも主のため、討死する傍輩に乞はれて、与えぬ者や侍らん。(略)」暫く待てといふ所に、敵三騎来りて、足立を討たんと駈け寄せたり。遠元、真前に進みたる武者を、能つ引いてひやうと射る。其の矢誤たず、内兜に立ちて、馬より真倒に落ちければ、残りの二騎は馬を惜んて駈けざりけり。遠元軈て走り寄りて、帯きたる太刀を引き切っておつ取り、汝が恨むる所尤なり。太刀とらするぞとて、郎党に与へ、打ち連れてこそ又駈けけれ。」
要約すると、武勇の士・金子家忠が激闘で太刀を失ったので、同輩の遠元に予備の太刀を貸してほしいと頼んだところ、予備の太刀のない遠元は郎党の太刀を取りあげてこれを家忠に与えました。
主君に太刀を取られた郎党は面目を失い切腹しようとするも、遠元はこれを押しとどめ、太刀を失った同輩(家忠)を見殺しにするわけにはいかぬ、しばし待てと諭しました。
そこへ討ち懸かった敵騎を遠元はすぐさま強弓一矢で射落とすやその太刀を取り上げ、郎党に「お前が恨みに思うのももっともだ。それ、太刀をとらすぞ」と、敵から取り上げた太刀を郎党に与え、気迫を取り戻した郎党とともに戦陣に駈け戻ったということです。
平治の乱の六波羅合戦といえば、名だたる武将がしのぎをけずった激戦です。
そのなかでこの逸話がとりあげられた足立遠元の戦ぶりは、戦場でも際立っていたのでは。
じっさい、平重盛との「待賢門の戦い」でも源氏17騎の一人として活躍しています。
これほどの武勇をもちながら公文所寄人に抜擢されるなど、文武両面に秀でた遠元は、しばしば京からの来賓の接待役に任ぜられています。
元暦元年(1184年)秋、公文所が設置されると5人の寄人(中原親能、二階堂行政、藤原邦通、大中臣秋家、足立遠元)の一人に選ばれています。
奥州合戦の勲功として頼朝公に御家人10人の推挙が与えられた際は、その一人に入り左衛門尉に任ぜられています。
とくに10人の推挙者は鎌倉御家人を代表する顔ぶれ(千葉常秀(父常胤→)、梶原景茂(父景時→)、八田知重(父知家→)、三浦義村(父義澄→)、葛西清重、和田義盛、佐原義連、小山朝政、比企能員、足立遠元)で、遠元は御家人屈指のポジションを占めていました。
奥州合戦勲功推挙の10人(武人の代表)と公文所寄人(文官の代表)、いずれにも名を連ねたのは足立遠元ただひとりで、ここからも文武両面から貢献する遠元の存在感がみてとれます。
遠元の記録は承元元年(1207年)3月で途絶えており、ほどなく世を去ったとみられています。
弘安八年(1285年)の霜月騒動で遠元の嫡曽孫・足立左衛門尉直元が安達泰盛側につき自害しているので、足立氏は霜月騒動までは安達氏と連携して勢力を保っていたのでは。
なお、この霜月騒動までには、足立氏の足立郡司職は北条氏に移ったとみられています。
霜月騒動で失脚した足立氏ですが、承久三年(1209年)、遠元の孫・遠政は丹波国氷上郡佐治庄の地頭職となり、佐治庄小倉に移っていました。
同地の山垣城(現・兵庫県丹波市青垣町)に拠った遠政は大いに勢力を張り、丹波の名門足立氏の祖となりました。
丹波足立氏は天正七年(1579年)5月に織田信長の丹波攻めを受け、山垣城は羽柴秀長と明智光秀の軍勢に攻められてついに落城。
丹波足立氏は戦国大名としては没落しましたが、いまも丹波の名族として知られています。
なので、足立氏ゆかりの史跡は関東よりも丹波に多く残ります。
遠元の本拠地は明らかになっていませんが、桶川市資料によると、遠元の館跡と伝わる場所は4か所あるそうです。
1.さいたま市西区内
2.桶川市川田谷の三ツ木城跡、
3.桶川市神明1丁目の諏訪雷電神社東側付近
4.末広2丁目の総合福祉センター付近
ただし、いずれの地も決定的な史料は見つかっていないそうです。
4は「一本杉」と呼ばれ、「新編武蔵風土記稿」の桶川宿の項に遠元館と伝わる地として記載されています。
ここでは、境内由緒書に「豪族足立氏が奉斎する氏神」と明記されている、さいたま市西区飯田の足立神社をご紹介します。
新編武蔵風土記稿には下記のとおりあります。
植田谷本村 足立神社
「名主勘太夫カ屋舗ノ内ニアリ(略)相傳ヘテ 延喜式神名帳ニ載スル足立神社ハ 即當社ナリト云 此説モシ然ランニハ 當國風土記ニ 神田六十束 四圍田 大日本根子彦太日天皇御宇二年戊子所祭猿田彦命也 有神戸巫戸等ト記スモノニシテ最古社ナリ(略)或ハ云シカハアラス當所ハ藤九郎盛長ノ領地ニシテ 在住セシヨシナレハ 盛長没後其靈ヲ祀リユヘ 足立ノ社ト號セシヲ 稱呼ノ同シケレハ誤リ傳ヘテ 神名帳ノ足立神社ト定メシモノナラント 是コト牽強ノ説トイウヘシ 盛長カ當郡ニ住セサルコトハ前ニ辨セルカ如シ モシクハ足立右馬允ヲ誤リ傳ヘシニヤ サレトソレモ慥カラル據ナキ時ハウケカヒカタシ」
「前ニ辨セル」とはおそらく植田谷本村の項で、以下のとおりあります。
「領主ハ詳ナラサレント 右大将頼朝ノ頃ハ藤九郎盛長此邊ヲ一圓領セシ由イヒ傳フレトオホツカナシ コレ恐ラクハ足立右馬允遠元ヲ誤リ傳ヘシナラン 此人當郡ヲ領セシコト且盛長ハ安達氏ニシテ足立氏ナラサルコト等ハ(略)」
まとめると、植田谷本村付近は鎌倉初期に藤九郎(安達)盛長の領地という言い伝えがあるが、これは誤りで、足立右馬允遠元の領地であるとしています。
そして、当初の領主は足立氏であり、安達氏ではないと念を入れています。
また、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)には下記のとおりあります。
「『延喜式』神名帳には、武蔵国足立郡内の神社として、氷川神社・足立神社・調神社・多気比売神社の四社の名が記されている。これらの諸社のうち、足立神社は、古代における殖田郷に鎮座し、この殖田郷を本拠地とした在地の豪族足立氏が奉斎した神社であったものと思われる。」
さらに境内掲示の説明書には以下のとおりあります。
「足立神社は、平安時代にその名が見える古い神社です。植水地区を中心とした殖田郷に本拠をおいた平安時代の豪族足立氏が奉斎する氏神でしたが、崇敬者も増え朝廷の『延喜式神名帳』に登載されるほどになりました。この神名帳にみえる足立神社だとする社が、浦和市・鴻巣市・市内宮原町にもありますが、『新編武蔵風土記稿』では足立氏の子孫と伝える植田谷本村の名主小島勘太夫家屋敷内にあった足立神社をそれと記しています。
この足立神社は明治40年に植田谷地内の12社を合祀して、氷川神社の社号を足立神社と改称したものです。」
------------------------


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 社号標
(飯田)足立神社は、所沢と大宮を結ぶ県道56号さいたまふじみ野所沢線沿いに御鎮座です。
荒川と鴨川に挟まれた低湿の地ですが、水利はよさそうです。
県道に面して社号の幟旗がはためいていましたが、これは正月だったからかもしれません。
県道に面して玉垣、右手に「総社 足立神社」の社号標とその先に石造の神明鳥居。
鳥居前には「足立遠元公」の幟がはためいています。


【写真 上(左)】 参道と鳥居
【写真 下(右)】 参道
そこからまっすぐ拝殿に向かって参道が伸び、二の鳥居は朱塗りの明神鳥居です。
全体に社叢がすくなく、明るく開けた雰囲気の境内。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 扁額
拝殿は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁はシンプル。
向拝上には社号扁額が掲げられています。
本殿はおそらく大がかりな一間社流造銅板葺で、身舎の朱塗りが鮮やか。


【写真 上(左)】 拝殿と本殿
【写真 下(右)】 御嶽神社
境内には立派な御嶽神社も御鎮座です。
参道向かって右手に社務所。
こちらは原則、正月や祭礼時のみの御朱印授与のようですが、正月に参拝したので社務所は開き、御朱印も直書で授与されていました。


【写真 上(左)】 御朱印案内
【写真 下(右)】 御朱印
足立遠元ゆかりで御朱印を授与されている寺社はこちらしか確認できておらず、しかも限定授与なので遅くなりましたが、ようやく記事にまとめることができました。
【 BGM 】
■ I.G.Y. - Donald Fagen
■ Oh Yeah! - Roxy Music
■ Our Love - Michael McDonald
■ Isn't It Time - Boz Scaggs
■ Both Sides Now - Marc Jordan
→ ■ 鎌倉殿の御家人
当初の記事の踏み込みが甘いので、補強も含めて追加していきます。
5.甘縄神明宮 〔源氏・安達盛長〕の補強版です。
5.甘縄神明宮 〔安達藤九郎盛長〕
神奈川県鎌倉市長谷1ー12ー1
主祭神:天照大神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:甘縄院(臨済宗)
鎌倉の御家人のなかでも別格だった存在に安達盛長がいます。
常に頼朝公に寄り添い、数ある政争のなかでも安定した存在感を示して、幕府重鎮の地位を保ったまま往生を遂げています。
頼朝公の逝去は正治元年(1199年)、盛長は翌正治二年(1200年)の没と、頼朝公のあとを追うように世を去っています。
頼朝公逝去後、出家して蓮西と号し十三人の合議制に名を連ねましたが、わずか1年で逝去したため出家後の事績はあまり残っていません。
『吾妻鏡』『源平盛衰記』などには”藤九郎盛長”という武士がしばしば登場しますが、この”藤九郎盛長”が安達盛長です。
”藤九郎”は藤原の九郎を示すとされますが、Wikipediaでは小野田三郎兼広(藤原北家魚名流)の子という説が紹介され、父は藤原忠兼あるいは小野田盛兼としている史料もあり、いずれ東国に移住した藤原氏(小野田氏)の流れとみられます。
兄は藤原遠兼(足立遠元の父)ともいわれ、そうなると安達盛長は足立遠元の叔父ということになります。
ただし史料からすると安達盛長よりも足立遠元の方が年長と推測されるので、この関係を疑う見方もあります。
なお、安達姓は文治五年(1189年)の奥州合戦後に新恩の地となった陸奥国安達荘(福島県二本松市)からという説が有力です。(それ以前は藤原姓、ないし小野田姓を名乗っていたのでは?)
盛長の室は、頼朝公の乳母・比企尼の娘の丹後内侍です。
丹後内侍は京で二条天皇に女房として仕え、和歌にも長じていたため京の公家衆と親交が深かったといいます。
盛長が伊豆配流の頼朝公にいちはやく仕えたのは、妻の母・比企尼の意向を受けたためともみられています。
盛長は伊豆の地で頼朝に仕え、挙兵までの雌伏の日々を支えました。
『曽我物語』には、頼朝公と北条政子の仲を取りもったのは盛長との記載もあります。
治承四年(1180年)夏の頼朝挙兵に従い、下総の千葉常胤を説得して味方につけました。
以降も一貫して頼朝公側近の地位を占め、『吾妻鏡』の公式行事の段には必ずといってよいほど”藤九郎盛長”の名が見られます。
*******
東京都三鷹市の井之頭弁財天は、「頼朝挙兵に際しては、その使者・安達盛長の夢枕に立って大願成就を予言したことから、『勝ち運の銭洗い弁天』として知られる。」(武蔵野市観光機構Web資料から)とされます。
孫引きになりますが、「近世都市周辺の宗教施設の由緒と『名所』化の動向(PDF)」(法政大学多摩論集編集委員会 2020-03)に引用されている『神田御上水源井之頭辨財略縁起』には下記のとおりあります。
「源頼朝公承安年中の頃、伊豆の国に配居し玉ふ時、平家追討の事を謀り玉ひて江戸・笠井・比企・河越の武士召さん迚安達藤九郎盛長使者なりし時、此所の小社に至り暫く休息し頻りに計畧をめくらし思慮未決せさる時、忽然として一人の美人立あらわれ盛長に告て曰、我汝か志願尤大なる事を知る、必本意を達すへし苦思することなかれ、斯謂我ハ源家厚く信仰し玉ふ開運天女の使なりと語り終りて忽に失玉ふ、盛長深く是を感し恐々とし奇異の思ひをなす、是より信心肝に銘し其跡を礼し誓願して謂らく我君速に平氏の一類を追罰し玉ハゝ、此所に一宇の宮殿を建立し奉るへしと一念し、程なく使者の趣を達し帰参の後此事を言上す、頼朝公深く是を感し信心祈誓し玉ひて後建久八年に至り終に宿願を遂玉ひて即此所に宮社を建立し神像を安置し奉れは(以下略)」
伊豆の頼朝公の意向を受け江戸・笠井(葛西)・比企・河越などの武蔵の有力氏族を味方に引き入れるため在所に向かう盛長が当地に休息したとき、御本尊の辨財天女が出現されて本意成就を告げられ、これを聞いた頼朝公は辨財天尊を信心祈誓、宿願成就ののちに宮社を建立し神像を安置したとの由。
頼朝公挙兵前から、盛長が武蔵の有力豪族の懐柔に動いていたことをうかがわせる内容です。
*******

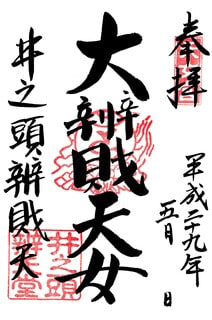
【写真 上(左)】 井之頭辨財天
【写真 下(右)】 井之頭辨財天の御朱印
盛長の邸宅は鎌倉の甘縄(現・甘縄神明神社付近)ないし扇ガ谷の無量寺谷付近とみられます。
当時の「甘縄」は無量寺谷までも含んでいたとされるので、無量寺谷説が有力かも。
(無量寺谷(むりょうじがやつ、現・鎌倉歴史文化交流館周辺)には安達氏の菩提寺とみられる無量寿院や安達氏邸があったと考えられ、発掘調査では鎌倉時代後期の遺跡が見つかり研究が進められています。)
しかし盛長の当初の本拠地については定説がみられません。
埼玉県鴻巣市糠田の糠田山 放光寺にはかつて安達盛長の館だったという伝承があり、南北朝時代制作とされる伝・安達盛長座像を所蔵しています。
鴻巣市糠田は足立氏の本拠に近く、盛長は足立遠元の叔父としてこの地に拠っていたということも考えられます。
放光寺の山内説明板には以下のとおりあります。
「放光寺の開基は、源頼朝の御旗奉行を務めた安達藤九郎盛長とされ、本堂にはこの盛長の坐像が安置されている。(略)安達藤九郎盛長は、治承四年(1180年)源頼朝の挙兵に応じて相模の地で功を挙げ、同国を安堵された。その後、盛長の所領は相模、下総、武蔵にまで及んだ。さらに建久五年(1194年)には頼朝の信任をうけて鶴岡八幡宮の奉公人となった。正治元年(1199年)1月の頼朝の死後出家したが、その後も北条時政や大江広元等とともに重要訴訟の調査・裁決などに係わるなど幕府の要職にあり、三河の守護に就いた。正治二年(1200年)に66歳で没した。」


【写真 上(左)】 放光寺
【写真 下(右)】 放光寺蔵の伝・安達盛長座像(山内説明板より)
放光寺の御朱印は通常不授与ですが、TVドラマ放送を記念し、2022年5月28日(土)14:00~16:00の2時間限定で開催された「安達藤九郎盛長坐像(埼玉県指定有形文化財)」の御開帳イベントでは御住職直筆の御朱印を複写したポストカードが限定配布された模様です。
御朱印イメージは → こちら。
御朱印尊格は大日如来。
主印は金剛界大日如来の種子「バン」(蓮華座+火焔宝珠)のようです。
華々しい逸話は少ないですが、雌伏の頼朝公をはやくから支えて千葉常胤を説得して味方につけ、あまたの合戦でも順調に戦歴を重ねていることから、並みの技倆ではなかったと思われます。
梶原景時の変ではとりまとめ役を果たしたという説があり、頼朝公逝去後、十三人の合議制に名を連ねていることからも相応の実力と人望を有していたのでは。
盛長の嫡男・景盛は宝治元年(1247年)の宝治合戦(北条時頼と三浦氏の抗争)で重要な役割を果たして北条氏の勝利・覇権確立に貢献。
幕閣での地位を高め、景盛は3代将軍実朝公と政子の信頼も厚かったといいます。
景盛の嫡男・義景(秋田城介)、その嫡男・泰盛は、北条氏と姻戚関係を強めたこともあり幕政の中枢を占めましたが、「新御式目」など幕政改革をめぐる御家人の内紛をきっかけに弘安八年(1285年)秋に勃発した「霜月騒動」の旗頭となって敗北し、安達一族はここに失脚しました。
泰盛党として蹶起したのは足利氏、小笠原氏、伊東氏、武藤氏(少弐氏)、宇都宮氏、吉良氏、足立氏などの有力御家人層で、この敗戦によりいずれも幕閣での政治力を失い北条得宗を中心とする専制が強まりました。
安達氏および関連氏族とされる大曾根氏は、江戸時代まで活動の記録がみられますが、最盛期は泰盛の代とされています。
上記のとおり、安達盛長の当初の本拠ははっきりせず、ゆかりの寺社も多くはみられません。
安達盛長の館と伝わる鴻巣・放光寺は御朱印不授与なので、ここでは邸宅跡と伝わる甘縄神明宮をご紹介します。
『新編鎌倉志』の藤九郎盛長屋敷に「甘縄明神の前、東の方を云。【東鏡】に、治承四年(1180年)十二月廿日、武衛御行始めとして、藤九郎盛長が甘縄の家に入御し給ふとあり。其後往々見へたり。」とあります。
頼朝公以来、将軍の来臨もしばしばあったといいます。
この邸址に御鎮座と伝わる甘縄神明宮は和銅三年(710年)行基の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社ともいわれます。
染屋時忠は山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立したといいます。
永保元年(1081年)源義家公が社殿を再建、以降も源頼朝公、政子の方、源実朝公などの崇敬が篤かったとされます。
源頼義公が相模守として下向の折に当宮に祈願して八幡太郎義家公が生まれたとも伝えられ、源家とつよいゆかりをもちます。
------------------------


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 参道-1
江ノ電「長谷」駅から長谷寺、鎌倉大仏へ向かう道は観光客で賑わいますが、長谷寺山門前から鎌倉駅方向へ向かう長谷小路は生活道路で、観光客の姿は少なくなります。
甘縄神明宮はこの長谷小路から参道が伸びていることもあって、人影のすくない落ち着いた神社です。
長谷小路沿いに木柱の社号標があるものの、目立たず見過ごしがちです。
それでも路地正面には石造の神明鳥居が見えています。
ここはちょうど由比ヶ浜の海岸からつづく平地が山手に差しかかるところで、鳥居おくに4つの階段を連ねています。

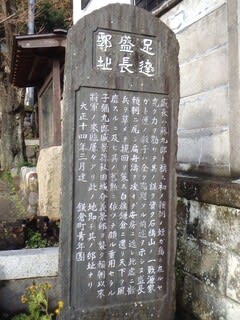
【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 邸址碑
踊り場に建つ「安達盛長邸址」碑には「盛長ハ藤九郎ト称ス 初メ頼朝ノ蛭ヶ島ニ在ルヤ 克ク力ヲ勠セテ其ノ謀ヲ資ク 石橋山ノ一戦源家ガ卜運ノ骰(さい)子ハ全く黯黮タル前途ヲ示シヌ 盛長頼朝ニ尾シ扁舟濤ヲ凌イデ安房ニ逃レ 此処ニ散兵ヲ萃(あつ)メテ挽回ヲ策ス 白旗鎌倉ニ還リ天下ヲ風靡スルニ及ビ 其ノ舊勲ニ拠ツテ頗ル重用セラル子彌九郎盛景 孫秋田城介義景邸ヲ襲グ 頼朝以来将軍ノ来臨屡々アリ 此ノ地即チ 其ノ邸址ナリ」とありました。
石灯籠二対のおくは急な階段となり、のぼりきると正面が銅板葺神明造(ないしは入母屋造流れ向拝)の拝殿です。
周囲はうっそうとした社叢におおわれ神さびて、長谷小路から少し入っただけなのにあたりの空気はまったく異質なものです。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
拝殿前に立派な二対の狛犬。
拝殿向拝の水引虹梁の装飾はシンプルですが、すこぶる均整がとれて風格があります。
向拝正面は板戸で閉扉。その上に「甘縄神明宮」の扁額。


【写真 上(左)】 五社神社
【写真 下(右)】 秋葉神社
境内社として五社神社と秋葉神社が御鎮座です。
境内掲示の略誌には、
御祭神 天照大神
伊邪那岐尊(白山)
倉稲魂命(稲荷)
武甕槌命(春日)
菅原道真公(天神)
とあるので、伊邪那岐尊以下の神々は五社神社祭祀かもしれません。
境内には北条時宗産湯の井があるようですが、超うかつにも写真を撮りわすれました。
北条時宗は鎌倉幕府第8代執権で、室の堀内殿は安達義景の息女。
北条時宗は安達景盛の息女・松下禅尼の邸で産まれ、それがこのあたりといいます。
松下禅尼の子、経時は第4第執権、時頼は第5第執権なので、この時代、安達氏は北条執権の外戚として絶大な権力を握っていたものと思われます。
なお、『徒然草』184段に松下禅尼が障子の切り貼りを手づからしてみせ、時頼に倹約の心を伝えたという逸話がみえ、国語教科書にも取り上げられていたそう。
鎌倉武士の質実剛健の心構えは、安達氏から北条執権家累代にもしっかり伝わっていたようです。
拝殿前には「当宮では御朱印は行っておりません」の掲示がありますが、大町八雲神社にて拝受できました。

甘縄神明宮の御朱印
41.(飯田)足立神社 〔足立右馬允遠元〕
埼玉県さいたま市西区飯田54
御祭神:天神七代尊、地神五代神、日本武尊、市杵島姫命、多岐都比売命、猿田彦命、大国主神、天手力男神、菊理姫命、倉稲御魂命、応神天皇、菅原道真公
旧社格:村社、延喜式内社論社(足立郡足立神社)
元別当:
武蔵国の御家人を代表する一人に足立右馬允遠元がいます。
足立氏は武蔵国足立郡に拠った豪族で、遠元の父・藤原遠兼が当地に土着し遠元の代から足立姓を名乗ったといいます。
『尊卑分脈』では藤原北家魚名流・藤原山蔭の後裔で、安達盛長は遠兼の弟としています。
そうなると安達盛長は足立遠元の叔父になりますが、史料からすると安達盛長よりも足立遠元の方が年長と推測されるので、この関係を疑う見方もあります。
『足立系図』(東大史料編纂所データベース)では、遠元は藤原北家勧修寺流・藤原朝忠の後裔となっています。
Wikipediaによると、武蔵国造家の流れで承平天慶の乱の時代の足立郡司・武蔵武芝の子孫とする説もあるようで、盛長以前の足立氏の系譜は錯綜しています。
諸説いずれも藤原氏ないし天孫系で、足立氏は自らの出自に矜持をもっていたと思われます。
多くの事績を遺しながら、足立遠元の生没年は伝わっておりません。
ゆかりの地の少なさも、鎌倉幕閣重鎮としては異例なほどです。
そのなかでも、桶川市はWebでよくまとまった資料を公開していますので、この資料やその他史料をベースにまとめてみたいと思います。
遠元は平治元年(1160年)の平治の乱で源義朝公に従って右馬允に任ぜられ、源義平率いる17騎の一人として活躍しました。
治承四年(1180年)夏の頼朝公旗揚げでは、頼朝公が下総から武蔵に入った10月2日に豊島清元・葛西清重父子らとともにいち早く参上し、武蔵国足立郡を本領安堵されています。
これは、頼朝公が東国武士に本領所有権を譲渡した最初の事例とみられています。
建久元年(1190年)、頼朝公上洛の際に右近衛大将拝賀の布衣侍7人(三浦義澄、千葉胤正、工藤祐経、後藤基清、葛西清重、八田知重、足立遠元)のうちに任ぜられ供奉。
鎌倉御家人の頂点のポジションを占めています。
頼朝公逝去後には十三人の合議制に名を連ね、晩年も相当の実力と人望を保っていたことがわかります。
母は秩父氏系の豊島康家の息女で、足立郡司職は豊島氏から承継との見方があります。
娘は畠山重忠、北条時房に嫁いで、有力御家人と縁戚関係を築いていました。
なお、畠山重忠に嫁いだ菊の前は、元久二年(1205年)、重忠が北条時政の謀略により討たれたときに自害と伝わります。
別の娘は後白河法皇の近臣の藤原光能に嫁ぎ、京との繋がりも深めています。
光能は永万元年(1165年)下野守に任ぜられているので、そのときに面識をもったのかもしれません。
この時点で院の近臣と縁戚関係をもった東国武士は少ないとされ、これも遠元のオリジナルな強みとなった可能性があります。
後世、どちらかというと文官的な捉え方をされる人物ですが、その武勇は『平治物語』の一幕からひしひしと感じられるので、長くなりますが抜粋引用してみます。
『平治物語/六波羅合戦事』
「金子ノ十郎家忠は(略)真先懸けて戦ひけり。矢種も皆射尽し、弓も引き折り、太刀をも折りければ、折太刀を提げて、あはれ太刀がな、今一合戦せんと思ひて駈け廻る処に、同国の住人足立右馬允遠元馳せ来れば、是れ御覧候へ、足立殿、太刀折れて候。御帯添(戦場で腰につける予備の太刀)候はば、御恩に蒙り候はんと申しければ、折節帯添なかりしかども、御邊が乞ふが優しきにとて、先を打たせたる郎等の太刀を取りて、金子にぞ与へける。家忠大ニ悦びて、又駈け入りて、敵数多討ちてけり。足立が郎党申しけるは(略)是程に見限られ奉りては、(略)既に腹を切らんと、上帯を押し切りければ、遠元馬より飛んで下り、汝が恨むる所尤も理なり。然れども、金子が所望黙止がたさに、御邊が太刀を取りつるなり。軍をするのも主のため、討死する傍輩に乞はれて、与えぬ者や侍らん。(略)」暫く待てといふ所に、敵三騎来りて、足立を討たんと駈け寄せたり。遠元、真前に進みたる武者を、能つ引いてひやうと射る。其の矢誤たず、内兜に立ちて、馬より真倒に落ちければ、残りの二騎は馬を惜んて駈けざりけり。遠元軈て走り寄りて、帯きたる太刀を引き切っておつ取り、汝が恨むる所尤なり。太刀とらするぞとて、郎党に与へ、打ち連れてこそ又駈けけれ。」
要約すると、武勇の士・金子家忠が激闘で太刀を失ったので、同輩の遠元に予備の太刀を貸してほしいと頼んだところ、予備の太刀のない遠元は郎党の太刀を取りあげてこれを家忠に与えました。
主君に太刀を取られた郎党は面目を失い切腹しようとするも、遠元はこれを押しとどめ、太刀を失った同輩(家忠)を見殺しにするわけにはいかぬ、しばし待てと諭しました。
そこへ討ち懸かった敵騎を遠元はすぐさま強弓一矢で射落とすやその太刀を取り上げ、郎党に「お前が恨みに思うのももっともだ。それ、太刀をとらすぞ」と、敵から取り上げた太刀を郎党に与え、気迫を取り戻した郎党とともに戦陣に駈け戻ったということです。
平治の乱の六波羅合戦といえば、名だたる武将がしのぎをけずった激戦です。
そのなかでこの逸話がとりあげられた足立遠元の戦ぶりは、戦場でも際立っていたのでは。
じっさい、平重盛との「待賢門の戦い」でも源氏17騎の一人として活躍しています。
これほどの武勇をもちながら公文所寄人に抜擢されるなど、文武両面に秀でた遠元は、しばしば京からの来賓の接待役に任ぜられています。
元暦元年(1184年)秋、公文所が設置されると5人の寄人(中原親能、二階堂行政、藤原邦通、大中臣秋家、足立遠元)の一人に選ばれています。
奥州合戦の勲功として頼朝公に御家人10人の推挙が与えられた際は、その一人に入り左衛門尉に任ぜられています。
とくに10人の推挙者は鎌倉御家人を代表する顔ぶれ(千葉常秀(父常胤→)、梶原景茂(父景時→)、八田知重(父知家→)、三浦義村(父義澄→)、葛西清重、和田義盛、佐原義連、小山朝政、比企能員、足立遠元)で、遠元は御家人屈指のポジションを占めていました。
奥州合戦勲功推挙の10人(武人の代表)と公文所寄人(文官の代表)、いずれにも名を連ねたのは足立遠元ただひとりで、ここからも文武両面から貢献する遠元の存在感がみてとれます。
遠元の記録は承元元年(1207年)3月で途絶えており、ほどなく世を去ったとみられています。
弘安八年(1285年)の霜月騒動で遠元の嫡曽孫・足立左衛門尉直元が安達泰盛側につき自害しているので、足立氏は霜月騒動までは安達氏と連携して勢力を保っていたのでは。
なお、この霜月騒動までには、足立氏の足立郡司職は北条氏に移ったとみられています。
霜月騒動で失脚した足立氏ですが、承久三年(1209年)、遠元の孫・遠政は丹波国氷上郡佐治庄の地頭職となり、佐治庄小倉に移っていました。
同地の山垣城(現・兵庫県丹波市青垣町)に拠った遠政は大いに勢力を張り、丹波の名門足立氏の祖となりました。
丹波足立氏は天正七年(1579年)5月に織田信長の丹波攻めを受け、山垣城は羽柴秀長と明智光秀の軍勢に攻められてついに落城。
丹波足立氏は戦国大名としては没落しましたが、いまも丹波の名族として知られています。
なので、足立氏ゆかりの史跡は関東よりも丹波に多く残ります。
遠元の本拠地は明らかになっていませんが、桶川市資料によると、遠元の館跡と伝わる場所は4か所あるそうです。
1.さいたま市西区内
2.桶川市川田谷の三ツ木城跡、
3.桶川市神明1丁目の諏訪雷電神社東側付近
4.末広2丁目の総合福祉センター付近
ただし、いずれの地も決定的な史料は見つかっていないそうです。
4は「一本杉」と呼ばれ、「新編武蔵風土記稿」の桶川宿の項に遠元館と伝わる地として記載されています。
ここでは、境内由緒書に「豪族足立氏が奉斎する氏神」と明記されている、さいたま市西区飯田の足立神社をご紹介します。
新編武蔵風土記稿には下記のとおりあります。
植田谷本村 足立神社
「名主勘太夫カ屋舗ノ内ニアリ(略)相傳ヘテ 延喜式神名帳ニ載スル足立神社ハ 即當社ナリト云 此説モシ然ランニハ 當國風土記ニ 神田六十束 四圍田 大日本根子彦太日天皇御宇二年戊子所祭猿田彦命也 有神戸巫戸等ト記スモノニシテ最古社ナリ(略)或ハ云シカハアラス當所ハ藤九郎盛長ノ領地ニシテ 在住セシヨシナレハ 盛長没後其靈ヲ祀リユヘ 足立ノ社ト號セシヲ 稱呼ノ同シケレハ誤リ傳ヘテ 神名帳ノ足立神社ト定メシモノナラント 是コト牽強ノ説トイウヘシ 盛長カ當郡ニ住セサルコトハ前ニ辨セルカ如シ モシクハ足立右馬允ヲ誤リ傳ヘシニヤ サレトソレモ慥カラル據ナキ時ハウケカヒカタシ」
「前ニ辨セル」とはおそらく植田谷本村の項で、以下のとおりあります。
「領主ハ詳ナラサレント 右大将頼朝ノ頃ハ藤九郎盛長此邊ヲ一圓領セシ由イヒ傳フレトオホツカナシ コレ恐ラクハ足立右馬允遠元ヲ誤リ傳ヘシナラン 此人當郡ヲ領セシコト且盛長ハ安達氏ニシテ足立氏ナラサルコト等ハ(略)」
まとめると、植田谷本村付近は鎌倉初期に藤九郎(安達)盛長の領地という言い伝えがあるが、これは誤りで、足立右馬允遠元の領地であるとしています。
そして、当初の領主は足立氏であり、安達氏ではないと念を入れています。
また、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)には下記のとおりあります。
「『延喜式』神名帳には、武蔵国足立郡内の神社として、氷川神社・足立神社・調神社・多気比売神社の四社の名が記されている。これらの諸社のうち、足立神社は、古代における殖田郷に鎮座し、この殖田郷を本拠地とした在地の豪族足立氏が奉斎した神社であったものと思われる。」
さらに境内掲示の説明書には以下のとおりあります。
「足立神社は、平安時代にその名が見える古い神社です。植水地区を中心とした殖田郷に本拠をおいた平安時代の豪族足立氏が奉斎する氏神でしたが、崇敬者も増え朝廷の『延喜式神名帳』に登載されるほどになりました。この神名帳にみえる足立神社だとする社が、浦和市・鴻巣市・市内宮原町にもありますが、『新編武蔵風土記稿』では足立氏の子孫と伝える植田谷本村の名主小島勘太夫家屋敷内にあった足立神社をそれと記しています。
この足立神社は明治40年に植田谷地内の12社を合祀して、氷川神社の社号を足立神社と改称したものです。」
------------------------


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 社号標
(飯田)足立神社は、所沢と大宮を結ぶ県道56号さいたまふじみ野所沢線沿いに御鎮座です。
荒川と鴨川に挟まれた低湿の地ですが、水利はよさそうです。
県道に面して社号の幟旗がはためいていましたが、これは正月だったからかもしれません。
県道に面して玉垣、右手に「総社 足立神社」の社号標とその先に石造の神明鳥居。
鳥居前には「足立遠元公」の幟がはためいています。


【写真 上(左)】 参道と鳥居
【写真 下(右)】 参道
そこからまっすぐ拝殿に向かって参道が伸び、二の鳥居は朱塗りの明神鳥居です。
全体に社叢がすくなく、明るく開けた雰囲気の境内。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 扁額
拝殿は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁はシンプル。
向拝上には社号扁額が掲げられています。
本殿はおそらく大がかりな一間社流造銅板葺で、身舎の朱塗りが鮮やか。


【写真 上(左)】 拝殿と本殿
【写真 下(右)】 御嶽神社
境内には立派な御嶽神社も御鎮座です。
参道向かって右手に社務所。
こちらは原則、正月や祭礼時のみの御朱印授与のようですが、正月に参拝したので社務所は開き、御朱印も直書で授与されていました。


【写真 上(左)】 御朱印案内
【写真 下(右)】 御朱印
足立遠元ゆかりで御朱印を授与されている寺社はこちらしか確認できておらず、しかも限定授与なので遅くなりましたが、ようやく記事にまとめることができました。
【 BGM 】
■ I.G.Y. - Donald Fagen
■ Oh Yeah! - Roxy Music
■ Our Love - Michael McDonald
■ Isn't It Time - Boz Scaggs
■ Both Sides Now - Marc Jordan
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県富士見市・ふじみの市・三芳町の御朱印
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印にまとめていましたが分離し御朱印を追加して別記事としました。
【エリア概要】
東武東上線のみずほ台~上福岡。
南は志木、北は川越、西は所沢、東は荒川を介してさいたま市に接するエリア。
川越の南側にあたるこのエリアは、江戸方面への物資(農産物・燃料など)供給地として農村が広がり、大きな街道もなかったため霊場札所はさほど多くない。
また、日蓮宗寺院もすくないエリア。
荒川・新河岸川沿いは低平地、東武東上線以西は武蔵野台地上にあり、とくに三芳町では典型的な武蔵野の風景が広がる。
観光地としてはあまり知られていないが、農産物直売所の商品のレベルの高さは県内でも屈指でさりげにドライブ向きのエリアでもある。
【富士見市・ふじみの市・三芳町と札所】
上記のとおりこのエリアを中核とする霊場は、弘法大師霊場、観音霊場ともに確認されていない。
関東九十一薬師霊場の瑠璃光寺(富士見市)、武州路十二支霊場の大應寺(富士見市)がみられる程度だが、大應寺は最近東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉8番の札所になっており、御朱印帳を頒布するなど札所機能を高めている模様。
神社では水宮神社(富士見市)と榛名神社(富士見市)が複数の兼務社の御朱印を授与されているが、常時授与かどうかは不明。
一部の非札所寺院や鎮守社でも授与されているので一定数の御朱印は拝受できるものの、授与期間が限定されていたりご不在があったりで、御朱印難易度は比較的高い。
御朱印エリア、川越と所沢にはさまれた、どちらかというとマニア向けのエリアとなっている。
【拝受データ】 (おおむね南部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
■ (針ヶ谷ノ)氷川神社


富士見市針ケ谷1-39-2
御祭神:素盞嗚尊
旧社格:村社、旧針ケ谷村鎮守
元別当:西光院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:針ヶ谷 氷川神社 直書(筆書)
■ (水子)氷川神社


富士見市水子5050
御祭神:素盞嗚尊、奇稲田姫尊
旧社格:旧水子村総鎮守
元別当:福性寺
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:水子 氷川神社 直書(筆書)
■ (水子・正網)八幡神社

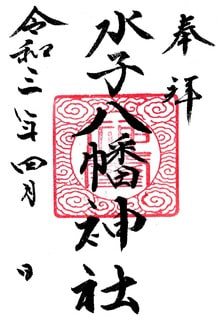
富士見市水子5084
御祭神:誉田別尊
旧社格:
元別当:薬師寺→大應寺
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:水子 八幡神社 直書(筆書)
■ 智永山 性蓮寺

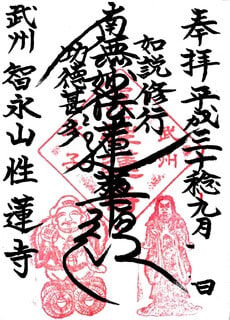
富士見市水子5082
日蓮宗
御首題
■ 水宮神社


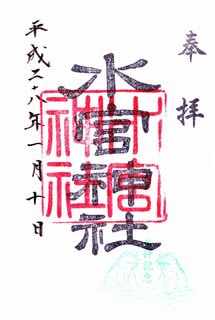
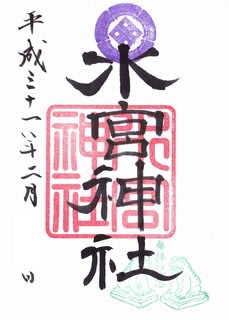
富士見市水子1762
御祭神:天照大神、素戔鳴命、木花開耶姫命、誉田別命、大國主命、罔象女神
元別当:神仏習合/摩訶山般若院
授与所:当社授与所
朱印揮毫:水宮神社(印判書置/直書)
※週末はタイミングにより書入御朱印拝受可の模様
■ 摩訶山 般若院 六蛙堂

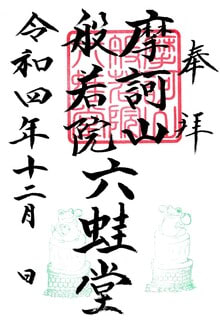
富士見市水子1762
堂宇尊格:役行者、不動明王ほか
元別当:神仏習合/摩訶山般若院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:摩訶山 般若院 六蛙堂 直書(筆書)
■ 水光山 不動院 大應寺


富士見市水子1765
真言宗智山派
御本尊:不動明王
司元別当:(水子・正網)八幡神社
札所:武州路十二支霊場(巳 普賢菩薩)

朱印尊格:本尊 普賢尊(普賢菩薩)
主印:種子/不詳 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
札所:東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉8番

朱印尊格:不動明王
主印:種子「カン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:あり
直書(規定)
〔御本尊〕

朱印尊格:本尊 不動明王
主印:種子「カン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
〔薬師堂〕

朱印尊格:薬師如来
主印:種子「バン」・金剛界大日如来 (蓮華座+火焔宝珠)
※揮毫は種子「バイ」・薬師如来
札所印:なし
直書(筆書)
〔観音堂〕
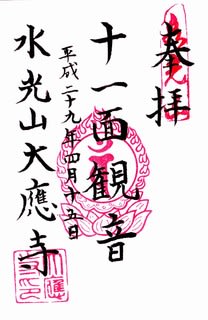
朱印尊格:十一面観音
主印:種子「バン」・金剛界大日如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
■ (北側・上水子ノ)氷川神社

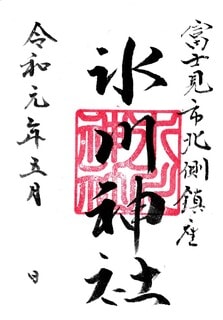
富士見市水子1399
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:無格社、旧水子第一区の鎮守
元別当:
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:富士見市北側鎮座 氷川神社 直書(筆書)
■ (山形)氷川神社


富士見市下南畑153
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:下南畑の旧山形地区鎮守
元別当:西廓山 万蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:山形 氷川神社 直書(筆書)
■ (下南畑)八幡神社

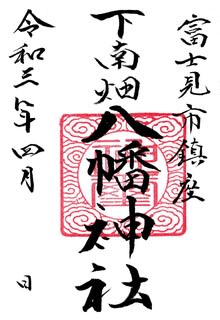
富士見市下南畑1148
御祭神:誉田別之命、神功皇后、姫大神、阿蘇津姫命、菅原道真公、北極星
旧社格:村社、旧下南畑村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:金蔵院・西蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:下南畑 八幡神社 直書(筆書)
■ 川龍山 興禅寺

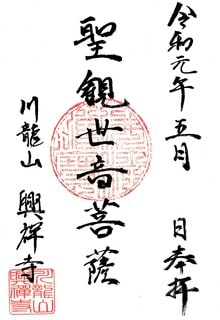
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
朱印尊格:聖観世音菩薩
主印:三寶印
札番:なし 直書(筆書)
■ 上南畑神社


富士見市上南畑295
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:村社、旧上南畑村鎮守
元別当:金蔵院・西蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:上南畑神社 直書(筆書)
■ 阿蘇神社

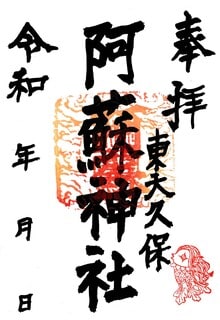
富士見市東大久保83
御祭神:阿蘇比女之命
旧社格:村社
元別当:神明山観音寺
授与所:勝瀬榛名神社社務所(宮司様宅)
朱印揮毫:東大久保 阿蘇神社 書置(筆書)
■ 寳瀧山 延命院 瑠璃光寺(鶴馬薬師)



富士見市諏訪1-8-3
天台宗
御本尊:薬師如来
札所:関東九十一薬師霊場第31番
朱印尊格:薬師如来・瑠璃殿(薬師如来)
主印:種子「バイ」・薬師如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東九十一薬師霊場第31番印判
■ 氷川神社

富士見市諏訪1-13-24
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:村社、旧鶴間村上組鎮守
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)、来迎寺、三光院?
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ 諏訪神社

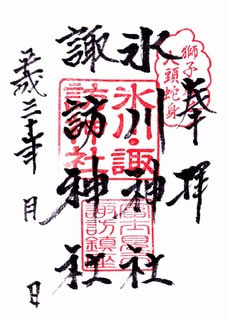
富士見市諏訪2-15-34
御祭神:建御名方之命
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ (下鶴馬)氷川神社

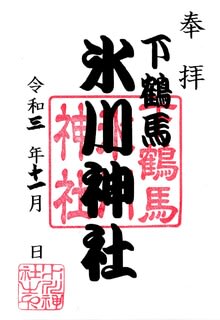
富士見市鶴間2-1-72
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:村社、旧鶴間村鎮守
元別当:来迎寺・三光院
授与所:宮司様
朱印揮毫:下鶴間 氷川神社
■ (勝瀬)榛名神社


富士見市勝瀬791
御祭神:埴上姫命、豊受姫命
旧社格:村社、勝瀬総鎮守
元別当:萬寶院
授与所:宮司様宅(当社からは離れています)
朱印揮毫:榛名神社 書置(筆書)
■ 見峰山 大願寺


富士見市勝瀬字寺山470-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
朱印尊格:瑞光観音
主印:聖観世音菩薩御影印
札所印:なし
直書(筆書)
■ 三富山 多福寺



三芳町上富1542
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:関東百八地蔵尊霊場第8番
朱印尊格:子育地蔵尊(地蔵菩薩(木ノ宮地蔵尊))
主印:三寶印
札所印:なし
印刷(規定)
※御本尊の御朱印は授与なし、護持堂の「木ノ宮地蔵堂」の御朱印を授与
■ (大井)氷川神社


ふじみ野市大井2-4-30
御祭神:素戔嗚尊、奇稲田姫命、大己貴命
旧社格:村社
元別当:天龍山 徳性寺(ふじみ野市大井)
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:大井 氷川神社 書置(筆書)
■ (苗間)神明神社

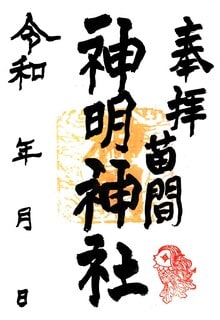
ふじみ野市苗間372-1
御祭神:天照大神
旧社格:村社、旧苗間村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:浄禅寺
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:苗間 神明神社 書置(筆書)
■ 佉羅陀山 地蔵院 薬王寺


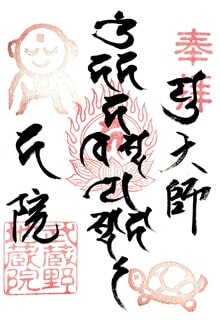
ふじみ野市亀久保3-11-11
真言宗智山派
御本尊:延命地蔵菩薩
札所:-
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
■ (上福岡)八雲神社


ふじみ野市上福岡1-7-7
御祭神:須佐之男命
旧社格:
元別当:
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:上福岡 八雲神社 書置(筆書)
■ 朝日天神神社(神道大教 天神大教会)

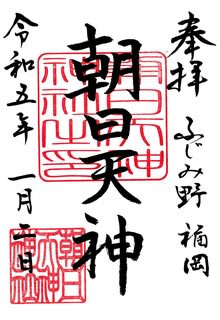
ふじみ野市西原1-1-18
御祭神:天之御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、伊弉那岐命、伊弉那美命
旧社格:
元別当:
授与所:境内授与所
朱印揮毫:朝日天神 直書(筆書)
■ 長宮氷川神社


ふじみ野市長宮 2-2-4
御祭神:建速須佐之男命、奇稲田姫命、大己貴命
旧社格:郷社、旧福岡村・旧中福岡村・福岡新田鎮守
元別当:
授与所:社務所(正月、祭礼時のみ)
朱印揮毫:長宮氷川神社 直書(筆書)
■ (駒林)八幡神社


ふじみ野市駒林890-イ
御祭神:誉田別命
旧社格:村社、旧駒林村鎮守
元別当:安楽寺(旧駒林村)
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:駒林 八雲神社 書置(筆書)
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印(分離前旧ページ)
■ 埼玉県所沢市の御朱印
■ 朝霞五社巡り
■ 志木開運・招福七社参り-1
■ 志木開運・招福七社参り-2
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熊谷市・深谷市の御朱印-1
■ 箱根の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】
■ 根岸古寺めぐり
■ 滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
■ 武州八十八霊場
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 谷中の御朱印・御首題
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 徳川家康公と御朱印
【BGM】
■ 堤防 - 二名敦子
G
■ 雨のウエンズデイ - 大滝詠一
■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
【エリア概要】
東武東上線のみずほ台~上福岡。
南は志木、北は川越、西は所沢、東は荒川を介してさいたま市に接するエリア。
川越の南側にあたるこのエリアは、江戸方面への物資(農産物・燃料など)供給地として農村が広がり、大きな街道もなかったため霊場札所はさほど多くない。
また、日蓮宗寺院もすくないエリア。
荒川・新河岸川沿いは低平地、東武東上線以西は武蔵野台地上にあり、とくに三芳町では典型的な武蔵野の風景が広がる。
観光地としてはあまり知られていないが、農産物直売所の商品のレベルの高さは県内でも屈指でさりげにドライブ向きのエリアでもある。
【富士見市・ふじみの市・三芳町と札所】
上記のとおりこのエリアを中核とする霊場は、弘法大師霊場、観音霊場ともに確認されていない。
関東九十一薬師霊場の瑠璃光寺(富士見市)、武州路十二支霊場の大應寺(富士見市)がみられる程度だが、大應寺は最近東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉8番の札所になっており、御朱印帳を頒布するなど札所機能を高めている模様。
神社では水宮神社(富士見市)と榛名神社(富士見市)が複数の兼務社の御朱印を授与されているが、常時授与かどうかは不明。
一部の非札所寺院や鎮守社でも授与されているので一定数の御朱印は拝受できるものの、授与期間が限定されていたりご不在があったりで、御朱印難易度は比較的高い。
御朱印エリア、川越と所沢にはさまれた、どちらかというとマニア向けのエリアとなっている。
【拝受データ】 (おおむね南部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
■ (針ヶ谷ノ)氷川神社


富士見市針ケ谷1-39-2
御祭神:素盞嗚尊
旧社格:村社、旧針ケ谷村鎮守
元別当:西光院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:針ヶ谷 氷川神社 直書(筆書)
■ (水子)氷川神社


富士見市水子5050
御祭神:素盞嗚尊、奇稲田姫尊
旧社格:旧水子村総鎮守
元別当:福性寺
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:水子 氷川神社 直書(筆書)
■ (水子・正網)八幡神社

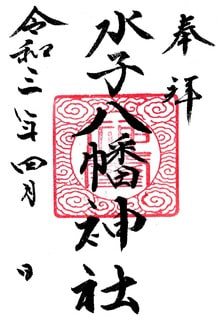
富士見市水子5084
御祭神:誉田別尊
旧社格:
元別当:薬師寺→大應寺
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:水子 八幡神社 直書(筆書)
■ 智永山 性蓮寺

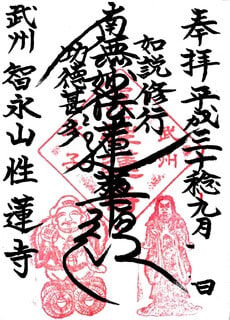
富士見市水子5082
日蓮宗
御首題
■ 水宮神社


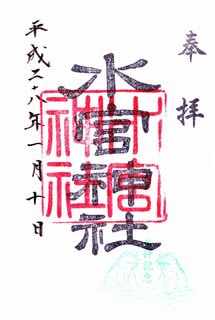
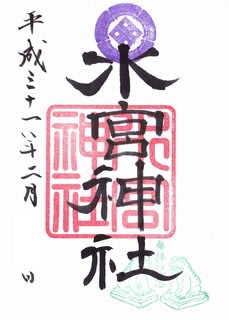
富士見市水子1762
御祭神:天照大神、素戔鳴命、木花開耶姫命、誉田別命、大國主命、罔象女神
元別当:神仏習合/摩訶山般若院
授与所:当社授与所
朱印揮毫:水宮神社(印判書置/直書)
※週末はタイミングにより書入御朱印拝受可の模様
■ 摩訶山 般若院 六蛙堂

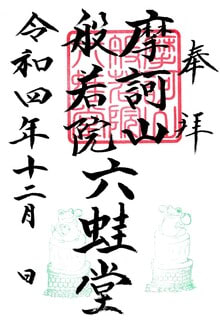
富士見市水子1762
堂宇尊格:役行者、不動明王ほか
元別当:神仏習合/摩訶山般若院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:摩訶山 般若院 六蛙堂 直書(筆書)
■ 水光山 不動院 大應寺


富士見市水子1765
真言宗智山派
御本尊:不動明王
司元別当:(水子・正網)八幡神社
札所:武州路十二支霊場(巳 普賢菩薩)

朱印尊格:本尊 普賢尊(普賢菩薩)
主印:種子/不詳 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
札所:東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉8番

朱印尊格:不動明王
主印:種子「カン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:あり
直書(規定)
〔御本尊〕

朱印尊格:本尊 不動明王
主印:種子「カン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
〔薬師堂〕

朱印尊格:薬師如来
主印:種子「バン」・金剛界大日如来 (蓮華座+火焔宝珠)
※揮毫は種子「バイ」・薬師如来
札所印:なし
直書(筆書)
〔観音堂〕
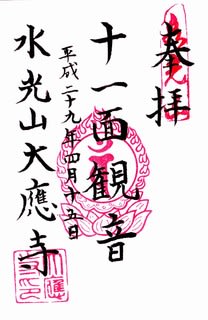
朱印尊格:十一面観音
主印:種子「バン」・金剛界大日如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
■ (北側・上水子ノ)氷川神社

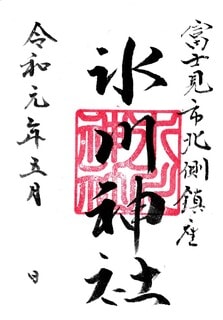
富士見市水子1399
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:無格社、旧水子第一区の鎮守
元別当:
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:富士見市北側鎮座 氷川神社 直書(筆書)
■ (山形)氷川神社


富士見市下南畑153
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:下南畑の旧山形地区鎮守
元別当:西廓山 万蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:山形 氷川神社 直書(筆書)
■ (下南畑)八幡神社

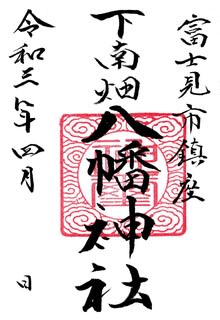
富士見市下南畑1148
御祭神:誉田別之命、神功皇后、姫大神、阿蘇津姫命、菅原道真公、北極星
旧社格:村社、旧下南畑村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:金蔵院・西蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:下南畑 八幡神社 直書(筆書)
■ 川龍山 興禅寺

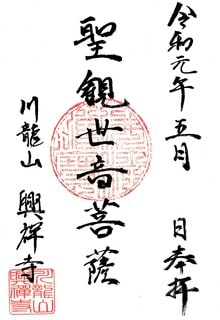
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
朱印尊格:聖観世音菩薩
主印:三寶印
札番:なし 直書(筆書)
■ 上南畑神社


富士見市上南畑295
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:村社、旧上南畑村鎮守
元別当:金蔵院・西蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:上南畑神社 直書(筆書)
■ 阿蘇神社

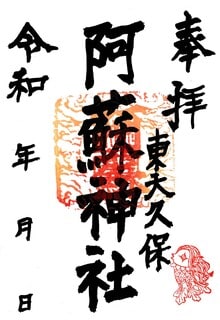
富士見市東大久保83
御祭神:阿蘇比女之命
旧社格:村社
元別当:神明山観音寺
授与所:勝瀬榛名神社社務所(宮司様宅)
朱印揮毫:東大久保 阿蘇神社 書置(筆書)
■ 寳瀧山 延命院 瑠璃光寺(鶴馬薬師)



富士見市諏訪1-8-3
天台宗
御本尊:薬師如来
札所:関東九十一薬師霊場第31番
朱印尊格:薬師如来・瑠璃殿(薬師如来)
主印:種子「バイ」・薬師如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東九十一薬師霊場第31番印判
■ 氷川神社

富士見市諏訪1-13-24
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:村社、旧鶴間村上組鎮守
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)、来迎寺、三光院?
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ 諏訪神社

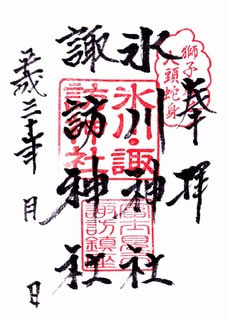
富士見市諏訪2-15-34
御祭神:建御名方之命
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ (下鶴馬)氷川神社

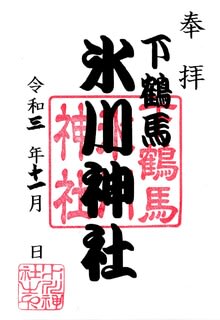
富士見市鶴間2-1-72
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:村社、旧鶴間村鎮守
元別当:来迎寺・三光院
授与所:宮司様
朱印揮毫:下鶴間 氷川神社
■ (勝瀬)榛名神社


富士見市勝瀬791
御祭神:埴上姫命、豊受姫命
旧社格:村社、勝瀬総鎮守
元別当:萬寶院
授与所:宮司様宅(当社からは離れています)
朱印揮毫:榛名神社 書置(筆書)
■ 見峰山 大願寺


富士見市勝瀬字寺山470-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
朱印尊格:瑞光観音
主印:聖観世音菩薩御影印
札所印:なし
直書(筆書)
■ 三富山 多福寺



三芳町上富1542
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:関東百八地蔵尊霊場第8番
朱印尊格:子育地蔵尊(地蔵菩薩(木ノ宮地蔵尊))
主印:三寶印
札所印:なし
印刷(規定)
※御本尊の御朱印は授与なし、護持堂の「木ノ宮地蔵堂」の御朱印を授与
■ (大井)氷川神社


ふじみ野市大井2-4-30
御祭神:素戔嗚尊、奇稲田姫命、大己貴命
旧社格:村社
元別当:天龍山 徳性寺(ふじみ野市大井)
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:大井 氷川神社 書置(筆書)
■ (苗間)神明神社

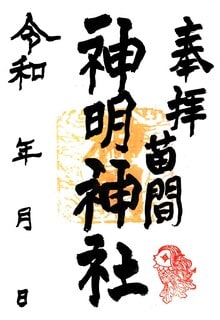
ふじみ野市苗間372-1
御祭神:天照大神
旧社格:村社、旧苗間村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:浄禅寺
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:苗間 神明神社 書置(筆書)
■ 佉羅陀山 地蔵院 薬王寺


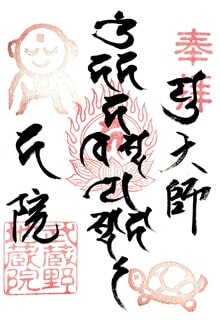
ふじみ野市亀久保3-11-11
真言宗智山派
御本尊:延命地蔵菩薩
札所:-
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
■ (上福岡)八雲神社


ふじみ野市上福岡1-7-7
御祭神:須佐之男命
旧社格:
元別当:
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:上福岡 八雲神社 書置(筆書)
■ 朝日天神神社(神道大教 天神大教会)

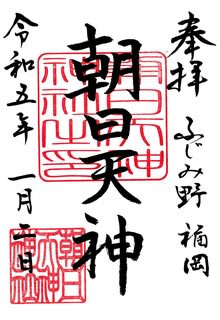
ふじみ野市西原1-1-18
御祭神:天之御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、伊弉那岐命、伊弉那美命
旧社格:
元別当:
授与所:境内授与所
朱印揮毫:朝日天神 直書(筆書)
■ 長宮氷川神社


ふじみ野市長宮 2-2-4
御祭神:建速須佐之男命、奇稲田姫命、大己貴命
旧社格:郷社、旧福岡村・旧中福岡村・福岡新田鎮守
元別当:
授与所:社務所(正月、祭礼時のみ)
朱印揮毫:長宮氷川神社 直書(筆書)
■ (駒林)八幡神社


ふじみ野市駒林890-イ
御祭神:誉田別命
旧社格:村社、旧駒林村鎮守
元別当:安楽寺(旧駒林村)
授与所:(勝瀬)榛名神社宮司様宅
朱印揮毫:駒林 八雲神社 書置(筆書)
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印(分離前旧ページ)
■ 埼玉県所沢市の御朱印
■ 朝霞五社巡り
■ 志木開運・招福七社参り-1
■ 志木開運・招福七社参り-2
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熊谷市・深谷市の御朱印-1
■ 箱根の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】
■ 根岸古寺めぐり
■ 滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
■ 武州八十八霊場
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 谷中の御朱印・御首題
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 徳川家康公と御朱印
【BGM】
■ 堤防 - 二名敦子
G
■ 雨のウエンズデイ - 大滝詠一
■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。
また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
(新?)第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11からつづく。
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)
第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12
旧第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)
第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)
第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)
第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)
第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 旧第85番 授寶山 大聖寺(だいしょうじ)
西伊豆町観光協会Web
西伊豆町安良里315
臨済宗円覚寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:-
授与所:龍泉寺(西伊豆町安良里浜川東14、現行の対応不明)
伊豆八十八ヶ所霊場の第85番札所でしたが、平成31年4月24日より沼津市西浦江梨の満行山 航浦院(旧別格第8番)に交替している模様です。
新旧いずれも巡拝し、御朱印を拝受しているのでご紹介します。
禅刹ながら密寺系の教不動尊霊場のイメージが強い古刹です。
『豆州志稿』『こころの旅』掲載の旧記によると、当山御本尊の不動尊は聖徳太子が刻され、文覚上人が苦行中に授けられた尊像で、かつては大きな滝のそばに御座していたといいます。
後醍醐帝の御代(1288-1339年)泰庵阿闍梨が現在地に不動尊を遷し奉安されて、真言宗寺院を開創と伝わります。
天文年間(1532-1555年)に臨済宗の高岳妙本(光嶽和尚とも)が山号を授寶山、寺号を大聖寺と号され臨済宗に改めて、奈古谷の國清寺の配下になりました。
西伊豆町Web資料によると、御本尊の不動明王は「波切不動」とも呼ばれ、安政の大地震による大津波がここで止まったと伝わるそうです。
御本尊は秘仏で、甲子に本開帳、甲午に中開帳で30年に一度の御開帳です。
『豆州志稿』には「安良里村 臨済宗円覚寺派 田方郡奈古谷國清寺末 本尊不動 大瀑布ニ石不動ノ古佛アリキ 後醍醐帝ノ時(1288-1339年) 泰庵阿闍梨此寺ヲ●メ 不動ヲコヽニ移ス 伊豆峯記ニ此寺ヲ不動ノ別当トス 泰庵善書ノ名アリ 大般若経ノ内三百巻ヲ謄写シテ伊濱普照寺ニ収ム 泰庵ヨリ後二百余年 光嶽和尚ノ時 真言ヲ改メ國清寺ニ隷ス(時ニ天文中(1532-1555年)ナリ) 舊記及泰庵ノ傳皆焼亡シヌ 近頃戌子ノ山水ニ寺押流サレテ 今草堂ノ如シ」とあります。
-------------------
この霊場は西伊豆町に入ると急に札所間の距離が長くなります。
仁科の第84番法眼寺から伊豆西海岸沿いに国道136号を北上し、堂ヶ島、田子の集落を通過して到着した安良里の港町から数百m山側に入ったところにあります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 駐車場から
山内は急斜面の山肌ですが、登り口に駐車場がありアプローチは比較的楽です。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 手水舎
参道入口の橋を渡って鐘楼の先から急な階段が始まります。
右手はうっそうとした森のなかに小滝が連続し、傍らには石像や石碑が並んでパワスボ的オーラを放っています。
もしかするとこちらが本来の不動尊霊場だったのかもしれません。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 不動尊の石像
参道階段両脇には「大聖不動明王」の赤いのぼりがたち並び、不動尊霊場の趣きゆたか。
昇り切った正面が本堂。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝平入りで、堂前に狛犬二対を配しています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝-1
水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に迫力のある龍の彫刻で見応えがあります。
正面桟唐戸でその上に山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
大聖寺は現在この霊場の札所ではないので、霊場巡拝者はほぼいないかと思います。
30年に一度の御開帳を待つ、静かな不動尊霊場に戻ったのでしょうか。
御朱印は円覚寺百観音霊場第35番の龍泉寺(西伊豆町安良里浜川東14)で拝受していますが、現在の御朱印対応は不明です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王 /主印はいずれも御寶印(種子「バン?」)
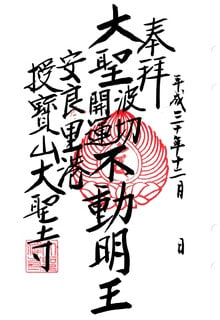

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第86番 吉祥山 安楽寺(あんらくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報Web
伊豆市観光協会土肥支部Web
伊豆市土肥711
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
土肥は松崎とならぶ西伊豆の要衝ですが、松崎に多くの札所があったのに対し土肥にはわずか1札所と対照的です。
大聖寺が札所から外れた現在、第84番仁科の法眼寺から長駆しての到着です。
土肥は西伊豆を代表する温泉地で、土肥金山の観光施設もあるため西伊豆観光では外せません。
こちらは金山採掘中の坑道より温泉が湧出し、入浴したところ病気が平癒したといういわれが残る「まぶ湯」のあるお寺です。
「まぶ湯」は土肥温泉発祥の湯とされ、「医王泉」「鉱山の湯」「砂金風呂」とも呼ばれて、かつては多くの人が薬効を求めて入浴しましたが、現在は入浴できません。
創建は天智天皇二年(663年)ともされる古刹で、行基菩薩が当地巡錫の際、国家鎮護の本地であると祭祀され、自ら釈迦如来像を彫り上げて奉安したのが創始と伝わります。
当初は密宗で医王山大泉寺と号しました。
一時衰退したものの天文三年(1534年)、大用精賢禅師(最勝院8世)が再興され寺号を安楽寺に改め、曹洞宗となりました。
『豆州志稿』には「土肥村 曹洞宗 賀茂郡宮上最勝院末 本尊釋迦 密宗ノ古刹ニシテ大泉寺ト号ス 天文中(1532-1555年)僧大用再興シテ安楽寺ト改ム 吾寶(最勝院開山)ノ徒大用和尚(最勝院八世)ノ時ヨリ宮上最勝院下ト為ル 大用ハ永禄二年(1559年)化ス(略)寺域ニ鉱湯アリ 采金鉱ヨリ湧出ス(千手院寺域)」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 大クス


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 寺号標
土肥港に注ぐ山川の山側にありますが、ほぼ土肥市街の中心エリアです。
山内入口に切妻屋根銅板葺の大ぶりの薬医門で山号扁額を掲げています。
門前に寺号標。
門前にあるクスは推定樹齢1000年、樹高25m、根回り14.2mの巨木で「安楽寺のクス」として静岡県指定天然記念物に指定されています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
南向きの明るい山内で、参道まわりは庭園をなして風趣があります。
石橋を渡り、右に鐘楼、正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 札所標

 【写真 上(左)】 本堂
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺で隅棟の長い、やや変わった意匠です。
向拝正面格子扉の上に掲げられた扁額は、達筆すぎて読めません。
軒裏は二軒の疎垂木ながら、どこか存在感があります。


【写真 上(左)】 分析表
【写真 下(右)】 地蔵尊
本堂内には「まぶ湯」のお寺らしく、明治37年の分析表が掲げられていました。
泉温77度、固形物総量1.624g/kgの塩類泉で石膏泉系の泉質と思われます。
本堂手前向かって右に誕生佛。左に聖観世音菩薩の立像。
別に地蔵堂があって、端正な地蔵菩薩立像が御座されています。


【写真 上(左)】 まぶ湯入口
【写真 下(右)】 まぶゆ地蔵
「まぶ湯」は山内山手にあり、庫裡で拝観料を払ってから入坑します。
入口に掲示の由来書によると、慶長十五年(1610年)当地に金鉱があり間部彦平がここから金を採掘していたところ、当山住職家翁隣仙大和尚が病を患いました。
当山の薬師如来に二十一日間の病平癒の祈願をおこなったところ、満願の日に「汝にいで湯を授けん」とのお告げがありました。
すると金鉱の岩間から霊湯が湧出しました。
すぐに金の採掘を止め、大和尚が薬師如来を拝しつつ湯浴みしたところ、病はたちまち癒えました。
大和尚のみならず、湯浴みした病人はいずれも平癒したので病に霊験あらたかと伝わり、遠近から湯治客が集まりました。
人々は金鉱から湧出したことからこのお湯を「鉱(まぶ)の湯」と名づけ、あり難く湯浴みにいそしんだといいます。


【写真 上(左)】 坑口
【写真 下(右)】 湯溜め槽と湯かけ地蔵尊


【写真 上(左)】 坑内
【写真 下(右)】 夫婦神社
入口の数体の「まぶゆ地蔵尊」。
棟門の向こうに入口が見えます。
坑内に湯溜め槽はありますが現在は入浴できず、槽の脇に御座す湯かけ地蔵尊の患部と同じところに、病気平癒を祈念しつつお湯を掛けると霊験ありとされています。
坑内各所には石膏らしき析出が出て、温泉湧出坑であることを物語ります。
坑内の最奥には子宝祈願にご利益あらたかとされる夫婦神社が御鎮座で、御神体がお祀りされています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
観光客の参詣も多いためか、手慣れたご対応でした。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ 土肥温泉 「屋形共同浴場」の入湯レポ
■ 第87番 専修山 大行寺(だいぎょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
沼津市Web
沼津市戸田926
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:本堂
土肥からふたたび長駆し、戸田の第87番大行寺に向かいます。
戸田も古くからの西伊豆の要衝ですが、伊豆にしてはめずらしく温泉がありませんでした。
昭和61年、念願の温泉掘削に成功し晴れて西伊豆の温泉地に名を連ねました。
戸田湾周辺は「駿河トラフ」に位置し、最深部は水深2,500メートルにも達します。
ここに富士山の豊富な湧き水が注ぎ、他ではみられないめずらしい魚種が揚がります。
なかでもタカアシガニと手長エビ(アカザエビ)はグルメ垂涎のレアアイテムで、これを求めて多くの観光客が訪れます。
戸田から駿河湾越しに眺める富士山は絶景で、温泉、グルメ、眺望の三拍子揃った観光地として近年人気を集めています。
大行寺は戸田のほぼ街なか、大川の河畔にある浄土宗寺院です。
火災により寺伝等を焼失しているので、情報の少ないお寺さまです。
『豆州志稿』には「天正四年(1576年)僧三譽創立 観音堂在寺域」とあるのみです。
『こころの旅』には天正四年(1576年)心蓮社三譽上人を開山とし、宗祖法然上人直示の「専修称名念仏」の教示を得て山・院号として草創とあります。
こちらは幕末の歴史で知られています。
安政年間(1855-1860年)、来日中のロシア使節プチャーチン提督は、安政東海大地震により座乗鑑ディアナ号を失い、代鑑建造のため戸田に滞在していました。
幕府は先に締結した和親条約改訂のため、勘定奉行・川路聖謨を全権特使として戸田へ出向させ、川路は大行寺を応接所として交渉にあたりました。
当山はこの歴史を受け「日露交渉地跡大行寺」として、沼津市の史跡に指定されています。
現在の建物は入浜の旧水野領の名主・斎藤本家邸を移築したもので、民家の移築につき本堂は書院造りとなっています。
『豆州志稿』には「戸田村 浄土宗 東京芝増上寺末 本尊阿彌陀 天正四年(1576年)僧三譽創立 観音堂在寺域」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 大川と大行院
【写真 下(右)】 山内入口


【写真 上(左)】 札所案内
【写真 下(右)】 山内
大川の河畔に面した寺院。山門はなく、門柱が山内入口になります。
正面に背後に山を背負って本堂。


【写真 上(左)】 六字御名号
【写真 下(右)】 寺号標
上記のとおり民家の移築なので書院造りですが、外観は寄棟造桟瓦葺で向拝を附設しています。
向拝見上げに山号扁額。そのうえに笈形付大瓶束と棟上に鬼板を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
山内の一画に宝形造銅板葺の堂宇があり、扁額に「施無畏」とあるので観音堂とみられます。
こちらの観音堂には海中出現と伝わる秘仏の聖観世音菩薩像が御座し、4年に一度の御開帳です。


【写真 上(左)】 観音堂?
【写真 下(右)】 観音堂?の向拝
また、山内のソテツは「大行寺の蘇鉄」として天然記念物に指定されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

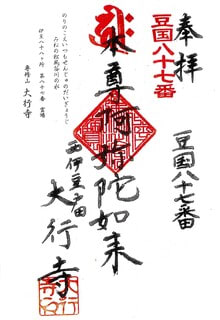
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ 戸田温泉 「壱の湯」の入湯レポ
■ 第88番 奥の院 正覚院
伊豆市観光情報Web
伊豆市観光ガイドWeb
伊豆半島ジオパークWeb
伊豆市観光協会修善寺支部Web
伊豆市修善寺2940-1
宗派:
御本尊:
札所本尊:
他札所:-
授与所:庫裡ないし第88番修禅寺
戸田の第87番大行寺から江梨の第85番航浦院に向かう行程も考えられますが、こちらはすでにご紹介しているので、いよいよ第88番結願の修禅寺です。
じつは修禅寺には「奥の院」(正覚院)があって、専用納経帳にも用紙が綴じ込まれています。
納経結願所は修禅寺なので、先に「奥の院」(正覚院)のご紹介をします。
『豆州志稿』、伊豆市Web資料等を基にまとめてみます。
「奥の院」(正覚院)は、修禅寺温泉からいろは道を辿り約5㎞西の湯舟集落にあります。
延暦十年(791年)に18歳の弘法大師が修業をされた所といわれています。
この地にはかつて天魔地妖が多く棲み、住民を煩わせていました。
弘法大師修行の折にも妨げをなしたので、弘法大師は天空に向かって大般若経の魔事品を書かれ、天魔地妖を岩谷(馳籠(かりごめ)の窟(いわや))に封じ込めたと伝わります。
『豆州志稿』には「正覚院 奥之院ト云 修禅寺ニ属ス 修禅寺ヨリ三十町許山中ニ在リ 弘法行状記曰 伊豆國桂谷ト云山寺ニ下リテ佛法修行シ玉ヒケルニ 此寺固ヨリ魔縁多キ所ニテ イカニモ障難アリケレハ 大師虚空蔵ニ向ヒ魔事品ヲ書セ玉ヒケリ 其後天魔モ境ヲ去リ 佛法モ廣マリレリ 大師大日ノ像ヲ造リテ安置シ玉ヘリ 今修禅寺ト申ス是也ト(今修禅寺ト申ス是也ト云ハ誤也) 按スルニ元●釋書ニ所謂 桂谷山寺トハ即此院也ト云傳フ 大日ノ像及驅籠ノ窟皆此ニ在リ 中比衰廃セシヲ 弘治丁巳(1557年)ニ山キト云夫人 北條氏康ニ詑テ堀越六郎(此人及山キ何人ナルカ 今其文書ヲ見ルニ貴人ト思ハル 蓋堀越御所政知ノ遺族ナル可シ 山木ノ事新編相模風土記曰 高源院長流泉香大姉ハ 北條氏直ノ妹(或ハ姉)ニテ 山木御大方ト称ス(略)氏直ハ氏政ノ後●堀越六郎ノ事未考)追福ノ為ニ寺領ヲ寄附シ 修禅寺隠居明山ヲシテ興廃セシム ナホ享保五年(1720年)修禅寺十六世筏山再建ス 今又僅ノ茅堂トナレリ」とあります。
毎年4月20日~21日の春季弘法忌には、弘法大師像を修禅寺より御輿で運び、こちらに1日安置する「お上りお下り」という行事が催行されています。
-------------------
修禅寺には「修禅寺桂谷(けいこく)八十八ヶ所」という霊場があります。
この霊場は昭和5年に修禅寺38世丘珠学が、四国八十八ヶ所霊場の土を修禅寺の桂谷に移され、桂谷八十八ヶ所として弘法大師のお像と札所本尊の梵字、名号を刻んだ石碑を建立したものと伝わります。


【写真 上(左)】 第60番札所
【写真 下(右)】 第61番札所
初番は修禅寺で、第19番は葭原観音堂、第44番が指月殿そば、第54番で修善寺市街を出て桂川~湯船川沿いに進み、第68番~第71番は 奥の院(正覚院)周辺にあります。
一旦北又川を遡って中島橋に戻り、神谷橋を経て第80番で修善寺市街に入り、第88番結願所は修禅寺山内です。
この札所配置をみると奥の院(正覚院)はハイライトで、修禅寺から 奥の院(正覚院)を詣でる霊場(札所巡り)とみることができるかもしれません。
毎年11月上旬には、3日間かけて札所を巡るツアーが催行されています。
車で巡拝しても、そのアプローチは桂谷八十八ヶ所と重なります。
なので道中、いくつもの札所石碑をみることができます。


【写真 上(左)】 奥の院への道-1
【写真 下(右)】 奥の院への道-2
こちらは観光地でもなく、行く先は行き止まりなので通行量はすこぶる少なく、観光客や車でごったがえす修善寺市街とはまったく雰囲気がことなります。
いくつかの石碑をみながら明るい山村の道を辿っていきます。
ひとしきり走ると公園「奥の院阿字苑」に到着で、たしかこちらの駐車場に停めたかと思います。


【写真 上(左)】 奥の院駐車場
【写真 下(右)】 寺号標
ここは谷間にやや開けた一画で、さすがに伊豆有数のパワスポといわれるだけあって、山内入口からしてただならぬ雰囲気がただよっています。


【写真 上(左)】 奥の院参道-1
【写真 下(右)】 奥の院参道-2
複雑な山内構成なので詳細の説明は省きますが、メインは本堂と阿吽の滝・馳籠の窟かと思われます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、向かって右手が庫裡のようです。
水引虹梁上の中備に板蟇股、正面格子扉の上に「修禅寺奥院」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 本堂前の掲示
【写真 下(右)】 山内の札所掲示
本堂向かって右側にある真新しい建物は護摩堂かと思われます。


【写真 上(左)】 護摩堂?
【写真 下(右)】 冠木門
阿吽の滝・馳籠の窟は、本堂への参道を向かって右に折れて急な階段を昇った高みにあります。
本堂への参道と直交するかたちで、階段手前にある冠木門は阿吽の滝・馳籠の窟の門かと思われます。


【写真 上(左)】 内湯
【写真 下(右)】 露天
参道階段を昇った正面が阿吽の滝、周囲には多くの石像と石碑。
阿吽の滝の飛沫をかぶるところに弘法大師像が御座され、この場所が「降魔壇」といわれる修行石かもしれません。
滝壺まわりは板状節理と呼ばれる巨石が折り重なり、どちらが馳籠の窟かはわかりませんでした。
さすがに東国有数の弘法大師霊場。
あたりは身が引き締まるような荘厳な気にあふれています。
勤行式は本堂と阿吽の滝両方でお唱えました。
たしかにパワスポだとは思いますが、観光や物見遊山で訪れる場所ではないような気がしました。
御朱印は、ご住職がいらっしゃるときはこちらでいただけるようですが、ご不在時は修禅寺授与所での拝受となります。
参拝時はご不在でしたので、修善寺で拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 奥之院 /主印はいずれも三寶印

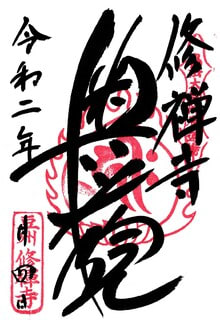
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(しゅぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報Web
伊豆市観光協会修善寺支部Web
伊豆市観光ガイドWeb
静岡県観光協会Web
伊豆市修善寺964
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第33番
授与所:授与所
いよいよ第88番修禅寺。伊豆八十八ヶ所の結願です。
修禅寺は、修善寺温泉の中心にあって数々の逸話を伝える伊豆を代表する名刹で、正式名称を福地山修禅萬安禅寺(ふくちざんしゅぜんばんなんぜんじ)といいます。
延暦十年(791年)弘法大師が18歳のとき当地を訪れて悪魔降伏の法を修され、大同二年(807年)に再訪されて開基と伝わります。
よって開創時は真言宗で、桂谷山寺と号していたようです。
なお、弘法大師の弟子の泉隣が大師を輔けて建立、大師を開基開山としたという説もあります。
鎌倉時代に北条氏が帰依して大寺としての伽藍を整えたといいます。
また、修禅寺と号したのも鎌倉時代とみられています。
源範頼公は兄の将軍頼朝公から猜疑を受けて当地に幽居、自刃したともいわれています。
鎌倉2代将軍頼家公は謀略により幽閉され、この地で生涯を終えたと伝わるなど、源家にとっては悲劇の地でもあります。
鹿山の麓にある指月殿は、北条政子が子・頼家公追善のために建立した経堂と伝わり、自ら「宋版放光般若経」を納経したと伝わります。
建長年間(1249-1256年)に蘭渓道隆(臨済宗鎌倉建長寺開山の宋禅僧・大覚禅師)が住し、周囲の風景が楊州の廬山に似ていることから肖廬山と号し、臨済宗に改めました。
康安元年(1361年)、畠山国清と足利基氏との戦のあおりを受け、應永九年(1402年)には火災で伽籃を全焼して寺は衰退したといいます。
延徳元年(1489-1492年)、北条早雲が再興外護し、寺運は再び隆盛しました。
北条早雲は一族で遠州石雲院の崇芝性岱の弟子となっていた隆渓繁紹を住職に招聘し、このとき曹洞宗に改め山号も福地山と改めました。
徳川家康公も後北条氏の外護を踏襲し、寺領三十石の朱章が承継されました。
幕末の文久三年(1863年)、火災により伽藍や宝物を焼失しますが、明治16年に本堂が再建されています。
平成26年9月には山門の修復に伴い仁王堂が新設され、指月殿に安置されていた金剛力士像が山門仁王堂に安置されました。
なお、修禅寺の由緒沿革は『修禪寺夜話』に詳しいとされますが、筆者は閲覧しておりません。
『豆州志稿』には「肖廬山 修禅寺肖廬山 修禅寺 修善寺村 曹洞宗 遠州榛原郡坂口石雲院末 本尊聖観世音 或ハ修善守ニ作ル 元福地山 修禅萬安禅寺ト号ス 弘法大師創建ス(略)寺記曰弘法大師十八歳ノ時来リテ 悪魔降伏ノ法ヲ修ス 後大同二年(807年)再来リテ 佛像数躯及自像ヲ刻ミ安置スト 其後建長中(1249-1256年)僧蘭溪(鎌倉建長寺開山大覺禅師也)来住シ臨済宗ニ改ム 建治年中(1275-1278年)鎌倉建長寺ノ派下トナル 蘭溪宗國ノ人也 此地楊州廬山ニ彷彿スルヲ以テ 更ニ肖廬山ト号ス 当寺宗理宗額ヲ贈テ曰ク 大宗敕賜大東福地肖廬山修禅寺ト 此古額文久三年(1863年)焼失ス 尋テ正安中(1299-1302年)僧寧一山来住ス 一山ハ元ノ人 平貞時当國ニ放流スル所也(略)小田原北條氏隆渓禅師(禅師当國北條ノ人遠州石雲院崇芝ノ法嗣也 其傳聯燈録ニ在リ(略))ト俗縁アルヲ以テ修禅寺ヲ重修シ 禅師ヲ住セシム 此時ヨリ曹洞宗トナリ 遠州可睡齋ニ隷ス 時ニ延徳年中(1489-1492年)也 爾来北條氏歴世寺領ヲ附ス 徳川家康先例に従ヒ三十石ノ朱章ヲ賜ヒ世襲セシム 昔ハ巨刹ニシテ八塔司アリキ 正覚院 東陽院(今廃ス) 信功院(今廃ス其址日枝神社ノ下ニ在リ傳云源範頼茲(ここ)ニ幽セラルト) 今尚存ス松竹院 日窓寺 梅林院 牟経寺 放光院 皆廃ス 古ハ修禅寺佛殿ハカリニテ 東陽院其事ヲ執行フ 総門ハ十町許 東横瀬ニ大門等アリ 文久三年(1863年)二月回禄ノ災ニ罹リ 以上ノ堂宇皆灰燼ニ帰ス 明治廿年再建ノ功ヲ竣ル 一切経蔵(源頼家追福ノ為ニ二位尼(北条政子)建立ス)ハ源頼家ノ墓ノ傍ニ在リ 牓シテ指月殿ト曰ク 経ハ乃二位尼所納(略)征夷大将軍左金吾督源頼家菩提ノ為ニ 尼之ヲ置クト 尼公ノ手書ト見ユ 又爪起(つまおこし)ノ名号 日蓮自筆ノ法華経(略)ヲ蔵ム」とあります。
-------------------
修禅寺は伊豆屈指の名刹で関連Webも多数あるので、山内のご案内は簡単にいきます。
桂川には風情ある5つの橋がかかり、いずれも観光スポットとなっています。
「渡月橋」が有名ですが、修禅寺参道正面の橋は「虎渓橋」(こけいばし)といいます。


【写真 上(左)】 虎渓橋
【写真 下(右)】 独鈷の湯-1


【写真 上(左)】 独鈷の湯-2
【写真 下(右)】 弘法大師碑と参道階段
「虎渓橋」を渡った右手の河畔には、弘法大師が病気の父親の身体を洗う少年の孝行心に打たれ、独鈷杵で岩を打ち砕かれて霊泉を湧出させ、この霊泉に浸かった父親の病はたちまち癒えたという「独鈷の湯」があります。
この「独鈷の湯」は修善寺温泉発祥の湯ともいわれ、以前は公衆浴場として入湯できましたが現在は見学のみとなっています。
橋のたもとから参道で、石の階段と手前に通種子「ア」と弘法大師の文字が彫られた石標があります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げには扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 手水舎の扁額


【写真 上(左)】 手水鉢と析出
【写真 下(右)】 山内
山門の先右手に手水舎があり、上部に「桂谷霊泉 大師の湯」の扁額。
こちらでは温泉が流され、温泉分析書も掲示されていました。(写真不鮮明で誤りあるかもしれません。)
源泉名は修善寺22号(瑞泉第2)、同26号(白井田泉)、同29号(五十(?)泉)、同41号(仁泉)、同58号(白井(?)の湯)、同63(?)号(●●小山泉)の混合泉。
泉温60.1℃、pH8.51、成分総計=0.547g/kgのアルカリ性単純温泉(Na-Cl・SO4型)です。
湯口には温泉特有の析出が出て、やわらかな湯の香もありました。
旁らには「この温泉は飲むことができます。」の掲示もあったので、こちらのお湯は源泉かけ流しかと。
しかし、手水舎で温泉の飲泉ができるとは、さすがに名湯・修善寺温泉の寺院です。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 六地蔵尊
左手には鐘楼と六地蔵尊。
周囲は修善寺らしい楓樹と竹林で、絵になるところです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
正面が本堂。
山内のふところはさほどありませんが、さすがに名刹の風格を醸しています。
入母屋造桟瓦葺で、千鳥破風と唐破風の二重破風を拝した向拝を附設しています。
唐破風下に朱雀?の彫刻、上に鬼板、千鳥破風に蕪懸魚、経の巻獅子口を置く変化のある意匠。


【写真 上(左)】 横からの向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
名刹だけに向拝柱は4本。
水引虹梁木鼻に獅子を置き、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ梁、中備には彫刻群。
向拝桟唐戸の上には寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 破風部の意匠
【写真 下(右)】 授与所
御本尊の木造大日如来坐像は、昭和59年の解体修理の際に発見された墨書から承元四年(1210年)、慶派仏師の実慶による造立と判明し国の重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 弘法大師塔
本堂向かって左手には弘法大師のお像。
こちらは禅刹ですが、やはりいまでも「お大師様のお寺」なのだと思います。
宝物館(瑞宝蔵)には、修禅寺物語ゆかりの古面などが展示されています。
御朱印は本堂向かって右の授与所にて拝受しました。
こちら様のご対応はとても親切で、専用納経帳の御朱印に「結願」の揮毫をいただけました。
有料ですが結願証も授与されているとのことでしたので、こちらも拝受しました。
曹洞宗寺院ですが、御本尊は大日如来、御朱印尊格も大日如来で、修禅寺の歴史や性格を物語るものです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来 /主印はいずれも御寶印(金剛界大日如来の種子「バン」)
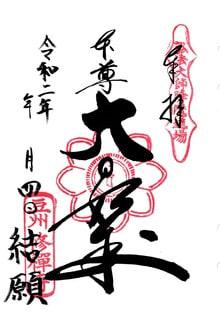
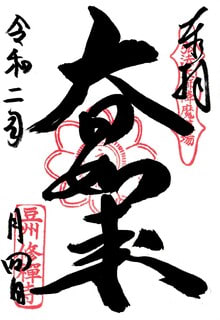
【写真 上(左)】 専用納経帳(結願の御朱印)
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の結願証 〕


【写真 上(左)】 結願証
【写真 下(右)】 お祝いのことば
〔 東海バスのパンフ掲載地図 〕

これで伊豆八十八ヶ所は無事結願です。
発願から結願まで数年を要した長丁場でしたが、歴史の香りや趣きのある札所が多く、充実の巡拝となりました。
事務局さんでは、いろいろと企画も展開されている模様なので、伊豆の湯旅を兼ねて、じっくりゆったりまわってみるのも面白いかと思います。
【 BGM 】
■ Memorial Story~夏に背を向けて~Heaven Beach - 杏里
〔 From 『Heaven Beach』(1982)〕
■ Over and Over - Every Little Thing
■ 未来 - Kalafina
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。
また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
(新?)第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11からつづく。
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)
第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12
旧第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)
第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)
第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)
第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)
第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 旧第85番 授寶山 大聖寺(だいしょうじ)
西伊豆町観光協会Web
西伊豆町安良里315
臨済宗円覚寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:-
授与所:龍泉寺(西伊豆町安良里浜川東14、現行の対応不明)
伊豆八十八ヶ所霊場の第85番札所でしたが、平成31年4月24日より沼津市西浦江梨の満行山 航浦院(旧別格第8番)に交替している模様です。
新旧いずれも巡拝し、御朱印を拝受しているのでご紹介します。
禅刹ながら密寺系の教不動尊霊場のイメージが強い古刹です。
『豆州志稿』『こころの旅』掲載の旧記によると、当山御本尊の不動尊は聖徳太子が刻され、文覚上人が苦行中に授けられた尊像で、かつては大きな滝のそばに御座していたといいます。
後醍醐帝の御代(1288-1339年)泰庵阿闍梨が現在地に不動尊を遷し奉安されて、真言宗寺院を開創と伝わります。
天文年間(1532-1555年)に臨済宗の高岳妙本(光嶽和尚とも)が山号を授寶山、寺号を大聖寺と号され臨済宗に改めて、奈古谷の國清寺の配下になりました。
西伊豆町Web資料によると、御本尊の不動明王は「波切不動」とも呼ばれ、安政の大地震による大津波がここで止まったと伝わるそうです。
御本尊は秘仏で、甲子に本開帳、甲午に中開帳で30年に一度の御開帳です。
『豆州志稿』には「安良里村 臨済宗円覚寺派 田方郡奈古谷國清寺末 本尊不動 大瀑布ニ石不動ノ古佛アリキ 後醍醐帝ノ時(1288-1339年) 泰庵阿闍梨此寺ヲ●メ 不動ヲコヽニ移ス 伊豆峯記ニ此寺ヲ不動ノ別当トス 泰庵善書ノ名アリ 大般若経ノ内三百巻ヲ謄写シテ伊濱普照寺ニ収ム 泰庵ヨリ後二百余年 光嶽和尚ノ時 真言ヲ改メ國清寺ニ隷ス(時ニ天文中(1532-1555年)ナリ) 舊記及泰庵ノ傳皆焼亡シヌ 近頃戌子ノ山水ニ寺押流サレテ 今草堂ノ如シ」とあります。
-------------------
この霊場は西伊豆町に入ると急に札所間の距離が長くなります。
仁科の第84番法眼寺から伊豆西海岸沿いに国道136号を北上し、堂ヶ島、田子の集落を通過して到着した安良里の港町から数百m山側に入ったところにあります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 駐車場から
山内は急斜面の山肌ですが、登り口に駐車場がありアプローチは比較的楽です。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 手水舎
参道入口の橋を渡って鐘楼の先から急な階段が始まります。
右手はうっそうとした森のなかに小滝が連続し、傍らには石像や石碑が並んでパワスボ的オーラを放っています。
もしかするとこちらが本来の不動尊霊場だったのかもしれません。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 不動尊の石像
参道階段両脇には「大聖不動明王」の赤いのぼりがたち並び、不動尊霊場の趣きゆたか。
昇り切った正面が本堂。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝平入りで、堂前に狛犬二対を配しています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝-1
水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に迫力のある龍の彫刻で見応えがあります。
正面桟唐戸でその上に山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
大聖寺は現在この霊場の札所ではないので、霊場巡拝者はほぼいないかと思います。
30年に一度の御開帳を待つ、静かな不動尊霊場に戻ったのでしょうか。
御朱印は円覚寺百観音霊場第35番の龍泉寺(西伊豆町安良里浜川東14)で拝受していますが、現在の御朱印対応は不明です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王 /主印はいずれも御寶印(種子「バン?」)
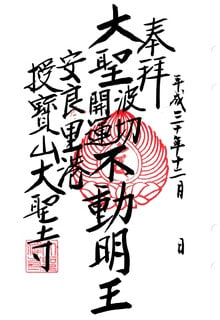

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第86番 吉祥山 安楽寺(あんらくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報Web
伊豆市観光協会土肥支部Web
伊豆市土肥711
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
土肥は松崎とならぶ西伊豆の要衝ですが、松崎に多くの札所があったのに対し土肥にはわずか1札所と対照的です。
大聖寺が札所から外れた現在、第84番仁科の法眼寺から長駆しての到着です。
土肥は西伊豆を代表する温泉地で、土肥金山の観光施設もあるため西伊豆観光では外せません。
こちらは金山採掘中の坑道より温泉が湧出し、入浴したところ病気が平癒したといういわれが残る「まぶ湯」のあるお寺です。
「まぶ湯」は土肥温泉発祥の湯とされ、「医王泉」「鉱山の湯」「砂金風呂」とも呼ばれて、かつては多くの人が薬効を求めて入浴しましたが、現在は入浴できません。
創建は天智天皇二年(663年)ともされる古刹で、行基菩薩が当地巡錫の際、国家鎮護の本地であると祭祀され、自ら釈迦如来像を彫り上げて奉安したのが創始と伝わります。
当初は密宗で医王山大泉寺と号しました。
一時衰退したものの天文三年(1534年)、大用精賢禅師(最勝院8世)が再興され寺号を安楽寺に改め、曹洞宗となりました。
『豆州志稿』には「土肥村 曹洞宗 賀茂郡宮上最勝院末 本尊釋迦 密宗ノ古刹ニシテ大泉寺ト号ス 天文中(1532-1555年)僧大用再興シテ安楽寺ト改ム 吾寶(最勝院開山)ノ徒大用和尚(最勝院八世)ノ時ヨリ宮上最勝院下ト為ル 大用ハ永禄二年(1559年)化ス(略)寺域ニ鉱湯アリ 采金鉱ヨリ湧出ス(千手院寺域)」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 大クス


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 寺号標
土肥港に注ぐ山川の山側にありますが、ほぼ土肥市街の中心エリアです。
山内入口に切妻屋根銅板葺の大ぶりの薬医門で山号扁額を掲げています。
門前に寺号標。
門前にあるクスは推定樹齢1000年、樹高25m、根回り14.2mの巨木で「安楽寺のクス」として静岡県指定天然記念物に指定されています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
南向きの明るい山内で、参道まわりは庭園をなして風趣があります。
石橋を渡り、右に鐘楼、正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 札所標

 【写真 上(左)】 本堂
【写真 上(左)】 本堂【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺で隅棟の長い、やや変わった意匠です。
向拝正面格子扉の上に掲げられた扁額は、達筆すぎて読めません。
軒裏は二軒の疎垂木ながら、どこか存在感があります。


【写真 上(左)】 分析表
【写真 下(右)】 地蔵尊
本堂内には「まぶ湯」のお寺らしく、明治37年の分析表が掲げられていました。
泉温77度、固形物総量1.624g/kgの塩類泉で石膏泉系の泉質と思われます。
本堂手前向かって右に誕生佛。左に聖観世音菩薩の立像。
別に地蔵堂があって、端正な地蔵菩薩立像が御座されています。


【写真 上(左)】 まぶ湯入口
【写真 下(右)】 まぶゆ地蔵
「まぶ湯」は山内山手にあり、庫裡で拝観料を払ってから入坑します。
入口に掲示の由来書によると、慶長十五年(1610年)当地に金鉱があり間部彦平がここから金を採掘していたところ、当山住職家翁隣仙大和尚が病を患いました。
当山の薬師如来に二十一日間の病平癒の祈願をおこなったところ、満願の日に「汝にいで湯を授けん」とのお告げがありました。
すると金鉱の岩間から霊湯が湧出しました。
すぐに金の採掘を止め、大和尚が薬師如来を拝しつつ湯浴みしたところ、病はたちまち癒えました。
大和尚のみならず、湯浴みした病人はいずれも平癒したので病に霊験あらたかと伝わり、遠近から湯治客が集まりました。
人々は金鉱から湧出したことからこのお湯を「鉱(まぶ)の湯」と名づけ、あり難く湯浴みにいそしんだといいます。


【写真 上(左)】 坑口
【写真 下(右)】 湯溜め槽と湯かけ地蔵尊


【写真 上(左)】 坑内
【写真 下(右)】 夫婦神社
入口の数体の「まぶゆ地蔵尊」。
棟門の向こうに入口が見えます。
坑内に湯溜め槽はありますが現在は入浴できず、槽の脇に御座す湯かけ地蔵尊の患部と同じところに、病気平癒を祈念しつつお湯を掛けると霊験ありとされています。
坑内各所には石膏らしき析出が出て、温泉湧出坑であることを物語ります。
坑内の最奥には子宝祈願にご利益あらたかとされる夫婦神社が御鎮座で、御神体がお祀りされています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
観光客の参詣も多いためか、手慣れたご対応でした。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ 土肥温泉 「屋形共同浴場」の入湯レポ
■ 第87番 専修山 大行寺(だいぎょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
沼津市Web
沼津市戸田926
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:本堂
土肥からふたたび長駆し、戸田の第87番大行寺に向かいます。
戸田も古くからの西伊豆の要衝ですが、伊豆にしてはめずらしく温泉がありませんでした。
昭和61年、念願の温泉掘削に成功し晴れて西伊豆の温泉地に名を連ねました。
戸田湾周辺は「駿河トラフ」に位置し、最深部は水深2,500メートルにも達します。
ここに富士山の豊富な湧き水が注ぎ、他ではみられないめずらしい魚種が揚がります。
なかでもタカアシガニと手長エビ(アカザエビ)はグルメ垂涎のレアアイテムで、これを求めて多くの観光客が訪れます。
戸田から駿河湾越しに眺める富士山は絶景で、温泉、グルメ、眺望の三拍子揃った観光地として近年人気を集めています。
大行寺は戸田のほぼ街なか、大川の河畔にある浄土宗寺院です。
火災により寺伝等を焼失しているので、情報の少ないお寺さまです。
『豆州志稿』には「天正四年(1576年)僧三譽創立 観音堂在寺域」とあるのみです。
『こころの旅』には天正四年(1576年)心蓮社三譽上人を開山とし、宗祖法然上人直示の「専修称名念仏」の教示を得て山・院号として草創とあります。
こちらは幕末の歴史で知られています。
安政年間(1855-1860年)、来日中のロシア使節プチャーチン提督は、安政東海大地震により座乗鑑ディアナ号を失い、代鑑建造のため戸田に滞在していました。
幕府は先に締結した和親条約改訂のため、勘定奉行・川路聖謨を全権特使として戸田へ出向させ、川路は大行寺を応接所として交渉にあたりました。
当山はこの歴史を受け「日露交渉地跡大行寺」として、沼津市の史跡に指定されています。
現在の建物は入浜の旧水野領の名主・斎藤本家邸を移築したもので、民家の移築につき本堂は書院造りとなっています。
『豆州志稿』には「戸田村 浄土宗 東京芝増上寺末 本尊阿彌陀 天正四年(1576年)僧三譽創立 観音堂在寺域」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 大川と大行院
【写真 下(右)】 山内入口


【写真 上(左)】 札所案内
【写真 下(右)】 山内
大川の河畔に面した寺院。山門はなく、門柱が山内入口になります。
正面に背後に山を背負って本堂。


【写真 上(左)】 六字御名号
【写真 下(右)】 寺号標
上記のとおり民家の移築なので書院造りですが、外観は寄棟造桟瓦葺で向拝を附設しています。
向拝見上げに山号扁額。そのうえに笈形付大瓶束と棟上に鬼板を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
山内の一画に宝形造銅板葺の堂宇があり、扁額に「施無畏」とあるので観音堂とみられます。
こちらの観音堂には海中出現と伝わる秘仏の聖観世音菩薩像が御座し、4年に一度の御開帳です。


【写真 上(左)】 観音堂?
【写真 下(右)】 観音堂?の向拝
また、山内のソテツは「大行寺の蘇鉄」として天然記念物に指定されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

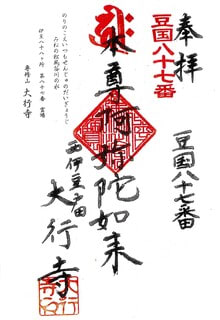
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ 戸田温泉 「壱の湯」の入湯レポ
■ 第88番 奥の院 正覚院
伊豆市観光情報Web
伊豆市観光ガイドWeb
伊豆半島ジオパークWeb
伊豆市観光協会修善寺支部Web
伊豆市修善寺2940-1
宗派:
御本尊:
札所本尊:
他札所:-
授与所:庫裡ないし第88番修禅寺
戸田の第87番大行寺から江梨の第85番航浦院に向かう行程も考えられますが、こちらはすでにご紹介しているので、いよいよ第88番結願の修禅寺です。
じつは修禅寺には「奥の院」(正覚院)があって、専用納経帳にも用紙が綴じ込まれています。
納経結願所は修禅寺なので、先に「奥の院」(正覚院)のご紹介をします。
『豆州志稿』、伊豆市Web資料等を基にまとめてみます。
「奥の院」(正覚院)は、修禅寺温泉からいろは道を辿り約5㎞西の湯舟集落にあります。
延暦十年(791年)に18歳の弘法大師が修業をされた所といわれています。
この地にはかつて天魔地妖が多く棲み、住民を煩わせていました。
弘法大師修行の折にも妨げをなしたので、弘法大師は天空に向かって大般若経の魔事品を書かれ、天魔地妖を岩谷(馳籠(かりごめ)の窟(いわや))に封じ込めたと伝わります。
『豆州志稿』には「正覚院 奥之院ト云 修禅寺ニ属ス 修禅寺ヨリ三十町許山中ニ在リ 弘法行状記曰 伊豆國桂谷ト云山寺ニ下リテ佛法修行シ玉ヒケルニ 此寺固ヨリ魔縁多キ所ニテ イカニモ障難アリケレハ 大師虚空蔵ニ向ヒ魔事品ヲ書セ玉ヒケリ 其後天魔モ境ヲ去リ 佛法モ廣マリレリ 大師大日ノ像ヲ造リテ安置シ玉ヘリ 今修禅寺ト申ス是也ト(今修禅寺ト申ス是也ト云ハ誤也) 按スルニ元●釋書ニ所謂 桂谷山寺トハ即此院也ト云傳フ 大日ノ像及驅籠ノ窟皆此ニ在リ 中比衰廃セシヲ 弘治丁巳(1557年)ニ山キト云夫人 北條氏康ニ詑テ堀越六郎(此人及山キ何人ナルカ 今其文書ヲ見ルニ貴人ト思ハル 蓋堀越御所政知ノ遺族ナル可シ 山木ノ事新編相模風土記曰 高源院長流泉香大姉ハ 北條氏直ノ妹(或ハ姉)ニテ 山木御大方ト称ス(略)氏直ハ氏政ノ後●堀越六郎ノ事未考)追福ノ為ニ寺領ヲ寄附シ 修禅寺隠居明山ヲシテ興廃セシム ナホ享保五年(1720年)修禅寺十六世筏山再建ス 今又僅ノ茅堂トナレリ」とあります。
毎年4月20日~21日の春季弘法忌には、弘法大師像を修禅寺より御輿で運び、こちらに1日安置する「お上りお下り」という行事が催行されています。
-------------------
修禅寺には「修禅寺桂谷(けいこく)八十八ヶ所」という霊場があります。
この霊場は昭和5年に修禅寺38世丘珠学が、四国八十八ヶ所霊場の土を修禅寺の桂谷に移され、桂谷八十八ヶ所として弘法大師のお像と札所本尊の梵字、名号を刻んだ石碑を建立したものと伝わります。


【写真 上(左)】 第60番札所
【写真 下(右)】 第61番札所
初番は修禅寺で、第19番は葭原観音堂、第44番が指月殿そば、第54番で修善寺市街を出て桂川~湯船川沿いに進み、第68番~第71番は 奥の院(正覚院)周辺にあります。
一旦北又川を遡って中島橋に戻り、神谷橋を経て第80番で修善寺市街に入り、第88番結願所は修禅寺山内です。
この札所配置をみると奥の院(正覚院)はハイライトで、修禅寺から 奥の院(正覚院)を詣でる霊場(札所巡り)とみることができるかもしれません。
毎年11月上旬には、3日間かけて札所を巡るツアーが催行されています。
車で巡拝しても、そのアプローチは桂谷八十八ヶ所と重なります。
なので道中、いくつもの札所石碑をみることができます。


【写真 上(左)】 奥の院への道-1
【写真 下(右)】 奥の院への道-2
こちらは観光地でもなく、行く先は行き止まりなので通行量はすこぶる少なく、観光客や車でごったがえす修善寺市街とはまったく雰囲気がことなります。
いくつかの石碑をみながら明るい山村の道を辿っていきます。
ひとしきり走ると公園「奥の院阿字苑」に到着で、たしかこちらの駐車場に停めたかと思います。


【写真 上(左)】 奥の院駐車場
【写真 下(右)】 寺号標
ここは谷間にやや開けた一画で、さすがに伊豆有数のパワスポといわれるだけあって、山内入口からしてただならぬ雰囲気がただよっています。


【写真 上(左)】 奥の院参道-1
【写真 下(右)】 奥の院参道-2
複雑な山内構成なので詳細の説明は省きますが、メインは本堂と阿吽の滝・馳籠の窟かと思われます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、向かって右手が庫裡のようです。
水引虹梁上の中備に板蟇股、正面格子扉の上に「修禅寺奥院」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 本堂前の掲示
【写真 下(右)】 山内の札所掲示
本堂向かって右側にある真新しい建物は護摩堂かと思われます。


【写真 上(左)】 護摩堂?
【写真 下(右)】 冠木門
阿吽の滝・馳籠の窟は、本堂への参道を向かって右に折れて急な階段を昇った高みにあります。
本堂への参道と直交するかたちで、階段手前にある冠木門は阿吽の滝・馳籠の窟の門かと思われます。


【写真 上(左)】 内湯
【写真 下(右)】 露天
参道階段を昇った正面が阿吽の滝、周囲には多くの石像と石碑。
阿吽の滝の飛沫をかぶるところに弘法大師像が御座され、この場所が「降魔壇」といわれる修行石かもしれません。
滝壺まわりは板状節理と呼ばれる巨石が折り重なり、どちらが馳籠の窟かはわかりませんでした。
さすがに東国有数の弘法大師霊場。
あたりは身が引き締まるような荘厳な気にあふれています。
勤行式は本堂と阿吽の滝両方でお唱えました。
たしかにパワスポだとは思いますが、観光や物見遊山で訪れる場所ではないような気がしました。
御朱印は、ご住職がいらっしゃるときはこちらでいただけるようですが、ご不在時は修禅寺授与所での拝受となります。
参拝時はご不在でしたので、修善寺で拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 奥之院 /主印はいずれも三寶印

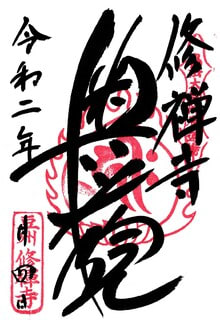
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(しゅぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報Web
伊豆市観光協会修善寺支部Web
伊豆市観光ガイドWeb
静岡県観光協会Web
伊豆市修善寺964
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第33番
授与所:授与所
いよいよ第88番修禅寺。伊豆八十八ヶ所の結願です。
修禅寺は、修善寺温泉の中心にあって数々の逸話を伝える伊豆を代表する名刹で、正式名称を福地山修禅萬安禅寺(ふくちざんしゅぜんばんなんぜんじ)といいます。
延暦十年(791年)弘法大師が18歳のとき当地を訪れて悪魔降伏の法を修され、大同二年(807年)に再訪されて開基と伝わります。
よって開創時は真言宗で、桂谷山寺と号していたようです。
なお、弘法大師の弟子の泉隣が大師を輔けて建立、大師を開基開山としたという説もあります。
鎌倉時代に北条氏が帰依して大寺としての伽藍を整えたといいます。
また、修禅寺と号したのも鎌倉時代とみられています。
源範頼公は兄の将軍頼朝公から猜疑を受けて当地に幽居、自刃したともいわれています。
鎌倉2代将軍頼家公は謀略により幽閉され、この地で生涯を終えたと伝わるなど、源家にとっては悲劇の地でもあります。
鹿山の麓にある指月殿は、北条政子が子・頼家公追善のために建立した経堂と伝わり、自ら「宋版放光般若経」を納経したと伝わります。
建長年間(1249-1256年)に蘭渓道隆(臨済宗鎌倉建長寺開山の宋禅僧・大覚禅師)が住し、周囲の風景が楊州の廬山に似ていることから肖廬山と号し、臨済宗に改めました。
康安元年(1361年)、畠山国清と足利基氏との戦のあおりを受け、應永九年(1402年)には火災で伽籃を全焼して寺は衰退したといいます。
延徳元年(1489-1492年)、北条早雲が再興外護し、寺運は再び隆盛しました。
北条早雲は一族で遠州石雲院の崇芝性岱の弟子となっていた隆渓繁紹を住職に招聘し、このとき曹洞宗に改め山号も福地山と改めました。
徳川家康公も後北条氏の外護を踏襲し、寺領三十石の朱章が承継されました。
幕末の文久三年(1863年)、火災により伽藍や宝物を焼失しますが、明治16年に本堂が再建されています。
平成26年9月には山門の修復に伴い仁王堂が新設され、指月殿に安置されていた金剛力士像が山門仁王堂に安置されました。
なお、修禅寺の由緒沿革は『修禪寺夜話』に詳しいとされますが、筆者は閲覧しておりません。
『豆州志稿』には「肖廬山 修禅寺肖廬山 修禅寺 修善寺村 曹洞宗 遠州榛原郡坂口石雲院末 本尊聖観世音 或ハ修善守ニ作ル 元福地山 修禅萬安禅寺ト号ス 弘法大師創建ス(略)寺記曰弘法大師十八歳ノ時来リテ 悪魔降伏ノ法ヲ修ス 後大同二年(807年)再来リテ 佛像数躯及自像ヲ刻ミ安置スト 其後建長中(1249-1256年)僧蘭溪(鎌倉建長寺開山大覺禅師也)来住シ臨済宗ニ改ム 建治年中(1275-1278年)鎌倉建長寺ノ派下トナル 蘭溪宗國ノ人也 此地楊州廬山ニ彷彿スルヲ以テ 更ニ肖廬山ト号ス 当寺宗理宗額ヲ贈テ曰ク 大宗敕賜大東福地肖廬山修禅寺ト 此古額文久三年(1863年)焼失ス 尋テ正安中(1299-1302年)僧寧一山来住ス 一山ハ元ノ人 平貞時当國ニ放流スル所也(略)小田原北條氏隆渓禅師(禅師当國北條ノ人遠州石雲院崇芝ノ法嗣也 其傳聯燈録ニ在リ(略))ト俗縁アルヲ以テ修禅寺ヲ重修シ 禅師ヲ住セシム 此時ヨリ曹洞宗トナリ 遠州可睡齋ニ隷ス 時ニ延徳年中(1489-1492年)也 爾来北條氏歴世寺領ヲ附ス 徳川家康先例に従ヒ三十石ノ朱章ヲ賜ヒ世襲セシム 昔ハ巨刹ニシテ八塔司アリキ 正覚院 東陽院(今廃ス) 信功院(今廃ス其址日枝神社ノ下ニ在リ傳云源範頼茲(ここ)ニ幽セラルト) 今尚存ス松竹院 日窓寺 梅林院 牟経寺 放光院 皆廃ス 古ハ修禅寺佛殿ハカリニテ 東陽院其事ヲ執行フ 総門ハ十町許 東横瀬ニ大門等アリ 文久三年(1863年)二月回禄ノ災ニ罹リ 以上ノ堂宇皆灰燼ニ帰ス 明治廿年再建ノ功ヲ竣ル 一切経蔵(源頼家追福ノ為ニ二位尼(北条政子)建立ス)ハ源頼家ノ墓ノ傍ニ在リ 牓シテ指月殿ト曰ク 経ハ乃二位尼所納(略)征夷大将軍左金吾督源頼家菩提ノ為ニ 尼之ヲ置クト 尼公ノ手書ト見ユ 又爪起(つまおこし)ノ名号 日蓮自筆ノ法華経(略)ヲ蔵ム」とあります。
-------------------
修禅寺は伊豆屈指の名刹で関連Webも多数あるので、山内のご案内は簡単にいきます。
桂川には風情ある5つの橋がかかり、いずれも観光スポットとなっています。
「渡月橋」が有名ですが、修禅寺参道正面の橋は「虎渓橋」(こけいばし)といいます。


【写真 上(左)】 虎渓橋
【写真 下(右)】 独鈷の湯-1


【写真 上(左)】 独鈷の湯-2
【写真 下(右)】 弘法大師碑と参道階段
「虎渓橋」を渡った右手の河畔には、弘法大師が病気の父親の身体を洗う少年の孝行心に打たれ、独鈷杵で岩を打ち砕かれて霊泉を湧出させ、この霊泉に浸かった父親の病はたちまち癒えたという「独鈷の湯」があります。
この「独鈷の湯」は修善寺温泉発祥の湯ともいわれ、以前は公衆浴場として入湯できましたが現在は見学のみとなっています。
橋のたもとから参道で、石の階段と手前に通種子「ア」と弘法大師の文字が彫られた石標があります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げには扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 手水舎の扁額


【写真 上(左)】 手水鉢と析出
【写真 下(右)】 山内
山門の先右手に手水舎があり、上部に「桂谷霊泉 大師の湯」の扁額。
こちらでは温泉が流され、温泉分析書も掲示されていました。(写真不鮮明で誤りあるかもしれません。)
源泉名は修善寺22号(瑞泉第2)、同26号(白井田泉)、同29号(五十(?)泉)、同41号(仁泉)、同58号(白井(?)の湯)、同63(?)号(●●小山泉)の混合泉。
泉温60.1℃、pH8.51、成分総計=0.547g/kgのアルカリ性単純温泉(Na-Cl・SO4型)です。
湯口には温泉特有の析出が出て、やわらかな湯の香もありました。
旁らには「この温泉は飲むことができます。」の掲示もあったので、こちらのお湯は源泉かけ流しかと。
しかし、手水舎で温泉の飲泉ができるとは、さすがに名湯・修善寺温泉の寺院です。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 六地蔵尊
左手には鐘楼と六地蔵尊。
周囲は修善寺らしい楓樹と竹林で、絵になるところです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
正面が本堂。
山内のふところはさほどありませんが、さすがに名刹の風格を醸しています。
入母屋造桟瓦葺で、千鳥破風と唐破風の二重破風を拝した向拝を附設しています。
唐破風下に朱雀?の彫刻、上に鬼板、千鳥破風に蕪懸魚、経の巻獅子口を置く変化のある意匠。


【写真 上(左)】 横からの向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
名刹だけに向拝柱は4本。
水引虹梁木鼻に獅子を置き、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ梁、中備には彫刻群。
向拝桟唐戸の上には寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 破風部の意匠
【写真 下(右)】 授与所
御本尊の木造大日如来坐像は、昭和59年の解体修理の際に発見された墨書から承元四年(1210年)、慶派仏師の実慶による造立と判明し国の重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 弘法大師塔
本堂向かって左手には弘法大師のお像。
こちらは禅刹ですが、やはりいまでも「お大師様のお寺」なのだと思います。
宝物館(瑞宝蔵)には、修禅寺物語ゆかりの古面などが展示されています。
御朱印は本堂向かって右の授与所にて拝受しました。
こちら様のご対応はとても親切で、専用納経帳の御朱印に「結願」の揮毫をいただけました。
有料ですが結願証も授与されているとのことでしたので、こちらも拝受しました。
曹洞宗寺院ですが、御本尊は大日如来、御朱印尊格も大日如来で、修禅寺の歴史や性格を物語るものです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来 /主印はいずれも御寶印(金剛界大日如来の種子「バン」)
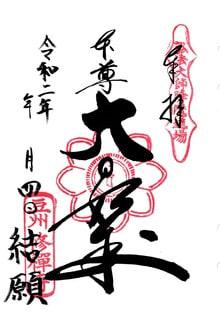
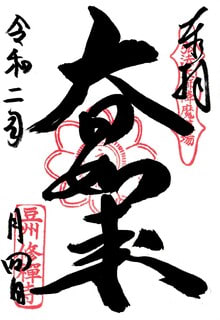
【写真 上(左)】 専用納経帳(結願の御朱印)
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の結願証 〕


【写真 上(左)】 結願証
【写真 下(右)】 お祝いのことば
〔 東海バスのパンフ掲載地図 〕

これで伊豆八十八ヶ所は無事結願です。
発願から結願まで数年を要した長丁場でしたが、歴史の香りや趣きのある札所が多く、充実の巡拝となりました。
事務局さんでは、いろいろと企画も展開されている模様なので、伊豆の湯旅を兼ねて、じっくりゆったりまわってみるのも面白いかと思います。
【 BGM 】
■ Memorial Story~夏に背を向けて~Heaven Beach - 杏里
〔 From 『Heaven Beach』(1982)〕
■ Over and Over - Every Little Thing
■ 未来 - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。
また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
(新?)第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10からつづく。
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)
第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12へつづく。
旧第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)
第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)
第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)
第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)
第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第80番 萬法山 帰一寺(きいちじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
公式Web
松崎町Web
松崎町船田39
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第2番
授与所:庫裡
第80番は萬法山 帰一寺。松崎でも屈指の名刹です。
正安三年(1301年)一山一寧によって開かれ、当初は帰一庵と称していましたが、のちに帰一寺に改めたといいます。
Wikipediaによると、一山一寧(いっさんいちねい)は元からの渡来僧で、台州臨海県(現在の浙江省台州市臨海市)の出身です。
早くに出家し、律・天台を修めた後、臨済禅に転じて阿育王寺の頑極行弥の法を嗣いだとされます。
二度の日本遠征(元寇)に失敗した元の世祖クビライの後を継いだ成宗は、日本との国交を結ぶべく、正安元年(1299年)一山一寧を朝貢督促の国使として日本へ派遣しました。
大宰府に入った一寧らは成宗の国書を執権・北条貞時に奉呈するものの、元寇再来をおそれた貞時は一寧らを伊豆修禅寺に幽閉しました。
修善寺に入られた一寧は禅の修養に専念、一寧の名声をきいて赦免を願い出る者もいたことから、貞時は幽閉を解き鎌倉近くの草庵に身柄を移しました。
鎌倉に入った一寧の名望を慕って多くの僧俗が草庵を訪れ、これを目の当たりにした貞時も疑念を解いて、建長寺を再建して住職に迎えたうえで自ら帰依したといいます。
深い学識と傑出した人柄で多くの人々から尊崇され、門下から雪村友梅ら五山文学を代表する文人墨客を輩出、みずからも能筆で知られその墨蹟は重要文化財に指定されています。朱子の新註を伝え、日本朱子学の祖ともされる名僧です。
円覚寺、浄智寺の住職を経て、正和二年(1313年)には後宇多上皇の請願に応じるかたちで上洛、南禅寺3世となりました。
文保元年(1317年)南禅寺で示寂。花園天皇より一山国師と諡号されました。
一寧の開山として、下諏訪の慈雲寺、信州中野の太清寺、そして帰一寺が伝わります。
松崎町Webによると、一山国師のあと数代は公家の帰依僧が跡を継いだものの、しばしば火災にあい、多くの寺宝を焼失しています。
正保年間(1644-1648年)徳川3代将軍家光の治世に、代官伊奈兵蔵は当山が伊豆50ヶ寺の中本山との理由で寺領回復を上申し、御朱印地を拝領しています。
『豆州志稿』には「船田村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊観世音 釋一山正安元年(1299年)豆州ニ流サレシ時 庵ヲ造リ帰一ト称ス 巳ニシテ寺トシ一山ヲ祖トス 建長寺派下タリ 一山ハ即一寧 宗ノ台州胡氏ノ子ナリ 初元主我國ニ寇シテ敗●ス 至是一寧其密使旨ヲ承ケ来テ間諜ヲ為ス 平貞時激怒豆州ニ放流ス 後鎌倉建長寺ニ居ラシム 一山ノ書二●ヲ蔵ム 経蔵(内ニ辨財天ヲ安ス) 領舎 弥勒堂有リ 中本寺格ニシテ末寺廿四ヶ寺ヲ有ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
松崎市街から婆娑羅峠を越えて、稲梓に抜ける県道15号松崎下田線。
帰一寺はこの道を松崎市街から数㎞走ったところ、船田地区の小高い丘の上にあります。
参道入口に扁額を掲げて桟瓦葺の重厚な高麗門。扁額には「海南禅林」とあります。
ここから坂道&石段を登っていきます。


【写真 上(左)】 山門からのアプローチ
【写真 下(右)】 霊場供養塔
途中に伊豆八十八ケ所と伊豆横道三十三観音の供養塔がありました。
「伊豆新四国八十八箇所」とありますが、この霊場で「新四国」の表記があるのはめずらしいです。


【写真 上(左)】 参道と門
【写真 下(右)】 門
ひとしきり登ると正面に門。これはふたつめの門で中門かもしれません。
切妻屋根桟瓦葺の重厚な四脚門で、高く立ち上げた大棟に葵紋を掲げています。
控柱に虹梁を渡し、見上げには山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 門の扁額
【写真 下(右)】 山内
くぐると正面に千鳥破風+唐破風桟瓦葺の建物。
左手には入母屋造桟瓦葺の立派な建物で「群龍殿」の扁額を掲げています。
右手の建物は庫裡かと思います。


【写真 上(左)】 左の建物(本堂?)
【写真 下(右)】 扁額
正面の建物は複雑な構成で、平入りか妻入りかもわかりませんでした。
正面と左手の建物の関係がよくわかりません。


【写真 上(左)】 中央の建物
【写真 下(右)】 中央の建物と庫裡
左の建物の堂内には寺号扁額と「慈光」の二つの扁額で三間構成なので、本堂御内陣の趣き。
中央の建物は観音堂かとも思いましたが、奥まったところに「萬法帰一」の扁額とその先は格子窓ごしに庭がみえます。
堂前に賽銭箱が置いてあるので、奥庭にある堂宇?の遙拝所的な位置づけなのかもしれません。
本堂の建立は弘化五年(1848年)、当初は茅葺でしたが現在は瓦葺に葺きかえられています。
べつに8代将軍吉宗のころ建立された六角形回転式の経蔵があるはずですが確認できず、伊豆の代表的名園とされる本堂裏の庭園もなぜか拝観していません。
ふつうこれだけナゾがあると、当然お寺の方に聴き込みに入るのですが、ナゾが解けていないところをみると、ご不在だったか、よほど急いでいたかのいずれかだと思います。
これだけの名刹を生兵法で説明するのはどうかと思うので(笑)、山内のご案内はこのくらいにしておきます。
御朱印は(たぶん)庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも「本尊観音」の印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第81番 富貴野山 寶蔵院(ほうぞういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町Web
松崎町観光協会Web
松崎町門野173-1
曹洞宗
御本尊:延命地蔵菩薩
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第7番
授与所:寺役管理
松崎の山中ふかくに立地する弘法大師ゆかりの古刹。
『こころの旅』記載の『宝蔵院畧縁起』、松崎町Web資料等によると草創は以下のとおりです。
延暦十九年(800年)(大同3年(808年)とも)、27歳の弘法大師は伊豆巡錫中に仁科を訪れました。
弘法大師が当地で読経されていると、森の中の六本の巨木が六条の光を放ちました。
お大師様はこれを六道衆生の苦しみを救済する地蔵菩薩有縁のものと考えられ、ここを富貴野山地蔵金剛法蔵密院と名づけられました。
天長七年(830年)57歳のお大師様はふたたびこの地を訪れ、庵を修復しお堂を建てられて密法修行の地とされました。
室町時代には末寺88を有する大霊場として栄え、一時衰えたものの僧・岩仲によって再興開基され、以来文明年間(1469-1486年)まで伊豆第一の山岳仏教の霊地として繁栄したといいます。
その後荒廃していたところ、文亀年間(1501-1504年)、河津逆川村の普門院4世・清安が堂宇を整備、真言宗から曹洞宗に改宗し寶蔵院と号を改めました。
御本尊・地蔵菩薩の信仰は営々とつづき、とくに作物の虫除けに霊験あらたかとされました。
その参詣道は一色口、白川口、江奈口、門野口など多くあったため、高野山になぞらえて「富貴野の七口」と呼ばれたそうです。
『豆州志稿』には「門野村 曹洞宗 賀茂郡逆川普門院末 本尊地蔵 富貴ハ山名 山嶽ノ部ニ出ツ 弘法大師遊行ノ時 此ヲ見立テ寺ヲ創ム 今名証ナシト雖 古ヨリ的ニ相傳フ 他ノ仮託ニ出ルカ如キニ非ス 大師自所負ノ笈ナリトテ今ニ存ス(略)又庭中ニ手植ノ岩桂車蓋ノ如クナル有リキ 惜ムラクハ巳ニ枯死シテ無シ 尚空海ノ遺物ト傳フル鍋幷杖ヲ蔵ス(略)モト金剛密院ト称ス 僧岩忠ヲ中興祖トス 永禄天文ノ頃普門院四世清安和尚住シテヨリ宗旨改ル 是時ヨリ寶蔵院ト号ス」とあります。
また、子院として寶徳寺(同村 号金剛山)が記載されています。
『霊場めぐり』によると、昭和初期ごろまではご縁日(4月10日と7月24日)、ことに夏のご縁日は賑わって本堂には100人ほども参籠し、山上露店も出たといいます。
松崎町Web資料には「第二次大戦後は訪れる人も途絶えて、山深い寺は次第に荒れていった。戦争中戦後の伐採により、周りの山を失った寺は風雨の影響をまともに受けるようになり、昭和24年(1949年)のパトリシア台風によって山門が倒壊、昭和34年(1959年)8月14年の風台風で本堂も半壊、復旧困難なため取り壊されて、今は山門・本堂ともにその礎石を残すのみとなった。」とあります。
現在は「富貴野山21世紀の森」のなかに堂宇や遺跡が点在するかたちとなっています。
-------------------


【写真 上(左)】 登り口
【写真 下(右)】 参道-1
富貴野山は松崎市街地の北東にそびえる標高550mの山で、当山はその山腹にあります。
「富貴野山21世紀の森」というリラクゼーションエリアとなっていますが、かなり山深く、そのアプローチの長さは第8番益山寺と双璧です。
ただし路面はしっかりした舗装路なので、益山寺よりはアプローチは楽です。
「富貴野山21世紀の森」の駐車場に停めて、参道をのぼっていきます。
本来の参道は下の駐車場から少し下って大師橋を渡り、男坂ないし女坂経由の行程とみられます。
上の駐車場は本堂下にあるので、横着にもこちらに停めました。
さすがにお大師様ゆかりの霊山。あたりは清々しい空気に包まれています。


【写真 上(左)】 富貴野山稲荷
【写真 下(右)】 参道-2
駐車場そばに御鎮座の富貴野山稲荷は、当山の地主神あるいは鎮守かもしれません。
現地掲示によると、こちらには白山大権現が祀られているそうです。
舗装道をトラバース気味に歩いていくと、両側に石仏が並ぶ苔むした参道階段が出てきます。
そびえる杉木立の相間から陽射しが射し込み、雰囲気は抜群です。
こちらの石仏群は「宝蔵院石仏群」と呼ばれ、江戸時代に奉安されたもの。
約120体もの石仏はお大師様、大日如来、薬師如来、阿弥陀如来、地蔵尊、観音菩薩などさまざまで、信仰厚い村人たちが一体づつ背負って運び上げたとのこと。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道-3
参道階段をのぼり切ると広々とした平地が広がり、かつては伽藍が建ち並んでいたと思われるスケール感を感じます。
建物は3つ。
右手に長屋門?。正面がおそらく本堂、左手が開山堂です。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2


【写真 上(左)】 長屋門
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造銅板葺で、比較的新しい建立と思われます。
向拝柱はなく、左右の身舎柱に「豆國八十一番札所」「伊豆横道七番札所」の札番が掲げられています。
向拝見上げに院号扁額。右手には「富貴峯」の扁額も掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額-1

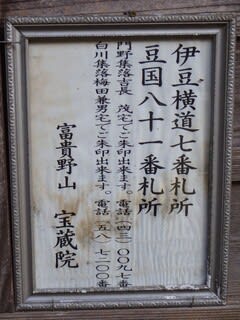
【写真 上(左)】 本堂扁額-2
【写真 下(右)】 御朱印案内
左手の開山堂は銅板葺宝形造で流れ向拝。
周囲に縁をめぐらし、相輪を立てた塔身の周囲に庇を降ろし、内側に身舎を抱く密教建築の山上伽藍です。


【写真 上(左)】 開山堂
【写真 下(右)】 開山堂向拝
水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に彫刻入りの板蟇股で、見上げに山号扁額。
正面の花狭間戸と左右の蔀戸が引き締まったイメージの意匠。
撮影角度が悪くて断言できないのですが、ひょっとすると天竺様の隅扇垂木かもしれません。
開山堂左手にある杉の大木は樹齢約400年。弘法大師の徳をしのび昔から「弘法杉」と呼ばれているそうです。
また、杉の根元にある二基の宝篋印塔は、曾我兄弟ゆかりと伝わります。


【写真 上(左)】 弘法杉
【写真 下(右)】 富貴野山からの展望
江戸時代の中期まで、寺庭に弘法大師お手植えと伝えられるモクセイ(モッコク・カツラとも)の巨木があったといいます。
また、お手植えのときにお大師様が遺された笈がいまも遺されているといいます。
御朱印は、本堂前に掲示されていた寺役さんに連絡をとり拝受しました。
寺役さんの納経所は山を下りた道沿いで、すぐにみつかりました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第82番 大悲山 慈眼寺(じげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
西伊豆町Web
西伊豆町一色56
臨済宗建長寺派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第6番
授与所:第83番東福寺
情報の少ない札所です。
始祖とされる復岩が明応三年(1494年)入寂であることから、開山はそれ以前、文明年間とみられています。
(延徳元年(1489年)、復山による開山という説もあり。)
正保元年(1644年)、僧・明山により再興されました。
赤穂四十七士のひとりで討ち入り後、大石の命を受け離脱した寺坂吉右ヱ門の墓があることで知られています。
『豆州志稿』には「一色村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊如意輪観世音 復岩ヲ祖トス(明応三年(1494年)寂ス) 正保元年(1644年)僧明山再興ス 地蔵堂寺域ニ有リ」とあります。
-------------------
伊豆の湯めぐりに没頭していた一時期、この山深い場所を一度通りかかったことがあります。
このお寺の先に、温泉マニアの間では有名な名湯、祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」がありそこに入湯したためです。
この札所へのアプローチとなる静岡県道59号伊東西伊豆線は、伊豆最悪の険道ともいわれます。
筆者は祢宜ノ畑温泉入湯後にこの県道を走って修禅寺に抜けたのですが、二度と通りたくないと思えるほどのキツイ道でした。
(険しいというか、細かいカーブが異様にしつこくつづく。)
この霊場巡りでは札番からいって慈眼寺から修禅寺に向かうことはないかと思いますが、「県道だから・・・」と安易に入り込むのは避けた方がいいかと思います。
こんな感じ↓です。
■ 怖っ!静岡険道(県道)59号(伊東西伊豆線) 松崎⇒仁科峠 バイク走行動画
慈眼寺へは大浜から仁科川沿いを3㎞ほどで、このあたりまでは川沿いのいたってふつうの道路なのでとくに問題はありません。


【写真 上(左)】 六地蔵群
【写真 下(右)】 参道入口


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂のすぐ横が駐車場なのでアプローチはすこぶる楽です。
昭和四十年代の建立の本堂はアーチ状の屋根の近代建築ですが、向拝はきっちり設けられています。
向拝見上げに山号扁額。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御本尊は小さな如意輪観世音菩薩像とのことで、伊豆横道三十三観音霊場第6番の札所本尊もこちらの観音様かと思われます。
こちらの鈴木氏墓地のなかに赤穂四十七士のひとり寺坂吉右ヱ門の墓と呼ばれてきた地蔵尊(あるいは石像とも)が安置されているそうです。
言い伝えによると、討ち入り後、義士供養のため僧形となり、諸国遍歴の途に鈴木権内方に滞在し一生を終えたといいます。
市資料によると、当寺過去帳に「寺坂吉右ヱ門事一相西円上座」、「但し、江戸の人四十七人の一人」とあるそうで、富貴野山宝蔵院に梵鐘を献納した話なども伝えられています。
御朱印は第83番東福寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 如意輪観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

→ 祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」の入湯レポ
■ 第83番 照嶺山 東福寺(とうふくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
西伊豆町Web
西伊豆町観光協会Web
西伊豆町中24-2
臨済宗建長寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
現地掲示の由緒書、『豆州志稿』等によると、濱村字澤田カ原(仁科字浜村、弘法大師遊行の折に安居された旧跡とも)に石室(岩の堂)として草創。
天福元年(1233年)、真言宗の一寺をなし草創時の年号から天福寺と号しました。
嘉元(1303-1306年)の頃(嘉元二年とも)災害に遭い、雲林和尚が濱村中村字中の島に移し旧天福寺の号に因んで天福山と号したといいます。(このとき東福寺と号したという説もあり。)
永和三年(1377年)災害のため諸堂が大破、應永二年(1395年)佛印大光禅師を中興開祖とし、真言宗から臨済宗へと改宗。
文明九年(1477年)激しい波浪に見舞われ堂宇は漂流、同十八年佐々木(山本)盛季が現在地に移して再興し、寺号を東福寺と改めたと伝わります。
よって、佐々木(山本)盛季を東福寺殿と称し、当山開基としています。
当山の本堂天井には漆喰の見事な五百羅漢が描かれているため、「五百羅漢の寺」としても知られています。
『豆州志稿』には「中村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊阿彌陀 嘉元(1303-1306年)ノ頃 雲林和尚濱村ノ天福寺ヲ引ク 因テ天福山ト称セリ 天福ノ紀号僅ニ一年ナリシ故 之ヲ忌テ照嶺ト改ム 天福元年(1233年)濱村字澤田カ原ニ創立ス 後僧雲林当村中島ニ移ス 應永中(1394-1428年)真言ヲ改テ臨済宗ト為シ 僧佛印ヲ祖トス 文明九年(1477年)激浪ノ為ニ漂流ス 同十八年佐々木盛季復現地ニ移ス 寺域地蔵堂観音堂有」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口&山門
【写真 下(右)】 山門扁額
静岡県道59号伊東西伊豆線沿い、第82番慈眼寺から大浜(伊豆西海岸)に戻る途中の仁科川沿いにあります。
参道入口の寺号標には「五百羅漢の寺」。
その先の山門は入母屋屋根桟瓦葺、上層鐘楼四脚の高欄付楼門で上層に山号扁額を置いています。
異様に高い礎盤は水害から護るためでしょうか。
小高い山を背に、こぢんまりとまとまった、落ちついた雰囲気のお寺さんです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面の本堂は寄棟造銅板葺で、向拝部に顕著な千鳥破風を附設しています。
平入りと思いますが、千鳥破風があまりに目立つので、一瞬妻入りかと思いました。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 寺号の表札?
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ梁、中備に龍の彫刻。
左右の繋ぎ虹梁上には板蟇股を置いています。
見上げには扁額というか、寺号の表札?を掲げています。
本堂向かって右手前のお像は修行大師像のようにも思えるのですが、確信もてず。
本堂内の天井には、昭和初期に浅草の仏師・田村利光(酒豪だったので「のん兵衛安さん」と呼ばれた)により漆喰で描かれた五百羅漢があり、御内陣の花鳥・龍・天女とともに秀作とされています。
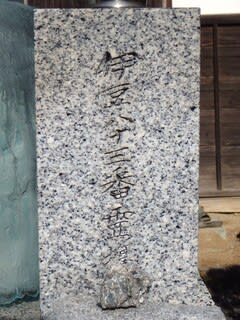

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 身代り地蔵尊
山内には地蔵堂があり、端正な地蔵尊坐像が御座します。
現地説明書によると、こちらは百五十余年前に当山第14世住職が両親菩提と諸民の災害除のために、大本山鎌倉建長寺の御本尊・身代り地蔵尊のお今身を願い当山に勤把したお地蔵様とのことです。


【写真 上(左)】 鎮守?
【写真 下(右)】 足神社
山内には鎮守とみられるお社、足神社が祀られています。
足神社は安政時代の創祀でもともと旧道に御鎮座でしたが、道路拡張に伴い平成元年当山に勧請とのことです。(山内石碑より)
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印
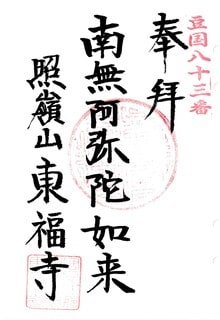

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第84番 正島山 法眼寺(ほうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
公式Web
西伊豆町仁科860-1
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡
ここから松崎町を離れ、西伊豆町に入ります。
第84番は、西海岸を走る国道136号に戻り仁科の街なかにある法眼寺です。
『こころの旅』によると、初めは仁科の安城山麓にあった法眼庵という小庵でしたが、波濤により大破、荒廃。
永享年間(1429-1441年)ののち、幽岩和尚が濱村長平寺を合せて起立・開林。(『豆州志稿』)
享保年間(1716-1736年)にこの地を修行で通りかかった僧、幽厳が法眼庵と堂ヶ島の走嶋山長平寺の荒廃を嘆き、二院を合併して正島山法眼寺としたという説もあります。(『こころの旅』)
法眼庵から数えて約四百年の間、西伊豆・仁科の海で働く人々の安全と繁栄のための鎮守の寺として続いてきたといいます。
『豆州志稿』には「濱村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊釋迦阿彌陀薬師 初法眼庵ト称ス 永享十六年(註:永享は十三年まで、1429-1441年)同村長平寺ヲ合セテ当寺ヲ起立ス 幽岩和尚開林(寛正六年(1465年)寂ス) 此寺安城山ヲ後ニシ 門前清渓ヲ帯ヒ 風景極テ幽邃」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 隣接する仁科港
【写真 下(右)】 山内入口
風光明媚な仁科港に面した、明るい雰囲気のお寺さまです。
なお、この仁科港の北側には西伊豆屈指のシーサイド露天として人気が高い「沢田公園露天風呂」があります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
開放的な山内で、正面に寄棟造本瓦葺流れ向拝の本堂。
水引虹梁両端に禅宗様の木鼻、身舎側に繋ぎ梁、中備に寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 堂内扁額
【写真 下(右)】 堂内天井画
本堂内は綺麗に整頓され、天井の格子には綺麗な花の天井画が施されていました。


【写真 上(左)】 天王神社
【写真 下(右)】 天王神社の扁額
隣接してスサノオノミコトを御祭神とする天王神社が御鎮座。
稲ワラを編み上げ社の頭上に張り渡す「天王様のお注連あげ」で知られる神社です。
位置関係からして法眼寺は元別当のような感じがしますが、これを示す史料はみつかりませんでした。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印
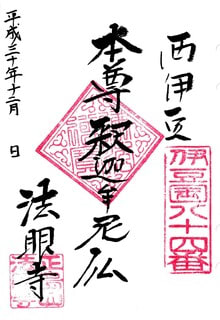

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第85番 満行山 航浦院(こうほいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
沼津市西浦江梨149
臨済宗円覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
この札所は、札番からするとかなり離れたところにありますが、札番順にご紹介していますのでここでとり上げます。
こちらはもともと旧別格第8番の札所でしたが、平成31年4月24日より第85番霊場になっているようです。
もともと第8番霊場についてはナゾがありました。
〔 「こころの旅」掲載地図より 〕

第5番玉洞院は狩野川右岸の牧之郷、第6番金剛寺・第7番泉龍寺は狩野川左岸の山田川、第8番益山寺は山田川支流の小山田川を山側にふかく遡ったところにあります。
一方、旧別格第8番の 航浦院は駿河湾に面した西浦江梨にあります。
山田川筋から西浦江梨に向かうには、峠越えをして内浦に降りそこから駿河湾沿いを延々と西進する必要があります。
第9番澄楽寺は第5番玉洞院のそばなので、帰路もその行程ないし三津浜経由の大回りの行程となります。
航浦院は伊豆水軍の名族・鈴木(杉本)氏ゆかりで、白隠禅師が受戒したという名刹なのでこれを外すわけにはいかず、(旧)別格第8番というかたちで設定されたのかもしれません。
ルートからすると戸田の第87番大行寺のつぎに別格ないしは掛所として設定した方が巡礼者の負担は少ないですが、そうはできない何らかの事情があったのかも。
いずれにしても、この札所は西伊豆・戸田からも中伊豆からも遠く隔たった場所にありますが、正式に第85番札所となった以上、避けて通れない存在となりました。
かなりの大回りにはなりますが、近くには伊豆の七不思議とされる大瀬崎大池・大瀬神社もあり、駿河湾の浦々を辿る県道17号沼津土肥線は優れたドライブ・ルートなので、訪れる価値は充分あると思います。
航浦院は、紀州から西浦に移住し、伊豆水軍の雄として約二百数十年間にわたり西浦一帯を治めた鈴木氏(杉本氏)の菩提寺です。
『豆州志稿』には、文明年間(1469-1487年)に地頭の鈴木繁用が父・繁郷冥助の為ニ造立とあり、僧・業道(業堂寿和尚大禅師とも)による開山とされています。
(1330年頃の創立という説もあり。)
開基の鈴木(杉本)氏は西浦江梨を根拠地にした伊豆水軍の雄で、その経済力を背景に菩提寺として営々当山を外護してきたものとみられます。
杉本左京大夫繁郷の法名は「航浦院殿江巖道海大居士」で、当山の院号はこちらと関連のあるものと思われます。
また、萬行山の山号は近くにあった萬行寺ゆかりのものとみられています。
『豆州志稿』によると、寛政年間(1789-1801年)僧・神洲が再興しています。
『豆州志稿』には「江梨村 臨済宗円覚寺派 田方郡奈古谷國清寺末 本尊阿彌陀 文明中(1469-1487年)地頭鈴木繁用其父繁郷冥助ノ為ニ造立ス(略)僧業道ヲ開山トス 後寛政中(1789-1801年)僧神洲再興ス 本尊ハ鈴木繁用ノ男繁宗ノ女ノ祈念佛也 観音堂在リ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
このエリアは伊豆半島にはめずらしい北向きの海岸ですが、当山は南傾の高台にあるので陽光降りそそぐ明るい山内です。
航浦院はこの高台に、円覚寺百観音霊場第32番廣大山 海蔵寺とともにあります。
城郭を思わせる石垣を幾重にも巡らし風格がありますが、山門はありません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂
参道手前に寺号標。その先には札所標もありました。
曲がり参道で階段を昇った中庭の左手に本堂があります。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂札所板
寄棟造銅板葺で向拝柱はありません。
向拝正面硝子扉のよこに札所板、上には山号扁額が掲げられています。
御本尊は開基・鈴木繁用の男(子)繁宗の女(室)の祈念佛と伝わります。


【写真 上(左)】 半僧坊大権現の堂宇
【写真 下(右)】 同扁額
庫裡のそばにもうひとつ堂宇があり、こちらは半僧坊大権現のお堂かと思われますがこちらにも伊豆八十八ヶ所の札所板が掲げられていました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 半僧坊大権現の御朱印 〕

【 BGM 】
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド - サザンオルスタース
■ さよなら夏の日 - 山下達郎
■ Crescent aventure - 角松敏生
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。
また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
(新?)第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10からつづく。
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)
第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12へつづく。
旧第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)
第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)
第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)
第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)
第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第80番 萬法山 帰一寺(きいちじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
公式Web
松崎町Web
松崎町船田39
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第2番
授与所:庫裡
第80番は萬法山 帰一寺。松崎でも屈指の名刹です。
正安三年(1301年)一山一寧によって開かれ、当初は帰一庵と称していましたが、のちに帰一寺に改めたといいます。
Wikipediaによると、一山一寧(いっさんいちねい)は元からの渡来僧で、台州臨海県(現在の浙江省台州市臨海市)の出身です。
早くに出家し、律・天台を修めた後、臨済禅に転じて阿育王寺の頑極行弥の法を嗣いだとされます。
二度の日本遠征(元寇)に失敗した元の世祖クビライの後を継いだ成宗は、日本との国交を結ぶべく、正安元年(1299年)一山一寧を朝貢督促の国使として日本へ派遣しました。
大宰府に入った一寧らは成宗の国書を執権・北条貞時に奉呈するものの、元寇再来をおそれた貞時は一寧らを伊豆修禅寺に幽閉しました。
修善寺に入られた一寧は禅の修養に専念、一寧の名声をきいて赦免を願い出る者もいたことから、貞時は幽閉を解き鎌倉近くの草庵に身柄を移しました。
鎌倉に入った一寧の名望を慕って多くの僧俗が草庵を訪れ、これを目の当たりにした貞時も疑念を解いて、建長寺を再建して住職に迎えたうえで自ら帰依したといいます。
深い学識と傑出した人柄で多くの人々から尊崇され、門下から雪村友梅ら五山文学を代表する文人墨客を輩出、みずからも能筆で知られその墨蹟は重要文化財に指定されています。朱子の新註を伝え、日本朱子学の祖ともされる名僧です。
円覚寺、浄智寺の住職を経て、正和二年(1313年)には後宇多上皇の請願に応じるかたちで上洛、南禅寺3世となりました。
文保元年(1317年)南禅寺で示寂。花園天皇より一山国師と諡号されました。
一寧の開山として、下諏訪の慈雲寺、信州中野の太清寺、そして帰一寺が伝わります。
松崎町Webによると、一山国師のあと数代は公家の帰依僧が跡を継いだものの、しばしば火災にあい、多くの寺宝を焼失しています。
正保年間(1644-1648年)徳川3代将軍家光の治世に、代官伊奈兵蔵は当山が伊豆50ヶ寺の中本山との理由で寺領回復を上申し、御朱印地を拝領しています。
『豆州志稿』には「船田村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊観世音 釋一山正安元年(1299年)豆州ニ流サレシ時 庵ヲ造リ帰一ト称ス 巳ニシテ寺トシ一山ヲ祖トス 建長寺派下タリ 一山ハ即一寧 宗ノ台州胡氏ノ子ナリ 初元主我國ニ寇シテ敗●ス 至是一寧其密使旨ヲ承ケ来テ間諜ヲ為ス 平貞時激怒豆州ニ放流ス 後鎌倉建長寺ニ居ラシム 一山ノ書二●ヲ蔵ム 経蔵(内ニ辨財天ヲ安ス) 領舎 弥勒堂有リ 中本寺格ニシテ末寺廿四ヶ寺ヲ有ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
松崎市街から婆娑羅峠を越えて、稲梓に抜ける県道15号松崎下田線。
帰一寺はこの道を松崎市街から数㎞走ったところ、船田地区の小高い丘の上にあります。
参道入口に扁額を掲げて桟瓦葺の重厚な高麗門。扁額には「海南禅林」とあります。
ここから坂道&石段を登っていきます。


【写真 上(左)】 山門からのアプローチ
【写真 下(右)】 霊場供養塔
途中に伊豆八十八ケ所と伊豆横道三十三観音の供養塔がありました。
「伊豆新四国八十八箇所」とありますが、この霊場で「新四国」の表記があるのはめずらしいです。


【写真 上(左)】 参道と門
【写真 下(右)】 門
ひとしきり登ると正面に門。これはふたつめの門で中門かもしれません。
切妻屋根桟瓦葺の重厚な四脚門で、高く立ち上げた大棟に葵紋を掲げています。
控柱に虹梁を渡し、見上げには山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 門の扁額
【写真 下(右)】 山内
くぐると正面に千鳥破風+唐破風桟瓦葺の建物。
左手には入母屋造桟瓦葺の立派な建物で「群龍殿」の扁額を掲げています。
右手の建物は庫裡かと思います。


【写真 上(左)】 左の建物(本堂?)
【写真 下(右)】 扁額
正面の建物は複雑な構成で、平入りか妻入りかもわかりませんでした。
正面と左手の建物の関係がよくわかりません。


【写真 上(左)】 中央の建物
【写真 下(右)】 中央の建物と庫裡
左の建物の堂内には寺号扁額と「慈光」の二つの扁額で三間構成なので、本堂御内陣の趣き。
中央の建物は観音堂かとも思いましたが、奥まったところに「萬法帰一」の扁額とその先は格子窓ごしに庭がみえます。
堂前に賽銭箱が置いてあるので、奥庭にある堂宇?の遙拝所的な位置づけなのかもしれません。
本堂の建立は弘化五年(1848年)、当初は茅葺でしたが現在は瓦葺に葺きかえられています。
べつに8代将軍吉宗のころ建立された六角形回転式の経蔵があるはずですが確認できず、伊豆の代表的名園とされる本堂裏の庭園もなぜか拝観していません。
ふつうこれだけナゾがあると、当然お寺の方に聴き込みに入るのですが、ナゾが解けていないところをみると、ご不在だったか、よほど急いでいたかのいずれかだと思います。
これだけの名刹を生兵法で説明するのはどうかと思うので(笑)、山内のご案内はこのくらいにしておきます。
御朱印は(たぶん)庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも「本尊観音」の印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第81番 富貴野山 寶蔵院(ほうぞういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町Web
松崎町観光協会Web
松崎町門野173-1
曹洞宗
御本尊:延命地蔵菩薩
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第7番
授与所:寺役管理
松崎の山中ふかくに立地する弘法大師ゆかりの古刹。
『こころの旅』記載の『宝蔵院畧縁起』、松崎町Web資料等によると草創は以下のとおりです。
延暦十九年(800年)(大同3年(808年)とも)、27歳の弘法大師は伊豆巡錫中に仁科を訪れました。
弘法大師が当地で読経されていると、森の中の六本の巨木が六条の光を放ちました。
お大師様はこれを六道衆生の苦しみを救済する地蔵菩薩有縁のものと考えられ、ここを富貴野山地蔵金剛法蔵密院と名づけられました。
天長七年(830年)57歳のお大師様はふたたびこの地を訪れ、庵を修復しお堂を建てられて密法修行の地とされました。
室町時代には末寺88を有する大霊場として栄え、一時衰えたものの僧・岩仲によって再興開基され、以来文明年間(1469-1486年)まで伊豆第一の山岳仏教の霊地として繁栄したといいます。
その後荒廃していたところ、文亀年間(1501-1504年)、河津逆川村の普門院4世・清安が堂宇を整備、真言宗から曹洞宗に改宗し寶蔵院と号を改めました。
御本尊・地蔵菩薩の信仰は営々とつづき、とくに作物の虫除けに霊験あらたかとされました。
その参詣道は一色口、白川口、江奈口、門野口など多くあったため、高野山になぞらえて「富貴野の七口」と呼ばれたそうです。
『豆州志稿』には「門野村 曹洞宗 賀茂郡逆川普門院末 本尊地蔵 富貴ハ山名 山嶽ノ部ニ出ツ 弘法大師遊行ノ時 此ヲ見立テ寺ヲ創ム 今名証ナシト雖 古ヨリ的ニ相傳フ 他ノ仮託ニ出ルカ如キニ非ス 大師自所負ノ笈ナリトテ今ニ存ス(略)又庭中ニ手植ノ岩桂車蓋ノ如クナル有リキ 惜ムラクハ巳ニ枯死シテ無シ 尚空海ノ遺物ト傳フル鍋幷杖ヲ蔵ス(略)モト金剛密院ト称ス 僧岩忠ヲ中興祖トス 永禄天文ノ頃普門院四世清安和尚住シテヨリ宗旨改ル 是時ヨリ寶蔵院ト号ス」とあります。
また、子院として寶徳寺(同村 号金剛山)が記載されています。
『霊場めぐり』によると、昭和初期ごろまではご縁日(4月10日と7月24日)、ことに夏のご縁日は賑わって本堂には100人ほども参籠し、山上露店も出たといいます。
松崎町Web資料には「第二次大戦後は訪れる人も途絶えて、山深い寺は次第に荒れていった。戦争中戦後の伐採により、周りの山を失った寺は風雨の影響をまともに受けるようになり、昭和24年(1949年)のパトリシア台風によって山門が倒壊、昭和34年(1959年)8月14年の風台風で本堂も半壊、復旧困難なため取り壊されて、今は山門・本堂ともにその礎石を残すのみとなった。」とあります。
現在は「富貴野山21世紀の森」のなかに堂宇や遺跡が点在するかたちとなっています。
-------------------


【写真 上(左)】 登り口
【写真 下(右)】 参道-1
富貴野山は松崎市街地の北東にそびえる標高550mの山で、当山はその山腹にあります。
「富貴野山21世紀の森」というリラクゼーションエリアとなっていますが、かなり山深く、そのアプローチの長さは第8番益山寺と双璧です。
ただし路面はしっかりした舗装路なので、益山寺よりはアプローチは楽です。
「富貴野山21世紀の森」の駐車場に停めて、参道をのぼっていきます。
本来の参道は下の駐車場から少し下って大師橋を渡り、男坂ないし女坂経由の行程とみられます。
上の駐車場は本堂下にあるので、横着にもこちらに停めました。
さすがにお大師様ゆかりの霊山。あたりは清々しい空気に包まれています。


【写真 上(左)】 富貴野山稲荷
【写真 下(右)】 参道-2
駐車場そばに御鎮座の富貴野山稲荷は、当山の地主神あるいは鎮守かもしれません。
現地掲示によると、こちらには白山大権現が祀られているそうです。
舗装道をトラバース気味に歩いていくと、両側に石仏が並ぶ苔むした参道階段が出てきます。
そびえる杉木立の相間から陽射しが射し込み、雰囲気は抜群です。
こちらの石仏群は「宝蔵院石仏群」と呼ばれ、江戸時代に奉安されたもの。
約120体もの石仏はお大師様、大日如来、薬師如来、阿弥陀如来、地蔵尊、観音菩薩などさまざまで、信仰厚い村人たちが一体づつ背負って運び上げたとのこと。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道-3
参道階段をのぼり切ると広々とした平地が広がり、かつては伽藍が建ち並んでいたと思われるスケール感を感じます。
建物は3つ。
右手に長屋門?。正面がおそらく本堂、左手が開山堂です。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2


【写真 上(左)】 長屋門
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造銅板葺で、比較的新しい建立と思われます。
向拝柱はなく、左右の身舎柱に「豆國八十一番札所」「伊豆横道七番札所」の札番が掲げられています。
向拝見上げに院号扁額。右手には「富貴峯」の扁額も掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額-1

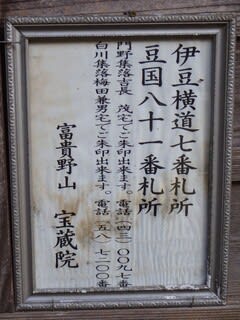
【写真 上(左)】 本堂扁額-2
【写真 下(右)】 御朱印案内
左手の開山堂は銅板葺宝形造で流れ向拝。
周囲に縁をめぐらし、相輪を立てた塔身の周囲に庇を降ろし、内側に身舎を抱く密教建築の山上伽藍です。


【写真 上(左)】 開山堂
【写真 下(右)】 開山堂向拝
水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に彫刻入りの板蟇股で、見上げに山号扁額。
正面の花狭間戸と左右の蔀戸が引き締まったイメージの意匠。
撮影角度が悪くて断言できないのですが、ひょっとすると天竺様の隅扇垂木かもしれません。
開山堂左手にある杉の大木は樹齢約400年。弘法大師の徳をしのび昔から「弘法杉」と呼ばれているそうです。
また、杉の根元にある二基の宝篋印塔は、曾我兄弟ゆかりと伝わります。


【写真 上(左)】 弘法杉
【写真 下(右)】 富貴野山からの展望
江戸時代の中期まで、寺庭に弘法大師お手植えと伝えられるモクセイ(モッコク・カツラとも)の巨木があったといいます。
また、お手植えのときにお大師様が遺された笈がいまも遺されているといいます。
御朱印は、本堂前に掲示されていた寺役さんに連絡をとり拝受しました。
寺役さんの納経所は山を下りた道沿いで、すぐにみつかりました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第82番 大悲山 慈眼寺(じげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
西伊豆町Web
西伊豆町一色56
臨済宗建長寺派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第6番
授与所:第83番東福寺
情報の少ない札所です。
始祖とされる復岩が明応三年(1494年)入寂であることから、開山はそれ以前、文明年間とみられています。
(延徳元年(1489年)、復山による開山という説もあり。)
正保元年(1644年)、僧・明山により再興されました。
赤穂四十七士のひとりで討ち入り後、大石の命を受け離脱した寺坂吉右ヱ門の墓があることで知られています。
『豆州志稿』には「一色村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊如意輪観世音 復岩ヲ祖トス(明応三年(1494年)寂ス) 正保元年(1644年)僧明山再興ス 地蔵堂寺域ニ有リ」とあります。
-------------------
伊豆の湯めぐりに没頭していた一時期、この山深い場所を一度通りかかったことがあります。
このお寺の先に、温泉マニアの間では有名な名湯、祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」がありそこに入湯したためです。
この札所へのアプローチとなる静岡県道59号伊東西伊豆線は、伊豆最悪の険道ともいわれます。
筆者は祢宜ノ畑温泉入湯後にこの県道を走って修禅寺に抜けたのですが、二度と通りたくないと思えるほどのキツイ道でした。
(険しいというか、細かいカーブが異様にしつこくつづく。)
この霊場巡りでは札番からいって慈眼寺から修禅寺に向かうことはないかと思いますが、「県道だから・・・」と安易に入り込むのは避けた方がいいかと思います。
こんな感じ↓です。
■ 怖っ!静岡険道(県道)59号(伊東西伊豆線) 松崎⇒仁科峠 バイク走行動画
慈眼寺へは大浜から仁科川沿いを3㎞ほどで、このあたりまでは川沿いのいたってふつうの道路なのでとくに問題はありません。


【写真 上(左)】 六地蔵群
【写真 下(右)】 参道入口


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂のすぐ横が駐車場なのでアプローチはすこぶる楽です。
昭和四十年代の建立の本堂はアーチ状の屋根の近代建築ですが、向拝はきっちり設けられています。
向拝見上げに山号扁額。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御本尊は小さな如意輪観世音菩薩像とのことで、伊豆横道三十三観音霊場第6番の札所本尊もこちらの観音様かと思われます。
こちらの鈴木氏墓地のなかに赤穂四十七士のひとり寺坂吉右ヱ門の墓と呼ばれてきた地蔵尊(あるいは石像とも)が安置されているそうです。
言い伝えによると、討ち入り後、義士供養のため僧形となり、諸国遍歴の途に鈴木権内方に滞在し一生を終えたといいます。
市資料によると、当寺過去帳に「寺坂吉右ヱ門事一相西円上座」、「但し、江戸の人四十七人の一人」とあるそうで、富貴野山宝蔵院に梵鐘を献納した話なども伝えられています。
御朱印は第83番東福寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 如意輪観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

→ 祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」の入湯レポ
■ 第83番 照嶺山 東福寺(とうふくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
西伊豆町Web
西伊豆町観光協会Web
西伊豆町中24-2
臨済宗建長寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
現地掲示の由緒書、『豆州志稿』等によると、濱村字澤田カ原(仁科字浜村、弘法大師遊行の折に安居された旧跡とも)に石室(岩の堂)として草創。
天福元年(1233年)、真言宗の一寺をなし草創時の年号から天福寺と号しました。
嘉元(1303-1306年)の頃(嘉元二年とも)災害に遭い、雲林和尚が濱村中村字中の島に移し旧天福寺の号に因んで天福山と号したといいます。(このとき東福寺と号したという説もあり。)
永和三年(1377年)災害のため諸堂が大破、應永二年(1395年)佛印大光禅師を中興開祖とし、真言宗から臨済宗へと改宗。
文明九年(1477年)激しい波浪に見舞われ堂宇は漂流、同十八年佐々木(山本)盛季が現在地に移して再興し、寺号を東福寺と改めたと伝わります。
よって、佐々木(山本)盛季を東福寺殿と称し、当山開基としています。
当山の本堂天井には漆喰の見事な五百羅漢が描かれているため、「五百羅漢の寺」としても知られています。
『豆州志稿』には「中村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊阿彌陀 嘉元(1303-1306年)ノ頃 雲林和尚濱村ノ天福寺ヲ引ク 因テ天福山ト称セリ 天福ノ紀号僅ニ一年ナリシ故 之ヲ忌テ照嶺ト改ム 天福元年(1233年)濱村字澤田カ原ニ創立ス 後僧雲林当村中島ニ移ス 應永中(1394-1428年)真言ヲ改テ臨済宗ト為シ 僧佛印ヲ祖トス 文明九年(1477年)激浪ノ為ニ漂流ス 同十八年佐々木盛季復現地ニ移ス 寺域地蔵堂観音堂有」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口&山門
【写真 下(右)】 山門扁額
静岡県道59号伊東西伊豆線沿い、第82番慈眼寺から大浜(伊豆西海岸)に戻る途中の仁科川沿いにあります。
参道入口の寺号標には「五百羅漢の寺」。
その先の山門は入母屋屋根桟瓦葺、上層鐘楼四脚の高欄付楼門で上層に山号扁額を置いています。
異様に高い礎盤は水害から護るためでしょうか。
小高い山を背に、こぢんまりとまとまった、落ちついた雰囲気のお寺さんです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面の本堂は寄棟造銅板葺で、向拝部に顕著な千鳥破風を附設しています。
平入りと思いますが、千鳥破風があまりに目立つので、一瞬妻入りかと思いました。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 寺号の表札?
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ梁、中備に龍の彫刻。
左右の繋ぎ虹梁上には板蟇股を置いています。
見上げには扁額というか、寺号の表札?を掲げています。
本堂向かって右手前のお像は修行大師像のようにも思えるのですが、確信もてず。
本堂内の天井には、昭和初期に浅草の仏師・田村利光(酒豪だったので「のん兵衛安さん」と呼ばれた)により漆喰で描かれた五百羅漢があり、御内陣の花鳥・龍・天女とともに秀作とされています。
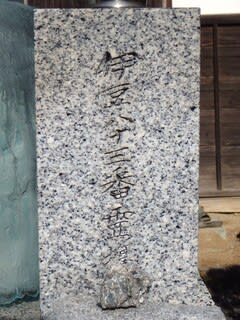

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 身代り地蔵尊
山内には地蔵堂があり、端正な地蔵尊坐像が御座します。
現地説明書によると、こちらは百五十余年前に当山第14世住職が両親菩提と諸民の災害除のために、大本山鎌倉建長寺の御本尊・身代り地蔵尊のお今身を願い当山に勤把したお地蔵様とのことです。


【写真 上(左)】 鎮守?
【写真 下(右)】 足神社
山内には鎮守とみられるお社、足神社が祀られています。
足神社は安政時代の創祀でもともと旧道に御鎮座でしたが、道路拡張に伴い平成元年当山に勧請とのことです。(山内石碑より)
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印
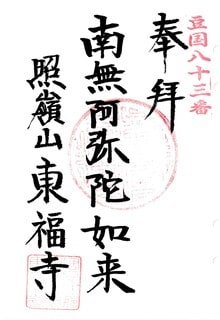

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第84番 正島山 法眼寺(ほうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
公式Web
西伊豆町仁科860-1
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡
ここから松崎町を離れ、西伊豆町に入ります。
第84番は、西海岸を走る国道136号に戻り仁科の街なかにある法眼寺です。
『こころの旅』によると、初めは仁科の安城山麓にあった法眼庵という小庵でしたが、波濤により大破、荒廃。
永享年間(1429-1441年)ののち、幽岩和尚が濱村長平寺を合せて起立・開林。(『豆州志稿』)
享保年間(1716-1736年)にこの地を修行で通りかかった僧、幽厳が法眼庵と堂ヶ島の走嶋山長平寺の荒廃を嘆き、二院を合併して正島山法眼寺としたという説もあります。(『こころの旅』)
法眼庵から数えて約四百年の間、西伊豆・仁科の海で働く人々の安全と繁栄のための鎮守の寺として続いてきたといいます。
『豆州志稿』には「濱村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊釋迦阿彌陀薬師 初法眼庵ト称ス 永享十六年(註:永享は十三年まで、1429-1441年)同村長平寺ヲ合セテ当寺ヲ起立ス 幽岩和尚開林(寛正六年(1465年)寂ス) 此寺安城山ヲ後ニシ 門前清渓ヲ帯ヒ 風景極テ幽邃」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 隣接する仁科港
【写真 下(右)】 山内入口
風光明媚な仁科港に面した、明るい雰囲気のお寺さまです。
なお、この仁科港の北側には西伊豆屈指のシーサイド露天として人気が高い「沢田公園露天風呂」があります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
開放的な山内で、正面に寄棟造本瓦葺流れ向拝の本堂。
水引虹梁両端に禅宗様の木鼻、身舎側に繋ぎ梁、中備に寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 堂内扁額
【写真 下(右)】 堂内天井画
本堂内は綺麗に整頓され、天井の格子には綺麗な花の天井画が施されていました。


【写真 上(左)】 天王神社
【写真 下(右)】 天王神社の扁額
隣接してスサノオノミコトを御祭神とする天王神社が御鎮座。
稲ワラを編み上げ社の頭上に張り渡す「天王様のお注連あげ」で知られる神社です。
位置関係からして法眼寺は元別当のような感じがしますが、これを示す史料はみつかりませんでした。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印
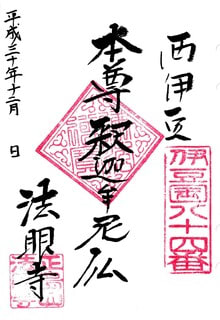

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第85番 満行山 航浦院(こうほいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
沼津市西浦江梨149
臨済宗円覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
この札所は、札番からするとかなり離れたところにありますが、札番順にご紹介していますのでここでとり上げます。
こちらはもともと旧別格第8番の札所でしたが、平成31年4月24日より第85番霊場になっているようです。
もともと第8番霊場についてはナゾがありました。
〔 「こころの旅」掲載地図より 〕

第5番玉洞院は狩野川右岸の牧之郷、第6番金剛寺・第7番泉龍寺は狩野川左岸の山田川、第8番益山寺は山田川支流の小山田川を山側にふかく遡ったところにあります。
一方、旧別格第8番の 航浦院は駿河湾に面した西浦江梨にあります。
山田川筋から西浦江梨に向かうには、峠越えをして内浦に降りそこから駿河湾沿いを延々と西進する必要があります。
第9番澄楽寺は第5番玉洞院のそばなので、帰路もその行程ないし三津浜経由の大回りの行程となります。
航浦院は伊豆水軍の名族・鈴木(杉本)氏ゆかりで、白隠禅師が受戒したという名刹なのでこれを外すわけにはいかず、(旧)別格第8番というかたちで設定されたのかもしれません。
ルートからすると戸田の第87番大行寺のつぎに別格ないしは掛所として設定した方が巡礼者の負担は少ないですが、そうはできない何らかの事情があったのかも。
いずれにしても、この札所は西伊豆・戸田からも中伊豆からも遠く隔たった場所にありますが、正式に第85番札所となった以上、避けて通れない存在となりました。
かなりの大回りにはなりますが、近くには伊豆の七不思議とされる大瀬崎大池・大瀬神社もあり、駿河湾の浦々を辿る県道17号沼津土肥線は優れたドライブ・ルートなので、訪れる価値は充分あると思います。
航浦院は、紀州から西浦に移住し、伊豆水軍の雄として約二百数十年間にわたり西浦一帯を治めた鈴木氏(杉本氏)の菩提寺です。
『豆州志稿』には、文明年間(1469-1487年)に地頭の鈴木繁用が父・繁郷冥助の為ニ造立とあり、僧・業道(業堂寿和尚大禅師とも)による開山とされています。
(1330年頃の創立という説もあり。)
開基の鈴木(杉本)氏は西浦江梨を根拠地にした伊豆水軍の雄で、その経済力を背景に菩提寺として営々当山を外護してきたものとみられます。
杉本左京大夫繁郷の法名は「航浦院殿江巖道海大居士」で、当山の院号はこちらと関連のあるものと思われます。
また、萬行山の山号は近くにあった萬行寺ゆかりのものとみられています。
『豆州志稿』によると、寛政年間(1789-1801年)僧・神洲が再興しています。
『豆州志稿』には「江梨村 臨済宗円覚寺派 田方郡奈古谷國清寺末 本尊阿彌陀 文明中(1469-1487年)地頭鈴木繁用其父繁郷冥助ノ為ニ造立ス(略)僧業道ヲ開山トス 後寛政中(1789-1801年)僧神洲再興ス 本尊ハ鈴木繁用ノ男繁宗ノ女ノ祈念佛也 観音堂在リ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
このエリアは伊豆半島にはめずらしい北向きの海岸ですが、当山は南傾の高台にあるので陽光降りそそぐ明るい山内です。
航浦院はこの高台に、円覚寺百観音霊場第32番廣大山 海蔵寺とともにあります。
城郭を思わせる石垣を幾重にも巡らし風格がありますが、山門はありません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂
参道手前に寺号標。その先には札所標もありました。
曲がり参道で階段を昇った中庭の左手に本堂があります。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂札所板
寄棟造銅板葺で向拝柱はありません。
向拝正面硝子扉のよこに札所板、上には山号扁額が掲げられています。
御本尊は開基・鈴木繁用の男(子)繁宗の女(室)の祈念佛と伝わります。


【写真 上(左)】 半僧坊大権現の堂宇
【写真 下(右)】 同扁額
庫裡のそばにもうひとつ堂宇があり、こちらは半僧坊大権現のお堂かと思われますがこちらにも伊豆八十八ヶ所の札所板が掲げられていました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 半僧坊大権現の御朱印 〕

【 BGM 】
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド - サザンオルスタース
■ さよなら夏の日 - 山下達郎
■ Crescent aventure - 角松敏生
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。
また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
(新?)第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11 ← 最新記事へつづく。
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第72番 黒崎山 禅宗院(ぜんしゅういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町石部74
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
温泉好きのあいだでは「平六地蔵露天風呂」で知られる石部の集落にあります。
西伊豆南部では石部の南のグルメ民宿で知られる雲見温泉が有名ですが、伊豆八十八ヶ所の札所は雲見にはなく、石部の当山から北上していくかたちとなります。
ただし札番からすると、第71番普照寺は南伊豆町伊浜なので、旧来は海沿いの現・国道136号を辿る巡路だったとみられます。
『こころの旅』『豆州志稿』によると当初は真言宗。
善瀲院という名で海浜にありましたが、寛文八年(1668年)以前に香雲寺十一世天國恩龍和尚が曹洞宗に改め、現地に遷ったとされています。
『豆州志稿』には「石部村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊観世音 本海濱ニ在リテ 善瀲院ト称セリ 初真言宗ナリ 蓋天國和尚(寛文八年(1668年)寂)ノ時寺ヲ移シ改宗シテ香雲寺ニ隷ス」
とあります。
-------------------
松崎の南には、三浦(さんぽ)地区と総称される岩地、石部、雲見の集落が点在し、魚料理のおいしい民宿エリアとして知られています。
また、霊場とは直接関係ないですが、松崎から石部にかけては風呂石として有名な「伊豆石」の産地で、道部の「室岩洞」は採掘遺跡として公開されています。
(これまた関係ないことですが(笑)、筆者は伊豆石の浴槽がいちばん好きです。)


【写真 上(左)】 平六地蔵露天風呂-1
【写真 下(右)】 平六地蔵露天風呂-2
さらに関係ないことですが、石部のとなりの岩地海岸には期間限定ですが、温泉船「ダジュール岩地」が開設されて、岩地温泉を楽しむことができます。
→ 岩地温泉 「(温泉船)ダジュール岩地」の入湯レポ
石部に来たのは2008年秋、「平六地蔵露天風呂」入湯以来です。
そのときは伊豆八十八ヶ所の存在じたい知らなかったので、当然禅宗院はスルーしています。
石部は泉質のよい温泉地で、温泉旅館&民宿が点在しています。
海水浴場がすぐなので、夏場はかなり賑わうようです。
すぐそばには石部漁港もあり、温泉、海鮮グルメ、マリンスポーツの三拍子揃った観光地です。


【写真 上(左)】 石部あたりの海岸
【写真 下(右)】 アプローチ道(参道)
禅宗院は石部集落の南東の山ぎわにあります。
集落からのアプローチ道を登っていくと、右手に「不許葷酒入山門」の戒壇石が出てきます。


【写真 上(左)】 六地蔵と本堂
【写真 下(右)】 地蔵尊群
さらに進むと六地蔵とそのおくに本堂。
地蔵信仰の篤い地域らしく、山内には赤い帽子と前掛けを着けられたたくさんの地蔵尊が御座します。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 庫裡サイドからの本堂
背後に小山を背負う寺院らしい立地で、西伊豆らしい明るい山内。
入母屋造銅板葺で向拝柱のないシンプルなつくり。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
屋根は照りを帯びしっかりとした降り棟も備えますが、平入りの身舎は桁行き方向にスクエアなサッシュ窓を連ねて、いささか風変わりな意匠です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第73番 霊鷲山 常在寺(じょうざいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町岩科南側321
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:本堂内に印判あり
風光明媚な松崎町は市街エリアでも温泉が楽しめ、西伊豆屈指の観光地となっています。
良港をもち、ふるくから物産の集積地として発展、明治初期には絹の輸出ブームに乗って養蚕が盛んになり、いまも残る豪商の蔵や邸宅の壁は”なまこ壁”(平瓦を壁に貼り付け、目地を漆喰で盛り上げる手法)で仕上げられ、「松崎のなまこ壁」として有名です。
教育も盛んな地で、「岩科学校」は甲府の旧陸沢学校、松本の旧開智学校などに次ぐ古い学校旧跡として国指定の重要文化財に指定されています。
江戸時代に左官の名工として名をあげた入江長八(伊豆の長八)は松崎出身で、町の中心部には「伊豆の長八美術館」があります。
このように文化の香り高い西伊豆の要地だけあって寺院も多く、この地も札所が集中しています。
常在寺は県道121号線南伊豆松崎線、蛇石峠から県道に沿って流れる岩科川沿いにあります。
札番からすると、第71番普照寺は南伊豆町伊浜、第72番禅宗院は海沿いの石部なので、海沿いの現・国道136号を辿ったのちに一旦蛇石峠側に岩科川を遡り、第73.74.75番と巡って松崎の街なか(第76番)に入る巡路となっています。
現在では第69番常石寺から県道121号蛇石峠を越えて松崎に入るルートも考えられますが、当時は蛇石峠は越えず、第69番常石寺から南方に山越えをして子浦の第70番金泉寺に入ったものとみられます。
このあたりのルート取りは悩むところですが、やはり一度は蛇石峠を越えることになるかと思います。
道幅は特段狭くはなく、全線舗装道ですがかなり小刻みなブラインドカーブがつづくので運転は要注意です。
【蛇石峠(県道121号)】静岡県賀茂郡松崎町~南伊豆町(2014.04.27)
※ 3.7倍速の動画です。
『こころの旅』『豆州志稿』によると、古くから小さな釈迦堂があったところに、永享元年(1429年)無範という禅僧が留まり、近在信徒の喜捨によって堂宇を建立し、常在寺と号して臨済宗寺院を開いたとされます。
『豆州志稿』には「平田山常在寺 岩科村 臨済宗建長寺派 那賀郡舟田帰一寺末 本尊釋迦 無範禅師(永享十二年(1440年)寂)ヲ初祖ニ為ス」とあります。
-------------------

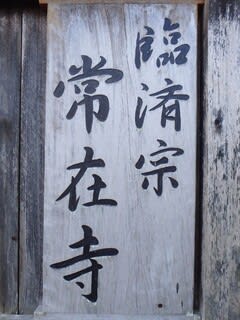
【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号板


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 本堂
県道から一本入った路地に、かなり急な参道階段を構えています。
階段右手に寺号板と札所板。
登り切るとすぐに本堂。竹林を背負う安定感あるロケーション。
本堂手前の2メートルほどもある法華千部供養塔が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、大棟を高く持ち上げた特徴のある意匠。
身舎はブラック系の桟格子サッシュできりりと引き締まったイメージ。
向拝見上げに扁額を掲げていますが、御詠歌かもしれません。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 巡拝案内
向拝に「納経所本堂内」の掲示があったので、扉を開けてみるとなかに巡拝案内が貼り出され、御朱印台に印判類がセットされていました。
本堂内に駕籠が吊されていたので、相応の格式をもった寺院なのかもしれません。
巡拝案内通りに御朱印をいただき、本堂をあとにしました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

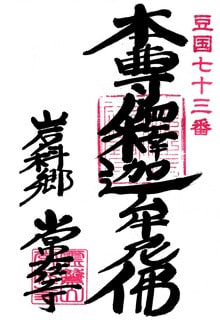
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳-1(揮毫)

御朱印帳-2(印判)
■ 第74番 嵯峨山 永禅寺(えいぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町岩科北側1312
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡玄関脇に印判あり
永禅寺も県道121号線南伊豆松崎線、蛇石峠から県道に沿って流れる岩科川沿いにあります。
『こころの旅』『豆州志稿』によると、仁安二年(1167年)に文覚上人がこの地を訪れた際、護持の釈迦如来像を安置して庵を建てたのが草創といいます。
建久中(1190-1199年)に永善寺(後永禅寺と改める)と号し、貞治中(1362-1368年)に僧寂室(近江永源寺の開山とも)が再興して臨済宗に改めたとされます。
『豆州志稿』には「岩科村 臨済宗建長寺派 那賀郡舟田帰一寺末 本尊釋迦 昔ハ真言宗ナリ 初庵ナリ 建久(1190-1199年)ヨリ永善寺(後永禅寺ト改ム)ト称ス 貞治中(1362-1368年)僧寂室再興シテ改宗ス 寂室禅師ヲ推テ開山トシ帰一寺ニ隷ス 寂室ハ江州永源寺ノ住僧ナリ(中略)本尊ハ亀玆國(筆者註:現.中国新疆ウイグル自治区/シルクロード上の古代アオシス都市)ノ佛工天竺國如来ノ像ヲ模刻シテ宗ノ聖禅院ノ本尊トス 釋●然宗佛工張滎ヲシテ又之ヲ模刻セシメ 帰國シテ洛西清冷寺ニ安置ス 運慶又清冷寺ノ像ヲ模刻シテ此寺ニ安ス」とあります。
『真言密教の本』(学研刊)などによると、文覚上人は鎌倉時代初期に活躍した真言宗の僧で俗名は遠藤盛遠。
出自は渡辺党・遠藤氏で摂津源氏の傘下にあり、北面の武士として鳥羽天皇の皇女統子内親王に出仕していましたが、19歳で出家したとされます。
『源平盛衰記』は、出家の原因として盛遠(文覚上人)が従兄弟で同僚の渡辺渡の妻で絶世の美女といわれた袈裟御前に横恋慕し、誤って殺してしまったことをあげています。
袈裟御前への恋に盲目となった盛遠は、袈裟御前に婚姻を迫りました。
このままでは夫を殺されると危惧した袈裟御前は、盛遠に「夫の渡辺渡を殺してから一緒になってほしい」旨もちかけ、夫の襲撃の手はずを整えました。
そして袈裟御前は自ら渡辺渡の寝床に入り、そうとは知らずに手はずどおりに襲撃した盛遠は、誤って袈裟御前を斬り殺してしまいました。
袈裟御前は夫の身を守るため、自ら犠牲になったともいわれます。
これを激しく悔いた盛遠はすべてを渡辺渡に告げ、「自分を手打ちにしてくれ」と懇願しました。
しかし、最愛の妻を失った渡辺渡は世の無常を感じ、盛遠を討つことなくその場で出家し仏門に入りました。
それを見た盛遠も追うように出家したということです。
自らの行為を贖罪するように、那智をはじめとする各地の霊地ですさまじい荒行を積み、呪術に通じた荒法師として知られるようになりました。
高雄山神護寺の再興を後白河天皇に強訴した咎で、伊豆国に配流されました。
承安三年(1173年)春、近藤四郎国高に預けられ、韮山の毘沙門堂を結んだとされます。
折しも源家の御曹司、頼朝公が近隣に流されていたため、頼朝公と知遇を得て源氏再興を熱烈に説いたとされます。
この際、頼朝公の父・義朝公の髑髏を取り出し蹶起を促したというのは有名な逸話です。
頼朝公が源氏再興を果たしたのちに、頼朝公は文覚上人に命じて毘沙門堂を建立させたという説もあります。(当初の号は安養浄土院、奈古屋寺から瑞龍山授福寺に改号、毘沙門堂は授福寺の堂宇)
伊豆から福原京の藤原光能のもとへ赴き、後白河法皇からの平氏追討の院宣をわずか8日で頼朝公にもたらしたという伝説的逸話も伝わります。
生来活動的な性格だったらしく、神護寺、東寺、高野山、東大寺、江の島弁財天などの大寺と深くかかわりをもったとされ、とくに神護寺は中興を果たしたとされます。
数々の修法を験じ「天狗を祀る」といわれたこと、また神出鬼没の移動の速さから、真言密教だけでなく、修験の道にも通じていたとみられています。
頼朝公存命中は大きな影響力をもったとされますが、頼朝公が逝去するや三左衛門事件(正治元年(1199年)2月、一条能保・高能父子の遺臣が権大納言源(土御門)通親の襲撃を企てたとして逮捕された事件)に巻き込まれ佐渡へ配流。
建仁二年(1202年)許されて京に戻るも、翌三年(1203年)後鳥羽上皇より守貞親王擁立の謀反の疑いをかけられ、対馬へ流罪となる途中、鎮西(九州)で客死と伝わります。
様々な験をあらわし、歯に衣を着せぬ物言いから「一代の怪僧」ともいわれ、歴史に名を残した文覚上人の遺跡は配流先の伊豆に多くあり、当山もそのひとつに数えられます。
御本尊の釈迦如来像は京都嵯峨の清涼寺の御本尊と同木同作(あるいは模刻とも)とされます。
なお、清涼寺の御本尊は天竺(インド)渡来の栴檀づくりの釈迦如来像と伝わります。(清涼寺寺伝)
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号板
第73番常在寺から蛇石峠に向かって県道をさらに遡ります。
県道に面して参道入口。
すぐそばには東海バスの「永禅寺前」バス停があります。
がっしりとした石垣を構え、右手に五輪塔、正面に山門、門柱には寺号板が掲げられていてこのあたりでは大がかりな寺院です。
山門手前に鉄柵が閉められているので、まさか参拝禁止? とおののきましたが、これはイノシシの侵入除けの鉄柵なのでした。
掲げられていた案内どおりに鉄柵を開け山内に入ります。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門。
左手背後に小山を背負った落ち着きのある山内で、清掃が行き届いて気持ちがいいです。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、こちらも大棟を高く持ち上げています。
身舎は木製の桟格子が連なり端正な印象。
向拝見上げに山号扁額を掲げています。
御朱印は霊場公式Webに「無住ですが御朱印所は庫裡側の玄関脇にございます。」とあるとおり、庫裡玄関脇でセルフで印判をいただきました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
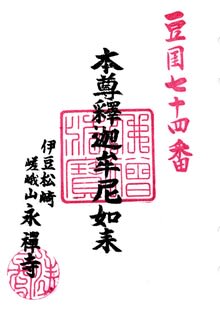

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第75番 岩科山 天然寺(てんねんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町岩科北側507
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
天然寺も県道121号線南伊豆松崎線、蛇石峠から県道に沿って流れる岩科川沿いにあります。
山内掲示および『こころの旅』『豆州志稿』によると、応仁二年(1468年)(文明九年(1477年)とも)雲譽文公上人により開創。
宝永二年(1705年)8月の大洪水により流失し、4年後の1709年に再建といいます。
『豆州志稿』には「岩科村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 文明九年(1477年)雲譽上人創ム 子院二定光院 天養院(明治七年廃ス)」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
岩科川から山裾に向かう傾斜地にあり参道も登りスロープです。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、たしか山号扁額を掲げていました。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 鐘楼と収蔵庫?
【写真 下(右)】 本堂
その先正面に形のよい小山を背負って本堂。
手前に鐘楼と見事ななまこ壁の収蔵庫?を構えています。
さすがになまこ壁の街、松崎の寺院です。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風。
水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ虹梁、中備には白色の彫刻入り板蟇股で見応えがあります。


【写真 上(左)】 木鼻
【写真 下(右)】 堂内の扁額
向拝身舎に扁額はありませんが、扉を開いた堂内見上げに寺号扁額が掲げられていました。
本堂内には、院派の仏師の作とみられる地蔵尊像、室町期作といわれる不動明王像のほか、釈迦如来、観世音菩薩、閻魔大王、青面金剛、弁財天、大黒天、毘沙門天、烏枢沙摩明王、徳川家康公像、歴代将軍の御位牌など多彩な尊格が御座すそうです。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第76番 清水山 浄泉寺(じょうせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町松崎43
浄土宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
この霊場ではめずらしく浄土宗寺院がつづきます。
松崎市街、延喜式内社の伊那下神社のそばにある浄土宗寺院です。
伊那下神社は、西伊豆では稀少な御朱印をいただける神社です。


【写真 上(左)】 伊那下神社
【写真 下(右)】 伊那下神社の御朱印
『こころの旅』によると、應永十一年(1404年)に及歎によって開創。
慶安元年(1648年)には徳川家光公による御朱印状を受けましたが、寛文十一年(1671年)八月洪水ニテ流出。
八世傳的が再興し、宝暦八年(1758年)には芝・増上寺の交代寺となりました。
『豆州志稿』には「松崎村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀観世音勢至 寺邊ニ清泉アリ取テ寺名トス 開祖及歎年代下知(或ハ云應永十一年(1404年)創立ナリト) 但曰当住迄十七世ナリト 寛文十一年(1671年)八月洪水ニテ流出 八世傳的再興ス 北条氏康寺領ヲ寄スト傳フレ共不詳 子院 寶壽院 随運院 西透院等(明治七年廃ス)」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
松崎の街なかにありますが、松崎は山が迫っているので、この寺院も背後に小山を背負う落ち着いたロケーションです。
参道入口に構える、入母屋屋根桟葺の朱塗りの四脚の楼門がひときわ目立ちます。
上層中央に山号扁額。
参道左手にたしか堂宇(経堂?)があったかと思いますが、なぜか写真がなく詳細不明。
参道正面の本堂は、入母屋造本瓦葺流れ向拝で整った軒唐破風を起こし、大棟には寺号が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ虹梁、中備上下に大がかりな板蟇股と彫刻。
さらにその上に兎毛通に経の巻獅子口を置いて見どころ豊富です。
向拝見上げには「法王殿?」の扁額、向拝柱には札所板が掲げられていました。
御本尊・阿弥陀三尊像は行基の作と伝わります。
御本尊の上の仏天蓋には、伊豆の長八作とされる飛天、左右の欄間には石田半兵衛の作と伝わる十六羅漢の透かし彫りが刻まれています。
また、裏庭は江戸時代に伊豆三名園のひとつと賞されたそうです。
山内掲示には下記のとおりありました。
・回る経堂、透かし彫り十六羅漢像、仏天蓋の長八天女、自然庭園、三十三観音、弘法大師作(伝)不動尊、水子・子育地蔵、もの思う石仏群
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第77番 文覚山 圓通寺(えんつうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町宮内130
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第4番
授与所:第78番禅海寺
山内由緒書、『こころの旅』によると、治承三年(1179年)の創始といわれ、僧文覚が伊豆韮山に流罪の際、ここに寄寓したことから文覚を開祖とし、のちに文覚山と号しました。
文覚はのちに当寺の奥の院となった観音堂で源頼朝公と会見し、源家再興を促したと伝わります。
(『豆州志稿』には、この説は「附会」とあります。)
『霊場めぐり』によると、この観音堂は相生堂と呼ばれましたが、いまは廃堂となって頼朝公、文覚の木像は圓通寺本堂に安置されているとの由。
相生堂には頼朝公お手植えの相生松がありましたが、枯れてしまったとのこと。
また、古くは妙智山円通寺という真言宗の小庵で、弘法大師の御作といわれる観音像を安置したともいいます。
のちに東林友丘和尚(應安二年(1369年)寂)により臨済宗に宗を改めました。
以前は那賀川の岸辺に沿って堂宇が建てられていましたが、200年ほど前に現地に遷って山号を改めています。
『豆州志稿』には「宮内村 臨済宗建長寺派 那賀郡舟田帰一寺末 本尊正観世音 文覚流人タル時 暫ク此ニ住ス 以テ開祖トス 俗ニ傳フ頼朝卿ニ父ノ髑髏ヲ視セシハ此ナリト 此傳附会ナリトス 文覚源義朝ノ髑髏ヲ頼朝ニ視セシハ田方郡奈印古谷ナリ(平家物語源平盛衰記等参観) 東林和尚ノ時ヨリ建長寺派下ト為ル 東林ハ應安二年(1369年)滅ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
松崎の街はずれ、伊那上神社の南側の路地おくにあります。
参道まわりは広く、かなりの格式の寺院であったことがうかがわれます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門ないし薬医門で、門柱に寺号板が掲げられています。
くぐるとすぐに階段。正面が庫裡で、いまは塾になっているようです。
左に棟つづきで本堂。その右手前に鐘楼。
この位置に鐘楼は、めずらしい伽藍配置かと思います。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上部に寺号扁額を掲げています。
向拝硝子戸下欄には伊豆八十八ヶ所と伊豆横道観音霊場の札所板が打ち付けられ、「御朱印は禅海寺まで」と読めます。
御本尊は弘法大師の御作とも伝わる聖観世音菩薩像です。
伊豆横道三十三観音霊場は頼朝公と所縁のふかい霊場で、頼朝公ゆかりの伝承が伝わるこの寺は札所にふさわしいかもしれません。


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 堂宇
本堂左手にある寄棟造桟瓦葺流れ向拝の堂宇の堂宇本尊は、扁額がないのでよくわかりません。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、中備に波様の彫刻はいずれも精緻な彫りです。
原則無住で、御朱印は第78番禅海寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
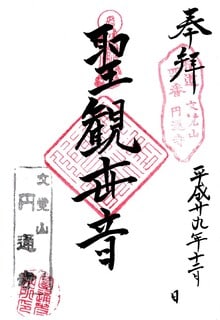
■ 第78番 祥雲山 禅海寺(ぜんかいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町江奈44
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』によると、当山の由緒書には、建久三年(1192年)に栄西禅師がこの地を訪れ一宇を造り、祥雲山禅海寺と名づけたとありますが、住職によると栄西禅師は勧請されて始祖になったもので、実際は弟子の建立とのことです。
建長四年(1252年)に当山の御本尊、釈迦如来を夢にみた鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王と執権・北条時頼が堂宇を再建、寄進をしたために宗尊親王の開基とされています。
『豆州志稿』には「江奈村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊釋迦 建久中(1190-1199年)創立 僧滎西ヲ請シテ開山トス 往昔鎌倉幕府ヨリ寺領ヲ附セリト傳フレトモ詳ナラス 永享五年(1433年)住山和尚建ツ 再興ナリ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
こちらは松崎港の東側の山手、江奈地区にあります。
ロケ的には松崎の街の北のはずれでしょうか。
山門は切妻屋根桟瓦葺で大棟に寺号を掲げ、がっしりとした降棟を降ろす四脚門で、名刹の風格があります。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2


【写真 上(左)】 六地蔵塔
【写真 下(右)】 本堂
本堂は背後に山を背負って寄棟造桟瓦葺。向かって左に寄せて唐破風の向拝を附設しています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備上に笈形付大瓶束。
左右の繋ぎ虹梁の上にも板蟇股をおき、上部は格天井と手が込んでいますが扁額はありません。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝扉を開くと堂内見上げに寺号扁額が掲げられていました。
堂内は禅刹らしく、すっきりと整えられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来 /主印はいずれも三寶印
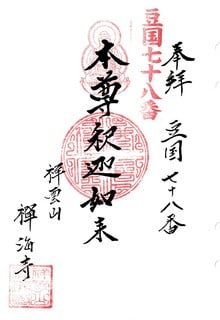

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第79番 曹源山 建久寺(けんきゅうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町建久寺68
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:建久寺酒店(松崎町那賀5-5)
建久年間(1190-1198年)に創立と伝わる古刹です。
後に安山という僧が再興、那賀村にあった当山を現在地に遷し、同時に檀徒も移住したといいます。
永正4年(1507年)に焼失し、これ以外の詳細は伝わっていません。
『豆州志稿』には「建久寺村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊観世音 建久中(1190-1199年)立ツ 今安山和尚ヲ祖トス 蓋中興ナリ 初那賀村ニ在リ 後現地ニ転ス 担徒随テ移住シ遂ニ一村ヲ為シ建久寺村ト称スト云 往昔巨刹ニシテ寺領ヲ有シタリト傳フレ共 永正四年(1507年)焼亡舊記ノ証スヘキ無シ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門と本堂
こちらは松崎港に注ぐ那賀川沿い、建久寺地区にあります。
『豆州志稿』によると「建久寺」の地名は、当初那賀村にあった当寺が檀家とともにこの地に移ったためつけられたとのこと。
人気宿として知られる桜田温泉「山芳園」の東側で、ここからさらに那賀川を遡ると”化粧の湯”と呼ばれ名宿として知られた大沢温泉「大沢温泉ホテル」がありましたが、令和2年12月末、日帰り温泉施設「大沢温泉 依田之庄」として装いを新たにした模様です。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山門扁額
参道左手前に真新しい札所標。
その先に寺号扁額を掲げた桟瓦葺の高麗門。
くぐった正面が本堂で、向かって右手前に白い聖観世音菩薩像が御座します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 聖観世音菩薩像


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱はなく、左に寄せた向拝の見上げに山号扁額を掲げています。
向拝はサッシュ扉で、比較的新しい建物とみられます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 建久寺酒店
こちらは無住で、御朱印は那賀地区の街なかにある建久寺酒店で拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11 ← 最新記事へつづく。
【 BGM 】
■ クリスマス イブ - 山下達郞 MV - JR東海 CM
■ 遠い街から - 今井美樹 MIKI IMAI LIVE AT ORCHARD HALL 2003
■ Celtic Prayer - Méav
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。
また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
(新?)第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11 ← 最新記事へつづく。
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第72番 黒崎山 禅宗院(ぜんしゅういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町石部74
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
温泉好きのあいだでは「平六地蔵露天風呂」で知られる石部の集落にあります。
西伊豆南部では石部の南のグルメ民宿で知られる雲見温泉が有名ですが、伊豆八十八ヶ所の札所は雲見にはなく、石部の当山から北上していくかたちとなります。
ただし札番からすると、第71番普照寺は南伊豆町伊浜なので、旧来は海沿いの現・国道136号を辿る巡路だったとみられます。
『こころの旅』『豆州志稿』によると当初は真言宗。
善瀲院という名で海浜にありましたが、寛文八年(1668年)以前に香雲寺十一世天國恩龍和尚が曹洞宗に改め、現地に遷ったとされています。
『豆州志稿』には「石部村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊観世音 本海濱ニ在リテ 善瀲院ト称セリ 初真言宗ナリ 蓋天國和尚(寛文八年(1668年)寂)ノ時寺ヲ移シ改宗シテ香雲寺ニ隷ス」
とあります。
-------------------
松崎の南には、三浦(さんぽ)地区と総称される岩地、石部、雲見の集落が点在し、魚料理のおいしい民宿エリアとして知られています。
また、霊場とは直接関係ないですが、松崎から石部にかけては風呂石として有名な「伊豆石」の産地で、道部の「室岩洞」は採掘遺跡として公開されています。
(これまた関係ないことですが(笑)、筆者は伊豆石の浴槽がいちばん好きです。)


【写真 上(左)】 平六地蔵露天風呂-1
【写真 下(右)】 平六地蔵露天風呂-2
さらに関係ないことですが、石部のとなりの岩地海岸には期間限定ですが、温泉船「ダジュール岩地」が開設されて、岩地温泉を楽しむことができます。
→ 岩地温泉 「(温泉船)ダジュール岩地」の入湯レポ
石部に来たのは2008年秋、「平六地蔵露天風呂」入湯以来です。
そのときは伊豆八十八ヶ所の存在じたい知らなかったので、当然禅宗院はスルーしています。
石部は泉質のよい温泉地で、温泉旅館&民宿が点在しています。
海水浴場がすぐなので、夏場はかなり賑わうようです。
すぐそばには石部漁港もあり、温泉、海鮮グルメ、マリンスポーツの三拍子揃った観光地です。


【写真 上(左)】 石部あたりの海岸
【写真 下(右)】 アプローチ道(参道)
禅宗院は石部集落の南東の山ぎわにあります。
集落からのアプローチ道を登っていくと、右手に「不許葷酒入山門」の戒壇石が出てきます。


【写真 上(左)】 六地蔵と本堂
【写真 下(右)】 地蔵尊群
さらに進むと六地蔵とそのおくに本堂。
地蔵信仰の篤い地域らしく、山内には赤い帽子と前掛けを着けられたたくさんの地蔵尊が御座します。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 庫裡サイドからの本堂
背後に小山を背負う寺院らしい立地で、西伊豆らしい明るい山内。
入母屋造銅板葺で向拝柱のないシンプルなつくり。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
屋根は照りを帯びしっかりとした降り棟も備えますが、平入りの身舎は桁行き方向にスクエアなサッシュ窓を連ねて、いささか風変わりな意匠です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第73番 霊鷲山 常在寺(じょうざいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町岩科南側321
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:本堂内に印判あり
風光明媚な松崎町は市街エリアでも温泉が楽しめ、西伊豆屈指の観光地となっています。
良港をもち、ふるくから物産の集積地として発展、明治初期には絹の輸出ブームに乗って養蚕が盛んになり、いまも残る豪商の蔵や邸宅の壁は”なまこ壁”(平瓦を壁に貼り付け、目地を漆喰で盛り上げる手法)で仕上げられ、「松崎のなまこ壁」として有名です。
教育も盛んな地で、「岩科学校」は甲府の旧陸沢学校、松本の旧開智学校などに次ぐ古い学校旧跡として国指定の重要文化財に指定されています。
江戸時代に左官の名工として名をあげた入江長八(伊豆の長八)は松崎出身で、町の中心部には「伊豆の長八美術館」があります。
このように文化の香り高い西伊豆の要地だけあって寺院も多く、この地も札所が集中しています。
常在寺は県道121号線南伊豆松崎線、蛇石峠から県道に沿って流れる岩科川沿いにあります。
札番からすると、第71番普照寺は南伊豆町伊浜、第72番禅宗院は海沿いの石部なので、海沿いの現・国道136号を辿ったのちに一旦蛇石峠側に岩科川を遡り、第73.74.75番と巡って松崎の街なか(第76番)に入る巡路となっています。
現在では第69番常石寺から県道121号蛇石峠を越えて松崎に入るルートも考えられますが、当時は蛇石峠は越えず、第69番常石寺から南方に山越えをして子浦の第70番金泉寺に入ったものとみられます。
このあたりのルート取りは悩むところですが、やはり一度は蛇石峠を越えることになるかと思います。
道幅は特段狭くはなく、全線舗装道ですがかなり小刻みなブラインドカーブがつづくので運転は要注意です。
【蛇石峠(県道121号)】静岡県賀茂郡松崎町~南伊豆町(2014.04.27)
※ 3.7倍速の動画です。
『こころの旅』『豆州志稿』によると、古くから小さな釈迦堂があったところに、永享元年(1429年)無範という禅僧が留まり、近在信徒の喜捨によって堂宇を建立し、常在寺と号して臨済宗寺院を開いたとされます。
『豆州志稿』には「平田山常在寺 岩科村 臨済宗建長寺派 那賀郡舟田帰一寺末 本尊釋迦 無範禅師(永享十二年(1440年)寂)ヲ初祖ニ為ス」とあります。
-------------------

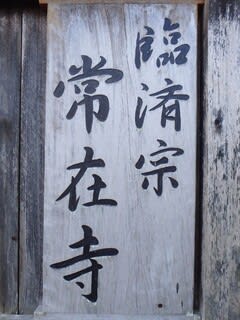
【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号板


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 本堂
県道から一本入った路地に、かなり急な参道階段を構えています。
階段右手に寺号板と札所板。
登り切るとすぐに本堂。竹林を背負う安定感あるロケーション。
本堂手前の2メートルほどもある法華千部供養塔が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、大棟を高く持ち上げた特徴のある意匠。
身舎はブラック系の桟格子サッシュできりりと引き締まったイメージ。
向拝見上げに扁額を掲げていますが、御詠歌かもしれません。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 巡拝案内
向拝に「納経所本堂内」の掲示があったので、扉を開けてみるとなかに巡拝案内が貼り出され、御朱印台に印判類がセットされていました。
本堂内に駕籠が吊されていたので、相応の格式をもった寺院なのかもしれません。
巡拝案内通りに御朱印をいただき、本堂をあとにしました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

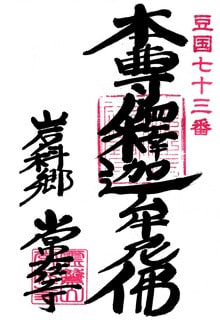
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳-1(揮毫)

御朱印帳-2(印判)
■ 第74番 嵯峨山 永禅寺(えいぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町岩科北側1312
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡玄関脇に印判あり
永禅寺も県道121号線南伊豆松崎線、蛇石峠から県道に沿って流れる岩科川沿いにあります。
『こころの旅』『豆州志稿』によると、仁安二年(1167年)に文覚上人がこの地を訪れた際、護持の釈迦如来像を安置して庵を建てたのが草創といいます。
建久中(1190-1199年)に永善寺(後永禅寺と改める)と号し、貞治中(1362-1368年)に僧寂室(近江永源寺の開山とも)が再興して臨済宗に改めたとされます。
『豆州志稿』には「岩科村 臨済宗建長寺派 那賀郡舟田帰一寺末 本尊釋迦 昔ハ真言宗ナリ 初庵ナリ 建久(1190-1199年)ヨリ永善寺(後永禅寺ト改ム)ト称ス 貞治中(1362-1368年)僧寂室再興シテ改宗ス 寂室禅師ヲ推テ開山トシ帰一寺ニ隷ス 寂室ハ江州永源寺ノ住僧ナリ(中略)本尊ハ亀玆國(筆者註:現.中国新疆ウイグル自治区/シルクロード上の古代アオシス都市)ノ佛工天竺國如来ノ像ヲ模刻シテ宗ノ聖禅院ノ本尊トス 釋●然宗佛工張滎ヲシテ又之ヲ模刻セシメ 帰國シテ洛西清冷寺ニ安置ス 運慶又清冷寺ノ像ヲ模刻シテ此寺ニ安ス」とあります。
『真言密教の本』(学研刊)などによると、文覚上人は鎌倉時代初期に活躍した真言宗の僧で俗名は遠藤盛遠。
出自は渡辺党・遠藤氏で摂津源氏の傘下にあり、北面の武士として鳥羽天皇の皇女統子内親王に出仕していましたが、19歳で出家したとされます。
『源平盛衰記』は、出家の原因として盛遠(文覚上人)が従兄弟で同僚の渡辺渡の妻で絶世の美女といわれた袈裟御前に横恋慕し、誤って殺してしまったことをあげています。
袈裟御前への恋に盲目となった盛遠は、袈裟御前に婚姻を迫りました。
このままでは夫を殺されると危惧した袈裟御前は、盛遠に「夫の渡辺渡を殺してから一緒になってほしい」旨もちかけ、夫の襲撃の手はずを整えました。
そして袈裟御前は自ら渡辺渡の寝床に入り、そうとは知らずに手はずどおりに襲撃した盛遠は、誤って袈裟御前を斬り殺してしまいました。
袈裟御前は夫の身を守るため、自ら犠牲になったともいわれます。
これを激しく悔いた盛遠はすべてを渡辺渡に告げ、「自分を手打ちにしてくれ」と懇願しました。
しかし、最愛の妻を失った渡辺渡は世の無常を感じ、盛遠を討つことなくその場で出家し仏門に入りました。
それを見た盛遠も追うように出家したということです。
自らの行為を贖罪するように、那智をはじめとする各地の霊地ですさまじい荒行を積み、呪術に通じた荒法師として知られるようになりました。
高雄山神護寺の再興を後白河天皇に強訴した咎で、伊豆国に配流されました。
承安三年(1173年)春、近藤四郎国高に預けられ、韮山の毘沙門堂を結んだとされます。
折しも源家の御曹司、頼朝公が近隣に流されていたため、頼朝公と知遇を得て源氏再興を熱烈に説いたとされます。
この際、頼朝公の父・義朝公の髑髏を取り出し蹶起を促したというのは有名な逸話です。
頼朝公が源氏再興を果たしたのちに、頼朝公は文覚上人に命じて毘沙門堂を建立させたという説もあります。(当初の号は安養浄土院、奈古屋寺から瑞龍山授福寺に改号、毘沙門堂は授福寺の堂宇)
伊豆から福原京の藤原光能のもとへ赴き、後白河法皇からの平氏追討の院宣をわずか8日で頼朝公にもたらしたという伝説的逸話も伝わります。
生来活動的な性格だったらしく、神護寺、東寺、高野山、東大寺、江の島弁財天などの大寺と深くかかわりをもったとされ、とくに神護寺は中興を果たしたとされます。
数々の修法を験じ「天狗を祀る」といわれたこと、また神出鬼没の移動の速さから、真言密教だけでなく、修験の道にも通じていたとみられています。
頼朝公存命中は大きな影響力をもったとされますが、頼朝公が逝去するや三左衛門事件(正治元年(1199年)2月、一条能保・高能父子の遺臣が権大納言源(土御門)通親の襲撃を企てたとして逮捕された事件)に巻き込まれ佐渡へ配流。
建仁二年(1202年)許されて京に戻るも、翌三年(1203年)後鳥羽上皇より守貞親王擁立の謀反の疑いをかけられ、対馬へ流罪となる途中、鎮西(九州)で客死と伝わります。
様々な験をあらわし、歯に衣を着せぬ物言いから「一代の怪僧」ともいわれ、歴史に名を残した文覚上人の遺跡は配流先の伊豆に多くあり、当山もそのひとつに数えられます。
御本尊の釈迦如来像は京都嵯峨の清涼寺の御本尊と同木同作(あるいは模刻とも)とされます。
なお、清涼寺の御本尊は天竺(インド)渡来の栴檀づくりの釈迦如来像と伝わります。(清涼寺寺伝)
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号板
第73番常在寺から蛇石峠に向かって県道をさらに遡ります。
県道に面して参道入口。
すぐそばには東海バスの「永禅寺前」バス停があります。
がっしりとした石垣を構え、右手に五輪塔、正面に山門、門柱には寺号板が掲げられていてこのあたりでは大がかりな寺院です。
山門手前に鉄柵が閉められているので、まさか参拝禁止? とおののきましたが、これはイノシシの侵入除けの鉄柵なのでした。
掲げられていた案内どおりに鉄柵を開け山内に入ります。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門。
左手背後に小山を背負った落ち着きのある山内で、清掃が行き届いて気持ちがいいです。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、こちらも大棟を高く持ち上げています。
身舎は木製の桟格子が連なり端正な印象。
向拝見上げに山号扁額を掲げています。
御朱印は霊場公式Webに「無住ですが御朱印所は庫裡側の玄関脇にございます。」とあるとおり、庫裡玄関脇でセルフで印判をいただきました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
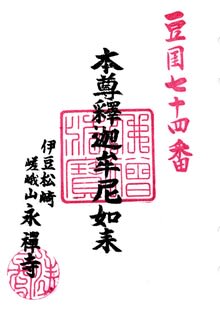

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第75番 岩科山 天然寺(てんねんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町岩科北側507
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
天然寺も県道121号線南伊豆松崎線、蛇石峠から県道に沿って流れる岩科川沿いにあります。
山内掲示および『こころの旅』『豆州志稿』によると、応仁二年(1468年)(文明九年(1477年)とも)雲譽文公上人により開創。
宝永二年(1705年)8月の大洪水により流失し、4年後の1709年に再建といいます。
『豆州志稿』には「岩科村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 文明九年(1477年)雲譽上人創ム 子院二定光院 天養院(明治七年廃ス)」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
岩科川から山裾に向かう傾斜地にあり参道も登りスロープです。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、たしか山号扁額を掲げていました。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 鐘楼と収蔵庫?
【写真 下(右)】 本堂
その先正面に形のよい小山を背負って本堂。
手前に鐘楼と見事ななまこ壁の収蔵庫?を構えています。
さすがになまこ壁の街、松崎の寺院です。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風。
水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ虹梁、中備には白色の彫刻入り板蟇股で見応えがあります。


【写真 上(左)】 木鼻
【写真 下(右)】 堂内の扁額
向拝身舎に扁額はありませんが、扉を開いた堂内見上げに寺号扁額が掲げられていました。
本堂内には、院派の仏師の作とみられる地蔵尊像、室町期作といわれる不動明王像のほか、釈迦如来、観世音菩薩、閻魔大王、青面金剛、弁財天、大黒天、毘沙門天、烏枢沙摩明王、徳川家康公像、歴代将軍の御位牌など多彩な尊格が御座すそうです。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第76番 清水山 浄泉寺(じょうせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町松崎43
浄土宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
この霊場ではめずらしく浄土宗寺院がつづきます。
松崎市街、延喜式内社の伊那下神社のそばにある浄土宗寺院です。
伊那下神社は、西伊豆では稀少な御朱印をいただける神社です。


【写真 上(左)】 伊那下神社
【写真 下(右)】 伊那下神社の御朱印
『こころの旅』によると、應永十一年(1404年)に及歎によって開創。
慶安元年(1648年)には徳川家光公による御朱印状を受けましたが、寛文十一年(1671年)八月洪水ニテ流出。
八世傳的が再興し、宝暦八年(1758年)には芝・増上寺の交代寺となりました。
『豆州志稿』には「松崎村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀観世音勢至 寺邊ニ清泉アリ取テ寺名トス 開祖及歎年代下知(或ハ云應永十一年(1404年)創立ナリト) 但曰当住迄十七世ナリト 寛文十一年(1671年)八月洪水ニテ流出 八世傳的再興ス 北条氏康寺領ヲ寄スト傳フレ共不詳 子院 寶壽院 随運院 西透院等(明治七年廃ス)」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
松崎の街なかにありますが、松崎は山が迫っているので、この寺院も背後に小山を背負う落ち着いたロケーションです。
参道入口に構える、入母屋屋根桟葺の朱塗りの四脚の楼門がひときわ目立ちます。
上層中央に山号扁額。
参道左手にたしか堂宇(経堂?)があったかと思いますが、なぜか写真がなく詳細不明。
参道正面の本堂は、入母屋造本瓦葺流れ向拝で整った軒唐破風を起こし、大棟には寺号が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ虹梁、中備上下に大がかりな板蟇股と彫刻。
さらにその上に兎毛通に経の巻獅子口を置いて見どころ豊富です。
向拝見上げには「法王殿?」の扁額、向拝柱には札所板が掲げられていました。
御本尊・阿弥陀三尊像は行基の作と伝わります。
御本尊の上の仏天蓋には、伊豆の長八作とされる飛天、左右の欄間には石田半兵衛の作と伝わる十六羅漢の透かし彫りが刻まれています。
また、裏庭は江戸時代に伊豆三名園のひとつと賞されたそうです。
山内掲示には下記のとおりありました。
・回る経堂、透かし彫り十六羅漢像、仏天蓋の長八天女、自然庭園、三十三観音、弘法大師作(伝)不動尊、水子・子育地蔵、もの思う石仏群
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第77番 文覚山 圓通寺(えんつうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町宮内130
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第4番
授与所:第78番禅海寺
山内由緒書、『こころの旅』によると、治承三年(1179年)の創始といわれ、僧文覚が伊豆韮山に流罪の際、ここに寄寓したことから文覚を開祖とし、のちに文覚山と号しました。
文覚はのちに当寺の奥の院となった観音堂で源頼朝公と会見し、源家再興を促したと伝わります。
(『豆州志稿』には、この説は「附会」とあります。)
『霊場めぐり』によると、この観音堂は相生堂と呼ばれましたが、いまは廃堂となって頼朝公、文覚の木像は圓通寺本堂に安置されているとの由。
相生堂には頼朝公お手植えの相生松がありましたが、枯れてしまったとのこと。
また、古くは妙智山円通寺という真言宗の小庵で、弘法大師の御作といわれる観音像を安置したともいいます。
のちに東林友丘和尚(應安二年(1369年)寂)により臨済宗に宗を改めました。
以前は那賀川の岸辺に沿って堂宇が建てられていましたが、200年ほど前に現地に遷って山号を改めています。
『豆州志稿』には「宮内村 臨済宗建長寺派 那賀郡舟田帰一寺末 本尊正観世音 文覚流人タル時 暫ク此ニ住ス 以テ開祖トス 俗ニ傳フ頼朝卿ニ父ノ髑髏ヲ視セシハ此ナリト 此傳附会ナリトス 文覚源義朝ノ髑髏ヲ頼朝ニ視セシハ田方郡奈印古谷ナリ(平家物語源平盛衰記等参観) 東林和尚ノ時ヨリ建長寺派下ト為ル 東林ハ應安二年(1369年)滅ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
松崎の街はずれ、伊那上神社の南側の路地おくにあります。
参道まわりは広く、かなりの格式の寺院であったことがうかがわれます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門ないし薬医門で、門柱に寺号板が掲げられています。
くぐるとすぐに階段。正面が庫裡で、いまは塾になっているようです。
左に棟つづきで本堂。その右手前に鐘楼。
この位置に鐘楼は、めずらしい伽藍配置かと思います。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上部に寺号扁額を掲げています。
向拝硝子戸下欄には伊豆八十八ヶ所と伊豆横道観音霊場の札所板が打ち付けられ、「御朱印は禅海寺まで」と読めます。
御本尊は弘法大師の御作とも伝わる聖観世音菩薩像です。
伊豆横道三十三観音霊場は頼朝公と所縁のふかい霊場で、頼朝公ゆかりの伝承が伝わるこの寺は札所にふさわしいかもしれません。


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 堂宇
本堂左手にある寄棟造桟瓦葺流れ向拝の堂宇の堂宇本尊は、扁額がないのでよくわかりません。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、中備に波様の彫刻はいずれも精緻な彫りです。
原則無住で、御朱印は第78番禅海寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
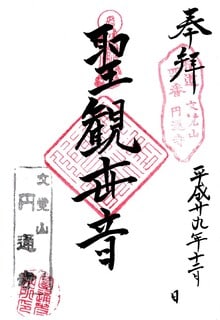
■ 第78番 祥雲山 禅海寺(ぜんかいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町江奈44
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』によると、当山の由緒書には、建久三年(1192年)に栄西禅師がこの地を訪れ一宇を造り、祥雲山禅海寺と名づけたとありますが、住職によると栄西禅師は勧請されて始祖になったもので、実際は弟子の建立とのことです。
建長四年(1252年)に当山の御本尊、釈迦如来を夢にみた鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王と執権・北条時頼が堂宇を再建、寄進をしたために宗尊親王の開基とされています。
『豆州志稿』には「江奈村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊釋迦 建久中(1190-1199年)創立 僧滎西ヲ請シテ開山トス 往昔鎌倉幕府ヨリ寺領ヲ附セリト傳フレトモ詳ナラス 永享五年(1433年)住山和尚建ツ 再興ナリ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
こちらは松崎港の東側の山手、江奈地区にあります。
ロケ的には松崎の街の北のはずれでしょうか。
山門は切妻屋根桟瓦葺で大棟に寺号を掲げ、がっしりとした降棟を降ろす四脚門で、名刹の風格があります。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2


【写真 上(左)】 六地蔵塔
【写真 下(右)】 本堂
本堂は背後に山を背負って寄棟造桟瓦葺。向かって左に寄せて唐破風の向拝を附設しています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備上に笈形付大瓶束。
左右の繋ぎ虹梁の上にも板蟇股をおき、上部は格天井と手が込んでいますが扁額はありません。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝扉を開くと堂内見上げに寺号扁額が掲げられていました。
堂内は禅刹らしく、すっきりと整えられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来 /主印はいずれも三寶印
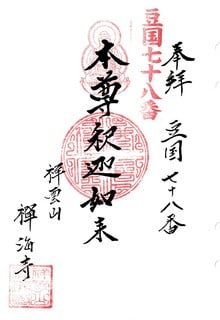

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第79番 曹源山 建久寺(けんきゅうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
松崎町建久寺68
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:建久寺酒店(松崎町那賀5-5)
建久年間(1190-1198年)に創立と伝わる古刹です。
後に安山という僧が再興、那賀村にあった当山を現在地に遷し、同時に檀徒も移住したといいます。
永正4年(1507年)に焼失し、これ以外の詳細は伝わっていません。
『豆州志稿』には「建久寺村 臨済宗建長寺派 船田帰一寺末 本尊観世音 建久中(1190-1199年)立ツ 今安山和尚ヲ祖トス 蓋中興ナリ 初那賀村ニ在リ 後現地ニ転ス 担徒随テ移住シ遂ニ一村ヲ為シ建久寺村ト称スト云 往昔巨刹ニシテ寺領ヲ有シタリト傳フレ共 永正四年(1507年)焼亡舊記ノ証スヘキ無シ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門と本堂
こちらは松崎港に注ぐ那賀川沿い、建久寺地区にあります。
『豆州志稿』によると「建久寺」の地名は、当初那賀村にあった当寺が檀家とともにこの地に移ったためつけられたとのこと。
人気宿として知られる桜田温泉「山芳園」の東側で、ここからさらに那賀川を遡ると”化粧の湯”と呼ばれ名宿として知られた大沢温泉「大沢温泉ホテル」がありましたが、令和2年12月末、日帰り温泉施設「大沢温泉 依田之庄」として装いを新たにした模様です。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山門扁額
参道左手前に真新しい札所標。
その先に寺号扁額を掲げた桟瓦葺の高麗門。
くぐった正面が本堂で、向かって右手前に白い聖観世音菩薩像が御座します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 聖観世音菩薩像


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱はなく、左に寄せた向拝の見上げに山号扁額を掲げています。
向拝はサッシュ扉で、比較的新しい建物とみられます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 建久寺酒店
こちらは無住で、御朱印は那賀地区の街なかにある建久寺酒店で拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11 ← 最新記事へつづく。
【 BGM 】
■ クリスマス イブ - 山下達郞 MV - JR東海 CM
■ 遠い街から - 今井美樹 MIKI IMAI LIVE AT ORCHARD HALL 2003
■ Celtic Prayer - Méav
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 武州八十八霊場
2022/12/10 UP
『幻の武州八十八霊場 埼玉の古寺をたずねて』の表紙に霊場の札所板書の写真が載っています。
これは第17番慈眼坊の板碑群屋桁に掲げられたもので、板に墨書ですがうっそうとした林のなかにあるようで、すでに朽ちてしまったかも知れないと思っていました。
先日巡拝におもむき、現物がかなりよい状態で残っていたのでご紹介します。


【写真 上(左)】 札所板書-1
【写真 下(右)】 札所板書-2


【写真 上(左)】 板碑群屋
【写真 下(右)】 多武峰
同書には掲載されていない16箇所の「奥の院」も記載されている貴重なものです。
せっかくなので奥の院も含めたリストをつくってみました。
(※リスト中「御朱印拝受」とあるものは、御本尊ないし他霊場のものがほとんどです。また、御開帳期間限定授与(通常は不授与)とみられる御朱印も含んでいます。)




--------------------
2022/08/05 UP
いちおう、これまでに拝受した御朱印はすべてUPしました。
現在、巡礼中です。新規の情報が入りましたら追記します。
→ 札所リスト(ニッポンの霊場様)
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
--------------------
2022/08/04 UP
この霊場については以前ざっくりとご紹介しましたが、「鎌倉殿の13人」に関係する寺院がいくつかあること、また、先日令和4年4月の中武蔵七十二薬師霊場の御開帳で御朱印を拝受できた札所がいくつかあるので、リスト化して御朱印をご紹介します。
なお、武州八十八霊場の札所御朱印を授与されている札所はごく少数です。
多くは他の霊場の御朱印となります。
また、武州八十八霊場は廃寺となった札所も多いので、場合により移転先の寺院、あるいは元別当を司どった神社の御朱印もご紹介します。
--------------------
2018/03/24 UP
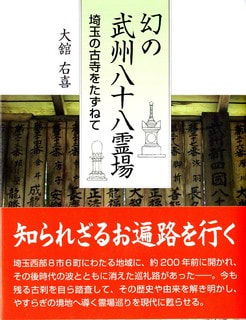

お大師様(弘法大師)ゆかりの寺院を巡る弘法大師霊場(通常八十八ヶ所ないし二十一ヶ所)は全国各地に開創され、三十三観音霊場とならんで代表的な巡拝霊場となっています。
東京周辺では、御府内八十八箇所(都内全域)、豊島八十八ヶ所(城北エリア)、玉川八十八ヶ所(城西エリア・神奈川)、多摩新四国八十八ヶ所(多摩エリア)、相州二十一ヶ所(鎌倉周辺)などがほぼ現役霊場として機能しています。
東京下町には、荒綾八十八ヶ所、荒川辺八十八ヶ所、南葛八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所、隅田川二十一ヵ所、多摩には奥多摩新四国霊場八十八ヶ所などが残り、霊場会はないものの札所として機能しているお寺さんもかなりあります。
千葉には新四国相馬八十八ヶ所、東葛印旛八十八所、下総四郡八十八ヶ所、江戸川八十八ヶ所、市原郡八十八ヶ所、上総八十八ヶ所、千葉寺八十八所、吉橋八十八所、印西大師など多くの大師霊場があり、神奈川にも新四国東国八十八ヶ所、相模国準四国八十八ヶ所などがあり、かなりのエリアがカバーされています。
ところが、埼玉では北足立八十八箇所、埼東八十八ヶ所が荒川左岸エリアに開創されているものの、荒川右岸域にはほとんど見当たりません。(一部、武玉八十八ヶ所と奥多摩新四国霊場八十八ヶ所がかかっているのみ。)
荒川右岸域には、武蔵野三十三観音、狭山三十三観音、入比板東三十三所観音、高麗板東三十三観音、比企西国三十三観音など比較的多くの観音霊場があるのに、かねがね不思議に思っていました。


【写真 上(左)】武蔵野三十三観音・初番 長命寺(練馬区)
【写真 下(右)】高麗板東三十三観音・初番 智観寺(飯能市)
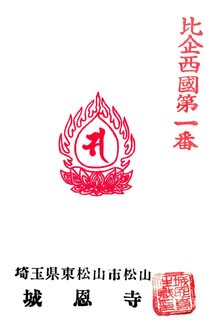
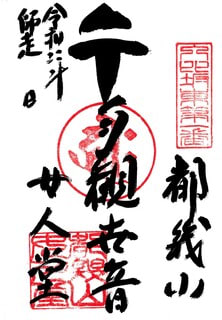
【写真 上(左)】比企西国三十三観音・初番 城恩寺(東松山市)
【写真 下(右)】入比板東三十三所観音・初番 女人堂(ときがわ町)
こんななか、先日、書店で目にとまったのが、『幻の武州八十八霊場 埼玉の古寺をたずねて』(さきたま出版会/2018.2.15初版)という出たての本です。
「武州八十八霊場」?・・・まったく初耳でした。Web上でもみたことがありません。
速攻で本を購入し、興味シンシン読みふけりました。
::::::::::::::::::::::::::::::::
武州八十八霊場とは、文化九年(1812年)、武州越生の法恩寺山主により企画された四国八十八札所の写し霊場(新四国霊場)で、範囲は越生、毛呂山、ときがわ、鳩山、坂戸、鶴ヶ島、東松山、吉見、川島、川越、狭山、入間、飯能、日高に渡っています。
まさに、上にあげた荒川右岸域の観音霊場群とエリアが重なります。
同書によると、御詠歌集の霊場名称は「印施新四国霊場」。
文化九年(1812年)3月5日、越生報恩寺山主は当地に新四国八十八霊場の開創を企図し、外秩父「武州山之根」の諸寺院に提案して順路を定めました。
また、親交のあった上野村の瑠璃山医王寺秀如や堂山村青龍山最勝寺海恵、田代村吉沢凡齋などから版行の寄付をうけ、有力商人の亀屋宗兵衛・藤屋宗八から用紙の寄付をえて『印施新四国遍路御詠歌』という順路の案内書を刊行したとあります。
同書によると、弘法大師千年忌を迎え、文化・文政~天保(1804~1843年)には全国各地で盛んに弘法大師霊場(新四国八十八箇所)が開創されたといいます。
しかし、弘化二年(1845年)に公布された新四国八十八札所の禁令により新規霊場の開創が禁止されると、新規開創は下火となったといいます。
「武州八十八霊場」は江戸期の新四国霊場開創最盛期に開創されているためか、きっちり奥の院まで設定されています。
ただし、番外や掛所、別格霊場などは設定されていない模様です。
発願寺は越生の松渓山法恩寺、結願寺は日高の聖天院勝楽寺で、奥武蔵越生から打ち始め、吉見・川島あたりの荒川辺まで出て、時計回りに奥武蔵の日高に戻るというコースです。
ときがわの慈光寺(18番)、東松山の正法寺(31番)、吉見の安楽寺(36番)、入間の円照寺(80番)、飯能の観音寺(83番)などメジャー寺院も含みますが、多くは小規模な寺院で10程度の廃寺を含みます。
札所一覧をみたとき、ちょっと不思議な感じがしたのは、禅寺がほとんど参画しておらず、ほとんどが真言宗、天台宗の寺院で占められているため、このエリアにかなりある禅寺の古刹が欠けているからだと思います。
(この本は、「印施新四国遍路御詠歌」という案内書をベースに編纂されたとみられ、また著者が元文学部教授ということもあってか、かなり専門的な内容で、宗派は宗派名でなく、●●寺末という本末制度からの記載となっています。なので、本寺の宗派がわからないと宗派がわからず、宗派不明の寺院もあります。)
著者は1933年のお生まれというご高齢ながら、すべての札所を回られたうえで上梓されています。
古文書と現地探訪の生情報が組み合わさったすこぶる密度の高い内容で、よくぞ世に出していただいた、という感じです。
御朱印はともかく、興味のある札所も多いので、時間をかけてじっくりと回ってみたいと思います。
--------------------------
第1番 松渓山 法恩寺
公式Web
埼玉県越生町越生704
真言宗智山派
御本尊:大日如来
関連武将:源頼朝公、越生次郎家行
他の札所:越生七福神(恵比須神)、真言宗智山派関東十一談林
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:大日如来

2.武州八十八霊場第1番
朱印尊格:大日如来

※札番揮毫はお願いしてお書きいただいたもの。通常は札番記入なしと思います。
3.越生七福神
朱印尊格:恵比須神
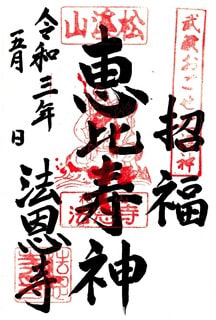
・天平十年(738年)行基の開創と伝わる古刹。児玉党の倉田孫四郎基行とその妻妙泉尼夫妻が出家、源頼朝公に寺の再興を願い出て許され、建久元年(1190年)頼朝公は越生次郎家行に命じて堂塔伽藍を建立して天台宗寺院として再興、将軍家繁盛の祈祷道場としたといいます。
・応永五年(1398年)に阿闍梨権大僧都法印榮曇和尚が入山し、真言宗に改宗して中興開山、天正十九年(1591年)には徳川家康公から寺領20石の御朱印状を拝領。
・新義真言宗の関東十一談林の一つに列し、住職が将軍に直接拝謁できる格式の高い寺院でした。
・後鳥羽上皇の御宸筆で頼朝公から拝領したとされる絹本着色高野・丹生明神像をはじめ、数多くの文化財を有しています。
第2番 大慈山 正法寺
埼玉県越生町越生960
臨済宗建長寺派 (旧)本寺:鎌倉円覚寺
御本尊:聖観世音菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第24番、越生七福神(大黒天)
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第24番
朱印尊格:聖観世音菩薩

2.越生七福神
朱印尊格:大黒天

第3番 瑠璃山 東園院 医王寺
埼玉県越生町上野2043
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
第4番 福壽山 滝房 多門寺
埼玉県越生町上野1454
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
第5番 澤谷山 光明院 宝福寺
埼玉県毛呂山町大谷木154
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:
関連武将:毛呂氏→大谷氏
他の札所:
第6番 息災山 吉祥院 延命寺
埼玉県毛呂山町下河原245
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:不動明王
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

第7番 観音寺
埼玉県坂戸市四日市場379
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:千手観世音菩薩
他の札所:
第8番 金剛山 地蔵院 南蔵寺
埼玉県毛呂山町350-0436
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
※廃寺?、現・川角八幡社境内に遺跡
第9番 山本坊
埼玉県毛呂山町西戸916
本山修験派
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、西戸国津神神社境内他に遺跡
第10番 御嶺山 不動院 龍台寺
埼玉県越生町西和田101 (旧)本寺:越生法恩寺
真言宗智山派
御本尊:大日如来
他の札所:
第11番 石樹山 常住院 興禅寺
埼玉県越生町西和田849
真言宗智山派 (旧)本寺:越生医王寺
御本尊:不動明王
他の札所:
第12番 能満山 見正寺
埼玉県越生町成瀬330
真言宗智山派 (旧)本寺:越生医王寺
御本尊:聖観世音菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第22番
司元別当:成瀬諏訪神社(越生町成瀬)
〔拝受御朱印〕 ・無住、妙見寺(越生町成瀬287)にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第22番
朱印尊格:聖観世音菩薩

第13番 如意山 地蔵院 高蔵寺
埼玉県越生町津久根253
真言宗智山派 (旧)本寺:越生最勝寺
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第26番
〔拝受御朱印〕 ・無住、最勝寺(越生町堂山287)にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第26番
朱印尊格:聖観世音菩薩

第14番 大泉院
埼玉県越生町小杉1
本山修験派?
司元別当:梅園神社(越生町小杉)
御本尊:
他の札所:
※属山本坊(第9番)、廃寺、小杉天神社別当、梅園神社内
第15番 青龍山 最勝寺
埼玉県越生町堂山287
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
関連武将:源頼朝公、兒玉氏雲太夫
他の札所:入比板東三十三観音霊場第27番、越生七福神(福禄寿)
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第27番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

第16番 仏心院
埼玉県越生町龍ケ谷
(旧)本寺:本坊は常楽院/高山不動尊(飯能市高山346)
真言宗智山派
御本尊:
他の札所:
※廃寺?
※ 御朱印は不授与です。本坊の常楽院/高山不動尊の御朱印を掲載します。
〔拝受御朱印〕
・高山不動尊にて拝受(原則として冬至の日、年1日のみの授与)
1.高山不動尊の御朱印

第17番 多武峰 慈眼坊
埼玉県ときがわ町西平
宗派不詳
御本尊:
他の札所:入比板東三十三観音霊場第31番
※廃寺?、個人宅に(多武峰神社)
第18番 都幾山 一乗法華院 慈光寺
埼玉県ときがわ町西平386
天台宗
御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩
関連武将:源頼朝公(祈願所)
他の札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第9番、関東九十一薬師霊場第33番、関東百八地蔵尊霊場第14番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.坂東三十三箇所(観音霊場)第9番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

2.関東九十一薬師霊場第33番
朱印尊格:薬師如来(抜苦輿楽)
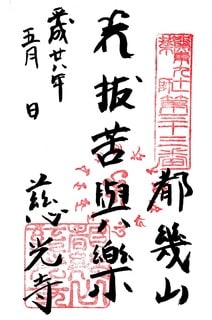
3.関東百八地蔵尊霊場第14番
朱印尊格:地蔵菩薩(巡礼地蔵尊)

4.阿弥陀如来
朱印尊格:阿弥陀如来
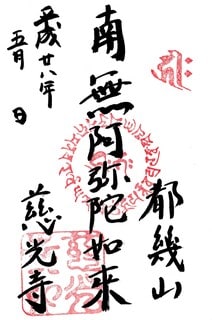
第19番 日影山 長勝寺
埼玉県ときがわ町日影
真言宗智山派 (旧)本寺:越生最勝寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
※廃寺?、日影神社周辺か?
第20番 鈴宮山 開敷院 観音寺
埼玉県ときがわ町本郷551
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:聖観世音菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第7番
〔拝受御朱印〕 ・無住、光明寺(第22番、ときがわ町玉川3017)にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第7番
朱印尊格:聖観世音菩薩
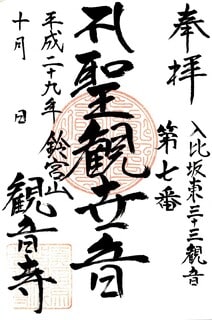
第21番 医王寺
埼玉県ときがわ町番匠
宗派不詳
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、寺跡あり
第22番 音無山 光明寺
埼玉県ときがわ町玉川3017
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:不動明王
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:不動明王・弘法大師

第23番 東光山 薬王院 満願寺
埼玉県鳩山町熊井800
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
他の札所:
第24番 西明山 法輪院 真光寺
埼玉県鳩山町大豆戸340
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
司元別当:大豆戸三嶋神社(鳩山町大豆戸)
御本尊:大日如来
他の札所:
第25番 延命山 奥野院 興長寺
埼玉県鳩山町小用240
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:阿弥陀如来
関連武将:源頼朝公、越生四郎家行
他の札所:
第26番 清水山 彼岸院 大榮寺
埼玉県坂戸市厚川78
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第6番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:阿弥陀如来
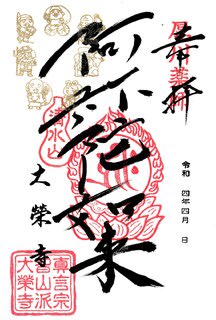
2.中武蔵七十二薬師霊場第6番
朱印尊格:薬師如来

第27番 八葉山 来迎院 長久寺
埼玉県坂戸市浅羽1486
真言宗智山派
御本尊:大日如来
他の札所:
第28番 安養山 蓮華院 善能寺
埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-3−10
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第11番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:阿弥陀如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第11番
朱印尊格:薬師如来
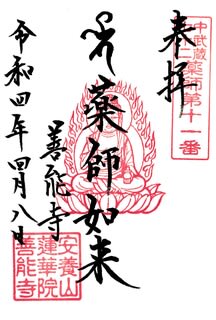
第29番 龍護山 實相院 大智寺
埼玉県坂戸市石井2331
真言宗智山派
御本尊:大日如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第23番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時のみ授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:大日如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第23番
朱印尊格:薬師如来
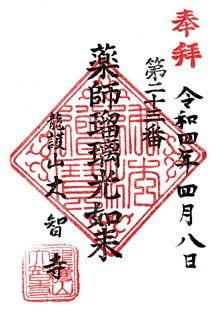
第30番 天神山 不動院 龍福寺
埼玉県坂戸市戸口453
真言宗智山派
御本尊:不動明王
(旧)本寺:坂戸大智寺
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第1番(戸口薬師)
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第1番
朱印尊格:薬師如来

第31番 巌殿山 修繕院 正法寺(巌殿観音)
埼玉県東松山市岩殿1229
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
関連武将:源頼朝公、比企判官能員
他の札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第10番、関東百八地蔵尊霊場第13番、七観音霊場第5番、中武蔵七十二薬師霊場第47番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.坂東三十三箇所(観音霊場)第10番
朱印尊格:千手観世音菩薩

2.関東百八地蔵尊霊場第13番
朱印尊格:地蔵菩薩(百地蔵尊)

3.七観音霊場第5番
朱印尊格:千手観世音菩薩

4.中武蔵七十二薬師霊場第47番
朱印尊格:薬師如来
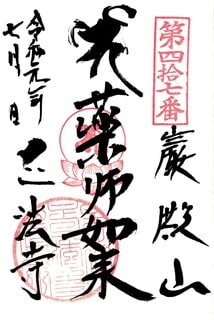
第32番 澤田山 修造院 長慶寺
埼玉県東松山市神戸1678
真言宗智山派
御本尊:不動明王
関連武将:畠山重忠
他の札所:比企西国三十三観音第21番、中武蔵七十二薬師霊場第48番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.武州八十八霊場第32番
朱印尊格:不動明王

2.比企西国三十三観音第21番
朱印尊格:十一面観世音菩薩
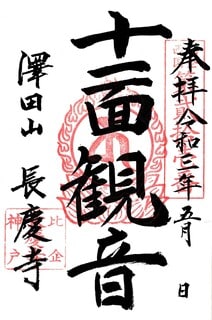
3.中武蔵七十二薬師霊場第48番
朱印尊格:薬師如来

第33番 安楽寺
埼玉県東松山市唐子
宗派不詳
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、墓地
第34番 成就院
埼玉県東松山市金井
宗派不詳
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、金井秋葉神社そば
第35番 岩室山 湯澤寺 龍性院
埼玉県吉見町北吉見459
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第63番、比企西国三十三観音第3番(岩室観音堂)
※岩室観音堂(吉見町北吉見309)は龍性院の境外仏堂
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

2.比企西国三十三観音第3番(岩室観音堂)
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.中武蔵七十二薬師霊場第63番
朱印尊格:薬師如来

第36番 岩殿山 光明院 安楽寺(吉見観音)
埼玉県吉見町御所374
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
関連武将:源範頼公
他の札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第11番、関東八十八箇所第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第17番、武州路十二支霊場(申)、中武蔵七十二薬師霊場第62番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時のみ授与の可能性あり)
1.坂東三十三箇所(観音霊場)第11番
朱印尊格:聖観世音菩薩

2.関東八十八箇所第75番
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.東国花の寺百ヶ寺霊場第17番
朱印尊格:聖観世音菩薩

4.武州路十二支霊場(申)
朱印尊格:金剛界大日如来
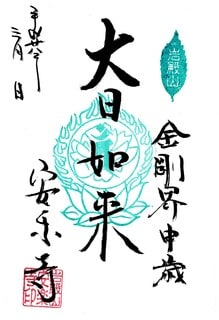
5.中武蔵七十二薬師霊場第62番
朱印尊格:薬師如来
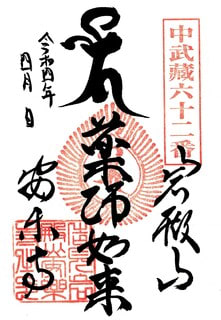
第37番 端松山 正伝寺
埼玉県吉見町和名359
真言宗霊雲寺派 (旧)本寺:湯島霊雲寺
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:
第38番 岩殿山 光明院 息障院
埼玉県吉見町御所146-1
真言宗智山派 (旧)本寺:山城國醍醐報恩院
御本尊:不動明王
関連武将:源範頼公
他の札所:
第39番 松岡山 光勝寺 明王院
埼玉県吉見町下細谷415
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:十一面観世音菩薩
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第60番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第60番
朱印尊格:薬師如来

第40番 愛宕山 寿命院 無量寺
埼玉県吉見町久保田1380
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第58番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

2.中武蔵七十二薬師霊場第58番
朱印尊格:薬師如来

第41番 大串山 宝珠院 観音寺
埼玉県吉見町大串1282
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:不動明王
他の札所:
第42番 頼綱山 観秀院 寶性寺
埼玉県吉見町江綱1299
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第66番(薬師堂)
〔拝受御朱印〕 ・明王院(吉見町下細谷)にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第66番
朱印尊格:薬師如来
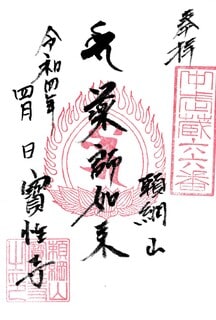
第43番 明光山 法鈴寺
埼玉県川島町下小見野155
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:不動明王?
司元別当:下小見野氷川神社(川島町下小見野)
関連武将:小野見氏
他の札所:
第44番 法蔵山 西養院 西見寺
埼玉県川島町吹塚232
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
第45番 法輪山 極楽寺
埼玉県川島町上八ツ林261
真言宗智山派 (旧)本寺:川島善福寺
御本尊:
他の札所:
第46番 寶塔山 善福寺
埼玉県川島町下八ツ林307
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第35番、第36番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

2.中武蔵七十二薬師霊場第35番(下八ツ林薬師堂)
朱印尊格:薬師如来
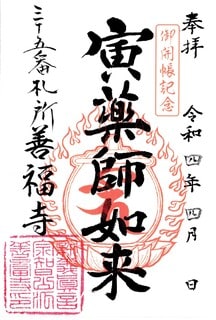
3.中武蔵七十二薬師霊場第36番(下八ツ林薬師堂)
朱印尊格:薬師如来

第47番 大御山 西福院 廣徳寺
埼玉県川島町表76
真言宗豊山派
御本尊:五大明王
関連武将:美尾谷十郎廣徳
他の札所:
第48番 蓮王山 十輪寺
埼玉県川島町
真言宗豊山派 (旧)本寺:川島廣徳寺
御本尊:不動明王
他の札所:
※無住?、お堂と墓地
第49番 龍池山 慈眼院
埼玉県川島町角泉110
真言宗豊山派 (旧)本寺:川島廣徳寺
御本尊:正観世音菩薩
他の札所:
第50番 法雲山 普門院 弘善寺
埼玉県川島町上狢
真言宗智山派 (旧)本寺:川島廣徳寺
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、上狢集落センターと墓地
第51番 大福寺
埼玉県川島町平沼308
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第30番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第30番
朱印尊格:薬師如来

第52番 草芽山 自性院 大聖寺
埼玉県川島町井草161
真言宗智山派
御本尊:大日如来 千手観世音菩薩?
関連武将:比企能員
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第29番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時限定授与の可能性あり)
1.武州八十八霊場第52番
朱印尊格:大日如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第29番
朱印尊格:薬師如来

第53番 土袋山 普門寺 金乗院
埼玉県川島町上伊草830
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
他の札所:比企西国三十三観音第13番
第54番 守護山 善能寺
埼玉県川島町中山1823
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:
他の札所:
第55番 清月山 元光院 金剛寺
埼玉県川島町中山1198
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:阿弥陀如来

第56番 三嶽山 普門院 延命寺
埼玉県川島町中山1285
真言宗智山派
御本尊:
他の札所:比企西国三十三観音第8番
第57番 勅王山 正福寺
埼玉県川島町南園部310
真言宗智山派
御本尊:
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:御寶印・寺院印のみ

第58番 光勝寺
埼玉県坂戸市赤尾1832
真言宗智山派
御本尊:不動明王
※墓地のみ
第59番 薬王山 浄水院 東光寺
埼玉県坂戸市小沼266
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:薬師如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第21番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第21番
朱印尊格:薬師如来

第60番 恵日山 法音寺
埼玉県坂戸市小沼902
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:不動明王
他の札所:
第61番 薩埵山 錫杖院 忠栄寺
埼玉県坂戸市横沼366
真言宗豊山派 (旧)本寺:伊草金乗院
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:
第62番 三寶山 実蔵院 長福寺
埼玉県坂戸市紺屋892
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:大日如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第17番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:大日如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第17番
朱印尊格:薬師如来

第63番 薬樹山 瑠璃光院 永命寺
埼玉県川越市下小阪688
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第16番、小江戸川越古寺巡礼第51番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:不動明王
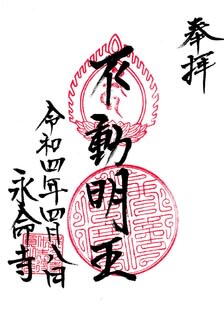
2.中武蔵七十二薬師霊場第16番
朱印尊格:薬師如来
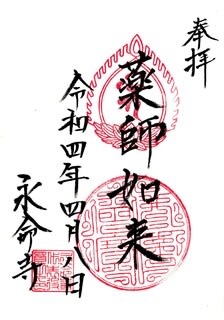
第64番 由城山 福聚院 慈眼寺
埼玉県坂戸市中小坂285
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:十一面観世音菩薩
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・郵送にて拝受
1.武州八十八霊場第64番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

2.閻魔大王の御朱印
朱印尊格:閻魔大王

第65番 広谷山 正音寺
埼玉県鶴ヶ島市上広谷605-1
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第13番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第13番
朱印尊格:薬師如来

第66番 慈眼山 喜見院 満福寺
埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷487
天台宗
御本尊:千手観世音菩薩
司元別当:熊野社(鶴ヶ島市太田ヶ谷)ほか
他の札所:武蔵国十三佛霊場第5番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:千手観世音菩薩

2.武蔵国十三佛霊場第5番
朱印尊格:地蔵菩薩

第67番 萬霊山 法護院 延命寺
埼玉県川越市笠幡4451
天台宗
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:武蔵国十三佛霊場第4番、小江戸川越古寺巡礼第3番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:延命地蔵菩薩

2.武蔵国十三佛霊場第4番
朱印尊格:普賢菩薩

第68番 観智山 地蔵寺 三明院
埼玉県川越市池辺507
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:大日如来
司元別当:熊野神社(川越市池辺)
他の札所:小江戸川越古寺巡礼第57番
第69番 薬王山 地蔵院 廣福寺
埼玉県狭山市下奥富844
天台宗 (旧)本寺:仙波中院
御本尊:薬師如来
他の札所:関東九十一薬師霊場第32番、関東百八地蔵尊霊場第9番、武蔵国十三佛霊場第3番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.関東九十一薬師霊場第32番
朱印尊格:薬師如来

2.関東百八地蔵尊霊場第9番
朱印尊格:地蔵菩薩

3.武蔵国十三佛霊場第3番
朱印尊格:文殊菩薩
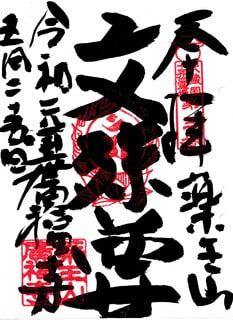
第70番 龍殿山 成就院 瑞光寺
埼玉県狭山市上奥富354
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:大日如来
他の札所:
第71番 金宝山 龍護院 永代寺
埼玉県狭山市柏原2492
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:
関連武将:畠山重忠
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.虚空蔵菩薩の御朱印
朱印尊格:虚空蔵菩薩
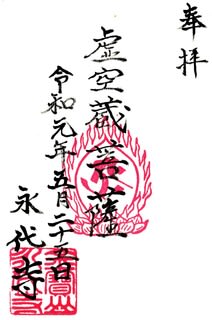
第72番 天竜山 薬王院 成円寺
埼玉県狭山市入間川2-3-11(徳林寺内へ(地蔵堂))
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:釈迦三尊
司元別当:八幡神社(狭山市入間川)、牛頭天王社、清水八幡宮、諏訪社
関連武将:木曽(清水冠者)義高
他の札所:(徳林寺)武蔵野三十三観音霊場第17番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.不動堂の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.武蔵野三十三観音霊場第17番
朱印尊格:●聚閣
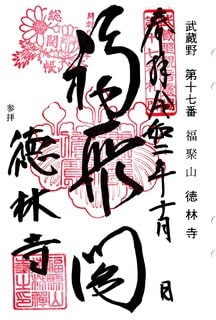
第73番 蔵王山 観音院 常泉寺
埼玉県狭山市北入曽315
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:釈迦如来
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:釈迦如来

2.観音堂の御朱印
朱印尊格:聖観世音菩薩

第74番 御嶽山 延命寺 金剛院
埼玉県狭山市南入曽460
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
司元別当:御嶽社(南入曽村/現・入間野神社)
他の札所:
※ 御朱印は不授与です。当寺が元別当をつとめた入間野神社の御朱印を掲載します。

第75番 龍岳山 歓喜院 龍圓寺
埼玉県入間市新久717
真言宗智山派
御本尊:虚空蔵菩薩
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第20番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第41番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.武蔵野三十三観音霊場第20番
朱印尊格:千手観世音菩薩

2.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第41番
朱印尊格:十一面観世音菩薩・弘法大師

第76番 世音山 妙智寺 蓮花院
埼玉県入間市春日町2-9-1
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第18番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第74番・第76番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.武蔵野三十三観音霊場第18番
朱印尊格:千手観世音菩薩
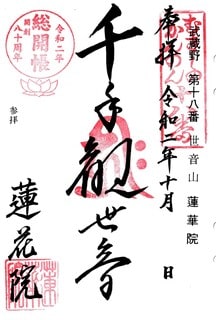
3.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第74番
朱印尊格:薬師如来・弘法大師

4.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第76番
朱印尊格:薬師如来・弘法大師

第77番 高竹山 光明院 明光寺
埼玉県狭山市根岸2-5-1
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第44番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:地蔵菩薩

2.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第44番
朱印尊格:十一面観世音菩薩・弘法大師
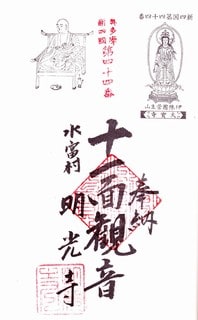
第78番 笹井観音堂(瀧音山 泊山寺)
埼玉県狭山市笹井
本山修験宗?(京都聖護院の直末)
御本尊:十一面観世音菩薩
他の札所:
※無住。現在、御朱印は不授与です。
第79番 千手山 教学院 普門寺
埼玉県飯能市川崎300
真言宗智山派
御本尊:
司元別当:白鬚神社(飯能市川崎)
他の札所:高麗板東三十三観音霊場第4番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.高麗板東三十三観音霊場第4番
朱印尊格:千手観世音菩薩

第80番 光明山 正覚院 圓照寺
埼玉県入間市野田158
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀三尊
関連武将:加治氏
他の札所:関東八十八箇所第73番、武蔵野三十三観音霊場第22番、高麗板東三十三観音霊場第11番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第58番、武蔵野七福神(弁財天)
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.関東八十八箇所第73番
朱印尊格:阿弥陀如来

2.武蔵野三十三観音霊場第22番
朱印尊格:如意輪観世音菩薩
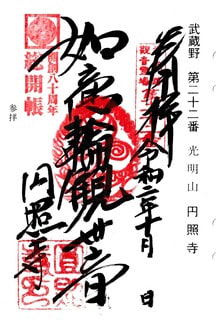
3.高麗板東三十三観音霊場第11番
朱印尊格:聖観世音菩薩

4.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第58番
朱印尊格:千手観世音菩薩・弘法大師

5.武蔵野七福神の御朱印
朱印尊格:弁財天

第81番 仏寿山 宝幢院 願成寺
埼玉県飯能市川寺688
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
第82番 岸高山 福寿院 歓喜寺
埼玉県飯能市岩渕658甲
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:
他の札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第32番
第83番 般若山 長寿院 観音寺
埼玉県飯能市山手町5-17
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第24番、高麗板東三十三観音霊場第10番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第64番、武蔵野七福神(寿老人)
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.武蔵野三十三観音霊場第24番
朱印尊格:如意輪観世音菩薩
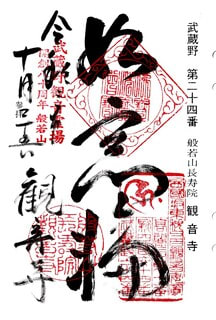
2.高麗板東三十三観音霊場第10番
朱印尊格:如意輪観世音菩薩

3.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第64番
朱印尊格:阿弥陀如来・弘法大師

第84番 常寂山 蓮華院 智観寺
埼玉県飯能市中山520
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
関連武将:中山氏
他の札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第28番、高麗板東三十三観音霊場第1番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第28番
朱印尊格:大日如来・弘法大師

3.高麗板東三十三観音霊場第1番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

第85番 慈眼山 真福寺
埼玉県飯能市中山436 (旧)本寺:中山智観寺
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
※無住? 加治神社門前
第86番 高岡山 龍泉寺
埼玉県日高市栗坪124
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:不動明王
他の札所:
第87番 箕輪山 満行院 霊巌寺
埼玉県日高市新堀740-1
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:武蔵野三十三観音霊場番外1、高麗板東三十三観音霊場番外2
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:地蔵菩薩

2.武蔵野三十三観音霊場番外1
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.高麗板東三十三観音霊場番外2
朱印尊格:聖観世音菩薩

第88番 高麗山 聖天院 勝楽寺
埼玉県日高市新堀990-1
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第26番、高麗板東三十三観音霊場第32番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.武蔵野三十三観音第26番
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.高麗板東三十三観音霊場第32番
朱印尊格:千手観世音菩薩

【 BGM 】
■ 歌に形はないけれど - ユリカ / 花たん
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
■ Endless Story - Yuna Ito
『幻の武州八十八霊場 埼玉の古寺をたずねて』の表紙に霊場の札所板書の写真が載っています。
これは第17番慈眼坊の板碑群屋桁に掲げられたもので、板に墨書ですがうっそうとした林のなかにあるようで、すでに朽ちてしまったかも知れないと思っていました。
先日巡拝におもむき、現物がかなりよい状態で残っていたのでご紹介します。


【写真 上(左)】 札所板書-1
【写真 下(右)】 札所板書-2


【写真 上(左)】 板碑群屋
【写真 下(右)】 多武峰
同書には掲載されていない16箇所の「奥の院」も記載されている貴重なものです。
せっかくなので奥の院も含めたリストをつくってみました。
(※リスト中「御朱印拝受」とあるものは、御本尊ないし他霊場のものがほとんどです。また、御開帳期間限定授与(通常は不授与)とみられる御朱印も含んでいます。)




--------------------
2022/08/05 UP
いちおう、これまでに拝受した御朱印はすべてUPしました。
現在、巡礼中です。新規の情報が入りましたら追記します。
→ 札所リスト(ニッポンの霊場様)
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
--------------------
2022/08/04 UP
この霊場については以前ざっくりとご紹介しましたが、「鎌倉殿の13人」に関係する寺院がいくつかあること、また、先日令和4年4月の中武蔵七十二薬師霊場の御開帳で御朱印を拝受できた札所がいくつかあるので、リスト化して御朱印をご紹介します。
なお、武州八十八霊場の札所御朱印を授与されている札所はごく少数です。
多くは他の霊場の御朱印となります。
また、武州八十八霊場は廃寺となった札所も多いので、場合により移転先の寺院、あるいは元別当を司どった神社の御朱印もご紹介します。
--------------------
2018/03/24 UP
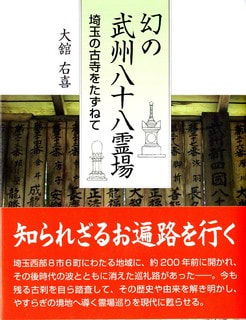

お大師様(弘法大師)ゆかりの寺院を巡る弘法大師霊場(通常八十八ヶ所ないし二十一ヶ所)は全国各地に開創され、三十三観音霊場とならんで代表的な巡拝霊場となっています。
東京周辺では、御府内八十八箇所(都内全域)、豊島八十八ヶ所(城北エリア)、玉川八十八ヶ所(城西エリア・神奈川)、多摩新四国八十八ヶ所(多摩エリア)、相州二十一ヶ所(鎌倉周辺)などがほぼ現役霊場として機能しています。
東京下町には、荒綾八十八ヶ所、荒川辺八十八ヶ所、南葛八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所、隅田川二十一ヵ所、多摩には奥多摩新四国霊場八十八ヶ所などが残り、霊場会はないものの札所として機能しているお寺さんもかなりあります。
千葉には新四国相馬八十八ヶ所、東葛印旛八十八所、下総四郡八十八ヶ所、江戸川八十八ヶ所、市原郡八十八ヶ所、上総八十八ヶ所、千葉寺八十八所、吉橋八十八所、印西大師など多くの大師霊場があり、神奈川にも新四国東国八十八ヶ所、相模国準四国八十八ヶ所などがあり、かなりのエリアがカバーされています。
ところが、埼玉では北足立八十八箇所、埼東八十八ヶ所が荒川左岸エリアに開創されているものの、荒川右岸域にはほとんど見当たりません。(一部、武玉八十八ヶ所と奥多摩新四国霊場八十八ヶ所がかかっているのみ。)
荒川右岸域には、武蔵野三十三観音、狭山三十三観音、入比板東三十三所観音、高麗板東三十三観音、比企西国三十三観音など比較的多くの観音霊場があるのに、かねがね不思議に思っていました。


【写真 上(左)】武蔵野三十三観音・初番 長命寺(練馬区)
【写真 下(右)】高麗板東三十三観音・初番 智観寺(飯能市)
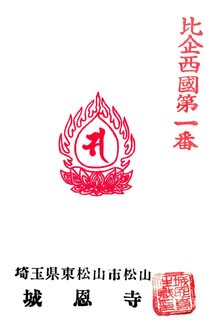
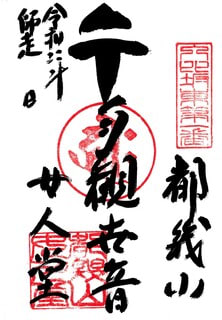
【写真 上(左)】比企西国三十三観音・初番 城恩寺(東松山市)
【写真 下(右)】入比板東三十三所観音・初番 女人堂(ときがわ町)
こんななか、先日、書店で目にとまったのが、『幻の武州八十八霊場 埼玉の古寺をたずねて』(さきたま出版会/2018.2.15初版)という出たての本です。
「武州八十八霊場」?・・・まったく初耳でした。Web上でもみたことがありません。
速攻で本を購入し、興味シンシン読みふけりました。
::::::::::::::::::::::::::::::::
武州八十八霊場とは、文化九年(1812年)、武州越生の法恩寺山主により企画された四国八十八札所の写し霊場(新四国霊場)で、範囲は越生、毛呂山、ときがわ、鳩山、坂戸、鶴ヶ島、東松山、吉見、川島、川越、狭山、入間、飯能、日高に渡っています。
まさに、上にあげた荒川右岸域の観音霊場群とエリアが重なります。
同書によると、御詠歌集の霊場名称は「印施新四国霊場」。
文化九年(1812年)3月5日、越生報恩寺山主は当地に新四国八十八霊場の開創を企図し、外秩父「武州山之根」の諸寺院に提案して順路を定めました。
また、親交のあった上野村の瑠璃山医王寺秀如や堂山村青龍山最勝寺海恵、田代村吉沢凡齋などから版行の寄付をうけ、有力商人の亀屋宗兵衛・藤屋宗八から用紙の寄付をえて『印施新四国遍路御詠歌』という順路の案内書を刊行したとあります。
同書によると、弘法大師千年忌を迎え、文化・文政~天保(1804~1843年)には全国各地で盛んに弘法大師霊場(新四国八十八箇所)が開創されたといいます。
しかし、弘化二年(1845年)に公布された新四国八十八札所の禁令により新規霊場の開創が禁止されると、新規開創は下火となったといいます。
「武州八十八霊場」は江戸期の新四国霊場開創最盛期に開創されているためか、きっちり奥の院まで設定されています。
ただし、番外や掛所、別格霊場などは設定されていない模様です。
発願寺は越生の松渓山法恩寺、結願寺は日高の聖天院勝楽寺で、奥武蔵越生から打ち始め、吉見・川島あたりの荒川辺まで出て、時計回りに奥武蔵の日高に戻るというコースです。
ときがわの慈光寺(18番)、東松山の正法寺(31番)、吉見の安楽寺(36番)、入間の円照寺(80番)、飯能の観音寺(83番)などメジャー寺院も含みますが、多くは小規模な寺院で10程度の廃寺を含みます。
札所一覧をみたとき、ちょっと不思議な感じがしたのは、禅寺がほとんど参画しておらず、ほとんどが真言宗、天台宗の寺院で占められているため、このエリアにかなりある禅寺の古刹が欠けているからだと思います。
(この本は、「印施新四国遍路御詠歌」という案内書をベースに編纂されたとみられ、また著者が元文学部教授ということもあってか、かなり専門的な内容で、宗派は宗派名でなく、●●寺末という本末制度からの記載となっています。なので、本寺の宗派がわからないと宗派がわからず、宗派不明の寺院もあります。)
著者は1933年のお生まれというご高齢ながら、すべての札所を回られたうえで上梓されています。
古文書と現地探訪の生情報が組み合わさったすこぶる密度の高い内容で、よくぞ世に出していただいた、という感じです。
御朱印はともかく、興味のある札所も多いので、時間をかけてじっくりと回ってみたいと思います。
--------------------------
第1番 松渓山 法恩寺
公式Web
埼玉県越生町越生704
真言宗智山派
御本尊:大日如来
関連武将:源頼朝公、越生次郎家行
他の札所:越生七福神(恵比須神)、真言宗智山派関東十一談林
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:大日如来

2.武州八十八霊場第1番
朱印尊格:大日如来

※札番揮毫はお願いしてお書きいただいたもの。通常は札番記入なしと思います。
3.越生七福神
朱印尊格:恵比須神
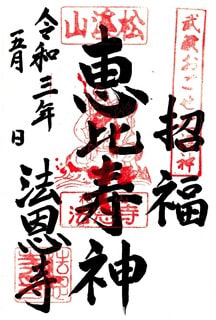
・天平十年(738年)行基の開創と伝わる古刹。児玉党の倉田孫四郎基行とその妻妙泉尼夫妻が出家、源頼朝公に寺の再興を願い出て許され、建久元年(1190年)頼朝公は越生次郎家行に命じて堂塔伽藍を建立して天台宗寺院として再興、将軍家繁盛の祈祷道場としたといいます。
・応永五年(1398年)に阿闍梨権大僧都法印榮曇和尚が入山し、真言宗に改宗して中興開山、天正十九年(1591年)には徳川家康公から寺領20石の御朱印状を拝領。
・新義真言宗の関東十一談林の一つに列し、住職が将軍に直接拝謁できる格式の高い寺院でした。
・後鳥羽上皇の御宸筆で頼朝公から拝領したとされる絹本着色高野・丹生明神像をはじめ、数多くの文化財を有しています。
第2番 大慈山 正法寺
埼玉県越生町越生960
臨済宗建長寺派 (旧)本寺:鎌倉円覚寺
御本尊:聖観世音菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第24番、越生七福神(大黒天)
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第24番
朱印尊格:聖観世音菩薩

2.越生七福神
朱印尊格:大黒天

第3番 瑠璃山 東園院 医王寺
埼玉県越生町上野2043
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
第4番 福壽山 滝房 多門寺
埼玉県越生町上野1454
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
第5番 澤谷山 光明院 宝福寺
埼玉県毛呂山町大谷木154
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:
関連武将:毛呂氏→大谷氏
他の札所:
第6番 息災山 吉祥院 延命寺
埼玉県毛呂山町下河原245
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:不動明王
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

第7番 観音寺
埼玉県坂戸市四日市場379
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:千手観世音菩薩
他の札所:
第8番 金剛山 地蔵院 南蔵寺
埼玉県毛呂山町350-0436
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
※廃寺?、現・川角八幡社境内に遺跡
第9番 山本坊
埼玉県毛呂山町西戸916
本山修験派
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、西戸国津神神社境内他に遺跡
第10番 御嶺山 不動院 龍台寺
埼玉県越生町西和田101 (旧)本寺:越生法恩寺
真言宗智山派
御本尊:大日如来
他の札所:
第11番 石樹山 常住院 興禅寺
埼玉県越生町西和田849
真言宗智山派 (旧)本寺:越生医王寺
御本尊:不動明王
他の札所:
第12番 能満山 見正寺
埼玉県越生町成瀬330
真言宗智山派 (旧)本寺:越生医王寺
御本尊:聖観世音菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第22番
司元別当:成瀬諏訪神社(越生町成瀬)
〔拝受御朱印〕 ・無住、妙見寺(越生町成瀬287)にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第22番
朱印尊格:聖観世音菩薩

第13番 如意山 地蔵院 高蔵寺
埼玉県越生町津久根253
真言宗智山派 (旧)本寺:越生最勝寺
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第26番
〔拝受御朱印〕 ・無住、最勝寺(越生町堂山287)にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第26番
朱印尊格:聖観世音菩薩

第14番 大泉院
埼玉県越生町小杉1
本山修験派?
司元別当:梅園神社(越生町小杉)
御本尊:
他の札所:
※属山本坊(第9番)、廃寺、小杉天神社別当、梅園神社内
第15番 青龍山 最勝寺
埼玉県越生町堂山287
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
関連武将:源頼朝公、兒玉氏雲太夫
他の札所:入比板東三十三観音霊場第27番、越生七福神(福禄寿)
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第27番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

第16番 仏心院
埼玉県越生町龍ケ谷
(旧)本寺:本坊は常楽院/高山不動尊(飯能市高山346)
真言宗智山派
御本尊:
他の札所:
※廃寺?
※ 御朱印は不授与です。本坊の常楽院/高山不動尊の御朱印を掲載します。
〔拝受御朱印〕
・高山不動尊にて拝受(原則として冬至の日、年1日のみの授与)
1.高山不動尊の御朱印

第17番 多武峰 慈眼坊
埼玉県ときがわ町西平
宗派不詳
御本尊:
他の札所:入比板東三十三観音霊場第31番
※廃寺?、個人宅に(多武峰神社)
第18番 都幾山 一乗法華院 慈光寺
埼玉県ときがわ町西平386
天台宗
御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩
関連武将:源頼朝公(祈願所)
他の札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第9番、関東九十一薬師霊場第33番、関東百八地蔵尊霊場第14番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.坂東三十三箇所(観音霊場)第9番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

2.関東九十一薬師霊場第33番
朱印尊格:薬師如来(抜苦輿楽)
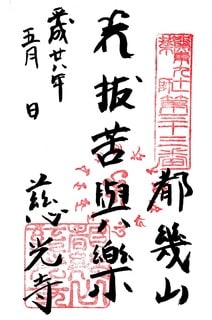
3.関東百八地蔵尊霊場第14番
朱印尊格:地蔵菩薩(巡礼地蔵尊)

4.阿弥陀如来
朱印尊格:阿弥陀如来
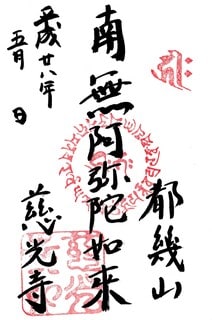
第19番 日影山 長勝寺
埼玉県ときがわ町日影
真言宗智山派 (旧)本寺:越生最勝寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
※廃寺?、日影神社周辺か?
第20番 鈴宮山 開敷院 観音寺
埼玉県ときがわ町本郷551
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:聖観世音菩薩
他の札所:入比板東三十三観音霊場第7番
〔拝受御朱印〕 ・無住、光明寺(第22番、ときがわ町玉川3017)にて拝受
1.入比板東三十三観音霊場第7番
朱印尊格:聖観世音菩薩
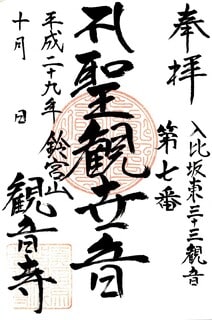
第21番 医王寺
埼玉県ときがわ町番匠
宗派不詳
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、寺跡あり
第22番 音無山 光明寺
埼玉県ときがわ町玉川3017
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:不動明王
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:不動明王・弘法大師

第23番 東光山 薬王院 満願寺
埼玉県鳩山町熊井800
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
他の札所:
第24番 西明山 法輪院 真光寺
埼玉県鳩山町大豆戸340
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
司元別当:大豆戸三嶋神社(鳩山町大豆戸)
御本尊:大日如来
他の札所:
第25番 延命山 奥野院 興長寺
埼玉県鳩山町小用240
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:阿弥陀如来
関連武将:源頼朝公、越生四郎家行
他の札所:
第26番 清水山 彼岸院 大榮寺
埼玉県坂戸市厚川78
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第6番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:阿弥陀如来
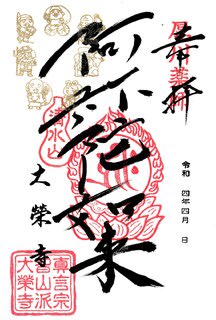
2.中武蔵七十二薬師霊場第6番
朱印尊格:薬師如来

第27番 八葉山 来迎院 長久寺
埼玉県坂戸市浅羽1486
真言宗智山派
御本尊:大日如来
他の札所:
第28番 安養山 蓮華院 善能寺
埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-3−10
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第11番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:阿弥陀如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第11番
朱印尊格:薬師如来
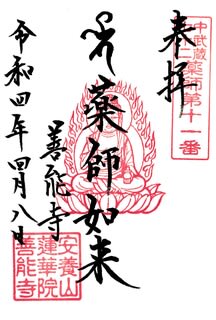
第29番 龍護山 實相院 大智寺
埼玉県坂戸市石井2331
真言宗智山派
御本尊:大日如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第23番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時のみ授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:大日如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第23番
朱印尊格:薬師如来
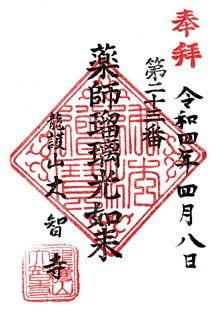
第30番 天神山 不動院 龍福寺
埼玉県坂戸市戸口453
真言宗智山派
御本尊:不動明王
(旧)本寺:坂戸大智寺
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第1番(戸口薬師)
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第1番
朱印尊格:薬師如来

第31番 巌殿山 修繕院 正法寺(巌殿観音)
埼玉県東松山市岩殿1229
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
関連武将:源頼朝公、比企判官能員
他の札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第10番、関東百八地蔵尊霊場第13番、七観音霊場第5番、中武蔵七十二薬師霊場第47番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.坂東三十三箇所(観音霊場)第10番
朱印尊格:千手観世音菩薩

2.関東百八地蔵尊霊場第13番
朱印尊格:地蔵菩薩(百地蔵尊)

3.七観音霊場第5番
朱印尊格:千手観世音菩薩

4.中武蔵七十二薬師霊場第47番
朱印尊格:薬師如来
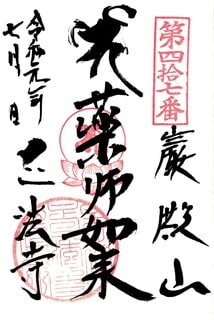
第32番 澤田山 修造院 長慶寺
埼玉県東松山市神戸1678
真言宗智山派
御本尊:不動明王
関連武将:畠山重忠
他の札所:比企西国三十三観音第21番、中武蔵七十二薬師霊場第48番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.武州八十八霊場第32番
朱印尊格:不動明王

2.比企西国三十三観音第21番
朱印尊格:十一面観世音菩薩
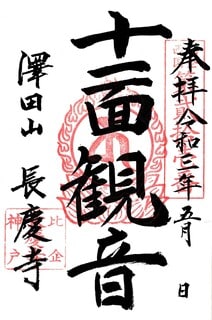
3.中武蔵七十二薬師霊場第48番
朱印尊格:薬師如来

第33番 安楽寺
埼玉県東松山市唐子
宗派不詳
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、墓地
第34番 成就院
埼玉県東松山市金井
宗派不詳
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、金井秋葉神社そば
第35番 岩室山 湯澤寺 龍性院
埼玉県吉見町北吉見459
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第63番、比企西国三十三観音第3番(岩室観音堂)
※岩室観音堂(吉見町北吉見309)は龍性院の境外仏堂
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

2.比企西国三十三観音第3番(岩室観音堂)
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.中武蔵七十二薬師霊場第63番
朱印尊格:薬師如来

第36番 岩殿山 光明院 安楽寺(吉見観音)
埼玉県吉見町御所374
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
関連武将:源範頼公
他の札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第11番、関東八十八箇所第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第17番、武州路十二支霊場(申)、中武蔵七十二薬師霊場第62番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時のみ授与の可能性あり)
1.坂東三十三箇所(観音霊場)第11番
朱印尊格:聖観世音菩薩

2.関東八十八箇所第75番
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.東国花の寺百ヶ寺霊場第17番
朱印尊格:聖観世音菩薩

4.武州路十二支霊場(申)
朱印尊格:金剛界大日如来
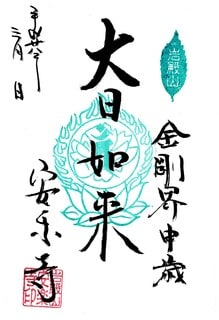
5.中武蔵七十二薬師霊場第62番
朱印尊格:薬師如来
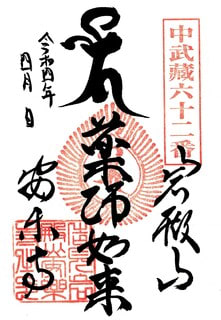
第37番 端松山 正伝寺
埼玉県吉見町和名359
真言宗霊雲寺派 (旧)本寺:湯島霊雲寺
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:
第38番 岩殿山 光明院 息障院
埼玉県吉見町御所146-1
真言宗智山派 (旧)本寺:山城國醍醐報恩院
御本尊:不動明王
関連武将:源範頼公
他の札所:
第39番 松岡山 光勝寺 明王院
埼玉県吉見町下細谷415
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:十一面観世音菩薩
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第60番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第60番
朱印尊格:薬師如来

第40番 愛宕山 寿命院 無量寺
埼玉県吉見町久保田1380
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第58番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

2.中武蔵七十二薬師霊場第58番
朱印尊格:薬師如来

第41番 大串山 宝珠院 観音寺
埼玉県吉見町大串1282
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:不動明王
他の札所:
第42番 頼綱山 観秀院 寶性寺
埼玉県吉見町江綱1299
真言宗智山派 (旧)本寺:吉見息障院
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第66番(薬師堂)
〔拝受御朱印〕 ・明王院(吉見町下細谷)にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第66番
朱印尊格:薬師如来
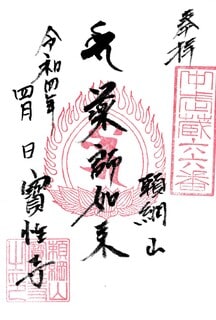
第43番 明光山 法鈴寺
埼玉県川島町下小見野155
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:不動明王?
司元別当:下小見野氷川神社(川島町下小見野)
関連武将:小野見氏
他の札所:
第44番 法蔵山 西養院 西見寺
埼玉県川島町吹塚232
真言宗智山派 (旧)本寺:越生法恩寺
御本尊:薬師如来
他の札所:
第45番 法輪山 極楽寺
埼玉県川島町上八ツ林261
真言宗智山派 (旧)本寺:川島善福寺
御本尊:
他の札所:
第46番 寶塔山 善福寺
埼玉県川島町下八ツ林307
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第35番、第36番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:不動明王

2.中武蔵七十二薬師霊場第35番(下八ツ林薬師堂)
朱印尊格:薬師如来
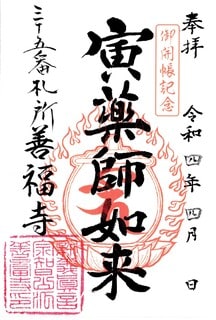
3.中武蔵七十二薬師霊場第36番(下八ツ林薬師堂)
朱印尊格:薬師如来

第47番 大御山 西福院 廣徳寺
埼玉県川島町表76
真言宗豊山派
御本尊:五大明王
関連武将:美尾谷十郎廣徳
他の札所:
第48番 蓮王山 十輪寺
埼玉県川島町
真言宗豊山派 (旧)本寺:川島廣徳寺
御本尊:不動明王
他の札所:
※無住?、お堂と墓地
第49番 龍池山 慈眼院
埼玉県川島町角泉110
真言宗豊山派 (旧)本寺:川島廣徳寺
御本尊:正観世音菩薩
他の札所:
第50番 法雲山 普門院 弘善寺
埼玉県川島町上狢
真言宗智山派 (旧)本寺:川島廣徳寺
御本尊:
他の札所:
※廃寺?、上狢集落センターと墓地
第51番 大福寺
埼玉県川島町平沼308
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第30番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第30番
朱印尊格:薬師如来

第52番 草芽山 自性院 大聖寺
埼玉県川島町井草161
真言宗智山派
御本尊:大日如来 千手観世音菩薩?
関連武将:比企能員
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第29番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場は御開帳時限定授与の可能性あり)
1.武州八十八霊場第52番
朱印尊格:大日如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第29番
朱印尊格:薬師如来

第53番 土袋山 普門寺 金乗院
埼玉県川島町上伊草830
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
他の札所:比企西国三十三観音第13番
第54番 守護山 善能寺
埼玉県川島町中山1823
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:
他の札所:
第55番 清月山 元光院 金剛寺
埼玉県川島町中山1198
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:阿弥陀如来

第56番 三嶽山 普門院 延命寺
埼玉県川島町中山1285
真言宗智山派
御本尊:
他の札所:比企西国三十三観音第8番
第57番 勅王山 正福寺
埼玉県川島町南園部310
真言宗智山派
御本尊:
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受
1.御本尊
朱印尊格:御寶印・寺院印のみ

第58番 光勝寺
埼玉県坂戸市赤尾1832
真言宗智山派
御本尊:不動明王
※墓地のみ
第59番 薬王山 浄水院 東光寺
埼玉県坂戸市小沼266
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:薬師如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第21番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第21番
朱印尊格:薬師如来

第60番 恵日山 法音寺
埼玉県坂戸市小沼902
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:不動明王
他の札所:
第61番 薩埵山 錫杖院 忠栄寺
埼玉県坂戸市横沼366
真言宗豊山派 (旧)本寺:伊草金乗院
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:
第62番 三寶山 実蔵院 長福寺
埼玉県坂戸市紺屋892
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:大日如来
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第17番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:大日如来

2.中武蔵七十二薬師霊場第17番
朱印尊格:薬師如来

第63番 薬樹山 瑠璃光院 永命寺
埼玉県川越市下小阪688
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第16番、小江戸川越古寺巡礼第51番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.御本尊
朱印尊格:不動明王
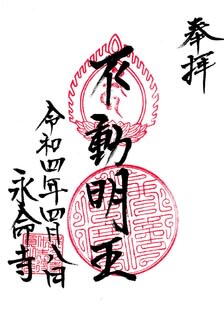
2.中武蔵七十二薬師霊場第16番
朱印尊格:薬師如来
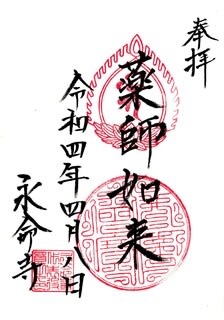
第64番 由城山 福聚院 慈眼寺
埼玉県坂戸市中小坂285
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:十一面観世音菩薩
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・郵送にて拝受
1.武州八十八霊場第64番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

2.閻魔大王の御朱印
朱印尊格:閻魔大王

第65番 広谷山 正音寺
埼玉県鶴ヶ島市上広谷605-1
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:
他の札所:中武蔵七十二薬師霊場第13番
〔拝受御朱印〕 ・当寺にて拝受(薬師霊場御開帳時限定授与の可能性あり)
1.中武蔵七十二薬師霊場第13番
朱印尊格:薬師如来

第66番 慈眼山 喜見院 満福寺
埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷487
天台宗
御本尊:千手観世音菩薩
司元別当:熊野社(鶴ヶ島市太田ヶ谷)ほか
他の札所:武蔵国十三佛霊場第5番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:千手観世音菩薩

2.武蔵国十三佛霊場第5番
朱印尊格:地蔵菩薩

第67番 萬霊山 法護院 延命寺
埼玉県川越市笠幡4451
天台宗
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:武蔵国十三佛霊場第4番、小江戸川越古寺巡礼第3番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:延命地蔵菩薩

2.武蔵国十三佛霊場第4番
朱印尊格:普賢菩薩

第68番 観智山 地蔵寺 三明院
埼玉県川越市池辺507
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:大日如来
司元別当:熊野神社(川越市池辺)
他の札所:小江戸川越古寺巡礼第57番
第69番 薬王山 地蔵院 廣福寺
埼玉県狭山市下奥富844
天台宗 (旧)本寺:仙波中院
御本尊:薬師如来
他の札所:関東九十一薬師霊場第32番、関東百八地蔵尊霊場第9番、武蔵国十三佛霊場第3番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.関東九十一薬師霊場第32番
朱印尊格:薬師如来

2.関東百八地蔵尊霊場第9番
朱印尊格:地蔵菩薩

3.武蔵国十三佛霊場第3番
朱印尊格:文殊菩薩
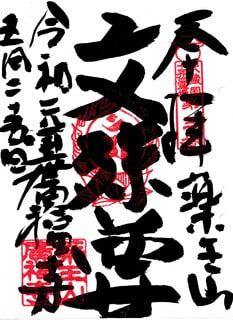
第70番 龍殿山 成就院 瑞光寺
埼玉県狭山市上奥富354
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:大日如来
他の札所:
第71番 金宝山 龍護院 永代寺
埼玉県狭山市柏原2492
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:
関連武将:畠山重忠
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.虚空蔵菩薩の御朱印
朱印尊格:虚空蔵菩薩
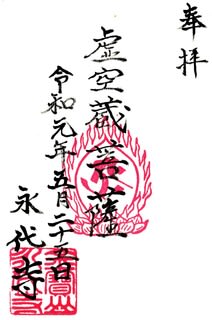
第72番 天竜山 薬王院 成円寺
埼玉県狭山市入間川2-3-11(徳林寺内へ(地蔵堂))
真言宗智山派 (旧)本寺:坂戸大智寺
御本尊:釈迦三尊
司元別当:八幡神社(狭山市入間川)、牛頭天王社、清水八幡宮、諏訪社
関連武将:木曽(清水冠者)義高
他の札所:(徳林寺)武蔵野三十三観音霊場第17番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.不動堂の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.武蔵野三十三観音霊場第17番
朱印尊格:●聚閣
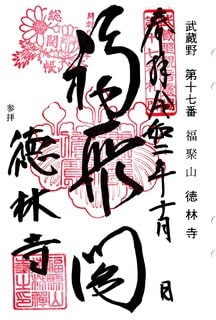
第73番 蔵王山 観音院 常泉寺
埼玉県狭山市北入曽315
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:釈迦如来
他の札所:
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:釈迦如来

2.観音堂の御朱印
朱印尊格:聖観世音菩薩

第74番 御嶽山 延命寺 金剛院
埼玉県狭山市南入曽460
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
司元別当:御嶽社(南入曽村/現・入間野神社)
他の札所:
※ 御朱印は不授与です。当寺が元別当をつとめた入間野神社の御朱印を掲載します。

第75番 龍岳山 歓喜院 龍圓寺
埼玉県入間市新久717
真言宗智山派
御本尊:虚空蔵菩薩
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第20番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第41番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.武蔵野三十三観音霊場第20番
朱印尊格:千手観世音菩薩

2.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第41番
朱印尊格:十一面観世音菩薩・弘法大師

第76番 世音山 妙智寺 蓮花院
埼玉県入間市春日町2-9-1
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第18番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第74番・第76番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.武蔵野三十三観音霊場第18番
朱印尊格:千手観世音菩薩
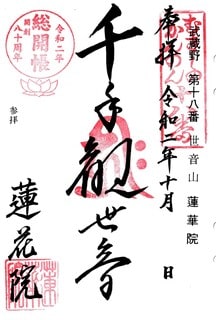
3.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第74番
朱印尊格:薬師如来・弘法大師

4.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第76番
朱印尊格:薬師如来・弘法大師

第77番 高竹山 光明院 明光寺
埼玉県狭山市根岸2-5-1
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第44番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:地蔵菩薩

2.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第44番
朱印尊格:十一面観世音菩薩・弘法大師
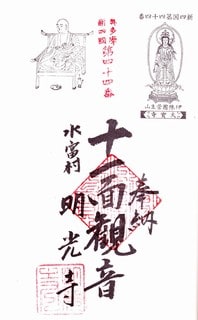
第78番 笹井観音堂(瀧音山 泊山寺)
埼玉県狭山市笹井
本山修験宗?(京都聖護院の直末)
御本尊:十一面観世音菩薩
他の札所:
※無住。現在、御朱印は不授与です。
第79番 千手山 教学院 普門寺
埼玉県飯能市川崎300
真言宗智山派
御本尊:
司元別当:白鬚神社(飯能市川崎)
他の札所:高麗板東三十三観音霊場第4番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.高麗板東三十三観音霊場第4番
朱印尊格:千手観世音菩薩

第80番 光明山 正覚院 圓照寺
埼玉県入間市野田158
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀三尊
関連武将:加治氏
他の札所:関東八十八箇所第73番、武蔵野三十三観音霊場第22番、高麗板東三十三観音霊場第11番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第58番、武蔵野七福神(弁財天)
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.関東八十八箇所第73番
朱印尊格:阿弥陀如来

2.武蔵野三十三観音霊場第22番
朱印尊格:如意輪観世音菩薩
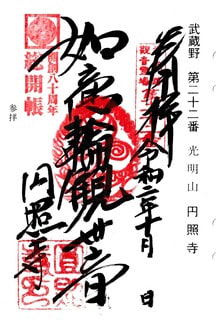
3.高麗板東三十三観音霊場第11番
朱印尊格:聖観世音菩薩

4.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第58番
朱印尊格:千手観世音菩薩・弘法大師

5.武蔵野七福神の御朱印
朱印尊格:弁財天

第81番 仏寿山 宝幢院 願成寺
埼玉県飯能市川寺688
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
第82番 岸高山 福寿院 歓喜寺
埼玉県飯能市岩渕658甲
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:
他の札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第32番
第83番 般若山 長寿院 観音寺
埼玉県飯能市山手町5-17
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第24番、高麗板東三十三観音霊場第10番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第64番、武蔵野七福神(寿老人)
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.武蔵野三十三観音霊場第24番
朱印尊格:如意輪観世音菩薩
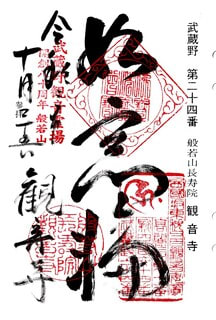
2.高麗板東三十三観音霊場第10番
朱印尊格:如意輪観世音菩薩

3.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第64番
朱印尊格:阿弥陀如来・弘法大師

第84番 常寂山 蓮華院 智観寺
埼玉県飯能市中山520
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
関連武将:中山氏
他の札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第28番、高麗板東三十三観音霊場第1番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第28番
朱印尊格:大日如来・弘法大師

3.高麗板東三十三観音霊場第1番
朱印尊格:十一面観世音菩薩

第85番 慈眼山 真福寺
埼玉県飯能市中山436 (旧)本寺:中山智観寺
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:
※無住? 加治神社門前
第86番 高岡山 龍泉寺
埼玉県日高市栗坪124
真言宗智山派 (旧)本寺:高麗聖天院
御本尊:不動明王
他の札所:
第87番 箕輪山 満行院 霊巌寺
埼玉県日高市新堀740-1
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:武蔵野三十三観音霊場番外1、高麗板東三十三観音霊場番外2
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:地蔵菩薩

2.武蔵野三十三観音霊場番外1
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.高麗板東三十三観音霊場番外2
朱印尊格:聖観世音菩薩

第88番 高麗山 聖天院 勝楽寺
埼玉県日高市新堀990-1
真言宗智山派
御本尊:不動明王
他の札所:武蔵野三十三観音霊場第26番、高麗板東三十三観音霊場第32番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.御本尊の御朱印
朱印尊格:不動明王

2.武蔵野三十三観音第26番
朱印尊格:聖観世音菩薩

3.高麗板東三十三観音霊場第32番
朱印尊格:千手観世音菩薩

【 BGM 】
■ 歌に形はないけれど - ユリカ / 花たん
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
■ Endless Story - Yuna Ito
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
■ 鎌倉殿の御家人
■ 源頼朝公ゆかりの寺社
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
40.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院
〔北条政子〕
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
坂東三十三観音公式サイト
鎌倉市大町3-1-22
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第3番、鎌倉三十三観音霊場第3番、鎌倉二十四地蔵霊場第24番、相州二十一ヶ所霊場第8番、小田急沿線花の寺四季めぐり第17番
北条政子はおそらく、史上もっとも波乱の人生をおくった女性で、その生涯を追っていくとキリがないので、こちらWikipediaをご覧ください。
Wikipediaに「『吾妻鏡』では建保七年(1219年)の実朝死去から嘉禄元年(1225年)の政子死去まで、北条政子を鎌倉殿と扱っている。」とあるように、北条政子が本当の意味で幕政の表舞台に登場するのは、建保七年(1219年)正月の将軍・実朝公暗殺から三寅(後の藤原頼経)を4代目の鎌倉殿として迎え入れたのちだと思います。
北条氏独裁化の流れのなかで御家人内に仇敵も多い北条義時よりも、頼朝公とともに歩んだ政子の方が、御家人たちとしても担ぎやすかったのでは。
承久三年(1221年)、承久の乱の際に御家人に発した「故右大将(頼朝公)の恩は山よりも高く、海よりも深い、逆臣の讒言により不義の綸旨が下された。秀康、胤義(上皇の近臣)を討って、三代将軍(実朝公)の遺跡を全うせよ。ただし、院に参じたい者は直ちに申し出て参じるがよい」(Wikipediaより)は世紀の名演説としてよく知られています。
これも頼朝公や御家人たちと苦楽をともにしてきた政子だからこそ、語れる言葉なのかもしれません。
貞応三年(1224年)、北条義時の急死後に勃発した「伊賀氏の変」では政子の政治的手腕がかいま見られます。
この政変は義時の後妻(継室)・伊賀の方が、実子・政村の執権就任と、娘婿・一条実雅の将軍職就任を画策したもので、政村の烏帽子親である三浦義村の動きによっては北条政権をくつがえす大乱となる可能性がありました。
これを察した政子は先手を打って義時の長男・泰時を執権に就任させ、三浦義村に対して泰時への支持を確約させたといわれています。
義時なきあと、最大の実力者で権謀術数をめぐらす三浦義村を相手に渡り合い、泰時を執権職に就けたこと、また執権の座を逃した政村が、その後も泰時を支えつづけたことは並みの手腕ではないと思われます。(泰時の人望もあるとは思いますが)
嘉禄元年(1225年)泰時への代替わりを見届けたあと逝去。享年69。
戒名は安養院殿如実妙観大禅定尼。
墓所は鎌倉・扇ヶ谷の壽福寺にあります。


【写真 上(左)】 壽福寺
【写真 下(右)】 壽福寺の御朱印(御本尊)
ここでは、政子が頼朝公の冥福を祈るために建立した祇園山長楽寺を前身とし、政子の戒名を号した祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院をご紹介します。
安養院の由緒はすこぶる複雑で、3つの前身寺院の由緒を追わなければならないので、「鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)」の記事をそのまま持ってきます。
ながくなりますがご容赦ください。
------------------------
安養院は鎌倉・大町にある浄土宗の名刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第3番札所として広く知られています。
このお寺はすこぶる複雑な由緒をもたれます。
まずは山内由緒書から(抜粋)。
「建立 嘉禄元年(1225)、開山 願行上人、開基 北条政子」
「北条政子が夫・頼朝公の冥福を祈るために佐々目ガ谷に建立した祇園山長楽寺が前身。鎌倉末期に善導寺の跡(現在地)に移って安養院になったといいます。延宝八年(1680)に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかつて建立した田代寺の観音堂を移します。こうして『祇園山安養院田代寺』になりました。」
つぎに鎌倉市観光協会Webから(抜粋)。
「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり。のちに北条政子が夫・頼朝公の菩提のために笹目に建てた長楽寺が焼失したため、鎌倉末期にこの地に長楽寺を移し、政子の法名・安養院を号し、さらに江戸時代の始めに田代寺の千手観音を移した。」
以上より、長楽寺・善導寺・田代寺という3つの前身寺院が関係していることになります。
『鎌倉市史 社寺編』から以下抜粋引用します。
「もと律宗。昌譽の時浄土宗となったという。もと名越派の本山、延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により京都知恩院末となる。開山、願行房憲静。開基、北条氏政子。寺伝では嘉禄元年(1225年)、頼朝夫人政子が頼朝の菩提のため佐々目の長楽寺谷に律寺を建立。願行を開山としたという。『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう。延慶三年(1310年)十一月、失火あり鎌倉中の大火となった。(『武家年代記裏書』)寺伝には、高時滅亡の後、稲瀬川の辺から現在の地、善導寺の跡に移りそれ以降安養院と号したという。延寶八年(1680年)十月、門外町屋から失火、全焼した。再建の時比企ヶ谷にあった末寺、田代観音堂を境内に移した。」
ところが『新編鎌倉志』には「名越の入口、海道の北にあり。祇園山と号す。浄土宗、知恩院の末寺なり。此寺初め律宗にて、開山願行上人なり。其十五世昌譽和尚と云より浄土宗となる。昌譽より前住の牌は皆律宗なり。初長谷の前稲瀬川の邊に在しを、相模入道滅亡の後、此に移すと云伝ふ。本堂に阿彌陀坐像、客殿にも阿彌陀の坐像を安ず。共に安阿彌が作なり。」とあり、前身3寺の所縁は明示されていません。
そこで『新編相模國風土記稿』の安養院の項を当たってみました。
こちらには山内絵図とともに詳しい記述がありました。要点のみ抜粋引用します。
「古ハ笹目ヶ谷ニ在。祇園山長楽寺と号ス。浄土宗。昔ハ無木(本)寺ニテ。名越一派ノ本山ナリ。延寶四年(1676年)諸宗寺院本末御改ヨリ。京知恩院末に属ス。嘉禄元年(1225年)二位ノ禅尼。故頼朝菩提ノ為。笹目ヶ谷邊(西方長谷村界笹目ヶ谷ニ長楽寺谷ト云フアリ。是当寺ノ舊蹟ナリ)ニテ。七堂伽藍ヲ営ミ。律寺ヲ建立シテ。僧願行ヲ開山トシ。又●年七月二位禅尼逝去アリシカバ。願行導師トナリ当寺ニ葬送シ。法名ヲ安養院ト号スト云フ。後兵火ノ為ニ。堂宇残ラズ烏有トナリシカバ。当所善導廃寺蹟ニ移テ堂宇ヲ営ミ両寺を合シテ再建ス。鎌倉志ニ当寺初長谷ノ前。稲瀬川ノ邊ニ在シヲ。相模入道滅亡ノ後此ニ移スト云伝フ云々。是ニ拠バ正應二年(1289年)ノ兵火ナルベシ。又善導寺モ其頃退転セシナルベシ。寺伝ニ彼善導寺開山ハ記主禅師ノ法嗣尊観ナリ。某年名越一派ヲ立。爰ニ一宇ヲ建立シ正和五年(1316年)寂スト云フ。後年現住昌譽カ時。律宗ヲ改メ今ノ宗派トナルと云フ。天文十三年(1544年)北條氏直敷地ヲ寄附ス。延寶八年(1680年)失火シテ諸堂残ナク焼亡ス。其頃比企谷ノ内田代ニ観音堂アリ。当院の末ナリシヲ。当寺再建ノ時境内ニ移シ。夫ヨリ三ヶ寺合成ノ梵宇ト称ス。」
『新編相模國風土記稿』には本堂、観音堂についての記事もありました。
「本堂 本尊阿彌陀 安阿彌作安ス。堂中頼朝又二位禅尼ノ牌。地蔵堂。本尊ハ石像(弘法大師作ト云フ)ニテ。鎌倉二十四所ノ一ナリ。子安地蔵ト云フ。」
「観音堂。本尊千手観音ナリ。立像長五尺四寸恵心作。坂東三十三所ノ札所第三番ト云フ。昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像(立像ニテ長九寸許。天竺竜樹菩薩筆)ヲ籠メ。更ニ比企谷田代ノ地ニ堂舎ヲ造建シテ安置シ。白花山普門寺ト号セリ。土俗ハ多く田代寺又田代堂ナド称セリ。厨子ニ納テ内殿ニ安スト云フ。延寶八年(1680年)当寺焼亡ノ後此境内ニ移セシナリ。前立ニ同像ヲ置キ脇壇ニ阿彌陀ノ座像ヲ置ク。恵心作。是ハ二位禅尼ノ持念佛ト云フ。」
さらに、田代寺についてWikipediaから引いてきました。
「田代寺は1192年(建久3年)田代信綱が尊乗を開山として比企ヶ谷(ひきがやつ)に建立」(原典不明)
引用だらけですみません。
でも、これらの情報がなければ安養寺の由緒(というか3箇寺合一の経緯)がたどれません。
上記資料の青字の箇所が、(おそらく現在地にあった)旧・善導寺についての記述です。
長楽寺、善導寺と合寺後の由緒が混在しているので、すこぶるわかりにくくなっています。
まずは、開山関係から当たってみます。
■ 願行上人憲静(長楽寺)
鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧。
今後のこともあるので、『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同)から経歴・事績の要点を引いてみます。
願行上人憲静は、健保三年(1215年)出生、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。
〔法統・真言宗系統〕
・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)
・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)
・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)
三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。
真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。
これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。
〔法統・律宗系統〕
・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。
・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。
月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。
その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。
この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。
以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。
〔鎌倉での活動〕
願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏)には下記のとおりあります。
・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。
ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。
また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。
「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)
これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。
佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。
なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。
願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。


【写真 上(左)】 西方寺
【写真 下(右)】 西方寺の御朱印(御本尊)
「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)
佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。
Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。
同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。
また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。
『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。
『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。
さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。
なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。
二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。
■ 尊観上人良弁(善導寺)
鎌倉市Webの「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり」および、『鎌倉市史 社寺編』の「もと名越派の本山、『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう」から探ってみました。
「記主禅師」(良忠上人)は、光明寺ゆかりの高僧です。
「記主禅師」(良忠上人)とは、嘉禎三年(1237年)浄土宗第三祖となられた高僧で、多くの門下を育てられました。 文応元年(1260年)鎌倉へ入られ北条朝直の帰依のもと悟真寺に住され、これがのちに浄土宗大本山光明寺となりました。

■ 光明寺の開山 記主禅師の御朱印
光明寺は名越エリアにあるので「名越一派」は大本山光明寺の流れかと思いましたが、「浄土宗 名越派」で検索してみるとなんと一発でヒットしました。
浄土宗「WEB版新纂浄土宗大辞典」の「名越派」(なごえは)です。
(「鎮西流(鎮西派)」は知っていましたが、不勉強で「名越派」は知りませんでした。)
ここには「三祖然阿良忠門下六派の一つ。派祖は良弁尊観。名越流とも称される。また、尊観が相模国鎌倉名越谷善導寺で布教したため善導寺義ともいう。」とありました。
いわき市山崎の専称寺と栃木県益子町の円通寺が本山格であったようですが、江戸時代は増上寺の支配下にあり、大正以前に浄土宗として統一されているようです。
さらに尊観についても記載がありました。
「延応元年(1239年)—正和五年(1316年)三月一四日。鎌倉時代中期の僧。字(あざな)は良弁。名越派派祖。また鎌倉名越谷の善導寺で布教したため、後世尊観の流派を名越流もしくは善導寺義という。」
どんぴしゃです。これで決め打ちです。
「名越一派」は「浄土宗名越派」をさし、「善導寺」は尊観上人が「浄土宗名越派」の布教の拠点とした寺院です。
これで『新編相模國風土記稿』にあった「名越一派ノ本山ナリ」のナゾが解けたことになります。
■ 田代冠者信綱(普門寺・田代寺)
『新編相模國風土記稿』の安養院観音堂に「昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像」として登場し、普門寺(田代寺)の開基とみられます。
『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「田代観音堂 普門寺と号す。妙本寺の南東なり。安養院末、堂の額に白華山と有。本尊千手観音、坂東第三番の札所。此西の方を田代屋敷と唱ふ。田代冠者信綱が舊跡。今は畑なり。」
「田代冠者信綱」は、おそらくWikipediaに「伊豆国司と狩野茂光の娘の子。石橋山の戦いで頼朝公挙兵時の武士の一人。平家物語の三草山の合戦や一ノ谷の戦い及び屋島の戦いにも登場し。義経公挙兵時の武士ともなり源義仲を追討した。しかし義経公の門下となったと同時に頼朝公から破門の書状を受け(た)。」とある鎌倉幕府草創期の武士とみられます。
これで、ようやく安養院の前身3寺のプロフィールが揃いました。
ごちゃごちゃになったので(笑)、ここで整理してみます。
1.現在地(大町)には、もともと尊観上人(正和五年(1316年)寂)が開かれた浄土宗名越派の善導寺があった。
(正應二年(1289年)の頃(現在地に?)退転したという記録もあり。)
2.一方、長谷笹目ヶ谷には嘉禄元年(1225年)北条政子が夫・頼朝公菩提のために創建した祇園山長楽寺(律宗)があった。開山は二階堂の理智光寺を開いた願行上人憲静。
嘉禄元年(1225年)、二位禅尼(北条政子)逝去の際、願行上人が導師となって当寺に葬送し、法名を安養院と号したという。
また、建治二年(1275年)前後の説法念仏会の折、願行上人が稲瀬川あたり(長谷~由比ヶ浜)に安養院ないしその前身となる寺院(祇園山)を開山された可能性もある。
※ただし、願行上人の鎌倉下向は弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間とみられ、二位禅尼(北条政子)逝去の嘉禄元年(1225年)と時代が合いません。
長楽寺は当初長谷稲瀬川にあり、正應二年(1289年)の兵火を受け笹目に移転した可能性もあるので、願行上人がこれにかかわり、その際に安養院と号したのかもしれません。
3.比企ヶ谷田代には建久三年(1192年)、伊豆の武士田代冠者信綱が尊乗上人を開山に建立した白花山普門寺(田代寺)があり、千手観世音菩薩を御本尊としていた。
普門寺(田代寺)は善導寺ないし長楽寺の末寺であった。
4.笹目の長楽寺は元弘元年(1333年)の兵火で焼失、大町の善導寺に統合されて『安養院長楽寺』と号した。安養院は政子の法号にちなむもの。(*Wikipedia)
5.統合時の安養院は律宗だったが後に浄土宗となり、天文十三年(1544年)には後北条氏第5代北條氏直の寄進を受ける。江戸時代の延寶八年(1680年)失火により諸堂焼亡する。
6.比企ヶ谷の普門寺(田代寺・田代観音)も同年延寶八年(1680年)に焼亡、焼亡した安養院再建の折に比企ヶ谷から本寺であった安養寺の境内に移る。この時点で3つの寺院の合一が為る。
7.坂東三十三箇所の札所本尊の千手観世音菩薩は、比企ヶ谷の普門寺(田代寺)から遷られての御座。
8.延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により、京都知恩院末となる。
以上から安養院は、
1.浄土宗名越派の派祖・尊観上人が名越派の当初の本山とされた善導寺
2.北条政子が頼朝公菩提のために創建。開山願行上人の祇園山長楽寺(律宗)
3.伊豆国守の子、田代冠者信綱が自身の守り本尊・千手観音を奉安した普門寺(田代寺)
という3つの由緒ある寺院の合寺であることがわかりました。
---------------------
※ 令和3年12月時点で当山山内は撮影禁止となっています。
以下の写真は撮影禁止となる前に撮影したものです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 坂東札所標
県道311号大町大路に面して参道入口。
「坂東第三番田代観音」の札所標と「浄土宗名越派根本霊場」の石標。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 名越派根本霊場碑
石段の先に切妻屋根本瓦葺の四脚門で、門下の木箱に拝観料を納めます。
山門をくぐって右手の地蔵堂は鎌倉二十四地蔵霊場第24番の結願所で、札所本尊の日切地蔵尊が御座します。
坐像の石像で弘法大師の御作とも伝わり、子安地蔵ともよばれたそうです。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 鬼板と兎毛通
正面の本堂は権現造のような複雑な意匠で詳細不明。
向拝側の屋根に千鳥破風、向拝軒に唐破風の二重破風となっています。
軒下の水引虹梁両端に雲形の獅子木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いていますが全体にシンプルなイメージ
見上げには山号扁額。


【写真 上(左)】 山号扁額
【写真 下(右)】 堂内向拝
堂内の外陣には札所の御詠歌板などが掲げられています。
格子扉越しに御内陣が拝め、扉うえには院号扁額。
「坂東第三番」の札所だけに、さすがに風格があります。

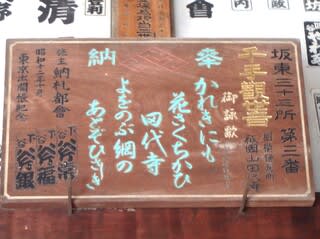
【写真 上(左)】 院号扁額
【写真 下(右)】 坂東霊場札所板
御本尊の阿弥陀如来は伝・安阿彌作。観音霊場札所本尊の千手観世音菩薩は立像長五尺四寸で恵心作と伝わります。
本堂内には北条政子像も安置されています。
こちらは相州二十一ヶ所霊場第8番の札所で、御朱印も授与されています。
こちらの札所については小町の宝戒寺で書きますが、浄土宗でありながら弘法大師霊場の札所となっているのは、旧・長楽寺の開山・願行上人が真言宗醍醐派三宝院流であったことも関係しているかも。
このほか、本堂裏手にある(らしい)、尊観上人の墓で鎌倉最古と伝わる宝篋印塔(国重要文化財)、伝・北条政子の墓、尊観上人お手植えの槙の大木などのみどころがあります。


【写真 上(左)】 撮影禁止看板
【写真 下(右)】 山門から山内
5月のオオムラサキツツジが有名ですが、令和3年12月時点で山門内は撮影禁止となっています。
御朱印拝受時に理由をお伺いしたところ、カメラマンの振る舞いのあまりの酷さにたまりかねての処置とのこと。(当山は以前から三脚類使用禁止でした)
こちらは全国から巡拝者が訪れる坂東霊場札所。巡拝記念に撮影されたい向きも大勢いるのでは? と問い掛けたところ、申し訳なさそうに、たしかにその通りだが、山門外からの撮影は禁止していないのでそちらからの撮影を案内しているとのことでした。
とくに鎌倉の古寺では、にわか(?)カメラマンの傍若無人な撮影っぷりをよく目にしますが、そういうことを続けていくと撮影禁止のお寺さんがどんどん増えていきそうでとても残念です。
〔 御本尊・阿弥陀如来(六字御名号)の御朱印 〕

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕
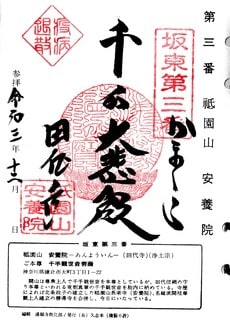
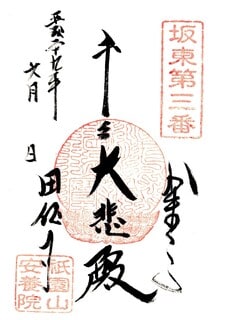
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
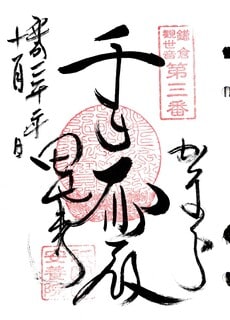

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
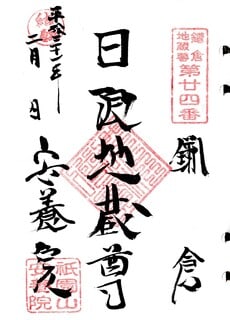

【写真 上(左)】 専用納経帳(結願御朱印)
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

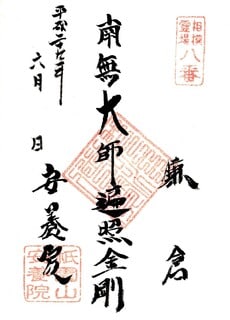
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ ハナミズキ [PV Version] - 新垣結衣
■ Yuna Ito - Endless Story
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
■ 鎌倉殿の御家人
■ 源頼朝公ゆかりの寺社
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
40.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院
〔北条政子〕
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
坂東三十三観音公式サイト
鎌倉市大町3-1-22
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第3番、鎌倉三十三観音霊場第3番、鎌倉二十四地蔵霊場第24番、相州二十一ヶ所霊場第8番、小田急沿線花の寺四季めぐり第17番
北条政子はおそらく、史上もっとも波乱の人生をおくった女性で、その生涯を追っていくとキリがないので、こちらWikipediaをご覧ください。
Wikipediaに「『吾妻鏡』では建保七年(1219年)の実朝死去から嘉禄元年(1225年)の政子死去まで、北条政子を鎌倉殿と扱っている。」とあるように、北条政子が本当の意味で幕政の表舞台に登場するのは、建保七年(1219年)正月の将軍・実朝公暗殺から三寅(後の藤原頼経)を4代目の鎌倉殿として迎え入れたのちだと思います。
北条氏独裁化の流れのなかで御家人内に仇敵も多い北条義時よりも、頼朝公とともに歩んだ政子の方が、御家人たちとしても担ぎやすかったのでは。
承久三年(1221年)、承久の乱の際に御家人に発した「故右大将(頼朝公)の恩は山よりも高く、海よりも深い、逆臣の讒言により不義の綸旨が下された。秀康、胤義(上皇の近臣)を討って、三代将軍(実朝公)の遺跡を全うせよ。ただし、院に参じたい者は直ちに申し出て参じるがよい」(Wikipediaより)は世紀の名演説としてよく知られています。
これも頼朝公や御家人たちと苦楽をともにしてきた政子だからこそ、語れる言葉なのかもしれません。
貞応三年(1224年)、北条義時の急死後に勃発した「伊賀氏の変」では政子の政治的手腕がかいま見られます。
この政変は義時の後妻(継室)・伊賀の方が、実子・政村の執権就任と、娘婿・一条実雅の将軍職就任を画策したもので、政村の烏帽子親である三浦義村の動きによっては北条政権をくつがえす大乱となる可能性がありました。
これを察した政子は先手を打って義時の長男・泰時を執権に就任させ、三浦義村に対して泰時への支持を確約させたといわれています。
義時なきあと、最大の実力者で権謀術数をめぐらす三浦義村を相手に渡り合い、泰時を執権職に就けたこと、また執権の座を逃した政村が、その後も泰時を支えつづけたことは並みの手腕ではないと思われます。(泰時の人望もあるとは思いますが)
嘉禄元年(1225年)泰時への代替わりを見届けたあと逝去。享年69。
戒名は安養院殿如実妙観大禅定尼。
墓所は鎌倉・扇ヶ谷の壽福寺にあります。


【写真 上(左)】 壽福寺
【写真 下(右)】 壽福寺の御朱印(御本尊)
ここでは、政子が頼朝公の冥福を祈るために建立した祇園山長楽寺を前身とし、政子の戒名を号した祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院をご紹介します。
安養院の由緒はすこぶる複雑で、3つの前身寺院の由緒を追わなければならないので、「鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)」の記事をそのまま持ってきます。
ながくなりますがご容赦ください。
------------------------
安養院は鎌倉・大町にある浄土宗の名刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第3番札所として広く知られています。
このお寺はすこぶる複雑な由緒をもたれます。
まずは山内由緒書から(抜粋)。
「建立 嘉禄元年(1225)、開山 願行上人、開基 北条政子」
「北条政子が夫・頼朝公の冥福を祈るために佐々目ガ谷に建立した祇園山長楽寺が前身。鎌倉末期に善導寺の跡(現在地)に移って安養院になったといいます。延宝八年(1680)に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかつて建立した田代寺の観音堂を移します。こうして『祇園山安養院田代寺』になりました。」
つぎに鎌倉市観光協会Webから(抜粋)。
「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり。のちに北条政子が夫・頼朝公の菩提のために笹目に建てた長楽寺が焼失したため、鎌倉末期にこの地に長楽寺を移し、政子の法名・安養院を号し、さらに江戸時代の始めに田代寺の千手観音を移した。」
以上より、長楽寺・善導寺・田代寺という3つの前身寺院が関係していることになります。
『鎌倉市史 社寺編』から以下抜粋引用します。
「もと律宗。昌譽の時浄土宗となったという。もと名越派の本山、延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により京都知恩院末となる。開山、願行房憲静。開基、北条氏政子。寺伝では嘉禄元年(1225年)、頼朝夫人政子が頼朝の菩提のため佐々目の長楽寺谷に律寺を建立。願行を開山としたという。『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう。延慶三年(1310年)十一月、失火あり鎌倉中の大火となった。(『武家年代記裏書』)寺伝には、高時滅亡の後、稲瀬川の辺から現在の地、善導寺の跡に移りそれ以降安養院と号したという。延寶八年(1680年)十月、門外町屋から失火、全焼した。再建の時比企ヶ谷にあった末寺、田代観音堂を境内に移した。」
ところが『新編鎌倉志』には「名越の入口、海道の北にあり。祇園山と号す。浄土宗、知恩院の末寺なり。此寺初め律宗にて、開山願行上人なり。其十五世昌譽和尚と云より浄土宗となる。昌譽より前住の牌は皆律宗なり。初長谷の前稲瀬川の邊に在しを、相模入道滅亡の後、此に移すと云伝ふ。本堂に阿彌陀坐像、客殿にも阿彌陀の坐像を安ず。共に安阿彌が作なり。」とあり、前身3寺の所縁は明示されていません。
そこで『新編相模國風土記稿』の安養院の項を当たってみました。
こちらには山内絵図とともに詳しい記述がありました。要点のみ抜粋引用します。
「古ハ笹目ヶ谷ニ在。祇園山長楽寺と号ス。浄土宗。昔ハ無木(本)寺ニテ。名越一派ノ本山ナリ。延寶四年(1676年)諸宗寺院本末御改ヨリ。京知恩院末に属ス。嘉禄元年(1225年)二位ノ禅尼。故頼朝菩提ノ為。笹目ヶ谷邊(西方長谷村界笹目ヶ谷ニ長楽寺谷ト云フアリ。是当寺ノ舊蹟ナリ)ニテ。七堂伽藍ヲ営ミ。律寺ヲ建立シテ。僧願行ヲ開山トシ。又●年七月二位禅尼逝去アリシカバ。願行導師トナリ当寺ニ葬送シ。法名ヲ安養院ト号スト云フ。後兵火ノ為ニ。堂宇残ラズ烏有トナリシカバ。当所善導廃寺蹟ニ移テ堂宇ヲ営ミ両寺を合シテ再建ス。鎌倉志ニ当寺初長谷ノ前。稲瀬川ノ邊ニ在シヲ。相模入道滅亡ノ後此ニ移スト云伝フ云々。是ニ拠バ正應二年(1289年)ノ兵火ナルベシ。又善導寺モ其頃退転セシナルベシ。寺伝ニ彼善導寺開山ハ記主禅師ノ法嗣尊観ナリ。某年名越一派ヲ立。爰ニ一宇ヲ建立シ正和五年(1316年)寂スト云フ。後年現住昌譽カ時。律宗ヲ改メ今ノ宗派トナルと云フ。天文十三年(1544年)北條氏直敷地ヲ寄附ス。延寶八年(1680年)失火シテ諸堂残ナク焼亡ス。其頃比企谷ノ内田代ニ観音堂アリ。当院の末ナリシヲ。当寺再建ノ時境内ニ移シ。夫ヨリ三ヶ寺合成ノ梵宇ト称ス。」
『新編相模國風土記稿』には本堂、観音堂についての記事もありました。
「本堂 本尊阿彌陀 安阿彌作安ス。堂中頼朝又二位禅尼ノ牌。地蔵堂。本尊ハ石像(弘法大師作ト云フ)ニテ。鎌倉二十四所ノ一ナリ。子安地蔵ト云フ。」
「観音堂。本尊千手観音ナリ。立像長五尺四寸恵心作。坂東三十三所ノ札所第三番ト云フ。昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像(立像ニテ長九寸許。天竺竜樹菩薩筆)ヲ籠メ。更ニ比企谷田代ノ地ニ堂舎ヲ造建シテ安置シ。白花山普門寺ト号セリ。土俗ハ多く田代寺又田代堂ナド称セリ。厨子ニ納テ内殿ニ安スト云フ。延寶八年(1680年)当寺焼亡ノ後此境内ニ移セシナリ。前立ニ同像ヲ置キ脇壇ニ阿彌陀ノ座像ヲ置ク。恵心作。是ハ二位禅尼ノ持念佛ト云フ。」
さらに、田代寺についてWikipediaから引いてきました。
「田代寺は1192年(建久3年)田代信綱が尊乗を開山として比企ヶ谷(ひきがやつ)に建立」(原典不明)
引用だらけですみません。
でも、これらの情報がなければ安養寺の由緒(というか3箇寺合一の経緯)がたどれません。
上記資料の青字の箇所が、(おそらく現在地にあった)旧・善導寺についての記述です。
長楽寺、善導寺と合寺後の由緒が混在しているので、すこぶるわかりにくくなっています。
まずは、開山関係から当たってみます。
■ 願行上人憲静(長楽寺)
鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧。
今後のこともあるので、『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同)から経歴・事績の要点を引いてみます。
願行上人憲静は、健保三年(1215年)出生、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。
〔法統・真言宗系統〕
・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)
・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)
・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)
三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。
真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。
これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。
〔法統・律宗系統〕
・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。
・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。
月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。
その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。
この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。
以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。
〔鎌倉での活動〕
願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏)には下記のとおりあります。
・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。
ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。
また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。
「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)
これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。
佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。
なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。
願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。


【写真 上(左)】 西方寺
【写真 下(右)】 西方寺の御朱印(御本尊)
「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)
佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。
Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。
同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。
また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。
『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。
『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。
さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。
なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。
二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。
■ 尊観上人良弁(善導寺)
鎌倉市Webの「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり」および、『鎌倉市史 社寺編』の「もと名越派の本山、『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう」から探ってみました。
「記主禅師」(良忠上人)は、光明寺ゆかりの高僧です。
「記主禅師」(良忠上人)とは、嘉禎三年(1237年)浄土宗第三祖となられた高僧で、多くの門下を育てられました。 文応元年(1260年)鎌倉へ入られ北条朝直の帰依のもと悟真寺に住され、これがのちに浄土宗大本山光明寺となりました。

■ 光明寺の開山 記主禅師の御朱印
光明寺は名越エリアにあるので「名越一派」は大本山光明寺の流れかと思いましたが、「浄土宗 名越派」で検索してみるとなんと一発でヒットしました。
浄土宗「WEB版新纂浄土宗大辞典」の「名越派」(なごえは)です。
(「鎮西流(鎮西派)」は知っていましたが、不勉強で「名越派」は知りませんでした。)
ここには「三祖然阿良忠門下六派の一つ。派祖は良弁尊観。名越流とも称される。また、尊観が相模国鎌倉名越谷善導寺で布教したため善導寺義ともいう。」とありました。
いわき市山崎の専称寺と栃木県益子町の円通寺が本山格であったようですが、江戸時代は増上寺の支配下にあり、大正以前に浄土宗として統一されているようです。
さらに尊観についても記載がありました。
「延応元年(1239年)—正和五年(1316年)三月一四日。鎌倉時代中期の僧。字(あざな)は良弁。名越派派祖。また鎌倉名越谷の善導寺で布教したため、後世尊観の流派を名越流もしくは善導寺義という。」
どんぴしゃです。これで決め打ちです。
「名越一派」は「浄土宗名越派」をさし、「善導寺」は尊観上人が「浄土宗名越派」の布教の拠点とした寺院です。
これで『新編相模國風土記稿』にあった「名越一派ノ本山ナリ」のナゾが解けたことになります。
■ 田代冠者信綱(普門寺・田代寺)
『新編相模國風土記稿』の安養院観音堂に「昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像」として登場し、普門寺(田代寺)の開基とみられます。
『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「田代観音堂 普門寺と号す。妙本寺の南東なり。安養院末、堂の額に白華山と有。本尊千手観音、坂東第三番の札所。此西の方を田代屋敷と唱ふ。田代冠者信綱が舊跡。今は畑なり。」
「田代冠者信綱」は、おそらくWikipediaに「伊豆国司と狩野茂光の娘の子。石橋山の戦いで頼朝公挙兵時の武士の一人。平家物語の三草山の合戦や一ノ谷の戦い及び屋島の戦いにも登場し。義経公挙兵時の武士ともなり源義仲を追討した。しかし義経公の門下となったと同時に頼朝公から破門の書状を受け(た)。」とある鎌倉幕府草創期の武士とみられます。
これで、ようやく安養院の前身3寺のプロフィールが揃いました。
ごちゃごちゃになったので(笑)、ここで整理してみます。
1.現在地(大町)には、もともと尊観上人(正和五年(1316年)寂)が開かれた浄土宗名越派の善導寺があった。
(正應二年(1289年)の頃(現在地に?)退転したという記録もあり。)
2.一方、長谷笹目ヶ谷には嘉禄元年(1225年)北条政子が夫・頼朝公菩提のために創建した祇園山長楽寺(律宗)があった。開山は二階堂の理智光寺を開いた願行上人憲静。
嘉禄元年(1225年)、二位禅尼(北条政子)逝去の際、願行上人が導師となって当寺に葬送し、法名を安養院と号したという。
また、建治二年(1275年)前後の説法念仏会の折、願行上人が稲瀬川あたり(長谷~由比ヶ浜)に安養院ないしその前身となる寺院(祇園山)を開山された可能性もある。
※ただし、願行上人の鎌倉下向は弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間とみられ、二位禅尼(北条政子)逝去の嘉禄元年(1225年)と時代が合いません。
長楽寺は当初長谷稲瀬川にあり、正應二年(1289年)の兵火を受け笹目に移転した可能性もあるので、願行上人がこれにかかわり、その際に安養院と号したのかもしれません。
3.比企ヶ谷田代には建久三年(1192年)、伊豆の武士田代冠者信綱が尊乗上人を開山に建立した白花山普門寺(田代寺)があり、千手観世音菩薩を御本尊としていた。
普門寺(田代寺)は善導寺ないし長楽寺の末寺であった。
4.笹目の長楽寺は元弘元年(1333年)の兵火で焼失、大町の善導寺に統合されて『安養院長楽寺』と号した。安養院は政子の法号にちなむもの。(*Wikipedia)
5.統合時の安養院は律宗だったが後に浄土宗となり、天文十三年(1544年)には後北条氏第5代北條氏直の寄進を受ける。江戸時代の延寶八年(1680年)失火により諸堂焼亡する。
6.比企ヶ谷の普門寺(田代寺・田代観音)も同年延寶八年(1680年)に焼亡、焼亡した安養院再建の折に比企ヶ谷から本寺であった安養寺の境内に移る。この時点で3つの寺院の合一が為る。
7.坂東三十三箇所の札所本尊の千手観世音菩薩は、比企ヶ谷の普門寺(田代寺)から遷られての御座。
8.延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により、京都知恩院末となる。
以上から安養院は、
1.浄土宗名越派の派祖・尊観上人が名越派の当初の本山とされた善導寺
2.北条政子が頼朝公菩提のために創建。開山願行上人の祇園山長楽寺(律宗)
3.伊豆国守の子、田代冠者信綱が自身の守り本尊・千手観音を奉安した普門寺(田代寺)
という3つの由緒ある寺院の合寺であることがわかりました。
---------------------
※ 令和3年12月時点で当山山内は撮影禁止となっています。
以下の写真は撮影禁止となる前に撮影したものです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 坂東札所標
県道311号大町大路に面して参道入口。
「坂東第三番田代観音」の札所標と「浄土宗名越派根本霊場」の石標。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 名越派根本霊場碑
石段の先に切妻屋根本瓦葺の四脚門で、門下の木箱に拝観料を納めます。
山門をくぐって右手の地蔵堂は鎌倉二十四地蔵霊場第24番の結願所で、札所本尊の日切地蔵尊が御座します。
坐像の石像で弘法大師の御作とも伝わり、子安地蔵ともよばれたそうです。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 鬼板と兎毛通
正面の本堂は権現造のような複雑な意匠で詳細不明。
向拝側の屋根に千鳥破風、向拝軒に唐破風の二重破風となっています。
軒下の水引虹梁両端に雲形の獅子木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いていますが全体にシンプルなイメージ
見上げには山号扁額。


【写真 上(左)】 山号扁額
【写真 下(右)】 堂内向拝
堂内の外陣には札所の御詠歌板などが掲げられています。
格子扉越しに御内陣が拝め、扉うえには院号扁額。
「坂東第三番」の札所だけに、さすがに風格があります。

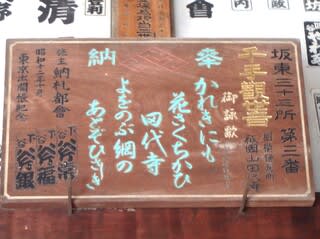
【写真 上(左)】 院号扁額
【写真 下(右)】 坂東霊場札所板
御本尊の阿弥陀如来は伝・安阿彌作。観音霊場札所本尊の千手観世音菩薩は立像長五尺四寸で恵心作と伝わります。
本堂内には北条政子像も安置されています。
こちらは相州二十一ヶ所霊場第8番の札所で、御朱印も授与されています。
こちらの札所については小町の宝戒寺で書きますが、浄土宗でありながら弘法大師霊場の札所となっているのは、旧・長楽寺の開山・願行上人が真言宗醍醐派三宝院流であったことも関係しているかも。
このほか、本堂裏手にある(らしい)、尊観上人の墓で鎌倉最古と伝わる宝篋印塔(国重要文化財)、伝・北条政子の墓、尊観上人お手植えの槙の大木などのみどころがあります。


【写真 上(左)】 撮影禁止看板
【写真 下(右)】 山門から山内
5月のオオムラサキツツジが有名ですが、令和3年12月時点で山門内は撮影禁止となっています。
御朱印拝受時に理由をお伺いしたところ、カメラマンの振る舞いのあまりの酷さにたまりかねての処置とのこと。(当山は以前から三脚類使用禁止でした)
こちらは全国から巡拝者が訪れる坂東霊場札所。巡拝記念に撮影されたい向きも大勢いるのでは? と問い掛けたところ、申し訳なさそうに、たしかにその通りだが、山門外からの撮影は禁止していないのでそちらからの撮影を案内しているとのことでした。
とくに鎌倉の古寺では、にわか(?)カメラマンの傍若無人な撮影っぷりをよく目にしますが、そういうことを続けていくと撮影禁止のお寺さんがどんどん増えていきそうでとても残念です。
〔 御本尊・阿弥陀如来(六字御名号)の御朱印 〕

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕
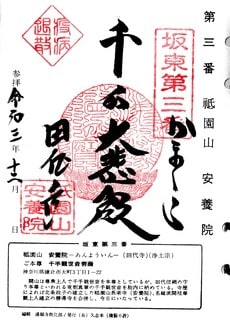
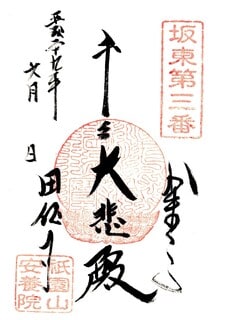
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
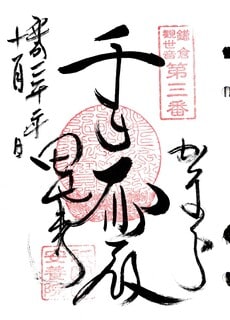

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
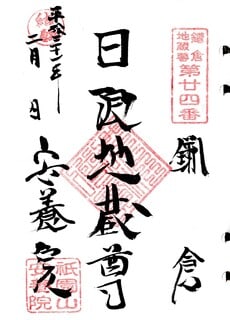

【写真 上(左)】 専用納経帳(結願御朱印)
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

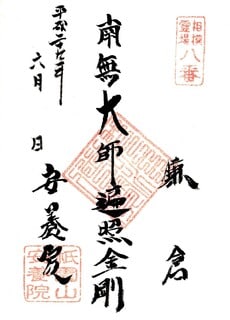
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ ハナミズキ [PV Version] - 新垣結衣
■ Yuna Ito - Endless Story
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、始まりました。
今回も東日本、とくに伊豆と鎌倉がメイン舞台なので、関連する御朱印を随時ご紹介していきます。
最新記事→ ■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
1.伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印
伊豆は北条(北條)氏の本拠地で、この霊場には北条氏や源頼朝公ゆかりの寺院がいくつかあります。
2.鎌倉市の御朱印
鎌倉市内でいただける御朱印・御首題は、おそらくほとんど拝受したと思うので、こちらについても随時UPしていきます。
→ ■ 鎌倉市の御朱印
3.「鎌倉殿の御家人」ゆかりの御朱印
「13人」とは、足立遠元、安達盛長、大江広元、梶原景時、中原親能、二階堂行政、八田知家、比企能員、北条時政、北条義時、三善康信、三浦義澄、和田義盛を指すそうです。
当初は「こちらの豪族ゆかりの寺社の御朱印も適宜ご紹介していきます。」と書きましたが、文官が多く意外にゆかりの寺院が少ないので、「鎌倉殿の御家人」とされている人物ゆかりの寺社についてもまとめてみます。
〔関連記事〕 → ■ 鎌倉殿の御家人
なお、頼朝公、北条政子とのゆかりがふかい伊豆山神社・伊豆山温泉については、→ こちら(〔 温泉地巡り 〕 伊豆山温泉)に書いています。
令和3年7月伊豆山土砂災害からの一日も早い復旧をお祈りいたします。
とりあえずランダムにUPし、あとでエリア別にまとめます。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
01.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮)
鎌倉市材木座
〔源頼朝公〕
02.巨徳山 北條寺
静岡県伊豆の国市
〔北條義時〕
03.(西御門)白旗神社
鎌倉市西御門
〔源頼朝公〕
04.天守君山 願成就院
静岡県伊豆の国市
〔北條時政〕
05.甘縄神明宮
鎌倉市長谷
〔源氏・安達盛長〕
06.清月山 元光院 金剛寺
埼玉県川島町
〔比企能員〕
07.慧日山 薬王院 寳泉寺
渋谷区東
〔常盤御前・源義経公〕
08.鷲峰山 覚園寺
鎌倉市二階堂
〔北条(北條)義時〕
09.高橋山 放光寺
山梨県甲州市
〔安田義定〕
10.粟船山 常楽寺
鎌倉市大船
〔北条(北條)泰時〕
11.萬年山 城願寺
神奈川県湯河原町
〔土肥實平〕
12.岩殿山 光明院 安楽寺
埼玉県吉見町
〔源範頼公〕
13.医王山 清光寺
北区豊島
〔豊島清元(清光)〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
14.稲荷山 東林寺
静岡県伊東市
〔工藤氏・伊東氏・曾我氏〕
15.葛見神社
静岡県伊東市
〔伊東氏〕
16.飯室山 大福寺
山梨県中央市
〔浅利冠者義遠(義成)〕
17.金色山 吉祥院 大悲願寺
東京都あきる野市
〔平山左衛門尉季重〕
18.古尾谷八幡神社/寳聚山 東漸寺 灌頂院
埼玉県川越市
〔源頼朝公・古尾谷氏〕
19.超越山 来迎院 西光寺
葛飾区四つ木
〔葛西三郎清重〕
20.龍ヶ崎鎮守 八坂神社
茨城県龍ヶ崎市
〔下河辺氏・下河辺四郎政義〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
21.冷水山 清浄土院 長徳寺
埼玉県川越市
〔仙波氏〕
22.阿毘盧山 密乗院 大日寺
千葉県千葉市稲毛区
〔千葉介常胤〕
23.和田(義盛)神社
静岡県富士市
〔和田太郎義盛〕
24.(羽根倉)浅間神社
埼玉県志木市
〔金子小太郎高範〕
25.瑠璃光山 薬師院 玉井寺
埼玉県熊谷市
〔玉井四郎資重/玉井氏〕
26.如意山 観音院 大輪寺
茨城県結城市
〔(小山七郎)結城朝光〕
27.宝林山 称念寺
静岡県河津町
〔河津三郎祐泰〕
28.慈眼山 無量院 萬福寺
大田区南馬込
〔梶原平三景時〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
28.慈眼山 無量院 萬福寺(つづき)
大田区南馬込
〔梶原平三景時〕
29.永劫山 華林院 慶元寺
世田谷区喜多見
〔江戸太郎重長〕
30.龍智山 毘廬遮那寺 常光院
埼玉県熊谷市
〔中条藤次家長〕
31.礒明山 松岸寺
群馬県安中市
〔佐々木三郎盛綱〕
32.勅使山 大光寺
埼玉県上里町
〔勅使河原三郎有直〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
33.金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺
栃木県足利市
〔足利上総介義兼〕
34.多福山 一乗院 大寳寺
鎌倉市大町
〔佐竹四郎秀義〕
35.萬徳山(梅田山) 梅林寺 明王院
足立区梅田
〔志田三郎先生義広〕
36.白山 東光寺
〔畠山次郎重忠〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
37.岩浦山 福寿寺
神奈川県三浦市
〔三浦平六義村〕
38.筑波山神社
茨城県つくば市
〔八田右衛門尉知家、八田太郎知重〕
39.大聖山 金剛寺
神奈川県秦野市
〔源実朝公〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
40.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院
鎌倉市大町
〔北条政子〕
■ 源頼朝公ゆかりの寺社
1.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮) 〔源頼朝公〕
神奈川県鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇、神功皇后、比売神
康平六年(1063年)源頼義公が、前九年の役で奥州を鎮定され京に帰る帰途、鎌倉に立ち寄られこの地に源氏の守り神である京の石清水八幡宮の御祭神を勧請されて創祀と伝わります。
後に源頼朝公が現在の鶴岡八幡宮の地(小林郷北山)に社殿を遷してからは、「元八幡」とも呼ばれるようになりました。
鶴岡八幡宮には、由比若宮遥拝所があります。


【写真 上(左)】 由比若宮の社頭
【写真 下(右)】 由比若宮の拝殿

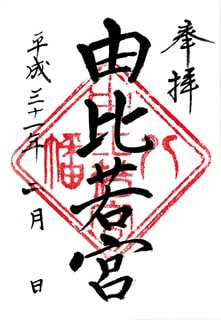
【写真 上(左)】 由比若宮遙拝所(鶴岡八幡宮境内)
【写真 下(右)】 由比若宮の御朱印
2.巨徳山 北條寺 〔北條義時〕
静岡県伊豆の国市南江間862-1
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第13番、伊豆中道三十三観音霊場第16番、駿豆両国横道三十三観音霊場第8番、中伊豆観音札所第20番
源頼朝公の正室・北條政子の弟である北條義時(江間小四郎)が創建した寺院です。
義時の嫡子安千代が領内の大池で大蛇に襲われ命を落とした際に、この北條寺を墓所とし七堂伽藍を建立し、運慶に仏像を作らせたといいます。
御本尊の聖観世音菩薩は南北朝期の作とされ中国宋風の像容で県文化財に指定されています。鎌倉極楽寺にあったものを北条政子が北條寺に奉納したとも伝わります。
境内の「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、義時夫妻の墓所があります。


【写真 上(左)】 北條寺の山門
【写真 下(右)】 北條寺の本堂
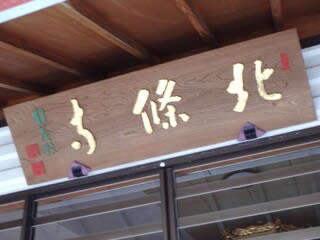
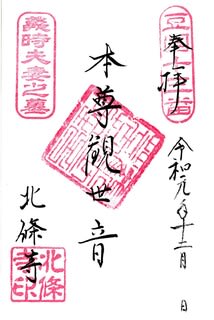
【写真 上(左)】 北條寺本堂の扁額
【写真 下(右)】 北條寺の御朱印(伊豆八十八ヶ所霊場)
3.(西御門)白旗神社 〔源頼朝公〕
神奈川県鎌倉市西御門2-1-24
御祭神:源頼朝公
現在の源頼朝公墓所にあった法華堂がこの地に移され、江戸期まで鶴岡八幡宮二十五坊の一つ相承院が別当を勤めていましたが、明治の神仏分離令により白旗神社に改められたとされます。
源頼朝公墓所の尾根つづきに北条義時法華堂跡があり、こちらは『吾妻鏡』に「頼朝の法華堂の東の山をもって墳墓となす」と記された地とみられています。
北条義時法華堂跡の山上に、大江広元の墓所があります。

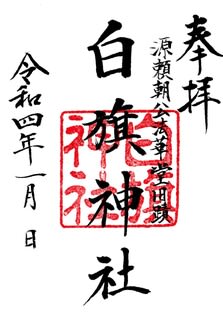
【写真 上(左)】 (西御門)白旗神社
【写真 下(右)】 (西御門)白旗神社の御朱印


【写真 上(左)】 北条義時法華堂跡
【写真 下(右)】 大江広元の墓所
4.天守君山 願成就院 〔北條時政〕
静岡県伊豆の国市寺家83-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆中道三十三観音霊場第18番、中伊豆観音札所第18番
文治五年(1189年)、源頼朝公の奥州藤原氏征討の戦勝を祈願して北條時政公が建立したと伝わる中伊豆の名刹。
時政公建立の大御堂と南塔、二代執権北條義時公建立の南新御堂、三代執権北條泰時公建立の北條御堂と北塔など、北條氏三代にわたり伽藍が整えられました。
御本尊、阿弥陀如来をはじめとする大御堂安置の五仏は、数少ない運慶の真作として国宝に指定されています。


【写真 上(左)】 願成就院
【写真 下(右)】 御本尊阿弥陀如来の御朱印
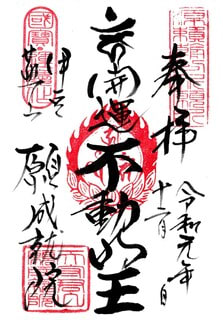

【写真 上(左)】 不動明王の御朱印
【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印
5.甘縄神明宮 〔源氏・安達盛長〕
神奈川県鎌倉市長谷1ー12ー1
主祭神:天照大神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:甘縄院(臨済宗)
和銅三年(710年)行基の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社ともいわれます。
永保元年(1081年)源義家公が社殿を再建、以降も源頼朝公、政子の方、源実朝公などの崇敬が篤かったと伝わります。
また、源頼義公が相模守として下向の折に当宮に祈願し、八幡太郎義家公が生まれたとも伝えられ、源氏とつよい所縁をもちます。
社殿がある場所は安達盛長の屋敷跡とされています。


【写真 上(左)】 甘縄神明宮
【写真 下(右)】 甘縄神明宮の御朱印
6.清月山 元光院 金剛寺 〔比企能員〕
「鎌倉殿を支えた武士の故郷 比企の史跡マップ」(PDF/川島町Web)
埼玉県川島町中山1198
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州八十八霊場第55番
比企能員は、息女・若狭局を二代将軍頼家公に嫁がせ、その子一幡が生まれてからは北条一門と対立して権勢を誇っていたものとみられています。
建仁二年(1203年)9月、比企氏の乱で北条方に破れ、比企能員は一族郎党とともに討死したと伝わります。
比企能員の舘は、埼玉県東松山市大谷付近にあったとされています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
比企能員の墓所は鎌倉の妙本寺にありますが、比企氏の末裔が天正(1573-1592年)の頃より当地一帯を舘とし比企左馬助則員が中興、金剛寺は比企氏の菩提寺となり比企氏歴代の墓所となっています。
山門と比企氏の位牌堂である金剛寺大日堂は、国の登録有形文化財に指定されています。
川島町Webによると、「比企地域9市町村(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、鳩山町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)と比企地域の各種関係団体は、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放映を契機として地域の活性化につなげようと、令和2年(2020年)12月に『大河ドラマ「鎌倉殿の13人」比企市町村推進協議会』を立ち上げ、大河ドラマが放映される令和4年(2022年)に向けてさまざまな取組を行っていきます。」とのことです。


【写真 上(左)】 大日堂
【写真 下(右)】 御朱印
7.慧日山 薬王院 寳泉寺 〔常盤御前・源義経公〕
天台宗東京教区Web
東京都渋谷区東2-6-16
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東九十一薬師霊場第12番、江戸西方三十三観音霊場第31番、弁財天百社参り番外6
渋谷と恵比寿の中間辺りに位置する都会のお寺さまで、御朱印で有名な氷川神社のすぐそばです。
御本尊は阿弥陀如来。平安中期から鎌倉の作とされる薬師如来像は、源義朝公の側室で義経公の母、常盤御前の守り佛(持彿)と伝わり「常盤薬師」としてふるくから信仰を集めています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
このあたりはかつて「常磐松町」といいましたが、その由来となった松の古木は常盤御前が植えたという言い伝えがあるそうです。
このような都会の真ん中に常盤御前ゆかりの寺院があるとはちょっと驚きです。
「常盤薬師」は関東九十一薬師霊場第12番の札所本尊で、御朱印が授与されています。


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 「常盤薬師」の御朱印
8.鷲峰山 覚園寺 〔北条(北條)義時〕
公式Web
神奈川県鎌倉市二階堂421
真言宗泉涌寺派
御本尊:薬師如来
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第13番(阿閃如来)
建保六年(1218年)、薬師如来の眷属・十二神将のうちの「戌神」(伐折羅大将)が北条義時の夢に現れ、これを受けて義時が建立した大倉薬師堂が覚園寺の草創とされます。
永仁四年(1296年)、九代執権北条貞時は外敵退散を祈念して、大倉薬師堂を正式の寺に改めた(覚園寺の創建)といいます
開基は北条貞時、開山は京・泉涌寺の智海心慧律師とされます。

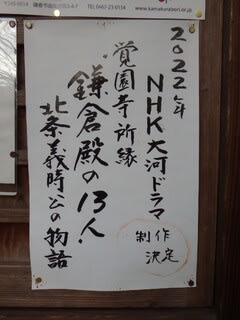
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 大河ドラマ関連の掲示
現在は真言宗泉涌寺派となっていますが、当初は北京系律の本拠地で、律を中心に天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学の道場であったと伝わります。
元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が勅願寺とされ、足利氏も祈願所として保護した名刹です。
なお、入口正面の愛染堂と諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
御本尊、薬師如来のほか、3種の札所の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御本尊の御朱印
※ その他の御朱印は■ 鎌倉市の御朱印でご紹介しています。
9.高橋山 放光寺 〔安田義定〕
公式Web
山梨県甲州市藤木2438
真言宗智山派
御本尊:金剛界大日如来
札所:甲斐百八霊場第8番、甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)
「鎌倉殿の13人」には何度か甲斐源氏の武田信義が登場していますが、平家追討のなかで大きな役割を担った甲斐源氏のひとりに安田義定がいます。
安田義定は、甲斐源氏の祖とされる源義光(新羅三郎)公の孫源清光公の子(清光の父義清の子説もあり)という名流で、現在の山梨市を中心とした峡東一帯に勢力を張りました。
平家追討の令旨に応じて挙兵し、「富士川の戦い」などでの戦功により遠江国守護に任じられました。(『吾妻鏡』)
寿永二年(1183年)、平家追討使として東海道から上洛。大内裏守護として京中を守護し、同年8月には従五位下遠江守に叙任。
「宇治川の戦い」、「一ノ谷の戦い」と歴戦。とくに「一ノ谷の戦い」では、義経の搦め手軍を率いて奮戦、平経正、平師盛、平教経を討ち取ったと伝わります。
放光寺の公式Webには、『吾妻鏡』による平家追討軍の編成は「大手の大将範頼軍には武田有義、小山朝政、下河辺行平、千葉常胤、梶原景時ほか五万六千余騎、搦手の大将義経軍には安田義定、大内惟義、土肥宗平、三浦義連、熊谷直実以下二万余騎とあり」とし、「甲斐源氏の中では安田義定と武田有義が副大将として活躍」とあります。
また、建久二年(1191年)の鶴岡八幡宮法会では、頼朝公御供の筆頭に義定の名がみられ、頼朝公配下のなかでもすこぶる高い地位を占めていたことがわかります。
建久四年(1193年)、義定の子、安田義資が罪を得て斬られ、義定の所領も没収。
翌建久五年(1194年)には義定みずからが謀反の疑いをうけ、放光寺にて自刃と伝わります。

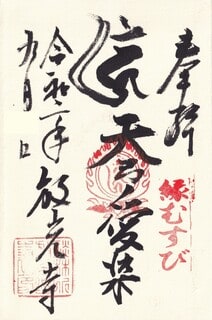
【写真 上(左)】 放光寺本堂
【写真 下(右)】 天弓愛染明王の御朱印
この当時の甲斐源氏には、武田信義、安田義定、一条忠頼らの有力武将がおり、「富士川の戦い」の主力は甲斐源氏であったともみられています。
しかし、安田義定は謀反の疑いで自刃、一条忠頼も鎌倉にて酒宴の最中に暗殺、武田信義の子逸見有義は頼朝公から疎まれ、同じく信義の子板垣兼信は違勅の罪を問われて配流されるなど、次々と失脚していきました。
また、小笠原長清の兄の秋山光朝は京で平重盛に仕え重盛の息女を娶ったため、甲斐国内の本拠地を頼朝公に攻められ自害したと伝わります。
当時の甲斐源氏は頼朝公も御せないほどの強大な勢力があり、武家の頭領としての地位を確立するために、頼朝公が甲斐源氏の力を削いでいったという見方が有力です。
頼朝公は八幡太郎義家公の流れ、甲斐源氏は新羅三郎義光公の流れで、たしかに嫡流系は頼朝公ですが、それをいえば源満仲公の長子は源頼光公で、その流れの多田源氏、摂津源氏などが清和源氏の嫡流筋にあたります。
しかし多田源氏の多田行綱は勢力を張れず没落、摂津源氏の土岐光衡も鎌倉殿の御家人に収まっているので、やはり武家の統領としての八幡太郎義家公とその流れの頼朝公の声望が高かったものとみられます。
以降、甲斐源氏では武田氏宗家となった信光の流れと信義の弟加賀美遠光から小笠原氏、南部氏が出て、以降勢力を張りました。
小笠原氏、南部氏は江戸時代も大名家として存続しています。(大和郡山藩の柳沢氏、新発田藩主の溝口氏、松前藩主の松前(蠣崎)氏なども甲斐源氏の末裔を称しています。)
放光寺は元暦元年(1184年)、安田義定が「一ノ谷の戦い」の戦勝を記念して創立したと伝わる、甲斐を代表する名刹です。
詳細およびその他の御朱印は■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印をご覧ください。
10.粟船山 常楽寺 〔北条(北條)泰時〕
鎌倉市観光協会Web
神奈川県鎌倉市大船5-8-29
臨済宗建長寺派
御本尊:阿弥陀三尊
札所:-
北条義時の子で、名君として知られる三代執権北条泰時の創建とされる名刹です。
鎌倉市には、鎌倉七口(八口)の外のエリアにも高い格式を誇る名刹がいくつかあって、こちらもそのひとつです。
嘉禎三年(1237年)、北条泰時が義母の供養のために建てた「粟船御堂」(あわふねみどう)が草創とされ、常楽寺の寺号は泰時の法名にちなむものとされます。
開山は退耕行勇、開基は北条泰時。
建長寺開山の蘭渓道隆が建長寺の建立まで当寺に住待され、「常楽は建長の根本なり」といわれて、臨済宗建長寺派において高い格式をもちます。
仏殿には蘭渓道隆像が安置されています。

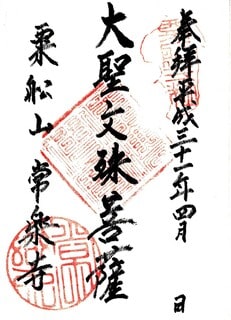
【写真 上(左)】 常楽寺
【写真 下(右)】 常楽寺の御朱印
仏殿は、元禄四年(1691年)建立の小形禅宗様で県指定重要文化財、鎌倉期作とされる木造文殊菩薩坐像も県指定重要文化財。
御本尊の阿弥陀如来像、山門は市の指定文化財。梵鐘は建長寺・円覚寺の梵鐘とともに「鎌倉三名鐘」に数えられ、国の重要文化財に指定されるなど文化財の宝庫です。
仏殿背後には北条泰時の墓があり、裏山には清水冠者(木曽義高)の墓と伝わる塚「木曽塚」があります。
清水冠者は木曽義仲の子で、源頼朝公の長女・大姫の婿の名目で鎌倉に入りましたが、父・義仲が粟津の戦いで討たれたのちは微妙な立場となり、鎌倉を脱出したところを入間河原であえなく討たれました。没年12歳と伝わります。
御朱印は、御本尊の阿弥陀三尊ではなく、蘭渓道隆ゆかりとされる文殊菩薩のものが授与されています。
11.萬年山 城願寺 〔土肥實平〕
公式Web
神奈川県湯河原町城堀252
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:-
土肥氏は、相模国の有力豪族中村氏の流れで桓武平氏良文流。足下郡・土肥郷(早川庄)(現在の湯河原、真鶴、早川周辺)を本拠として勢力を張りました。
鎌倉幕府草創期の当主は土肥實平で、東国武士のあいだで人望があり、『曽我物語』で有名な伊豆奥野の狩場での河津祐泰と俣野景久のいさかいの際に、仲裁に入ったと伝わります。
治承四年(1180年)、頼朝公挙兵の際には嫡子遠平をはじめ中村一族を率いて参じ、石橋山の敗戦から安房落ちの際にも頼朝公につき従ったとされます。
以降も一貫して頼朝公を支えて公の信任篤く、奥州から参陣した義経公を取り次ぎ、平家方から頼朝公に降った梶原景時をとりなしたのも實平という説があります。
養和元年(1181年)の鶴岡八幡宮の造営にあたっては奉行をつとめています。
源平合戦では宇治川の戦い、大江山守護、一ノ谷の戦い、壇ノ浦の戦いと歴戦し、一ノ谷の戦いののちには吉備三国(備前・備中・備後)の惣追捕使(のちに長門・周防を加える)に補任と伝わります。
建久元年(1190年)の頼朝公上洛の際には、右近衛大将拝賀の随兵7人の内に選ばれ、公側近の重職の地位を占めていたことがわかります。
以降子孫は繁栄し、相模土肥氏の祖とされています。
なお、戦国期「毛利両川」の小早川氏は、實平の子・遠平が土肥郷の小早川に拠り小早川を称し、平家討伐の恩賞として安芸国沼田荘の地頭職を拝領して土着、以降この地で勢力を伸ばしたものとされています。
實平の居舘は城願寺のあたりとされ、寺伝(城願寺公式Web)には「實平が、萬年の世までも家運が栄えるように「萬年山」と号して持仏堂を整えたことから城願寺の歴史は始まる。」とあります。
草創は實平。以来、城願寺は土肥一族の菩提寺となっています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
もともとは密寺でしたが臨済宗に改め萬年山成願寺として勧請開山、五山十刹につぐ諸山に定められ、戦国期の再興(重興開山)で曹洞宗に改め、城願寺と号して現在に至ります。
湯河原と土肥一族とのゆかりは深く、毎年春には「土肥祭」が催され、城願寺でも式典が催されます。
御本尊は聖観世音菩薩。
公式Webには「寺院が禅宗に改宗する場合には、以前の本尊をそのまま受け継いでも構わないとされることも多く、或いは創建時そのままの御本尊様かもしれません。」とあります。
このような例は、伊豆の寺院にとくに多くみられます。→■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印


【写真 上(左)】 七騎堂
【写真 下(右)】 城願寺の御朱印
土肥実平・遠平像(湯河原町指定文化財)を所蔵し、實平をはじめとする土肥一族の墓所や、石橋山の戦いで頼朝公とともに落ちのびた七騎を祀る七騎堂があります。
ちなみに、「七騎」とは、源頼朝公、土肥實平、安達盛長、土屋宗遠、岡崎義実、田代信綱、新開忠氏をさすようです。(→出典:『観光かながわNOW』)
→ 境内360度画像(公式Web)
湯河原の高台にあり、落ち着いたたたずまい。
實平手植えと伝わるビャクシンは樹齢800年を越え、国の天然記念物に指定されています。
御朱印は御本尊の聖観世音菩薩(観自在菩薩)のものが授与されています。
→ ■ 湯河原温泉「中屋旅館」の入湯レポ
→ ■ 湯河原温泉「若草荘」の入湯レポ
12.岩殿山 光明院 安楽寺 〔源範頼公〕
公式Web
埼玉県吉見町御所374
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第11番、関東八十八箇所第75番、武州路十二支霊場(申・金剛界大日如来)、東国花の寺百ヶ寺霊場第17番、中武蔵七十二薬師霊場第62番、武州八十八霊場第36番
源範頼公は源義朝公の子(六男と伝わる)で、頼朝公の異母弟、義経公の異母兄です。
『尊卑分脈』では生母は遠江国池田宿の遊女とされていますが、池田宿周辺の然るべき家の娘という説もあります。
江国蒲御厨(現在の浜松市)で生まれ育ったため、蒲冠者(かばのかじゃ)、蒲殿(かばどの)とも称されました。
後白河法皇の近臣、従二位・式部権少輔藤原範季に養育され、その縁から「範頼」を名乗ったとされます。
兄・頼朝公への合流時期は明確ではないようで、当初は安田義定など甲斐源氏との交流が深かったとの見方もあります。
また、寿永二年(1183年)、常陸国の志田義広と下野国の小山氏の野木宮合戦に参戦の記録が残っています。
寿永三年(1184年)、頼朝公の代官として源義仲追討の大将軍となり上洛、義経公の軍勢に合流して宇治・瀬田の戦いに参戦。
以降、平家追討の大手軍の大将として一ノ谷の戦い、九州進軍の率将としても勝利し、以降も義経軍と別働しつつ大手軍の大将として諸戦を戦い、壇ノ浦で平氏追討を成しました。
義経公の活躍があまりに華々しいため脇役に回っているきらいもありますが、大手軍の大将として個性の強い鎌倉武士をまとめ、戦を勝利に導いた手腕を評価する見方も少なくありません。
義経軍の進軍にくらべ範頼軍の動きが遅かったことは事実のようで、これをもって範頼公を凡将とみなす説もありますが、中世、華々しい戦さぶりを展開したのはたいてい動きの軽い別働隊や搦手軍で、これをもって範頼公を凡将とすることに疑問を呈する向きもあります。
また、大手の範頼軍の安定した働きあればこそ、搦手の義経軍の奇襲が奏功したという見方もあります。
独断専行が目立った義経公に対し、頼朝公への報告を怠らなかった範頼公は平家追討後も鎌倉での立場を保ち、文治五年(1189年)の奥州合戦には頼朝公に従い参戦。建久元年(1190年)11月にも頼朝公に従い上洛しています。
しかし、その後次第に頼朝公との関係は微妙なものとなり、建久四年(1193年)8月、範頼公は頼朝公に対して忠誠を誓う起請文を差し出すものの、頼朝公は状中で「源範頼」と源姓を名乗った事を過分として責め、範頼公は伊豆国に流され、修禅寺に幽閉されました。
その後の消息については不明とする説が有力です。
範頼公は頼朝公に対して公然と反旗を翻したわけでもなく、「源範頼」を名乗る資格も名分もある筈です。
にもかかわらずの伊豆への配流は、独裁色をつよめる頼朝公にとって異母兄弟の存在じたいが危険なものとして映った結果かもしれません。
実際、頼朝公の実弟で源平合戦の功労者でもある範頼公でさえ、対応を誤ればたちまち立場を失うという事実は、鎌倉御家人たちを震え上がらせたものと思われます。
範頼公の配流は、あるいはこのような効果を狙っての政治的な動きだったのかもしれません。
範頼公の墓所は伊豆・修善寺にあります。
伊豆配流後の範頼公の消息が不明なため、範頼公にはいくつかの配流伝説が残りますが、範頼公ゆかりの寺院は多くはありません。


【写真 上(左)】 安楽寺参道と山門内湯
【写真 下(右)】 範頼公旧跡を示す寺号標
吉見の吉見観音・安楽寺は、範頼公とのゆかりが明示されている貴重な例のひとつです。
武蔵国横見郡(現埼玉県吉見町)の吉見観音への隠住説は範頼公配流伝説のひとつで、吉見観音周辺の大字”御所”は貴人の居住地をあらわし、範頼公にちなむものと伝わります。
これとは別に、吉見は範頼公の妻の祖母で、頼朝公の乳母でもある比企尼の居所に近いので、この縁により移り住み、その子孫は吉見氏として続いたという説もあります。
範頼公の妻は安達盛長の息女で、頼朝公の乳母を務めた比企尼の長女丹後内侍の子です。
安達盛長の館は吉見にもほど近い現・鴻巣市糠田とされていますから、安達盛長の壻となった縁で吉見に所領を得たのかもしれません。
範頼公の次男範圓と三男源昭は外曾祖母の比企尼から吉見庄を分与され、範圓の子為頼が吉見を名字とした、という説もあります。


【写真 上(左)】 安楽寺山内
【写真 下(右)】 「比企一族と武蔵武士ゆかりの地」のポスター
安楽寺の公式Webには「平安時代の末期には、源頼朝の弟範頼がその幼少期に身を隠していたと伝えられ、安楽寺の東約500メートルには『伝範頼館跡』と呼ばれる息障院がある。この息障院と安楽寺は、かつては一つの大寺院を形成していたことが知られている。」とあり、吉見御所への範頼公の居住は配流後ではなく、幼少期であるとしています。
範頼公が『吾妻鏡』に登場するのは30歳すこし前で、それ以前、とくに幼少期ははっきりしないことが多いので、幼少期吉見居住説が出てくるのだと思います。


【写真 上(左)】 息障院山門
【写真 下(右)】 息障院本堂
吉見の名刹・息障院は「伝範頼館跡」とされ、吉見町の公式Webには「息障院がある一帯が、源範頼の居館跡と伝えられている。源範頼は頼朝の弟で平治の乱後、岩殿山に逃げ比企氏の庇護によって成長した。頼朝が鎌倉で勢力を得た後も吉見に住んでいたと思われ、館を中心とするこの地を御所と呼ぶようになったと言われている。」とあります。


【写真 上(左)】 安楽寺本堂向拝
【写真 下(右)】 安楽寺本堂扁額
比企市町村推進協議会企画の「鎌倉殿の13人」資料には、「息障院と安楽寺はかつては一つの大寺院を形成していたことが知られています。当時、息障院には多くの御堂がありましたが、その一つの観音堂が現在の安楽寺になったと伝わります。」とあります。
なお、安楽寺、息障院ともに創建・開基は天平年中(730年頃)の行基菩薩、あるいは大同元年(806年)の坂上田村麻呂と伝わり、鎌倉幕府草創のはるか以前です。
範頼公の記事だけで長くなりましたので、安楽寺山内のご案内は省略です。
メジャーな坂東霊場の札所、パワスポとしても知られており関連情報はWeb上でたくさんみつかるので、そちらをご覧ください。(と逃げる・・・(笑))
山門下の寺号標側面には「蒲冠者 源 範頼 旧蹟」と刻まれています。
また、山内の三重塔の説明書には「鎌倉時代に源範頼は十六丈の三重大塔と二十五間四面の大講堂を建立し、非常に壮大であったと伝えられております。しかし天文年間に松山城の落城に際してこれらの大伽藍もことごとく焼失いたしました。」とあります。


【写真 上(左)】 三重塔
【写真 下(右)】 御開帳時の薬師堂
安楽寺は複数の現役霊場の札所を兼ねられ、数種の御朱印が授与されています。
うち、中武蔵七十二薬師霊場第62番の御朱印は、12年に一度の寅年御開帳時(本年令和4年4月7日~13日)のみの授与とみられます。


【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 関東八十八箇所の御朱印
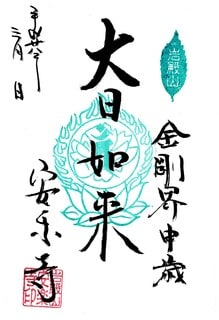
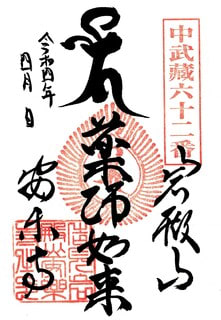
【写真 上(左)】 武州路十二支霊場(申・金剛界大日如来)の御朱印
【写真 下(右)】 中武蔵七十二薬師霊場の御朱印

東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
13.医王山 清光寺 〔豊島清元(清光)〕
東京都北区豊島7-31-7
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
他札所:豊島八十八ヶ所第79番、荒川辺八十八ヶ所霊場第18番、豊島七佛第1番(不動明王)、第2番(釈迦如来)
豊島氏は武蔵国の名族で、桓武平氏の平良文の孫の平(秩父)将常の次男秩父武常が治安三年(1023年)の戦功により武蔵国豊島郡を賜り、豊島氏を称したことにはじまるとされます。
いわゆる「坂東八平氏」の流れです。
発祥は現在の北区豊島、平塚神社が豊島舘跡と伝わります。
鎌倉幕府草創期の当主は豊島清元(清光とも、以下清光と記します)で、子の清重とともに隅田川で頼朝軍に参陣し、御家人の列に加わりました。
清光の三男清重は葛西御厨を継いで葛西氏の祖となり、清重は平家追討で範頼軍に加わり九州で武功をあげています。
有経が豊島氏を継ぎ紀伊守護人に任ぜられ、子(?)の朝経は土佐守護に任じられて各地で勢力を張りました。
豊島武常は源頼義公・義家公に従って奥州で戦死しており、累代の源氏の家人の立ち位置で、豊島清光に対する頼朝公の信頼は厚かったとされます。
豊島舘跡とされる平塚神社の御祭神は源義家公、義綱公、義光公。
後三年の役の帰路、源義家公、義綱公、義光公の三兄弟がこの豊島館に逗留して豊島近義にもてなしを受け、義家公は鎧一領と十一面観音像を豊島氏に下賜され、後にこの鎧を本尊として塚を築き埋めたのが創祀とも伝わります。
豊島一族と源氏のつながりの深さを伝える由緒といえましょう。
豊島清光は行基菩薩ゆかりのふたつの霊場に深い関係をもち、武蔵国の仏教(霊場)を語るうえで重要な役柄です。
行基菩薩は奈良時代の人、豊島清光は鎌倉幕府草創期の人でそもそも時代が合いませんが、とにかくそういうことになっています。
1.豊島七佛
清光が、行基菩薩の東国布教の際に彫ってもらった七体の仏像が安置される寺院を巡る霊場。
2.江戸六阿弥陀
行基作の阿弥陀佛を巡る江戸時代の代表的な女人霊場。霊場縁起に「豊島左衛門尉清光」が登場します。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~
清光の二男清康ないし娘は荒川で命を落としており、その供養のためにいくつかの寺院の開創にかかわっている可能性があります。
江戸六阿弥陀第1番の西福寺は豊嶋左衛門清光の創建とされ、『新編武蔵風土記稿』には「豊嶋左衛門清光、(略)一人の女子を産す、(略)彼女私に逃れ荒川に身を投て死す、父清光悲に堪す是より佛教に心を委ねしか(以下略)」との記載があります。

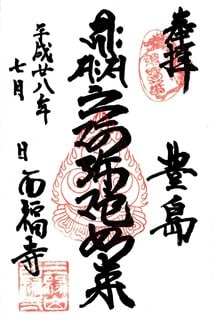
【写真 上(左)】 平塚神社の御朱印
【写真 下(右)】 西福寺の江戸六阿弥陀如来第1番目の御朱印
----------------
ここでは清光の館跡ともいわれ、清元が開基し、僧形の清元の木像が残る医王山 清光寺(東京都北区)をご紹介します。
清光寺は豊島清光の開基(父の康家とも)と伝わり、戦国時代末期の豊島明重により再興とされる真言宗豊山派の寺院です。


【写真 上(左)】 清光寺の山門
【写真 下(右)】 清光寺の本堂
山内の説明書には「豊島清光は、その子葛西清重とともに源頼朝の幕府創業に参加し、豊島氏一族のなかでもっとも名の知られた人で『吾妻鏡』などにもその名が見えます。またこの地に豊島氏の居館があり、その持仏堂が清光寺であったという説や(中略)この寺は、豊島清光が家庭的に不幸であったため菩提寺として建立したという説もあります。」とあり、豊島七佛や江戸六阿弥陀との関係を示唆しています。
かつては大寺であったと推定される古刹で、山門・本堂ともがっしりした本瓦葺きであることから、寺格の高さがうかがわれます。

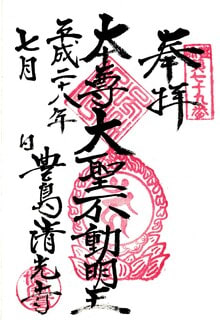
【写真 上(左)】 清光寺の向拝
【写真 下(右)】 清光寺の御朱印(豊島八十八ヶ所)
御本尊の不動明王、および釈迦堂の釈迦如来は行基作とされ、豊島七佛に数えられています。
当寺所蔵の豊島清光像は江戸時代の作で、北区指定文化財です。
御朱印は、現役霊場と目される豊島八十八ヶ所のものが授与されています。
→ ■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2へつづく。
〔 関連記事 〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ I.G.Y. - Donald Fagen
■ Oh Yeah! - Roxy Music
■ Our Love - Michael McDonald
■ Isn't It Time - Boz Scaggs
■ Both Sides Now - Marc Jordan
今回も東日本、とくに伊豆と鎌倉がメイン舞台なので、関連する御朱印を随時ご紹介していきます。
最新記事→ ■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
1.伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印
伊豆は北条(北條)氏の本拠地で、この霊場には北条氏や源頼朝公ゆかりの寺院がいくつかあります。
2.鎌倉市の御朱印
鎌倉市内でいただける御朱印・御首題は、おそらくほとんど拝受したと思うので、こちらについても随時UPしていきます。
→ ■ 鎌倉市の御朱印
3.「鎌倉殿の御家人」ゆかりの御朱印
「13人」とは、足立遠元、安達盛長、大江広元、梶原景時、中原親能、二階堂行政、八田知家、比企能員、北条時政、北条義時、三善康信、三浦義澄、和田義盛を指すそうです。
当初は「こちらの豪族ゆかりの寺社の御朱印も適宜ご紹介していきます。」と書きましたが、文官が多く意外にゆかりの寺院が少ないので、「鎌倉殿の御家人」とされている人物ゆかりの寺社についてもまとめてみます。
〔関連記事〕 → ■ 鎌倉殿の御家人
なお、頼朝公、北条政子とのゆかりがふかい伊豆山神社・伊豆山温泉については、→ こちら(〔 温泉地巡り 〕 伊豆山温泉)に書いています。
令和3年7月伊豆山土砂災害からの一日も早い復旧をお祈りいたします。
とりあえずランダムにUPし、あとでエリア別にまとめます。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
01.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮)
鎌倉市材木座
〔源頼朝公〕
02.巨徳山 北條寺
静岡県伊豆の国市
〔北條義時〕
03.(西御門)白旗神社
鎌倉市西御門
〔源頼朝公〕
04.天守君山 願成就院
静岡県伊豆の国市
〔北條時政〕
05.甘縄神明宮
鎌倉市長谷
〔源氏・安達盛長〕
06.清月山 元光院 金剛寺
埼玉県川島町
〔比企能員〕
07.慧日山 薬王院 寳泉寺
渋谷区東
〔常盤御前・源義経公〕
08.鷲峰山 覚園寺
鎌倉市二階堂
〔北条(北條)義時〕
09.高橋山 放光寺
山梨県甲州市
〔安田義定〕
10.粟船山 常楽寺
鎌倉市大船
〔北条(北條)泰時〕
11.萬年山 城願寺
神奈川県湯河原町
〔土肥實平〕
12.岩殿山 光明院 安楽寺
埼玉県吉見町
〔源範頼公〕
13.医王山 清光寺
北区豊島
〔豊島清元(清光)〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
14.稲荷山 東林寺
静岡県伊東市
〔工藤氏・伊東氏・曾我氏〕
15.葛見神社
静岡県伊東市
〔伊東氏〕
16.飯室山 大福寺
山梨県中央市
〔浅利冠者義遠(義成)〕
17.金色山 吉祥院 大悲願寺
東京都あきる野市
〔平山左衛門尉季重〕
18.古尾谷八幡神社/寳聚山 東漸寺 灌頂院
埼玉県川越市
〔源頼朝公・古尾谷氏〕
19.超越山 来迎院 西光寺
葛飾区四つ木
〔葛西三郎清重〕
20.龍ヶ崎鎮守 八坂神社
茨城県龍ヶ崎市
〔下河辺氏・下河辺四郎政義〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
21.冷水山 清浄土院 長徳寺
埼玉県川越市
〔仙波氏〕
22.阿毘盧山 密乗院 大日寺
千葉県千葉市稲毛区
〔千葉介常胤〕
23.和田(義盛)神社
静岡県富士市
〔和田太郎義盛〕
24.(羽根倉)浅間神社
埼玉県志木市
〔金子小太郎高範〕
25.瑠璃光山 薬師院 玉井寺
埼玉県熊谷市
〔玉井四郎資重/玉井氏〕
26.如意山 観音院 大輪寺
茨城県結城市
〔(小山七郎)結城朝光〕
27.宝林山 称念寺
静岡県河津町
〔河津三郎祐泰〕
28.慈眼山 無量院 萬福寺
大田区南馬込
〔梶原平三景時〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
28.慈眼山 無量院 萬福寺(つづき)
大田区南馬込
〔梶原平三景時〕
29.永劫山 華林院 慶元寺
世田谷区喜多見
〔江戸太郎重長〕
30.龍智山 毘廬遮那寺 常光院
埼玉県熊谷市
〔中条藤次家長〕
31.礒明山 松岸寺
群馬県安中市
〔佐々木三郎盛綱〕
32.勅使山 大光寺
埼玉県上里町
〔勅使河原三郎有直〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
33.金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺
栃木県足利市
〔足利上総介義兼〕
34.多福山 一乗院 大寳寺
鎌倉市大町
〔佐竹四郎秀義〕
35.萬徳山(梅田山) 梅林寺 明王院
足立区梅田
〔志田三郎先生義広〕
36.白山 東光寺
〔畠山次郎重忠〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
37.岩浦山 福寿寺
神奈川県三浦市
〔三浦平六義村〕
38.筑波山神社
茨城県つくば市
〔八田右衛門尉知家、八田太郎知重〕
39.大聖山 金剛寺
神奈川県秦野市
〔源実朝公〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
40.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院
鎌倉市大町
〔北条政子〕
■ 源頼朝公ゆかりの寺社
1.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮) 〔源頼朝公〕
神奈川県鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇、神功皇后、比売神
康平六年(1063年)源頼義公が、前九年の役で奥州を鎮定され京に帰る帰途、鎌倉に立ち寄られこの地に源氏の守り神である京の石清水八幡宮の御祭神を勧請されて創祀と伝わります。
後に源頼朝公が現在の鶴岡八幡宮の地(小林郷北山)に社殿を遷してからは、「元八幡」とも呼ばれるようになりました。
鶴岡八幡宮には、由比若宮遥拝所があります。


【写真 上(左)】 由比若宮の社頭
【写真 下(右)】 由比若宮の拝殿

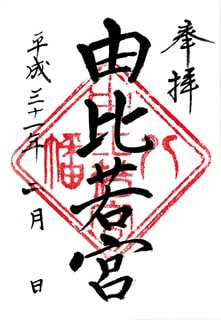
【写真 上(左)】 由比若宮遙拝所(鶴岡八幡宮境内)
【写真 下(右)】 由比若宮の御朱印
2.巨徳山 北條寺 〔北條義時〕
静岡県伊豆の国市南江間862-1
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第13番、伊豆中道三十三観音霊場第16番、駿豆両国横道三十三観音霊場第8番、中伊豆観音札所第20番
源頼朝公の正室・北條政子の弟である北條義時(江間小四郎)が創建した寺院です。
義時の嫡子安千代が領内の大池で大蛇に襲われ命を落とした際に、この北條寺を墓所とし七堂伽藍を建立し、運慶に仏像を作らせたといいます。
御本尊の聖観世音菩薩は南北朝期の作とされ中国宋風の像容で県文化財に指定されています。鎌倉極楽寺にあったものを北条政子が北條寺に奉納したとも伝わります。
境内の「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、義時夫妻の墓所があります。


【写真 上(左)】 北條寺の山門
【写真 下(右)】 北條寺の本堂
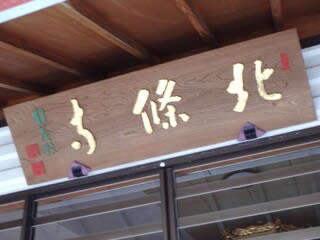
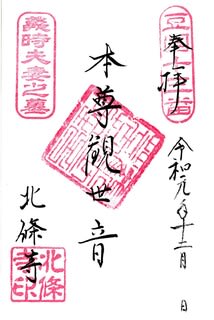
【写真 上(左)】 北條寺本堂の扁額
【写真 下(右)】 北條寺の御朱印(伊豆八十八ヶ所霊場)
3.(西御門)白旗神社 〔源頼朝公〕
神奈川県鎌倉市西御門2-1-24
御祭神:源頼朝公
現在の源頼朝公墓所にあった法華堂がこの地に移され、江戸期まで鶴岡八幡宮二十五坊の一つ相承院が別当を勤めていましたが、明治の神仏分離令により白旗神社に改められたとされます。
源頼朝公墓所の尾根つづきに北条義時法華堂跡があり、こちらは『吾妻鏡』に「頼朝の法華堂の東の山をもって墳墓となす」と記された地とみられています。
北条義時法華堂跡の山上に、大江広元の墓所があります。

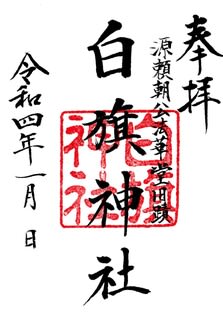
【写真 上(左)】 (西御門)白旗神社
【写真 下(右)】 (西御門)白旗神社の御朱印


【写真 上(左)】 北条義時法華堂跡
【写真 下(右)】 大江広元の墓所
4.天守君山 願成就院 〔北條時政〕
静岡県伊豆の国市寺家83-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆中道三十三観音霊場第18番、中伊豆観音札所第18番
文治五年(1189年)、源頼朝公の奥州藤原氏征討の戦勝を祈願して北條時政公が建立したと伝わる中伊豆の名刹。
時政公建立の大御堂と南塔、二代執権北條義時公建立の南新御堂、三代執権北條泰時公建立の北條御堂と北塔など、北條氏三代にわたり伽藍が整えられました。
御本尊、阿弥陀如来をはじめとする大御堂安置の五仏は、数少ない運慶の真作として国宝に指定されています。


【写真 上(左)】 願成就院
【写真 下(右)】 御本尊阿弥陀如来の御朱印
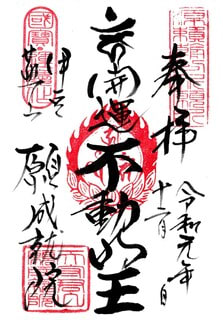

【写真 上(左)】 不動明王の御朱印
【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印
5.甘縄神明宮 〔源氏・安達盛長〕
神奈川県鎌倉市長谷1ー12ー1
主祭神:天照大神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:甘縄院(臨済宗)
和銅三年(710年)行基の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社ともいわれます。
永保元年(1081年)源義家公が社殿を再建、以降も源頼朝公、政子の方、源実朝公などの崇敬が篤かったと伝わります。
また、源頼義公が相模守として下向の折に当宮に祈願し、八幡太郎義家公が生まれたとも伝えられ、源氏とつよい所縁をもちます。
社殿がある場所は安達盛長の屋敷跡とされています。


【写真 上(左)】 甘縄神明宮
【写真 下(右)】 甘縄神明宮の御朱印
6.清月山 元光院 金剛寺 〔比企能員〕
「鎌倉殿を支えた武士の故郷 比企の史跡マップ」(PDF/川島町Web)
埼玉県川島町中山1198
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州八十八霊場第55番
比企能員は、息女・若狭局を二代将軍頼家公に嫁がせ、その子一幡が生まれてからは北条一門と対立して権勢を誇っていたものとみられています。
建仁二年(1203年)9月、比企氏の乱で北条方に破れ、比企能員は一族郎党とともに討死したと伝わります。
比企能員の舘は、埼玉県東松山市大谷付近にあったとされています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
比企能員の墓所は鎌倉の妙本寺にありますが、比企氏の末裔が天正(1573-1592年)の頃より当地一帯を舘とし比企左馬助則員が中興、金剛寺は比企氏の菩提寺となり比企氏歴代の墓所となっています。
山門と比企氏の位牌堂である金剛寺大日堂は、国の登録有形文化財に指定されています。
川島町Webによると、「比企地域9市町村(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、鳩山町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)と比企地域の各種関係団体は、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放映を契機として地域の活性化につなげようと、令和2年(2020年)12月に『大河ドラマ「鎌倉殿の13人」比企市町村推進協議会』を立ち上げ、大河ドラマが放映される令和4年(2022年)に向けてさまざまな取組を行っていきます。」とのことです。


【写真 上(左)】 大日堂
【写真 下(右)】 御朱印
7.慧日山 薬王院 寳泉寺 〔常盤御前・源義経公〕
天台宗東京教区Web
東京都渋谷区東2-6-16
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東九十一薬師霊場第12番、江戸西方三十三観音霊場第31番、弁財天百社参り番外6
渋谷と恵比寿の中間辺りに位置する都会のお寺さまで、御朱印で有名な氷川神社のすぐそばです。
御本尊は阿弥陀如来。平安中期から鎌倉の作とされる薬師如来像は、源義朝公の側室で義経公の母、常盤御前の守り佛(持彿)と伝わり「常盤薬師」としてふるくから信仰を集めています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
このあたりはかつて「常磐松町」といいましたが、その由来となった松の古木は常盤御前が植えたという言い伝えがあるそうです。
このような都会の真ん中に常盤御前ゆかりの寺院があるとはちょっと驚きです。
「常盤薬師」は関東九十一薬師霊場第12番の札所本尊で、御朱印が授与されています。


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 「常盤薬師」の御朱印
8.鷲峰山 覚園寺 〔北条(北條)義時〕
公式Web
神奈川県鎌倉市二階堂421
真言宗泉涌寺派
御本尊:薬師如来
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第13番(阿閃如来)
建保六年(1218年)、薬師如来の眷属・十二神将のうちの「戌神」(伐折羅大将)が北条義時の夢に現れ、これを受けて義時が建立した大倉薬師堂が覚園寺の草創とされます。
永仁四年(1296年)、九代執権北条貞時は外敵退散を祈念して、大倉薬師堂を正式の寺に改めた(覚園寺の創建)といいます
開基は北条貞時、開山は京・泉涌寺の智海心慧律師とされます。

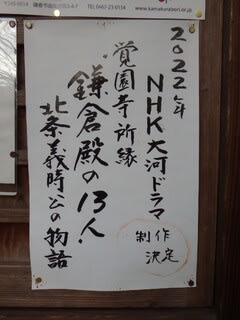
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 大河ドラマ関連の掲示
現在は真言宗泉涌寺派となっていますが、当初は北京系律の本拠地で、律を中心に天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学の道場であったと伝わります。
元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が勅願寺とされ、足利氏も祈願所として保護した名刹です。
なお、入口正面の愛染堂と諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
御本尊、薬師如来のほか、3種の札所の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御本尊の御朱印
※ その他の御朱印は■ 鎌倉市の御朱印でご紹介しています。
9.高橋山 放光寺 〔安田義定〕
公式Web
山梨県甲州市藤木2438
真言宗智山派
御本尊:金剛界大日如来
札所:甲斐百八霊場第8番、甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)
「鎌倉殿の13人」には何度か甲斐源氏の武田信義が登場していますが、平家追討のなかで大きな役割を担った甲斐源氏のひとりに安田義定がいます。
安田義定は、甲斐源氏の祖とされる源義光(新羅三郎)公の孫源清光公の子(清光の父義清の子説もあり)という名流で、現在の山梨市を中心とした峡東一帯に勢力を張りました。
平家追討の令旨に応じて挙兵し、「富士川の戦い」などでの戦功により遠江国守護に任じられました。(『吾妻鏡』)
寿永二年(1183年)、平家追討使として東海道から上洛。大内裏守護として京中を守護し、同年8月には従五位下遠江守に叙任。
「宇治川の戦い」、「一ノ谷の戦い」と歴戦。とくに「一ノ谷の戦い」では、義経の搦め手軍を率いて奮戦、平経正、平師盛、平教経を討ち取ったと伝わります。
放光寺の公式Webには、『吾妻鏡』による平家追討軍の編成は「大手の大将範頼軍には武田有義、小山朝政、下河辺行平、千葉常胤、梶原景時ほか五万六千余騎、搦手の大将義経軍には安田義定、大内惟義、土肥宗平、三浦義連、熊谷直実以下二万余騎とあり」とし、「甲斐源氏の中では安田義定と武田有義が副大将として活躍」とあります。
また、建久二年(1191年)の鶴岡八幡宮法会では、頼朝公御供の筆頭に義定の名がみられ、頼朝公配下のなかでもすこぶる高い地位を占めていたことがわかります。
建久四年(1193年)、義定の子、安田義資が罪を得て斬られ、義定の所領も没収。
翌建久五年(1194年)には義定みずからが謀反の疑いをうけ、放光寺にて自刃と伝わります。

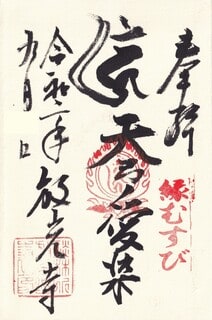
【写真 上(左)】 放光寺本堂
【写真 下(右)】 天弓愛染明王の御朱印
この当時の甲斐源氏には、武田信義、安田義定、一条忠頼らの有力武将がおり、「富士川の戦い」の主力は甲斐源氏であったともみられています。
しかし、安田義定は謀反の疑いで自刃、一条忠頼も鎌倉にて酒宴の最中に暗殺、武田信義の子逸見有義は頼朝公から疎まれ、同じく信義の子板垣兼信は違勅の罪を問われて配流されるなど、次々と失脚していきました。
また、小笠原長清の兄の秋山光朝は京で平重盛に仕え重盛の息女を娶ったため、甲斐国内の本拠地を頼朝公に攻められ自害したと伝わります。
当時の甲斐源氏は頼朝公も御せないほどの強大な勢力があり、武家の頭領としての地位を確立するために、頼朝公が甲斐源氏の力を削いでいったという見方が有力です。
頼朝公は八幡太郎義家公の流れ、甲斐源氏は新羅三郎義光公の流れで、たしかに嫡流系は頼朝公ですが、それをいえば源満仲公の長子は源頼光公で、その流れの多田源氏、摂津源氏などが清和源氏の嫡流筋にあたります。
しかし多田源氏の多田行綱は勢力を張れず没落、摂津源氏の土岐光衡も鎌倉殿の御家人に収まっているので、やはり武家の統領としての八幡太郎義家公とその流れの頼朝公の声望が高かったものとみられます。
以降、甲斐源氏では武田氏宗家となった信光の流れと信義の弟加賀美遠光から小笠原氏、南部氏が出て、以降勢力を張りました。
小笠原氏、南部氏は江戸時代も大名家として存続しています。(大和郡山藩の柳沢氏、新発田藩主の溝口氏、松前藩主の松前(蠣崎)氏なども甲斐源氏の末裔を称しています。)
放光寺は元暦元年(1184年)、安田義定が「一ノ谷の戦い」の戦勝を記念して創立したと伝わる、甲斐を代表する名刹です。
詳細およびその他の御朱印は■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印をご覧ください。
10.粟船山 常楽寺 〔北条(北條)泰時〕
鎌倉市観光協会Web
神奈川県鎌倉市大船5-8-29
臨済宗建長寺派
御本尊:阿弥陀三尊
札所:-
北条義時の子で、名君として知られる三代執権北条泰時の創建とされる名刹です。
鎌倉市には、鎌倉七口(八口)の外のエリアにも高い格式を誇る名刹がいくつかあって、こちらもそのひとつです。
嘉禎三年(1237年)、北条泰時が義母の供養のために建てた「粟船御堂」(あわふねみどう)が草創とされ、常楽寺の寺号は泰時の法名にちなむものとされます。
開山は退耕行勇、開基は北条泰時。
建長寺開山の蘭渓道隆が建長寺の建立まで当寺に住待され、「常楽は建長の根本なり」といわれて、臨済宗建長寺派において高い格式をもちます。
仏殿には蘭渓道隆像が安置されています。

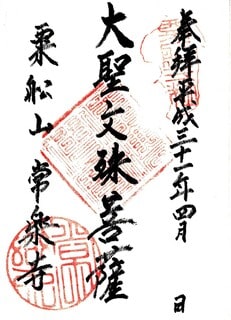
【写真 上(左)】 常楽寺
【写真 下(右)】 常楽寺の御朱印
仏殿は、元禄四年(1691年)建立の小形禅宗様で県指定重要文化財、鎌倉期作とされる木造文殊菩薩坐像も県指定重要文化財。
御本尊の阿弥陀如来像、山門は市の指定文化財。梵鐘は建長寺・円覚寺の梵鐘とともに「鎌倉三名鐘」に数えられ、国の重要文化財に指定されるなど文化財の宝庫です。
仏殿背後には北条泰時の墓があり、裏山には清水冠者(木曽義高)の墓と伝わる塚「木曽塚」があります。
清水冠者は木曽義仲の子で、源頼朝公の長女・大姫の婿の名目で鎌倉に入りましたが、父・義仲が粟津の戦いで討たれたのちは微妙な立場となり、鎌倉を脱出したところを入間河原であえなく討たれました。没年12歳と伝わります。
御朱印は、御本尊の阿弥陀三尊ではなく、蘭渓道隆ゆかりとされる文殊菩薩のものが授与されています。
11.萬年山 城願寺 〔土肥實平〕
公式Web
神奈川県湯河原町城堀252
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:-
土肥氏は、相模国の有力豪族中村氏の流れで桓武平氏良文流。足下郡・土肥郷(早川庄)(現在の湯河原、真鶴、早川周辺)を本拠として勢力を張りました。
鎌倉幕府草創期の当主は土肥實平で、東国武士のあいだで人望があり、『曽我物語』で有名な伊豆奥野の狩場での河津祐泰と俣野景久のいさかいの際に、仲裁に入ったと伝わります。
治承四年(1180年)、頼朝公挙兵の際には嫡子遠平をはじめ中村一族を率いて参じ、石橋山の敗戦から安房落ちの際にも頼朝公につき従ったとされます。
以降も一貫して頼朝公を支えて公の信任篤く、奥州から参陣した義経公を取り次ぎ、平家方から頼朝公に降った梶原景時をとりなしたのも實平という説があります。
養和元年(1181年)の鶴岡八幡宮の造営にあたっては奉行をつとめています。
源平合戦では宇治川の戦い、大江山守護、一ノ谷の戦い、壇ノ浦の戦いと歴戦し、一ノ谷の戦いののちには吉備三国(備前・備中・備後)の惣追捕使(のちに長門・周防を加える)に補任と伝わります。
建久元年(1190年)の頼朝公上洛の際には、右近衛大将拝賀の随兵7人の内に選ばれ、公側近の重職の地位を占めていたことがわかります。
以降子孫は繁栄し、相模土肥氏の祖とされています。
なお、戦国期「毛利両川」の小早川氏は、實平の子・遠平が土肥郷の小早川に拠り小早川を称し、平家討伐の恩賞として安芸国沼田荘の地頭職を拝領して土着、以降この地で勢力を伸ばしたものとされています。
實平の居舘は城願寺のあたりとされ、寺伝(城願寺公式Web)には「實平が、萬年の世までも家運が栄えるように「萬年山」と号して持仏堂を整えたことから城願寺の歴史は始まる。」とあります。
草創は實平。以来、城願寺は土肥一族の菩提寺となっています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
もともとは密寺でしたが臨済宗に改め萬年山成願寺として勧請開山、五山十刹につぐ諸山に定められ、戦国期の再興(重興開山)で曹洞宗に改め、城願寺と号して現在に至ります。
湯河原と土肥一族とのゆかりは深く、毎年春には「土肥祭」が催され、城願寺でも式典が催されます。
御本尊は聖観世音菩薩。
公式Webには「寺院が禅宗に改宗する場合には、以前の本尊をそのまま受け継いでも構わないとされることも多く、或いは創建時そのままの御本尊様かもしれません。」とあります。
このような例は、伊豆の寺院にとくに多くみられます。→■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印


【写真 上(左)】 七騎堂
【写真 下(右)】 城願寺の御朱印
土肥実平・遠平像(湯河原町指定文化財)を所蔵し、實平をはじめとする土肥一族の墓所や、石橋山の戦いで頼朝公とともに落ちのびた七騎を祀る七騎堂があります。
ちなみに、「七騎」とは、源頼朝公、土肥實平、安達盛長、土屋宗遠、岡崎義実、田代信綱、新開忠氏をさすようです。(→出典:『観光かながわNOW』)
→ 境内360度画像(公式Web)
湯河原の高台にあり、落ち着いたたたずまい。
實平手植えと伝わるビャクシンは樹齢800年を越え、国の天然記念物に指定されています。
御朱印は御本尊の聖観世音菩薩(観自在菩薩)のものが授与されています。
→ ■ 湯河原温泉「中屋旅館」の入湯レポ
→ ■ 湯河原温泉「若草荘」の入湯レポ
12.岩殿山 光明院 安楽寺 〔源範頼公〕
公式Web
埼玉県吉見町御所374
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第11番、関東八十八箇所第75番、武州路十二支霊場(申・金剛界大日如来)、東国花の寺百ヶ寺霊場第17番、中武蔵七十二薬師霊場第62番、武州八十八霊場第36番
源範頼公は源義朝公の子(六男と伝わる)で、頼朝公の異母弟、義経公の異母兄です。
『尊卑分脈』では生母は遠江国池田宿の遊女とされていますが、池田宿周辺の然るべき家の娘という説もあります。
江国蒲御厨(現在の浜松市)で生まれ育ったため、蒲冠者(かばのかじゃ)、蒲殿(かばどの)とも称されました。
後白河法皇の近臣、従二位・式部権少輔藤原範季に養育され、その縁から「範頼」を名乗ったとされます。
兄・頼朝公への合流時期は明確ではないようで、当初は安田義定など甲斐源氏との交流が深かったとの見方もあります。
また、寿永二年(1183年)、常陸国の志田義広と下野国の小山氏の野木宮合戦に参戦の記録が残っています。
寿永三年(1184年)、頼朝公の代官として源義仲追討の大将軍となり上洛、義経公の軍勢に合流して宇治・瀬田の戦いに参戦。
以降、平家追討の大手軍の大将として一ノ谷の戦い、九州進軍の率将としても勝利し、以降も義経軍と別働しつつ大手軍の大将として諸戦を戦い、壇ノ浦で平氏追討を成しました。
義経公の活躍があまりに華々しいため脇役に回っているきらいもありますが、大手軍の大将として個性の強い鎌倉武士をまとめ、戦を勝利に導いた手腕を評価する見方も少なくありません。
義経軍の進軍にくらべ範頼軍の動きが遅かったことは事実のようで、これをもって範頼公を凡将とみなす説もありますが、中世、華々しい戦さぶりを展開したのはたいてい動きの軽い別働隊や搦手軍で、これをもって範頼公を凡将とすることに疑問を呈する向きもあります。
また、大手の範頼軍の安定した働きあればこそ、搦手の義経軍の奇襲が奏功したという見方もあります。
独断専行が目立った義経公に対し、頼朝公への報告を怠らなかった範頼公は平家追討後も鎌倉での立場を保ち、文治五年(1189年)の奥州合戦には頼朝公に従い参戦。建久元年(1190年)11月にも頼朝公に従い上洛しています。
しかし、その後次第に頼朝公との関係は微妙なものとなり、建久四年(1193年)8月、範頼公は頼朝公に対して忠誠を誓う起請文を差し出すものの、頼朝公は状中で「源範頼」と源姓を名乗った事を過分として責め、範頼公は伊豆国に流され、修禅寺に幽閉されました。
その後の消息については不明とする説が有力です。
範頼公は頼朝公に対して公然と反旗を翻したわけでもなく、「源範頼」を名乗る資格も名分もある筈です。
にもかかわらずの伊豆への配流は、独裁色をつよめる頼朝公にとって異母兄弟の存在じたいが危険なものとして映った結果かもしれません。
実際、頼朝公の実弟で源平合戦の功労者でもある範頼公でさえ、対応を誤ればたちまち立場を失うという事実は、鎌倉御家人たちを震え上がらせたものと思われます。
範頼公の配流は、あるいはこのような効果を狙っての政治的な動きだったのかもしれません。
範頼公の墓所は伊豆・修善寺にあります。
伊豆配流後の範頼公の消息が不明なため、範頼公にはいくつかの配流伝説が残りますが、範頼公ゆかりの寺院は多くはありません。


【写真 上(左)】 安楽寺参道と山門内湯
【写真 下(右)】 範頼公旧跡を示す寺号標
吉見の吉見観音・安楽寺は、範頼公とのゆかりが明示されている貴重な例のひとつです。
武蔵国横見郡(現埼玉県吉見町)の吉見観音への隠住説は範頼公配流伝説のひとつで、吉見観音周辺の大字”御所”は貴人の居住地をあらわし、範頼公にちなむものと伝わります。
これとは別に、吉見は範頼公の妻の祖母で、頼朝公の乳母でもある比企尼の居所に近いので、この縁により移り住み、その子孫は吉見氏として続いたという説もあります。
範頼公の妻は安達盛長の息女で、頼朝公の乳母を務めた比企尼の長女丹後内侍の子です。
安達盛長の館は吉見にもほど近い現・鴻巣市糠田とされていますから、安達盛長の壻となった縁で吉見に所領を得たのかもしれません。
範頼公の次男範圓と三男源昭は外曾祖母の比企尼から吉見庄を分与され、範圓の子為頼が吉見を名字とした、という説もあります。


【写真 上(左)】 安楽寺山内
【写真 下(右)】 「比企一族と武蔵武士ゆかりの地」のポスター
安楽寺の公式Webには「平安時代の末期には、源頼朝の弟範頼がその幼少期に身を隠していたと伝えられ、安楽寺の東約500メートルには『伝範頼館跡』と呼ばれる息障院がある。この息障院と安楽寺は、かつては一つの大寺院を形成していたことが知られている。」とあり、吉見御所への範頼公の居住は配流後ではなく、幼少期であるとしています。
範頼公が『吾妻鏡』に登場するのは30歳すこし前で、それ以前、とくに幼少期ははっきりしないことが多いので、幼少期吉見居住説が出てくるのだと思います。


【写真 上(左)】 息障院山門
【写真 下(右)】 息障院本堂
吉見の名刹・息障院は「伝範頼館跡」とされ、吉見町の公式Webには「息障院がある一帯が、源範頼の居館跡と伝えられている。源範頼は頼朝の弟で平治の乱後、岩殿山に逃げ比企氏の庇護によって成長した。頼朝が鎌倉で勢力を得た後も吉見に住んでいたと思われ、館を中心とするこの地を御所と呼ぶようになったと言われている。」とあります。


【写真 上(左)】 安楽寺本堂向拝
【写真 下(右)】 安楽寺本堂扁額
比企市町村推進協議会企画の「鎌倉殿の13人」資料には、「息障院と安楽寺はかつては一つの大寺院を形成していたことが知られています。当時、息障院には多くの御堂がありましたが、その一つの観音堂が現在の安楽寺になったと伝わります。」とあります。
なお、安楽寺、息障院ともに創建・開基は天平年中(730年頃)の行基菩薩、あるいは大同元年(806年)の坂上田村麻呂と伝わり、鎌倉幕府草創のはるか以前です。
範頼公の記事だけで長くなりましたので、安楽寺山内のご案内は省略です。
メジャーな坂東霊場の札所、パワスポとしても知られており関連情報はWeb上でたくさんみつかるので、そちらをご覧ください。(と逃げる・・・(笑))
山門下の寺号標側面には「蒲冠者 源 範頼 旧蹟」と刻まれています。
また、山内の三重塔の説明書には「鎌倉時代に源範頼は十六丈の三重大塔と二十五間四面の大講堂を建立し、非常に壮大であったと伝えられております。しかし天文年間に松山城の落城に際してこれらの大伽藍もことごとく焼失いたしました。」とあります。


【写真 上(左)】 三重塔
【写真 下(右)】 御開帳時の薬師堂
安楽寺は複数の現役霊場の札所を兼ねられ、数種の御朱印が授与されています。
うち、中武蔵七十二薬師霊場第62番の御朱印は、12年に一度の寅年御開帳時(本年令和4年4月7日~13日)のみの授与とみられます。


【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 関東八十八箇所の御朱印
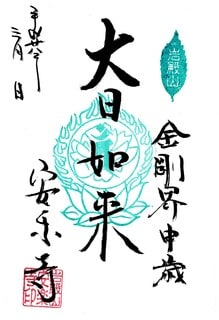
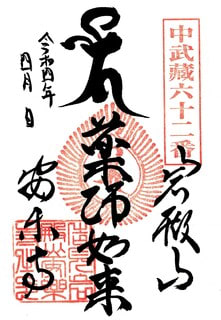
【写真 上(左)】 武州路十二支霊場(申・金剛界大日如来)の御朱印
【写真 下(右)】 中武蔵七十二薬師霊場の御朱印

東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
13.医王山 清光寺 〔豊島清元(清光)〕
東京都北区豊島7-31-7
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
他札所:豊島八十八ヶ所第79番、荒川辺八十八ヶ所霊場第18番、豊島七佛第1番(不動明王)、第2番(釈迦如来)
豊島氏は武蔵国の名族で、桓武平氏の平良文の孫の平(秩父)将常の次男秩父武常が治安三年(1023年)の戦功により武蔵国豊島郡を賜り、豊島氏を称したことにはじまるとされます。
いわゆる「坂東八平氏」の流れです。
発祥は現在の北区豊島、平塚神社が豊島舘跡と伝わります。
鎌倉幕府草創期の当主は豊島清元(清光とも、以下清光と記します)で、子の清重とともに隅田川で頼朝軍に参陣し、御家人の列に加わりました。
清光の三男清重は葛西御厨を継いで葛西氏の祖となり、清重は平家追討で範頼軍に加わり九州で武功をあげています。
有経が豊島氏を継ぎ紀伊守護人に任ぜられ、子(?)の朝経は土佐守護に任じられて各地で勢力を張りました。
豊島武常は源頼義公・義家公に従って奥州で戦死しており、累代の源氏の家人の立ち位置で、豊島清光に対する頼朝公の信頼は厚かったとされます。
豊島舘跡とされる平塚神社の御祭神は源義家公、義綱公、義光公。
後三年の役の帰路、源義家公、義綱公、義光公の三兄弟がこの豊島館に逗留して豊島近義にもてなしを受け、義家公は鎧一領と十一面観音像を豊島氏に下賜され、後にこの鎧を本尊として塚を築き埋めたのが創祀とも伝わります。
豊島一族と源氏のつながりの深さを伝える由緒といえましょう。
豊島清光は行基菩薩ゆかりのふたつの霊場に深い関係をもち、武蔵国の仏教(霊場)を語るうえで重要な役柄です。
行基菩薩は奈良時代の人、豊島清光は鎌倉幕府草創期の人でそもそも時代が合いませんが、とにかくそういうことになっています。
1.豊島七佛
清光が、行基菩薩の東国布教の際に彫ってもらった七体の仏像が安置される寺院を巡る霊場。
2.江戸六阿弥陀
行基作の阿弥陀佛を巡る江戸時代の代表的な女人霊場。霊場縁起に「豊島左衛門尉清光」が登場します。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~
清光の二男清康ないし娘は荒川で命を落としており、その供養のためにいくつかの寺院の開創にかかわっている可能性があります。
江戸六阿弥陀第1番の西福寺は豊嶋左衛門清光の創建とされ、『新編武蔵風土記稿』には「豊嶋左衛門清光、(略)一人の女子を産す、(略)彼女私に逃れ荒川に身を投て死す、父清光悲に堪す是より佛教に心を委ねしか(以下略)」との記載があります。

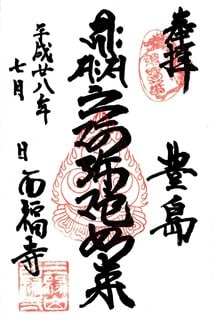
【写真 上(左)】 平塚神社の御朱印
【写真 下(右)】 西福寺の江戸六阿弥陀如来第1番目の御朱印
----------------
ここでは清光の館跡ともいわれ、清元が開基し、僧形の清元の木像が残る医王山 清光寺(東京都北区)をご紹介します。
清光寺は豊島清光の開基(父の康家とも)と伝わり、戦国時代末期の豊島明重により再興とされる真言宗豊山派の寺院です。


【写真 上(左)】 清光寺の山門
【写真 下(右)】 清光寺の本堂
山内の説明書には「豊島清光は、その子葛西清重とともに源頼朝の幕府創業に参加し、豊島氏一族のなかでもっとも名の知られた人で『吾妻鏡』などにもその名が見えます。またこの地に豊島氏の居館があり、その持仏堂が清光寺であったという説や(中略)この寺は、豊島清光が家庭的に不幸であったため菩提寺として建立したという説もあります。」とあり、豊島七佛や江戸六阿弥陀との関係を示唆しています。
かつては大寺であったと推定される古刹で、山門・本堂ともがっしりした本瓦葺きであることから、寺格の高さがうかがわれます。

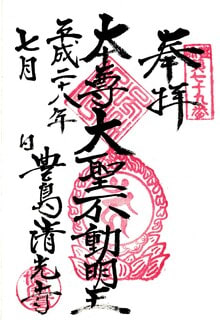
【写真 上(左)】 清光寺の向拝
【写真 下(右)】 清光寺の御朱印(豊島八十八ヶ所)
御本尊の不動明王、および釈迦堂の釈迦如来は行基作とされ、豊島七佛に数えられています。
当寺所蔵の豊島清光像は江戸時代の作で、北区指定文化財です。
御朱印は、現役霊場と目される豊島八十八ヶ所のものが授与されています。
→ ■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2へつづく。
〔 関連記事 〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ I.G.Y. - Donald Fagen
■ Oh Yeah! - Roxy Music
■ Our Love - Michael McDonald
■ Isn't It Time - Boz Scaggs
■ Both Sides Now - Marc Jordan
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 源頼朝公ゆかりの寺社
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印から分離して別記事とします。
今後、発見次第追加していきます。
「鎌倉殿の13人」では、頼朝公がしばしば神仏に祈願するシーンが出てきます。
鎌倉幕府において鶴岡八幡宮の存在はきわめて大きく、鎌倉にはほかにも多くの寺社が建立されて、一種の「宗教都市」の様相を呈していたのではないでしょうか。
頼朝公はのちに白旗神社の御祭神として各地に祀られるのですが、自ら勧請・開基(創建)された寺社も少なくありません。
レファレンス事例詳細(国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している、調べ物のためのデータベース)での「源頼朝が鎌倉に建てた社寺はいくつあるか。」という質問に対しての鎌倉市中央図書館の回答 (2015年10月)には、「鶴岡八幡宮寺、永福寺、勝長寿院の3つと考えるのが妥当なようです。(鶴岡八幡宮寺を「勧請」ととれば2つです。)伝説を含めれば佐助稲荷神社も頼朝創建と伝えられています。」とあります。
上記回答プロセスでの「ネットで『頼朝の建てた社寺』で検索してみると、佐助稲荷が引っかかってくる。」つう表記はいかがなものかと思いますが(笑)、これに倣ってWeb検索し、寺社伝、自治体資料などで由緒が裏付けられたものを以下にあげてみます。
京都の建仁寺、福岡の聖福寺、長野の十念寺などは頼朝公開基・創建の寺院として知られていますが、ここでは関東地方周辺のみに絞ります。
★は御朱印授与ありの寺社です。
1.鶴岡八幡宮寺(神奈川県鎌倉市) ★(鶴岡八幡宮)
鶴岡八幡宮別当。建久二年(1191年)、あらためて石清水八幡宮護国寺を勧請。

2.永福寺(二階堂)(廃寺)(神奈川県鎌倉市)
頼朝公建立。建久三年(1192年)11月落慶供養。奥州合戦の戦死者供養の為。
3.阿弥陀山 勝長寿院(大御堂)(廃寺)(神奈川県鎌倉市)
頼朝公建立。文治元年(1185年)10月落慶供養。父・義朝公菩提の為。
4.佐助稲荷神社(神奈川県鎌倉市) ★
頼朝公が畠山重忠に命じ再建。建久年間(1190~1199年)、平家討伐祈願の御礼。

5.銭洗弁財天宇賀福神社(神奈川県鎌倉市) ★
伝・頼朝公創祀。文治元年(1185年)頼朝公の霊夢により天下泰平の世を祈願の為。

6.能蔵寺(現・材木座来迎寺)(神奈川県鎌倉市) ★(来迎寺)
頼朝公創建。建久五年(1194年)、三浦大介義明菩提の為。

7.南向山 補陀洛寺(神奈川県鎌倉市) ★
伝・頼朝公開基。

8.朝比奈熊野神社(横浜市金沢区)
頼朝公建立。覇府艮方守護の為。
9.瀬戸神社(瀬戸三島明神)(横浜市金沢区) ★
頼朝公が挙兵にあたり御利益を蒙った伊豆三島明神の御分霊を祭祀。

10.富岡八幡宮(横浜市金沢区) ★
頼朝公造営。建久二年(1191年)、鎌倉の鬼門除けとして摂津西宮神社の蛭子尊の分霊を勧請。

11.(芝生)浅間神社(横浜市西区) ★
境内由緒書に「創祀は承暦四年(1080年)ともいわれ、源頼朝公文治元年平家討滅に依るべきを思い且つは戦勝奉賽のため(略)芝生村に富士山の形状の山地あるを卜とし社殿の修築をなし報賽の至誠を致せる(略)」とあり、「(頼朝公が)御分霊を奉祀して創祀」とする資料も複数あり。
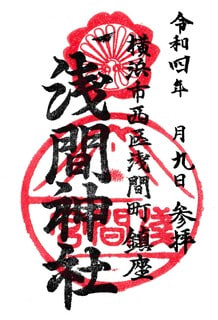
12.瑞雲山 本覚院 三會寺(横浜市港北区) ★
頼朝公建立の密場(新編武蔵風土記稿)。旧小机領三十三所子歳観音霊場の御朱印にも「開基:頼朝公」とあり。源頼朝公が大檀那となり佐々木高綱が奉行して建立とも。

13.補陀洛山 安養院 西方寺(横浜市港北区) ★
旧小机領三十三所子歳観音霊場の御朱印に「開基:頼朝公」とあり。西方寺の公式Webには開基は明記されていませんが、頼朝公は開山の醍醐覚洞院座主に帰依していることから、このような表記になっているのかもしれません。
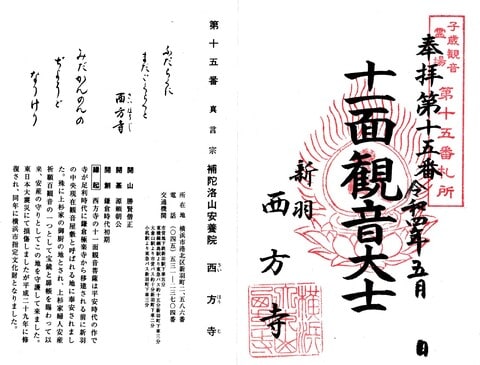
14.森戸神社 (森戸大明神)(神奈川県葉山町) ★
頼朝公勧請。治承四年(1180年)、天下平定の御礼に三嶋明神の御分霊を勧請。

15.義明山 満昌寺(神奈川県横須賀市) ★
頼朝公建立。建久五年(1194年)、三浦大介義明を開基として源頼朝が建立。

16.五明山 最宝寺(神奈川県横須賀市) ★
頼朝公開基。建久六年(1195年)。

17.日金山 松源寺(現・松得山 東漸寺の日金地蔵尊)(神奈川県横須賀市) ★
頼朝公勧請。伊豆配流時、出世あれば勧請と約し、願成就ののちに日金山 東光寺より勧請、松源寺を創建。

18.江島弁財天(神奈川県藤沢市) ★
頼朝公が文覚に命じて勧請。養和2年(1182年)、奥州藤原秀衡調伏の為。

19.三嶋山 感応院(瑞光密寺)(神奈川県藤沢市) ★
頼朝公による「三嶋神社」の勧請が創祀。

20.(上大井)三嶋神社(神奈川県大井町) ★
頼朝公建立。治承四年(1180年)、平家打倒・源氏再興の御礼に三嶋大社より御分霊を勧請。
以上が神奈川県内の寺社で、鎌倉・三浦半島を中心に相当数みられます。
ところが神奈川県外となると、その数はぐっと少なくなります。
21.品川神社(東京都品川区) ★
頼朝公創始。文治三年(1187年)、海上交通安全祈願成就御礼の為、安房国洲崎明神を勧請。
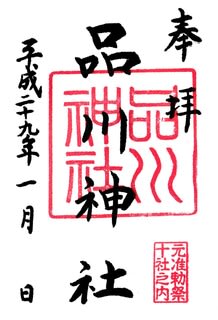
22.牛天神北野神社(東京都文京区) ★
頼朝公創建。元暦元年(1184年)、頼朝公の霊夢(菅原道真公の御神託)による。

23.田端八幡神社(東京都北区) ★
頼朝公創祀。文治五年(1189年)、奥州平定後に鶴岡八幡宮を勧請し祭祀。

24.上田端八幡神社(東京都北区) ★
頼朝公創祀。文治五年(1189年)、奥州平定後に鶴岡八幡宮を勧請し祭祀。

25.神楽坂若宮八幡神社(東京都新宿区) ★
頼朝公勧請創建。文治五年(1189年)、奥州征伐後に鶴岡八幡宮の御分霊を勧請。

26.産安社(武蔵御嶽神社の摂社)(東京都青梅市) ★(武蔵御嶽神社)
頼朝公創建。文治年間(1185-1189年)。
27.天津神明宮(千葉県鴨川市) ★
頼朝公勧請。寿永三年(1184年)、安房の地で源家再興を伊勢大廟に祈願・成就の御礼に伊勢より御神霊を勧請。

28.長沼八幡宮(栃木県真岡市) ★
頼朝公勧請。建久四年(1193年)、神夢により加茂社(別雷尊)・春日社(天児屋根尊)の両神を勧請して創祀。
29.玉村八幡宮(群馬県玉村町) ★
頼朝公勧請。建久六年(1195年)、安達盛長に命じ鶴岡八幡宮の御分霊を勧請。
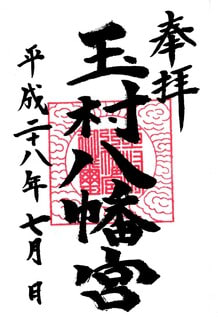
30.若宮八幡宮(大寶八幡宮の摂社)(茨城県下妻市) ★(大寶八幡宮)
頼朝公勧請。文治五年(1189年)、奥州征伐平定の日に鶴岡八幡宮若宮を勧請して摂社を創建。

31.海雲山 長勝寺(茨城県潮来市) ★
頼朝公建立。文治元年(1185年)。

埼玉県に至っては、ほとんどWebではヒットしません。
埼玉県内には、比企氏、畠山氏、熊谷氏、河越氏、武蔵七党など有力御家人が多く、寺社の創再建はこれらの武家たちが担っていたからかもしれません。
今後、発見次第追加していきます。
「鎌倉殿の13人」では、頼朝公がしばしば神仏に祈願するシーンが出てきます。
鎌倉幕府において鶴岡八幡宮の存在はきわめて大きく、鎌倉にはほかにも多くの寺社が建立されて、一種の「宗教都市」の様相を呈していたのではないでしょうか。
頼朝公はのちに白旗神社の御祭神として各地に祀られるのですが、自ら勧請・開基(創建)された寺社も少なくありません。
レファレンス事例詳細(国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している、調べ物のためのデータベース)での「源頼朝が鎌倉に建てた社寺はいくつあるか。」という質問に対しての鎌倉市中央図書館の回答 (2015年10月)には、「鶴岡八幡宮寺、永福寺、勝長寿院の3つと考えるのが妥当なようです。(鶴岡八幡宮寺を「勧請」ととれば2つです。)伝説を含めれば佐助稲荷神社も頼朝創建と伝えられています。」とあります。
上記回答プロセスでの「ネットで『頼朝の建てた社寺』で検索してみると、佐助稲荷が引っかかってくる。」つう表記はいかがなものかと思いますが(笑)、これに倣ってWeb検索し、寺社伝、自治体資料などで由緒が裏付けられたものを以下にあげてみます。
京都の建仁寺、福岡の聖福寺、長野の十念寺などは頼朝公開基・創建の寺院として知られていますが、ここでは関東地方周辺のみに絞ります。
★は御朱印授与ありの寺社です。
1.鶴岡八幡宮寺(神奈川県鎌倉市) ★(鶴岡八幡宮)
鶴岡八幡宮別当。建久二年(1191年)、あらためて石清水八幡宮護国寺を勧請。

2.永福寺(二階堂)(廃寺)(神奈川県鎌倉市)
頼朝公建立。建久三年(1192年)11月落慶供養。奥州合戦の戦死者供養の為。
3.阿弥陀山 勝長寿院(大御堂)(廃寺)(神奈川県鎌倉市)
頼朝公建立。文治元年(1185年)10月落慶供養。父・義朝公菩提の為。
4.佐助稲荷神社(神奈川県鎌倉市) ★
頼朝公が畠山重忠に命じ再建。建久年間(1190~1199年)、平家討伐祈願の御礼。

5.銭洗弁財天宇賀福神社(神奈川県鎌倉市) ★
伝・頼朝公創祀。文治元年(1185年)頼朝公の霊夢により天下泰平の世を祈願の為。

6.能蔵寺(現・材木座来迎寺)(神奈川県鎌倉市) ★(来迎寺)
頼朝公創建。建久五年(1194年)、三浦大介義明菩提の為。

7.南向山 補陀洛寺(神奈川県鎌倉市) ★
伝・頼朝公開基。

8.朝比奈熊野神社(横浜市金沢区)
頼朝公建立。覇府艮方守護の為。
9.瀬戸神社(瀬戸三島明神)(横浜市金沢区) ★
頼朝公が挙兵にあたり御利益を蒙った伊豆三島明神の御分霊を祭祀。

10.富岡八幡宮(横浜市金沢区) ★
頼朝公造営。建久二年(1191年)、鎌倉の鬼門除けとして摂津西宮神社の蛭子尊の分霊を勧請。

11.(芝生)浅間神社(横浜市西区) ★
境内由緒書に「創祀は承暦四年(1080年)ともいわれ、源頼朝公文治元年平家討滅に依るべきを思い且つは戦勝奉賽のため(略)芝生村に富士山の形状の山地あるを卜とし社殿の修築をなし報賽の至誠を致せる(略)」とあり、「(頼朝公が)御分霊を奉祀して創祀」とする資料も複数あり。
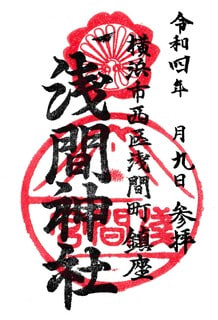
12.瑞雲山 本覚院 三會寺(横浜市港北区) ★
頼朝公建立の密場(新編武蔵風土記稿)。旧小机領三十三所子歳観音霊場の御朱印にも「開基:頼朝公」とあり。源頼朝公が大檀那となり佐々木高綱が奉行して建立とも。

13.補陀洛山 安養院 西方寺(横浜市港北区) ★
旧小机領三十三所子歳観音霊場の御朱印に「開基:頼朝公」とあり。西方寺の公式Webには開基は明記されていませんが、頼朝公は開山の醍醐覚洞院座主に帰依していることから、このような表記になっているのかもしれません。
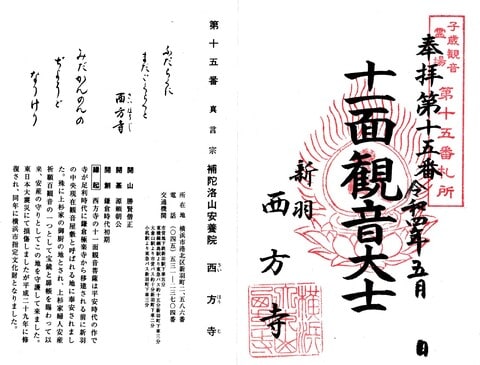
14.森戸神社 (森戸大明神)(神奈川県葉山町) ★
頼朝公勧請。治承四年(1180年)、天下平定の御礼に三嶋明神の御分霊を勧請。

15.義明山 満昌寺(神奈川県横須賀市) ★
頼朝公建立。建久五年(1194年)、三浦大介義明を開基として源頼朝が建立。

16.五明山 最宝寺(神奈川県横須賀市) ★
頼朝公開基。建久六年(1195年)。

17.日金山 松源寺(現・松得山 東漸寺の日金地蔵尊)(神奈川県横須賀市) ★
頼朝公勧請。伊豆配流時、出世あれば勧請と約し、願成就ののちに日金山 東光寺より勧請、松源寺を創建。

18.江島弁財天(神奈川県藤沢市) ★
頼朝公が文覚に命じて勧請。養和2年(1182年)、奥州藤原秀衡調伏の為。

19.三嶋山 感応院(瑞光密寺)(神奈川県藤沢市) ★
頼朝公による「三嶋神社」の勧請が創祀。

20.(上大井)三嶋神社(神奈川県大井町) ★
頼朝公建立。治承四年(1180年)、平家打倒・源氏再興の御礼に三嶋大社より御分霊を勧請。
以上が神奈川県内の寺社で、鎌倉・三浦半島を中心に相当数みられます。
ところが神奈川県外となると、その数はぐっと少なくなります。
21.品川神社(東京都品川区) ★
頼朝公創始。文治三年(1187年)、海上交通安全祈願成就御礼の為、安房国洲崎明神を勧請。
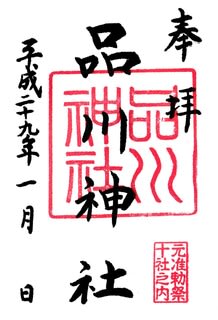
22.牛天神北野神社(東京都文京区) ★
頼朝公創建。元暦元年(1184年)、頼朝公の霊夢(菅原道真公の御神託)による。

23.田端八幡神社(東京都北区) ★
頼朝公創祀。文治五年(1189年)、奥州平定後に鶴岡八幡宮を勧請し祭祀。

24.上田端八幡神社(東京都北区) ★
頼朝公創祀。文治五年(1189年)、奥州平定後に鶴岡八幡宮を勧請し祭祀。

25.神楽坂若宮八幡神社(東京都新宿区) ★
頼朝公勧請創建。文治五年(1189年)、奥州征伐後に鶴岡八幡宮の御分霊を勧請。

26.産安社(武蔵御嶽神社の摂社)(東京都青梅市) ★(武蔵御嶽神社)
頼朝公創建。文治年間(1185-1189年)。
27.天津神明宮(千葉県鴨川市) ★
頼朝公勧請。寿永三年(1184年)、安房の地で源家再興を伊勢大廟に祈願・成就の御礼に伊勢より御神霊を勧請。

28.長沼八幡宮(栃木県真岡市) ★
頼朝公勧請。建久四年(1193年)、神夢により加茂社(別雷尊)・春日社(天児屋根尊)の両神を勧請して創祀。
29.玉村八幡宮(群馬県玉村町) ★
頼朝公勧請。建久六年(1195年)、安達盛長に命じ鶴岡八幡宮の御分霊を勧請。
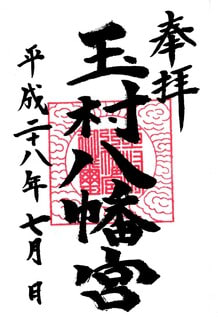
30.若宮八幡宮(大寶八幡宮の摂社)(茨城県下妻市) ★(大寶八幡宮)
頼朝公勧請。文治五年(1189年)、奥州征伐平定の日に鶴岡八幡宮若宮を勧請して摂社を創建。

31.海雲山 長勝寺(茨城県潮来市) ★
頼朝公建立。文治元年(1185年)。

埼玉県に至っては、ほとんどWebではヒットしません。
埼玉県内には、比企氏、畠山氏、熊谷氏、河越氏、武蔵七党など有力御家人が多く、寺社の創再建はこれらの武家たちが担っていたからかもしれません。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10へつづく。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第62番 石屏山 法伝寺(ほうでんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町二條458
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:第58番正眼寺にて
第61番法泉寺から下賀茂に向けて進んだところにあります。
国道136号線から1本南に入ったところですが、国道からも見えます。
開創当初は真言宗で大窪というところにありました。
寛永年中(1624-1644年)松屋祝公和尚が現在地に遷し、臨済宗建長寺派に改めました。
『豆州志稿』には「二條村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 昔大窪ニ在リ 松屋和尚今ノ地ニ移ス 寛永(1624-1644年)の頃ナリ 初真言宗ナリ 松屋改宗ス 或作寶傳寺」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 六地蔵
このあたりの国道136号線は川沿いの水田地帯を辿ります。
南伊豆らしい陽光明るくおだやかな風景です。
国道136号線から枝道に入り、小橋で川を渡った先が参道です。
参道入口右手に札所標、左手には六地蔵。
六地蔵の上手には祠が見え、こちらは地主神かもしれません。


【写真 上(左)】 地主神?の祠
【写真 下(右)】 山内
山内正面に入母屋造銅板葺の本堂と右手に庫裡を配し、L字型の堂宇配置です。
堂前は校庭さながらに整地され、なんとなく分校のようです。

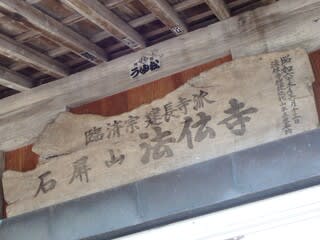
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
本堂に向拝柱はなく、全面サッシュ扉のシンプルな堂宇。
御本尊、札所本尊ともに聖観世音菩薩で、おそらく同一のお像かと思われます。
現在無住につき、御朱印は第58番正眼寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
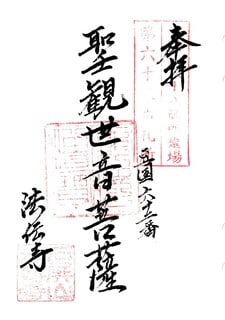
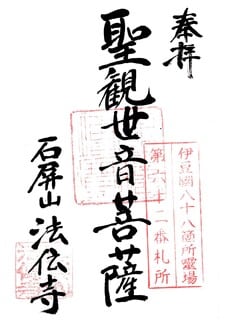
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第63番 五峰山 保春寺(ほしゅんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町加納177-1
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡(第50番玄通寺も)
下賀茂の街並みに入ったところにある曹洞宗寺院です。
開基の山本長門守道政が永正四年(1507年)に没しているので、それ以前の草創とみられています。
開山は僧・法山(天文十一年(1542年)寂)。
草創当時は真言宗で、慶安二年(1649年)太梅寺四世法山秀禅和尚により曹洞宗に改宗されたと伝わります。
『豆州志稿』には「加納村 曹洞宗 横川太梅寺末 本尊虚空蔵 開山法山和尚(天文十一年(1542年)化ス) 山本長門守道政(永正四年(1507年)死ス)ヲ開基トス 初真言宗也 慶安二年(1649年)太梅寺四世秀禅改宗ス 地頭清水康英ノ喜捨文を蔵ム」とあります。
-------------------
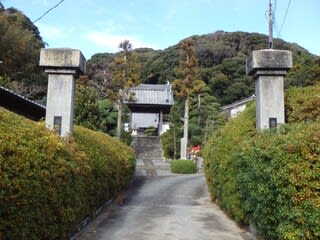

【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道と山門
国道136号から北側に入った山裾にあります。
よく整備された明るい雰囲気の寺院で、落ち着いた参拝ができます。
すこし進むと禅刹らしい「不許葷酒入山門」の石標。
数段の石段の先に切妻屋根桟瓦葺四脚門の均整のとれた山門。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 山内
小高い山を背後に背負った落ち着きのよい山内。
左手手前から鐘楼、鎮守天満宮、正面に本堂とつづきます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
入母屋造桟瓦葺で大棟に「五峰山」。隅棟の貼り出しが大きく存在感ある堂宇です。
向拝柱はなく格子扉メインのシンプルな身舎。
見上げに扁額はなく、桐紋入りの蟇股が置かれています。
開けていただいた本堂内は見上げに山号扁額、金襴幕と複数の天蓋が懸かる華やかなものでした。
御本尊および札所本尊は虚空蔵菩薩。
この霊場では、第45番向陽院と当山の2つの札所本尊が虚空蔵菩薩です。
禅刹、ことに曹洞宗では虚空蔵菩薩が御本尊の寺院はかなりあります。
十三仏、 十二支守り本尊の一尊でもありますが、御真言は「ノウボウ アキャシャキャラバヤ オンアリキャ マリボリソワカ」とかなり複雑です。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 鐘楼と天満宮
鎮守の天満宮は一間社流造桟瓦葺。鮮やかな朱色の水引虹梁が印象的です。
手前に狛犬一対。向拝見上げに「天満宮」の扁額。
一間社流造は覆屋で、なかに本殿が安置されています。
『こころの旅』によると、本殿には「伊豆の小市」と呼ばれた鈴木市五郎の見事な彫刻が施されているようですが、うかつにもチェックしわすれました。
鈴木市五郎は当地生まれの宮大工で、江戸で修業し、築地本願寺を手掛けてその才能は高く評価されたとのことです。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
第50番玄通寺の御朱印も授与されているので、そちらを巡拝してからお伺いした方がベターかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
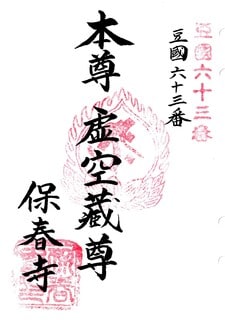
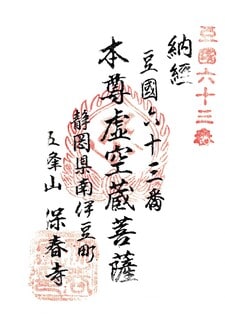
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第64番 金嶽山 慈雲寺(じうんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町下賀茂433
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第27番
授与所:庫裡
南伊豆の名湯、下賀茂温泉にある札所です。
東日本有数の泉温と豊富な湧出量をもつ下賀茂温泉については、→こちらのレポをご覧くださいませ。
『新南伊豆風土記』には「下賀茂の金嶽山 慈雲寺の開創縁起には「永禄年間(1558-1569年)に土地の住民が河原の砂礫のなかに湯舟を作り、自然に湧出する温泉に浸かっていた。」とあり、当山は温泉と深いかかわりをもつことがわかります。
当山の御詠歌は、『わきかえる 湯つぼの中に影すみて 金のみ嶽に月もとうとき』
ここからも、温泉とのかかわりの深さが感じられます。
なお、伊豆八十八ヶ所の多くの札所が下賀茂温泉のまわりに集中しているので、巡拝の折には一度は下賀茂温泉泊まりになるかと思います。
『こころの旅』によると、 慈雲寺の開創年代等は不明ですが当初は慈雲院という真言宗の寺院でした。
一時衰微していましたが、香雲寺の五世仏華為長が再興され現在に至ります。
山内の「岩谷観音」は伊豆横道三十三観音霊場第27番の札所本尊となっています。
『豆州志稿』には「下賀茂村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 初慈雲院ト称シ真言ノ道場也 後久ク廃絶ス 永禄中(1558-1570年)香雲寺五世為長当地に来遊シ 里民ニ謀テ再興ス 此時ヨリ改宗シテ寺号ト為ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 すぐとなりの「伊古奈」の泉源
【写真 下(右)】 参道入口
下賀茂温泉は温泉街の趣きはうすいものの、南伊豆らしい明るい景色のなかをゆったり流れる青野川沿いに、落ち着いたたたずまいをみせています。
青野川と二条川は下賀茂の「銀の湯会館」前で合流し、青野川となって弓ヶ浜に注ぎます。
熱帯植物園下流の「石廊館」から「南楽」にかけての500mほどの青野川沿いに、下賀茂温泉の主だった旅館が集中します。
左岸には「石廊館」と「南楽」、右岸には閉館した「伊古奈」(→入湯レポ)と「河内屋」。
慈雲寺は閉館した老舗旅館「伊古奈」のすぐ隣にあり、「伊古奈」は数本の自家源泉を持っていましたから、やはり慈雲寺は温泉とゆかりのふかいお寺なのかと。
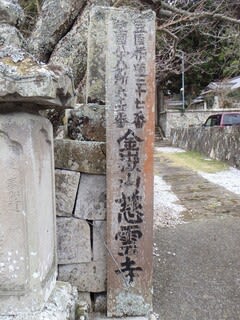

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
参道入口に伊豆八十八ヶ所&伊豆横道三十三観音の札所標。正面門柱の先に本堂が見えます。
背後に山を背負う寺院らしい立地です。
手前に六地蔵、正面に本堂、左手に水子地蔵尊のお堂があります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂

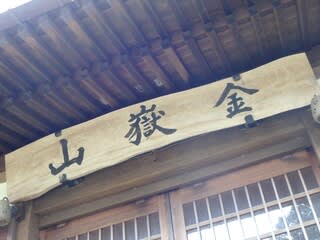
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は寄棟造銅板葺で小規模な流れ向拝を置いています。
堂宇前面は連子様の意匠で引き締まった印象です。
向拝見上げに山号扁額。


【写真 上(左)】 ガマの守護神
【写真 下(右)】 ガマ地蔵
山内にはあちこちにガマがいます。
こちらはガマにゆかりのあるお寺さんなのでした。
山内掲示類から、そのゆかりをひいてみます。
********
むかしむかし、慈雲寺の本堂裏に池があり、そこに一匹の大きなガマが棲んでおりました。
この大ガマは和尚さんや里人にたいそう親しまれ、大事にされておりました。
ある日、青野川の氾濫でガマは流されてしまい、和尚さんたちはガマの無事を祈りました。
ガマは沼津の千本松原に流れ着き、いつの間にか人に姿を変えていました。
元和二年(1616年)●月二十六日、慈雲寺の和尚さんが小田原の最乗寺に出かけた帰り、三島土狩の松岡庄平と名乗る男に出会いました。
男が言うには「わたくしは以前お宅の池でお世話になっていたガマでございます。毎朝晩に和尚さまのありがたいお経をお聞きし功徳を得まして、いまはこのとおり人間になることができました。これはこのご恩へのお礼のしるしです。」
と、一領の袈裟を和尚さんに捧げました。
その袈裟は二十五条織りの見事なもので、和尚さんは「それはご奇特なことじゃ」と受け取りました。
和尚さんはこの袈裟を里人に披露し、人の恩に報ゆることの大切さ、有り難さを説かれました。
この袈裟は「ガマの袈裟」といい、いまも本堂に飾られています。
********
本堂向かって右手の堂前にはひときわおおきなガマが鎮座し、まわりを小ガマがとりまいています。
「平成十九年三月、慈雲寺第十九世和尚は結制修行を終えて大和尚の称号を戴きました。
これを記念して、法恩の伝承にならい、そして慈雲寺の守り神として鎮座されました。」
という掲示があるので、この大ガマが守り神なのかもしれません。
参道入口には、ガマ地蔵も御座されます。
慈雲寺のガマは畜生道?から功徳を積んで人間となり、恩返しをしたことでついに菩薩(地蔵菩薩)になったことになります。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
伊豆横道三十三観音霊場の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
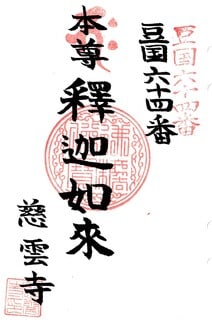
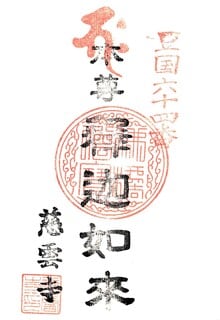
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
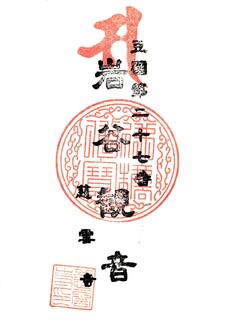
■ 第65番 田村山 最福寺(さいふくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町上賀茂301
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:第53番寶徳院
下賀茂温泉の北側、上賀茂地区にある札所寺院です。
『こころの旅』によると明応九年(1500年)泉屋鉄眼の開基により草創された律院で、当初は普済庵と号しました。
のちに、田村将軍の末孫・田村正広が来山し一宇を建立して田村将軍を祀り、信仰厚かった観音像を本尊として奉安し中興開基、大安寺三世の祖庵孝孫を中興開山として律を改め曹洞宗に改宗し、寺号も最福寺と改めて現在に至ります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標
上賀茂集落内、一条川に近いところにあり、南伊豆の札所のなかではわりに開けた立地です。
「上賀茂」のバス停脇から山手に向かって参道が伸びています。
右手に寺号標、左手に「不許葷酒入山門」の戒壇石という禅刹らしい構え。


【写真 上(左)】 冠木門
【写真 下(右)】 参道階段
その先に石造の冠木門。さらに進むと参道階段とその先に山門。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門?で、山号扁額を掲げています。大棟に鯱戈(しゃちほこ)を配した存在感ある門です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
正面が本堂。左手前に鐘楼。
鐘楼の方形の屋根と本堂の寄棟造の屋根が意匠的によくバランスしています。
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱のないシンプルつくり。
向拝見上げに寺号扁額を掲げています。
現況無住のようですが、山内はすっきりと手入れされています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
御朱印は第53番寶徳院にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第66番 波次磯山 岩殿寺(がんでんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町岩殿120
真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理
現地由緒書および『こころの旅』によると、貞元二年(976年)に僧継雲によって創建。
文永十年(1273年)阿闍梨丁快によって中興され、御本尊薬師如来像(ないし御前立)は丁快の作と伝わります。
往時は大寺と伝わり北條氏の庇護を受けて隆盛しましたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原討伐の際、戦場となり炎上、北條氏の庇護も失い衰退の途をたどりました。
『豆州志稿』には「岩殿村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊不動薬師 創建不詳 僧継運ヲ開祖トス 此寺往昔大ナリ 今大門ノ地名存ス 文永十年(1273年)阿闍梨丁快薬師前立ノ佛像ヲ造ル 寺内ニ薬師堂アリ 寺後山上ノ岩窟ニカケノ御堂ト云アリタリ 今柱二三本残ル」とあります。
-------------------
県道121号南伊豆松崎線は下賀茂と松崎を結びますが、蛇石峠を越えるため、ふつうは海岸沿いの国道136号(マーガレットライン)が選択され、交通量は少ないです。
岩殿寺はこの県道121号からさらに枝道に入ったところにあり、一般観光客はまず訪れない立地です。
伊豆八十八ヶ所でもっとも奥深く感じる札所は南伊豆~松崎にかけてで、この岩殿寺もそんなイメージの札所です。
ただし、対面に岩殿寺窯があるので、焼き物好きは足を運ぶかもしれません。


【写真 上(左)】 岩殿寺窯
【写真 下(右)】 参道入口


【写真 上(左)】 正面堂宇と庫裡?
【写真 下(右)】 山内
寺号標も山門もないシンプルな参道。
正面に寄棟造桟瓦造の堂宇と左手に宝形造のお堂があり、左手お堂の方に寺号扁額が掲げられているのでこちらが本堂かもしれません。


【写真 上(左)】 左手お堂
【写真 下(右)】 扁額
現地由緒書に、安置佛として薬師如来、十二神将、不動明王尊、地蔵菩薩、宗祖 弘法大師とあるので、どちらかの堂宇は不動堂、地蔵堂あるいは大師堂かもしれません。
御朱印はお堂向拝に貼り出されていた寺役さんの電話番号に連絡したら、しばらくしておいでになり、無事拝受できました。ありがとうございました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

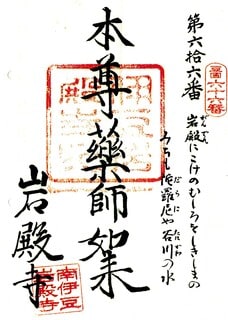
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第67番 太梅山 安楽寺(あんらくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町上小野683
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:寺役管理だが、本堂内に印判あり
現地本堂内掲示および『こころの旅』によると、かつては真言宗で、法境山祥安寺と号しました
弘治元年(1555年)に現地に移転し、曹洞院(第52番札所)四世の花翁宗菊を(中興)開山として曹洞宗に改めいまに至ります。
『豆州志稿』には「上小野村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊釋迦 初真言宗ニシテ上安寺ト号シ 字寶境ニ在リキ 弘治元年(1555年)現地ニ移シテ改称シ曹洞宗トナル」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 六地蔵と参道
静岡県道119号下田南伊豆線沿いにありますが、こちらも交通量はすくなく奥まった感じの立地です。
変則の冠木門。その先右手に六地蔵。正面に参道階段と本堂が見えます。
背後に竹林を背負う寺院らしいたたずまい。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 札所板
寄棟造銅板葺で向拝を付設しています。
平成7年の改築なのでまだ新しい感じを残しています。
向拝まわりはシンプルですが、向拝両側の花頭窓とその下の青紅葉の絵がいいアクセントになっています。

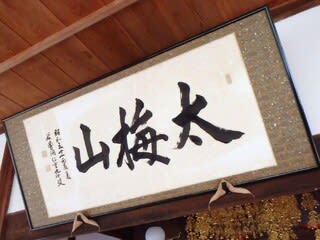
【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 堂内扁額
御朱印は本堂内に印判がありましたので、そちらをセルフで押印しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
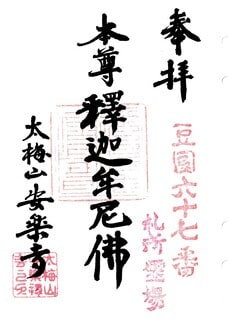
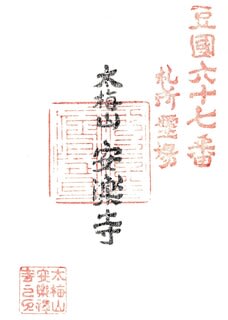
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第68番 廬岳山 東林寺(とうりんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町下小野414-1
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理(筆者は第61番法泉寺にて拝受)
『こころの旅』『豆州志稿』によると、文録年間(1592-1596年)に僧龍山寺廬岳に創立された小庵でしたが、慶長五年(1600年)現地に遷り、曹洞院八世巨雄天策を開山とし、堂宇を建立して曹洞宗寺院となりました。
伊豆国守・通國書写の大般若経を所蔵します。
『豆州志稿』には「下小野村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊薬師 文録中(1592-1596年)僧龍山寺廬岳ニ創立 小庵ナリ 慶長五年(1600年)現地ニ移シテ寺ト為シ 曹洞院八世天策ヲ開山トス 國司通國(按スルニ二子世系不詳 或ハ曰源頼盛ハ醍醐天皇ノ後裔 西宮左大臣源高明公六世ノ孫 源世雅ノ二男ナリ 伊豆守ト為ル 通國ハ大江音人六世ノ孫 掃部頭大江佐國ノ次男ナリ 大治中(1126-1131年)任伊豆國司ト)書スル大般若経ヲ蔵ム 妙楼閣在寺観世音ヲ安ス 明治十二年建立ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 地蔵尊
青野川に沿って走る県道121号南伊豆松崎線の下小野の集落にあります。
真新しい参道階段と、その右手前に寺号標。
階段脇には地蔵尊が並びます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
階段を昇った正面が竹林を背負う本堂。
寄棟造銅板葺で、中央に向拝を附設しています。
水引虹梁両端の木鼻は角材、頭貫上もシンプルな造作ですが、水引虹梁中備に寺号扁額を掲げ、直上に二軒の平行垂木を置くいささか変わったつくり。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
堂宇全容はシンメトリで端正な印象です。
御朱印は、筆者は第61番法泉寺にて拝受というメモが残っていますが、公式Webでは寺役さん授与となっています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
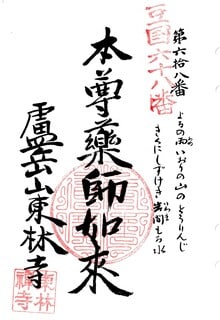
専用納経帳
■ 第69番 塔峰山 常石寺(じょうせきじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町蛇石80
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』『豆州志稿』によると、慶長七年(1602年)に慈雲寺(第64番札所)四世の関翁全鐵により開創と伝わります。
『豆州志稿』には「東峯山常石寺 蛇石村 曹洞宗 下賀茂慈雲寺末 本尊薬師 慶長七年(1602年)慈雲寺四世全鐵創立ス」とあります。
-------------------
県道121号の南伊豆町側の最奥で、蛇石峠を越えた松崎側には数箇所の札所がありますが、海側を走る国道136号(マーガレットライン)沿いにも札所があり、ルート選択に悩むところです。
ただし、いずれにしてもこのあたりは1回の巡拝でコンプリートは困難なので、最低でも国道136号(マーガレットライン)経由1回、県道121号経由1回の旅程が必要かと思います。(西伊豆や南伊豆で連泊するなら話は別ですが・・・)


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 石仏群
県道121号が青野川を離れ、蛇石峠の登りにかかるヘアピンカーブの手前山側にあります。
苔むした参道階段。本堂裏に小高い小山を背負う雰囲気のあるアプローチ。
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱、扁額ともにありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
年末の大掃除でしょうか。
開け放たれた本堂の縁側に御住職が座って居られたので、御朱印をお願いすると、快く授与いただけました。
お話しがはずんだ記憶がありますが、内容についてはよく覚えていません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
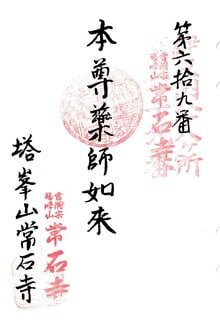
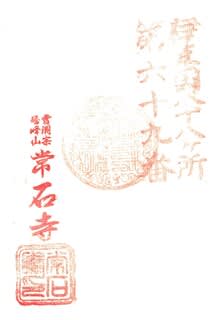
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第70番 医王山 金泉寺(きんせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町子浦901
浄土宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理
『こころの旅』『豆州志稿』によると、正保元年(1644年)に僧超傳(西林寺五世玄譽ノ徒弟)により創立された浄土宗寺院です。
『豆州志稿』には「子浦村 浄土宗 子浦村西林寺末 本尊薬師 正保元年(1644年)僧超傳(西林寺五世玄譽ノ徒弟)創立ス」とあります。
-------------------
こちらは駐車場がなく、狭い路地に面して石塀に囲まれているので、境内乗り入れができず寺前は無余地駐車となります。(冠木門をくぐった先に若干のスペースはありますが、冠木門は狭くて通り抜けできず)
港町は道が狭いうえに車の出入りが激しいので路上駐車に対して厳しいですし、一般車用のパーキングもほとんどありません。
スーパーなどの商業施設もなきに等しく、駐車は本当に難儀します。
筆者は連れも免許を持っているのでなんとかなりますが、一人での車参拝はきびしい札所のひとつです。


【写真 上(左)】 子浦あたりの海岸
【写真 下(右)】 冠木門
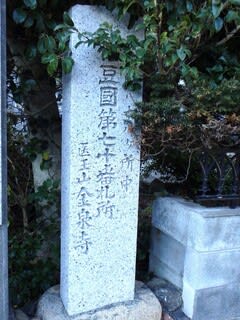

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
路地に面して立派な冠木門を構えています。その横に真新しい札所標。
山内はこぢんまりとしてすぐに本堂です。
寄棟造銅板葺で向拝柱はなく、格子戸のうえに山号扁額。
全体に端正で引き締まったイメージのある本堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 寺号板


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
浄土宗寺院ですが、御本尊・札所本尊ともに薬師如来となっています。
こちらは無住で寺役管理です。
当日は連絡がとれず、御朱印は後日郵送をいただきました。
旧本寺である子浦の西林寺は伊豆国(下田南伊豆)七福神の毘沙門天、同じ子浦にある臨済宗建長寺派の潮音寺は伊豆横道三十三観音霊場第32番の札所で、いずれも御朱印を授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
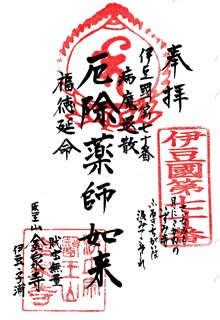

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第71番 翁生山 普照寺(ふしょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町伊浜1289-1
真言宗
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第33番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(寿老人)
授与所:庫裡
18を数えた南伊豆町の札所もこちらで最後となり、以降は西伊豆に移ります。
『こころの旅』『豆州志稿』『霊場めぐり』によると、延暦十二年(793年)に地元の漁師の網にかかった観音像を小庵に祀ったのが草創で、 寛正年間(1460-1466年)に僧盛賢が再興しました。
当初は僧泰庵(後醍醐帝の時代の人)が書写した大般若経三百巻を蔵しました。
『豆州志稿』には「伊濱村 真言宗 紀州高野山高室院末 本尊正観世音不動 元観音堂ノ庵也 後普照寺ノ号ヲ冒ラシテ高野山ニ隷ス 寛正中(1460-1466年)僧盛賢再興ス」とあります。
御本尊の観音像には粟にまつわる伝説が伝わります。
詳細は↑の『豆州志稿』に記されていますが、概略は以下のとおりです。
『伊豆峯記』によると、聖武帝の御代(701- 756年)遠江國司藤原朝臣某の家臣・磯崎八郎吉富は当地・伊浜を領していました。
吉富は生来観音信仰が篤く、常々観音像を得ることを願っていましたが、ある晩夢のお告げにより従者の一角とともに海岸で良材を得ました。
このとき当地を訪れていた行基は、これを聞いてこの良材から観音像を彫りだし、吉富に与えました。
吉富の死後、子の吉勝から数代後、従者の子は一角の名を継いでいましたが、ある番夢告を受けて件の観音像を海中に投じ、相州に出奔しました。
20年後、伊浜の漁夫がこの観音像を網で引き揚げ、村人たちは一宇を建ててこの尊像を安置しました。
相州にいた一角はこれを聞いて自らが海中に投じた観音像と確信し、いそぎ伊浜に戻ってみると、栄えていた主人の磯崎家はまったく衰えていました。
一角は涙を流し、すぐさま堂容を整えてひたすら誦経をつづけると、ある晩霊夢を授かりました。
観音様が粟七茎を授けられていわく、東方の蛇野の地に赴けばここに馬がいるので、この馬に乗り馬の趣くままにこの粟を撒きなさいとのこと。
一角はすぐさま観音様のお告げのとおり粟を撒くと、耕してもいないのにみるみる粟が育って大豊作となり、これが年々つづいて一角は長者となり「粟長者」、この地蛇野は「長者ヶ原」と称されました。
しかし、一角の子孫は驕奢を極めたため、ついに没落してしまったとのことです。
『こころの旅』によると、近年、数百年昔の粟が発見され植物試験所で発芽に成功。
「長者ヶ原」の粟が蘇ったと話題になったそうです。
-------------------


【写真 上(左)】 伊浜漁港
【写真 下(右)】 参道入口
子浦から雲見にかけての国道136号線は海岸線を離れ、山あいの高みを走ります。
なので、途中の集落は国道からアプローチ道に入り、山肌を縫って降りていくかたちとなります。
ここ伊浜の集落もそんなアプローチです。
普照寺は漁港まで降りきらない高台にあります。
陽のながい西伊豆らしい明るい雰囲気のお寺さまです。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 札所板
西伊豆では比較的規模の大きい寺院で、伊豆横道三十三観音霊場第33番の結願所、および伊豆国(下田南伊豆)七福神の寿老人霊場となっています。
山肌にあるので山内の傾斜がきつく、上下ふたつに分かれた参道階段を昇っていきます。
参道入口には3つの札所の札所板が掲げられています。


【写真 上(左)】 踊り場からの本堂
【写真 下(右)】 普照寺からの眺め
踊り場には一躯のお地蔵さま。さらに昇ると正面が本堂です。
本堂はおそらく寄棟造銅板で向拝柱はありません。
正面桟唐戸と両脇の花頭窓がいいコントラストをみせ、見上げには山号扁額が掲げられています。
高台にあるので、眼下に西伊豆の海を望めます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
山内掲示には以下のとおりありました。
・聖観世音菩薩(通称長寿観音) 延暦十二年(793年)漁師の網に掛り海中より出現す
・大般若経 南北朝時代 → 県の有形文化財です
・梵鐘 寛正五年、室町時代 → 県の有形文化財です
・鰐口 元応二年、鎌倉時代 → 県の有形文化財です
なお、行基作と伝わる御本尊の観世音菩薩像は、町指定の文化財に指定されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
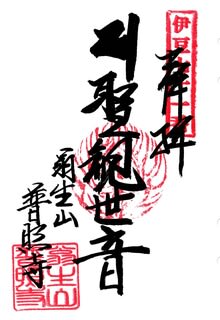
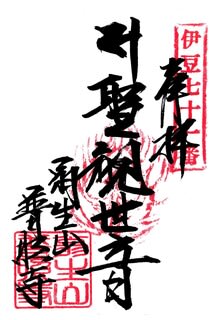
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
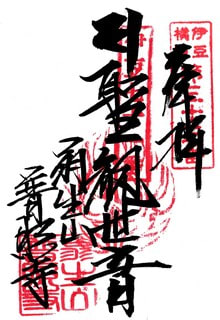
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10へつづく。
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI/杏里
→ ■ 杏里の名バラード20曲!
■ 片恋日記 - 中村舞子
→ ■ 中村舞子の名バラード20曲
■ 夏をかさねて - 今井美樹
→ ■ 今井美樹の名バラード25曲!
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10へつづく。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第62番 石屏山 法伝寺(ほうでんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町二條458
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:第58番正眼寺にて
第61番法泉寺から下賀茂に向けて進んだところにあります。
国道136号線から1本南に入ったところですが、国道からも見えます。
開創当初は真言宗で大窪というところにありました。
寛永年中(1624-1644年)松屋祝公和尚が現在地に遷し、臨済宗建長寺派に改めました。
『豆州志稿』には「二條村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 昔大窪ニ在リ 松屋和尚今ノ地ニ移ス 寛永(1624-1644年)の頃ナリ 初真言宗ナリ 松屋改宗ス 或作寶傳寺」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 六地蔵
このあたりの国道136号線は川沿いの水田地帯を辿ります。
南伊豆らしい陽光明るくおだやかな風景です。
国道136号線から枝道に入り、小橋で川を渡った先が参道です。
参道入口右手に札所標、左手には六地蔵。
六地蔵の上手には祠が見え、こちらは地主神かもしれません。


【写真 上(左)】 地主神?の祠
【写真 下(右)】 山内
山内正面に入母屋造銅板葺の本堂と右手に庫裡を配し、L字型の堂宇配置です。
堂前は校庭さながらに整地され、なんとなく分校のようです。

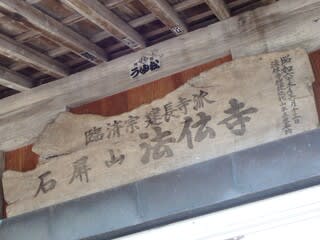
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
本堂に向拝柱はなく、全面サッシュ扉のシンプルな堂宇。
御本尊、札所本尊ともに聖観世音菩薩で、おそらく同一のお像かと思われます。
現在無住につき、御朱印は第58番正眼寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
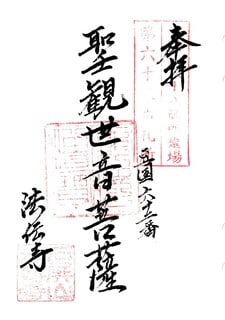
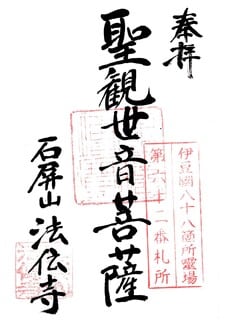
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第63番 五峰山 保春寺(ほしゅんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町加納177-1
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡(第50番玄通寺も)
下賀茂の街並みに入ったところにある曹洞宗寺院です。
開基の山本長門守道政が永正四年(1507年)に没しているので、それ以前の草創とみられています。
開山は僧・法山(天文十一年(1542年)寂)。
草創当時は真言宗で、慶安二年(1649年)太梅寺四世法山秀禅和尚により曹洞宗に改宗されたと伝わります。
『豆州志稿』には「加納村 曹洞宗 横川太梅寺末 本尊虚空蔵 開山法山和尚(天文十一年(1542年)化ス) 山本長門守道政(永正四年(1507年)死ス)ヲ開基トス 初真言宗也 慶安二年(1649年)太梅寺四世秀禅改宗ス 地頭清水康英ノ喜捨文を蔵ム」とあります。
-------------------
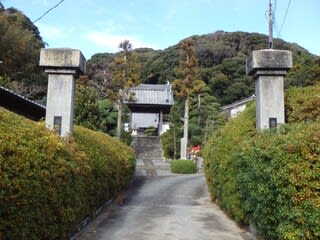

【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道と山門
国道136号から北側に入った山裾にあります。
よく整備された明るい雰囲気の寺院で、落ち着いた参拝ができます。
すこし進むと禅刹らしい「不許葷酒入山門」の石標。
数段の石段の先に切妻屋根桟瓦葺四脚門の均整のとれた山門。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 山内
小高い山を背後に背負った落ち着きのよい山内。
左手手前から鐘楼、鎮守天満宮、正面に本堂とつづきます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
入母屋造桟瓦葺で大棟に「五峰山」。隅棟の貼り出しが大きく存在感ある堂宇です。
向拝柱はなく格子扉メインのシンプルな身舎。
見上げに扁額はなく、桐紋入りの蟇股が置かれています。
開けていただいた本堂内は見上げに山号扁額、金襴幕と複数の天蓋が懸かる華やかなものでした。
御本尊および札所本尊は虚空蔵菩薩。
この霊場では、第45番向陽院と当山の2つの札所本尊が虚空蔵菩薩です。
禅刹、ことに曹洞宗では虚空蔵菩薩が御本尊の寺院はかなりあります。
十三仏、 十二支守り本尊の一尊でもありますが、御真言は「ノウボウ アキャシャキャラバヤ オンアリキャ マリボリソワカ」とかなり複雑です。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 鐘楼と天満宮
鎮守の天満宮は一間社流造桟瓦葺。鮮やかな朱色の水引虹梁が印象的です。
手前に狛犬一対。向拝見上げに「天満宮」の扁額。
一間社流造は覆屋で、なかに本殿が安置されています。
『こころの旅』によると、本殿には「伊豆の小市」と呼ばれた鈴木市五郎の見事な彫刻が施されているようですが、うかつにもチェックしわすれました。
鈴木市五郎は当地生まれの宮大工で、江戸で修業し、築地本願寺を手掛けてその才能は高く評価されたとのことです。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
第50番玄通寺の御朱印も授与されているので、そちらを巡拝してからお伺いした方がベターかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
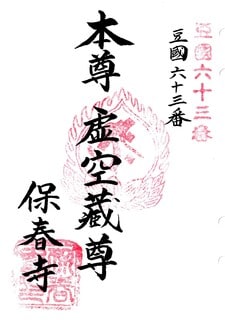
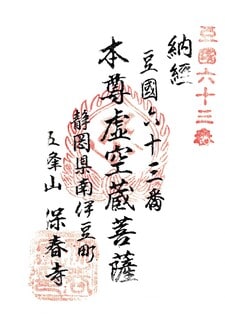
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第64番 金嶽山 慈雲寺(じうんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町下賀茂433
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第27番
授与所:庫裡
南伊豆の名湯、下賀茂温泉にある札所です。
東日本有数の泉温と豊富な湧出量をもつ下賀茂温泉については、→こちらのレポをご覧くださいませ。
『新南伊豆風土記』には「下賀茂の金嶽山 慈雲寺の開創縁起には「永禄年間(1558-1569年)に土地の住民が河原の砂礫のなかに湯舟を作り、自然に湧出する温泉に浸かっていた。」とあり、当山は温泉と深いかかわりをもつことがわかります。
当山の御詠歌は、『わきかえる 湯つぼの中に影すみて 金のみ嶽に月もとうとき』
ここからも、温泉とのかかわりの深さが感じられます。
なお、伊豆八十八ヶ所の多くの札所が下賀茂温泉のまわりに集中しているので、巡拝の折には一度は下賀茂温泉泊まりになるかと思います。
『こころの旅』によると、 慈雲寺の開創年代等は不明ですが当初は慈雲院という真言宗の寺院でした。
一時衰微していましたが、香雲寺の五世仏華為長が再興され現在に至ります。
山内の「岩谷観音」は伊豆横道三十三観音霊場第27番の札所本尊となっています。
『豆州志稿』には「下賀茂村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 初慈雲院ト称シ真言ノ道場也 後久ク廃絶ス 永禄中(1558-1570年)香雲寺五世為長当地に来遊シ 里民ニ謀テ再興ス 此時ヨリ改宗シテ寺号ト為ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 すぐとなりの「伊古奈」の泉源
【写真 下(右)】 参道入口
下賀茂温泉は温泉街の趣きはうすいものの、南伊豆らしい明るい景色のなかをゆったり流れる青野川沿いに、落ち着いたたたずまいをみせています。
青野川と二条川は下賀茂の「銀の湯会館」前で合流し、青野川となって弓ヶ浜に注ぎます。
熱帯植物園下流の「石廊館」から「南楽」にかけての500mほどの青野川沿いに、下賀茂温泉の主だった旅館が集中します。
左岸には「石廊館」と「南楽」、右岸には閉館した「伊古奈」(→入湯レポ)と「河内屋」。
慈雲寺は閉館した老舗旅館「伊古奈」のすぐ隣にあり、「伊古奈」は数本の自家源泉を持っていましたから、やはり慈雲寺は温泉とゆかりのふかいお寺なのかと。
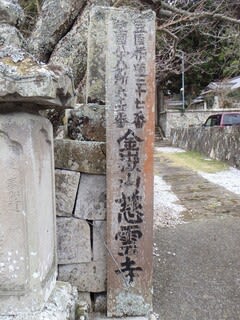

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
参道入口に伊豆八十八ヶ所&伊豆横道三十三観音の札所標。正面門柱の先に本堂が見えます。
背後に山を背負う寺院らしい立地です。
手前に六地蔵、正面に本堂、左手に水子地蔵尊のお堂があります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂

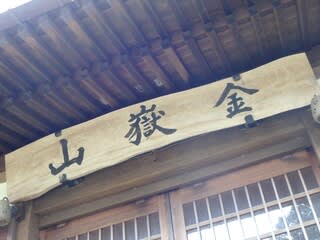
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は寄棟造銅板葺で小規模な流れ向拝を置いています。
堂宇前面は連子様の意匠で引き締まった印象です。
向拝見上げに山号扁額。


【写真 上(左)】 ガマの守護神
【写真 下(右)】 ガマ地蔵
山内にはあちこちにガマがいます。
こちらはガマにゆかりのあるお寺さんなのでした。
山内掲示類から、そのゆかりをひいてみます。
********
むかしむかし、慈雲寺の本堂裏に池があり、そこに一匹の大きなガマが棲んでおりました。
この大ガマは和尚さんや里人にたいそう親しまれ、大事にされておりました。
ある日、青野川の氾濫でガマは流されてしまい、和尚さんたちはガマの無事を祈りました。
ガマは沼津の千本松原に流れ着き、いつの間にか人に姿を変えていました。
元和二年(1616年)●月二十六日、慈雲寺の和尚さんが小田原の最乗寺に出かけた帰り、三島土狩の松岡庄平と名乗る男に出会いました。
男が言うには「わたくしは以前お宅の池でお世話になっていたガマでございます。毎朝晩に和尚さまのありがたいお経をお聞きし功徳を得まして、いまはこのとおり人間になることができました。これはこのご恩へのお礼のしるしです。」
と、一領の袈裟を和尚さんに捧げました。
その袈裟は二十五条織りの見事なもので、和尚さんは「それはご奇特なことじゃ」と受け取りました。
和尚さんはこの袈裟を里人に披露し、人の恩に報ゆることの大切さ、有り難さを説かれました。
この袈裟は「ガマの袈裟」といい、いまも本堂に飾られています。
********
本堂向かって右手の堂前にはひときわおおきなガマが鎮座し、まわりを小ガマがとりまいています。
「平成十九年三月、慈雲寺第十九世和尚は結制修行を終えて大和尚の称号を戴きました。
これを記念して、法恩の伝承にならい、そして慈雲寺の守り神として鎮座されました。」
という掲示があるので、この大ガマが守り神なのかもしれません。
参道入口には、ガマ地蔵も御座されます。
慈雲寺のガマは畜生道?から功徳を積んで人間となり、恩返しをしたことでついに菩薩(地蔵菩薩)になったことになります。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
伊豆横道三十三観音霊場の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
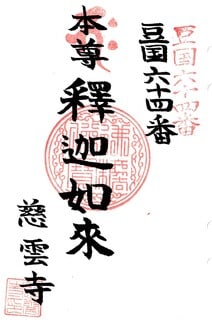
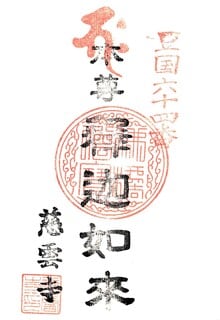
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
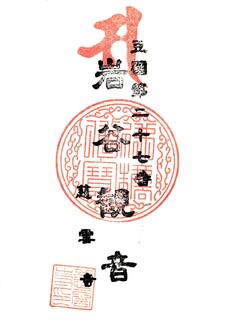
■ 第65番 田村山 最福寺(さいふくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町上賀茂301
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:第53番寶徳院
下賀茂温泉の北側、上賀茂地区にある札所寺院です。
『こころの旅』によると明応九年(1500年)泉屋鉄眼の開基により草創された律院で、当初は普済庵と号しました。
のちに、田村将軍の末孫・田村正広が来山し一宇を建立して田村将軍を祀り、信仰厚かった観音像を本尊として奉安し中興開基、大安寺三世の祖庵孝孫を中興開山として律を改め曹洞宗に改宗し、寺号も最福寺と改めて現在に至ります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標
上賀茂集落内、一条川に近いところにあり、南伊豆の札所のなかではわりに開けた立地です。
「上賀茂」のバス停脇から山手に向かって参道が伸びています。
右手に寺号標、左手に「不許葷酒入山門」の戒壇石という禅刹らしい構え。


【写真 上(左)】 冠木門
【写真 下(右)】 参道階段
その先に石造の冠木門。さらに進むと参道階段とその先に山門。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門?で、山号扁額を掲げています。大棟に鯱戈(しゃちほこ)を配した存在感ある門です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
正面が本堂。左手前に鐘楼。
鐘楼の方形の屋根と本堂の寄棟造の屋根が意匠的によくバランスしています。
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱のないシンプルつくり。
向拝見上げに寺号扁額を掲げています。
現況無住のようですが、山内はすっきりと手入れされています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
御朱印は第53番寶徳院にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第66番 波次磯山 岩殿寺(がんでんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町岩殿120
真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理
現地由緒書および『こころの旅』によると、貞元二年(976年)に僧継雲によって創建。
文永十年(1273年)阿闍梨丁快によって中興され、御本尊薬師如来像(ないし御前立)は丁快の作と伝わります。
往時は大寺と伝わり北條氏の庇護を受けて隆盛しましたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原討伐の際、戦場となり炎上、北條氏の庇護も失い衰退の途をたどりました。
『豆州志稿』には「岩殿村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊不動薬師 創建不詳 僧継運ヲ開祖トス 此寺往昔大ナリ 今大門ノ地名存ス 文永十年(1273年)阿闍梨丁快薬師前立ノ佛像ヲ造ル 寺内ニ薬師堂アリ 寺後山上ノ岩窟ニカケノ御堂ト云アリタリ 今柱二三本残ル」とあります。
-------------------
県道121号南伊豆松崎線は下賀茂と松崎を結びますが、蛇石峠を越えるため、ふつうは海岸沿いの国道136号(マーガレットライン)が選択され、交通量は少ないです。
岩殿寺はこの県道121号からさらに枝道に入ったところにあり、一般観光客はまず訪れない立地です。
伊豆八十八ヶ所でもっとも奥深く感じる札所は南伊豆~松崎にかけてで、この岩殿寺もそんなイメージの札所です。
ただし、対面に岩殿寺窯があるので、焼き物好きは足を運ぶかもしれません。


【写真 上(左)】 岩殿寺窯
【写真 下(右)】 参道入口


【写真 上(左)】 正面堂宇と庫裡?
【写真 下(右)】 山内
寺号標も山門もないシンプルな参道。
正面に寄棟造桟瓦造の堂宇と左手に宝形造のお堂があり、左手お堂の方に寺号扁額が掲げられているのでこちらが本堂かもしれません。


【写真 上(左)】 左手お堂
【写真 下(右)】 扁額
現地由緒書に、安置佛として薬師如来、十二神将、不動明王尊、地蔵菩薩、宗祖 弘法大師とあるので、どちらかの堂宇は不動堂、地蔵堂あるいは大師堂かもしれません。
御朱印はお堂向拝に貼り出されていた寺役さんの電話番号に連絡したら、しばらくしておいでになり、無事拝受できました。ありがとうございました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

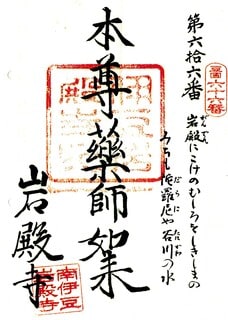
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第67番 太梅山 安楽寺(あんらくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町上小野683
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:寺役管理だが、本堂内に印判あり
現地本堂内掲示および『こころの旅』によると、かつては真言宗で、法境山祥安寺と号しました
弘治元年(1555年)に現地に移転し、曹洞院(第52番札所)四世の花翁宗菊を(中興)開山として曹洞宗に改めいまに至ります。
『豆州志稿』には「上小野村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊釋迦 初真言宗ニシテ上安寺ト号シ 字寶境ニ在リキ 弘治元年(1555年)現地ニ移シテ改称シ曹洞宗トナル」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 六地蔵と参道
静岡県道119号下田南伊豆線沿いにありますが、こちらも交通量はすくなく奥まった感じの立地です。
変則の冠木門。その先右手に六地蔵。正面に参道階段と本堂が見えます。
背後に竹林を背負う寺院らしいたたずまい。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 札所板
寄棟造銅板葺で向拝を付設しています。
平成7年の改築なのでまだ新しい感じを残しています。
向拝まわりはシンプルですが、向拝両側の花頭窓とその下の青紅葉の絵がいいアクセントになっています。

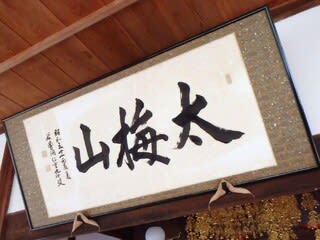
【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 堂内扁額
御朱印は本堂内に印判がありましたので、そちらをセルフで押印しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
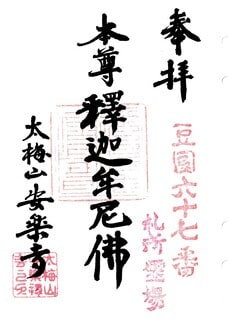
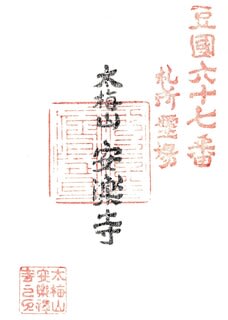
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第68番 廬岳山 東林寺(とうりんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町下小野414-1
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理(筆者は第61番法泉寺にて拝受)
『こころの旅』『豆州志稿』によると、文録年間(1592-1596年)に僧龍山寺廬岳に創立された小庵でしたが、慶長五年(1600年)現地に遷り、曹洞院八世巨雄天策を開山とし、堂宇を建立して曹洞宗寺院となりました。
伊豆国守・通國書写の大般若経を所蔵します。
『豆州志稿』には「下小野村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊薬師 文録中(1592-1596年)僧龍山寺廬岳ニ創立 小庵ナリ 慶長五年(1600年)現地ニ移シテ寺ト為シ 曹洞院八世天策ヲ開山トス 國司通國(按スルニ二子世系不詳 或ハ曰源頼盛ハ醍醐天皇ノ後裔 西宮左大臣源高明公六世ノ孫 源世雅ノ二男ナリ 伊豆守ト為ル 通國ハ大江音人六世ノ孫 掃部頭大江佐國ノ次男ナリ 大治中(1126-1131年)任伊豆國司ト)書スル大般若経ヲ蔵ム 妙楼閣在寺観世音ヲ安ス 明治十二年建立ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 地蔵尊
青野川に沿って走る県道121号南伊豆松崎線の下小野の集落にあります。
真新しい参道階段と、その右手前に寺号標。
階段脇には地蔵尊が並びます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
階段を昇った正面が竹林を背負う本堂。
寄棟造銅板葺で、中央に向拝を附設しています。
水引虹梁両端の木鼻は角材、頭貫上もシンプルな造作ですが、水引虹梁中備に寺号扁額を掲げ、直上に二軒の平行垂木を置くいささか変わったつくり。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
堂宇全容はシンメトリで端正な印象です。
御朱印は、筆者は第61番法泉寺にて拝受というメモが残っていますが、公式Webでは寺役さん授与となっています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
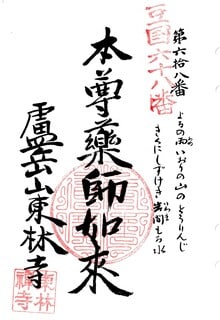
専用納経帳
■ 第69番 塔峰山 常石寺(じょうせきじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町蛇石80
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』『豆州志稿』によると、慶長七年(1602年)に慈雲寺(第64番札所)四世の関翁全鐵により開創と伝わります。
『豆州志稿』には「東峯山常石寺 蛇石村 曹洞宗 下賀茂慈雲寺末 本尊薬師 慶長七年(1602年)慈雲寺四世全鐵創立ス」とあります。
-------------------
県道121号の南伊豆町側の最奥で、蛇石峠を越えた松崎側には数箇所の札所がありますが、海側を走る国道136号(マーガレットライン)沿いにも札所があり、ルート選択に悩むところです。
ただし、いずれにしてもこのあたりは1回の巡拝でコンプリートは困難なので、最低でも国道136号(マーガレットライン)経由1回、県道121号経由1回の旅程が必要かと思います。(西伊豆や南伊豆で連泊するなら話は別ですが・・・)


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 石仏群
県道121号が青野川を離れ、蛇石峠の登りにかかるヘアピンカーブの手前山側にあります。
苔むした参道階段。本堂裏に小高い小山を背負う雰囲気のあるアプローチ。
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱、扁額ともにありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
年末の大掃除でしょうか。
開け放たれた本堂の縁側に御住職が座って居られたので、御朱印をお願いすると、快く授与いただけました。
お話しがはずんだ記憶がありますが、内容についてはよく覚えていません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
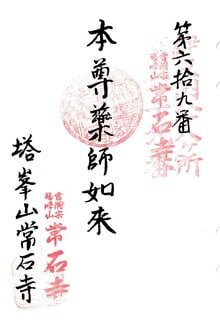
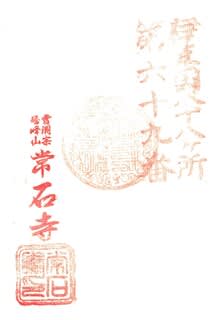
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第70番 医王山 金泉寺(きんせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町子浦901
浄土宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理
『こころの旅』『豆州志稿』によると、正保元年(1644年)に僧超傳(西林寺五世玄譽ノ徒弟)により創立された浄土宗寺院です。
『豆州志稿』には「子浦村 浄土宗 子浦村西林寺末 本尊薬師 正保元年(1644年)僧超傳(西林寺五世玄譽ノ徒弟)創立ス」とあります。
-------------------
こちらは駐車場がなく、狭い路地に面して石塀に囲まれているので、境内乗り入れができず寺前は無余地駐車となります。(冠木門をくぐった先に若干のスペースはありますが、冠木門は狭くて通り抜けできず)
港町は道が狭いうえに車の出入りが激しいので路上駐車に対して厳しいですし、一般車用のパーキングもほとんどありません。
スーパーなどの商業施設もなきに等しく、駐車は本当に難儀します。
筆者は連れも免許を持っているのでなんとかなりますが、一人での車参拝はきびしい札所のひとつです。


【写真 上(左)】 子浦あたりの海岸
【写真 下(右)】 冠木門
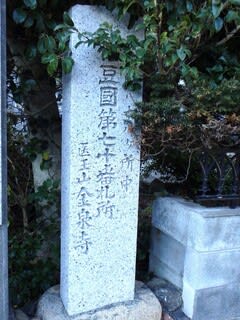

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
路地に面して立派な冠木門を構えています。その横に真新しい札所標。
山内はこぢんまりとしてすぐに本堂です。
寄棟造銅板葺で向拝柱はなく、格子戸のうえに山号扁額。
全体に端正で引き締まったイメージのある本堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 寺号板


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
浄土宗寺院ですが、御本尊・札所本尊ともに薬師如来となっています。
こちらは無住で寺役管理です。
当日は連絡がとれず、御朱印は後日郵送をいただきました。
旧本寺である子浦の西林寺は伊豆国(下田南伊豆)七福神の毘沙門天、同じ子浦にある臨済宗建長寺派の潮音寺は伊豆横道三十三観音霊場第32番の札所で、いずれも御朱印を授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
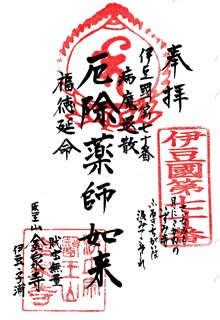

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第71番 翁生山 普照寺(ふしょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町伊浜1289-1
真言宗
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第33番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(寿老人)
授与所:庫裡
18を数えた南伊豆町の札所もこちらで最後となり、以降は西伊豆に移ります。
『こころの旅』『豆州志稿』『霊場めぐり』によると、延暦十二年(793年)に地元の漁師の網にかかった観音像を小庵に祀ったのが草創で、 寛正年間(1460-1466年)に僧盛賢が再興しました。
当初は僧泰庵(後醍醐帝の時代の人)が書写した大般若経三百巻を蔵しました。
『豆州志稿』には「伊濱村 真言宗 紀州高野山高室院末 本尊正観世音不動 元観音堂ノ庵也 後普照寺ノ号ヲ冒ラシテ高野山ニ隷ス 寛正中(1460-1466年)僧盛賢再興ス」とあります。
御本尊の観音像には粟にまつわる伝説が伝わります。
詳細は↑の『豆州志稿』に記されていますが、概略は以下のとおりです。
『伊豆峯記』によると、聖武帝の御代(701- 756年)遠江國司藤原朝臣某の家臣・磯崎八郎吉富は当地・伊浜を領していました。
吉富は生来観音信仰が篤く、常々観音像を得ることを願っていましたが、ある晩夢のお告げにより従者の一角とともに海岸で良材を得ました。
このとき当地を訪れていた行基は、これを聞いてこの良材から観音像を彫りだし、吉富に与えました。
吉富の死後、子の吉勝から数代後、従者の子は一角の名を継いでいましたが、ある番夢告を受けて件の観音像を海中に投じ、相州に出奔しました。
20年後、伊浜の漁夫がこの観音像を網で引き揚げ、村人たちは一宇を建ててこの尊像を安置しました。
相州にいた一角はこれを聞いて自らが海中に投じた観音像と確信し、いそぎ伊浜に戻ってみると、栄えていた主人の磯崎家はまったく衰えていました。
一角は涙を流し、すぐさま堂容を整えてひたすら誦経をつづけると、ある晩霊夢を授かりました。
観音様が粟七茎を授けられていわく、東方の蛇野の地に赴けばここに馬がいるので、この馬に乗り馬の趣くままにこの粟を撒きなさいとのこと。
一角はすぐさま観音様のお告げのとおり粟を撒くと、耕してもいないのにみるみる粟が育って大豊作となり、これが年々つづいて一角は長者となり「粟長者」、この地蛇野は「長者ヶ原」と称されました。
しかし、一角の子孫は驕奢を極めたため、ついに没落してしまったとのことです。
『こころの旅』によると、近年、数百年昔の粟が発見され植物試験所で発芽に成功。
「長者ヶ原」の粟が蘇ったと話題になったそうです。
-------------------


【写真 上(左)】 伊浜漁港
【写真 下(右)】 参道入口
子浦から雲見にかけての国道136号線は海岸線を離れ、山あいの高みを走ります。
なので、途中の集落は国道からアプローチ道に入り、山肌を縫って降りていくかたちとなります。
ここ伊浜の集落もそんなアプローチです。
普照寺は漁港まで降りきらない高台にあります。
陽のながい西伊豆らしい明るい雰囲気のお寺さまです。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 札所板
西伊豆では比較的規模の大きい寺院で、伊豆横道三十三観音霊場第33番の結願所、および伊豆国(下田南伊豆)七福神の寿老人霊場となっています。
山肌にあるので山内の傾斜がきつく、上下ふたつに分かれた参道階段を昇っていきます。
参道入口には3つの札所の札所板が掲げられています。


【写真 上(左)】 踊り場からの本堂
【写真 下(右)】 普照寺からの眺め
踊り場には一躯のお地蔵さま。さらに昇ると正面が本堂です。
本堂はおそらく寄棟造銅板で向拝柱はありません。
正面桟唐戸と両脇の花頭窓がいいコントラストをみせ、見上げには山号扁額が掲げられています。
高台にあるので、眼下に西伊豆の海を望めます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
山内掲示には以下のとおりありました。
・聖観世音菩薩(通称長寿観音) 延暦十二年(793年)漁師の網に掛り海中より出現す
・大般若経 南北朝時代 → 県の有形文化財です
・梵鐘 寛正五年、室町時代 → 県の有形文化財です
・鰐口 元応二年、鎌倉時代 → 県の有形文化財です
なお、行基作と伝わる御本尊の観世音菩薩像は、町指定の文化財に指定されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
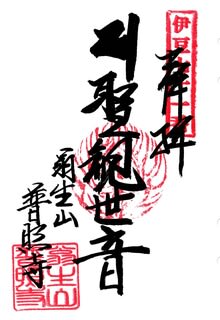
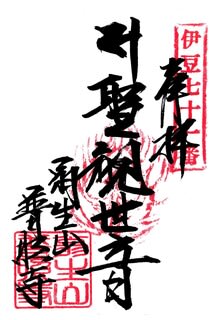
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
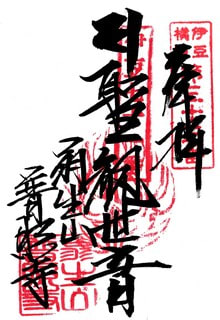
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10へつづく。
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI/杏里
→ ■ 杏里の名バラード20曲!
■ 片恋日記 - 中村舞子
→ ■ 中村舞子の名バラード20曲
■ 夏をかさねて - 今井美樹
→ ■ 今井美樹の名バラード25曲!
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




