関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 箱根湯本温泉 「天成園 別館 飛烟閣」 (閉館、新施設へ)


 箱根湯本温泉 「天成園 別館 飛烟閣」
箱根湯本温泉 「天成園 別館 飛烟閣」※この施設は現存しません。下記はかつての営業時のデータです。
住 所 :神奈川県足柄下郡箱根町湯本682
電 話 :0460-5-5995 (現施設0460-83-8500(代))
時 間 :10:00~21:00
料 金 :1,630円
■ オフィシャルHP(現施設)
※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。
箱根湯本を代表する大型旅館だった旧「天成園」は2008年3月に閉館、「万葉倶楽部」の傘下に入り、2009年12月16日全面新築改装されてオープンしました。
このレポは旧「天成園」閉館の約2年前、2006年6月に宿泊したときの記録です。
宿泊したのは別館「飛烟閣」。和風情緒あふれるこの建物は新築改装にともない本館とともに取り壊され、現存していません。(なお、本編はレポ形式としたので、表記は過去形にしていません。)


【写真 上(左)】 改装前の箱根湯本駅
【写真 下(右)】 夕暮れの湯本橋


【写真 上(左)】 滝通り
【写真 下(右)】 滝通りから天成園本館
箱根湯本、早川と須雲川が合流するあたりにかかる弥栄橋から須雲川沿いに川上に向かう道を滝通りといい、沿道には湯宿が軒をならべてエリア名にもなっています。
この滝通りから玉簾橋で須雲川を渡ったところにこの宿はあります。滝通り地区で須雲川の左岸にある唯一の湯宿です。


【写真 上(左)】 対岸から飛烟閣
【写真 下(右)】 対岸から本館
川下側右手に鉄筋コンクリ造の本館、左手に「飛烟閣」があります。
飛烟閣はかつて、小田原城主、稲葉丹後守の別邸があったとされ、飛烟閣も重厚な和風のつくりとなっています。
山肌に「玉簾の瀧」「飛烟の瀧」がかかる風光明媚なこの地は、与謝野晶子、荻原井泉水などの文人墨客が訪れています。
現「天成園」のWebには「建築に際しては、この地の自然を愛した自由律の俳人・荻原井泉水も協力、「天成園」の名(天の成したる園の意)、および各部屋の命名や揮毫を行いました。」とあります。


【写真 上(左)】 風格ある玄関
【写真 下(右)】 将棋の宿でもあります
~ 山荘へ 玉簾の瀧流れ入り 客房の灯をもてあそぶかな ~ 与謝野晶子
泊まったのは1階の須雲川沿い、離れ風の角部屋で前庭をそなえたゆったりとした部屋で、部屋風呂まで付いていました。格安の宿泊代(素泊まり)だったので、いい意味で予想を裏切られました。
滝通りの車の音は須雲川の瀬音にまぎれてここまでは届かず、かじかの声が夜どおし流れて風流でした。


【写真 上(左)】 客室
【写真 下(右)】 前庭の向こうは須雲川
はやめのチェックインでしたが、湯本の他のお湯を攻め、湯本の洋食屋で夕食をとって滝通りを歩いて帰ってくると、6月下旬の長い日もさすがに暮れた20時すぎでした。
さて、いよいよ攻略開始です。


【写真 上(左)】 浴場案内-1
【写真 下(右)】 浴場案内-2
天成園には本館、別館(飛烟閣)あわせて5ヶ所の浴場があり(貸し切り風呂のぞく)、時間による男女入れ替え制をとっています。(「美肌湯」のみ女性専用)
【飛烟閣】
●「椿の湯(露天)」 <1階>
男性13:30~24:00 女性5:00~13:00
●「滝の大湯(大浴場)・四季の湯(露天)」 <2階>
男性2:00~13:30 女性14:00~24:00
●「美肌湯」 <1階>
女性専用/終日(清掃時間以外)
【本館】
●「古代檜の湯(大浴場)」 <地下1階>
男性14:00~24:00 女性2:00~13:30
●「屋上露天風呂」 <屋上>
男性5:00~13:00 女性13:30~24:00
※ 別に有料貸切風呂として、「飛烟閣」1階に「せせらぎの湯」・「清流の湯」(ともに内湯)、「本館」屋上に「そよかぜの湯」「満天の湯」(ともに露天)があります。


【写真 上(左)】 滝の大湯への案内
【写真 下(右)】 貸切露天
【天成園の源泉について】
天成園は掲出物などで「当園は源泉四本を有し、良質な温泉を一日当たりドラム缶で千八百七十六本分という豊富な湧出量を有します」「箱根湯本でもその湧出量は比類のない豊かさ」と謳っています。
やませみさんのデータでは下記3本が記載されています。(やませみさんデータ、以下■印)
■湯本45号 単純温泉 45.9℃ pH=8.6 142 L/min 227m 総計=0.430 (Na-Cl・SO4)
■湯本55号 単純温泉 58.9℃ pH=8.4 62 L/min 455m 総計=0.770 (Na-Cl・SO4)
■湯本60号 単純温泉 56.0℃ pH=8.4 61 L/min 462m 総計=0.560 (Na-Cl・SO4)
このうち、湯本60号は「椿の湯(露天)」で分析書掲示、他の浴場では湯本45号の掲示がありました。「美肌湯」は確認し忘れましたが、パンフその他で「特別源泉を引いた」「弱アルカリ性単純温泉の自家源泉1本は、女性専用の内湯『美肌湯』に注がれています。」などとあるので、湯本55号ないしもう1本の源泉使用かもしれません。
(自遊人Webには「自家源泉は4本あり、1日の湧出量はドラム缶1,876本分。源泉温度が50度とやや高温のため配管を工夫し、湯口で42度になるように調整。弱アルカリ性単純温泉の自家源泉1本は、女性専用の内湯『美肌湯』に注がれています。そのほかの浴槽には3本あるアルカリ性単純温泉の源泉がかけ流されています。」とあります。
平成14年の分析では湯本45号、60号ともにpH=8.7でアル単(pH8.5以上)となっています。湯本55号がpH=8.4のままだとすると、(弱アルカリ性の)単純温泉となり、上記の記事と符合します。)


【写真 上(左)】 敷地内の第45号源泉
【写真 下(右)】 部屋風呂は「源泉風呂」
なお、もう1本(4本目)の源泉は須雲川の右岸玉簾橋手前(駐車場のあたり)にある湯本15号(単純温泉 51.7℃ pH=8.7 総計=0.563 (Na-Cl・SO4))の可能性がありますが、現在の天成園のWebでは「天成園は、敷地内に3本の源泉を自社所有しており、この温泉を露天風呂、内湯、客室露天風呂、家族風呂(貸し切り制)へ振り分け、お客様にご提供しています。このうち、最も湧出量が多い「湯本 第45号源泉」につきましては、地下227メートルから、毎分142リットル/泉温45.9度の温泉が揚湯できます。」とあるので湯本45.60.55号の使用とみるとすっきりします。
ところが、同Webに掲載されている最新の分析書では、湯本第2.45.60.97号混合泉となっています。
湯本第2号はパークス吉野の東側、第97号は北西側山手の城山(片倉)地区にあります。
■湯本2号 単純温泉 56.5℃ pH=8.4 総計=0.964 (Na-Cl・SO4)
■湯本97号 単純温泉 56.0℃ pH=8.6 総計=0.286 (Na-Cl・HCO3)
これで45.60号以外の使用源泉は、本数を含めてまたナゾにつつまれてしまいました。
※ 滝通り経由で回り込むアプローチなので意外に気づきにくいですが、湯場地区の福住横穴源泉(湯本3号)と天成園は数百mしか離れていません。天成園隣のパークス吉野のまわりには湯本1号、2号源泉があり、このあたりは湯本でも古い泉源のあるエリアであることがわかります。


【写真 上(左)】 館内-1
【写真 下(右)】 館内-2


【写真 上(左)】 館内-3
【写真 下(右)】 粋な意匠
------------------------------------------------------
それでは入った順にレポしていきます。
1.「椿の湯(露天)」 【飛烟閣/1階】


【写真 上(左)】 「椿の湯」入口
【写真 下(右)】 「椿の湯」脱衣所
純和風づくりのなかなか趣のある露天です。屋根や東屋はなく、開放感もあります。
岩組み青鉄平づくりで12人以上、ゆったりふかめの入りごこちのいい湯船。
カラン3、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。


【写真 上(左)】 「椿の湯」 (館内掲示より)
【写真 下(右)】 「椿の湯」浴槽
岩間に設えた竹樋の湯口から40L/min弱ほどの熱湯(50℃弱・源泉だと思う)を投入し、端の上面排湯口からの排湯で、槽内注入・底面吸湯ともに確認できず。
やや微濁した適温~ややぬるのお湯には少量の湯の花が出ています。また、岩組みのところどころに石膏の析出がでています。
よわい芒硝味+微塩味、かすかな芒硝臭、味臭ともおだやかでカルキ気は感じられませんでした。
ヌル(ツル)すべとよわいとろみを感じます。


【写真 上(左)】 「椿の湯」湯口
【写真 下(右)】 石膏の析出と湯色
広くて深い浴槽のわりに鮮度感は悪くなく、しっとりした雰囲気で箱根湯本らしい繊細でおだやかなお湯を楽しめるなかなかの浴場だと思います。
2.「古代檜の湯(大浴場)」 【本館/地下1階】


【写真 上(左)】 本館のロビー
【写真 下(右)】 「古代檜の湯」入口
飛烟閣の2階から本館の2階に連絡通路が架けられていて、屋外に出ることなく本館に行けます。2階からエレベーターでアプローチします。
入口まわり、脱衣所ともスケール感があり、大型旅館のメイン浴場らしい華やぎをみせています。
浴場もかなりの広さがあります。夜だったのでよくはわかりませんが、地下浴場ながら大きめの窓があり、昼間は須雲川を見下ろせるのでは?


【写真 上(左)】 「古代檜風呂」の脱衣所
【写真 下(右)】 「古代檜風呂」の浴場


【写真 上(左)】 「古代檜風呂」浴槽
【写真 下(右)】 機能浴槽
檜づくり(踏み込みは石造)30人以上の豪壮なメイン浴槽と、奥に黒みかげ石枠木底10人ほどの機能浴槽(ジャグジー・ジェット、打たせ湯×2)があります。
檜風呂は説明板によると「悠々、三千年を越えて香る総古代檜作りのお風呂です」とのこと。
カラン15、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。


【写真 上(左)】 「古代檜風呂」の湯口
【写真 下(右)】 機能浴槽の湯口
メイン浴槽は木枠で覆われ、赤く変色した石の湯口から熱めのお湯を40L/minほどの投入+底面注入でザンザコのオーバーフロー。
機能浴槽は派手に石膏の析出の出た石の湯口からの投入+底面注入で槽内排湯し、オーバーフローはありません。
お湯のイメージは両槽とも大差ありません。
ほぼ適温のお湯はほぼ無色透明で、わずかにこまかな茶色の湯の花が確認できます。
よわい芒硝味+微塩味に微芒硝臭(カルキ気わずかにあるか?)。
「椿の湯」よりとろみは強く、ヌルすべはよわいイメージ。こちらも浴感おだやかで、なかなかに入りごこちのいいお湯ですが、なんとなく「椿の湯」より力強い感じ。
3.「滝の大湯(大浴場)・四季の湯(露天)」 【飛烟閣/2階】


【写真 上(左)】 「滝の大湯」入口
【写真 下(右)】 「滝の大湯」浴室
滝の大湯(大浴場)と四季の湯(露天)が隣接してあり、はだかのまま移動できます。
手前が滝の大湯、奥が四季の湯です。
滝の大湯はやや暗めながらスペースはたっぷりとれています。
カラン11、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。


【写真 上(左)】 「滝の大湯」の浴槽
【写真 下(右)】 「滝の大湯」の浴槽湯口
赤みかげ石枠水色タイル貼20人以上の浴槽で、中央の円盤状の石の湯口から投入+底面注入でかなり大量のオーバーフロー。
<四季の湯(露天)>


【写真 上(左)】 「四季の湯」-1
【写真 下(右)】 「四季の湯」-2
四季の湯は軒下的な配置ですが、正面に竹藪、右手奥に小滝を配した、やや暗めながら野趣あふれる露天。石組み鉄平石敷で15人はいけそうです。
石組みから突き出たパイプを竹樋で受け、それをさらに石で受けて湯船に注ぎ込んでいます。
複雑な注ぎ込みは、湯温調整(高温源泉の冷却)のためでは?
緑青や石膏の析出やお湯の感じからして、この湯口は源泉だと思います。
また、すぐ上手に45号泉源がある(立ち入り禁止)ので、この湯口は45号直引きでは?
ただし、この浴槽にも底面注入があり、完全なかけ流しではないのでは?
浴槽端の上面排湯口からの配湯。


【写真 上(左)】 見上げると竹林
【写真 下(右)】 「四季の湯」の湯口
お湯は両槽とも大差ありません。
ほぼ適温でほぼ無色透明で浮遊物はなし。
微芒硝味。よわい芒硝臭にわずかにカルキ臭がまじります。
湯づかいは、昨晩の「古代檜の湯」よりいいような感じがするのに、こちらだけでカルキを感じたのはなぜ?
ひょっとすると、深夜のお湯の入れ替え時に浴槽を塩素消毒するか、消毒剤を投入しているのかもしれません。
湯ざわりは「椿の湯」「古代檜の湯」よりあきらかにきしきし感がつよく、ここは45号泉単独使用で、45号泉はきしきしの強い泉質なのかもしれません。
4.「屋上露天風呂」 【本館/屋上】


【写真 上(左)】 屋上露天の脱衣所
【写真 下(右)】 明るくウッディな露天
天成園のなかではもっとも開放感のある浴場です。となりに有料貸切露天の「そよかぜの湯」「満天の湯」があります。
総木造り30人以上の大ぶりな浴槽。内床も木張りでウッドデッキのよう。
木の湯口2ヶ所から50℃は優にある熱湯の投入+側面注入で排湯不明。(オーバーフローなし)
カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。


【写真 上(左)】 屋上露天
【写真 下(右)】 屋上露天の湯口
お湯はほぼ適温、無色透明で浮遊物はなし。
ほぼ無味ではっきりとしたカルキ臭が感じられます。
湯ざわりは淡泊で、あまり個性の感じられないお湯です。
湯口ではカルキ臭は感じられなかったので、側面から消毒されたお湯を注入しているかも。
ツルすべの湯ざわりが明瞭で、45号泉ではないのでは?(分析書掲示なし)
お湯はいまひとつでしたが、開放感抜群なので、人によってはベストの評価になるかもしれません。
■ 「美肌湯」 【飛烟閣/1階】
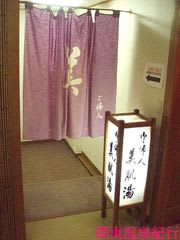

【写真 上(左)】 「美肌湯」入口
【写真 下(右)】 「美肌湯」 (館内掲示より)
女性専用なので入れずよくわかりません。
ただ、連れによると「混んでいたけど、お湯はここがいちばんよかった。」とのことなので、やはり別源泉をつかっているのだと思います。
■ 部屋付きの源泉風呂


【写真 上(左)】 部屋風呂 (入れはじめ)
【写真 下(右)】 溜まってきました
泊まった部屋には風呂が付いていました。黒みかげ石枠丸タイル貼の味のある浴槽です。
当然休止しているかと思いきや、カランを捻ると水がでてきました。しばらくしても水のままでしたが、こういう風呂は新鮮な源泉が出るまで時間がかかることが多いので、なおも粘っていると次第に湯温が上がってきました。
ただ、湯量は少ないので、溜まるまでに1時間は優にかかりました。また、湯温は37℃くらいまでしか上がりませんでした。
べつにシャワー付洗い場カランがありましたが、こちらを出すと浴槽カランの量が減るので、供給源泉を振り分けていると思います。
(なお、浴室脇にはしっかりと分析書(湯本第45号泉/平成4年9月分析)が掲示されていました。)


【写真 下(右)】 カラン
【写真 上(左)】 洗い場カランも温泉
お湯のイメージは芒硝味臭、とろみ、きしきし、ヌルすべが入り混じり「古代檜風呂」に似ています。
ただ、ぬる湯だし鮮度感もあるので入っていてすこぶる気持ちよく、いくらでも入れそう。


【写真 上(左)】 玉簾の瀧
【写真 下(右)】 飛煙の滝


【写真 上(左)】 延命の湧水
【写真 下(右)】 玉簾神社
天成園裏手の庭園は、箱根の名所として知られ、「玉簾の瀧」「飛烟の瀧」の二つの滝は古くから「延命の水」として知られるもの。
また、最近パワースポットとして人気を集めているらしい玉簾神社も滝に隣接して鎮座まします。


【写真 上(左)】 玉簾の瀧から飛烟閣
【写真 下(右)】 対岸「青風荘」から飛烟閣
新装なってさらに箱根を代表する大型温泉ホテルとなった天成園。現在も日帰り入浴を受け付けていますが、いいお値段なのでいまだに入湯していません。
〔 源泉名:湯本 第60号 〕 <H14.12.5分析>
アルカリ性単純温泉(Na-Cl・SO4型) 54.6℃、pH=8.7、61L/min(動力揚湯)、成分総計=0.683g/kg
Na^+=195mg/kg (85.14mval%)、Ca^2+=28.2 (14.16)、Fe^2+=0.06
Cl^-=224 (63.33)、SO_4^2-=137 (28.56)、HCO_3^-=37.7 (6.21)、CO_3^2-=1.46
陽イオン計=226 (9.96mval)、陰イオン計=407 (9.98mval)、メタけい酸=42.7、メタほう酸=6.91、遊離炭酸=0.12
〔 源泉名:湯本 第45号 〕 <H14.12.5分析>
アルカリ性単純温泉(Na-Cl・SO4型) 45.4℃、pH=8.7、湧出量不明、成分総計=0.515g/kg
Na^+=131mg/kg (79.92mval%)、Ca^2+=27.8 (19.46)、Fe^2+=0.02
Cl^-=139 (54.98)、SO_4^2-=117 (34.16)、HCO_3^-=36.6 (8.41)、CO_3^2-=1.41
陽イオン計=160.19 (7.13mval)、陰イオン計=302.0 (7.13mval)、メタけい酸=47.5、メタほう酸=4.86、遊離炭酸=0.11
※mval%、イオン計mvalは筆者にて概数算出
【現在の分析書】
〔 源泉名:湯本 第2、45、60、97号 混合 〕 <H21.10.23分析>
アルカリ性単純温泉(Na-Cl・SO4型) 48.0℃、pH=8.6、湧出量不明、成分総計=599mg/kg
Na^+=157mg/kg (82.83mval%)、Ca^2+=26.7 (16.16)
Cl^-=167 (56.19)、SO_4^2-=124 (30.80)、HCO_3^-=40.9 (8.00)、CO_3^2-=11.4
陽イオン計=186.5 (8.24mval)、陰イオン計=345.0 (8.38mval)、メタけい酸=57.5、メタほう酸=9.72
※mval%、イオン計mvalは筆者にて概数算出
<温泉利用掲示>(館内掲示より)
「箱根随一の湧出量に恵まれた、四本の源泉は柔らかな肌ざわりの弱アルカリ単純泉で身体への刺激が少なく(中略)客室風呂をはじめ、すべてのお風呂は源泉100%純天然温泉で(以後略)」
〔 2015/01/06UP (2006/06入湯) 〕
E139.5.52.110N35.13.31.290
【 BGM 】
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 強羅温泉 「薬師の湯 吉浜」 〔 リニューアルUp 〕


 強羅温泉 「薬師の湯 吉浜」
強羅温泉 「薬師の湯 吉浜」住 所 :神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-39
電 話 :0460-82-2258
時 間 :10:00~19:00 / 月休
料 金 :850円
■ オフィシャルHP
■ 紹介ページ (@nifty温泉)
■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)
■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)
■ 紹介ページ (楽天トラベル)
箱根では大湧谷、早雲山、湯の花沢などで温泉が造成されていて、強羅エリアには大湧谷と早雲山の2系統が引湯されていますが、ここは早雲山造成泉をつかっています。(→箱根の造成泉リスト(古いデータです念のため))
前回レポから使用源泉をチェンジしているようなので2012/11月入湯時の様子を追加してリニューアルUPします。
強羅駅のすぐよこにある日帰り温泉施設で、もとは旅館だったものを業態転換したもの。いまでも素泊まりは対応しています。
場所はわかりにくく、強羅駅から強羅公園にのぼる細い一方通行の路地に入ってすぐの路地(駐車場?)を右折すると突き当たりに建物があり、Pは左に折れたところ。
強羅駅のロータリーから入った方がよほどわかりやすいですが、車両進入禁止。
こぢんまりとした旅館のつくりで、入ってすぐ廊下の右側に男湯と女湯。
脱衣所・浴室ともによくメンテされています。


【写真 上(左)】 脱衣所 (2006年)
【写真 下(右)】 ミストサウナ (2006年)
窓の小さいやや暗めでこもり気味の浴室に、みかげ石造5-6人のシンプルで入りごこちのいい浴槽と手前に北投石使用のミストサウナ。
カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。
休日11時で男女湯とも独占~2人。(2006年入湯時)


【写真 上(左)】 浴槽 (2006年)
【写真 下(右)】 湯口 (2006年)


【写真 上(左)】 外観 (2012年)
【写真 下(右)】 浴槽 (2012年)
【新源泉(2012年入湯)】
内湯は金気で赤茶に色づいたみかげ石の湯口から熱湯(たぶん源泉)を投入、槽内注排湯なしでオーバーフロー+切欠からの上面排湯はかけ流しでしょう。
今回は源泉温度が上がっているためか、湯口から竹樋で浴槽外にお湯を逃がしていました。
この日は紅葉の真っ盛りで入浴客が多かったのか、お湯はやや温め。鮮度もいまひとつでしたが、投入量がけっこうあるのでお客が引ければすぐに回復すると思います。
お湯はうすく茶色がかってうす茶の湯の花をうかべています。
弱塩味+微収斂味に強羅の揚湯泉系でときおり感じる焼け石臭(or炊きたてのご飯の香り)を感じます。前回ほどのイオウ気は感じられませんでしたが、裏でイオウが存在を主張している感じ。
明瞭なとろみときしきしとヌルすべが入り混じる複雑な湯ざわりで、温まりがつよくしっかりとした濃度感も感じられます。
力感は及ばないものの、「文の郷」(宮城野第35号/2013春閉館との情報あり)や「箱根みたか荘」(宮城野第74号泉/日帰り不可の情報あり)のようなイメージがあり、旧源泉とはかなり変わっています。


【写真 上(左)】 湯口&竹樋 (2012年)
【写真 下(右)】 浴槽の外に逃がしています (2012年)
分析書上では、強羅温泉4、5号井混合(宮城野第132、133号混合泉)から強羅温泉5、6号井混合蒸気造成泉(宮城野第133、134号混合泉)に変わっていて、4号井(宮城野第132号)が6号井(宮城野第134号)に入れ替わったかたちですが、ここまでお湯のイメージを変えてしまうとは、6号井(宮城野第134号)がかなり強力なのでは?
「混合蒸気造成泉」と明示してある以上、造成泉だとは思いますが、強羅の揚湯泉的なイメージからして6号井の用水は強羅揚湯泉的な性格をもっているのではないでしょうか。
強羅揚湯泉は日帰りで入れる施設が減ってきているので、その力感あるイメージを味わえる貴重な施設だと思います。
※スタッフの方に伺うと、「2年ほど前(2010年秋?)から源泉が変わっている。」とのことでした。
数年前(2010年頃)から早雲山造成泉を使っていると思われる施設のいくつかが塩化物泉となり、自家源泉を復活したか、早雲山造成泉の泉質が変わったかのどちらかだと思っていましたが、真相は上記のとおりでした。
------------------------------
【旧源泉(2006年入湯)】
内湯は金気で赤茶に色づいたみかげ石の湯口から熱湯(たぶん源泉)を投入、槽内注排湯なしでオーバーフロー+切欠からの上面排湯はかけ流しでしょう。
排湯の流路は成分で赤茶に色づいています。
あつめ43℃ほどのお湯は、かすかににごりを帯びて白と茶色の湯の花がただよいます。
僅微たまご味によわい焦げ臭で、総硫黄7.56mg/kgほどのイオウ気は感じられませんでした。
浴感は軽めなものの、やわらかでよく温まる入りごこちのいいお湯で、浴後の温まり感も相当なものです。
ここで使用している「早雲山造成泉」は、「大湧谷造成泉」にくらべ総じて白濁もイオウ気もよわいですが、肌に染み入るような微妙な滋味があってわたしはさりげに好きです。


【写真 上(左)】 湯色&切欠 (2006年)
【写真 下(右)】 茶色に色づく内床 (2006年)
【2012年】
今回はミストサウナは休止していました。
公式Webに「当温泉は、秋田県玉川温泉を再現致しました。放射線を持つ天然記念物の「北投石」を入手できた事により、早雲山からのナトリウム塩化物泉を北投石に通した融合温泉でおくつろぎ下さい。」という案内が出ています。新源泉もなかなかどうして良質なお湯なので、もっとお湯に自信をもってもいいのでは?
【2006年】
ミストサウナも入りましたが、ときおり頭上から霧雨状に冷たい水が降り注いできて、あまり気分のいいものではなかったので、すぐに出てしまいました(^^;)
女将さんは、温泉はたいしたことないけど、北投石サウナは自信がある旨の話をされていましたが、なかなかどうして良質なお湯なので、もっとお湯に自信をもってもいいのでは?
【新源泉】
〔 源泉名:強羅温泉5、6号井混合蒸気造成泉(宮城野第133、134号混合)=早雲山造成泉) 〕 <H20.7.16分析>
Na-塩化物泉 64.5℃、pH=6.5、成分総計=1.484g/kg
Na^+=413mg/kg、Mg^2+=2.06、Ca^2+=33.1、Fe^2+=0.15
Cl^-=713、HS^-=0.12、SO_4^2-=28.5、HCO_3^-=16.2
メタけい酸=173、メタほう酸=36.7、遊離炭酸=9.82、硫化水素=0.44
【旧源泉】
〔 源泉名:強羅温泉4、5号井混合(宮城野第132、133号混合泉)=早雲山造成泉) 〕 <H14.7.31分析>
単純硫黄温泉(硫化水素型)(Na・Ca-SO4・Cl型) 58.6℃、pH=6.9、成分総計=0.202g/kg
Na^+=21.2mg/kg (51.14mval%)、Ca^2+=11.4 (31.55)、Fe^2+=0.02
Al^3+=0.07、Cl^-=23.8 (34.90)、HS^-=3.12、SO_4^2-=43.0 (46.53)、HCO_3^-=14.7 (12.52)
メタけい酸=69.8、硫化水素=4.44
(mval%は筆者の概算値)
<温泉利用掲示> (2012年)
加水:行っていません 加温:行っていません 循環装置等の使用:なし 消毒処理:行っていません
〔 2015/01/01リニューアルUP (2006/01・201211入湯) 〕
E139.3.2.458N35.14.49.949
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




