関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
22.榛名神社 (高崎市榛名山町)
23.大森神社 (高崎市下室田町)
24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)
25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)
26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)
27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)
22.榛名神社

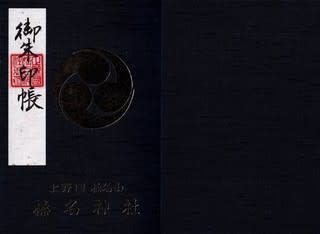
公式Web
高崎市榛名山町849
主祭神:火産霊神、埴山姫神
式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社
御朱印揮毫:榛名神社
・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。


赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。
榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。
社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。
下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。
『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。
戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。
慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。
江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。
榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。
高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。
また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。
江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。
ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。


-----------------------------------------------------
御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。
榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。
この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。
いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。
「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。
『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。
また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。
元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。
なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。
同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。
まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)
”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。
柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。
また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。
↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。
榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。
『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」
「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。
また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。
ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。
榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。
つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。
この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。
『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。
源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。
さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。
以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。
八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。
-----------------------------------------------------




講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。
随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。
奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。
神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。




対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。
手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。


石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。
信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。




彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。
あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。


神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。
本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。
本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。
御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。
国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。
祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。
境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。
ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。
御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。
23.大森神社
高崎市下室田町919
主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社
御朱印揮毫:大森神社

御朱印


【写真 上(左)】 境内掲示
【写真 下(右)】 参道と拝殿
現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。
■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より
国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら
「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」
これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。
伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。
「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))
主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命
國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。
國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。
國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。
『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。
武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。
また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。
以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。
なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。
滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。
向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 神楽殿
【写真 下(右)】 拝殿
社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。
参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。
拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。
軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。


【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿
【写真 下(右)】 水引虹梁中備


【写真 上(左)】 木鼻(右)
【写真 下(右)】 木鼻(左)
千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。
水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。
虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。
海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。
向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。


【写真 上(左)】 拝殿向拝
【写真 下(右)】 拝殿扁額
本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 金鑽神社
摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。
手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。
御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。
通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。
24.中嶋稲荷神社
高崎市下室田町1219
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:中嶋稲荷神社
この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。
とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

 【写真 上(左)】 神社への道
【写真 上(左)】 神社への道
【写真 下(右)】 鳥居の扁額
そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。
拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。
鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。


【写真 上(左)】 鳥居と拝殿
【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印
石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。
拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。
由緒書はなく創祀などは不明です。
御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。
25.矢背負稲荷神社
高崎市下室田町3293
主祭神:
旧社格:
御朱印揮毫:稲荷大明神


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。
鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。
しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。
その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)
武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。
永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。
この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。
鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。
遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。
鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。
4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。
上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。
その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。
創祀にはもう一説あるようです。
里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。
白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)
里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。
里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。
里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。
とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。
発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。
室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。
家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。
また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。
永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。
以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。
しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。
いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。
それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)
26.根古屋天満宮
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋天満宮

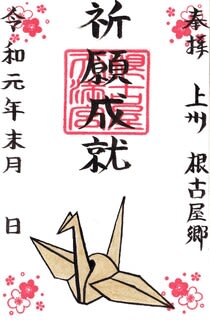
【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。
城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。
「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。
御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。
27.根古屋道祖神
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)
矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)
そちらの道祖神の御朱印かと思われます。
道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。
矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。
絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。
下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。
道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。


【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居
【写真 下(右)】 鳥居
集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。
この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 参道からの拝殿
そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。
ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。
あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。
階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。
登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。
切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。
水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。


【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮
【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額
根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。
「天満宮」の扁額が掲げられています。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ ノーサイド - 松任谷由実
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
22.榛名神社 (高崎市榛名山町)
23.大森神社 (高崎市下室田町)
24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)
25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)
26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)
27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)
22.榛名神社

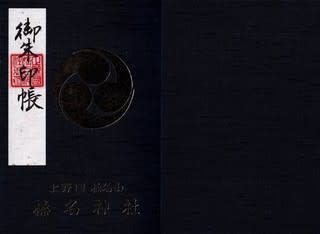
公式Web
高崎市榛名山町849
主祭神:火産霊神、埴山姫神
式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社
御朱印揮毫:榛名神社
・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。


赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。
榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。
社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。
下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。
『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。
戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。
慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。
江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。
榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。
高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。
また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。
江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。
ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。


-----------------------------------------------------
御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。
榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。
この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。
いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。
「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。
『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。
また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。
元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。
なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。
同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。
まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)
”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。
柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。
また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。
↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。
榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。
『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」
「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。
また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。
ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。
榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。
つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。
この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。
『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。
源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。
さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。
以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。
八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。
-----------------------------------------------------




講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。
随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。
奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。
神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。




対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。
手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。


石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。
信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。




彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。
あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。


神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。
本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。
本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。
御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。
国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。
祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。
境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。
ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。
御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。
23.大森神社
高崎市下室田町919
主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社
御朱印揮毫:大森神社

御朱印


【写真 上(左)】 境内掲示
【写真 下(右)】 参道と拝殿
現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。
■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より
国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら
「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」
これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。
伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。
「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))
主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命
國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。
國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。
國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。
『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。
武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。
また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。
以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。
なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。
滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。
向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 神楽殿
【写真 下(右)】 拝殿
社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。
参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。
拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。
軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。


【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿
【写真 下(右)】 水引虹梁中備


【写真 上(左)】 木鼻(右)
【写真 下(右)】 木鼻(左)
千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。
水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。
虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。
海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。
向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。


【写真 上(左)】 拝殿向拝
【写真 下(右)】 拝殿扁額
本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 金鑽神社
摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。
手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。
御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。
通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。
24.中嶋稲荷神社
高崎市下室田町1219
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:中嶋稲荷神社
この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。
とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

 【写真 上(左)】 神社への道
【写真 上(左)】 神社への道【写真 下(右)】 鳥居の扁額
そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。
拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。
鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。


【写真 上(左)】 鳥居と拝殿
【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印
石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。
拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。
由緒書はなく創祀などは不明です。
御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。
25.矢背負稲荷神社
高崎市下室田町3293
主祭神:
旧社格:
御朱印揮毫:稲荷大明神


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。
鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。
しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。
その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)
武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。
永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。
この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。
鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。
遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。
鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。
4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。
上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。
その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。
創祀にはもう一説あるようです。
里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。
白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)
里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。
里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。
里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。
とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。
発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。
室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。
家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。
また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。
永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。
以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。
しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。
いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。
それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)
26.根古屋天満宮
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋天満宮

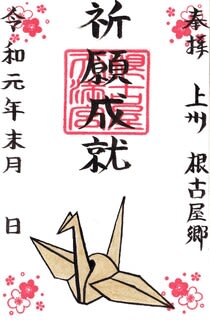
【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。
城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。
「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。
御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。
27.根古屋道祖神
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)
矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)
そちらの道祖神の御朱印かと思われます。
道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。
矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。
絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。
下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。
道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。


【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居
【写真 下(右)】 鳥居
集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。
この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 参道からの拝殿
そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。
ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。
あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。
階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。
登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。
切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。
水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。


【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮
【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額
根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。
「天満宮」の扁額が掲げられています。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ ノーサイド - 松任谷由実
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)
12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)
13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)
14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)
15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)
16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)
17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺
高崎市箕輪町西明屋247
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。
寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。
観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。
平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。
明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。
また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。
この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。
ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。
伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。
こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。
御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。
12.黒髪山神社
榛東村広馬場3615
主祭神:大山祇命


〔 御朱印 〕
中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。
榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。
榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。
主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。
神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。
大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。
群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。
相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。
相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。
「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。
雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。
駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。
木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。
拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。
境内には有栖川宮神社も鎮座します。
祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。
御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。
13.威徳山 常楽院 長松寺
吉岡町漆原1284
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神
札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)


【写真 上(左)】 長松寺本堂
【写真 下(右)】 長松寺観音堂
〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。
左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。
その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。
新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。
寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。
当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。
上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。
ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。
矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。
境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。
山門をくぐると境内正面に本堂。
本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。
タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。
境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。
駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。
朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。
観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。
見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。
御朱印は庫裡にていただきました。
ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。
14.玉輪山 龍傳寺
渋川市半田1124
曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第19番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。
左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。
こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。
境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。
天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。
天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。
などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。
境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。
御朱印は庫裡にて拝受。
ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。
御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。
15.慈眼山 福聚院 神宮寺
渋川市有馬1301
天台宗 御本尊:釈迦如来
札所:新上州三十三観音霊場第30番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。
右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。
このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。
中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。
またまた話が逸れました。
新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。
天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。
天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。
神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。
(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)
有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。
信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。
当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。
こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。
(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)
明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。
お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社
御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。
また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。
16.威徳山 無量寿院 眞光寺
渋川市並木町748
天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)
札所:群馬郡三十三観音霊場第10番
札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)


〔 御朱印 〕
中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。
右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。
ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。
平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。
中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。
名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。
境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。
御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。
周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。
高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。
また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。
観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。
西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。
17.渋川八幡宮
渋川市渋川甲1
主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后


〔 御朱印 〕
中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。
こちらでは御朱印帳も購入しました。
紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳
渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。
義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。
義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。
その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。
八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。
境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。
子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。
境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。
御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。
こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺
渋川市金井甲1965
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。
応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。
当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)
樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。
こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。
参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。
また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ 見えない月 - 藤田麻衣子
■ 夢の途中 - KOKIA
■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)
12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)
13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)
14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)
15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)
16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)
17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺
高崎市箕輪町西明屋247
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。
寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。
観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。
平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。
明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。
また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。
この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。
ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。
伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。
こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。
御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。
12.黒髪山神社
榛東村広馬場3615
主祭神:大山祇命


〔 御朱印 〕
中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。
榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。
榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。
主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。
神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。
大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。
群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。
相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。
相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。
「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。
雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。
駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。
木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。
拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。
境内には有栖川宮神社も鎮座します。
祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。
御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。
13.威徳山 常楽院 長松寺
吉岡町漆原1284
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神
札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)


【写真 上(左)】 長松寺本堂
【写真 下(右)】 長松寺観音堂
〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。
左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。
その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。
新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。
寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。
当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。
上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。
ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。
矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。
境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。
山門をくぐると境内正面に本堂。
本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。
タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。
境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。
駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。
朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。
観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。
見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。
御朱印は庫裡にていただきました。
ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。
14.玉輪山 龍傳寺
渋川市半田1124
曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第19番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。
左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。
こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。
境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。
天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。
天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。
などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。
境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。
御朱印は庫裡にて拝受。
ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。
御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。
15.慈眼山 福聚院 神宮寺
渋川市有馬1301
天台宗 御本尊:釈迦如来
札所:新上州三十三観音霊場第30番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。
右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。
このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。
中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。
またまた話が逸れました。
新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。
天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。
天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。
神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。
(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)
有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。
信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。
当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。
こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。
(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)
明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。
お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社
御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。
また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。
16.威徳山 無量寿院 眞光寺
渋川市並木町748
天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)
札所:群馬郡三十三観音霊場第10番
札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)


〔 御朱印 〕
中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。
右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。
ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。
平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。
中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。
名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。
境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。
御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。
周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。
高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。
また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。
観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。
西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。
17.渋川八幡宮
渋川市渋川甲1
主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后


〔 御朱印 〕
中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。
こちらでは御朱印帳も購入しました。
紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳
渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。
義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。
義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。
その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。
八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。
境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。
子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。
境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。
御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。
こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺
渋川市金井甲1965
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。
応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。
当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)
樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。
こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。
参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。
また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ 見えない月 - 藤田麻衣子
■ 夢の途中 - KOKIA
■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 岩塙鉱泉 「井筒屋」
しばらく休廃業したお湯のレポのリニューアルUPをつづけます。
「関東周辺 立ち寄り温泉みしゅらん」様の特集に掲載いただいていますが、追記&画像を追加してリニューアルUPします。
※ この施設はWeb情報によると、平成24年(2012年)12月に閉館しています。
営業データは入湯時(2003年11月)のものです。


 岩塙鉱泉 「井筒屋」
岩塙鉱泉 「井筒屋」
住 所 :茨城県北茨城市関本町福田1481
電 話 :0293-46-3270
時 間 :時間要問合せ
定休日 :不明
料 金 :600円
すでに閉館していますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。
入湯・レポともに2003年11月。今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。
-----------------------------------------
湯巡りをつづけていると、ときおり強烈な印象を受けるお湯に巡り会うことがあります。
このお湯もそんな一湯です。
北茨城やいわきにはこの手のお湯が多いのですが、ここのインパクトは「カンチ山鉱泉」と双璧だと思います。
北茨城の山あいに潜むナゾの鉱泉で、「いわはな」と読みます。
位置的にはJR常磐線「大津港」駅の600mほど西側のところです。
相当に鄙び入っているという事前情報があり、気合いを入れて(笑)突入しましたが、どうにも場所がわからずTELするとおばちゃんが出ました。
「岩塙山荘」というのはさっき発見できましたが、どうやらその手前にあるらしい。
「でも、レジャーとかで入るところじゃなくて、湯治につかうようなところだけど・・・」
前ふりが入りました。これは相当なもんみたいです (^^;


【写真 上(左)】 庭先に廃材
【写真 下(右)】 浴場棟
さきほど通った道を再度進撃すると、庭先に廃材を積み上げた民家が・・・。
ここかぁ。
どうりでわからなかったハズです、入口はおろか玄関にも看板も何もありません。
手前右手に母屋、おくの別棟が浴場等で、どちらも瓦屋根がかけられているので、建物にB級感はありません。
背後に紅葉した斜面を背負い、里山の秘湯の雰囲気をまとっています。
「井筒屋」の屋号をもつ湯宿ですが、母屋にその雰囲気はなく、いまは立ち寄り湯に絞っての営業かもしれません。
奥の浴場棟の裏手からは青い煙りが立ち昇り、覗いてみると薪を焚いていました。
母屋から出てきたおばちゃんに料金を払って浴場へ。


【写真 上(左)】 浴場棟入口
【写真 下(右)】 脱衣所
とにかく、なにもかにもが鄙びきっています。
浴室はふたつありますが、ひとつは使っている気配がありません。
左側の浴室に案内されました。
脱衣所は緑色の壁面、せまいアルミの開き戸。床は歩くとミシミシと鳴り、B級入っています。
アルミの開き戸を開けると浴室。
土曜15時で先客がひとりいたので、浴室全体の写真は撮れていませんが、左手(女湯?)との仕切りは上が空いており声がとおります。
晩秋11月の入湯でしたが、天高があるので湯気のこもりはありませんでした。
全体に暗めで脱衣所よりさらに低くなっているので穴ぐらのような感じですが、かえって落ち着いて入れます。
細長の浴室で、手前が洗い場ソーン、おくの浴槽はタイル貼扇型1-2人のこぢんまりとしたもの。
カラン・シャワー・シャンプー・ドライヤーなどすべてなし。


【写真 上(左)】 薪焚きです
【写真 下(右)】 源泉カラン
浴槽に溜められたお湯、これが熱い。おそらく44℃くらいはあったかと思います。
おもわず先客のご年配に「熱いですねぇ」と言うと、「今日はぬるいほうだよ、さっききた●●さんなんか、ぬるくて入れね~って帰ってったよ」・・・。
共同浴場ではよくあるパターンですが・・・ ~~;)。
まぁ、熱湯は嫌いじゃないし、入れないほどでもないのですこし湯もみをしてそのまま入りました。
湯口はなく側面から熱いお湯が出て、もうひとつ穴(吸湯はしていない)があってオーバーフローはないので、薪焚きによる追い焚きの溜め湯方式かと。
浴槽の上、塩ビ管で引かれた先にカランがあってこれはおそらく源泉カランです。
しぶ焦げイオウ臭にたまご味+金気臭を帯びた、特徴のある冷たい水が出ます。
カランよこにコップも置いてあります。
溜め湯の冷鉱泉でも、源泉に触れられるのはありがたいですね。
薄コーヒー色のうす目の黒湯は味不明無臭でややツルすべがあり、薪焚きらしいやわらかなお湯はじわりじわりと染みてくるような深みのある浴感。
分析表はありませんでしたが、イオウと重曹が頑張っている感じのお湯でなかなか個性的。
料金600円はいささか高い感じもしますが、薪焚きを考えるとやむを得ないかと。
出ようとするともう一人入ってきたので、地元では意外と人気があるのかもしれません。
鄙び湯、B級湯は好物なので (^^;、個人的にはハマリでしたが、佇まいといい、湯温といい、ふつうの人(笑)にはハードル激高かと・・・。
お湯もなかなか、なにより鄙び加減が絶妙なので、機会があったらまた訪れたいと思います。
泉質などの掲示はありませんでしたが、県観光物産課のWebによると、「硫黄泉(硫化水素型)」とのこと。
また、やませみさんからご提供いただいたデータは、「単純S冷鉱泉? 17℃ pH=7.1 〔自家源泉〕」となっています。
-----------------------------------------
東日本大震災の翌年、平成24年(2012年)12月に閉館となっているようです。
Web上で震災後に入湯したレポがみつかるので、震災でも大きな被害は受けなかったようですが、やはり何らかのかたちで震災の影響はあったのかもしれません。
〔 2003年11月入湯・レポに加筆(最新UP2021/01/24) 〕
E140.46.22.410N36.50.35.370
【 BGM 】
■Anymore - BRICK(1982)
記事内容とえらくミスマッチですが(笑)
「関東周辺 立ち寄り温泉みしゅらん」様の特集に掲載いただいていますが、追記&画像を追加してリニューアルUPします。
※ この施設はWeb情報によると、平成24年(2012年)12月に閉館しています。
営業データは入湯時(2003年11月)のものです。


 岩塙鉱泉 「井筒屋」
岩塙鉱泉 「井筒屋」住 所 :茨城県北茨城市関本町福田1481
電 話 :0293-46-3270
時 間 :時間要問合せ
定休日 :不明
料 金 :600円
すでに閉館していますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。
入湯・レポともに2003年11月。今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。
-----------------------------------------
湯巡りをつづけていると、ときおり強烈な印象を受けるお湯に巡り会うことがあります。
このお湯もそんな一湯です。
北茨城やいわきにはこの手のお湯が多いのですが、ここのインパクトは「カンチ山鉱泉」と双璧だと思います。
北茨城の山あいに潜むナゾの鉱泉で、「いわはな」と読みます。
位置的にはJR常磐線「大津港」駅の600mほど西側のところです。
相当に鄙び入っているという事前情報があり、気合いを入れて(笑)突入しましたが、どうにも場所がわからずTELするとおばちゃんが出ました。
「岩塙山荘」というのはさっき発見できましたが、どうやらその手前にあるらしい。
「でも、レジャーとかで入るところじゃなくて、湯治につかうようなところだけど・・・」
前ふりが入りました。これは相当なもんみたいです (^^;


【写真 上(左)】 庭先に廃材
【写真 下(右)】 浴場棟
さきほど通った道を再度進撃すると、庭先に廃材を積み上げた民家が・・・。
ここかぁ。
どうりでわからなかったハズです、入口はおろか玄関にも看板も何もありません。
手前右手に母屋、おくの別棟が浴場等で、どちらも瓦屋根がかけられているので、建物にB級感はありません。
背後に紅葉した斜面を背負い、里山の秘湯の雰囲気をまとっています。
「井筒屋」の屋号をもつ湯宿ですが、母屋にその雰囲気はなく、いまは立ち寄り湯に絞っての営業かもしれません。
奥の浴場棟の裏手からは青い煙りが立ち昇り、覗いてみると薪を焚いていました。
母屋から出てきたおばちゃんに料金を払って浴場へ。


【写真 上(左)】 浴場棟入口
【写真 下(右)】 脱衣所
とにかく、なにもかにもが鄙びきっています。
浴室はふたつありますが、ひとつは使っている気配がありません。
左側の浴室に案内されました。
脱衣所は緑色の壁面、せまいアルミの開き戸。床は歩くとミシミシと鳴り、B級入っています。
アルミの開き戸を開けると浴室。
土曜15時で先客がひとりいたので、浴室全体の写真は撮れていませんが、左手(女湯?)との仕切りは上が空いており声がとおります。
晩秋11月の入湯でしたが、天高があるので湯気のこもりはありませんでした。
全体に暗めで脱衣所よりさらに低くなっているので穴ぐらのような感じですが、かえって落ち着いて入れます。
細長の浴室で、手前が洗い場ソーン、おくの浴槽はタイル貼扇型1-2人のこぢんまりとしたもの。
カラン・シャワー・シャンプー・ドライヤーなどすべてなし。


【写真 上(左)】 薪焚きです
【写真 下(右)】 源泉カラン
浴槽に溜められたお湯、これが熱い。おそらく44℃くらいはあったかと思います。
おもわず先客のご年配に「熱いですねぇ」と言うと、「今日はぬるいほうだよ、さっききた●●さんなんか、ぬるくて入れね~って帰ってったよ」・・・。
共同浴場ではよくあるパターンですが・・・ ~~;)。
まぁ、熱湯は嫌いじゃないし、入れないほどでもないのですこし湯もみをしてそのまま入りました。
湯口はなく側面から熱いお湯が出て、もうひとつ穴(吸湯はしていない)があってオーバーフローはないので、薪焚きによる追い焚きの溜め湯方式かと。
浴槽の上、塩ビ管で引かれた先にカランがあってこれはおそらく源泉カランです。
しぶ焦げイオウ臭にたまご味+金気臭を帯びた、特徴のある冷たい水が出ます。
カランよこにコップも置いてあります。
溜め湯の冷鉱泉でも、源泉に触れられるのはありがたいですね。
薄コーヒー色のうす目の黒湯は味不明無臭でややツルすべがあり、薪焚きらしいやわらかなお湯はじわりじわりと染みてくるような深みのある浴感。
分析表はありませんでしたが、イオウと重曹が頑張っている感じのお湯でなかなか個性的。
料金600円はいささか高い感じもしますが、薪焚きを考えるとやむを得ないかと。
出ようとするともう一人入ってきたので、地元では意外と人気があるのかもしれません。
鄙び湯、B級湯は好物なので (^^;、個人的にはハマリでしたが、佇まいといい、湯温といい、ふつうの人(笑)にはハードル激高かと・・・。
お湯もなかなか、なにより鄙び加減が絶妙なので、機会があったらまた訪れたいと思います。
泉質などの掲示はありませんでしたが、県観光物産課のWebによると、「硫黄泉(硫化水素型)」とのこと。
また、やませみさんからご提供いただいたデータは、「単純S冷鉱泉? 17℃ pH=7.1 〔自家源泉〕」となっています。
-----------------------------------------
東日本大震災の翌年、平成24年(2012年)12月に閉館となっているようです。
Web上で震災後に入湯したレポがみつかるので、震災でも大きな被害は受けなかったようですが、やはり何らかのかたちで震災の影響はあったのかもしれません。
〔 2003年11月入湯・レポに加筆(最新UP2021/01/24) 〕
E140.46.22.410N36.50.35.370
【 BGM 】
■Anymore - BRICK(1982)
記事内容とえらくミスマッチですが(笑)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 総社鉱泉 「せせらぎの湯」
※ この施設はWeb上で休業、ないし閉館の情報が多数みつかります。
現況については確認しておらず不明です。(2021年1月現在)
営業データは入湯時(2003年1月)のものです。


 総社鉱泉 「せせらぎの湯」
総社鉱泉 「せせらぎの湯」
住 所 :群馬県前橋市総社町植野985-2
電 話 :027-253-1126
時 間 :11:00~21:00 / 随時変更あり、時間要問合せ
定休日 :毎週金曜
料 金 :700円(以前は500円)
休廃業の可能性もありますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。
入湯は2003年1月で、レポは2003年1月27日。2005年11月08日に加筆したものに今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。
-----------------------------------------
大正14年(1925年)開湯の歴史ある鉱泉宿。
現在は日帰り温泉としても積極的に営業しています。
鉱泉につき、とくに開店時間は変動があるようで、事前の電話確認必須かと・・・。
JR上越線「群馬総社」駅前から細い路地を東に入り、住宅地を300mほど走ると唯一?の看板があり、その先に小さな駐車場があります。


【写真 上(左)】 駐車場
【写真 下(右)】 アプローチ
日帰り温泉ガイドにはけっこう載っていたりしますが、異常にわかりにくいアプローチなのでたどりつけない人もいるかも。
駐車場から宿までのアクセスもサインは出ているもののわかりにくく、途中の小さな橋を渡ると看板があって、その先にようやく見えてきます。


【写真 上(左)】 橋を渡ります
【写真 下(右)】 成分の出た河床
橋から見下ろす午王頭川の河床は、ところどころ鉄分で赤茶けていて期待が高まります。まわりは住宅地なのにここだけ異空間。一気に秘湯モードに突入です。


【写真 上(左)】 見えてきました
【写真 下(右)】 エントランス
外観はかなりの鄙び系、雀荘の看板も出ていて、これはB級ワールド炸裂か!? とさらに期待(笑)が高まります。
エントランス脇のサイン「総社温泉センター せせらぎの湯」が正式名称かもしれません。


【写真 上(左)】 帳場
【写真 下(右)】 館内
B級ワールド覚悟で突入すると、館内は意外にきれい。
小物の粋なあしらいなど、大正時代からつづく老舗の矜持のようなものさえ感じられます。


【写真 上(左)】 館内のあしらい
【写真 下(右)】 掲示板
掲示板に掲げられていた「鑛泉旅館 総社鑛泉」の暖簾もいい味を出しています。
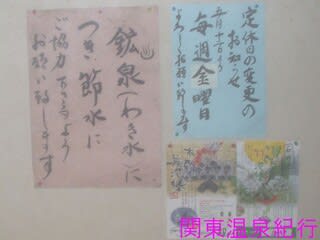
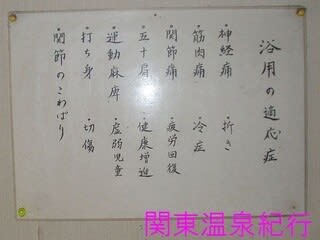
【写真 上(左)】 注意書き
【写真 下(右)】 適応症
せまい廊下を渡った奥に午王頭川沿いにある男女別の浴室。これがまた渋い。
木格子の脱衣棚に籐かごのお約束の展開。
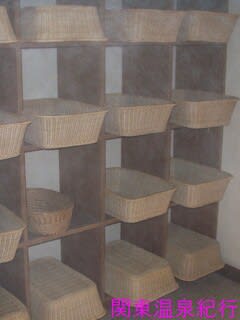

【写真 上(左)】 脱衣所
【写真 下(右)】 日差しの差し込む浴室
扉を開けると板張りの壁、鉄平石の内床の浴室。
午王頭川に面した広い窓から、冬のやわらかな陽射しがさし込んでいます。


【写真 上(左)】 浴室からの景色
【写真 下(右)】 洗い場
カラン6、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。
土曜の12時で贅沢にも独占でした。


【写真 上(左)】 浴槽
【写真 下(右)】 浴槽まわりの析出
浴槽は石枠鉄平石貼り4-5人の趣あるもので、鉄分と石灰華の析出で赤茶に染まった湯船まわりがさらに雰囲気を盛り上げています。
樹脂製の天井が唯一の難点か?


【写真 上(左)】 湯口まわり
【写真 下(右)】 湯口
白い石膏系の析出が出た竹の湯口からおそらく加温した源泉を7L/minほど投入で、槽内注排湯は見あたらず、少量オーバーフローは加温かけ流しメインでは。
やや熱めのお湯は、緑がかった黄褐色ににごった(透明度40㎝)深みのあるいい湯色。
無味で粉っぽい鉄泉臭は、伊勢崎の五色温泉を薄くしたようなイメージ。

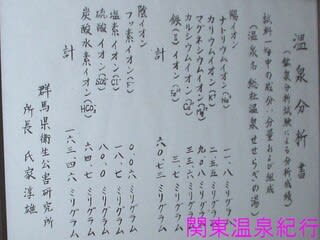
【写真 上(左)】 湯口&湯色
【写真 下(右)】 分析書
濃度感はさほどないものの、よく温まりさらさらとした浴後感が出るなかなかにいいお湯です。
泉質名は不明ですが、温泉分析書の温泉名に「総社温泉 せせらぎの湯」とあるので、分析書記載外の成分、たとえばメタけい酸、メタほう酸などで温泉規定に適合しているかもしれません。
(鉄分(Fe^2+=3.7mg/kg)では温泉規定には乗りません。)
〔関連記事〕
■ 温泉分析書の見方の補足編
■ 療養泉と規定泉
泉質云々よりも、浴室の雰囲気とあわせてじっくり味わうお湯のような気がします。
北関東にはこのような味わいぶかい一軒宿がたくさんありましたが、近年かなりの宿が休廃業となっています。
このお宿も休廃業だとしたら、残念ながらまたひとつ古きよき一軒宿が姿を消してしまったことになります。
〔 温泉名:総社温泉 せせらぎの湯 〕
泉質不明 泉温・pH・湧出量・成分総計不明、Na^+=11.8mg/kg、Ca^2+=33.6、Fe^2+=3.7、Cl^-=18.7、SO_4^2-=80.0、HCO_3^-=64.7、陽イオン計=60.73、陰イオン計=163.46 <分析日不明>
〔 2003年1月入湯、2003/01/27レポに加筆(最新UP2021/01/23) 〕
E139.2.26.370N36.24.51.700
【 BGM 】
■ I.G.Y. - Donald Fagen
現況については確認しておらず不明です。(2021年1月現在)
営業データは入湯時(2003年1月)のものです。


 総社鉱泉 「せせらぎの湯」
総社鉱泉 「せせらぎの湯」住 所 :群馬県前橋市総社町植野985-2
電 話 :027-253-1126
時 間 :11:00~21:00 / 随時変更あり、時間要問合せ
定休日 :毎週金曜
料 金 :700円(以前は500円)
休廃業の可能性もありますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。
入湯は2003年1月で、レポは2003年1月27日。2005年11月08日に加筆したものに今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。
-----------------------------------------
大正14年(1925年)開湯の歴史ある鉱泉宿。
現在は日帰り温泉としても積極的に営業しています。
鉱泉につき、とくに開店時間は変動があるようで、事前の電話確認必須かと・・・。
JR上越線「群馬総社」駅前から細い路地を東に入り、住宅地を300mほど走ると唯一?の看板があり、その先に小さな駐車場があります。


【写真 上(左)】 駐車場
【写真 下(右)】 アプローチ
日帰り温泉ガイドにはけっこう載っていたりしますが、異常にわかりにくいアプローチなのでたどりつけない人もいるかも。
駐車場から宿までのアクセスもサインは出ているもののわかりにくく、途中の小さな橋を渡ると看板があって、その先にようやく見えてきます。


【写真 上(左)】 橋を渡ります
【写真 下(右)】 成分の出た河床
橋から見下ろす午王頭川の河床は、ところどころ鉄分で赤茶けていて期待が高まります。まわりは住宅地なのにここだけ異空間。一気に秘湯モードに突入です。


【写真 上(左)】 見えてきました
【写真 下(右)】 エントランス
外観はかなりの鄙び系、雀荘の看板も出ていて、これはB級ワールド炸裂か!? とさらに期待(笑)が高まります。
エントランス脇のサイン「総社温泉センター せせらぎの湯」が正式名称かもしれません。


【写真 上(左)】 帳場
【写真 下(右)】 館内
B級ワールド覚悟で突入すると、館内は意外にきれい。
小物の粋なあしらいなど、大正時代からつづく老舗の矜持のようなものさえ感じられます。


【写真 上(左)】 館内のあしらい
【写真 下(右)】 掲示板
掲示板に掲げられていた「鑛泉旅館 総社鑛泉」の暖簾もいい味を出しています。
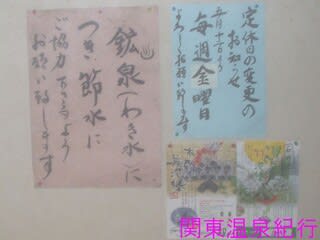
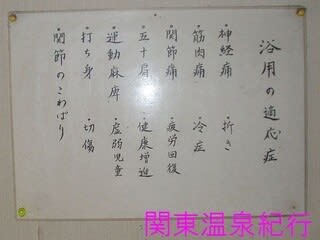
【写真 上(左)】 注意書き
【写真 下(右)】 適応症
せまい廊下を渡った奥に午王頭川沿いにある男女別の浴室。これがまた渋い。
木格子の脱衣棚に籐かごのお約束の展開。
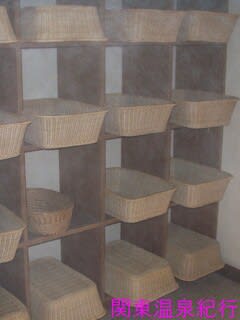

【写真 上(左)】 脱衣所
【写真 下(右)】 日差しの差し込む浴室
扉を開けると板張りの壁、鉄平石の内床の浴室。
午王頭川に面した広い窓から、冬のやわらかな陽射しがさし込んでいます。


【写真 上(左)】 浴室からの景色
【写真 下(右)】 洗い場
カラン6、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。
土曜の12時で贅沢にも独占でした。


【写真 上(左)】 浴槽
【写真 下(右)】 浴槽まわりの析出
浴槽は石枠鉄平石貼り4-5人の趣あるもので、鉄分と石灰華の析出で赤茶に染まった湯船まわりがさらに雰囲気を盛り上げています。
樹脂製の天井が唯一の難点か?


【写真 上(左)】 湯口まわり
【写真 下(右)】 湯口
白い石膏系の析出が出た竹の湯口からおそらく加温した源泉を7L/minほど投入で、槽内注排湯は見あたらず、少量オーバーフローは加温かけ流しメインでは。
やや熱めのお湯は、緑がかった黄褐色ににごった(透明度40㎝)深みのあるいい湯色。
無味で粉っぽい鉄泉臭は、伊勢崎の五色温泉を薄くしたようなイメージ。

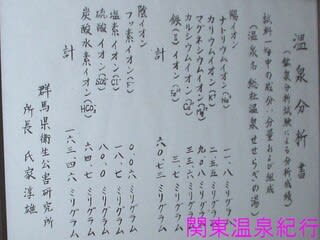
【写真 上(左)】 湯口&湯色
【写真 下(右)】 分析書
濃度感はさほどないものの、よく温まりさらさらとした浴後感が出るなかなかにいいお湯です。
泉質名は不明ですが、温泉分析書の温泉名に「総社温泉 せせらぎの湯」とあるので、分析書記載外の成分、たとえばメタけい酸、メタほう酸などで温泉規定に適合しているかもしれません。
(鉄分(Fe^2+=3.7mg/kg)では温泉規定には乗りません。)
〔関連記事〕
■ 温泉分析書の見方の補足編
■ 療養泉と規定泉
泉質云々よりも、浴室の雰囲気とあわせてじっくり味わうお湯のような気がします。
北関東にはこのような味わいぶかい一軒宿がたくさんありましたが、近年かなりの宿が休廃業となっています。
このお宿も休廃業だとしたら、残念ながらまたひとつ古きよき一軒宿が姿を消してしまったことになります。
〔 温泉名:総社温泉 せせらぎの湯 〕
泉質不明 泉温・pH・湧出量・成分総計不明、Na^+=11.8mg/kg、Ca^2+=33.6、Fe^2+=3.7、Cl^-=18.7、SO_4^2-=80.0、HCO_3^-=64.7、陽イオン計=60.73、陰イオン計=163.46 <分析日不明>
〔 2003年1月入湯、2003/01/27レポに加筆(最新UP2021/01/23) 〕
E139.2.26.370N36.24.51.700
【 BGM 】
■ I.G.Y. - Donald Fagen
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ユーミンの謎?
2021/01/22 UP
このところ、TVで初期~中期のユーミンの曲をよく聴く。
いま聴いても、圧倒的な存在感あり。
どうしてこんなメロディが生み出せたんだろう。
■ ずっとそばに 14th Original Album『REINCARNATION』(1983)収録
淡々とした曲調なのに、ハンパじゃないフック感。
やっぱりユーミンの謎は深い。
-----------------------
2020/11/30 UP
昨日放送の「関ジャム」の松任谷由実特集、録画したやつさっきまで視てました。
今回はなんと松任谷正隆氏がゲスト。
ところどころ、音楽的に掘り下げた内容も。
ユーミンの曲(とくに1980年代中盤までの曲)って、オクターブが広いわけでも音数が多いわけでもないのに、音の広がり感がすごい。
今回、視ていてヒントがふたつ。
ブロックコードと分数コード。
ブロックコードは、ユニゾンにコードトーンを加えていくやつ。↓
分数コード(オン・コード)は、→こういうやつ。
ギター脱初心者レッスン【簡単!分数コード(オンコード)の使い方】これを知ってるとかっいいアルペジオが弾けるよ!(ひこうき雲編)
ちょうど「ひこうき雲」を例にあげている動画がありました。↑
松任谷正隆氏の衝撃発言「コードは考えていない」(笑)
メロディとインプロがあって、あとからコードを充てていくのかな??
それと、松任谷正隆氏の「ローズやめてピアノにかえた」発言。
これわかる。
だって、フェンダーローズとピアノじゃ、曲のイメージぜんぜん変わってしまうから・・・。
こういう楽器のチョイスひとつとっても、ユーミン・サウンドをつくる大事な要素なんだと思う。
それにしても面白かった。
また、こういう構成の音楽番組放送してほしい。
ユーミンは「ラテンの血が騒ぐ曲」もお気に入りみたいだけど、
個人的には「ラテンの血が騒いでいない曲」が好きです(笑)↓
■ ノーサイド 16th Original Album『NO SIDE』(1984)収録
このイントロ、フェンダーローズだと思う。
にしても、すごい名曲。
■ ベルベット・イースター 【YUMING COVER】 1st Original Album『ひこうき雲』(1973)収録
天才的な歌詞と曲構成。初期ユーミンならではの凜とした透明感。
イントロからのクリシェがかった弾むピアノのフレーズが絶妙。
フェンダーローズだったらこの空気感出ないと思う。
■ ロッヂで待つクリスマス 【歌おうfavorite songs 171】
「恋人がサンタクロース」よりも名曲では?
リゾートと都会が直につながっていた1980年前後のユーミンの世界。
全曲名曲の神ALBUM『流線形'80』(1978年)収録。
■ 瞳を閉じて 2nd Original Album『MISSLIM』(1974)収録
この、空に開けていく感じが初期のユーミン。
Tin Pan Alleyのサポートだけに小ワザが効いている。Back Vo.は山下達郎?
■ 翳りゆく部屋 【サンプル?】 7th Original Single(1976)
ユーミン屈指の名曲。神がかった旋律。
c/wが「ベルベット・イースター」とは・・・。
■ 1976 荒井由実(22)コンサート(FM放送フル楽曲版)
超貴重な1976年のライブ音声 2:20~ 翳りゆく部屋
■ 静かなまぼろし 【スタジオライヴ】 6th Original Album『流線形'80』(1978)収録
沢田研二に提供した曲だけど、オリジナルのユーミンVers.がすごくいい。
■ DESTINY 【歌おうfavorite songs 87】 8th Original Album『悲しいほどお天気』(1979)収録
この曲ははずせない。伝説のイントロ。伝説の歌詞。
■ 守ってあげたい (WINGS OF LIGHT "THE GATES OF HEAVEN" TOUR) 12th Original Album『昨晩お会いしましょう』(1981)収録
シンプルなステージでハイトーンのユーミン! コーラスも好演。
観客、楽しそうだな(笑)、もうバブルはじけてるけど・・・(1990~1991年のLIVE)
■ サーフ天国、スキー天国 (初音ミクVers.)
1980年リリースの名盤『SURF&SNOW』収録曲。
これは初音ミクバージョン。名曲です。ぜひユーミンの原曲 ↑ を聴いてみてください。
■ 卒業写真 【カバー】 3rd Original Album『COBALT HOUR』(1975)収録
神曲は時代を超える!
このところ、TVで初期~中期のユーミンの曲をよく聴く。
いま聴いても、圧倒的な存在感あり。
どうしてこんなメロディが生み出せたんだろう。
■ ずっとそばに 14th Original Album『REINCARNATION』(1983)収録
淡々とした曲調なのに、ハンパじゃないフック感。
やっぱりユーミンの謎は深い。
-----------------------
2020/11/30 UP
昨日放送の「関ジャム」の松任谷由実特集、録画したやつさっきまで視てました。
今回はなんと松任谷正隆氏がゲスト。
ところどころ、音楽的に掘り下げた内容も。
ユーミンの曲(とくに1980年代中盤までの曲)って、オクターブが広いわけでも音数が多いわけでもないのに、音の広がり感がすごい。
今回、視ていてヒントがふたつ。
ブロックコードと分数コード。
ブロックコードは、ユニゾンにコードトーンを加えていくやつ。↓
分数コード(オン・コード)は、→こういうやつ。
ギター脱初心者レッスン【簡単!分数コード(オンコード)の使い方】これを知ってるとかっいいアルペジオが弾けるよ!(ひこうき雲編)
ちょうど「ひこうき雲」を例にあげている動画がありました。↑
松任谷正隆氏の衝撃発言「コードは考えていない」(笑)
メロディとインプロがあって、あとからコードを充てていくのかな??
それと、松任谷正隆氏の「ローズやめてピアノにかえた」発言。
これわかる。
だって、フェンダーローズとピアノじゃ、曲のイメージぜんぜん変わってしまうから・・・。
こういう楽器のチョイスひとつとっても、ユーミン・サウンドをつくる大事な要素なんだと思う。
それにしても面白かった。
また、こういう構成の音楽番組放送してほしい。
ユーミンは「ラテンの血が騒ぐ曲」もお気に入りみたいだけど、
個人的には「ラテンの血が騒いでいない曲」が好きです(笑)↓
■ ノーサイド 16th Original Album『NO SIDE』(1984)収録
このイントロ、フェンダーローズだと思う。
にしても、すごい名曲。
■ ベルベット・イースター 【YUMING COVER】 1st Original Album『ひこうき雲』(1973)収録
天才的な歌詞と曲構成。初期ユーミンならではの凜とした透明感。
イントロからのクリシェがかった弾むピアノのフレーズが絶妙。
フェンダーローズだったらこの空気感出ないと思う。
■ ロッヂで待つクリスマス 【歌おうfavorite songs 171】
「恋人がサンタクロース」よりも名曲では?
リゾートと都会が直につながっていた1980年前後のユーミンの世界。
全曲名曲の神ALBUM『流線形'80』(1978年)収録。
■ 瞳を閉じて 2nd Original Album『MISSLIM』(1974)収録
この、空に開けていく感じが初期のユーミン。
Tin Pan Alleyのサポートだけに小ワザが効いている。Back Vo.は山下達郎?
■ 翳りゆく部屋 【サンプル?】 7th Original Single(1976)
ユーミン屈指の名曲。神がかった旋律。
c/wが「ベルベット・イースター」とは・・・。
■ 1976 荒井由実(22)コンサート(FM放送フル楽曲版)
超貴重な1976年のライブ音声 2:20~ 翳りゆく部屋
■ 静かなまぼろし 【スタジオライヴ】 6th Original Album『流線形'80』(1978)収録
沢田研二に提供した曲だけど、オリジナルのユーミンVers.がすごくいい。
■ DESTINY 【歌おうfavorite songs 87】 8th Original Album『悲しいほどお天気』(1979)収録
この曲ははずせない。伝説のイントロ。伝説の歌詞。
■ 守ってあげたい (WINGS OF LIGHT "THE GATES OF HEAVEN" TOUR) 12th Original Album『昨晩お会いしましょう』(1981)収録
シンプルなステージでハイトーンのユーミン! コーラスも好演。
観客、楽しそうだな(笑)、もうバブルはじけてるけど・・・(1990~1991年のLIVE)
■ サーフ天国、スキー天国 (初音ミクVers.)
1980年リリースの名盤『SURF&SNOW』収録曲。
これは初音ミクバージョン。名曲です。ぜひユーミンの原曲 ↑ を聴いてみてください。
■ 卒業写真 【カバー】 3rd Original Album『COBALT HOUR』(1975)収録
神曲は時代を超える!
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)
2021/01/10 UP
ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。
1981年版です。
■ 1979年版
■ 1980年版
■ 1981年版
■ 1982年版
■ 1983年版
※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)
-------------------------
2021/01/09 UP
コメントを入れました。
-------------------------
2021/01/06 UP
8曲追加して20曲にしました。
コメントは追って入れます。
-------------------------
2021/01/04 UP
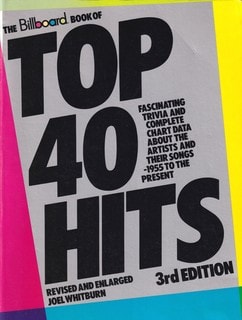
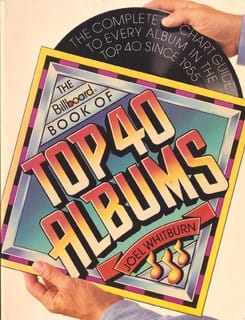
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
01.Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.
3/01/1981 / 2位 16Weeks
洒落た曲だらけの当時でも、ひときわ際立っていたお洒落感はやっぱり「Just the Two of Us進行」によるものか・・・。
はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。
02.More Than Just The Two Of Us - Sneaker
12/19/1981 / 34位 6Weeks
知名度の低いグループだが、これは人気の高い名曲。
エアーサプライっぽいけど、音楽的にははるかに高度。曲調はもろにウエスト・コースト。
レーベルは非メジャーのHandshake、しかもニューフェイスの1St ALBUM。こういう作品もこの頃の日本のレコード会社はしっかりフォローしていた。
03.Let's Groove - Earth, Wind & Fire
10/31/1981 / 3位 16Weeks
1981年秋リリースの『Raise!』(天空の女神)からの大ヒット曲でディスコ・クラシックス。
1977年の『All 'N All』(太陽神)は名盤。1979年の『I Am』(黙示録)も曲に恵まれたがDavid FosterのAORカラーが強く、1980年の『Faces』は2枚組の大作で大きなヒットは出なかった。
このALBUM『Raise!』は一転してHornセクションを前面で打ち出し、ファンク色を強めている。
1983年の『Powerlight』(創世記)はコンセプト色が強すぎ、同じく1983年の『Electric Universe』はエレクトリック色を強めるも振るわず以降一時活動を休止したため、『Raise!』は後期E, W & Fの代表作に位置づけられている。
この曲を聴くとPhilip Baileyのファルセットが、E, W & Fサウンドでいかに重要な役割を果たしていたかがよくわかる。
04.Breaking Away - Balance
8/15/1981 / 22位 9Weeks
知名度は高くないものの質のよい楽曲を残したAOR系グループで、これは1st ALBUM『Balance』からのシングルカット。
ブライトな曲調ながら、どこか引き締まったニュアンスは、ニューヨークベースの活動を物語るところか。
05.While You See A Chance - Steve Winwood
2/28/1981 / 7位 12Weeks
弱冠10歳代でThe Spencer Davis Groupの中心メンバーを張って”天才少年”の名をほしいままにし、以降も、Traffic、Blind Faithと英国名門Rockグループのメインとなった英国のマルチプレイヤー。
R&B、ブルース、ジャズなど多彩なジャンルをベースとする幅広い音楽性をもつ。
'70年代後半からはソロとしても活躍し、これはソロ2作目のALBUM『Arc of a Diver』 (1980) 収録の佳作。
フォーマットはエレクトロポップだが、幅広い音楽性が隠し味となって味わいふかい。
06.In Your Letter - REO SPEEDWAGON
イリノイ州出身のアメリカン・プログレハードの代表グループ。
これは彼らの最大のヒットALBUMとなった名盤『Hi Infidelity』(禁じられた夜)からのシングルカットで邦題は「涙のレター」。
こういう軽快な曲だけでなく、こういうプログレ的なドラマティックなスロー曲→(「I Wish You Were There」)も繰り出せるのがこのグループの強みだった。
07.Bette Davis Eyes - Kim Carnes
4/11/1981 / 1位 20Weeks
1981年5月16日から6月13日にかけてBillboard・Hot 100の1位を5週連続で記録した大ヒット曲。
「ベティ・デイビスの瞳」の邦題で、日本でもヘビロテされていた。
ハスキーな声質でAC/AORの流れからは若干距離のある人だが、AOR系の名手として知られるBill Cuomoのキーボード(シンセ)・リフが絶妙に効いてアダルトで洗練感のある仕上がりとなっている。
08.Steal The Night - Stevie Woods
11/14/1981 / 25位 10Weeks
米国のR&B系アーティストのなかで、もっともAORに接近した一人。
これは1981年リリースの1st ALBUM『Take Me To Your Heaven』からのシングルカット。
DrumsにEd Greene/James Gadson/Ndugu Chancler/Michael Baird、PercussionにPaulinho Da Costa、BassにNathan East、KeyboardにClarence McDonald/Greg Mathieson、GuitarにPaul Jackson, Jr/Steve Lukather/Tim Mayなどの強者を揃え、曲調はモロにAOR。
09.Hearts - Marty Balin
8/15/1981 / 35位 3Weeks
Jefferson Airplane を結成しリードVo.をつとめたMarty Balinの1981年の1stソロALBUM『Balin』からのヒット曲。
どちらかというとMOR寄りでベタな曲が多い人だが、この曲は時代を反映してかAOR的な曲調に仕上がっている。
Jesse Barishの作曲で、名手Bill ChamplinがBack.voに入っていることも大きいかも・・・。
フェンダー・ローズ(by Mark Cummings?)も大活躍。
10.No Reply At All - Genesis
11/07/1981 / 29位 6Weeks
英国プログレッシブ・ロックの代表格、Genesisは1976年に名盤『Wind & Wuthering』(静寂の嵐)を残した後、次第にポップ寄りに舵を切り、これはそんな中で1981年にリリースされたALBUM『Abacab』からのヒット曲。
ポップななかにもところどころにみせるプログレ風味、Phil Collinsのシャープで手数の多いドラムス、Earth, Wind & Fireのホーンセクションなど聴きどころが多い。
11.9 to 5 (Morning Train) - Sheena Easton
2/28/1981 / 1位 15Weeks
じつは当時はかなりAOR/BCM系に振れていたので、こういうMORは積極的には聴いていなかったが、今回聴き返してみて思いのほかよかった。
オールディーズを巧みにモチーフ化して、英国のアーティストらしからぬブライトな曲をものしている。
こういう曲が1位をとるアメリカって、いまからするととても想像できないが・・・。
12.Cool Love - Pablo Cruise
7/25/1981 / 13位 11Weeks
たぶん、1970年代後半にもっともよく聴いていた洋楽グループのひとつだと思う。
(なぜかkalapanaやPablo Cruiseは、1970年代中盤の初期の頃からリアルタイムで聴いていた。)
サラサラと乾いた曲調はThe Beach Boys、kalapanaなどとともに「Surf Rock」と称されて、日本でも人気が高かった。
なんといってもクラシカルなCory Leriosのキーボードが聴きどころで、その醍醐味はこのヒット曲でも堪能できる。
13.Harden My Heart - Quarterflash
11/07/1981 / 3位 19Weeks
オレゴン州ポートランドから彗星のごとくあらわれたバンドで、これは彼らの最初にして最大のヒット曲。
当時はPOPS曲にサックスが入ることはめずらしくなかったが、女性リードボーカルのRindy Rossがみずからサックスを吹いてしまうところに妙なインパクトがあった。
14.Is It You? - Lee Ritenour featuring Eric Tagg
5/23/1981 / 15位 9Weeks
アメリカのフュージョン・ギタリストLee Ritenourが、AOR系シンガー Eric Taggをフューチャーして放ったヒット曲。
1981年リリースのALBUM『Rit』収録。
Jerry Hey(Arranged)、David Foster(key)、Richard Tee(key)、Abraham Laboriel(b)、Harvey Mason(ds)、Alex Acuña(per)、 Bill Champlin(Back vo.)と、ほとんどAORオールスター状態。
あまりに当時の売れ線どまんなかだったため評価は毀誉褒貶相半ばだったが、Lee Ritenourのヒット作のひとつに数えられる作品。
15.Jessie's Girl - Rick Springfield
5/09/1981 / 1位 22Weeks
オーストラリア出身のミュージシャンで俳優もこなしていた。
軽めのウエストコースト系ロックと相性のよい爽快感ある声質で、数曲のヒットを飛ばした。
これは1980年リリースの『Working Class Dog』からの大ヒット曲。
1982年リリースの『Success Hasn't Spoiled Me Yet』も名盤で、この大ヒット曲を凌ぐテイクがある。(たとえば→「Just One Kiss」)
16.How 'bout Us - Champaign
3/28/1981 / 12位 13Weeks
グルーヴの効いたリズム、デュエットにサックスを散りばめた洒落っ気のあるMid~Slowチューン。
POPSとブラコンがもっとも接近したこの時代ならではのユニット&曲調だと思う。
17.Don't Stop Believin' - Journey
11/07/1981 / 9位 13Weeks
全世界で1,000万枚以上を売り上げた大ヒットアルバム『Escape』からのシングルヒットで邦題は「愛に狂って」。
Jonathan Cain / Steve Perry / Neal Schon共作の文句なしの名曲。
↑ はJourney全盛期の伝説的なLIVE動画。こういうパフォーマンスはSteve Perry抜きには絶対に成立しない。
18.Never Too Much - Luther Vandross
11/14/1981 / 33位 4Weeks
Changeの「A Lover's Holiday」「The Glow of Love」「Searching」などでの名唱で名を馳せたLuther Vandrossのデビュー・アルバム『Never Too Much』からのシングルヒット。
↑ このLIVE、Lutherのボーカルもいいけど、ドラムスとベースのグルーヴ出しがハンパじゃない。そして観客のノリ。
19.Kiss On My List - Hall & Oates
2/14/1981 / 1位 17Weeks
やっぱり彼らのベストって個人的には「Maneater」じゃなくて、この曲や「Wait for Me」「Everytime You Go Away」あたりだと思う。
20.Just Once - Quincy Jones (feat. James Ingram)
9/19/1981 / 17位 10Weeks
「愛のコリーダ」の大ヒットを出し日本でも人気の高かった大御所Quincy Jones。
これは1981の名盤『The Dude』からのシングルヒットで、秘蔵っ子といわれたJames Ingramがリードをとり、同じく秘蔵っ子といわれた Patti AustinがBacki voに入っている。
Barry Mann & Cynthia Weilならではのメロディアスなバラードでフックあり。
David Foster、Robbie Buchanan、Ian Underwoodの名手3人が繰り出すキーボードが強力すぎる(笑)
ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。
1981年版です。
■ 1979年版
■ 1980年版
■ 1981年版
■ 1982年版
■ 1983年版
※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)
-------------------------
2021/01/09 UP
コメントを入れました。
-------------------------
2021/01/06 UP
8曲追加して20曲にしました。
コメントは追って入れます。
-------------------------
2021/01/04 UP
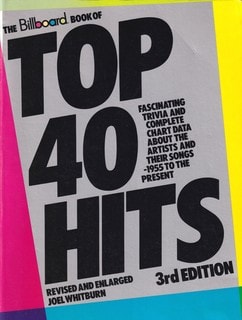
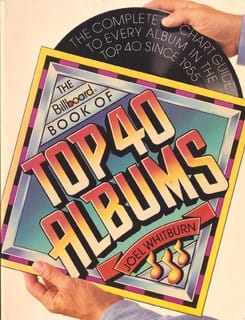
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
01.Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.
3/01/1981 / 2位 16Weeks
洒落た曲だらけの当時でも、ひときわ際立っていたお洒落感はやっぱり「Just the Two of Us進行」によるものか・・・。
はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。
02.More Than Just The Two Of Us - Sneaker
12/19/1981 / 34位 6Weeks
知名度の低いグループだが、これは人気の高い名曲。
エアーサプライっぽいけど、音楽的にははるかに高度。曲調はもろにウエスト・コースト。
レーベルは非メジャーのHandshake、しかもニューフェイスの1St ALBUM。こういう作品もこの頃の日本のレコード会社はしっかりフォローしていた。
03.Let's Groove - Earth, Wind & Fire
10/31/1981 / 3位 16Weeks
1981年秋リリースの『Raise!』(天空の女神)からの大ヒット曲でディスコ・クラシックス。
1977年の『All 'N All』(太陽神)は名盤。1979年の『I Am』(黙示録)も曲に恵まれたがDavid FosterのAORカラーが強く、1980年の『Faces』は2枚組の大作で大きなヒットは出なかった。
このALBUM『Raise!』は一転してHornセクションを前面で打ち出し、ファンク色を強めている。
1983年の『Powerlight』(創世記)はコンセプト色が強すぎ、同じく1983年の『Electric Universe』はエレクトリック色を強めるも振るわず以降一時活動を休止したため、『Raise!』は後期E, W & Fの代表作に位置づけられている。
この曲を聴くとPhilip Baileyのファルセットが、E, W & Fサウンドでいかに重要な役割を果たしていたかがよくわかる。
04.Breaking Away - Balance
8/15/1981 / 22位 9Weeks
知名度は高くないものの質のよい楽曲を残したAOR系グループで、これは1st ALBUM『Balance』からのシングルカット。
ブライトな曲調ながら、どこか引き締まったニュアンスは、ニューヨークベースの活動を物語るところか。
05.While You See A Chance - Steve Winwood
2/28/1981 / 7位 12Weeks
弱冠10歳代でThe Spencer Davis Groupの中心メンバーを張って”天才少年”の名をほしいままにし、以降も、Traffic、Blind Faithと英国名門Rockグループのメインとなった英国のマルチプレイヤー。
R&B、ブルース、ジャズなど多彩なジャンルをベースとする幅広い音楽性をもつ。
'70年代後半からはソロとしても活躍し、これはソロ2作目のALBUM『Arc of a Diver』 (1980) 収録の佳作。
フォーマットはエレクトロポップだが、幅広い音楽性が隠し味となって味わいふかい。
06.In Your Letter - REO SPEEDWAGON
イリノイ州出身のアメリカン・プログレハードの代表グループ。
これは彼らの最大のヒットALBUMとなった名盤『Hi Infidelity』(禁じられた夜)からのシングルカットで邦題は「涙のレター」。
こういう軽快な曲だけでなく、こういうプログレ的なドラマティックなスロー曲→(「I Wish You Were There」)も繰り出せるのがこのグループの強みだった。
07.Bette Davis Eyes - Kim Carnes
4/11/1981 / 1位 20Weeks
1981年5月16日から6月13日にかけてBillboard・Hot 100の1位を5週連続で記録した大ヒット曲。
「ベティ・デイビスの瞳」の邦題で、日本でもヘビロテされていた。
ハスキーな声質でAC/AORの流れからは若干距離のある人だが、AOR系の名手として知られるBill Cuomoのキーボード(シンセ)・リフが絶妙に効いてアダルトで洗練感のある仕上がりとなっている。
08.Steal The Night - Stevie Woods
11/14/1981 / 25位 10Weeks
米国のR&B系アーティストのなかで、もっともAORに接近した一人。
これは1981年リリースの1st ALBUM『Take Me To Your Heaven』からのシングルカット。
DrumsにEd Greene/James Gadson/Ndugu Chancler/Michael Baird、PercussionにPaulinho Da Costa、BassにNathan East、KeyboardにClarence McDonald/Greg Mathieson、GuitarにPaul Jackson, Jr/Steve Lukather/Tim Mayなどの強者を揃え、曲調はモロにAOR。
09.Hearts - Marty Balin
8/15/1981 / 35位 3Weeks
Jefferson Airplane を結成しリードVo.をつとめたMarty Balinの1981年の1stソロALBUM『Balin』からのヒット曲。
どちらかというとMOR寄りでベタな曲が多い人だが、この曲は時代を反映してかAOR的な曲調に仕上がっている。
Jesse Barishの作曲で、名手Bill ChamplinがBack.voに入っていることも大きいかも・・・。
フェンダー・ローズ(by Mark Cummings?)も大活躍。
10.No Reply At All - Genesis
11/07/1981 / 29位 6Weeks
英国プログレッシブ・ロックの代表格、Genesisは1976年に名盤『Wind & Wuthering』(静寂の嵐)を残した後、次第にポップ寄りに舵を切り、これはそんな中で1981年にリリースされたALBUM『Abacab』からのヒット曲。
ポップななかにもところどころにみせるプログレ風味、Phil Collinsのシャープで手数の多いドラムス、Earth, Wind & Fireのホーンセクションなど聴きどころが多い。
11.9 to 5 (Morning Train) - Sheena Easton
2/28/1981 / 1位 15Weeks
じつは当時はかなりAOR/BCM系に振れていたので、こういうMORは積極的には聴いていなかったが、今回聴き返してみて思いのほかよかった。
オールディーズを巧みにモチーフ化して、英国のアーティストらしからぬブライトな曲をものしている。
こういう曲が1位をとるアメリカって、いまからするととても想像できないが・・・。
12.Cool Love - Pablo Cruise
7/25/1981 / 13位 11Weeks
たぶん、1970年代後半にもっともよく聴いていた洋楽グループのひとつだと思う。
(なぜかkalapanaやPablo Cruiseは、1970年代中盤の初期の頃からリアルタイムで聴いていた。)
サラサラと乾いた曲調はThe Beach Boys、kalapanaなどとともに「Surf Rock」と称されて、日本でも人気が高かった。
なんといってもクラシカルなCory Leriosのキーボードが聴きどころで、その醍醐味はこのヒット曲でも堪能できる。
13.Harden My Heart - Quarterflash
11/07/1981 / 3位 19Weeks
オレゴン州ポートランドから彗星のごとくあらわれたバンドで、これは彼らの最初にして最大のヒット曲。
当時はPOPS曲にサックスが入ることはめずらしくなかったが、女性リードボーカルのRindy Rossがみずからサックスを吹いてしまうところに妙なインパクトがあった。
14.Is It You? - Lee Ritenour featuring Eric Tagg
5/23/1981 / 15位 9Weeks
アメリカのフュージョン・ギタリストLee Ritenourが、AOR系シンガー Eric Taggをフューチャーして放ったヒット曲。
1981年リリースのALBUM『Rit』収録。
Jerry Hey(Arranged)、David Foster(key)、Richard Tee(key)、Abraham Laboriel(b)、Harvey Mason(ds)、Alex Acuña(per)、 Bill Champlin(Back vo.)と、ほとんどAORオールスター状態。
あまりに当時の売れ線どまんなかだったため評価は毀誉褒貶相半ばだったが、Lee Ritenourのヒット作のひとつに数えられる作品。
15.Jessie's Girl - Rick Springfield
5/09/1981 / 1位 22Weeks
オーストラリア出身のミュージシャンで俳優もこなしていた。
軽めのウエストコースト系ロックと相性のよい爽快感ある声質で、数曲のヒットを飛ばした。
これは1980年リリースの『Working Class Dog』からの大ヒット曲。
1982年リリースの『Success Hasn't Spoiled Me Yet』も名盤で、この大ヒット曲を凌ぐテイクがある。(たとえば→「Just One Kiss」)
16.How 'bout Us - Champaign
3/28/1981 / 12位 13Weeks
グルーヴの効いたリズム、デュエットにサックスを散りばめた洒落っ気のあるMid~Slowチューン。
POPSとブラコンがもっとも接近したこの時代ならではのユニット&曲調だと思う。
17.Don't Stop Believin' - Journey
11/07/1981 / 9位 13Weeks
全世界で1,000万枚以上を売り上げた大ヒットアルバム『Escape』からのシングルヒットで邦題は「愛に狂って」。
Jonathan Cain / Steve Perry / Neal Schon共作の文句なしの名曲。
↑ はJourney全盛期の伝説的なLIVE動画。こういうパフォーマンスはSteve Perry抜きには絶対に成立しない。
18.Never Too Much - Luther Vandross
11/14/1981 / 33位 4Weeks
Changeの「A Lover's Holiday」「The Glow of Love」「Searching」などでの名唱で名を馳せたLuther Vandrossのデビュー・アルバム『Never Too Much』からのシングルヒット。
↑ このLIVE、Lutherのボーカルもいいけど、ドラムスとベースのグルーヴ出しがハンパじゃない。そして観客のノリ。
19.Kiss On My List - Hall & Oates
2/14/1981 / 1位 17Weeks
やっぱり彼らのベストって個人的には「Maneater」じゃなくて、この曲や「Wait for Me」「Everytime You Go Away」あたりだと思う。
20.Just Once - Quincy Jones (feat. James Ingram)
9/19/1981 / 17位 10Weeks
「愛のコリーダ」の大ヒットを出し日本でも人気の高かった大御所Quincy Jones。
これは1981の名盤『The Dude』からのシングルヒットで、秘蔵っ子といわれたJames Ingramがリードをとり、同じく秘蔵っ子といわれた Patti AustinがBacki voに入っている。
Barry Mann & Cynthia Weilならではのメロディアスなバラードでフックあり。
David Foster、Robbie Buchanan、Ian Underwoodの名手3人が繰り出すキーボードが強力すぎる(笑)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 1980年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)
2021/01/10 UP
ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。
まずは1980年版です。
■ 1979年版
■ 1980年版
■ 1981年版
■ 1982年版
■ 1983年版
※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)
-------------------------
2021/01/09 UP
コメントを入れました。
-------------------------
2021/01/06 UP
8曲追加して20曲にしました。
コメントは追って入れます。
-------------------------
2021/01/04 UP
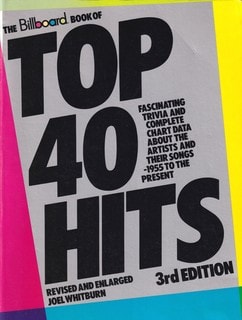
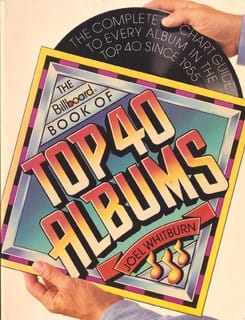
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
01.Celebration - Kool & The Gang
11/22/1980 / 1位 21Weeks
ニュージャージー州出身で、もともとファンクバンドだったこともあって、この頃のBCMユニットとしては洗練度は弱いが、それだけにMOR寄りのメジャー感が受けて大きなヒットをいくつか飛ばしている。これはその中でも代表曲。
リズムセクションはどちらかというと荒削りだが、カッティング・ギターがほどよく効いてグルーヴ感を醸し出している。
02.Biggest Part Of Me - Ambrosia
4/19/1980 / 3位 14Weeks
もともとはアメリカン・プログレ(ハード)バンドだったが次第に洗練度を増し、満を持して放った名盤『One Eighty』(真夜中の晩餐会)からのシングルカット曲。
AORな曲調にDavid Packのハイトーンボーカルがひときわ光っている。
1995年にコーラスユニット「Take 6」がカバーし、これもヒットした。
03.Sexy Eyes - Dr. Hook
3/15/1980 / 5位 15Weeks
1968年ニュージャージーで結成された古株バンドで当初はカントリー系の曲風だったが、1970年代中盤からAOR風味を強め、その手のALBUMを何枚か残している。
フロントマンRay Sawyerの個性的な風貌から「キワモノバンド」と思われがちだが、なかなかどうしてこ洒落たパフォーマンスを展開している
04.No Right So Long - Dionne Warwick
9/06/1980 / 23位 6Weeks
Whitney Houstonの従姉妹としても知られる米国のメジャー・シンガー。
Burt Bacharach作品の歌い手としてキャリアーを積んできただけに、こういうメロディアスなバラードはお手のもの。
Richard Kerr作のこの曲はやや単調な構成だが、ALBUM曲に名曲多数なのでリストしてみました。
(1982年にはこんな名曲↓「Never Gonna Let You Go」も。)
05.Last Train To London - Electric Light Orchestra
1/26/1980 / 39位 2Weeks
ストリングスを導入し、華麗なメロディ&アレンジに定評があった英国のロックバンドで、プログレハードのジャンルで語られることが多い。
これは1979年リリースの名盤『Discovery』からのシングルカットで「ロンドン行き最終列車」の邦題がつけられ日本でもよくかかっていた。
同ALBUM収録の「Confusion」もキャッチーなメロディラインの名曲。
06.A Lover's Holiday - Change
7/19/1980 / 40位 1Weeks
イタリア系のJacques Fred PetrusとMauro Malavasiがプロデュースした1980年代前半を代表するディスコ・ユニットの初期のヒット曲。
1980年リリースの1st ALBUM『The Glow Of Love』のA-1曲で、なんといってもLuther Vandrossのボーカルが秀逸。
Luther Vandrossの濃厚なボーカルがChangeならではのこ洒落たサウンドと絶妙にマッチした好テイク。
07.Shining Star - Manhattans
5/31/1980 / 5位 14Weeks
名盤『After Midnight』(マンハッタン・ミッドナイト)からのシングルカット。
この頃のブラコンは、ディスコ曲だけじゃなく、こういうバラード曲も粒ぞろいだった。
洗練された曲調で、やっぱり”ソウル”じゃなくて”ブラコン”だと思う。
1980年代前半には、Temptaions、Whispers、Chi-Lites、Tavaresなど並み居るソウル・コーラス・グループも数々の名盤をリリースしていた。
08.And The Beat Goes On - The Whispers
3/15/1980 / 19位 8Weeks
日本ではわりと地味な存在ながら1970年代後半~1980年代前半にかけて多くの好盤をリリースしたカリフォリニアのコーラス・グループ。
これは1979年リリースの『The Whispers』からのヒット曲。
ディスコ曲もバラードもそつなくこなす彼らの技量が感じられる佳曲。
カッティングギター、チョッパーベース、シンセリフ、ショートなストリングスなど、この時代ならではの音。
09.99 - TOTO
2/09/1980 / 26位 8Weeks
1979年リリースの2nd ALBUM『Hydra』からのシングルカット曲。
TOTOの楽曲のなかでは、ハードすぎずベタすぎず、もっともアダルトなイメージがある曲だと思う。
10.Do You Love What You Feel - Rufus & Chaka Khan
1/19/1980 / 30位 4Weeks
その気性の激しさから「Chaka」(アフリカの言語で「炎」「赤い」をあらわす)の芸名がついたという、R&B屈指のディーバChaka Khan。
実力者揃いのRufusを向こうに回し、一歩も引かない存在感はさすがにディーバの貫禄。
それにしても、リズムよく跳ねてます。(Drums-John Robinson、Bass -Bobby Watson)
1979年の名盤『Masterjam』収録。
11.Hey Nineteen - Steely Dan
12/13/1980 / 10位 13Weeks
Steely Danの1980年リリースの『Gaucho』からのシングルヒット。
個人的には1977年リリースの『Aja』の方が出来は上だと思うが、この曲でもSteely Danならではの洒落っ気は十分に感じられる。
Drums はRick Marottaで、Steve GaddがPercussionにまわっているめずらしい展開。
12.If You Should Sail - Nielsen/Pearson
11/15/1980 / 38位 2Weeks
AORフリークには人気の高いユニットで1980年リリースの『Nielsen/Pearson』からのシングルカット。
この曲のMark PearsonのボーカルはほとんどBill Champlinじゃないかと思うほど張りがある。
中盤やや荒削りな感じはあるが、安定のAORテイストはこのつぎに出されたAOR屈指の名盤『Blind Luck』(1983年)につながるものだと思う。
13.Give Me The Night - George Benson
8/09/1980 / 3位 20Weeks
フュージョンとAORの接点としてGeorge Bensonの存在は欠かすことができない。
これは1980年リリースのフュージョンのマスターピース『Give Me The Night』からの大ヒット曲。
軽めにグルーヴするギター&リズム、嫌みなくスキャットをかますセンスは抜群。
でも、個人的には彼のベストALBUMは1983年の『In Your Eyes』 だと思う。
14.He's So Shy - Pointer Sisters
8/30/1980 / 3位 17Weeks
カリフォルニア州オークランド出身のR&B系姉妹バンドが放ったヒット曲。
全盛期は1984年だが、1980年時点でも人気は高くR&B系ながらMORとしても通用するポピュラリティ-をもっていた。
15.How Do I Survive - Amy Holland
9/13/1980 / 22位 6Weeks
Michael McDonaldの奥様Amy Hollandが1980年の夏に放ったヒット曲。
英国のAORバンド「The Bliss Band 」のオリジナル曲をカバー。
同じくAOR系のDan Sealsも1980年のALBUM『Stones』でカバーしている。
AOR的に捌きやすい曲調だったのだと思う。
16.Special Lady - Ray, Goodman & Brown
2/16/1980 / 5位 14Weeks
ワシントンD.C.で結成されたソウル・コーラス・グループの1st ALBUM『Ray, Goodman & Brown』からのヒット曲。
もともとはThe Moments名義で活動し、Polydor移籍時にグループ名を改称。
Harry Ray、Al Goodman,、Billy Brownのハーモニーが抜群で、このALBUMののち'80年代中盤にかけてリリースされた『Ray, Goodman & Brown II』『Stay』『Open Up』はどれも粒ぞろいの名盤。
17.Real Love - The Doobie Brothers
9/06/1980 / 5位 11Weeks
The Doobie BrothersがもっともAOR色を強めたALBUM『One Step Closer』からのシングル曲。
後期のThe Doobie Brothersで、Michael McDonaldの存在がいかに大きかったかは、↑のソロLIVEを聴くいてみるとよくわかる。
18.Someone That I Used To Love - Natalie Cole
8/09/1980 / 21位 9Weeks
1980年リリースのALBUM『Don't Look Back』からのシングルヒット曲。
Gerry Goffin&Michael Masserの作曲らしい華麗なバラード。
KeyはMichael Masserがみずから参画し、Rick Schlosser(ds)、Leland Sklar(b)という渋い取りあわせのリズムセクションもいい味を出している。
この曲のヒットで勢いを得たNatalieは、'80年代中盤にかけて『I'm Ready』『Everlasting』『Good To Be Back』などの名作を世に送り出すことになる。
19.JoJo - Boz Scaggs
7/12/1980 / 17位 9Weeks
典型的なBoz節。ゆらぐことのないグルーヴ感。
20.Sailing - Christopher Cross
7/05/1980 / 1位 13Weeks
AOR屈指の名曲。なにもいうことはありません(笑)
ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。
まずは1980年版です。
■ 1979年版
■ 1980年版
■ 1981年版
■ 1982年版
■ 1983年版
※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)
-------------------------
2021/01/09 UP
コメントを入れました。
-------------------------
2021/01/06 UP
8曲追加して20曲にしました。
コメントは追って入れます。
-------------------------
2021/01/04 UP
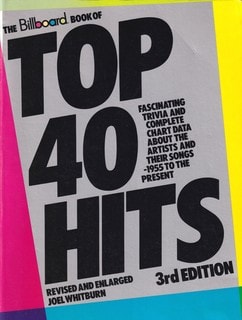
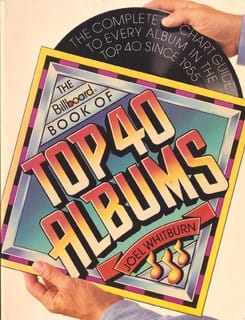
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)
→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。
今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。
つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。
今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。
日付はチャート最高位の獲得日です。
とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)
コメントは後日入れます。
このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。
01.Celebration - Kool & The Gang
11/22/1980 / 1位 21Weeks
ニュージャージー州出身で、もともとファンクバンドだったこともあって、この頃のBCMユニットとしては洗練度は弱いが、それだけにMOR寄りのメジャー感が受けて大きなヒットをいくつか飛ばしている。これはその中でも代表曲。
リズムセクションはどちらかというと荒削りだが、カッティング・ギターがほどよく効いてグルーヴ感を醸し出している。
02.Biggest Part Of Me - Ambrosia
4/19/1980 / 3位 14Weeks
もともとはアメリカン・プログレ(ハード)バンドだったが次第に洗練度を増し、満を持して放った名盤『One Eighty』(真夜中の晩餐会)からのシングルカット曲。
AORな曲調にDavid Packのハイトーンボーカルがひときわ光っている。
1995年にコーラスユニット「Take 6」がカバーし、これもヒットした。
03.Sexy Eyes - Dr. Hook
3/15/1980 / 5位 15Weeks
1968年ニュージャージーで結成された古株バンドで当初はカントリー系の曲風だったが、1970年代中盤からAOR風味を強め、その手のALBUMを何枚か残している。
フロントマンRay Sawyerの個性的な風貌から「キワモノバンド」と思われがちだが、なかなかどうしてこ洒落たパフォーマンスを展開している
04.No Right So Long - Dionne Warwick
9/06/1980 / 23位 6Weeks
Whitney Houstonの従姉妹としても知られる米国のメジャー・シンガー。
Burt Bacharach作品の歌い手としてキャリアーを積んできただけに、こういうメロディアスなバラードはお手のもの。
Richard Kerr作のこの曲はやや単調な構成だが、ALBUM曲に名曲多数なのでリストしてみました。
(1982年にはこんな名曲↓「Never Gonna Let You Go」も。)
05.Last Train To London - Electric Light Orchestra
1/26/1980 / 39位 2Weeks
ストリングスを導入し、華麗なメロディ&アレンジに定評があった英国のロックバンドで、プログレハードのジャンルで語られることが多い。
これは1979年リリースの名盤『Discovery』からのシングルカットで「ロンドン行き最終列車」の邦題がつけられ日本でもよくかかっていた。
同ALBUM収録の「Confusion」もキャッチーなメロディラインの名曲。
06.A Lover's Holiday - Change
7/19/1980 / 40位 1Weeks
イタリア系のJacques Fred PetrusとMauro Malavasiがプロデュースした1980年代前半を代表するディスコ・ユニットの初期のヒット曲。
1980年リリースの1st ALBUM『The Glow Of Love』のA-1曲で、なんといってもLuther Vandrossのボーカルが秀逸。
Luther Vandrossの濃厚なボーカルがChangeならではのこ洒落たサウンドと絶妙にマッチした好テイク。
07.Shining Star - Manhattans
5/31/1980 / 5位 14Weeks
名盤『After Midnight』(マンハッタン・ミッドナイト)からのシングルカット。
この頃のブラコンは、ディスコ曲だけじゃなく、こういうバラード曲も粒ぞろいだった。
洗練された曲調で、やっぱり”ソウル”じゃなくて”ブラコン”だと思う。
1980年代前半には、Temptaions、Whispers、Chi-Lites、Tavaresなど並み居るソウル・コーラス・グループも数々の名盤をリリースしていた。
08.And The Beat Goes On - The Whispers
3/15/1980 / 19位 8Weeks
日本ではわりと地味な存在ながら1970年代後半~1980年代前半にかけて多くの好盤をリリースしたカリフォリニアのコーラス・グループ。
これは1979年リリースの『The Whispers』からのヒット曲。
ディスコ曲もバラードもそつなくこなす彼らの技量が感じられる佳曲。
カッティングギター、チョッパーベース、シンセリフ、ショートなストリングスなど、この時代ならではの音。
09.99 - TOTO
2/09/1980 / 26位 8Weeks
1979年リリースの2nd ALBUM『Hydra』からのシングルカット曲。
TOTOの楽曲のなかでは、ハードすぎずベタすぎず、もっともアダルトなイメージがある曲だと思う。
10.Do You Love What You Feel - Rufus & Chaka Khan
1/19/1980 / 30位 4Weeks
その気性の激しさから「Chaka」(アフリカの言語で「炎」「赤い」をあらわす)の芸名がついたという、R&B屈指のディーバChaka Khan。
実力者揃いのRufusを向こうに回し、一歩も引かない存在感はさすがにディーバの貫禄。
それにしても、リズムよく跳ねてます。(Drums-John Robinson、Bass -Bobby Watson)
1979年の名盤『Masterjam』収録。
11.Hey Nineteen - Steely Dan
12/13/1980 / 10位 13Weeks
Steely Danの1980年リリースの『Gaucho』からのシングルヒット。
個人的には1977年リリースの『Aja』の方が出来は上だと思うが、この曲でもSteely Danならではの洒落っ気は十分に感じられる。
Drums はRick Marottaで、Steve GaddがPercussionにまわっているめずらしい展開。
12.If You Should Sail - Nielsen/Pearson
11/15/1980 / 38位 2Weeks
AORフリークには人気の高いユニットで1980年リリースの『Nielsen/Pearson』からのシングルカット。
この曲のMark PearsonのボーカルはほとんどBill Champlinじゃないかと思うほど張りがある。
中盤やや荒削りな感じはあるが、安定のAORテイストはこのつぎに出されたAOR屈指の名盤『Blind Luck』(1983年)につながるものだと思う。
13.Give Me The Night - George Benson
8/09/1980 / 3位 20Weeks
フュージョンとAORの接点としてGeorge Bensonの存在は欠かすことができない。
これは1980年リリースのフュージョンのマスターピース『Give Me The Night』からの大ヒット曲。
軽めにグルーヴするギター&リズム、嫌みなくスキャットをかますセンスは抜群。
でも、個人的には彼のベストALBUMは1983年の『In Your Eyes』 だと思う。
14.He's So Shy - Pointer Sisters
8/30/1980 / 3位 17Weeks
カリフォルニア州オークランド出身のR&B系姉妹バンドが放ったヒット曲。
全盛期は1984年だが、1980年時点でも人気は高くR&B系ながらMORとしても通用するポピュラリティ-をもっていた。
15.How Do I Survive - Amy Holland
9/13/1980 / 22位 6Weeks
Michael McDonaldの奥様Amy Hollandが1980年の夏に放ったヒット曲。
英国のAORバンド「The Bliss Band 」のオリジナル曲をカバー。
同じくAOR系のDan Sealsも1980年のALBUM『Stones』でカバーしている。
AOR的に捌きやすい曲調だったのだと思う。
16.Special Lady - Ray, Goodman & Brown
2/16/1980 / 5位 14Weeks
ワシントンD.C.で結成されたソウル・コーラス・グループの1st ALBUM『Ray, Goodman & Brown』からのヒット曲。
もともとはThe Moments名義で活動し、Polydor移籍時にグループ名を改称。
Harry Ray、Al Goodman,、Billy Brownのハーモニーが抜群で、このALBUMののち'80年代中盤にかけてリリースされた『Ray, Goodman & Brown II』『Stay』『Open Up』はどれも粒ぞろいの名盤。
17.Real Love - The Doobie Brothers
9/06/1980 / 5位 11Weeks
The Doobie BrothersがもっともAOR色を強めたALBUM『One Step Closer』からのシングル曲。
後期のThe Doobie Brothersで、Michael McDonaldの存在がいかに大きかったかは、↑のソロLIVEを聴くいてみるとよくわかる。
18.Someone That I Used To Love - Natalie Cole
8/09/1980 / 21位 9Weeks
1980年リリースのALBUM『Don't Look Back』からのシングルヒット曲。
Gerry Goffin&Michael Masserの作曲らしい華麗なバラード。
KeyはMichael Masserがみずから参画し、Rick Schlosser(ds)、Leland Sklar(b)という渋い取りあわせのリズムセクションもいい味を出している。
この曲のヒットで勢いを得たNatalieは、'80年代中盤にかけて『I'm Ready』『Everlasting』『Good To Be Back』などの名作を世に送り出すことになる。
19.JoJo - Boz Scaggs
7/12/1980 / 17位 9Weeks
典型的なBoz節。ゆらぐことのないグルーヴ感。
20.Sailing - Christopher Cross
7/05/1980 / 1位 13Weeks
AOR屈指の名曲。なにもいうことはありません(笑)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 熱海温泉(上宿)「上宿新宿共同浴場」 / 法界山 誓欣院
数年ぶりに温泉のレポ記事を書こうと思うのですが、新型コロナ禍が収まる気配をみせないなか、現役施設のレポはどうかな? とも思うので、しばらくは休廃業となった施設をレポしていきます。
熱海温泉には、水口共同浴場、水口第二共同浴場、渚共同浴場、清水町浴場、山田湯、駅前温泉浴場、そして上宿新宿共同浴場など、いくつかの共同浴場がありました。
熱海はもともと内湯が主力の温泉地で、共同浴場など外湯の数は多くありませんでした。
熱海の温泉は高温で塩分を含むものが多く、温泉施設の維持にはコストがかかり、温泉組合員の減少などの問題も顕在化していました。
そんなこともあってか、これらの貴重な共同浴場の多くは近年相次いで休廃業となり、現在外来客が入浴できる施設は数少なくなりました。
熱海の共同浴場はもともと地元住民向けの施設が多く、その入浴難易度はかなり高いものでした。
Web上のレポも多くはないので、順次記録の意味でUPしていきたいと思います。
今回は「上宿(かみしゅく)新宿共同浴場」。
「関東周辺立ち寄り温泉みしゅらん」で特集いただいた記事のリニューアル版です。
※ この施設は平成21年(2009年)に廃止されました。下記は営業時のデータです。
 熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」
熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」
住 所 :静岡県熱海市上宿町6-2
電 話 :0557-81-5773
時 間 :14:30~20:20 / 不定休
料 金 :400円
廃止施設ですが、以前の情報や雰囲気を記録するため、極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。
入湯は2005年11月および2008年4月で、主に2005年11月をベースに書いています。


【写真 上(左)】 外観(2005年)
【写真 下(右)】 男湯(2008年)
市内上宿地区にある共同浴場です。
やませみさんから「明治期の大湯の分析にひじょうに近い」という情報をいただき、たまらず突入しました。
場所は市役所の山側、上宿地区。大湯間欠泉から糸川を一本隔てた位置にあります。
市役所となりの中央町公共Pが近いですが混んでいて入れにくく有料なので、スーパー「マックスバリュ」のPにとめて(なにか買い物をすれば2時間まで無料)歩いて行ったほうがいいかも。徒歩4.5分です。


【写真 上(左)】 観音橋
【写真 下(右)】 入口(2008年)


【写真 上(左)】 糸川側から
【写真 下(右)】 糸川への排湯
市役所の前を通り「ニューフジヤホテル」手前(糸川を渡る橋の手前)の路地を山側に入り、温泉寺を左にみてそのすぐ先にある誓欣院参道の観音橋のたもと。
「山田湯」や「渚浴場」にくらべるとぜんぜんわかりやすいです。
朱塗りの橋と共同浴場の白壁、その上に誓欣院の鐘楼と山門が重なり見ごたえがあります。


【写真 上(左)】 内廊下(2005年)
【写真 下(右)】 番台(2008年)
総木造の館内に男女別の浴場。
小さな番台と壁に祀られた神棚、木格子の脱衣棚に年季入った台秤など、共同浴場ならではの風情をただよわせています。
なお、番台は無人のときがあるようなので、小銭で400円用意していったほうがいいかと。


【写真 上(左)】 脱衣所-1(2005年)
【写真 下(右)】 脱衣所-2(2005年)
扉をあけると浴室。
浴室は思いのほか広く、左右の壁面にカラン(計8位)、中央に椅子と桶が山型に積まれています。


【写真 上(左)】 男湯(2005年)
【写真 下(右)】 女湯(2008年)
奥に水色タイル貼3-4人のふたつの浴槽があり、向かって右が熱湯槽、左が適温槽。
ともに石膏の析出と緑青におおわれたカランからゲキ熱の源泉を投入で、よこにうめ水用の水カランもあります。


【写真 上(左)】 男湯適温槽(2008年)
【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2008年)
こういう場合は、外来客は熱湯槽の水カランは使わないのが暗黙のルールで、熱湯槽はゲキ熱でしたが、あとから入ってきた常連さんが水を入れてくれました。
なお、熱湯槽の表示は2005年は「あつい湯」、2008年は「上り湯」で、2008年時点では熱湯槽は上がり湯専用になっていたかもしれません。
共同浴場につきアメニティ類はなし。
常連さんによるとお湯は湯前神社あたりから引いていて、ここにくると70℃くらい、熱交換で冷ましているがそれでも熱いとのこと。
なお、温泉分析書記載の源泉名は「熱海19号泉・野村湯」。
熱海市発行の「熱海温泉誌」(2017年)記載の「昭和11年(1936年)頃の温泉源地一覧」によると、「野村湯」は温泉番号65番、熱海町有、掘削深度49.10m、所在地番は本町447-2となっています。

【写真】 男湯適温槽の湯口(2005年)
熱交換でつくられる真湯のお湯がカランから出るのがありがたいとも・・・。
そういえば(2005年)夏に行った蔵王でも、真湯の浴槽やカランがあるのが宿のウリになるという話をききました。
温泉好きはカランも温泉だと嬉しいものですが、強くて熱いお湯の温泉地では、そんなものなのでしょう。


【写真 上(左)】 男湯適温槽(2005年)
【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2005年)
やや懸濁したお湯は弱い苦味と強いながらもどこかまろみを感じる塩味。
おだやかな磯の香が香り立ち、等張泉らしい適度な重みに明瞭なとろみと土類系の肌に食い込んでくるような力強さが加わるすばらしいもの。
このとろみは、たぶんメタけい酸=271.0mg/kgによるものと思います。
熱海がお湯のよさで語られることは意外と少ないですが、熱海本来のお湯は、力感と深みをあわせ持つこのようなすぐれモノのお湯だったのでしょうか。
やませみさん情報では、「近ごろ空洞化による組合員の減少で存続がきびしい状況」とのことですが、たしかに16時台で2人とゲキ空きで、やはり運営がたいへんなのかも・・・。
熱海の共同浴場は一見客にはきびしいという説もありますが、こちらは番台の方も常連さんも親切で、いろいろお話もうかがえて楽しく入れました。
雰囲気もお湯もすばらしい共同浴場なので、ここはおすすめです。(ただし、あくまでも共同浴場なので入浴にあたってはマナー厳守が必要かと。)
2008年4月に再度入湯しましたが、お湯はぬるめで想定外の強カルキ臭があったので早々に退散しました。
あの素晴らしいお湯がカルキ湯と化したことに割り切れないものを感じましたが、この風情ある共同浴場は平成21年(2009年)に廃止され、現在は誓欣院の墓地となっています。
熱海はこのところ復権気味の温泉地ともいわれ、とくに若い客層が増えているといわれます。
その理由としてロケ地としてメディア露出が増えたこと(→関連記事)や外資系施設の増加によるインバウンド客の増加などもあるかと思います。
地魚料理を積極導入するなど、商店街の頑張りもあるかもしれません。
コロナ禍のなか、当面はインバウンド客は望めない反面、東京への好アクセスを見込んで移住やリゾートワークのニーズが増える可能性もあり、熱海の将来性については不透明感が増しています。
華やかな歴史やさまざまな資源をもつ素晴らしい温泉地なので、一部の「勝ち組」だけでなく、街全体が潤うかたちで発展していけるといいですね。
Na・Ca-塩化物温泉 87.5℃、pH=8.0、湧出量不明、成分総計=8.873g/kg
Na^+=2035.0mg/kg、Ca^2+=1057.0、Fe^2+=1.4、Cl^-=4983.0、SO_4^2-=180.7、I^-=5.4、メタけい酸=271.0、メタほう酸=8.3
<H9.1.14分析> (源泉名:熱海19号泉・野村湯)
せっかくなので、誓欣院もご紹介します。
ただし、参拝時の画像をHDD不調でなくしてしまったので、山内の画像はありません。
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
法界山 誓欣院
公式Web
熱海市上宿町6-3
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来


【写真 上(左)】 誓欣院の参道
【下(右)】 誓欣院の御朱印
浄土宗の古刹で「せいごんいん」と読みます。
もとは真言宗の道光寺で、天正十七年(1589年)浄土宗明珠庵と改めました。
承応三年(1654年)、千葉常周の持念仏であった恵心僧都作「阿弥陀如来」を善譽誓欣上人が御本尊としてこの地に遷化されて開山。
のちに開山の徳を慕って浄土宗 法界山 誓欣院と改めました。
万治三年(1660年)の大火で焼失したものの、芝増上寺の聞誉随範上人により寛政九年(1757年)現在の湯前神社東側に再建。
再建された堂宇もふたたび火災をこうむり、廃寺の危機となりましたが安政七年(1778年)芝増上寺の了諦上人により現在地に再興されいまに至ります。
画像をなくしてしまったので山内の紹介は控えますが、公式Webによると、本堂、庫裏ともに初島の松材を使ったもの。
昔から芝増上寺との関係が深く、本堂屋根には「葵の御紋」が使用されているとのことです。
また、インド大菩提会事務総長ジナラタナ師が奉戴して昭和41年当山に伝授された仏舎利が、仏舎利奉安殿に奉安されています。
山内には樹齢推定800年 幹周約4メートルのクロマツ(雄松)の大木があります。
この松の大木に触れ参拝祈願した、子宝に恵まれない人が参拝後に子を授かったと言われたため、「子宝の松」と命名されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
中央に三寶印と南無阿弥陀佛の六字御名号の揮毫と「舎利奉安の寺院」の揮毫。
右に「本尊 阿彌陀如来」の印判。
左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
公式Webには御朱印の案内もあり、授与に積極的なお寺様とみられます。
なお、そばにある温泉寺でも御朱印を授与されています。(→熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印)


【写真 上(左)】 温泉寺の参道
【下(右)】 温泉寺の御朱印
【 BGM 】
今を抱きしめて - YOSHIKI(X JAPAN) NOA(1993年)
熱海温泉には、水口共同浴場、水口第二共同浴場、渚共同浴場、清水町浴場、山田湯、駅前温泉浴場、そして上宿新宿共同浴場など、いくつかの共同浴場がありました。
熱海はもともと内湯が主力の温泉地で、共同浴場など外湯の数は多くありませんでした。
熱海の温泉は高温で塩分を含むものが多く、温泉施設の維持にはコストがかかり、温泉組合員の減少などの問題も顕在化していました。
そんなこともあってか、これらの貴重な共同浴場の多くは近年相次いで休廃業となり、現在外来客が入浴できる施設は数少なくなりました。
熱海の共同浴場はもともと地元住民向けの施設が多く、その入浴難易度はかなり高いものでした。
Web上のレポも多くはないので、順次記録の意味でUPしていきたいと思います。
今回は「上宿(かみしゅく)新宿共同浴場」。
「関東周辺立ち寄り温泉みしゅらん」で特集いただいた記事のリニューアル版です。
※ この施設は平成21年(2009年)に廃止されました。下記は営業時のデータです。
 熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」
熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」住 所 :静岡県熱海市上宿町6-2
電 話 :0557-81-5773
時 間 :14:30~20:20 / 不定休
料 金 :400円
廃止施設ですが、以前の情報や雰囲気を記録するため、極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。
入湯は2005年11月および2008年4月で、主に2005年11月をベースに書いています。


【写真 上(左)】 外観(2005年)
【写真 下(右)】 男湯(2008年)
市内上宿地区にある共同浴場です。
やませみさんから「明治期の大湯の分析にひじょうに近い」という情報をいただき、たまらず突入しました。
場所は市役所の山側、上宿地区。大湯間欠泉から糸川を一本隔てた位置にあります。
市役所となりの中央町公共Pが近いですが混んでいて入れにくく有料なので、スーパー「マックスバリュ」のPにとめて(なにか買い物をすれば2時間まで無料)歩いて行ったほうがいいかも。徒歩4.5分です。


【写真 上(左)】 観音橋
【写真 下(右)】 入口(2008年)


【写真 上(左)】 糸川側から
【写真 下(右)】 糸川への排湯
市役所の前を通り「ニューフジヤホテル」手前(糸川を渡る橋の手前)の路地を山側に入り、温泉寺を左にみてそのすぐ先にある誓欣院参道の観音橋のたもと。
「山田湯」や「渚浴場」にくらべるとぜんぜんわかりやすいです。
朱塗りの橋と共同浴場の白壁、その上に誓欣院の鐘楼と山門が重なり見ごたえがあります。


【写真 上(左)】 内廊下(2005年)
【写真 下(右)】 番台(2008年)
総木造の館内に男女別の浴場。
小さな番台と壁に祀られた神棚、木格子の脱衣棚に年季入った台秤など、共同浴場ならではの風情をただよわせています。
なお、番台は無人のときがあるようなので、小銭で400円用意していったほうがいいかと。


【写真 上(左)】 脱衣所-1(2005年)
【写真 下(右)】 脱衣所-2(2005年)
扉をあけると浴室。
浴室は思いのほか広く、左右の壁面にカラン(計8位)、中央に椅子と桶が山型に積まれています。


【写真 上(左)】 男湯(2005年)
【写真 下(右)】 女湯(2008年)
奥に水色タイル貼3-4人のふたつの浴槽があり、向かって右が熱湯槽、左が適温槽。
ともに石膏の析出と緑青におおわれたカランからゲキ熱の源泉を投入で、よこにうめ水用の水カランもあります。


【写真 上(左)】 男湯適温槽(2008年)
【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2008年)
こういう場合は、外来客は熱湯槽の水カランは使わないのが暗黙のルールで、熱湯槽はゲキ熱でしたが、あとから入ってきた常連さんが水を入れてくれました。
なお、熱湯槽の表示は2005年は「あつい湯」、2008年は「上り湯」で、2008年時点では熱湯槽は上がり湯専用になっていたかもしれません。
共同浴場につきアメニティ類はなし。
常連さんによるとお湯は湯前神社あたりから引いていて、ここにくると70℃くらい、熱交換で冷ましているがそれでも熱いとのこと。
なお、温泉分析書記載の源泉名は「熱海19号泉・野村湯」。
熱海市発行の「熱海温泉誌」(2017年)記載の「昭和11年(1936年)頃の温泉源地一覧」によると、「野村湯」は温泉番号65番、熱海町有、掘削深度49.10m、所在地番は本町447-2となっています。

【写真】 男湯適温槽の湯口(2005年)
熱交換でつくられる真湯のお湯がカランから出るのがありがたいとも・・・。
そういえば(2005年)夏に行った蔵王でも、真湯の浴槽やカランがあるのが宿のウリになるという話をききました。
温泉好きはカランも温泉だと嬉しいものですが、強くて熱いお湯の温泉地では、そんなものなのでしょう。


【写真 上(左)】 男湯適温槽(2005年)
【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2005年)
やや懸濁したお湯は弱い苦味と強いながらもどこかまろみを感じる塩味。
おだやかな磯の香が香り立ち、等張泉らしい適度な重みに明瞭なとろみと土類系の肌に食い込んでくるような力強さが加わるすばらしいもの。
このとろみは、たぶんメタけい酸=271.0mg/kgによるものと思います。
熱海がお湯のよさで語られることは意外と少ないですが、熱海本来のお湯は、力感と深みをあわせ持つこのようなすぐれモノのお湯だったのでしょうか。
やませみさん情報では、「近ごろ空洞化による組合員の減少で存続がきびしい状況」とのことですが、たしかに16時台で2人とゲキ空きで、やはり運営がたいへんなのかも・・・。
熱海の共同浴場は一見客にはきびしいという説もありますが、こちらは番台の方も常連さんも親切で、いろいろお話もうかがえて楽しく入れました。
雰囲気もお湯もすばらしい共同浴場なので、ここはおすすめです。(ただし、あくまでも共同浴場なので入浴にあたってはマナー厳守が必要かと。)
2008年4月に再度入湯しましたが、お湯はぬるめで想定外の強カルキ臭があったので早々に退散しました。
あの素晴らしいお湯がカルキ湯と化したことに割り切れないものを感じましたが、この風情ある共同浴場は平成21年(2009年)に廃止され、現在は誓欣院の墓地となっています。
熱海はこのところ復権気味の温泉地ともいわれ、とくに若い客層が増えているといわれます。
その理由としてロケ地としてメディア露出が増えたこと(→関連記事)や外資系施設の増加によるインバウンド客の増加などもあるかと思います。
地魚料理を積極導入するなど、商店街の頑張りもあるかもしれません。
コロナ禍のなか、当面はインバウンド客は望めない反面、東京への好アクセスを見込んで移住やリゾートワークのニーズが増える可能性もあり、熱海の将来性については不透明感が増しています。
華やかな歴史やさまざまな資源をもつ素晴らしい温泉地なので、一部の「勝ち組」だけでなく、街全体が潤うかたちで発展していけるといいですね。
Na・Ca-塩化物温泉 87.5℃、pH=8.0、湧出量不明、成分総計=8.873g/kg
Na^+=2035.0mg/kg、Ca^2+=1057.0、Fe^2+=1.4、Cl^-=4983.0、SO_4^2-=180.7、I^-=5.4、メタけい酸=271.0、メタほう酸=8.3
<H9.1.14分析> (源泉名:熱海19号泉・野村湯)
せっかくなので、誓欣院もご紹介します。
ただし、参拝時の画像をHDD不調でなくしてしまったので、山内の画像はありません。
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
法界山 誓欣院
公式Web
熱海市上宿町6-3
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来


【写真 上(左)】 誓欣院の参道
【下(右)】 誓欣院の御朱印
浄土宗の古刹で「せいごんいん」と読みます。
もとは真言宗の道光寺で、天正十七年(1589年)浄土宗明珠庵と改めました。
承応三年(1654年)、千葉常周の持念仏であった恵心僧都作「阿弥陀如来」を善譽誓欣上人が御本尊としてこの地に遷化されて開山。
のちに開山の徳を慕って浄土宗 法界山 誓欣院と改めました。
万治三年(1660年)の大火で焼失したものの、芝増上寺の聞誉随範上人により寛政九年(1757年)現在の湯前神社東側に再建。
再建された堂宇もふたたび火災をこうむり、廃寺の危機となりましたが安政七年(1778年)芝増上寺の了諦上人により現在地に再興されいまに至ります。
画像をなくしてしまったので山内の紹介は控えますが、公式Webによると、本堂、庫裏ともに初島の松材を使ったもの。
昔から芝増上寺との関係が深く、本堂屋根には「葵の御紋」が使用されているとのことです。
また、インド大菩提会事務総長ジナラタナ師が奉戴して昭和41年当山に伝授された仏舎利が、仏舎利奉安殿に奉安されています。
山内には樹齢推定800年 幹周約4メートルのクロマツ(雄松)の大木があります。
この松の大木に触れ参拝祈願した、子宝に恵まれない人が参拝後に子を授かったと言われたため、「子宝の松」と命名されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
中央に三寶印と南無阿弥陀佛の六字御名号の揮毫と「舎利奉安の寺院」の揮毫。
右に「本尊 阿彌陀如来」の印判。
左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
公式Webには御朱印の案内もあり、授与に積極的なお寺様とみられます。
なお、そばにある温泉寺でも御朱印を授与されています。(→熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印)


【写真 上(左)】 温泉寺の参道
【下(右)】 温泉寺の御朱印
【 BGM 】
今を抱きしめて - YOSHIKI(X JAPAN) NOA(1993年)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 大雪
2021/01/09 UP
日本海側で大雪が続いています。
不思議なのは、昨日今日と関東での北風の吹き出しはさほど強くないのに、一部で記録的な降雪を記録していることです。
現在の積雪量は→ こちら
24時間降雪量は→ こちら
24時間降雪量で、過去最高、または1月としての過去最高を記録した地点は下記のとおりです。(本州のみ)
秋田、酒田、高田(上越市)、魚津、富山、福井、(越前)大野、下関
ほとんどが日本海側の平野部です。
新潟県の積雪量は、高田198cm、小出192cmと、いずれも山沿いの湯沢191cmよりも多くなっています。
これは、12月中旬の魚沼・奥利根を中心とした豪雪(山雪型)とは様相が異なり、むしろ平成30年の福井豪雪に近い降り方(里雪型)だと思います。
この豪雪は、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ/以前の北陸不連続線)によるものとされ、日本海側の平野部に大きな被害をもたらした「サンパチ豪雪」(昭和38年1月の記録的豪雪)もこの形だったとされています。
実際、雲画像(現況・予想)をみると、北陸沿岸でいくつかの雲の渦がみられます。
里雪型は人口密度の高い平野部で降るため、被害が大きくなりがちです。
コロナ禍のなか、少しでも被害がすくなく収まることを祈ります。
「暖国の雪一尺以下ならば山川村里立所に銀世界をなし、雪の飄々翩々たるを観て花に論へ玉に比べ、勝望美景を愛し、酒食音律の楽を添へ、画に写し詞をつらねて賞翫するは和漢古今の通例なれども、是雪の浅き国の楽みなり。我越後のごとく年毎に幾丈の雪を視ば何の楽き事あらん。雪の為に力を費し千辛万苦する事、下に説く所を視ておもひはかるべし。」
『北越雪譜』 鈴木牧之著
--------------------
2020/12/30 UP
国土交通省から「大雪に対する緊急発表」が発表されています。
「30日から1月1日頃にかけて強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪や大荒れとなるおそれがあり、平地でも大雪となるおそれがあります。
東日本と西日本の太平洋側の平地でも積雪となるところがある見込みです。その後も日本海側を中心にさらに降雪量が増えるおそれがあります。
大雪による立ち往生等に警戒が必要です。不要不急の外出は控えて下さい。」
とのことです。
これ(高層気温解析図)をみると、
昨日12/29の21時時点の上空約5500m(500hPa天気図)の気温は、樺太付近で-46℃以下となっています。
通常、雪となる目安は-30℃、大雪の目安は-36℃といわれますから、今回の寒気はだだものでないことがわかります。(→大雪の目安)
関連ニュースをみると、新潟県の24時間予想降雪量は、
30日の夕方から31日夕方にかけて、70センチから100センチ
31日の夕方から年明け1月1日の夕方にかけて、80センチから120センチ
山沿いの雪の多いところでは、本日30日の夕方からの48時間でじつに220センチのとてつもない大雪が予想されています。
これまでの記録は24時間で100~150センチ程度のところが多いので、記録的な豪雪になる可能性があります。
交通機関の混乱はもちろん、これだけ降ると新雪なだれも心配です。
また、これだけ強い寒気だと夏場のゲリラ豪雨と同じで、どこで局地的な降雪があってもおかしくなく、太平洋側でも油断できないと思います。
コロナ感染も歯止めがきかなくなっているし、年末年始は「お家でゆったり」が正解なのかもしれません。
--------------------
2020/12/17 UP
日本海の海水温と上空寒気の差が50℃以上って、相当ヤバそうだと思ったけどまさかここまで降るとは・・・。→気象庁データ
これ(新潟県雪情報)みると、典型的な山雪型であることがわかるが、それにしても群馬・奥利根地域の降り方は異常。
津南171cm、湯沢182cmに対して、藤原202cmって、こんなデータ見たことがない。
奥利根の冬はスキーや温泉でさんざん行っているので、このエリアの雪の降り方はわかっているけど、ふつうは藤原よりも湯桧曽・土合方面の方が雪が深く、津南や湯沢はこれよりもさらに深い。
でも、今回は様相が違う。
群馬県の雪情報
ニュースのなかで、「発達した雪雲の高さがあまりに高かったため、(三国)山脈を越えた群馬の藤原や水上でも大雪となった。」と解説していたけど、なるほどそうなのかもしれないし、地形的な要因もあると思う。
実際、さきほど自宅から見た上越国境方面、山々がほとんど雪雲に覆われていて雪雲が太平洋側まで出張ってきているのがわかる。
(本日テレワーク中)

これ(新潟県雪情報)みると、信濃川沿いの津南、松之山よりも魚野川沿いの湯沢の方が50cmほど多い。(ふつうは逆)
魚野川沿いに雪雲が押し込み、谷川岳で一気に吹き上がってそれが風下の藤原・水上に流れ込んだのではないか。
立ち往生がつづく関越自動車道もやっぱり魚野川沿い。
こういう異常降雨・異常降雪はしばらくクセになるといわれるので、このエリアはとくに当面要注意では?
12月の雪は日照時間が少ないのでなかなか溶けない。
積雪が多ければ換気はしにくくなるし、本当に試練の冬がやってきているのだと思う。
GoTo騒動があって、年末年始の客足は読めないし、それに加えてこの豪雪。
水上、谷川、湯桧曽、宝川、湯ノ小屋、鎌田、片品、戸倉・・・。
何回となく通った温泉たち。なんとか持ちこたえてほしいと思います。
群馬-3 (北毛・新治) 温泉リスト
群馬-4.1 (尾瀬・赤城/片品村の温泉) リスト
※ いろいろな意見が出てますが、正直なところ、推進策がいいのか否かよくわかりません。
立場によって人それぞれ状況が違うから・・・。
でも、推進策をとれば当然リスクは高まるし、クラスターでも発生したらその施設の致命傷になるかもしれない。
いちばん効きそうなのは、期間を絞った休業要請+粗利補償(対昨年)のような気もするけど、予算とのからみあり・・・?。
対策費予算70兆円も真水じゃないといわれてるし、ほんとうによくわかりません。
日本海側で大雪が続いています。
不思議なのは、昨日今日と関東での北風の吹き出しはさほど強くないのに、一部で記録的な降雪を記録していることです。
現在の積雪量は→ こちら
24時間降雪量は→ こちら
24時間降雪量で、過去最高、または1月としての過去最高を記録した地点は下記のとおりです。(本州のみ)
秋田、酒田、高田(上越市)、魚津、富山、福井、(越前)大野、下関
ほとんどが日本海側の平野部です。
新潟県の積雪量は、高田198cm、小出192cmと、いずれも山沿いの湯沢191cmよりも多くなっています。
これは、12月中旬の魚沼・奥利根を中心とした豪雪(山雪型)とは様相が異なり、むしろ平成30年の福井豪雪に近い降り方(里雪型)だと思います。
この豪雪は、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ/以前の北陸不連続線)によるものとされ、日本海側の平野部に大きな被害をもたらした「サンパチ豪雪」(昭和38年1月の記録的豪雪)もこの形だったとされています。
実際、雲画像(現況・予想)をみると、北陸沿岸でいくつかの雲の渦がみられます。
里雪型は人口密度の高い平野部で降るため、被害が大きくなりがちです。
コロナ禍のなか、少しでも被害がすくなく収まることを祈ります。
「暖国の雪一尺以下ならば山川村里立所に銀世界をなし、雪の飄々翩々たるを観て花に論へ玉に比べ、勝望美景を愛し、酒食音律の楽を添へ、画に写し詞をつらねて賞翫するは和漢古今の通例なれども、是雪の浅き国の楽みなり。我越後のごとく年毎に幾丈の雪を視ば何の楽き事あらん。雪の為に力を費し千辛万苦する事、下に説く所を視ておもひはかるべし。」
『北越雪譜』 鈴木牧之著
--------------------
2020/12/30 UP
国土交通省から「大雪に対する緊急発表」が発表されています。
「30日から1月1日頃にかけて強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪や大荒れとなるおそれがあり、平地でも大雪となるおそれがあります。
東日本と西日本の太平洋側の平地でも積雪となるところがある見込みです。その後も日本海側を中心にさらに降雪量が増えるおそれがあります。
大雪による立ち往生等に警戒が必要です。不要不急の外出は控えて下さい。」
とのことです。
これ(高層気温解析図)をみると、
昨日12/29の21時時点の上空約5500m(500hPa天気図)の気温は、樺太付近で-46℃以下となっています。
通常、雪となる目安は-30℃、大雪の目安は-36℃といわれますから、今回の寒気はだだものでないことがわかります。(→大雪の目安)
関連ニュースをみると、新潟県の24時間予想降雪量は、
30日の夕方から31日夕方にかけて、70センチから100センチ
31日の夕方から年明け1月1日の夕方にかけて、80センチから120センチ
山沿いの雪の多いところでは、本日30日の夕方からの48時間でじつに220センチのとてつもない大雪が予想されています。
これまでの記録は24時間で100~150センチ程度のところが多いので、記録的な豪雪になる可能性があります。
交通機関の混乱はもちろん、これだけ降ると新雪なだれも心配です。
また、これだけ強い寒気だと夏場のゲリラ豪雨と同じで、どこで局地的な降雪があってもおかしくなく、太平洋側でも油断できないと思います。
コロナ感染も歯止めがきかなくなっているし、年末年始は「お家でゆったり」が正解なのかもしれません。
--------------------
2020/12/17 UP
日本海の海水温と上空寒気の差が50℃以上って、相当ヤバそうだと思ったけどまさかここまで降るとは・・・。→気象庁データ
これ(新潟県雪情報)みると、典型的な山雪型であることがわかるが、それにしても群馬・奥利根地域の降り方は異常。
津南171cm、湯沢182cmに対して、藤原202cmって、こんなデータ見たことがない。
奥利根の冬はスキーや温泉でさんざん行っているので、このエリアの雪の降り方はわかっているけど、ふつうは藤原よりも湯桧曽・土合方面の方が雪が深く、津南や湯沢はこれよりもさらに深い。
でも、今回は様相が違う。
群馬県の雪情報
ニュースのなかで、「発達した雪雲の高さがあまりに高かったため、(三国)山脈を越えた群馬の藤原や水上でも大雪となった。」と解説していたけど、なるほどそうなのかもしれないし、地形的な要因もあると思う。
実際、さきほど自宅から見た上越国境方面、山々がほとんど雪雲に覆われていて雪雲が太平洋側まで出張ってきているのがわかる。
(本日テレワーク中)

これ(新潟県雪情報)みると、信濃川沿いの津南、松之山よりも魚野川沿いの湯沢の方が50cmほど多い。(ふつうは逆)
魚野川沿いに雪雲が押し込み、谷川岳で一気に吹き上がってそれが風下の藤原・水上に流れ込んだのではないか。
立ち往生がつづく関越自動車道もやっぱり魚野川沿い。
こういう異常降雨・異常降雪はしばらくクセになるといわれるので、このエリアはとくに当面要注意では?
12月の雪は日照時間が少ないのでなかなか溶けない。
積雪が多ければ換気はしにくくなるし、本当に試練の冬がやってきているのだと思う。
GoTo騒動があって、年末年始の客足は読めないし、それに加えてこの豪雪。
水上、谷川、湯桧曽、宝川、湯ノ小屋、鎌田、片品、戸倉・・・。
何回となく通った温泉たち。なんとか持ちこたえてほしいと思います。
群馬-3 (北毛・新治) 温泉リスト
群馬-4.1 (尾瀬・赤城/片品村の温泉) リスト
※ いろいろな意見が出てますが、正直なところ、推進策がいいのか否かよくわかりません。
立場によって人それぞれ状況が違うから・・・。
でも、推進策をとれば当然リスクは高まるし、クラスターでも発生したらその施設の致命傷になるかもしれない。
いちばん効きそうなのは、期間を絞った休業要請+粗利補償(対昨年)のような気もするけど、予算とのからみあり・・・?。
対策費予算70兆円も真水じゃないといわれてるし、ほんとうによくわかりません。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第12番
現徳山 妙見寺
公式Web
北区西ヶ原2-9-5
日蓮宗
御首題
第12番は、日蓮宗の妙見寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、つぎの記載があります。
・ 正中山法華経寺大荒行堂の大験者、慈徳院日陽上人が昭和9年(1934年)荒川区尾久に草創された妙見堂教会が昭和19年(1944年)当地に疎開移転して開山。
・第2世として法燈を承継された慈正院日慶上人が昭和22年(1946年)、日蓮宗門より現徳山妙見寺の寺号公称を認可される。
・昭和57年(1982年)、老朽化した本堂と書院を再建落慶。
・第2世日慶上人は正中山大荒行堂加行700日、第3世の慈昌院日観上人も正中山第四行の修法師で檀信徒の方々から信仰を集めている。
山門には「日蓮宗祈祷所」が立額され、公式Webにも「日蓮宗祈祷所『妙見寺』は日蓮宗伝統の祈祷を受け継ぎ、全国の方々の幸福に寄与します。」と掲載されています。


【写真 上(左)】 飛鳥山公園の紅葉
【写真 下(右)】 山門
本郷通りから北に少し入ったところ、飛鳥山公園に面した緑濃い立地です。
山門はおそらく薬医門ないし高麗門で、小ぶりながら存在感があります。


【写真 上(左)】 斜めから山門
【写真 下(右)】 山門主門まわり
降り棟の外側が本瓦葺、内側が桟瓦葺、掛瓦も太くてどっしりとした質感。
右の柱に「日蓮宗祈祷所」、左の柱には寺号の板標が掲げられ、正面には「現徳山」の山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
境内には八大竜王碑、浄行菩薩、不動明王、稲荷社などが鎮座し、パワスポ的な雰囲気を感じます。
稲荷社奥の2階の入母屋造妻入りの建物が本堂のように見えますが、定かではありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の棟飾り


【写真 上(左)】 浄行菩薩
【写真 下(右)】 庫裡
御首題は山門くぐって左の階段をのぼった庫裡にて拝受しました。
滝野川寺院めぐりの御朱印も御首題で授与されます。
ご不在の場合もあるので、事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第12番の御朱印(御首題)
【下(右)】 通常の御首題
滝野川寺院めぐりの御朱印は御首題で、「滝野川寺院めぐり第十二番寺」の札所印が捺されています。
通常の御首題にこの札番はなく、構成も若干異なります。
第13番
北龍山 法音寺
北区栄町14-9
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
第13番は、真宗大谷派の法音寺です。
第13番で一旦京浜東北線の東側に出ます。
田端駅から上中里駅にかけてのJR京浜東北線北側にはJR尾久車両センター(尾久客車操車場)があって、都内有数の交通分断エリアとなっています。
第12番妙見寺からだと上中里駅東側の跨線橋を渡り、さらに梶原踏切か上中里さわやか橋経由のルートが順当かと思います。


【写真 上(左)】 上中里さわやか橋からのJR尾久車両センター
【写真 下(右)】 山門からの山内
西ヶ原から京浜東北線の線路を渡って栄町に入ると、路地が入り組む下町的な町並みとなり、法音寺も路地の一角にあります。
妙見寺からの距離はさほどではありませんが、跨線橋を渡ったり、街の雰囲気が変わったりで、けっこう遠く感じました。
なお、法音寺の最寄り駅は都電荒川線の「梶原」駅となります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 掲示版
『滝野川寺院めぐり案内』によると、当寺はもと富山県下新川郡新屋にあり、上京された釈法忍師は明治40年(1907年)、滝野川に居住されて布教活動に着手。
大正13年(1924年)、この地に本堂を建立され法音寺説教所を開設。
東京大空襲で本堂を焼失しましたが、昭和24年(1949年)には正式に寺号を取得、昭和30年(1955年)には本堂を再建し、現在に至ります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂見上げ
こぢんまりとした境内正面に立派な本堂。
入母屋造銅板葺流れ向拝。水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配しています。
参拝時、ご住職はご不在で大黒さんの対応をいただきました。
「真宗なので御朱印は出されていない。」とのことでしたが、納経帳をお見せし、滝野川寺院めぐりを巡拝中との主旨をお話しすると、「それであれば」とお受けいただき、御朱印(というか参拝記念)に準ずるものを納経帳にいただけました。
ご親切な対応をいただき、ありがとうごさいました。
ただし、今回だけの特例対応であったかもしれず、拝受した「おしるし」は掲載を控えます。
第14番
思惟山 浄業三昧寺 正受院
北区滝野川2-49-5
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番、北豊島三十三観音霊場第23番
第14番は、浄土宗の正受院です。
法音寺から赤羽駅のガードをくぐり、王子神社下の緑ゆたかな音無親水公園を抜けてのアプローチとなります。
下町の住宅街から一転、渓谷を抜けて台地に登るこのコースは変化に富み、この巡拝のハイライトともいえる道のり。
正受院は滝野川に面していますが北側滝野川岸からの参道はないので、一旦滝野川をはなれ、南側の住宅地から回り込むかたちとなります。


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 不動尊への道標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、室町時代末、弘治年間(1555-1558年)に大和國宇多郡滝門の奥の功曽久という所から夢告に従って来られた学仙坊法印が、王子七滝のひとつ「不動の滝」で修行され、滝野川から1体の不動尊像をすくい上げました。
法印は不動堂を建立され、のちに弘法大師の御作といわれ信仰を集めるこの不動尊像を安置されたのが当寺の開創とされます。
慶長年間(1596-1615年)に円誉上人が入寺されて浄土宗となりました。
浄土宗のお寺様ながら、人々のこのお不動様に対する信仰は篤く、「瀧不動尊」とも呼ばれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号18/114)に以下の記述があります。
「「浄土宗芝増上寺末 思惟山三昧寺ト号ス 弘治年中大和國宇多郡龍門ノ奥功曾久ト云所ニ學仙坊と云僧住し 不動即我ノ密法ヲ修スル事年アリ 靈夢ヲ得テ當國ニ来リテ當寺ヲ草創セリ 其年タマタマ洪水アリテ砌ノ川中ヨリ弘法大師作ノ不動ヲ得タリ 其後又旅僧来テ一軀ノ不動ヲ授クシモノ今堂中ニ安置スル處ナリ 學仙坊は弘治三年三月四日寂ス 其墳墓庭ノ小山ノ上ニアリテ五輪塔ナリ 其後寂阿了山ト云僧堂舎ヲ再建ス 文禄三年九月三日圓譽光道本堂再建ノ棟札アリ 本尊阿彌陀ハ行基ノ作ニテ坐身長二尺五分此餘惠心作ノ彌陀像一軀を置 撞鐘 古鐘ナリシカ文政三年改鑄スト云 不動堂 弘法大師作ノ立像ヲ置 観音堂 西國札所第四番観音の寫と云 瀧 本堂の脇峽下ニアリ病者ツトイ来テ浴セリ」
慈眼堂(赤ちゃんの納骨堂)があり、「赤ちゃん寺」として知られています。


【写真 上(左)】 鐘楼門
【写真 下(右)】 参道
狭い路地から意外に長い参道がつづきます。
しばらく行くと鐘楼門。下を石積みのアーチにし、上に木造建築を構えるいわゆる「竜宮門」で、おそらく入母屋屋根桟瓦葺で水引虹梁を置いています。
軒裏の垂木はめずらしい扇垂木だと思います。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
正面が本堂。入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝の均整がとれた仏堂。
水引虹梁両端に獅子と貘の彫刻木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
正面桟唐戸の上に「思惟山」の扁額。
本堂前には江戸時代の探検家近藤重蔵(守重)の甲冑姿の石像が鎮座します。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂上部
本堂向かって左の渓谷寄りには不動堂。
入母屋造桟瓦葺唐破風向拝で、水引虹梁両端に獅子彫刻の木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
唐破風の鬼板や兎毛通の仕上げも精緻で見応えがあります。
本堂右手の客殿や庫裡もしっとりと風情ある構えを見せています。
境内には不動尊の露仏が数座御座し、やはりお不動様とのゆかりがふかいお寺だと思います。
なお、「不動の滝」(泉流の滝)は現存していません。
『江戸名所図会』
「正受院の本堂の後、坂路を廻り下る事、数十歩にして飛泉あり、滔々として硝壁に趨る、此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をさゝえ、青苔露なめらかにして人跡稀なり」
境内はしっとりと落ち着いた雰囲気があり、↑で描写された面影をいまも遺しています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。書置はなく、ご住職ご不在の場合もあるので事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 御本尊の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」の揮毫と三寶印とその左横に「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印。左上に印判(不明)。
左上には「瀧不動」の揮毫、左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印がなく、上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番(「西國四番寫」の札所印)の札所印が捺されていました。
第15番
瀧河山 松橋院 金剛寺
北区滝野川3-88-17
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第43番、荒川辺八十八ヶ所霊場第16番、北豊島三十三観音霊場第31番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第28番、弁財天百社参り第52番、豊島六地蔵霊場第4番
第15番は、真言宗豊山派の金剛寺です。
第14番正受院から第16番結願の寿徳寺までは滝野川に沿うかたちで立地し、ひときわ風情のあるところです。
このあたりは江戸時代から紅葉の名所で、とくに金剛寺は「もみじ寺」の別称があります。


【写真 上(左)】 滝野川の紅葉-1
【写真 下(右)】 滝野川の紅葉-2
滝野川沿いの遊歩道脇には、音無さくら緑地、音無もみじ緑地があり、音無さくら緑地では旧石神井川の流路跡、音無もみじ緑地ではかつての江戸の名所であった松橋辨財天周辺の様子をしのぶことができます。

【写真 下(右)】 音無もみじ緑地
『滝野川寺院めぐり案内』によると、金剛寺は弘法大師が東国巡錫の折、石神井川(滝野川)にさしかかり、対岸へ渡る橋がなかったため川岸の松を切り倒して一本橋(松橋)を渡され、その際にその松の木で不動明王の尊像一躯を彫られて石上に安置されたのが草創とされています。
治承四年(1180年)10月、伊豆国で挙兵し、石橋山での敗戦ののち安房に逃れて再挙を図られた源頼朝公は、府中の六所明神(大國魂神社)へ向かう途中、滝野川松橋に布陣し、東方千住方面からの敵をここで迎え撃ち大勝利を収めたとされます。
その折、頼朝公は金剛寺に戦勝祈願したことから寄進など寺の興隆に尽くしたとされます。
一時荒廃したものの、天文年間(1532-1555年)に阿闍梨宥印が北条氏康の賛意を得て再興。
江戸時代には、八代将軍吉宗公が滝野川流域に紅葉の植林を奨励したこともあって、江戸近郊を代表する紅葉の名所となり、金剛寺は「もみじ寺」と呼ばれて秋の庶民の参詣・行楽の場として広く親しまれました。
その様子は広重の『名所江戸百景』や『東都名所』など多くの錦絵に描かれています。
また、金剛寺一帯は、豊島氏支族滝野川氏の居館滝野川城跡ともいわれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗田端村與楽寺門徒 瀧河山松橋院ト号ス 本尊不動ハ坐像ニテ長一尺餘弘法大師ノ作ト云 縁起の●ニ當所ハ弘法大師達遊歴ノ古蹟ニシテ 其頃手ツカラ此像ヲ彫刻アリテ假ニ石上ニ安ス 今其石ヲ不動影向石ト称シテ境内ニ現存シ 疾病ノモノ此石ニ水ヲソソキテ其水を服スレハ立所ニ平癒スト云 又治承年中右大将頼朝境内辨財天信仰ノ餘リ堂舎建立 及ヒ田園ヲモ寄附アリシニ 其後兵火ニ焼レ強盗ニ田園を掠メ奪ハレ 宗門タニ定カナリシヲ、天文ノ頃阿闍梨宥印ト云僧是ヲ歎キ 北條氏康ヘ訴ヘ永ク眞言ノ道場ニ復スト云 影向石 三箇ノ石ヲ重置 是縁起ニ云ヘル不動ノ像ヲ安置セル處ナリ 辨財天社 弘法大師作坐身長七寸ノ像ヲ安シ 別ニ護摩ノ灰ニテ作レル像ヲモ置リ 地蔵堂 大黒天 本堂ノ後ノ方岩窟ノ中ニ安置ス」
「辨財天 峽下ノ洞中ニ安ス長一尺ノ石像ニテ松橋辨天ト号ス 弘法大師ノ作 當時此地ニ松橋ト云橋アリシ故地名ヲオハセテ唱トイヘリ 松橋ノ名ハ前ニ云ル如ク源平盛衰記ニ見エテ舊キ地名ナリ 治承ノ頃頼朝此辨天ヲ帰依ノ餘リ太刀ヲ寄附アリシ由縁起ニ載タレト今是ヲ失ナヘリ 洞中ニ文保三年三月ト彫タル古碑一基アリ 恵比須毘沙門石像紫の楓 紅葉ノ秋紫色ヲ帶ル故此名アリ」


【写真 上(左)】 旧松橋辨財天周辺
【写真 下(右)】 江戸名所図絵(松橋辨財天窟)
〔松橋辨財天〕
金剛寺は辨天様ともゆかりのふかいお寺です。
かつての滝野川は金剛寺付近で蛇行しており、その崖には辨天の滝がかかり、崖下にあった洞窟には辨財天が祀られていました。
この辨天様は弘法大師の御作ともいわれ、松橋辨天または岩屋辨天と呼ばれて信仰を集めました。
この辨天様は、源頼朝公が戦勝を祈願し太刀一振を奉納し、戦勝ののちに辨財天の堂舎を建立、田園の寄進をしたとも伝えられています。
滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』で犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がこの松橋辨天とされています。
辨天の滝は昭和初期に枯れ、昭和33年(1958年)の狩野川台風で辨天様の洞窟は崩壊し、一部は昭和50年(1975年)前後まで残っていたようですが、その後の護岸工事や流路改修の際に取り壊され、現在は音無もみじ緑地となっています。
現地の案内版より引用抜粋してみます。
「『江戸名所図絵』には『この地は石神井河の流れに臨み、自然の山水あり。両岸高く桜楓の二樹枝を交へ、春秋ともにながめあるの一勝地なり。』」「崖下の岩屋の中には弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。また、現在都営住宅が建っている付近の崖に瀧があり、弁天の滝と呼ばれていました。」
『新編武蔵風土記稿』によると、崖下洞窟内の「松橋辨財天(岩屋辨財天)」/弘法大師作長一尺ノ石像とは別に、金剛寺境内(崖上)にも「弘法大師作坐身長七寸ノ辨天像」が安置されていた様ですが、詳細はよくわかりません。
ただし、松橋辨天の崖下洞窟も金剛寺の領地内であったようなので、金剛寺=松橋辨天と捉えられていたのでは。
松橋辨天は江戸市内でもよく知られており、江戸三十三ヶ所弁財天霊場、弁財天百社参りの札所となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 紅葉寺の寺号標


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 西國霊場札所標
江戸時代からの行楽地とあって、金剛寺周辺はいまでも華やいだ雰囲気が感じられます。
入母屋造桟瓦葺の薬医門。扁額は「瀧河山」。頭貫部梁先の雲形木鼻がダイナミック。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
参道正面、階段の上に本堂向拝。
入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝。向かって左手手前に修行大師が御座します。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に本蟇股を配しています。
正面桟唐戸の上に「金剛寺」の扁額。
虹梁に金色の彫刻を置いた、名刹らしい堂々たる向拝です。


【写真 上(左)】 辨天堂
【写真 下(右)】 辨天堂扁額
本堂向かって右手に宝形造銅板葺の辨天堂と坐像の地蔵尊が御座します。
弁天堂の御本尊は松橋辨天の系譜を引かれるお像でしょうか。
手入れの行き届いた境内で、落ち着いて参拝ができます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 滝野川七福神
御朱印は本堂向かって左手の庫裡(客殿?)にて、ご丁寧なご対応をいただき拝受しました。

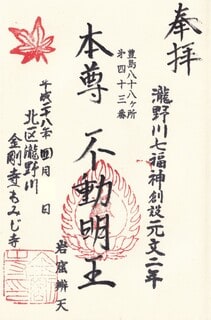
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第15番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第43番の御朱印
中央に「本尊 不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「滝野川寺院めぐり第十五番寺」と「滝野川七福神創設元文二年」の印判。左上に「豊島八十八ヶ所第四十三番」と「もみじ」の印判。左下に「岩窟辨天」の印判。
左下に寺号の印判と寺院印が捺されています。
豊島霊場の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十五番寺」の印判がなく、印判の位置も若干異なります。
「松橋辨天」の御朱印については伺っていませんが、Web上で見当たらないこと、既存の御朱印に「岩窟辨天」の印判があることから、おそらくは授与されていないと思います。
なお、「滝野川七福神」は、金剛寺境内に祀られている七福神をさすようです。
第16番
南照山 観音院 寿徳寺
北区滝野川4-22-1
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第17番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第12番、大東京百観音霊場第80番、北豊島三十三観音霊場第32番
ついに結願の16番。真言宗豊山派の寿徳寺です。
金剛寺とは反対側の滝野川の左岸にあります。


【写真 上(左)】 川沿いの遊歩道
【写真 下(右)】 滝野川橋
金剛寺から寿徳寺への順路には音無もみじ緑地があり、滝野川沿いの遊歩道の紅葉も綺麗で、歩いていて楽しいところです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、寿徳寺は寿永年間(1182-1185年)、梶原氏の家臣であった早船・小宮の両氏が梶原氏と不和になり落ち延びる途中で、海中から拾いあげた観世音菩薩を滝野川の北岸沿いの堂山の地に小堂を設け安置したのが創建と伝わります。
本尊は谷津子育観音と親しまれ、新撰組の近藤勇、および隊士の菩提寺としても知られています。
境外地には谷津大観音、近藤勇の墓所(JR埼京線「板橋」駅前)があります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
なお、『新編武蔵風土記稿』の「寿福寺」は誤植です。
「新義真言宗田端村東覺寺門徒、南照山観音院ト号ス 本尊子安観音」


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 近藤勇の碑


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 西國霊場札所碑
住宅地のなか、ぽっかりと開けた一角に立地し、境内も広々としています。
門外左手に不動堂。境内左手に修行大師像が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め右からの本堂
正面に昭和41年(1966年)落慶の本堂。
両脇に仁王尊像を置いた石段の上に、アーチ形の屋根をもつ独特なつくりの朱色の建物。
正面向拝部に「南照山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
寺伝によると、秘仏の御本尊、谷津観音は蓮華座に坐り、両手で乳児を膝の上に抱えている姿で、指を阿弥陀如来と同じ弥陀の定印に結んでおられるそうです。
本堂の向かって右にある護摩堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁と向拝柱を備え、これは以前の本堂とのこと。


【写真 上(左)】 旧本堂(護摩堂)
【写真 下(右)】 乳が垂れている銀杏
境内に切株から芽吹いている銀杏は、かつては巨木で、この樹の皮をはいで本尊に供え、祈願した後に煎じて飲むと母乳が良く出るようになるという信仰がありました。
正岡子規の高弟として知られる俳人、河東 碧梧桐の句
- 秋立つや子安詣での花の束 -
が残されており、明治に入っても谷津観音への子安詣では盛んであったことがうかがわれます。
山内には、独特の雰囲気を放つインド仏も露座しています。


【写真 上(左)】 インド仏
【写真 下(右)】 滝野川と谷津大観音
谷津大観音は山内から少しくはなれた滝野川の河岸、観音橋のたもとに御座しています。
右手与願印、左手に蓮華をもたれるおだやかな表情の銅製の坐像です。
観音橋から寿徳寺に向かい登っていく坂を「観音の坂」といいます。
現地案内標には「観音橋の北から寿徳寺へ登る坂です。坂名は、坂上にある寿徳寺に谷津観音の名で知られる観音様がまつられているからです。江戸時代には大門通とも呼ばれていました。」とあります。(北区教育委員会)


【写真 上(左)】 観音橋と谷津大観音
【写真 下(右)】 谷津大観音
御朱印は本堂向かって右手奥の庫裡にて拝受しました。
ご丁寧なご対応をいただき、「滝野川十六番満願」の揮毫もいただきました。
やはり「滝野川寺院めぐり」の巡拝者は少ないとのことでした。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第16番(満願)の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第12番の御朱印
中央に御本尊聖観世音菩薩の種子「サ」・「子育 谷津観音」の揮毫と「谷津子育観音」の印判。右上に聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。左下に寺号の揮毫と寺院印。右に「滝野川十六番満願」の揮毫をいただきました。
豊島霊場の御朱印とは、札番の揮毫が異なります。
これで滝野川寺院めぐりは結願です。
北区の落ち着いた街区を巡るこの巡拝コース、札所構成も変化に富んでいて、知名度は低いですがおすすめだと思います。
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 孤独な生きもの - KOKIA
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第12番
現徳山 妙見寺
公式Web
北区西ヶ原2-9-5
日蓮宗
御首題
第12番は、日蓮宗の妙見寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、つぎの記載があります。
・ 正中山法華経寺大荒行堂の大験者、慈徳院日陽上人が昭和9年(1934年)荒川区尾久に草創された妙見堂教会が昭和19年(1944年)当地に疎開移転して開山。
・第2世として法燈を承継された慈正院日慶上人が昭和22年(1946年)、日蓮宗門より現徳山妙見寺の寺号公称を認可される。
・昭和57年(1982年)、老朽化した本堂と書院を再建落慶。
・第2世日慶上人は正中山大荒行堂加行700日、第3世の慈昌院日観上人も正中山第四行の修法師で檀信徒の方々から信仰を集めている。
山門には「日蓮宗祈祷所」が立額され、公式Webにも「日蓮宗祈祷所『妙見寺』は日蓮宗伝統の祈祷を受け継ぎ、全国の方々の幸福に寄与します。」と掲載されています。


【写真 上(左)】 飛鳥山公園の紅葉
【写真 下(右)】 山門
本郷通りから北に少し入ったところ、飛鳥山公園に面した緑濃い立地です。
山門はおそらく薬医門ないし高麗門で、小ぶりながら存在感があります。


【写真 上(左)】 斜めから山門
【写真 下(右)】 山門主門まわり
降り棟の外側が本瓦葺、内側が桟瓦葺、掛瓦も太くてどっしりとした質感。
右の柱に「日蓮宗祈祷所」、左の柱には寺号の板標が掲げられ、正面には「現徳山」の山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
境内には八大竜王碑、浄行菩薩、不動明王、稲荷社などが鎮座し、パワスポ的な雰囲気を感じます。
稲荷社奥の2階の入母屋造妻入りの建物が本堂のように見えますが、定かではありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の棟飾り


【写真 上(左)】 浄行菩薩
【写真 下(右)】 庫裡
御首題は山門くぐって左の階段をのぼった庫裡にて拝受しました。
滝野川寺院めぐりの御朱印も御首題で授与されます。
ご不在の場合もあるので、事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第12番の御朱印(御首題)
【下(右)】 通常の御首題
滝野川寺院めぐりの御朱印は御首題で、「滝野川寺院めぐり第十二番寺」の札所印が捺されています。
通常の御首題にこの札番はなく、構成も若干異なります。
第13番
北龍山 法音寺
北区栄町14-9
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
第13番は、真宗大谷派の法音寺です。
第13番で一旦京浜東北線の東側に出ます。
田端駅から上中里駅にかけてのJR京浜東北線北側にはJR尾久車両センター(尾久客車操車場)があって、都内有数の交通分断エリアとなっています。
第12番妙見寺からだと上中里駅東側の跨線橋を渡り、さらに梶原踏切か上中里さわやか橋経由のルートが順当かと思います。


【写真 上(左)】 上中里さわやか橋からのJR尾久車両センター
【写真 下(右)】 山門からの山内
西ヶ原から京浜東北線の線路を渡って栄町に入ると、路地が入り組む下町的な町並みとなり、法音寺も路地の一角にあります。
妙見寺からの距離はさほどではありませんが、跨線橋を渡ったり、街の雰囲気が変わったりで、けっこう遠く感じました。
なお、法音寺の最寄り駅は都電荒川線の「梶原」駅となります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 掲示版
『滝野川寺院めぐり案内』によると、当寺はもと富山県下新川郡新屋にあり、上京された釈法忍師は明治40年(1907年)、滝野川に居住されて布教活動に着手。
大正13年(1924年)、この地に本堂を建立され法音寺説教所を開設。
東京大空襲で本堂を焼失しましたが、昭和24年(1949年)には正式に寺号を取得、昭和30年(1955年)には本堂を再建し、現在に至ります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂見上げ
こぢんまりとした境内正面に立派な本堂。
入母屋造銅板葺流れ向拝。水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配しています。
参拝時、ご住職はご不在で大黒さんの対応をいただきました。
「真宗なので御朱印は出されていない。」とのことでしたが、納経帳をお見せし、滝野川寺院めぐりを巡拝中との主旨をお話しすると、「それであれば」とお受けいただき、御朱印(というか参拝記念)に準ずるものを納経帳にいただけました。
ご親切な対応をいただき、ありがとうごさいました。
ただし、今回だけの特例対応であったかもしれず、拝受した「おしるし」は掲載を控えます。
第14番
思惟山 浄業三昧寺 正受院
北区滝野川2-49-5
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番、北豊島三十三観音霊場第23番
第14番は、浄土宗の正受院です。
法音寺から赤羽駅のガードをくぐり、王子神社下の緑ゆたかな音無親水公園を抜けてのアプローチとなります。
下町の住宅街から一転、渓谷を抜けて台地に登るこのコースは変化に富み、この巡拝のハイライトともいえる道のり。
正受院は滝野川に面していますが北側滝野川岸からの参道はないので、一旦滝野川をはなれ、南側の住宅地から回り込むかたちとなります。


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 不動尊への道標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、室町時代末、弘治年間(1555-1558年)に大和國宇多郡滝門の奥の功曽久という所から夢告に従って来られた学仙坊法印が、王子七滝のひとつ「不動の滝」で修行され、滝野川から1体の不動尊像をすくい上げました。
法印は不動堂を建立され、のちに弘法大師の御作といわれ信仰を集めるこの不動尊像を安置されたのが当寺の開創とされます。
慶長年間(1596-1615年)に円誉上人が入寺されて浄土宗となりました。
浄土宗のお寺様ながら、人々のこのお不動様に対する信仰は篤く、「瀧不動尊」とも呼ばれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号18/114)に以下の記述があります。
「「浄土宗芝増上寺末 思惟山三昧寺ト号ス 弘治年中大和國宇多郡龍門ノ奥功曾久ト云所ニ學仙坊と云僧住し 不動即我ノ密法ヲ修スル事年アリ 靈夢ヲ得テ當國ニ来リテ當寺ヲ草創セリ 其年タマタマ洪水アリテ砌ノ川中ヨリ弘法大師作ノ不動ヲ得タリ 其後又旅僧来テ一軀ノ不動ヲ授クシモノ今堂中ニ安置スル處ナリ 學仙坊は弘治三年三月四日寂ス 其墳墓庭ノ小山ノ上ニアリテ五輪塔ナリ 其後寂阿了山ト云僧堂舎ヲ再建ス 文禄三年九月三日圓譽光道本堂再建ノ棟札アリ 本尊阿彌陀ハ行基ノ作ニテ坐身長二尺五分此餘惠心作ノ彌陀像一軀を置 撞鐘 古鐘ナリシカ文政三年改鑄スト云 不動堂 弘法大師作ノ立像ヲ置 観音堂 西國札所第四番観音の寫と云 瀧 本堂の脇峽下ニアリ病者ツトイ来テ浴セリ」
慈眼堂(赤ちゃんの納骨堂)があり、「赤ちゃん寺」として知られています。


【写真 上(左)】 鐘楼門
【写真 下(右)】 参道
狭い路地から意外に長い参道がつづきます。
しばらく行くと鐘楼門。下を石積みのアーチにし、上に木造建築を構えるいわゆる「竜宮門」で、おそらく入母屋屋根桟瓦葺で水引虹梁を置いています。
軒裏の垂木はめずらしい扇垂木だと思います。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
正面が本堂。入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝の均整がとれた仏堂。
水引虹梁両端に獅子と貘の彫刻木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
正面桟唐戸の上に「思惟山」の扁額。
本堂前には江戸時代の探検家近藤重蔵(守重)の甲冑姿の石像が鎮座します。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂上部
本堂向かって左の渓谷寄りには不動堂。
入母屋造桟瓦葺唐破風向拝で、水引虹梁両端に獅子彫刻の木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
唐破風の鬼板や兎毛通の仕上げも精緻で見応えがあります。
本堂右手の客殿や庫裡もしっとりと風情ある構えを見せています。
境内には不動尊の露仏が数座御座し、やはりお不動様とのゆかりがふかいお寺だと思います。
なお、「不動の滝」(泉流の滝)は現存していません。
『江戸名所図会』
「正受院の本堂の後、坂路を廻り下る事、数十歩にして飛泉あり、滔々として硝壁に趨る、此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をさゝえ、青苔露なめらかにして人跡稀なり」
境内はしっとりと落ち着いた雰囲気があり、↑で描写された面影をいまも遺しています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。書置はなく、ご住職ご不在の場合もあるので事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 御本尊の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」の揮毫と三寶印とその左横に「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印。左上に印判(不明)。
左上には「瀧不動」の揮毫、左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印がなく、上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番(「西國四番寫」の札所印)の札所印が捺されていました。
第15番
瀧河山 松橋院 金剛寺
北区滝野川3-88-17
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第43番、荒川辺八十八ヶ所霊場第16番、北豊島三十三観音霊場第31番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第28番、弁財天百社参り第52番、豊島六地蔵霊場第4番
第15番は、真言宗豊山派の金剛寺です。
第14番正受院から第16番結願の寿徳寺までは滝野川に沿うかたちで立地し、ひときわ風情のあるところです。
このあたりは江戸時代から紅葉の名所で、とくに金剛寺は「もみじ寺」の別称があります。


【写真 上(左)】 滝野川の紅葉-1
【写真 下(右)】 滝野川の紅葉-2
滝野川沿いの遊歩道脇には、音無さくら緑地、音無もみじ緑地があり、音無さくら緑地では旧石神井川の流路跡、音無もみじ緑地ではかつての江戸の名所であった松橋辨財天周辺の様子をしのぶことができます。

【写真 下(右)】 音無もみじ緑地
『滝野川寺院めぐり案内』によると、金剛寺は弘法大師が東国巡錫の折、石神井川(滝野川)にさしかかり、対岸へ渡る橋がなかったため川岸の松を切り倒して一本橋(松橋)を渡され、その際にその松の木で不動明王の尊像一躯を彫られて石上に安置されたのが草創とされています。
治承四年(1180年)10月、伊豆国で挙兵し、石橋山での敗戦ののち安房に逃れて再挙を図られた源頼朝公は、府中の六所明神(大國魂神社)へ向かう途中、滝野川松橋に布陣し、東方千住方面からの敵をここで迎え撃ち大勝利を収めたとされます。
その折、頼朝公は金剛寺に戦勝祈願したことから寄進など寺の興隆に尽くしたとされます。
一時荒廃したものの、天文年間(1532-1555年)に阿闍梨宥印が北条氏康の賛意を得て再興。
江戸時代には、八代将軍吉宗公が滝野川流域に紅葉の植林を奨励したこともあって、江戸近郊を代表する紅葉の名所となり、金剛寺は「もみじ寺」と呼ばれて秋の庶民の参詣・行楽の場として広く親しまれました。
その様子は広重の『名所江戸百景』や『東都名所』など多くの錦絵に描かれています。
また、金剛寺一帯は、豊島氏支族滝野川氏の居館滝野川城跡ともいわれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗田端村與楽寺門徒 瀧河山松橋院ト号ス 本尊不動ハ坐像ニテ長一尺餘弘法大師ノ作ト云 縁起の●ニ當所ハ弘法大師達遊歴ノ古蹟ニシテ 其頃手ツカラ此像ヲ彫刻アリテ假ニ石上ニ安ス 今其石ヲ不動影向石ト称シテ境内ニ現存シ 疾病ノモノ此石ニ水ヲソソキテ其水を服スレハ立所ニ平癒スト云 又治承年中右大将頼朝境内辨財天信仰ノ餘リ堂舎建立 及ヒ田園ヲモ寄附アリシニ 其後兵火ニ焼レ強盗ニ田園を掠メ奪ハレ 宗門タニ定カナリシヲ、天文ノ頃阿闍梨宥印ト云僧是ヲ歎キ 北條氏康ヘ訴ヘ永ク眞言ノ道場ニ復スト云 影向石 三箇ノ石ヲ重置 是縁起ニ云ヘル不動ノ像ヲ安置セル處ナリ 辨財天社 弘法大師作坐身長七寸ノ像ヲ安シ 別ニ護摩ノ灰ニテ作レル像ヲモ置リ 地蔵堂 大黒天 本堂ノ後ノ方岩窟ノ中ニ安置ス」
「辨財天 峽下ノ洞中ニ安ス長一尺ノ石像ニテ松橋辨天ト号ス 弘法大師ノ作 當時此地ニ松橋ト云橋アリシ故地名ヲオハセテ唱トイヘリ 松橋ノ名ハ前ニ云ル如ク源平盛衰記ニ見エテ舊キ地名ナリ 治承ノ頃頼朝此辨天ヲ帰依ノ餘リ太刀ヲ寄附アリシ由縁起ニ載タレト今是ヲ失ナヘリ 洞中ニ文保三年三月ト彫タル古碑一基アリ 恵比須毘沙門石像紫の楓 紅葉ノ秋紫色ヲ帶ル故此名アリ」


【写真 上(左)】 旧松橋辨財天周辺
【写真 下(右)】 江戸名所図絵(松橋辨財天窟)
〔松橋辨財天〕
金剛寺は辨天様ともゆかりのふかいお寺です。
かつての滝野川は金剛寺付近で蛇行しており、その崖には辨天の滝がかかり、崖下にあった洞窟には辨財天が祀られていました。
この辨天様は弘法大師の御作ともいわれ、松橋辨天または岩屋辨天と呼ばれて信仰を集めました。
この辨天様は、源頼朝公が戦勝を祈願し太刀一振を奉納し、戦勝ののちに辨財天の堂舎を建立、田園の寄進をしたとも伝えられています。
滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』で犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がこの松橋辨天とされています。
辨天の滝は昭和初期に枯れ、昭和33年(1958年)の狩野川台風で辨天様の洞窟は崩壊し、一部は昭和50年(1975年)前後まで残っていたようですが、その後の護岸工事や流路改修の際に取り壊され、現在は音無もみじ緑地となっています。
現地の案内版より引用抜粋してみます。
「『江戸名所図絵』には『この地は石神井河の流れに臨み、自然の山水あり。両岸高く桜楓の二樹枝を交へ、春秋ともにながめあるの一勝地なり。』」「崖下の岩屋の中には弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。また、現在都営住宅が建っている付近の崖に瀧があり、弁天の滝と呼ばれていました。」
『新編武蔵風土記稿』によると、崖下洞窟内の「松橋辨財天(岩屋辨財天)」/弘法大師作長一尺ノ石像とは別に、金剛寺境内(崖上)にも「弘法大師作坐身長七寸ノ辨天像」が安置されていた様ですが、詳細はよくわかりません。
ただし、松橋辨天の崖下洞窟も金剛寺の領地内であったようなので、金剛寺=松橋辨天と捉えられていたのでは。
松橋辨天は江戸市内でもよく知られており、江戸三十三ヶ所弁財天霊場、弁財天百社参りの札所となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 紅葉寺の寺号標


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 西國霊場札所標
江戸時代からの行楽地とあって、金剛寺周辺はいまでも華やいだ雰囲気が感じられます。
入母屋造桟瓦葺の薬医門。扁額は「瀧河山」。頭貫部梁先の雲形木鼻がダイナミック。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
参道正面、階段の上に本堂向拝。
入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝。向かって左手手前に修行大師が御座します。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に本蟇股を配しています。
正面桟唐戸の上に「金剛寺」の扁額。
虹梁に金色の彫刻を置いた、名刹らしい堂々たる向拝です。


【写真 上(左)】 辨天堂
【写真 下(右)】 辨天堂扁額
本堂向かって右手に宝形造銅板葺の辨天堂と坐像の地蔵尊が御座します。
弁天堂の御本尊は松橋辨天の系譜を引かれるお像でしょうか。
手入れの行き届いた境内で、落ち着いて参拝ができます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 滝野川七福神
御朱印は本堂向かって左手の庫裡(客殿?)にて、ご丁寧なご対応をいただき拝受しました。

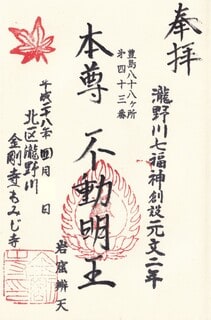
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第15番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第43番の御朱印
中央に「本尊 不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「滝野川寺院めぐり第十五番寺」と「滝野川七福神創設元文二年」の印判。左上に「豊島八十八ヶ所第四十三番」と「もみじ」の印判。左下に「岩窟辨天」の印判。
左下に寺号の印判と寺院印が捺されています。
豊島霊場の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十五番寺」の印判がなく、印判の位置も若干異なります。
「松橋辨天」の御朱印については伺っていませんが、Web上で見当たらないこと、既存の御朱印に「岩窟辨天」の印判があることから、おそらくは授与されていないと思います。
なお、「滝野川七福神」は、金剛寺境内に祀られている七福神をさすようです。
第16番
南照山 観音院 寿徳寺
北区滝野川4-22-1
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第17番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第12番、大東京百観音霊場第80番、北豊島三十三観音霊場第32番
ついに結願の16番。真言宗豊山派の寿徳寺です。
金剛寺とは反対側の滝野川の左岸にあります。


【写真 上(左)】 川沿いの遊歩道
【写真 下(右)】 滝野川橋
金剛寺から寿徳寺への順路には音無もみじ緑地があり、滝野川沿いの遊歩道の紅葉も綺麗で、歩いていて楽しいところです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、寿徳寺は寿永年間(1182-1185年)、梶原氏の家臣であった早船・小宮の両氏が梶原氏と不和になり落ち延びる途中で、海中から拾いあげた観世音菩薩を滝野川の北岸沿いの堂山の地に小堂を設け安置したのが創建と伝わります。
本尊は谷津子育観音と親しまれ、新撰組の近藤勇、および隊士の菩提寺としても知られています。
境外地には谷津大観音、近藤勇の墓所(JR埼京線「板橋」駅前)があります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
なお、『新編武蔵風土記稿』の「寿福寺」は誤植です。
「新義真言宗田端村東覺寺門徒、南照山観音院ト号ス 本尊子安観音」


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 近藤勇の碑


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 西國霊場札所碑
住宅地のなか、ぽっかりと開けた一角に立地し、境内も広々としています。
門外左手に不動堂。境内左手に修行大師像が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め右からの本堂
正面に昭和41年(1966年)落慶の本堂。
両脇に仁王尊像を置いた石段の上に、アーチ形の屋根をもつ独特なつくりの朱色の建物。
正面向拝部に「南照山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
寺伝によると、秘仏の御本尊、谷津観音は蓮華座に坐り、両手で乳児を膝の上に抱えている姿で、指を阿弥陀如来と同じ弥陀の定印に結んでおられるそうです。
本堂の向かって右にある護摩堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁と向拝柱を備え、これは以前の本堂とのこと。


【写真 上(左)】 旧本堂(護摩堂)
【写真 下(右)】 乳が垂れている銀杏
境内に切株から芽吹いている銀杏は、かつては巨木で、この樹の皮をはいで本尊に供え、祈願した後に煎じて飲むと母乳が良く出るようになるという信仰がありました。
正岡子規の高弟として知られる俳人、河東 碧梧桐の句
- 秋立つや子安詣での花の束 -
が残されており、明治に入っても谷津観音への子安詣では盛んであったことがうかがわれます。
山内には、独特の雰囲気を放つインド仏も露座しています。


【写真 上(左)】 インド仏
【写真 下(右)】 滝野川と谷津大観音
谷津大観音は山内から少しくはなれた滝野川の河岸、観音橋のたもとに御座しています。
右手与願印、左手に蓮華をもたれるおだやかな表情の銅製の坐像です。
観音橋から寿徳寺に向かい登っていく坂を「観音の坂」といいます。
現地案内標には「観音橋の北から寿徳寺へ登る坂です。坂名は、坂上にある寿徳寺に谷津観音の名で知られる観音様がまつられているからです。江戸時代には大門通とも呼ばれていました。」とあります。(北区教育委員会)


【写真 上(左)】 観音橋と谷津大観音
【写真 下(右)】 谷津大観音
御朱印は本堂向かって右手奥の庫裡にて拝受しました。
ご丁寧なご対応をいただき、「滝野川十六番満願」の揮毫もいただきました。
やはり「滝野川寺院めぐり」の巡拝者は少ないとのことでした。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第16番(満願)の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第12番の御朱印
中央に御本尊聖観世音菩薩の種子「サ」・「子育 谷津観音」の揮毫と「谷津子育観音」の印判。右上に聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。左下に寺号の揮毫と寺院印。右に「滝野川十六番満願」の揮毫をいただきました。
豊島霊場の御朱印とは、札番の揮毫が異なります。
これで滝野川寺院めぐりは結願です。
北区の落ち着いた街区を巡るこの巡拝コース、札所構成も変化に富んでいて、知名度は低いですがおすすめだと思います。
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 孤独な生きもの - KOKIA
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第7番
光明山 照徳院 円勝寺
北区中里町3-1-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:南無阿彌陀佛(六字御名号)
江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番
第7番は、浄土宗の円勝寺です。
鎌倉期の文永年間(1264-1275年)、浄土宗第2祖鎮西正宗國師の弟子信阿聖法の開山と伝わる古刹です。
一時荒廃しましたが文明年間(1469-1487年)、香誉上人が中興
戦国時代までは(江戸城)曲輪内龍ノ口(和田倉門の周辺)にあり、のちに当地に移転したと伝わります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号104/107)に以下の記述があります。
「浄土宗芝増上寺末 光明山照徳院ト号ス 本尊彌陀ハ立像長ニ尺許慈覚大師ノ作ト云 開山僧信阿聖法弘安九年二月十五日寂 御入國ノ頃ハ御曲輪内龍ノ口辺ニアリシト云 勢至堂 佛師春日ノ作レル立身ノ勢至ヲ前立トシ故アツテ三尊彌陀ヲ内佛ニ安ス 鐘楼 正徳二年新鋳ノ鐘ヲカク 御腰掛松 古木ハ枯テ植纏シモノナリ相伝フ慶長ノ頃此辺御遊猟ノ時當寺ヘ成ラセラレ此松ニ御腰ヲ掛サセラレシ故此名アリ 又此時寺領五石ノ御朱印ヲ賜ヒシガ五石松トモ称ズトイヘリ 其御朱印ハ後年回録ニカカリ烏有トナリ地所ハ今ニ領セリ」
江戸名所図会には「圓照寺 五石松」として載っています。(参考資料)
慶長の頃、家康公が御放鷹の折に当寺にお成り、上の由来をもってこの地の名所となっていたようですが(「家康公の腰掛け松」とも云われたらしい)、いまは残されていないようです。
寺宝として、護良親王の鉄冠、知恩院宮第6世尊超法親王の名号などを蔵します。
石州流茶道の流れをくむ伊佐家代々の墓所(→ 文化財説明板伊佐家の墓/北区飛鳥山博物館資料)で、茶道と所縁のふかいお寺です。
筆者は茶道の心得はまったくありませんが、茶道の流派について少しく勉強してみました。
茶道の流派の多くは、武野紹鴎の門人か千利休の直弟子の流れとされています。
(以下、系譜については諸説あるようです。)
■ 利休七哲
千利休には利休七哲(りきゅうしちてつ、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田重然(織部)、芝山宗綱(監物)、瀬田正忠(掃部)、高山長房(右近/南坊)、牧村利貞(兵部))と称される高弟があり、ここからつながる流派があります。
細川忠興(三斎)→ 三斎流(一尾流)、御家流
古田重然(織部)→ 織部流 、遠州流、小堀遠州流、大和遠州流、上田宗箇流、御家流
■ 千道安の流れ(堺千家系)
・宗和流 流祖、金森重近(宗和)は千利休の門下、長近の養子金森可重は千道安の門下とされる。加賀藩にて隆盛。
・石州流 流祖、片桐石州は千道安門下の桑山宗仙に師事。
・石州流怡渓派
・石州流伊佐派 怡渓派の伊佐家の系譜につながるとされる。
※他に石州流として数派あり
・鎮信流 流祖は肥前平戸藩四代藩主松浦鎮信公。石州流・宗和流の流れ。
・不昧流 流祖は松平不昧公(治郷公)。不昧公は石州流怡渓派三代伊佐幸琢から石州流怡渓派を学んだため、石州流不昧派と称されることがある。
■ 千宗旦の流れ(宗旦流)
・三千家 千利休の後妻の連れ子である千少庵の系統
・表千家 不審庵 宗旦の三男の系統。江戸千家もこの流れ。
・裏千家 今日庵 宗旦の四男の系統
・武者小路千家 官休庵 宗旦の二男の系統
・宗旦四天王 宗旦の門弟のうち、とくに活躍した4人にちなむ流派
・宗徧流 流祖は山田宗徧。
・庸軒流 流祖は藤村庸軒。
・普斎流 流祖は杉木普斎。
※ 久須美疎安にちなむ流派は不詳
★ 柳営茶道(武家茶道四派)
江戸幕府で重んじられた武家茶道。「武家茶道四派」とも称され、現在も柳営会により啓蒙活動が営まれ、護国寺などで定例の茶会が催されています。
・旧磐城平藩主安藤家御家流
・小堀遠州流
・石州流伊佐派(石州流怡渓派の流れ)
・鎮信流
柳営(武家)茶道はいずれも利休七哲、ないし千道安の流れで、円勝寺とゆかりのふかい石州流怡渓派・伊佐派も江戸幕府と深いつながりがありました。
伊佐家は代々”幸琢”(こうたく)を名乗り、五代にわたって江戸幕府の数寄屋頭を勤めました。
数寄屋頭とは幕府の職名で、若年寄に属し、殿中の茶礼・茶器などを司り、数寄屋坊主を統轄したとされます。
怡渓宗悦(いけいそうえつ)は大徳寺二五三世に就かれた後、江戸の広尾祥雲寺や品川東海寺に入られた高僧で、茶人としても名高く、『石州流三百ヶ条註解』を著されて石州流怡渓派の派祖とされます。
なお、怡渓宗悦は関東大震災を契機に品川から世田谷烏山に移転した高源院の開山とされます。(高源院の御朱印はこちらに掲載しています。)
数寄屋頭初代の伊佐幸琢(半々庵)は怡渓宗悦より皆伝を受けた高弟で、以後五代にわたって幕府の御数寄屋頭となり石州流怡渓派の名を高めました。
不昧流の流祖、松平不昧公(治郷公)が、三代伊佐幸琢(半寸庵)から石州流怡渓派を学ばれたことからも、柳営茶道における伊佐家(石州流怡渓派)の権威のほどがうかがわれます。


【写真 上(左)】 「第二中里踏切」
【写真 下(右)】 参道入口
JR山手線の唯一の踏切「第二中里踏切」のすぐそばにある寺院です。
踏切のよこから伸びる参道は銀杏の並木、大ぶりな降り棟、袖塀を備えた立派な薬医門のおくに本堂が姿を見せています。


【写真 上(左)】 勢至菩薩碑
【写真 下(右)】 秋の参道
参道脇に「厄除 大勢至菩薩霊●」と刻まれた石碑があります。
『新編武蔵風土記稿』によると、かつて山内に勢至堂があり春日仏師による立身の勢至菩薩が祀られていたとされるので、これに因むものかと思われます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
山手線の線路に近いものの、山内には古刹特有の落ち着いた空気が流れています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、鬼板部、降り棟、隅棟、稚児棟すべての棟飾りに経の巻獅子口を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ


【写真 上(左)】 木鼻の獅子(左)
【写真 下(右)】 木鼻の獅子(右)
水引虹梁木鼻では、彫りの深い獅子が睨みをきかせています。
頭貫上に出三つ斗、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上に「光明山」の扁額。
扁額後ろの小壁にも彫り物が置かれ、向拝両脇の格子窓は奥に花頭窓を繰抜くなど芸が細かいです。


【写真 上(左)】 扁額と中備の龍
【写真 下(右)】 扁額
本堂右手の墓所、伊佐家の墓石には初代、二代半寸庵の和歌と俳句が刻まれています。
(文化五年(1808年)十一月銘)
- 出る日も入る日も遠き霊鷲山 またゝくひまに入相のかね -
初代 半寸庵知當


【写真 上(左)】 本堂手前から庫裡方向
【写真 下(右)】 庫裡
本堂左手の庫裡の方に進むと、さらに奥ゆかしい佇まいに。
こちらは、滝野川寺院めぐり第7番、江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番の3つの札所を兼ねておられますが、いずれも巡拝者は多いとは思われません。
しかし、ご住職は心あたたまるご対応で、御朱印の揮毫についてしきりに謙遜なさっておられましたが、素晴らしい筆致の御朱印を授与いただけました。
丸みを帯びた六字御名号は、祐天上人の御名号、徳本上人の「徳本文字」を彷彿とさせる筆致です。
当寺は、幡随意上人、祐天上人、徳本上人などの墨跡を蔵されるとのことなので、ご住職は六字御名号墨跡の研究をされているのかもしれません。
江戸・東京四十四閻魔参り第36番の札所で、閻魔様の御縁日の16日にも参拝しましたが、現在は閻魔大王の御朱印はお出しになられていないとのことです。

● 滝野川寺院めぐり第7番の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫と梵字九字の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左上に勢至菩薩の種子「サク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「勢至菩薩」を含む印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第七番寺」の札所印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
中央の梵字九字の内容は、不勉強につきよくわかりません。
御朱印にも勢至菩薩が登場されるので、やはりこのお寺様において勢至菩薩は格別の尊格なのかもしれません。
(寺宝として秘仏の大勢至菩薩像を蔵されます。また、勢至菩薩は浄土宗の根本所依教典である「観無量寿経」で説かれ、法然上人を勢至菩薩の化身(勢至菩薩は法然上人(幼名は勢至丸)の本地身)とする信仰もあって、浄土宗でもなじみのふかい尊格です。)


【上(左)】 御本尊(札所無申告)の御朱印
【下(右)】 閻魔大王御縁日(十六日)の御朱印
御本尊の御朱印は、滝野川寺院めぐりと同様の構成で、札所印は捺されていません。
閻魔大王御縁日の御朱印は、御本尊の御朱印と同じ内容です。
第8番
平塚山 案烙院 城官寺
公式Web
北区上中里1-42-8
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:阿弥陀如来
御府内八十八箇所第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、江戸八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番
第8番は、真言宗豊山派の城官寺です。
寺伝(当寺公式Web)によると、筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号102/107)に以下の記述があります。
「(平塚明神社別當)城官寺 新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作と云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ寛永十一年社領修理アリシ時、金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ、今ノ宗門ニ改ムト云(以下略)」
江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。
山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚明神(現在の平塚神社)に治癒を日夜祈った。その霊験もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。
寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。
これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。
享保三年(1718年)寂の真恵を法流開基として、現在に至ります。
当寺には、江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。
奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏、外科は桂川氏が世襲しました。
当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当寺は医術とふかい所縁をもつことになります。
別当を勤めた平塚神社とは神仏分離により分かれましたが、少しく触れてみます。
御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。
略縁起によると、創立は平安後期元永年中、八幡太郎義家公が奥州征伐の凱旋途中にこの地を訪れ領主豊島近義に鎧一領を賜われました。近義は拝領した鎧を清浄な地に埋め塚を築いて自城の鎮守として祀りました。平坦な塚だったので平塚と呼ばれ、三兄弟にちなんで平塚三所大明神として崇められました。
家光公の時代、上記の病平癒の件もあって再建され、家光公もたびたび参詣に訪れたとされます。
徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。


【写真 上(左)】 平塚神社の境内
【下(右)】 平塚神社の御朱印
当寺の最寄り駅はJR京浜東北線「上中里」駅か東京メトロ「西ケ原」駅。
いずれも都内屈指の閑散駅で、都内育ちでも知らない方が多いのでは?(わたしも寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。)
ただし、周辺には寺社が意外に多いので、御朱印巡りの際には便利な駅といえましょう。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。
「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。
山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 ???
全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。
正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 向拝拝み部
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。
向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所の札所なので、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。

● 滝野川寺院めぐり第8番の御朱印
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右下に「滝野川寺院めぐり 第八番寺」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
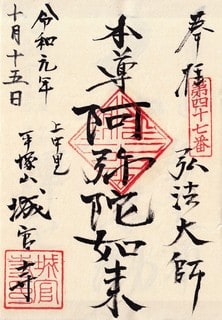
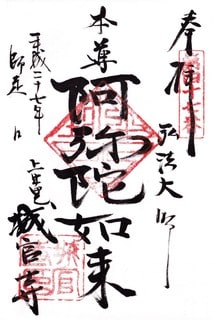
【上(左)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「本尊 阿弥陀如来」と「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右に「第四十七番」の札所印。左下に山号と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右上に「第四十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
滝野川寺院めぐりの御朱印とは札所印がことなるのみです。
第9番
佛寶山 西光院 無量寺
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王・弘法大師
御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番
第9番は、真言宗豊山派の無量寺です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。
また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺で、もともと参詣者の多い寺院とみられます。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」
「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」
「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」
「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」
創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。
大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。


【写真 上(左)】 七社神社の社頭
【写真 下(右)】 七社神社の境内
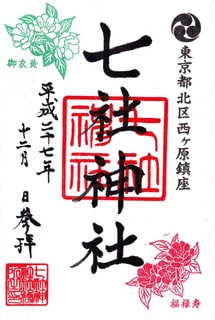

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)
【下(右)】 七社神社の御朱印
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。
第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。
緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。
この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
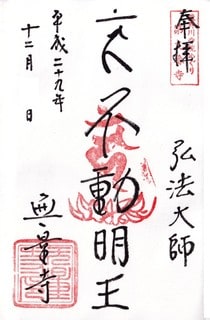
● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

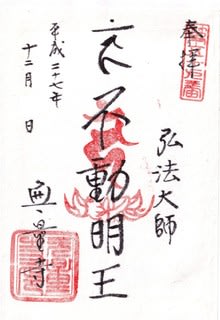
【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀如来第3番の御朱印
中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
第10番
補陀山 補陀落寿院 昌林寺
北区西ケ原3-12-6
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
御朱印尊格:末木観音
江戸六阿弥陀霊場(末木観音)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番
第10番は、曹洞宗の昌林寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」
昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られています。
江戸(武州)六阿弥陀は、行基菩薩が一本の霊木から刻み上げた7体の阿弥陀仏と1体の観音様を参拝する阿弥陀巡りで、江戸時代、とくに春秋の彼岸に女性を中心に大流行したとされます。
五番常楽院の縁起、三番無量寺・木残昌林寺の寺伝、足立区資料、および「江戸の3 つの「六阿弥陀参」における「武州六阿弥陀参」の特徴」から創祀を辿ってみます。
その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、熊野権現に祈ると女の子を授かりました。
「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。
成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、誹りを受けて12人(6人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。
足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。
紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。
この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。
後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀参りとしてとくに江戸期に信仰を集めました。
『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。
滝野川寺院めぐりの無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は江戸六阿弥陀の札所と重複します。
また、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、滝野川寺院めぐりの周辺エリアが江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていることがわかります。
昌林寺の末木観世音菩薩については、『江戸名所図会』に、「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸(武州)六阿弥陀との関連が裏付けられています。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標
谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。
山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め左から本堂
入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
朱の欄干と横長の花頭窓が印象的な本堂の手前には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標と昭和62年造立の百寿観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 百寿観世音菩薩
【写真 下(右)】 本堂扁額
メジャー霊場の札所ではありませんが、最近は「江戸六阿弥陀」巡拝者も増えているのか、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は、「江戸六阿弥陀」の参拝でも捺されているようです。

● 滝野川寺院めぐり第10番の御朱印
中央に「末木観音」の揮毫と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に「滝野川寺院めぐり 第十番寺」の札所印で、札所無申告で授与されると思われる「藤井寺寫 西國第五番」の上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は捺されていません。
左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀(木残)の御朱印
中央に「本尊 末木観世音菩薩」の印判と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印の札所印「藤井寺寫 西國第五番」の札所印が捺されています。
左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
滝野川霊場の御朱印では「末木観音」の揮毫。江戸六阿弥陀と観音霊場の御朱印では「本尊 末木観世音菩薩」の印判の様式にて授与されるようです。
第11番
明王山 大聖寺 不動院
北区西ヶ原3-23-2
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第53番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番、北豊島三十三観音霊場第29番
第11番は、真言宗豊山派の不動院です。
第10番昌林寺から谷田川通り沿いに少し歩くと不動院です。
ここで通りの由来となった「谷田川」について少し考えてみます。
谷田川はいまはすべて暗渠となり地図上から辿るのは困難ですが、世の中には奇特な方がおられ、かつての谷田川を辿る紀行がWebでいくつかみつかるので、そちらも参考にさせていただきまとめてみます。
谷田川はかつての石神井川とみる説もありますが、多くの説は染井霊園の北側ないし巣鴨あたりを源流とする別の流れと.みています。
そこから西ヶ原銀座通りに入り、染井銀座商店街~霜降銀座商店街と流れます。
本郷通りの「霜降橋」交差点は、谷田川にかかっていた橋名のなごりとされています。
ここからはほぼ谷田川通りに沿って、池之端の不忍池をめざして下っていきます。
谷田川通りは不忍通りのすぐ東側を走っています。
JR駒込駅の東側あたりで山手線内に入り、西日暮里駅の西側を通って、谷中と千駄木のあいだを流れます。根津駅から谷中への登り口にあたる大黒屋煎餅の下あたりを流れ、池之端辺で不忍池に流れ込みます。
ここで気づいたのは、「滝野川寺院めぐり」は、ほぼ旧谷田川に沿って札所が置かれているということです。
JR田端駅南側から旧古河庭園にかけては高台にあり、その名もずばり「田端高台通り」が走っています。
また、旧古河庭園から王子・飛鳥山にかけても高台で、ふるくは「御殿山」と呼ばれていました。なので、田端駅から王子駅にかけてのJRの南側はすべて高台にあります。
谷田川はこの高台の南側下を沿うように流れていました。
「滝野川寺院めぐり」の札所は一部の例外をのぞいて、この高台と旧谷田川のあいだの南傾地に位置しています。
寺社は崖線に沿って置かれる例が多いので、こちらも例外ではありません。
第1番与楽寺~第7番円勝寺は、すべて「田端高台通り」と旧谷田川のあいだにあり、南傾斜面をトラバースしていくので、大きな高低差はありません。
第8番城官寺は「御殿山」まわりの高台にあり、そこから旧谷田川の流れに近い第9番無量寺の山門までは、急なくだりとなります。
旧谷田川沿いの第10番昌林寺、第11番不動寺を経て、ふたたび「御殿山」エリアにある第12番妙見寺に向けて登りがつづきます。
以上のとおり、第8番城官寺から第12番妙見寺にかけては、地形的にも変化に富んだ巡拝を味わうことができます。
不動院の開創については『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「同宗田端村與樂寺門徒明王山ト號ス 本尊不動開山僧海善 元和六年六月六日寂」
開山は海善和尚(元和六年(1620年)遷化)。その後は数度の火災により寺伝が焼失し詳細は不明のようです。
また、『新編武蔵風土記稿』に「阿彌陀堂。西國二十三番攝州勝尼寺寫の観音を相殿とす。」とあるので、不動明王が御座す本堂のほかに阿弥陀堂があって、そちらに西國二十三番(上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番)の札所本尊の観音様が祀られていたのかもしれません。
同書によると、当初は田端与楽寺の末でしたが、『滝野川寺院めぐり案内』によると、昭和16年(1941年)、総本山長谷寺に本寺換えをしています。
『滝野川寺院めぐり案内』には、当寺御本尊のお不動様ゆかりの逸話が記されています。
先の終戦直後、一帯は焼け野原となりましたが、いち早く境内に小屋(お堂)が建てられました。あるときこの小屋(お堂)に賊が侵入し、堂守をされていた慈信和尚の御母堂に刃物を突きつけました。そのとき、どこからともなく人の近づく足音が聞こえ、賊は一物もとらずに退散したそうです。
件の賊は後年、本人の努力と関係者の指導よろしきを得て立派に更正し、平和な一生を全うしたそうです。
このことが近辺に伝わり、当寺のお不動様は「魔除け不動」として信者さんの信仰を集めているそうです。


【写真 上(左)】 豊島霊場札所標
【写真 下(右)】 寺号標
山門向かって右側に「弘法大師」と豊島霊場が一体となった石碑、右手に寺号標と真新しい六地蔵が御座します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 山門付近から山内
本堂は昭和51年建立の鉄筋建てで、手前の階段をのぼった2階正面が向拝となっています。
本堂下には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第23番の札所標がありました。


【写真 上(左)】 本堂下
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 西国霊場札所標
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて授与いただけます。
最近巡拝者が増えているといわれる豊島八十八ヶ所霊場の第53番の札所なので、御朱印授与は手慣れておられ、書置のご用意もありました。
参拝時、ご住職はご不在で豊島霊場の御朱印ならば書置に札所印を捺してすぐにお出しになれるとのことでしたが、滝野川霊場の札所印は所在不明とのこと。
郵送をお願いすると快くお受けいただいたので、郵送にて拝受しました。
(ちなみに、筆者は宛先を書いて切手を貼り、郵送のお願い文書と御朱印用紙を同封した返信用の封筒を持ち歩いています。)


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第53番の御朱印
中央に「不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の荘厳体種子「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「豊島八十八ヶ所第五十三番」の札所印。
左上に「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判。
左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
豊島霊場御朱印との違いは「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判の有無のみです。
(第12番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 茜色の約束 - 森恵
■ 夢の大地 - Kalafina
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第7番
光明山 照徳院 円勝寺
北区中里町3-1-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:南無阿彌陀佛(六字御名号)
江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番
第7番は、浄土宗の円勝寺です。
鎌倉期の文永年間(1264-1275年)、浄土宗第2祖鎮西正宗國師の弟子信阿聖法の開山と伝わる古刹です。
一時荒廃しましたが文明年間(1469-1487年)、香誉上人が中興
戦国時代までは(江戸城)曲輪内龍ノ口(和田倉門の周辺)にあり、のちに当地に移転したと伝わります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号104/107)に以下の記述があります。
「浄土宗芝増上寺末 光明山照徳院ト号ス 本尊彌陀ハ立像長ニ尺許慈覚大師ノ作ト云 開山僧信阿聖法弘安九年二月十五日寂 御入國ノ頃ハ御曲輪内龍ノ口辺ニアリシト云 勢至堂 佛師春日ノ作レル立身ノ勢至ヲ前立トシ故アツテ三尊彌陀ヲ内佛ニ安ス 鐘楼 正徳二年新鋳ノ鐘ヲカク 御腰掛松 古木ハ枯テ植纏シモノナリ相伝フ慶長ノ頃此辺御遊猟ノ時當寺ヘ成ラセラレ此松ニ御腰ヲ掛サセラレシ故此名アリ 又此時寺領五石ノ御朱印ヲ賜ヒシガ五石松トモ称ズトイヘリ 其御朱印ハ後年回録ニカカリ烏有トナリ地所ハ今ニ領セリ」
江戸名所図会には「圓照寺 五石松」として載っています。(参考資料)
慶長の頃、家康公が御放鷹の折に当寺にお成り、上の由来をもってこの地の名所となっていたようですが(「家康公の腰掛け松」とも云われたらしい)、いまは残されていないようです。
寺宝として、護良親王の鉄冠、知恩院宮第6世尊超法親王の名号などを蔵します。
石州流茶道の流れをくむ伊佐家代々の墓所(→ 文化財説明板伊佐家の墓/北区飛鳥山博物館資料)で、茶道と所縁のふかいお寺です。
筆者は茶道の心得はまったくありませんが、茶道の流派について少しく勉強してみました。
茶道の流派の多くは、武野紹鴎の門人か千利休の直弟子の流れとされています。
(以下、系譜については諸説あるようです。)
■ 利休七哲
千利休には利休七哲(りきゅうしちてつ、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田重然(織部)、芝山宗綱(監物)、瀬田正忠(掃部)、高山長房(右近/南坊)、牧村利貞(兵部))と称される高弟があり、ここからつながる流派があります。
細川忠興(三斎)→ 三斎流(一尾流)、御家流
古田重然(織部)→ 織部流 、遠州流、小堀遠州流、大和遠州流、上田宗箇流、御家流
■ 千道安の流れ(堺千家系)
・宗和流 流祖、金森重近(宗和)は千利休の門下、長近の養子金森可重は千道安の門下とされる。加賀藩にて隆盛。
・石州流 流祖、片桐石州は千道安門下の桑山宗仙に師事。
・石州流怡渓派
・石州流伊佐派 怡渓派の伊佐家の系譜につながるとされる。
※他に石州流として数派あり
・鎮信流 流祖は肥前平戸藩四代藩主松浦鎮信公。石州流・宗和流の流れ。
・不昧流 流祖は松平不昧公(治郷公)。不昧公は石州流怡渓派三代伊佐幸琢から石州流怡渓派を学んだため、石州流不昧派と称されることがある。
■ 千宗旦の流れ(宗旦流)
・三千家 千利休の後妻の連れ子である千少庵の系統
・表千家 不審庵 宗旦の三男の系統。江戸千家もこの流れ。
・裏千家 今日庵 宗旦の四男の系統
・武者小路千家 官休庵 宗旦の二男の系統
・宗旦四天王 宗旦の門弟のうち、とくに活躍した4人にちなむ流派
・宗徧流 流祖は山田宗徧。
・庸軒流 流祖は藤村庸軒。
・普斎流 流祖は杉木普斎。
※ 久須美疎安にちなむ流派は不詳
★ 柳営茶道(武家茶道四派)
江戸幕府で重んじられた武家茶道。「武家茶道四派」とも称され、現在も柳営会により啓蒙活動が営まれ、護国寺などで定例の茶会が催されています。
・旧磐城平藩主安藤家御家流
・小堀遠州流
・石州流伊佐派(石州流怡渓派の流れ)
・鎮信流
柳営(武家)茶道はいずれも利休七哲、ないし千道安の流れで、円勝寺とゆかりのふかい石州流怡渓派・伊佐派も江戸幕府と深いつながりがありました。
伊佐家は代々”幸琢”(こうたく)を名乗り、五代にわたって江戸幕府の数寄屋頭を勤めました。
数寄屋頭とは幕府の職名で、若年寄に属し、殿中の茶礼・茶器などを司り、数寄屋坊主を統轄したとされます。
怡渓宗悦(いけいそうえつ)は大徳寺二五三世に就かれた後、江戸の広尾祥雲寺や品川東海寺に入られた高僧で、茶人としても名高く、『石州流三百ヶ条註解』を著されて石州流怡渓派の派祖とされます。
なお、怡渓宗悦は関東大震災を契機に品川から世田谷烏山に移転した高源院の開山とされます。(高源院の御朱印はこちらに掲載しています。)
数寄屋頭初代の伊佐幸琢(半々庵)は怡渓宗悦より皆伝を受けた高弟で、以後五代にわたって幕府の御数寄屋頭となり石州流怡渓派の名を高めました。
不昧流の流祖、松平不昧公(治郷公)が、三代伊佐幸琢(半寸庵)から石州流怡渓派を学ばれたことからも、柳営茶道における伊佐家(石州流怡渓派)の権威のほどがうかがわれます。


【写真 上(左)】 「第二中里踏切」
【写真 下(右)】 参道入口
JR山手線の唯一の踏切「第二中里踏切」のすぐそばにある寺院です。
踏切のよこから伸びる参道は銀杏の並木、大ぶりな降り棟、袖塀を備えた立派な薬医門のおくに本堂が姿を見せています。


【写真 上(左)】 勢至菩薩碑
【写真 下(右)】 秋の参道
参道脇に「厄除 大勢至菩薩霊●」と刻まれた石碑があります。
『新編武蔵風土記稿』によると、かつて山内に勢至堂があり春日仏師による立身の勢至菩薩が祀られていたとされるので、これに因むものかと思われます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
山手線の線路に近いものの、山内には古刹特有の落ち着いた空気が流れています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、鬼板部、降り棟、隅棟、稚児棟すべての棟飾りに経の巻獅子口を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ


【写真 上(左)】 木鼻の獅子(左)
【写真 下(右)】 木鼻の獅子(右)
水引虹梁木鼻では、彫りの深い獅子が睨みをきかせています。
頭貫上に出三つ斗、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上に「光明山」の扁額。
扁額後ろの小壁にも彫り物が置かれ、向拝両脇の格子窓は奥に花頭窓を繰抜くなど芸が細かいです。


【写真 上(左)】 扁額と中備の龍
【写真 下(右)】 扁額
本堂右手の墓所、伊佐家の墓石には初代、二代半寸庵の和歌と俳句が刻まれています。
(文化五年(1808年)十一月銘)
- 出る日も入る日も遠き霊鷲山 またゝくひまに入相のかね -
初代 半寸庵知當


【写真 上(左)】 本堂手前から庫裡方向
【写真 下(右)】 庫裡
本堂左手の庫裡の方に進むと、さらに奥ゆかしい佇まいに。
こちらは、滝野川寺院めぐり第7番、江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番の3つの札所を兼ねておられますが、いずれも巡拝者は多いとは思われません。
しかし、ご住職は心あたたまるご対応で、御朱印の揮毫についてしきりに謙遜なさっておられましたが、素晴らしい筆致の御朱印を授与いただけました。
丸みを帯びた六字御名号は、祐天上人の御名号、徳本上人の「徳本文字」を彷彿とさせる筆致です。
当寺は、幡随意上人、祐天上人、徳本上人などの墨跡を蔵されるとのことなので、ご住職は六字御名号墨跡の研究をされているのかもしれません。
江戸・東京四十四閻魔参り第36番の札所で、閻魔様の御縁日の16日にも参拝しましたが、現在は閻魔大王の御朱印はお出しになられていないとのことです。

● 滝野川寺院めぐり第7番の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫と梵字九字の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左上に勢至菩薩の種子「サク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「勢至菩薩」を含む印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第七番寺」の札所印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
中央の梵字九字の内容は、不勉強につきよくわかりません。
御朱印にも勢至菩薩が登場されるので、やはりこのお寺様において勢至菩薩は格別の尊格なのかもしれません。
(寺宝として秘仏の大勢至菩薩像を蔵されます。また、勢至菩薩は浄土宗の根本所依教典である「観無量寿経」で説かれ、法然上人を勢至菩薩の化身(勢至菩薩は法然上人(幼名は勢至丸)の本地身)とする信仰もあって、浄土宗でもなじみのふかい尊格です。)


【上(左)】 御本尊(札所無申告)の御朱印
【下(右)】 閻魔大王御縁日(十六日)の御朱印
御本尊の御朱印は、滝野川寺院めぐりと同様の構成で、札所印は捺されていません。
閻魔大王御縁日の御朱印は、御本尊の御朱印と同じ内容です。
第8番
平塚山 案烙院 城官寺
公式Web
北区上中里1-42-8
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:阿弥陀如来
御府内八十八箇所第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、江戸八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番
第8番は、真言宗豊山派の城官寺です。
寺伝(当寺公式Web)によると、筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号102/107)に以下の記述があります。
「(平塚明神社別當)城官寺 新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作と云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ寛永十一年社領修理アリシ時、金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ、今ノ宗門ニ改ムト云(以下略)」
江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。
山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚明神(現在の平塚神社)に治癒を日夜祈った。その霊験もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。
寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。
これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。
享保三年(1718年)寂の真恵を法流開基として、現在に至ります。
当寺には、江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。
奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏、外科は桂川氏が世襲しました。
当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当寺は医術とふかい所縁をもつことになります。
別当を勤めた平塚神社とは神仏分離により分かれましたが、少しく触れてみます。
御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。
略縁起によると、創立は平安後期元永年中、八幡太郎義家公が奥州征伐の凱旋途中にこの地を訪れ領主豊島近義に鎧一領を賜われました。近義は拝領した鎧を清浄な地に埋め塚を築いて自城の鎮守として祀りました。平坦な塚だったので平塚と呼ばれ、三兄弟にちなんで平塚三所大明神として崇められました。
家光公の時代、上記の病平癒の件もあって再建され、家光公もたびたび参詣に訪れたとされます。
徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。


【写真 上(左)】 平塚神社の境内
【下(右)】 平塚神社の御朱印
当寺の最寄り駅はJR京浜東北線「上中里」駅か東京メトロ「西ケ原」駅。
いずれも都内屈指の閑散駅で、都内育ちでも知らない方が多いのでは?(わたしも寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。)
ただし、周辺には寺社が意外に多いので、御朱印巡りの際には便利な駅といえましょう。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。
「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。
山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 ???
全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。
正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 向拝拝み部
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。
向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所の札所なので、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。

● 滝野川寺院めぐり第8番の御朱印
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右下に「滝野川寺院めぐり 第八番寺」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
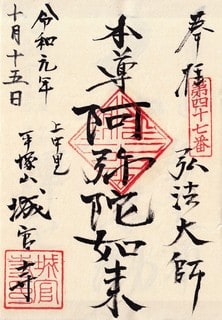
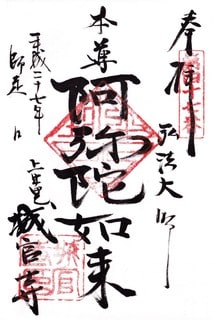
【上(左)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「本尊 阿弥陀如来」と「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右に「第四十七番」の札所印。左下に山号と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右上に「第四十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
滝野川寺院めぐりの御朱印とは札所印がことなるのみです。
第9番
佛寶山 西光院 無量寺
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王・弘法大師
御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番
第9番は、真言宗豊山派の無量寺です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。
また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺で、もともと参詣者の多い寺院とみられます。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」
「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」
「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」
「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」
創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。
大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。


【写真 上(左)】 七社神社の社頭
【写真 下(右)】 七社神社の境内
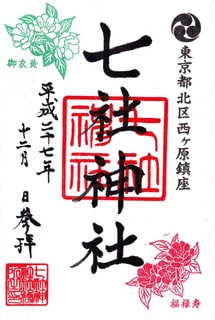

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)
【下(右)】 七社神社の御朱印
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。
第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。
緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。
この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
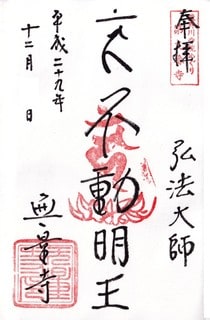
● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

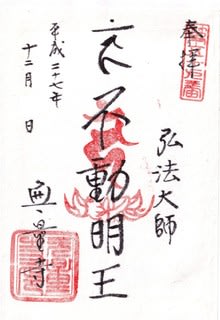
【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀如来第3番の御朱印
中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
第10番
補陀山 補陀落寿院 昌林寺
北区西ケ原3-12-6
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
御朱印尊格:末木観音
江戸六阿弥陀霊場(末木観音)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番
第10番は、曹洞宗の昌林寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」
昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られています。
江戸(武州)六阿弥陀は、行基菩薩が一本の霊木から刻み上げた7体の阿弥陀仏と1体の観音様を参拝する阿弥陀巡りで、江戸時代、とくに春秋の彼岸に女性を中心に大流行したとされます。
五番常楽院の縁起、三番無量寺・木残昌林寺の寺伝、足立区資料、および「江戸の3 つの「六阿弥陀参」における「武州六阿弥陀参」の特徴」から創祀を辿ってみます。
その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、熊野権現に祈ると女の子を授かりました。
「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。
成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、誹りを受けて12人(6人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。
足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。
紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。
この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。
後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀参りとしてとくに江戸期に信仰を集めました。
『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。
滝野川寺院めぐりの無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は江戸六阿弥陀の札所と重複します。
また、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、滝野川寺院めぐりの周辺エリアが江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていることがわかります。
昌林寺の末木観世音菩薩については、『江戸名所図会』に、「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸(武州)六阿弥陀との関連が裏付けられています。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標
谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。
山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め左から本堂
入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
朱の欄干と横長の花頭窓が印象的な本堂の手前には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標と昭和62年造立の百寿観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 百寿観世音菩薩
【写真 下(右)】 本堂扁額
メジャー霊場の札所ではありませんが、最近は「江戸六阿弥陀」巡拝者も増えているのか、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は、「江戸六阿弥陀」の参拝でも捺されているようです。

● 滝野川寺院めぐり第10番の御朱印
中央に「末木観音」の揮毫と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に「滝野川寺院めぐり 第十番寺」の札所印で、札所無申告で授与されると思われる「藤井寺寫 西國第五番」の上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は捺されていません。
左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀(木残)の御朱印
中央に「本尊 末木観世音菩薩」の印判と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印の札所印「藤井寺寫 西國第五番」の札所印が捺されています。
左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
滝野川霊場の御朱印では「末木観音」の揮毫。江戸六阿弥陀と観音霊場の御朱印では「本尊 末木観世音菩薩」の印判の様式にて授与されるようです。
第11番
明王山 大聖寺 不動院
北区西ヶ原3-23-2
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第53番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番、北豊島三十三観音霊場第29番
第11番は、真言宗豊山派の不動院です。
第10番昌林寺から谷田川通り沿いに少し歩くと不動院です。
ここで通りの由来となった「谷田川」について少し考えてみます。
谷田川はいまはすべて暗渠となり地図上から辿るのは困難ですが、世の中には奇特な方がおられ、かつての谷田川を辿る紀行がWebでいくつかみつかるので、そちらも参考にさせていただきまとめてみます。
谷田川はかつての石神井川とみる説もありますが、多くの説は染井霊園の北側ないし巣鴨あたりを源流とする別の流れと.みています。
そこから西ヶ原銀座通りに入り、染井銀座商店街~霜降銀座商店街と流れます。
本郷通りの「霜降橋」交差点は、谷田川にかかっていた橋名のなごりとされています。
ここからはほぼ谷田川通りに沿って、池之端の不忍池をめざして下っていきます。
谷田川通りは不忍通りのすぐ東側を走っています。
JR駒込駅の東側あたりで山手線内に入り、西日暮里駅の西側を通って、谷中と千駄木のあいだを流れます。根津駅から谷中への登り口にあたる大黒屋煎餅の下あたりを流れ、池之端辺で不忍池に流れ込みます。
ここで気づいたのは、「滝野川寺院めぐり」は、ほぼ旧谷田川に沿って札所が置かれているということです。
JR田端駅南側から旧古河庭園にかけては高台にあり、その名もずばり「田端高台通り」が走っています。
また、旧古河庭園から王子・飛鳥山にかけても高台で、ふるくは「御殿山」と呼ばれていました。なので、田端駅から王子駅にかけてのJRの南側はすべて高台にあります。
谷田川はこの高台の南側下を沿うように流れていました。
「滝野川寺院めぐり」の札所は一部の例外をのぞいて、この高台と旧谷田川のあいだの南傾地に位置しています。
寺社は崖線に沿って置かれる例が多いので、こちらも例外ではありません。
第1番与楽寺~第7番円勝寺は、すべて「田端高台通り」と旧谷田川のあいだにあり、南傾斜面をトラバースしていくので、大きな高低差はありません。
第8番城官寺は「御殿山」まわりの高台にあり、そこから旧谷田川の流れに近い第9番無量寺の山門までは、急なくだりとなります。
旧谷田川沿いの第10番昌林寺、第11番不動寺を経て、ふたたび「御殿山」エリアにある第12番妙見寺に向けて登りがつづきます。
以上のとおり、第8番城官寺から第12番妙見寺にかけては、地形的にも変化に富んだ巡拝を味わうことができます。
不動院の開創については『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「同宗田端村與樂寺門徒明王山ト號ス 本尊不動開山僧海善 元和六年六月六日寂」
開山は海善和尚(元和六年(1620年)遷化)。その後は数度の火災により寺伝が焼失し詳細は不明のようです。
また、『新編武蔵風土記稿』に「阿彌陀堂。西國二十三番攝州勝尼寺寫の観音を相殿とす。」とあるので、不動明王が御座す本堂のほかに阿弥陀堂があって、そちらに西國二十三番(上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番)の札所本尊の観音様が祀られていたのかもしれません。
同書によると、当初は田端与楽寺の末でしたが、『滝野川寺院めぐり案内』によると、昭和16年(1941年)、総本山長谷寺に本寺換えをしています。
『滝野川寺院めぐり案内』には、当寺御本尊のお不動様ゆかりの逸話が記されています。
先の終戦直後、一帯は焼け野原となりましたが、いち早く境内に小屋(お堂)が建てられました。あるときこの小屋(お堂)に賊が侵入し、堂守をされていた慈信和尚の御母堂に刃物を突きつけました。そのとき、どこからともなく人の近づく足音が聞こえ、賊は一物もとらずに退散したそうです。
件の賊は後年、本人の努力と関係者の指導よろしきを得て立派に更正し、平和な一生を全うしたそうです。
このことが近辺に伝わり、当寺のお不動様は「魔除け不動」として信者さんの信仰を集めているそうです。


【写真 上(左)】 豊島霊場札所標
【写真 下(右)】 寺号標
山門向かって右側に「弘法大師」と豊島霊場が一体となった石碑、右手に寺号標と真新しい六地蔵が御座します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 山門付近から山内
本堂は昭和51年建立の鉄筋建てで、手前の階段をのぼった2階正面が向拝となっています。
本堂下には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第23番の札所標がありました。


【写真 上(左)】 本堂下
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 西国霊場札所標
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて授与いただけます。
最近巡拝者が増えているといわれる豊島八十八ヶ所霊場の第53番の札所なので、御朱印授与は手慣れておられ、書置のご用意もありました。
参拝時、ご住職はご不在で豊島霊場の御朱印ならば書置に札所印を捺してすぐにお出しになれるとのことでしたが、滝野川霊場の札所印は所在不明とのこと。
郵送をお願いすると快くお受けいただいたので、郵送にて拝受しました。
(ちなみに、筆者は宛先を書いて切手を貼り、郵送のお願い文書と御朱印用紙を同封した返信用の封筒を持ち歩いています。)


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第53番の御朱印
中央に「不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の荘厳体種子「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「豊島八十八ヶ所第五十三番」の札所印。
左上に「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判。
左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
豊島霊場御朱印との違いは「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判の有無のみです。
(第12番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 茜色の約束 - 森恵
■ 夢の大地 - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
■ 完成版です。3編に分けて再構成しました。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

「根岸古寺めぐり」の面白さに味をしめて(笑)、つぎに狙ったのが「滝野川寺院めぐり」で、2017年12月に結願しています。
平成5年7月1日開創の比較的新しい霊場なので、札所配置が整っていて容易に順打ちができます。しかも範囲が広くないので徒歩で巡拝できるのも魅力です。
ただし、一般的な認知度はほとんどなく、ある札所のお寺さんによると「滝野川寺院めぐりの御朱印を求められたのは数年ぶり」とのことでした。
宗派横断的な滝野川仏教会が開創された霊場で宗派は多彩なため、一冊の御朱印帳でまとめて集印していくとすこぶるバラエティに富んだ内容となります。
第1番 宝珠山 地蔵院 與楽寺
真言宗豊山派 北区田端1-25-1
第2番 白龍山 寿命院 東覚寺
真言宗豊山派 北区田端2-7-3
第3番 寿徳山 萬栄寺
真宗大谷派 北区田端5-7-7
第4番 教風山 普光院 大久寺
法華宗陣門流 北区田端3-21-1
第5番 薬王山 遍照寺 光明院
真言宗豊山派 北区田端3-25-5
第6番 和光山 興源院 大龍寺
真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4
第7番 光明山 照徳院 円勝寺
浄土宗 北区中里町3-1-1
第8番 平塚山 安楽院 城官寺
真言宗豊山派 北区上中里1-42-8
第9番 仏宝山 西光院 無量寺
真言宗豊山派 北区西ヶ原1-34-8
第10番 補陀山 補陀楽寿院 昌林寺
曹洞宗 北区西ケ原3-12-6
第11番 明王山 大聖寺 不動院
真言宗豊山派 北区西ヶ原3-23-2
第12番 現徳山 妙見寺
日蓮宗 北区西ヶ原2-9-5
第13番 北龍山 法音寺
真宗大谷派 北区栄町14-9
第14番 思惟山 浄業三昧寺 正受院
浄土宗 北区滝野川2-49-5
第15番 瀧河山 松橋院 金剛寺
真言宗豊山派 北区滝野川3-88-17
第16番 南照山 観音院 寿徳寺
真言宗豊山派 北区滝野川4-22-1
今回は気合いを入れて、御朱印帳は順打ちで集印してみました。
この方法がよかったのか、札所印が残っていない札所さんでも札番の揮毫をいただくなど、度々ご配慮をいただきました。

第5番光明院の御朱印と第4番大久寺の御首題
16の札所の多くは豊島八十八ヶ所などの現役霊場と重複しているので、ご住職がいらっしゃれば御朱印の拝受はさほどむずかしくはありません。ただ、豊島八十八ヶ所の札所じたいがご不在率が高いので、集印のための出直し参拝は必須かと思います。
日蓮宗と法華宗陣門流の札所がありますが、いずれも快く御首題を授与いただけました。
真宗大谷派の札所がふたつ。うちひとつは「御朱印を出されていない。」とのことでしたが、御朱印帳に参拝記念となるようなものを授与いただけました。
この真宗大谷派の札所は例外対応をいただいたかもしれず、ひょっとすると集印は15に留まる可能性もありますが、当初は2~3箇寺はいただけないものと覚悟していたので、予想以上の拝受数となりました。
札所印が16寺のうち13寺でいただけたのも想定外の収穫(?)で、あまり使われていないためか、印影はどれも綺麗です。
ガイドブックとして、滝野川仏教会が平成5年7月に発行された「滝野川寺院めぐり案内」があります。
いくつかの札所で在庫をご確認いただきましたが、いずれも在庫はなく、北区立滝野川図書館でお借りしてコピーをとりました。
このガイドによると、「『滝野川寺院めぐり』は、滝野川仏教会の会員寺院を、宗派にとらわれることなく巡拝するコースです。」「高齢化がすすむなか、心のゆとりを求める方々が増えています。豊島八十八カ所巡りや江戸六阿弥陀詣りなど、昔からすでに設けられている寺院めぐりをする方は、むしろ増加しています。今回の『滝野川寺院めぐり』は、全国に地域仏教会が沢山あるなかで、組織を巡拝コースに置きかえて、社会と寺院とのコミュニケーションを深めようとする初めての試みであると自負しております。」とあります。
たしかに、平成5年の時点で地域仏教会主導の霊場開創は、先駆的な動きだと思います。
札所は北区内を流れる石神井川に沿って、またいくつかは武蔵野台地の北縁に立地します。
このあたりの石神井川の流れは変化に富み、武蔵野台地にあがっても緑の多い住宅街がつづく風光明媚なところです。
江戸期から桜の名所として名を馳せた飛鳥山もエリア内に含みます。
札所もしっとり落ち着いたお寺さんが多く、ご不在出直し参拝も苦にならない感じがします。(おのおの駅から近いのも心理的に楽。)
これから、発願寺から16番の結願寺まで連載パターンで順繰りにご案内していきたいと思います。
---------------------------------
滝野川寺院めぐりの札所の多くは、昭和22年(1947年)3月15日 、旧 東京35区が22区に再編されたことに伴い北区に統合され消滅した旧 滝野川区域に立地します。
「滝野川」は、石神井川の別称で、このあたりの石神井川の流れが「滝の様に勢いよく」流れていたことに由来するといわれます。
当時の面影は、音無親水公園や音無さくら緑地で偲ぶことができます。
音無さくら緑地の案内看板にはつぎのように書かれています。
「石神井川は大部分が台地上を流れているため、ゆるやかな流れの区間が多いのですが、板橋区加賀から下流になると渓谷状となり、水流もかなり急になります。そのため、昔はこの一帯の石神井川は滝野川とその名を変えて呼ばれ、飛鳥山のあたりでは、この地を愛した徳川吉宗のふるさとにちなみ、音無川とさらに名を変えて呼ばれていました。ごうごうと音をたて、流れる川を音無川と呼んだところに、この地と将軍吉宗との深い関係が読み取れます。」
また、このあたりには、王子七滝(王子の七瀑)という名勝がありました。
不動の滝(正受院境内)、稲荷の滝(王子稲荷社の別当寺金輪寺境内)、名主の滝(現 名主の滝公園内)、弁天の滝(金剛寺内松橋弁天境内)、権現の滝(王子神社の別当寺金輪寺内の王子権現境内)などで、いくつかは、滝野川寺院めぐりの札所境内にありました。
江戸期から、王子飛鳥山は桜の名所、滝野川は紅葉の名所として知られ、神社仏閣参詣と併せ日帰りで楽しめる行楽地として親しまれていました。
「吉宗は『春は花、秋は紅葉』の例えにならい、飛鳥山に桜を植えさせる一方で、石神井川の両岸に紅葉を植えさせました。文化文政の頃には、滝野川の紅葉は江戸中に知られ、江戸名所図絵にも『楓樹の名所として其の名遠近に高し』と述べられています。」(音無さくら緑地の案内看板より)
その様子は、錦絵で楽しむ江戸の名所/国立国会図書館Webなどの資料でも情緒ゆたかにあらわされています。


【上(左)】 『飛鳥山』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『飛鳥山はな見』/広重(広重画帖)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
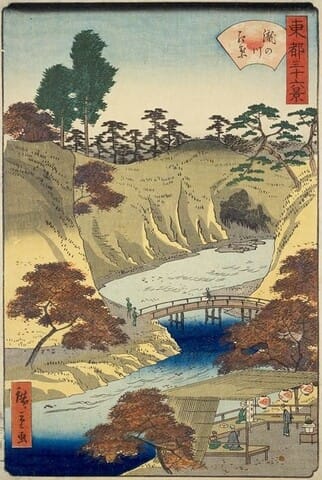

【上(左)】 『滝野川紅葉』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『王子滝の川』/広重(東都名所)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
滝野川寺院めぐりは、JR田端駅からはじまります。
田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。
ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)
この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。
芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。
第1番
宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
朱印尊格:地蔵菩薩
御府内八十八箇所第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、江戸八十八ヶ所霊場第56番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
発願の第1番は、真言宗豊山派の與楽寺です。
弘法大師の建立とも伝わり、慶安元年(1648年)に寺領20石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、寺歴は相当に古そうです。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔當寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ、翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ、是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト伝フ 開山ヲ秀榮ト云」「鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク」「阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ」「九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云」
複数の霊場の札所を兼ねておられ、とくに御府内八十八箇所と武州江戸六阿弥陀で参拝される方が多いのでは。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番の札所です。
武州江戸六阿弥陀霊場は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木・末木で刻した阿弥陀仏と聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、江戸期には女人成仏の阿弥陀仏としてあがめられ、とくに春秋の彼岸に盛んに巡拝されていたようです。(武州江戸六阿弥陀については、第10番昌林寺の記事をご参照ください。)
なお、「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
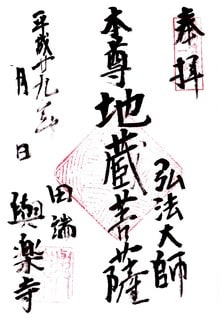
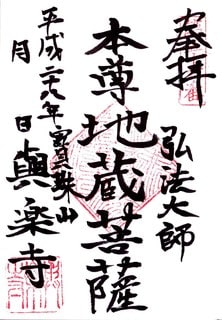
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第1番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第56番の御朱印

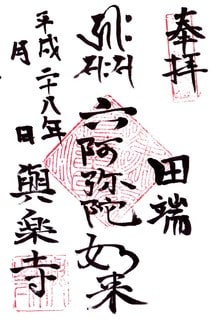
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第56番の御朱印
【下(右)】 武州江戸六阿弥陀霊場第4番の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 地蔵菩薩」の揮毫と三寶印の捺印、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第1番」の札所印。
尊格構成は御府内霊場や豊島霊場など、弘法大師霊場と同様です。
こちらに限らず、滝野川寺院めぐりの御朱印は弘法大師霊場の構成に近く、御朱印尊格は御本尊となる例が多いようです。
なお、武州江戸六阿弥陀霊場の御朱印は、中央上部に阿弥陀如来の種子(キリーク)、右に聖観世音菩薩の種子(サ)、左に勢至菩薩の種子(サク)が揮毫された阿弥陀三尊様式で、この霊場の御朱印で複数みられるものです。
第2番
白龍山 寿命院 東覚寺
北区田端2-7-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
朱印尊格:不動明王
御府内八十八箇所第66番、豊島八十八ヶ所第66番、江戸・東京四十四閻魔参り第35番、谷中七福神(福禄寿)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第29番、江戸八十八ヶ所霊場第66番、九品仏霊場第2番(上品中生)、閻魔三拾遺第5番
第2番は、真言宗豊山派の東覚寺です。
第1番與楽寺からほどなく東覚寺に到着です。
複数の霊場札所を兼ね、「赤紙仁王尊」でも知られる寺院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「與楽寺末白龍山壽命院ト号ス 寺領七石の御朱印ヲ附セラル 本尊不動ハ弘法大師の作ナリ」
延徳三年(1491年)源雅和尚が神田筋違橋(現在の万世橋付近)に創建。その後根岸御印田を経て、慶長の初め(1600年頃)にこの地に移転したと伝わります。


【写真 上(左)】 赤紙仁王尊と明王堂
【写真 下(右)】 奉納された草鞋
区画整理が進んだ広々とした街区に、赤紙を貼られた赤紙仁王尊の出現はインパクトがあります。
この赤紙仁王尊(区の指定文化財)は寛永十八年(1641年)の背銘があり、当時江戸市中に流行していた疫病を鎮めるため宋海上人が願主建立されたもので、赤紙を自分の患部と同じところに貼って願をかけると霊験ありと信じられ、いまもたくさんの赤紙が貼られています。
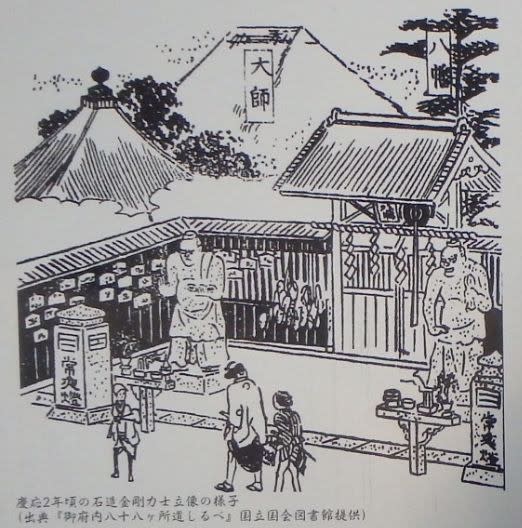
【絵図】 慶応2年頃の石像金剛力士像の様子(北区教育委員会の現地説明板より/出典『御府内八十八ヶ所道しるべ』/国立国会図書館提供)
ときどき赤紙を剥がすそうですが、剥がす前のタイミングだと石造の仁王尊は赤紙に貼り尽くされほとんどお姿が見えません。
病が治癒すると草履を供えるとされ、仁王尊の脇にはたくさんの草履が奉納されています。
この赤紙仁王尊は門前の明王堂(護摩堂)参道に御座しますが、もともとは当寺が別当を務めた田端八幡神社の参道に安置されていたと伝わります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は新しいですが本瓦葺、二軒の平行垂木を備えた立派なものでおそらく薬医門。
正面本堂左手前の修行大師像と金色の金剛界大日如来坐像、向拝欄干には御本尊不動明王の御真言とお大師様の御寶号が掲げられ、保守本流の真言宗寺院の空気感。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「白龍山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 札所標
本堂左手客殿前には金色の阿弥陀如来坐像、その奥に「九品佛第二番 阿弥陀如来」と西國廿九番(上野王子駒込辺三十三観音霊場、札所本尊馬頭観世音菩薩)の札所標が並びます。
九品佛霊場は江戸時代開創の古い霊場で発願は巣鴨の真性寺、結願は板橋の智清寺。東覚寺は第2番で上品中生の阿弥陀如来です。
両霊場ともに御朱印の有無をお伺いしましたが、いずれもお出しになられていないとのことでした。


【写真 上(左)】 鼓翼(はばたき)平和観音像
【写真 下(右)】 馬頭観世音
庫裡に回り込む手前に、鼓翼(はばたき)平和観音像と馬頭観世音菩薩が御座します。
馬頭観世音菩薩は三面八臂の坐像で、髻に馬頭をいだかれた憤怒相です。
馬頭観世音菩薩は観世音菩薩にはめずらしい憤怒尊で、「馬頭明王」と呼ばれることもあります。
この立派な馬頭観世音菩薩は、上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所本尊なのかもしれません。
本堂裏には回遊式の庭園があり、庭内に諸仏が安置されています。
- むらすずめ さわくち声も もも声も つるの林の つるの一声 -
太田蜀山人 / 雀塚の石塔
こちらは江戸・東京四十四閻魔参り第35番の札所で、御縁日に参拝したところ閻魔大王の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印をいただきました。
閻魔大王は奪衣婆とともに、本堂内に御座されているそうです。
また、歴史ある谷中七福神の福禄寿尊天をお祀りされます。
この福禄寿尊天は、もとは通称「六角山」にあった六角堂(西行庵)に西行法師坐像とともに祀られていたもので、明治に入って当寺に遷座されました。
毎年正月には本堂で御開帳されています。
御朱印は、向かって左裏手の寺務所で拝受します。
こちらも御府内霊場や谷中七福神などメジャー霊場の札所となっているので、揮毫いただけることが多そう。
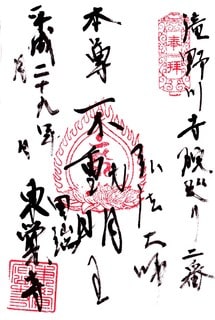

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第2番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第66番の御朱印

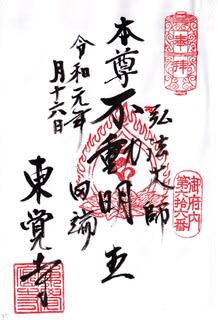
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第66番の御朱印
【下(右)】 閻魔様の御縁日に拝受した御本尊の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 不動明王」の揮毫と種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、「滝野川寺院めぐり 第2番」の札所印はお持ちでないとのことでしたが、ご厚意で揮毫の札番をいただけました。ありがとうございました。
尊格構成は、札所印をのぞいて御府内霊場や豊島霊場などの弘法大師霊場と同様です。
なお、東覚寺が別当を務めていた田端八幡神社(北区田端2-7-2、お隣り)でも御朱印を授与されています。

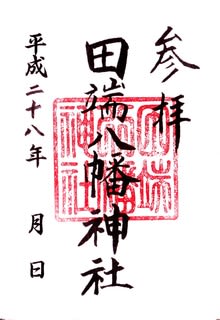
【写真 上(左)】 田端八幡神社拝殿
【下(右)】 田端八幡神社の御朱印
第3番
寿徳山 萬榮寺
北区田端5-7-7
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:不可思議光如来


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 寺号標
第3番は、真宗大谷派の萬榮寺です。
この霊場は第3番、第4番に至って一気にマニアック度(?)が高まりますが、これは宗派によるところが大きいと思います。
第3番は真宗大谷派、第4番は法華宗陣門流で、いずれも霊場札所としての例は多くはありません。とくに真宗大谷派、法華宗陣門流とつづく霊場はほとんど例がないのでは。
宗派を超えた、地域仏教界開創の霊場ならではの札所展開といえましょう。
真宗は教義的に御朱印を授与されない寺院が多く(名刹で参拝記念的なスタンプはけっこう出されている)、この宗派の檀家寺に御朱印授与のお願いをすることはいつもは避けますが、霊場札所となると話は別です。
三浦二十八不動尊霊場、三浦二十一ヶ所薬師霊場、行徳・浦安三十三観音霊場、甲斐百八霊場などで真宗寺院が札所となっている例があり、実際、これまでに御朱印を拝受しています。
萬榮寺は、新潟県西蒲原郡中之口村六分の円明寺他4箇寺の東京在住の壇信徒をまとめるために設立された真宗大谷派萬榮教会が前身の、真宗大谷派の寺院です。
こじんまりとした境内。
本堂は近代建築で様式はよくわかりませんが、葡萄茶色の柱と梁が印象的な二層の建物で、上層の屋根妻部には鬼板と猪ノ目懸魚を備えています。
御本尊の阿弥陀如来立像は寄木造で、衣部に金箔、48本の光背を備えられ、江戸時代後期の作といわれています。
御朱印授与は、ベルを鳴らしてのお願いとなります。
こちらは以前お伺いしたときはご不在、今回もお取り込み中のようでしたが快く授与をいただけました。

● 滝野川寺院めぐり第3番の御朱印
御朱印は中央に「南無不可思議光如来」の揮毫と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第三番寺」の札所印。
真宗の「正信偈」に「南無不可思議光」とあり、「不可思議光」は阿弥陀仏の「智慧」をあらわすそうですから、尊格としては阿弥陀(無量光)如来で、真宗ならではの御朱印(?)のようにも思えます。
第4番
教風山 普光院 大久寺
北区田端3-21-1
法華宗陣門流
朱印尊格:御首題
第4番は、法華宗陣門流の大久寺です。
日蓮聖人を開祖(宗祖・高祖)とし、妙法蓮華経を依拠教典とする宗旨(広義の法華宗)には多くの流れ(門流)があり、その差異を理解するのは甚だ困難ですが、大きくは「所依の妙法蓮華経を構成する二十八品前半の『迹門』、後半の『本門』の関係解釈」、「釈迦をもって本仏とするか、日蓮聖人をもって本仏とするか」により分流しているようです。
前者で「一致派」と「勝劣派」に分かれ、法華宗陣門流は「勝劣派」の、日陣門流(本成寺派)の流れになるものとみられます。
((広義の)法華宗は総じて教義解釈に厳格で、これにより細かく門流が分かれているので、素人が表面的に理解するのは不可能かと思います。)
「勝劣派」には原則御首題を授与されない門流もあるようですが、法華宗陣門流と法華宗本門流は比較的授与例が多いように思われます。
文禄元年(1592年)大久保相模守忠世が一族の菩提を弔うため、越後の名僧・日英上人を招聘、開祖として小田原に創建され、寛永七年(1630年)江戸下谷車坂に移転の後、明治三十六年(1903年)に当地に移転したとされます。
大久保家との所縁がふかく、「おおくぼでら」とも呼ばれているようです。
伊勢亀山藩石川家に養子となっていた忠隣の二男忠総の流れで、石川家の菩提寺でもあります。
また、大正三年(1914年)に田端の上台寺を合併しています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
さほど広くはないものの、緑が多く手入れの行き届いた境内。
正面に昭和34年(1959年)建立の本堂。入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟、隅棟、稚児棟、掛瓦のバランスがよく、整った印象の建物です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
水引虹梁両端に禅宗様の雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「教風山」の扁額。向拝両脇に花頭窓、小壁の欄間に菱格子と、向拝まわりもきっちり整った印象です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内
境内には、昔日参拝者を集めた日蓮聖人の伊豆法難の際の「腰掛石」がいまも残ります。
こちらは以前にも御首題をいただいておりますが、そのときも今回もたいへん丁重なご対応をいただきました。
ただし、札所の場合も尊格は御首題なので、ご住職ご不在時は出直し参拝になろうかと思われます。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第4番の御首題
【下(右)】 御首題
御首題は、中央にお題目と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と宗派+寺院の印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第四番寺」の札所印が捺されています。
こちらは以前にも御首題を拝受していますが、そのときは御首題をお願いしたので札所印の捺印はありません。
第5番
薬王山 遍照寺 光明院
北区田端3-25-5
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第9番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第20番
第5番は、霊場札所の保守本流、真言宗豊山派の光明院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「同宗西ヶ原村無量寺末薬王山遍照寺ト号ス本尊大日 薬師堂 聖徳太子ノ作ノ薬師ヲ置ク立像長一尺五寸 観音堂」
天正十九年(1591年)の検地水帳に白髭神社の別当として「光明院」の名があり、創建はそれ以前と推定されますが詳細は不明。
寺伝は寛文四年(1664年)、朝海法印による再建を伝えます。
古くは医王山、白髭山の山号を号し無量寺の末寺でした。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
閑静な住宅街にあるこのお寺さんは光明院幼稚園を併設されていて、平日昼間の境内は園児たちが元気に遊びまわり、当然のことながら門扉は固く閉ざされています。
1回目、豊島霊場の参拝でお伺いしたときは時間が遅く、園児や親御さんもおおむね帰宅して落ち着いていましたが、2回目、滝野川霊場の参拝時はちょうど帰宅時で境内は園児と母親達で大盛況。ここに男性1人で踏み込むのは相当気合い?が要りそうですが、このときは連れ同伴だったので大手を振っての?参拝です。
(じつはこの日、2人併せて平日休をとり、昼過ぎに東京国立博物館の運慶展に赴いたのですが、あまりの大混雑に嫌気がさし、一旦滝野川霊場の参拝に回り、少しく空いてきた夕刻から突入したのでした。)
参道は幼稚園側にありますが、高麗門の格子戸は閉まっていて入れません。
本堂側に回り込むと開き戸(幼稚園出入口)があり、門脇のインターフォンから参拝の許可をいただきます。
いずれも通用門そばに先生がおられたので、お声掛けすると快く本堂(庫裡)にご案内いただけました。(3回目は、たしかインターフォンを鳴らしたかと思います。)
3度ともご住職、大黒さんにお会いできましたが、温厚で上品なお人柄のように感じられました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 左手からの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
昭和50年(1975年)再建の本堂はコンクリ造で寄棟造銅板葺流れ向拝。
コンクリ造のためか向拝柱はなし。細部の意匠が効いていて、コンクリ造のお堂にありがちな無機質感はありません。
ただし、かなり離れたところに柵があり賽銭箱もないので、お参りはいささかしにくいです。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内の西國第20番を示す札所碑
1回目、豊島霊場のときはスムーズに御朱印を拝受できましたが(最近、豊島霊場の巡拝者が増えている模様)、2回目に滝野川寺院めぐりの御朱印を申告すると、いささか驚かれたご様子でした。
やはり、滝野川寺院めぐりの参拝者はすこぶる少ないそうです。
3回目、上野王子駒込辺三十三観音霊場に至っては、大黒さんは??モードでしたが、「西國20番」と言い直すと合点がいかれたらしく、無事、ご住職から御朱印を拝受できました。
本堂手前の観音様(札所碑あり)が札所本尊ではないか、との由でした。
上野王子駒込辺三十三観音霊場じたいが正式名称ではなく(東都歳時記に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」とある)、御朱印授与の札所も少ないですが、北区のある札所寺院様によると、最近、この霊場で申告されるケースが増えている感じがする、との由。
御府内、豊島などのメジャー霊場には参画されていない寺院も複数含まれているので、復活があるとうれしいです。(廃寺が複数ありますが・・・)
↑の札所印や、谷中の長安寺(第22番)で本堂扁額横に「西國三十三ヶ所寫」の札所板が掲げられていることなどから、「西國三十三ヶ所寫(観音)参り」とされていた可能性があります。
また、府内七薬師霊場第2番札所との情報がありますが、この霊場じたい調べがついておらず、現在のところ詳細不明です。(東都七仏薬師とは異なるようです。)

● 滝野川寺院めぐり第5番の御朱印
中央に「大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に院号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第五番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印をのぞいて豊島霊場と同様です。


【上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場第9番の御朱印
【下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音(西國写)霊場第20番の御朱印
第6番
和光山 興源院 大龍寺
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第21番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第17番、御府内八十八箇所第13番(不詳)
第6番は、真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ、天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置 八幡社 村ノ鎮守トス 稲荷社」
創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興し、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂露天
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れた対応です。
滝野川寺院めぐりの御朱印についても、特段驚かれた風はありませんでした。
こちらはWeb上で、「弘法大師第13番」の札所印(揮毫)の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
近年メジャー霊場化している御府内八十八箇所は、番外等の札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院がリストされています。
御府内第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺で、龍生院に引き継がれたとされていて、大龍寺との関連は不詳です。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
なお、真言宗霊雲寺派総本山の霊雲寺は、御府内八十八箇所の第28番の札所となっています。
真言宗霊雲寺派は東都を拠点とする宗派で、その霊雲寺派が江戸の弘法大師霊場である御府内八十八箇所の一画を占めているのは、頷けるものがあります。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第6番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第21番の御朱印
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に寺号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第六番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印と種子「ア」の様式が豊島霊場とは異なります。
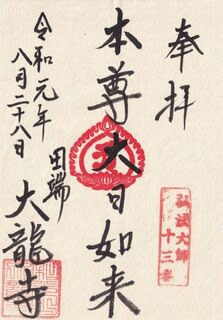
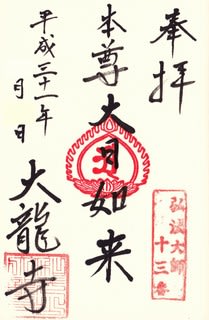
【上(左)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(御朱印帳)
(第7番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ I Will Be There with You ~日本語版~ - 杏里
■ 空に近い週末 - 今井美樹
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

「根岸古寺めぐり」の面白さに味をしめて(笑)、つぎに狙ったのが「滝野川寺院めぐり」で、2017年12月に結願しています。
平成5年7月1日開創の比較的新しい霊場なので、札所配置が整っていて容易に順打ちができます。しかも範囲が広くないので徒歩で巡拝できるのも魅力です。
ただし、一般的な認知度はほとんどなく、ある札所のお寺さんによると「滝野川寺院めぐりの御朱印を求められたのは数年ぶり」とのことでした。
宗派横断的な滝野川仏教会が開創された霊場で宗派は多彩なため、一冊の御朱印帳でまとめて集印していくとすこぶるバラエティに富んだ内容となります。
第1番 宝珠山 地蔵院 與楽寺
真言宗豊山派 北区田端1-25-1
第2番 白龍山 寿命院 東覚寺
真言宗豊山派 北区田端2-7-3
第3番 寿徳山 萬栄寺
真宗大谷派 北区田端5-7-7
第4番 教風山 普光院 大久寺
法華宗陣門流 北区田端3-21-1
第5番 薬王山 遍照寺 光明院
真言宗豊山派 北区田端3-25-5
第6番 和光山 興源院 大龍寺
真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4
第7番 光明山 照徳院 円勝寺
浄土宗 北区中里町3-1-1
第8番 平塚山 安楽院 城官寺
真言宗豊山派 北区上中里1-42-8
第9番 仏宝山 西光院 無量寺
真言宗豊山派 北区西ヶ原1-34-8
第10番 補陀山 補陀楽寿院 昌林寺
曹洞宗 北区西ケ原3-12-6
第11番 明王山 大聖寺 不動院
真言宗豊山派 北区西ヶ原3-23-2
第12番 現徳山 妙見寺
日蓮宗 北区西ヶ原2-9-5
第13番 北龍山 法音寺
真宗大谷派 北区栄町14-9
第14番 思惟山 浄業三昧寺 正受院
浄土宗 北区滝野川2-49-5
第15番 瀧河山 松橋院 金剛寺
真言宗豊山派 北区滝野川3-88-17
第16番 南照山 観音院 寿徳寺
真言宗豊山派 北区滝野川4-22-1
今回は気合いを入れて、御朱印帳は順打ちで集印してみました。
この方法がよかったのか、札所印が残っていない札所さんでも札番の揮毫をいただくなど、度々ご配慮をいただきました。

第5番光明院の御朱印と第4番大久寺の御首題
16の札所の多くは豊島八十八ヶ所などの現役霊場と重複しているので、ご住職がいらっしゃれば御朱印の拝受はさほどむずかしくはありません。ただ、豊島八十八ヶ所の札所じたいがご不在率が高いので、集印のための出直し参拝は必須かと思います。
日蓮宗と法華宗陣門流の札所がありますが、いずれも快く御首題を授与いただけました。
真宗大谷派の札所がふたつ。うちひとつは「御朱印を出されていない。」とのことでしたが、御朱印帳に参拝記念となるようなものを授与いただけました。
この真宗大谷派の札所は例外対応をいただいたかもしれず、ひょっとすると集印は15に留まる可能性もありますが、当初は2~3箇寺はいただけないものと覚悟していたので、予想以上の拝受数となりました。
札所印が16寺のうち13寺でいただけたのも想定外の収穫(?)で、あまり使われていないためか、印影はどれも綺麗です。
ガイドブックとして、滝野川仏教会が平成5年7月に発行された「滝野川寺院めぐり案内」があります。
いくつかの札所で在庫をご確認いただきましたが、いずれも在庫はなく、北区立滝野川図書館でお借りしてコピーをとりました。
このガイドによると、「『滝野川寺院めぐり』は、滝野川仏教会の会員寺院を、宗派にとらわれることなく巡拝するコースです。」「高齢化がすすむなか、心のゆとりを求める方々が増えています。豊島八十八カ所巡りや江戸六阿弥陀詣りなど、昔からすでに設けられている寺院めぐりをする方は、むしろ増加しています。今回の『滝野川寺院めぐり』は、全国に地域仏教会が沢山あるなかで、組織を巡拝コースに置きかえて、社会と寺院とのコミュニケーションを深めようとする初めての試みであると自負しております。」とあります。
たしかに、平成5年の時点で地域仏教会主導の霊場開創は、先駆的な動きだと思います。
札所は北区内を流れる石神井川に沿って、またいくつかは武蔵野台地の北縁に立地します。
このあたりの石神井川の流れは変化に富み、武蔵野台地にあがっても緑の多い住宅街がつづく風光明媚なところです。
江戸期から桜の名所として名を馳せた飛鳥山もエリア内に含みます。
札所もしっとり落ち着いたお寺さんが多く、ご不在出直し参拝も苦にならない感じがします。(おのおの駅から近いのも心理的に楽。)
これから、発願寺から16番の結願寺まで連載パターンで順繰りにご案内していきたいと思います。
---------------------------------
滝野川寺院めぐりの札所の多くは、昭和22年(1947年)3月15日 、旧 東京35区が22区に再編されたことに伴い北区に統合され消滅した旧 滝野川区域に立地します。
「滝野川」は、石神井川の別称で、このあたりの石神井川の流れが「滝の様に勢いよく」流れていたことに由来するといわれます。
当時の面影は、音無親水公園や音無さくら緑地で偲ぶことができます。
音無さくら緑地の案内看板にはつぎのように書かれています。
「石神井川は大部分が台地上を流れているため、ゆるやかな流れの区間が多いのですが、板橋区加賀から下流になると渓谷状となり、水流もかなり急になります。そのため、昔はこの一帯の石神井川は滝野川とその名を変えて呼ばれ、飛鳥山のあたりでは、この地を愛した徳川吉宗のふるさとにちなみ、音無川とさらに名を変えて呼ばれていました。ごうごうと音をたて、流れる川を音無川と呼んだところに、この地と将軍吉宗との深い関係が読み取れます。」
また、このあたりには、王子七滝(王子の七瀑)という名勝がありました。
不動の滝(正受院境内)、稲荷の滝(王子稲荷社の別当寺金輪寺境内)、名主の滝(現 名主の滝公園内)、弁天の滝(金剛寺内松橋弁天境内)、権現の滝(王子神社の別当寺金輪寺内の王子権現境内)などで、いくつかは、滝野川寺院めぐりの札所境内にありました。
江戸期から、王子飛鳥山は桜の名所、滝野川は紅葉の名所として知られ、神社仏閣参詣と併せ日帰りで楽しめる行楽地として親しまれていました。
「吉宗は『春は花、秋は紅葉』の例えにならい、飛鳥山に桜を植えさせる一方で、石神井川の両岸に紅葉を植えさせました。文化文政の頃には、滝野川の紅葉は江戸中に知られ、江戸名所図絵にも『楓樹の名所として其の名遠近に高し』と述べられています。」(音無さくら緑地の案内看板より)
その様子は、錦絵で楽しむ江戸の名所/国立国会図書館Webなどの資料でも情緒ゆたかにあらわされています。


【上(左)】 『飛鳥山』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『飛鳥山はな見』/広重(広重画帖)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
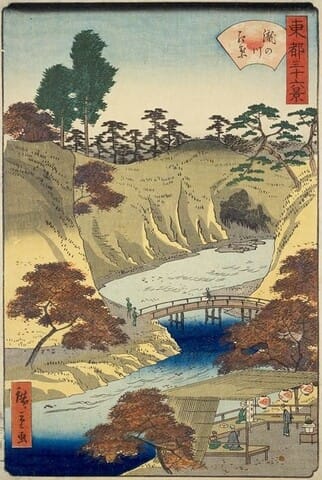

【上(左)】 『滝野川紅葉』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『王子滝の川』/広重(東都名所)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
滝野川寺院めぐりは、JR田端駅からはじまります。
田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。
ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)
この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。
芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。
第1番
宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
朱印尊格:地蔵菩薩
御府内八十八箇所第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、江戸八十八ヶ所霊場第56番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
発願の第1番は、真言宗豊山派の與楽寺です。
弘法大師の建立とも伝わり、慶安元年(1648年)に寺領20石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、寺歴は相当に古そうです。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔當寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ、翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ、是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト伝フ 開山ヲ秀榮ト云」「鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク」「阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ」「九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云」
複数の霊場の札所を兼ねておられ、とくに御府内八十八箇所と武州江戸六阿弥陀で参拝される方が多いのでは。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番の札所です。
武州江戸六阿弥陀霊場は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木・末木で刻した阿弥陀仏と聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、江戸期には女人成仏の阿弥陀仏としてあがめられ、とくに春秋の彼岸に盛んに巡拝されていたようです。(武州江戸六阿弥陀については、第10番昌林寺の記事をご参照ください。)
なお、「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
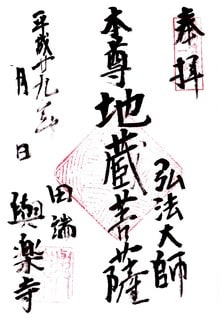
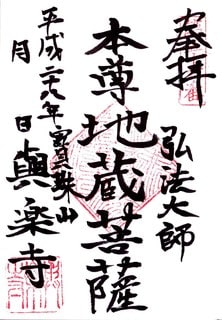
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第1番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第56番の御朱印

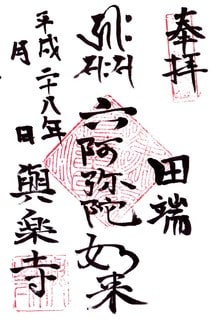
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第56番の御朱印
【下(右)】 武州江戸六阿弥陀霊場第4番の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 地蔵菩薩」の揮毫と三寶印の捺印、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第1番」の札所印。
尊格構成は御府内霊場や豊島霊場など、弘法大師霊場と同様です。
こちらに限らず、滝野川寺院めぐりの御朱印は弘法大師霊場の構成に近く、御朱印尊格は御本尊となる例が多いようです。
なお、武州江戸六阿弥陀霊場の御朱印は、中央上部に阿弥陀如来の種子(キリーク)、右に聖観世音菩薩の種子(サ)、左に勢至菩薩の種子(サク)が揮毫された阿弥陀三尊様式で、この霊場の御朱印で複数みられるものです。
第2番
白龍山 寿命院 東覚寺
北区田端2-7-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
朱印尊格:不動明王
御府内八十八箇所第66番、豊島八十八ヶ所第66番、江戸・東京四十四閻魔参り第35番、谷中七福神(福禄寿)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第29番、江戸八十八ヶ所霊場第66番、九品仏霊場第2番(上品中生)、閻魔三拾遺第5番
第2番は、真言宗豊山派の東覚寺です。
第1番與楽寺からほどなく東覚寺に到着です。
複数の霊場札所を兼ね、「赤紙仁王尊」でも知られる寺院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「與楽寺末白龍山壽命院ト号ス 寺領七石の御朱印ヲ附セラル 本尊不動ハ弘法大師の作ナリ」
延徳三年(1491年)源雅和尚が神田筋違橋(現在の万世橋付近)に創建。その後根岸御印田を経て、慶長の初め(1600年頃)にこの地に移転したと伝わります。


【写真 上(左)】 赤紙仁王尊と明王堂
【写真 下(右)】 奉納された草鞋
区画整理が進んだ広々とした街区に、赤紙を貼られた赤紙仁王尊の出現はインパクトがあります。
この赤紙仁王尊(区の指定文化財)は寛永十八年(1641年)の背銘があり、当時江戸市中に流行していた疫病を鎮めるため宋海上人が願主建立されたもので、赤紙を自分の患部と同じところに貼って願をかけると霊験ありと信じられ、いまもたくさんの赤紙が貼られています。
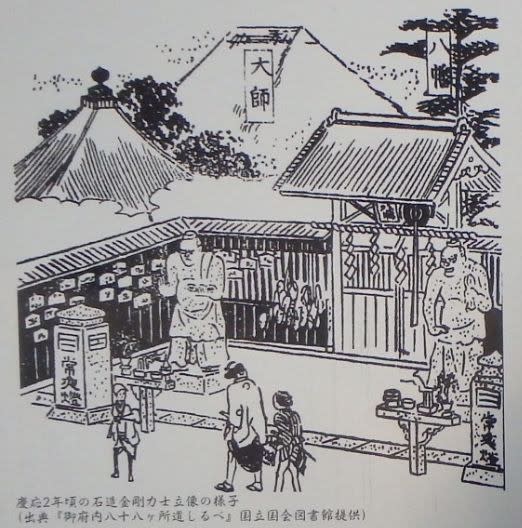
【絵図】 慶応2年頃の石像金剛力士像の様子(北区教育委員会の現地説明板より/出典『御府内八十八ヶ所道しるべ』/国立国会図書館提供)
ときどき赤紙を剥がすそうですが、剥がす前のタイミングだと石造の仁王尊は赤紙に貼り尽くされほとんどお姿が見えません。
病が治癒すると草履を供えるとされ、仁王尊の脇にはたくさんの草履が奉納されています。
この赤紙仁王尊は門前の明王堂(護摩堂)参道に御座しますが、もともとは当寺が別当を務めた田端八幡神社の参道に安置されていたと伝わります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は新しいですが本瓦葺、二軒の平行垂木を備えた立派なものでおそらく薬医門。
正面本堂左手前の修行大師像と金色の金剛界大日如来坐像、向拝欄干には御本尊不動明王の御真言とお大師様の御寶号が掲げられ、保守本流の真言宗寺院の空気感。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「白龍山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 札所標
本堂左手客殿前には金色の阿弥陀如来坐像、その奥に「九品佛第二番 阿弥陀如来」と西國廿九番(上野王子駒込辺三十三観音霊場、札所本尊馬頭観世音菩薩)の札所標が並びます。
九品佛霊場は江戸時代開創の古い霊場で発願は巣鴨の真性寺、結願は板橋の智清寺。東覚寺は第2番で上品中生の阿弥陀如来です。
両霊場ともに御朱印の有無をお伺いしましたが、いずれもお出しになられていないとのことでした。


【写真 上(左)】 鼓翼(はばたき)平和観音像
【写真 下(右)】 馬頭観世音
庫裡に回り込む手前に、鼓翼(はばたき)平和観音像と馬頭観世音菩薩が御座します。
馬頭観世音菩薩は三面八臂の坐像で、髻に馬頭をいだかれた憤怒相です。
馬頭観世音菩薩は観世音菩薩にはめずらしい憤怒尊で、「馬頭明王」と呼ばれることもあります。
この立派な馬頭観世音菩薩は、上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所本尊なのかもしれません。
本堂裏には回遊式の庭園があり、庭内に諸仏が安置されています。
- むらすずめ さわくち声も もも声も つるの林の つるの一声 -
太田蜀山人 / 雀塚の石塔
こちらは江戸・東京四十四閻魔参り第35番の札所で、御縁日に参拝したところ閻魔大王の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印をいただきました。
閻魔大王は奪衣婆とともに、本堂内に御座されているそうです。
また、歴史ある谷中七福神の福禄寿尊天をお祀りされます。
この福禄寿尊天は、もとは通称「六角山」にあった六角堂(西行庵)に西行法師坐像とともに祀られていたもので、明治に入って当寺に遷座されました。
毎年正月には本堂で御開帳されています。
御朱印は、向かって左裏手の寺務所で拝受します。
こちらも御府内霊場や谷中七福神などメジャー霊場の札所となっているので、揮毫いただけることが多そう。
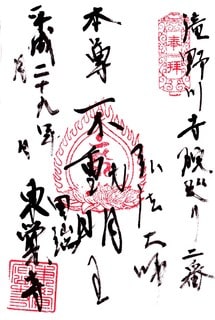

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第2番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第66番の御朱印

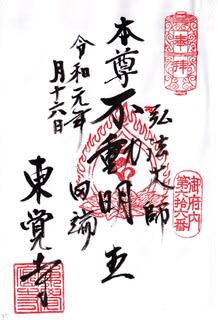
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第66番の御朱印
【下(右)】 閻魔様の御縁日に拝受した御本尊の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 不動明王」の揮毫と種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、「滝野川寺院めぐり 第2番」の札所印はお持ちでないとのことでしたが、ご厚意で揮毫の札番をいただけました。ありがとうございました。
尊格構成は、札所印をのぞいて御府内霊場や豊島霊場などの弘法大師霊場と同様です。
なお、東覚寺が別当を務めていた田端八幡神社(北区田端2-7-2、お隣り)でも御朱印を授与されています。

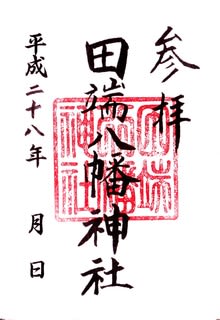
【写真 上(左)】 田端八幡神社拝殿
【下(右)】 田端八幡神社の御朱印
第3番
寿徳山 萬榮寺
北区田端5-7-7
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:不可思議光如来


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 寺号標
第3番は、真宗大谷派の萬榮寺です。
この霊場は第3番、第4番に至って一気にマニアック度(?)が高まりますが、これは宗派によるところが大きいと思います。
第3番は真宗大谷派、第4番は法華宗陣門流で、いずれも霊場札所としての例は多くはありません。とくに真宗大谷派、法華宗陣門流とつづく霊場はほとんど例がないのでは。
宗派を超えた、地域仏教界開創の霊場ならではの札所展開といえましょう。
真宗は教義的に御朱印を授与されない寺院が多く(名刹で参拝記念的なスタンプはけっこう出されている)、この宗派の檀家寺に御朱印授与のお願いをすることはいつもは避けますが、霊場札所となると話は別です。
三浦二十八不動尊霊場、三浦二十一ヶ所薬師霊場、行徳・浦安三十三観音霊場、甲斐百八霊場などで真宗寺院が札所となっている例があり、実際、これまでに御朱印を拝受しています。
萬榮寺は、新潟県西蒲原郡中之口村六分の円明寺他4箇寺の東京在住の壇信徒をまとめるために設立された真宗大谷派萬榮教会が前身の、真宗大谷派の寺院です。
こじんまりとした境内。
本堂は近代建築で様式はよくわかりませんが、葡萄茶色の柱と梁が印象的な二層の建物で、上層の屋根妻部には鬼板と猪ノ目懸魚を備えています。
御本尊の阿弥陀如来立像は寄木造で、衣部に金箔、48本の光背を備えられ、江戸時代後期の作といわれています。
御朱印授与は、ベルを鳴らしてのお願いとなります。
こちらは以前お伺いしたときはご不在、今回もお取り込み中のようでしたが快く授与をいただけました。

● 滝野川寺院めぐり第3番の御朱印
御朱印は中央に「南無不可思議光如来」の揮毫と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第三番寺」の札所印。
真宗の「正信偈」に「南無不可思議光」とあり、「不可思議光」は阿弥陀仏の「智慧」をあらわすそうですから、尊格としては阿弥陀(無量光)如来で、真宗ならではの御朱印(?)のようにも思えます。
第4番
教風山 普光院 大久寺
北区田端3-21-1
法華宗陣門流
朱印尊格:御首題
第4番は、法華宗陣門流の大久寺です。
日蓮聖人を開祖(宗祖・高祖)とし、妙法蓮華経を依拠教典とする宗旨(広義の法華宗)には多くの流れ(門流)があり、その差異を理解するのは甚だ困難ですが、大きくは「所依の妙法蓮華経を構成する二十八品前半の『迹門』、後半の『本門』の関係解釈」、「釈迦をもって本仏とするか、日蓮聖人をもって本仏とするか」により分流しているようです。
前者で「一致派」と「勝劣派」に分かれ、法華宗陣門流は「勝劣派」の、日陣門流(本成寺派)の流れになるものとみられます。
((広義の)法華宗は総じて教義解釈に厳格で、これにより細かく門流が分かれているので、素人が表面的に理解するのは不可能かと思います。)
「勝劣派」には原則御首題を授与されない門流もあるようですが、法華宗陣門流と法華宗本門流は比較的授与例が多いように思われます。
文禄元年(1592年)大久保相模守忠世が一族の菩提を弔うため、越後の名僧・日英上人を招聘、開祖として小田原に創建され、寛永七年(1630年)江戸下谷車坂に移転の後、明治三十六年(1903年)に当地に移転したとされます。
大久保家との所縁がふかく、「おおくぼでら」とも呼ばれているようです。
伊勢亀山藩石川家に養子となっていた忠隣の二男忠総の流れで、石川家の菩提寺でもあります。
また、大正三年(1914年)に田端の上台寺を合併しています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
さほど広くはないものの、緑が多く手入れの行き届いた境内。
正面に昭和34年(1959年)建立の本堂。入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟、隅棟、稚児棟、掛瓦のバランスがよく、整った印象の建物です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
水引虹梁両端に禅宗様の雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「教風山」の扁額。向拝両脇に花頭窓、小壁の欄間に菱格子と、向拝まわりもきっちり整った印象です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内
境内には、昔日参拝者を集めた日蓮聖人の伊豆法難の際の「腰掛石」がいまも残ります。
こちらは以前にも御首題をいただいておりますが、そのときも今回もたいへん丁重なご対応をいただきました。
ただし、札所の場合も尊格は御首題なので、ご住職ご不在時は出直し参拝になろうかと思われます。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第4番の御首題
【下(右)】 御首題
御首題は、中央にお題目と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と宗派+寺院の印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第四番寺」の札所印が捺されています。
こちらは以前にも御首題を拝受していますが、そのときは御首題をお願いしたので札所印の捺印はありません。
第5番
薬王山 遍照寺 光明院
北区田端3-25-5
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第9番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第20番
第5番は、霊場札所の保守本流、真言宗豊山派の光明院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「同宗西ヶ原村無量寺末薬王山遍照寺ト号ス本尊大日 薬師堂 聖徳太子ノ作ノ薬師ヲ置ク立像長一尺五寸 観音堂」
天正十九年(1591年)の検地水帳に白髭神社の別当として「光明院」の名があり、創建はそれ以前と推定されますが詳細は不明。
寺伝は寛文四年(1664年)、朝海法印による再建を伝えます。
古くは医王山、白髭山の山号を号し無量寺の末寺でした。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
閑静な住宅街にあるこのお寺さんは光明院幼稚園を併設されていて、平日昼間の境内は園児たちが元気に遊びまわり、当然のことながら門扉は固く閉ざされています。
1回目、豊島霊場の参拝でお伺いしたときは時間が遅く、園児や親御さんもおおむね帰宅して落ち着いていましたが、2回目、滝野川霊場の参拝時はちょうど帰宅時で境内は園児と母親達で大盛況。ここに男性1人で踏み込むのは相当気合い?が要りそうですが、このときは連れ同伴だったので大手を振っての?参拝です。
(じつはこの日、2人併せて平日休をとり、昼過ぎに東京国立博物館の運慶展に赴いたのですが、あまりの大混雑に嫌気がさし、一旦滝野川霊場の参拝に回り、少しく空いてきた夕刻から突入したのでした。)
参道は幼稚園側にありますが、高麗門の格子戸は閉まっていて入れません。
本堂側に回り込むと開き戸(幼稚園出入口)があり、門脇のインターフォンから参拝の許可をいただきます。
いずれも通用門そばに先生がおられたので、お声掛けすると快く本堂(庫裡)にご案内いただけました。(3回目は、たしかインターフォンを鳴らしたかと思います。)
3度ともご住職、大黒さんにお会いできましたが、温厚で上品なお人柄のように感じられました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 左手からの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
昭和50年(1975年)再建の本堂はコンクリ造で寄棟造銅板葺流れ向拝。
コンクリ造のためか向拝柱はなし。細部の意匠が効いていて、コンクリ造のお堂にありがちな無機質感はありません。
ただし、かなり離れたところに柵があり賽銭箱もないので、お参りはいささかしにくいです。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内の西國第20番を示す札所碑
1回目、豊島霊場のときはスムーズに御朱印を拝受できましたが(最近、豊島霊場の巡拝者が増えている模様)、2回目に滝野川寺院めぐりの御朱印を申告すると、いささか驚かれたご様子でした。
やはり、滝野川寺院めぐりの参拝者はすこぶる少ないそうです。
3回目、上野王子駒込辺三十三観音霊場に至っては、大黒さんは??モードでしたが、「西國20番」と言い直すと合点がいかれたらしく、無事、ご住職から御朱印を拝受できました。
本堂手前の観音様(札所碑あり)が札所本尊ではないか、との由でした。
上野王子駒込辺三十三観音霊場じたいが正式名称ではなく(東都歳時記に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」とある)、御朱印授与の札所も少ないですが、北区のある札所寺院様によると、最近、この霊場で申告されるケースが増えている感じがする、との由。
御府内、豊島などのメジャー霊場には参画されていない寺院も複数含まれているので、復活があるとうれしいです。(廃寺が複数ありますが・・・)
↑の札所印や、谷中の長安寺(第22番)で本堂扁額横に「西國三十三ヶ所寫」の札所板が掲げられていることなどから、「西國三十三ヶ所寫(観音)参り」とされていた可能性があります。
また、府内七薬師霊場第2番札所との情報がありますが、この霊場じたい調べがついておらず、現在のところ詳細不明です。(東都七仏薬師とは異なるようです。)

● 滝野川寺院めぐり第5番の御朱印
中央に「大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に院号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第五番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印をのぞいて豊島霊場と同様です。


【上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場第9番の御朱印
【下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音(西國写)霊場第20番の御朱印
第6番
和光山 興源院 大龍寺
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第21番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第17番、御府内八十八箇所第13番(不詳)
第6番は、真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ、天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置 八幡社 村ノ鎮守トス 稲荷社」
創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興し、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂露天
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れた対応です。
滝野川寺院めぐりの御朱印についても、特段驚かれた風はありませんでした。
こちらはWeb上で、「弘法大師第13番」の札所印(揮毫)の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
近年メジャー霊場化している御府内八十八箇所は、番外等の札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院がリストされています。
御府内第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺で、龍生院に引き継がれたとされていて、大龍寺との関連は不詳です。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
なお、真言宗霊雲寺派総本山の霊雲寺は、御府内八十八箇所の第28番の札所となっています。
真言宗霊雲寺派は東都を拠点とする宗派で、その霊雲寺派が江戸の弘法大師霊場である御府内八十八箇所の一画を占めているのは、頷けるものがあります。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第6番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第21番の御朱印
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に寺号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第六番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印と種子「ア」の様式が豊島霊場とは異なります。
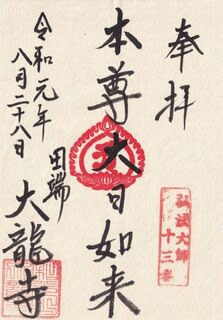
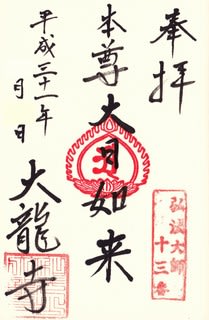
【上(左)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(御朱印帳)
(第7番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ I Will Be There with You ~日本語版~ - 杏里
■ 空に近い週末 - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 冬場もつかえるハーブ-2
つづきで10種ご紹介します。
01.タイム(タボール)

コモン系のタイムは前回ご紹介しましたが、イメージ的に別の系統のタイムがありますのでご紹介します。
ピザタイムという品種があり、これは見事にピザの香りがしますがあまり店頭に出てこないのと、意外に栽培がむずかしいので常時栽培は困難でした。
最近ホームセンターでもよく見かけるタイム・タボールという品種はピザタイムに近い芳香があり、ピザタイムより樹勢が強い感じがしています。
香辛料的なピリッとした風味もあり、タイムというよりオレガノに近い使い方だと思います。
02.ウインターセボリー

セボリーもよく栽培されるハーブです。多年草のウインター種と一年草のサマー種があり、
ウインター種の方が香りが強いです。
スパイシーな香りと独特の辛味があり、欧米では「豆のハーブ」として主に豆料理に使われます。
寒さには耐えますが暑さや湿気にやや弱く、栽培難易度は中程度だと思います。
03.ローレル

別名を月桂樹、ベイリーフ、ローリエなど。
ふるくからよく知られたハーブで、煮込み料理やシチューなどに使われます。
生でもドライでも使いますが、ドライの方が香りは強くなります。
樹勢は強く、カイガラムシに気をつければ栽培はやさしいですが、大株になるので大鉢が必要です。
04.カモミール(ローマン)

多年草のローマン種と一年草のジャーマン種に分かれ、八重咲き品種もあります。
リンゴの芳香を凝縮したような良質な香りがあります。
料理にはあまり使いませんが、カモミールティーとして飲用されます。
少し触れただけで良質な香りが匂い立つので、それだけでも利用価値はあるかも。
暑さと湿気に弱く、夏越しはけっこうむずかしいハーブです。
05.スイートマジョラム

和名はマヨラナ。オレガノと同系ですが、香りはぜんぜん違います。
どちらかというと、タイムやヒソップに近く、これに甘さが加わったとてもよい香りがします。
香りを楽しむハーブとされ、イタリア料理ではパスタや煮込み、卵料理の仕上げ(香りづけ)に使われることが多いようです。
ドイツでは伝統料理「ガチョウのロースト」に使われます。
寒さに弱いハーブとされていますが、これまで寒さで枯らしたことは一度もなく、関東では育てやすいハーブだと思います。
06.マートル


【写真 上(左)】 コモン種
【写真 下(右)】 斑入り種
ギンバイカとも呼ばれる常緑低木で、白いかわいい花をつけます。
フルーテイーな芳香があり、肉料理の香り付けに使われるようです。
こちらも寒さに弱いハーブとされていますが、寒さで枯らしたことは一度もなく、育てやすいハーブだと思います。
強剪定に耐えるのでトピアリーに仕立てることもでき、園芸的にも面白いハーブだと思います。
斑入り種もありますが、コモン種の方が香りが強いと思います。
07.レモンバーム

レモンの香りがする人気の高いハーブでメリッサとも呼ばれます。
シャーベットなどによく添えられているやつで、ハーブティーも人気です。
寒さにも暑さにもつよく、土壌もさほど選ばないので栽培しやすい品種です。
08.レモンバーベナー

これは冬場は室内にとりこまないと枯れてしまうハーブです。
日当たりのいい室内であれば、冬場でも緑を保つことができます。
レモンの香りを強めたようなきわめて質のよい芳香があり、その香りはレモンバームよりはるかに強いです。
料理にはあまり使われず、主にハーブティーに使われます。
09.4シーズンタラゴン(ミントマリーゴールド)

個人的には、ハーブの王者はタラゴン(エストラゴン)だと思いますが、これはすこぶる栽培がむずかしく、いままで何回枯らしたかわかりません。(多年草ですが、日本では実質一年草だと思う。)
その代用になりそうなのが、この4シーズンタラゴンです。
冬場は樹勢が落ちますが、収穫に耐えるくらいの葉数は保っているようです。
10.ゼラニウム(ローズ)

センテッド(匂い)ゼラニウムの一種で、よく栽培されます。
たくさんの品種がありますがローズは基本種とされ、栽培は容易です。挿し木で簡単にふやすことができます。
料理にはあまり使われませんが、クッキーづくりに利用されるようです。
☆ミックススパイス2種
ハーブを数種類栽培していると、合わせワザも楽しむことができます。
・フィーヌゼルブ

フランスの伝統的なミックススパイスです。
パセリ、チャービル、エストラゴン(タラゴン)、チャイブなどを細かくきざんで使います。
写真は、素材(パセリ、チャービル、4シーズンタラゴン、チャイブ)です。
・ブーケガルニ

ブイヤベースやポトフなどの煮込み料理やスープなどに臭み消しや風味づけとして使うハーブの束です。
ローレル、タイム、パセリ、エストラゴン(タラゴン)が基本のようですが、用途に応じて他のハーブが加えられることもあるようです。
写真は、ローレル、タイム、パセリ、4シーズンタラゴン、セージ(グローワーズフレンド)、ローズマリー(ハーブコテージ)、チャービルを組み合わせたものですが、ふつうはこんなにたくさんの種類は使わないと思います。
☆寄せ植え
コンパクトな品種は、四季の花との寄せ植えにも向いています。

ラムズイヤー・フェンネル・ローマンカモマイルとビオラ

ローズマリー(ブルー・ラグーン)とビオラ
■ 冬場もつかえるハーブ-1
【 BGM 】
■ The Time Is Now - Michael Omartian
■ Falling In Love With You Tonight - Norman Saleet
■ Ballerina - Paul Parrish
■ The Gift Of Love - Sissel kyrkjebø
■ Returning Home - Steve Haun
01.タイム(タボール)

コモン系のタイムは前回ご紹介しましたが、イメージ的に別の系統のタイムがありますのでご紹介します。
ピザタイムという品種があり、これは見事にピザの香りがしますがあまり店頭に出てこないのと、意外に栽培がむずかしいので常時栽培は困難でした。
最近ホームセンターでもよく見かけるタイム・タボールという品種はピザタイムに近い芳香があり、ピザタイムより樹勢が強い感じがしています。
香辛料的なピリッとした風味もあり、タイムというよりオレガノに近い使い方だと思います。
02.ウインターセボリー

セボリーもよく栽培されるハーブです。多年草のウインター種と一年草のサマー種があり、
ウインター種の方が香りが強いです。
スパイシーな香りと独特の辛味があり、欧米では「豆のハーブ」として主に豆料理に使われます。
寒さには耐えますが暑さや湿気にやや弱く、栽培難易度は中程度だと思います。
03.ローレル

別名を月桂樹、ベイリーフ、ローリエなど。
ふるくからよく知られたハーブで、煮込み料理やシチューなどに使われます。
生でもドライでも使いますが、ドライの方が香りは強くなります。
樹勢は強く、カイガラムシに気をつければ栽培はやさしいですが、大株になるので大鉢が必要です。
04.カモミール(ローマン)

多年草のローマン種と一年草のジャーマン種に分かれ、八重咲き品種もあります。
リンゴの芳香を凝縮したような良質な香りがあります。
料理にはあまり使いませんが、カモミールティーとして飲用されます。
少し触れただけで良質な香りが匂い立つので、それだけでも利用価値はあるかも。
暑さと湿気に弱く、夏越しはけっこうむずかしいハーブです。
05.スイートマジョラム

和名はマヨラナ。オレガノと同系ですが、香りはぜんぜん違います。
どちらかというと、タイムやヒソップに近く、これに甘さが加わったとてもよい香りがします。
香りを楽しむハーブとされ、イタリア料理ではパスタや煮込み、卵料理の仕上げ(香りづけ)に使われることが多いようです。
ドイツでは伝統料理「ガチョウのロースト」に使われます。
寒さに弱いハーブとされていますが、これまで寒さで枯らしたことは一度もなく、関東では育てやすいハーブだと思います。
06.マートル


【写真 上(左)】 コモン種
【写真 下(右)】 斑入り種
ギンバイカとも呼ばれる常緑低木で、白いかわいい花をつけます。
フルーテイーな芳香があり、肉料理の香り付けに使われるようです。
こちらも寒さに弱いハーブとされていますが、寒さで枯らしたことは一度もなく、育てやすいハーブだと思います。
強剪定に耐えるのでトピアリーに仕立てることもでき、園芸的にも面白いハーブだと思います。
斑入り種もありますが、コモン種の方が香りが強いと思います。
07.レモンバーム

レモンの香りがする人気の高いハーブでメリッサとも呼ばれます。
シャーベットなどによく添えられているやつで、ハーブティーも人気です。
寒さにも暑さにもつよく、土壌もさほど選ばないので栽培しやすい品種です。
08.レモンバーベナー

これは冬場は室内にとりこまないと枯れてしまうハーブです。
日当たりのいい室内であれば、冬場でも緑を保つことができます。
レモンの香りを強めたようなきわめて質のよい芳香があり、その香りはレモンバームよりはるかに強いです。
料理にはあまり使われず、主にハーブティーに使われます。
09.4シーズンタラゴン(ミントマリーゴールド)

個人的には、ハーブの王者はタラゴン(エストラゴン)だと思いますが、これはすこぶる栽培がむずかしく、いままで何回枯らしたかわかりません。(多年草ですが、日本では実質一年草だと思う。)
その代用になりそうなのが、この4シーズンタラゴンです。
冬場は樹勢が落ちますが、収穫に耐えるくらいの葉数は保っているようです。
10.ゼラニウム(ローズ)

センテッド(匂い)ゼラニウムの一種で、よく栽培されます。
たくさんの品種がありますがローズは基本種とされ、栽培は容易です。挿し木で簡単にふやすことができます。
料理にはあまり使われませんが、クッキーづくりに利用されるようです。
☆ミックススパイス2種
ハーブを数種類栽培していると、合わせワザも楽しむことができます。
・フィーヌゼルブ

フランスの伝統的なミックススパイスです。
パセリ、チャービル、エストラゴン(タラゴン)、チャイブなどを細かくきざんで使います。
写真は、素材(パセリ、チャービル、4シーズンタラゴン、チャイブ)です。
・ブーケガルニ

ブイヤベースやポトフなどの煮込み料理やスープなどに臭み消しや風味づけとして使うハーブの束です。
ローレル、タイム、パセリ、エストラゴン(タラゴン)が基本のようですが、用途に応じて他のハーブが加えられることもあるようです。
写真は、ローレル、タイム、パセリ、4シーズンタラゴン、セージ(グローワーズフレンド)、ローズマリー(ハーブコテージ)、チャービルを組み合わせたものですが、ふつうはこんなにたくさんの種類は使わないと思います。
☆寄せ植え
コンパクトな品種は、四季の花との寄せ植えにも向いています。

ラムズイヤー・フェンネル・ローマンカモマイルとビオラ

ローズマリー(ブルー・ラグーン)とビオラ
■ 冬場もつかえるハーブ-1
【 BGM 】
■ The Time Is Now - Michael Omartian
■ Falling In Love With You Tonight - Norman Saleet
■ Ballerina - Paul Parrish
■ The Gift Of Love - Sissel kyrkjebø
■ Returning Home - Steve Haun
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




