関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
文字数オーバーしたので、Vol.6をつくりました。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
37.岩浦山 福寿寺
〔三浦平六義村〕
三浦三十三観音霊場Web
三浦市南下浦町金田2062
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番
鎌倉幕府内の数々の政変で微妙な役回りを演じながら、生涯幕府重鎮の座をまっとうした希有の武将がいます。
三浦平六義村です。
三浦氏は桓武平氏良文流(ないし良兼流)で、神奈川県資料『三浦一族関連略系図』によると、高望王の子孫・為通が村岡姓を三浦姓に改め、為継、義継、義明と嗣いでいます。
三浦大介義明は三浦郡衣笠城に拠った武将で三浦荘の在庁官人。
”三浦介”を称して三浦半島一円に勢力を張りました。
三浦氏は、千葉氏・上総氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏とともに「坂東八平氏」に数えられる名族です。
義明の娘は源義朝公の側室に入ったとされ、義朝の子・義平が叔父の義賢と戦った「大蔵合戦」でも義朝・義平側に与しました。
(義平公の母が義明の娘という説もあり)
このような背景もあってか、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げ時には当初から頼朝側につき、頼朝公加勢のため伊豆に向けて出撃するも、大雨で酒匂川を渡れず石橋山の戦いには参戦していません。
衣笠城に帰参してほどない治承四年8月26日、畠山重忠・河越重頼・江戸重長らの秩父一族に攻められ、子の義澄以下一族を安房に逃した後、義明は奮戦むなしく討ち死にしました。(衣笠城合戦)
落ち延びた三浦一族は安房国で頼朝勢に合流、千葉常胤・上総介広常などの加勢を得て頼朝公は再挙し、10月に武蔵国へ入ると、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父一族は隅田川の長井の渡で頼朝公に帰伏しました。
『吾妻鏡』には、三浦氏総領・義明のかたきである秩父一族の帰順に抵抗を示す三浦一族を、頼朝公みずからが説得したという記述があります。
三浦義明の長男・杉本義宗の子は和田義盛で侍所別当。
次男・三浦義澄は三浦氏を嗣ぎ、他の子息も大多和氏、佐原氏、長井氏、森戸氏などを興し、また重鎮・岡崎義実は義明の弟で、三浦党は一大勢力となりました。
三浦義澄は源平合戦でも武功を重ね、建久元年(1190年)頼朝公上洛の右近衛大将拝賀の際に布衣侍7人に選ばれて参院供奉、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」の一人となり幕政でも重きをなしました。
ただし、今回の「鎌倉殿の13人」でもそうですが、後世の知名度はその嫡子の三浦義村の方が高いような感じがあります。
三浦義村は源平合戦に父・義澄とともに従軍して名をあげました。
文治元年(1185年)10月には頼朝公の勝長寿院供養供奉、建久元年(1190年)の頼朝公上洛にも父・義澄とともに供奉し、父の勲功を嗣ぐかたちで右兵衛尉に任官しています。
ここからの義村の動きは、さながら「乱変の立役者」の様相を呈しています。
これらの乱変が祖父のかたき秩父一族やみずからの三浦党にまつわるものであったことも大きいですが、義村一流の処世術も大きなポイントとなったと思われます。
義村の縦横無尽の働きがなかったとしたら、鎌倉幕府の以降の勢力図はまったく異なるものとなっていた可能性があります。
建久十年(1199年)、「梶原景時の変」では景時の讒言にあい窮地に陥った結城朝光は善後策を義村に相談しました。
義村は和田義盛、安達盛長に諮った上で景時排除を推進、有力御家人66人が連署した「景時糾弾訴状」を将軍宛に提出し、景時は失脚してのちに討たれました。
結城朝光と義村は強い姻戚関係があったわけでもないのに、このような大事を義村に相談するとは、やはり義村は「頼れる奴」との評価を得ていた証ではないでしょうか。
元久二年(1205年)の「畠山重忠の乱」では、三浦勢は重忠の子・重保を由比ヶ浜で討ち取り、つづく二俣川での重忠軍との戦でも三浦勢が主力となりました。
乱後の稲毛重成父子、榛谷重朝父子ら秩父一族の誅殺にも義村がかかわっていたとされ、これは衣笠城の戦いで祖父義明を討たれたかたきの意味合いが強いとみられています。
秩父一族は御家人中でもとくにその武威が謳われており、その一族を三浦党がメインとなって討ち果たしたということは、三浦党の武力の高さを世に示したものとみられます。
北条執権家といえども、うかつには敵にまわせない手強い相手だったことがわかります。
つづく「牧氏の変」においても義村は重要な立場を占めています。
執権・時政と牧の方は将軍実朝公を廃して、頼朝の猶子・平賀朝雅を新将軍として擁立することを画策しました。
「鎌倉殿の13人」では、時政と牧の方が計画を事前に義村に打ち明け味方に引き入れようとしていますが、義村はこれに乗る風を装い、すぐさま政子・義時に密告しています。
これが史実であったかはわかりませんが、時勢をみる判断力と局面を逃さず果断に行動できる胆力を、義村は兼ね備えていたものと思われます。
建暦三年(1213年)春、北条義時排除を画策した泉親衡(源満仲公の子孫)の謀反に絡んで和田義盛の子の義直、義重と甥の胤長が捕縛されます。
事態収拾の過程で北条氏と和田氏の関係が悪化、和田義盛は三浦党の味方を得て北条打倒をめざしたものの、義村は直前で裏切って義時に義盛の挙兵を告げ、義時は急ぎ多数派工作に出たため、人望のあったさしもの義盛も勢力を拡大することなく討ち死にしました。
この後、義村は侍所別当の座に就いています。
この時点ではもはや秩父一族に力はなく、和田義盛と三浦義村が手を結んで北条義時に対峙していたら、その後の情勢は大きくかわっていたものとみられます。
このように数々の政変のキーマンとなってきた義村。
しかも父・義澄の娘は二代将軍頼家公の子・善哉(公暁)の母、公暁の乳母は義村の妻(義村は公暁の乳母夫)という説もあります。
また、建永元年(1206年)、北条政子の計らいにより実朝公は頼家公の遺児・善哉を猶子としているので、義村が将軍家に対する野望を抱いたとしても不思議はありません。
建保七年(1219年)1月27日、鶴岡八幡宮で催された右大臣拝賀の儀のさなか、将軍実朝公は公暁に暗殺されました。
事後公暁は義村に対し「我こそは東国の大将軍である。その準備をせよ」という書状を送り、これに対して義村は「お迎えの使者を差し上げます」と偽り討手を差し向けました。
待ちきれなくなった公暁が義村邸に向かったところで討手に遭遇し、あえなく討ち取られました。
この実朝公暗殺事件は日本史上屈指のナゾとされ、動機について多くの説が展開されています。
そのなかには、義村が公暁をそそのかし、鶴岡八幡宮で実朝と義時を同時に葬ろうとしたものの義時討ち取りに失敗したため、土壇場で公暁を裏切ったという説もあります。
義村は公暁討伐の功により駿河守に任官されているので、おそらく実朝公暗殺の黒幕の疑いはかけられていなかったかと。
承久三年(1221年)の承久の乱では、検非違使として在京していた弟の胤義から京方与力の誘いを受けるもこれを一蹴し、即座にこの件を義時に伝えました。
義村は東海道の大将軍の一人として東海道を上り、鎌倉方の勝利に貢献。
元仁元年(1224年)、北条義時が逝去すると、後家の伊賀の方が実子・北条政村を執権に、娘婿の一条実雅を将軍にと企図した「伊賀氏の変」が起こります。
政村の烏帽子親であった義村は当初この陰謀に関わったとされますが、北条政子の訪問を受けて翻意し、「伊賀氏の変」は収まり北条泰時が執権となりました。
嘉禄元年(1225年)、北条政子亡きあと評定衆が設置され、義村は宿老としてこれに就任し北条氏に次ぐ地位を得たとされます。
4代鎌倉将軍・藤原頼経との関係も良好で、『吾妻鏡』には頼経が現在の平塚市にあった義村の館を度々訪れたとの記載がみえます。
生涯鎌倉幕府重鎮の座を占めて、延応元年(1239年)12月5日逝去しています。
「鎌倉殿の13人」で山本耕史が好演しているとおり、三浦義村はどこかナゾめいたキレ者だったようで、藤原定家は『明月記』のなかで「義村八難六奇之謀略、不可思議者歟」と京の貴族からみても義村の動きは策謀に富み、理解不能であったことを記しています。
ある年の正月、将軍御所の侍の間の上座を占めていた義村のさらに上座に千葉胤綱が着座すると、義村は「下総犬は、臥所を知らぬぞとよ」とつぶやくと、胤綱は「三浦犬は友を食らふなり」と切り返したという逸話が伝わります。(『古今著聞集』)
御家人として高い地位にあるという矜持と、序列を重んじるという貌をもちながら、『吾妻鏡』にはしばしば義村をめぐる争いごとが記されています。
平時は冷静でありながら、いったん主張をはじめたら決して譲らずもめ事も辞さない意思の強さは、後の「婆娑羅大名」を彷彿とさせるものがあります。
さしもの北条義時も、義村に対しては一目置かざるを得なかったと思われます。
正直なところ、北条氏の専制強化には地位も実力もある三浦氏の存在は邪魔だったとみられるわけで、じっさい義村亡きあとの宝治元年(1247年)6月5日の「宝治合戦」で、三浦一族は北条氏と外戚安達氏らによって滅ぼされています。
三浦一族の流れとしては、三浦義明の七男・佐原義連から蘆名(芦名)氏が出て会津で勢力を張り、戦国期に伊達氏と奥州の覇を競いました。
三浦義村ゆかりの寺社はいくつかあります。
横須賀市大矢部の近殿神社(ちかたじんじゃ)は三浦義村を御祭神として祀ります。御朱印は授与されていない模様です。
ここでは三浦義村開基とされる岩浦山 福寿寺をご紹介します。
なお、三浦市南下浦町金田、岩浦あたりは三浦義村ゆかりの史跡が多く、(岩浦)八坂神社境内(そば)には三浦義村新旧の墓があります。


【写真 上(左)】 金田漁港
【写真 下(右)】 三浦義村の墓(新)

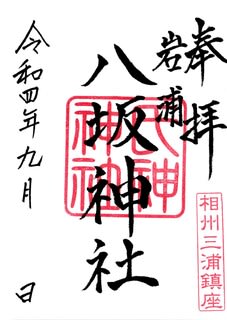
【写真 上(左)】 (岩浦)八坂神社
【写真 下(右)】 (岩浦)八坂神社の御朱印
こちらの資料(purakara.com/)によると、(岩浦)八坂神社は「金田村の古文書によれば、三浦義村の守本尊(まもりほんぞん=守護神)」とのことです。
この地からの海を見下ろす景観を、三浦義村は愛したと伝わります。
(岩浦)八坂神社の御朱印は、南下浦町菊名の白山神社で授与されています。
福寿寺は、寺伝によると建暦二年(1212年)、開山は慶叔大孝禅師、開基は三浦駿河守義村です。
御本尊の聖観世音菩薩は、行基菩薩の御作と伝わる高さ48cmの座像です。
寺宝として義村愛用の鞍・鐙・脇差などが所蔵されています。
境内には西堀栄三郎、植村直巳、多田雄幸の各氏を顕彰する碑が建立されています。
塔頭南向院はおそらく(岩浦)八坂神社のそばにありましたが、いまは廃寺となり、三浦義村旧墓が建立されているようです。


【写真 上(左)】 門柱
【写真 下(右)】 札所標
朝市で知られる金田湾の山手にある禅刹で、三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所となっています。
三浦の寺院に多い、階段をのぼってのアプローチ。
正面の本堂は大正時代に震災で焼失、平成元年に落慶との由で、近年の建立ながら堂々たる寺院建築です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造本瓦葺で向拝柱はないものの、桁行きがあり風格のある構え。
向拝桟唐戸のうえに寺号扁額を掲げ、向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。
本瓦の軒丸瓦には三浦氏の家紋である「三浦三つ引」紋が刻まれています。
山内には三浦義村とのゆかりを示す由緒書もありました。

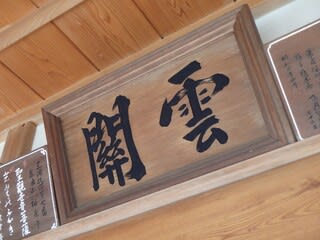
【写真 上(左)】 扁額-1
【写真 下(右)】 扁額-2
三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所本尊とみられる地蔵菩薩は、寿永八年(1184年)義村が一ノ谷の鵯越で路に迷った際、日頃信仰していた地蔵菩薩が馬首にあらわれ、義村を導いて鵯越の逆落としを成功させたという逸話が伝わります。
御朱印は平成29年5月に観音霊場第7番、地蔵尊霊場第12番のものを拝受していますが、新型コロナ禍以降、両霊場では御朱印授与を休止されている札所があり、本年(令和4年)春に予定されていた観音霊場の中開帳も中止となっているので、現時点の御朱印授与については不明です。

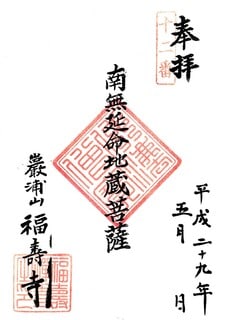
【写真 上(左)】 観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 地蔵霊場の御朱印
38.筑波山神社
〔八田右衛門尉知家、八田太郎知重〕
公式Web
茨城県つくば市筑波1
御神体:筑波山
御祭神:筑波男大神(伊弉諾尊)、筑波女大神(伊弉冊尊)
旧社格:延喜式式内社(名神大1座、小1座)、県社、別表神社
元別当:筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)→ 護持院 → 大御堂
「鎌倉殿の13人」でひときわ存在感を放っている御家人がいます。
八田右衛門尉知家です。
大河ドラマでこれほどのキーマンになっていながら、八田知家はナゾの多い人物です。
八田知家の出自については諸説があり、そのいずれもが幕府内における知家の特異なポジションを裏付けるものとなっています。
知家は宇都宮氏の当主・宇都宮宗綱(八田宗綱)の子(四男)で、姉に源頼朝の乳母のひとり寒河尼がいるというのが通説です。
宇都宮(八田)宗綱の父は藤原兼仲(諸説あり)、母は益子正隆の女とされます。
藤原兼仲の父(知家の曾祖父)は藤原兼房とされます。(諸説あり)
藤原兼房は藤原北家で中納言・藤原兼隆の長男という名流ですが、血気盛んな性格だったらしく宮中であまたのいさかいを引き起こし、生涯公卿への昇任を果たせなかったという人物です。
宇都宮(八田)宗綱の母・益子氏の本姓は紀氏で武内宿禰の末裔ともいわれますが、下野国芳賀郡益子邑を拠点とする一豪族で、父・母いずれの系譜からして知家の特異なポジションを説明づけるものではありません。
そこで、「知家は源義朝公の実子/頼朝公の異母弟」説がでてきます。(Wikipediaによると『尊卑分脈』『諸家系図纂』などにこれに関連する記載ありとする。)
また、「筑波山神社由緒」にも「頼朝の異母弟、八田知家」と明記されています。
八田氏の本拠は常陸国新治郡八田郷(現在の茨城県筑西市~つくば市)とされます。
常陸国はもともと常陸大掾氏(常陸平氏の吉田氏、多気氏、のちの馬場氏など)、佐竹氏、志田義広など強豪揃いの土地でした。
そのなかで八田知家は寿永二年(1183年)の野木宮合戦で小山氏と連携して志田義広を撃破、建久四年(1193年)には知略をもって常陸大掾氏(多気氏)を降しています。
また、頼朝公は金砂合戦で佐竹氏を討伐した帰りに八田館に立ち寄ったとされているので、八田氏は金砂合戦で佐竹氏討伐側についていたことがわかります。
『保元物語』には、下野国の八田四郎(知家?)が源義朝公の郎党として保元の乱に参戦したという記載があり、下野国の八田氏は源義朝公の麾下であったとみられます。
頼朝公の挙兵にもはやくから呼応したとされ、源平合戦では「葦屋浦の戦い」「壇ノ浦の戦い」などで武功を挙げています。
はやくから頼朝公与党の色彩がつよい知家ですが、寿永三年(1184年)頼朝公の推挙を得ずに後白河法皇から右衛門尉に任官されると、他の御家人同様に頼朝公から罵倒されるなど、特別な扱いはされていないようにもみえます。
しかし、文治5年(1189年)の奥州合戦では千葉常胤とともに東海道軍の大将軍に任じられ、はやい時期(建久四年(1193年)か?)に常陸国守護に任じられるなど重鎮としての待遇を受け、これに対する御家人達の反発もとくに伝えられていないので、「頼朝の異母弟」という認知はともかく相当な武力と知略を有していたのでは。
「頼朝の異母弟」ではなかったとしても知家の姉・寒河尼は頼朝公の乳母で、寒河尼の子・小山朝光は下野国の大勢力・小山氏の嫡流ですから、これを背景として相応の地盤はもっていたとみられます。
※なお、「頼朝の異母弟」は後世、知家の末裔である小田氏が源氏の血筋を名乗るための付会とする説があります。
茨城大学図書館のWeb公開資料『八田知家とは何者か』をみると、こういう付会が成立するほど八田知家の出自がナゾ多きものであることがわかります。
また、御家人内の序列についても、たとえば文治五年(1189年)七月十九日の「奥州征伐 自鎌倉出御御供輩」で69番目にありながら格高の「列御後人々」(ほとんど1~10番目の清和源氏に集中)に列せられるなど、イレギュラーな扱いがなされています。
『吾妻鏡』巻十建久元年(1190年)十月三日の条の頼朝公上洛進発の場面で「令進發給。御共輩之中爲宗之者多以列居南庭。而前右衛門尉知家自常陸國遲參。令待給之間已移時剋。御氣色太不快。及午剋。知家參上。乍着行騰。經南庭直昇沓解。於此所撤行騰。參御座之傍。仰曰。依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參。懈緩之所致也云々。知家稱所勞之由。又申云。先後陣誰人奉之哉。御乘馬被用何哉者。仰曰。先陣事。重忠申領状訖。後陣所思食煩也。御馬被召景時黒駮者。知家申云。先陣事尤可然。後陣者常胤爲宿老可奉之仁也。更不可及御案事歟。御乘馬。彼駮雖爲逸物。不可叶御鎧之馬也。知家用意一疋細馬。可被召歟者。」
という記載があります。
御家人達が(朝から)南庭に居並ぶなか、八田知家はなんと遅刻してくるのです。
しかもその理由は「所勞之由」。体調が悪かったというのです。
並みの御家人であれば到底許されない物言いです。
しかも、頼朝公は「依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參」、進発前に知家と打ち合わせたいことがあるので、皆を待たせていたのに遅れてきた、怠慢じゃないか、と恨み言をいいながらも、先頭としんがりの人選について知家に諮問するのです。
知家は原案の先頭畠山重忠に同意、しんがりに千葉介常胤を推挙し、常胤の乗馬までも細々と具申してすべて頼朝公に採用されています。
上洛勢の先頭としんがりといえば、鎌倉武士の名誉にかかわる最重要事項です。
これを体調不良で遅参した知家が、のうのうと差配しているのです。
そして、これに異をとなえる御家人はないようにみられます。
並大抵の存在感ではなく、御家人たちは一目も二目も置いていたことがわかります。
建久元年(1190年)の時点ですでにこのポジションを確保し、建久十年(1199年)頼朝公没後は「十三人の合議制」の一員となりましたが、これは智謀もさることながら、常陸国守護であったこと、頼朝公の乳母(寒河尼)の弟であることも大きかったとみられます。
頼家公絡みで一時期窮地に陥りかけたこともありましたがこれを巧みにこなし、有力御家人の座を嫡子・(小田)知重に順当に譲りました。
知重もまた優れ者で、すでに治承五年(1181年)に頼朝公より弓術の達人11人のなかに選ばれ、寝所の警備役に任じられています。
父子ともに能く連携して梶原景時の変、畠山重忠の乱、和田合戦を与党・北条義時方として対処し、とくに和田合戦は知重がその端緒を開いたといわれています。
常陸国守護の地位を知家から受け継ぎ、常陸国での地盤を固めています。
常陸国は従来、在庁官人系の常陸大掾家と常陸国守護家が並立してきましたが、気鋭の知重は常陸大掾の座までも狙いました。
安貞元年(1228年)幕府より「非分之望」としてこれを退けられたものの、八田氏嫡流筋の小田氏は常陸国守護職として戦国時代までその勢力を保ちました。
『沙石集』巻三第二話「忠言有感事」に、知家の発言とされる逸話が載っています。
「故鎌倉大臣(註.源頼朝公?、実朝公とも)殿、御上洛アルベキニ定マリナガラ。世間ノ人々内々歎キ申ス。子細聞コサ(?)被ルカニテ京上アルベシシヤ。イナヤノ評定有ケルニ。上ノ御気色ヲ恐レテ、コトニアラハレテ子細申ス人ナカリケルニ。故筑後ノ入道知家遅参ス。古キ人ナリ。異見申ベキ由御気色有ケレバ『天竺ニ獅子ト申候ナルハ、ケダ物(註.獣)ノ王ニテ候ナル故ニ。獣ヲ悩マサムト思心ナシトイヘドモ、カノホ(吠)ユル音(コエ)ヲキク獣。コトゴトク肝心ヲウシナヒ。或ハ命モ絶エ候ヘバ。君ハ人ヲ悩セント思食(召)ス。御心ナシト云ヘ共。民ノナゲキイカデカ候ハサラント申ゲレバ。御京上トマリヌト。仰下レテケリ。萬人掌(タナゴコロ)ヲ合テ悦ケリ。」
鎌倉将軍の上洛について人々は内心反対でしたが、将軍は乗り気で人々は畏れて意見もできずに無言で嘆くのみでした。
そこに遅れてやってきた八田知家は「百獣の王である獅子は、(べつに他の獣を悩まそうと思わずとも)その鳴き声だけで獣たちを恐れおののかせてしまいます。君主が人心を悩まそうと思っていなくとも、(将軍の上洛発言に対する)人民の畏れはどれほどのものでしょう。」と正面から将軍に諫言しました。
これを聞いた将軍は思い直して上洛をとりやめ、人々は手をあわせてこれを喜んだといいます。
人々が畏れて口にできない正論を、権威に屈せず堂々と論ぜられる知家の人柄がうかがわれます。
ここにも「遅参」の文字があります。
世間の決まり事に縛られず、信念に基づいて我が道をいくタイプの人間だったのではないでしょうか。
また、知家は謀反の疑いで常陸国に配流されていた頼朝公の異母弟・阿野全成を、頼家公の命を受けて下野国・益子で誅殺したとも伝わります。
主君の命ならば、たとえ前将軍の弟であっても躊躇なく誅殺するという苛烈さを、知家はこの重要な局面で示しています。
このような逸話から「鎌倉殿の13人」でのむやみに群れない孤高の人柄、そして上意であればなにをおいても冷徹かつ確実に実行するという必殺仕事人ぶりが描き出されたのではないでしょうか。
このあたりは配役の市原隼人が好演しています。
知家の鎌倉屋敷は大倉御所の南門外にあり、しばしば京からの使者の宿所になっています。
これは知家が京文化に通じていたためといわれます。
知家は神仏への信仰も篤く、筑後入道尊念とも称しました。→「筑後入道」の名乗りについてのWeb記事(NEWSつくば)
土浦市の真宗大谷派寺院、蓮光山 正定聚院 等覚寺の前身は知家の子・了信が開山した藤沢山 三教閣 極楽寺とされ、同山には知家寄進と伝わる銅鐘が残って「常陸三古鐘」のひとつに数えられ、国指定の重要文化財に指定されています。
茨城県筑西市松原の時宗寺院、如体山 広島院 新善光寺は、知家(朝家)の七男・知勝が出家して解意阿弥陀仏観鏡と名乗り、証空や一遍に学んで笠間の宍戸城近くに当山を建立し、文禄四年(1595年)当地に移転と伝わります。
また、Wikipediaによると、奥州合戦で捕虜になった樋爪俊衡を預けられましたが、一切の弁明もせずひたすら法華経を唱えつづける俊衡の姿に感銘を受け、頼朝公をうごかして俊衡を免罪させたといいます。
「親鸞聖人を訪ねて」真宗教団連合には「常陸の豪族八田一族には、阿弥陀仏信仰を持つ者が多く、常陸の守護であった八田知家や、その子・知重らは熱心な阿弥陀信仰者であった。」とあります。
「筑波山神社由緒」には「頼朝の異母弟、八田知家は筑波山麓に小田城を築き、且つ十男筑波八郎(明玄)をして筑波国造の名籍を継がしめ、筑波別当大夫に補しその支族筑波大膳を社司に任じて当神社に奉仕させた。」と記されています。
八田知家の墓所は笠間市平町の「宍戸清則家」墓地内の五輪石塔とされます。
宍戸氏の子孫である一木理兵衛が先祖供養のために新善光寺境内に建て、新善光寺が当地から現・筑西市松原に移転したので墓地が残ったものと伝わります。


【写真 上(左)】 筑波山
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 随神門
【写真 下(右)】 拝殿
以上挙げた寺社のうち、これまでに筆者が御朱印を拝受しているのは筑波山神社なので、筑波山神社の記事としました。


【写真 上(左)】 拝殿の扁額
【写真 下(右)】 御朱印の数々
筑波山神社については、見どころ多数でWebのガイドもたくさんあるので、まずは公式Webをご覧ください。(と、逃げる(笑))
授与所にて多種類の御朱印が授与されています。

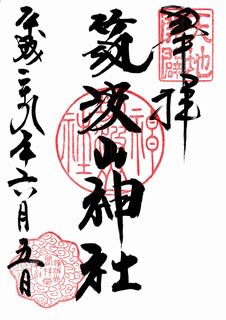
【写真 上(左)】 御朱印帳
【写真 下(右)】 筑波山神社の御朱印

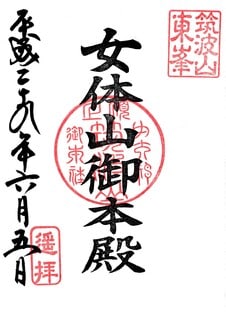
【写真 上(左)】 男体山御本殿の御朱印
【写真 下(右)】 女体山御本殿の御朱印
ケーブルカーとロープウェイがあるので、御神体の筑波山(男体山、女体山)への登拝をおすすめします。
なお、坂東三十三観音第25番の筑波山 大御堂(御朱印拝受)も筑波山神社の別当であった筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)の流れを汲むとされています。

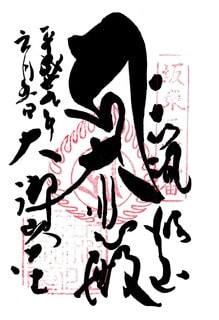
【写真 上(左)】 筑波山 大御堂
【写真 下(右)】 筑波山 大御堂の御朱印
39.大聖山 金剛寺
〔源実朝公〕
神奈川県秦野市東田原1116
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:関東九十一薬師霊場第24番
源実朝公は鎌倉幕府第3代征夷大将軍で、鎌倉幕府最後の源家将軍です。
建久三年(1192年)8月、父を頼朝公、母を正妻・北条政子として産まれ、乳母は政子の妹・阿波局、養育係は大弐局(甲斐源氏の有力者・加賀美遠光の娘)。
押しも押されぬ源家の御曹司で、幼名は千幡、別名を羽林、右府、鎌倉右大臣とも。
建仁三年(1203年)9月、比企能員の変により将軍職を追われた頼家公に替わり千幡(実朝公)は弱冠12歳で従五位下・征夷大将軍に補任され翌月に元服。
後鳥羽院の命名により実朝と称しました。
元久元年(1204年)、後鳥羽院の寵臣・坊門信清の娘(西八条禅尼/本覚尼)を正室に迎え皇室との関係を深めました。
(坊門信清は従三位・藤原信隆(藤原北家道隆流)の子で、後鳥羽帝の外祖父に当たります。)
『吾妻鏡』によると、正室は当初足利義兼の娘(北条時政の孫)が候補としてあげられていたものの、実朝公はこれを認めず京に使いを出して妻を求めたといいます。
元久二年(1205年)正五位下、建永元年(1206年)従四位下、承元元年(1207年)従四位上、同二年(1208年)正四位下、同三年(1209年)従三位・右近衛中将に任ぜられ公卿、建暦元年(1211年)正三位、同二年(1212年)従二位、同三年(1213年)正二位、同四年(1216年)には権中納言・左近衛中将、同六年(1218年)には権大納言・左近衛大将から右大臣へ昇りました。
父・頼朝公の最高位は右近衛大将なので、この時点で武家統領としては最高位に昇ったことになります。
あまりの昇進のはやさに大江広元などは官打ち(官職の位が能力より高くなりすぎ負担が増して不幸な目にあうこと)を危惧しましたが、実朝公はこの叙任を受けました。
実朝公の京・皇室志向の強さは、和歌への入れ込みからもうかがわれます。
もともと和歌の才に恵まれ、藤原定家の門下に入ったということもあり、家集『金槐和歌集』定家所伝本にはじつに663首の歌が収められ、『新勅撰和歌集』にも25首入集されています。(Wikipediaより)
当時の鎌倉屈指の文化人といえますが、反面、”文”より”武”を貴ぶ御家人との距離は開いてしまったのかもしれません。
しかし、御家人の”武”の象徴ともいえる和田義盛(初代侍所別当)との関係はすこぶるよかったと伝わり、これが御家人との感情的な橋渡しになっていたのかも。
建暦三年(1213年)2月、頼家公の遺児(栄実・千寿丸)を大将軍として北条義時を討とうという企て(泉親衡の乱)が勃発。
その中に和田義盛の子(義直、義重)がいたことは、実朝公の和田党への信頼を損ねるものだったかもしれません。
つづく同年5月の和田合戦で和田義盛を失った実朝公はおそらく落胆するとともに、北条氏に対抗する有力な後立てを失ったことにもなりました。
この後、自身が先導した渡宋計画が頓挫するなど、実朝公には暗い影がつきまといます。
ここで、源家(河内源氏)棟梁の血筋を整理してみると、
頼朝公は源家嫡流の義朝公の嫡子(正室:由良御前の子)。
頼朝公の嫡男は正室・北条政子の産んだ頼家公。三男は庶子・貞暁で高野山入山。
実朝公は母を政子とする嫡子だったので、頼家公のあとの源家嫡流を嗣ぎました。
頼家公には一幡、公暁、栄実、禅暁の男子が伝わります。
頼家公の正室は不詳とされ、誰もが源家嫡流を名乗れる不安定な状況だったのでは。
(将軍の正室が”不詳”とは考えにくく、なんらかの事情があったのかもしれません。)
一幡は比企能員の娘・若狭局の子で、建仁三年(1203年)の比企能員の変で命を落としています。
栄実(千寿丸)は法橋・一品房昌寛の娘で、建保元年(1213年)の泉親衡の乱を受けて自害。
禅暁は栄実(千寿丸)と同母とされ、公暁による実朝公暗殺を受けて承久二年(1220年)京で暗殺されたといいます。
公暁(善哉)は実母に諸説あり、『吾妻鏡』は足助(加茂)重長の娘の辻殿としています。
建保五年(1217年)6月、受戒先の園城寺(大津)から18歳で鎌倉に戻った時点では、頼家公の男子は公暁と禅暁のふたりのみとなっていました。
じつは、建永元年(1206年)、7歳の善哉(公暁)は尼御台政子の計らいで叔父実朝公の猶子となっています。
一般に猶子は養子と異なり家督や財産などの相続を目的としないとされますが、相続する場合もあります。
善哉(公暁)の乳母夫は有力御家人・三浦義村ということもあり、僧籍に入っていたとはいえ還俗して源家棟梁となるポテンシャルは充分もっていたものとみられます。
折しも、実子のない実朝公は京より後継者(次期将軍)の迎え入れを画策し、これに源家嫡流の血筋にある公暁が反発したことは大いに考えられます。
そして建保七年(1219年)1月27日の大雪の夜、ついに事が起こりました。
実朝公右大臣拝賀のための鶴岡八幡宮参詣の場で公暁が実朝公に斬りかかり、実朝公は命を落としました。享年28。
実朝公を討ち取った公暁はすぐさま乳母夫の三浦義村に「我は東国の大将軍。その準備をせよ」との使いを出し、義村はこれに「お迎えの者をお送ります」と回答。
しかし、義村は北条義時にこの事を告げ、義時は公暁誅殺を決断しました。
義村の迎えが来ないことにしびれをきらした公暁は、雪中鶴岡八幡宮の裏山を登り、義村邸に向かう途中で討手に遭遇、斬り散らしつつ義村邸までたどり着いたもののここで力尽き討ち取られたと伝わります。
この事件はふるくから「日本史屈指のナゾ」とされ、『吾妻鑑』『愚管抄』に犯行を示唆する記述や不可解な記述があることから、その動機についてさまざまな説が唱えられてきました。
犯行を示唆する記述や不可解な記述とは、たとえば
・公暁が「親の敵はかく討つぞ」と叫びつつ斬りかかったこと。
・公暁は源仲章も斬り殺したが、『愚管抄』にはこれを北条義時と誤ったものだという記載があること。
・北条義時は供奉の予定だったが、途中で具合が悪いといい、その役を源仲章に譲ったこと。
などがあげられます。
公暁の犯行については
1.公暁個人の野心による単独犯行説
2.公暁と乳母夫の三浦義村が連携し北条打倒をねらったとする説
3.北条義時が公暁をそそのかしたという説
4.将軍親裁(京への接近)を強める実朝公に対する鎌倉御家人共謀反抗説
などが見られます。
なかでもよく唱えられてきたのは「野心家の三浦義村が政権奪取をもくろみ、公暁をそそのかして義時と実朝公暗殺を狙ったものの、義時が事前に察知して退去したため企ては成就せずと見切り、公暁を裏切った。」という説です。
もしこれが事実とすれば、この時期の義時の振る舞いからして(直前で寝返ったとしても)義村を赦しておくはずはなく、義村がその後も義時の盟友として幕府重鎮の地位を保ったことから考えると無理がある、という見解も示されています。
(ただし、三浦党は宝治元年(1247年)5代執権時頼の代の「宝治合戦」で北条氏と安達景盛らに滅ぼされています。)
三浦氏の影は実朝公の供養においても感じられます。
実朝公の亡骸は、勝長寿院(大御堂、鎌倉雪の下、廃寺)に葬られたとされます。
しかし首級はみつからず、その首級は公暁の追っ手の三浦氏の家人・武常晴が護持し、秦野の金剛寺、ないしはそのそばの御首塚に葬ったといわれます。
墓所は壽福寺(鎌倉・扇ガ谷)境内に掘られたやぐらの内の石層塔とされ、隣は母・政子の墓とされます。

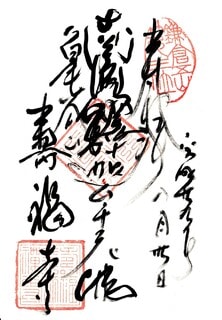
【写真 上(左)】 壽福寺
【写真 下(右)】 壽福寺の御朱印(御本尊)
また、高野山内の金剛三昧院は政子の発願で、実朝公菩提のために創建とされます。
神社では鶴ヶ岡八幡宮境内の柳営社の御祭神が源実朝公(源實朝命)でした。
明治に入り柳営社は現在の白旗神社に合祀され、父・源頼朝公(源頼朝命)とともに御鎮座されています。
拝殿前の立札には「白旗神社 御祭神 源頼朝命 源實朝命」と明記されています。


【写真 上(左)】 白旗神社の鳥居
【写真 下(右)】 白旗神社


【写真 上(左)】 白旗神社の立札
【写真 下(右)】 白旗神社の御朱印(正月限定)
寿福寺については情報も多いので、ここでは秦野の金剛寺をご紹介します。
秦野市観光協会のWebには「金剛寺は(中略)鎌倉時代に武常晴が3代将軍源実朝の御首を当寺に持参して埋葬したことに始まるといわれています。 退耕行勇を招いて木造の五輪等を建て実朝の供養をしました。その後、実朝の法号金剛寺殿にちなみ、金剛寺と改めました。1250年(建長2年)に、波多野忠綱が実朝の33回忌のため再興しました。本堂には、源実朝像が安置されています。」とあります。
三浦氏の家臣・武常晴が、実朝公の御首を当寺に持参し供養したというのです。
また『関東九十一お薬師霊場めぐり』(佛教文化振興会)には以下のとおりあります。
「草創は平安時代中頃、丹沢修験より起こった真言宗系寺院で、建長二年(1250年)波多野忠綱が実朝公菩提のため、鎌倉の名僧・退耕行勇禅師を請じて開山。」
波多野忠綱といえば、和田合戦の褒賞で先陣をめぐって三浦義村と争い、実朝公の御前で義村と対決し自身の功を勝ち取りましたが、「(あきらかに)先陣の忠綱を見落とした義村は盲目」との罵倒が咎められ褒賞は与えられなかったという人物です。
いわば、三浦義村と反目した御家人の一人といえましょう。
波多野氏は佐伯氏流ともいわれ、源頼義公の相模守補任の際に目代として相模国へ下向したのが起こりとされ、朝廷内でも高い位を誇ったとされます。
このような家柄とゆたかな秦野盆地を本拠とする軍事力から、「三浦なにするものぞ」という気概が生まれたのかもしれません。
それにしても、三浦氏家臣の武常晴が、三浦義村の仇敵ともいえる波多野忠綱ゆかりの金剛寺に将軍・実朝公の首級を葬るというのはどうにも理解しがたい流れです。
秦野市のWeb資料には「武常晴は三浦氏が公暁を討ち取るために差し向けた家臣の中の一人で、公暁との戦いの中、偶然に実朝の御首を手に入れました。その後、何らかの理由により首を主人である三浦氏のところへ持ち帰らず、当時三浦氏と仲の悪かった波多野氏を頼り埋葬したと伝えられています。」と記されています。
公暁-三浦義村/実朝公-波多野忠綱というラインがあって、武常晴が実朝公を追悼して反三浦の波多野忠綱に託したということならばこのような流れも説明はつくのですが、それもいまとなっては闇のなかです。
なお、実朝公の正室・西八条禅尼(本覚尼)は、子は設けなかったものの実朝公との仲はよかったと伝わります。
建保七年(1219年)1月、実朝公暗殺の翌日には壽福寺にて出家し京に戻りました。
承久三年(1221年)の承久の乱で兄(坊門忠信、忠清)たちが幕府と敵対して敗北した際、西八条禅尼の嘆願によって死罪を免がれたと伝わります。
九条大宮に遍照心院(現.大通寺)を建立して夫・実朝公の菩提を弔い、文永十一年(1274年)秋、享年82で逝去しています。
頼家公の息女・竹御所は建保四年(1216年)、祖母・北条政子の命で実朝公の正室・西八条禅尼の猶子となりました。
実朝公暗殺後、西八条禅尼が京に戻ったのちは政子の庇護のもと鎌倉で暮らし寛喜二年(1230年)、29歳で第4代将軍藤原頼経に嫁ぎました。
北条政子逝去(嘉禄元年(1225年))ののち、 頼朝公嫡流の血が将軍家に入ったことは御家人たちにとって明るい出来事であり、竹御所は政子の後継者として鎌倉御家人たちの結束の柱になったとも伝わります。
Wikipediaでは、竹御所が二所権現(伊豆山神社・箱根権現)に奉幣使を立てていますが、これは鎌倉殿将軍固有の祭祀権に属するものであり、竹御所の立場は鎌倉殿に準じるものであったという説が紹介されています。
しかし竹御所は4年後に懐妊したものの男児を死産し、本人も逝去しました。享年33と伝わります。
これにより源家の直系子孫は断絶し、鎌倉御家人たちはついに源家嫡流のカリスマを失いました。
金剛寺は秦野市の北側山手の田原地区にある禅宗の古刹です。
関東九十一薬師霊場第24番の札所なので、巡拝で訪れる方もいるかと思います。


【写真 上(左)】 山門と六地蔵
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
山門は切妻屋根本瓦葺様の銅板葺の四脚門。左手前に寺号標、右手覆屋内に六地蔵。
参道はかなり長く、手前右手に阿弥陀堂と地主神とみられる稲荷大明神。
禅刹らしく、山内はすっきりと整備され、きもちのよい参拝ができます。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 本堂
参道正面に寄棟造流れ向拝の本堂が端正な堂容を見せています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股で装飾はすくなくシンプルですが、禅堂らしい力づよさを感じます。
向拝上部に「実相殿」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御本尊の釋迦牟尼佛は四尺八寸の木彫坐像で鎌倉期運慶の作と伝わり、現在は鎌倉国宝館に収蔵の模様です。
阿弥陀堂には堂宇本尊の阿弥陀三佛尊と別尊の薬師如来が奉安されています。
阿弥陀三佛尊は藤原時代の作とされ、源頼朝公が奥州征伐の際、奥州白河関で心蓮法師より献上された尊佛と伝わります。
神奈川新聞Webによると、秦野市重要文化財に指定され、実朝公の「念持仏」として伝わる尊像のようです。
薬師霊場札所本尊の薬師如来は奈良時代・伝行基の作とされる木彫坐像の丈六佛で、かつて裏山山頂にあった東照院の御本尊と伝わるものです。
実朝公の御首塚は金剛寺の南側、田原ふるふさと公園の北隣りにあり、秦野市の指定史跡となっています。
入口には実朝公の和歌が刻まれ、歌碑のおくに石造の五輪塔がおかれています。
現在、鎌倉国宝館に収蔵されている「実朝の木造五輪塔」は金剛寺の所有で、この御首塚に安置されていたものです。
毎年11月23日には御首塚および田原ふるさと公園で実朝まつりが開催され、実朝公の供養が手厚く施されています。
~ 世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の 綱手かなしも ~
(百人一首93番、鎌倉右大臣)
御朱印は庫裡にて拝受しました。

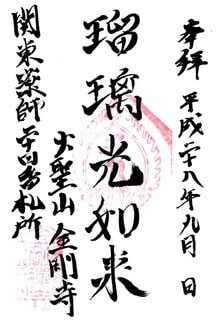
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 薬師霊場(薬師瑠璃光如来)の御朱印
ps.
中野区上高田の恵日山 金剛寺(旧:江戸小日向郷金杉村)も実朝公ゆかりの寺院とされますが、御朱印は授与されていない模様です。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7へつづく。
【 BGM 】
■ Sailing - Christopher Cross
■ Waiting For A Star To Fall - Boy Meets Girl
■ Stay With Me - Boggy Caldwell
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
37.岩浦山 福寿寺
〔三浦平六義村〕
三浦三十三観音霊場Web
三浦市南下浦町金田2062
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番
鎌倉幕府内の数々の政変で微妙な役回りを演じながら、生涯幕府重鎮の座をまっとうした希有の武将がいます。
三浦平六義村です。
三浦氏は桓武平氏良文流(ないし良兼流)で、神奈川県資料『三浦一族関連略系図』によると、高望王の子孫・為通が村岡姓を三浦姓に改め、為継、義継、義明と嗣いでいます。
三浦大介義明は三浦郡衣笠城に拠った武将で三浦荘の在庁官人。
”三浦介”を称して三浦半島一円に勢力を張りました。
三浦氏は、千葉氏・上総氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏とともに「坂東八平氏」に数えられる名族です。
義明の娘は源義朝公の側室に入ったとされ、義朝の子・義平が叔父の義賢と戦った「大蔵合戦」でも義朝・義平側に与しました。
(義平公の母が義明の娘という説もあり)
このような背景もあってか、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げ時には当初から頼朝側につき、頼朝公加勢のため伊豆に向けて出撃するも、大雨で酒匂川を渡れず石橋山の戦いには参戦していません。
衣笠城に帰参してほどない治承四年8月26日、畠山重忠・河越重頼・江戸重長らの秩父一族に攻められ、子の義澄以下一族を安房に逃した後、義明は奮戦むなしく討ち死にしました。(衣笠城合戦)
落ち延びた三浦一族は安房国で頼朝勢に合流、千葉常胤・上総介広常などの加勢を得て頼朝公は再挙し、10月に武蔵国へ入ると、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父一族は隅田川の長井の渡で頼朝公に帰伏しました。
『吾妻鏡』には、三浦氏総領・義明のかたきである秩父一族の帰順に抵抗を示す三浦一族を、頼朝公みずからが説得したという記述があります。
三浦義明の長男・杉本義宗の子は和田義盛で侍所別当。
次男・三浦義澄は三浦氏を嗣ぎ、他の子息も大多和氏、佐原氏、長井氏、森戸氏などを興し、また重鎮・岡崎義実は義明の弟で、三浦党は一大勢力となりました。
三浦義澄は源平合戦でも武功を重ね、建久元年(1190年)頼朝公上洛の右近衛大将拝賀の際に布衣侍7人に選ばれて参院供奉、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」の一人となり幕政でも重きをなしました。
ただし、今回の「鎌倉殿の13人」でもそうですが、後世の知名度はその嫡子の三浦義村の方が高いような感じがあります。
三浦義村は源平合戦に父・義澄とともに従軍して名をあげました。
文治元年(1185年)10月には頼朝公の勝長寿院供養供奉、建久元年(1190年)の頼朝公上洛にも父・義澄とともに供奉し、父の勲功を嗣ぐかたちで右兵衛尉に任官しています。
ここからの義村の動きは、さながら「乱変の立役者」の様相を呈しています。
これらの乱変が祖父のかたき秩父一族やみずからの三浦党にまつわるものであったことも大きいですが、義村一流の処世術も大きなポイントとなったと思われます。
義村の縦横無尽の働きがなかったとしたら、鎌倉幕府の以降の勢力図はまったく異なるものとなっていた可能性があります。
建久十年(1199年)、「梶原景時の変」では景時の讒言にあい窮地に陥った結城朝光は善後策を義村に相談しました。
義村は和田義盛、安達盛長に諮った上で景時排除を推進、有力御家人66人が連署した「景時糾弾訴状」を将軍宛に提出し、景時は失脚してのちに討たれました。
結城朝光と義村は強い姻戚関係があったわけでもないのに、このような大事を義村に相談するとは、やはり義村は「頼れる奴」との評価を得ていた証ではないでしょうか。
元久二年(1205年)の「畠山重忠の乱」では、三浦勢は重忠の子・重保を由比ヶ浜で討ち取り、つづく二俣川での重忠軍との戦でも三浦勢が主力となりました。
乱後の稲毛重成父子、榛谷重朝父子ら秩父一族の誅殺にも義村がかかわっていたとされ、これは衣笠城の戦いで祖父義明を討たれたかたきの意味合いが強いとみられています。
秩父一族は御家人中でもとくにその武威が謳われており、その一族を三浦党がメインとなって討ち果たしたということは、三浦党の武力の高さを世に示したものとみられます。
北条執権家といえども、うかつには敵にまわせない手強い相手だったことがわかります。
つづく「牧氏の変」においても義村は重要な立場を占めています。
執権・時政と牧の方は将軍実朝公を廃して、頼朝の猶子・平賀朝雅を新将軍として擁立することを画策しました。
「鎌倉殿の13人」では、時政と牧の方が計画を事前に義村に打ち明け味方に引き入れようとしていますが、義村はこれに乗る風を装い、すぐさま政子・義時に密告しています。
これが史実であったかはわかりませんが、時勢をみる判断力と局面を逃さず果断に行動できる胆力を、義村は兼ね備えていたものと思われます。
建暦三年(1213年)春、北条義時排除を画策した泉親衡(源満仲公の子孫)の謀反に絡んで和田義盛の子の義直、義重と甥の胤長が捕縛されます。
事態収拾の過程で北条氏と和田氏の関係が悪化、和田義盛は三浦党の味方を得て北条打倒をめざしたものの、義村は直前で裏切って義時に義盛の挙兵を告げ、義時は急ぎ多数派工作に出たため、人望のあったさしもの義盛も勢力を拡大することなく討ち死にしました。
この後、義村は侍所別当の座に就いています。
この時点ではもはや秩父一族に力はなく、和田義盛と三浦義村が手を結んで北条義時に対峙していたら、その後の情勢は大きくかわっていたものとみられます。
このように数々の政変のキーマンとなってきた義村。
しかも父・義澄の娘は二代将軍頼家公の子・善哉(公暁)の母、公暁の乳母は義村の妻(義村は公暁の乳母夫)という説もあります。
また、建永元年(1206年)、北条政子の計らいにより実朝公は頼家公の遺児・善哉を猶子としているので、義村が将軍家に対する野望を抱いたとしても不思議はありません。
建保七年(1219年)1月27日、鶴岡八幡宮で催された右大臣拝賀の儀のさなか、将軍実朝公は公暁に暗殺されました。
事後公暁は義村に対し「我こそは東国の大将軍である。その準備をせよ」という書状を送り、これに対して義村は「お迎えの使者を差し上げます」と偽り討手を差し向けました。
待ちきれなくなった公暁が義村邸に向かったところで討手に遭遇し、あえなく討ち取られました。
この実朝公暗殺事件は日本史上屈指のナゾとされ、動機について多くの説が展開されています。
そのなかには、義村が公暁をそそのかし、鶴岡八幡宮で実朝と義時を同時に葬ろうとしたものの義時討ち取りに失敗したため、土壇場で公暁を裏切ったという説もあります。
義村は公暁討伐の功により駿河守に任官されているので、おそらく実朝公暗殺の黒幕の疑いはかけられていなかったかと。
承久三年(1221年)の承久の乱では、検非違使として在京していた弟の胤義から京方与力の誘いを受けるもこれを一蹴し、即座にこの件を義時に伝えました。
義村は東海道の大将軍の一人として東海道を上り、鎌倉方の勝利に貢献。
元仁元年(1224年)、北条義時が逝去すると、後家の伊賀の方が実子・北条政村を執権に、娘婿の一条実雅を将軍にと企図した「伊賀氏の変」が起こります。
政村の烏帽子親であった義村は当初この陰謀に関わったとされますが、北条政子の訪問を受けて翻意し、「伊賀氏の変」は収まり北条泰時が執権となりました。
嘉禄元年(1225年)、北条政子亡きあと評定衆が設置され、義村は宿老としてこれに就任し北条氏に次ぐ地位を得たとされます。
4代鎌倉将軍・藤原頼経との関係も良好で、『吾妻鏡』には頼経が現在の平塚市にあった義村の館を度々訪れたとの記載がみえます。
生涯鎌倉幕府重鎮の座を占めて、延応元年(1239年)12月5日逝去しています。
「鎌倉殿の13人」で山本耕史が好演しているとおり、三浦義村はどこかナゾめいたキレ者だったようで、藤原定家は『明月記』のなかで「義村八難六奇之謀略、不可思議者歟」と京の貴族からみても義村の動きは策謀に富み、理解不能であったことを記しています。
ある年の正月、将軍御所の侍の間の上座を占めていた義村のさらに上座に千葉胤綱が着座すると、義村は「下総犬は、臥所を知らぬぞとよ」とつぶやくと、胤綱は「三浦犬は友を食らふなり」と切り返したという逸話が伝わります。(『古今著聞集』)
御家人として高い地位にあるという矜持と、序列を重んじるという貌をもちながら、『吾妻鏡』にはしばしば義村をめぐる争いごとが記されています。
平時は冷静でありながら、いったん主張をはじめたら決して譲らずもめ事も辞さない意思の強さは、後の「婆娑羅大名」を彷彿とさせるものがあります。
さしもの北条義時も、義村に対しては一目置かざるを得なかったと思われます。
正直なところ、北条氏の専制強化には地位も実力もある三浦氏の存在は邪魔だったとみられるわけで、じっさい義村亡きあとの宝治元年(1247年)6月5日の「宝治合戦」で、三浦一族は北条氏と外戚安達氏らによって滅ぼされています。
三浦一族の流れとしては、三浦義明の七男・佐原義連から蘆名(芦名)氏が出て会津で勢力を張り、戦国期に伊達氏と奥州の覇を競いました。
三浦義村ゆかりの寺社はいくつかあります。
横須賀市大矢部の近殿神社(ちかたじんじゃ)は三浦義村を御祭神として祀ります。御朱印は授与されていない模様です。
ここでは三浦義村開基とされる岩浦山 福寿寺をご紹介します。
なお、三浦市南下浦町金田、岩浦あたりは三浦義村ゆかりの史跡が多く、(岩浦)八坂神社境内(そば)には三浦義村新旧の墓があります。


【写真 上(左)】 金田漁港
【写真 下(右)】 三浦義村の墓(新)

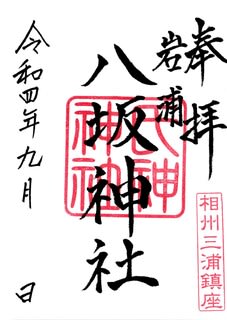
【写真 上(左)】 (岩浦)八坂神社
【写真 下(右)】 (岩浦)八坂神社の御朱印
こちらの資料(purakara.com/)によると、(岩浦)八坂神社は「金田村の古文書によれば、三浦義村の守本尊(まもりほんぞん=守護神)」とのことです。
この地からの海を見下ろす景観を、三浦義村は愛したと伝わります。
(岩浦)八坂神社の御朱印は、南下浦町菊名の白山神社で授与されています。
福寿寺は、寺伝によると建暦二年(1212年)、開山は慶叔大孝禅師、開基は三浦駿河守義村です。
御本尊の聖観世音菩薩は、行基菩薩の御作と伝わる高さ48cmの座像です。
寺宝として義村愛用の鞍・鐙・脇差などが所蔵されています。
境内には西堀栄三郎、植村直巳、多田雄幸の各氏を顕彰する碑が建立されています。
塔頭南向院はおそらく(岩浦)八坂神社のそばにありましたが、いまは廃寺となり、三浦義村旧墓が建立されているようです。


【写真 上(左)】 門柱
【写真 下(右)】 札所標
朝市で知られる金田湾の山手にある禅刹で、三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所となっています。
三浦の寺院に多い、階段をのぼってのアプローチ。
正面の本堂は大正時代に震災で焼失、平成元年に落慶との由で、近年の建立ながら堂々たる寺院建築です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造本瓦葺で向拝柱はないものの、桁行きがあり風格のある構え。
向拝桟唐戸のうえに寺号扁額を掲げ、向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。
本瓦の軒丸瓦には三浦氏の家紋である「三浦三つ引」紋が刻まれています。
山内には三浦義村とのゆかりを示す由緒書もありました。

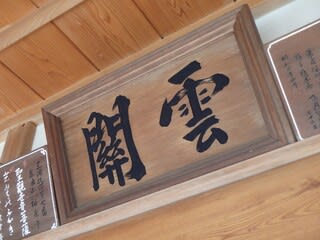
【写真 上(左)】 扁額-1
【写真 下(右)】 扁額-2
三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所本尊とみられる地蔵菩薩は、寿永八年(1184年)義村が一ノ谷の鵯越で路に迷った際、日頃信仰していた地蔵菩薩が馬首にあらわれ、義村を導いて鵯越の逆落としを成功させたという逸話が伝わります。
御朱印は平成29年5月に観音霊場第7番、地蔵尊霊場第12番のものを拝受していますが、新型コロナ禍以降、両霊場では御朱印授与を休止されている札所があり、本年(令和4年)春に予定されていた観音霊場の中開帳も中止となっているので、現時点の御朱印授与については不明です。

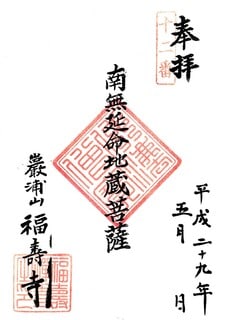
【写真 上(左)】 観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 地蔵霊場の御朱印
38.筑波山神社
〔八田右衛門尉知家、八田太郎知重〕
公式Web
茨城県つくば市筑波1
御神体:筑波山
御祭神:筑波男大神(伊弉諾尊)、筑波女大神(伊弉冊尊)
旧社格:延喜式式内社(名神大1座、小1座)、県社、別表神社
元別当:筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)→ 護持院 → 大御堂
「鎌倉殿の13人」でひときわ存在感を放っている御家人がいます。
八田右衛門尉知家です。
大河ドラマでこれほどのキーマンになっていながら、八田知家はナゾの多い人物です。
八田知家の出自については諸説があり、そのいずれもが幕府内における知家の特異なポジションを裏付けるものとなっています。
知家は宇都宮氏の当主・宇都宮宗綱(八田宗綱)の子(四男)で、姉に源頼朝の乳母のひとり寒河尼がいるというのが通説です。
宇都宮(八田)宗綱の父は藤原兼仲(諸説あり)、母は益子正隆の女とされます。
藤原兼仲の父(知家の曾祖父)は藤原兼房とされます。(諸説あり)
藤原兼房は藤原北家で中納言・藤原兼隆の長男という名流ですが、血気盛んな性格だったらしく宮中であまたのいさかいを引き起こし、生涯公卿への昇任を果たせなかったという人物です。
宇都宮(八田)宗綱の母・益子氏の本姓は紀氏で武内宿禰の末裔ともいわれますが、下野国芳賀郡益子邑を拠点とする一豪族で、父・母いずれの系譜からして知家の特異なポジションを説明づけるものではありません。
そこで、「知家は源義朝公の実子/頼朝公の異母弟」説がでてきます。(Wikipediaによると『尊卑分脈』『諸家系図纂』などにこれに関連する記載ありとする。)
また、「筑波山神社由緒」にも「頼朝の異母弟、八田知家」と明記されています。
八田氏の本拠は常陸国新治郡八田郷(現在の茨城県筑西市~つくば市)とされます。
常陸国はもともと常陸大掾氏(常陸平氏の吉田氏、多気氏、のちの馬場氏など)、佐竹氏、志田義広など強豪揃いの土地でした。
そのなかで八田知家は寿永二年(1183年)の野木宮合戦で小山氏と連携して志田義広を撃破、建久四年(1193年)には知略をもって常陸大掾氏(多気氏)を降しています。
また、頼朝公は金砂合戦で佐竹氏を討伐した帰りに八田館に立ち寄ったとされているので、八田氏は金砂合戦で佐竹氏討伐側についていたことがわかります。
『保元物語』には、下野国の八田四郎(知家?)が源義朝公の郎党として保元の乱に参戦したという記載があり、下野国の八田氏は源義朝公の麾下であったとみられます。
頼朝公の挙兵にもはやくから呼応したとされ、源平合戦では「葦屋浦の戦い」「壇ノ浦の戦い」などで武功を挙げています。
はやくから頼朝公与党の色彩がつよい知家ですが、寿永三年(1184年)頼朝公の推挙を得ずに後白河法皇から右衛門尉に任官されると、他の御家人同様に頼朝公から罵倒されるなど、特別な扱いはされていないようにもみえます。
しかし、文治5年(1189年)の奥州合戦では千葉常胤とともに東海道軍の大将軍に任じられ、はやい時期(建久四年(1193年)か?)に常陸国守護に任じられるなど重鎮としての待遇を受け、これに対する御家人達の反発もとくに伝えられていないので、「頼朝の異母弟」という認知はともかく相当な武力と知略を有していたのでは。
「頼朝の異母弟」ではなかったとしても知家の姉・寒河尼は頼朝公の乳母で、寒河尼の子・小山朝光は下野国の大勢力・小山氏の嫡流ですから、これを背景として相応の地盤はもっていたとみられます。
※なお、「頼朝の異母弟」は後世、知家の末裔である小田氏が源氏の血筋を名乗るための付会とする説があります。
茨城大学図書館のWeb公開資料『八田知家とは何者か』をみると、こういう付会が成立するほど八田知家の出自がナゾ多きものであることがわかります。
また、御家人内の序列についても、たとえば文治五年(1189年)七月十九日の「奥州征伐 自鎌倉出御御供輩」で69番目にありながら格高の「列御後人々」(ほとんど1~10番目の清和源氏に集中)に列せられるなど、イレギュラーな扱いがなされています。
『吾妻鏡』巻十建久元年(1190年)十月三日の条の頼朝公上洛進発の場面で「令進發給。御共輩之中爲宗之者多以列居南庭。而前右衛門尉知家自常陸國遲參。令待給之間已移時剋。御氣色太不快。及午剋。知家參上。乍着行騰。經南庭直昇沓解。於此所撤行騰。參御座之傍。仰曰。依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參。懈緩之所致也云々。知家稱所勞之由。又申云。先後陣誰人奉之哉。御乘馬被用何哉者。仰曰。先陣事。重忠申領状訖。後陣所思食煩也。御馬被召景時黒駮者。知家申云。先陣事尤可然。後陣者常胤爲宿老可奉之仁也。更不可及御案事歟。御乘馬。彼駮雖爲逸物。不可叶御鎧之馬也。知家用意一疋細馬。可被召歟者。」
という記載があります。
御家人達が(朝から)南庭に居並ぶなか、八田知家はなんと遅刻してくるのです。
しかもその理由は「所勞之由」。体調が悪かったというのです。
並みの御家人であれば到底許されない物言いです。
しかも、頼朝公は「依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參」、進発前に知家と打ち合わせたいことがあるので、皆を待たせていたのに遅れてきた、怠慢じゃないか、と恨み言をいいながらも、先頭としんがりの人選について知家に諮問するのです。
知家は原案の先頭畠山重忠に同意、しんがりに千葉介常胤を推挙し、常胤の乗馬までも細々と具申してすべて頼朝公に採用されています。
上洛勢の先頭としんがりといえば、鎌倉武士の名誉にかかわる最重要事項です。
これを体調不良で遅参した知家が、のうのうと差配しているのです。
そして、これに異をとなえる御家人はないようにみられます。
並大抵の存在感ではなく、御家人たちは一目も二目も置いていたことがわかります。
建久元年(1190年)の時点ですでにこのポジションを確保し、建久十年(1199年)頼朝公没後は「十三人の合議制」の一員となりましたが、これは智謀もさることながら、常陸国守護であったこと、頼朝公の乳母(寒河尼)の弟であることも大きかったとみられます。
頼家公絡みで一時期窮地に陥りかけたこともありましたがこれを巧みにこなし、有力御家人の座を嫡子・(小田)知重に順当に譲りました。
知重もまた優れ者で、すでに治承五年(1181年)に頼朝公より弓術の達人11人のなかに選ばれ、寝所の警備役に任じられています。
父子ともに能く連携して梶原景時の変、畠山重忠の乱、和田合戦を与党・北条義時方として対処し、とくに和田合戦は知重がその端緒を開いたといわれています。
常陸国守護の地位を知家から受け継ぎ、常陸国での地盤を固めています。
常陸国は従来、在庁官人系の常陸大掾家と常陸国守護家が並立してきましたが、気鋭の知重は常陸大掾の座までも狙いました。
安貞元年(1228年)幕府より「非分之望」としてこれを退けられたものの、八田氏嫡流筋の小田氏は常陸国守護職として戦国時代までその勢力を保ちました。
『沙石集』巻三第二話「忠言有感事」に、知家の発言とされる逸話が載っています。
「故鎌倉大臣(註.源頼朝公?、実朝公とも)殿、御上洛アルベキニ定マリナガラ。世間ノ人々内々歎キ申ス。子細聞コサ(?)被ルカニテ京上アルベシシヤ。イナヤノ評定有ケルニ。上ノ御気色ヲ恐レテ、コトニアラハレテ子細申ス人ナカリケルニ。故筑後ノ入道知家遅参ス。古キ人ナリ。異見申ベキ由御気色有ケレバ『天竺ニ獅子ト申候ナルハ、ケダ物(註.獣)ノ王ニテ候ナル故ニ。獣ヲ悩マサムト思心ナシトイヘドモ、カノホ(吠)ユル音(コエ)ヲキク獣。コトゴトク肝心ヲウシナヒ。或ハ命モ絶エ候ヘバ。君ハ人ヲ悩セント思食(召)ス。御心ナシト云ヘ共。民ノナゲキイカデカ候ハサラント申ゲレバ。御京上トマリヌト。仰下レテケリ。萬人掌(タナゴコロ)ヲ合テ悦ケリ。」
鎌倉将軍の上洛について人々は内心反対でしたが、将軍は乗り気で人々は畏れて意見もできずに無言で嘆くのみでした。
そこに遅れてやってきた八田知家は「百獣の王である獅子は、(べつに他の獣を悩まそうと思わずとも)その鳴き声だけで獣たちを恐れおののかせてしまいます。君主が人心を悩まそうと思っていなくとも、(将軍の上洛発言に対する)人民の畏れはどれほどのものでしょう。」と正面から将軍に諫言しました。
これを聞いた将軍は思い直して上洛をとりやめ、人々は手をあわせてこれを喜んだといいます。
人々が畏れて口にできない正論を、権威に屈せず堂々と論ぜられる知家の人柄がうかがわれます。
ここにも「遅参」の文字があります。
世間の決まり事に縛られず、信念に基づいて我が道をいくタイプの人間だったのではないでしょうか。
また、知家は謀反の疑いで常陸国に配流されていた頼朝公の異母弟・阿野全成を、頼家公の命を受けて下野国・益子で誅殺したとも伝わります。
主君の命ならば、たとえ前将軍の弟であっても躊躇なく誅殺するという苛烈さを、知家はこの重要な局面で示しています。
このような逸話から「鎌倉殿の13人」でのむやみに群れない孤高の人柄、そして上意であればなにをおいても冷徹かつ確実に実行するという必殺仕事人ぶりが描き出されたのではないでしょうか。
このあたりは配役の市原隼人が好演しています。
知家の鎌倉屋敷は大倉御所の南門外にあり、しばしば京からの使者の宿所になっています。
これは知家が京文化に通じていたためといわれます。
知家は神仏への信仰も篤く、筑後入道尊念とも称しました。→「筑後入道」の名乗りについてのWeb記事(NEWSつくば)
土浦市の真宗大谷派寺院、蓮光山 正定聚院 等覚寺の前身は知家の子・了信が開山した藤沢山 三教閣 極楽寺とされ、同山には知家寄進と伝わる銅鐘が残って「常陸三古鐘」のひとつに数えられ、国指定の重要文化財に指定されています。
茨城県筑西市松原の時宗寺院、如体山 広島院 新善光寺は、知家(朝家)の七男・知勝が出家して解意阿弥陀仏観鏡と名乗り、証空や一遍に学んで笠間の宍戸城近くに当山を建立し、文禄四年(1595年)当地に移転と伝わります。
また、Wikipediaによると、奥州合戦で捕虜になった樋爪俊衡を預けられましたが、一切の弁明もせずひたすら法華経を唱えつづける俊衡の姿に感銘を受け、頼朝公をうごかして俊衡を免罪させたといいます。
「親鸞聖人を訪ねて」真宗教団連合には「常陸の豪族八田一族には、阿弥陀仏信仰を持つ者が多く、常陸の守護であった八田知家や、その子・知重らは熱心な阿弥陀信仰者であった。」とあります。
「筑波山神社由緒」には「頼朝の異母弟、八田知家は筑波山麓に小田城を築き、且つ十男筑波八郎(明玄)をして筑波国造の名籍を継がしめ、筑波別当大夫に補しその支族筑波大膳を社司に任じて当神社に奉仕させた。」と記されています。
八田知家の墓所は笠間市平町の「宍戸清則家」墓地内の五輪石塔とされます。
宍戸氏の子孫である一木理兵衛が先祖供養のために新善光寺境内に建て、新善光寺が当地から現・筑西市松原に移転したので墓地が残ったものと伝わります。


【写真 上(左)】 筑波山
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 随神門
【写真 下(右)】 拝殿
以上挙げた寺社のうち、これまでに筆者が御朱印を拝受しているのは筑波山神社なので、筑波山神社の記事としました。


【写真 上(左)】 拝殿の扁額
【写真 下(右)】 御朱印の数々
筑波山神社については、見どころ多数でWebのガイドもたくさんあるので、まずは公式Webをご覧ください。(と、逃げる(笑))
授与所にて多種類の御朱印が授与されています。

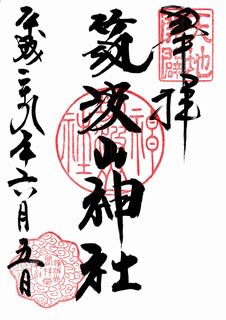
【写真 上(左)】 御朱印帳
【写真 下(右)】 筑波山神社の御朱印

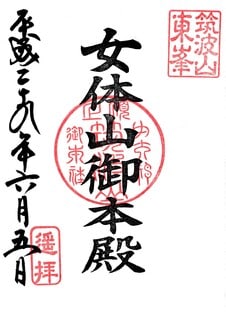
【写真 上(左)】 男体山御本殿の御朱印
【写真 下(右)】 女体山御本殿の御朱印
ケーブルカーとロープウェイがあるので、御神体の筑波山(男体山、女体山)への登拝をおすすめします。
なお、坂東三十三観音第25番の筑波山 大御堂(御朱印拝受)も筑波山神社の別当であった筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)の流れを汲むとされています。

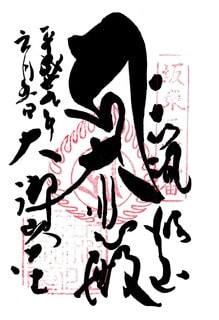
【写真 上(左)】 筑波山 大御堂
【写真 下(右)】 筑波山 大御堂の御朱印
39.大聖山 金剛寺
〔源実朝公〕
神奈川県秦野市東田原1116
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:関東九十一薬師霊場第24番
源実朝公は鎌倉幕府第3代征夷大将軍で、鎌倉幕府最後の源家将軍です。
建久三年(1192年)8月、父を頼朝公、母を正妻・北条政子として産まれ、乳母は政子の妹・阿波局、養育係は大弐局(甲斐源氏の有力者・加賀美遠光の娘)。
押しも押されぬ源家の御曹司で、幼名は千幡、別名を羽林、右府、鎌倉右大臣とも。
建仁三年(1203年)9月、比企能員の変により将軍職を追われた頼家公に替わり千幡(実朝公)は弱冠12歳で従五位下・征夷大将軍に補任され翌月に元服。
後鳥羽院の命名により実朝と称しました。
元久元年(1204年)、後鳥羽院の寵臣・坊門信清の娘(西八条禅尼/本覚尼)を正室に迎え皇室との関係を深めました。
(坊門信清は従三位・藤原信隆(藤原北家道隆流)の子で、後鳥羽帝の外祖父に当たります。)
『吾妻鏡』によると、正室は当初足利義兼の娘(北条時政の孫)が候補としてあげられていたものの、実朝公はこれを認めず京に使いを出して妻を求めたといいます。
元久二年(1205年)正五位下、建永元年(1206年)従四位下、承元元年(1207年)従四位上、同二年(1208年)正四位下、同三年(1209年)従三位・右近衛中将に任ぜられ公卿、建暦元年(1211年)正三位、同二年(1212年)従二位、同三年(1213年)正二位、同四年(1216年)には権中納言・左近衛中将、同六年(1218年)には権大納言・左近衛大将から右大臣へ昇りました。
父・頼朝公の最高位は右近衛大将なので、この時点で武家統領としては最高位に昇ったことになります。
あまりの昇進のはやさに大江広元などは官打ち(官職の位が能力より高くなりすぎ負担が増して不幸な目にあうこと)を危惧しましたが、実朝公はこの叙任を受けました。
実朝公の京・皇室志向の強さは、和歌への入れ込みからもうかがわれます。
もともと和歌の才に恵まれ、藤原定家の門下に入ったということもあり、家集『金槐和歌集』定家所伝本にはじつに663首の歌が収められ、『新勅撰和歌集』にも25首入集されています。(Wikipediaより)
当時の鎌倉屈指の文化人といえますが、反面、”文”より”武”を貴ぶ御家人との距離は開いてしまったのかもしれません。
しかし、御家人の”武”の象徴ともいえる和田義盛(初代侍所別当)との関係はすこぶるよかったと伝わり、これが御家人との感情的な橋渡しになっていたのかも。
建暦三年(1213年)2月、頼家公の遺児(栄実・千寿丸)を大将軍として北条義時を討とうという企て(泉親衡の乱)が勃発。
その中に和田義盛の子(義直、義重)がいたことは、実朝公の和田党への信頼を損ねるものだったかもしれません。
つづく同年5月の和田合戦で和田義盛を失った実朝公はおそらく落胆するとともに、北条氏に対抗する有力な後立てを失ったことにもなりました。
この後、自身が先導した渡宋計画が頓挫するなど、実朝公には暗い影がつきまといます。
ここで、源家(河内源氏)棟梁の血筋を整理してみると、
頼朝公は源家嫡流の義朝公の嫡子(正室:由良御前の子)。
頼朝公の嫡男は正室・北条政子の産んだ頼家公。三男は庶子・貞暁で高野山入山。
実朝公は母を政子とする嫡子だったので、頼家公のあとの源家嫡流を嗣ぎました。
頼家公には一幡、公暁、栄実、禅暁の男子が伝わります。
頼家公の正室は不詳とされ、誰もが源家嫡流を名乗れる不安定な状況だったのでは。
(将軍の正室が”不詳”とは考えにくく、なんらかの事情があったのかもしれません。)
一幡は比企能員の娘・若狭局の子で、建仁三年(1203年)の比企能員の変で命を落としています。
栄実(千寿丸)は法橋・一品房昌寛の娘で、建保元年(1213年)の泉親衡の乱を受けて自害。
禅暁は栄実(千寿丸)と同母とされ、公暁による実朝公暗殺を受けて承久二年(1220年)京で暗殺されたといいます。
公暁(善哉)は実母に諸説あり、『吾妻鏡』は足助(加茂)重長の娘の辻殿としています。
建保五年(1217年)6月、受戒先の園城寺(大津)から18歳で鎌倉に戻った時点では、頼家公の男子は公暁と禅暁のふたりのみとなっていました。
じつは、建永元年(1206年)、7歳の善哉(公暁)は尼御台政子の計らいで叔父実朝公の猶子となっています。
一般に猶子は養子と異なり家督や財産などの相続を目的としないとされますが、相続する場合もあります。
善哉(公暁)の乳母夫は有力御家人・三浦義村ということもあり、僧籍に入っていたとはいえ還俗して源家棟梁となるポテンシャルは充分もっていたものとみられます。
折しも、実子のない実朝公は京より後継者(次期将軍)の迎え入れを画策し、これに源家嫡流の血筋にある公暁が反発したことは大いに考えられます。
そして建保七年(1219年)1月27日の大雪の夜、ついに事が起こりました。
実朝公右大臣拝賀のための鶴岡八幡宮参詣の場で公暁が実朝公に斬りかかり、実朝公は命を落としました。享年28。
実朝公を討ち取った公暁はすぐさま乳母夫の三浦義村に「我は東国の大将軍。その準備をせよ」との使いを出し、義村はこれに「お迎えの者をお送ります」と回答。
しかし、義村は北条義時にこの事を告げ、義時は公暁誅殺を決断しました。
義村の迎えが来ないことにしびれをきらした公暁は、雪中鶴岡八幡宮の裏山を登り、義村邸に向かう途中で討手に遭遇、斬り散らしつつ義村邸までたどり着いたもののここで力尽き討ち取られたと伝わります。
この事件はふるくから「日本史屈指のナゾ」とされ、『吾妻鑑』『愚管抄』に犯行を示唆する記述や不可解な記述があることから、その動機についてさまざまな説が唱えられてきました。
犯行を示唆する記述や不可解な記述とは、たとえば
・公暁が「親の敵はかく討つぞ」と叫びつつ斬りかかったこと。
・公暁は源仲章も斬り殺したが、『愚管抄』にはこれを北条義時と誤ったものだという記載があること。
・北条義時は供奉の予定だったが、途中で具合が悪いといい、その役を源仲章に譲ったこと。
などがあげられます。
公暁の犯行については
1.公暁個人の野心による単独犯行説
2.公暁と乳母夫の三浦義村が連携し北条打倒をねらったとする説
3.北条義時が公暁をそそのかしたという説
4.将軍親裁(京への接近)を強める実朝公に対する鎌倉御家人共謀反抗説
などが見られます。
なかでもよく唱えられてきたのは「野心家の三浦義村が政権奪取をもくろみ、公暁をそそのかして義時と実朝公暗殺を狙ったものの、義時が事前に察知して退去したため企ては成就せずと見切り、公暁を裏切った。」という説です。
もしこれが事実とすれば、この時期の義時の振る舞いからして(直前で寝返ったとしても)義村を赦しておくはずはなく、義村がその後も義時の盟友として幕府重鎮の地位を保ったことから考えると無理がある、という見解も示されています。
(ただし、三浦党は宝治元年(1247年)5代執権時頼の代の「宝治合戦」で北条氏と安達景盛らに滅ぼされています。)
三浦氏の影は実朝公の供養においても感じられます。
実朝公の亡骸は、勝長寿院(大御堂、鎌倉雪の下、廃寺)に葬られたとされます。
しかし首級はみつからず、その首級は公暁の追っ手の三浦氏の家人・武常晴が護持し、秦野の金剛寺、ないしはそのそばの御首塚に葬ったといわれます。
墓所は壽福寺(鎌倉・扇ガ谷)境内に掘られたやぐらの内の石層塔とされ、隣は母・政子の墓とされます。

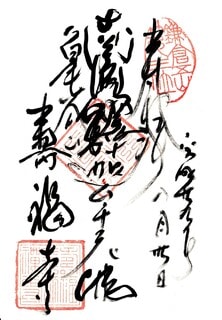
【写真 上(左)】 壽福寺
【写真 下(右)】 壽福寺の御朱印(御本尊)
また、高野山内の金剛三昧院は政子の発願で、実朝公菩提のために創建とされます。
神社では鶴ヶ岡八幡宮境内の柳営社の御祭神が源実朝公(源實朝命)でした。
明治に入り柳営社は現在の白旗神社に合祀され、父・源頼朝公(源頼朝命)とともに御鎮座されています。
拝殿前の立札には「白旗神社 御祭神 源頼朝命 源實朝命」と明記されています。


【写真 上(左)】 白旗神社の鳥居
【写真 下(右)】 白旗神社


【写真 上(左)】 白旗神社の立札
【写真 下(右)】 白旗神社の御朱印(正月限定)
寿福寺については情報も多いので、ここでは秦野の金剛寺をご紹介します。
秦野市観光協会のWebには「金剛寺は(中略)鎌倉時代に武常晴が3代将軍源実朝の御首を当寺に持参して埋葬したことに始まるといわれています。 退耕行勇を招いて木造の五輪等を建て実朝の供養をしました。その後、実朝の法号金剛寺殿にちなみ、金剛寺と改めました。1250年(建長2年)に、波多野忠綱が実朝の33回忌のため再興しました。本堂には、源実朝像が安置されています。」とあります。
三浦氏の家臣・武常晴が、実朝公の御首を当寺に持参し供養したというのです。
また『関東九十一お薬師霊場めぐり』(佛教文化振興会)には以下のとおりあります。
「草創は平安時代中頃、丹沢修験より起こった真言宗系寺院で、建長二年(1250年)波多野忠綱が実朝公菩提のため、鎌倉の名僧・退耕行勇禅師を請じて開山。」
波多野忠綱といえば、和田合戦の褒賞で先陣をめぐって三浦義村と争い、実朝公の御前で義村と対決し自身の功を勝ち取りましたが、「(あきらかに)先陣の忠綱を見落とした義村は盲目」との罵倒が咎められ褒賞は与えられなかったという人物です。
いわば、三浦義村と反目した御家人の一人といえましょう。
波多野氏は佐伯氏流ともいわれ、源頼義公の相模守補任の際に目代として相模国へ下向したのが起こりとされ、朝廷内でも高い位を誇ったとされます。
このような家柄とゆたかな秦野盆地を本拠とする軍事力から、「三浦なにするものぞ」という気概が生まれたのかもしれません。
それにしても、三浦氏家臣の武常晴が、三浦義村の仇敵ともいえる波多野忠綱ゆかりの金剛寺に将軍・実朝公の首級を葬るというのはどうにも理解しがたい流れです。
秦野市のWeb資料には「武常晴は三浦氏が公暁を討ち取るために差し向けた家臣の中の一人で、公暁との戦いの中、偶然に実朝の御首を手に入れました。その後、何らかの理由により首を主人である三浦氏のところへ持ち帰らず、当時三浦氏と仲の悪かった波多野氏を頼り埋葬したと伝えられています。」と記されています。
公暁-三浦義村/実朝公-波多野忠綱というラインがあって、武常晴が実朝公を追悼して反三浦の波多野忠綱に託したということならばこのような流れも説明はつくのですが、それもいまとなっては闇のなかです。
なお、実朝公の正室・西八条禅尼(本覚尼)は、子は設けなかったものの実朝公との仲はよかったと伝わります。
建保七年(1219年)1月、実朝公暗殺の翌日には壽福寺にて出家し京に戻りました。
承久三年(1221年)の承久の乱で兄(坊門忠信、忠清)たちが幕府と敵対して敗北した際、西八条禅尼の嘆願によって死罪を免がれたと伝わります。
九条大宮に遍照心院(現.大通寺)を建立して夫・実朝公の菩提を弔い、文永十一年(1274年)秋、享年82で逝去しています。
頼家公の息女・竹御所は建保四年(1216年)、祖母・北条政子の命で実朝公の正室・西八条禅尼の猶子となりました。
実朝公暗殺後、西八条禅尼が京に戻ったのちは政子の庇護のもと鎌倉で暮らし寛喜二年(1230年)、29歳で第4代将軍藤原頼経に嫁ぎました。
北条政子逝去(嘉禄元年(1225年))ののち、 頼朝公嫡流の血が将軍家に入ったことは御家人たちにとって明るい出来事であり、竹御所は政子の後継者として鎌倉御家人たちの結束の柱になったとも伝わります。
Wikipediaでは、竹御所が二所権現(伊豆山神社・箱根権現)に奉幣使を立てていますが、これは鎌倉殿将軍固有の祭祀権に属するものであり、竹御所の立場は鎌倉殿に準じるものであったという説が紹介されています。
しかし竹御所は4年後に懐妊したものの男児を死産し、本人も逝去しました。享年33と伝わります。
これにより源家の直系子孫は断絶し、鎌倉御家人たちはついに源家嫡流のカリスマを失いました。
金剛寺は秦野市の北側山手の田原地区にある禅宗の古刹です。
関東九十一薬師霊場第24番の札所なので、巡拝で訪れる方もいるかと思います。


【写真 上(左)】 山門と六地蔵
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
山門は切妻屋根本瓦葺様の銅板葺の四脚門。左手前に寺号標、右手覆屋内に六地蔵。
参道はかなり長く、手前右手に阿弥陀堂と地主神とみられる稲荷大明神。
禅刹らしく、山内はすっきりと整備され、きもちのよい参拝ができます。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 本堂
参道正面に寄棟造流れ向拝の本堂が端正な堂容を見せています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股で装飾はすくなくシンプルですが、禅堂らしい力づよさを感じます。
向拝上部に「実相殿」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御本尊の釋迦牟尼佛は四尺八寸の木彫坐像で鎌倉期運慶の作と伝わり、現在は鎌倉国宝館に収蔵の模様です。
阿弥陀堂には堂宇本尊の阿弥陀三佛尊と別尊の薬師如来が奉安されています。
阿弥陀三佛尊は藤原時代の作とされ、源頼朝公が奥州征伐の際、奥州白河関で心蓮法師より献上された尊佛と伝わります。
神奈川新聞Webによると、秦野市重要文化財に指定され、実朝公の「念持仏」として伝わる尊像のようです。
薬師霊場札所本尊の薬師如来は奈良時代・伝行基の作とされる木彫坐像の丈六佛で、かつて裏山山頂にあった東照院の御本尊と伝わるものです。
実朝公の御首塚は金剛寺の南側、田原ふるふさと公園の北隣りにあり、秦野市の指定史跡となっています。
入口には実朝公の和歌が刻まれ、歌碑のおくに石造の五輪塔がおかれています。
現在、鎌倉国宝館に収蔵されている「実朝の木造五輪塔」は金剛寺の所有で、この御首塚に安置されていたものです。
毎年11月23日には御首塚および田原ふるさと公園で実朝まつりが開催され、実朝公の供養が手厚く施されています。
~ 世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の 綱手かなしも ~
(百人一首93番、鎌倉右大臣)
御朱印は庫裡にて拝受しました。

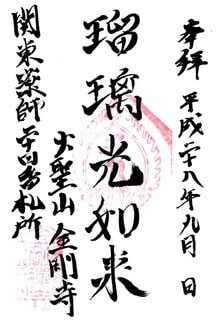
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 薬師霊場(薬師瑠璃光如来)の御朱印
ps.
中野区上高田の恵日山 金剛寺(旧:江戸小日向郷金杉村)も実朝公ゆかりの寺院とされますが、御朱印は授与されていない模様です。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7へつづく。
【 BGM 】
■ Sailing - Christopher Cross
■ Waiting For A Star To Fall - Boy Meets Girl
■ Stay With Me - Boggy Caldwell
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
以前UPした記事ですが、ゆかりのある武将などのデータ(伝承含む)を加えてリニューアルUPします。
字数オーバーになったので、2つに分割します。
第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
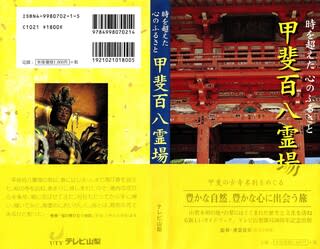
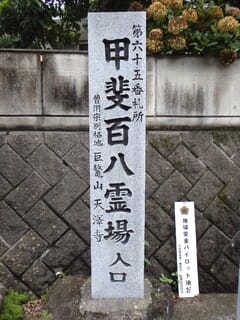
甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。
霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。
札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。
先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。
なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。
ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。
専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。
ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。
札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。
(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)
なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。
ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。
第1番 定額山 善光寺
甲府市善光寺3-36-1
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 善光寺如来(阿弥陀三尊)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第67番、府内観音札所第7番
・武田信玄公(信濃善光寺から移して建立)、加藤遠江守光泰(墓所)


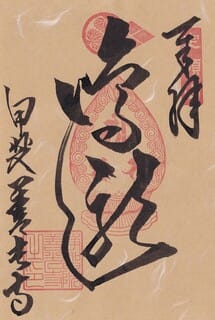
〔鳴き龍の御朱印〕
第2番 岩泉山 寂静院 光福寺
甲府市横根町1110
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐国三十三番観音札所第21番、第22番
・新羅三郎義光公(開創)、武田信玄公(再建)

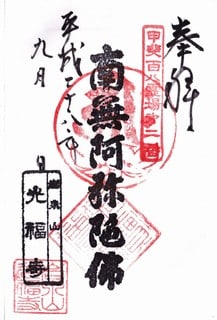
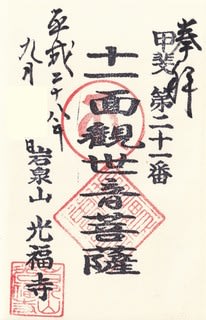

【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第21番)の御朱印〕
【下(右)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第22番)の御朱印〕
第3番 松本山 大蔵経寺
笛吹市石和町松本610
真言宗智山派
御本尊 不動明王
札所本尊 不動明王
他札所 石和温泉郷七福神(寿老人)
・武田信成公(武田氏8代当主、諸堂建立)、徳川氏(祈願所)


第4番 龍石山 永昌院
山梨市矢坪1088
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第69番
・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)


第5番 金峰山 洞雲寺
山梨市牧丘町北原1117
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第33番
・安田義定・西保義安父子(菩提)、渡瀬志摩守清満(開創)、加藤遠江守光泰(中興開基)

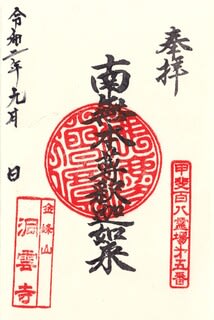
第6番 妙高山 普門寺
山梨市牧丘町西保下3631
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・安田義定(祈願寺)

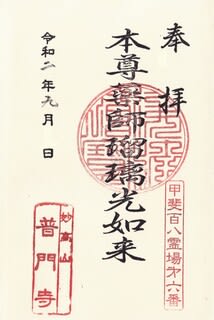
第7番 徳和山 吉祥寺
山梨市三富徳和2
真言宗智山派
御本尊 毘沙門天
札所本尊 毘沙門天
他札所 甲州東郡七福神(毘沙門天)
・武田信光公(武田氏2代当主、開創)、武田信玄公(再興)、武田百足衆

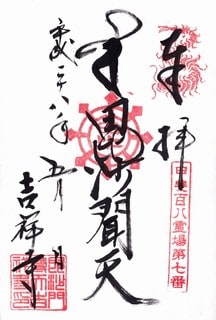
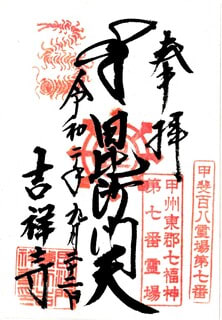
〔甲州東郡七福神(毘沙門天)の御朱印〕
第8番 高橋山 放光寺
甲州市藤木2438
真言宗智山派
御本尊 大日如来
札所本尊 大日如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)
・安田氏(菩提寺)、保田宗雪(中興開基)

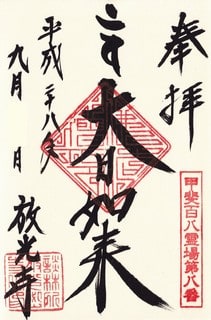
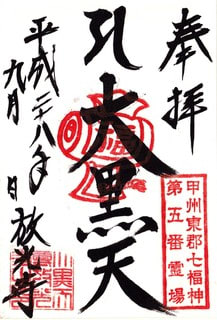
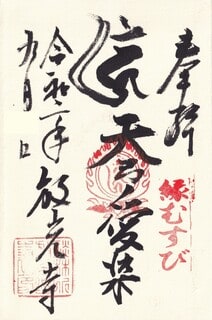
【上(左)】 〔甲州東郡七福神(大黒天)の御朱印〕
【下(右)】 〔天弓愛染明王の御朱印〕
第9番 乾徳山 恵林寺
甲州市小屋敷2280
臨済宗妙心寺派
御本尊 大日如来
札所本尊 大日如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第73
・二階堂貞藤(道蘊)(草創)、武田信玄公(菩提寺)

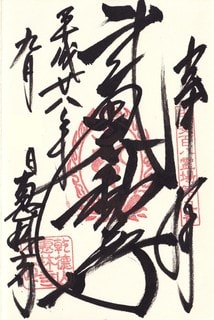
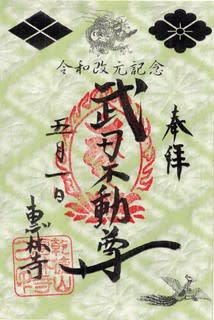
〔令和改元記念の御朱印〕
第10番 天龍山 慈雲寺
甲州市塩山中萩原352
臨済宗妙心寺派
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩

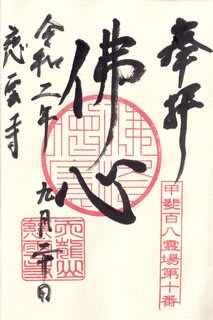
第11番 裂石山 雲峰寺
甲州市塩山上萩原2678
臨済宗妙心寺派
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第75番、甲斐国三十三番観音札所第16番
・武田氏(祈願寺)、武田信虎公(武田氏15代当主、再興)

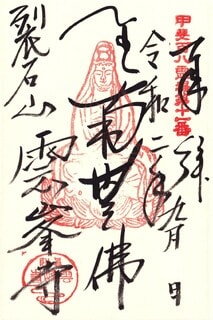
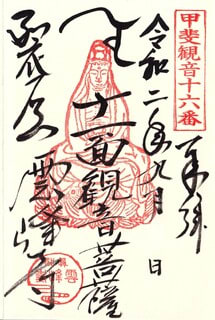
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第12番 塩山 向嶽寺
臨済宗向嶽寺派本山
甲州市上於曽2026
御本尊 観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番
・武田信虎公(武田氏8代当主、寄進再興)

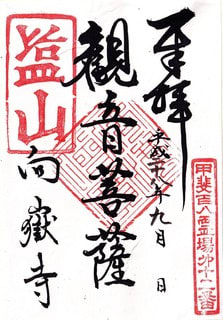
第13番 神竜山 雲光寺
山梨市下井尻673
臨済宗妙心寺派
御本尊 観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番
・安田義定(開基、墓所)

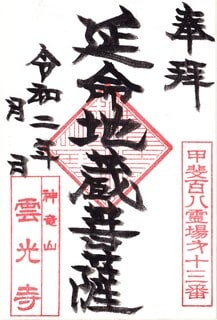
第14番 海涌山 清白寺
山梨市三ヶ所620
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 千手観世音菩薩
・足利尊氏公(開基)

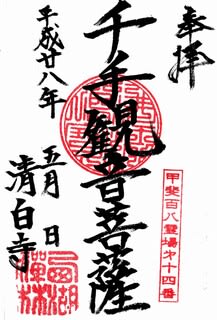
第15番 休息山 立正寺
甲州市勝沼町休息1713
日蓮宗
御首題
・徳川氏(寄進)、田安家(寄進)

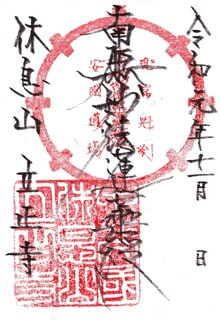
第16番 等々力山 万福寺(杉之御坊)
甲州市勝沼町等々力1289
真宗本願寺派
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・足利将軍家(祈願所)


第17番 菱渓山 上宮院 三光寺
甲州市勝沼町菱山928
真宗本願寺派
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・武田治郎左衛門(寄進)

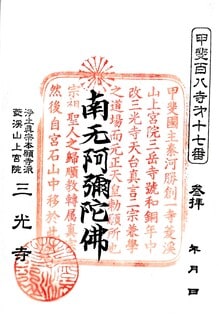
第18番 柏尾山 大善寺
甲州市勝沼町勝沼3559
真言宗智山派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第77番、甲州東郡七福神(弁財天)
・三枝守国(氏寺、墓所)、北条貞時(再興)

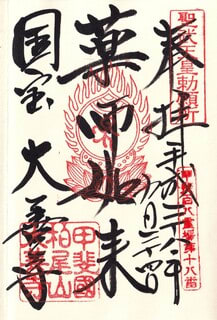
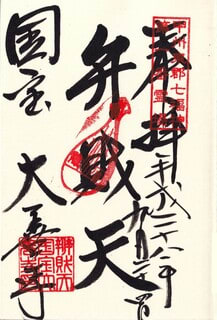
〔甲州東郡七福神(弁財天)の御朱印〕
第19番 天童山 景徳院
甲州市大和町田野389
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
(御朱印揮毫) 武田勝頼公廟所
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第2番
・武田勝頼公、武田信勝公(自刃の地、菩提所)


第20番 天目山 棲雲寺
甲州市大和町木賊122
臨済宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第1番
・武田家(菩提寺)、武田信満公(武田氏10代当主、墓所)

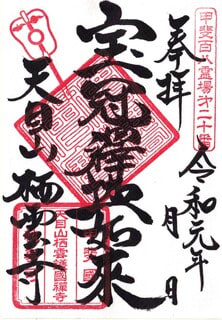
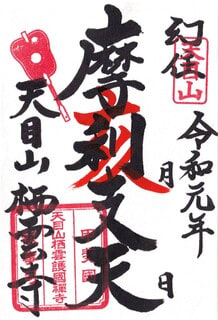
〔摩利支天の御朱印〕
第21番 安寧山 保福寺
上野原市上野原3400
曹洞宗
御本尊 地蔵菩薩
札所本尊 地蔵菩薩
・加藤丹後守景忠(上野原城城主、開基)


第22番 水上山 花井寺
大月市七保町下和田1219
臨済宗向嶽寺派
御本尊 弥勒菩薩
札所本尊 弥勒菩薩

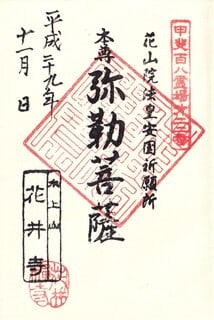
第23番 徳巌山 福泉寺
大月市七保町葛野1695
臨済宗建長寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 郡内三十三番観音霊場第21番

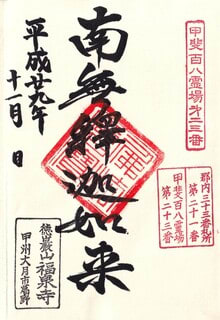
第24番 岩殿山 真蔵院
大月市賑岡町岩殿160(地図)
真言宗智山派
御本尊 千手観世音菩薩
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第5番、甲斐国三十三番観音札所第30番、郡内三十三番観音霊場第20番

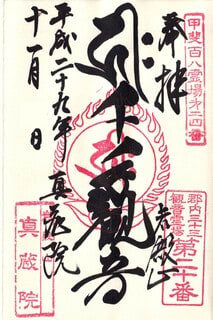

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第25番 大儀山 長生寺
都留市下谷2954
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第8番、都留七福神(弁財天)
・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)、小山田信有、鳥居成次、秋元泰朝(いずれも護持、あるいは菩提所)



〔都留七福神(弁財天)の御朱印〕
第26番 大幡山 広教寺
都留市大幡1541
曹洞宗
御本尊 地蔵菩薩
札所本尊 地蔵菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第10番、都留七福神(福禄寿)
・源頼家公(開基本願)

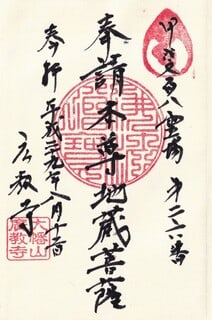
第27番 金鼇山 宝鏡寺
都留市桂町1047
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第11番
・鶏岳永金(執権北条重時の九男、開山)

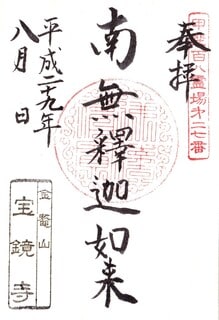
第28番 引接山 西方寺
富士吉田市小明見2058
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 郡内三十三番観音霊場第8番
・祖底禅師(新田大炊助義重の五男、開山)

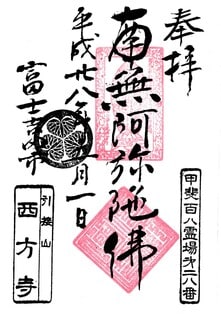
第29番 水上山 月江寺
富士吉田市下吉田869
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第13番

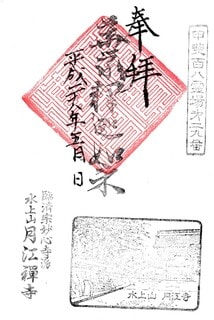
第30番 吉積山 西念寺
富士吉田市上吉田7-7-1
時宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第14番、郡内三十三番観音霊場第13番


第31番 醫王山 承天寺
忍野村内野192
臨済宗妙心寺派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 郡内三十三番観音霊場第9番
・畠山重忠(寄進)

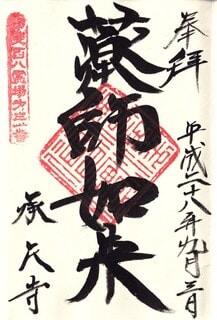
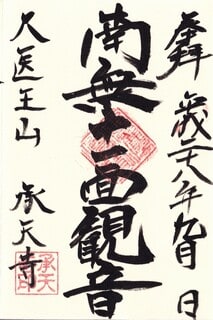
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第32番 蓮華山 妙法寺
富士河口湖町小立692
法華宗本門流
御首題

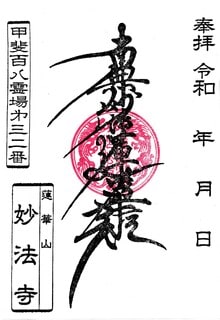
第33番 霊鷲山 常在寺
富士河口湖町小立139
法華宗本門流
御首題
・秋元但馬守(谷村城主、寄進)

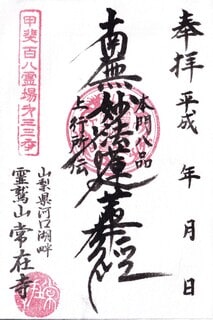
第34番 竜玉山 称願寺
笛吹市御坂町上黒駒2969
時宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第15番

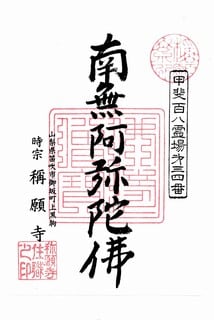
第35番 妙亀山 広厳院
笛吹市一宮町金沢227-1
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第16番
・降矢対馬守(開基)、武田信昌公(武田氏13代当主、寄進整備)

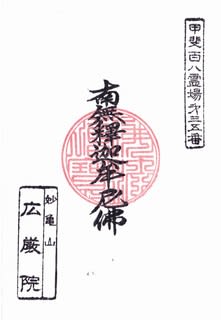
第36番 塩田山 超願寺
笛吹市一宮町塩田818
真宗大谷派
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・下間頼竜(所縁)

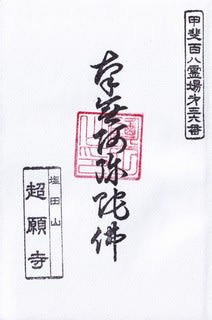
第37番 護国山 国分寺
笛吹市一宮町国分197-1
臨済宗妙心寺派
御本尊 阿弥陀如来・薬師如来
札所本尊 阿弥陀如来・薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第18番
・武田信玄公(寄進)

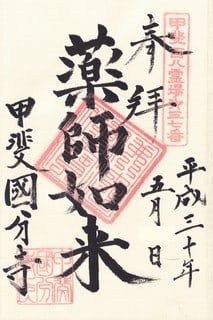
第38番 金剛山 慈眼寺
笛吹市一宮町末木336
真言宗智山派
御本尊 千手観世音菩薩
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第17番
・武田氏(祈願所)

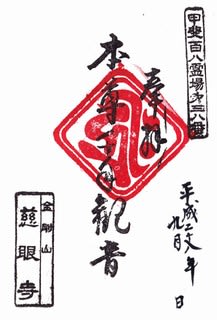
第39番 鵜飼山 遠妙寺
笛吹市石和町市部1016
日蓮宗
御首題
他札所 石和温泉郷七福神(大黒天)



〔石和温泉郷七福神(大黒天)の御朱印〕
第40番 大野山 福光園寺
笛吹市御坂町大野2027
真言宗智山派
御本尊 不動明王
札所本尊 不動明王
・大野対馬守重包(中興開基)、三枝氏(所縁)


第41番 宝樹山 広済寺
笛吹市八代町奈良原865
臨済宗向嶽寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
・武田信春公(武田氏9代当主、中興)


第42番 慧光山 定林寺
笛吹市八代町南747
日蓮宗
御首題

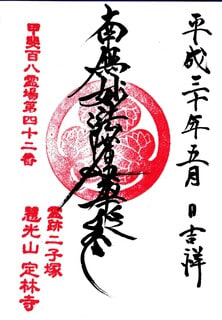
第43番 無碍山 瑜伽寺
笛吹市八代町永井1543
臨済宗向嶽寺派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第20番

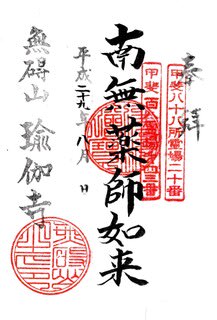
第44番 長国山 聖應寺
笛吹市境川町大黒坂1090
臨済宗向嶽寺派
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第21番
・黒坂五郎信光(寄進)

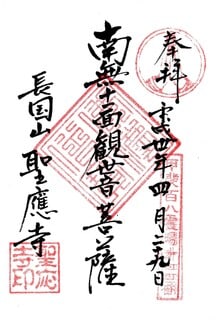
第45番 万亀山 向昌院
笛吹市境川町藤垈363
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩

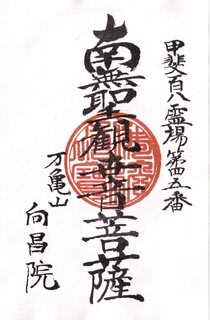
第46番 吉国山 龍華院
甲府市上曽根町4042
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第23番

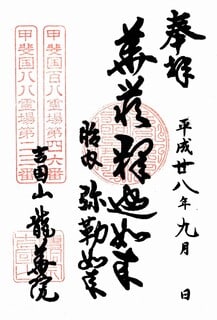
第47番 悟道山 安国寺
甲府市心経寺町1200
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
・足利尊氏公・直義兄弟(発願)

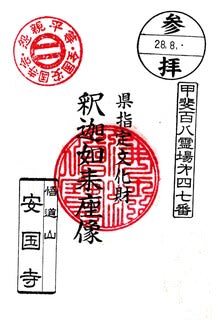
第48番 七覚山 円楽寺
甲府市右左口町4104
真言宗智山派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第24番
・源頼朝公(六角堂創建、祈願所)

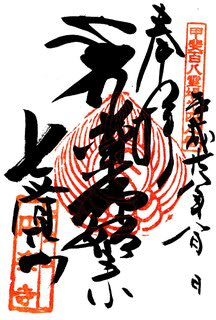
第49番 飯室山 大福寺
中央市大鳥居1621
真言宗智山派
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
他札所 甲斐国三十三番観音札所第11番
・飯室禅師光厳(武田信義公(武田氏初代当主)の孫、再興)、浅利与一義成(所縁)


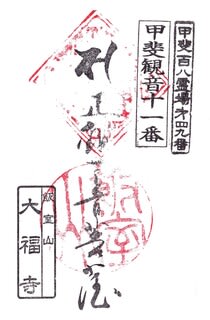
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第50番-1 豊田山 永源寺
中央市下河東880
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第86番、甲斐国三十三番観音札所第2番
・加藤梵玄(開基)


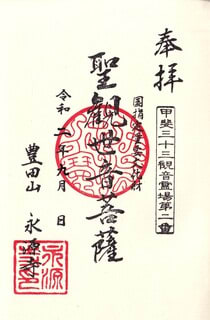
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第50番-2 富田山 歓盛院
中央市下三條88
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第85番
・秋山太郎光朝(開基)、富田対馬守範良(寄進)

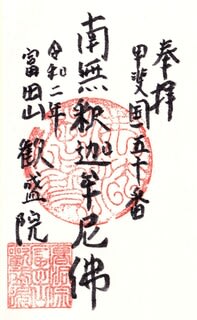
字数オーバーになったので、2つに分割します。
第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
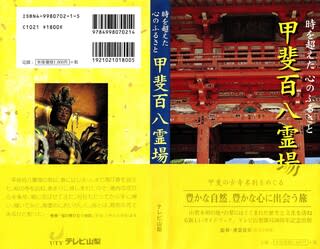
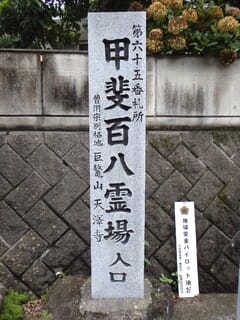
甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。
霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。
札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。
先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。
なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。
ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。
専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。
ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。
札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。
(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)
なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。
ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。
第1番 定額山 善光寺
甲府市善光寺3-36-1
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 善光寺如来(阿弥陀三尊)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第67番、府内観音札所第7番
・武田信玄公(信濃善光寺から移して建立)、加藤遠江守光泰(墓所)


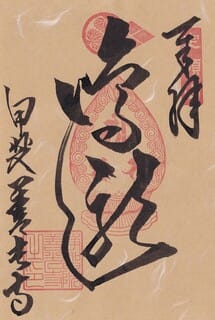
〔鳴き龍の御朱印〕
第2番 岩泉山 寂静院 光福寺
甲府市横根町1110
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐国三十三番観音札所第21番、第22番
・新羅三郎義光公(開創)、武田信玄公(再建)

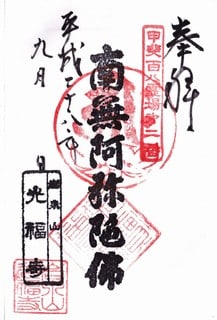
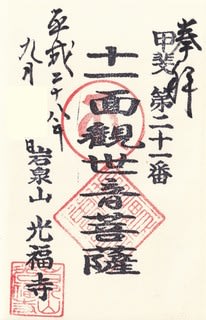

【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第21番)の御朱印〕
【下(右)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第22番)の御朱印〕
第3番 松本山 大蔵経寺
笛吹市石和町松本610
真言宗智山派
御本尊 不動明王
札所本尊 不動明王
他札所 石和温泉郷七福神(寿老人)
・武田信成公(武田氏8代当主、諸堂建立)、徳川氏(祈願所)


第4番 龍石山 永昌院
山梨市矢坪1088
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第69番
・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)


第5番 金峰山 洞雲寺
山梨市牧丘町北原1117
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第33番
・安田義定・西保義安父子(菩提)、渡瀬志摩守清満(開創)、加藤遠江守光泰(中興開基)

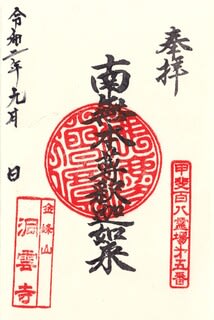
第6番 妙高山 普門寺
山梨市牧丘町西保下3631
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・安田義定(祈願寺)

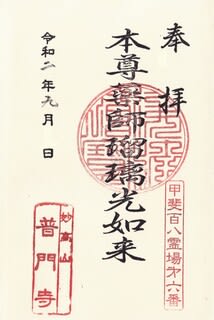
第7番 徳和山 吉祥寺
山梨市三富徳和2
真言宗智山派
御本尊 毘沙門天
札所本尊 毘沙門天
他札所 甲州東郡七福神(毘沙門天)
・武田信光公(武田氏2代当主、開創)、武田信玄公(再興)、武田百足衆

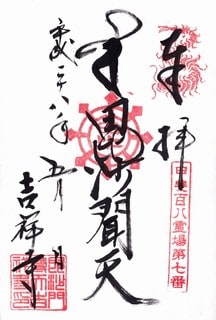
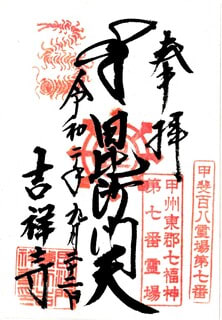
〔甲州東郡七福神(毘沙門天)の御朱印〕
第8番 高橋山 放光寺
甲州市藤木2438
真言宗智山派
御本尊 大日如来
札所本尊 大日如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)
・安田氏(菩提寺)、保田宗雪(中興開基)

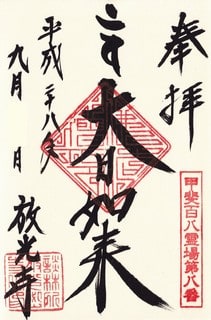
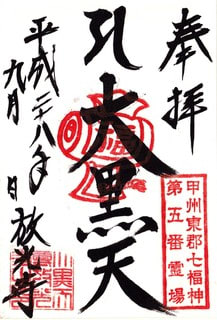
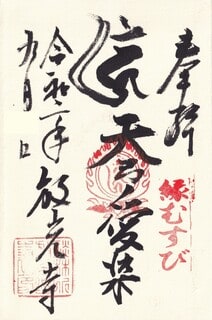
【上(左)】 〔甲州東郡七福神(大黒天)の御朱印〕
【下(右)】 〔天弓愛染明王の御朱印〕
第9番 乾徳山 恵林寺
甲州市小屋敷2280
臨済宗妙心寺派
御本尊 大日如来
札所本尊 大日如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第73
・二階堂貞藤(道蘊)(草創)、武田信玄公(菩提寺)

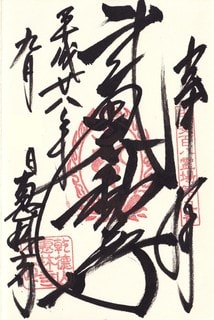
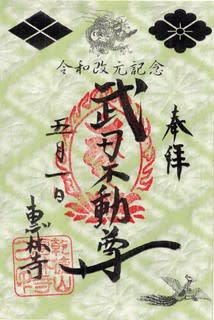
〔令和改元記念の御朱印〕
第10番 天龍山 慈雲寺
甲州市塩山中萩原352
臨済宗妙心寺派
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩

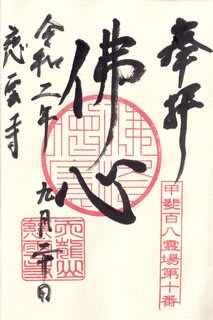
第11番 裂石山 雲峰寺
甲州市塩山上萩原2678
臨済宗妙心寺派
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第75番、甲斐国三十三番観音札所第16番
・武田氏(祈願寺)、武田信虎公(武田氏15代当主、再興)

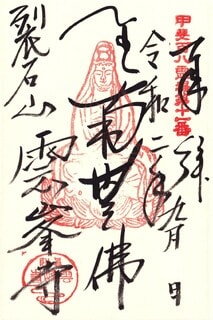
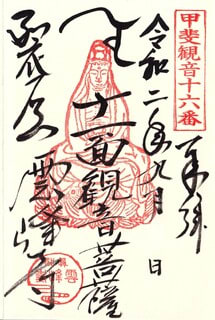
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第12番 塩山 向嶽寺
臨済宗向嶽寺派本山
甲州市上於曽2026
御本尊 観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番
・武田信虎公(武田氏8代当主、寄進再興)

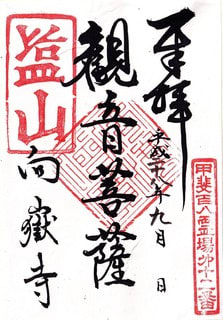
第13番 神竜山 雲光寺
山梨市下井尻673
臨済宗妙心寺派
御本尊 観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番
・安田義定(開基、墓所)

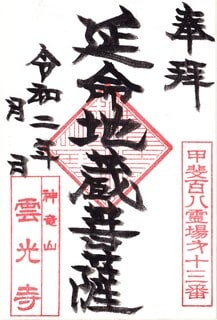
第14番 海涌山 清白寺
山梨市三ヶ所620
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 千手観世音菩薩
・足利尊氏公(開基)

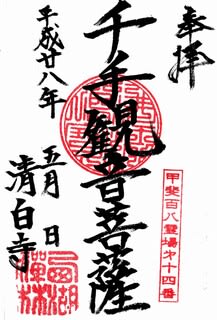
第15番 休息山 立正寺
甲州市勝沼町休息1713
日蓮宗
御首題
・徳川氏(寄進)、田安家(寄進)

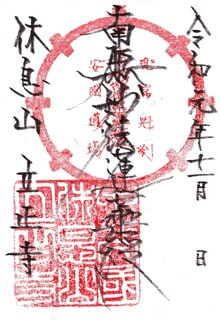
第16番 等々力山 万福寺(杉之御坊)
甲州市勝沼町等々力1289
真宗本願寺派
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・足利将軍家(祈願所)


第17番 菱渓山 上宮院 三光寺
甲州市勝沼町菱山928
真宗本願寺派
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・武田治郎左衛門(寄進)

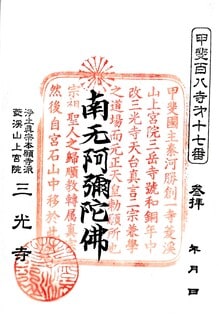
第18番 柏尾山 大善寺
甲州市勝沼町勝沼3559
真言宗智山派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第77番、甲州東郡七福神(弁財天)
・三枝守国(氏寺、墓所)、北条貞時(再興)

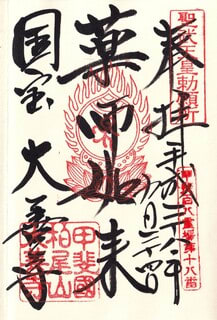
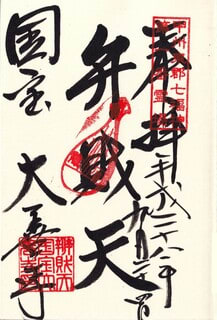
〔甲州東郡七福神(弁財天)の御朱印〕
第19番 天童山 景徳院
甲州市大和町田野389
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
(御朱印揮毫) 武田勝頼公廟所
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第2番
・武田勝頼公、武田信勝公(自刃の地、菩提所)


第20番 天目山 棲雲寺
甲州市大和町木賊122
臨済宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第1番
・武田家(菩提寺)、武田信満公(武田氏10代当主、墓所)

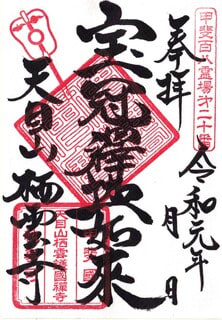
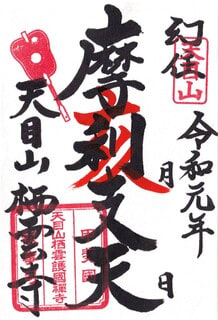
〔摩利支天の御朱印〕
第21番 安寧山 保福寺
上野原市上野原3400
曹洞宗
御本尊 地蔵菩薩
札所本尊 地蔵菩薩
・加藤丹後守景忠(上野原城城主、開基)


第22番 水上山 花井寺
大月市七保町下和田1219
臨済宗向嶽寺派
御本尊 弥勒菩薩
札所本尊 弥勒菩薩

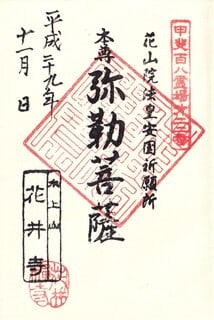
第23番 徳巌山 福泉寺
大月市七保町葛野1695
臨済宗建長寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 郡内三十三番観音霊場第21番

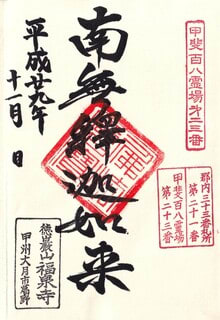
第24番 岩殿山 真蔵院
大月市賑岡町岩殿160(地図)
真言宗智山派
御本尊 千手観世音菩薩
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第5番、甲斐国三十三番観音札所第30番、郡内三十三番観音霊場第20番

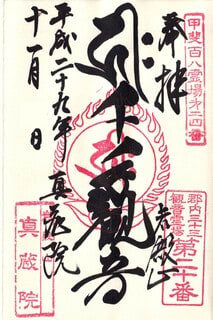

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第25番 大儀山 長生寺
都留市下谷2954
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第8番、都留七福神(弁財天)
・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)、小山田信有、鳥居成次、秋元泰朝(いずれも護持、あるいは菩提所)



〔都留七福神(弁財天)の御朱印〕
第26番 大幡山 広教寺
都留市大幡1541
曹洞宗
御本尊 地蔵菩薩
札所本尊 地蔵菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第10番、都留七福神(福禄寿)
・源頼家公(開基本願)

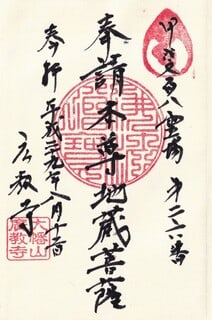
第27番 金鼇山 宝鏡寺
都留市桂町1047
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第11番
・鶏岳永金(執権北条重時の九男、開山)

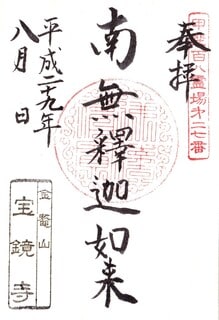
第28番 引接山 西方寺
富士吉田市小明見2058
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 郡内三十三番観音霊場第8番
・祖底禅師(新田大炊助義重の五男、開山)

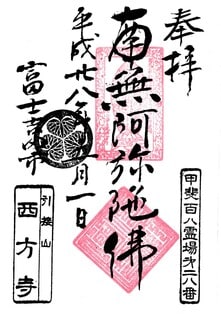
第29番 水上山 月江寺
富士吉田市下吉田869
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第13番

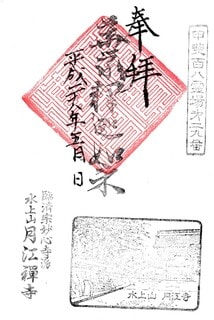
第30番 吉積山 西念寺
富士吉田市上吉田7-7-1
時宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第14番、郡内三十三番観音霊場第13番


第31番 醫王山 承天寺
忍野村内野192
臨済宗妙心寺派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 郡内三十三番観音霊場第9番
・畠山重忠(寄進)

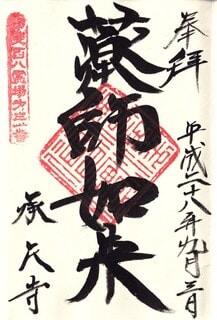
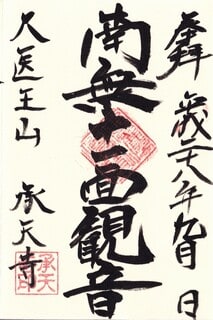
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第32番 蓮華山 妙法寺
富士河口湖町小立692
法華宗本門流
御首題

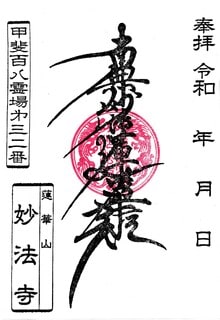
第33番 霊鷲山 常在寺
富士河口湖町小立139
法華宗本門流
御首題
・秋元但馬守(谷村城主、寄進)

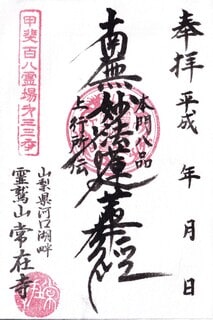
第34番 竜玉山 称願寺
笛吹市御坂町上黒駒2969
時宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第15番

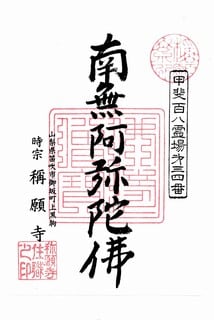
第35番 妙亀山 広厳院
笛吹市一宮町金沢227-1
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第16番
・降矢対馬守(開基)、武田信昌公(武田氏13代当主、寄進整備)

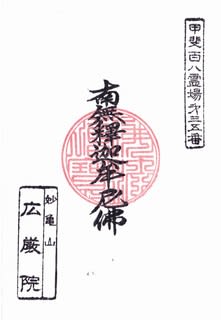
第36番 塩田山 超願寺
笛吹市一宮町塩田818
真宗大谷派
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・下間頼竜(所縁)

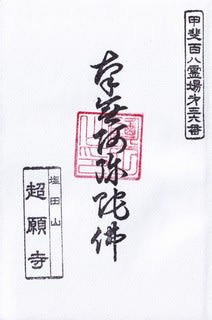
第37番 護国山 国分寺
笛吹市一宮町国分197-1
臨済宗妙心寺派
御本尊 阿弥陀如来・薬師如来
札所本尊 阿弥陀如来・薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第18番
・武田信玄公(寄進)

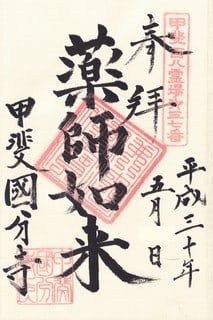
第38番 金剛山 慈眼寺
笛吹市一宮町末木336
真言宗智山派
御本尊 千手観世音菩薩
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第17番
・武田氏(祈願所)

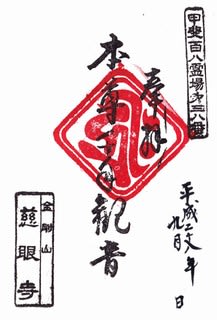
第39番 鵜飼山 遠妙寺
笛吹市石和町市部1016
日蓮宗
御首題
他札所 石和温泉郷七福神(大黒天)



〔石和温泉郷七福神(大黒天)の御朱印〕
第40番 大野山 福光園寺
笛吹市御坂町大野2027
真言宗智山派
御本尊 不動明王
札所本尊 不動明王
・大野対馬守重包(中興開基)、三枝氏(所縁)


第41番 宝樹山 広済寺
笛吹市八代町奈良原865
臨済宗向嶽寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
・武田信春公(武田氏9代当主、中興)


第42番 慧光山 定林寺
笛吹市八代町南747
日蓮宗
御首題

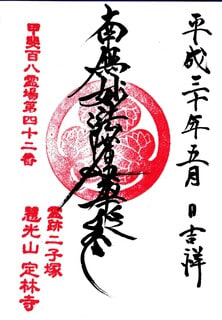
第43番 無碍山 瑜伽寺
笛吹市八代町永井1543
臨済宗向嶽寺派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第20番

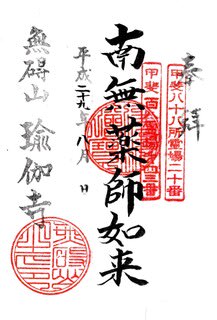
第44番 長国山 聖應寺
笛吹市境川町大黒坂1090
臨済宗向嶽寺派
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第21番
・黒坂五郎信光(寄進)

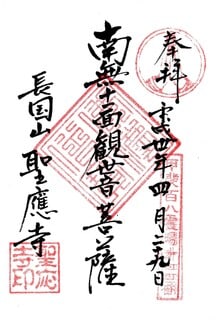
第45番 万亀山 向昌院
笛吹市境川町藤垈363
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩

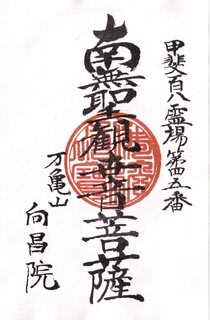
第46番 吉国山 龍華院
甲府市上曽根町4042
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第23番

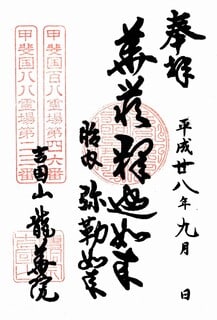
第47番 悟道山 安国寺
甲府市心経寺町1200
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
・足利尊氏公・直義兄弟(発願)

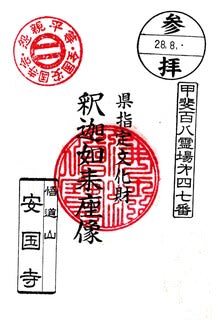
第48番 七覚山 円楽寺
甲府市右左口町4104
真言宗智山派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第24番
・源頼朝公(六角堂創建、祈願所)

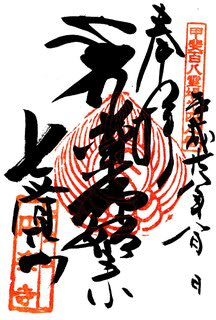
第49番 飯室山 大福寺
中央市大鳥居1621
真言宗智山派
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
他札所 甲斐国三十三番観音札所第11番
・飯室禅師光厳(武田信義公(武田氏初代当主)の孫、再興)、浅利与一義成(所縁)


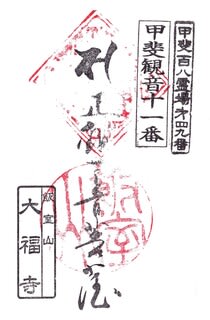
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第50番-1 豊田山 永源寺
中央市下河東880
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第86番、甲斐国三十三番観音札所第2番
・加藤梵玄(開基)


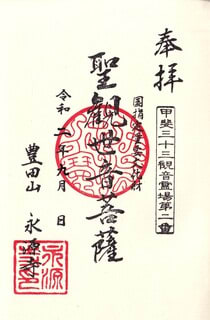
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第50番-2 富田山 歓盛院
中央市下三條88
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第85番
・秋山太郎光朝(開基)、富田対馬守範良(寄進)

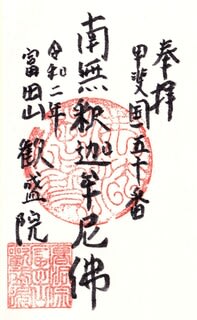
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
以前UPした記事ですが、ゆかりのある武将などのデータ(伝承含む)を加えてリニューアルUPします。
字数オーバーになったので、2つに分割します。
第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
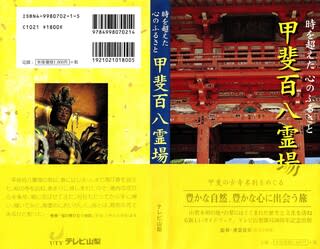
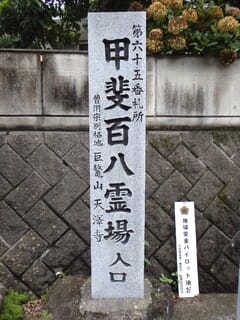
甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。
霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。
札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。
先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。
なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。
ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。
専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。
ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。
札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。
(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)
なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。
ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。
第51番 宝塔山 遠光寺
甲府市伊勢2-2-3
日蓮宗
御首題
・加賀美遠光(菩提寺)

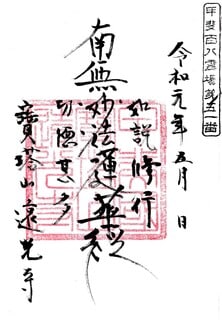
第52番 住吉山 千松院
甲府市相生3-8-9
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 府内観音札所第1番
・武田氏(水難除け祈願所)

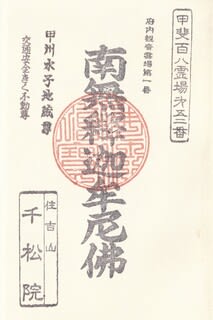
第53番 稲久山 一蓮寺
甲府市太田町5-16
単立
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第63番
・一条忠頼(武田信義公嫡男、菩提)、一条信長(再興)

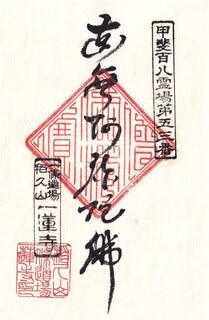
第54番 広教山 信立寺
甲府市若松町6-5
日蓮宗
御首題
・武田信虎公(武田氏15代当主、建立)

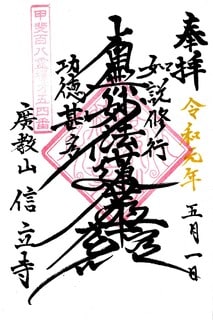
第55番 功徳山 尊躰寺
甲府市城東1-13-17
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 真向如来御尊影(阿弥陀如来)
・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、大久保長安(所縁)


第56番 法蓋山 東光寺
甲府市東光寺3-7-37
臨済宗妙心寺派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・新羅三郎義光公(建立、祈願所)、藍田上人(信玄公の伯父、住職)、武田義信公(墓所)、諏訪頼重(墓所)、柳沢家(甲府城主、寄進)


第57番 定林山 能成寺
甲府市東光寺町2153
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来

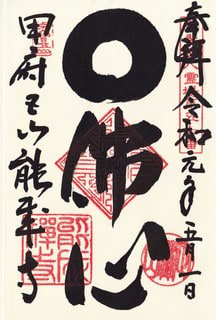
第58番 瑞雲山 長禅寺
甲府市愛宕町208
単立
御本尊 釈迦如来
札所本尊 不明
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第64番、甲斐国三十三番観音札所第9番、府内観音札所第9番
・大井夫人(信玄公の生母、墓所)

第59番 万年山 大泉寺
甲府市古府中町5015
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第62番
・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、信虎公、信玄公、勝頼公三代(墓所)、浅野家(外護)、柳沢家(外護)


第60番 瑞巌山 圓光院
甲府市岩窪町500-1
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
・三条夫人(信玄公正室、開基、墓所)、信玄公(守り本尊護持)

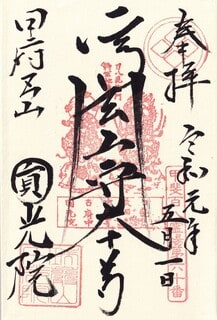
第61番 万松山 積翠寺
甲府市上積翠寺町984
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来(御朱印尊格:信玄公誕生寺)
・武田信玄公生誕の地

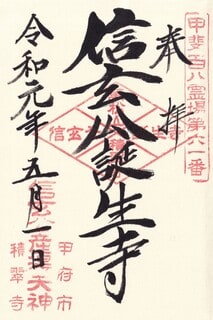
第62番 金剛福聚山 法泉寺
甲府市和田町2595-4
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第32番
・武田信武公(武田氏7代当主、開基、菩提寺)、武田勝頼公(菩提寺)


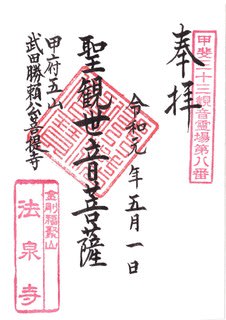
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第63番 福田山 塩澤寺
甲府市湯村3-17-2
真言宗智山派
御本尊 地蔵菩薩
札所本尊 地蔵菩薩
他札所 山の手七福神めぐり(大黒天)


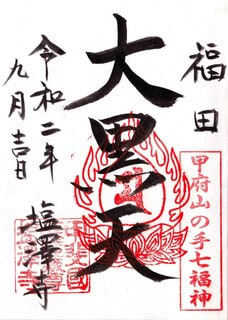
〔山の手七福神めぐり(大黒天)の御朱印〕
第64番 天台山 羅漢寺
甲斐市吉沢4835
曹洞宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 阿弥陀如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第55番
・源頼朝公(中興開基)

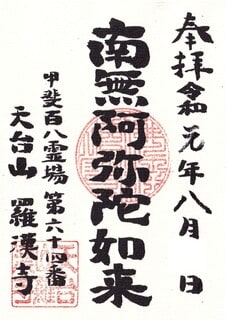
第65番 巨鼇山 天澤寺
甲斐市亀沢4609
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第54番
・飯富兵部少輔虎昌、山県三郎兵衛尉昌景兄弟(開基)


第66番 有富山 慈照寺
甲斐市竜王629
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来(釈迦三尊)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第84番
・諸角豊後守昌清(開基)

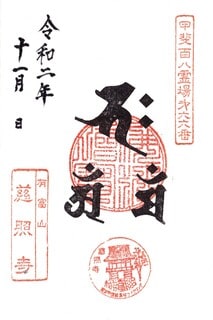
第67番 朝輝山 光照寺
甲斐市岩森1622-1
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・武田信虎公(武田氏15代当主、移転建立)

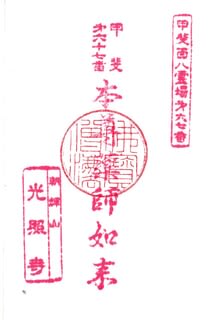
第68番 大竜山 満福寺
韮崎市穴山町1509
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・穴山四郎義武(菩提寺)、穴山氏(菩提寺)

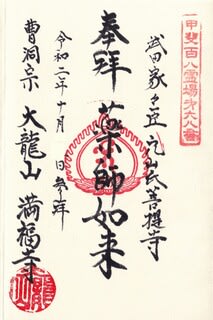
第69番 湯沢山 長泉寺
北杜市須玉町若神子1973
時宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・源義清公(開創)


第70番 陽谷山 正覚寺
北杜市須玉町若神子2739
曹洞宗
御本尊 虚空蔵菩薩
札所本尊 釈迦如来
・新羅三郎義光公(菩提寺)


第71番 津金山 海岸寺
北杜市須玉町上津金1222
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第48番、甲斐国三十三番観音札所第13番
・逸見忠俊(創建)、徳川家康公(寄進)



〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第72番 朝陽山 清光寺
北杜市長坂町大八田6600
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第47番、中部四十九薬師霊場第9番、甲斐七福神(布袋尊)
・逸見玄(黒)源太清光公(創建)

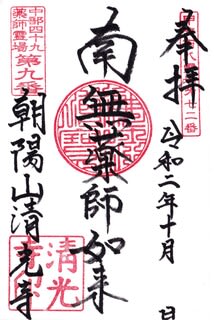
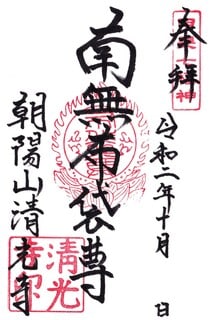
〔甲斐七福神(布袋尊)の御朱印〕
第73番 霊長山 清泰寺
北杜市白州町花水1461
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第46番
・逸見冠者刑部三郎義清公(開基)、逸見四郎清泰(開基)、武川衆曲淵氏(中興開基)

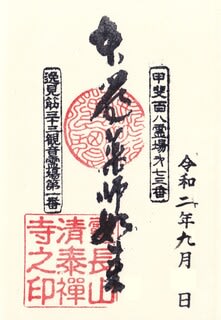
第74番 鳳凰山 高龍寺
北杜市武川町山高2480
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第44番、甲斐七福神(寿老人)
・山高越後守信之(開基)、山高氏(菩提寺)


第75番 大津山 実相寺
北杜市武川町山高2763
日蓮宗
御朱印揮毫 洗心
・波木井伊豆守実氏(改宗)、蔦木越前守(所縁)、一条治郎忠頼(所縁)

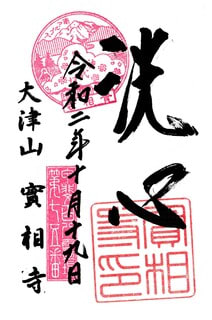
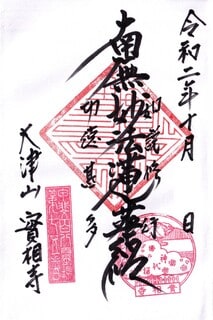
〔御首題〕
第76番 武隆山 常光寺
韮崎市清哲町青木2878
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・青木十郎太郎常光(武川衆、開基)

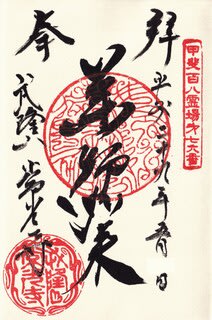
第77番 鳳凰山 願成寺
韮崎市神山町鍋山1111
曹洞宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 阿弥陀如来
他札所 武川筋三十三ヶ所観音霊場第33番
・武田信義公(武田氏初代当主、開基、墓所)

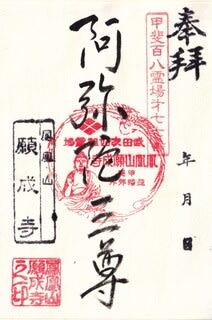
第78番 蕃竹山 大公寺
韮崎市旭上条南割1961
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第42番、武川筋三十三ヶ所観音霊場第22番
・一色太郎範氏(開基)

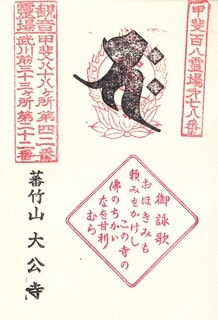
第79番 法永山 本照寺
韮崎市竜岡町下条東割493
日蓮宗
御首題

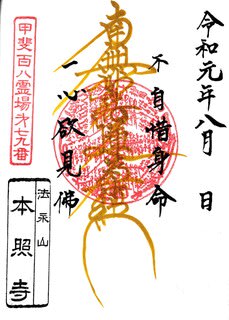
第80番 八田山 長谷寺
南アルプス市榎原442
真言宗智山派
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐国三十三番観音札所第4番

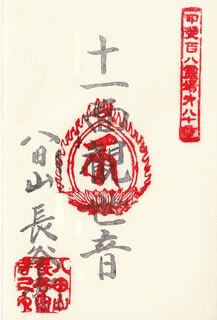

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第81番 大神山 伝嗣院
南アルプス市上宮地1424
曹洞宗
御本尊 釈迦如来(仏舎利)
札所本尊 不明
・今沢山城守(創建)

第82番 高峰山 妙了寺
南アルプス市上市之瀬724
日蓮宗
御首題
・武田信玄公(所縁)、田安家(所縁)

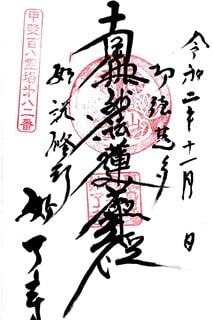
第83番 金剛山 明王寺
富士川町舂米2
真言宗智山派
御本尊 薬師如来
札所本尊 不動明王
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第37番
・武田氏(祈願寺)、徳川氏(祈願寺)

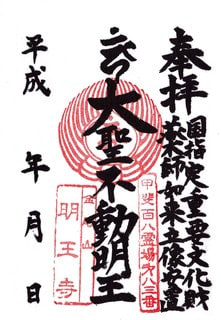
第84番 補陀山 南明寺
富士川町小林2247
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
・徳川家康公(所縁)

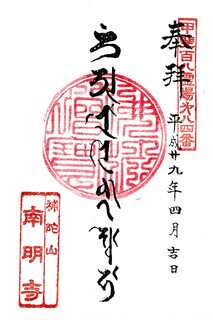
第85番 天澤山 深向院
南アルプス市宮沢1172
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・武田信光公(武田氏2代当主、外護)、大井春信(外護)


第86番 瑞雲山 古長禅寺
南アルプス市鮎沢505
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・大井夫人(信玄公の生母、菩提寺)、信玄公(参禅の地)


第87番 恵光山 長遠寺
南アルプス市鏡中条700
日蓮宗
御首題
・加賀美遠光(建立、祈願寺)、五味土佐守長遠(再興)

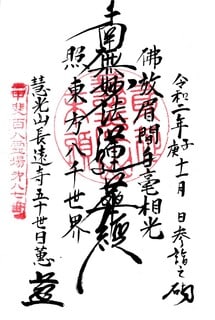
第88番 加賀美山 法善護国寺
南アルプス市加賀美3509
高野山真言宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 阿弥陀如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第88番
・加賀美遠光(館跡)、(加賀美)遠経(移築)、武田氏(祈願所)

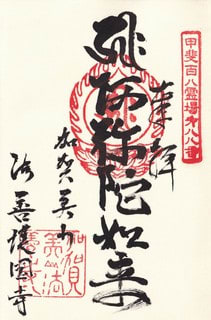
第89番 寿命山 昌福寺
富士川町青柳483
日蓮宗
御首題

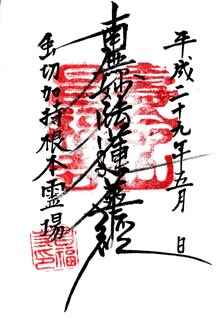
第90番 最勝山 最勝寺
富士川町最勝寺2016
高野山真言宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第36番

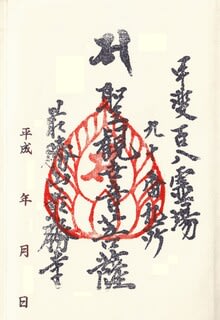
第91番 徳栄山 妙法寺
富士川町小室3063
日蓮宗
御首題

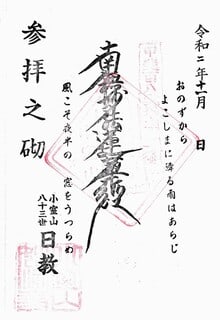
第92番 恵命山 蓮華寺
富士川町鰍沢2321
日蓮宗
御首題

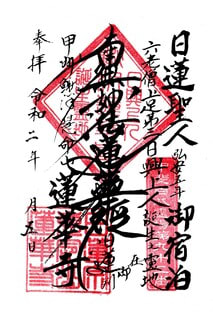
第93番 霊亀山 永泰寺
甲府市古関町1555
臨済宗建長寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第25番
・上九一色衆?


第94番 市瀬山 光勝寺
市川三郷町上野4308
高野山真言宗
御本尊 千手観世音菩薩
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第27番、甲斐国三十三番観音札所第3番、甲斐西八代七福神(大黒天)

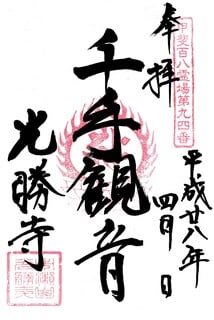
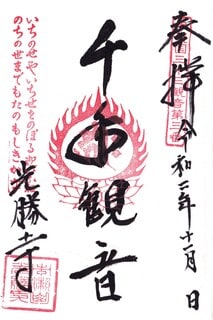
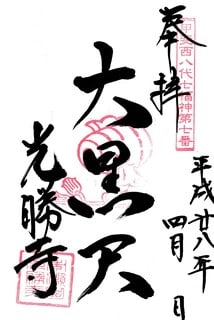
【写真 上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
【写真 下(右)】 〔甲斐西八代七福神(大黒天)の御朱印〕
第95番 河浦山 薬王寺
市川三郷町上野199
高野山真言宗
御本尊 毘沙門天
札所本尊 毘沙門天
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第28番、甲斐国三十三番観音札所第1番、甲斐西八代七福神(恵比寿大神)
・八之宮良純親王(所縁)、源義清公(寄進)、武田信玄公(外護)、徳川家康公(外護)

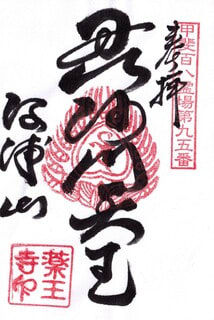


【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
【下(右)】 〔甲斐西八代七福神(恵比寿)の御朱印〕
第96番 金剛山 宝寿院
市川三郷町市川大門5711
高野山真言宗
御本尊 虚空蔵菩薩
札所本尊 虚空蔵菩薩
他札所 甲斐西八代七福神(福禄寿)

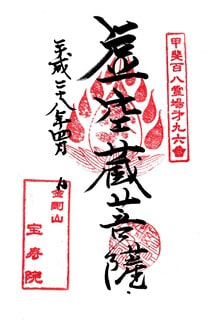
第97番 巌龍山 慈観寺
身延町道143
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩


第98番 龍湖山 方外院
身延町瀬戸135
曹洞宗
御本尊 如意輪観世音菩薩
札所本尊 如意輪観世音菩薩
他札所 甲斐国三十三番観音札所第27番
・武田信玄公(所縁)

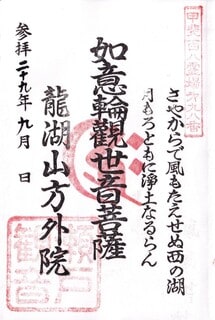
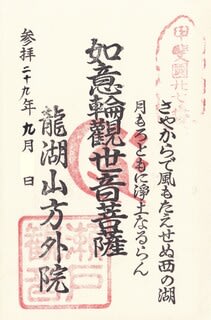
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第99番 見命山 永寿庵
身延町古関3772
曹洞宗
御本尊 五智如来
札所本尊 五智如来

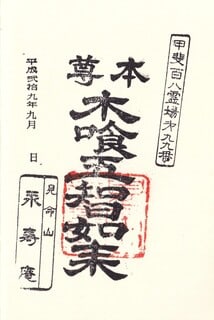
第100番 三守皇山 長光王院 大聖明王寺
身延町八日市場539
真言宗醍醐派
御本尊 不動明王
札所本尊 不動明王
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第35番
・新羅三郎義光公(開基)、加賀美遠光(所縁)

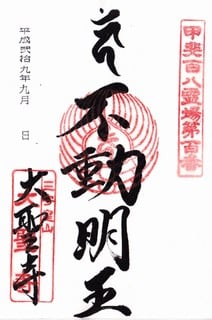
第101番 法喜山 上澤寺
身延町下山279
日蓮宗
御首題揮毫 是好良薬

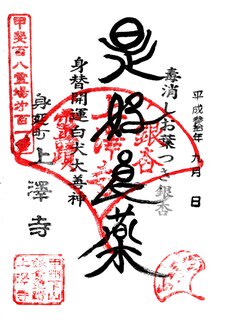
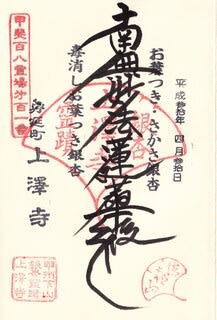
〔御首題〕
第102番 正福寿山 南松院
身延町下山3221
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・穴山信君(梅雪、創建)、水戸徳川家(外護)

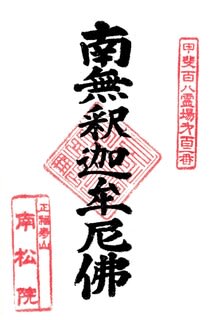
第103番 華嶽山 龍雲寺
身延町下山4614
曹洞宗
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第34番
・穴山信綱(創建、菩提寺)

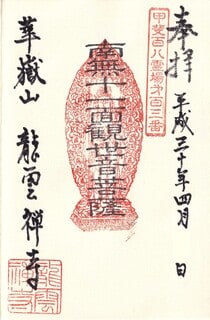
第104番 大野山 本遠寺
身延町大野839
日蓮宗
御朱印揮毫 観察自在
・お万の方(家康公側室、寄進)


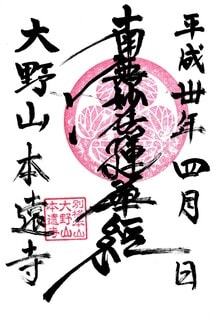
〔御首題〕
第105番 南部山 円蔵院
南部町南部7576
臨済宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
・穴山信友(建立、墓所)

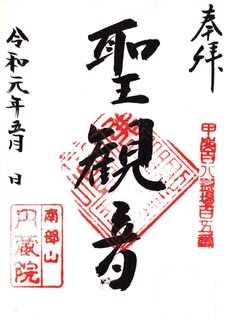
第106番 正住山 内船寺
南部町内船3599
日蓮宗
御首題
・四条金吾頼基夫妻(所縁)


第107番 福士山 最恩寺
南部町福士23502
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・武田氏(寄進)、見性院(穴山梅雪夫人、開基、子息・勝千代の菩提寺)

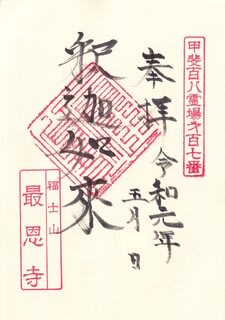
第108番 身延山 久遠寺
身延町身延3567
日蓮宗総本山
御朱印揮毫 妙法
・波木井実長(寄進)

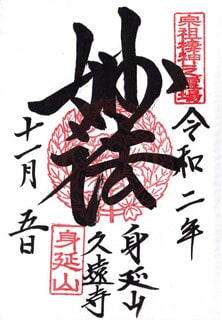
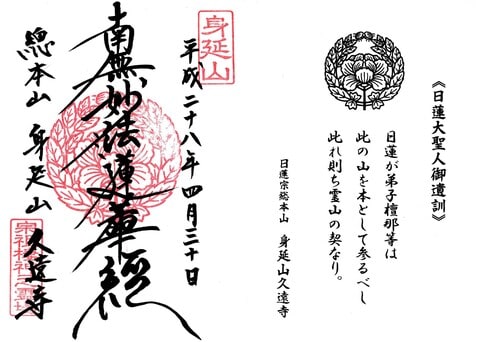
御首題
字数オーバーになったので、2つに分割します。
第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
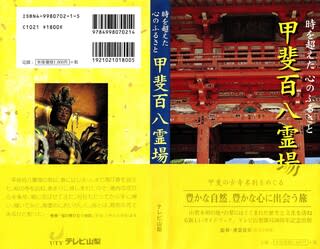
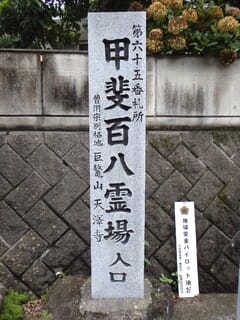
甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。
霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。
札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。
先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。
なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。
ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。
専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。
ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。
札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。
(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)
なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。
ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。
第51番 宝塔山 遠光寺
甲府市伊勢2-2-3
日蓮宗
御首題
・加賀美遠光(菩提寺)

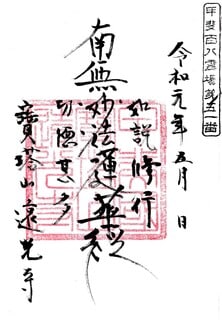
第52番 住吉山 千松院
甲府市相生3-8-9
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 府内観音札所第1番
・武田氏(水難除け祈願所)

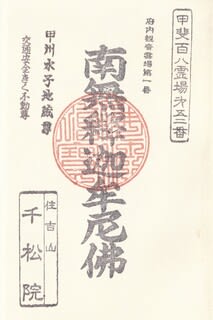
第53番 稲久山 一蓮寺
甲府市太田町5-16
単立
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第63番
・一条忠頼(武田信義公嫡男、菩提)、一条信長(再興)

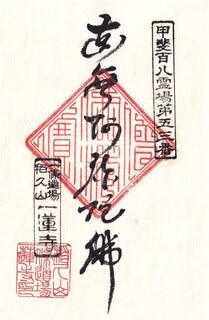
第54番 広教山 信立寺
甲府市若松町6-5
日蓮宗
御首題
・武田信虎公(武田氏15代当主、建立)

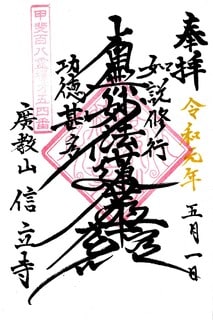
第55番 功徳山 尊躰寺
甲府市城東1-13-17
浄土宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 真向如来御尊影(阿弥陀如来)
・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、大久保長安(所縁)


第56番 法蓋山 東光寺
甲府市東光寺3-7-37
臨済宗妙心寺派
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・新羅三郎義光公(建立、祈願所)、藍田上人(信玄公の伯父、住職)、武田義信公(墓所)、諏訪頼重(墓所)、柳沢家(甲府城主、寄進)


第57番 定林山 能成寺
甲府市東光寺町2153
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来

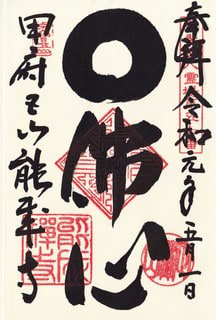
第58番 瑞雲山 長禅寺
甲府市愛宕町208
単立
御本尊 釈迦如来
札所本尊 不明
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第64番、甲斐国三十三番観音札所第9番、府内観音札所第9番
・大井夫人(信玄公の生母、墓所)

第59番 万年山 大泉寺
甲府市古府中町5015
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第62番
・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、信虎公、信玄公、勝頼公三代(墓所)、浅野家(外護)、柳沢家(外護)


第60番 瑞巌山 圓光院
甲府市岩窪町500-1
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
・三条夫人(信玄公正室、開基、墓所)、信玄公(守り本尊護持)

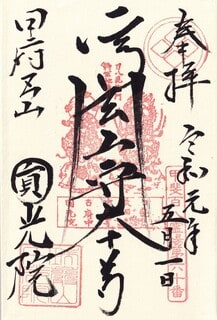
第61番 万松山 積翠寺
甲府市上積翠寺町984
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来(御朱印尊格:信玄公誕生寺)
・武田信玄公生誕の地

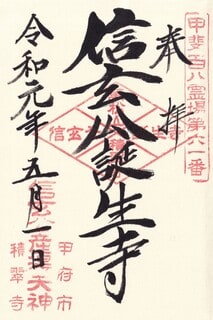
第62番 金剛福聚山 法泉寺
甲府市和田町2595-4
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第32番
・武田信武公(武田氏7代当主、開基、菩提寺)、武田勝頼公(菩提寺)


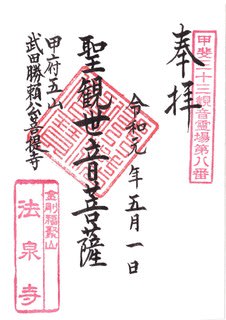
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第63番 福田山 塩澤寺
甲府市湯村3-17-2
真言宗智山派
御本尊 地蔵菩薩
札所本尊 地蔵菩薩
他札所 山の手七福神めぐり(大黒天)


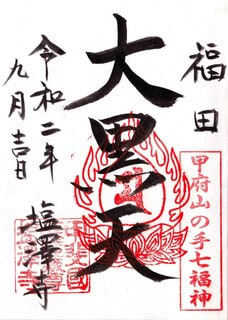
〔山の手七福神めぐり(大黒天)の御朱印〕
第64番 天台山 羅漢寺
甲斐市吉沢4835
曹洞宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 阿弥陀如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第55番
・源頼朝公(中興開基)

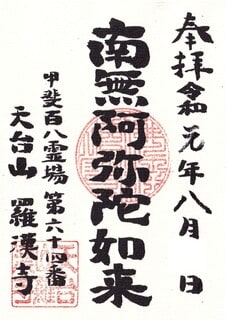
第65番 巨鼇山 天澤寺
甲斐市亀沢4609
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第54番
・飯富兵部少輔虎昌、山県三郎兵衛尉昌景兄弟(開基)


第66番 有富山 慈照寺
甲斐市竜王629
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来(釈迦三尊)
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第84番
・諸角豊後守昌清(開基)

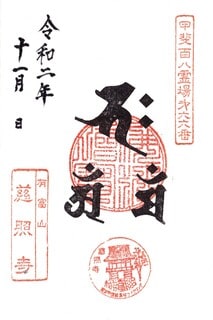
第67番 朝輝山 光照寺
甲斐市岩森1622-1
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・武田信虎公(武田氏15代当主、移転建立)

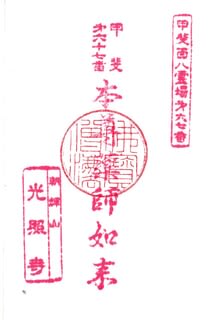
第68番 大竜山 満福寺
韮崎市穴山町1509
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・穴山四郎義武(菩提寺)、穴山氏(菩提寺)

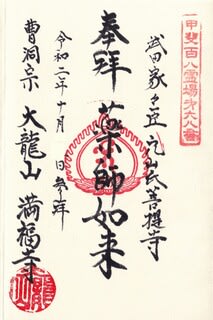
第69番 湯沢山 長泉寺
北杜市須玉町若神子1973
時宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)
・源義清公(開創)


第70番 陽谷山 正覚寺
北杜市須玉町若神子2739
曹洞宗
御本尊 虚空蔵菩薩
札所本尊 釈迦如来
・新羅三郎義光公(菩提寺)


第71番 津金山 海岸寺
北杜市須玉町上津金1222
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦如来
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第48番、甲斐国三十三番観音札所第13番
・逸見忠俊(創建)、徳川家康公(寄進)



〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第72番 朝陽山 清光寺
北杜市長坂町大八田6600
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第47番、中部四十九薬師霊場第9番、甲斐七福神(布袋尊)
・逸見玄(黒)源太清光公(創建)

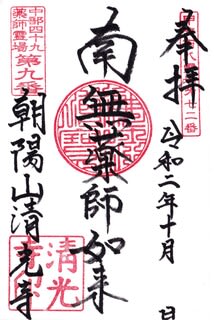
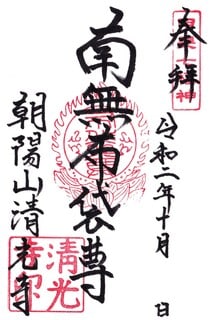
〔甲斐七福神(布袋尊)の御朱印〕
第73番 霊長山 清泰寺
北杜市白州町花水1461
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第46番
・逸見冠者刑部三郎義清公(開基)、逸見四郎清泰(開基)、武川衆曲淵氏(中興開基)

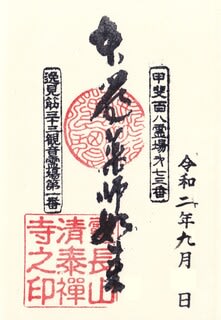
第74番 鳳凰山 高龍寺
北杜市武川町山高2480
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第44番、甲斐七福神(寿老人)
・山高越後守信之(開基)、山高氏(菩提寺)


第75番 大津山 実相寺
北杜市武川町山高2763
日蓮宗
御朱印揮毫 洗心
・波木井伊豆守実氏(改宗)、蔦木越前守(所縁)、一条治郎忠頼(所縁)

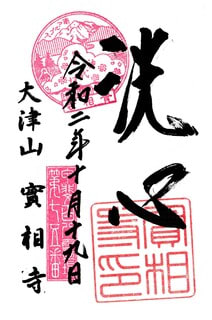
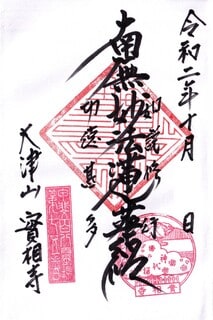
〔御首題〕
第76番 武隆山 常光寺
韮崎市清哲町青木2878
曹洞宗
御本尊 薬師如来
札所本尊 薬師如来
・青木十郎太郎常光(武川衆、開基)

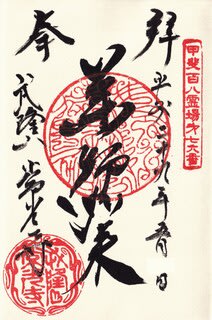
第77番 鳳凰山 願成寺
韮崎市神山町鍋山1111
曹洞宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 阿弥陀如来
他札所 武川筋三十三ヶ所観音霊場第33番
・武田信義公(武田氏初代当主、開基、墓所)

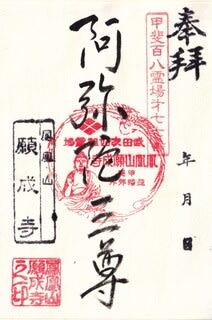
第78番 蕃竹山 大公寺
韮崎市旭上条南割1961
曹洞宗
御本尊 釈迦如来
札所本尊 釈迦如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第42番、武川筋三十三ヶ所観音霊場第22番
・一色太郎範氏(開基)

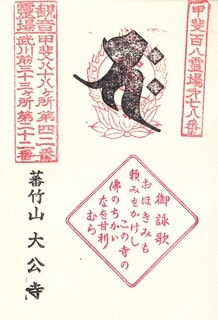
第79番 法永山 本照寺
韮崎市竜岡町下条東割493
日蓮宗
御首題

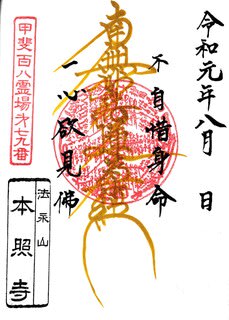
第80番 八田山 長谷寺
南アルプス市榎原442
真言宗智山派
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐国三十三番観音札所第4番

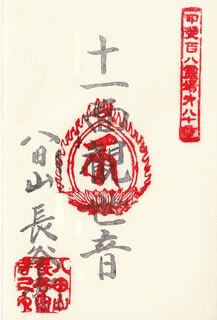

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第81番 大神山 伝嗣院
南アルプス市上宮地1424
曹洞宗
御本尊 釈迦如来(仏舎利)
札所本尊 不明
・今沢山城守(創建)

第82番 高峰山 妙了寺
南アルプス市上市之瀬724
日蓮宗
御首題
・武田信玄公(所縁)、田安家(所縁)

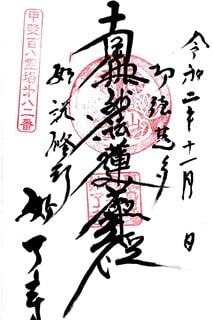
第83番 金剛山 明王寺
富士川町舂米2
真言宗智山派
御本尊 薬師如来
札所本尊 不動明王
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第37番
・武田氏(祈願寺)、徳川氏(祈願寺)

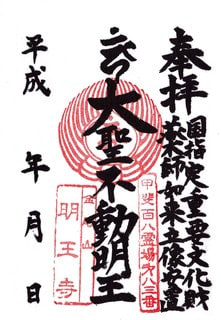
第84番 補陀山 南明寺
富士川町小林2247
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
・徳川家康公(所縁)

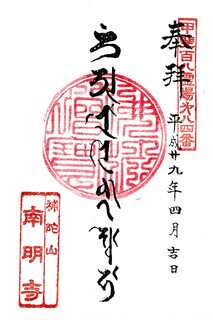
第85番 天澤山 深向院
南アルプス市宮沢1172
曹洞宗
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・武田信光公(武田氏2代当主、外護)、大井春信(外護)


第86番 瑞雲山 古長禅寺
南アルプス市鮎沢505
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・大井夫人(信玄公の生母、菩提寺)、信玄公(参禅の地)


第87番 恵光山 長遠寺
南アルプス市鏡中条700
日蓮宗
御首題
・加賀美遠光(建立、祈願寺)、五味土佐守長遠(再興)

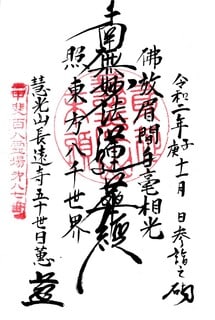
第88番 加賀美山 法善護国寺
南アルプス市加賀美3509
高野山真言宗
御本尊 阿弥陀如来
札所本尊 阿弥陀如来
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第88番
・加賀美遠光(館跡)、(加賀美)遠経(移築)、武田氏(祈願所)

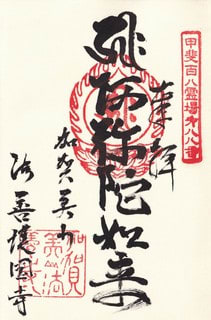
第89番 寿命山 昌福寺
富士川町青柳483
日蓮宗
御首題

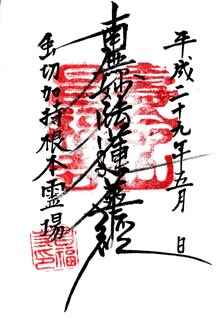
第90番 最勝山 最勝寺
富士川町最勝寺2016
高野山真言宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第36番

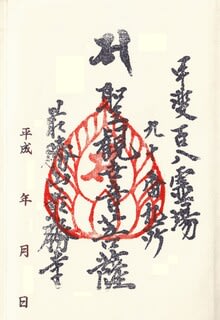
第91番 徳栄山 妙法寺
富士川町小室3063
日蓮宗
御首題

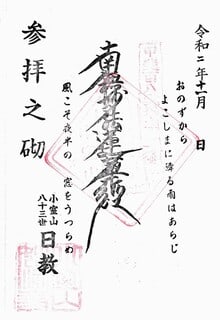
第92番 恵命山 蓮華寺
富士川町鰍沢2321
日蓮宗
御首題

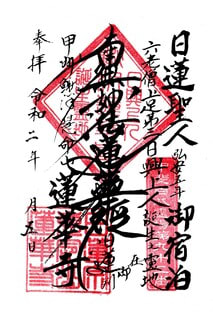
第93番 霊亀山 永泰寺
甲府市古関町1555
臨済宗建長寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第25番
・上九一色衆?


第94番 市瀬山 光勝寺
市川三郷町上野4308
高野山真言宗
御本尊 千手観世音菩薩
札所本尊 千手観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第27番、甲斐国三十三番観音札所第3番、甲斐西八代七福神(大黒天)

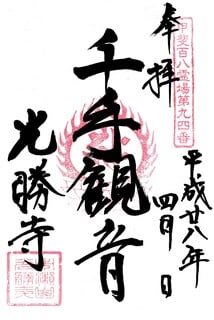
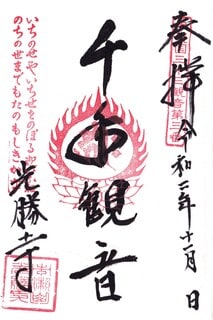
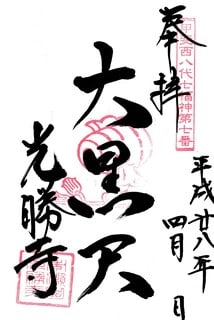
【写真 上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
【写真 下(右)】 〔甲斐西八代七福神(大黒天)の御朱印〕
第95番 河浦山 薬王寺
市川三郷町上野199
高野山真言宗
御本尊 毘沙門天
札所本尊 毘沙門天
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第28番、甲斐国三十三番観音札所第1番、甲斐西八代七福神(恵比寿大神)
・八之宮良純親王(所縁)、源義清公(寄進)、武田信玄公(外護)、徳川家康公(外護)

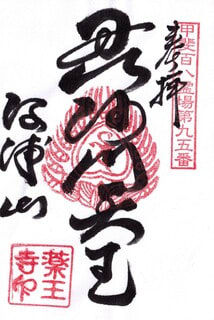


【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
【下(右)】 〔甲斐西八代七福神(恵比寿)の御朱印〕
第96番 金剛山 宝寿院
市川三郷町市川大門5711
高野山真言宗
御本尊 虚空蔵菩薩
札所本尊 虚空蔵菩薩
他札所 甲斐西八代七福神(福禄寿)

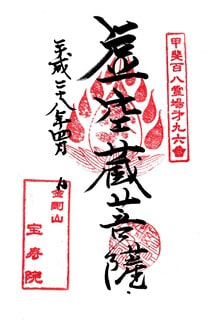
第97番 巌龍山 慈観寺
身延町道143
曹洞宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩


第98番 龍湖山 方外院
身延町瀬戸135
曹洞宗
御本尊 如意輪観世音菩薩
札所本尊 如意輪観世音菩薩
他札所 甲斐国三十三番観音札所第27番
・武田信玄公(所縁)

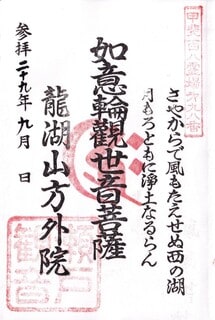
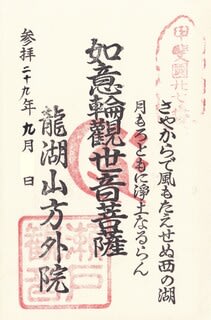
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
第99番 見命山 永寿庵
身延町古関3772
曹洞宗
御本尊 五智如来
札所本尊 五智如来

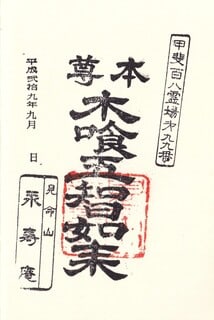
第100番 三守皇山 長光王院 大聖明王寺
身延町八日市場539
真言宗醍醐派
御本尊 不動明王
札所本尊 不動明王
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第35番
・新羅三郎義光公(開基)、加賀美遠光(所縁)

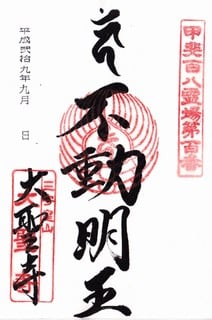
第101番 法喜山 上澤寺
身延町下山279
日蓮宗
御首題揮毫 是好良薬

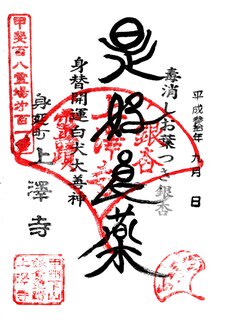
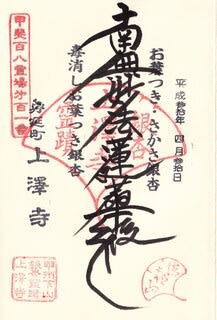
〔御首題〕
第102番 正福寿山 南松院
身延町下山3221
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・穴山信君(梅雪、創建)、水戸徳川家(外護)

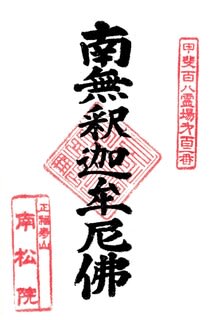
第103番 華嶽山 龍雲寺
身延町下山4614
曹洞宗
御本尊 十一面観世音菩薩
札所本尊 十一面観世音菩薩
他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第34番
・穴山信綱(創建、菩提寺)

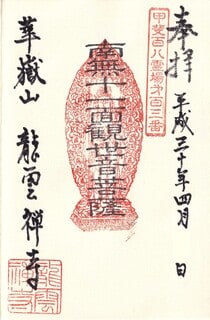
第104番 大野山 本遠寺
身延町大野839
日蓮宗
御朱印揮毫 観察自在
・お万の方(家康公側室、寄進)


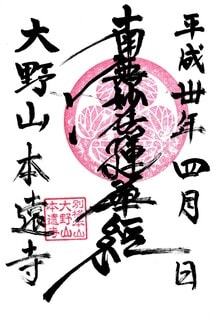
〔御首題〕
第105番 南部山 円蔵院
南部町南部7576
臨済宗
御本尊 聖観世音菩薩
札所本尊 聖観世音菩薩
・穴山信友(建立、墓所)

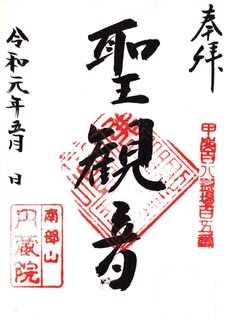
第106番 正住山 内船寺
南部町内船3599
日蓮宗
御首題
・四条金吾頼基夫妻(所縁)


第107番 福士山 最恩寺
南部町福士23502
臨済宗妙心寺派
御本尊 釈迦牟尼佛
札所本尊 釈迦牟尼佛
・武田氏(寄進)、見性院(穴山梅雪夫人、開基、子息・勝千代の菩提寺)

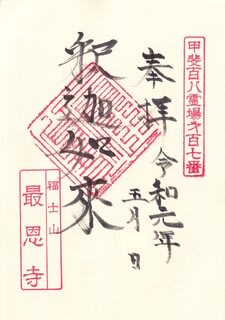
第108番 身延山 久遠寺
身延町身延3567
日蓮宗総本山
御朱印揮毫 妙法
・波木井実長(寄進)

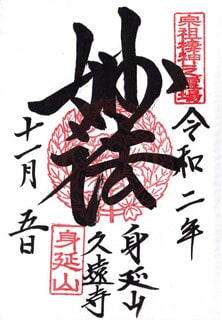
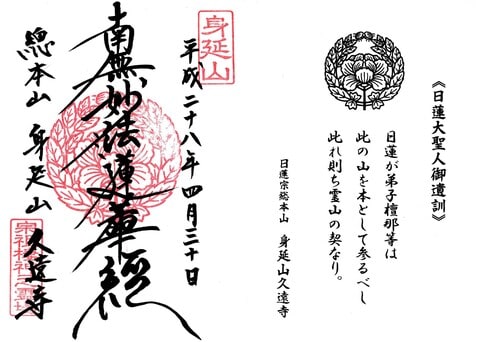
御首題
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
2020/11/15 補足UP・2021/01/31・2022/11/02 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(前編A)
19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)
20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)
21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)
19.船尾山 等覚院 柳澤寺
公式Web
榛東村山子田2535
天台宗
御本尊:千手千眼観世音菩薩 (釈迦三尊)
札所:新上州三十三観音霊場第25番、東国花の寺百ヶ寺霊場第34番(群馬第8番)、関東九十一薬師霊場第46番、関東百八地蔵尊霊場第34番、群馬郡三十三観音霊場第2番、上州七福神(毘沙門天)
札所本尊:千手観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第25番)、千手観世音菩薩(東国花の寺百ヶ寺霊場第34番(群馬第8番))、薬師如来(関東九十一薬師霊場第46番)、地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第34番)、毘沙門天(上州七福神)




榛名東麓屈指の古刹で、複数の札所を兼ねているこのお寺は複雑な開山由緒をもたれます。
公式Webにある「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院 息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山」というのが当初の開山伝承のようです。
その後「神道集」の「上野国桃井郷上村八ヶ権現の事」、およびこれをベースとして成立した「船尾山縁起」が広まります。
「船尾山縁起」はデリケートな内容で抜粋引用がはばかられ、全文引用すると長くなるのでこちら(公式Web)をご覧ください。
近世にはこの地との関わりがうすい千葉氏が主役で、その千葉氏が悲劇的な結末をもってその姿を隠してしまうというこの伝承については、その背景として様々な説が打ち出されています。
「6.三鈷山 吉祥院 妙見寺」にも千葉氏にまつわる伝承が残りますが、柳澤寺は「妙見院 息災寺」を通じて妙見寺と相応のつながりがあったのでは。
それにしても、このエリアは「神道集」との関わりが深いです。
神道集(しんとうしゅう)は、南北朝時代中期に成立とされている十巻五十条からなる説話集で、安居院唱導教団(あぐいしょうどうきょうだん)の著作とされます。
安居院唱導教団は当時の仏教宗派のひとつとされ、詳細は不明ですが伊勢神道(度会神道、神本仏迹説系)との関連を指摘する説がみられます。
内容はすこぶる劇的でスペクタクル。アニメや映画になじみそう。
主に関東(とくに上州)の神社について、その成り立ちと本地仏(神本仏迹説からすると垂迹仏?)が詳細に記されています。
(いわゆる本地譚・本地物/神体の前生説話のひとつとされる。)
登場される神々はかならずしも現在の主祀神ではなく、主にその土地とつながりのふかい神々です。
生身の人間が説話を介して一気に神となる不思議なイメージ漂う内容ですが、これは神本仏迹系本地譚の特徴なのかもしれません。
(「権現系」ではなく「明神系」、神名も大明神を名乗られる例が多い。)
この「神道集」があることで上州の寺社はダイナミックにつながり、寺社巡りに興を添えています。
「上野国桃井郷上村八ヶ権現の事」(神道集第四十七)は、こちらで紹介されています。
「神道集」と「船尾山縁起」はともに凄絶な展開で内容は酷似していますが、「神道集」の主役は上野国国司の桃苑左大将家光。
千葉氏が主役となる「船尾山縁起」の成立は「神道集」から約二百年後とされるので、この二百年のあいだに千葉氏にかかわる大きなできごとがあったのかもしれません。
ちなみに、柳澤寺そばには平常将大明神を主祭神とする常将神社が鎮座しています。
寺伝(公式Web)によると、延暦寺の直末として中世には学僧も多く輩出、戦国時代末の動乱を経て、江戸時代に入は天海僧正、高崎城主・安藤右京進などの尽力により朱印地三十石を賜ったとされる名刹です。
背後に榛名山を背負い、眼下に利根川が流れる開けた立地に名刹にふさわしい広大な境内を擁します。
風格ある二層丹塗りの楼門、御本尊、千手千眼観世音菩薩が御座す本堂(観音堂)、寄棟平屋造りの風趣ある客殿(釈迦三尊、薬師如来、不動明王、毘沙門天などが御座)、県内最古とされる鐘楼、阿弥陀堂、薬師堂、平成10年建立の五重塔など壮麗な伽藍を連ねます。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 五重塔
本堂(観音堂)は右手に離れてあるのでややわかりにくいですが、新上州三十三観音と東国花の寺百ヶ寺霊場の札所はこちらになります。
納経所(御朱印授与所)は客殿左手の庫裡、ないし客殿が開いているときは客殿内となります。
複数の札所を兼ねているので手慣れたご対応ですが、目的の御朱印(霊場)をはっきり申告する必要があります。
それでは、それぞれの霊場の御朱印を紹介していきます。
なお、Web情報からすると霊場申告なしの御朱印は新上州三十三観音霊場のものとなる模様。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

本堂(観音堂)
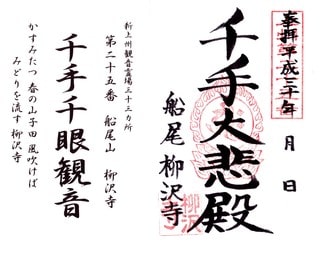

【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
札所本尊の千手千眼観世音菩薩は境内右手の本堂(観音堂)に御座します。
元禄年間の様式を残すとされる、方六間の木造青銅葺きの建物で古趣を湛えています。
中央に札所本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。
右上に「上州第二十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳の御朱印も同様の構成です。
客殿にて御朱印帳に書入れ、専用納経帳御朱印は庫裡にていただきました。
〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

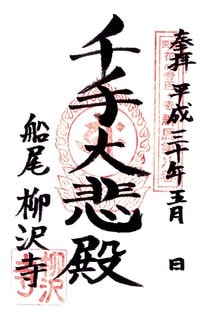
指定花種はサクラ(ソメイヨシノ)ですが、サツキも有名なようです。
この霊場は御本尊が札所本尊となるケースが多いですが、やはり本堂御本尊の千手千眼観世音菩薩の御朱印でした。
なので、霊場の参拝所は境内右手の本堂(観音堂)となります。
なお、公式Webには客殿の欄に「本尊釈迦三尊像」の記載がありますが、本堂御本尊=千手観世音菩薩、客殿御本尊=釈迦三尊という位置づけかもしれません。
中央に札所本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。
右上に「東国花の寺百ヶ寺群馬第八番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。(主印が千手観世音菩薩の御影印となる場合もあるようです。)
霊場専用納経帳用の書置御朱印もあるようですが、庫裡にて御朱印書入れをいただきました。
〔 関東九十一薬師霊場の御朱印 〕

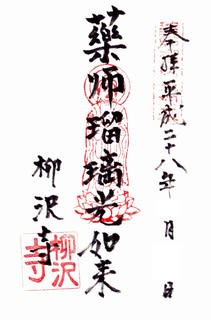
【写真 上(左)】 本堂(観音堂)参道右手の真新しい建物が薬師堂の覆堂?
【写真 下(右)】 御朱印
御座所をお尋ねするのを忘れましたが、霊場ガイドブックによると、札所本尊は本堂(観音堂)脇の唐破風宮殿造の薬師堂に御座す秘仏、船尾薬師如来(江戸初期、二尺一寸木彫座像)で、往昔より眼の病、万病平癒の守護佛として信仰されてきたとのこと。
中央に薬師如来立像の御影印と「薬師瑠璃光如来」の揮毫。右上に「薬師瑠璃光如来」の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。
〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 札所本尊の延命地蔵尊
【写真 下(右)】 子授地蔵尊
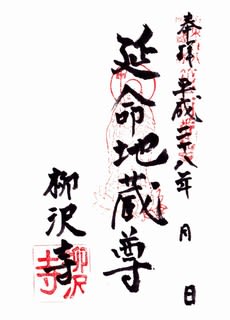
札所本尊御座所は、「仁王門から本堂(観音堂)に向かう途中の石像のお地蔵さま」との由。
霊場ガイドブックによると、「仁王門から観音堂に通ずる中段境内に近年建立された”延命地蔵尊”(石佛立像一丈三尺)」とあります。
鐘楼脇には元禄期建立とされる石佛立像の”子授地蔵尊”も御座しますが、ガイドには札所本尊欄に「延命地蔵尊」と明記されているので、こちらが札所本尊と思われます。
関東百八地蔵尊霊場の札所本尊は露仏も多く、ガイドブックがないとこのように特定しにくいケースがあります。
中央に地蔵菩薩立像の御影印と「延命地蔵尊」の揮毫。右上に「関東百八地蔵尊第三四番札所」の札所印。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。
〔 上州七福神(毘沙門天)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 殿の扁額と上州七福神の札所板

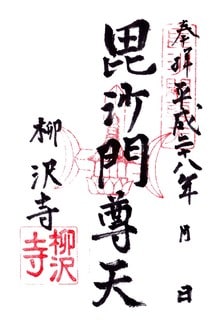
【写真 上(左)】 毘沙門天の説明板
【写真 下(右)】 御朱印
上州七福神は県内全域にまたがる広域の七福神で、通年でどれだけ参拝客がいるかはわかりませんが、霊場会があり御朱印帳書入れもおおむねOKのようです。
客殿に御座す、毘沙門天が札所本尊です。
中央に法具(鈷杵?)を背景にした宝塔(毘沙門天の持物)の印と「毘沙門尊天」の揮毫。
右上に「毘沙門尊天」の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。
20.五徳山 無量寿院 水澤寺(水澤観音)
公式Web
渋川市伊香保町水沢214
天台宗
御本尊:十一面千手観世音菩薩
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第16番、新上州三十三観音霊場別格、関東百八地蔵尊霊場第33番、群馬郡三十三観音霊場第3番
札所本尊:十一面千手観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第16番)、十一面千手観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)、地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第33番)、十一面千手観世音菩薩(群馬郡三十三観音霊場第3番)


通称、水澤観音として親しまれる水澤寺は、上州を代表する天台宗の古刹です。
坂東三十三観音霊場の第十六番礼所でもあり、広く巡拝客を集めています。
寺伝(公式Webより)には、「千三百有余年の昔、推古天皇・持統天皇の勅願による、高麗の高僧恵灌僧正の開基であり、五徳山 水澤寺の名称は、推古天皇の御宸筆(ごしんぴつ)の額名によるものです。
ご本尊は国司高野辺家成公の三女 伊香保姫のご持仏の十一面千手観世音菩薩であり、霊験あたらたかなること、特に七難即滅七福即生のご利益顕著です。」とあります。
この伊香保姫は、くだんの「神道集」でも大きくとりあげられています。
後段の伊香保神社の縁起にもかかわる内容なので、すこしく長くなりますが、第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事、第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事から抜粋引用してみます。
■ 第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事
人皇十八代履中天皇の御代、高野辺左大将家成は無実の罪で上野国深栖郷に流され、その地で奥方との間に一人の若君と三人の姫君をもうけた。
奥方が亡くなった後、左大将は信濃国更科郡の地頭・更科大夫宗行の娘を後妻とし、その間に一人の娘をもうけた。
その後左大将は罪を許されて都へ戻り、上野国の国司に任じられ、若君も都へ上り、帝から仕官を許された。
三人の姫君のうち、姉姫は淵名次郎家兼に預けられ淵名姫、次の姫は大室太郎兼保に預けられ赤城御前、末姫は群馬郡の地頭・伊香保大夫伊保に預けられて伊香保姫といった。
三人の姫君は見目麗しく、心根も優しく、相応の婿を選んで嫁ぐこととなったが、継母はこれに嫉妬し、弟の更科次郎兼光を唆して三人の姫君を亡きものにしようとした。
兼光は兵を興して淵名次郎と大室太郎を捕らえ、斬り殺した。
次に、淵名姫と淵名の女房を捕らえて亡きものにした。
その後、大室の宿所に押し寄せたが、赤城御前と大室の女房は赤城山へ逃れた。有馬郷の伊香保大夫は守りを固めて迎え撃ったので、伊香保姫は無事だった。
〔姉姫淵名姫は淵名明神に、赤城御前は唵佐羅摩女(赤城沼の龍神)の跡を継いで赤城大明神として顕れたと「神道集」は伝えますが、詳細は別稿に譲ります。〕
上野国の国司に任じられた左大将は、淵名姫の死を知ると姫の跡を追って身を投げた。
中納言となっていた若君はこれを知ると東国へ下り、上野国の国司となって更級次郎父子を捕らえ仇を討つた。
国司は無事であった伊香保姫と再会し、国司の職を伊香保姫に譲った。
伊香保姫は兄(国司高野辺中納言)の奥方の弟にあたる高光少将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤められた。
伊香保大夫は目代となり、自在丸という地に御所を建てた。当国の惣社は伊香保姫の御所の跡である。
■ 第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事(話の内容が第四十と整合しない箇所があります。)
伊香保大明神は赤城大明神の妹で、高野辺大将の三番目の姫君である。
高野辺中納言の奥方の弟の高光中将と結婚して、一人の姫君をもうけた。
伊香保姫と高光中将は上野国国司を他に譲ったあと、有馬の伊香保大夫のもとで暮らしていた。
伊香保姫は淵名神社へ参詣の折、現在の国司である大伴大将と出会い、伊香保姫の美貌に懸想した大伴大将は、国司の威勢で姫を奪おうとした。
伊香保大夫は九人の息子と三人の婿を将として防戦したが劣勢となり、伊香保姫とその姫君、女房と娘の石童御前・有御前を連れて児持山に入った。負傷した高光中将は行方知れずとなった。
伊香保太夫は上京して状況を帝に奏聞すると、帝は伊香保姫に国司の職を持たせ、伊香保太夫を目代とされた。
また、高光中将(と伊香保姫)の姫君を上京させて更衣とされ、皇子が生まれたので国母として仰がれた。
伊香保太夫は伊香保山の東麓の岩滝沢の北岸に寺を建てて、高光中将の遺骨を納めた。
月日は流れて伊香保太夫とその女房は亡くなり、その娘の石童御前と有御前は伊香保姫と暮らしていた。
高光中将の甥の恵美僧正が別当になって寺はますます栄え、岩滝沢に因んで寺号を水沢寺とした。
伊香保姫は夫高光中将の形見の千手観世音菩薩を寺の本尊に祀り、二人の御前とともに亡き人々の菩提を弔ったところ、高光中将・伊香保大夫夫妻とその一族があらわれて千手観世音菩薩に礼拝した。
伊香保大夫の女房は 「あなた方の千手経読誦の功徳により、伊香保山の神や伊香保沼(榛名湖)の龍神・吠尸羅摩女に大切にされ、我らは悟りを開くことができました。
今は高光中将を主君とし、その眷属として崇められています」と云った。
夢から覚めた伊香保姫は「沼に身を投げて、龍宮城の力で高光中将の所に行こうと思います」と云って伊香保沼に身を投げた。石童御前と有御前もその後を追った。
恵美僧正は三人の遺骨を本堂の仏壇に下に収めて菩提を弔った。
その後、恵美僧正の夢の中に伊香保姫が現れ、この寺の鎮守と成ろうと告げた。
夜が明けて枕もとを見ると、一冊の日記が有り、以下のように記されていた。
伊香保姫は伊香保大明神として顕れた。
伊香保太夫は早尾大明神として顕れた。
太夫の女房は宿禰大明神として顕れた。
以上長くなりましたが、まとめると伊香保姫の生涯は以下のようにあらわされています。
・伊香保姫は、上野国国司高野辺家成公の三女である。
・見目麗しく、心根も優しかったが、継母はこれに嫉妬し姫の命を狙うが有馬郷の伊香保大夫に護られた。
・兄(国司高野辺中納言)の奥方の弟にあたる高光少(中)将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤められた。
・伊香保姫と高光少(中)将の姫君は京に上って更衣となり、皇子を産んで国母(天皇の母、皇太后)となられた。
・伊香保姫は伊香保沼に身を投げた後、水澤寺の別当恵美僧正がその遺骨を本堂の仏壇下に納めた。伊香保姫は恵美僧正の夢にあらわれ、水澤寺の鎮守となられた。
・伊香保姫は伊香保大明神として顕れた。
水澤寺の寺伝と「神道集」で寺の開基は若干異なりますが、御本尊が国司高野辺家成公の三女 伊香保姫のご持仏の(十一面)千手観世音菩薩という点は符合しています。
水澤寺は歴代天皇の勅願寺という高い格式を有しますが、これは「神道集」で伊香保姫の娘が国母(天皇の母、皇太后)になられたという内容と関係があるのかもしれません。
公式Webによると、「現在の建物は大永年間に仮堂を造立し、元禄年間より宝暦天命年間に至る三十三ヶ年の大改築によるもの」とのこと。
坂東三十三観音霊場の礼所であり、名湯、伊香保温泉のそばにあることから古くから多くの参詣客を集めました。
山内はさほど広くはないものの、霊場札所特有のパワスポ的雰囲気にあふれています。
背景の深い緑に朱塗りの伽藍が映えて、華やぎのある境内です。
また、参道に店が軒を連ねる水沢うどんは、讃岐うどん・稲庭うどんとともに「日本三大うどん」とされています。(諸説あり)


【写真 上(左)】 うどん店街からの表参道登り口
【写真 下(右)】 有名店の元祖田丸屋


【写真 上(左)】 水沢うどん
【写真 下(右)】 マイタケの天麩羅も名物です
境内の中心は本堂ですが、駐車場が手前にあるため、まず目に入る仏殿は釈迦堂です。
釈迦三尊像をお祀りし、円空仏(阿弥陀如来像)・二十八部衆像・十一面観世音菩薩像等を安置、坂東三十三観世音菩薩像をお祀りし、お砂踏みができるなど見応えがあります。
こちらでは釈迦三尊の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 釈迦堂
【写真 下(右)】 花まつりの誕生仏
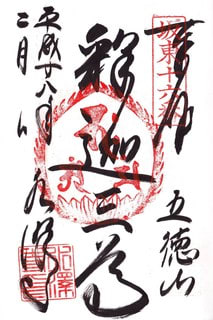

【写真 上(左)】 釈迦三尊の御朱印
【写真 下(右)】 平成最後の花まつり当日の釈迦三尊の御朱印
〔 釈迦三尊の御朱印 〕
釈迦三尊は、釈迦如来を中尊とし、左右に脇侍を配する安置形式です。
ふつう、向かって右に文殊菩薩、向かって左に普賢菩薩が置かれます。
左右逆に配置される場合もありますが、文殊菩薩は獅子、普賢菩薩は白象の上の蓮華座に結跏趺坐されているので、識別は比較的容易です。
水澤寺釈迦堂の釈迦三尊像(→公式Web)の画像は施無畏印、与願印を結ぶ釈迦如来を中尊に、向かって右に文殊菩薩、左に普賢菩薩が御座します。
御朱印の御寶印の種子も同様の配置で、中央上に釈迦如来の種子「バク」、右に文殊菩薩の種子「マン」、左に普賢菩薩の種子「アン」が、蓮華座+火焔宝珠のなかに置かれています。
中央に「釋迦三尊」の揮毫。右上に「坂東十六番」の札所印。右下に山号、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
画像は灌仏会(花まつり/4月8日)当日の御朱印で、釈迦堂前には誕生仏像と甘茶が用意されていました。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鐘楼
参道を進むとすぐに本堂が見えてきます。
御本尊が観世音菩薩なので、本堂が観音堂となります。
天明七年竣工の五間堂で、正面向拝、軒唐破風朱塗りの趣きあるつくり。透かし彫りや丸彫り技法を駆使した向拝柱の龍の彫刻はとくに見応えがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 向拝の天井画
【写真 下(右)】 札所扁額
御本尊の十一面千手観世音菩薩は絶対秘仏で御開帳はされません。
坂東三十三箇所(観音霊場)第16番、新上州三十三観音霊場別格の札所はこちらになります。


【写真 上(左)】 御札場の札所板
【写真 下(右)】 表参道の山門
なお、釈迦三尊像(釈迦堂)以外の御朱印および御朱印帳は、すべて本堂前御札場で授与されています。
本来の表参道はこの御札場横の階段で、水沢うどん店街から昇るもの。
仁王門も雰囲気があり、こちらにも回ることをおすすめします。
〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕

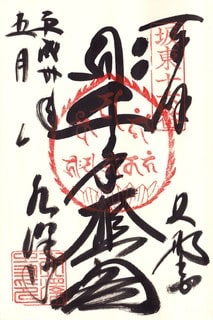
【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印-1
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印-2
中央に札所本尊、十一面千手観世音菩薩の種子「キリーク」と「千手大悲閣」の揮毫。
御寶印は蓮華座、火焔宝珠のなかに上段3つ、下段5つの8つの種子が置かれています。
上段の3つは、おそらく中央に聖観世音菩薩の種子「サ」、右に不動明王の種子「カン」、左に毘沙門天の種子「ベイ」。
天台宗系寺院では中尊の右に不動明王、左に毘沙門天を置く様式がありますが(これは複数のご住職からお聞きしたので間違いないと思う)、なぜ中央に十一面千手観世音菩薩の種子「キリーク」ではなく、聖観世音菩薩の種子「サ」が置かれているかは不明。
下段の5つの種子については、上段の中尊と併せて六観音を構成しているのではないかと思います。
通常、天台宗の六観音は聖観世音菩薩(種子サ)、十一面観世音菩薩(キャ)、千手観世音菩薩(キリーク)、馬頭観世音菩薩(カン)、如意輪観世音菩薩(キリーク)、不空羂索観世音菩薩(モ)です。
下段の種子は左からキリーク、サ、キリーク、キャ、カンで、不空羂索観世音菩薩のモを除いて揃っています。
サを不空羂索観世音菩薩の種子に当てていると考えると六観音説が成立しますが、委細はよくわかりません。
右上に「坂東十六番」の札所印。右下には山号、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
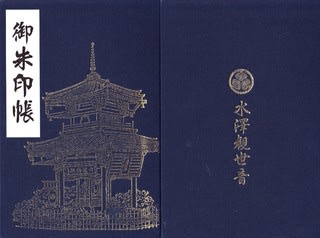
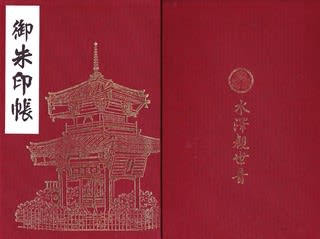
【写真 上(左)】 オリジナル御朱印帳(紺)
【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳(朱)
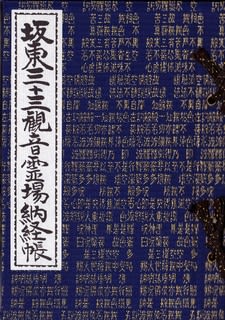
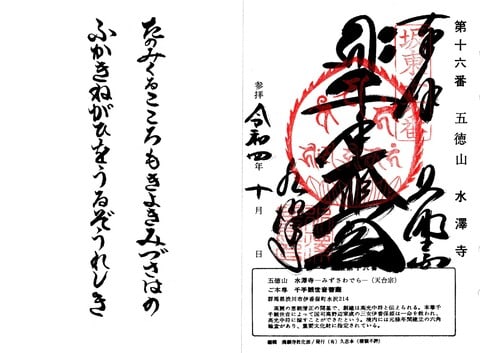
【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の専用納経帳(表紙)
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の専用納経帳御朱印
こちらのオリジナル御朱印帳は紙質がよく、おすすめです。
下段に寺院の概略が記載された「幻の坂東三十三箇所専用納経帳」はようやくこちらで入手できましたので、現在2巡目の巡拝中です。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
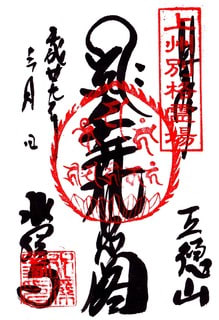

【写真 上(左)】 御朱印帳書入れの御朱印
【写真 下(右)】 専用納経帳の御朱印
こちらは新上州三十三観音霊場の番外札所になっていて、御朱印を授与されています。
中央に捺された御寶印は上の坂東霊場のものと同様です。
中央に「キリーク」の種子と「千手大悲閣」の揮毫。右上に「上州別格霊場」の霊場印。
右下には山号、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳の御朱印も同様の構成ですが、両面タイプで左側には尊格や御詠歌の印刷があります。
〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕


【写真 下(右)】 六角堂
【写真 下(右)】 六角堂正面


【写真 上(左)】 六角堂向拝
【写真 下(右)】 祈念を込めて廻します

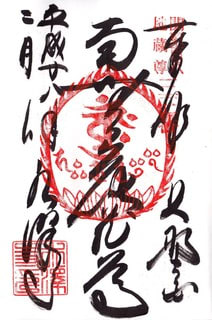
【写真 上(左)】 六地蔵尊
【写真 下(右)】 六地蔵尊の御朱印
あまり知られていないようですが、こちらは関東百八地蔵尊霊場33番の札所で、御朱印も授与されています。
本堂向かって右手にある朱塗りの六角堂(地蔵堂)は天明七年竣工の銅板瓦棒葺。堂内に御座す、元禄期、唐金立像の六体の開運地蔵尊(六地蔵尊)が札所本尊で、県指定重文のようです。
この六地蔵尊を左に三回廻して罪障消滅、後生善処を祈念します。
人気のスポットで、いつも参詣客が楽しそうに回し棒を押しています。
お堂の二層には上がれませんが、大日如来が安置されているそうです。
中央に「南無六地蔵尊」の揮毫。
御寶印は蓮華座と火焔宝珠のなかに上段に大きくひとつ、下段に小さく6つの種子が置かれています。
上段の大きな種子はおそらく金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。
下の6つはこの資料からすると、六地蔵を示し、左からふたつはカ(法性)、イ(宝性)、右からふたつはイー(地持)、イ(光昧)を示すと思われますが、揮毫がかかっている中央のふたつは不明です。
(六地蔵の名称や尊容は一定していないといわれ、六道との対応もよくわからない場合があります。)
六角堂(地蔵堂)は、2層に大日如来、1層に六地蔵尊が御座されているので、尊像配置とご寶印が整合しているようにも思われますが、さてさてどうでしょうか。
右上に「関東百八地蔵尊三三番」の札所印。右下に山号、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 飯綱大権現
【写真 下(右)】 十二支守り本尊


【写真 上(左)】 龍王弁財天
【写真 下(右)】 めずらしい尊格配置
この他にも、飯綱大権現、十二支守り本尊、龍王弁財天など、ふるくから参詣客を集めた古刹らしいみどころがつづきます。
車であと少し走れば名湯、伊香保温泉。午後に訪れて伊香保泊まりのゆったりとした参詣をおすすめします。
21.伊香保神社
渋川市伊香保町伊香保2
主祭神:大己貴命、少彦名命
式内社(名神大)、上野国三宮 旧社格:県社兼郷社

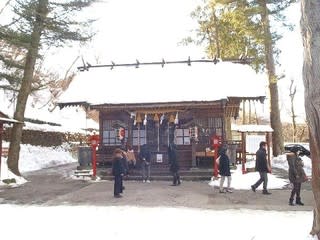
ようやく、この記事のハイライト、伊香保神社まできました。
伊香保温泉街の石段三百六十五段を昇りきったところに鎮座するこの神社は、式内社(名神大)、上野国三宮、旧県社という高い格式をもつ古社で、すこぶる複雑な由緒来歴を有します。
興味を惹かれたので、御朱印とは関係なく関連する神社も回ってみましたので、こちらも含めてご紹介します。


【写真 上(左)】 伊香保石段街
【写真 下(右)】 参道の階段
神社の創祀由緒をたどる有力な手がかりは境内の由来書です。
まずは、伊香保神社の由来書から要旨を抜粋引用してみます。
・第十一代垂仁天皇朝時代(紀元前二九~七0)の開起と伝えられ、第五十四代仁明天皇朝承和二年(八三五)九月十九日名神大社に。
・延喜五年(九0五)編纂開始の神名帳に記載され、朝廷公認の神社となった。
・上野国は十二宮を定めたが、伊香保神社は一宮貫前神社、二宮赤城神社についで三宮の神社となった。
・明治維新後、あらたに近代社格制度が敷かれ、伊香保神社は県社を賜ることとなった。


【写真 上(左)】 社号標
【写真 下(右)】 神楽殿
また、比較的信憑性の高い資料として所在市町村資料がありますが、当社所在の渋川市のWebにも記載があります。
いささか長いですが、興味ある内容を含んでいるので以下に引用します。
「(前略)延喜式内社です。「伊香保」の地名は古く、『万葉集』の東歌にも詠まれています。「厳つ峰」(いかつほ)とか「雷の峰」(いかつちのほ)に由来し、榛名山、とくに水沢山を指す古名だったと言われています。伊香保神社ももとは、水沢山を信仰の対象としたもので、別の場所にあったようです。
平安時代の記録では承和6年(839)に従五位下、元慶4年(880)には従四位上、長元3年(1030)ころに正一位に叙せられ、やがて上野国三宮となります。その後は衰微しますが、いつしか伊香保の源泉近くへ移り、温泉の守護神となったようです。
現在の祭神は、温泉・医療の神である大己貴命・少彦名命であり、湯元近くに移ってから後の祭神と思われます。(以下略)」


【写真 上(左)】 伊香保神社拝殿(2003年)
【写真 下(右)】 拝殿扁額
市町村資料としてはかなりナゾめいた内容ですが(笑)、以下の内容が読みとれます。
1.(延喜式内社)名神大社、上野国三宮、旧県社という社格の高い神社であること。
2.もともと水沢山を信仰の対象とし、別の場所にあった可能性があること。
3.伊香保の湯元のそば(現社地)に移られる前は別の祭神であった可能性があること。


【写真 上(左)】 社号の提灯
【写真 下(右)】 境内社
これとは別に「明治維新前には湯前神社(明神)と称していましたが、明治6年、旧号の伊香保神社と改称」という情報も得られました。併せて、「伊香保温泉にはそれ以前から薬師堂(温泉明神)が祀られていたが、伊香保神社の勧請後はその本地仏(薬師如来)とみなされるようになった。」という説もあり、これは上記2や3の内容と整合するものです。(詳細後述)
なお、群馬郡三十三観音霊場第4番の医王寺は、伊香保神社参道階段下から露天風呂に向かう途中の「医王寺薬師堂」のことかと思われます。


【写真 上(左)】 利根川越しの榛名連山
【写真 下(右)】 伊香保薬師堂(医王寺)
さらに、「群馬県群馬郡誌」には下記の記述があります。
「祭神は大己貴命少彦名命にして(略)淳和天皇の御代の創建なり。夫れより仁明天皇の承和二年辛羊九月名神大の社格たり(略)歴代國々の諸神に位階を給ひたれば本社は正一位に昇格す、故に上野國神名帳に正一位伊香保大明神と記載あり。」「明治六年縣社に列し更に二四大邑?の郷社を兼ねたり」
ところで上野国十二宮(社)をたどっていくと、伊香保神社のほかにもう一社、三宮に比定されている神社がみつかります。
吉岡町大久保に鎮座する三宮神社です。


【写真 上(左)】 三宮神社社頭
【写真 下(右)】 三宮神社の社号標と鳥居
三宮神社境内の由来書から抜粋引用します。(句読点は適宜付加。)
・天平勝宝二年(750)の勧請・創祀と伝えられる古名社、また「神道集」に『女体ハ里ヘ下給テ三宮渋河保ニ御座ス、本地ハ十一面也』とあり、伊香保神社の里宮とする説がある。
・彦火々出見命 豊玉姫命 少彦名命の三柱の神を奉斉している。
・三宮と称する所以は三柱の神を祭るためでなく、上野国三之宮であったことによる。
・九条家本延喜式神名帳には上野国三之宮は伊香保大明神とあり、当社はその里宮の中心であったと考えられる。
・古代当地方の人々は榛名山を伊香保山と称し、その山頂を祖霊降臨の地と崇め、麓に遙拝所をつくり里宮とした。
・上野国神名帳には伊香保神が五社記載されてあり、その中心の宮を正一位三宮伊香保大明神と記している。
・当地三宮神社は伊香保神を祭る中心地であったため、三宮の呼称が伝えられたのである。
・神道集所収の上野国三宮伊香保大明神の由来には、伊香保神は男体女体の二神あり男体は伊香保の湯を守護する薬師如来で、女体は里に下り十一面観音となるとある。
・当社は、古来十一面観音像を御神体として奉安してきたのである。

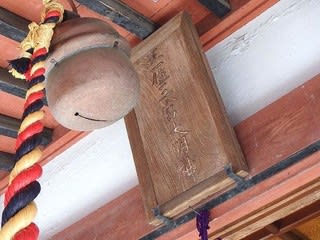
【写真 上(左)】 三宮神社拝殿
【写真 下(右)】 三宮神社拝殿の扁額
なお、本地垂迹資料便覧様の「伊香保神社」には、伊香保大明神は南体・女体が御在し、男体(湯前)は伊香保の湯を守護され本地は薬師如来、女体(里下)は里へ下られ三宮神社に御在し本地は十一面観世音菩薩とあります。
渋川市有馬に鎮座する若伊香保神社も伊香保神社との関連が指摘されています。


【写真 上(左)】 若伊香保神社の社号標
【写真 下(右)】 若伊香保神社拝殿
社頭の石碑はうかつにも現地で記録し忘れましたが、Web上で見つかるのでこちらの内容を抜粋引用させていただきます。
・有馬の地の産土神は、大名牟遅命、少彦名命を併せ祀る若伊香保神社である。
・貞観五年それまでは正六位であった神格から、従五位下を授けられたことが「三代実録」に明らかである。
・中世には、「上野国五の宮」と証され、県下神社中の第五位に置かれ、惣社明神相殿十柱の一となり正一位を与えられた。
若伊香保大明神の本地は千手観世音菩薩とされ、これは各種の資料で一貫しています。


【写真 上(左)】 若伊香保神社拝殿の扁額
【写真 下(右)】 満行山泰叟寺
「水沢寺之縁起」には、「高光中将并びに北の方は伊香保大明神男躰女躰の両神なり」「夫れ高光中将殿は男躰伊香保大明神、御本地は薬師如来、別当は医王寺」とあります。
「北の方」とは高貴な方の奥方(正妻)をさすので、高光中将は男体伊香保大明神、「北の方」である伊香保姫は女体伊香保大明神ということになります。
また、「水沢寺之縁起」には「姫御前は推古帝崩御の後当国に下着し、弱伊香保明神と顕現はる」とあり、神道集と同様、高光中将と伊香保姫の息女(姫御前)は弱伊香保明神(若伊香保大明神)であることを示唆しています。
(以上、本地垂迹資料便覧様の「伊香保神社」からの引用による。)
神道集「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」には、「中将殿の姫君は帝が崩御された後に国に下り、若伊香保大明神として顕れた。」とあります。
文脈からすると、中将殿は伊香保姫(伊香保大明神)の夫である高光中将であり、「中将殿の姫君」は、すなわち伊香保姫の御息女にあたることになります。
(『神道集』の神々様「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」から引用。)
「若宮」「若」とはふつう本宮の祭神の子(御子神)を祀った神社をさしますから、御息女である姫御前を祀った神社の社名に「若」がついているのは、うなづけるところでしょうか。
なお、「尾崎喜左雄の説によると、伊香保神社は古くは阿利真公(有馬君)によって有馬の地に祀られており、後に三宮の地に遷座した。これが伊香保神社の里宮(現在の三宮神社)となり、有馬の元社は若伊香保神社と呼ばれるようになった。その後、伊香保温泉の湯前の守護神として分社が勧請され、現在の伊香保神社となった。伊香保温泉にはそれ以前から薬師堂(温泉明神)が祀られていたが、伊香保神社の勧請後はその本地仏とみなされるようになったと考えられる。」(参考文献 尾崎喜左雄「伊香保神社の研究」、『上野国の信仰と文化』所収、尾崎先生著書刊行会、1970)という貴重な情報があります。
→ 情報元・『神道集』の神々様「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」
また、いくつかの資料で「伊香保神社は元々当地に鎮座したとされ、同社が上野国国府近くの三宮神社(北群馬郡吉岡町大久保)に遷座した際、旧社地に祀られたのが若伊香保神社」という説が紹介されています。
〔二ッ岳噴火との関係〕
------------------------------------
神道集の第四十一上野国第三宮伊香保大明神事には、伊香保神社の創祀伝承が描かれています。
前段は「20.五徳山 無量寿院 水澤寺」で引用しましたが、後段にはつぎのような不思議な記述があります。
「人皇四十九代光仁天皇の御代、上野国司の柏階大将知隆は伊香保山で七日間の巻狩を行って山と沼を荒らした。 沼の深さを測ろうとすると、夜の内に小山が出現したので、国司は上奏のために里に下った。 その後、沼は小山の西に移動し、元の沼地は野原になった。 国司は里に下る途中、一頭の鹿を水沢寺の本堂に追い込んで射殺した。 寺の僧たちは殺された鹿を奪い取って埋葬し、国司たちを追い出した。 怒った国司は寺に火をつけて焼き払った。 別当恵美僧正は上京して委細を帝に奏聞した。 帝は国司を佐渡島に流すよう検非違使に命じた。」「伊香保大明神は山の神たちを呼び集めて石楼を造った。 国司が蹴鞠をしていると、伊香保山から黒雲が立ち上り、一陣の旋風が吹き下ろした。 国司と目代は旋風にさらわれて石楼に閉じ込められ、今も焦熱地獄の苦しみを受けている。 山の神たちが石楼を造った山が石楼山である。 この山の北麓の北谷沢には冷水が流れていたが、石楼山が出来てから熱湯が流れるようになり、これを見た人は涌嶺と呼んだ。」
(『神道集』の神々様「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」から引用。)
まとめると、
1.光仁天皇の御代(宝亀元年(770年)~天応元年(781年))、伊香保山に一夜にして小山が出現し、山中にある沼が西に移動して元の沼地は野原となった。
2.伊香保大明神は山の神たちを呼び集めて石楼を造った。伊香保山から黒雲が立ち上り、一陣の旋風が吹き下ろした。 国司と目代は旋風にさらわれて石楼に閉じ込められ、今も焦熱地獄の苦しみを受けている。
3.山の神たちが石楼を造った山が石楼山で、この山の北麓の北谷沢には冷水が流れていたが、石楼山が出来てから熱湯が流れるようになり、これを見た人は涌嶺と呼んだ。
1.からは地殻変動、2.からは火山の噴火、3.からは温泉湧出が連想されます。
伊香保温泉には、古墳時代の第十一代垂仁天皇の御代に開かれたという説と、天平時代の僧、行基(668-749年)によって発見されたというふたつの湯縁起が伝わります。(〔 温泉地巡り 〕 伊香保温泉(本ブログ)を参照)
行基伝説をとると、3.と伊香保温泉の開湯は時期的にほぼ符合します。
伊香保温泉の熱源は、6世紀に活動した二ッ岳の火山活動の余熱と考えられています。
伊香保の二ッ岳は、5世紀に火山活動を再開し6世紀中頃までに3回の噴火が発生、うち489~498年に渋川噴火、525~550年にかけて伊香保噴火というふたつの大規模噴火を起こしたことがわかっています。(気象庁「関東・中部地方の活火山 榛名山」より)
神道集の上記2.は光仁天皇の御代(770年~781年)のできごととされているので、二ッ岳の噴火と時代が合いませんが、この噴火を後世で記録したもの、という説があります。
「やぐひろネット・歴史解明のための考古学」様では、この点について詳細かつ綿密な考証をされています。(同Webの関連記事)
また、論文「6世紀における榛名火山の2回の噴火とそ の災害」(1989年早田 勉氏)によると、これら複数の噴火は、伊香保神社、三宮神社、若伊香保神社などが鎮座する榛名山東麓、北麓にかけて甚大な被害をもたらしたことがわかります。
これらの噴火が忘れてはならないできごととして語り継がれ、神道集に繋がったという見方もできるかもしれません。
神道集はかなりスペクタクルな展開で一見荒唐無稽な感じも受けますが、意外と史実を伝えているのかも・・・。
あまりに逸話が多いのでとりとめがなくなってきましたが(笑)、無理矢理とりまとめると、
1.伊香保神社のかつての祭神は伊香保大明神(高野辺大将の三番目の姫君)。
2.伊香保大明神には男体・女体があり、男体は伊香保神社、女体は三宮神社(吉岡町大久保)に鎮座される。
3.伊香保大明神男体(湯前・伊香保神社)は高光中将が顕れ、伊香保大明神女体(里下・三宮神社)は伊香保姫が顕れた。
4.伊香保大明神男体(高光中将)と伊香保大明神女体(伊香保姫)の御息女は若伊香保大明神(渋川・有馬の若伊香保神社)として顕れた。
5.三宮神社は、伊香保神社の里宮とする説がある
6.伊香保神社はもともと若伊香保神社の社地に鎮座し、同社が三宮神社に遷座した際、旧社地に祀られたのが若伊香保神社という説がある。
7.伊香保の湯前神社はもともと薬師堂(温泉明神)で、伊香保神社の遷座?にともない習合して本地薬師如来となったという説がある。
8.伊香保大明神の創祀は、5世紀の渋川噴火、6世紀の伊香保噴火とかかわりをもつという説がある。
無理矢理とりまとめても(笑)、やはりぜんぜんまとめきれません。
というかナゾは深まるばかりです。
伊香保はお気に入りの温泉地なので、時間をかけてナゾを解きほぐしていければと考えています。
〔 御朱印 〕
これほどの古名社でありながら、現在伊香保神社には神職は常駐されておりません。(最近は、週末は社務所で授与いただけます。)
わたしは以前、参道階段下の饅頭屋さんで書置のものをいただきましたが、最近は平日でも拝殿前に書置が置かれているという情報もあります。
また、渋川八幡宮でも神職がいらっしゃれば書入れの御朱印を拝受できます。(現況は不明)

土日祝に社務所で授与される鶴亀の御朱印
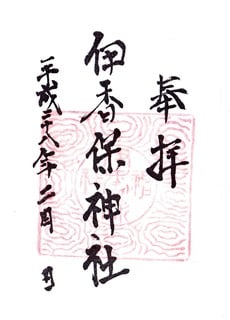

【写真 上(左)】 書置の御朱印(参道階段横饅頭屋さんにて)
【写真 下(右)】 書入れの御朱印(渋川八幡宮にて)
書置き、書入れともに中央に神社印、中央に「伊香保神社」の揮毫があります。
なお、三宮神社、若伊香保神社ともに無住で、御朱印の授与については確認できておりません。
また、若伊香保神社のとなりに、いかにも別当寺然としてある曹洞宗の満行山泰叟寺も参拝しましたが、御朱印は非授与とのことでした。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)へ
※ 渋川スカイランドそばに令和元年建立された関東石鎚神社でも御朱印を授与されています。
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ ホール・ニュー・ワールド - 熊田このは & 二木蒼生
"A Whole New World" by Konoha Kumada(with Aoi Niki).1/12/2020 at The Mizonokuchi Theater in Kawasaki/JAPAN.
■ Open Your Heart - Yuki Kajiura(FictionJunction)
■ PLANETES - Hitomi(黒石ひとみ)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(前編A)
19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)
20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)
21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)
19.船尾山 等覚院 柳澤寺
公式Web
榛東村山子田2535
天台宗
御本尊:千手千眼観世音菩薩 (釈迦三尊)
札所:新上州三十三観音霊場第25番、東国花の寺百ヶ寺霊場第34番(群馬第8番)、関東九十一薬師霊場第46番、関東百八地蔵尊霊場第34番、群馬郡三十三観音霊場第2番、上州七福神(毘沙門天)
札所本尊:千手観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第25番)、千手観世音菩薩(東国花の寺百ヶ寺霊場第34番(群馬第8番))、薬師如来(関東九十一薬師霊場第46番)、地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第34番)、毘沙門天(上州七福神)




榛名東麓屈指の古刹で、複数の札所を兼ねているこのお寺は複雑な開山由緒をもたれます。
公式Webにある「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院 息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山」というのが当初の開山伝承のようです。
その後「神道集」の「上野国桃井郷上村八ヶ権現の事」、およびこれをベースとして成立した「船尾山縁起」が広まります。
「船尾山縁起」はデリケートな内容で抜粋引用がはばかられ、全文引用すると長くなるのでこちら(公式Web)をご覧ください。
近世にはこの地との関わりがうすい千葉氏が主役で、その千葉氏が悲劇的な結末をもってその姿を隠してしまうというこの伝承については、その背景として様々な説が打ち出されています。
「6.三鈷山 吉祥院 妙見寺」にも千葉氏にまつわる伝承が残りますが、柳澤寺は「妙見院 息災寺」を通じて妙見寺と相応のつながりがあったのでは。
それにしても、このエリアは「神道集」との関わりが深いです。
神道集(しんとうしゅう)は、南北朝時代中期に成立とされている十巻五十条からなる説話集で、安居院唱導教団(あぐいしょうどうきょうだん)の著作とされます。
安居院唱導教団は当時の仏教宗派のひとつとされ、詳細は不明ですが伊勢神道(度会神道、神本仏迹説系)との関連を指摘する説がみられます。
内容はすこぶる劇的でスペクタクル。アニメや映画になじみそう。
主に関東(とくに上州)の神社について、その成り立ちと本地仏(神本仏迹説からすると垂迹仏?)が詳細に記されています。
(いわゆる本地譚・本地物/神体の前生説話のひとつとされる。)
登場される神々はかならずしも現在の主祀神ではなく、主にその土地とつながりのふかい神々です。
生身の人間が説話を介して一気に神となる不思議なイメージ漂う内容ですが、これは神本仏迹系本地譚の特徴なのかもしれません。
(「権現系」ではなく「明神系」、神名も大明神を名乗られる例が多い。)
この「神道集」があることで上州の寺社はダイナミックにつながり、寺社巡りに興を添えています。
「上野国桃井郷上村八ヶ権現の事」(神道集第四十七)は、こちらで紹介されています。
「神道集」と「船尾山縁起」はともに凄絶な展開で内容は酷似していますが、「神道集」の主役は上野国国司の桃苑左大将家光。
千葉氏が主役となる「船尾山縁起」の成立は「神道集」から約二百年後とされるので、この二百年のあいだに千葉氏にかかわる大きなできごとがあったのかもしれません。
ちなみに、柳澤寺そばには平常将大明神を主祭神とする常将神社が鎮座しています。
寺伝(公式Web)によると、延暦寺の直末として中世には学僧も多く輩出、戦国時代末の動乱を経て、江戸時代に入は天海僧正、高崎城主・安藤右京進などの尽力により朱印地三十石を賜ったとされる名刹です。
背後に榛名山を背負い、眼下に利根川が流れる開けた立地に名刹にふさわしい広大な境内を擁します。
風格ある二層丹塗りの楼門、御本尊、千手千眼観世音菩薩が御座す本堂(観音堂)、寄棟平屋造りの風趣ある客殿(釈迦三尊、薬師如来、不動明王、毘沙門天などが御座)、県内最古とされる鐘楼、阿弥陀堂、薬師堂、平成10年建立の五重塔など壮麗な伽藍を連ねます。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 五重塔
本堂(観音堂)は右手に離れてあるのでややわかりにくいですが、新上州三十三観音と東国花の寺百ヶ寺霊場の札所はこちらになります。
納経所(御朱印授与所)は客殿左手の庫裡、ないし客殿が開いているときは客殿内となります。
複数の札所を兼ねているので手慣れたご対応ですが、目的の御朱印(霊場)をはっきり申告する必要があります。
それでは、それぞれの霊場の御朱印を紹介していきます。
なお、Web情報からすると霊場申告なしの御朱印は新上州三十三観音霊場のものとなる模様。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

本堂(観音堂)
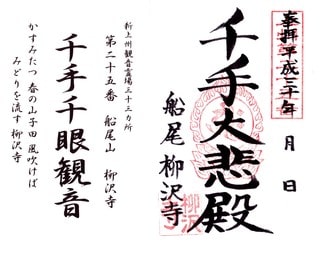

【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
札所本尊の千手千眼観世音菩薩は境内右手の本堂(観音堂)に御座します。
元禄年間の様式を残すとされる、方六間の木造青銅葺きの建物で古趣を湛えています。
中央に札所本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。
右上に「上州第二十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳の御朱印も同様の構成です。
客殿にて御朱印帳に書入れ、専用納経帳御朱印は庫裡にていただきました。
〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

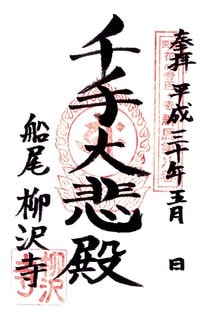
指定花種はサクラ(ソメイヨシノ)ですが、サツキも有名なようです。
この霊場は御本尊が札所本尊となるケースが多いですが、やはり本堂御本尊の千手千眼観世音菩薩の御朱印でした。
なので、霊場の参拝所は境内右手の本堂(観音堂)となります。
なお、公式Webには客殿の欄に「本尊釈迦三尊像」の記載がありますが、本堂御本尊=千手観世音菩薩、客殿御本尊=釈迦三尊という位置づけかもしれません。
中央に札所本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。
右上に「東国花の寺百ヶ寺群馬第八番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。(主印が千手観世音菩薩の御影印となる場合もあるようです。)
霊場専用納経帳用の書置御朱印もあるようですが、庫裡にて御朱印書入れをいただきました。
〔 関東九十一薬師霊場の御朱印 〕

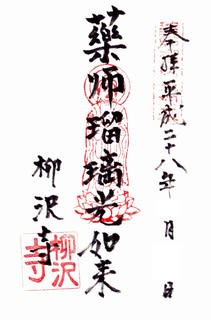
【写真 上(左)】 本堂(観音堂)参道右手の真新しい建物が薬師堂の覆堂?
【写真 下(右)】 御朱印
御座所をお尋ねするのを忘れましたが、霊場ガイドブックによると、札所本尊は本堂(観音堂)脇の唐破風宮殿造の薬師堂に御座す秘仏、船尾薬師如来(江戸初期、二尺一寸木彫座像)で、往昔より眼の病、万病平癒の守護佛として信仰されてきたとのこと。
中央に薬師如来立像の御影印と「薬師瑠璃光如来」の揮毫。右上に「薬師瑠璃光如来」の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。
〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 札所本尊の延命地蔵尊
【写真 下(右)】 子授地蔵尊
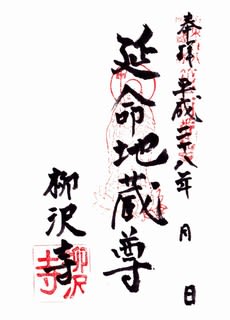
札所本尊御座所は、「仁王門から本堂(観音堂)に向かう途中の石像のお地蔵さま」との由。
霊場ガイドブックによると、「仁王門から観音堂に通ずる中段境内に近年建立された”延命地蔵尊”(石佛立像一丈三尺)」とあります。
鐘楼脇には元禄期建立とされる石佛立像の”子授地蔵尊”も御座しますが、ガイドには札所本尊欄に「延命地蔵尊」と明記されているので、こちらが札所本尊と思われます。
関東百八地蔵尊霊場の札所本尊は露仏も多く、ガイドブックがないとこのように特定しにくいケースがあります。
中央に地蔵菩薩立像の御影印と「延命地蔵尊」の揮毫。右上に「関東百八地蔵尊第三四番札所」の札所印。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。
〔 上州七福神(毘沙門天)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 殿の扁額と上州七福神の札所板

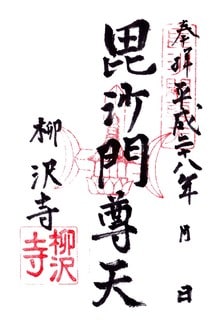
【写真 上(左)】 毘沙門天の説明板
【写真 下(右)】 御朱印
上州七福神は県内全域にまたがる広域の七福神で、通年でどれだけ参拝客がいるかはわかりませんが、霊場会があり御朱印帳書入れもおおむねOKのようです。
客殿に御座す、毘沙門天が札所本尊です。
中央に法具(鈷杵?)を背景にした宝塔(毘沙門天の持物)の印と「毘沙門尊天」の揮毫。
右上に「毘沙門尊天」の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。
20.五徳山 無量寿院 水澤寺(水澤観音)
公式Web
渋川市伊香保町水沢214
天台宗
御本尊:十一面千手観世音菩薩
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第16番、新上州三十三観音霊場別格、関東百八地蔵尊霊場第33番、群馬郡三十三観音霊場第3番
札所本尊:十一面千手観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第16番)、十一面千手観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)、地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第33番)、十一面千手観世音菩薩(群馬郡三十三観音霊場第3番)


通称、水澤観音として親しまれる水澤寺は、上州を代表する天台宗の古刹です。
坂東三十三観音霊場の第十六番礼所でもあり、広く巡拝客を集めています。
寺伝(公式Webより)には、「千三百有余年の昔、推古天皇・持統天皇の勅願による、高麗の高僧恵灌僧正の開基であり、五徳山 水澤寺の名称は、推古天皇の御宸筆(ごしんぴつ)の額名によるものです。
ご本尊は国司高野辺家成公の三女 伊香保姫のご持仏の十一面千手観世音菩薩であり、霊験あたらたかなること、特に七難即滅七福即生のご利益顕著です。」とあります。
この伊香保姫は、くだんの「神道集」でも大きくとりあげられています。
後段の伊香保神社の縁起にもかかわる内容なので、すこしく長くなりますが、第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事、第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事から抜粋引用してみます。
■ 第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事
人皇十八代履中天皇の御代、高野辺左大将家成は無実の罪で上野国深栖郷に流され、その地で奥方との間に一人の若君と三人の姫君をもうけた。
奥方が亡くなった後、左大将は信濃国更科郡の地頭・更科大夫宗行の娘を後妻とし、その間に一人の娘をもうけた。
その後左大将は罪を許されて都へ戻り、上野国の国司に任じられ、若君も都へ上り、帝から仕官を許された。
三人の姫君のうち、姉姫は淵名次郎家兼に預けられ淵名姫、次の姫は大室太郎兼保に預けられ赤城御前、末姫は群馬郡の地頭・伊香保大夫伊保に預けられて伊香保姫といった。
三人の姫君は見目麗しく、心根も優しく、相応の婿を選んで嫁ぐこととなったが、継母はこれに嫉妬し、弟の更科次郎兼光を唆して三人の姫君を亡きものにしようとした。
兼光は兵を興して淵名次郎と大室太郎を捕らえ、斬り殺した。
次に、淵名姫と淵名の女房を捕らえて亡きものにした。
その後、大室の宿所に押し寄せたが、赤城御前と大室の女房は赤城山へ逃れた。有馬郷の伊香保大夫は守りを固めて迎え撃ったので、伊香保姫は無事だった。
〔姉姫淵名姫は淵名明神に、赤城御前は唵佐羅摩女(赤城沼の龍神)の跡を継いで赤城大明神として顕れたと「神道集」は伝えますが、詳細は別稿に譲ります。〕
上野国の国司に任じられた左大将は、淵名姫の死を知ると姫の跡を追って身を投げた。
中納言となっていた若君はこれを知ると東国へ下り、上野国の国司となって更級次郎父子を捕らえ仇を討つた。
国司は無事であった伊香保姫と再会し、国司の職を伊香保姫に譲った。
伊香保姫は兄(国司高野辺中納言)の奥方の弟にあたる高光少将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤められた。
伊香保大夫は目代となり、自在丸という地に御所を建てた。当国の惣社は伊香保姫の御所の跡である。
■ 第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事(話の内容が第四十と整合しない箇所があります。)
伊香保大明神は赤城大明神の妹で、高野辺大将の三番目の姫君である。
高野辺中納言の奥方の弟の高光中将と結婚して、一人の姫君をもうけた。
伊香保姫と高光中将は上野国国司を他に譲ったあと、有馬の伊香保大夫のもとで暮らしていた。
伊香保姫は淵名神社へ参詣の折、現在の国司である大伴大将と出会い、伊香保姫の美貌に懸想した大伴大将は、国司の威勢で姫を奪おうとした。
伊香保大夫は九人の息子と三人の婿を将として防戦したが劣勢となり、伊香保姫とその姫君、女房と娘の石童御前・有御前を連れて児持山に入った。負傷した高光中将は行方知れずとなった。
伊香保太夫は上京して状況を帝に奏聞すると、帝は伊香保姫に国司の職を持たせ、伊香保太夫を目代とされた。
また、高光中将(と伊香保姫)の姫君を上京させて更衣とされ、皇子が生まれたので国母として仰がれた。
伊香保太夫は伊香保山の東麓の岩滝沢の北岸に寺を建てて、高光中将の遺骨を納めた。
月日は流れて伊香保太夫とその女房は亡くなり、その娘の石童御前と有御前は伊香保姫と暮らしていた。
高光中将の甥の恵美僧正が別当になって寺はますます栄え、岩滝沢に因んで寺号を水沢寺とした。
伊香保姫は夫高光中将の形見の千手観世音菩薩を寺の本尊に祀り、二人の御前とともに亡き人々の菩提を弔ったところ、高光中将・伊香保大夫夫妻とその一族があらわれて千手観世音菩薩に礼拝した。
伊香保大夫の女房は 「あなた方の千手経読誦の功徳により、伊香保山の神や伊香保沼(榛名湖)の龍神・吠尸羅摩女に大切にされ、我らは悟りを開くことができました。
今は高光中将を主君とし、その眷属として崇められています」と云った。
夢から覚めた伊香保姫は「沼に身を投げて、龍宮城の力で高光中将の所に行こうと思います」と云って伊香保沼に身を投げた。石童御前と有御前もその後を追った。
恵美僧正は三人の遺骨を本堂の仏壇に下に収めて菩提を弔った。
その後、恵美僧正の夢の中に伊香保姫が現れ、この寺の鎮守と成ろうと告げた。
夜が明けて枕もとを見ると、一冊の日記が有り、以下のように記されていた。
伊香保姫は伊香保大明神として顕れた。
伊香保太夫は早尾大明神として顕れた。
太夫の女房は宿禰大明神として顕れた。
以上長くなりましたが、まとめると伊香保姫の生涯は以下のようにあらわされています。
・伊香保姫は、上野国国司高野辺家成公の三女である。
・見目麗しく、心根も優しかったが、継母はこれに嫉妬し姫の命を狙うが有馬郷の伊香保大夫に護られた。
・兄(国司高野辺中納言)の奥方の弟にあたる高光少(中)将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤められた。
・伊香保姫と高光少(中)将の姫君は京に上って更衣となり、皇子を産んで国母(天皇の母、皇太后)となられた。
・伊香保姫は伊香保沼に身を投げた後、水澤寺の別当恵美僧正がその遺骨を本堂の仏壇下に納めた。伊香保姫は恵美僧正の夢にあらわれ、水澤寺の鎮守となられた。
・伊香保姫は伊香保大明神として顕れた。
水澤寺の寺伝と「神道集」で寺の開基は若干異なりますが、御本尊が国司高野辺家成公の三女 伊香保姫のご持仏の(十一面)千手観世音菩薩という点は符合しています。
水澤寺は歴代天皇の勅願寺という高い格式を有しますが、これは「神道集」で伊香保姫の娘が国母(天皇の母、皇太后)になられたという内容と関係があるのかもしれません。
公式Webによると、「現在の建物は大永年間に仮堂を造立し、元禄年間より宝暦天命年間に至る三十三ヶ年の大改築によるもの」とのこと。
坂東三十三観音霊場の礼所であり、名湯、伊香保温泉のそばにあることから古くから多くの参詣客を集めました。
山内はさほど広くはないものの、霊場札所特有のパワスポ的雰囲気にあふれています。
背景の深い緑に朱塗りの伽藍が映えて、華やぎのある境内です。
また、参道に店が軒を連ねる水沢うどんは、讃岐うどん・稲庭うどんとともに「日本三大うどん」とされています。(諸説あり)


【写真 上(左)】 うどん店街からの表参道登り口
【写真 下(右)】 有名店の元祖田丸屋


【写真 上(左)】 水沢うどん
【写真 下(右)】 マイタケの天麩羅も名物です
境内の中心は本堂ですが、駐車場が手前にあるため、まず目に入る仏殿は釈迦堂です。
釈迦三尊像をお祀りし、円空仏(阿弥陀如来像)・二十八部衆像・十一面観世音菩薩像等を安置、坂東三十三観世音菩薩像をお祀りし、お砂踏みができるなど見応えがあります。
こちらでは釈迦三尊の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 釈迦堂
【写真 下(右)】 花まつりの誕生仏
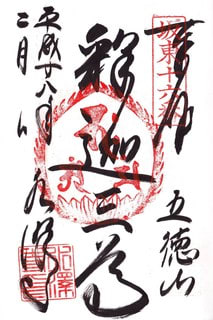

【写真 上(左)】 釈迦三尊の御朱印
【写真 下(右)】 平成最後の花まつり当日の釈迦三尊の御朱印
〔 釈迦三尊の御朱印 〕
釈迦三尊は、釈迦如来を中尊とし、左右に脇侍を配する安置形式です。
ふつう、向かって右に文殊菩薩、向かって左に普賢菩薩が置かれます。
左右逆に配置される場合もありますが、文殊菩薩は獅子、普賢菩薩は白象の上の蓮華座に結跏趺坐されているので、識別は比較的容易です。
水澤寺釈迦堂の釈迦三尊像(→公式Web)の画像は施無畏印、与願印を結ぶ釈迦如来を中尊に、向かって右に文殊菩薩、左に普賢菩薩が御座します。
御朱印の御寶印の種子も同様の配置で、中央上に釈迦如来の種子「バク」、右に文殊菩薩の種子「マン」、左に普賢菩薩の種子「アン」が、蓮華座+火焔宝珠のなかに置かれています。
中央に「釋迦三尊」の揮毫。右上に「坂東十六番」の札所印。右下に山号、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
画像は灌仏会(花まつり/4月8日)当日の御朱印で、釈迦堂前には誕生仏像と甘茶が用意されていました。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鐘楼
参道を進むとすぐに本堂が見えてきます。
御本尊が観世音菩薩なので、本堂が観音堂となります。
天明七年竣工の五間堂で、正面向拝、軒唐破風朱塗りの趣きあるつくり。透かし彫りや丸彫り技法を駆使した向拝柱の龍の彫刻はとくに見応えがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 向拝の天井画
【写真 下(右)】 札所扁額
御本尊の十一面千手観世音菩薩は絶対秘仏で御開帳はされません。
坂東三十三箇所(観音霊場)第16番、新上州三十三観音霊場別格の札所はこちらになります。


【写真 上(左)】 御札場の札所板
【写真 下(右)】 表参道の山門
なお、釈迦三尊像(釈迦堂)以外の御朱印および御朱印帳は、すべて本堂前御札場で授与されています。
本来の表参道はこの御札場横の階段で、水沢うどん店街から昇るもの。
仁王門も雰囲気があり、こちらにも回ることをおすすめします。
〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕

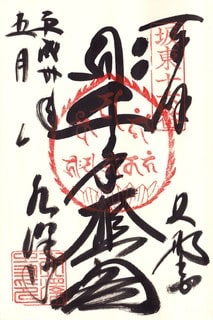
【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印-1
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印-2
中央に札所本尊、十一面千手観世音菩薩の種子「キリーク」と「千手大悲閣」の揮毫。
御寶印は蓮華座、火焔宝珠のなかに上段3つ、下段5つの8つの種子が置かれています。
上段の3つは、おそらく中央に聖観世音菩薩の種子「サ」、右に不動明王の種子「カン」、左に毘沙門天の種子「ベイ」。
天台宗系寺院では中尊の右に不動明王、左に毘沙門天を置く様式がありますが(これは複数のご住職からお聞きしたので間違いないと思う)、なぜ中央に十一面千手観世音菩薩の種子「キリーク」ではなく、聖観世音菩薩の種子「サ」が置かれているかは不明。
下段の5つの種子については、上段の中尊と併せて六観音を構成しているのではないかと思います。
通常、天台宗の六観音は聖観世音菩薩(種子サ)、十一面観世音菩薩(キャ)、千手観世音菩薩(キリーク)、馬頭観世音菩薩(カン)、如意輪観世音菩薩(キリーク)、不空羂索観世音菩薩(モ)です。
下段の種子は左からキリーク、サ、キリーク、キャ、カンで、不空羂索観世音菩薩のモを除いて揃っています。
サを不空羂索観世音菩薩の種子に当てていると考えると六観音説が成立しますが、委細はよくわかりません。
右上に「坂東十六番」の札所印。右下には山号、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
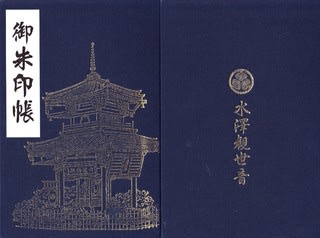
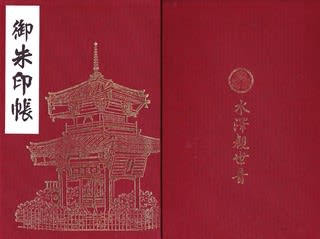
【写真 上(左)】 オリジナル御朱印帳(紺)
【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳(朱)
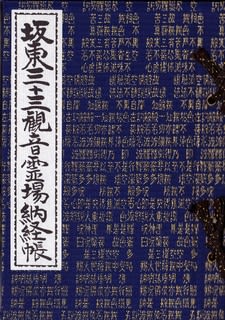
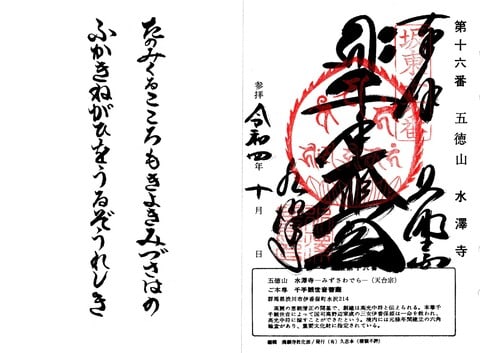
【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の専用納経帳(表紙)
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の専用納経帳御朱印
こちらのオリジナル御朱印帳は紙質がよく、おすすめです。
下段に寺院の概略が記載された「幻の坂東三十三箇所専用納経帳」はようやくこちらで入手できましたので、現在2巡目の巡拝中です。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
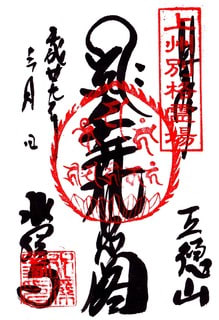

【写真 上(左)】 御朱印帳書入れの御朱印
【写真 下(右)】 専用納経帳の御朱印
こちらは新上州三十三観音霊場の番外札所になっていて、御朱印を授与されています。
中央に捺された御寶印は上の坂東霊場のものと同様です。
中央に「キリーク」の種子と「千手大悲閣」の揮毫。右上に「上州別格霊場」の霊場印。
右下には山号、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳の御朱印も同様の構成ですが、両面タイプで左側には尊格や御詠歌の印刷があります。
〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕


【写真 下(右)】 六角堂
【写真 下(右)】 六角堂正面


【写真 上(左)】 六角堂向拝
【写真 下(右)】 祈念を込めて廻します

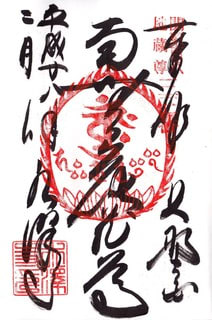
【写真 上(左)】 六地蔵尊
【写真 下(右)】 六地蔵尊の御朱印
あまり知られていないようですが、こちらは関東百八地蔵尊霊場33番の札所で、御朱印も授与されています。
本堂向かって右手にある朱塗りの六角堂(地蔵堂)は天明七年竣工の銅板瓦棒葺。堂内に御座す、元禄期、唐金立像の六体の開運地蔵尊(六地蔵尊)が札所本尊で、県指定重文のようです。
この六地蔵尊を左に三回廻して罪障消滅、後生善処を祈念します。
人気のスポットで、いつも参詣客が楽しそうに回し棒を押しています。
お堂の二層には上がれませんが、大日如来が安置されているそうです。
中央に「南無六地蔵尊」の揮毫。
御寶印は蓮華座と火焔宝珠のなかに上段に大きくひとつ、下段に小さく6つの種子が置かれています。
上段の大きな種子はおそらく金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。
下の6つはこの資料からすると、六地蔵を示し、左からふたつはカ(法性)、イ(宝性)、右からふたつはイー(地持)、イ(光昧)を示すと思われますが、揮毫がかかっている中央のふたつは不明です。
(六地蔵の名称や尊容は一定していないといわれ、六道との対応もよくわからない場合があります。)
六角堂(地蔵堂)は、2層に大日如来、1層に六地蔵尊が御座されているので、尊像配置とご寶印が整合しているようにも思われますが、さてさてどうでしょうか。
右上に「関東百八地蔵尊三三番」の札所印。右下に山号、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 飯綱大権現
【写真 下(右)】 十二支守り本尊


【写真 上(左)】 龍王弁財天
【写真 下(右)】 めずらしい尊格配置
この他にも、飯綱大権現、十二支守り本尊、龍王弁財天など、ふるくから参詣客を集めた古刹らしいみどころがつづきます。
車であと少し走れば名湯、伊香保温泉。午後に訪れて伊香保泊まりのゆったりとした参詣をおすすめします。
21.伊香保神社
渋川市伊香保町伊香保2
主祭神:大己貴命、少彦名命
式内社(名神大)、上野国三宮 旧社格:県社兼郷社

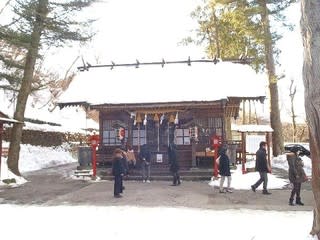
ようやく、この記事のハイライト、伊香保神社まできました。
伊香保温泉街の石段三百六十五段を昇りきったところに鎮座するこの神社は、式内社(名神大)、上野国三宮、旧県社という高い格式をもつ古社で、すこぶる複雑な由緒来歴を有します。
興味を惹かれたので、御朱印とは関係なく関連する神社も回ってみましたので、こちらも含めてご紹介します。


【写真 上(左)】 伊香保石段街
【写真 下(右)】 参道の階段
神社の創祀由緒をたどる有力な手がかりは境内の由来書です。
まずは、伊香保神社の由来書から要旨を抜粋引用してみます。
・第十一代垂仁天皇朝時代(紀元前二九~七0)の開起と伝えられ、第五十四代仁明天皇朝承和二年(八三五)九月十九日名神大社に。
・延喜五年(九0五)編纂開始の神名帳に記載され、朝廷公認の神社となった。
・上野国は十二宮を定めたが、伊香保神社は一宮貫前神社、二宮赤城神社についで三宮の神社となった。
・明治維新後、あらたに近代社格制度が敷かれ、伊香保神社は県社を賜ることとなった。


【写真 上(左)】 社号標
【写真 下(右)】 神楽殿
また、比較的信憑性の高い資料として所在市町村資料がありますが、当社所在の渋川市のWebにも記載があります。
いささか長いですが、興味ある内容を含んでいるので以下に引用します。
「(前略)延喜式内社です。「伊香保」の地名は古く、『万葉集』の東歌にも詠まれています。「厳つ峰」(いかつほ)とか「雷の峰」(いかつちのほ)に由来し、榛名山、とくに水沢山を指す古名だったと言われています。伊香保神社ももとは、水沢山を信仰の対象としたもので、別の場所にあったようです。
平安時代の記録では承和6年(839)に従五位下、元慶4年(880)には従四位上、長元3年(1030)ころに正一位に叙せられ、やがて上野国三宮となります。その後は衰微しますが、いつしか伊香保の源泉近くへ移り、温泉の守護神となったようです。
現在の祭神は、温泉・医療の神である大己貴命・少彦名命であり、湯元近くに移ってから後の祭神と思われます。(以下略)」


【写真 上(左)】 伊香保神社拝殿(2003年)
【写真 下(右)】 拝殿扁額
市町村資料としてはかなりナゾめいた内容ですが(笑)、以下の内容が読みとれます。
1.(延喜式内社)名神大社、上野国三宮、旧県社という社格の高い神社であること。
2.もともと水沢山を信仰の対象とし、別の場所にあった可能性があること。
3.伊香保の湯元のそば(現社地)に移られる前は別の祭神であった可能性があること。


【写真 上(左)】 社号の提灯
【写真 下(右)】 境内社
これとは別に「明治維新前には湯前神社(明神)と称していましたが、明治6年、旧号の伊香保神社と改称」という情報も得られました。併せて、「伊香保温泉にはそれ以前から薬師堂(温泉明神)が祀られていたが、伊香保神社の勧請後はその本地仏(薬師如来)とみなされるようになった。」という説もあり、これは上記2や3の内容と整合するものです。(詳細後述)
なお、群馬郡三十三観音霊場第4番の医王寺は、伊香保神社参道階段下から露天風呂に向かう途中の「医王寺薬師堂」のことかと思われます。


【写真 上(左)】 利根川越しの榛名連山
【写真 下(右)】 伊香保薬師堂(医王寺)
さらに、「群馬県群馬郡誌」には下記の記述があります。
「祭神は大己貴命少彦名命にして(略)淳和天皇の御代の創建なり。夫れより仁明天皇の承和二年辛羊九月名神大の社格たり(略)歴代國々の諸神に位階を給ひたれば本社は正一位に昇格す、故に上野國神名帳に正一位伊香保大明神と記載あり。」「明治六年縣社に列し更に二四大邑?の郷社を兼ねたり」
ところで上野国十二宮(社)をたどっていくと、伊香保神社のほかにもう一社、三宮に比定されている神社がみつかります。
吉岡町大久保に鎮座する三宮神社です。


【写真 上(左)】 三宮神社社頭
【写真 下(右)】 三宮神社の社号標と鳥居
三宮神社境内の由来書から抜粋引用します。(句読点は適宜付加。)
・天平勝宝二年(750)の勧請・創祀と伝えられる古名社、また「神道集」に『女体ハ里ヘ下給テ三宮渋河保ニ御座ス、本地ハ十一面也』とあり、伊香保神社の里宮とする説がある。
・彦火々出見命 豊玉姫命 少彦名命の三柱の神を奉斉している。
・三宮と称する所以は三柱の神を祭るためでなく、上野国三之宮であったことによる。
・九条家本延喜式神名帳には上野国三之宮は伊香保大明神とあり、当社はその里宮の中心であったと考えられる。
・古代当地方の人々は榛名山を伊香保山と称し、その山頂を祖霊降臨の地と崇め、麓に遙拝所をつくり里宮とした。
・上野国神名帳には伊香保神が五社記載されてあり、その中心の宮を正一位三宮伊香保大明神と記している。
・当地三宮神社は伊香保神を祭る中心地であったため、三宮の呼称が伝えられたのである。
・神道集所収の上野国三宮伊香保大明神の由来には、伊香保神は男体女体の二神あり男体は伊香保の湯を守護する薬師如来で、女体は里に下り十一面観音となるとある。
・当社は、古来十一面観音像を御神体として奉安してきたのである。

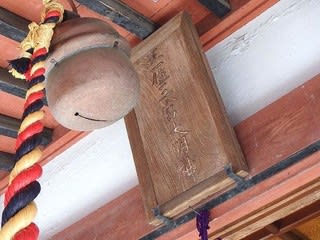
【写真 上(左)】 三宮神社拝殿
【写真 下(右)】 三宮神社拝殿の扁額
なお、本地垂迹資料便覧様の「伊香保神社」には、伊香保大明神は南体・女体が御在し、男体(湯前)は伊香保の湯を守護され本地は薬師如来、女体(里下)は里へ下られ三宮神社に御在し本地は十一面観世音菩薩とあります。
渋川市有馬に鎮座する若伊香保神社も伊香保神社との関連が指摘されています。


【写真 上(左)】 若伊香保神社の社号標
【写真 下(右)】 若伊香保神社拝殿
社頭の石碑はうかつにも現地で記録し忘れましたが、Web上で見つかるのでこちらの内容を抜粋引用させていただきます。
・有馬の地の産土神は、大名牟遅命、少彦名命を併せ祀る若伊香保神社である。
・貞観五年それまでは正六位であった神格から、従五位下を授けられたことが「三代実録」に明らかである。
・中世には、「上野国五の宮」と証され、県下神社中の第五位に置かれ、惣社明神相殿十柱の一となり正一位を与えられた。
若伊香保大明神の本地は千手観世音菩薩とされ、これは各種の資料で一貫しています。


【写真 上(左)】 若伊香保神社拝殿の扁額
【写真 下(右)】 満行山泰叟寺
「水沢寺之縁起」には、「高光中将并びに北の方は伊香保大明神男躰女躰の両神なり」「夫れ高光中将殿は男躰伊香保大明神、御本地は薬師如来、別当は医王寺」とあります。
「北の方」とは高貴な方の奥方(正妻)をさすので、高光中将は男体伊香保大明神、「北の方」である伊香保姫は女体伊香保大明神ということになります。
また、「水沢寺之縁起」には「姫御前は推古帝崩御の後当国に下着し、弱伊香保明神と顕現はる」とあり、神道集と同様、高光中将と伊香保姫の息女(姫御前)は弱伊香保明神(若伊香保大明神)であることを示唆しています。
(以上、本地垂迹資料便覧様の「伊香保神社」からの引用による。)
神道集「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」には、「中将殿の姫君は帝が崩御された後に国に下り、若伊香保大明神として顕れた。」とあります。
文脈からすると、中将殿は伊香保姫(伊香保大明神)の夫である高光中将であり、「中将殿の姫君」は、すなわち伊香保姫の御息女にあたることになります。
(『神道集』の神々様「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」から引用。)
「若宮」「若」とはふつう本宮の祭神の子(御子神)を祀った神社をさしますから、御息女である姫御前を祀った神社の社名に「若」がついているのは、うなづけるところでしょうか。
なお、「尾崎喜左雄の説によると、伊香保神社は古くは阿利真公(有馬君)によって有馬の地に祀られており、後に三宮の地に遷座した。これが伊香保神社の里宮(現在の三宮神社)となり、有馬の元社は若伊香保神社と呼ばれるようになった。その後、伊香保温泉の湯前の守護神として分社が勧請され、現在の伊香保神社となった。伊香保温泉にはそれ以前から薬師堂(温泉明神)が祀られていたが、伊香保神社の勧請後はその本地仏とみなされるようになったと考えられる。」(参考文献 尾崎喜左雄「伊香保神社の研究」、『上野国の信仰と文化』所収、尾崎先生著書刊行会、1970)という貴重な情報があります。
→ 情報元・『神道集』の神々様「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」
また、いくつかの資料で「伊香保神社は元々当地に鎮座したとされ、同社が上野国国府近くの三宮神社(北群馬郡吉岡町大久保)に遷座した際、旧社地に祀られたのが若伊香保神社」という説が紹介されています。
〔二ッ岳噴火との関係〕
------------------------------------
神道集の第四十一上野国第三宮伊香保大明神事には、伊香保神社の創祀伝承が描かれています。
前段は「20.五徳山 無量寿院 水澤寺」で引用しましたが、後段にはつぎのような不思議な記述があります。
「人皇四十九代光仁天皇の御代、上野国司の柏階大将知隆は伊香保山で七日間の巻狩を行って山と沼を荒らした。 沼の深さを測ろうとすると、夜の内に小山が出現したので、国司は上奏のために里に下った。 その後、沼は小山の西に移動し、元の沼地は野原になった。 国司は里に下る途中、一頭の鹿を水沢寺の本堂に追い込んで射殺した。 寺の僧たちは殺された鹿を奪い取って埋葬し、国司たちを追い出した。 怒った国司は寺に火をつけて焼き払った。 別当恵美僧正は上京して委細を帝に奏聞した。 帝は国司を佐渡島に流すよう検非違使に命じた。」「伊香保大明神は山の神たちを呼び集めて石楼を造った。 国司が蹴鞠をしていると、伊香保山から黒雲が立ち上り、一陣の旋風が吹き下ろした。 国司と目代は旋風にさらわれて石楼に閉じ込められ、今も焦熱地獄の苦しみを受けている。 山の神たちが石楼を造った山が石楼山である。 この山の北麓の北谷沢には冷水が流れていたが、石楼山が出来てから熱湯が流れるようになり、これを見た人は涌嶺と呼んだ。」
(『神道集』の神々様「第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事」から引用。)
まとめると、
1.光仁天皇の御代(宝亀元年(770年)~天応元年(781年))、伊香保山に一夜にして小山が出現し、山中にある沼が西に移動して元の沼地は野原となった。
2.伊香保大明神は山の神たちを呼び集めて石楼を造った。伊香保山から黒雲が立ち上り、一陣の旋風が吹き下ろした。 国司と目代は旋風にさらわれて石楼に閉じ込められ、今も焦熱地獄の苦しみを受けている。
3.山の神たちが石楼を造った山が石楼山で、この山の北麓の北谷沢には冷水が流れていたが、石楼山が出来てから熱湯が流れるようになり、これを見た人は涌嶺と呼んだ。
1.からは地殻変動、2.からは火山の噴火、3.からは温泉湧出が連想されます。
伊香保温泉には、古墳時代の第十一代垂仁天皇の御代に開かれたという説と、天平時代の僧、行基(668-749年)によって発見されたというふたつの湯縁起が伝わります。(〔 温泉地巡り 〕 伊香保温泉(本ブログ)を参照)
行基伝説をとると、3.と伊香保温泉の開湯は時期的にほぼ符合します。
伊香保温泉の熱源は、6世紀に活動した二ッ岳の火山活動の余熱と考えられています。
伊香保の二ッ岳は、5世紀に火山活動を再開し6世紀中頃までに3回の噴火が発生、うち489~498年に渋川噴火、525~550年にかけて伊香保噴火というふたつの大規模噴火を起こしたことがわかっています。(気象庁「関東・中部地方の活火山 榛名山」より)
神道集の上記2.は光仁天皇の御代(770年~781年)のできごととされているので、二ッ岳の噴火と時代が合いませんが、この噴火を後世で記録したもの、という説があります。
「やぐひろネット・歴史解明のための考古学」様では、この点について詳細かつ綿密な考証をされています。(同Webの関連記事)
また、論文「6世紀における榛名火山の2回の噴火とそ の災害」(1989年早田 勉氏)によると、これら複数の噴火は、伊香保神社、三宮神社、若伊香保神社などが鎮座する榛名山東麓、北麓にかけて甚大な被害をもたらしたことがわかります。
これらの噴火が忘れてはならないできごととして語り継がれ、神道集に繋がったという見方もできるかもしれません。
神道集はかなりスペクタクルな展開で一見荒唐無稽な感じも受けますが、意外と史実を伝えているのかも・・・。
あまりに逸話が多いのでとりとめがなくなってきましたが(笑)、無理矢理とりまとめると、
1.伊香保神社のかつての祭神は伊香保大明神(高野辺大将の三番目の姫君)。
2.伊香保大明神には男体・女体があり、男体は伊香保神社、女体は三宮神社(吉岡町大久保)に鎮座される。
3.伊香保大明神男体(湯前・伊香保神社)は高光中将が顕れ、伊香保大明神女体(里下・三宮神社)は伊香保姫が顕れた。
4.伊香保大明神男体(高光中将)と伊香保大明神女体(伊香保姫)の御息女は若伊香保大明神(渋川・有馬の若伊香保神社)として顕れた。
5.三宮神社は、伊香保神社の里宮とする説がある
6.伊香保神社はもともと若伊香保神社の社地に鎮座し、同社が三宮神社に遷座した際、旧社地に祀られたのが若伊香保神社という説がある。
7.伊香保の湯前神社はもともと薬師堂(温泉明神)で、伊香保神社の遷座?にともない習合して本地薬師如来となったという説がある。
8.伊香保大明神の創祀は、5世紀の渋川噴火、6世紀の伊香保噴火とかかわりをもつという説がある。
無理矢理とりまとめても(笑)、やはりぜんぜんまとめきれません。
というかナゾは深まるばかりです。
伊香保はお気に入りの温泉地なので、時間をかけてナゾを解きほぐしていければと考えています。
〔 御朱印 〕
これほどの古名社でありながら、現在伊香保神社には神職は常駐されておりません。(最近は、週末は社務所で授与いただけます。)
わたしは以前、参道階段下の饅頭屋さんで書置のものをいただきましたが、最近は平日でも拝殿前に書置が置かれているという情報もあります。
また、渋川八幡宮でも神職がいらっしゃれば書入れの御朱印を拝受できます。(現況は不明)

土日祝に社務所で授与される鶴亀の御朱印
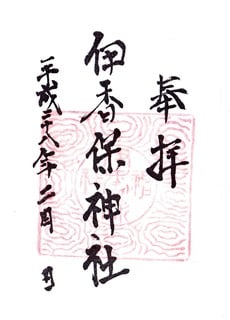

【写真 上(左)】 書置の御朱印(参道階段横饅頭屋さんにて)
【写真 下(右)】 書入れの御朱印(渋川八幡宮にて)
書置き、書入れともに中央に神社印、中央に「伊香保神社」の揮毫があります。
なお、三宮神社、若伊香保神社ともに無住で、御朱印の授与については確認できておりません。
また、若伊香保神社のとなりに、いかにも別当寺然としてある曹洞宗の満行山泰叟寺も参拝しましたが、御朱印は非授与とのことでした。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)へ
※ 渋川スカイランドそばに令和元年建立された関東石鎚神社でも御朱印を授与されています。
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ ホール・ニュー・ワールド - 熊田このは & 二木蒼生
"A Whole New World" by Konoha Kumada(with Aoi Niki).1/12/2020 at The Mizonokuchi Theater in Kawasaki/JAPAN.
■ Open Your Heart - Yuki Kajiura(FictionJunction)
■ PLANETES - Hitomi(黒石ひとみ)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町石廊崎18
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番
授与所:庫裡
山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。
(由緒書では開山は高厳。)
すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。
正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。
海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。
当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。
『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。
また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山内
県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。
石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。
木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。
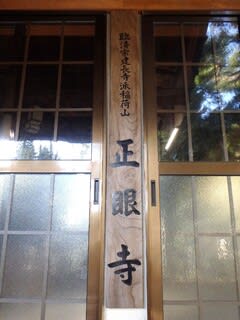

【写真 上(左)】 寺号板
【写真 下(右)】 大棟妻部
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天井絵
本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。
御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。
『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。
また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
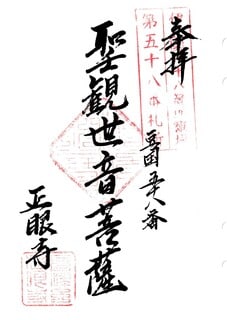
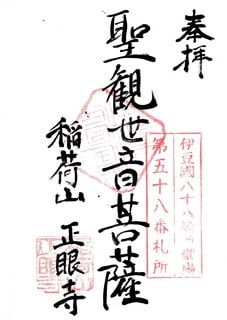
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
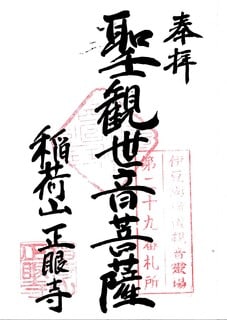
すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。
数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。
■ 石室神社(いろうじんじゃ)
南伊豆町観光協会Web
南伊豆町石廊崎125
主祭神:伊波例命
旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)
授与所:社務所
伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。
石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。
古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。
拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。
役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。
文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。
そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。
天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)
南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、
延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。
延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。
上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。
以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。
『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」
「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。
南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。
また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)
天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。
社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。
こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。
南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。
その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。
すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。
江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。
船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。
現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。
石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。
こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)
石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。
幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。
(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)
ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。
その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。
お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。
お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。
------------------------------


【写真 上(左)】 石廊崎港
【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)


【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク
【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道
石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。
石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 遊歩道
【写真 下(右)】 ツワブキ
オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。
途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。
石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。


【写真 上(左)】 灯台近く
【写真 下(右)】 石廊崎灯台


【写真 上(左)】 灯台の説明板
【写真 下(右)】 灯台~石室神社
ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。
このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。


【写真 上(左)】 拝殿への降り階段
【写真 下(右)】 拝殿


【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1
【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2
灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。
明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。


【写真 上(左)】 拝殿内
【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内


【写真 上(左)】 帆柱の説明
【写真 下(右)】 帆柱
床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。
長さ六間約12メートルとのことです。
拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。


【写真 上(左)】 役行者の奉納額
【写真 下(右)】 拝所


【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社
【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿
そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。
突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。


【写真 上(左)】 熊野神社参道-1
【写真 下(右)】 熊野神社参道-2


【写真 上(左)】 東側の眺望-1
【写真 下(右)】 東側の眺望-2
木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。
『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。


【写真 上(左)】 突端-1
【写真 下(右)】 突端-2
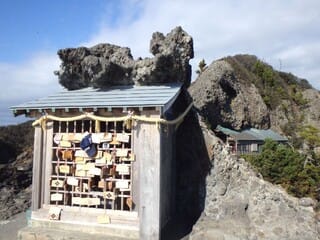

【写真 上(左)】 熊野神社-1
【写真 下(右)】 熊野神社-2
岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。
岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。


【写真 上(左)】 南側の眺望-1
【写真 下(右)】 南側の眺望-2
振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。
ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。


【写真 上(左)】 クルーズ船
【写真 下(右)】 北側の眺望


【写真 上(左)】 西側の眺望-1
【写真 下(右)】 西側の眺望-2
御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。


【写真 上(左)】 拝殿と社号標
【写真 下(右)】 授与所
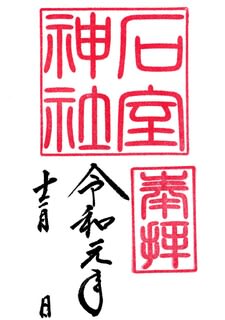
石室神社の御朱印
なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。
--------------------
・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。
御祭神 伊波例命・物忌奈命
合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王
境内社 熊野神社(須佐之男命)
※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。
■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町入間949
臨済宗建長寺派
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:弥勒菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。
東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。
集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。
無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。
ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。
第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。
入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。
千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。
開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。
明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。
海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。
『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。
このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 あたりの海岸-1
【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

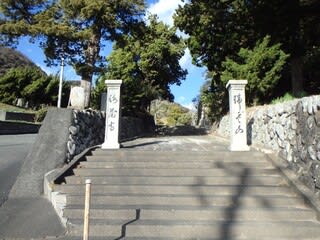
【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン
【写真 下(右)】 参道入口
南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。
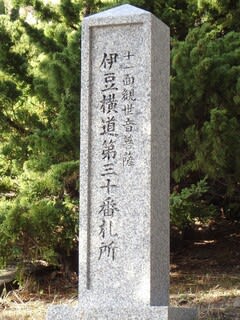

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。
伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。
山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。
門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。


【写真 上(左)】 おたふくの石像
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 十二支守り本尊
【写真 下(右)】 六地蔵
境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。
参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。
向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。
御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。


【写真 上(左)】 堂内山号扁額
【写真 下(右)】 布袋尊
なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
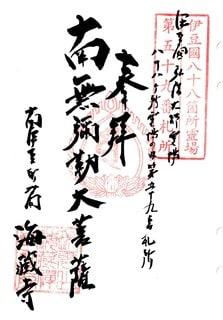

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。
(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
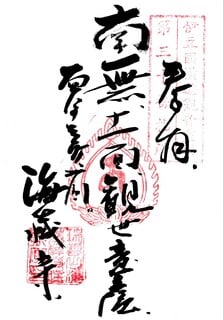
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕
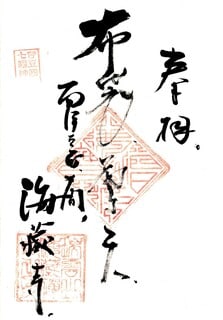
■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良809
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)
授与所:庫裡
第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。
妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。
妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。
「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。
周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。
第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。
三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。
なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。
詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。
善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。
天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。
妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。
『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。
このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 妻良港
【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道階段
妻良の集落の西側山ぎわにあります。
路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。
階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

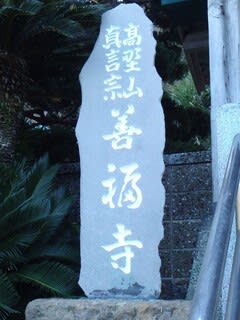
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。
向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。
見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。
御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。
伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
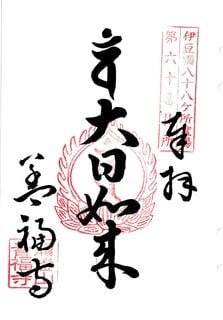
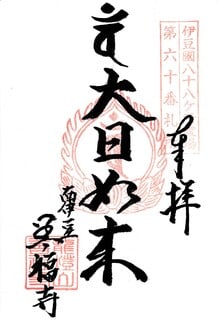
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
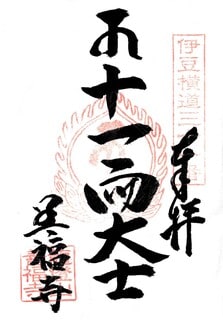
※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。
■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良1213
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:寺役管理
妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。
国道136号から枝道を少し入ったところ。
住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。
この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。
『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。
『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。
現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。
その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。
参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。
思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。
向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)
現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。
なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。
--------------------
【 BGM 】
■ Just Be Yourself - 杏里/Anri
■ Never Let Me Go - 中村舞子
■ LONESOME MERMAID - 今井美樹
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町石廊崎18
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番
授与所:庫裡
山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。
(由緒書では開山は高厳。)
すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。
正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。
海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。
当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。
『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。
また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山内
県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。
石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。
木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。
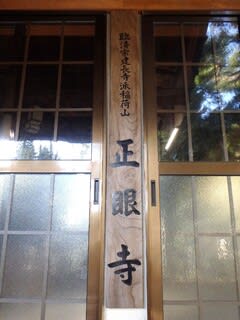

【写真 上(左)】 寺号板
【写真 下(右)】 大棟妻部
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天井絵
本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。
御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。
『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。
また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
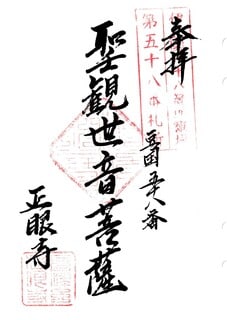
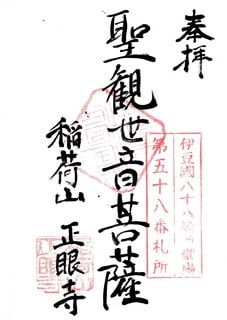
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
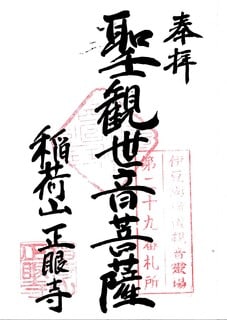
すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。
数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。
■ 石室神社(いろうじんじゃ)
南伊豆町観光協会Web
南伊豆町石廊崎125
主祭神:伊波例命
旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)
授与所:社務所
伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。
石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。
古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。
拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。
役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。
文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。
そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。
天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)
南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、
延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。
延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。
上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。
以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。
『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」
「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。
南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。
また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)
天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。
社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。
こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。
南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。
その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。
すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。
江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。
船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。
現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。
石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。
こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)
石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。
幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。
(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)
ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。
その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。
お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。
お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。
------------------------------


【写真 上(左)】 石廊崎港
【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)


【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク
【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道
石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。
石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 遊歩道
【写真 下(右)】 ツワブキ
オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。
途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。
石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。


【写真 上(左)】 灯台近く
【写真 下(右)】 石廊崎灯台


【写真 上(左)】 灯台の説明板
【写真 下(右)】 灯台~石室神社
ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。
このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。


【写真 上(左)】 拝殿への降り階段
【写真 下(右)】 拝殿


【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1
【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2
灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。
明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。


【写真 上(左)】 拝殿内
【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内


【写真 上(左)】 帆柱の説明
【写真 下(右)】 帆柱
床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。
長さ六間約12メートルとのことです。
拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。


【写真 上(左)】 役行者の奉納額
【写真 下(右)】 拝所


【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社
【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿
そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。
突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。


【写真 上(左)】 熊野神社参道-1
【写真 下(右)】 熊野神社参道-2


【写真 上(左)】 東側の眺望-1
【写真 下(右)】 東側の眺望-2
木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。
『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。


【写真 上(左)】 突端-1
【写真 下(右)】 突端-2
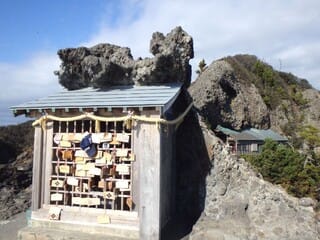

【写真 上(左)】 熊野神社-1
【写真 下(右)】 熊野神社-2
岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。
岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。


【写真 上(左)】 南側の眺望-1
【写真 下(右)】 南側の眺望-2
振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。
ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。


【写真 上(左)】 クルーズ船
【写真 下(右)】 北側の眺望


【写真 上(左)】 西側の眺望-1
【写真 下(右)】 西側の眺望-2
御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。


【写真 上(左)】 拝殿と社号標
【写真 下(右)】 授与所
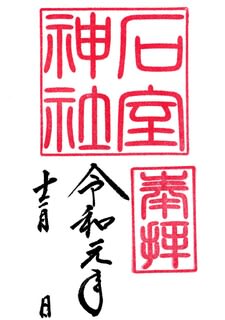
石室神社の御朱印
なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。
--------------------
・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。
御祭神 伊波例命・物忌奈命
合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王
境内社 熊野神社(須佐之男命)
※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。
■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町入間949
臨済宗建長寺派
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:弥勒菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。
東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。
集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。
無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。
ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。
第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。
入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。
千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。
開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。
明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。
海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。
『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。
このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 あたりの海岸-1
【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

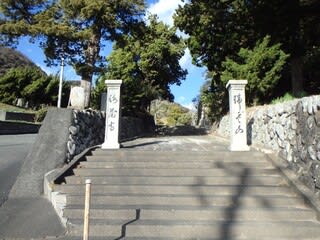
【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン
【写真 下(右)】 参道入口
南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。
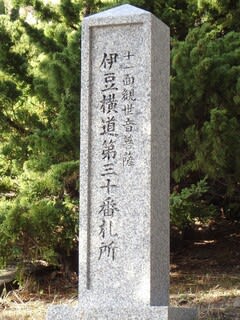

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。
伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。
山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。
門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。


【写真 上(左)】 おたふくの石像
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 十二支守り本尊
【写真 下(右)】 六地蔵
境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。
参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。
向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。
御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。


【写真 上(左)】 堂内山号扁額
【写真 下(右)】 布袋尊
なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
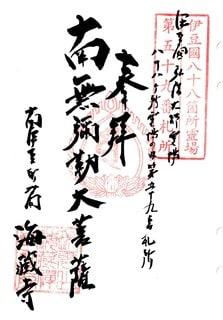

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。
(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
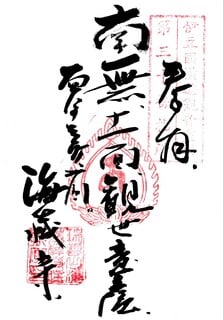
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕
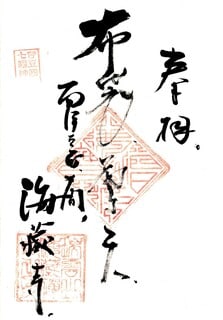
■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良809
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)
授与所:庫裡
第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。
妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。
妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。
「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。
周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。
第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。
三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。
なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。
詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。
善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。
天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。
妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。
『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。
このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 妻良港
【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道階段
妻良の集落の西側山ぎわにあります。
路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。
階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

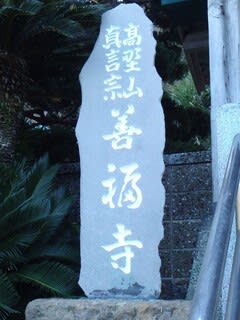
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。
向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。
見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。
御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。
伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
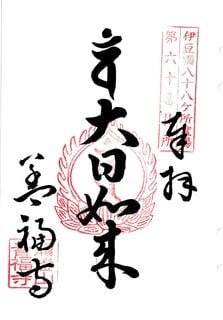
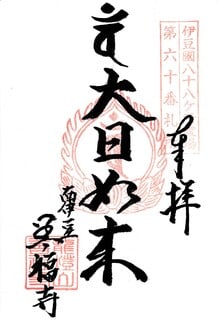
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
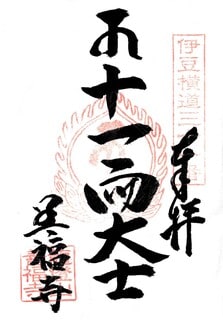
※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。
■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良1213
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:寺役管理
妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。
国道136号から枝道を少し入ったところ。
住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。
この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。
『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。
『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。
現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。
その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。
参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。
思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。
向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)
現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。
なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。
--------------------
【 BGM 】
■ Just Be Yourself - 杏里/Anri
■ Never Let Me Go - 中村舞子
■ LONESOME MERMAID - 今井美樹
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)から。
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづく。
26.多福山 一乗院 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
大町にある日蓮宗寺院。
新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。
現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ以降佐竹氏の屋敷になったといいます。
應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。
源義光公は戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。
山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)はもともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀されて、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。
ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。
『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。
佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。
『新編鎌倉志』
「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」
『鎌倉攬勝考』
「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」
ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。
佐竹隆義・秀義は、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げの際に参陣せず、同年秋の富士川の戦いでは平家方につきました。
富士川の敗戦の後、本拠の常陸へ逃れた秀義は頼朝勢に追撃され(金砂城の戦い)、奥州・花園へと落ち延びました。
しかし文治五年(1189年)以前に秀義は頼朝公に帰順、奥州合戦で武功を上げて御家人の地位を確保しています。
富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。
佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とする常陸の名族。
しかも義光公の室(義業の母)は桓武平氏の平(吉田)清幹の息女で、佐竹氏は桓武平氏の流れもひいています。
秋霜烈日な頼朝公も、名族・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。
「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」
「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。
應永十四年(1407年)第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。
足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。
与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。
應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。
これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝わります。
上記から、1400年代中盤までは佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。
應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。
「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。
佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。
新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。
義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。
その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。
---------------------


【写真 上(左)】 道標
【写真 下(右)】 山内入口
大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどみられず閑静な住宅地となっています。
大寳寺は、この小路からさらに左手山側に入ったところにあります。
位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。


【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。
参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 お題目塔
本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。
正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。
こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。
本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。


【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神
【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額
山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。
拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。
新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)
御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。
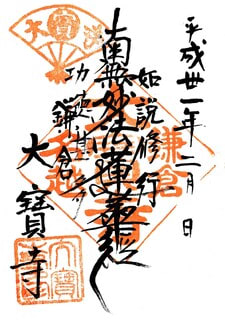
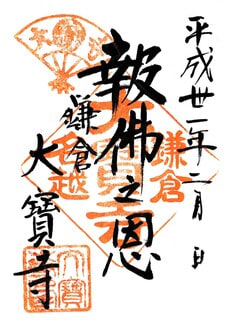
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
永保三年(1083年)新羅三郎源義光公の勧請とされる、鎌倉を代表する古社で大町の鎮守です。
神奈川県神社庁Web、『鎌倉市史』などによる創祀は以下のとおりです。
永保三年(1083年)、義光公は奥州討伐「後三年の役」で苦戦している兄・八幡太郎源義家公の助勢に赴く途中、鎌倉に立ちよられました。
この地に悪疫が流行し郷民が苦しんでいるのをみた義光公は、「厄除神」として霊験あらたかな京の祇園社を勧請して祈願されたところ悪疫は退散し郷民は救われました
以後郷民はこのお社を”祇園さま”と崇め奉り、篤く信仰してきました。
應永年間(1394-1428年)には、当社東側の佐竹屋敷に祀られていた祠が合祀されて「佐竹天王」と称し、また御輿一座を「佐竹天王」と呼びならわすともいいます。
文安六年(1449年)、当社の神興が足利成氏の管領屋敷に渡御し奉幣の式が催されています。(『鎌倉年中行事』)
天正十四年(1586年)、北条氏直治世の時には「当社祭礼に際し不敬不礼の者は権門といえでも厳科に処す」という禁制守護状が下賜され、当社の神威がきわめて高かったことがうかがわれます。
徳川家康公も当社への尊崇の念篤く、朱印地(神領)を下賜されています。
社号は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社とも称していましたが、明治維新に際して八雲神社と改号しています。
大町総鎮守として明治6年村社に列格、明治40年神饌幣帛料供進神社に昇格。
明治44年には村内の上諏訪神社(名越)、下諏訪神社(米町)、神明社(米町)、古八幡社(中座町)の4社を合併しています。
いまも厄除開運の神社として地元では「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれて親しまれ、毎年7月の神幸祭(大町まつり)の「神興渡御」や「神輿くぐり」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり祇園天王社の記載があります。
「松殿町ニアリ。永保年中(1081-1084年)新羅三郎義光ノ勧請ニテ。神体ハ秘像ト云伝フ。氏成管領ノ頃ハ。毎年六月七日。公方屋敷ニ御輿ヲ渡シテ。神楽ヲ奏シ奉幣ノ式アリ。又十四日ノ祇園会モ是ト同シ。築地ノ上桟敷ヲ構ヘ。舞練物等見物アリ。又應永年中(1394-1428年)佐竹四郎義秀ノ霊ヲ祀シ社。其屋鋪蹟ニアリシカ。後年大破ニ及シヨリ玆ニ合祀スト云フ。其年代詳ラナス。故ニ土俗佐竹天王ト称ス。按スルニ。義秀ハ頼朝ニ属セシ人ニテ時代違ヘリ。應永(1394-1428年)ノ末ニ。其末葉佐竹上総介義顕入道。管領持氏ノ不審ヲ蒙リ討手ヲ引請。終ニ比企谷ノ法華堂(今ノ妙本寺也)ニテ自害ス。其霊祟アリトテ。一社ニ祀リシ事アリ。是今相殿ノ舊社ニテ。義秀ト云フハ義顕ノ誤ナルベシ。例祭舊ニ因テ。六月七日ヨリ十四日迄行ハル。本日当村乱橋村ノ二所ニ。仮屋ヲ設。前ノ二村。小町村。又雪ノ下村ノ内。大蔵町ノ四所ニ。四座ノ神輿。巡行アルヲ例トス。天正十四年(1586年)六月小田原北條氏ヨリ祭礼ノ時ノ制札ヲ出セリ。」
御祭神として須佐之男命(スサノヲ)、配偶神である稲田姫命、スサノヲの御子神とされる八王子命、そして佐竹氏霊が祀られています。
『新編相模國風土記稿』の大寳寺(多福明神社)の項には下記の記載があります。
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
大寳寺(多福明神社)には佐竹氏の霊廟があり、こちらは佐竹天王祭禮で彼神渡御を行っていたので、八雲神社の御祭神の一座「佐竹氏霊」とゆかりがあるのかも。
また「彼祇園ノ相殿」とは八雲神社の相殿をさすのかもしれません。
大寳寺の山内掲示(抜粋)には以下のとおりあるので、やはり八雲神社に合祀ののち、大多福稲荷大明神として大寳寺に再勧請という流れとみられます。
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
スサノヲは神仏習合のもとで牛頭天王と習合し、「祇園信仰」のもと各地で祀られています。
「祇園信仰」にはいくつかの流れがあり、社号によってそのおおよその流れがわかるともいわれますが、例外も多くあります。
・京都祇園の八坂神社からの勧請系では、八坂神社、弥栄神社、祇園神社、八雲神社、八剣神社など。
・播磨・姫路の広峯神社からの勧請系では、広峯神社、素盞嗚神社など。
・須佐神社(紀伊有田ないし出雲国)からの勧請系では、須佐神社、八雲神社など。
・須賀神社からの勧請系では、須賀神社、素鵞神社、須我神社など。
・愛知の津島神社からの勧請系では、津島神社、天王(神)社など
当社は京祇園の八坂神社からの勧請系で当初は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社を号し、明治以降は八雲神社を号されています。
なお、関東地方でスサノヲを祀る神社として氷川神社がありますが、こちらは「氷川(簸川)信仰」にもとづくもので「祇園信仰」とは別の系統という説があります。
鎌倉の祇園信仰関連社として当社を含む4つの八雲神社(大町、西御門、山ノ内、常盤)が数えられ、うち御朱印授与は当社のみの模様です。
---------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 社頭
小町大路を蛭子神社の北から東に別れ、滑川にかかる琴弾橋を渡って妙本寺総門、常栄寺、八雲神社と辿って南下する小路(名称不明)は、東に山肌が迫り古都らしい落ち着いた住宅地がつづく風情ある道行きです。
八雲神社の社頭はこの小路に面しています。
この小路は狭く駐車場もないので、1本西の小町大路沿いのコインパーキングへの駐車がベター。近年リーズナブル料金のPが増えてきました。


【写真 上(左)】 一の鳥居
【写真 下(右)】 二の鳥居
社頭は石垣で数段高く、裏山づたいの緑がうっそうと茂っています。
石造の神明鳥居(一の鳥居)をくぐると空気感が変わります。
参道を行くと左手に手水舎。
その先に朱塗り灯籠一対、玉垣&石段の左右に阿吽の狛犬一対、さらに金属造の神明鳥居(二の鳥居)と、地域の中核社らしくきっちりまとまった印象。


【写真 上(左)】 境内-1
【写真 下(右)】 境内-2
山肌迫る境内の正面に本社拝殿、左右に境内社、左手手前に「新羅三郎手玉石」、左手脇に宝物殿。
本殿左右の社叢は生い茂ってほの暗く、パワスポ的雰囲気をまとっています。
本殿向かって右手は祇園山ハイキングコースの登り口です。


【写真 上(左)】 手玉石
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿は入母屋造桟瓦葺で、手前に軒唐破風の向拝を付設しています。
鬼板に御神紋。兎毛通部に鳥の彫刻。
水引虹梁両端には見返りの獅子、頭貫上に大がかりな斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に豪壮な龍?の彫刻を配して見応えのある意匠です。
こちらは、鎌倉・逗子・葉山エリアの十数社の神社の本務社で、それぞれ御朱印を授与されているので幾度となくお伺いしていますが、どんな季節でも天気でも、この神さびた雰囲気は変わりませんでした。
御朱印は向かって右の社務所にて授与されていますが、12時から13時半は避けた方がいいかもしれません。
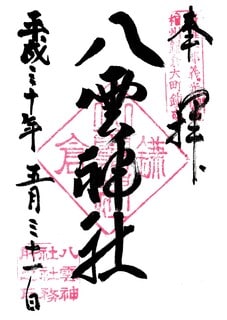
御朱印
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
「ぼたもち寺」として親しまれる日蓮宗寺院です。
「龍ノ口法難」の際、片瀬の処刑場に引かれていく日蓮聖人にこの地に住む尼が胡麻のぼたもちを献上、その直後に片瀬龍ノ口で日蓮聖人を救う奇跡が起こったため、このぼたもちは「頸つぎのぼたもち」といわれ、「ぼたもち寺」として名が広がりました。
龍口寺の公式Webによると「龍ノ口法難」は以下のような内容です。
鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病など災厄に見舞われていました。
これを憂えた日蓮聖人は『立正安国論』を著されて幕府に奏上しました。
しかし、幕府はこれを政策への中傷と捉え、文永八年(1272年)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえて斬首するために鎌倉から片瀬の刑場龍ノ口へ連行し土牢へと押し込めました。
(御内人・平頼綱の独断で連行という説もあり。)
翌13日の未明、土牢から引き出された日蓮聖人は敷皮石に坐らされあわや斬首になるというそのとき、「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。
この法難は後世「龍ノ口法難」と呼ばれ、日蓮聖人の四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)に数えられています。
「龍ノ口法難」の地である龍ノ口には、日蓮聖人直弟子の日法上人が延元二年(1337年)一堂を建立され、その後本山(霊跡寺院)として高い寺格を有しています。
毎年9月11~13日「龍口法難会」として大法要が営まれ、ぼたもちが御宝前にお供ええされ、高所から撒かれて参詣者にも振る舞われます。
これが龍口寺の「難除けのぼたもち」で、「龍ノ口法難」における”ぼたもち”の存在の大きさがうかがわれます。
常栄寺にも資料類の掲示がありましたので、こちらをベースに縁起等をまとめてみます。
源頼朝公は由比ヶ浜での千羽鶴の放鳥を遠望するため、当山の裏山に桟敷(展望台)を設けたといわれます。
この地には鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王(在任1252-1266年)の近臣、印東次郎左衛門尉祐信夫妻が住んでおり、理縁尼ないし桟敷の尼(法名:妙常日栄)と称したその妻がくだんのぼたもちの尼であったといいます。
当山資料には「七百年後の今日においてもなお毎年九月十二日御法難会に際し、当寺より住職、信徒威儀を正して唱題のうちに片瀬龍口寺の祖師像に胡麻の餅を供えるのを古来よりの例としている。」とあります。
印東夫妻の法華経信仰を褒めたたえる日蓮聖人の書簡が伝わっているので、すでにこの地で草庵が結ばれていたとみられますが、寺院としての創立は比企谷・池上両山十四世自証院日証上人(日祐上人とも)により慶長十一年(1606年)と伝わります。
創立時に宝篋堂壇林(僧侶養成所)も開かれ、元禄二年(1689年)池上に移されて南谷壇林となりました。
開山の際、桟敷の尼の法名から常栄寺と号し、夫妻の墓を桟敷大明神として勧請されたようです。
桟敷の尼がぼたもちづくりに使われた木鉢とおはぐろ壺は当山に、お盆替わりに使われた鍋蓋は龍口寺にいまも所蔵されるといいます。
---------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山門
八雲神社の並びに山を背にしてあります。
朱塗りで屋根つきの冠木門といった風の変わった山門で、門柱には「ぼたもち寺」とあります。
左の門柱には「たつのくち 首の御座をふし拝む 老婆のまごころ ぼたもち 常栄寺」の句。


【写真 上(左)】 山門からの山内
【写真 下(右)】 山内のあしらい
山門左右には立派なお題目塔。
本堂に向かってまっすぐのびる参道の両脇には草花が植えられ、野趣あふれる山内です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂

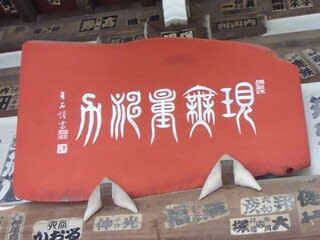
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝で、屋根中央に大がかりな千鳥破風を興して見応えがあります。
破風上には経の巻獅子口、下には猪の目懸魚、板蟇股の左右に端正な斗栱を備えています。
水引虹梁両端は貫がなく木鼻もありません。頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
全体に鎌倉の古寺らしい風雅な趣きを備えています。
向拝見上げには扁額がかかっていますが、不勉強につき読解不能です。


【写真 上(左)】 縁起
【写真 下(右)】 ぼたもちの句
御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できますが。受付は下記の通りで要注意です。
11:00~12:00、13:00~15:00
御首題は御首題帳限定授与かもしれませんが未確認。
御朱印は句と御詠歌の2種あるようですが、混雑時には1人1種となることもあるようです。

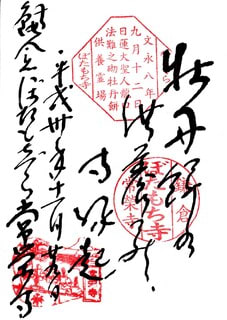
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印(句)
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
大聖寺殿東陽岱公(北條左京大夫氏康/1515-1571年)が開基となり、知阿上人が開山と伝わる時宗寺院です。
当初は光明寺山内の北の山際にありましたが、延寶六年(1678年)現在地へ移転。
現在地にはもともと光明寺末の善昌寺があり、廃寺となったため移転と伝わります。
大町の街なかにひっそりと佇む比較的地味なお寺ですが、平家の公達にかかわる哀しい寺伝をもちます。
『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。
「寶海山と号す。米町の内にあり。時宗、藤澤道場の末寺なり。里老の伝、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを、延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ、平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像。打ちうなづきけるとなん。寺寶 盃壱個 平重衡、千壽前と酒宴の時の盃なりと言伝ふ。」
また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり教恩寺の記載があります。
「中座町ニアリ。中座山(鎌倉志に寶海山トアリ。貞享已後改シニヤ。)大聖院ト号ス。藤澤清浄光寺末。開山ハ知阿開基ハ俗称ヲ傳ヘズ。大聖院東陽岱公トノミ伝フ。是北條左京大夫氏康ノ法名ニテ。今大住郡栗原村萬松寺ニ其碑アリ。鎌倉志。里老ノ言ヲ引テ。舊ハ光明寺ノ境内。北ノ山際ニ在シヲ。延寶六年(1678年)僧貴譽此地ニ移ス。元此地ニ善昌寺ト云フ光明寺ノ末寺アリ。其寺廃無セシガ故当寺ヲ爰ニ移シ。元ノ当寺蹟ヲ所化寮トスト記セリ。三尊ノ彌陀(運慶作)ヲ本尊トス。寺伝ニ是ハ元暦元年(1184年)平家沒落ノ時。三位中将重衡囚レテ。鎌倉ニ在シ程。賴朝ガ授与ノ靈像ニテ重衡ガ帰依佛ナリト伝フ。当安置ノ来由伝ハラズ。寺寶 盃三口 共ニ重衡ノ盃ト伝フ。」
御本尊の阿弥陀三尊像は、一ノ谷の戦いで敗れて捕虜になり鎌倉へ護送された三位中将平重衡に、「平家一族の冥福を祈るように」と源頼朝公が贈ったお像と伝わります。
重衡はこの阿弥陀像に篤く帰依し、臨終正念(極楽成仏?)を祈ったところ、この阿弥陀像は「打ちうなづきけるとなん。」と伝わります。(『新編鎌倉志』)
また、当山寺宝として重衡の盃が伝わり、これは重衡が愛した”千手の前”との酒宴で使われたものとの由。
平重衡(たいらのしげひら)は、平清盛公の五男で母は清盛の継室・平時子(二位尼)。
妻は大納言藤原邦綱の息女・藤原輔子。
若くして正三位左近衛権中将に進み、三位中将と称された平家の公達です。
弱冠ながら平家の大将として各地を転戦し、源平合戦の墨俣川の戦い、水島の戦いで源氏方を破るなど活躍したものの一ノ谷の戦いで捕虜になり、寿永三年(1184年)3月、伊豆を経て鎌倉へと護送されました。
平氏滅亡後、重衡による南都焼討を恨んだ南都衆徒の要求で引き渡され、木津川畔で斬首されました。
その優れた将器は「武勇の器量に堪ふる」(『玉葉』)と賞されるとともに、その容姿は牡丹の花に例えられるほどだったといいます。
また、『玉葉和歌集』に撰ばれた勅撰歌人でもあります。
いわば文武兼ね備えたイケメン公達で、他人への心づかいがあり、話術にも長けていたため宮中の女性にすこぶる人気があったらしく、『平家公達草紙』によると都落ちの際、御所に別れの挨拶に訪れた折には大勢の女房たちが涙にくれたといいます。
こういう清々しい人物はどこにいっても大事にされるものですが、じっさい鎌倉に送られたあとも風雅な逸話を残しています。
『吾妻鏡』には、重衡がはじめて頼朝公に対面した折、「囚人の身となったからには、もはやあれこれ言う事もない。弓馬の者が敵方の(武功の)ために捕虜になり命を落とすことは恥ではない。早く斬罪にされよ。」ときっぱり答えて周囲を感歎させたとあります。
頼朝公は重衡の度量に感心して彼を狩野宗茂に預け、北条政子は重衡の世話役として侍女の千手の前をつけました。
頼朝公が重衡を慰めるため設けた宴では、工藤祐経が鼓を打って今様を謡い、千手の前は琵琶を弾き、重衡がこれにあわせて横笛を吹き、朗詠を吟じてその風雅なありさまは『平家物語』にも描かれています。
千手の前は駿河国手越長者の娘で、温和な性格の女性だったと伝わります。(実在については諸説あり。)
ほどなく重衡に惹かれるようになり、重衡と千手の前は恋におちて結ばれたといいます。
元暦二年(1185年)6月、南都焼討を恨む南都衆徒の要求により、重衡はやむなく南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。
東大寺の使者に引き渡されてほどなく木津川畔にて斬首されました。
享年29と伝わります。
なお、重衡は生前の元暦元年(1184年)に法然と対面し、受戒しているとされます。(→「平重衡の問に念仏往生を示す御詞」/浄土宗大辞典Web)
重衡の妻の輔子は重衡の南都護送の途中、伏見の日野で最期の対面を果たし、『平家物語』の名場面のひとつに数えられています。
輔子は重衡の遺骸を引き取り、日野に墓を建て法界寺(日野薬師)の僧に供養を託しました。
輔子はその後出家して、大原寂光院に隠棲した建礼門院に仕えたといいます。
『平家物語』の”大原御幸の巻”で登場し、”六道の巻”では建礼門院が極楽往生を遂げる際に阿波内侍とともにこれを看取った様が描かれています。
千手の前は重衡の死のわずか三年後に24歳でこの世を去り、鎌倉の人々は千手が重衡を朝夕恋慕し、それが積み重なっての憂死と噂したといいます。(『吾妻鏡』)
『平家物語』では、千手は出家して信濃の善光寺に入り、重衡の菩提を弔ったとあります。
重衡と千手とのかかわりは能の『千手』で演じられ、仏都・南都を焼き討ちした身と敬虔な仏徒としての葛藤を描いた修羅能『重衡』も能の演目として知られています。
- 住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ -
(『玉葉和歌集』(勅撰)巻第8 旅歌 平重衡)
---------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門からの山内
大町大路と小町大路が交差する「大町四ツ角」の北西の路地のおくにひっそりと佇みます。
鎌倉観光ではエアポケット的な立地で、鎌倉三十三観音霊場の巡拝者のほかは拝観者は少ない模様です。


【写真 上(左)】 紫陽花と本堂
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、前面中備の十六羅漢と裏面の牡丹の彫刻がみどころとされます。
すこぶる手入れのいきとどいた山内で、小枝ひとつ落ちていません。


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 向拝-1
石畳の参道正面に(おそらく)入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
いずれもすばらしい仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額で、ムダがなくバランスのよい向拝まわりです。


【写真 上(左)】 御朱印所
【写真 下(右)】 寺号板
御本尊の阿弥陀如来像と両脇侍立像は鎌倉時代前期の作とみられ、一説では運慶の作ともいわれる名作で県重要文化財に指定されています。
鎌倉三十三観音第12番の札所本尊、聖観世音菩薩も本堂内の御座です。
御朱印は本堂脇の御朱印所にて拝受しました。
〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕
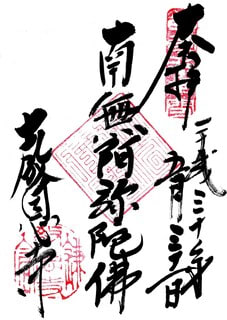
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

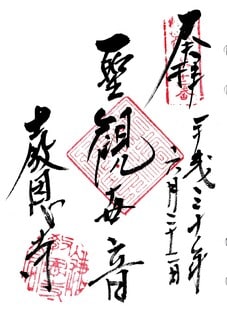
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は三寶印です。
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづきます。
【 BGM 】
■ New Frontier - Donald Fagen
■ On And On - Angela Bofill
■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)から。
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづく。
26.多福山 一乗院 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
大町にある日蓮宗寺院。
新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。
現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ以降佐竹氏の屋敷になったといいます。
應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。
源義光公は戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。
山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)はもともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀されて、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。
ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。
『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。
佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。
『新編鎌倉志』
「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」
『鎌倉攬勝考』
「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」
ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。
佐竹隆義・秀義は、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げの際に参陣せず、同年秋の富士川の戦いでは平家方につきました。
富士川の敗戦の後、本拠の常陸へ逃れた秀義は頼朝勢に追撃され(金砂城の戦い)、奥州・花園へと落ち延びました。
しかし文治五年(1189年)以前に秀義は頼朝公に帰順、奥州合戦で武功を上げて御家人の地位を確保しています。
富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。
佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とする常陸の名族。
しかも義光公の室(義業の母)は桓武平氏の平(吉田)清幹の息女で、佐竹氏は桓武平氏の流れもひいています。
秋霜烈日な頼朝公も、名族・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。
「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」
「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。
應永十四年(1407年)第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。
足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。
与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。
應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。
これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝わります。
上記から、1400年代中盤までは佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。
應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。
「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。
佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。
新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。
義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。
その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。
---------------------


【写真 上(左)】 道標
【写真 下(右)】 山内入口
大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどみられず閑静な住宅地となっています。
大寳寺は、この小路からさらに左手山側に入ったところにあります。
位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。


【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。
参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 お題目塔
本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。
正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。
こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。
本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。


【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神
【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額
山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。
拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。
新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)
御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。
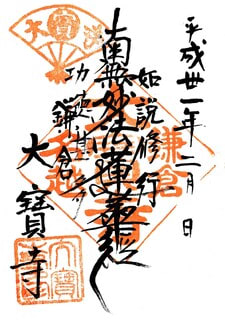
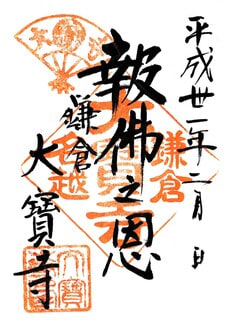
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
永保三年(1083年)新羅三郎源義光公の勧請とされる、鎌倉を代表する古社で大町の鎮守です。
神奈川県神社庁Web、『鎌倉市史』などによる創祀は以下のとおりです。
永保三年(1083年)、義光公は奥州討伐「後三年の役」で苦戦している兄・八幡太郎源義家公の助勢に赴く途中、鎌倉に立ちよられました。
この地に悪疫が流行し郷民が苦しんでいるのをみた義光公は、「厄除神」として霊験あらたかな京の祇園社を勧請して祈願されたところ悪疫は退散し郷民は救われました
以後郷民はこのお社を”祇園さま”と崇め奉り、篤く信仰してきました。
應永年間(1394-1428年)には、当社東側の佐竹屋敷に祀られていた祠が合祀されて「佐竹天王」と称し、また御輿一座を「佐竹天王」と呼びならわすともいいます。
文安六年(1449年)、当社の神興が足利成氏の管領屋敷に渡御し奉幣の式が催されています。(『鎌倉年中行事』)
天正十四年(1586年)、北条氏直治世の時には「当社祭礼に際し不敬不礼の者は権門といえでも厳科に処す」という禁制守護状が下賜され、当社の神威がきわめて高かったことがうかがわれます。
徳川家康公も当社への尊崇の念篤く、朱印地(神領)を下賜されています。
社号は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社とも称していましたが、明治維新に際して八雲神社と改号しています。
大町総鎮守として明治6年村社に列格、明治40年神饌幣帛料供進神社に昇格。
明治44年には村内の上諏訪神社(名越)、下諏訪神社(米町)、神明社(米町)、古八幡社(中座町)の4社を合併しています。
いまも厄除開運の神社として地元では「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれて親しまれ、毎年7月の神幸祭(大町まつり)の「神興渡御」や「神輿くぐり」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり祇園天王社の記載があります。
「松殿町ニアリ。永保年中(1081-1084年)新羅三郎義光ノ勧請ニテ。神体ハ秘像ト云伝フ。氏成管領ノ頃ハ。毎年六月七日。公方屋敷ニ御輿ヲ渡シテ。神楽ヲ奏シ奉幣ノ式アリ。又十四日ノ祇園会モ是ト同シ。築地ノ上桟敷ヲ構ヘ。舞練物等見物アリ。又應永年中(1394-1428年)佐竹四郎義秀ノ霊ヲ祀シ社。其屋鋪蹟ニアリシカ。後年大破ニ及シヨリ玆ニ合祀スト云フ。其年代詳ラナス。故ニ土俗佐竹天王ト称ス。按スルニ。義秀ハ頼朝ニ属セシ人ニテ時代違ヘリ。應永(1394-1428年)ノ末ニ。其末葉佐竹上総介義顕入道。管領持氏ノ不審ヲ蒙リ討手ヲ引請。終ニ比企谷ノ法華堂(今ノ妙本寺也)ニテ自害ス。其霊祟アリトテ。一社ニ祀リシ事アリ。是今相殿ノ舊社ニテ。義秀ト云フハ義顕ノ誤ナルベシ。例祭舊ニ因テ。六月七日ヨリ十四日迄行ハル。本日当村乱橋村ノ二所ニ。仮屋ヲ設。前ノ二村。小町村。又雪ノ下村ノ内。大蔵町ノ四所ニ。四座ノ神輿。巡行アルヲ例トス。天正十四年(1586年)六月小田原北條氏ヨリ祭礼ノ時ノ制札ヲ出セリ。」
御祭神として須佐之男命(スサノヲ)、配偶神である稲田姫命、スサノヲの御子神とされる八王子命、そして佐竹氏霊が祀られています。
『新編相模國風土記稿』の大寳寺(多福明神社)の項には下記の記載があります。
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
大寳寺(多福明神社)には佐竹氏の霊廟があり、こちらは佐竹天王祭禮で彼神渡御を行っていたので、八雲神社の御祭神の一座「佐竹氏霊」とゆかりがあるのかも。
また「彼祇園ノ相殿」とは八雲神社の相殿をさすのかもしれません。
大寳寺の山内掲示(抜粋)には以下のとおりあるので、やはり八雲神社に合祀ののち、大多福稲荷大明神として大寳寺に再勧請という流れとみられます。
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
スサノヲは神仏習合のもとで牛頭天王と習合し、「祇園信仰」のもと各地で祀られています。
「祇園信仰」にはいくつかの流れがあり、社号によってそのおおよその流れがわかるともいわれますが、例外も多くあります。
・京都祇園の八坂神社からの勧請系では、八坂神社、弥栄神社、祇園神社、八雲神社、八剣神社など。
・播磨・姫路の広峯神社からの勧請系では、広峯神社、素盞嗚神社など。
・須佐神社(紀伊有田ないし出雲国)からの勧請系では、須佐神社、八雲神社など。
・須賀神社からの勧請系では、須賀神社、素鵞神社、須我神社など。
・愛知の津島神社からの勧請系では、津島神社、天王(神)社など
当社は京祇園の八坂神社からの勧請系で当初は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社を号し、明治以降は八雲神社を号されています。
なお、関東地方でスサノヲを祀る神社として氷川神社がありますが、こちらは「氷川(簸川)信仰」にもとづくもので「祇園信仰」とは別の系統という説があります。
鎌倉の祇園信仰関連社として当社を含む4つの八雲神社(大町、西御門、山ノ内、常盤)が数えられ、うち御朱印授与は当社のみの模様です。
---------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 社頭
小町大路を蛭子神社の北から東に別れ、滑川にかかる琴弾橋を渡って妙本寺総門、常栄寺、八雲神社と辿って南下する小路(名称不明)は、東に山肌が迫り古都らしい落ち着いた住宅地がつづく風情ある道行きです。
八雲神社の社頭はこの小路に面しています。
この小路は狭く駐車場もないので、1本西の小町大路沿いのコインパーキングへの駐車がベター。近年リーズナブル料金のPが増えてきました。


【写真 上(左)】 一の鳥居
【写真 下(右)】 二の鳥居
社頭は石垣で数段高く、裏山づたいの緑がうっそうと茂っています。
石造の神明鳥居(一の鳥居)をくぐると空気感が変わります。
参道を行くと左手に手水舎。
その先に朱塗り灯籠一対、玉垣&石段の左右に阿吽の狛犬一対、さらに金属造の神明鳥居(二の鳥居)と、地域の中核社らしくきっちりまとまった印象。


【写真 上(左)】 境内-1
【写真 下(右)】 境内-2
山肌迫る境内の正面に本社拝殿、左右に境内社、左手手前に「新羅三郎手玉石」、左手脇に宝物殿。
本殿左右の社叢は生い茂ってほの暗く、パワスポ的雰囲気をまとっています。
本殿向かって右手は祇園山ハイキングコースの登り口です。


【写真 上(左)】 手玉石
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿は入母屋造桟瓦葺で、手前に軒唐破風の向拝を付設しています。
鬼板に御神紋。兎毛通部に鳥の彫刻。
水引虹梁両端には見返りの獅子、頭貫上に大がかりな斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に豪壮な龍?の彫刻を配して見応えのある意匠です。
こちらは、鎌倉・逗子・葉山エリアの十数社の神社の本務社で、それぞれ御朱印を授与されているので幾度となくお伺いしていますが、どんな季節でも天気でも、この神さびた雰囲気は変わりませんでした。
御朱印は向かって右の社務所にて授与されていますが、12時から13時半は避けた方がいいかもしれません。
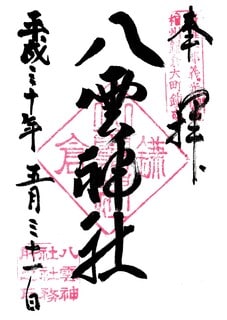
御朱印
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
「ぼたもち寺」として親しまれる日蓮宗寺院です。
「龍ノ口法難」の際、片瀬の処刑場に引かれていく日蓮聖人にこの地に住む尼が胡麻のぼたもちを献上、その直後に片瀬龍ノ口で日蓮聖人を救う奇跡が起こったため、このぼたもちは「頸つぎのぼたもち」といわれ、「ぼたもち寺」として名が広がりました。
龍口寺の公式Webによると「龍ノ口法難」は以下のような内容です。
鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病など災厄に見舞われていました。
これを憂えた日蓮聖人は『立正安国論』を著されて幕府に奏上しました。
しかし、幕府はこれを政策への中傷と捉え、文永八年(1272年)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえて斬首するために鎌倉から片瀬の刑場龍ノ口へ連行し土牢へと押し込めました。
(御内人・平頼綱の独断で連行という説もあり。)
翌13日の未明、土牢から引き出された日蓮聖人は敷皮石に坐らされあわや斬首になるというそのとき、「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。
この法難は後世「龍ノ口法難」と呼ばれ、日蓮聖人の四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)に数えられています。
「龍ノ口法難」の地である龍ノ口には、日蓮聖人直弟子の日法上人が延元二年(1337年)一堂を建立され、その後本山(霊跡寺院)として高い寺格を有しています。
毎年9月11~13日「龍口法難会」として大法要が営まれ、ぼたもちが御宝前にお供ええされ、高所から撒かれて参詣者にも振る舞われます。
これが龍口寺の「難除けのぼたもち」で、「龍ノ口法難」における”ぼたもち”の存在の大きさがうかがわれます。
常栄寺にも資料類の掲示がありましたので、こちらをベースに縁起等をまとめてみます。
源頼朝公は由比ヶ浜での千羽鶴の放鳥を遠望するため、当山の裏山に桟敷(展望台)を設けたといわれます。
この地には鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王(在任1252-1266年)の近臣、印東次郎左衛門尉祐信夫妻が住んでおり、理縁尼ないし桟敷の尼(法名:妙常日栄)と称したその妻がくだんのぼたもちの尼であったといいます。
当山資料には「七百年後の今日においてもなお毎年九月十二日御法難会に際し、当寺より住職、信徒威儀を正して唱題のうちに片瀬龍口寺の祖師像に胡麻の餅を供えるのを古来よりの例としている。」とあります。
印東夫妻の法華経信仰を褒めたたえる日蓮聖人の書簡が伝わっているので、すでにこの地で草庵が結ばれていたとみられますが、寺院としての創立は比企谷・池上両山十四世自証院日証上人(日祐上人とも)により慶長十一年(1606年)と伝わります。
創立時に宝篋堂壇林(僧侶養成所)も開かれ、元禄二年(1689年)池上に移されて南谷壇林となりました。
開山の際、桟敷の尼の法名から常栄寺と号し、夫妻の墓を桟敷大明神として勧請されたようです。
桟敷の尼がぼたもちづくりに使われた木鉢とおはぐろ壺は当山に、お盆替わりに使われた鍋蓋は龍口寺にいまも所蔵されるといいます。
---------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山門
八雲神社の並びに山を背にしてあります。
朱塗りで屋根つきの冠木門といった風の変わった山門で、門柱には「ぼたもち寺」とあります。
左の門柱には「たつのくち 首の御座をふし拝む 老婆のまごころ ぼたもち 常栄寺」の句。


【写真 上(左)】 山門からの山内
【写真 下(右)】 山内のあしらい
山門左右には立派なお題目塔。
本堂に向かってまっすぐのびる参道の両脇には草花が植えられ、野趣あふれる山内です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂

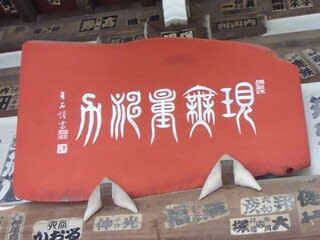
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝で、屋根中央に大がかりな千鳥破風を興して見応えがあります。
破風上には経の巻獅子口、下には猪の目懸魚、板蟇股の左右に端正な斗栱を備えています。
水引虹梁両端は貫がなく木鼻もありません。頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
全体に鎌倉の古寺らしい風雅な趣きを備えています。
向拝見上げには扁額がかかっていますが、不勉強につき読解不能です。


【写真 上(左)】 縁起
【写真 下(右)】 ぼたもちの句
御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できますが。受付は下記の通りで要注意です。
11:00~12:00、13:00~15:00
御首題は御首題帳限定授与かもしれませんが未確認。
御朱印は句と御詠歌の2種あるようですが、混雑時には1人1種となることもあるようです。

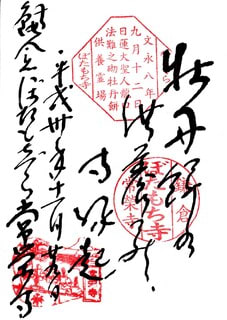
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印(句)
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
大聖寺殿東陽岱公(北條左京大夫氏康/1515-1571年)が開基となり、知阿上人が開山と伝わる時宗寺院です。
当初は光明寺山内の北の山際にありましたが、延寶六年(1678年)現在地へ移転。
現在地にはもともと光明寺末の善昌寺があり、廃寺となったため移転と伝わります。
大町の街なかにひっそりと佇む比較的地味なお寺ですが、平家の公達にかかわる哀しい寺伝をもちます。
『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。
「寶海山と号す。米町の内にあり。時宗、藤澤道場の末寺なり。里老の伝、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを、延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ、平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像。打ちうなづきけるとなん。寺寶 盃壱個 平重衡、千壽前と酒宴の時の盃なりと言伝ふ。」
また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり教恩寺の記載があります。
「中座町ニアリ。中座山(鎌倉志に寶海山トアリ。貞享已後改シニヤ。)大聖院ト号ス。藤澤清浄光寺末。開山ハ知阿開基ハ俗称ヲ傳ヘズ。大聖院東陽岱公トノミ伝フ。是北條左京大夫氏康ノ法名ニテ。今大住郡栗原村萬松寺ニ其碑アリ。鎌倉志。里老ノ言ヲ引テ。舊ハ光明寺ノ境内。北ノ山際ニ在シヲ。延寶六年(1678年)僧貴譽此地ニ移ス。元此地ニ善昌寺ト云フ光明寺ノ末寺アリ。其寺廃無セシガ故当寺ヲ爰ニ移シ。元ノ当寺蹟ヲ所化寮トスト記セリ。三尊ノ彌陀(運慶作)ヲ本尊トス。寺伝ニ是ハ元暦元年(1184年)平家沒落ノ時。三位中将重衡囚レテ。鎌倉ニ在シ程。賴朝ガ授与ノ靈像ニテ重衡ガ帰依佛ナリト伝フ。当安置ノ来由伝ハラズ。寺寶 盃三口 共ニ重衡ノ盃ト伝フ。」
御本尊の阿弥陀三尊像は、一ノ谷の戦いで敗れて捕虜になり鎌倉へ護送された三位中将平重衡に、「平家一族の冥福を祈るように」と源頼朝公が贈ったお像と伝わります。
重衡はこの阿弥陀像に篤く帰依し、臨終正念(極楽成仏?)を祈ったところ、この阿弥陀像は「打ちうなづきけるとなん。」と伝わります。(『新編鎌倉志』)
また、当山寺宝として重衡の盃が伝わり、これは重衡が愛した”千手の前”との酒宴で使われたものとの由。
平重衡(たいらのしげひら)は、平清盛公の五男で母は清盛の継室・平時子(二位尼)。
妻は大納言藤原邦綱の息女・藤原輔子。
若くして正三位左近衛権中将に進み、三位中将と称された平家の公達です。
弱冠ながら平家の大将として各地を転戦し、源平合戦の墨俣川の戦い、水島の戦いで源氏方を破るなど活躍したものの一ノ谷の戦いで捕虜になり、寿永三年(1184年)3月、伊豆を経て鎌倉へと護送されました。
平氏滅亡後、重衡による南都焼討を恨んだ南都衆徒の要求で引き渡され、木津川畔で斬首されました。
その優れた将器は「武勇の器量に堪ふる」(『玉葉』)と賞されるとともに、その容姿は牡丹の花に例えられるほどだったといいます。
また、『玉葉和歌集』に撰ばれた勅撰歌人でもあります。
いわば文武兼ね備えたイケメン公達で、他人への心づかいがあり、話術にも長けていたため宮中の女性にすこぶる人気があったらしく、『平家公達草紙』によると都落ちの際、御所に別れの挨拶に訪れた折には大勢の女房たちが涙にくれたといいます。
こういう清々しい人物はどこにいっても大事にされるものですが、じっさい鎌倉に送られたあとも風雅な逸話を残しています。
『吾妻鏡』には、重衡がはじめて頼朝公に対面した折、「囚人の身となったからには、もはやあれこれ言う事もない。弓馬の者が敵方の(武功の)ために捕虜になり命を落とすことは恥ではない。早く斬罪にされよ。」ときっぱり答えて周囲を感歎させたとあります。
頼朝公は重衡の度量に感心して彼を狩野宗茂に預け、北条政子は重衡の世話役として侍女の千手の前をつけました。
頼朝公が重衡を慰めるため設けた宴では、工藤祐経が鼓を打って今様を謡い、千手の前は琵琶を弾き、重衡がこれにあわせて横笛を吹き、朗詠を吟じてその風雅なありさまは『平家物語』にも描かれています。
千手の前は駿河国手越長者の娘で、温和な性格の女性だったと伝わります。(実在については諸説あり。)
ほどなく重衡に惹かれるようになり、重衡と千手の前は恋におちて結ばれたといいます。
元暦二年(1185年)6月、南都焼討を恨む南都衆徒の要求により、重衡はやむなく南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。
東大寺の使者に引き渡されてほどなく木津川畔にて斬首されました。
享年29と伝わります。
なお、重衡は生前の元暦元年(1184年)に法然と対面し、受戒しているとされます。(→「平重衡の問に念仏往生を示す御詞」/浄土宗大辞典Web)
重衡の妻の輔子は重衡の南都護送の途中、伏見の日野で最期の対面を果たし、『平家物語』の名場面のひとつに数えられています。
輔子は重衡の遺骸を引き取り、日野に墓を建て法界寺(日野薬師)の僧に供養を託しました。
輔子はその後出家して、大原寂光院に隠棲した建礼門院に仕えたといいます。
『平家物語』の”大原御幸の巻”で登場し、”六道の巻”では建礼門院が極楽往生を遂げる際に阿波内侍とともにこれを看取った様が描かれています。
千手の前は重衡の死のわずか三年後に24歳でこの世を去り、鎌倉の人々は千手が重衡を朝夕恋慕し、それが積み重なっての憂死と噂したといいます。(『吾妻鏡』)
『平家物語』では、千手は出家して信濃の善光寺に入り、重衡の菩提を弔ったとあります。
重衡と千手とのかかわりは能の『千手』で演じられ、仏都・南都を焼き討ちした身と敬虔な仏徒としての葛藤を描いた修羅能『重衡』も能の演目として知られています。
- 住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ -
(『玉葉和歌集』(勅撰)巻第8 旅歌 平重衡)
---------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門からの山内
大町大路と小町大路が交差する「大町四ツ角」の北西の路地のおくにひっそりと佇みます。
鎌倉観光ではエアポケット的な立地で、鎌倉三十三観音霊場の巡拝者のほかは拝観者は少ない模様です。


【写真 上(左)】 紫陽花と本堂
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、前面中備の十六羅漢と裏面の牡丹の彫刻がみどころとされます。
すこぶる手入れのいきとどいた山内で、小枝ひとつ落ちていません。


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 向拝-1
石畳の参道正面に(おそらく)入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
いずれもすばらしい仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額で、ムダがなくバランスのよい向拝まわりです。


【写真 上(左)】 御朱印所
【写真 下(右)】 寺号板
御本尊の阿弥陀如来像と両脇侍立像は鎌倉時代前期の作とみられ、一説では運慶の作ともいわれる名作で県重要文化財に指定されています。
鎌倉三十三観音第12番の札所本尊、聖観世音菩薩も本堂内の御座です。
御朱印は本堂脇の御朱印所にて拝受しました。
〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕
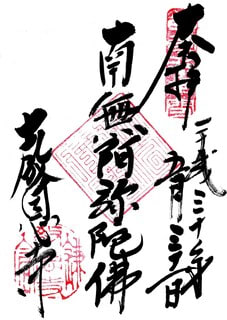
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

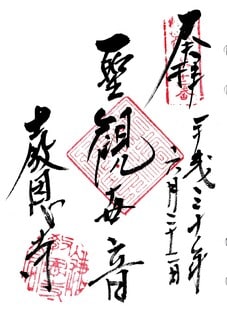
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は三寶印です。
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづきます。
【 BGM 】
■ New Frontier - Donald Fagen
■ On And On - Angela Bofill
■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第49番 神護山 太梅寺(たいばいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市横川342
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』『霊場めぐり』には以下のとおりあります。
寛徳三年(1046年)、弘法大師の法孫・桓舜僧都がこの地に行脚の折、霊夢にひとりの童子があらわれて云うには「此地末世仏法興隆の勝境なれば、ここに一宇を建て法灯を永く伝えて光明世間を照さば利益広大なり。」と。
この地はまさに桓舜僧都の求めていた霊地の地勢でもあったため、歓喜して近在の村人から勧募しこの地に草庵を結びました。この童子は東方の明星(の化身)と伝わります。
ある晩の深夜、ひとりの老人があらわれて「此の地は地蔵薩埵有縁の地なり。汝常に持念の地蔵尊を安置して群生を利せよ。」と告げられました。
桓舜僧都がその名を問うたところ「吾是稲荷神なり。」と告げ、姿を消されました。
桓舜僧都には日頃持念する行基菩薩の御作と伝わる地蔵菩薩があり、このお告げにしたがいこの地蔵尊を御本尊と仰ぎ、背後の山に稲荷神を勧請して守護神(鎮守神)とし、明星山満珠寺と号しました。
保元年中(1156-1159年)、京都高雄山神護寺の再興を後白河天皇に強訴したため、伊豆に流された文覚上人が当寺にて大般若経を写経して源氏再興を祈願され、神護寺と改めたといいます。
後に太梅山深居庵と改め臨済宗に改宗、さらに弘治三年(1557年)には曹洞宗に改宗し深居山太梅寺、嘉永五年(1852年)に現在の神護山太梅寺に定まったと伝わります。
『豆州志稿』には「横川村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊地蔵 寛徳二年(1045年)真言ノ僧建ツ 僧桓舜ヲ祖トス 太梅山深居庵ト号ス(諏訪神社文明十七年(1485年)上梁文ニ深居庵住僧徹定トアリ) 康應元年(1389年)●特賜一源和尚住シ臨済宗ト為ル 天文八年(1539年)相州大住郡田原香雲寺ニ隷ス 香雲寺ハ舊本州下田ニ在テ壽福寺ト称ス ●鵜嶋城(下田城?)ヲ増築ノ時相州ニ移ル 弘治三年(1557年)實堂和尚継席ス 是ヲ開山初祖トス 元和(1615-1624年)ノ頃今ノ称号トス 八幡社慶長十三年(1608年)上梁文ニ太梅寺寂用叟ト記ス 地頭吉田泰盛ノ喜捨文小田原北條氏及安國寺(天正十八年(1590年)豊臣氏東征ノ時ノ文書ナリ)ノ禁牓(札)ヲ蔵ム」とあり、かなり複雑な寺歴をもたれるようです。
下田市宇土金の「(公財)上原美術館」のWebによると、太梅寺には、戦国時代頃に書かれた伊豆最古の禅語録『寂用禅師語録』や、下田の地が戦国時代に戦場だったことを物語る『安国寺恵瓊奉制札』などの貴重な資料が遺されているそうです。
また、御本尊の地蔵菩薩像は絶対秘仏ですが、御前立ちの地蔵菩薩坐像も、中世鎌倉を中心とした禅刹で流行した「法衣垂下」の技法を用いた名作として知られているようです。
■ 紹介動画 ↓
報本寺、太梅寺いずれも、当地の明神、守護神があらわれ、そのお告げを受けて開山されています。
これは、弘法大師が高野山に金剛峯寺を開かれるにあたり、高野御子大神(狩場明神)が高野山まで導かれ、地主神の丹生都比売大神(丹生明神)が神領を譲られて、以降も高野山と深い関係をもったという御由緒に似た展開となっています。
報本寺、太梅寺ともに当初は真言宗での開山であり、高野山開山伝承の影響を受けているのかもしれません。
札所本尊は御本尊の地蔵菩薩。
伊豆八十八ヶ所の南伊豆エリアでは唯一の地蔵菩薩の札所となります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 冠木門
第48番報本寺からすこし下田寄りに戻ったところ、横川温泉のそばにあります。
このあたりには、”飲む温泉”で有名な「観音温泉」、お湯のよさで知られる「昭吉の湯」もあり、温泉好きにはなじみのあるエリアです。
県道側の寺号標から境内までかなりの距離があり、名刹であることがわかります。
駐車場はたしか県道沿いにあったかと思います。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門下
参道入口に冠木門。その先に杉木立の下、苔むした石段が伸びています。
石段の先の山門下は報本寺と同様のがっしりとした石垣で、この寺構はこのあたりの寺院の特徴なのかもしれません。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額
山門は切妻屋根瓦葺、がっしりとした朱塗りの四脚門の山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 鐘楼
山内は正面に本堂、左手に堂宇、右手が庫裡のコの字の伽藍配置。
本堂前の2本の巨木が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、格子戸メインのシンプルな構成。
向拝見上げに寺号扁額を掲げています。
左手の堂宇はなぜか写真が残っていないので不明ですが、経堂か収蔵庫のようなものかもしれません。


【写真 上(左)】 本堂と庫裡
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は雰囲気ある庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第50番 古松山 玄通寺(げんつうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町一條456
曹洞宗
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:-
授与所:第63番保春寺
巡路は稲生沢川沿いの第49番の横川・太梅寺から、いきなり一条川沿いの第50番の玄通寺(南伊豆町一條)に飛び、そこから51番、52番と下田方向に戻るかたちとなります。
いまの道路状況からすると唐突な巡路にみえますが、おそらく稲生沢川沿いの横川から峠を越えて一条川筋に至る巡礼路があったかと思われます。
寺伝によると当初は下田寄りの小松野山の頂上にありましたが、数度の火災で記録を失い創建等は不詳となっています。
開山は玄翁心昭(源翁心照空外)。應永三年(1396年)の入寂につき草創はそれ以前とみられています。
『豆州志稿』には、玄翁心昭は那須野が原の殺生石を破砕して妖事を止められたと記されています。
慶長・元和の頃(1596-1624年)、鶴翁和尚により再興。
明治44年(1911年)に庫裏、翌年には本堂が現在地に移されています。
『豆州志稿』には「一條村 曹洞宗 下田大安寺末 本尊観世音 源翁禅師開基 禅師名ハ心照空外ト号ス 後小松帝能照法王禅師ト(勅)賜スト云(應永三年(1396年)正月七日奥州会津示現寺ニ於テ寂ス 鎌倉海蔵寺源翁傳ニ云弘安三年(1280年)正月七日寂スト) 世ニ傳フ昔下野國那須野ニ毒石アリ 人畜触ルヽ者皆斃レ飛鳥空ヲ過ル者忽堕ツ 世俗殺生石ト云 至徳二年(1385年)八月源翁其地ニ至リ 桂杖ヲ以テ破碎ス 妖事立トコロニ止ムト 是蓋齊東野人ノ談ナラム 此地水ナキヲ憂フ 村人四郎左衛門地ヲ穿チテ泉ヲ得タリ 其井今存ス 禅師之ヲ賞シテ古钁ノ氏ヲ賜フ 寺野焼ニ遇フ事数々ニシテ世代ヲ失ス 今鶴翁和尚ヲ祖トス 慶長(1596-1615年)元和(1615-1624年)ノ頃ノ人ナリ 至徳三年(1386年)源翁ニ賜フト云綸旨 幷松永清左衛門(天文廿年(1551年)ノ文書ナリ)今村傳四郎父子等ノ寄進状ヲ蔵ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 六地蔵と参道階段
一条川に沿って走る県道119号下田松崎線に面して参道入口。そのよこに若干の駐車スペースがあります。
周囲は人家も少なく、通る車もまれです。
入口は木柵で閉じられていますが、鍵はかかっていないので木柵を引いて入れます。
右手に六地蔵と立派な寺号標。正面参道階段の先に本堂が見えます。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内
境内には六字御名号「南無阿弥陀佛」の碑がありました。
曹洞宗で御本尊は正観世音菩薩ですが、阿彌陀信仰が入っていたのかもしれません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱のないすっきりとしたつくり。
右手には庫裡がありますが、こちらは無住寺院です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 庫裡
上原美術館のWebによると、当寺には江戸後期~明治時代作の木像「鳥抱き猿像」が伝わり、「その姿には災いや病を『取り(鳥)去る(猿』という意味が込められている可能性があります。」との由。
上原美術館に収蔵され通常非公開ですが、特別展などで展示されることがあるようです。
御朱印は第63番保春寺(南伊豆町加納)にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 正観世音菩薩

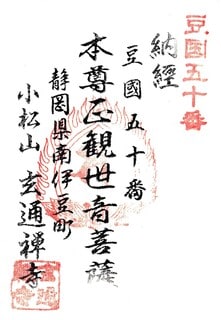
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第51番 青谷山 龍雲寺(りゅううんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町青市143
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:第54番長谷寺
現地掲示の寺伝などによると、鎌倉時代の宝治二年(1284年)に青市地内別当向丘に真言宗の寺院として創建。
永禄十二年(1569年)、下田曹洞院三世了堂和尚により再興し曹洞宗に改宗されています。
その後、火災により焼失したのち、天文五年(1740年)に当山裏山の地に新築移転。
暴風により倒壊したため文化二年(1805年)、現在地に本堂などを新築しています。
『豆州志稿』には「青市村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊阿彌陀 永禄中(1558-1570年)曹洞院三世了堂和尚建ツ 初真言宗ナリ 了堂再興シテ改宗ス 寺後ニ側黒石ト云アリ 天正十八年(1590年)安國寺ノ禁牓ヲ蔵ム」とあります。
「安國寺ノ禁牓(制状)」(天正十八年(1590年)豊臣秀吉東征の役の文書)を蔵しています。
-------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 山内入口
県道119号下田松崎線から南下して国道136号の下賀茂北部に至る枝道から、さらに入ったところにあります。
観光ではほとんど来ない場所かと思います。


【写真 上(左)】 天神社
【写真 下(右)】 山内-1
道はさほど悪くなく、駐車スペースもあります。
参道よこの天神社は菅原道真公を祀り、昭和58年の改修です。


【写真 上(左)】 山内-2
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造銅板葺。がっしりとした大棟にはふたつの御紋、両端に経の巻獅子口。
そこから降る隅棟には一の鬼、二の鬼を配し、あわせて6つの経の巻獅子口を備えて見応えがあります。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
右手の庫裡寄りには海鼠壁とその上に端正な花頭窓を置いて、インパクトのある意匠。
正面格子扉のうえに山号扁額をおいています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は第54番長谷寺(下田市田牛)にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第52番 少林山 曹洞院(そうとういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市大賀茂89
曹洞宗
御本尊:胎蔵大日如来
札所本尊:胎蔵大日如来・十一面観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第25番
授与所:庫裡
ふたたび県道119号に戻り、大賀茂付近で山側に入ったところにあります。
このあたりの札所では大規模な寺院です。
幾度の火災で記録を失い沿革は不明ですが、かつては弘法大師修行の霊蹟で大師山(永禅庵)と号し、末寺十数箇寺を擁した真言宗の大刹と伝わります。(のちに少林山と改号)
下田市Web資料『弘法大師の御墨水』によると、弘法大師が御巡錫の折に秘法を修された曹洞院は、もとは下田市大賀茂林山にありました。
弘法大師が修法中に裏山で錫を立てられると、清列な水が湧き出たのでこの水を硯にとられて経を浄書されたので「弘法大師の御墨水」「金剛浄水」とも呼ばれています。
天文元年(1532年)、中村民部少輔宗賢は相州・海沢、新井の二城に拠って三浦道寸と戦いましたが破れ、大賀茂の曹洞院に逃れてこれを再興して開基となりました。(『南豆風土記』)
宗賢遺物の太刀、鎗、兜、鎧、轡などが曹洞院に所蔵されているそうです。
なお「三浦道寸」は、ふつう相模国守護の三浦義同(1451-1516年)を指すようです。
中村宗賢による再建は大永五年(1525年)で、このときに香雲寺の能庵宗為を請して曹洞宗へ改宗、慶長元年(1596年)、開基宗賢の嫡子・兵部宗尊が堂宇を再建という説もあります。
『豆州志稿』には「吉佐美村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 開林能庵和尚(天文十年(1541年)寂ス)寺ニ前ノ民部侍郎竹了宗賢ノ牌アリ 旁書曰弘治三年(1557年)ト豈此人ノ開基ナルカ 寮舎ノ後ニ民部ノ宅跡アリ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
山門は切妻屋根の四脚門で、以前は茅葺でしたが現在は桟瓦葺となっています。
延宝九年(1681年)建立の棟札が残ります。
江戸時代初期の様式を残すとされ、彫刻は左甚五郎作とも伝わります。
天保十二年(1841年)火災により堂字什宝を失いましたが、山門は類焼を免れ往時の面影をとどめるといいます。
山門に立ち手を打つと、裏山より鶯の鳴き声に似た応えがあるので「鶯門」とも呼ばれます。
山門には山号扁額が掲げられ、その手前には札所標があります。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2
数段の階段をのぼった先に、花緑青色の鮮やかな屋根が葺かれた本堂。
入母屋造銅板葺で向拝柱はありませんが、向拝屋根が付設されています。
向拝正面はアールヌーヴォー風の両開きの扉で、どことなく龍宮門的な趣きがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は庫裡にて拝受しました。
伊豆横道三十三観音霊場の札所で、こちらの御朱印も拝受しています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 胎蔵大日如来・十一面観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※御朱印帳書入の御朱印尊格は胎蔵大日如来となっています。
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第53番 佛谷山 寶徳院(ほうとくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市吉佐美1667
曹洞宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:-
授与所:庫裡
三島の第17番(泉福寺)以来の不動明王の札所です。
こちらも比較的規模の大きな寺院で、草創は貞観年中(859-877年)と伝わります。
天安二年(858年)、中国の長安にある青龍寺で学んだ僧が千体仏を請じて帰国した際、船が難破し吉佐美の浜に打ち上げられました。
浜に漂着した千体仏を安置するために結んだ庵が当寺の始まりと伝わります。
応永二年(1395年)に吉佐美入条の人土屋某が(改めて?)小庵を結び、宝徳元年(1449年)、伊豆山の僧が来住し寺となして真言宗に属しました。
天正五年(1577年)には、曹洞宗の僧吉叟が尾賀茂の延命寺をここに遷して合併し伽藍を整えたと伝わります。
その後一時空院となりましたが、寛文二年(1662年)香雲寺の僧天国が再興したといいます。
寺伝によると御本尊の不動明王は六、七世紀頃、中インドのマカダ国から中国の都・長安の青龍寺に伝えられたもので、入唐して青龍寺で学ばれた智証大師円珍(814-891年)が請来した千体仏のひとつであるといわれています。
『霊場めぐり』によると、治承四年(1180年)、源頼朝公が武衛七人を連れて当院に立ち寄ったとき、砂鉄で茶釜をつくり薬湯を点じて病人に飲ませたところ、たちどころに病が癒えたと伝わります。
こういう奇瑞もあってか頼朝公の御本尊の不動明王への尊崇は篤く、後世も伊豆一円の人々の信仰を集めたと伝わります。
わが国への不動明王の伝来は天平年間(729-766年)~800年代初頭とみられており、こちらの不動明王は最初期の御像とみることができます。
→ ご参考〔日本最古の不動明王について〕
『豆州志稿』には「吉佐美村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊不動 寶徳中土屋某庵ヲ立ツ 天正五年吉叟和尚(俗姓土屋)寺トシ創建ノ時ノ紀号ヲ寺名トス 昔佛像ヲ多く載タル船 此濱ニテ破壊セリ 因テ取立テ此谷ニ夥ク積ミ置ケリ故ニ佛谷ト云 人取去テ今ハ無シ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
吉佐美の集落の山側にあり、開けて明るいイメージの寺院です。
本堂は入母屋造桟瓦葺妻入りで、向拝柱を置いています。
向拝格子扉のうえに山号扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 札所板
堂内は妻入りだけあってふところがふかく、不動尊の堂宇らしい張り詰めた空気感。
背後の山手、通称”ホトケ岩”には三十三観音、十六羅漢、金比羅堂などが安置され山内霊場(佛谷山)となっています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 山内霊場(佛谷山)の参道
御朱印は庫裡にて拝受しました。
第65番最福寺(南伊豆町上賀茂)の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第54番 浦岳山 長谷寺(ちょうこくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市田牛156
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
下田の吉佐美から海岸沿いをタライ岬方面に進んだところに田牛(とうじ)の集落があります。
ここには田牛温泉という独自源泉があり、以前から温泉巡りのなかで狙っていましたが、日帰り施設がみつからず痛恨の未湯湯となっています。
南伊豆の湯巡りルートからは外れているので、今回初の来訪です。
天平年間(729-749年)、行基菩薩の開創と伝わる古刹で、もとは真言宗古義派に属し、西老山昌善寺と称しました。
天文十四年(1545年)に現在の浦岳山長谷寺に号を改め、明暦元年(1655年)、曹洞院九世来室栄撮を請じて曹洞宗に改宗しました。
『豆州志稿』には「田牛村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊阿彌陀 天平中行基建ツト云 古名西光山昌善寺 治承四年八月僧弘禅彌陀像ヲ遠谷島ノ岳浦ニ獲タリ 天文十四年正月初テ寺ニ納ム 其後所獲ノ地名ヲ以テ寺号トシ 亦真言ヲ改テ洞家トナリ曹洞院ニ隷ス 時ノ住僧来室ヲ以テ始祖トス(時ニ寛永二年ナリト云 来室ハ曹洞院九世宗) 天文十三年激浪ノ為寺地●没ス 乃現地ニ移ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 本堂
田牛の集落の山手にあります。
石垣に堀割の参道階段。階段のぼり口には「国指定 重要文化財 木像阿弥陀如来坐像」の標識が建っています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 札所板
山内はこぢんまりとして、すぐ正面が本堂です。
入母屋造銅板葺で、向拝柱と屋根を付設しています。
屋根の勾配が緩く、ちょっと変わったイメージの堂宇です。
簡素な水引虹梁。向拝柱には札所板が掲げられています。
御本尊の阿弥陀如来像は治承四年(1180年)田牛村遠国島の岳浦に漂着し、末寺の昌幸寺に安置されていたもので、天文十四年(1545年)、改宗と同時期に当山に御本尊として遷座されたといいます。
檜材割矧(わりはぎ)造、定朝様式の坐像で国の重要文化財に指定され、文化庁資料には「平安時代の作品」とあります。
『霊場めぐり』には「田牛から青市、湊辺にかけては蒲屋御厨(かばやみくりや)と呼ばれ、古くは伊勢神宮領であったことが『神鳳抄』(鎌倉時代の書)にあることから、この地方が意外に早く開けたことを示している。」とあり、平安時代の仏像が遺されている理由となっているかもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
第51番龍雲寺(南伊豆町青市)の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来
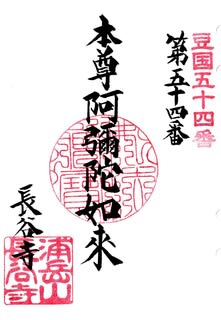
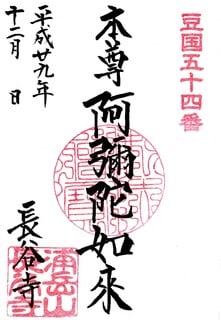
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第55番 飯盛山 修福寺(しゅうふくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町湊662
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第26番
授与所:庫裡
第55番~58番は、下田から石廊崎に向かう県道16号下田石廊松崎線沿いに点在します。
南伊豆の海岸線をたどる風光明媚な巡路です。
第55番修福寺は『こころの旅』によると、「当初大和の国大安寺の支院として開創。(大安寺は現在は真言宗だが以前は(南都六宗の一つ)三論宗で大安寺流の寺として知れわたっていた。)」とのこと。
三論宗の歴史をたどれる寺院は東日本では稀少です。
当初は南伊豆町青市の大寺山にあって石門寺と号し、後に手石から現在地に移転しています。
手石から現在地へは天文十三年(1544年)寂用栄順和尚が移され、師の香雲寺四世実堂宗梅を開山として請じ、その折に寺名と宗旨を改めたといいます。
『豆州志稿』には「湊村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊薬師 本手石村石ノ洞門ニ在テ石門寺ト称ス 天文十三年(1544年)寂用和尚玆ニ移シ寺名ト宗旨トヲ易フ 初真言ノ道場ナリキ香雲寺四世宗梅ヲ請シテ改宗ノ祖ト為ス」とあります。
所蔵の「紙本墨書大般若経」は大治五年(1130年)国司(大江)通国、源盛賴等の奥書があり、国の重要文化財に指定されています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
伊豆屈指の砂浜、弓ヶ浜の山側にある禅刹です。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 六地蔵と参道
うっそうと木立の茂る石段をのぼっていきます。
石段手前には寺号標と札所標。
こちらは伊豆横道三十三観音霊場の札所でもあるので、併記された札所標です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 収蔵庫?
のぼり切ると正面に本堂。左手に収蔵庫?、右手に庫裡。
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱のないシンプルな構成ですが、桁行きがありどっしり落ち着いた印象です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
お声がけすると本堂を開けていだけました。
本堂内見上げに「瑠璃殿」の扁額。
堂内は天蓋がかかって華やかで、どことなく密寺の雰囲気もあるのは、元真言密寺のなごりでしょうか。
観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩。こちらは十句観音経と御真言をお唱えし、庫裡にて両霊場の御朱印を拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
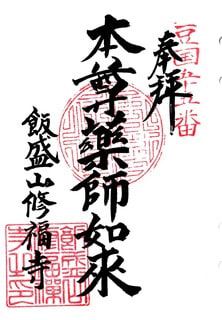

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第56番 養珠山 正善寺(しょうぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町手石165
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:第55番修福寺
当初は真言宗寺院で詳善寺と号していました。
寛永年間(1624-1644年)に修福寺五世嶺屋秀雪が開山となり曹洞宗に改宗しています。
『豆州志稿』には「手石村 曹洞宗 湊村修福寺末 本尊薬師 法継不詳 寛永(1624-1644年)ノ嶺屋和尚ヨリ修福寺ニ隷ス 寺号初作詳善寺 寺内ノ大日堂近年焼亡ス 或云ニ寺(青龍正善)倶ニ係新建ト当村ノ古寺ハ皆小堂ト為リタリ」とあります。
御本尊の「木造伝大日如来坐像」は運慶作とも伝わり、静岡県の有形文化財に指定されています。
県Web資料には「桧材、寄木造、彩色及び古色、玉眼嵌入 鎌倉時代 鎌倉時代前期の檜材寄木造。慶派の作品。台座に付いていた銘札によれば、元久2(1205)年、大仏師雲慶作の大日如来と伝えられている。」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内
青野川沿いにある禅刹です。
青野川河岸から伸びる参道脇には石仏が並んでいます。
無住でこぢんまりとした山内。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺、向拝柱のないシンプルな堂前で扁額もありません。
御朱印は第55番修福寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来

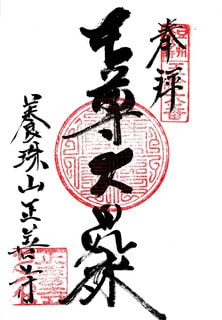
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第57番 東海山 青龍寺(せいりゅうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町手石329
臨済宗建長寺派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
寺伝には嘉禄元年(1225年)の開創とありますが、享保(1716-1736年)初期の火災で記録一切を焼失しているため詳細は不明とされます。
『豆州志稿』によると、佛印禅師(應永四年(1397年)寂)を開山として再興しています。
現在の本堂は享保五年(1720年)築と伝わります。
『豆州志稿』には「手石村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊観世音 佛印禅師ヲ開山トス(應永四年(1397年)寂ス) 嘉禄(1225-1227年)中ノ創立ナリト云 後衰頽ニ属セシヲ 佛印再興ス」とあります。
寺宝として白隠禅師直筆の「宝鏡窟の記」が所蔵されています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標
こちらも青野川の流れにほど近いところにあります。
参道入口に自然石の寺号標。
そこから山門に向かってまっすぐに参道が伸びています。


【写真 上(左)】 山門と本堂
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根本瓦葺の風格ある四脚門で、正面の本堂の屋根といいコントラストをみせています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁と身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股をおいています。
札所本尊はこの霊場では比較的めずらしい如意輪観世音菩薩。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 如意輪観世音菩薩
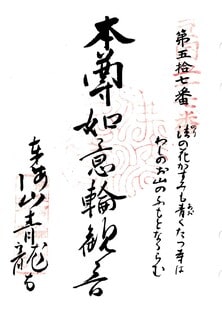

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8へつづく。
【 BGM 】
■ 涙色 - 西野カナ
■ ずるいよ… - CHIHIRO
■ 夢暦 - 川江美奈子
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8へ。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第49番 神護山 太梅寺(たいばいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市横川342
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』『霊場めぐり』には以下のとおりあります。
寛徳三年(1046年)、弘法大師の法孫・桓舜僧都がこの地に行脚の折、霊夢にひとりの童子があらわれて云うには「此地末世仏法興隆の勝境なれば、ここに一宇を建て法灯を永く伝えて光明世間を照さば利益広大なり。」と。
この地はまさに桓舜僧都の求めていた霊地の地勢でもあったため、歓喜して近在の村人から勧募しこの地に草庵を結びました。この童子は東方の明星(の化身)と伝わります。
ある晩の深夜、ひとりの老人があらわれて「此の地は地蔵薩埵有縁の地なり。汝常に持念の地蔵尊を安置して群生を利せよ。」と告げられました。
桓舜僧都がその名を問うたところ「吾是稲荷神なり。」と告げ、姿を消されました。
桓舜僧都には日頃持念する行基菩薩の御作と伝わる地蔵菩薩があり、このお告げにしたがいこの地蔵尊を御本尊と仰ぎ、背後の山に稲荷神を勧請して守護神(鎮守神)とし、明星山満珠寺と号しました。
保元年中(1156-1159年)、京都高雄山神護寺の再興を後白河天皇に強訴したため、伊豆に流された文覚上人が当寺にて大般若経を写経して源氏再興を祈願され、神護寺と改めたといいます。
後に太梅山深居庵と改め臨済宗に改宗、さらに弘治三年(1557年)には曹洞宗に改宗し深居山太梅寺、嘉永五年(1852年)に現在の神護山太梅寺に定まったと伝わります。
『豆州志稿』には「横川村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊地蔵 寛徳二年(1045年)真言ノ僧建ツ 僧桓舜ヲ祖トス 太梅山深居庵ト号ス(諏訪神社文明十七年(1485年)上梁文ニ深居庵住僧徹定トアリ) 康應元年(1389年)●特賜一源和尚住シ臨済宗ト為ル 天文八年(1539年)相州大住郡田原香雲寺ニ隷ス 香雲寺ハ舊本州下田ニ在テ壽福寺ト称ス ●鵜嶋城(下田城?)ヲ増築ノ時相州ニ移ル 弘治三年(1557年)實堂和尚継席ス 是ヲ開山初祖トス 元和(1615-1624年)ノ頃今ノ称号トス 八幡社慶長十三年(1608年)上梁文ニ太梅寺寂用叟ト記ス 地頭吉田泰盛ノ喜捨文小田原北條氏及安國寺(天正十八年(1590年)豊臣氏東征ノ時ノ文書ナリ)ノ禁牓(札)ヲ蔵ム」とあり、かなり複雑な寺歴をもたれるようです。
下田市宇土金の「(公財)上原美術館」のWebによると、太梅寺には、戦国時代頃に書かれた伊豆最古の禅語録『寂用禅師語録』や、下田の地が戦国時代に戦場だったことを物語る『安国寺恵瓊奉制札』などの貴重な資料が遺されているそうです。
また、御本尊の地蔵菩薩像は絶対秘仏ですが、御前立ちの地蔵菩薩坐像も、中世鎌倉を中心とした禅刹で流行した「法衣垂下」の技法を用いた名作として知られているようです。
■ 紹介動画 ↓
報本寺、太梅寺いずれも、当地の明神、守護神があらわれ、そのお告げを受けて開山されています。
これは、弘法大師が高野山に金剛峯寺を開かれるにあたり、高野御子大神(狩場明神)が高野山まで導かれ、地主神の丹生都比売大神(丹生明神)が神領を譲られて、以降も高野山と深い関係をもったという御由緒に似た展開となっています。
報本寺、太梅寺ともに当初は真言宗での開山であり、高野山開山伝承の影響を受けているのかもしれません。
札所本尊は御本尊の地蔵菩薩。
伊豆八十八ヶ所の南伊豆エリアでは唯一の地蔵菩薩の札所となります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 冠木門
第48番報本寺からすこし下田寄りに戻ったところ、横川温泉のそばにあります。
このあたりには、”飲む温泉”で有名な「観音温泉」、お湯のよさで知られる「昭吉の湯」もあり、温泉好きにはなじみのあるエリアです。
県道側の寺号標から境内までかなりの距離があり、名刹であることがわかります。
駐車場はたしか県道沿いにあったかと思います。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門下
参道入口に冠木門。その先に杉木立の下、苔むした石段が伸びています。
石段の先の山門下は報本寺と同様のがっしりとした石垣で、この寺構はこのあたりの寺院の特徴なのかもしれません。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額
山門は切妻屋根瓦葺、がっしりとした朱塗りの四脚門の山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 鐘楼
山内は正面に本堂、左手に堂宇、右手が庫裡のコの字の伽藍配置。
本堂前の2本の巨木が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、格子戸メインのシンプルな構成。
向拝見上げに寺号扁額を掲げています。
左手の堂宇はなぜか写真が残っていないので不明ですが、経堂か収蔵庫のようなものかもしれません。


【写真 上(左)】 本堂と庫裡
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は雰囲気ある庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第50番 古松山 玄通寺(げんつうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町一條456
曹洞宗
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:-
授与所:第63番保春寺
巡路は稲生沢川沿いの第49番の横川・太梅寺から、いきなり一条川沿いの第50番の玄通寺(南伊豆町一條)に飛び、そこから51番、52番と下田方向に戻るかたちとなります。
いまの道路状況からすると唐突な巡路にみえますが、おそらく稲生沢川沿いの横川から峠を越えて一条川筋に至る巡礼路があったかと思われます。
寺伝によると当初は下田寄りの小松野山の頂上にありましたが、数度の火災で記録を失い創建等は不詳となっています。
開山は玄翁心昭(源翁心照空外)。應永三年(1396年)の入寂につき草創はそれ以前とみられています。
『豆州志稿』には、玄翁心昭は那須野が原の殺生石を破砕して妖事を止められたと記されています。
慶長・元和の頃(1596-1624年)、鶴翁和尚により再興。
明治44年(1911年)に庫裏、翌年には本堂が現在地に移されています。
『豆州志稿』には「一條村 曹洞宗 下田大安寺末 本尊観世音 源翁禅師開基 禅師名ハ心照空外ト号ス 後小松帝能照法王禅師ト(勅)賜スト云(應永三年(1396年)正月七日奥州会津示現寺ニ於テ寂ス 鎌倉海蔵寺源翁傳ニ云弘安三年(1280年)正月七日寂スト) 世ニ傳フ昔下野國那須野ニ毒石アリ 人畜触ルヽ者皆斃レ飛鳥空ヲ過ル者忽堕ツ 世俗殺生石ト云 至徳二年(1385年)八月源翁其地ニ至リ 桂杖ヲ以テ破碎ス 妖事立トコロニ止ムト 是蓋齊東野人ノ談ナラム 此地水ナキヲ憂フ 村人四郎左衛門地ヲ穿チテ泉ヲ得タリ 其井今存ス 禅師之ヲ賞シテ古钁ノ氏ヲ賜フ 寺野焼ニ遇フ事数々ニシテ世代ヲ失ス 今鶴翁和尚ヲ祖トス 慶長(1596-1615年)元和(1615-1624年)ノ頃ノ人ナリ 至徳三年(1386年)源翁ニ賜フト云綸旨 幷松永清左衛門(天文廿年(1551年)ノ文書ナリ)今村傳四郎父子等ノ寄進状ヲ蔵ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 六地蔵と参道階段
一条川に沿って走る県道119号下田松崎線に面して参道入口。そのよこに若干の駐車スペースがあります。
周囲は人家も少なく、通る車もまれです。
入口は木柵で閉じられていますが、鍵はかかっていないので木柵を引いて入れます。
右手に六地蔵と立派な寺号標。正面参道階段の先に本堂が見えます。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内
境内には六字御名号「南無阿弥陀佛」の碑がありました。
曹洞宗で御本尊は正観世音菩薩ですが、阿彌陀信仰が入っていたのかもしれません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱のないすっきりとしたつくり。
右手には庫裡がありますが、こちらは無住寺院です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 庫裡
上原美術館のWebによると、当寺には江戸後期~明治時代作の木像「鳥抱き猿像」が伝わり、「その姿には災いや病を『取り(鳥)去る(猿』という意味が込められている可能性があります。」との由。
上原美術館に収蔵され通常非公開ですが、特別展などで展示されることがあるようです。
御朱印は第63番保春寺(南伊豆町加納)にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 正観世音菩薩

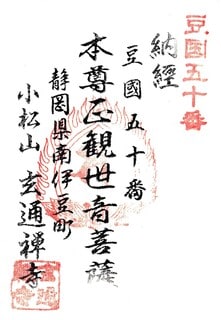
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第51番 青谷山 龍雲寺(りゅううんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町青市143
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:第54番長谷寺
現地掲示の寺伝などによると、鎌倉時代の宝治二年(1284年)に青市地内別当向丘に真言宗の寺院として創建。
永禄十二年(1569年)、下田曹洞院三世了堂和尚により再興し曹洞宗に改宗されています。
その後、火災により焼失したのち、天文五年(1740年)に当山裏山の地に新築移転。
暴風により倒壊したため文化二年(1805年)、現在地に本堂などを新築しています。
『豆州志稿』には「青市村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊阿彌陀 永禄中(1558-1570年)曹洞院三世了堂和尚建ツ 初真言宗ナリ 了堂再興シテ改宗ス 寺後ニ側黒石ト云アリ 天正十八年(1590年)安國寺ノ禁牓ヲ蔵ム」とあります。
「安國寺ノ禁牓(制状)」(天正十八年(1590年)豊臣秀吉東征の役の文書)を蔵しています。
-------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 山内入口
県道119号下田松崎線から南下して国道136号の下賀茂北部に至る枝道から、さらに入ったところにあります。
観光ではほとんど来ない場所かと思います。


【写真 上(左)】 天神社
【写真 下(右)】 山内-1
道はさほど悪くなく、駐車スペースもあります。
参道よこの天神社は菅原道真公を祀り、昭和58年の改修です。


【写真 上(左)】 山内-2
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造銅板葺。がっしりとした大棟にはふたつの御紋、両端に経の巻獅子口。
そこから降る隅棟には一の鬼、二の鬼を配し、あわせて6つの経の巻獅子口を備えて見応えがあります。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
右手の庫裡寄りには海鼠壁とその上に端正な花頭窓を置いて、インパクトのある意匠。
正面格子扉のうえに山号扁額をおいています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は第54番長谷寺(下田市田牛)にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第52番 少林山 曹洞院(そうとういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市大賀茂89
曹洞宗
御本尊:胎蔵大日如来
札所本尊:胎蔵大日如来・十一面観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第25番
授与所:庫裡
ふたたび県道119号に戻り、大賀茂付近で山側に入ったところにあります。
このあたりの札所では大規模な寺院です。
幾度の火災で記録を失い沿革は不明ですが、かつては弘法大師修行の霊蹟で大師山(永禅庵)と号し、末寺十数箇寺を擁した真言宗の大刹と伝わります。(のちに少林山と改号)
下田市Web資料『弘法大師の御墨水』によると、弘法大師が御巡錫の折に秘法を修された曹洞院は、もとは下田市大賀茂林山にありました。
弘法大師が修法中に裏山で錫を立てられると、清列な水が湧き出たのでこの水を硯にとられて経を浄書されたので「弘法大師の御墨水」「金剛浄水」とも呼ばれています。
天文元年(1532年)、中村民部少輔宗賢は相州・海沢、新井の二城に拠って三浦道寸と戦いましたが破れ、大賀茂の曹洞院に逃れてこれを再興して開基となりました。(『南豆風土記』)
宗賢遺物の太刀、鎗、兜、鎧、轡などが曹洞院に所蔵されているそうです。
なお「三浦道寸」は、ふつう相模国守護の三浦義同(1451-1516年)を指すようです。
中村宗賢による再建は大永五年(1525年)で、このときに香雲寺の能庵宗為を請して曹洞宗へ改宗、慶長元年(1596年)、開基宗賢の嫡子・兵部宗尊が堂宇を再建という説もあります。
『豆州志稿』には「吉佐美村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 開林能庵和尚(天文十年(1541年)寂ス)寺ニ前ノ民部侍郎竹了宗賢ノ牌アリ 旁書曰弘治三年(1557年)ト豈此人ノ開基ナルカ 寮舎ノ後ニ民部ノ宅跡アリ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
山門は切妻屋根の四脚門で、以前は茅葺でしたが現在は桟瓦葺となっています。
延宝九年(1681年)建立の棟札が残ります。
江戸時代初期の様式を残すとされ、彫刻は左甚五郎作とも伝わります。
天保十二年(1841年)火災により堂字什宝を失いましたが、山門は類焼を免れ往時の面影をとどめるといいます。
山門に立ち手を打つと、裏山より鶯の鳴き声に似た応えがあるので「鶯門」とも呼ばれます。
山門には山号扁額が掲げられ、その手前には札所標があります。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2
数段の階段をのぼった先に、花緑青色の鮮やかな屋根が葺かれた本堂。
入母屋造銅板葺で向拝柱はありませんが、向拝屋根が付設されています。
向拝正面はアールヌーヴォー風の両開きの扉で、どことなく龍宮門的な趣きがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は庫裡にて拝受しました。
伊豆横道三十三観音霊場の札所で、こちらの御朱印も拝受しています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 胎蔵大日如来・十一面観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※御朱印帳書入の御朱印尊格は胎蔵大日如来となっています。
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第53番 佛谷山 寶徳院(ほうとくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市吉佐美1667
曹洞宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:-
授与所:庫裡
三島の第17番(泉福寺)以来の不動明王の札所です。
こちらも比較的規模の大きな寺院で、草創は貞観年中(859-877年)と伝わります。
天安二年(858年)、中国の長安にある青龍寺で学んだ僧が千体仏を請じて帰国した際、船が難破し吉佐美の浜に打ち上げられました。
浜に漂着した千体仏を安置するために結んだ庵が当寺の始まりと伝わります。
応永二年(1395年)に吉佐美入条の人土屋某が(改めて?)小庵を結び、宝徳元年(1449年)、伊豆山の僧が来住し寺となして真言宗に属しました。
天正五年(1577年)には、曹洞宗の僧吉叟が尾賀茂の延命寺をここに遷して合併し伽藍を整えたと伝わります。
その後一時空院となりましたが、寛文二年(1662年)香雲寺の僧天国が再興したといいます。
寺伝によると御本尊の不動明王は六、七世紀頃、中インドのマカダ国から中国の都・長安の青龍寺に伝えられたもので、入唐して青龍寺で学ばれた智証大師円珍(814-891年)が請来した千体仏のひとつであるといわれています。
『霊場めぐり』によると、治承四年(1180年)、源頼朝公が武衛七人を連れて当院に立ち寄ったとき、砂鉄で茶釜をつくり薬湯を点じて病人に飲ませたところ、たちどころに病が癒えたと伝わります。
こういう奇瑞もあってか頼朝公の御本尊の不動明王への尊崇は篤く、後世も伊豆一円の人々の信仰を集めたと伝わります。
わが国への不動明王の伝来は天平年間(729-766年)~800年代初頭とみられており、こちらの不動明王は最初期の御像とみることができます。
→ ご参考〔日本最古の不動明王について〕
『豆州志稿』には「吉佐美村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊不動 寶徳中土屋某庵ヲ立ツ 天正五年吉叟和尚(俗姓土屋)寺トシ創建ノ時ノ紀号ヲ寺名トス 昔佛像ヲ多く載タル船 此濱ニテ破壊セリ 因テ取立テ此谷ニ夥ク積ミ置ケリ故ニ佛谷ト云 人取去テ今ハ無シ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
吉佐美の集落の山側にあり、開けて明るいイメージの寺院です。
本堂は入母屋造桟瓦葺妻入りで、向拝柱を置いています。
向拝格子扉のうえに山号扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 札所板
堂内は妻入りだけあってふところがふかく、不動尊の堂宇らしい張り詰めた空気感。
背後の山手、通称”ホトケ岩”には三十三観音、十六羅漢、金比羅堂などが安置され山内霊場(佛谷山)となっています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 山内霊場(佛谷山)の参道
御朱印は庫裡にて拝受しました。
第65番最福寺(南伊豆町上賀茂)の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第54番 浦岳山 長谷寺(ちょうこくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市田牛156
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
下田の吉佐美から海岸沿いをタライ岬方面に進んだところに田牛(とうじ)の集落があります。
ここには田牛温泉という独自源泉があり、以前から温泉巡りのなかで狙っていましたが、日帰り施設がみつからず痛恨の未湯湯となっています。
南伊豆の湯巡りルートからは外れているので、今回初の来訪です。
天平年間(729-749年)、行基菩薩の開創と伝わる古刹で、もとは真言宗古義派に属し、西老山昌善寺と称しました。
天文十四年(1545年)に現在の浦岳山長谷寺に号を改め、明暦元年(1655年)、曹洞院九世来室栄撮を請じて曹洞宗に改宗しました。
『豆州志稿』には「田牛村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊阿彌陀 天平中行基建ツト云 古名西光山昌善寺 治承四年八月僧弘禅彌陀像ヲ遠谷島ノ岳浦ニ獲タリ 天文十四年正月初テ寺ニ納ム 其後所獲ノ地名ヲ以テ寺号トシ 亦真言ヲ改テ洞家トナリ曹洞院ニ隷ス 時ノ住僧来室ヲ以テ始祖トス(時ニ寛永二年ナリト云 来室ハ曹洞院九世宗) 天文十三年激浪ノ為寺地●没ス 乃現地ニ移ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 本堂
田牛の集落の山手にあります。
石垣に堀割の参道階段。階段のぼり口には「国指定 重要文化財 木像阿弥陀如来坐像」の標識が建っています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 札所板
山内はこぢんまりとして、すぐ正面が本堂です。
入母屋造銅板葺で、向拝柱と屋根を付設しています。
屋根の勾配が緩く、ちょっと変わったイメージの堂宇です。
簡素な水引虹梁。向拝柱には札所板が掲げられています。
御本尊の阿弥陀如来像は治承四年(1180年)田牛村遠国島の岳浦に漂着し、末寺の昌幸寺に安置されていたもので、天文十四年(1545年)、改宗と同時期に当山に御本尊として遷座されたといいます。
檜材割矧(わりはぎ)造、定朝様式の坐像で国の重要文化財に指定され、文化庁資料には「平安時代の作品」とあります。
『霊場めぐり』には「田牛から青市、湊辺にかけては蒲屋御厨(かばやみくりや)と呼ばれ、古くは伊勢神宮領であったことが『神鳳抄』(鎌倉時代の書)にあることから、この地方が意外に早く開けたことを示している。」とあり、平安時代の仏像が遺されている理由となっているかもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
第51番龍雲寺(南伊豆町青市)の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来
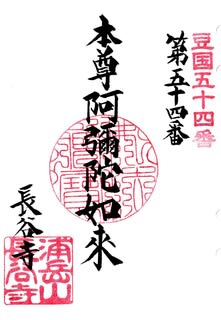
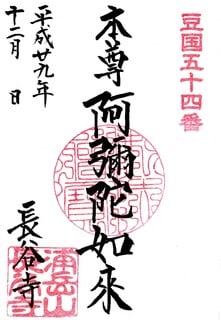
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第55番 飯盛山 修福寺(しゅうふくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町湊662
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第26番
授与所:庫裡
第55番~58番は、下田から石廊崎に向かう県道16号下田石廊松崎線沿いに点在します。
南伊豆の海岸線をたどる風光明媚な巡路です。
第55番修福寺は『こころの旅』によると、「当初大和の国大安寺の支院として開創。(大安寺は現在は真言宗だが以前は(南都六宗の一つ)三論宗で大安寺流の寺として知れわたっていた。)」とのこと。
三論宗の歴史をたどれる寺院は東日本では稀少です。
当初は南伊豆町青市の大寺山にあって石門寺と号し、後に手石から現在地に移転しています。
手石から現在地へは天文十三年(1544年)寂用栄順和尚が移され、師の香雲寺四世実堂宗梅を開山として請じ、その折に寺名と宗旨を改めたといいます。
『豆州志稿』には「湊村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊薬師 本手石村石ノ洞門ニ在テ石門寺ト称ス 天文十三年(1544年)寂用和尚玆ニ移シ寺名ト宗旨トヲ易フ 初真言ノ道場ナリキ香雲寺四世宗梅ヲ請シテ改宗ノ祖ト為ス」とあります。
所蔵の「紙本墨書大般若経」は大治五年(1130年)国司(大江)通国、源盛賴等の奥書があり、国の重要文化財に指定されています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
伊豆屈指の砂浜、弓ヶ浜の山側にある禅刹です。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 六地蔵と参道
うっそうと木立の茂る石段をのぼっていきます。
石段手前には寺号標と札所標。
こちらは伊豆横道三十三観音霊場の札所でもあるので、併記された札所標です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 収蔵庫?
のぼり切ると正面に本堂。左手に収蔵庫?、右手に庫裡。
本堂は寄棟造桟瓦葺で向拝柱のないシンプルな構成ですが、桁行きがありどっしり落ち着いた印象です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
お声がけすると本堂を開けていだけました。
本堂内見上げに「瑠璃殿」の扁額。
堂内は天蓋がかかって華やかで、どことなく密寺の雰囲気もあるのは、元真言密寺のなごりでしょうか。
観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩。こちらは十句観音経と御真言をお唱えし、庫裡にて両霊場の御朱印を拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
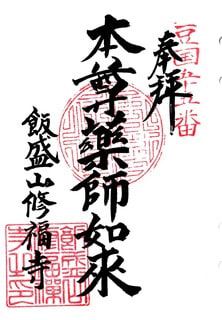

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

■ 第56番 養珠山 正善寺(しょうぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町手石165
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:第55番修福寺
当初は真言宗寺院で詳善寺と号していました。
寛永年間(1624-1644年)に修福寺五世嶺屋秀雪が開山となり曹洞宗に改宗しています。
『豆州志稿』には「手石村 曹洞宗 湊村修福寺末 本尊薬師 法継不詳 寛永(1624-1644年)ノ嶺屋和尚ヨリ修福寺ニ隷ス 寺号初作詳善寺 寺内ノ大日堂近年焼亡ス 或云ニ寺(青龍正善)倶ニ係新建ト当村ノ古寺ハ皆小堂ト為リタリ」とあります。
御本尊の「木造伝大日如来坐像」は運慶作とも伝わり、静岡県の有形文化財に指定されています。
県Web資料には「桧材、寄木造、彩色及び古色、玉眼嵌入 鎌倉時代 鎌倉時代前期の檜材寄木造。慶派の作品。台座に付いていた銘札によれば、元久2(1205)年、大仏師雲慶作の大日如来と伝えられている。」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内
青野川沿いにある禅刹です。
青野川河岸から伸びる参道脇には石仏が並んでいます。
無住でこぢんまりとした山内。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺、向拝柱のないシンプルな堂前で扁額もありません。
御朱印は第55番修福寺にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来

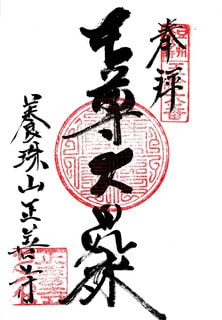
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第57番 東海山 青龍寺(せいりゅうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町手石329
臨済宗建長寺派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
寺伝には嘉禄元年(1225年)の開創とありますが、享保(1716-1736年)初期の火災で記録一切を焼失しているため詳細は不明とされます。
『豆州志稿』によると、佛印禅師(應永四年(1397年)寂)を開山として再興しています。
現在の本堂は享保五年(1720年)築と伝わります。
『豆州志稿』には「手石村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊観世音 佛印禅師ヲ開山トス(應永四年(1397年)寂ス) 嘉禄(1225-1227年)中ノ創立ナリト云 後衰頽ニ属セシヲ 佛印再興ス」とあります。
寺宝として白隠禅師直筆の「宝鏡窟の記」が所蔵されています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標
こちらも青野川の流れにほど近いところにあります。
参道入口に自然石の寺号標。
そこから山門に向かってまっすぐに参道が伸びています。


【写真 上(左)】 山門と本堂
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根本瓦葺の風格ある四脚門で、正面の本堂の屋根といいコントラストをみせています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁と身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股をおいています。
札所本尊はこの霊場では比較的めずらしい如意輪観世音菩薩。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 如意輪観世音菩薩
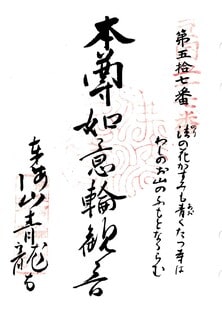

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8へつづく。
【 BGM 】
■ 涙色 - 西野カナ
■ ずるいよ… - CHIHIRO
■ 夢暦 - 川江美奈子
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8へ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
文字数オーバーしたので、Vol.5をつくりました。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
33.金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺
〔足利上総介義兼〕
公式Web
足利市Web資料
栃木県足利市家富町2220
真言宗大日派
御本尊:大日如来
札所:関東八十八箇所第16番、下野三十三観音霊場第28番、両野観音霊場第24番、足利七福神(大黒天)
高い家格と実力をもちながら、御家人として表舞台にあまり出てこなかった人々がいます。
足利義兼もそのひとりではないでしょうか。
しかし、調べていくと鎌倉幕府内の政争で、じつは足利氏は重要な役割を担っていたことがわかります。
鎌倉幕府における足利氏の立ち位置を捉えるとき「御門葉(ごもんよう)」という概念は避けて通れません。
「御門葉」は制度で定めた地位ではないですが、『吾妻鏡』にしばしば出てきます。
それは、たいてい武士の面目にかかわる場面で、甲斐源氏の板垣兼信は桓武平氏の土肥実平との競り合いで「御門葉」を引き合いに出し(元暦元年三月十七日条)、毛呂季光と中条家長の諍いでは、季光は自身が「御門葉」に準じる格にあるとし、家長の非礼を咎めています。(建久六年正月八日条)
職制の規定はなく任命もされていないので、誰が「御門葉」だったのかは確定できませんが、『吾妻鏡』文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者(→ 原典(国会図書館D.C))で、毛呂季光より上位に記されているのは以下の9名です。
1.武藏守(平賀)義信 清和源氏義光流
2.遠江守(安田)義定 清和源氏義光流(甲斐源氏)
3.參河守(源)範頼 清和源氏為義流(河内源氏)
4.信濃守(加々美)遠光 清和源氏義光流(甲斐源氏)
5.相摸守(大内)惟義 清和源氏義光流
6.駿河守(源)廣綱 清和源氏頼光流(多田源氏)
7.上総介(足利)義兼 清和源氏義国流(河内源氏)
8.伊豆守(山名)義範 清和源氏義国流(河内源氏)
9.越後守(安田)義資 清和源氏義光流(甲斐源氏)
(10.豊後守(毛呂)季光 藤原北家小野宮流)
(11.北條四郎(時政) 桓武平氏直方流)
(12.同小四郎(義時) 桓武平氏直方流)
いずれも嫡流系の多田源氏、ないし八幡太郎義家公、新羅三郎義光公の血筋の由緒正しい清和源氏で国司に任ぜられ、このあたりが「御門葉」と認識されていたのでは。
清和源氏が必須条件とみられ、誇り高い藤原北家の毛呂季光でさえ、自らを「『御門葉』に準ずる」としています。
頼朝公の義父・北條時政は11番目、その子義時は12番目ですから、「御門葉」の格は北條(北条)氏より上であったことがわかります。
(詳細は、→こちら(鎌倉殿の御家人))をご覧くださいませ。また、清和源氏の略系図については→こちら(全国山名氏一族会資料)をご覧ください。)
足利義兼の7番目は北関東の武将では筆頭で、その点からも「御門葉」の資格を備えていたことがわかります。
時代が下った宝治二年(1248年)においてなお、義兼の子・義氏は結城朝光との争論で自らを「吾是右大將家御氏族也」とし、「御門葉」は使っていないものの、源氏宗家(右大將家)の御氏族としての矜持をもっていたことがわかります。(『吾妻鏡』宝治二年閏十二月廿八日条)
足利義兼は清和源氏義国流で八幡太郎義家公のひ孫。
足利氏二代当主として下野国足利荘に拠って勢力を蓄えました。
父・義康が早世したため若年で足利氏の家督を継ぎ、治承四年(1180年)の源頼朝公旗揚げに早くから従軍しました。
先年の保元の乱では、父・義康は源義朝公とともに後白河天皇側につきました。
また、義兼の室は藤原季範の息女(ないし養女)とされ、季範の母は尾張氏(熱田神宮大宮司職)の出で、季範の息女は源頼朝の母(由良御前)なので、頼朝公と義兼はともに藤原季範の娘を娶った(頼朝公とは相婿の間柄の)可能性があります。
このような関係のふかさから、早々に頼朝公の麾下に参じたのかもしれません。
また、以仁王の猶母・暲子内親王(八条院)の蔵人であったことを指摘する説もあります。
木曽義仲の遺児・義高の残党討伐に加わり、源平合戦では範頼公に属して従軍。
その戦功により上総国国司(上総介)に推挙され受任。
奥州合戦にも従軍し、建久元年(1190年)の奥州大河兼任の乱では追討使としてこれを平定しています。
「御門葉」としての家格、頼朝公との縁のふかさ、そしてここまでの経歴からすると、「十三人の合議制」(1999年)に名を連ねてもおかしくないですが、これに先んじて建久六年(1195年)3月、東大寺で出家し義称と称しました。
すでに1184年に甲斐源氏の嫡流筋の一条忠頼が謀殺、1190年には多田源氏の源廣綱が逐電し、甲斐源氏の有力者板垣兼信が配流、1193年には源範頼公が失脚、次いで甲斐源氏の安田義資、義定が断罪されるなど源氏一族の失脚粛清が相次ぎ、頼朝公との縁がふかい足利義兼といえども、保身のために出家せざるを得なかったという見方があります。
ことに自身より上位の範頼公の失脚(1193年)、安田義定の断罪(1194年)が大きかったのではないでしょうか。
出家後、足利氏の家督は三男の義氏が継ぎ、幾多の政変をこなして幕府重鎮の地位を保ちました。
これは、義氏が北条時政の息女・時子の実子であったためという考え方もありますが、実際はそんな生やさしい理由ではなかったように思われます。
北条時政には多くの娘がおり、政子は頼朝公、阿波局は阿野全成(頼朝公の異母弟)、時子は足利義兼に嫁いでいます。
さらに、有力御家人の稲毛重成、畠山重忠、平賀朝雅、宇都宮頼綱などにも嫁いでいますが、阿野全成、稲毛重成、畠山重忠、平賀朝雅、宇都宮頼綱はいずれも失脚または出家しているのです。
平賀氏、宇都宮氏は元久二年(1205年)の「牧氏の変」(北条時政と妻・牧の方が企図したとされる政変)を受けての失脚ですが、畠山重忠、稲毛重成の失脚はナゾが多いものとされています。
北条時政の娘を娶り、以降鎌倉御家人の重鎮として関東で命脈を保ったのはなんと足利氏しかいないのです。(宇都宮氏は関西に拠点を移す)
足利氏は一貫して北条氏との連携姿勢を崩さず、第五代頼氏まではすべて北条一門から迎えた嫁の子を嫡子としています。なので足利氏では末子相続が多くなっています。
これは足利氏が立場を維持するうえでの、大きなファクターだったと思われます。
実際、北条系を外れた第六代家時は「自分は(八幡太郎義家公)七代の子孫に生まれ変わって天下を取る」という有名な置文をのこして自害しています。
そして、八幡太郎義家公七代、家時から二代後の足利尊氏は、北条氏を倒して置文どおりに天下を取っています。
(この置文については後世の創作とする説もありますが、北条氏の縁戚を外れた足利氏の声望がにわかに高まったことは事実としてあるかと思います。)
清和源氏の流れをみると、武家の統領、八幡太郎義家公の次男・義親公が嫡流で義朝公・頼朝公ラインにつながりますが、三代実朝公で源家将軍家は断絶。
長男・義宗、三男・義忠は早世したため、義家公の嫡流は四男・義国となり、その長男の(新田)義重と次男の(足利)義康につながります。
新田義重は源家の名流として人望も実力もあったといいますが、頼朝公とのつながりがうすく、旗揚げにも遅参したため弟・足利義康ほどの厚遇は得られなかったとされます。
ただし、足利尊氏も新田義貞も北条討伐の主役ですから、やはり清和源氏義国流に対する「武家の統領」の声望は高かったようです。
また、これは筆者の勝手な想像ですが、北条氏は狭隘な伊豆の出身で、御家人のなかで突出した軍事力をもっていたとは思えません。
一方、足利氏は北関東の広大な所領を背景に、強大な武力を蓄えていたとみられます。
御家人が北条氏とことを構えるとき、北条氏のみならず縁戚の足利氏も同時に敵にまわすという事実は、北条氏の権力の大きな支えになったのでは。
北条氏が足利氏を優遇した(排斥できなかった)背景にはこのようなパワー・バランスもあったかもしれません。
なお、義兼の正室時子について「蛭子伝説」というナゾめいた言い伝えがありますが、その意味するところはよくわかりません。
藤姓足利氏の足利忠綱が登場することから、義兼(源姓足利氏)と藤姓足利氏の確執を暗示したものかもしれません。
出家後の義兼は足利荘の樺崎寺(現在の樺崎八幡宮)に隠棲し、逝去後は同地に葬られました。(樺崎八幡宮本殿が義兼の廟所である赤御堂とされる)
樺崎八幡宮は御朱印を授与されているようですが筆者は未拝受なので、義兼の居館跡に建立・整備された足利氏の氏寺・鑁阿寺(ばんなじ)をご紹介します。
前段が長くなったので簡単にいきます。
鑁阿寺は、建久七年(1197年)足利義兼により建立された真言宗大日派の本山です。
本尊は足利氏(ないし義兼)の守り本尊とされる大日如来です。
4万平米にも及ぶ敷地はもともと足利氏館で、現在も土塁や堀をめぐらして中世の武士館の面影を残し「史跡足利氏宅跡」として国の史跡名勝天然記念物に指定されています。
また、「日本百名城」のひとつでもあります。
義兼(戒名:鑁阿)が僧理真を招聘、発心得度して館内に持仏堂(堀内御堂)を建てたのが開基とされ、義兼の死後、子・義氏が本堂はじめ伽藍を建立して足利氏の氏寺にしています。
以降、足利氏の隆盛を背景に山内整備が進み、将軍家・足利氏の氏寺として手厚く庇護されました。


【写真 上(左)】 反橋と楼門
【写真 下(右)】 寺号標
名刹だけに寺宝も多く、本堂(入母屋造本瓦葺 桁行5間、梁間5間 折衷様、正安元年(1299年)建立)は国宝。
国指定重要文化財として鐘楼、経堂、金銅鑁字御正体など、栃木県指定有形文化財として木造大日如来像、御霊屋、多宝塔、山門(仁王門)などがあります。
山内は広すぎてややとりとめのない印象ですが、山内入口の重厚な反橋と楼門、本堂をはじめ堂宇群もさすがに風格を備えています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は御本尊大日如来、左脇本尊 聖観世音菩薩 歓喜天、右脇本尊 薬師如来 弘法大師とあります。


【写真 上(左)】 中御堂(不動堂)
【写真 下(右)】 経堂
中御堂(不動堂)は義兼の創建、生実御所国朝の再建で成田山からの勧請。
御本尊の不動明王は興教大師のお作とも伝わります。
(一切)経堂は、義兼が妻時子の供養のため一切経会を修する道場として創建、関東管領足利満兼の再建とされます。


【写真 上(左)】 多宝塔
【写真 下(右)】 大酉堂
多宝塔は説明板によると徳川五代将軍家綱公の母・桂昌院、あるいはそれ以前の建立で、「徳川氏は新田氏の後裔と称し、新田氏は足利の庄より新田の庄に分家したるが故に徳川氏は祖先発祥の地なるを以て、此の宝塔を祖先の菩提供養のため再度寄進した。」とあります。
新田氏宗家の本領は上野国碓氷郡八幡荘(現・安中市)とみられていますが、新田庄(現・太田市)には徳川氏ゆかりの寺院や遺跡がたくさんあり、ここ足利にも律儀にゆかりの事物が配置されていることは、徳川氏の新田氏発祥説(清和源氏義国流説)へのこだわりを感じさせます。
大酉堂は足利尊氏公を祀るお堂として室町時代に建立と伝わります。
本堂裏手の北側にある智願寺殿御霊屋(蛭子堂)は、義兼の正室(北条)時子をお祀りするものです。


【写真 上(左)】 校倉(大黒天)
【写真 下(右)】 北門
御朱印は本堂脇の授与所にて拝受しました。
札所として関東八十八箇所第16番、下野三十三観音霊場第28番の御朱印を授与。
両野観音霊場第24番も授与情報がありますが、足利七福神(大黒天)は不授与のようです。

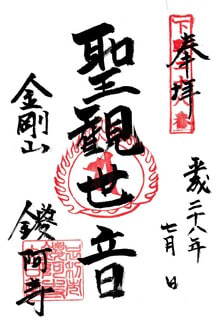
【写真 上(左)】 関東八十八箇所の御朱印
【写真 下(右)】 下野三十三観音霊場の御朱印
34.多福山 一乗院 大寳寺
〔佐竹四郎秀義〕
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
神奈川県鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
佐竹氏は新羅三郎源義光公嫡流の常陸の名族。
源義光公の嫡男・義業の子・昌義 - 隆義 - 秀義とつづきます。
義光公の室(義業の母)は 平(吉田)清幹の息女です。
桓武天皇の孫の平高望(高望王)- 平国香 - 平(大掾)繁盛 - 平(大掾・多気)維幹 - 平(多気)為幹 - 平(多気)重幹 - 平(吉田)清幹 - 娘(義光公の室) - 源義業 - 佐竹昌義の流れで、佐竹氏は清和源氏義光流嫡流であるとともに、桓武平氏の流れもひくという名族です。
いわゆる常陸平氏は、平(吉田)清幹以前からすでに常陸国に勢力基盤を築き、源義業も佐竹氏の名字の地である久慈郡佐竹郷を領したといわれますが、佐竹氏を名乗ったのは佐竹昌義からとされます。(よって、佐竹氏初代は昌義とされる。)
鎌倉幕府草創期の当主は2代隆義、3代秀義で、隆義は平家に仕えて在京が長かったとみられます。
治承四年(1180年)8月の源頼朝公旗揚時、佐竹氏は平家との縁が深かったため参陣せず、同年10月の富士川の戦いでも平家方についています。
平家方の敗戦をうけて佐竹秀義は本拠の常陸国に撤収しますが、頼朝公は上総介広常らの意もあってこれを追撃。
佐竹隆義は在京中で、軍事折衝は隆義の子(兄弟ともいわれる)義政(大掾忠義)と秀義が当たり、攻軍の将・上総介広常との面会に応じた義政はその場で討たれ、金砂城に拠った秀義ら佐竹一族は頼朝軍に攻め落とされて奥州・花園へと落ち延びました。(金砂城の戦い)
寿永二年(1183年)、父・隆義の死により秀義は佐竹氏の家督を相続、佐竹氏3代当主となりました。
その後のいきさつがはっきりしないのですが、秀義は文治五年(1189年)の奥州討伐で頼朝軍のなかにその名が見えるので、それ以前に頼朝公に帰順したとみられます。
『吾妻鏡』の文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者にはその名が見えず、帰順はそれ以降かもしれません。
奥州討伐では武功を挙げ、御家人の地位を固めています。
奥州討伐の往路、秀義は頼朝公から佐竹氏の家紋「五本骨扇に月丸」を賜っているので、すでに有力御家人として認知されていることがわかります。
文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩にはその名が見えず、常陸からの途中参陣かも知れません。
(上記の家紋賜いは宇都宮出立時という資料(→『新編鎌倉志』)があります。)
建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩(→ 原典(国会図書館D.C))には先陣随兵廿八番に「佐竹別當」としてその名が見えます。
先陣随兵廿八番は格高の番で、他に「武田太郎」(武田信義?)、「遠江四郎」(安田義定?)の有力御家人2名がいるので、やはり相応の地位を得ていたのでは。
承久の乱後の嘉禄元年(1225年)末、有力御家人としての地位を保って鎌倉名越の館にて死去。
この「名越の館」は現・大寶寺周辺とみられています。
後を継いだ4代義重は承久の乱でも活躍し、寛元三年(1245年)常陸介に任ぜられています。
佐竹氏は本来国司にふさわしい家柄ですから、その格式を義重の代でとりもどしたということになります。
(秀義の代に、すでに常陸介に任ぜられたという説もあり。)
富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく、このように有力御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。
佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とし、桓武平氏の流れもひく常陸の名族。
秋霜烈日な頼朝公も、名流・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。
鎌倉・大町にある日蓮宗寺院、大寶寺は、新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。
現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が、兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ、以降佐竹氏の屋敷になったといいます。
應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。
源義光公は、戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。
山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)は、もともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀され、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。
ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。
『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。
佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。
『新編鎌倉志』
「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」
『鎌倉攬勝考』
「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」
ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。
「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」
「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。
應永十四年(1407年)、第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。
足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。
与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。
應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では、義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。
これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝えられます。
上記から、1400年代中盤までは、佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。
應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。
「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。
佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。
新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。
義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。
その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。


【写真 上(左)】 道標
【写真 下(右)】 山内入口
大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどなく、閑静な住宅地となっています。
大寳寺はこの小路から、さらに左手山側に入ったところにあります。
位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。


【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。
参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 お題目塔
本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。
正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。
こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。
本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。


【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神
【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額
山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。
拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。
新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが、墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)
御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。
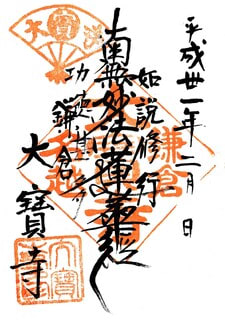
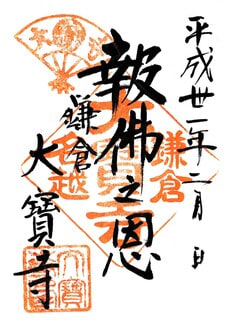
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
35.萬徳山(梅田山) 梅林寺 明王院
〔志田三郎先生義広〕
公式Web
東京都足立区梅田4-15-30
真言宗豊山派
御本尊:不動明王(赤不動尊)
札所:荒綾八十八ヶ所霊場第35番、荒川辺八十八ヶ所霊場第43番
このあたりで、少しく時代を遡ります。
源頼朝公の祖父・源為義公の三男・義広ははやくから都で東宮帯刀先生職にあり、仁平三年(1151年)頃関東に下向し常陸国信太(志田)荘(現・茨城県稲敷市)を開墾して本拠地(志田庄を立荘)としたため、通称を志田(志太、信太)三郎先生と呼ばれました。
『吾妻鏡』(文治四年六月大四日条)には、八條院領として常陸國志太庄が載っています。
八條院領は美福門院(1117-1160年)およびその息女・八条院暲子内親王の所領なので、志田義広は所領を通じて美福門院、八条院、あるいは八条院の猶子・以仁王と関係があったとみられます。
その当時、源為義公は京にあって摂関家との関係を強めたのに対し、長男・義朝公は東国へ下り相州を中心とした南関東で勢力を伸ばしました。
義朝公は妻の実家の熱田大宮司家を通じて鳥羽法皇に接近し、摂関家方の為義公とは政治的にも対立関係にありました。
仁平三年(1153年)義朝公は下野守に任じられ、父・為義公を凌いで受領となりました。為義公は東国における義朝公の勢力を削ぐために次男の義賢を上野国に下向させ、義賢は武蔵国で留守所総検校職にあった秩父重隆の娘を娶り、武蔵国比企郡の大蔵に館を構えました。
久寿二年(1155年)8月、義朝公の長男・義平(悪源太)が大蔵館を襲撃し、義賢と秩父重隆を攻め殺しました。(大蔵合戦)
その背景には諸説ありますが、鎌倉を本拠とする義平が北上をもくろみ、武蔵國の叔父・義賢と対立したためとみられています。
義賢は義広の同母兄とされますが、大蔵合戦時における義広の動向は不明です。
保元元年(1156年)の保元の乱は、後白河天皇方として義朝公、義朝公の父・為義公以下、四男・頼賢、五男・頼仲、六男・為宗、七男・為成、八男・為朝、九男・為仲が崇徳上皇方につき、上皇方の敗戦により伊豆大島に流された八男・為朝をのぞいて斬首されました。
保元の乱(保元元年(1156年))、平治の乱(平治元年(1159年))における志田義広の動向は諸説ありよくわかりませんが、乱後も勢力を保っていることから、無傷で乗り切ったとみられています。
次男・義賢(木曾義仲の父)は、大蔵合戦で討ち死にしているので、治承四年(1180年)5月の以仁王挙兵時点では、三男・義憲(義広)と十男・行家を残すのみでした。(ほかにも庶子がいたという説あり。)
十男・行家は東国に地盤をもたず、以仁王の平家追討の令旨を各地の源氏に伝達していたので、この時点で東国で勢力を張っていたのは義広のみでした。
以仁王挙兵の際、末弟の源行家が甥の頼朝公に以仁王の令旨を伝達したのち、義広の元に向かったとされ(『平家物語』)、これは以仁王令旨が八條院領に触れられたという記録と合致します。
同年11月、頼朝公と常陸佐竹氏が戦った「金砂城の戦い」での義広動向はよくわかりませんが、戦の直後に常陸国府で行家ととともに頼朝公に対面しているので(『吾妻鏡』)、頼朝公と直接の敵対関係はなかったとみられます。
その後も頼朝公の麾下に入ったということもなく、常陸で独自の勢力を維持しました。
東国に地盤をもつ唯一の叔父、志田義広に対し、の時点では頼朝公も強い態度を打ち出せなかったのかもしれません。
寿永二年(1183年)2月、義広は鹿島社所領の押領を頼朝公に諫められたことに反発、下野に勢力を張る藤姓足利氏の足利俊綱・忠綱父子と連合し2万の兵を集めて頼朝公に反旗を翻し下野に兵を進めました。
下野国の有力者小山朝政は、源範頼公、結城朝光、長沼宗政、佐野基綱らと連合して野木宮(現・野木町)で義広勢に攻めかかり、激戦ののち義広勢は敗れて常陸の本拠地を失いました。(野木宮合戦)
頼朝公は野木宮合戦に直接関与していないという説もありますが、頼朝公からすると叔父に当たり、常陸に勢力を維持していた義広に強い警戒感をもっていたことは確かかと。
その後、義広は同母兄・義賢の子・木曾義仲に合流し、義仲は義広を叔父として遇して義仲とともに上洛を果たし、義広は信濃守に任官されています。
元暦元年(1184年)の宇治川の戦いでは西上した義経軍と対峙、粟津の戦いで義仲が討ち死にした後も反頼朝の立場を崩さず、同年5月伊勢国羽取山(現・三重県鈴鹿市)で波多野盛通、大井実春、山内首藤経俊らと合戦の末、斬首されました(『吾妻鏡』)。
志田義広の子として、志田義延、志田義国、志田頼重の名が伝わり、Wikipediaによると「志駄氏、梅田氏、楢崎氏、比志島氏、小山田氏などが義広の後裔を称している」とのことです。
東京都足立区の明王院は義広の開基と伝わり、同寺の公式Webには以下のとおりあります。
-------------------
1178 治承2 志田三郎先生源義廣、榎戸(現在地より南方、荒川寄り)に祈願所を草創する
義廣三世の左馬之助義純、当所に蟄居する
以後、その子孫が代々居住する
義廣五世常陸介久廣、天満宮を勧請する
久廣、この頃より性を梅田氏と名乗る
また、寺の山号を萬徳山、寺号を梅林寺と称するようになる
永正年間 義廣二十一世梅田久義、丹波に移住
-------------------
治承二年(1178年)の時点で義広が榎戸の地に祈願所を草創していたということは、この地に所領をもっていたのかもしれません。
「義廣三世の左馬之助義純」は、義広の子・志田義延、志田義国、志田頼重いずれかの子ということになります。
その後、梅田と姓を改め、少なくとも室町後期の永正年間(1504-1521年)までは当寺と関係があったとみられます。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内
東武伊勢崎線「梅島」駅から徒歩約20分と交通はやや不便ですが、「赤不動尊」と通称され、このあたりでは有数の名刹として親しまれています。
下町らしく狭い路地に家が建て込む街区ですが、そのなかに広々とした山内を構え、基壇のうえにそびえる入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂は、さすがに名刹の風格があります。


【写真 上(左)】 回向堂
【写真 下(右)】 本堂
参道正面は回向堂で不動三尊が御本尊。
参道右手の朱塗りの堂宇が不動堂(本堂)で、御本尊・感得不動明王、如意輪観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 荒綾霊場の札所板
御本尊の感得不動明王(赤不動尊)は、弘法大師が御歳42歳のときに厄除祈願のため造立された御像と伝わります。
当初高野山に安置、根来寺、清閑寺と遷られ、寛保二年(1742年)当寺に奉戴されました。(当寺縁起書)
如意輪観世音菩薩像は南北朝時代の応安二年(1369年)、院派の院秀作とされ、都の有形文化財に指定されています。
当山の鎮守として天満宮、咳止めに霊験あらたかな八彦尊もお祀りされています。
不動尊とのゆかりがふかい寺院で、明和元年(1764年)8月には成田山の出張開帳がおこなわれ、明和二年(1765年)には本所回向院で御本尊・感得不動明王の出開帳がなされているので、篤く信仰されたお不動さまであることがわかります。
徳川家光公・八代将軍吉宗公・十二代将軍家慶公など歴代将軍の鷹狩りの折の御膳所となり、『江戸名所図絵』にも掲載されている江戸の名所のひとつです。
御朱印は庫裡にて荒綾霊場のものが授与されています。

■ 明王院の御朱印
36.白山 東光寺
〔畠山次郎重忠〕
公式Web
神奈川県横浜市金沢区釜利谷2-40-8
臨済宗円覚寺派
御本尊:薬師如来
札所:武州金沢三十四観音霊場第16番、かなざわの霊場めぐり第12番
畠山氏は足利幕府の管領家だったこともあり清和源氏のイメージがありますが、もともとの発祥は桓武平氏良文流で秩父氏の一族です。
秩父氏初代の平将恒は、平良文公の子・武蔵介忠頼公と平将門公の娘・春姫との間に生まれ、武蔵国秩父郡に拠って秩父氏を称しました。
将恒の子孫は武蔵国の各所に土着して勢力を広げ、将恒の曾孫・秩父重綱は「武蔵国留守所総検校職」に就きました。
「武蔵国留守所総検校職」は、国司のいなかった武蔵国の国衙で在庁官人のトップとして、武蔵国内の武士を統率・動員する権限をともなう役職で、大きな権限をもっていました。
重綱の孫・重能は武蔵国大里郡畠山荘(現在の埼玉県深谷市)に拠り勢力を張って、畠山氏初代となりました。
桓武平氏良文流で坂東で発展した8つの氏族はとくに「坂東八平氏」と呼ばれ、上総氏・千葉氏・相馬氏・三浦氏・土肥氏・梶原氏・秩父氏・畠山氏などが名を連ねます。(諸説あり)
うち秩父氏・畠山氏が秩父姓で、「坂東八平氏」以外にも小山田氏、稲毛氏、河越氏、渋谷氏、師岡氏、豊島氏、江戸氏などの有力氏族が秩父姓(秩父党)です。
平安時代後期の当主は初代の畠山重能。
久寿二年(1155年)、重能は関東に下向していた源義朝・源義平父子と結んで比企郡の大蔵館を襲い、叔父の重隆とその婿・源義賢を討ちました。(大蔵合戦)
父・秩父重弘が長男でありながら、秩父氏嫡流は次男の重隆が継いだことへの不満が動機のひとつとみられています。
重能はこの勝戦により、秩父氏嫡流が嗣ぐ「武蔵国留守所総検校職」となる立場を得た筈ですが、なぜかこの職は重隆の孫・河越重頼が継いでいます。
保元元年(1156年)の保元の乱には参戦せず、平治元年(1159年)の平治の乱では重能・有重兄弟は平家の郎等として記されています。(『平家物語』『愚管抄』)
源頼朝公の旗揚げ時、重能は大番役として在京し平家方として転戦しています。
武蔵国の領地を守っていたのは、三浦義明(ないし江戸重継)の息女を母とする17歳の嫡男・重忠。
重忠も平家方として頼朝公と対立、治承四年(1180年)8月には秩父党(河越氏、江戸氏)、村山党などを糾合し、源氏方の三浦義明を衣笠城に攻めて討ち取っています。(衣笠城合戦)
この戦の背景は、畠山:平家方、三浦:源氏方という単純な理由だけではないとみられ、諸説展開されていますがここでは触れません。
このあたりから畠山氏の主役は重忠に移り、重忠は弱冠17歳の時点から源平合戦に突入していくことになります。
治承四年(1180年)10月、重忠は河越重頼、江戸重長とともに隅田川の長井渡しで頼朝公に帰順しました。
反頼朝公の色が強かったのは江戸重長で、重忠は先祖の平武綱が八幡太郎義家公より賜った白旗を持って帰参し、頼朝を喜ばせたという逸話(『源平盛衰記』)もあるので、遅参したとはいえ頼朝公の重忠への心証は悪くはなかったとみられます。
源平合戦では数々の戦功を打ち立て、武名をあげました。
宇治川の渡河で立ち往生した同僚の大串重親を対岸へ投げ上げ、三条河原では木曾義仲の愛妾・巴御前と一騎討ちを演じ、一ノ谷の鵯越では馬をいたわりこれを背負って逆落としを掛けるなど、無双の強者ぶりが『平家物語』などに描かれています。
秩父氏嫡流を嗣いでいた河越重頼は義経の舅だったこともあって誅殺され、「武蔵国留守所総検校職」は重忠が継承、名実ともに武蔵国を代表する御家人となりました。
その後も梶原景時の讒言により重忠追討が審議されるなどの危機がありましたが、これをこなして文治五年(1189年)の奥州合戦では先陣を務めて戦功をあげています。
建久元年(1190年)、頼朝公上洛の際は先陣を務め、右近衛大将拝賀の随兵7人の内に選ばれて参院の供奉をしています。
北条時政の息女を娶っていた重忠の立場は重く、幕閣でも重きをなしたとみられます。
建仁三年(1203年)の比企能員の変では北条側につき、比企氏一族を滅ぼしています。
上洛して京都守護職となった平賀朝雅は、北条時政の娘婿で武蔵守でした。
その名分もあってか、武蔵国の大勢力・比企氏亡き後、時政はその後釜として武蔵国掌握を目論んだとみられます。
本領の中伊豆とは比較にならない広大な武蔵国は、時政にとっては垂涎の地だったのでは。
武蔵国には強豪・畠山氏が健在でしたが、当主の重忠は娘婿なので甘くみていたふしもあります。
しかし、畠山重忠はけっして甘い人間ではなく、時政と重忠は次第に対立を深めていきました。
建仁三年(1204年)11月、源実朝公の御台所を京から迎えるため上洛していた重忠の子・畠山重保と平賀朝雅の間で口論となり、畠山氏と平賀氏の確執は強まりました。
両者の義父である北条時政は一貫して平賀朝雅を支持したとみられ、時政は重忠父子を勘当したという説もみられます。
時政が寵愛した後妻・牧の方の娘が平賀朝雅の壻であったことも大きいとみられます。
また、畠山重保と平賀朝雅の口論の前後に、牧の方の息子の北条政範が京で命を落としていることも重要なファクターという見方もあります。(諸説あり)
牧の方は池禅尼の姪という説があり、池禅尼は中納言・藤原隆家の血筋で平清盛の継母、崇徳天皇の皇子・重仁親王の乳母でもあったので、先妻の伊東祐親の娘よりも血筋的には上で、自分の子が北条氏を継ぐべきという考えをもっていたのかもしれません。
じっさい、北条政範は16歳にしてすでに従五位下・左馬権助に任ぜられており、政範が北条氏の嫡子であったとみなす説さえあります。
元久二年(1205年)6月、平賀朝雅は重保から悪口を受けたと牧の方に訴え、牧の方はこれを重忠・重保父子の叛意であるとして時政に対応を迫りました。
時政は子の義時と時房に畠山討伐を相談すると、2人は反対したものの時政の意思は堅く、ついに義時も討伐に同意したといいます。
6月22日、時政の意を受けた三浦義村が由比ヶ浜で畠山重保を討ち、鎌倉へ向かった重忠を迎撃すべく鎌倉から大軍が発向しました。
重忠は鎌倉の不穏を感じてすでに6月19日に菅谷館(現・埼玉県嵐山町)を発っており、22日に二俣川で鎌倉軍と遭遇して激戦を展開したものの衆寡敵せず、ついにこの地で討ち死にしました。
享年42と伝わります。(畠山重忠の乱)
翌23日、義時は重忠謀反は虚報で重忠は無実であった旨を時政に伝えると、その日の夕方、重忠討伐軍に加わった秩父党の稲毛重成父子、榛谷重朝父子が三浦義村らによって殺害されました。
畠山討伐にあたり三浦義村の動きが目立ちますが、これは衣笠城合戦で畠山氏をはじめとする秩父党に衣笠城を攻められ、祖父・義明を討ち取られた恨みもあったものとみられています。
義時は戦後送られてきた重忠の首級に接し「年来合眼の昵を忘れず、悲涙禁じがたし」と嘆いたといいます。
重忠父子は無実の罪で誅されたとされ、討伐を強引に押し進めた時政に対する御家人たちの不満が高まって、ついに時政と牧の方は義時・政子によって伊豆に追放され、平賀朝雅は誅殺されました。(牧氏事件)
↑ ざっと調べた概略だけでもこれだけのボリュームになるので、深く掘り下げれば1冊の本が仕上がるほどのネタがあるかと思います。
『吾妻鏡』も政子と義時が父時政を追放したという事実は描きにくいらしく、この一連の政変の背景については明示していません。
それだけ複雑な事情と、多くのナゾを秘めた政変であったということかと。
乱後の情勢をみると武蔵の強豪・秩父党はほとんどその勢力を失い、相対的に北条執権家(義時・政子)の力が強まりました。
このあたりにも、この政変を評価する深い意味合いがあるのかもしれません。
畠山重忠の乱が時政の失脚に直結したのは、時政の独裁への反発もさることながら、重忠の人望も大きかったのではないでしょうか。
奥州討伐ののちに藤原泰衡の郎党・由利八郎を取り調べた際、梶原景時は傲慢不遜な態度で接したため八郎は頑として取り調べに応じませんでした。
かたや重忠は八郎に礼を尽くして接し、取り調べに応じた八郎は「先ほどの男(景時)とは雲泥の違いである」と述べたという逸話が伝わります。
『源平盛衰記』『義経記』では分別をわきまえた模範的な武士として描かれ、『曽我物語』では曾我兄弟を讒言から救う恩人として描かれています。
東光寺の公式Webではその人柄をつぎのように記しています。
「義を重んじて正路を覆み 文武両道全うし忠良にして私心無く(中略)公明にして寛大 人は其の誠純を敬す」
判官びいきのきらいはあるにしても、人々からその高潔な人格を認められていたことはまちがいないかと思います。
重忠亡きあと、畠山氏の旧領と名跡は足利義兼の子・義純が重忠の未亡人(時政の息女)と婚姻することで継承し、以降畠山氏は源姓の足利家一門として存続することとなります。
(義純の室は重忠と時政の娘の息女という説もあり。)
室町幕府では三管領の一画を占め、高い家格を保つとともに奥州二本松、紀伊、和泉、大和、河内など各地の守護大名としても発展しました。
戦国期に緒戦で敗れ大名の地位は失うものの、子孫は江戸幕府の高家として幕末まで家格を保ちました。
畠山重忠ゆかりの寺社はいくつかありますが、御朱印を授与されている例は少なくここでは横浜市金沢区の東光寺をご紹介します。
長くなったので簡単にいきます。
東光寺は、建仁年間(1201-1204年)畠山重忠が開基となり、重忠の念持佛・薬師如来を御本尊として建長寺六世勅謚大興禅師が鎌倉二階堂薬師ヶ谷(現・鎌倉宮周辺)に開山、医王山東光寺を号したと伝わります。(弘安五年(1282年)開山説もあり。)
応仁年間(1467-1469年)に現在地(釜利谷)へ移転。
釜利谷付近には重忠・重保父子の供養塔があり、重忠の自領か一族の誰かが住していたとされ、そのゆかりで当地に移転したとみられています。
当寺所蔵の鞍・鐙・轡・鞖は重忠ゆかりのものと伝えられ、横浜市の有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 山門-1
【写真 下(右)】 山門-2
金沢区には落ち着きのある禅刹が多いですが、こちらもそのひとつ。
戸建て住宅が整然と並ぶニュータウンに緑ゆたかな山内を残しています。
山門は風格のある切妻屋根本瓦葺の四脚門で、山号扁額が掲げられています。
軒丸瓦に描かれた五三の桐紋は、畠山氏の家紋のひとつとされているものです。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2
手入れのきいた参道まわりのおくに入母屋造銅板葺の本堂で、向拝柱のないすっきりとした向拝です。


【写真 上(左)】 山内-3
【写真 下(右)】 本堂
向拝正面格子扉のうえには「東光禅寺」の寺号扁額。
上部の斗栱や垂木、下場の格子窓とのバランスが絶妙です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額と軒
御本尊の薬師如来の説明書には「厳しい顔つき、ひきしまった肉どり、うねりの強い写実的な衣文などに鎌倉時代初期の運慶派の特色が明らかである。」とありました。
名刹にふさわしく、「酸漿蒔絵蔵」「絹本著色釈迦十六善神図」などの文化財も所蔵しています。
山内には畠山重忠の供養塔もあります。

■ 東光寺の御朱印
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6へつづく。
【 BGM 】
■ Paradise Island - Thom Rotella (1989)
■ If You'd Only Believe - Randy Crawford (1992)
■ Sailing - Rodney Franklin (1982)
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
33.金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺
〔足利上総介義兼〕
公式Web
足利市Web資料
栃木県足利市家富町2220
真言宗大日派
御本尊:大日如来
札所:関東八十八箇所第16番、下野三十三観音霊場第28番、両野観音霊場第24番、足利七福神(大黒天)
高い家格と実力をもちながら、御家人として表舞台にあまり出てこなかった人々がいます。
足利義兼もそのひとりではないでしょうか。
しかし、調べていくと鎌倉幕府内の政争で、じつは足利氏は重要な役割を担っていたことがわかります。
鎌倉幕府における足利氏の立ち位置を捉えるとき「御門葉(ごもんよう)」という概念は避けて通れません。
「御門葉」は制度で定めた地位ではないですが、『吾妻鏡』にしばしば出てきます。
それは、たいてい武士の面目にかかわる場面で、甲斐源氏の板垣兼信は桓武平氏の土肥実平との競り合いで「御門葉」を引き合いに出し(元暦元年三月十七日条)、毛呂季光と中条家長の諍いでは、季光は自身が「御門葉」に準じる格にあるとし、家長の非礼を咎めています。(建久六年正月八日条)
職制の規定はなく任命もされていないので、誰が「御門葉」だったのかは確定できませんが、『吾妻鏡』文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者(→ 原典(国会図書館D.C))で、毛呂季光より上位に記されているのは以下の9名です。
1.武藏守(平賀)義信 清和源氏義光流
2.遠江守(安田)義定 清和源氏義光流(甲斐源氏)
3.參河守(源)範頼 清和源氏為義流(河内源氏)
4.信濃守(加々美)遠光 清和源氏義光流(甲斐源氏)
5.相摸守(大内)惟義 清和源氏義光流
6.駿河守(源)廣綱 清和源氏頼光流(多田源氏)
7.上総介(足利)義兼 清和源氏義国流(河内源氏)
8.伊豆守(山名)義範 清和源氏義国流(河内源氏)
9.越後守(安田)義資 清和源氏義光流(甲斐源氏)
(10.豊後守(毛呂)季光 藤原北家小野宮流)
(11.北條四郎(時政) 桓武平氏直方流)
(12.同小四郎(義時) 桓武平氏直方流)
いずれも嫡流系の多田源氏、ないし八幡太郎義家公、新羅三郎義光公の血筋の由緒正しい清和源氏で国司に任ぜられ、このあたりが「御門葉」と認識されていたのでは。
清和源氏が必須条件とみられ、誇り高い藤原北家の毛呂季光でさえ、自らを「『御門葉』に準ずる」としています。
頼朝公の義父・北條時政は11番目、その子義時は12番目ですから、「御門葉」の格は北條(北条)氏より上であったことがわかります。
(詳細は、→こちら(鎌倉殿の御家人))をご覧くださいませ。また、清和源氏の略系図については→こちら(全国山名氏一族会資料)をご覧ください。)
足利義兼の7番目は北関東の武将では筆頭で、その点からも「御門葉」の資格を備えていたことがわかります。
時代が下った宝治二年(1248年)においてなお、義兼の子・義氏は結城朝光との争論で自らを「吾是右大將家御氏族也」とし、「御門葉」は使っていないものの、源氏宗家(右大將家)の御氏族としての矜持をもっていたことがわかります。(『吾妻鏡』宝治二年閏十二月廿八日条)
足利義兼は清和源氏義国流で八幡太郎義家公のひ孫。
足利氏二代当主として下野国足利荘に拠って勢力を蓄えました。
父・義康が早世したため若年で足利氏の家督を継ぎ、治承四年(1180年)の源頼朝公旗揚げに早くから従軍しました。
先年の保元の乱では、父・義康は源義朝公とともに後白河天皇側につきました。
また、義兼の室は藤原季範の息女(ないし養女)とされ、季範の母は尾張氏(熱田神宮大宮司職)の出で、季範の息女は源頼朝の母(由良御前)なので、頼朝公と義兼はともに藤原季範の娘を娶った(頼朝公とは相婿の間柄の)可能性があります。
このような関係のふかさから、早々に頼朝公の麾下に参じたのかもしれません。
また、以仁王の猶母・暲子内親王(八条院)の蔵人であったことを指摘する説もあります。
木曽義仲の遺児・義高の残党討伐に加わり、源平合戦では範頼公に属して従軍。
その戦功により上総国国司(上総介)に推挙され受任。
奥州合戦にも従軍し、建久元年(1190年)の奥州大河兼任の乱では追討使としてこれを平定しています。
「御門葉」としての家格、頼朝公との縁のふかさ、そしてここまでの経歴からすると、「十三人の合議制」(1999年)に名を連ねてもおかしくないですが、これに先んじて建久六年(1195年)3月、東大寺で出家し義称と称しました。
すでに1184年に甲斐源氏の嫡流筋の一条忠頼が謀殺、1190年には多田源氏の源廣綱が逐電し、甲斐源氏の有力者板垣兼信が配流、1193年には源範頼公が失脚、次いで甲斐源氏の安田義資、義定が断罪されるなど源氏一族の失脚粛清が相次ぎ、頼朝公との縁がふかい足利義兼といえども、保身のために出家せざるを得なかったという見方があります。
ことに自身より上位の範頼公の失脚(1193年)、安田義定の断罪(1194年)が大きかったのではないでしょうか。
出家後、足利氏の家督は三男の義氏が継ぎ、幾多の政変をこなして幕府重鎮の地位を保ちました。
これは、義氏が北条時政の息女・時子の実子であったためという考え方もありますが、実際はそんな生やさしい理由ではなかったように思われます。
北条時政には多くの娘がおり、政子は頼朝公、阿波局は阿野全成(頼朝公の異母弟)、時子は足利義兼に嫁いでいます。
さらに、有力御家人の稲毛重成、畠山重忠、平賀朝雅、宇都宮頼綱などにも嫁いでいますが、阿野全成、稲毛重成、畠山重忠、平賀朝雅、宇都宮頼綱はいずれも失脚または出家しているのです。
平賀氏、宇都宮氏は元久二年(1205年)の「牧氏の変」(北条時政と妻・牧の方が企図したとされる政変)を受けての失脚ですが、畠山重忠、稲毛重成の失脚はナゾが多いものとされています。
北条時政の娘を娶り、以降鎌倉御家人の重鎮として関東で命脈を保ったのはなんと足利氏しかいないのです。(宇都宮氏は関西に拠点を移す)
足利氏は一貫して北条氏との連携姿勢を崩さず、第五代頼氏まではすべて北条一門から迎えた嫁の子を嫡子としています。なので足利氏では末子相続が多くなっています。
これは足利氏が立場を維持するうえでの、大きなファクターだったと思われます。
実際、北条系を外れた第六代家時は「自分は(八幡太郎義家公)七代の子孫に生まれ変わって天下を取る」という有名な置文をのこして自害しています。
そして、八幡太郎義家公七代、家時から二代後の足利尊氏は、北条氏を倒して置文どおりに天下を取っています。
(この置文については後世の創作とする説もありますが、北条氏の縁戚を外れた足利氏の声望がにわかに高まったことは事実としてあるかと思います。)
清和源氏の流れをみると、武家の統領、八幡太郎義家公の次男・義親公が嫡流で義朝公・頼朝公ラインにつながりますが、三代実朝公で源家将軍家は断絶。
長男・義宗、三男・義忠は早世したため、義家公の嫡流は四男・義国となり、その長男の(新田)義重と次男の(足利)義康につながります。
新田義重は源家の名流として人望も実力もあったといいますが、頼朝公とのつながりがうすく、旗揚げにも遅参したため弟・足利義康ほどの厚遇は得られなかったとされます。
ただし、足利尊氏も新田義貞も北条討伐の主役ですから、やはり清和源氏義国流に対する「武家の統領」の声望は高かったようです。
また、これは筆者の勝手な想像ですが、北条氏は狭隘な伊豆の出身で、御家人のなかで突出した軍事力をもっていたとは思えません。
一方、足利氏は北関東の広大な所領を背景に、強大な武力を蓄えていたとみられます。
御家人が北条氏とことを構えるとき、北条氏のみならず縁戚の足利氏も同時に敵にまわすという事実は、北条氏の権力の大きな支えになったのでは。
北条氏が足利氏を優遇した(排斥できなかった)背景にはこのようなパワー・バランスもあったかもしれません。
なお、義兼の正室時子について「蛭子伝説」というナゾめいた言い伝えがありますが、その意味するところはよくわかりません。
藤姓足利氏の足利忠綱が登場することから、義兼(源姓足利氏)と藤姓足利氏の確執を暗示したものかもしれません。
出家後の義兼は足利荘の樺崎寺(現在の樺崎八幡宮)に隠棲し、逝去後は同地に葬られました。(樺崎八幡宮本殿が義兼の廟所である赤御堂とされる)
樺崎八幡宮は御朱印を授与されているようですが筆者は未拝受なので、義兼の居館跡に建立・整備された足利氏の氏寺・鑁阿寺(ばんなじ)をご紹介します。
前段が長くなったので簡単にいきます。
鑁阿寺は、建久七年(1197年)足利義兼により建立された真言宗大日派の本山です。
本尊は足利氏(ないし義兼)の守り本尊とされる大日如来です。
4万平米にも及ぶ敷地はもともと足利氏館で、現在も土塁や堀をめぐらして中世の武士館の面影を残し「史跡足利氏宅跡」として国の史跡名勝天然記念物に指定されています。
また、「日本百名城」のひとつでもあります。
義兼(戒名:鑁阿)が僧理真を招聘、発心得度して館内に持仏堂(堀内御堂)を建てたのが開基とされ、義兼の死後、子・義氏が本堂はじめ伽藍を建立して足利氏の氏寺にしています。
以降、足利氏の隆盛を背景に山内整備が進み、将軍家・足利氏の氏寺として手厚く庇護されました。


【写真 上(左)】 反橋と楼門
【写真 下(右)】 寺号標
名刹だけに寺宝も多く、本堂(入母屋造本瓦葺 桁行5間、梁間5間 折衷様、正安元年(1299年)建立)は国宝。
国指定重要文化財として鐘楼、経堂、金銅鑁字御正体など、栃木県指定有形文化財として木造大日如来像、御霊屋、多宝塔、山門(仁王門)などがあります。
山内は広すぎてややとりとめのない印象ですが、山内入口の重厚な反橋と楼門、本堂をはじめ堂宇群もさすがに風格を備えています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は御本尊大日如来、左脇本尊 聖観世音菩薩 歓喜天、右脇本尊 薬師如来 弘法大師とあります。


【写真 上(左)】 中御堂(不動堂)
【写真 下(右)】 経堂
中御堂(不動堂)は義兼の創建、生実御所国朝の再建で成田山からの勧請。
御本尊の不動明王は興教大師のお作とも伝わります。
(一切)経堂は、義兼が妻時子の供養のため一切経会を修する道場として創建、関東管領足利満兼の再建とされます。


【写真 上(左)】 多宝塔
【写真 下(右)】 大酉堂
多宝塔は説明板によると徳川五代将軍家綱公の母・桂昌院、あるいはそれ以前の建立で、「徳川氏は新田氏の後裔と称し、新田氏は足利の庄より新田の庄に分家したるが故に徳川氏は祖先発祥の地なるを以て、此の宝塔を祖先の菩提供養のため再度寄進した。」とあります。
新田氏宗家の本領は上野国碓氷郡八幡荘(現・安中市)とみられていますが、新田庄(現・太田市)には徳川氏ゆかりの寺院や遺跡がたくさんあり、ここ足利にも律儀にゆかりの事物が配置されていることは、徳川氏の新田氏発祥説(清和源氏義国流説)へのこだわりを感じさせます。
大酉堂は足利尊氏公を祀るお堂として室町時代に建立と伝わります。
本堂裏手の北側にある智願寺殿御霊屋(蛭子堂)は、義兼の正室(北条)時子をお祀りするものです。


【写真 上(左)】 校倉(大黒天)
【写真 下(右)】 北門
御朱印は本堂脇の授与所にて拝受しました。
札所として関東八十八箇所第16番、下野三十三観音霊場第28番の御朱印を授与。
両野観音霊場第24番も授与情報がありますが、足利七福神(大黒天)は不授与のようです。

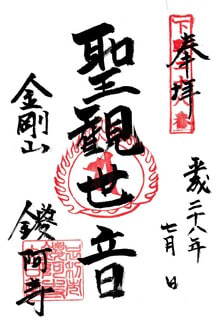
【写真 上(左)】 関東八十八箇所の御朱印
【写真 下(右)】 下野三十三観音霊場の御朱印
34.多福山 一乗院 大寳寺
〔佐竹四郎秀義〕
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
神奈川県鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
佐竹氏は新羅三郎源義光公嫡流の常陸の名族。
源義光公の嫡男・義業の子・昌義 - 隆義 - 秀義とつづきます。
義光公の室(義業の母)は 平(吉田)清幹の息女です。
桓武天皇の孫の平高望(高望王)- 平国香 - 平(大掾)繁盛 - 平(大掾・多気)維幹 - 平(多気)為幹 - 平(多気)重幹 - 平(吉田)清幹 - 娘(義光公の室) - 源義業 - 佐竹昌義の流れで、佐竹氏は清和源氏義光流嫡流であるとともに、桓武平氏の流れもひくという名族です。
いわゆる常陸平氏は、平(吉田)清幹以前からすでに常陸国に勢力基盤を築き、源義業も佐竹氏の名字の地である久慈郡佐竹郷を領したといわれますが、佐竹氏を名乗ったのは佐竹昌義からとされます。(よって、佐竹氏初代は昌義とされる。)
鎌倉幕府草創期の当主は2代隆義、3代秀義で、隆義は平家に仕えて在京が長かったとみられます。
治承四年(1180年)8月の源頼朝公旗揚時、佐竹氏は平家との縁が深かったため参陣せず、同年10月の富士川の戦いでも平家方についています。
平家方の敗戦をうけて佐竹秀義は本拠の常陸国に撤収しますが、頼朝公は上総介広常らの意もあってこれを追撃。
佐竹隆義は在京中で、軍事折衝は隆義の子(兄弟ともいわれる)義政(大掾忠義)と秀義が当たり、攻軍の将・上総介広常との面会に応じた義政はその場で討たれ、金砂城に拠った秀義ら佐竹一族は頼朝軍に攻め落とされて奥州・花園へと落ち延びました。(金砂城の戦い)
寿永二年(1183年)、父・隆義の死により秀義は佐竹氏の家督を相続、佐竹氏3代当主となりました。
その後のいきさつがはっきりしないのですが、秀義は文治五年(1189年)の奥州討伐で頼朝軍のなかにその名が見えるので、それ以前に頼朝公に帰順したとみられます。
『吾妻鏡』の文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者にはその名が見えず、帰順はそれ以降かもしれません。
奥州討伐では武功を挙げ、御家人の地位を固めています。
奥州討伐の往路、秀義は頼朝公から佐竹氏の家紋「五本骨扇に月丸」を賜っているので、すでに有力御家人として認知されていることがわかります。
文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩にはその名が見えず、常陸からの途中参陣かも知れません。
(上記の家紋賜いは宇都宮出立時という資料(→『新編鎌倉志』)があります。)
建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩(→ 原典(国会図書館D.C))には先陣随兵廿八番に「佐竹別當」としてその名が見えます。
先陣随兵廿八番は格高の番で、他に「武田太郎」(武田信義?)、「遠江四郎」(安田義定?)の有力御家人2名がいるので、やはり相応の地位を得ていたのでは。
承久の乱後の嘉禄元年(1225年)末、有力御家人としての地位を保って鎌倉名越の館にて死去。
この「名越の館」は現・大寶寺周辺とみられています。
後を継いだ4代義重は承久の乱でも活躍し、寛元三年(1245年)常陸介に任ぜられています。
佐竹氏は本来国司にふさわしい家柄ですから、その格式を義重の代でとりもどしたということになります。
(秀義の代に、すでに常陸介に任ぜられたという説もあり。)
富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく、このように有力御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。
佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とし、桓武平氏の流れもひく常陸の名族。
秋霜烈日な頼朝公も、名流・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。
鎌倉・大町にある日蓮宗寺院、大寶寺は、新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。
現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が、兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ、以降佐竹氏の屋敷になったといいます。
應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。
源義光公は、戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。
山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)は、もともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀され、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。
ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。
『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。
佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。
『新編鎌倉志』
「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」
『鎌倉攬勝考』
「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」
ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。
「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」
「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。
應永十四年(1407年)、第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。
足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。
与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。
應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では、義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。
これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝えられます。
上記から、1400年代中盤までは、佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。
應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。
「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。
佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。
新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。
義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。
その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。


【写真 上(左)】 道標
【写真 下(右)】 山内入口
大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどなく、閑静な住宅地となっています。
大寳寺はこの小路から、さらに左手山側に入ったところにあります。
位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。


【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。
参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 お題目塔
本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。
正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。
こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。
本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。


【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神
【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額
山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。
拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。
新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが、墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)
御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。
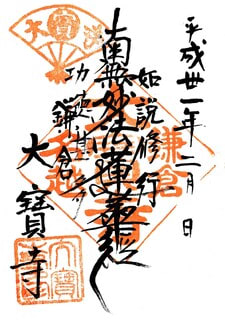
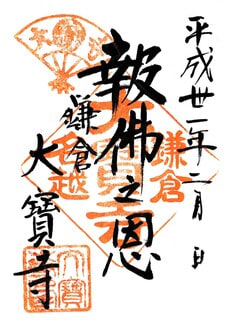
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
35.萬徳山(梅田山) 梅林寺 明王院
〔志田三郎先生義広〕
公式Web
東京都足立区梅田4-15-30
真言宗豊山派
御本尊:不動明王(赤不動尊)
札所:荒綾八十八ヶ所霊場第35番、荒川辺八十八ヶ所霊場第43番
このあたりで、少しく時代を遡ります。
源頼朝公の祖父・源為義公の三男・義広ははやくから都で東宮帯刀先生職にあり、仁平三年(1151年)頃関東に下向し常陸国信太(志田)荘(現・茨城県稲敷市)を開墾して本拠地(志田庄を立荘)としたため、通称を志田(志太、信太)三郎先生と呼ばれました。
『吾妻鏡』(文治四年六月大四日条)には、八條院領として常陸國志太庄が載っています。
八條院領は美福門院(1117-1160年)およびその息女・八条院暲子内親王の所領なので、志田義広は所領を通じて美福門院、八条院、あるいは八条院の猶子・以仁王と関係があったとみられます。
その当時、源為義公は京にあって摂関家との関係を強めたのに対し、長男・義朝公は東国へ下り相州を中心とした南関東で勢力を伸ばしました。
義朝公は妻の実家の熱田大宮司家を通じて鳥羽法皇に接近し、摂関家方の為義公とは政治的にも対立関係にありました。
仁平三年(1153年)義朝公は下野守に任じられ、父・為義公を凌いで受領となりました。為義公は東国における義朝公の勢力を削ぐために次男の義賢を上野国に下向させ、義賢は武蔵国で留守所総検校職にあった秩父重隆の娘を娶り、武蔵国比企郡の大蔵に館を構えました。
久寿二年(1155年)8月、義朝公の長男・義平(悪源太)が大蔵館を襲撃し、義賢と秩父重隆を攻め殺しました。(大蔵合戦)
その背景には諸説ありますが、鎌倉を本拠とする義平が北上をもくろみ、武蔵國の叔父・義賢と対立したためとみられています。
義賢は義広の同母兄とされますが、大蔵合戦時における義広の動向は不明です。
保元元年(1156年)の保元の乱は、後白河天皇方として義朝公、義朝公の父・為義公以下、四男・頼賢、五男・頼仲、六男・為宗、七男・為成、八男・為朝、九男・為仲が崇徳上皇方につき、上皇方の敗戦により伊豆大島に流された八男・為朝をのぞいて斬首されました。
保元の乱(保元元年(1156年))、平治の乱(平治元年(1159年))における志田義広の動向は諸説ありよくわかりませんが、乱後も勢力を保っていることから、無傷で乗り切ったとみられています。
次男・義賢(木曾義仲の父)は、大蔵合戦で討ち死にしているので、治承四年(1180年)5月の以仁王挙兵時点では、三男・義憲(義広)と十男・行家を残すのみでした。(ほかにも庶子がいたという説あり。)
十男・行家は東国に地盤をもたず、以仁王の平家追討の令旨を各地の源氏に伝達していたので、この時点で東国で勢力を張っていたのは義広のみでした。
以仁王挙兵の際、末弟の源行家が甥の頼朝公に以仁王の令旨を伝達したのち、義広の元に向かったとされ(『平家物語』)、これは以仁王令旨が八條院領に触れられたという記録と合致します。
同年11月、頼朝公と常陸佐竹氏が戦った「金砂城の戦い」での義広動向はよくわかりませんが、戦の直後に常陸国府で行家ととともに頼朝公に対面しているので(『吾妻鏡』)、頼朝公と直接の敵対関係はなかったとみられます。
その後も頼朝公の麾下に入ったということもなく、常陸で独自の勢力を維持しました。
東国に地盤をもつ唯一の叔父、志田義広に対し、の時点では頼朝公も強い態度を打ち出せなかったのかもしれません。
寿永二年(1183年)2月、義広は鹿島社所領の押領を頼朝公に諫められたことに反発、下野に勢力を張る藤姓足利氏の足利俊綱・忠綱父子と連合し2万の兵を集めて頼朝公に反旗を翻し下野に兵を進めました。
下野国の有力者小山朝政は、源範頼公、結城朝光、長沼宗政、佐野基綱らと連合して野木宮(現・野木町)で義広勢に攻めかかり、激戦ののち義広勢は敗れて常陸の本拠地を失いました。(野木宮合戦)
頼朝公は野木宮合戦に直接関与していないという説もありますが、頼朝公からすると叔父に当たり、常陸に勢力を維持していた義広に強い警戒感をもっていたことは確かかと。
その後、義広は同母兄・義賢の子・木曾義仲に合流し、義仲は義広を叔父として遇して義仲とともに上洛を果たし、義広は信濃守に任官されています。
元暦元年(1184年)の宇治川の戦いでは西上した義経軍と対峙、粟津の戦いで義仲が討ち死にした後も反頼朝の立場を崩さず、同年5月伊勢国羽取山(現・三重県鈴鹿市)で波多野盛通、大井実春、山内首藤経俊らと合戦の末、斬首されました(『吾妻鏡』)。
志田義広の子として、志田義延、志田義国、志田頼重の名が伝わり、Wikipediaによると「志駄氏、梅田氏、楢崎氏、比志島氏、小山田氏などが義広の後裔を称している」とのことです。
東京都足立区の明王院は義広の開基と伝わり、同寺の公式Webには以下のとおりあります。
-------------------
1178 治承2 志田三郎先生源義廣、榎戸(現在地より南方、荒川寄り)に祈願所を草創する
義廣三世の左馬之助義純、当所に蟄居する
以後、その子孫が代々居住する
義廣五世常陸介久廣、天満宮を勧請する
久廣、この頃より性を梅田氏と名乗る
また、寺の山号を萬徳山、寺号を梅林寺と称するようになる
永正年間 義廣二十一世梅田久義、丹波に移住
-------------------
治承二年(1178年)の時点で義広が榎戸の地に祈願所を草創していたということは、この地に所領をもっていたのかもしれません。
「義廣三世の左馬之助義純」は、義広の子・志田義延、志田義国、志田頼重いずれかの子ということになります。
その後、梅田と姓を改め、少なくとも室町後期の永正年間(1504-1521年)までは当寺と関係があったとみられます。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内
東武伊勢崎線「梅島」駅から徒歩約20分と交通はやや不便ですが、「赤不動尊」と通称され、このあたりでは有数の名刹として親しまれています。
下町らしく狭い路地に家が建て込む街区ですが、そのなかに広々とした山内を構え、基壇のうえにそびえる入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂は、さすがに名刹の風格があります。


【写真 上(左)】 回向堂
【写真 下(右)】 本堂
参道正面は回向堂で不動三尊が御本尊。
参道右手の朱塗りの堂宇が不動堂(本堂)で、御本尊・感得不動明王、如意輪観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 荒綾霊場の札所板
御本尊の感得不動明王(赤不動尊)は、弘法大師が御歳42歳のときに厄除祈願のため造立された御像と伝わります。
当初高野山に安置、根来寺、清閑寺と遷られ、寛保二年(1742年)当寺に奉戴されました。(当寺縁起書)
如意輪観世音菩薩像は南北朝時代の応安二年(1369年)、院派の院秀作とされ、都の有形文化財に指定されています。
当山の鎮守として天満宮、咳止めに霊験あらたかな八彦尊もお祀りされています。
不動尊とのゆかりがふかい寺院で、明和元年(1764年)8月には成田山の出張開帳がおこなわれ、明和二年(1765年)には本所回向院で御本尊・感得不動明王の出開帳がなされているので、篤く信仰されたお不動さまであることがわかります。
徳川家光公・八代将軍吉宗公・十二代将軍家慶公など歴代将軍の鷹狩りの折の御膳所となり、『江戸名所図絵』にも掲載されている江戸の名所のひとつです。
御朱印は庫裡にて荒綾霊場のものが授与されています。

■ 明王院の御朱印
36.白山 東光寺
〔畠山次郎重忠〕
公式Web
神奈川県横浜市金沢区釜利谷2-40-8
臨済宗円覚寺派
御本尊:薬師如来
札所:武州金沢三十四観音霊場第16番、かなざわの霊場めぐり第12番
畠山氏は足利幕府の管領家だったこともあり清和源氏のイメージがありますが、もともとの発祥は桓武平氏良文流で秩父氏の一族です。
秩父氏初代の平将恒は、平良文公の子・武蔵介忠頼公と平将門公の娘・春姫との間に生まれ、武蔵国秩父郡に拠って秩父氏を称しました。
将恒の子孫は武蔵国の各所に土着して勢力を広げ、将恒の曾孫・秩父重綱は「武蔵国留守所総検校職」に就きました。
「武蔵国留守所総検校職」は、国司のいなかった武蔵国の国衙で在庁官人のトップとして、武蔵国内の武士を統率・動員する権限をともなう役職で、大きな権限をもっていました。
重綱の孫・重能は武蔵国大里郡畠山荘(現在の埼玉県深谷市)に拠り勢力を張って、畠山氏初代となりました。
桓武平氏良文流で坂東で発展した8つの氏族はとくに「坂東八平氏」と呼ばれ、上総氏・千葉氏・相馬氏・三浦氏・土肥氏・梶原氏・秩父氏・畠山氏などが名を連ねます。(諸説あり)
うち秩父氏・畠山氏が秩父姓で、「坂東八平氏」以外にも小山田氏、稲毛氏、河越氏、渋谷氏、師岡氏、豊島氏、江戸氏などの有力氏族が秩父姓(秩父党)です。
平安時代後期の当主は初代の畠山重能。
久寿二年(1155年)、重能は関東に下向していた源義朝・源義平父子と結んで比企郡の大蔵館を襲い、叔父の重隆とその婿・源義賢を討ちました。(大蔵合戦)
父・秩父重弘が長男でありながら、秩父氏嫡流は次男の重隆が継いだことへの不満が動機のひとつとみられています。
重能はこの勝戦により、秩父氏嫡流が嗣ぐ「武蔵国留守所総検校職」となる立場を得た筈ですが、なぜかこの職は重隆の孫・河越重頼が継いでいます。
保元元年(1156年)の保元の乱には参戦せず、平治元年(1159年)の平治の乱では重能・有重兄弟は平家の郎等として記されています。(『平家物語』『愚管抄』)
源頼朝公の旗揚げ時、重能は大番役として在京し平家方として転戦しています。
武蔵国の領地を守っていたのは、三浦義明(ないし江戸重継)の息女を母とする17歳の嫡男・重忠。
重忠も平家方として頼朝公と対立、治承四年(1180年)8月には秩父党(河越氏、江戸氏)、村山党などを糾合し、源氏方の三浦義明を衣笠城に攻めて討ち取っています。(衣笠城合戦)
この戦の背景は、畠山:平家方、三浦:源氏方という単純な理由だけではないとみられ、諸説展開されていますがここでは触れません。
このあたりから畠山氏の主役は重忠に移り、重忠は弱冠17歳の時点から源平合戦に突入していくことになります。
治承四年(1180年)10月、重忠は河越重頼、江戸重長とともに隅田川の長井渡しで頼朝公に帰順しました。
反頼朝公の色が強かったのは江戸重長で、重忠は先祖の平武綱が八幡太郎義家公より賜った白旗を持って帰参し、頼朝を喜ばせたという逸話(『源平盛衰記』)もあるので、遅参したとはいえ頼朝公の重忠への心証は悪くはなかったとみられます。
源平合戦では数々の戦功を打ち立て、武名をあげました。
宇治川の渡河で立ち往生した同僚の大串重親を対岸へ投げ上げ、三条河原では木曾義仲の愛妾・巴御前と一騎討ちを演じ、一ノ谷の鵯越では馬をいたわりこれを背負って逆落としを掛けるなど、無双の強者ぶりが『平家物語』などに描かれています。
秩父氏嫡流を嗣いでいた河越重頼は義経の舅だったこともあって誅殺され、「武蔵国留守所総検校職」は重忠が継承、名実ともに武蔵国を代表する御家人となりました。
その後も梶原景時の讒言により重忠追討が審議されるなどの危機がありましたが、これをこなして文治五年(1189年)の奥州合戦では先陣を務めて戦功をあげています。
建久元年(1190年)、頼朝公上洛の際は先陣を務め、右近衛大将拝賀の随兵7人の内に選ばれて参院の供奉をしています。
北条時政の息女を娶っていた重忠の立場は重く、幕閣でも重きをなしたとみられます。
建仁三年(1203年)の比企能員の変では北条側につき、比企氏一族を滅ぼしています。
上洛して京都守護職となった平賀朝雅は、北条時政の娘婿で武蔵守でした。
その名分もあってか、武蔵国の大勢力・比企氏亡き後、時政はその後釜として武蔵国掌握を目論んだとみられます。
本領の中伊豆とは比較にならない広大な武蔵国は、時政にとっては垂涎の地だったのでは。
武蔵国には強豪・畠山氏が健在でしたが、当主の重忠は娘婿なので甘くみていたふしもあります。
しかし、畠山重忠はけっして甘い人間ではなく、時政と重忠は次第に対立を深めていきました。
建仁三年(1204年)11月、源実朝公の御台所を京から迎えるため上洛していた重忠の子・畠山重保と平賀朝雅の間で口論となり、畠山氏と平賀氏の確執は強まりました。
両者の義父である北条時政は一貫して平賀朝雅を支持したとみられ、時政は重忠父子を勘当したという説もみられます。
時政が寵愛した後妻・牧の方の娘が平賀朝雅の壻であったことも大きいとみられます。
また、畠山重保と平賀朝雅の口論の前後に、牧の方の息子の北条政範が京で命を落としていることも重要なファクターという見方もあります。(諸説あり)
牧の方は池禅尼の姪という説があり、池禅尼は中納言・藤原隆家の血筋で平清盛の継母、崇徳天皇の皇子・重仁親王の乳母でもあったので、先妻の伊東祐親の娘よりも血筋的には上で、自分の子が北条氏を継ぐべきという考えをもっていたのかもしれません。
じっさい、北条政範は16歳にしてすでに従五位下・左馬権助に任ぜられており、政範が北条氏の嫡子であったとみなす説さえあります。
元久二年(1205年)6月、平賀朝雅は重保から悪口を受けたと牧の方に訴え、牧の方はこれを重忠・重保父子の叛意であるとして時政に対応を迫りました。
時政は子の義時と時房に畠山討伐を相談すると、2人は反対したものの時政の意思は堅く、ついに義時も討伐に同意したといいます。
6月22日、時政の意を受けた三浦義村が由比ヶ浜で畠山重保を討ち、鎌倉へ向かった重忠を迎撃すべく鎌倉から大軍が発向しました。
重忠は鎌倉の不穏を感じてすでに6月19日に菅谷館(現・埼玉県嵐山町)を発っており、22日に二俣川で鎌倉軍と遭遇して激戦を展開したものの衆寡敵せず、ついにこの地で討ち死にしました。
享年42と伝わります。(畠山重忠の乱)
翌23日、義時は重忠謀反は虚報で重忠は無実であった旨を時政に伝えると、その日の夕方、重忠討伐軍に加わった秩父党の稲毛重成父子、榛谷重朝父子が三浦義村らによって殺害されました。
畠山討伐にあたり三浦義村の動きが目立ちますが、これは衣笠城合戦で畠山氏をはじめとする秩父党に衣笠城を攻められ、祖父・義明を討ち取られた恨みもあったものとみられています。
義時は戦後送られてきた重忠の首級に接し「年来合眼の昵を忘れず、悲涙禁じがたし」と嘆いたといいます。
重忠父子は無実の罪で誅されたとされ、討伐を強引に押し進めた時政に対する御家人たちの不満が高まって、ついに時政と牧の方は義時・政子によって伊豆に追放され、平賀朝雅は誅殺されました。(牧氏事件)
↑ ざっと調べた概略だけでもこれだけのボリュームになるので、深く掘り下げれば1冊の本が仕上がるほどのネタがあるかと思います。
『吾妻鏡』も政子と義時が父時政を追放したという事実は描きにくいらしく、この一連の政変の背景については明示していません。
それだけ複雑な事情と、多くのナゾを秘めた政変であったということかと。
乱後の情勢をみると武蔵の強豪・秩父党はほとんどその勢力を失い、相対的に北条執権家(義時・政子)の力が強まりました。
このあたりにも、この政変を評価する深い意味合いがあるのかもしれません。
畠山重忠の乱が時政の失脚に直結したのは、時政の独裁への反発もさることながら、重忠の人望も大きかったのではないでしょうか。
奥州討伐ののちに藤原泰衡の郎党・由利八郎を取り調べた際、梶原景時は傲慢不遜な態度で接したため八郎は頑として取り調べに応じませんでした。
かたや重忠は八郎に礼を尽くして接し、取り調べに応じた八郎は「先ほどの男(景時)とは雲泥の違いである」と述べたという逸話が伝わります。
『源平盛衰記』『義経記』では分別をわきまえた模範的な武士として描かれ、『曽我物語』では曾我兄弟を讒言から救う恩人として描かれています。
東光寺の公式Webではその人柄をつぎのように記しています。
「義を重んじて正路を覆み 文武両道全うし忠良にして私心無く(中略)公明にして寛大 人は其の誠純を敬す」
判官びいきのきらいはあるにしても、人々からその高潔な人格を認められていたことはまちがいないかと思います。
重忠亡きあと、畠山氏の旧領と名跡は足利義兼の子・義純が重忠の未亡人(時政の息女)と婚姻することで継承し、以降畠山氏は源姓の足利家一門として存続することとなります。
(義純の室は重忠と時政の娘の息女という説もあり。)
室町幕府では三管領の一画を占め、高い家格を保つとともに奥州二本松、紀伊、和泉、大和、河内など各地の守護大名としても発展しました。
戦国期に緒戦で敗れ大名の地位は失うものの、子孫は江戸幕府の高家として幕末まで家格を保ちました。
畠山重忠ゆかりの寺社はいくつかありますが、御朱印を授与されている例は少なくここでは横浜市金沢区の東光寺をご紹介します。
長くなったので簡単にいきます。
東光寺は、建仁年間(1201-1204年)畠山重忠が開基となり、重忠の念持佛・薬師如来を御本尊として建長寺六世勅謚大興禅師が鎌倉二階堂薬師ヶ谷(現・鎌倉宮周辺)に開山、医王山東光寺を号したと伝わります。(弘安五年(1282年)開山説もあり。)
応仁年間(1467-1469年)に現在地(釜利谷)へ移転。
釜利谷付近には重忠・重保父子の供養塔があり、重忠の自領か一族の誰かが住していたとされ、そのゆかりで当地に移転したとみられています。
当寺所蔵の鞍・鐙・轡・鞖は重忠ゆかりのものと伝えられ、横浜市の有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 山門-1
【写真 下(右)】 山門-2
金沢区には落ち着きのある禅刹が多いですが、こちらもそのひとつ。
戸建て住宅が整然と並ぶニュータウンに緑ゆたかな山内を残しています。
山門は風格のある切妻屋根本瓦葺の四脚門で、山号扁額が掲げられています。
軒丸瓦に描かれた五三の桐紋は、畠山氏の家紋のひとつとされているものです。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2
手入れのきいた参道まわりのおくに入母屋造銅板葺の本堂で、向拝柱のないすっきりとした向拝です。


【写真 上(左)】 山内-3
【写真 下(右)】 本堂
向拝正面格子扉のうえには「東光禅寺」の寺号扁額。
上部の斗栱や垂木、下場の格子窓とのバランスが絶妙です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額と軒
御本尊の薬師如来の説明書には「厳しい顔つき、ひきしまった肉どり、うねりの強い写実的な衣文などに鎌倉時代初期の運慶派の特色が明らかである。」とありました。
名刹にふさわしく、「酸漿蒔絵蔵」「絹本著色釈迦十六善神図」などの文化財も所蔵しています。
山内には畠山重忠の供養塔もあります。

■ 東光寺の御朱印
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6へつづく。
【 BGM 】
■ Paradise Island - Thom Rotella (1989)
■ If You'd Only Believe - Randy Crawford (1992)
■ Sailing - Rodney Franklin (1982)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 隠れた(?)名曲10曲
リンク切れつなぎなおして2曲追加しました。
---------------------
2022/04/24 UP
ビッグヒット=名曲とは、かならずしも言えないと思う。
大ヒットしてなくても、シングルに切られていなくても、「名曲」として聴き継がれ、愛されている曲があります。
そんな曲を8曲集めてみました。
■ 松田聖子 - Canary
1983年12月リリースの『Canary』収録の聖子ちゃん初作曲曲。
やっぱり作曲の才能あると思う。ドミナントのかけ方がただごとじゃない。
→ 松田聖子 夜ヒットにおける7年の変遷 (貴重版!)
■ Teenage Walk - 渡辺美里
1986年5月リリースのシングル曲だが、「My Revolution」ほどには売れていない。
作曲:小室哲哉、編曲:大村雅朗で、初期小室サウンドの名作だと思う。
この転調、最初に聴いたとき、ほんとになにかの間違いかと思った(笑)
■ M - プリンセス プリンセス
1988年リリースの『LET'S GET CRAZY』収録曲で、ミリオンセラーとなった『Diamonds』のカップリング曲。
抜群のメロディラインで、シングルでもぜんぜんいけたと思う。
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド - サザンオールスターズ
1985年9月リリースの『KAMAKURA』収録曲。
あまりクローズアップされない曲だけど、個人的にはサザン屈指の名曲だと思う。
■ ロッヂで待つクリスマス - 松任谷由実(cover)
1978年リリースの『流線形'80』のトップを飾る名曲。
個人的には「恋人がサンタクロース」よりできがいいと思う。
■ 空から降りてくるLONELINESS - 杉山清貴
sorakara oritekuru LONELINESS (2016 remaster)
杉山清貴の4枚目のアルバムで1989年リリースの『here & there』収録のバラード。
抜群のメロディーラインに、杉山清貴の伸びのあるハイトーンが乗る名曲。
■ 千年の恋 - ANRI・杏里
2000年7月リリースのアルバム『The Beach House』収録の名バラード。
杏里はメロディアスなバラードたくさんもってるけど、これはわけても印象的なメロ曲。
1980年代にシングルで切られてたら、売れたかもしれぬ。
■ Over and Over - Every Little Thing
なぜかオリコン最高位4位に留まったが、これも好メロの名曲。
メロディーを余している感じさえあり、おそらくEメロくらいまであると思う。
■ YOUR EYES - 山下達郎
1982年1月リリースの名盤『FOR YOU』収録。
当初は竹内まりやに書き下ろした作品だったらしいが、見送りとなり『FOR YOU』収録となったらしい。
英語オンリーだが、目の前に夏の海の夕暮れが自然にうかんでくる。
■ Heart Beat (小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド) - 佐野元春
1981年という時代と、佐野元春の希有の才能がシンクロして生み出された神曲。
---------------------
2022/04/24 UP
ビッグヒット=名曲とは、かならずしも言えないと思う。
大ヒットしてなくても、シングルに切られていなくても、「名曲」として聴き継がれ、愛されている曲があります。
そんな曲を8曲集めてみました。
■ 松田聖子 - Canary
1983年12月リリースの『Canary』収録の聖子ちゃん初作曲曲。
やっぱり作曲の才能あると思う。ドミナントのかけ方がただごとじゃない。
→ 松田聖子 夜ヒットにおける7年の変遷 (貴重版!)
■ Teenage Walk - 渡辺美里
1986年5月リリースのシングル曲だが、「My Revolution」ほどには売れていない。
作曲:小室哲哉、編曲:大村雅朗で、初期小室サウンドの名作だと思う。
この転調、最初に聴いたとき、ほんとになにかの間違いかと思った(笑)
■ M - プリンセス プリンセス
1988年リリースの『LET'S GET CRAZY』収録曲で、ミリオンセラーとなった『Diamonds』のカップリング曲。
抜群のメロディラインで、シングルでもぜんぜんいけたと思う。
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド - サザンオールスターズ
1985年9月リリースの『KAMAKURA』収録曲。
あまりクローズアップされない曲だけど、個人的にはサザン屈指の名曲だと思う。
■ ロッヂで待つクリスマス - 松任谷由実(cover)
1978年リリースの『流線形'80』のトップを飾る名曲。
個人的には「恋人がサンタクロース」よりできがいいと思う。
■ 空から降りてくるLONELINESS - 杉山清貴
sorakara oritekuru LONELINESS (2016 remaster)
杉山清貴の4枚目のアルバムで1989年リリースの『here & there』収録のバラード。
抜群のメロディーラインに、杉山清貴の伸びのあるハイトーンが乗る名曲。
■ 千年の恋 - ANRI・杏里
2000年7月リリースのアルバム『The Beach House』収録の名バラード。
杏里はメロディアスなバラードたくさんもってるけど、これはわけても印象的なメロ曲。
1980年代にシングルで切られてたら、売れたかもしれぬ。
■ Over and Over - Every Little Thing
なぜかオリコン最高位4位に留まったが、これも好メロの名曲。
メロディーを余している感じさえあり、おそらくEメロくらいまであると思う。
■ YOUR EYES - 山下達郎
1982年1月リリースの名盤『FOR YOU』収録。
当初は竹内まりやに書き下ろした作品だったらしいが、見送りとなり『FOR YOU』収録となったらしい。
英語オンリーだが、目の前に夏の海の夕暮れが自然にうかんでくる。
■ Heart Beat (小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド) - 佐野元春
1981年という時代と、佐野元春の希有の才能がシンクロして生み出された神曲。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第42番 大浦山 長楽寺(ちょうらくじ)
下田市Web資料
下田市観光ガイド
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市三丁目13-19
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第23番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(弁財天)
授与所:庫裡
安政元年(1854年)12月、大目付格・筒井政憲/勘定奉行・川路聖謨とロシア全権提督・プチャーチンとの間で日露和親条約(日露通好条約)が締結、翌年1月に日本側応接掛・井戸対馬守等と米国使節・アダムス中佐との間で日米和親条約批准書の交換が行われた寺院で、下田市の文化財に指定されています。
現地由緒書には「真言宗 弘治元年(1555)中興開山尊有により再興創建」と明記されていますが、草創年代は諸説あるようです。
現在の長楽寺は、明治初頭の神仏分離令で廃寺の危機に追い込まれた際、法光院長命寺と合併することで存続したといいます。
法光院長命寺は、ペリー艦隊に便乗して海外渡航するという企てに失敗した吉田松陰と金子重輔が一時拘禁された寺で、長命寺跡地は「吉田松陰拘禁之跡(長命寺跡)」として下田市の文化財に指定されています。
長楽寺について、『豆州志稿』には「下田町七間 真言宗 紀州高野山金剛峯寺末 本尊薬師 本尊薬師文明七年(1475年)之ヲ鍋田ノ海ニ得タリト 今尊有ヲ以テ開山トス(承應元年(1652年)入滅) 北條氏勝ノ文書ヲ蔵ム」とあります。
『豆州志稿』で法光院長命寺についての記載はみあたりませんでした。
文明七年(1475年)に鍋田の海(岸)に示現された薬師如来を僧尊宥(承應元年(1652年寂)が御本尊として開山という説があります。
当初は薬師院長楽寺と号して別の地にあったものを、弘治元年(1555年)に僧尊宥が現在地に移して再興開山という説もあります。
『霊場めぐり』では長楽寺の旧地は大浦の大浦堂(西向院)という説を紹介しています。
文明七年(1475年)に鍋田の海(岸)で示現された薬師如来が大浦の薬師院長楽寺で祀られ、弘治元年(1555年)に僧尊宥が現在地に移して再興開山という流れではないでしょうか。
伊豆横道三十三観音霊場第23番の札所ですが、札所本尊の聖観世音菩薩はもともと法光院長命寺の御本尊と伝わります。
-------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 山内
市内中心部ペリーロードのそばにあり、下田の観光ルートに組み込まれています。
なぜか山門の写真がみつからないので、山門はなかったかもしれません。
塀はナマコ壁で、南伊豆らしさを盛り上げています。


【写真 上(左)】 十二支守り本尊とナマコ壁
【写真 下(右)】 弁財天?
山内左手の朱の鳥居のお堂が七福神の弁財天とも思いましたが、本堂内かもしれません。
市の観光資料には「おすみ弁天」とありますが、こちらが七福神の札所本尊かどうかは不明です。
また、山内には宝物館があり、「お吉観音」が祀られています。吉田松陰ゆかりの遺品も収められているようです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂はおそらく宝形造で、頂部にはしっかり露盤、伏鉢、宝珠の3点セットが置かれています。
桟瓦葺。流れ向拝が設けられ飾り瓦つきの降り棟もあるので、典型的な宝形造ではありません。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
こぶりながら、端正にまとまったいい堂宇です。


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 3種の御朱印
御朱印は庫裡にて拝受しました。
こちらは伊豆八十八ヶ所(薬師如来)、伊豆横道三十三観音(聖観世音菩薩)、伊豆国(下田南伊豆)七福神(弁財天)の3種の御朱印を授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
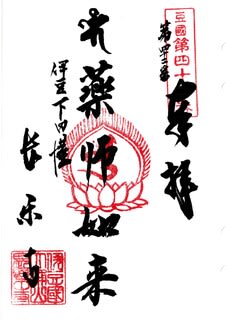

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩
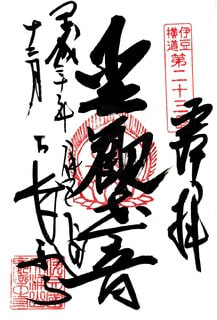
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神の御朱印 〕
● 弁財天
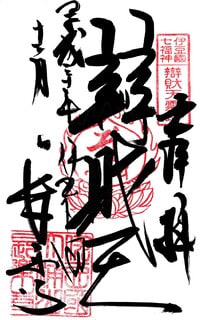
■ 第43番 乳峰山 大安寺(だいあんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市四丁目2-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:伊豆国(下田南伊豆)七福神(大黒天)
授与所:庫裡
当初は小田原にあったともいわれ、暘谷山因善寺と号した真言宗寺院でしたが、天正十年(1590年)寂用英順が相州香雲寺の実堂宗梅を請じて開山とし、曹洞宗に改め改号と伝わります。(異説あり)
『豆州志稿』には「下田町山岸 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 本真言宗ニシテ因善寺ト号ス 天文中(1532-1555年)僧寂用再興改宗シテ寺号ヲ改ム 後天正十九年(1591年)戸田三郎右衛門忠次中興スト云 或ハ云永禄中(1558-1570年)寶堂和尚今ノ宗トシ寺名ヲ改ムト 天文十六年(1547年)明ノ商客李金橋養眞軒ノ記ヲ作ル 養眞軒ハ当寺ノ住層寂用和尚ノ号ナリ 此時改宗シテ香雲寺ニ隷ス 天正八年(1580年)北條氏政ノ寄進状を蔵ス 薬師堂太子堂天神祠倶寺域」とあります。
将軍綱吉公代の貞享五年(1688年)3月、日向国佐土原藩主が将軍家御用材を御手船に積み江戸へ送る途中、遠州灘で嵐に遭い、やむなく積荷の一部を海に捨て難を逃れました。
しかし乗組員16名は御用材を海に捨てた責任をとって全員が切腹し、大安寺に埋葬されました。
船に残されていた材木は、大安寺の本堂の柱としていまも残っているそうです。
乗組員16名の墓は「薩摩十六烈士の墓」として下田市の文化財に指定されています。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
伊豆急下田駅から南にのびる「マイマイ通り」は下田のメインストリート。
この通りから、西側山手に向かって稲田寺、海善寺、宝福寺、八幡神社、大安寺、本覚寺、泰平寺、正面に了仙寺と並びさながら寺社町の様相を呈しています。
(そのほとんどが御朱印を授与され、下田は伊豆でも有数の御朱印エリアです。)
大安寺はそのまんなかにあり、「マイマイ通り」に向かって長く参道を延ばしています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内
山門は切妻屋根銅板葺の薬医門で、山号扁額を掲げています。
山門まわりはこぢんまりとした感じですが、山内は思いのほか広がりがあります。


【写真 上(左)】 列士墓所の案内
【写真 下(右)】 本堂
山門正面が本堂、その左手に聖観世音菩薩像、地蔵尊、鐘楼、その奥に切妻造のお堂。
お堂内の尊格は不明ですが、『豆州志稿』に「薬師堂太子堂天神祠倶寺域」とあるので薬師堂か太子堂かもしれません。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂まわり
本堂は入母屋造本瓦葺の風格ある建物で向拝柱はありません。
向拝見上げに寺号扁額。
本堂前は多重塔、狛犬、石灯籠、摩尼車、天水鉢と賑やかです。
この摩尼車は、摩訶般若波羅蜜多心経、大悲心陀羅尼、消災妙吉祥陀羅尼、舎利礼文、四弘誓願文と刻まれたすぐれものです。


【写真 上(左)】 摩尼車
【写真 下(右)】 向拝
七福神の大黒天は本堂向かって左手にお前立が御座しましたが、御本尊は本堂内のようです。
本堂内は華やかで、見上げには「大覚尊」の扁額が掲げられていました。
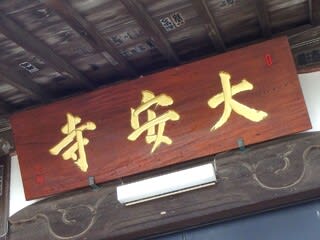

【写真 上(左)】 向拝扁額
【写真 下(右)】 本堂内扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来
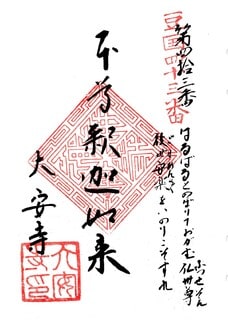

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神の御朱印 〕
● 大黒天
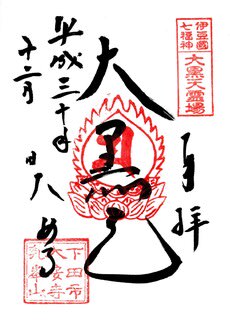
■ 第44番 湯谷山 廣台寺(こうだいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市蓮台寺140
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第19番
授与所:庫裡
蓮台寺温泉は奈良時代、行基菩薩による開湯とも伝わる南伊豆有数の名湯です。
廣台寺はこの蓮台寺温泉にある曹洞宗寺院です。
当初は藤原峯上(那岐里山)の桂昌庵という真言宗の小庵でしたが、慶長十七年(1612年)現在地に移り格雄宗逸和尚により曹洞宗に改宗して開山、湯谷山廣台寺と号を改めました。
『豆州志稿』には「蓮臺寺村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊観世音 昔那岐里山ニ在リ 以テ山号トセリ 元和(1615-1624年)寛永(1624-1644年)ノ間今ノ地ニ移シ 以格雄和尚初祖トス 初桂昌庵ト号ス 格雄ノ時改称ス」とあります。
安政元年(1854年)の大津波の際、下田に滞在していたロシアのプチャーチン提督と勘定奉行川路聖謨が当寺に避難しています。
明治の初年には、地名のもととなった旧蓮臺寺の御本尊・大日如来が当寺で護持されていたとも伝わります。
蓮臺寺についても『豆州志稿』に記載がありました。
「蓮臺寺村号温泉山 天平勝寶三年(751年)行基開場 承久(1219-1222年)の頃廃ス 尚小堂ヲ立テヽ本尊大日ノ像ヲ安ス 村名蓋シ寺号ヨリ起ル」
現在、この旧蓮臺寺の御本尊・木造大日如来坐像(鎌倉期・木彫漆箔寄木造)は国の重要文化財に指定され、蓮台寺温泉街の西のはずれの丘上にある天神神社の収蔵庫に安置されています。
御本尊は聖観世音菩薩で伊豆八十八ヶ所の札所本尊。
別尊の十一面観世音菩薩は、伊豆横道三十三観音霊場の札所本尊です。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道
蓮台寺温泉は高級宿が点在しているイメージで、温泉街のイメージは強くありません。
その一角に廣台寺があります。
参道入口に寺号標。少しくおいて山肌を背に山門と本堂の屋根が見えます。
山門手前に禅刹お決まりの「不許葷酒入山門」碑と欄干を備えた「天門橋」。
山門は切妻屋根本瓦葺で整った掛け瓦と大棟に山号、戸上に山号扁額を掲げて堂々たる構え。
おそらく薬医門かと思われますが、確信ありません。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
手入れの行き届いた山内で、背後の山肌のかかり具合が絶妙です。
正面の本堂は入母屋造桟瓦葺で、降り棟と隅棟がおり成す直線が印象的。
向拝柱はなく、すっきり端正にまとまった堂まわり。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 六地蔵

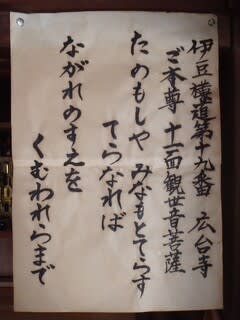
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 横道観音霊場の御詠歌
庫裡でお声掛けすると、本堂に通していただけました。
金色の立派な天蓋に紫色の向拝幕も映えて、華々しい印象の堂内。
正面お厨子内のお像は御本尊の聖観世音菩薩でしょうか。
別に閉扉のお厨子があって、横に「伊豆横道札所 広台寺 十九番 観世音菩薩」の札所板がおかれ、御詠歌も掲げられていました。
このとき、伊豆八十八ヶ所と伊豆横道観音札所をともに巡拝したので、御本尊・聖観音の御前では勤行一式。
横道札所・十一面観世音菩薩の御前では十句観音経、十一面観世音菩薩の御真言などをお唱えしました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩

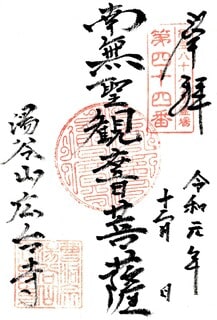
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩
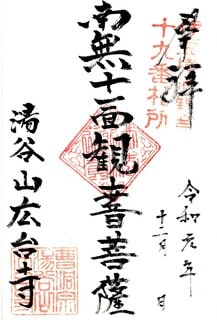
■ 第45番 三壺山 向陽院(こうよういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市河内289
臨済宗建長寺派
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:伊豆国(下田南伊豆)七福神(恵比寿)
授与所:庫裡
「千人風呂」で有名な河内温泉「金谷旅館」のそばにある臨済宗建長寺派の古刹です。
『こころの旅』『霊場めぐり』から由緒を追ってみます。
應永九年(1402年)叡山天台宗の学僧・公範阿闍梨が諸国行脚の折に河内を訪れました。
阿闍梨は、この辺りはいかにも諸佛遊化の霊地勝境と感得され、草庵を結ばれ虚空蔵菩薩と地蔵菩薩を奉安し、地蔵密庵と号したのが草創開基と伝わります。
明應元年(1492年)、鎌倉から宣梅和尚(普翁國師とも)が入られ臨済宗に改宗して三壺山向陽院と号を改めて開山。
『豆州志稿』には「河内村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊虚空蔵 應永中(1394-1428年)僧公範創立地蔵寺院ト称シ天台宗ナリ 明應元年(1492年)僧宣梅改宗シテ向陽院ト号ス 宣梅和尚創建(天文元年(1532年)示寂)」とあります。
『霊場めぐり』で紹介されている『高根地蔵略縁起』によると、御本尊・地蔵菩薩は向陽院の縁の下から掘り出された石佛で、自ら疱瘡をなして里人の身代わりとなり、伊豆沖を航行する廻船が闇夜灘風に進路を失うときは、自ら燈火をともして航路を示されたといいます。
とくに、海上安全、家内安全祈願の地蔵尊として信仰を集めているとのこと。
現在、向陽院本堂には虚空蔵菩薩、高根山山上の境外仏堂には高根地蔵尊が奉安されている模様です。
高根地蔵尊は享保九年(1724年)に向陽院から高根山にご遷座で、嵐の廻船を救われたというのは、この山上からではないでしょうか。
なお、高根山は伊豆山の古々比の森、堂ヶ島の揺橋とともに”伊豆三勝”に数えられるそうです。
山上の様子と地蔵堂は→こちら(YAMAP)で紹介されています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
国道414号天城街道から一本入った道から参道がはじまります。
河内温泉は湯量が豊富で、『霊場めぐり』によると以前はこの近くに「水道の湯」という自然湧出の共同浴場があり、向陽院裏手では53℃の温泉が湧出しているそうです。


【写真 上(左)】 高根地蔵尊別当碑
【写真 下(右)】 山内の地蔵尊
山門手前の「高根山地蔵尊別当」の碑と門柱の「壱月廿四日 高根地蔵海上交通安全祈祷会」の札板は、当山が高根山の地蔵尊の別当(いまでいうと護持寺院)であることを示しています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 右手の堂宇
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門、柱が細めですっきりとした印象。
正面は本堂、参道左手に地蔵堂、右手にも堂宇があり、各堂の屋根が重なり合って美しいラインを描き出しています。


【写真 上(左)】 ふたつの地蔵堂
【写真 下(右)】 手前の地蔵堂
地蔵堂は直角に2宇設置され、手前には多くの地蔵尊、奥のお堂には一躯の地蔵尊が奉安され、手前のお堂には高根不動尊の由緒書が掲げられていました。
叙情ゆたかな文章なので、そのまま引用させていただきます。
「ある年の暮、紀州の国の蜜柑船が大島沖で時化にあい、舵がこわされてしまって船は木の葉のように波にゆりうごかされ今にも沈みそうになりました。その時一人の水夫が高根のお地蔵さんが海難をお守り下さることを思い出して一心不乱に『南無、高根地蔵尊』と唱えてお祈りしました。すると高根山の頂から白い光が現れ、船はその光にみちびかれて無事下田の港につくことが出来たと云われて居ります。それから急に高根の地蔵さんの名は船乗りの間に有名になり、伊豆沖を通過する漁船、運搬船など多くの船がこの地蔵さんに救われたと云われております。(伊豆の民話より)」
右手の堂宇には「金比羅宮」「天満宮」の銘板が掲げられ地主神かもしれません。
堂内にはお像が御座しますが、尊格はわかりませんでした。
『霊場めぐり』に「本堂前にある200㎏余りの石は、当山のダッカイ和尚(三世伝外和尚か)という怪力の和尚が手玉にとった」とありますが、うかつにも見落としました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺で手前に千鳥破風、大棟に山号を掲げています。
千鳥破風が大がかりなので付設向拝のように見えますが、大棟から降る流れ向拝かと思います。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、中備には本蟇股。
向拝柱が太くがっしり安定感ある向拝です。
虚空蔵菩薩を御本尊とする寺院はめずらしくないですが、伊豆八十八ヶ所ではこちらと第63番保春寺の2箇所のみとなっています。
→ 札所リスト
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 虚空蔵菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 河内温泉 「千人風呂 金谷旅館」の入湯レポ
■ 第46番 砥石山 米山寺(べいざんじ/よねやまじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市箕作
無属
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理
伊豆八十八カ所もようやくなかばを過ぎたところ。
ここからいよいよ霊場の核心部ともいえる南伊豆の山中に入っていきます。
ここからの巡路は、伊豆急「稲梓」駅そばの46番米山寺から松崎に向かう県道15号沿いの龍門院(47)、太梅寺(49)、報本寺(48)と回り、婆娑羅峠を越えずに県道を引き返し、小浦・妻良へ向かう県道119号沿いの大賀茂の曹洞院(52)というやっかいなルートです。
しかもここからは無住寺院がいきなり増えます。
他札所での拝受はまだしも、「寺役管理」(寺役さんを電話でお呼びしてお出しいただく、あるいはご自宅にお伺いする)という札所も少なくありません。
運に恵まれないと後日事務局でいただく枚数が多くなるし、御朱印帳の場合は授与いただけない札所も出てきます。
それに加えて、カーナビが頼りにならないことも。
近くまで行ってもいきなり畦道に誘導されたり、そもそもカーナビに登録されていない札所もあったかと思います。
(カーナビよりグーグルMAPの方がカバーしている可能性が高いので、カーナビ不可の場合はグーグルMAPが有効。)
交通量は総じて少ないですが、札所へのアプローチは狭い道が多く、運転には細心の注意が必要です。
それでは第46番米山寺です。
住所はいきなり「下田市箕作」。地番がありません(笑)
でも、国道414号に面しているし、「米山薬師」というバス停もあるので到達難易度はさほどではありません。
現地掲示によると、米山薬師は天平五年(733年)、行基菩薩が当地に留錫されたとき「此の地を観ずるに、東方医王の浄刹に似て仏を作り寺を建つるに佳なるべし」とお告げになり、茶粉と苦芋(トコロ)を練り合わせ、斎戒沐浴、四十八日の長き行の末に薬師如来像を造立されました。
村人たちは堂宇を建ててこの尊像を安置し、以降篤く信仰しました。(『米山薬師縁起』)
その御利益は「僅かに御名を唱ふる輩は万事諸願に満足し、故に定業必死の人も此に来れば、則ち快癒を得る」といわれ、ことに眼病疾病に霊験あらたかで越後の薬師寺(米山薬師)、伊予の薬師寺(山田薬師)とともに「日本三薬師」に数えられ広く信仰を集めます。
下田市Web資料でも米山薬師の縁起が紹介されています。
伊豆八十八ヶ所唯一の無属寺院で現在無住。信徒会によって護持されているようです。
現地掲示によると、御本尊の薬師如来は拝堂から約500m30分ほど登った山頂の本堂(奥の院)に安置とのこと。
御本尊は秘仏で、60年毎(30年目に中開帳)の11月に3日間の御開帳。直近では2015年が中開帳でした。
-------------------


【写真 上(左)】 国道沿いの看板
【写真 下(右)】 参道入口
国道414号天城街道沿いに拝堂があり、伊豆急「稲梓」駅近くのヤマト運輸配送センターの対面。若干の駐車スペースがあります。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 参道階段
国道に面して札所標、石灯籠に石段。少しくのぼると拝堂です。
拝堂はおそらく寄棟造瓦葺で、向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 拝堂
【写真 下(右)】 向拝
拝堂の壁に御朱印案内があり、御朱印代をお堂の浄財口に納めてから、案内にある寺役さん宅に伺うか龍巣院(箕作620-1)で拝受するかたちです。
筆者は寺役さんから授与いただきました。


【写真 上(左)】 奥の院への参道
【写真 下(右)】 石仏
拝堂の向かって右裏手から本堂(奥の院)への石段参道がはじまりますが、筆者は拝堂からの遙拝とさせていただきました。
参道登り口には石仏が安置され、霊場らしい厳かな空気が感じられました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
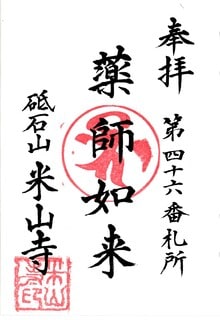

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第47番 保月山 龍門院(りゅうもんいん)
下田市Web資料
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市相玉386
曹洞宗
御本尊:青面金剛明王
札所本尊:青面金剛明王
他札所:-
授与所:第52番曹洞院
『こころの旅』『霊場めぐり』によると由緒は以下のとおりです。
康和元年(1099年)6月、保月嶽頂上の老松に光を放つものがあり、頂に登ってみるとそれは一躰の仏像でした。
人々は「龍が降臨する」と云われていた龍門ヶ嶽に庵を建て、この尊像を安置しました。
あるとき、この地を訪れた行脚の僧が「この像は青面金剛明王である」と云い、以降、青面金剛明王として奉安するようになりました。
『豆州志稿』によると、寛治中(1087-1094年)僧海光が真言宗寺院として創立。
文禄二年(1593年)横川太梅寺四世法山秀禅が再興して曹洞宗に改宗しています。
下田市資料(相玉の庚申さま)によると、こちらの青面金剛明王(庚申さま)はまことに霊験あらたかで、土地の人達は俗に「相玉の庚申様」と呼んで尊信篤く、ことに大漁の神として漁業関係の人々をはじめ、花柳界の人たちの信仰も篤いとのこと。
62年に1回、7日間の御開帳があるそうです。
『豆州志稿』には「銀泉山龍門院 相玉村 曹洞宗 横川太梅寺末 本尊青面金剛 寛治中(1087-1094年)僧海光創立 真言宗ナリ 文禄二年(1593年)太梅寺四世秀禅再興シテ改宗ス 庚申堂寺内」とあります。
御本尊の青面金剛明王は複雑な尊格で、庚申様と同体とみる説もありますが、別の尊格とする説もあります。
『神仏混淆の歴史探訪』(川口謙二氏著、東京美術刊)には「庚申の神像と密教で奉ずる青面金剛とは(もともと)なんの関係もなく、日本に庚申信仰が渡来して密教と結びつき付会されたものである。」とあります。
一方、同書には「『真俗仏事編』第一に古徳の口説をあげ、『青面金剛の法は伝尸病を除く秘法なり。而るに伝尸は則ち三尸の虫なりとす。因レ茲青面金剛を庚申の本地となす。』」という記載があります。
三尸とは、道教由来とされる人間の体内にいる虫で、庚申信仰(庚申待)と深いかかわりをもちます。
詳細は→こちら(Wikipedia)
わが国に伝来する前は別々の尊格で、日本の神仏習合のもとで「庚申の本地は青面金剛」とされ習合したものとみられているようです。
よって、青面金剛明王が御本尊の当寺を「相玉の庚申さま」として崇めるのは、神仏習合のもとでは自然な流れかと。
青面金剛の御朱印は、関西では大阪市天王寺区の四天王寺庚申堂のものが知られていますが、東日本では例がすくなく稀少です。
もちろん、伊豆八十八ヶ所でも唯一の尊格です。
-------------------


【写真 上(左)】 龍門院バス停
【写真 下(右)】 参道
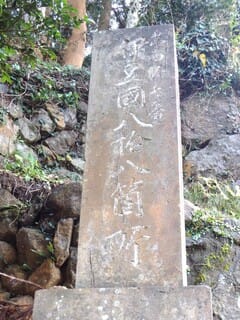

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 冠木門
第46番米山寺からもほど近い、県道15号下田松崎線沿いにあります。
道路沿いから参道階段が伸び、「龍門院」のバス停もあるのでわかりやすいです。
中世の武家館のようないかつい石段に囲まれた石段。
上り口に立派な札所標。すこしく昇ると石造の冠木門。そのよこに「庚申尊」の石碑が見えます。


【写真 上(左)】 「庚申尊」の石碑
【写真 下(右)】 境内入口


【写真 上(左)】 参道正面の堂宇
【写真 下(右)】 同 斜め右手から
のぼり切ると正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の堂宇で、おくに一段高く青緑色の妻入りの建物が千鳥破風を見せています。
位置関係からすると、手前が拝殿、おくが本殿の神社様式のようにも見えますがよくわかりません。
向かって左手に向拝柱と簡素な水引虹梁。


【写真 上(左)】 同 向拝
【写真 下(右)】 2つの堂宇


【写真 上(左)】 右手の堂宇
【写真 下(右)】 同 向拝
右手には、宝形造桟瓦葺流れ向拝のお堂があります。
こちらは仏堂のつくりですが、どちらが本堂かはよくわかりません。
参道正面の方はつくりからして参籠所のような感じもしましたが、そうなるとおくに本殿様の別堂を設けている意味がわかりません。
御朱印は大賀茂の第52番曹洞院でいただけますが、距離があるので夕刻など要注意です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 青面金剛明王

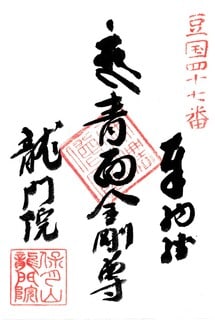
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第48番 婆娑羅山 報本寺(ほうほんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市加増野433-1
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』『霊場めぐり』には以下のとおりあります。
元享三年(1323年)、富貴野山宝蔵院(第81番札所)に向かっていた堀ノ内村の真言宗成就院の円願阿闍梨は、加増野村の風岩峠で濃霧のため道に迷いました。
すると、白衣の老人があらわれ「吾はこの山を守護する明神である。この山は弘法大師の霊境で仏法有縁の地であり、一宇を建てれば功徳多かるべし。」と告げられて忽然と姿を消しました。
円願阿闍梨は歓喜して堂宇を建立し、嘉暦元年(1326年)成就院の観世音菩薩像を遷し御本尊として奉安、婆娑羅山神護寺と号して開山と伝わります。
しばらく無住の時期もありましたが、河津町の沢田林際寺の開山・松嶺に随行されていた哲叟友愚禅師が中興開山して臨済宗に改めました。
『豆州志稿』には「加増野村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 本婆娑羅山ニ観音ノ小堂アリ 嘉暦中(1326-1329年)僧圓岩ノ創立ニシテ真言宗ナリキ 慶永中(1394-1428年)湛忠和尚今ノ地ニ移シ寺号ト為ス 此時ヨリ建長寺ニ隷ス 寺後石窟ニ四國八十八ヶ所ノ諸佛ヲ置ク」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 石段下
【写真 下(右)】 門柱
県道15号下田松崎線の婆娑羅峠の手前にあります。
順打ちでは婆娑羅峠は越えずに下田方面に引き返すことになるので、下田側最奥の札所になります。
ちなみに、下田市Web資料によると「婆娑羅山はその昔弘法大師が婆娑羅三摩耶を修した霊場で仏法有縁の地として知られ、『婆娑羅山』の名もそれから出ている」とのことで、お大師さまゆかりの山域のようです。
また、上記によると、ここには「親捨て」にまつわる伝承が残っています。
県道沿いに参道入口がありますが、周辺は駐車スペースがないので、たしか脇道からいったん本堂そばまで車でのぼり、そこから徒歩で下って参拝しました。


【写真 上(左)】 参道-1
【写真 下(右)】 参道-2
県道からかなりの段数の参道階段がのびています。
その先に山号、寺号が刻まれた門柱。
ここから先は杉木立の下、太鼓橋様の石橋や石仏を見ながらの道行きとなります。


【写真 上(左)】 山門下
【写真 下(右)】 境内
山門の下は踊り場になっていて、二段の石垣が組まれて城内の曲輪のようです。
山門は切妻屋根桟瓦葺で大がかりな降り棟を置き、おそらく四脚門と思われます。
山門をくぐると一気に視界が広がります。
境内前庭の枝垂桜は樹齢200年を越え、下田市の文化財に指定されています。
境内のオガタマノキは県の天然記念物に指定されているようです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
文化年代(1804-1817年)の築と伝わる本堂は、寄棟造桟瓦葺で照りのきいた端正なつくり。
向拝柱はなく、格子戸がメインのシンプルな構成。右手は庫裡です。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 扁額
庫裡でお声掛けすると本堂を開けていただけました。
禅刹らしいすっきり整頓された堂内、向拝見上げには山号扁額が掲げられていました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩

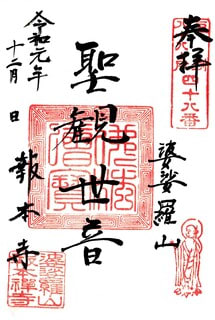
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7へつづく。
【 BGM 】
■ Home - ANGELA AKI
■ 夢の大地 - Kalafina
■ Always You - milet
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第42番 大浦山 長楽寺(ちょうらくじ)
下田市Web資料
下田市観光ガイド
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市三丁目13-19
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第23番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(弁財天)
授与所:庫裡
安政元年(1854年)12月、大目付格・筒井政憲/勘定奉行・川路聖謨とロシア全権提督・プチャーチンとの間で日露和親条約(日露通好条約)が締結、翌年1月に日本側応接掛・井戸対馬守等と米国使節・アダムス中佐との間で日米和親条約批准書の交換が行われた寺院で、下田市の文化財に指定されています。
現地由緒書には「真言宗 弘治元年(1555)中興開山尊有により再興創建」と明記されていますが、草創年代は諸説あるようです。
現在の長楽寺は、明治初頭の神仏分離令で廃寺の危機に追い込まれた際、法光院長命寺と合併することで存続したといいます。
法光院長命寺は、ペリー艦隊に便乗して海外渡航するという企てに失敗した吉田松陰と金子重輔が一時拘禁された寺で、長命寺跡地は「吉田松陰拘禁之跡(長命寺跡)」として下田市の文化財に指定されています。
長楽寺について、『豆州志稿』には「下田町七間 真言宗 紀州高野山金剛峯寺末 本尊薬師 本尊薬師文明七年(1475年)之ヲ鍋田ノ海ニ得タリト 今尊有ヲ以テ開山トス(承應元年(1652年)入滅) 北條氏勝ノ文書ヲ蔵ム」とあります。
『豆州志稿』で法光院長命寺についての記載はみあたりませんでした。
文明七年(1475年)に鍋田の海(岸)に示現された薬師如来を僧尊宥(承應元年(1652年寂)が御本尊として開山という説があります。
当初は薬師院長楽寺と号して別の地にあったものを、弘治元年(1555年)に僧尊宥が現在地に移して再興開山という説もあります。
『霊場めぐり』では長楽寺の旧地は大浦の大浦堂(西向院)という説を紹介しています。
文明七年(1475年)に鍋田の海(岸)で示現された薬師如来が大浦の薬師院長楽寺で祀られ、弘治元年(1555年)に僧尊宥が現在地に移して再興開山という流れではないでしょうか。
伊豆横道三十三観音霊場第23番の札所ですが、札所本尊の聖観世音菩薩はもともと法光院長命寺の御本尊と伝わります。
-------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 山内
市内中心部ペリーロードのそばにあり、下田の観光ルートに組み込まれています。
なぜか山門の写真がみつからないので、山門はなかったかもしれません。
塀はナマコ壁で、南伊豆らしさを盛り上げています。


【写真 上(左)】 十二支守り本尊とナマコ壁
【写真 下(右)】 弁財天?
山内左手の朱の鳥居のお堂が七福神の弁財天とも思いましたが、本堂内かもしれません。
市の観光資料には「おすみ弁天」とありますが、こちらが七福神の札所本尊かどうかは不明です。
また、山内には宝物館があり、「お吉観音」が祀られています。吉田松陰ゆかりの遺品も収められているようです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂はおそらく宝形造で、頂部にはしっかり露盤、伏鉢、宝珠の3点セットが置かれています。
桟瓦葺。流れ向拝が設けられ飾り瓦つきの降り棟もあるので、典型的な宝形造ではありません。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
こぶりながら、端正にまとまったいい堂宇です。


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 3種の御朱印
御朱印は庫裡にて拝受しました。
こちらは伊豆八十八ヶ所(薬師如来)、伊豆横道三十三観音(聖観世音菩薩)、伊豆国(下田南伊豆)七福神(弁財天)の3種の御朱印を授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
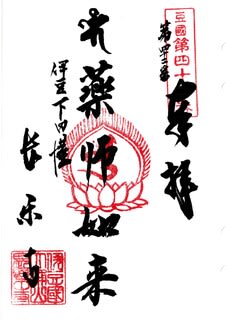

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩
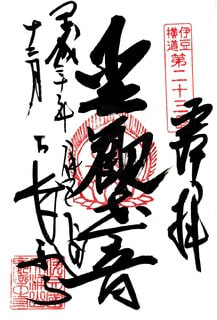
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神の御朱印 〕
● 弁財天
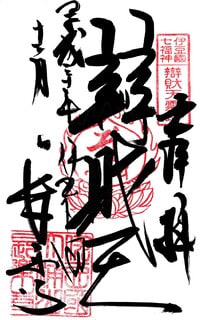
■ 第43番 乳峰山 大安寺(だいあんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市四丁目2-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:伊豆国(下田南伊豆)七福神(大黒天)
授与所:庫裡
当初は小田原にあったともいわれ、暘谷山因善寺と号した真言宗寺院でしたが、天正十年(1590年)寂用英順が相州香雲寺の実堂宗梅を請じて開山とし、曹洞宗に改め改号と伝わります。(異説あり)
『豆州志稿』には「下田町山岸 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 本真言宗ニシテ因善寺ト号ス 天文中(1532-1555年)僧寂用再興改宗シテ寺号ヲ改ム 後天正十九年(1591年)戸田三郎右衛門忠次中興スト云 或ハ云永禄中(1558-1570年)寶堂和尚今ノ宗トシ寺名ヲ改ムト 天文十六年(1547年)明ノ商客李金橋養眞軒ノ記ヲ作ル 養眞軒ハ当寺ノ住層寂用和尚ノ号ナリ 此時改宗シテ香雲寺ニ隷ス 天正八年(1580年)北條氏政ノ寄進状を蔵ス 薬師堂太子堂天神祠倶寺域」とあります。
将軍綱吉公代の貞享五年(1688年)3月、日向国佐土原藩主が将軍家御用材を御手船に積み江戸へ送る途中、遠州灘で嵐に遭い、やむなく積荷の一部を海に捨て難を逃れました。
しかし乗組員16名は御用材を海に捨てた責任をとって全員が切腹し、大安寺に埋葬されました。
船に残されていた材木は、大安寺の本堂の柱としていまも残っているそうです。
乗組員16名の墓は「薩摩十六烈士の墓」として下田市の文化財に指定されています。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
伊豆急下田駅から南にのびる「マイマイ通り」は下田のメインストリート。
この通りから、西側山手に向かって稲田寺、海善寺、宝福寺、八幡神社、大安寺、本覚寺、泰平寺、正面に了仙寺と並びさながら寺社町の様相を呈しています。
(そのほとんどが御朱印を授与され、下田は伊豆でも有数の御朱印エリアです。)
大安寺はそのまんなかにあり、「マイマイ通り」に向かって長く参道を延ばしています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内
山門は切妻屋根銅板葺の薬医門で、山号扁額を掲げています。
山門まわりはこぢんまりとした感じですが、山内は思いのほか広がりがあります。


【写真 上(左)】 列士墓所の案内
【写真 下(右)】 本堂
山門正面が本堂、その左手に聖観世音菩薩像、地蔵尊、鐘楼、その奥に切妻造のお堂。
お堂内の尊格は不明ですが、『豆州志稿』に「薬師堂太子堂天神祠倶寺域」とあるので薬師堂か太子堂かもしれません。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂まわり
本堂は入母屋造本瓦葺の風格ある建物で向拝柱はありません。
向拝見上げに寺号扁額。
本堂前は多重塔、狛犬、石灯籠、摩尼車、天水鉢と賑やかです。
この摩尼車は、摩訶般若波羅蜜多心経、大悲心陀羅尼、消災妙吉祥陀羅尼、舎利礼文、四弘誓願文と刻まれたすぐれものです。


【写真 上(左)】 摩尼車
【写真 下(右)】 向拝
七福神の大黒天は本堂向かって左手にお前立が御座しましたが、御本尊は本堂内のようです。
本堂内は華やかで、見上げには「大覚尊」の扁額が掲げられていました。
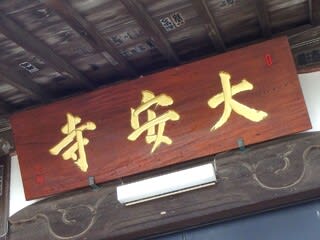

【写真 上(左)】 向拝扁額
【写真 下(右)】 本堂内扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来
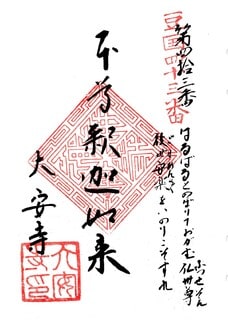

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神の御朱印 〕
● 大黒天
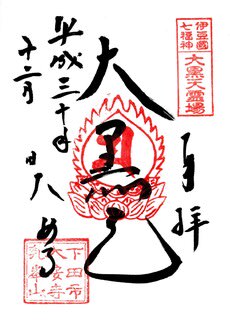
■ 第44番 湯谷山 廣台寺(こうだいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市蓮台寺140
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第19番
授与所:庫裡
蓮台寺温泉は奈良時代、行基菩薩による開湯とも伝わる南伊豆有数の名湯です。
廣台寺はこの蓮台寺温泉にある曹洞宗寺院です。
当初は藤原峯上(那岐里山)の桂昌庵という真言宗の小庵でしたが、慶長十七年(1612年)現在地に移り格雄宗逸和尚により曹洞宗に改宗して開山、湯谷山廣台寺と号を改めました。
『豆州志稿』には「蓮臺寺村 曹洞宗 吉佐美曹洞院末 本尊観世音 昔那岐里山ニ在リ 以テ山号トセリ 元和(1615-1624年)寛永(1624-1644年)ノ間今ノ地ニ移シ 以格雄和尚初祖トス 初桂昌庵ト号ス 格雄ノ時改称ス」とあります。
安政元年(1854年)の大津波の際、下田に滞在していたロシアのプチャーチン提督と勘定奉行川路聖謨が当寺に避難しています。
明治の初年には、地名のもととなった旧蓮臺寺の御本尊・大日如来が当寺で護持されていたとも伝わります。
蓮臺寺についても『豆州志稿』に記載がありました。
「蓮臺寺村号温泉山 天平勝寶三年(751年)行基開場 承久(1219-1222年)の頃廃ス 尚小堂ヲ立テヽ本尊大日ノ像ヲ安ス 村名蓋シ寺号ヨリ起ル」
現在、この旧蓮臺寺の御本尊・木造大日如来坐像(鎌倉期・木彫漆箔寄木造)は国の重要文化財に指定され、蓮台寺温泉街の西のはずれの丘上にある天神神社の収蔵庫に安置されています。
御本尊は聖観世音菩薩で伊豆八十八ヶ所の札所本尊。
別尊の十一面観世音菩薩は、伊豆横道三十三観音霊場の札所本尊です。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道
蓮台寺温泉は高級宿が点在しているイメージで、温泉街のイメージは強くありません。
その一角に廣台寺があります。
参道入口に寺号標。少しくおいて山肌を背に山門と本堂の屋根が見えます。
山門手前に禅刹お決まりの「不許葷酒入山門」碑と欄干を備えた「天門橋」。
山門は切妻屋根本瓦葺で整った掛け瓦と大棟に山号、戸上に山号扁額を掲げて堂々たる構え。
おそらく薬医門かと思われますが、確信ありません。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
手入れの行き届いた山内で、背後の山肌のかかり具合が絶妙です。
正面の本堂は入母屋造桟瓦葺で、降り棟と隅棟がおり成す直線が印象的。
向拝柱はなく、すっきり端正にまとまった堂まわり。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 六地蔵

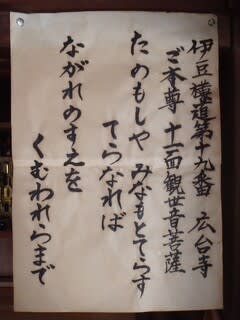
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 横道観音霊場の御詠歌
庫裡でお声掛けすると、本堂に通していただけました。
金色の立派な天蓋に紫色の向拝幕も映えて、華々しい印象の堂内。
正面お厨子内のお像は御本尊の聖観世音菩薩でしょうか。
別に閉扉のお厨子があって、横に「伊豆横道札所 広台寺 十九番 観世音菩薩」の札所板がおかれ、御詠歌も掲げられていました。
このとき、伊豆八十八ヶ所と伊豆横道観音札所をともに巡拝したので、御本尊・聖観音の御前では勤行一式。
横道札所・十一面観世音菩薩の御前では十句観音経、十一面観世音菩薩の御真言などをお唱えしました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩

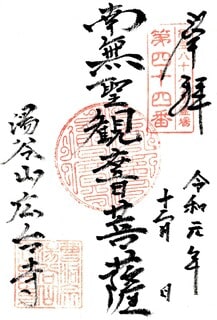
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩
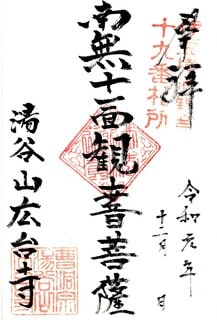
■ 第45番 三壺山 向陽院(こうよういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市河内289
臨済宗建長寺派
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:伊豆国(下田南伊豆)七福神(恵比寿)
授与所:庫裡
「千人風呂」で有名な河内温泉「金谷旅館」のそばにある臨済宗建長寺派の古刹です。
『こころの旅』『霊場めぐり』から由緒を追ってみます。
應永九年(1402年)叡山天台宗の学僧・公範阿闍梨が諸国行脚の折に河内を訪れました。
阿闍梨は、この辺りはいかにも諸佛遊化の霊地勝境と感得され、草庵を結ばれ虚空蔵菩薩と地蔵菩薩を奉安し、地蔵密庵と号したのが草創開基と伝わります。
明應元年(1492年)、鎌倉から宣梅和尚(普翁國師とも)が入られ臨済宗に改宗して三壺山向陽院と号を改めて開山。
『豆州志稿』には「河内村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊虚空蔵 應永中(1394-1428年)僧公範創立地蔵寺院ト称シ天台宗ナリ 明應元年(1492年)僧宣梅改宗シテ向陽院ト号ス 宣梅和尚創建(天文元年(1532年)示寂)」とあります。
『霊場めぐり』で紹介されている『高根地蔵略縁起』によると、御本尊・地蔵菩薩は向陽院の縁の下から掘り出された石佛で、自ら疱瘡をなして里人の身代わりとなり、伊豆沖を航行する廻船が闇夜灘風に進路を失うときは、自ら燈火をともして航路を示されたといいます。
とくに、海上安全、家内安全祈願の地蔵尊として信仰を集めているとのこと。
現在、向陽院本堂には虚空蔵菩薩、高根山山上の境外仏堂には高根地蔵尊が奉安されている模様です。
高根地蔵尊は享保九年(1724年)に向陽院から高根山にご遷座で、嵐の廻船を救われたというのは、この山上からではないでしょうか。
なお、高根山は伊豆山の古々比の森、堂ヶ島の揺橋とともに”伊豆三勝”に数えられるそうです。
山上の様子と地蔵堂は→こちら(YAMAP)で紹介されています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
国道414号天城街道から一本入った道から参道がはじまります。
河内温泉は湯量が豊富で、『霊場めぐり』によると以前はこの近くに「水道の湯」という自然湧出の共同浴場があり、向陽院裏手では53℃の温泉が湧出しているそうです。


【写真 上(左)】 高根地蔵尊別当碑
【写真 下(右)】 山内の地蔵尊
山門手前の「高根山地蔵尊別当」の碑と門柱の「壱月廿四日 高根地蔵海上交通安全祈祷会」の札板は、当山が高根山の地蔵尊の別当(いまでいうと護持寺院)であることを示しています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 右手の堂宇
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門、柱が細めですっきりとした印象。
正面は本堂、参道左手に地蔵堂、右手にも堂宇があり、各堂の屋根が重なり合って美しいラインを描き出しています。


【写真 上(左)】 ふたつの地蔵堂
【写真 下(右)】 手前の地蔵堂
地蔵堂は直角に2宇設置され、手前には多くの地蔵尊、奥のお堂には一躯の地蔵尊が奉安され、手前のお堂には高根不動尊の由緒書が掲げられていました。
叙情ゆたかな文章なので、そのまま引用させていただきます。
「ある年の暮、紀州の国の蜜柑船が大島沖で時化にあい、舵がこわされてしまって船は木の葉のように波にゆりうごかされ今にも沈みそうになりました。その時一人の水夫が高根のお地蔵さんが海難をお守り下さることを思い出して一心不乱に『南無、高根地蔵尊』と唱えてお祈りしました。すると高根山の頂から白い光が現れ、船はその光にみちびかれて無事下田の港につくことが出来たと云われて居ります。それから急に高根の地蔵さんの名は船乗りの間に有名になり、伊豆沖を通過する漁船、運搬船など多くの船がこの地蔵さんに救われたと云われております。(伊豆の民話より)」
右手の堂宇には「金比羅宮」「天満宮」の銘板が掲げられ地主神かもしれません。
堂内にはお像が御座しますが、尊格はわかりませんでした。
『霊場めぐり』に「本堂前にある200㎏余りの石は、当山のダッカイ和尚(三世伝外和尚か)という怪力の和尚が手玉にとった」とありますが、うかつにも見落としました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺で手前に千鳥破風、大棟に山号を掲げています。
千鳥破風が大がかりなので付設向拝のように見えますが、大棟から降る流れ向拝かと思います。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、中備には本蟇股。
向拝柱が太くがっしり安定感ある向拝です。
虚空蔵菩薩を御本尊とする寺院はめずらしくないですが、伊豆八十八ヶ所ではこちらと第63番保春寺の2箇所のみとなっています。
→ 札所リスト
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 虚空蔵菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 河内温泉 「千人風呂 金谷旅館」の入湯レポ
■ 第46番 砥石山 米山寺(べいざんじ/よねやまじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市箕作
無属
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:寺役管理
伊豆八十八カ所もようやくなかばを過ぎたところ。
ここからいよいよ霊場の核心部ともいえる南伊豆の山中に入っていきます。
ここからの巡路は、伊豆急「稲梓」駅そばの46番米山寺から松崎に向かう県道15号沿いの龍門院(47)、太梅寺(49)、報本寺(48)と回り、婆娑羅峠を越えずに県道を引き返し、小浦・妻良へ向かう県道119号沿いの大賀茂の曹洞院(52)というやっかいなルートです。
しかもここからは無住寺院がいきなり増えます。
他札所での拝受はまだしも、「寺役管理」(寺役さんを電話でお呼びしてお出しいただく、あるいはご自宅にお伺いする)という札所も少なくありません。
運に恵まれないと後日事務局でいただく枚数が多くなるし、御朱印帳の場合は授与いただけない札所も出てきます。
それに加えて、カーナビが頼りにならないことも。
近くまで行ってもいきなり畦道に誘導されたり、そもそもカーナビに登録されていない札所もあったかと思います。
(カーナビよりグーグルMAPの方がカバーしている可能性が高いので、カーナビ不可の場合はグーグルMAPが有効。)
交通量は総じて少ないですが、札所へのアプローチは狭い道が多く、運転には細心の注意が必要です。
それでは第46番米山寺です。
住所はいきなり「下田市箕作」。地番がありません(笑)
でも、国道414号に面しているし、「米山薬師」というバス停もあるので到達難易度はさほどではありません。
現地掲示によると、米山薬師は天平五年(733年)、行基菩薩が当地に留錫されたとき「此の地を観ずるに、東方医王の浄刹に似て仏を作り寺を建つるに佳なるべし」とお告げになり、茶粉と苦芋(トコロ)を練り合わせ、斎戒沐浴、四十八日の長き行の末に薬師如来像を造立されました。
村人たちは堂宇を建ててこの尊像を安置し、以降篤く信仰しました。(『米山薬師縁起』)
その御利益は「僅かに御名を唱ふる輩は万事諸願に満足し、故に定業必死の人も此に来れば、則ち快癒を得る」といわれ、ことに眼病疾病に霊験あらたかで越後の薬師寺(米山薬師)、伊予の薬師寺(山田薬師)とともに「日本三薬師」に数えられ広く信仰を集めます。
下田市Web資料でも米山薬師の縁起が紹介されています。
伊豆八十八ヶ所唯一の無属寺院で現在無住。信徒会によって護持されているようです。
現地掲示によると、御本尊の薬師如来は拝堂から約500m30分ほど登った山頂の本堂(奥の院)に安置とのこと。
御本尊は秘仏で、60年毎(30年目に中開帳)の11月に3日間の御開帳。直近では2015年が中開帳でした。
-------------------


【写真 上(左)】 国道沿いの看板
【写真 下(右)】 参道入口
国道414号天城街道沿いに拝堂があり、伊豆急「稲梓」駅近くのヤマト運輸配送センターの対面。若干の駐車スペースがあります。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 参道階段
国道に面して札所標、石灯籠に石段。少しくのぼると拝堂です。
拝堂はおそらく寄棟造瓦葺で、向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 拝堂
【写真 下(右)】 向拝
拝堂の壁に御朱印案内があり、御朱印代をお堂の浄財口に納めてから、案内にある寺役さん宅に伺うか龍巣院(箕作620-1)で拝受するかたちです。
筆者は寺役さんから授与いただきました。


【写真 上(左)】 奥の院への参道
【写真 下(右)】 石仏
拝堂の向かって右裏手から本堂(奥の院)への石段参道がはじまりますが、筆者は拝堂からの遙拝とさせていただきました。
参道登り口には石仏が安置され、霊場らしい厳かな空気が感じられました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
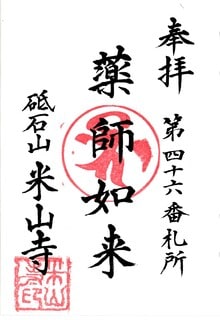

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第47番 保月山 龍門院(りゅうもんいん)
下田市Web資料
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市相玉386
曹洞宗
御本尊:青面金剛明王
札所本尊:青面金剛明王
他札所:-
授与所:第52番曹洞院
『こころの旅』『霊場めぐり』によると由緒は以下のとおりです。
康和元年(1099年)6月、保月嶽頂上の老松に光を放つものがあり、頂に登ってみるとそれは一躰の仏像でした。
人々は「龍が降臨する」と云われていた龍門ヶ嶽に庵を建て、この尊像を安置しました。
あるとき、この地を訪れた行脚の僧が「この像は青面金剛明王である」と云い、以降、青面金剛明王として奉安するようになりました。
『豆州志稿』によると、寛治中(1087-1094年)僧海光が真言宗寺院として創立。
文禄二年(1593年)横川太梅寺四世法山秀禅が再興して曹洞宗に改宗しています。
下田市資料(相玉の庚申さま)によると、こちらの青面金剛明王(庚申さま)はまことに霊験あらたかで、土地の人達は俗に「相玉の庚申様」と呼んで尊信篤く、ことに大漁の神として漁業関係の人々をはじめ、花柳界の人たちの信仰も篤いとのこと。
62年に1回、7日間の御開帳があるそうです。
『豆州志稿』には「銀泉山龍門院 相玉村 曹洞宗 横川太梅寺末 本尊青面金剛 寛治中(1087-1094年)僧海光創立 真言宗ナリ 文禄二年(1593年)太梅寺四世秀禅再興シテ改宗ス 庚申堂寺内」とあります。
御本尊の青面金剛明王は複雑な尊格で、庚申様と同体とみる説もありますが、別の尊格とする説もあります。
『神仏混淆の歴史探訪』(川口謙二氏著、東京美術刊)には「庚申の神像と密教で奉ずる青面金剛とは(もともと)なんの関係もなく、日本に庚申信仰が渡来して密教と結びつき付会されたものである。」とあります。
一方、同書には「『真俗仏事編』第一に古徳の口説をあげ、『青面金剛の法は伝尸病を除く秘法なり。而るに伝尸は則ち三尸の虫なりとす。因レ茲青面金剛を庚申の本地となす。』」という記載があります。
三尸とは、道教由来とされる人間の体内にいる虫で、庚申信仰(庚申待)と深いかかわりをもちます。
詳細は→こちら(Wikipedia)
わが国に伝来する前は別々の尊格で、日本の神仏習合のもとで「庚申の本地は青面金剛」とされ習合したものとみられているようです。
よって、青面金剛明王が御本尊の当寺を「相玉の庚申さま」として崇めるのは、神仏習合のもとでは自然な流れかと。
青面金剛の御朱印は、関西では大阪市天王寺区の四天王寺庚申堂のものが知られていますが、東日本では例がすくなく稀少です。
もちろん、伊豆八十八ヶ所でも唯一の尊格です。
-------------------


【写真 上(左)】 龍門院バス停
【写真 下(右)】 参道
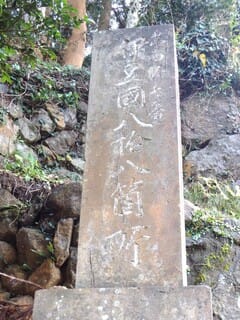

【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 冠木門
第46番米山寺からもほど近い、県道15号下田松崎線沿いにあります。
道路沿いから参道階段が伸び、「龍門院」のバス停もあるのでわかりやすいです。
中世の武家館のようないかつい石段に囲まれた石段。
上り口に立派な札所標。すこしく昇ると石造の冠木門。そのよこに「庚申尊」の石碑が見えます。


【写真 上(左)】 「庚申尊」の石碑
【写真 下(右)】 境内入口


【写真 上(左)】 参道正面の堂宇
【写真 下(右)】 同 斜め右手から
のぼり切ると正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の堂宇で、おくに一段高く青緑色の妻入りの建物が千鳥破風を見せています。
位置関係からすると、手前が拝殿、おくが本殿の神社様式のようにも見えますがよくわかりません。
向かって左手に向拝柱と簡素な水引虹梁。


【写真 上(左)】 同 向拝
【写真 下(右)】 2つの堂宇


【写真 上(左)】 右手の堂宇
【写真 下(右)】 同 向拝
右手には、宝形造桟瓦葺流れ向拝のお堂があります。
こちらは仏堂のつくりですが、どちらが本堂かはよくわかりません。
参道正面の方はつくりからして参籠所のような感じもしましたが、そうなるとおくに本殿様の別堂を設けている意味がわかりません。
御朱印は大賀茂の第52番曹洞院でいただけますが、距離があるので夕刻など要注意です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 青面金剛明王

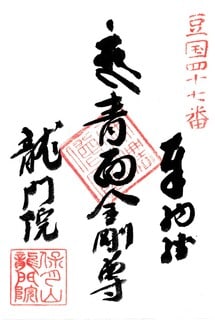
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第48番 婆娑羅山 報本寺(ほうほんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市加増野433-1
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
『こころの旅』『霊場めぐり』には以下のとおりあります。
元享三年(1323年)、富貴野山宝蔵院(第81番札所)に向かっていた堀ノ内村の真言宗成就院の円願阿闍梨は、加増野村の風岩峠で濃霧のため道に迷いました。
すると、白衣の老人があらわれ「吾はこの山を守護する明神である。この山は弘法大師の霊境で仏法有縁の地であり、一宇を建てれば功徳多かるべし。」と告げられて忽然と姿を消しました。
円願阿闍梨は歓喜して堂宇を建立し、嘉暦元年(1326年)成就院の観世音菩薩像を遷し御本尊として奉安、婆娑羅山神護寺と号して開山と伝わります。
しばらく無住の時期もありましたが、河津町の沢田林際寺の開山・松嶺に随行されていた哲叟友愚禅師が中興開山して臨済宗に改めました。
『豆州志稿』には「加増野村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 本婆娑羅山ニ観音ノ小堂アリ 嘉暦中(1326-1329年)僧圓岩ノ創立ニシテ真言宗ナリキ 慶永中(1394-1428年)湛忠和尚今ノ地ニ移シ寺号ト為ス 此時ヨリ建長寺ニ隷ス 寺後石窟ニ四國八十八ヶ所ノ諸佛ヲ置ク」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 石段下
【写真 下(右)】 門柱
県道15号下田松崎線の婆娑羅峠の手前にあります。
順打ちでは婆娑羅峠は越えずに下田方面に引き返すことになるので、下田側最奥の札所になります。
ちなみに、下田市Web資料によると「婆娑羅山はその昔弘法大師が婆娑羅三摩耶を修した霊場で仏法有縁の地として知られ、『婆娑羅山』の名もそれから出ている」とのことで、お大師さまゆかりの山域のようです。
また、上記によると、ここには「親捨て」にまつわる伝承が残っています。
県道沿いに参道入口がありますが、周辺は駐車スペースがないので、たしか脇道からいったん本堂そばまで車でのぼり、そこから徒歩で下って参拝しました。


【写真 上(左)】 参道-1
【写真 下(右)】 参道-2
県道からかなりの段数の参道階段がのびています。
その先に山号、寺号が刻まれた門柱。
ここから先は杉木立の下、太鼓橋様の石橋や石仏を見ながらの道行きとなります。


【写真 上(左)】 山門下
【写真 下(右)】 境内
山門の下は踊り場になっていて、二段の石垣が組まれて城内の曲輪のようです。
山門は切妻屋根桟瓦葺で大がかりな降り棟を置き、おそらく四脚門と思われます。
山門をくぐると一気に視界が広がります。
境内前庭の枝垂桜は樹齢200年を越え、下田市の文化財に指定されています。
境内のオガタマノキは県の天然記念物に指定されているようです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
文化年代(1804-1817年)の築と伝わる本堂は、寄棟造桟瓦葺で照りのきいた端正なつくり。
向拝柱はなく、格子戸がメインのシンプルな構成。右手は庫裡です。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 扁額
庫裡でお声掛けすると本堂を開けていただけました。
禅刹らしいすっきり整頓された堂内、向拝見上げには山号扁額が掲げられていました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩

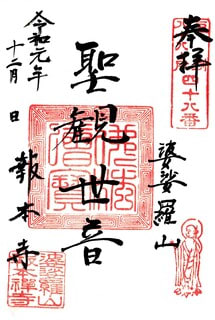
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7へつづく。
【 BGM 】
■ Home - ANGELA AKI
■ 夢の大地 - Kalafina
■ Always You - milet
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)から
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
24.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院(あんよういん)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
坂東三十三観音公式サイト
鎌倉市大町3-1-22
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第3番、鎌倉三十三観音霊場第3番、鎌倉二十四地蔵霊場第24番、相州二十一ヶ所霊場第8番、小田急沿線花の寺四季めぐり第17番
大町にある浄土宗の名刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第3番札所として広く知られています。
このお寺は複雑な由緒をもたれます。
まずは山内由緒書から(抜粋)。
「建立 嘉禄元年(1225)、開山 願行上人、開基 北条政子」
「北条政子が夫・頼朝公の冥福を祈るために佐々目ガ谷に建立した祇園山長楽寺が前身。鎌倉末期に善導寺の跡(現在地)に移って安養院になったといいます。延宝八年(1680)に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかつて建立した田代寺の観音堂を移します。こうして『祇園山安養院田代寺』になりました。」
つぎに鎌倉市観光協会Webから(抜粋)。
「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり。のちに北条政子が夫・頼朝公の菩提のために笹目に建てた長楽寺が焼失したため、鎌倉末期にこの地に長楽寺を移し、政子の法名・安養院を号し、さらに江戸時代の始めに田代寺の千手観音を移した。」
以上より、長楽寺・善導寺・田代寺という3つの前身寺院が関係していることになります。
『鎌倉市史 社寺編』から以下抜粋引用します。
「もと律宗。昌譽の時浄土宗となったという。もと名越派の本山、延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により京都知恩院末となる。開山、願行房憲静。開基、北条氏政子。寺伝では嘉禄元年(1225年)、頼朝夫人政子が頼朝の菩提のため佐々目の長楽寺谷に律寺を建立。願行を開山としたという。『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう。延慶三年(1310年)十一月、失火あり鎌倉中の大火となった。(『武家年代記裏書』)寺伝には、高時滅亡の後、稲瀬川の辺から現在の地、善導寺の跡に移りそれ以降安養院と号したという。延寶八年(1680年)十月、門外町屋から失火、全焼した。再建の時比企ヶ谷にあった末寺、田代観音堂を境内に移した。」
ところが『新編鎌倉志』には「名越の入口、海道の北にあり。祇園山と号す。浄土宗、知恩院の末寺なり。此寺初め律宗にて、開山願行上人なり。其十五世昌譽和尚と云より浄土宗となる。昌譽より前住の牌は皆律宗なり。初長谷の前稲瀬川の邊に在しを、相模入道滅亡の後、此に移すと云伝ふ。本堂に阿彌陀坐像、客殿にも阿彌陀の坐像を安ず。共に安阿彌が作なり。」とあり、前身3寺の所縁は明示されていません。
そこで『新編相模國風土記稿』の安養院の項を当たってみました。
こちらには山内絵図とともに詳しい記述がありました。要点のみ抜粋引用します。
「古ハ笹目ヶ谷ニ在。祇園山長楽寺と号ス。浄土宗。昔ハ無木(本)寺ニテ。名越一派ノ本山ナリ。延寶四年(1676年)諸宗寺院本末御改ヨリ。京知恩院末に属ス。嘉禄元年(1225年)二位ノ禅尼。故頼朝菩提ノ為。笹目ヶ谷邊(西方長谷村界笹目ヶ谷ニ長楽寺谷ト云フアリ。是当寺ノ舊蹟ナリ)ニテ。七堂伽藍ヲ営ミ。律寺ヲ建立シテ。僧願行ヲ開山トシ。又●年七月二位禅尼逝去アリシカバ。願行導師トナリ当寺ニ葬送シ。法名ヲ安養院ト号スト云フ。後兵火ノ為ニ。堂宇残ラズ烏有トナリシカバ。当所善導廃寺蹟ニ移テ堂宇ヲ営ミ両寺を合シテ再建ス。鎌倉志ニ当寺初長谷ノ前。稲瀬川ノ邊ニ在シヲ。相模入道滅亡ノ後此ニ移スト云伝フ云々。是ニ拠バ正應二年(1289年)ノ兵火ナルベシ。又善導寺モ其頃退転セシナルベシ。寺伝ニ彼善導寺開山ハ記主禅師ノ法嗣尊観ナリ。某年名越一派ヲ立。爰ニ一宇ヲ建立シ正和五年(1316年)寂スト云フ。後年現住昌譽カ時。律宗ヲ改メ今ノ宗派トナルと云フ。天文十三年(1544年)北條氏直敷地ヲ寄附ス。延寶八年(1680年)失火シテ諸堂残ナク焼亡ス。其頃比企谷ノ内田代ニ観音堂アリ。当院の末ナリシヲ。当寺再建ノ時境内ニ移シ。夫ヨリ三ヶ寺合成ノ梵宇ト称ス。」
『新編相模國風土記稿』には本堂、観音堂についての記事もありました。
「本堂 本尊阿彌陀 安阿彌作安ス。堂中頼朝又二位禅尼ノ牌。地蔵堂。本尊ハ石像(弘法大師作ト云フ)ニテ。鎌倉二十四所ノ一ナリ。子安地蔵ト云フ。」
「観音堂。本尊千手観音ナリ。立像長五尺四寸恵心作。坂東三十三所ノ札所第三番ト云フ。昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像(立像ニテ長九寸許。天竺竜樹菩薩筆)ヲ籠メ。更ニ比企谷田代ノ地ニ堂舎ヲ造建シテ安置シ。白花山普門寺ト号セリ。土俗ハ多く田代寺又田代堂ナド称セリ。厨子ニ納テ内殿ニ安スト云フ。延寶八年(1680年)当寺焼亡ノ後此境内ニ移セシナリ。前立ニ同像ヲ置キ脇壇ニ阿彌陀ノ座像ヲ置ク。恵心作。是ハ二位禅尼ノ持念佛ト云フ。」
さらに、田代寺についてWikipediaから引いてきました。
「田代寺は1192年(建久3年)田代信綱が尊乗を開山として比企ヶ谷(ひきがやつ)に建立」(原典不明)
引用だらけですみません。
でも、これらの情報がなければ安養寺の由緒(というか3箇寺合一の経緯)がたどれません。
上記資料の青字の箇所が、(おそらく現在地にあった)旧・善導寺についての記述です。
長楽寺、善導寺と合寺後の由緒が混在しているので、すこぶるわかりにくくなっています。
まずは、開山関係から当たってみます。
■ 願行上人憲静(長楽寺)
鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧。
今後のこともあるので、『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同)から経歴・事績の要点を引いてみます。
願行上人憲静は、健保三年(1215年)出生、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。
〔法統・真言宗系統〕
・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)
・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)
・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)
三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。
真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。
これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。
〔法統・律宗系統〕
・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。
・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。
月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。
その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。
この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。
以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。
〔鎌倉での活動〕
願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏)には下記のとおりあります。
・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。
ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。
また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。
「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)
これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。
佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。
なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。
願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。
「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)
佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。
Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。
同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。
また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。
『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。
『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。
さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。
なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。
二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。
■ 尊観上人良弁(善導寺)
鎌倉市Webの「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり」および、『鎌倉市史 社寺編』の「もと名越派の本山、『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう」から探ってみました。
「記主禅師」(良忠上人)は、光明寺ゆかりの高僧です。
「記主禅師」(良忠上人)とは、嘉禎三年(1237年)浄土宗第三祖となられた高僧で、多くの門下を育てられました。 文応元年(1260年)鎌倉へ入られ北条朝直の帰依のもと悟真寺に住され、これがのちに浄土宗大本山光明寺となりました。

■ 光明寺の開山 記主禅師の御朱印
光明寺は名越エリアにあるので「名越一派」は大本山光明寺の流れかと思いましたが、「浄土宗 名越派」で検索してみるとなんと一発でヒットしました。
浄土宗「WEB版新纂浄土宗大辞典」の「名越派」(なごえは)です。
(「鎮西流(鎮西派)」は知っていましたが、不勉強で「名越派」は知りませんでした。)
ここには「三祖然阿良忠門下六派の一つ。派祖は良弁尊観。名越流とも称される。また、尊観が相模国鎌倉名越谷善導寺で布教したため善導寺義ともいう。」とありました。
いわき市山崎の専称寺と栃木県益子町の円通寺が本山格であったようですが、江戸時代は増上寺の支配下にあり、大正以前に浄土宗として統一されているようです。
さらに尊観についても記載がありました。
「延応元年(1239年)—正和五年(1316年)三月一四日。鎌倉時代中期の僧。字(あざな)は良弁。名越派派祖。また鎌倉名越谷の善導寺で布教したため、後世尊観の流派を名越流もしくは善導寺義という。」
どんぴしゃです。これで決め打ちです。
「名越一派」は「浄土宗名越派」をさし、「善導寺」は尊観上人が「浄土宗名越派」の布教の拠点とした寺院です。
これで『新編相模國風土記稿』にあった「名越一派ノ本山ナリ」のナゾが解けたことになります。
■ 田代冠者信綱(普門寺・田代寺)
『新編相模國風土記稿』の安養院観音堂に「昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像」として登場し、普門寺(田代寺)の開基とみられます。
『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「田代観音堂 普門寺と号す。妙本寺の南東なり。安養院末、堂の額に白華山と有。本尊千手観音、坂東第三番の札所。此西の方を田代屋敷と唱ふ。田代冠者信綱が舊跡。今は畑なり。」
「田代冠者信綱」は、おそらくWikipediaに「伊豆国司と狩野茂光の娘の子。石橋山の戦いで頼朝公挙兵時の武士の一人。平家物語の三草山の合戦や一ノ谷の戦い及び屋島の戦いにも登場し。義経公挙兵時の武士ともなり源義仲を追討した。しかし義経公の門下となったと同時に頼朝公から破門の書状を受け(た)。」とある鎌倉幕府草創期の武士とみられます。
これで、ようやく安養院の前身3寺のプロフィールが揃いました。
ごちゃごちゃになったので(笑)、ここで整理してみます。
1.現在地(大町)には、もともと尊観上人(正和五年(1316年)寂)が開かれた浄土宗名越派の善導寺があった。
(正應二年(1289年)の頃(現在地に?)退転したという記録もあり。)
2.一方、長谷笹目ヶ谷には嘉禄元年(1225年)北条政子が夫・頼朝公菩提のために創建した祇園山長楽寺(律宗)があった。開山は二階堂の理智光寺を開いた願行上人憲静。
嘉禄元年(1225年)、二位禅尼(北条政子)逝去の際、願行上人が導師となって当寺に葬送し、法名を安養院と号したという。
また、建治二年(1275年)前後の説法念仏会の折、願行上人が稲瀬川あたり(長谷~由比ヶ浜)に安養院ないしその前身となる寺院(祇園山)を開山された可能性もある。
※ただし、願行上人の鎌倉下向は弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間とみられ、二位禅尼(北条政子)逝去の嘉禄元年(1225年)と時代が合いません。
長楽寺は当初長谷稲瀬川にあり、正應二年(1289年)の兵火を受け笹目に移転した可能性もあるので、願行上人がこれにかかわり、その際に安養院と号したのかもしれません。
3.比企ヶ谷田代には建久三年(1192年)、伊豆の武士田代冠者信綱が尊乗上人を開山に建立した白花山普門寺(田代寺)があり、千手観世音菩薩を御本尊としていた。
普門寺(田代寺)は善導寺ないし長楽寺の末寺であった。
4.笹目の長楽寺は元弘元年(1333年)の兵火で焼失、大町の善導寺に統合されて『安養院長楽寺』と号した。安養院は政子の法号にちなむもの。(*Wikipedia)
5.統合時の安養院は律宗だったが後に浄土宗となり、天文十三年(1544年)には後北条氏第5代北條氏直の寄進を受ける。江戸時代の延寶八年(1680年)失火により諸堂焼亡する。
6.比企ヶ谷の普門寺(田代寺・田代観音)も同年延寶八年(1680年)に焼亡、焼亡した安養院再建の折に比企ヶ谷から本寺であった安養寺の境内に移る。この時点で3つの寺院の合一が為る。
7.坂東三十三箇所の札所本尊の千手観世音菩薩は、比企ヶ谷の普門寺(田代寺)から遷られての御座。
8.延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により、京都知恩院末となる。
以上から安養院は、
1.浄土宗名越派の派祖・尊観上人が名越派の当初の本山とされた善導寺
2.北条政子が頼朝公菩提のために創建。開山願行上人の祇園山長楽寺(律宗)
3.伊豆国守の子、田代冠者信綱が自身の守り本尊・千手観音を奉安した普門寺(田代寺)
という3つの由緒ある寺院の合寺であることがわかりました。
---------------------
※ 令和3年12月時点で当山山内は撮影禁止となっています。
以下の写真は撮影禁止となる前に撮影したものです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 坂東札所標
県道311号大町大路に面して参道入口。
「坂東第三番田代観音」の札所標と「浄土宗名越派根本霊場」の石標。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 名越派根本霊場碑
石段の先に切妻屋根本瓦葺の四脚門で、門下の木箱に拝観料を納めます。
山門をくぐって右手の地蔵堂は鎌倉二十四地蔵霊場第24番の結願所で、札所本尊の日切地蔵尊が御座します。
坐像の石像で弘法大師の御作とも伝わり、子安地蔵ともよばれたそうです。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 鬼板と兎毛通
正面の本堂は権現造のような複雑な意匠で詳細不明。
向拝側の屋根に千鳥破風、向拝軒に唐破風の二重破風となっています。
軒下の水引虹梁両端に雲形の獅子木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いていますが全体にシンプルなイメージ
見上げには山号扁額。


【写真 上(左)】 山号扁額
【写真 下(右)】 堂内向拝
堂内の外陣には札所の御詠歌板などが掲げられています。
格子扉越しに御内陣が拝め、扉うえには院号扁額。
「坂東第三番」の札所だけに、さすがに風格があります。

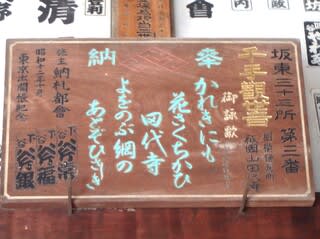
【写真 上(左)】 院号扁額
【写真 下(右)】 坂東霊場札所板
御本尊の阿弥陀如来は伝・安阿彌作。観音霊場札所本尊の千手観世音菩薩は立像長五尺四寸で恵心作と伝わります。
本堂内には北条政子像も安置されています。
こちらは相州二十一ヶ所霊場第8番の札所で、御朱印も授与されています。
こちらの札所については小町の宝戒寺で書きますが、浄土宗でありながら弘法大師霊場の札所となっているのは、旧・長楽寺の開山・願行上人が真言宗醍醐派三宝院流であったことも関係しているかも。
このほか、本堂裏手にある(らしい)、尊観上人の墓で鎌倉最古と伝わる宝篋印塔(国重要文化財)、伝・北条政子の墓、尊観上人お手植えの槙の大木などのみどころがあります。


【写真 上(左)】 撮影禁止看板
【写真 下(右)】 山門から山内
5月のオオムラサキツツジが有名ですが、令和3年12月時点で山門内は撮影禁止となっています。
御朱印拝受時に理由をお伺いしたところ、カメラマンの振る舞いのあまりの酷さにたまりかねての処置とのこと。(当山は以前から三脚類使用禁止でした)
こちらは全国から巡拝者が訪れる坂東霊場札所。巡拝記念に撮影されたい向きも大勢いるのでは? と問い掛けたところ、申し訳なさそうに、たしかにその通りだが、山門外からの撮影は禁止していないのでそちらからの撮影を案内しているとのことでした。
とくに鎌倉の古寺では、にわか(?)カメラマンの傍若無人な撮影っぷりをよく目にしますが、そういうことを続けていくと撮影禁止のお寺さんがどんどん増えていきそうでとても残念です。
〔 御本尊・阿弥陀如来(六字御名号)の御朱印 〕

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕
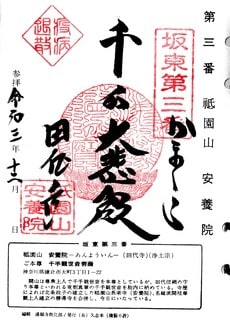
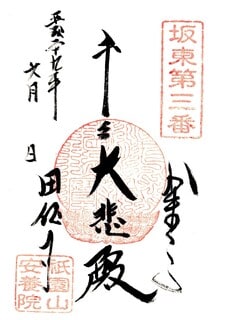
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
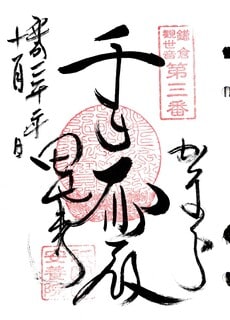

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
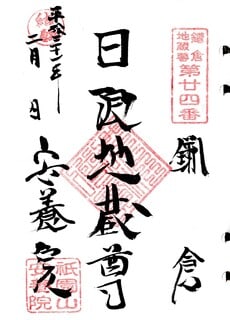

【写真 上(左)】 専用納経帳(結願御朱印)
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

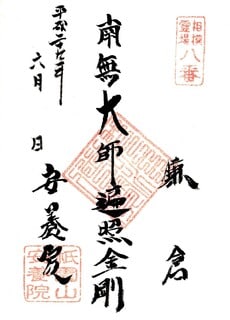
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
25.稲荷山 超世院 別願寺(べつがんじ)
鎌倉市大町1-11-4
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第13番
大町にある時宗寺院で鎌倉三十三観音霊場第13番札所です。
鎌倉公方家ゆかりの寺院で、基氏、氏満、満兼三代の菩提寺であったといわれ、山内には第4代足利持氏公の供養塔と伝わる宝塔があります。
創建開山は不詳ですが、もとは真言宗の能成寺で、弘安五年(1282年)公忍上人(後に覺阿)が時宗に帰依して改宗し、別願寺に改めたのが開基のようです。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおりあります。
「名越町ニアリ 稲荷山超世院ト号ス 時宗(藤澤清浄光寺末) 本尊彌陀ヲ置ク 銅佛立像長二尺二寸 佐竹稲荷ノ神作ト云フ 往昔ハ真言宗ニテ能成寺ト云ヒシトゾ 起立年代開山等詳ナラズ 弘安五年(1282年)五月遊行始祖一遍廻國ノ時 住僧公忍故有テ改宗し 則一遍弟子トナリ 今の寺院号ニ改メ 名ヲモ覺阿ト改ム 故ニ此僧ヲ開基ト称ス
(中略)寺寶 阿弥陀像一幅行基筆(中略) 足利持氏墓 本堂ノ西ニアリ 五輪塔ニテ 長春院殿其阿彌陀佛 永享十一年二月十日ト彫ル 持氏追福ノ為後ニ建タルモノカ 来由詳ナラズ」
『新編相模國風土記稿』には寺領寄進の記録が延々とつづき、管領足利氏満、持氏、満兼、北條の臣大道寺駿河守政繁などの名がみえ、寄進地は下総相馬御厨、下野國薬師寺庄など広域に及んでいます。
『新編相模国風土記稿』には、御本尊の阿弥陀如来は「佐竹稲荷ノ神作ト云フ」という不思議な記述があり、それに因んでか本山の山号は稲荷山です。
ふつう稲荷神の本地は上社(御前):十一面観世音菩薩、中社(御前):千手観世音菩薩、下社(御前):如意輪とされるので、阿弥陀如来との関連はよくわかりません。
また「佐竹」が気になりますが、鎌倉の佐竹氏の屋敷は大町の大寶寺付近とされていますが、こちらとの関連を示す史料はみつかりませんでした。
---------------------


【写真 上(左)】 県道からの山内
【写真 下(右)】 寺号標
県道311号大町大路に面し、安養院のすぐそばにあります。
山門はなく開かれたイメージの山内。
境内に藤棚があり、藤の寺としても知られています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂の様式はよくわかりません。
本堂は妻入りで千鳥破風をみせており、その前に付設した向拝の軒も千鳥破風様になっています。
向拝に寺号扁額。
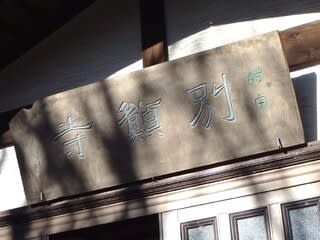

【写真 上(左)】 寺号扁額
【写真 下(右)】 札所板
向拝扉は開く場合があり、なかは外陣で鎌倉観音霊場の札所板が掲げられています。
こちらの札所本尊はめずらしい魚籃観音(ぎょらんかんのん)で、中国の馬郎婦観音と同体とされます。
三十三観世音のひとつで、法華経を広めるために現れた観音とされ、羅刹・毒龍・悪鬼の害を除くことあらたかと信仰されています。
ふつう一面二臂で魚籃(魚入れの籠)を持たれますが、いろいろな像容例がみられるようです。
東京三田・魚籃寺の魚籃観音(江戸三十三箇所観音霊場第25番)は有名で、寺名に由来する魚籃坂の名はいまものこります。
なお、こちらの本堂は令和3年10月に建て替えられていますが、掲載写真は建て替え前のものです。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

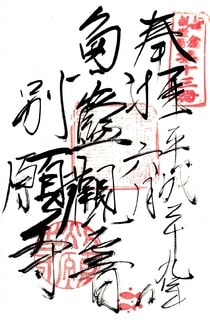
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
以下、つづきます。
26.多福山 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-15-1
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
31.金龍山 釈満院 宝戒寺(ほうかいじ)
公式Web
鎌倉市小町3-5-22
天台宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番
32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)
33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市小町2-23-3
御祭神:大己貴命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神
元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)
34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
単立
御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町1-12-12
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)
司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)
36.天照山 蓮華院 光明寺(こうみょうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-17-19
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第18番、鎌倉二十四地蔵霊場第22番、東国花の寺百ヶ寺霊場第94番、七観音霊場第3番、鎌倉六阿弥陀霊場第3番、小田急沿線花の寺四季めぐり第25番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第48番、関東十八檀林
37.天照山 蓮乗院(れんじょういん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-16-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第19番、相州二十一ヶ所霊場第11番
38.天照山 千手院(せんじゅいん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-12-8
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第20番
39.石井山 長勝寺(ちょうしょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-12-17
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
40.隨我山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市材木座2-9-5
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第14番
41.五所神社(ごしょじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市材木座2-9-1
御祭神:大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、材木座の氏神
42.弘延山 實相寺(じっそうじ)
鎌倉市Web
鎌倉市材木座4-3-13
日蓮宗
御本尊:一尊四士(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
43.南向山 帰命院 補陀落寺(ふだらくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番、新四国東国八十八ヶ所霊場第81番
44.内裏山 霊獄院 九品寺(くほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座5-13-14
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第16番、相州二十一ヶ所霊場第9番、小田急沿線花の寺四季めぐり第18番
45.円龍山 向福寺(こうふくじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座3-15-13
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第15番
46.海潮山 妙長寺(みょうちょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-7-41
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:
47.由比若宮(ゆいのわかみや)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇、神功皇后、比売神
旧社格:鶴岡八幡宮の元宮(元八幡)
48.帰命山 延命寺(えんめいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-1-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番
25.稲荷山 超世院 別願寺(べつがんじ)
鎌倉市大町1-11-4
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第13番
26.多福山 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-15-1
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
31.金龍山 釈満院 宝戒寺(ほうかいじ)
公式Web
鎌倉市小町3-5-22
天台宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番
32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)
33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市小町2-23-3
御祭神:大己貴命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神
元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)
34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
単立
御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町1-12-12
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)
司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)
36.天照山 蓮華院 光明寺(こうみょうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-17-19
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第18番、鎌倉二十四地蔵霊場第22番、東国花の寺百ヶ寺霊場第94番、七観音霊場第3番、鎌倉六阿弥陀霊場第3番、小田急沿線花の寺四季めぐり第25番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第48番、関東十八檀林
37.天照山 蓮乗院(れんじょういん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-16-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第19番、相州二十一ヶ所霊場第11番
38.天照山 千手院(せんじゅいん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-12-8
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第20番
39.石井山 長勝寺(ちょうしょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-12-17
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
40.隨我山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市材木座2-9-5
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第14番
41.五所神社(ごしょじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市材木座2-9-1
御祭神:大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、材木座の氏神
42.弘延山 實相寺(じっそうじ)
鎌倉市Web
鎌倉市材木座4-3-13
日蓮宗
御本尊:一尊四士(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
43.南向山 帰命院 補陀落寺(ふだらくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番、新四国東国八十八ヶ所霊場第81番
44.内裏山 霊獄院 九品寺(くほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座5-13-14
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第16番、相州二十一ヶ所霊場第9番、小田急沿線花の寺四季めぐり第18番
45.円龍山 向福寺(こうふくじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座3-15-13
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第15番
46.海潮山 妙長寺(みょうちょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-7-41
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:
47.由比若宮(ゆいのわかみや)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇、神功皇后、比売神
旧社格:鶴岡八幡宮の元宮(元八幡)
48.帰命山 延命寺(えんめいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-1-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番
【 BGM 】
■ Look Who's Lonely Now - Bill Labounty
■ Emily - Dave Koz
■ I'll Be There - Jack Wagner
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)から
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
24.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院(あんよういん)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
坂東三十三観音公式サイト
鎌倉市大町3-1-22
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第3番、鎌倉三十三観音霊場第3番、鎌倉二十四地蔵霊場第24番、相州二十一ヶ所霊場第8番、小田急沿線花の寺四季めぐり第17番
大町にある浄土宗の名刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第3番札所として広く知られています。
このお寺は複雑な由緒をもたれます。
まずは山内由緒書から(抜粋)。
「建立 嘉禄元年(1225)、開山 願行上人、開基 北条政子」
「北条政子が夫・頼朝公の冥福を祈るために佐々目ガ谷に建立した祇園山長楽寺が前身。鎌倉末期に善導寺の跡(現在地)に移って安養院になったといいます。延宝八年(1680)に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかつて建立した田代寺の観音堂を移します。こうして『祇園山安養院田代寺』になりました。」
つぎに鎌倉市観光協会Webから(抜粋)。
「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり。のちに北条政子が夫・頼朝公の菩提のために笹目に建てた長楽寺が焼失したため、鎌倉末期にこの地に長楽寺を移し、政子の法名・安養院を号し、さらに江戸時代の始めに田代寺の千手観音を移した。」
以上より、長楽寺・善導寺・田代寺という3つの前身寺院が関係していることになります。
『鎌倉市史 社寺編』から以下抜粋引用します。
「もと律宗。昌譽の時浄土宗となったという。もと名越派の本山、延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により京都知恩院末となる。開山、願行房憲静。開基、北条氏政子。寺伝では嘉禄元年(1225年)、頼朝夫人政子が頼朝の菩提のため佐々目の長楽寺谷に律寺を建立。願行を開山としたという。『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう。延慶三年(1310年)十一月、失火あり鎌倉中の大火となった。(『武家年代記裏書』)寺伝には、高時滅亡の後、稲瀬川の辺から現在の地、善導寺の跡に移りそれ以降安養院と号したという。延寶八年(1680年)十月、門外町屋から失火、全焼した。再建の時比企ヶ谷にあった末寺、田代観音堂を境内に移した。」
ところが『新編鎌倉志』には「名越の入口、海道の北にあり。祇園山と号す。浄土宗、知恩院の末寺なり。此寺初め律宗にて、開山願行上人なり。其十五世昌譽和尚と云より浄土宗となる。昌譽より前住の牌は皆律宗なり。初長谷の前稲瀬川の邊に在しを、相模入道滅亡の後、此に移すと云伝ふ。本堂に阿彌陀坐像、客殿にも阿彌陀の坐像を安ず。共に安阿彌が作なり。」とあり、前身3寺の所縁は明示されていません。
そこで『新編相模國風土記稿』の安養院の項を当たってみました。
こちらには山内絵図とともに詳しい記述がありました。要点のみ抜粋引用します。
「古ハ笹目ヶ谷ニ在。祇園山長楽寺と号ス。浄土宗。昔ハ無木(本)寺ニテ。名越一派ノ本山ナリ。延寶四年(1676年)諸宗寺院本末御改ヨリ。京知恩院末に属ス。嘉禄元年(1225年)二位ノ禅尼。故頼朝菩提ノ為。笹目ヶ谷邊(西方長谷村界笹目ヶ谷ニ長楽寺谷ト云フアリ。是当寺ノ舊蹟ナリ)ニテ。七堂伽藍ヲ営ミ。律寺ヲ建立シテ。僧願行ヲ開山トシ。又●年七月二位禅尼逝去アリシカバ。願行導師トナリ当寺ニ葬送シ。法名ヲ安養院ト号スト云フ。後兵火ノ為ニ。堂宇残ラズ烏有トナリシカバ。当所善導廃寺蹟ニ移テ堂宇ヲ営ミ両寺を合シテ再建ス。鎌倉志ニ当寺初長谷ノ前。稲瀬川ノ邊ニ在シヲ。相模入道滅亡ノ後此ニ移スト云伝フ云々。是ニ拠バ正應二年(1289年)ノ兵火ナルベシ。又善導寺モ其頃退転セシナルベシ。寺伝ニ彼善導寺開山ハ記主禅師ノ法嗣尊観ナリ。某年名越一派ヲ立。爰ニ一宇ヲ建立シ正和五年(1316年)寂スト云フ。後年現住昌譽カ時。律宗ヲ改メ今ノ宗派トナルと云フ。天文十三年(1544年)北條氏直敷地ヲ寄附ス。延寶八年(1680年)失火シテ諸堂残ナク焼亡ス。其頃比企谷ノ内田代ニ観音堂アリ。当院の末ナリシヲ。当寺再建ノ時境内ニ移シ。夫ヨリ三ヶ寺合成ノ梵宇ト称ス。」
『新編相模國風土記稿』には本堂、観音堂についての記事もありました。
「本堂 本尊阿彌陀 安阿彌作安ス。堂中頼朝又二位禅尼ノ牌。地蔵堂。本尊ハ石像(弘法大師作ト云フ)ニテ。鎌倉二十四所ノ一ナリ。子安地蔵ト云フ。」
「観音堂。本尊千手観音ナリ。立像長五尺四寸恵心作。坂東三十三所ノ札所第三番ト云フ。昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像(立像ニテ長九寸許。天竺竜樹菩薩筆)ヲ籠メ。更ニ比企谷田代ノ地ニ堂舎ヲ造建シテ安置シ。白花山普門寺ト号セリ。土俗ハ多く田代寺又田代堂ナド称セリ。厨子ニ納テ内殿ニ安スト云フ。延寶八年(1680年)当寺焼亡ノ後此境内ニ移セシナリ。前立ニ同像ヲ置キ脇壇ニ阿彌陀ノ座像ヲ置ク。恵心作。是ハ二位禅尼ノ持念佛ト云フ。」
さらに、田代寺についてWikipediaから引いてきました。
「田代寺は1192年(建久3年)田代信綱が尊乗を開山として比企ヶ谷(ひきがやつ)に建立」(原典不明)
引用だらけですみません。
でも、これらの情報がなければ安養寺の由緒(というか3箇寺合一の経緯)がたどれません。
上記資料の青字の箇所が、(おそらく現在地にあった)旧・善導寺についての記述です。
長楽寺、善導寺と合寺後の由緒が混在しているので、すこぶるわかりにくくなっています。
まずは、開山関係から当たってみます。
■ 願行上人憲静(長楽寺)
鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧。
今後のこともあるので、『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同)から経歴・事績の要点を引いてみます。
願行上人憲静は、健保三年(1215年)出生、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。
〔法統・真言宗系統〕
・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)
・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)
・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)
三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。
真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。
これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。
〔法統・律宗系統〕
・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。
・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。
月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。
その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。
この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。
以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。
〔鎌倉での活動〕
願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏)には下記のとおりあります。
・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。
ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。
また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。
「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)
これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。
佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。
なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。
願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。
「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)
佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。
Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。
同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。
また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。
『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。
『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。
さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。
なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。
二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。
■ 尊観上人良弁(善導寺)
鎌倉市Webの「当初この地には尊観が開いた浄土宗の善導寺があり」および、『鎌倉市史 社寺編』の「もと名越派の本山、『壇林鎌倉光明寺志』には記主良忠門資として、良弁尊観を相州名越安養祖としている。これは善導寺の祖とすべきであろう」から探ってみました。
「記主禅師」(良忠上人)は、光明寺ゆかりの高僧です。
「記主禅師」(良忠上人)とは、嘉禎三年(1237年)浄土宗第三祖となられた高僧で、多くの門下を育てられました。 文応元年(1260年)鎌倉へ入られ北条朝直の帰依のもと悟真寺に住され、これがのちに浄土宗大本山光明寺となりました。

■ 光明寺の開山 記主禅師の御朱印
光明寺は名越エリアにあるので「名越一派」は大本山光明寺の流れかと思いましたが、「浄土宗 名越派」で検索してみるとなんと一発でヒットしました。
浄土宗「WEB版新纂浄土宗大辞典」の「名越派」(なごえは)です。
(「鎮西流(鎮西派)」は知っていましたが、不勉強で「名越派」は知りませんでした。)
ここには「三祖然阿良忠門下六派の一つ。派祖は良弁尊観。名越流とも称される。また、尊観が相模国鎌倉名越谷善導寺で布教したため善導寺義ともいう。」とありました。
いわき市山崎の専称寺と栃木県益子町の円通寺が本山格であったようですが、江戸時代は増上寺の支配下にあり、大正以前に浄土宗として統一されているようです。
さらに尊観についても記載がありました。
「延応元年(1239年)—正和五年(1316年)三月一四日。鎌倉時代中期の僧。字(あざな)は良弁。名越派派祖。また鎌倉名越谷の善導寺で布教したため、後世尊観の流派を名越流もしくは善導寺義という。」
どんぴしゃです。これで決め打ちです。
「名越一派」は「浄土宗名越派」をさし、「善導寺」は尊観上人が「浄土宗名越派」の布教の拠点とした寺院です。
これで『新編相模國風土記稿』にあった「名越一派ノ本山ナリ」のナゾが解けたことになります。
■ 田代冠者信綱(普門寺・田代寺)
『新編相模國風土記稿』の安養院観音堂に「昔田代冠者信綱此像ノ●中ニ守本尊三面ノ千手観音ノ画像」として登場し、普門寺(田代寺)の開基とみられます。
『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「田代観音堂 普門寺と号す。妙本寺の南東なり。安養院末、堂の額に白華山と有。本尊千手観音、坂東第三番の札所。此西の方を田代屋敷と唱ふ。田代冠者信綱が舊跡。今は畑なり。」
「田代冠者信綱」は、おそらくWikipediaに「伊豆国司と狩野茂光の娘の子。石橋山の戦いで頼朝公挙兵時の武士の一人。平家物語の三草山の合戦や一ノ谷の戦い及び屋島の戦いにも登場し。義経公挙兵時の武士ともなり源義仲を追討した。しかし義経公の門下となったと同時に頼朝公から破門の書状を受け(た)。」とある鎌倉幕府草創期の武士とみられます。
これで、ようやく安養院の前身3寺のプロフィールが揃いました。
ごちゃごちゃになったので(笑)、ここで整理してみます。
1.現在地(大町)には、もともと尊観上人(正和五年(1316年)寂)が開かれた浄土宗名越派の善導寺があった。
(正應二年(1289年)の頃(現在地に?)退転したという記録もあり。)
2.一方、長谷笹目ヶ谷には嘉禄元年(1225年)北条政子が夫・頼朝公菩提のために創建した祇園山長楽寺(律宗)があった。開山は二階堂の理智光寺を開いた願行上人憲静。
嘉禄元年(1225年)、二位禅尼(北条政子)逝去の際、願行上人が導師となって当寺に葬送し、法名を安養院と号したという。
また、建治二年(1275年)前後の説法念仏会の折、願行上人が稲瀬川あたり(長谷~由比ヶ浜)に安養院ないしその前身となる寺院(祇園山)を開山された可能性もある。
※ただし、願行上人の鎌倉下向は弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間とみられ、二位禅尼(北条政子)逝去の嘉禄元年(1225年)と時代が合いません。
長楽寺は当初長谷稲瀬川にあり、正應二年(1289年)の兵火を受け笹目に移転した可能性もあるので、願行上人がこれにかかわり、その際に安養院と号したのかもしれません。
3.比企ヶ谷田代には建久三年(1192年)、伊豆の武士田代冠者信綱が尊乗上人を開山に建立した白花山普門寺(田代寺)があり、千手観世音菩薩を御本尊としていた。
普門寺(田代寺)は善導寺ないし長楽寺の末寺であった。
4.笹目の長楽寺は元弘元年(1333年)の兵火で焼失、大町の善導寺に統合されて『安養院長楽寺』と号した。安養院は政子の法号にちなむもの。(*Wikipedia)
5.統合時の安養院は律宗だったが後に浄土宗となり、天文十三年(1544年)には後北条氏第5代北條氏直の寄進を受ける。江戸時代の延寶八年(1680年)失火により諸堂焼亡する。
6.比企ヶ谷の普門寺(田代寺・田代観音)も同年延寶八年(1680年)に焼亡、焼亡した安養院再建の折に比企ヶ谷から本寺であった安養寺の境内に移る。この時点で3つの寺院の合一が為る。
7.坂東三十三箇所の札所本尊の千手観世音菩薩は、比企ヶ谷の普門寺(田代寺)から遷られての御座。
8.延享四年(1747年)六月の諸宗寺院本末改により、京都知恩院末となる。
以上から安養院は、
1.浄土宗名越派の派祖・尊観上人が名越派の当初の本山とされた善導寺
2.北条政子が頼朝公菩提のために創建。開山願行上人の祇園山長楽寺(律宗)
3.伊豆国守の子、田代冠者信綱が自身の守り本尊・千手観音を奉安した普門寺(田代寺)
という3つの由緒ある寺院の合寺であることがわかりました。
---------------------
※ 令和3年12月時点で当山山内は撮影禁止となっています。
以下の写真は撮影禁止となる前に撮影したものです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 坂東札所標
県道311号大町大路に面して参道入口。
「坂東第三番田代観音」の札所標と「浄土宗名越派根本霊場」の石標。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 名越派根本霊場碑
石段の先に切妻屋根本瓦葺の四脚門で、門下の木箱に拝観料を納めます。
山門をくぐって右手の地蔵堂は鎌倉二十四地蔵霊場第24番の結願所で、札所本尊の日切地蔵尊が御座します。
坐像の石像で弘法大師の御作とも伝わり、子安地蔵ともよばれたそうです。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 鬼板と兎毛通
正面の本堂は権現造のような複雑な意匠で詳細不明。
向拝側の屋根に千鳥破風、向拝軒に唐破風の二重破風となっています。
軒下の水引虹梁両端に雲形の獅子木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いていますが全体にシンプルなイメージ
見上げには山号扁額。


【写真 上(左)】 山号扁額
【写真 下(右)】 堂内向拝
堂内の外陣には札所の御詠歌板などが掲げられています。
格子扉越しに御内陣が拝め、扉うえには院号扁額。
「坂東第三番」の札所だけに、さすがに風格があります。

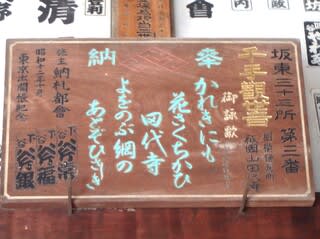
【写真 上(左)】 院号扁額
【写真 下(右)】 坂東霊場札所板
御本尊の阿弥陀如来は伝・安阿彌作。観音霊場札所本尊の千手観世音菩薩は立像長五尺四寸で恵心作と伝わります。
本堂内には北条政子像も安置されています。
こちらは相州二十一ヶ所霊場第8番の札所で、御朱印も授与されています。
こちらの札所については小町の宝戒寺で書きますが、浄土宗でありながら弘法大師霊場の札所となっているのは、旧・長楽寺の開山・願行上人が真言宗醍醐派三宝院流であったことも関係しているかも。
このほか、本堂裏手にある(らしい)、尊観上人の墓で鎌倉最古と伝わる宝篋印塔(国重要文化財)、伝・北条政子の墓、尊観上人お手植えの槙の大木などのみどころがあります。


【写真 上(左)】 撮影禁止看板
【写真 下(右)】 山門から山内
5月のオオムラサキツツジが有名ですが、令和3年12月時点で山門内は撮影禁止となっています。
御朱印拝受時に理由をお伺いしたところ、カメラマンの振る舞いのあまりの酷さにたまりかねての処置とのこと。(当山は以前から三脚類使用禁止でした)
こちらは全国から巡拝者が訪れる坂東霊場札所。巡拝記念に撮影されたい向きも大勢いるのでは? と問い掛けたところ、申し訳なさそうに、たしかにその通りだが、山門外からの撮影は禁止していないのでそちらからの撮影を案内しているとのことでした。
とくに鎌倉の古寺では、にわか(?)カメラマンの傍若無人な撮影っぷりをよく目にしますが、そういうことを続けていくと撮影禁止のお寺さんがどんどん増えていきそうでとても残念です。
〔 御本尊・阿弥陀如来(六字御名号)の御朱印 〕

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕
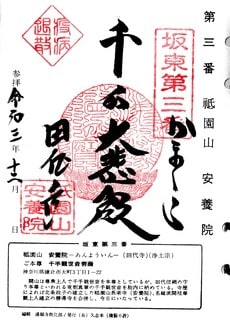
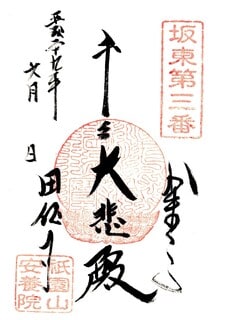
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
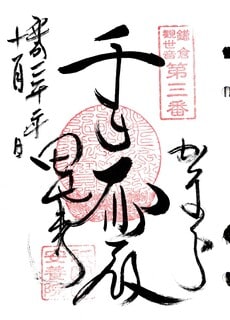

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
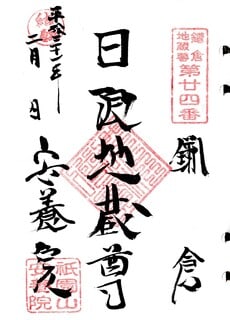

【写真 上(左)】 専用納経帳(結願御朱印)
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

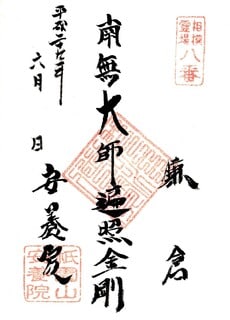
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
25.稲荷山 超世院 別願寺(べつがんじ)
鎌倉市大町1-11-4
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第13番
大町にある時宗寺院で鎌倉三十三観音霊場第13番札所です。
鎌倉公方家ゆかりの寺院で、基氏、氏満、満兼三代の菩提寺であったといわれ、山内には第4代足利持氏公の供養塔と伝わる宝塔があります。
創建開山は不詳ですが、もとは真言宗の能成寺で、弘安五年(1282年)公忍上人(後に覺阿)が時宗に帰依して改宗し、別願寺に改めたのが開基のようです。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおりあります。
「名越町ニアリ 稲荷山超世院ト号ス 時宗(藤澤清浄光寺末) 本尊彌陀ヲ置ク 銅佛立像長二尺二寸 佐竹稲荷ノ神作ト云フ 往昔ハ真言宗ニテ能成寺ト云ヒシトゾ 起立年代開山等詳ナラズ 弘安五年(1282年)五月遊行始祖一遍廻國ノ時 住僧公忍故有テ改宗し 則一遍弟子トナリ 今の寺院号ニ改メ 名ヲモ覺阿ト改ム 故ニ此僧ヲ開基ト称ス
(中略)寺寶 阿弥陀像一幅行基筆(中略) 足利持氏墓 本堂ノ西ニアリ 五輪塔ニテ 長春院殿其阿彌陀佛 永享十一年二月十日ト彫ル 持氏追福ノ為後ニ建タルモノカ 来由詳ナラズ」
『新編相模國風土記稿』には寺領寄進の記録が延々とつづき、管領足利氏満、持氏、満兼、北條の臣大道寺駿河守政繁などの名がみえ、寄進地は下総相馬御厨、下野國薬師寺庄など広域に及んでいます。
『新編相模国風土記稿』には、御本尊の阿弥陀如来は「佐竹稲荷ノ神作ト云フ」という不思議な記述があり、それに因んでか本山の山号は稲荷山です。
ふつう稲荷神の本地は上社(御前):十一面観世音菩薩、中社(御前):千手観世音菩薩、下社(御前):如意輪とされるので、阿弥陀如来との関連はよくわかりません。
また「佐竹」が気になりますが、鎌倉の佐竹氏の屋敷は大町の大寶寺付近とされていますが、こちらとの関連を示す史料はみつかりませんでした。
---------------------


【写真 上(左)】 県道からの山内
【写真 下(右)】 寺号標
県道311号大町大路に面し、安養院のすぐそばにあります。
山門はなく開かれたイメージの山内。
境内に藤棚があり、藤の寺としても知られています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂の様式はよくわかりません。
本堂は妻入りで千鳥破風をみせており、その前に付設した向拝の軒も千鳥破風様になっています。
向拝に寺号扁額。
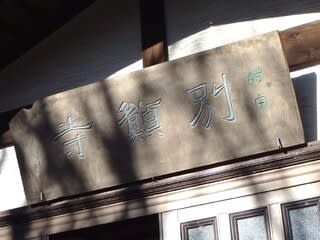

【写真 上(左)】 寺号扁額
【写真 下(右)】 札所板
向拝扉は開く場合があり、なかは外陣で鎌倉観音霊場の札所板が掲げられています。
こちらの札所本尊はめずらしい魚籃観音(ぎょらんかんのん)で、中国の馬郎婦観音と同体とされます。
三十三観世音のひとつで、法華経を広めるために現れた観音とされ、羅刹・毒龍・悪鬼の害を除くことあらたかと信仰されています。
ふつう一面二臂で魚籃(魚入れの籠)を持たれますが、いろいろな像容例がみられるようです。
東京三田・魚籃寺の魚籃観音(江戸三十三箇所観音霊場第25番)は有名で、寺名に由来する魚籃坂の名はいまものこります。
なお、こちらの本堂は令和3年10月に建て替えられていますが、掲載写真は建て替え前のものです。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

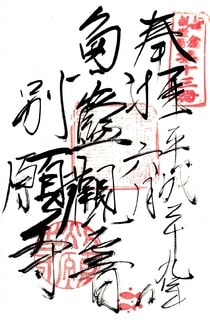
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
以下、つづきます。
26.多福山 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-15-1
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
31.金龍山 釈満院 宝戒寺(ほうかいじ)
公式Web
鎌倉市小町3-5-22
天台宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番
32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)
33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市小町2-23-3
御祭神:大己貴命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神
元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)
34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
単立
御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町1-12-12
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)
司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)
36.天照山 蓮華院 光明寺(こうみょうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-17-19
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第18番、鎌倉二十四地蔵霊場第22番、東国花の寺百ヶ寺霊場第94番、七観音霊場第3番、鎌倉六阿弥陀霊場第3番、小田急沿線花の寺四季めぐり第25番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第48番、関東十八檀林
37.天照山 蓮乗院(れんじょういん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-16-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第19番、相州二十一ヶ所霊場第11番
38.天照山 千手院(せんじゅいん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-12-8
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第20番
39.石井山 長勝寺(ちょうしょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-12-17
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
40.隨我山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市材木座2-9-5
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第14番
41.五所神社(ごしょじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市材木座2-9-1
御祭神:大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、材木座の氏神
42.弘延山 實相寺(じっそうじ)
鎌倉市Web
鎌倉市材木座4-3-13
日蓮宗
御本尊:一尊四士(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
43.南向山 帰命院 補陀落寺(ふだらくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番、新四国東国八十八ヶ所霊場第81番
44.内裏山 霊獄院 九品寺(くほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座5-13-14
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第16番、相州二十一ヶ所霊場第9番、小田急沿線花の寺四季めぐり第18番
45.円龍山 向福寺(こうふくじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座3-15-13
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第15番
46.海潮山 妙長寺(みょうちょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-7-41
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:
47.由比若宮(ゆいのわかみや)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇、神功皇后、比売神
旧社格:鶴岡八幡宮の元宮(元八幡)
48.帰命山 延命寺(えんめいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-1-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番
25.稲荷山 超世院 別願寺(べつがんじ)
鎌倉市大町1-11-4
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第13番
26.多福山 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-15-1
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
31.金龍山 釈満院 宝戒寺(ほうかいじ)
公式Web
鎌倉市小町3-5-22
天台宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番
32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)
33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市小町2-23-3
御祭神:大己貴命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神
元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)
34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町2-17-20
単立
御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町1-12-12
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)
司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)
36.天照山 蓮華院 光明寺(こうみょうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-17-19
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第18番、鎌倉二十四地蔵霊場第22番、東国花の寺百ヶ寺霊場第94番、七観音霊場第3番、鎌倉六阿弥陀霊場第3番、小田急沿線花の寺四季めぐり第25番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第48番、関東十八檀林
37.天照山 蓮乗院(れんじょういん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-16-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第19番、相州二十一ヶ所霊場第11番
38.天照山 千手院(せんじゅいん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-12-8
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第20番
39.石井山 長勝寺(ちょうしょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-12-17
日蓮宗
御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
40.隨我山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市材木座2-9-5
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第14番
41.五所神社(ごしょじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市材木座2-9-1
御祭神:大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、材木座の氏神
42.弘延山 實相寺(じっそうじ)
鎌倉市Web
鎌倉市材木座4-3-13
日蓮宗
御本尊:一尊四士(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
43.南向山 帰命院 補陀落寺(ふだらくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番、新四国東国八十八ヶ所霊場第81番
44.内裏山 霊獄院 九品寺(くほんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座5-13-14
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第16番、相州二十一ヶ所霊場第9番、小田急沿線花の寺四季めぐり第18番
45.円龍山 向福寺(こうふくじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座3-15-13
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第15番
46.海潮山 妙長寺(みょうちょうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-7-41
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:
47.由比若宮(ゆいのわかみや)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇、神功皇后、比売神
旧社格:鶴岡八幡宮の元宮(元八幡)
48.帰命山 延命寺(えんめいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座1-1-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番
【 BGM 】
■ Look Who's Lonely Now - Bill Labounty
■ Emily - Dave Koz
■ I'll Be There - Jack Wagner
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)から
鎌倉市の南東側(県道311号葉山鎌倉線、国道134号線)から入るルートで、若宮大路東側の大町、小町一丁目・二丁目、材木座の寺社をご紹介します。
まずはリストです。
日蓮宗と浄土宗の寺院が多いエリアです。
20.妙法華経山 安国論寺(あんこくろんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町4-4-18
日蓮宗
御本尊:十界未曾有大曼荼羅と日蓮聖人像
札所:東国花の寺百ヶ寺霊場第95番
大町、材木座は、日蓮宗寺院の名刹が集中しています。
こちらも日蓮宗の名刹です。
寺伝によると、日蓮聖人が建長五年(1253年)に房総の清澄寺で立教開宗された後、鎌倉での布教を志され、松葉ヶ谷の岩窟に草庵を結ばれたのが当山の始まりです。
日蓮聖人はこの地で約20年を過ごされ、『立正安国論』もここで執筆されました。
重要な内容なので、公式Webからそのまま引用します。
「(日蓮聖人は)『立正安国論』を奏進したことにより権力者や他宗派の人々の怒りを買い、同年(文応元年(1260年))8月27日に焼き討ちに遭いました。此処の地名を取って『松葉ヶ谷の法難』と呼びます。このような縁起により 当山は『松葉ヶ谷霊跡 妙法華経山 安国論寺』といいます。昔は『安国論窟寺』とも言いました。『松葉ヶ谷の法難』だけでなく『伊豆流罪』の時も『龍口法難』の時もこの地で捕縛されました。その意味で、日蓮聖人のご生涯中でもとりわけ重要な場所と言えます。また、この地で多くの人が弟子となり信者となりました。教団としての日蓮宗の始まりの地とも言え、安国論寺はとても大切なお寺です。」
「日蓮聖人の代表的著作である『立正安国論』は、文応元年(1260年)7月16日に前執権北条時頼に奏進されました。(中略)『立正安国論』という題名から非常に難しい内容のように思われますが(中略)簡潔に言うと、法華経(妙法蓮華経)は苦難に満ちたこの世に生きる私達を救う最高の教えです。その教えを信仰し、落ち着いた平和な国を作りましょうというのがその主題です。この日蓮聖人の主張は仏教の本義に基づき、現実の世界にも照らし、また理性的論理的判断としても合理的なものですが その舌鋒の鋭さから 特に他の宗教の僧侶や信者から大変な怒りをかうことになりました。『立正安国論』は幕府に無視されたばかりか、これにより日蓮聖人は数多くの攻撃や迫害を受けることになります。しかしその後、本書の警告通りに他国侵逼難(外国からの侵略)・自界叛逆難(内乱)が実際に起きたことからその正しさが明らかとなり、一方で日蓮聖人を信仰する人々も増えてゆくことになります。日蓮聖人は 最期の門弟への講義でも取り上げるなど 生涯に亘って本書を重んじました。」
引用が長くなりましたが、このように日蓮宗においてたいへん重要な寺院です。
---------------------
県道311号鎌倉葉山線が逆川を渡る二俣を左手の道に入ります。
この分岐にはすでに安国論寺の寺号標がありました。
ここから安国論寺の前まではほぼまっすぐで、参道的な趣き。


【写真 上(左)】 県道沿いの寺号標
【写真 下(右)】 県道からの道行き
ここ大町四丁目あたりは鎌倉市街から山側の名越切り通しへののぼり口で、あたりは閑静な住宅街です。
ここには当寺と、日蓮宗の名刹、妙法寺があり、日蓮宗にとっては聖域的な場所ですが、観光客のすがたはあまり多くはありません。
駐車場はないので、車の場合、材木座寄りのコインパーキングに停めることになります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
参道は道からすぐに階段で、脇に「日蓮上人草庵跡」の石碑があります。
「建長五年(1913年)日蓮上人房州小湊ヨリ来リ此地ニ小庵ヲ営ミ初メテ法華経ノ首題ヲ唱ヘ正嘉元年(1917年)ヨリ文應元年(1920年)ニ及ビ巌窟内ニ籠リ立正安國一巻ヲ編述セシハ則チ此所ナリト云フ」
その先には「松葉谷根本霊場 安國論寺」の寺号標。


【写真 上(左)】 山門前
【写真 下(右)】 山門
さらに進むと山門。
切妻屋根桟瓦葺の唐様四脚門で、延享三年(1746年)尾張徳川家によって再建されたもの。
「安國法窟」の扁額は、元禄四年(1691年)佐々木文山の揮毫によるものです


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 境内案内
その先に拝観料納所と、その奥に庫裡。御首題・御朱印は参拝後にこちらでいただけます。


【写真 上(左)】 早春の参道
【写真 下(右)】 晩秋の参道
その先の参道は石畳で両側に竹垣が結われ、左手には重厚な石灯籠と、引き出された縁台には緋毛氈がひかれて趣きがあります。
背後を山に囲まれた風情のある山内で、秋の紅葉も見事です。


【写真 上(左)】 本堂前
【写真 下(右)】 本堂
参道正面の本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
正面格子扉の上には「立正安國」の扁額。
向拝軒から身舎まで四軒の垂木を並べ、名刹にふさわしい堂々たる構えです。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝-1


【写真 上(左)】 本堂向拝-2
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂向かって右手に進むと日朗聖人荼毘所。
当所で日蓮聖人に弟子入りした日朗聖人は本弟子六人の一人で、この地で荼毘に付して欲しいと御遺言されました。現在のお堂は昭和57年に建てられたものです。


【写真 上(左)】 日朗聖人荼毘所
【写真 下(右)】 日朗聖人荼毘所の扁額
本堂対面の熊王殿は、日蓮聖人に従った熊王丸が勧請した熊王大善神をお祀りするお堂で、厄除、眼病や歯痛などに霊験あらたかとされます。
切妻造ないし入母屋造の妻入りで、前面に大ふりな向拝が設えられています。
背後の岩盤に嵌め込むように建てられているので、間口の狭い妻入り様式なのかもしれません。
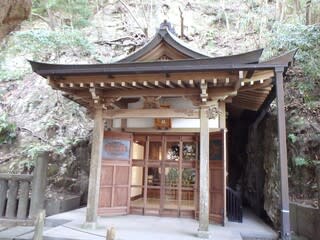

【写真 上(左)】 熊王殿
【写真 下(右)】 熊王殿扁額
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
正面硝子格子扉の上には「熊王殿」の扁額。


【写真 上(左)】 富士見台への階段
【写真 下(右)】 富士見台からの眺望
熊王殿脇の急な階段をのぼると富士見台。
鎌倉駅付近から由比ガ浜まで一望でき、晴れた日には富士山や伊豆大島も望めるそうです。
そのまま尾根伝いに行くと「立正安国の鐘」、さらに進むと南面窟で15分ほどの巡拝コースとなっています。
南面窟は、松葉ヶ谷法難の際に日蓮聖人が白猿に導かれて難を逃れ一夜を明かされたところといわれます。


【写真 上(左)】 本堂側からの御小庵
【写真 下(右)】 御小庵
熊王殿の奥には御小庵と御法窟がありますが、現在非公開となっています。
御小庵はその奥にある御法窟の拝殿で、御法窟は御小庵の奥にある岩屋です。
この御法窟がかつて日蓮聖人がお住まいになられた御草庵跡で、こちらで『立正安国論』も執筆されたと伝わります。


【写真 上(左)】 御小庵の見事な彫刻
【写真 下(右)】 御小庵の扁額
御小庵は宝形造で本瓦葺、本堂は桟瓦葺なので、御小庵の堂格の高さがうかがわれます。
江戸時代末期、尾張徳川家の寄進によるもので総欅造り、屋根の照りが効いた均整のとれたお堂です。
軒下向拝の水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
彫刻類はいずれも見事な仕上がりで、正面格子扉の上には「御小庵」の扁額が掲げられています。
当山は花の寺で、御小庵そばの樹齢760年ともいわれる山桜は「妙法桜」と呼ばれ、「日蓮上人が地面についた杖から根付いた」という伝説をもち鎌倉市天然記念物。
本堂手前左の山茶花も銘木として知られ、こちらも鎌倉市天然記念物に指定されています。
東国花の寺百ヶ寺霊場第95番の花種は「妙法桜」です。
こちらの御朱印は豪快な筆致で知られています。
御朱印は書置が用意されている模様ですが、御首題は御住職ご不在時はいただけないので、御首題拝受の際には事前TEL確認がベターかもしれません。
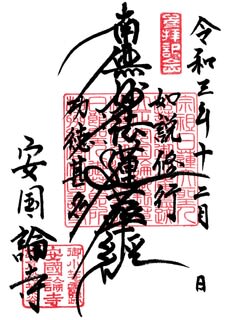
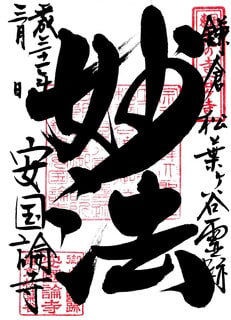
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 花の寺霊場の御朱印(御朱印帳書入)
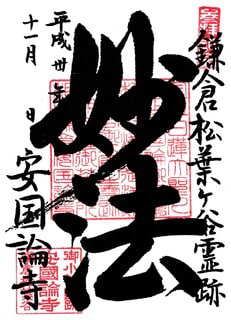
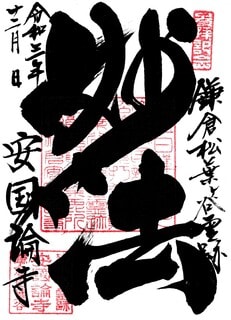
【写真 上(左)】 御朱印(平成30年11月)
【写真 下(右)】 御朱印(令和3年12月)
21.楞厳山 妙法寺(みょうほうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市Web
鎌倉市大町4-7-4
日蓮宗
御本尊:釈迦三尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
鎌倉市資料(市史、Webなど)によると、妙法寺は房総から布教のため鎌倉に入った日蓮聖人が最初に結ばれた草庵(松葉ヶ谷御小庵)の地とされています。
鎌倉の僧や武士により焼き打ちされた松葉ヶ谷法難も、この地であるという伝承があります。
この草庵跡に日蓮聖人が建てられた法華堂が本圀(國)寺で、本圀寺が室町時代に京都へ移されたあと、延文二年(1357年)日叡上人が父・大塔宮護良親王の菩提のために寺を再興したのが妙法寺の起こりといわれます。
「開山は日蓮と称し、中興開山を五世日叡とする。」(『鎌倉市史 社寺編』)
日蓮聖人は文永八年九月までこの地(御小庵)を布教伝道の拠点とされたと伝わります。
日叡上人は幼名を楞厳(りょうごん)丸といい、妙法房と称したのでこれを山号・寺号としたともいいます。
鎌倉市史には「塔頭として重善院、円蔵院、顕応坊、蓮乗坊、常縁坊など五院があって、南北朝から室町時代にかけては、なかなか盛んな寺であったことが想像できる。」とありますが、その後荒廃したと記されています。
しかし「十一代家斉が参拝し、明治三十年頃までお成の間があった。また現在の本堂は肥後の細川氏の建立」とあるので、江戸後期には相応の寺格を有していたものとみられます。
松葉ヶ谷(本國寺旧跡)は日蓮宗にとって大切な霊地ですが、その変遷については諸説あるようです。
『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「松葉ヶ谷 名越の内なり。長勝寺の境内を松葉ヶ谷と唱ふ。日蓮安房國小湊より当所へ渡りし時、三浦へ着岸し、夫より切通を経て此邊に庵室を結ひ給ひし地なり。後に京都へ移されし本國寺の舊跡の條を合せ見るへし。」
本國寺舊跡について、『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「本國寺舊跡 松葉が谷といふ。名越切通坂下、今の長勝寺の地なりといふ。安國寺も松葉の谷なり。最初日蓮居住の舊跡、貞和(1345-1350年)の初に本國寺を京都へ移さる。長勝寺、今は地名を石井と唱ふ。日蓮上人舊跡由緒を失ふにひとし。日蓮、松葉が谷本國寺を日朗へ与へ、日朗より日印・日靜と註し、日靜は貞和元年(1345年)の頃本國寺を京都へ移し、此所を日叡に授与せしむ。其後日叡本國寺を改め、妙法寺と号し、其後断絶せしを、再興の長勝寺と称する由。●京都へ移されし日靜といふは、尊氏将軍の御叔父なり。夫ゆへに、本國寺大伽藍建立せられ、大寺となれり。」
境内には美しい苔の石段があることから、「苔寺」とも呼ばれます。
鎌倉ゆかりの俳人・高浜虚子が俳句会を開いたとされ、虚子の次女・星野立子や門下の汾陽(かわみなみ)昌子などの句碑が残ります。
本堂向かって右手の仁王門の奥(奥の院エリア)には苔の階段、法華堂、松葉谷御小菴霊跡、伝・護良親王の御墓などの見どころがあります。
---------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 石標
安国論寺の参道前を右手に行く道が、妙法寺への参道です。
この分岐に台座に「松葉谷」と刻まれたお題目塔、寺号標、「高祖御小菴之本土」と刻まれた石標が建っています。
少し進むと右手に山側に向かう道、その正面が山門です。
このあたり、来訪者はさして多くはないようですが、鎌倉らしい寂びた雰囲気があります。


【写真 上(左)】 山門前
【写真 下(右)】 石標と山門
山門手前に「松葉谷御小菴霊跡」と刻まれた石碑。
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で通常閉門のようです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 受付から本堂方向
山門右手をすすむと、拝観料受付です。
現在の状況は不明ですが、2019年春時点(新型コロナ禍前)では夏期(7-8月)、冬期(12-3月)は奥の院の参拝は土・日・祭日のみ可能で、本堂までは通年お参りできました。
筆者は奥の院参拝可能日に参拝していないため、こちらについての写真やご案内はありません。
後日参拝したうえで加筆したいと思います。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺で前面に均整のとれた唐破風を起こしています。
水引虹梁両端に獅子・貘雲の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備には龍の彫刻、兎毛通の朱雀?の彫刻もなかなか見事なものです。
向拝正面桟唐戸のうえには山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 扁額
本堂は欅造りで、均整のとれた構えや彫刻類の精緻さからみても大名・細川氏の寄進を物語るものがあります。
御首題・御朱印は庫裡にて拝受しました。

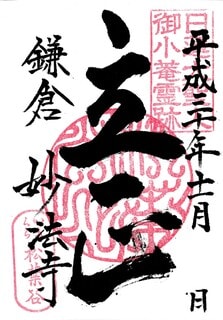
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
22.法華山 本興寺(ほんこうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町2-5-32
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
日蓮聖人の直弟子で「九老僧」の一人・天目上人が延元元年(1336年)に開創した寺で、日蓮聖人が辻説法の途中に休息されたことから、当所は休息山 本興寺と称していました。
その後二世日什上人(明徳三年(1392年)寂)により山号を法華山と改め、開基を天目上人、開山は日什上人とされています。
日蓮聖人の辻説法ゆかりの寺院であることから、通称「辻の本興寺」とも呼ばれています。
『新編相模國風土記稿』の本興寺の項に「辻町ニアリ。法華山と号ス。本寺前ニ同じ(妙本寺?)。古ハ京妙満寺の末ナリシガ。中興ノ後今ノ末トナルト云フ。本尊三寶祖師ヲ安セリ。開山ヲ日什(明徳三年(1392年)二月廿八寂ス)。中興ヲ日逞ト云フ。延寶三年(1675年)五月十七日寂ス。」とあります。
鎌倉市観光協会Webには「1660年に幕府により取り潰しに遭いましたが、1670年(寛文十年)本山妙本寺日逞上人により再建され現在に至ります。」とあります。
日蓮系の諸宗派は一致派と勝劣派、さらに不受不施派など教義により複雑に分派しますが、このような教義により寺歴を変遷した寺院と伝わります。
その経緯については、横浜市泉区にある日蓮宗の本山(由緒寺院)法華山 本興寺の公式Webに記載されているので、そちらをご覧ください。
---------------------


【写真 上(左)】 お題目塔
【写真 下(右)】 辻説法之舊地の碑
材木座海岸から雪ノ下に向かう小町大路がJR横須賀線の踏切を渡ったすぐ北側が参道入口。
参道入口に建つ「日蓮大聖人辻説法之舊地」の碑の文面はつぎのとおりです。
「本興寺縁起 日蓮大聖人鎌倉御弘通の当時 此の地点は若宮小路に至る辻なるにより今猶辻の本興寺と称す 御弟子天目上人聖躅を継いで又 此地に折伏説法あり 實に当山の開基なり 後年日什上人(顕本法華宗開祖)留錫せられ寺観大いに面目を改めむ 常楽日経上人も亦当寺の第廿七世なり」


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
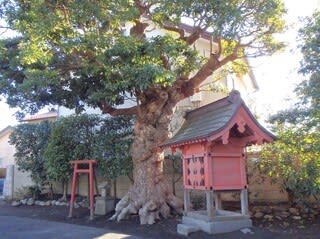

【写真 上(左)】 聖徳太子堂
【写真 下(右)】 本堂
小町大路から石敷の参道。その先の山門は切妻屋根桟瓦葺、朱塗りの丸柱の四脚門です。
山内はさほど広くはないものの、よく整備されています。
「百日紅」と「しだれ桜」の寺としても知られています。
朱塗りの一間社流造の堂宇は、聖徳太子堂とみられます。


【写真 上(左)】 飾り瓦
【写真 下(右)】 向拝
正面の本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
向拝屋根の先端にいは存在感ある獅子の飾り瓦。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を置いています。
御首題は庫裡にて拝受しました。
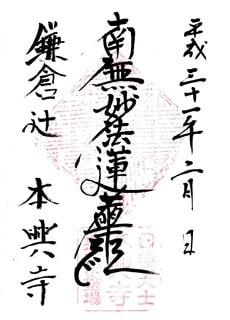
23.法久山 大前院 上行寺(じょうぎょうじ)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町2-8-17
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
鎌倉市資料によると、正和二年(1313年)日範上人の創建と伝わる日蓮宗の寺院です。
境内には御本尊の三宝祖師のほか、瘡守稲荷、鬼子母神が奉られています。
本堂左手には万延元年(1860年)に桜田門外で大老井伊直弼を襲撃した水戸浪士のひとり、広木松之助の墓があります。
『新編相模國風土記稿』の上行寺の項に「名越町ニアリ。法久山大前院ト号ス。本寺前ニ同じ(京都本國寺?)。正和二年(1313年)僧日範起立スト云フ。本尊宗法ノ諸尊及ヒ宗祖ノ像ヲ安ス。」
「稲荷社。瘡守稲荷ト号ス。正暦年中(990-995年)ノ勧請ト云伝フ。按スルニ。正暦ハ当寺起立ヨリ三百二十余年以前ナレバ。往昔ヨリ此所ニ在シ社ナルヤ。」とあります。
こちらは北条政子が源頼朝の「おでき」を治すために参拝したとも伝わり、そのゆかりからか癌封じのお寺として有名です。
山内には御利益が記された手書きの貼紙がたくさん貼られ、祈願寺の空気感。
現在の本堂は明治19年(1886年)に松葉ヶ谷の妙法寺の法華堂を移築したものといわれています。
こちらは、山内をあれこれご紹介する寺院ではないように思われますので、ご紹介はここまでです。
御首題、御朱印とも授与されていますが、御首題のみ拝受しています。
御首題授与にあたっては、ご親切な対応をいただきました。

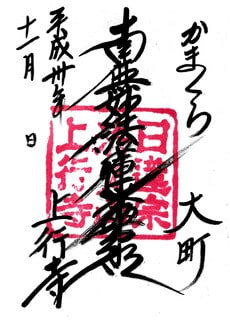
【写真 上(左)】 上行寺全景
【写真 下(右)】 御首題
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)へつづく。
【 BGM 】
■ Hero - David Crosby & Phil Collins
■ The Way It Is - Bruce Hornsby and the Range
■ All Of My Heart - ABC
■ If I Belive - Patti Austin
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
鎌倉市の南東側(県道311号葉山鎌倉線、国道134号線)から入るルートで、若宮大路東側の大町、小町一丁目・二丁目、材木座の寺社をご紹介します。
まずはリストです。
日蓮宗と浄土宗の寺院が多いエリアです。
20.妙法華経山 安国論寺(あんこくろんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町4-4-18
日蓮宗
御本尊:十界未曾有大曼荼羅と日蓮聖人像
札所:東国花の寺百ヶ寺霊場第95番
大町、材木座は、日蓮宗寺院の名刹が集中しています。
こちらも日蓮宗の名刹です。
寺伝によると、日蓮聖人が建長五年(1253年)に房総の清澄寺で立教開宗された後、鎌倉での布教を志され、松葉ヶ谷の岩窟に草庵を結ばれたのが当山の始まりです。
日蓮聖人はこの地で約20年を過ごされ、『立正安国論』もここで執筆されました。
重要な内容なので、公式Webからそのまま引用します。
「(日蓮聖人は)『立正安国論』を奏進したことにより権力者や他宗派の人々の怒りを買い、同年(文応元年(1260年))8月27日に焼き討ちに遭いました。此処の地名を取って『松葉ヶ谷の法難』と呼びます。このような縁起により 当山は『松葉ヶ谷霊跡 妙法華経山 安国論寺』といいます。昔は『安国論窟寺』とも言いました。『松葉ヶ谷の法難』だけでなく『伊豆流罪』の時も『龍口法難』の時もこの地で捕縛されました。その意味で、日蓮聖人のご生涯中でもとりわけ重要な場所と言えます。また、この地で多くの人が弟子となり信者となりました。教団としての日蓮宗の始まりの地とも言え、安国論寺はとても大切なお寺です。」
「日蓮聖人の代表的著作である『立正安国論』は、文応元年(1260年)7月16日に前執権北条時頼に奏進されました。(中略)『立正安国論』という題名から非常に難しい内容のように思われますが(中略)簡潔に言うと、法華経(妙法蓮華経)は苦難に満ちたこの世に生きる私達を救う最高の教えです。その教えを信仰し、落ち着いた平和な国を作りましょうというのがその主題です。この日蓮聖人の主張は仏教の本義に基づき、現実の世界にも照らし、また理性的論理的判断としても合理的なものですが その舌鋒の鋭さから 特に他の宗教の僧侶や信者から大変な怒りをかうことになりました。『立正安国論』は幕府に無視されたばかりか、これにより日蓮聖人は数多くの攻撃や迫害を受けることになります。しかしその後、本書の警告通りに他国侵逼難(外国からの侵略)・自界叛逆難(内乱)が実際に起きたことからその正しさが明らかとなり、一方で日蓮聖人を信仰する人々も増えてゆくことになります。日蓮聖人は 最期の門弟への講義でも取り上げるなど 生涯に亘って本書を重んじました。」
引用が長くなりましたが、このように日蓮宗においてたいへん重要な寺院です。
---------------------
県道311号鎌倉葉山線が逆川を渡る二俣を左手の道に入ります。
この分岐にはすでに安国論寺の寺号標がありました。
ここから安国論寺の前まではほぼまっすぐで、参道的な趣き。


【写真 上(左)】 県道沿いの寺号標
【写真 下(右)】 県道からの道行き
ここ大町四丁目あたりは鎌倉市街から山側の名越切り通しへののぼり口で、あたりは閑静な住宅街です。
ここには当寺と、日蓮宗の名刹、妙法寺があり、日蓮宗にとっては聖域的な場所ですが、観光客のすがたはあまり多くはありません。
駐車場はないので、車の場合、材木座寄りのコインパーキングに停めることになります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標
参道は道からすぐに階段で、脇に「日蓮上人草庵跡」の石碑があります。
「建長五年(1913年)日蓮上人房州小湊ヨリ来リ此地ニ小庵ヲ営ミ初メテ法華経ノ首題ヲ唱ヘ正嘉元年(1917年)ヨリ文應元年(1920年)ニ及ビ巌窟内ニ籠リ立正安國一巻ヲ編述セシハ則チ此所ナリト云フ」
その先には「松葉谷根本霊場 安國論寺」の寺号標。


【写真 上(左)】 山門前
【写真 下(右)】 山門
さらに進むと山門。
切妻屋根桟瓦葺の唐様四脚門で、延享三年(1746年)尾張徳川家によって再建されたもの。
「安國法窟」の扁額は、元禄四年(1691年)佐々木文山の揮毫によるものです


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 境内案内
その先に拝観料納所と、その奥に庫裡。御首題・御朱印は参拝後にこちらでいただけます。


【写真 上(左)】 早春の参道
【写真 下(右)】 晩秋の参道
その先の参道は石畳で両側に竹垣が結われ、左手には重厚な石灯籠と、引き出された縁台には緋毛氈がひかれて趣きがあります。
背後を山に囲まれた風情のある山内で、秋の紅葉も見事です。


【写真 上(左)】 本堂前
【写真 下(右)】 本堂
参道正面の本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
正面格子扉の上には「立正安國」の扁額。
向拝軒から身舎まで四軒の垂木を並べ、名刹にふさわしい堂々たる構えです。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝-1


【写真 上(左)】 本堂向拝-2
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂向かって右手に進むと日朗聖人荼毘所。
当所で日蓮聖人に弟子入りした日朗聖人は本弟子六人の一人で、この地で荼毘に付して欲しいと御遺言されました。現在のお堂は昭和57年に建てられたものです。


【写真 上(左)】 日朗聖人荼毘所
【写真 下(右)】 日朗聖人荼毘所の扁額
本堂対面の熊王殿は、日蓮聖人に従った熊王丸が勧請した熊王大善神をお祀りするお堂で、厄除、眼病や歯痛などに霊験あらたかとされます。
切妻造ないし入母屋造の妻入りで、前面に大ふりな向拝が設えられています。
背後の岩盤に嵌め込むように建てられているので、間口の狭い妻入り様式なのかもしれません。
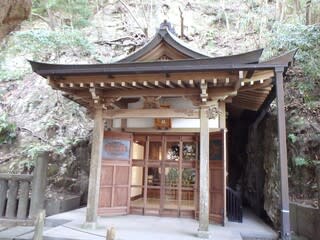

【写真 上(左)】 熊王殿
【写真 下(右)】 熊王殿扁額
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
正面硝子格子扉の上には「熊王殿」の扁額。


【写真 上(左)】 富士見台への階段
【写真 下(右)】 富士見台からの眺望
熊王殿脇の急な階段をのぼると富士見台。
鎌倉駅付近から由比ガ浜まで一望でき、晴れた日には富士山や伊豆大島も望めるそうです。
そのまま尾根伝いに行くと「立正安国の鐘」、さらに進むと南面窟で15分ほどの巡拝コースとなっています。
南面窟は、松葉ヶ谷法難の際に日蓮聖人が白猿に導かれて難を逃れ一夜を明かされたところといわれます。


【写真 上(左)】 本堂側からの御小庵
【写真 下(右)】 御小庵
熊王殿の奥には御小庵と御法窟がありますが、現在非公開となっています。
御小庵はその奥にある御法窟の拝殿で、御法窟は御小庵の奥にある岩屋です。
この御法窟がかつて日蓮聖人がお住まいになられた御草庵跡で、こちらで『立正安国論』も執筆されたと伝わります。


【写真 上(左)】 御小庵の見事な彫刻
【写真 下(右)】 御小庵の扁額
御小庵は宝形造で本瓦葺、本堂は桟瓦葺なので、御小庵の堂格の高さがうかがわれます。
江戸時代末期、尾張徳川家の寄進によるもので総欅造り、屋根の照りが効いた均整のとれたお堂です。
軒下向拝の水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
彫刻類はいずれも見事な仕上がりで、正面格子扉の上には「御小庵」の扁額が掲げられています。
当山は花の寺で、御小庵そばの樹齢760年ともいわれる山桜は「妙法桜」と呼ばれ、「日蓮上人が地面についた杖から根付いた」という伝説をもち鎌倉市天然記念物。
本堂手前左の山茶花も銘木として知られ、こちらも鎌倉市天然記念物に指定されています。
東国花の寺百ヶ寺霊場第95番の花種は「妙法桜」です。
こちらの御朱印は豪快な筆致で知られています。
御朱印は書置が用意されている模様ですが、御首題は御住職ご不在時はいただけないので、御首題拝受の際には事前TEL確認がベターかもしれません。
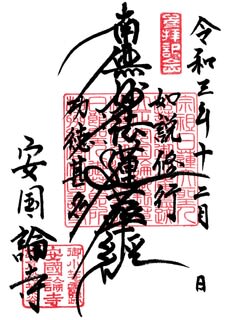
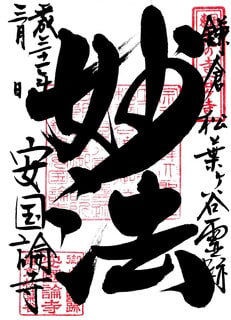
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 花の寺霊場の御朱印(御朱印帳書入)
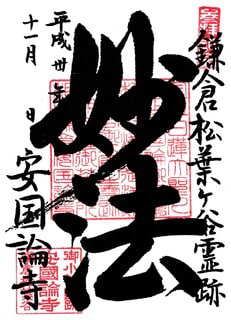
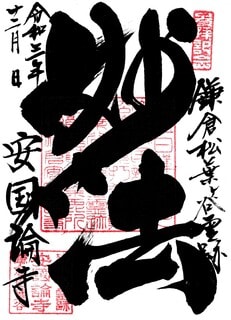
【写真 上(左)】 御朱印(平成30年11月)
【写真 下(右)】 御朱印(令和3年12月)
21.楞厳山 妙法寺(みょうほうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市Web
鎌倉市大町4-7-4
日蓮宗
御本尊:釈迦三尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
鎌倉市資料(市史、Webなど)によると、妙法寺は房総から布教のため鎌倉に入った日蓮聖人が最初に結ばれた草庵(松葉ヶ谷御小庵)の地とされています。
鎌倉の僧や武士により焼き打ちされた松葉ヶ谷法難も、この地であるという伝承があります。
この草庵跡に日蓮聖人が建てられた法華堂が本圀(國)寺で、本圀寺が室町時代に京都へ移されたあと、延文二年(1357年)日叡上人が父・大塔宮護良親王の菩提のために寺を再興したのが妙法寺の起こりといわれます。
「開山は日蓮と称し、中興開山を五世日叡とする。」(『鎌倉市史 社寺編』)
日蓮聖人は文永八年九月までこの地(御小庵)を布教伝道の拠点とされたと伝わります。
日叡上人は幼名を楞厳(りょうごん)丸といい、妙法房と称したのでこれを山号・寺号としたともいいます。
鎌倉市史には「塔頭として重善院、円蔵院、顕応坊、蓮乗坊、常縁坊など五院があって、南北朝から室町時代にかけては、なかなか盛んな寺であったことが想像できる。」とありますが、その後荒廃したと記されています。
しかし「十一代家斉が参拝し、明治三十年頃までお成の間があった。また現在の本堂は肥後の細川氏の建立」とあるので、江戸後期には相応の寺格を有していたものとみられます。
松葉ヶ谷(本國寺旧跡)は日蓮宗にとって大切な霊地ですが、その変遷については諸説あるようです。
『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「松葉ヶ谷 名越の内なり。長勝寺の境内を松葉ヶ谷と唱ふ。日蓮安房國小湊より当所へ渡りし時、三浦へ着岸し、夫より切通を経て此邊に庵室を結ひ給ひし地なり。後に京都へ移されし本國寺の舊跡の條を合せ見るへし。」
本國寺舊跡について、『鎌倉攬勝考』には以下のとおりあります。
「本國寺舊跡 松葉が谷といふ。名越切通坂下、今の長勝寺の地なりといふ。安國寺も松葉の谷なり。最初日蓮居住の舊跡、貞和(1345-1350年)の初に本國寺を京都へ移さる。長勝寺、今は地名を石井と唱ふ。日蓮上人舊跡由緒を失ふにひとし。日蓮、松葉が谷本國寺を日朗へ与へ、日朗より日印・日靜と註し、日靜は貞和元年(1345年)の頃本國寺を京都へ移し、此所を日叡に授与せしむ。其後日叡本國寺を改め、妙法寺と号し、其後断絶せしを、再興の長勝寺と称する由。●京都へ移されし日靜といふは、尊氏将軍の御叔父なり。夫ゆへに、本國寺大伽藍建立せられ、大寺となれり。」
境内には美しい苔の石段があることから、「苔寺」とも呼ばれます。
鎌倉ゆかりの俳人・高浜虚子が俳句会を開いたとされ、虚子の次女・星野立子や門下の汾陽(かわみなみ)昌子などの句碑が残ります。
本堂向かって右手の仁王門の奥(奥の院エリア)には苔の階段、法華堂、松葉谷御小菴霊跡、伝・護良親王の御墓などの見どころがあります。
---------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 石標
安国論寺の参道前を右手に行く道が、妙法寺への参道です。
この分岐に台座に「松葉谷」と刻まれたお題目塔、寺号標、「高祖御小菴之本土」と刻まれた石標が建っています。
少し進むと右手に山側に向かう道、その正面が山門です。
このあたり、来訪者はさして多くはないようですが、鎌倉らしい寂びた雰囲気があります。


【写真 上(左)】 山門前
【写真 下(右)】 石標と山門
山門手前に「松葉谷御小菴霊跡」と刻まれた石碑。
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で通常閉門のようです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 受付から本堂方向
山門右手をすすむと、拝観料受付です。
現在の状況は不明ですが、2019年春時点(新型コロナ禍前)では夏期(7-8月)、冬期(12-3月)は奥の院の参拝は土・日・祭日のみ可能で、本堂までは通年お参りできました。
筆者は奥の院参拝可能日に参拝していないため、こちらについての写真やご案内はありません。
後日参拝したうえで加筆したいと思います。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺で前面に均整のとれた唐破風を起こしています。
水引虹梁両端に獅子・貘雲の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備には龍の彫刻、兎毛通の朱雀?の彫刻もなかなか見事なものです。
向拝正面桟唐戸のうえには山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 扁額
本堂は欅造りで、均整のとれた構えや彫刻類の精緻さからみても大名・細川氏の寄進を物語るものがあります。
御首題・御朱印は庫裡にて拝受しました。

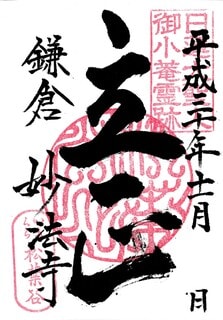
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
22.法華山 本興寺(ほんこうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町2-5-32
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
日蓮聖人の直弟子で「九老僧」の一人・天目上人が延元元年(1336年)に開創した寺で、日蓮聖人が辻説法の途中に休息されたことから、当所は休息山 本興寺と称していました。
その後二世日什上人(明徳三年(1392年)寂)により山号を法華山と改め、開基を天目上人、開山は日什上人とされています。
日蓮聖人の辻説法ゆかりの寺院であることから、通称「辻の本興寺」とも呼ばれています。
『新編相模國風土記稿』の本興寺の項に「辻町ニアリ。法華山と号ス。本寺前ニ同じ(妙本寺?)。古ハ京妙満寺の末ナリシガ。中興ノ後今ノ末トナルト云フ。本尊三寶祖師ヲ安セリ。開山ヲ日什(明徳三年(1392年)二月廿八寂ス)。中興ヲ日逞ト云フ。延寶三年(1675年)五月十七日寂ス。」とあります。
鎌倉市観光協会Webには「1660年に幕府により取り潰しに遭いましたが、1670年(寛文十年)本山妙本寺日逞上人により再建され現在に至ります。」とあります。
日蓮系の諸宗派は一致派と勝劣派、さらに不受不施派など教義により複雑に分派しますが、このような教義により寺歴を変遷した寺院と伝わります。
その経緯については、横浜市泉区にある日蓮宗の本山(由緒寺院)法華山 本興寺の公式Webに記載されているので、そちらをご覧ください。
---------------------


【写真 上(左)】 お題目塔
【写真 下(右)】 辻説法之舊地の碑
材木座海岸から雪ノ下に向かう小町大路がJR横須賀線の踏切を渡ったすぐ北側が参道入口。
参道入口に建つ「日蓮大聖人辻説法之舊地」の碑の文面はつぎのとおりです。
「本興寺縁起 日蓮大聖人鎌倉御弘通の当時 此の地点は若宮小路に至る辻なるにより今猶辻の本興寺と称す 御弟子天目上人聖躅を継いで又 此地に折伏説法あり 實に当山の開基なり 後年日什上人(顕本法華宗開祖)留錫せられ寺観大いに面目を改めむ 常楽日経上人も亦当寺の第廿七世なり」


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
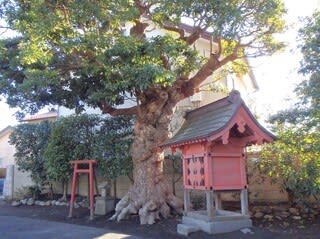

【写真 上(左)】 聖徳太子堂
【写真 下(右)】 本堂
小町大路から石敷の参道。その先の山門は切妻屋根桟瓦葺、朱塗りの丸柱の四脚門です。
山内はさほど広くはないものの、よく整備されています。
「百日紅」と「しだれ桜」の寺としても知られています。
朱塗りの一間社流造の堂宇は、聖徳太子堂とみられます。


【写真 上(左)】 飾り瓦
【写真 下(右)】 向拝
正面の本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
向拝屋根の先端にいは存在感ある獅子の飾り瓦。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を置いています。
御首題は庫裡にて拝受しました。
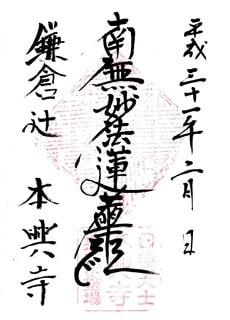
23.法久山 大前院 上行寺(じょうぎょうじ)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町2-8-17
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
鎌倉市資料によると、正和二年(1313年)日範上人の創建と伝わる日蓮宗の寺院です。
境内には御本尊の三宝祖師のほか、瘡守稲荷、鬼子母神が奉られています。
本堂左手には万延元年(1860年)に桜田門外で大老井伊直弼を襲撃した水戸浪士のひとり、広木松之助の墓があります。
『新編相模國風土記稿』の上行寺の項に「名越町ニアリ。法久山大前院ト号ス。本寺前ニ同じ(京都本國寺?)。正和二年(1313年)僧日範起立スト云フ。本尊宗法ノ諸尊及ヒ宗祖ノ像ヲ安ス。」
「稲荷社。瘡守稲荷ト号ス。正暦年中(990-995年)ノ勧請ト云伝フ。按スルニ。正暦ハ当寺起立ヨリ三百二十余年以前ナレバ。往昔ヨリ此所ニ在シ社ナルヤ。」とあります。
こちらは北条政子が源頼朝の「おでき」を治すために参拝したとも伝わり、そのゆかりからか癌封じのお寺として有名です。
山内には御利益が記された手書きの貼紙がたくさん貼られ、祈願寺の空気感。
現在の本堂は明治19年(1886年)に松葉ヶ谷の妙法寺の法華堂を移築したものといわれています。
こちらは、山内をあれこれご紹介する寺院ではないように思われますので、ご紹介はここまでです。
御首題、御朱印とも授与されていますが、御首題のみ拝受しています。
御首題授与にあたっては、ご親切な対応をいただきました。

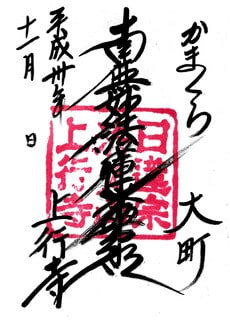
【写真 上(左)】 上行寺全景
【写真 下(右)】 御首題
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)へつづく。
【 BGM 】
■ Hero - David Crosby & Phil Collins
■ The Way It Is - Bruce Hornsby and the Range
■ All Of My Heart - ABC
■ If I Belive - Patti Austin
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ (新?)第35番 天城山 慈眼院(じげんいん)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
賀茂郡河津町梨本28-1
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:温泉施設「禅の湯」内
※今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から慈眼院に変更されたようです。
慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますのでUPします。
伊豆88遍路の紹介ページには「安政4年(1857年)初代駐日総領事タウンゼント・ハリスが、日米修好通商条約締結のため江戸へ赴く途中で一泊したお寺。ハリスが使用した曲録(椅子)が残っています。」とありますが、情報の少ないお寺さまです。
『豆州志稿』に「梨本村 曹洞宗 逆川普門院末 本尊観世音 舊真言宗慈眼庵ト称シテ天城山中ニ在リキ 慶安(1648-1652年)中此地ニ移シ 普門院雲國和尚ヲ開山祖トス 是時ヨリ院号ト為ス」とありますので、少なくとも江戸時代には創立しているようです。
伊豆山中に真言宗の庵として草創、慶安(1648-1652年)年間に現在地に遷り普門院雲國和尚を開山祖として庵を院に改めています。
「寺社Nowオンライン」の記事によると、もともと檀家がすくなく寺院経営がきびしかったため、境内にユースホステルを起業、温泉を掘削して温泉施設「禅の湯」としてリニューアルオープンしたとのこと。
-------------------
国道414号天城街道が天城峠から七滝ループ橋を経て下ってきたところ、温泉地としても知られる梨本エリアにあります。
国道に面し、お寺というより温泉施設「禅の湯」が前面に出ています。


【写真 上(左)】 サイン
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 石仏群
国道に面した山門は切妻屋根銅板葺の四脚門。
正面の本堂は寄棟造桟瓦葺で大棟に「慈眼院」の院号を掲げています。
向拝柱はなく、向拝扉と両側に花頭窓。
本堂内は禅刹らしいすっきりとしたつくりで、正面見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 龍の天井絵
御朱印は「禅の湯」のフロントで授与されています。
御朱印は御本尊・聖観世音菩薩、弘法大師、ほうそうばあさん、龍(両面)の4種類。
いずれも御朱印帳への印判でした。
非札所の曹洞宗寺院で弘法大師の御朱印はめずらしいですが、こちらはもともと真言宗でお大師さまとゆかりがあるとの由。
このたびの伊豆八十八ヶ所霊場への参画で、ゆかりがより深まったとみるべきでしょうか。
龍の御朱印は、本堂の豪快な天井絵にちなむもの。
「ほうそうばあさん」は、疱瘡神(疱瘡を患うことがないよう祈念する神様)です。

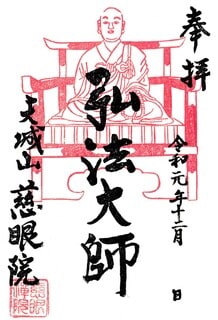
【写真 上(左)】 御本尊・聖観世音菩薩の御朱印
【写真 下(右)】 弘法大師の御朱印

■ ほうそうばあさんの御朱印
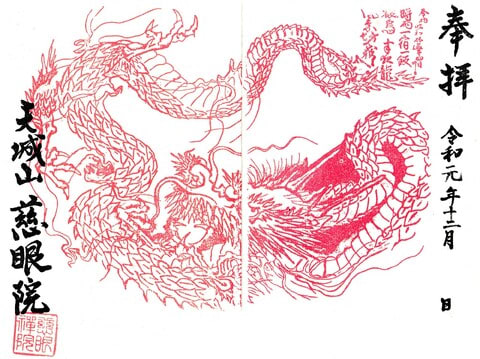
■ 龍の御朱印
-------------------
こちらは、以前に日帰り入浴していますが、横着なのでまだレポをあげていません (~~;
近いうちにUPしたいと思います。
こちらは自家源泉で、平成17年春に温泉分析しています。
源泉名は梨本17号、泉温47.0℃、pH=9.0(アルカリ性泉)、湧出量169L/min、成分総計=1.383g/kgのカルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉。
なかなかの良泉を非加水・非加温・非消毒でかけ流し利用しています。
「禅の湯」はロハス系のあかるいイメージの宿泊施設で、日帰り入浴も受け付けています。
座禅やリトリート体験もできるようです。
■ 第36番 長運山 乗安寺(じょうあんじ)
河津町観光協会
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町谷津413
日蓮宗
御本尊:十界曼荼羅
札所本尊:
他札所:-
授与所:庫裡
伊豆半島には、中伊豆、伊東などを中心に日蓮宗寺院がかなりありますが、伊豆八十八ヶ所霊場は禅刹がメインで日蓮宗の札所は1ヶ所しかありません。
こちらはその貴重な日蓮宗の札所寺院です。
『こころの旅』『霊場めぐり』によると、慶長年間(1596-1615年)縄地金山採掘の際、縄地に身延山久遠寺廿二世日遠上人を開山に創立、のちに現在地に移されたといいます。
開山日遠上人が法輪のため駿府城に赴いた際、家康公の怒りにふれ安倍川の河原で斬罪に処せられるところ、側室お万の方が上人を自らの女駕籠に乗せてこの地へ逃したという伝承があります。
当山には、そのときの女乗物駕籠が保存されています。
この事件のいきさつについては、Wikipediaの「養珠院」のページにまとめられているので、以下に引用させていただきます。
-----------------------(引用はじめ)
(養珠院(お万の方)の)義父の蔭山家は代々日蓮宗を信仰しており、万もその影響を受けて日遠に帰依した。家康は浄土宗であり、日頃から宗論を挑む日遠を不快に思っていたため、慶長13年(1608年)11月15日、江戸城での問答の直前に日蓮宗側の論者を家臣に襲わせた結果、日蓮宗側は半死半生の状態となり、浄土宗側を勝利させた。この不法な家康のやり方に怒った日遠は身延山法主を辞し、家康が禁止した宗論を上申した。これに激怒した家康は、日遠を捕まえて駿府の安倍川原で磔にしようとしたため、万は家康に日遠の助命嘆願をするが、家康は聞き入れなかった。すると万は「師の日遠が死ぬ時は自分も死ぬ」と、日遠と自分の2枚の死に衣を縫う。これには家康も驚いて日遠を放免した
-----------------------(引用おわり)
家康公は日蓮宗に対して総じて厳しい態度をとり、幾度も関係者に対論させたといわれています。
この事件も上記のとおり宗論が絡んでいるといわれますが、かなりデリケートな内容も含むのでここではこれ以上とりあげません。
いずれにしても、身延山久遠寺廿二世日遠上人の開山という由緒ある日蓮宗寺院であることはまちがいなさそうです。
上記のとおりお万の方は熱心な日蓮宗の信者で、三島の日蓮宗の名刹、経王山 妙法華寺ともふかいゆかりをもちます。
『豆州志稿』には「谷津村 日蓮宗 甲州身延山久遠寺末 本尊十界曼荼羅 慶長中(1596-1615年)創立 久遠寺廿二世日遠ヲ開山トス(中略)縄地ニ黄金出シ時(慶長中金鉱開掘)新ニ建タテルカ事罷テ此ニ移ス」とあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御題目碑
河津川が河津浜に注ぐ河口そばの右岸にあります。
「河津の足湯処・ほっとステーション」のちょうど山側です。
山内入口に御題目碑と「元祖日蓮大士」の石碑。
そのすぐ先に山を背負って本堂。
右手の山腹に朱塗りのお堂がありますが、何のお堂かきき忘れました。


【写真 上(左)】 朱塗りのお堂
【写真 下(右)】 本堂
-------------------
2015年落慶の真新しい本堂は、寄棟造銅板葺で向拝柱のないシンプルなつくり。
向拝サッシュ扉のうえに寺号扁額を掲げています。
庫裡にお声掛けすると本堂を開けていただけ、本堂内にも寺号扁額が懸けられていました。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
「こころの旅」を読んだうえで参拝しているので、当然「女乗物駕籠」の認識はあったはずですが、このときはなぜか「女乗物駕籠」の一部しか撮影しておりません。


【写真 上(左)】 堂内扁額
【写真 下(右)】 女駕籠(一部)
別のものを撮った写真に「女乗物駕籠」の説明書きも写っていました。
写角が悪く不明瞭ですが、読み取れる範囲で書き起こしてみます。
「徳川家康の側室、お万の方(養珠院)は生涯の師と仰ぐ日遠上人を『駿府の法難』からお救い致しました。そして処刑は免れたものの他宗の迫害を恐れたお万の方は上人ゆかりの地、河津へ愛用の『女駕籠』を使い乗安寺へかくまわれました。」
本堂設備工事の施工企業「㈱宮崎商会」様のWebに「お万の方の駕籠がある乗安寺本堂改築完成!!」という記事があり、改装前の本堂、「女駕籠」や新本堂の落慶法要などの写真がばっちり載っていますのでそちらをご覧ください。
この記事にはお万の方と河津とのゆかりを示す貴重な情報も載っていますので、以下に引用させていただきます。
-----------------------(引用はじめ)
「お万の方は天正3年(1575年)、上総勝浦城(千葉県勝浦市)の城主正木時忠の五男頼忠を実父に、北条氏隆の娘である智光院を母に、小田原に生まれている。その後すぐ、時忠が亡くなり、頼忠が後を継ぐため妻子を残し勝浦城に戻った。智光院は伊豆河津郷に移り、北条家臣の河津城主の蔭山長門守氏広と再婚、お万の方はこの養父蔭山氏広に育てられている。天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅び、その後慶長3年(1598年)父である氏広が死去、この頃から深く仏門に帰依し、日蓮宗、身延山の上人を信ずるようになる。その後徳川家康の側室となった。」
-----------------------(引用おわり)
この記事によると、お万の方の母・智光院は北条家臣の河津城主・蔭山長門守氏広と再婚し、お万の方は養父蔭山氏広に育てられたとの由。
とすると、お万の方は河津の地で育ったことになり、仏法の師、日遠上人の危機に際して第二の故郷の河津にかくまわれた、というのはわかりやすい流れです。
御首題は、たしか本堂向かって左手の庫裡にていただきました。
御首題帳にいただきましたが、御朱印帳でも拝受できるかは不明です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 御首題

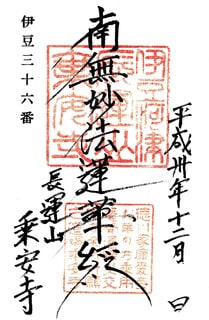
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御首題帳
■ 第37番 玉田山 地福院(じふくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町縄地430
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:第38番禅福寺庫裡
平安時代の創立ともいわれ、かつては玉田山金生院という真言宗寺院でしたが、慶長五年(1600年)に曹洞宗に改め再興。
縄地金山が栄えた際に、近隣に創立された9つの寺院のうちの一ヶ寺で、金山衰退後に他の8つの寺院は移転ないし廃寺となりましたが、地福院だけはこの地に残ったとの由。
『豆州志稿』には「縄地村 曹洞宗 武州金澤禅林寺末 本尊大日 初真言ニシテ金生院と称ス 後中絶ス 慶長五年(1600年)禅林寺二世天随再興改宗シテ地福院ト号ス」とあります。
せっかくなので縄地金山について調べてみようと思いましたが、廃墟系・探索系サイトはたくさんヒットするものの、公的な資料がほとんどみつかりません。
関心を惹きやすい閉鉱金山で、現在、民間所有なので自治体としてもとり上げにくいようです。
静岡県立中央図書館のWeb開示資料がヒットしたので抜粋引用します。
「縄地金山(河津町)は1598年(慶長三年)から採掘が始まったとされる。『佐渡年代記』1601年(同六年)大久保長安が伊豆・石見・佐渡銀山の支配を命じられたことが記され、1606年(同十一年)、伊豆金山奉行となったことから最盛を極めた。(中略)大久保長安は1607年(同十二年)に河津町の縄地神社に鰐口を奉納して(中略)鉱山の隆盛と安全を祈願した。」
また、『霊場めぐり』にも関連記事がありました。出典は『伊豆伝説集』からとみられ、貴重な内容なので抜粋引用します。
「縄地は南伊豆第一の金山であった。慶長十年(1605年)大久保岩見守長安が金山奉行として此地に来て採掘を続けた。最盛期には戸数8,000を算した。劇場もあり、相撲場もあり、遊女御免。長安は金山奉行として巨万を積んだ。その不正贓罪は死後にあばかれ、一族は処刑され、不正に連座した坑夫は磔刑に処せられた。岩見守の邸跡は寺坂にある。縄地の子安神社、山神社に長安奉納の金の鍔が残っていた。最大なのは重さ約7貫匁(26kg)黄金を含んでいて、音響が極めてよかったといわれたが、賊に奪われて今はない。」
伊豆の金山について、『伊豆志稿』には「黄金 白銀 天正●●頃ヨリ土肥村 黄金初メテ出テ 湯ガ島 縄地 瓜生野 修善寺等相継デホリ出シ 夥シキ●● 就中縄地ヨリ出シハ又特ニ多シ 大抵五十余年ニテ止ム 慶長十年(1610年)ノ頃ヨリ盛ニ出テ其ノ数大形佐渡ヨリ出ルガ如● 程ナク出ル●多カラズ トルノヲ止メラルト」とあり、伊豆の金山、ことに縄地は慶長の頃には佐渡にも劣らないほどの産金があったものの、ほどなく産金量が激減したことが記されています。
一時期とはいえこれだけ栄え、過酷な鉱山労働もあいまって村内に9つもの寺院が成立したのかも。
『豆州志稿』には縄地村からの移転寺院として(廃)金生山富来寺、(廃)栄寶院(当山派)、西光寺などがみられ、第36番乗安寺、第41番海善寺も縄地からの移転とあるので旧・縄地九箇寺かもしれません。
なお、大久保長安は数奇な運命をたどった武将で、逸話が山ほどあるので興味のある方は→こちら(Wikipedia)をご覧くださいませ。
-------------------

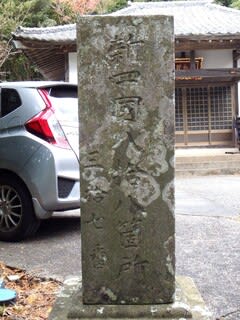
【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 札所標
国道135号線、縄地トンネルのすぐ西から北へ向かう細い道を上がったところ。
石垣が積まれた参道。本堂手前に伊豆八十八ヶ所の札所標。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺流れ向拝。向かって右手に庫裡らしき建物がせり出し、ちょっと面白い構成です。
水引虹梁は木鼻の抜けがなく、身舎側の繋ぎ虹梁と併せて向拝上にスクエアを構成。
向拝正面サッシュ扉のうえに院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
山内掲示によると、御本尊の金剛界大日如来像は銅製で室町時代後期以降。
吉祥天女像は桧一本造りで平安中期。こちらはかつて縄地尾ヶ崎の小堂に薬師如来として祀られていたお像とのこと。
こちらは無住で、御朱印は第38番禅福寺でいただきました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来
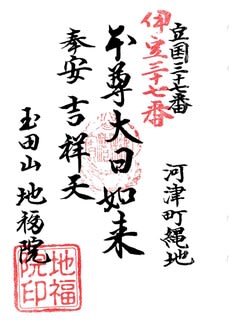

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第38番 興國山 禅福寺(ぜんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市白浜351
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
司元別当:伊古奈比咩命神社・白濱神社(下田市白浜)
他札所:-
授与所:庫裡
ここから巡路は下田市内に入ります。
下田は東・西廻海運の風待ち湊として栄え、江戸時代初期には天領となり下田奉行ないし浦賀奉行所支配下にあって独自の文化圏を築いたところです。
下田に陸路で入るルートは中伊豆からの天城越えがメインで、東海岸ルートは相当の難路であったと思われます。
これだけの観光資源をもちながら、伊豆急が下田まで開通したのはなんと昭和36年(1961年)。
東伊豆海岸沿いを走る国道135号も当初は険しい海沿いを走ることができずに山側をたどり、のちに海側につけられた国道は災害等で廃道になっている箇所があります。
この海岸の異様な険しさについては、ヨッキれん氏の壮絶なレポで実感してみてください。
江戸時代の東伊豆の陸路はかように難路で、域外、ことに江戸方面へのメインルートは海路でした。
じっさい下田市のWeb資料「下田の歴史年表」の多くは、水軍、船改め番所、御台場など海運施設の記述に費やされています。
なお、伊豆の海運については「海の東海道」((社)静岡県建築士会)というよくまとまったWeb記事があります。
陸路が厳しく海上交通が盛んであれば、その土地は海運関係者で繁昌し、南伊豆の物産の集散地となった筈です。
その繁栄ぶりは、「下田節」(下田市Web資料)の「伊豆の下田に長居はおよし、縞の財布が軽くなる」からも容易に想像できます。
■ 下田節(静岡県民謡)~峰村利子
伊豆八十八ヶ所の札所が、いまでは交通便利な東伊豆に少なく、南伊豆に集中しているのは不思議な感じもしますが、背景にはこのような事情があったかもしれません。
禅福寺について、『豆州志稿』には「白濱村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 昔禅教庵ト云 寛永中(1624-1644年)大室和尚寺号ト為ス」とあります。
(山号が「奥谷山」となっています。)
当初は観世音菩薩を奉安する真言宗の小庵で、貞和年間(1345-1350年)以来衰えましたが、 永正(1504-1521年)のころ相州香雲寺開山の霊叟禅師が入られて曹洞宗となり「禅居庵(または禅教院)」と号し、元和八年(1622年)に香雲寺9世宗樹ないし、寛永中(1624-1644年)に大室和尚が伽藍を整え「禅福寺」と号を改めたと伝わります。
禅福寺は、かつて伊豆最古の神社とされる伊古奈比咩命神社(白濱神社)の別当をつとめたともいわれます。
名社、伊古奈比咩命神社について書き始めると膨大な量になりそうなので、以前温泉レポ「下賀茂温泉 「伊古奈」【閉館】」でまとめた文章をそのまま持ってきます。
白濱(浜)神社は正式名を伊古奈比咩命神社といい、公式Webによると、御祭神は伊古奈比咩命、三嶋大明神、見目、若宮、剣の御子の5柱です。
当社の御由緒には「三嶋大明神は、その昔遥か南方より黒潮に乗り、この伊豆に到着されました。(中略)伊豆の南に定住していた賀茂族の姫神(伊古奈比咩命)様を后として迎え、白浜という所に宮を造り住まわれました。」とあります。
また、御祭神の説明には以下のとおりあります。
「主神 伊古奈比咩命(いこなひめのみこと) 女性神 三嶋大明神の最愛の后神で縁結びと子育ての神様です。」
「相殿 三嶋大明神 男性神 事代主命(ことしろぬしのみこと)であると言われています。大国主命の御子神様にあたり、大国主命を大国(だいこく)さんを呼ぶのに対して、事代主命は恵比寿さんと呼ばれています。商業と漁業の神様です。」
御鎮座は六代孝安天皇元年(約2400年前)と伝わり、『日本後紀 巻下(六国史.巻6)』(国立国会図書館DC)の淳和天皇天長九年(832年)5月22日の條に「伊豆國言上、三島神、伊古奈比咩神、二前預名神」とあります。
公式Webには「御土御門天皇文亀元年(1501年)には、三島神、伊古奈比咩神共、正一位という高い位を受けています。そして延喜式には三島神社、伊古奈比咩命神社が、二社共この白浜に鎮座していた事が書かれていて、その社格は三島神社が官幣大社、伊古奈比咩命神社が国幣大社となっています。」とあります。
以上より、伊古奈比咩命神社(白濱神社)が伊豆有数の古い歴史をもち、高い社格をもたれることがわかります。

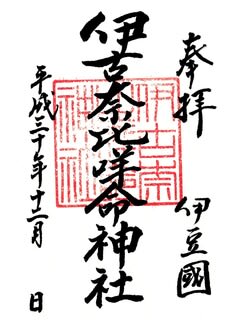
【写真 上(左)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)
【写真 下(右)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)の御朱印
-------------------


【写真 上(左)】 参道の石段
【写真 下(右)】 門柱
白浜漁港の山側、路地奥に階段参道。
門柱のむこう正面が本堂で、入母屋造銅板葺流れ向拝。向拝部に端正な軒唐破風を起こしています。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股の構成ですが、全体にすっきりとしたイメージ。
向拝正面サッシュ扉のうえに山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて、第37番地福院とともに拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来
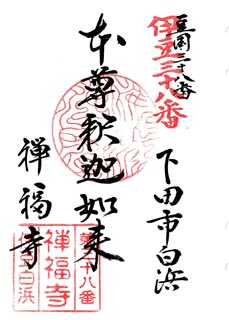

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 下賀茂温泉 「伊古奈」【閉館】の入湯レポ
■ 第39番 西向山 観音寺(かんのんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市須崎615
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第21番、第22番
授与所:庫裡
下田市の南東、須崎半島にあり、運慶作と伝わる十一面観世音菩薩像を御本尊として奉安する禅刹です。
『豆州志稿』には「須崎村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊観世音 舊暘谷院トテ真言宗ナリ 寛永(1624-1644年)ノ頃大室和尚宗及寺号ヲ改ム 初同村字川上ニ在リ 大室ノ時現地ニ移ス」とあります。
開創年代は不明。当初は真言宗で須崎川上にあり、暘谷院と号しました。
元和元年(1615年)(寛永年間とも)、相州秦野香雲寺九世・大室宗樹が曹洞宗に改宗し、現寺号に改めました。
延享四年(1747年)、火災に遭い現在地に移転と伝わります。
こちらは伊豆横道三十三観音霊場第21番、第22番の札所を兼ねています。
伊豆横道三十三観音霊場は、伊豆に流されていた源頼朝公と高雄山神護寺の僧・文覚により源氏再興を祈念して開創とされる、すこぶる古い観音霊場です。
発願の西伊豆町の延命寺(滝見観音堂)から松崎、下田、河津と廻り、結願は南伊豆町伊浜の普照寺です。
無住のお堂も多いですが、すべて巡拝でき御朱印も揃います。
筆者は結願していますので、後日あらためてご紹介したいと思います。
(本編でもとりあえず御朱印は掲載します。)
一部で伊豆八十八ヶ所と札所が重複しますが、河津町の札所は重複がないので、順打ちでくるとこちらが初めての重複札所となります
観音寺は第21番。末寺の第22番補陀庵も現在観音寺に遷られているので2札所となります。
-------------------
須崎半島は南伊豆でも早くから拓けた地で、須崎港は下田の玄関口のひとつでした。
爪木崎や恵比寿島などの観光地はあるものの、水仙の時季以外は訪れる観光客は少なそうです。
筆者も子供のころから伊豆にはよく行きましたが、須崎半島に足を踏み入れたのは今回が初めてです。


【写真 上(左)】 (たぶん)須崎漁港
【写真 下(右)】 参道入口
観音寺はこの須崎半島の南端、須崎漁港の山側、海抜約15mの高台にあります。
あたりは港町の趣きゆたか。それだけに狭い路地が入り組み車の運転は難儀します。
観音寺の門前まで車道は通じていますが、すこぶる狭く駐車場もないようなので車参拝は要注意。
お寺さまに駐車場所を事前TEL確認がベターかと思います。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山内からの海
【写真 下(右)】 山内
参道は石段で、石段右手に札所標。その先に切妻屋根桟瓦葺の端正な四脚門を構えています。
山門正面が本堂。寄棟造銅板で、向拝柱のないシンプルな堂容です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂向かって右手奥の庫裡で御朱印をお願いすると、本堂にあげていただけました。
五色幕が張り巡らされた本堂内は観音霊場らしい華やぎがあります。


【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 本堂内扁額
向拝見上げに「圓通閣」の扁額。
御本尊は運慶作と伝わる十一面観世音菩薩像で、伊豆八十八ヶ所と伊豆横道三十三観音霊場第21番の札所本尊ですが秘仏かもしれません。
山内掲示によると、伊豆横道三十三観音霊場第22番の札所本尊は、本堂ご内陣正面向かって右の厨子内に安置される秘仏の聖観世音菩薩像で、市の指定文化財です。
こちらはかつて小白浜の観音山上にあった補陀庵という末寺の御本尊で、そこから遷られたもの。
檜材一本造りの立像で行基作ともいわれますが、市のWeb資料には「平安後期の作と考えられる」とあります。
山内掲示には「平安後期の作とも伝わるが、和様化の進んだ像容から十一世紀頃の作と推定される。」とありました。
本堂御内陣向かって左の厨子内の薬師如来坐像は檜材一本造りで、制作年代は10世紀末から11世紀初頭に遡ると考えられ、こちらも市の指定文化財です。


【写真 上(左)】 石佛群
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場第21番の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩

〔 伊豆横道三十三観音霊場第22番(補陀庵)の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩
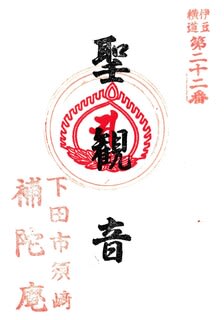
■ 第40番 瑞龍山 玉泉寺(ぎょくせんじ)
公式Web
下田市観光ガイド
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市柿崎31-6
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
伊豆八十八ヶ所の札所は伊東を過ぎると札所色が強まり、観光客のすがたはまばらですが、こちらは下田の観光名所として人気があります。
寺伝(公式Web、『こころの旅』『霊場めぐり』)によると、もとは真言宗の草庵でしたが、天正のはじめ(1580年代)開山一嶺俊栄大和尚の来錫により曹洞宗に改宗されました。
元禄十二年(1699年)四世心翁三悦和尚のとき、上の山に改築落慶して海上山玉泉禅寺と号し、嘉永元年(1848年)、遺弟二十世翠岩眉毛和尚が現在地に伽藍を整備、山号を瑞龍山に改めたといいます。
嘉永七年(1854年)3月、日米和親条約締結、同年5月の付録13ヶ条締結の際、当寺は米国黒船乗員の休息所・埋葬所に指定されました。
安政三年(1856年)タウンゼンド・ハリス総領事、通訳官ヒュースケンが米艦サン・ハシント号で下田に着任し、同年8月に玉泉寺を日本最初の米国総領事館としました。
境内には星条旗が掲揚され、以来安政六年(1859年)5月江戸麻布の善福寺に移転するまでの2年10ヶ月、幕末開国史のメイン舞台となりました。
また、日露和親条約の交渉の場となり、プチャーチン提督やディアナ号高官の滞在など、開国の歴史を彩る寺歴を有して国の史跡文化財に指定されています。
天皇、皇后両陛下が行幸され、ジミー・カーター米国大統領も訪れてペリー艦隊の将兵墓地をお参りしています。
黒船来航は嘉永六年(1853年)6月、玉泉寺の山内整備は嘉永元年(1848年)なので、黒船来航の数年前に下田の地で伽藍を整えたこのお寺は、期せずして開国の歴史の表舞台に躍り出たことになります。
『豆州志稿』には「柿崎村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 天正中(1573-1592年)香雲寺七世俊榮創立」と記述は少なく、やはり開国の歴史で語られるお寺なのだと思います。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
下田市柿崎。国道135号線から須崎方面へ入ってすぐ左手の下田湾を見下ろす高台にあり、港一望の立地も総領事館として好都合だったのでしょう。
石段のうえに構える山門は切妻屋根桟瓦葺。大棟と掛瓦の意匠が複雑で存在感があります。
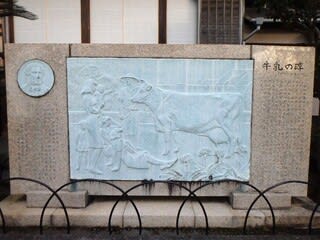

【写真 上(左)】 牛乳の碑
【写真 下(右)】 牛王如来
3年足らずでしたが正式な米国の総領事館であったため、ふつう寺院にはみられない変わった遺跡がのこります。
日本の門戸を世界に開いたハリスの功績を称える「ハリスの石碑」。
日本で初めて牛乳売買が行われた記念として森永乳業が建てた「牛乳の碑」。領事館の料理用に牛が屠殺されたことにちなむ「日本最初の屠殺場跡」など。
山内には屠殺された牛の菩提のため、東京の牛肉商によって「牛王如来」が建立されています。
本堂右手の「ハリス記念館」では領事館時代にハリスが愛用した品々や文書、そして、玉泉寺の復興に尽力した渋沢栄一にかかわる品などが展示されています。
山内には日本で最初の「外人墓地」とされる「ペリー艦隊」乗員、ロシアの「ディアナ」号の乗員などの墓があります。


【写真 上(左)】 ハリス記念館入口
【写真 下(右)】 本堂
本堂は間口(桁行)七間半、奥行き(梁間)七間、総欅造りの寄棟造で銅板葺、軒先にかけてやわらかな照りをもつ上品な造りです。
向拝柱はなく、扁額もかかげていません。
本堂は開放されて御内陣まで拝め、見上げには寺号扁額。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 扁額
『下田市観光ガイド』によると、米国総領事館は本堂に設置されたため、御本尊等の仏像は運び出され、現在ハリスの石碑が建っているあたりに移されていたそうです。
御朱印は授与所にて拝受しました。
授与所前に御朱印が見本が出ているので、慣れない方も拝受しやすいです。
また、こちらは南伊豆では貴重な御朱印帳も頒布されています。
御朱印は伊豆八十八ヶ所(釋迦如来)と「開国史跡 玄波朝天」の二種。
「玄波朝天」とは(異国から)波が押し寄せ朝日が昇る(日本の夜明け)というほどの意味のようです。


【写真 上(左)】 授与案内
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釋迦如来

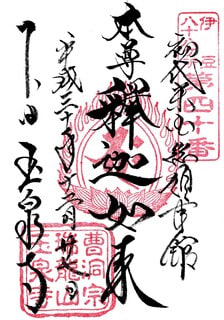
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 「玄波朝天」の御朱印 〕
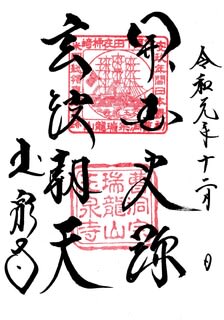
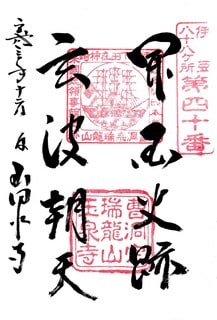
【写真 上(左)】 札所印なし
【写真 下(右)】 札所印あり
■ 第41番 富巖山 天気院 海善寺(かいぜんじ)
公式facebook
下田市観光ガイド
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市一丁目14-18
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
公式facebookによると観応元年(1350年)、河津の縄地村に明蓮社量誉昭善和尚により開創。(当初は真言宗寺院という説もあり)
天正十七年(1589年)賀茂郡本郷村字天気に移り、慶長年中(1596-1615年)に現在地に移ったとあります。
他の資料には観応元年(1350年)僧昭善が真言宗寺院として開創し、その後下田市本郷に移り布根山天気院と号し、天正十七年(1589年)僧量譽によって浄土宗へ改宗、天正十八年(1590年)現在地に移転して富巖山海善寺と号したという記載もみられます。
当山は、戸田忠次が徳川家康公より五千石をもって下田領主として封ぜられた居館の跡とされます。
その後戸田家は関ヶ原の功により加増を受け、三河田原一万石の大名となりました。
文久三年(1863年)12月、攘夷を迫られた十四代将軍家茂公が蒸気船「翔鶴丸」で上洛の途中、西風に阻まれ下田に待避し当寺で越年したという記録が残ります。
『豆州志稿』には「下田町殿小路 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 初僧照善縄地村ニ創立ス年代不詳 往古縄地ヨリ本郷村ニ移シ 布根山天気院ト云 布根ハ山名天気ハ地名 蓋量譽上人ノ時真言ヲ改宗シテ浄土ト為ル 量譽ハ天正中ニ寂ス 其後又戸田氏ノ館跡ニ 徳川家康此地ニ戸田忠次ヲ封ス 引ク子院四 徳水軒 浄入庵 浄體軒 周印軒 元治元年(1864年)正月 徳川家茂海上上洛ノ時 当寺ヲ旅館トス 庭前ノ松樹ハ其手栽ナリ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
伊豆急下田駅にもほど近い下田市一丁目。
参道門柱から山門までかなりの距離があり、山門も堂々たる楼門で寺格を感じます。
この山門は江戸時代の建立とのこと。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御名号標


【写真 上(左)】 聖観世音菩薩像
【写真 下(右)】 観音堂?
山内には六地蔵、御名号標、聖観世音菩薩像に「施無畏」の扁額が掛かったお堂。
「施無畏」は観世音菩薩をさすこともあるので観音堂かもしれません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
本堂は昭和34年の火災で焼失し、近代建築となっています。
向拝に扁額はありませんでしたが、なぜか寺号扁額の写真があるので、本堂を開けていただいたかもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿彌陀如来

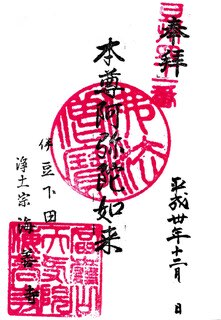
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6へつづく。
【 BGM 】
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
■ 私きっとこの恋を永遠にね忘れない - CHIHIRO
■ Cloudyな午後 - 中原めいこ
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ (新?)第35番 天城山 慈眼院(じげんいん)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
賀茂郡河津町梨本28-1
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:温泉施設「禅の湯」内
※今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から慈眼院に変更されたようです。
慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますのでUPします。
伊豆88遍路の紹介ページには「安政4年(1857年)初代駐日総領事タウンゼント・ハリスが、日米修好通商条約締結のため江戸へ赴く途中で一泊したお寺。ハリスが使用した曲録(椅子)が残っています。」とありますが、情報の少ないお寺さまです。
『豆州志稿』に「梨本村 曹洞宗 逆川普門院末 本尊観世音 舊真言宗慈眼庵ト称シテ天城山中ニ在リキ 慶安(1648-1652年)中此地ニ移シ 普門院雲國和尚ヲ開山祖トス 是時ヨリ院号ト為ス」とありますので、少なくとも江戸時代には創立しているようです。
伊豆山中に真言宗の庵として草創、慶安(1648-1652年)年間に現在地に遷り普門院雲國和尚を開山祖として庵を院に改めています。
「寺社Nowオンライン」の記事によると、もともと檀家がすくなく寺院経営がきびしかったため、境内にユースホステルを起業、温泉を掘削して温泉施設「禅の湯」としてリニューアルオープンしたとのこと。
-------------------
国道414号天城街道が天城峠から七滝ループ橋を経て下ってきたところ、温泉地としても知られる梨本エリアにあります。
国道に面し、お寺というより温泉施設「禅の湯」が前面に出ています。


【写真 上(左)】 サイン
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 石仏群
国道に面した山門は切妻屋根銅板葺の四脚門。
正面の本堂は寄棟造桟瓦葺で大棟に「慈眼院」の院号を掲げています。
向拝柱はなく、向拝扉と両側に花頭窓。
本堂内は禅刹らしいすっきりとしたつくりで、正面見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 龍の天井絵
御朱印は「禅の湯」のフロントで授与されています。
御朱印は御本尊・聖観世音菩薩、弘法大師、ほうそうばあさん、龍(両面)の4種類。
いずれも御朱印帳への印判でした。
非札所の曹洞宗寺院で弘法大師の御朱印はめずらしいですが、こちらはもともと真言宗でお大師さまとゆかりがあるとの由。
このたびの伊豆八十八ヶ所霊場への参画で、ゆかりがより深まったとみるべきでしょうか。
龍の御朱印は、本堂の豪快な天井絵にちなむもの。
「ほうそうばあさん」は、疱瘡神(疱瘡を患うことがないよう祈念する神様)です。

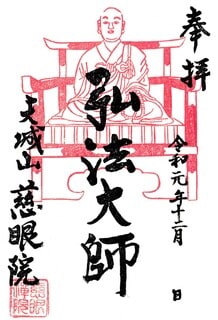
【写真 上(左)】 御本尊・聖観世音菩薩の御朱印
【写真 下(右)】 弘法大師の御朱印

■ ほうそうばあさんの御朱印
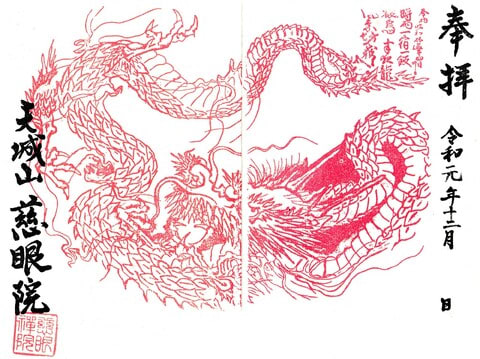
■ 龍の御朱印
-------------------
こちらは、以前に日帰り入浴していますが、横着なのでまだレポをあげていません (~~;
近いうちにUPしたいと思います。
こちらは自家源泉で、平成17年春に温泉分析しています。
源泉名は梨本17号、泉温47.0℃、pH=9.0(アルカリ性泉)、湧出量169L/min、成分総計=1.383g/kgのカルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉。
なかなかの良泉を非加水・非加温・非消毒でかけ流し利用しています。
「禅の湯」はロハス系のあかるいイメージの宿泊施設で、日帰り入浴も受け付けています。
座禅やリトリート体験もできるようです。
■ 第36番 長運山 乗安寺(じょうあんじ)
河津町観光協会
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町谷津413
日蓮宗
御本尊:十界曼荼羅
札所本尊:
他札所:-
授与所:庫裡
伊豆半島には、中伊豆、伊東などを中心に日蓮宗寺院がかなりありますが、伊豆八十八ヶ所霊場は禅刹がメインで日蓮宗の札所は1ヶ所しかありません。
こちらはその貴重な日蓮宗の札所寺院です。
『こころの旅』『霊場めぐり』によると、慶長年間(1596-1615年)縄地金山採掘の際、縄地に身延山久遠寺廿二世日遠上人を開山に創立、のちに現在地に移されたといいます。
開山日遠上人が法輪のため駿府城に赴いた際、家康公の怒りにふれ安倍川の河原で斬罪に処せられるところ、側室お万の方が上人を自らの女駕籠に乗せてこの地へ逃したという伝承があります。
当山には、そのときの女乗物駕籠が保存されています。
この事件のいきさつについては、Wikipediaの「養珠院」のページにまとめられているので、以下に引用させていただきます。
-----------------------(引用はじめ)
(養珠院(お万の方)の)義父の蔭山家は代々日蓮宗を信仰しており、万もその影響を受けて日遠に帰依した。家康は浄土宗であり、日頃から宗論を挑む日遠を不快に思っていたため、慶長13年(1608年)11月15日、江戸城での問答の直前に日蓮宗側の論者を家臣に襲わせた結果、日蓮宗側は半死半生の状態となり、浄土宗側を勝利させた。この不法な家康のやり方に怒った日遠は身延山法主を辞し、家康が禁止した宗論を上申した。これに激怒した家康は、日遠を捕まえて駿府の安倍川原で磔にしようとしたため、万は家康に日遠の助命嘆願をするが、家康は聞き入れなかった。すると万は「師の日遠が死ぬ時は自分も死ぬ」と、日遠と自分の2枚の死に衣を縫う。これには家康も驚いて日遠を放免した
-----------------------(引用おわり)
家康公は日蓮宗に対して総じて厳しい態度をとり、幾度も関係者に対論させたといわれています。
この事件も上記のとおり宗論が絡んでいるといわれますが、かなりデリケートな内容も含むのでここではこれ以上とりあげません。
いずれにしても、身延山久遠寺廿二世日遠上人の開山という由緒ある日蓮宗寺院であることはまちがいなさそうです。
上記のとおりお万の方は熱心な日蓮宗の信者で、三島の日蓮宗の名刹、経王山 妙法華寺ともふかいゆかりをもちます。
『豆州志稿』には「谷津村 日蓮宗 甲州身延山久遠寺末 本尊十界曼荼羅 慶長中(1596-1615年)創立 久遠寺廿二世日遠ヲ開山トス(中略)縄地ニ黄金出シ時(慶長中金鉱開掘)新ニ建タテルカ事罷テ此ニ移ス」とあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御題目碑
河津川が河津浜に注ぐ河口そばの右岸にあります。
「河津の足湯処・ほっとステーション」のちょうど山側です。
山内入口に御題目碑と「元祖日蓮大士」の石碑。
そのすぐ先に山を背負って本堂。
右手の山腹に朱塗りのお堂がありますが、何のお堂かきき忘れました。


【写真 上(左)】 朱塗りのお堂
【写真 下(右)】 本堂
-------------------
2015年落慶の真新しい本堂は、寄棟造銅板葺で向拝柱のないシンプルなつくり。
向拝サッシュ扉のうえに寺号扁額を掲げています。
庫裡にお声掛けすると本堂を開けていただけ、本堂内にも寺号扁額が懸けられていました。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
「こころの旅」を読んだうえで参拝しているので、当然「女乗物駕籠」の認識はあったはずですが、このときはなぜか「女乗物駕籠」の一部しか撮影しておりません。


【写真 上(左)】 堂内扁額
【写真 下(右)】 女駕籠(一部)
別のものを撮った写真に「女乗物駕籠」の説明書きも写っていました。
写角が悪く不明瞭ですが、読み取れる範囲で書き起こしてみます。
「徳川家康の側室、お万の方(養珠院)は生涯の師と仰ぐ日遠上人を『駿府の法難』からお救い致しました。そして処刑は免れたものの他宗の迫害を恐れたお万の方は上人ゆかりの地、河津へ愛用の『女駕籠』を使い乗安寺へかくまわれました。」
本堂設備工事の施工企業「㈱宮崎商会」様のWebに「お万の方の駕籠がある乗安寺本堂改築完成!!」という記事があり、改装前の本堂、「女駕籠」や新本堂の落慶法要などの写真がばっちり載っていますのでそちらをご覧ください。
この記事にはお万の方と河津とのゆかりを示す貴重な情報も載っていますので、以下に引用させていただきます。
-----------------------(引用はじめ)
「お万の方は天正3年(1575年)、上総勝浦城(千葉県勝浦市)の城主正木時忠の五男頼忠を実父に、北条氏隆の娘である智光院を母に、小田原に生まれている。その後すぐ、時忠が亡くなり、頼忠が後を継ぐため妻子を残し勝浦城に戻った。智光院は伊豆河津郷に移り、北条家臣の河津城主の蔭山長門守氏広と再婚、お万の方はこの養父蔭山氏広に育てられている。天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅び、その後慶長3年(1598年)父である氏広が死去、この頃から深く仏門に帰依し、日蓮宗、身延山の上人を信ずるようになる。その後徳川家康の側室となった。」
-----------------------(引用おわり)
この記事によると、お万の方の母・智光院は北条家臣の河津城主・蔭山長門守氏広と再婚し、お万の方は養父蔭山氏広に育てられたとの由。
とすると、お万の方は河津の地で育ったことになり、仏法の師、日遠上人の危機に際して第二の故郷の河津にかくまわれた、というのはわかりやすい流れです。
御首題は、たしか本堂向かって左手の庫裡にていただきました。
御首題帳にいただきましたが、御朱印帳でも拝受できるかは不明です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 御首題

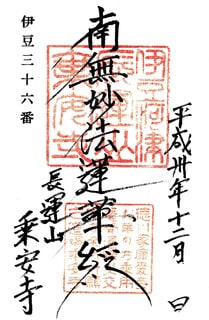
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御首題帳
■ 第37番 玉田山 地福院(じふくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町縄地430
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:第38番禅福寺庫裡
平安時代の創立ともいわれ、かつては玉田山金生院という真言宗寺院でしたが、慶長五年(1600年)に曹洞宗に改め再興。
縄地金山が栄えた際に、近隣に創立された9つの寺院のうちの一ヶ寺で、金山衰退後に他の8つの寺院は移転ないし廃寺となりましたが、地福院だけはこの地に残ったとの由。
『豆州志稿』には「縄地村 曹洞宗 武州金澤禅林寺末 本尊大日 初真言ニシテ金生院と称ス 後中絶ス 慶長五年(1600年)禅林寺二世天随再興改宗シテ地福院ト号ス」とあります。
せっかくなので縄地金山について調べてみようと思いましたが、廃墟系・探索系サイトはたくさんヒットするものの、公的な資料がほとんどみつかりません。
関心を惹きやすい閉鉱金山で、現在、民間所有なので自治体としてもとり上げにくいようです。
静岡県立中央図書館のWeb開示資料がヒットしたので抜粋引用します。
「縄地金山(河津町)は1598年(慶長三年)から採掘が始まったとされる。『佐渡年代記』1601年(同六年)大久保長安が伊豆・石見・佐渡銀山の支配を命じられたことが記され、1606年(同十一年)、伊豆金山奉行となったことから最盛を極めた。(中略)大久保長安は1607年(同十二年)に河津町の縄地神社に鰐口を奉納して(中略)鉱山の隆盛と安全を祈願した。」
また、『霊場めぐり』にも関連記事がありました。出典は『伊豆伝説集』からとみられ、貴重な内容なので抜粋引用します。
「縄地は南伊豆第一の金山であった。慶長十年(1605年)大久保岩見守長安が金山奉行として此地に来て採掘を続けた。最盛期には戸数8,000を算した。劇場もあり、相撲場もあり、遊女御免。長安は金山奉行として巨万を積んだ。その不正贓罪は死後にあばかれ、一族は処刑され、不正に連座した坑夫は磔刑に処せられた。岩見守の邸跡は寺坂にある。縄地の子安神社、山神社に長安奉納の金の鍔が残っていた。最大なのは重さ約7貫匁(26kg)黄金を含んでいて、音響が極めてよかったといわれたが、賊に奪われて今はない。」
伊豆の金山について、『伊豆志稿』には「黄金 白銀 天正●●頃ヨリ土肥村 黄金初メテ出テ 湯ガ島 縄地 瓜生野 修善寺等相継デホリ出シ 夥シキ●● 就中縄地ヨリ出シハ又特ニ多シ 大抵五十余年ニテ止ム 慶長十年(1610年)ノ頃ヨリ盛ニ出テ其ノ数大形佐渡ヨリ出ルガ如● 程ナク出ル●多カラズ トルノヲ止メラルト」とあり、伊豆の金山、ことに縄地は慶長の頃には佐渡にも劣らないほどの産金があったものの、ほどなく産金量が激減したことが記されています。
一時期とはいえこれだけ栄え、過酷な鉱山労働もあいまって村内に9つもの寺院が成立したのかも。
『豆州志稿』には縄地村からの移転寺院として(廃)金生山富来寺、(廃)栄寶院(当山派)、西光寺などがみられ、第36番乗安寺、第41番海善寺も縄地からの移転とあるので旧・縄地九箇寺かもしれません。
なお、大久保長安は数奇な運命をたどった武将で、逸話が山ほどあるので興味のある方は→こちら(Wikipedia)をご覧くださいませ。
-------------------

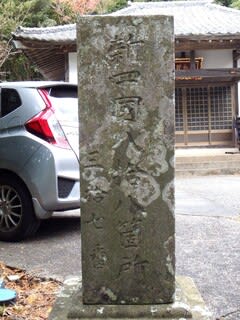
【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 札所標
国道135号線、縄地トンネルのすぐ西から北へ向かう細い道を上がったところ。
石垣が積まれた参道。本堂手前に伊豆八十八ヶ所の札所標。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺流れ向拝。向かって右手に庫裡らしき建物がせり出し、ちょっと面白い構成です。
水引虹梁は木鼻の抜けがなく、身舎側の繋ぎ虹梁と併せて向拝上にスクエアを構成。
向拝正面サッシュ扉のうえに院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
山内掲示によると、御本尊の金剛界大日如来像は銅製で室町時代後期以降。
吉祥天女像は桧一本造りで平安中期。こちらはかつて縄地尾ヶ崎の小堂に薬師如来として祀られていたお像とのこと。
こちらは無住で、御朱印は第38番禅福寺でいただきました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来
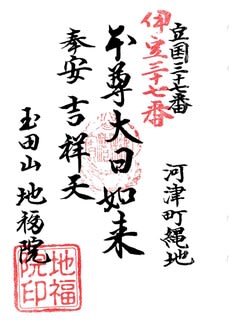

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第38番 興國山 禅福寺(ぜんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市白浜351
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
司元別当:伊古奈比咩命神社・白濱神社(下田市白浜)
他札所:-
授与所:庫裡
ここから巡路は下田市内に入ります。
下田は東・西廻海運の風待ち湊として栄え、江戸時代初期には天領となり下田奉行ないし浦賀奉行所支配下にあって独自の文化圏を築いたところです。
下田に陸路で入るルートは中伊豆からの天城越えがメインで、東海岸ルートは相当の難路であったと思われます。
これだけの観光資源をもちながら、伊豆急が下田まで開通したのはなんと昭和36年(1961年)。
東伊豆海岸沿いを走る国道135号も当初は険しい海沿いを走ることができずに山側をたどり、のちに海側につけられた国道は災害等で廃道になっている箇所があります。
この海岸の異様な険しさについては、ヨッキれん氏の壮絶なレポで実感してみてください。
江戸時代の東伊豆の陸路はかように難路で、域外、ことに江戸方面へのメインルートは海路でした。
じっさい下田市のWeb資料「下田の歴史年表」の多くは、水軍、船改め番所、御台場など海運施設の記述に費やされています。
なお、伊豆の海運については「海の東海道」((社)静岡県建築士会)というよくまとまったWeb記事があります。
陸路が厳しく海上交通が盛んであれば、その土地は海運関係者で繁昌し、南伊豆の物産の集散地となった筈です。
その繁栄ぶりは、「下田節」(下田市Web資料)の「伊豆の下田に長居はおよし、縞の財布が軽くなる」からも容易に想像できます。
■ 下田節(静岡県民謡)~峰村利子
伊豆八十八ヶ所の札所が、いまでは交通便利な東伊豆に少なく、南伊豆に集中しているのは不思議な感じもしますが、背景にはこのような事情があったかもしれません。
禅福寺について、『豆州志稿』には「白濱村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 昔禅教庵ト云 寛永中(1624-1644年)大室和尚寺号ト為ス」とあります。
(山号が「奥谷山」となっています。)
当初は観世音菩薩を奉安する真言宗の小庵で、貞和年間(1345-1350年)以来衰えましたが、 永正(1504-1521年)のころ相州香雲寺開山の霊叟禅師が入られて曹洞宗となり「禅居庵(または禅教院)」と号し、元和八年(1622年)に香雲寺9世宗樹ないし、寛永中(1624-1644年)に大室和尚が伽藍を整え「禅福寺」と号を改めたと伝わります。
禅福寺は、かつて伊豆最古の神社とされる伊古奈比咩命神社(白濱神社)の別当をつとめたともいわれます。
名社、伊古奈比咩命神社について書き始めると膨大な量になりそうなので、以前温泉レポ「下賀茂温泉 「伊古奈」【閉館】」でまとめた文章をそのまま持ってきます。
白濱(浜)神社は正式名を伊古奈比咩命神社といい、公式Webによると、御祭神は伊古奈比咩命、三嶋大明神、見目、若宮、剣の御子の5柱です。
当社の御由緒には「三嶋大明神は、その昔遥か南方より黒潮に乗り、この伊豆に到着されました。(中略)伊豆の南に定住していた賀茂族の姫神(伊古奈比咩命)様を后として迎え、白浜という所に宮を造り住まわれました。」とあります。
また、御祭神の説明には以下のとおりあります。
「主神 伊古奈比咩命(いこなひめのみこと) 女性神 三嶋大明神の最愛の后神で縁結びと子育ての神様です。」
「相殿 三嶋大明神 男性神 事代主命(ことしろぬしのみこと)であると言われています。大国主命の御子神様にあたり、大国主命を大国(だいこく)さんを呼ぶのに対して、事代主命は恵比寿さんと呼ばれています。商業と漁業の神様です。」
御鎮座は六代孝安天皇元年(約2400年前)と伝わり、『日本後紀 巻下(六国史.巻6)』(国立国会図書館DC)の淳和天皇天長九年(832年)5月22日の條に「伊豆國言上、三島神、伊古奈比咩神、二前預名神」とあります。
公式Webには「御土御門天皇文亀元年(1501年)には、三島神、伊古奈比咩神共、正一位という高い位を受けています。そして延喜式には三島神社、伊古奈比咩命神社が、二社共この白浜に鎮座していた事が書かれていて、その社格は三島神社が官幣大社、伊古奈比咩命神社が国幣大社となっています。」とあります。
以上より、伊古奈比咩命神社(白濱神社)が伊豆有数の古い歴史をもち、高い社格をもたれることがわかります。

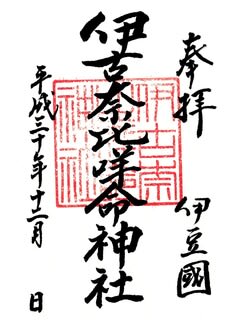
【写真 上(左)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)
【写真 下(右)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)の御朱印
-------------------


【写真 上(左)】 参道の石段
【写真 下(右)】 門柱
白浜漁港の山側、路地奥に階段参道。
門柱のむこう正面が本堂で、入母屋造銅板葺流れ向拝。向拝部に端正な軒唐破風を起こしています。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股の構成ですが、全体にすっきりとしたイメージ。
向拝正面サッシュ扉のうえに山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて、第37番地福院とともに拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来
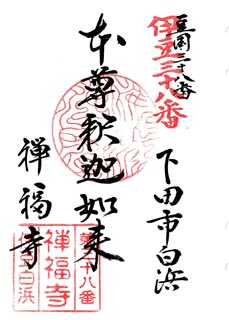

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 下賀茂温泉 「伊古奈」【閉館】の入湯レポ
■ 第39番 西向山 観音寺(かんのんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市須崎615
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第21番、第22番
授与所:庫裡
下田市の南東、須崎半島にあり、運慶作と伝わる十一面観世音菩薩像を御本尊として奉安する禅刹です。
『豆州志稿』には「須崎村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊観世音 舊暘谷院トテ真言宗ナリ 寛永(1624-1644年)ノ頃大室和尚宗及寺号ヲ改ム 初同村字川上ニ在リ 大室ノ時現地ニ移ス」とあります。
開創年代は不明。当初は真言宗で須崎川上にあり、暘谷院と号しました。
元和元年(1615年)(寛永年間とも)、相州秦野香雲寺九世・大室宗樹が曹洞宗に改宗し、現寺号に改めました。
延享四年(1747年)、火災に遭い現在地に移転と伝わります。
こちらは伊豆横道三十三観音霊場第21番、第22番の札所を兼ねています。
伊豆横道三十三観音霊場は、伊豆に流されていた源頼朝公と高雄山神護寺の僧・文覚により源氏再興を祈念して開創とされる、すこぶる古い観音霊場です。
発願の西伊豆町の延命寺(滝見観音堂)から松崎、下田、河津と廻り、結願は南伊豆町伊浜の普照寺です。
無住のお堂も多いですが、すべて巡拝でき御朱印も揃います。
筆者は結願していますので、後日あらためてご紹介したいと思います。
(本編でもとりあえず御朱印は掲載します。)
一部で伊豆八十八ヶ所と札所が重複しますが、河津町の札所は重複がないので、順打ちでくるとこちらが初めての重複札所となります
観音寺は第21番。末寺の第22番補陀庵も現在観音寺に遷られているので2札所となります。
-------------------
須崎半島は南伊豆でも早くから拓けた地で、須崎港は下田の玄関口のひとつでした。
爪木崎や恵比寿島などの観光地はあるものの、水仙の時季以外は訪れる観光客は少なそうです。
筆者も子供のころから伊豆にはよく行きましたが、須崎半島に足を踏み入れたのは今回が初めてです。


【写真 上(左)】 (たぶん)須崎漁港
【写真 下(右)】 参道入口
観音寺はこの須崎半島の南端、須崎漁港の山側、海抜約15mの高台にあります。
あたりは港町の趣きゆたか。それだけに狭い路地が入り組み車の運転は難儀します。
観音寺の門前まで車道は通じていますが、すこぶる狭く駐車場もないようなので車参拝は要注意。
お寺さまに駐車場所を事前TEL確認がベターかと思います。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山内からの海
【写真 下(右)】 山内
参道は石段で、石段右手に札所標。その先に切妻屋根桟瓦葺の端正な四脚門を構えています。
山門正面が本堂。寄棟造銅板で、向拝柱のないシンプルな堂容です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂向かって右手奥の庫裡で御朱印をお願いすると、本堂にあげていただけました。
五色幕が張り巡らされた本堂内は観音霊場らしい華やぎがあります。


【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 本堂内扁額
向拝見上げに「圓通閣」の扁額。
御本尊は運慶作と伝わる十一面観世音菩薩像で、伊豆八十八ヶ所と伊豆横道三十三観音霊場第21番の札所本尊ですが秘仏かもしれません。
山内掲示によると、伊豆横道三十三観音霊場第22番の札所本尊は、本堂ご内陣正面向かって右の厨子内に安置される秘仏の聖観世音菩薩像で、市の指定文化財です。
こちらはかつて小白浜の観音山上にあった補陀庵という末寺の御本尊で、そこから遷られたもの。
檜材一本造りの立像で行基作ともいわれますが、市のWeb資料には「平安後期の作と考えられる」とあります。
山内掲示には「平安後期の作とも伝わるが、和様化の進んだ像容から十一世紀頃の作と推定される。」とありました。
本堂御内陣向かって左の厨子内の薬師如来坐像は檜材一本造りで、制作年代は10世紀末から11世紀初頭に遡ると考えられ、こちらも市の指定文化財です。


【写真 上(左)】 石佛群
【写真 下(右)】 庫裡
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場第21番の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩

〔 伊豆横道三十三観音霊場第22番(補陀庵)の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩
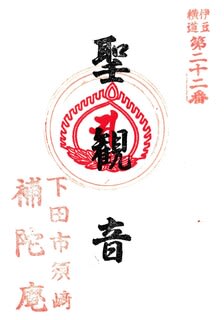
■ 第40番 瑞龍山 玉泉寺(ぎょくせんじ)
公式Web
下田市観光ガイド
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市柿崎31-6
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
伊豆八十八ヶ所の札所は伊東を過ぎると札所色が強まり、観光客のすがたはまばらですが、こちらは下田の観光名所として人気があります。
寺伝(公式Web、『こころの旅』『霊場めぐり』)によると、もとは真言宗の草庵でしたが、天正のはじめ(1580年代)開山一嶺俊栄大和尚の来錫により曹洞宗に改宗されました。
元禄十二年(1699年)四世心翁三悦和尚のとき、上の山に改築落慶して海上山玉泉禅寺と号し、嘉永元年(1848年)、遺弟二十世翠岩眉毛和尚が現在地に伽藍を整備、山号を瑞龍山に改めたといいます。
嘉永七年(1854年)3月、日米和親条約締結、同年5月の付録13ヶ条締結の際、当寺は米国黒船乗員の休息所・埋葬所に指定されました。
安政三年(1856年)タウンゼンド・ハリス総領事、通訳官ヒュースケンが米艦サン・ハシント号で下田に着任し、同年8月に玉泉寺を日本最初の米国総領事館としました。
境内には星条旗が掲揚され、以来安政六年(1859年)5月江戸麻布の善福寺に移転するまでの2年10ヶ月、幕末開国史のメイン舞台となりました。
また、日露和親条約の交渉の場となり、プチャーチン提督やディアナ号高官の滞在など、開国の歴史を彩る寺歴を有して国の史跡文化財に指定されています。
天皇、皇后両陛下が行幸され、ジミー・カーター米国大統領も訪れてペリー艦隊の将兵墓地をお参りしています。
黒船来航は嘉永六年(1853年)6月、玉泉寺の山内整備は嘉永元年(1848年)なので、黒船来航の数年前に下田の地で伽藍を整えたこのお寺は、期せずして開国の歴史の表舞台に躍り出たことになります。
『豆州志稿』には「柿崎村 曹洞宗 相州田原香雲寺末 本尊釋迦 天正中(1573-1592年)香雲寺七世俊榮創立」と記述は少なく、やはり開国の歴史で語られるお寺なのだと思います。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
下田市柿崎。国道135号線から須崎方面へ入ってすぐ左手の下田湾を見下ろす高台にあり、港一望の立地も総領事館として好都合だったのでしょう。
石段のうえに構える山門は切妻屋根桟瓦葺。大棟と掛瓦の意匠が複雑で存在感があります。
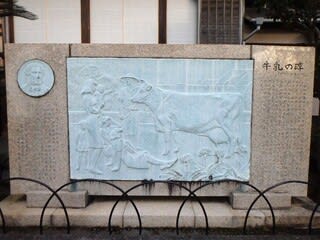

【写真 上(左)】 牛乳の碑
【写真 下(右)】 牛王如来
3年足らずでしたが正式な米国の総領事館であったため、ふつう寺院にはみられない変わった遺跡がのこります。
日本の門戸を世界に開いたハリスの功績を称える「ハリスの石碑」。
日本で初めて牛乳売買が行われた記念として森永乳業が建てた「牛乳の碑」。領事館の料理用に牛が屠殺されたことにちなむ「日本最初の屠殺場跡」など。
山内には屠殺された牛の菩提のため、東京の牛肉商によって「牛王如来」が建立されています。
本堂右手の「ハリス記念館」では領事館時代にハリスが愛用した品々や文書、そして、玉泉寺の復興に尽力した渋沢栄一にかかわる品などが展示されています。
山内には日本で最初の「外人墓地」とされる「ペリー艦隊」乗員、ロシアの「ディアナ」号の乗員などの墓があります。


【写真 上(左)】 ハリス記念館入口
【写真 下(右)】 本堂
本堂は間口(桁行)七間半、奥行き(梁間)七間、総欅造りの寄棟造で銅板葺、軒先にかけてやわらかな照りをもつ上品な造りです。
向拝柱はなく、扁額もかかげていません。
本堂は開放されて御内陣まで拝め、見上げには寺号扁額。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂内
【写真 下(右)】 扁額
『下田市観光ガイド』によると、米国総領事館は本堂に設置されたため、御本尊等の仏像は運び出され、現在ハリスの石碑が建っているあたりに移されていたそうです。
御朱印は授与所にて拝受しました。
授与所前に御朱印が見本が出ているので、慣れない方も拝受しやすいです。
また、こちらは南伊豆では貴重な御朱印帳も頒布されています。
御朱印は伊豆八十八ヶ所(釋迦如来)と「開国史跡 玄波朝天」の二種。
「玄波朝天」とは(異国から)波が押し寄せ朝日が昇る(日本の夜明け)というほどの意味のようです。


【写真 上(左)】 授与案内
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釋迦如来

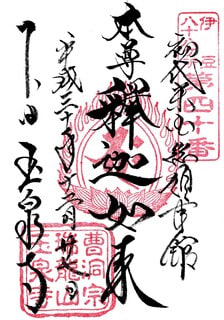
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 「玄波朝天」の御朱印 〕
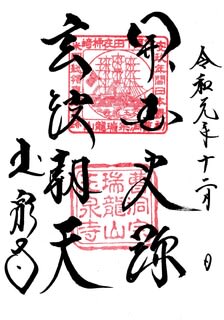
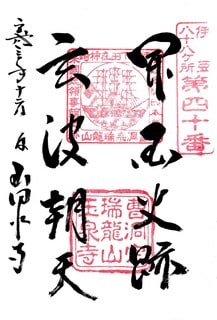
【写真 上(左)】 札所印なし
【写真 下(右)】 札所印あり
■ 第41番 富巖山 天気院 海善寺(かいぜんじ)
公式facebook
下田市観光ガイド
伊豆88遍路の紹介ページ
下田市一丁目14-18
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
公式facebookによると観応元年(1350年)、河津の縄地村に明蓮社量誉昭善和尚により開創。(当初は真言宗寺院という説もあり)
天正十七年(1589年)賀茂郡本郷村字天気に移り、慶長年中(1596-1615年)に現在地に移ったとあります。
他の資料には観応元年(1350年)僧昭善が真言宗寺院として開創し、その後下田市本郷に移り布根山天気院と号し、天正十七年(1589年)僧量譽によって浄土宗へ改宗、天正十八年(1590年)現在地に移転して富巖山海善寺と号したという記載もみられます。
当山は、戸田忠次が徳川家康公より五千石をもって下田領主として封ぜられた居館の跡とされます。
その後戸田家は関ヶ原の功により加増を受け、三河田原一万石の大名となりました。
文久三年(1863年)12月、攘夷を迫られた十四代将軍家茂公が蒸気船「翔鶴丸」で上洛の途中、西風に阻まれ下田に待避し当寺で越年したという記録が残ります。
『豆州志稿』には「下田町殿小路 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 初僧照善縄地村ニ創立ス年代不詳 往古縄地ヨリ本郷村ニ移シ 布根山天気院ト云 布根ハ山名天気ハ地名 蓋量譽上人ノ時真言ヲ改宗シテ浄土ト為ル 量譽ハ天正中ニ寂ス 其後又戸田氏ノ館跡ニ 徳川家康此地ニ戸田忠次ヲ封ス 引ク子院四 徳水軒 浄入庵 浄體軒 周印軒 元治元年(1864年)正月 徳川家茂海上上洛ノ時 当寺ヲ旅館トス 庭前ノ松樹ハ其手栽ナリ」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
伊豆急下田駅にもほど近い下田市一丁目。
参道門柱から山門までかなりの距離があり、山門も堂々たる楼門で寺格を感じます。
この山門は江戸時代の建立とのこと。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御名号標


【写真 上(左)】 聖観世音菩薩像
【写真 下(右)】 観音堂?
山内には六地蔵、御名号標、聖観世音菩薩像に「施無畏」の扁額が掛かったお堂。
「施無畏」は観世音菩薩をさすこともあるので観音堂かもしれません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
本堂は昭和34年の火災で焼失し、近代建築となっています。
向拝に扁額はありませんでしたが、なぜか寺号扁額の写真があるので、本堂を開けていただいたかもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿彌陀如来

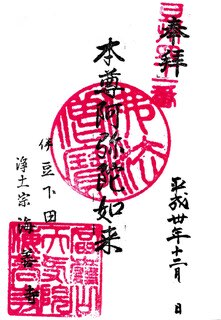
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6へつづく。
【 BGM 】
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
■ 私きっとこの恋を永遠にね忘れない - CHIHIRO
■ Cloudyな午後 - 中原めいこ
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
文字数オーバーしたので、Vol.4をつくりました。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
28.慈眼山 無量院 萬福寺 (つづき)
〔梶原平三景時〕
東京都大田区南馬込1-49-1
曹洞宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:江戸・東京四十四閻魔参り第19番、閻魔三拾遺第29番
--------
南馬込の禅刹、萬福寺。山内掲示の縁起書には以下のとおりあります。
「当寺は鎌倉時代の初期、建久年間(1190年頃)に梶原景時が将軍源頼朝の命により大檀那となり梶原家相伝の阿弥陀如来三尊仏を本尊として大井丸山と云う処に建立された。
元応二年(1320年)に火災にあい、景時の墓所のある馬込へ移され再建された。」
『新編武蔵風土記稿』(国会図書館DC)には、当山と梶原景時のかかわりについて詳細に記されています。
(同書では、景時の所領は多磨郡柚井領(現・八王子市)としており、じっさい、元(梶原)八王子八幡神社の由緒には、この地が梶原景時の所領(梶原屋敷)であったことが記されています。)
そのうえで「景時モシ一寺ヲモ建立セントセハ 其住所及ヒ所領ノ地ヲ置テ遠ク当所ヘ起立スヘケンヤ 寺ニ傳フル所イフカシキ事ナリ ヨリテ按ニ小田原北條家人梶原三河守 当寺ノ大檀那ニシテ此人ヲ萬福寺ト号セリ 此人当寺ヲ中興セシユヘニヨリ 梶原ノ家号ヨリ 誤テ平三景時カ開基トセシナラン」と辛辣な書き様ですが、「境内ニ建テタル梶原氏ノ碑陰ニ梶原三河守影時同子息助五郎影末云々」と山内の碑に”梶原三河守影時”の文字があることを認め、「其誤シモ又ユヘアルニ似タリ」としています。
景時の墓所(開基寺院)が、八王子の所領から通く離れた馬込の地にあることに疑問を呈しつつ、梶原家が当山の大旦那であることを含め、一定の所縁は認めているわけです。
一方、萬福寺の公式Webには、「建久年間(1190~99)大井村丸山の地に密教寺院として創建されました。開基は梶原平三景時公であったと伝えられています。元応2年(1320)火災にあい、第六代の梶原掃部助景嗣が居城とともに馬込へ移転したと伝えられます。」とあります。
これによれば、当地へ移転したのは梶原景時(六代)の子孫であり、それが正しいとすると当山は梶原景時の子孫の菩提寺であり、子孫が菩提のために先祖(景時)の墓所となすことは、あながち無理筋ではないような気もします。
また、『江戸名所図会巻二』の萬福寺の項には「相傳ふ、当寺は梶原平蔵景時、創立の梵宇なりと云ふ。霊碑ならびに墳墓あり。」とあります。
ただし注記に「(梶原平蔵)景時三河守に任ぜし事、古書に所見なし」として、北条家家臣の梶原三河守ないし、梶原助五郎の開創ではないかと記しています。
いずれにしても、仮に後世の付会があつたとしても梶原景時ゆかりの寺院として伝承されてきたことは間違いなく、景時ゆかりの見どころも多いのでこちらでご紹介します。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 するすみの像
高台の閑静な住宅地に風流な山内入口、どっしりと構える山門はおそらく茅葺き。
山門左手前には名馬「するすみ」の像。
磨墨(するすみ)は景時の嫡男・景季が頼朝公から賜った名馬で、『平家物語』の宇治川の先陣争いの段で登場します。
頼朝公お気に入りの郎党、佐々木四郎高綱も頼朝公から生食(いけづき)という名馬を下賜されていました。
宇治川をはさんで、対岸の木曽義仲軍と対峙した景季と高綱は、いずれも先駆けを狙っていました。
まずは磨墨に乗った景季が川に乗り入れ、六間ほどおくれて生食に乗った高綱が川入りして先陣争いを展開。
初動でおくれをとった高綱は、「梶原殿、この川は西国一の大河。貴殿の馬の腹帯が緩んでおる。締め直したまえ」と景季に声を掛けました。
これを聞いた景季は「それはそうだ」と馬を止め、腹帯を調べるとべつに異常はない。
その隙に高綱に先を越され、一番乗りを逃したという有名なくだりです。
名うての武将が腹帯を確かめずに先駆けとは疑問ですが、宇治川の川底には進撃よけの縄が張り巡らせられ、これを刀で絶ちつつ進撃したためにこの忠告が効いたとされています。
馬込は「磨墨」の生誕地との伝承があり、「磨墨」を供養する「するすみ塚」もあって当山が管理しています。
そのような所縁もあって、この「するすみ像」が建てられたのでしょう。
また、当山は梶原景時が戦場で用いたと伝わる馬具(区指定文化財)を所蔵しています。
だとすると「磨墨」につけられた可能性がありますが、山内の説明板には「『新編武蔵風土記稿』では北条氏直の家臣梶原三河守のものであろうと記す。」とありました。


【写真 上(左)】 閻魔堂
【写真 下(右)】 のぼり
山門をくぐって右手には閻魔堂。江戸時代から広く知られた閻魔様のようで、閻魔三拾遺第29番、江戸・東京四十四閻魔参り第19番の札所になっています。
「鎌倉の武将 梶原景時公菩提寺」ののぼりはためく階段をさらにのぼると無量門(中門)。
切妻屋根本瓦葺のすこぶる整った意匠の四脚門で、大棟には梶原氏の紋「丸に並び矢」が金色に輝いています。


【写真 上(左)】 無量門
【写真 下(右)】 鐘楼門
参道とは別に庫裡に向かう通用道があり、そちらには楼閣造りの鐘楼門があります。
無量門をくぐると門脇にお幸(身代り)地蔵尊。
右手には楼閣造りの摩尼輪堂で、一層の摩尼車には四天王と地蔵菩薩が御座。
二層には「磨墨観音」の扁額があるので名馬・磨墨ゆかりの観音様(馬頭観世音?)が奉安されているのかもしれません。


【写真 上(左)】 摩尼輪堂
【写真 下(右)】 磨墨観音の扁額
さらに進むと右手に子安観音と「当山開基 源頼朝随将 梶原平三景時公菩提寺」の石標。


【写真 上(左)】 山内案内図
【写真 下(右)】 「菩提寺」の石標
その先には鬼子母神。
当寺には重病の日蓮聖人が一夜参籠されたという伝承があり、参籠明けに聖人が奉納された持佛の鬼子母神というもので、当山相伝の守護神とのこと。
お像(御前立?)よこには「日蓮聖人参籠祈願之霊跡」の石碑が建っています。
鬼子母神縁起と日蓮聖人参籠のいきさつについては、公式Webに掲載されています。
馬込における曹洞宗と日蓮宗の関係が記された貴重な内容です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝-1


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂は入母屋造本瓦葺。正面手前に大がかりな千鳥破風の向拝を起こして風格があります。
水引虹梁両端に獅子二連の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に龍の彫刻。
格天井。正面硝子格子扉のうえに扁額が掲げられていますが、すみません、達筆すぎて筆者には読めません ^^;)
「慈眼 萬福」か?
御本尊の阿弥陀三尊は一光三尊の善光寺式で天文三年(1534年)以前の作とみられ、区の文化財に指定されています。(いまは光背は逸失とのこと)


【写真 上(左)】 「丸に並び矢」の天水鉢
【写真 下(右)】 レリーフ
本堂前の天水鉢には梶原氏の「丸に並び矢」の紋。本堂脇には景時ゆかりのレリーフと、梶原カラー満載です。
景時の墓所は本堂向かって左手の歴代住職の墓のよこにあります。
墓所は撮影しておりませんので、→こちら(公式Web)をご覧くださいませ。
当寺の隣地は室井犀星の旧宅で、「春の寺」で描かれた”うつくしきみ寺”は当寺のこと。
山内には犀星旧宅の銘石を譲り受け犀星の句を刻んだ句碑が安置されています。
御朱印は、雰囲気ある庫裡にて拝受しました。
こちらは3回参拝していますが、すべて異なる揮毫でしたので3体ともご紹介します。
うちひとつは、閻魔霊場へのご縁日(16日)の参拝です。
閻魔様の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印を拝受しています。
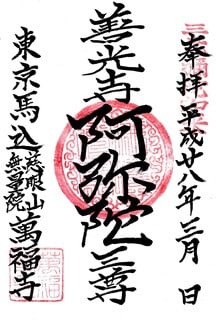
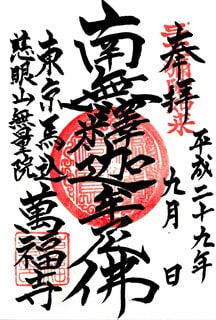
【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 宗派本尊・釈迦牟尼佛の御朱印
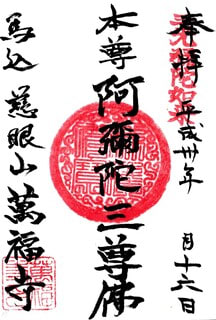
■ 江戸・東京四十四閻魔参り第19番の申告でいただいた御朱印
29.永劫山 華林院 慶元寺
〔江戸太郎重長〕
東京都世田谷区喜多見4-17-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:多摩川三十四観音霊場第4番、小田急武相三十三観音霊場第6番、玉川六阿弥陀霊場第2番、玉川北百番霊場第10番
江戸氏は桓武平氏良文流、秩父氏族の一流で豊島郡江戸郷(現在の千代田区~文京区)に拠って勢力を伸ばしました。
常陸國那珂郡(現・茨城県)には別流の江戸氏があるので、通常「武蔵江戸氏」として区別されます。
鎌倉幕府草創時の当主は第2代の江戸太郎重長で、当初は平家方に属していました。
治承四年(1180年)8月の衣笠城合戦では、同族の畠山重忠、河越重頼とともに三浦・衣笠城の三浦氏を攻め、三浦氏当主の三浦義明を討ち取っています。
この合戦の原因については所説ありますが、平家への義理や外聞からの挙兵を採る説はすくないようです。
こちらの系図(さくらいようへいブログ様掲載)をみると、城を攻めた畠山、河越、江戸氏はすべて秩父姓で、攻められた三浦氏は千葉姓です。
おなじ桓武平氏良文流とはいえ、支流同士で確執があったのかもしれません。
ちなみに桓武平氏良文流は秩父姓に畠山氏、小山田・稲毛氏、河越氏、江戸氏、渋谷氏、豊島氏、葛西氏。千葉姓に上総氏、千葉氏、村山氏、三浦氏、和田氏、岡崎氏と、多くの有力御家人を生み出した血統です。
『吾妻鏡』9月28日条には、頼朝公はこの強大な秩父一族の切り崩しを狙って重長に使いを送り、「大庭景親の催促を受け、石橋山で合戦に及んだのはやむを得ないが、以仁王の令旨の通り(頼朝公に)従うべきである。畠山重能・小山田有重が在京の今、武蔵国では汝(重長)が棟梁である。もっとも頼りにしているので近辺の武士達を率いて参上すべし」と伝えたとあります。
頼朝公が江戸重長の家柄と実力を「武蔵国の統領」ということばを使って認めていることがわかります。
その一方で、重長が景親に味方してなかなか自陣に参じないので、はやくから麾下となった秩父姓の葛西清重に、大井の要害に重長を誘い出し討ち取るよう命じています。(『吾妻鏡』9月29日条)
10月2日、頼朝軍が武蔵に入ると、4日、重長は畠山重忠、河越重頼とともに頼朝に帰順し、重長は頼朝公から武蔵の在庁官人や諸郡司を統率して国の諸雑事を沙汰する権限を与えられたといわれます。
(この権限は「武蔵国留守所総検校職」によるものとも思われますが、この職は河越氏の世襲という見方もあり、江戸氏がこれに任ぜられたかどうかは諸説ある模様。)
しかし、頼朝公の遅参への怒りは収まらず、重長の所領を没収して葛西清重に与えようとしました。
この話を受けた清重は「(秩父)一族の重長の所領を賜うのは私の意志にあらず。」と拒絶。
清重にも激怒した頼朝公は従わないなら清重の所領も没収すると脅しましたが、清重は「受けるべきものでないものを受けるのは義にあらず。」と峻拒。
清重の気骨に感じ入った頼朝公は、ついに重長を許したといいます。(『沙石集』)
以降、頼朝公の御家人となり文治五年(1189年)の奥州合戦には兄弟の親重とともに従軍、建久元年(1190年)秋の頼朝公上洛参院では後陣随兵をつとめています。
同族の河越重頼、畠山重忠は政権内部の勢力争いで滅ぼされましたが、江戸氏は巧みに命脈を保ち幕政に参画しています。
鎌倉幕府では無難に処世を図ったとみられる江戸氏ですが、それ以降は幾多の波乱に見舞われます。
「鎌倉殿の13人」を離れますが、江戸氏の菩提寺・慶元寺が世田谷にあることも含めて関係しますので、しばらく辿ってみます。
なお、江戸氏はすでに鎌倉期から宗家の武蔵江戸氏と庶流の浅草江戸氏の系譜が錯綜したともいわれますが、これにかかわると煩雑になるので割愛します。
ともかくも、江戸氏は江戸郷の所領を保って室町時代に入りました。
南北朝では家内で南北に分かれてこれをしのぎましたが、応安元年(1368年)、運命の武蔵平一揆を迎えます。
これは、秩父氏一族、相模の中村氏一族などの平氏を中心とした国人がおこした一揆で、関東管領・上杉憲顕が上洛した隙を狙い、河越直重以下、高坂氏、豊島氏、江戸氏、高山氏、古屋谷氏、仙波氏、山口氏、金子氏など武蔵の武士が河越館に拠り、下野の宇都宮氏、越後の新田氏などと連携したもの。
上杉憲顕は京で室町幕府を味方にし、足利基氏の後を継いだ鎌倉公方・足利氏満を擁して関東入りし河越に出兵。一揆は鎮圧されました。
戦に敗れた河越直重一党は南朝の北畠顕能を頼り伊勢国へ敗走し、領地はすべて没収され、関係した武将も領地を削られ没落しました。
その例にもれず、武蔵(江戸)宗家の江戸氏も没落しています。
以降、江戸の地には太田道灌が進出し、宗家江戸氏はこれに対抗できずに江戸郷を退去して世田谷木田見(喜多見)へと移住。
長禄元年(1457年)春には、太田道灌が江戸城を築いたと伝わります。
江戸氏は、鎌倉時代からすでに新恩として喜多見を領していたという説があります。
家勢が衰えた江戸氏が喜多見の地にやすやすと新領地を得たというのは無理があり、やはりなんらかの拠点があって、そこに退去したとみるのが自然です。
(「城郭図鑑」様Webに典拠は不明ですが「鎌倉時代には江戸武重が木田見次郎と名乗って木田見郷を領有しており、このとき既に江戸氏と喜多見の地には関係ができていたことが窺える。」という記事がありました。)
喜多見に移った宗家江戸氏は御北条氏の将、世田谷城主・吉良氏の家臣として仕え、徳川家康公の江戸入府後はその家臣(旗本)となり、喜多見領を安堵され姓を江戸から喜多見に改めました。
綱吉公治世の当主・喜多見重政は綱吉の寵臣として出世、約千石の旗本から加増を重ね、天和三年(1683年)ついに1万石の譜代大名となり喜多見藩を立藩しました。
のちに1万石の加増を受けて2万石。貞享二年(1685年)には側用人となるなど異例の出世を遂げたものの、元禄二年(1689年)2月に突如改易され大名の座を失いました。
改易の理由については諸説あり、定説はないようです。
江戸氏累代の菩提寺である慶元寺は、文治二年(1186年)江戸太郎重長が、江戸氏始祖江戸重継(重長の父)の菩提のため、のちの江戸城紅葉山のあたりに創建とされます。
創建当時は天台宗で、岩戸山 大沢院 東福寺と号しました。
以降、現地案内板、新編武蔵風土記稿、『多摩川三十四ヶ所観音霊場札所案内』などから寺歴を追ってみます。
上記のとおり、江戸氏の江戸退去を受けて康正二年(1451年)元喜多見(現・成城)に移転、次いで応仁二年(1468年)には喜多見の現在地に移転。
天文九年(1540年)、真蓮社空誉上人により中興開山、浄土宗に改宗して京・知恩院の末寺となり永劫山 華林院 慶元寺と号を改めました。
文禄二年(1593年)喜多見氏初代の若狭守勝忠が再建、寛永十三年(1635年)には三代将軍家光公より寺領十石の御朱印地を賜りました。
名刹だけに寺宝も多く、江戸・喜多見両氏の系図も蔵しています。
十夜法要(11月24日)と仏名会(12月31日)で奏される「(喜多見)双盤念仏」は相互に鉦を打ち鳴らし、節のついた念仏を唱えるもので、江戸時代に奥沢の九品仏浄真寺から伝えられたといいます。世田谷区指定無形民俗文化財(民俗芸能)です。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
所在は喜多見一丁目。交通の便はいまひとつですが、喜多見氷川神社や区立喜多見農業公園などがあり緑の多いところです。
参道脇には慶元寺幼稚園があり、園児の声でにぎやかです。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 銅像
山内入口は築地塀で本瓦葺の屋根を乗せています。その手前に寺号標。
ここから本堂にかけて木立の下の長い参道がつづき、その途中に狩衣姿の江戸太郎重長の銅像があります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
その先の山門は切妻屋根桟瓦葺の重厚な四脚門で、山号扁額を置いています。
江戸中期の宝暦五年(1755年)築で、かつては喜多見陣屋の門であったとも伝わります。
鐘楼堂も江戸中期の築とされています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は享保元年(1716年)築で、現存する世田谷区内の寺院本堂では最古の建物といわれています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。桟瓦葺ながら屋根の勾配や照りに勢いがあり、名刹ならではの風格を感じます。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に大ぶりな本蟇股。
向拝正面桟唐戸の上欄は菱狭間で、そのうえに寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂妻部
【写真 下(右)】 庫裡と本堂
妻側にまわると破風部は三連の斗栱のうえに虹梁、その上には笈形なしの大瓶束で、それを覆うように猪の目懸魚。
鬼板部は整った経の巻獅子口です。


【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 三重塔
墓地エリアには、江戸氏・喜多見氏累代の墓所があり、江戸重長追善供養のためといわれる五輪塔があります。
この喜多見家(江戸家)墓所は、世田谷区指定史跡となっています。
また、山内には喜多見古墳群のうち、慶元寺三号墳から六号墳までの4基の古墳が現存しています。
名族・江戸氏、そして短期間ではありますが大名・喜多見氏の菩提寺だけあって、随所に風格を感じる山内です。
御朱印は庫裡にて多摩川三十四観音霊場のものを拝受しました。
御本尊・阿弥陀如来の御朱印は不授与とのことです。
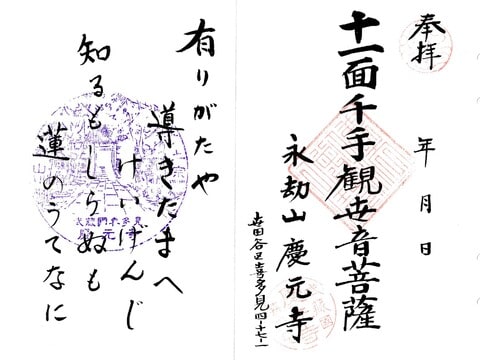
■ 多摩川三十四観音霊場の御朱印
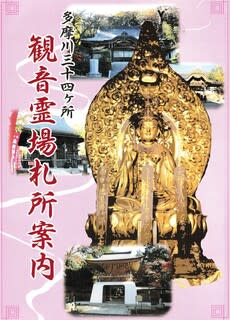

【写真 上(左)】 観音霊場の札所案内
【写真 下(右)】 観音霊場の専用納経帳
多摩川三十四観音霊場は、調布常演寺観音講が中心となり昭和8年に制定された多摩川中流域を巡る観音霊場です。
風情のある名刹が多く廻り応えがあり、原則として札所御朱印は常時授与されているようですが、当寺のように御朱印は観音霊場のもの(専用納経帳用用紙)のみで、御本尊御朱印は不授与のケースが目立ちます。
なお、近くに御鎮座の(喜多見)氷川神社も喜多見氏にゆかりをもちますが、別の機会にご紹介します。(御朱印授与されています。)
30.龍智山 毘廬遮那寺 常光院
〔中条藤次家長〕
公式Web
埼玉県熊谷市上中条1160
天台宗
御本尊:釈迦如来(三尊佛)
札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番
中条藤次家長は、八田知家の猶子となり、幾度か失脚の危機に見舞われながらもその地位を巧みに保ち、晩年まで幕府中枢の座を保ったという有力御家人です。
中条(ちゅうじょう)氏の出自は諸説ありますが、武蔵七党の横山党の流れとみる説が有力です。
横山党は、小野篁の子孫の小野孝泰が武蔵守として武蔵国に下向し、その子義孝が南多摩郡横山に拠り横山を称したのが始まりとされます。
義孝の末裔、成田太郎成綱は保元の乱では源義朝公に従い、頼朝の旗揚げには一族とともに馳せ参じました。
成綱の弟成尋は北埼玉郡中条保に拠って中条義勝房法橋(中条兼綱)を称し、石橋山の合戦にも加わったといいます。
成尋の子・家長も源平合戦、奥州合戦などに参戦して戦功をあげ、御家人としての地位を固めていきます。(源平合戦に「藤次家長」の名がみられます。)
家長の叔母(近衛局)は宇都宮宗綱に嫁いで八田知家を生んだといわれ、頼朝公の乳母もつとめたとされます。
八田知家はその縁から家長を養子とし、中条藤次家長を名乗らせました。
その際に本姓藤原氏(藤原北家道兼流)を称したといいます。
家長は有力者八田知家の後ろ盾もあって、一時は不遜な挙動も目立ったといいます。
建久元年(1190年)、頼朝公の許諾を得ずに右馬允に補任され、頼朝公の怒りを買って辞官しています。
建久六年(1195年)には毛呂季光と私闘を起こして公的行事を延期させ、頼朝公は養父知家を通じて家長に出仕停止を命じています。
ここまではかなりの暴れん坊だった可能性がありますが、これ以降はみずからの行いを悔い改めたとされ、建久六年(1195年)頼朝公上洛の随兵に召されています。
『吾妻鏡』では、中條藤次のほか中條平六という名もみられ、こちらは文治元年(1185年)十月廿四日の勝長壽院供養で「六御馬」の重責を担っていますが、家長との関係は不明です。
建仁三年(1203年)頼朝公を祀る法華堂の奉行。法華堂は頼朝公の公的な墓所とされていますから、こちらの奉行職はかなりの重職とみられます。
その後も政権内の権力闘争を巧みにかわし、嘉禄元年(1225年)評定衆設置の際にはその一員に任ぜられ、以降も幕政の中枢を占めて御成敗式目の策定にもかかわっています。
坂東武者にはめずらしく御成敗式目の策定に係わったということは、文官の才も当代一流のものがあったとみられます。
尾張国守護職にも任ぜられ、以降中条氏が数代世襲し、とくに高橋庄(猿投・挙母など)を中心に強く勢力を張りました。
室町時代には幕府内で地位を確保して評定衆をつとめ、家伝の剣法中条流を足利将軍に師範したと伝わります。
戦国期に入るとその勢力は漸減し、永禄年間(1558年-)、徳川家康、織田信長に相次いで攻められいかんともしがたく、ついに本拠の挙母城は落ちたとされます。
龍智山 常光院は中条家長が鎌倉に住んだため、かつての中条氏居館・中條館を寺とし、中条(條)氏の祖で祖父である中条常光などの菩提のため開基した寺院と伝わります。
公式Webおよび現地掲示に中条家長の出自・業績と併せ、由緒の記載があるので要点を抜粋引用します。
・長承元年(1132年)藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光が武蔵国司として下向、当地に公文所を建て、土地の豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。同年に中条館を築館。
・常光の孫の中條出羽守藤次家長は、若干16歳で石橋山の合戦時にはすでに頼朝公に扈従していて信任が厚かった。
・家長は評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺とし、祖父常光などの菩提を弔うため、比叡山から名僧金海法印を迎えて建久三年(1192年)に開基。
・開基以来延暦寺の直末で天台宗に属し、とくに梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章「梶竪一葉紋」を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至って寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇を与えられ、東比叡山の伴頭寺。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内まわり
熊谷市街の北東の利根川寄り、山内まわりに堀、石垣、土塀を構えて中世豪族の居館の趣きがあります。
参道庫裡入口に「県指定 中條氏舘跡 常光院」の石標。山内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。


【写真 上(左)】 史跡標
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 参道
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、門柱には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。見上げには山号扁額。
深い木立のなかつづく参道を辿ると本堂が見えてきます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺のどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。
正面が御本尊向拝、向かって左が「熊谷厄除大師」の二連向拝で、さらにそのよこが授与所です。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 「熊谷厄除大師」向拝
御本尊向拝は、軒下に向拝柱を構え、手前に寺紋「梶竪一葉紋」の向拝幕。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備の板蟇股にはめずらしく山号が刻まれていますが、現・山号とは異なるようです。
「熊谷厄除大師」の向拝にも「梶竪一葉紋」の向拝幕が懸けられていました。
山内は広く、いろいろと見どころがありますが長くなったので省略です。
こちらは「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度参拝がベターかもしれません。
なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)
本堂に御座します。

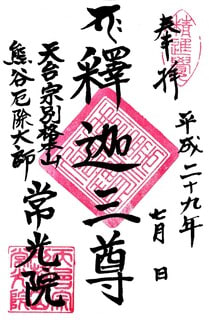
2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)
本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

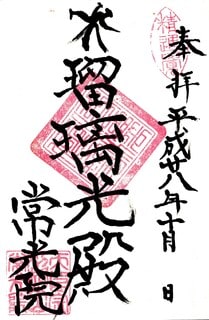
3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)
本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

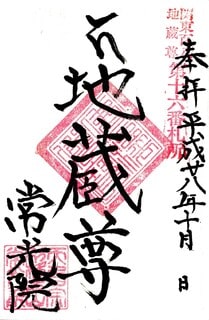
4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)
境内に露仏として奉安されています。

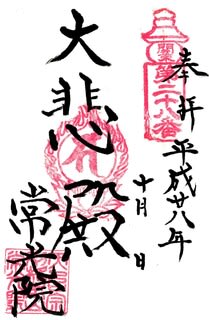
5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)
境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

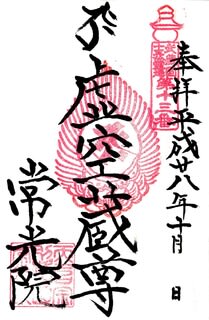
→ ■ 熊谷温泉 「熊谷温泉 湯楽の里」のレポ
31.礒明山 松岸寺
〔佐々木三郎盛綱〕
安中市Web資料
群馬県安中市磯部4-4-27
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:
佐々木氏は宇多源氏の名流で、近江国佐々木庄を地盤として勢力を蓄えました。
平安末期の当主、秀義は八幡太郎義家公の孫で、頼朝公の祖父為義公の息女を娶ったとされ、清和(河内)源氏とふかいつながりがありました。
保元の乱では秀義は義朝公に属して勝利、平治元年(1159年)の平治の乱でも義朝公に属したものの敗れ、縁を頼って奥州へと落ちのびる途中、相模国の渋谷重国に引き止められ、重国の息女を娶って此所に落ち着きました。
秀義には長男:定綱、次男:経高、三男:盛綱、四男:高綱、五男:義清などの優れた息子がおりました。
治承四年(1180年)頼朝公の旗揚げにあたり、平家方の大庭景親から頼朝公討伐の計画を聞き、急遽定綱を頼朝公に使わして危急を知らせ、定綱、経高、盛綱、高綱を頼朝公挙兵の援軍として向かわせて頼朝公の信任を得ました。
秀義の三男、盛綱は源為義の息女を母にもつという源家としては抜群の血筋で、一説には頼朝公の伊豆配流時代から仕えていたともされます。
Wikipediaには典拠不明ながら「治承4年(1180年)8月6日、平氏打倒を決意した頼朝の私室に一人呼ばれ、挙兵の計画を告げられる。この時に頼朝は『未だ口外せざるといえも、偏に汝を恃むに依って話す』と述べた。」とあり、旗揚げ前から頼朝公の信任厚かったことがうかがえます。
治承四年(1180年)8月の伊豆目代・山木兼隆館襲撃にも加わったとされています。
石橋山敗戦後はいったん渋谷館に逃れたもののふたたび鎌倉で頼朝公の許に参じ、富士川の戦いや佐竹氏討伐にも参加しています。
源平合戦では藤戸合戦(児島合戦)で範頼公麾下として奮戦、対岸の平行盛勢を前にわずか6騎で乗馬のまま海路を押し渡り、行盛軍を追い落としたと伝わります。
この戦いの戦後のいきさつは「藤戸」として能の演目のひとつとなりました。
弟の高綱も宇治川の戦いで梶原景季と先陣を争い、名馬「いけづき」とともに名を残しており、佐々木兄弟は華やかな戦歴に彩られています。
頼朝公館での双六の最中、盛綱の息子・信実が工藤祐経の額を石で打ち割るといういさかいが勃発。盛綱は頼朝公より信実追補の命を受けるも「信実はすでに出家し親子の縁を切った」としてこの上意を拒むという、なかなか骨のある対応をとっています。
それでも盛綱に特段のお咎めはなかったようですから、それだけ頼朝公の信任が厚かったのでしょう。
『吾妻鏡』によると、文治元年(1185年)十月廿四日の勝長壽院供養では「十御馬」という重責、建久元年(1190年)十一月七日の頼朝公上洛参院御供では「先陣随兵」、同月十一日の石淸水八幡宮御參にも供奉し、以降もしばしば『吾妻鏡』に記名されていることから一貫して主力御家人の地位にあったことがわかります。
建久六年(1195年)4月10日、東大寺供養参内供奉の折に兵衛尉に任官。
頼朝公逝去後の建久十年(1199年)3月、出家して西念と称しました。
備前国児島荘、越後国加地荘、上野国磯部などを領し、出家後は主に磯部郷に在ったようです。
出家後も武将としての働きを期待され、越後国鳥坂城の城資盛を激戦の末に破っています。
越後国加地荘では子孫が加地氏を称し、戦国時代までかなりの勢力を張りました。
また、備前国児島荘五流尊瀧院は修験道でも高い格式を誇る「児島修験」の本拠でしたが、五流尊瀧院とゆかりのある南北朝時代の南朝の忠臣・児島高徳は、盛綱の子・盛則の次男・重範の流れとする説もあるようです。
盛綱の領地であった上野国磯部の松岸寺には、佐々木盛綱夫妻の墓と伝わる五輪塔があり、県指定の重要文化財となっています。
非札所で情報があまりとれないのですが、「群馬県:歴史・観光・見所様」によると「平安時代の天暦六年(952年)に開かれたと伝わる古刹」のようです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山門鬼板
【写真 下(右)】 本堂-1
磯部温泉にもほど近い、中磯部の碓井川沿いにあります。
参道入口に寺号標。その先には塀つきの切妻屋根桟瓦葺の四脚門。
妻側に経の巻獅子口とその下に「松岸寺」の瓦板を掲げ、さらに下には渦巻き様の変わった形状の懸魚。
境内向かって右手が本堂。その右手の奥にかの五輪塔があります。本堂右手には庫裡。


【写真 上(左)】 本堂-2
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺。向拝柱のない禅刹らしいすっきりとした意匠。
向拝正面サッシュ扉のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 五輪塔
二基ある五輪塔は立派な覆屋のなかに安置され、横に建つ石碑には「佐々木盛綱古墳」とあります。
覆屋前の説明板には正応六年(1293年)造建とあります。
盛綱の没年は不明ですが、生年は仁平元年(1151年)と年代差があるので、墓所というより供養塔のようなものかもしれません。
こちらは、以前に一度参拝してご不在。
今回「ウクライナ難民支援御朱印」(令和4年4月8日~6月30日)で参拝して御朱印を拝受しました。。
札所ではないので、ご住職ご不在時には拝受できない可能性があります。

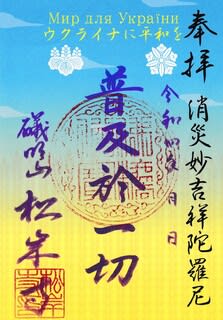
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 ウクライナ難民支援御朱印(限定)
→ 〔 温泉地巡り 〕 磯部温泉
32.勅使山 大光寺
〔勅使河原三郎有直〕
埼玉県上里町勅使河原1864
臨済宗円覚寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:円覚寺百観音霊場第49番
勅使河原氏は武蔵国七党のひとつ丹党の流れで、宣化天皇の子孫である多治比氏の後裔を称します。
丹党は神流川流域の児玉地方を本拠地とし、勅使河原氏も神流川右岸の現・上里町付近に拠りました。
秩父(丹)基房の長男直時を始祖とし、直時の孫三郎有直は御家人として『吾妻鏡』にその名がみえます。
上里町のWeb資料「上里町の中世」では、有直が範頼公・義経公麾下として六条河原合戦で木曽方の那波広純らと戦ったこと(平家物語九)、元暦元年(1184年)範頼公・義経公に追われて京都を脱出する木曽義仲を勅使河原有直・有則兄弟が追撃したこと(源平盛衰記)が紹介されています。
『吾妻鏡』によると、有直は文治元年(1185年)十月廿四日の南御堂(勝長壽院)供養供奉では「次随兵西方」、建久元年(1190年)十一月七日の頼朝公上洛参院では「先陣随兵」をつとめ、文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵にもその名がみえます。
埼玉県上里町の大光寺は勅使河原(権)三郎有直の創建と伝わる古刹です。
現地由緒書および「円覚寺百観音霊場納経帳」によると、建保三年(1215年)に勅使河原(権)三郎有直が創建、勧請開山は日本における臨済宗の開祖・栄西禅師です。
栄西禅師の入滅は京の建仁寺で建保三年(1215年)の夏。
栄西禅師は建久九年(1198年)以降に鎌倉に下向、正治二年(1200年)頼朝公一周忌の導師を務め、寿福寺住職に招聘という記録があります。
鎌倉にゆかりのふかい栄西禅師を、その没年に勧請ということでしょうか。
南北朝に入ると勅使河原直重(- 建武三年(1336年))は南朝方として新田義貞に従い上京、九州から進軍した足利尊氏軍を迎撃しましたが大渡で敗れ、次いで三条河原で奮戦するも後醍醐帝の比叡山への脱出を知ると悲嘆して羅城門近くで自刃したと伝わります。
一時廃れた大光寺は応永十八年(1411年)に現・伊勢崎市の泉龍寺・白崖宝生禅師により再興されたものの、天正十年(1582年)の神流川合戦により総門のみを残して焼失しました。
神流川合戦は上野厩橋城主滝川一益と武蔵鉢形城主北条氏邦・小田原城主北条氏直との戦いです。
上里町資料によると、滝川一益は甲斐の武田家滅亡後、信濃・上野の領国支配を任され関東管領として箕輪城、後に厩橋城(前橋市)に入城しました。
天正十年(1582年)6月、本能寺の変が勃発。一報を聞いた一益はまずは本国伊勢に向かおうとしました。
北条氏直は信長殺害の報を得ると鉢形城の北条氏邦を先方として神流川に陣を張り、滝川一益軍と数日にわたる激しい戦いとなりました。
大光寺の総門には、神流川合戦の矢の跡が当時のまま残されています。
大光寺の境内は勅使河原氏の館跡とも伝わります。
みどころも多く、総門(勅使門)、神流川の渡しの安全を祈念した見透燈籠、親子地蔵、石幢は上里町の有形文化財に指定されています。
毎年4月23日には勅使河原氏の慰霊祭でもある”蚕影山”が催され、植木市なども立って賑わいを見せるそうです。


【写真 上(左)】 総門
【写真 下(右)】 総門扁額
国道17号線の群馬県との境「神流川橋南」の交差点から脇道へ入り、高崎線の高架下をくぐった、神流川河畔にもほど近いところです。
総門は切妻屋根本瓦葺の風格ある四脚門で、山号扁額を掲げています。
総門手前に寺号標と「勅使河原氏館跡」の石標。
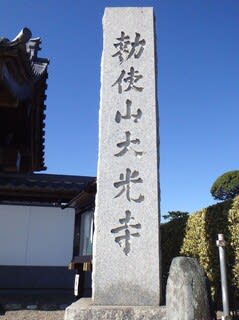

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内
広々とした山内、手前に立派な鐘楼とそのおくに本堂。
参道右手の百体観音は霊験あらたかにして篤い信仰があるとのこと。


【写真 上(左)】 円覚寺百観音霊場ののぼり
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造桟葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備には龍の彫刻を置いています。
向拝正面サッシュ扉のうえに寺号扁額を掲げます。
当山は栄西禅師直筆の扁額を蔵すとのことですが、こちらがその扁額かどうかは不明です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
こちらは円覚寺百観音霊場の札所なので手慣れたご対応です。
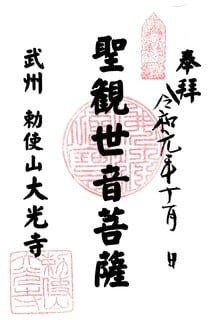
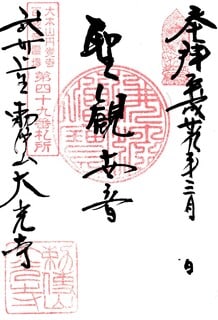
【写真 上(左)】 円覚寺百観音霊場 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 円覚寺百観音霊場 御朱印帳揮毫御朱印
→ ■ 神川温泉 「かんなの湯」のレポ
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5へつづく。
【 BGM 】
■ Whatcha' Gonna Do For Me - Average White Band (1980)
■ What Love Can Do - Island Band (1983)
■ Closer To You - Roby Duke (1984)
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
28.慈眼山 無量院 萬福寺 (つづき)
〔梶原平三景時〕
東京都大田区南馬込1-49-1
曹洞宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:江戸・東京四十四閻魔参り第19番、閻魔三拾遺第29番
--------
南馬込の禅刹、萬福寺。山内掲示の縁起書には以下のとおりあります。
「当寺は鎌倉時代の初期、建久年間(1190年頃)に梶原景時が将軍源頼朝の命により大檀那となり梶原家相伝の阿弥陀如来三尊仏を本尊として大井丸山と云う処に建立された。
元応二年(1320年)に火災にあい、景時の墓所のある馬込へ移され再建された。」
『新編武蔵風土記稿』(国会図書館DC)には、当山と梶原景時のかかわりについて詳細に記されています。
(同書では、景時の所領は多磨郡柚井領(現・八王子市)としており、じっさい、元(梶原)八王子八幡神社の由緒には、この地が梶原景時の所領(梶原屋敷)であったことが記されています。)
そのうえで「景時モシ一寺ヲモ建立セントセハ 其住所及ヒ所領ノ地ヲ置テ遠ク当所ヘ起立スヘケンヤ 寺ニ傳フル所イフカシキ事ナリ ヨリテ按ニ小田原北條家人梶原三河守 当寺ノ大檀那ニシテ此人ヲ萬福寺ト号セリ 此人当寺ヲ中興セシユヘニヨリ 梶原ノ家号ヨリ 誤テ平三景時カ開基トセシナラン」と辛辣な書き様ですが、「境内ニ建テタル梶原氏ノ碑陰ニ梶原三河守影時同子息助五郎影末云々」と山内の碑に”梶原三河守影時”の文字があることを認め、「其誤シモ又ユヘアルニ似タリ」としています。
景時の墓所(開基寺院)が、八王子の所領から通く離れた馬込の地にあることに疑問を呈しつつ、梶原家が当山の大旦那であることを含め、一定の所縁は認めているわけです。
一方、萬福寺の公式Webには、「建久年間(1190~99)大井村丸山の地に密教寺院として創建されました。開基は梶原平三景時公であったと伝えられています。元応2年(1320)火災にあい、第六代の梶原掃部助景嗣が居城とともに馬込へ移転したと伝えられます。」とあります。
これによれば、当地へ移転したのは梶原景時(六代)の子孫であり、それが正しいとすると当山は梶原景時の子孫の菩提寺であり、子孫が菩提のために先祖(景時)の墓所となすことは、あながち無理筋ではないような気もします。
また、『江戸名所図会巻二』の萬福寺の項には「相傳ふ、当寺は梶原平蔵景時、創立の梵宇なりと云ふ。霊碑ならびに墳墓あり。」とあります。
ただし注記に「(梶原平蔵)景時三河守に任ぜし事、古書に所見なし」として、北条家家臣の梶原三河守ないし、梶原助五郎の開創ではないかと記しています。
いずれにしても、仮に後世の付会があつたとしても梶原景時ゆかりの寺院として伝承されてきたことは間違いなく、景時ゆかりの見どころも多いのでこちらでご紹介します。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 するすみの像
高台の閑静な住宅地に風流な山内入口、どっしりと構える山門はおそらく茅葺き。
山門左手前には名馬「するすみ」の像。
磨墨(するすみ)は景時の嫡男・景季が頼朝公から賜った名馬で、『平家物語』の宇治川の先陣争いの段で登場します。
頼朝公お気に入りの郎党、佐々木四郎高綱も頼朝公から生食(いけづき)という名馬を下賜されていました。
宇治川をはさんで、対岸の木曽義仲軍と対峙した景季と高綱は、いずれも先駆けを狙っていました。
まずは磨墨に乗った景季が川に乗り入れ、六間ほどおくれて生食に乗った高綱が川入りして先陣争いを展開。
初動でおくれをとった高綱は、「梶原殿、この川は西国一の大河。貴殿の馬の腹帯が緩んでおる。締め直したまえ」と景季に声を掛けました。
これを聞いた景季は「それはそうだ」と馬を止め、腹帯を調べるとべつに異常はない。
その隙に高綱に先を越され、一番乗りを逃したという有名なくだりです。
名うての武将が腹帯を確かめずに先駆けとは疑問ですが、宇治川の川底には進撃よけの縄が張り巡らせられ、これを刀で絶ちつつ進撃したためにこの忠告が効いたとされています。
馬込は「磨墨」の生誕地との伝承があり、「磨墨」を供養する「するすみ塚」もあって当山が管理しています。
そのような所縁もあって、この「するすみ像」が建てられたのでしょう。
また、当山は梶原景時が戦場で用いたと伝わる馬具(区指定文化財)を所蔵しています。
だとすると「磨墨」につけられた可能性がありますが、山内の説明板には「『新編武蔵風土記稿』では北条氏直の家臣梶原三河守のものであろうと記す。」とありました。


【写真 上(左)】 閻魔堂
【写真 下(右)】 のぼり
山門をくぐって右手には閻魔堂。江戸時代から広く知られた閻魔様のようで、閻魔三拾遺第29番、江戸・東京四十四閻魔参り第19番の札所になっています。
「鎌倉の武将 梶原景時公菩提寺」ののぼりはためく階段をさらにのぼると無量門(中門)。
切妻屋根本瓦葺のすこぶる整った意匠の四脚門で、大棟には梶原氏の紋「丸に並び矢」が金色に輝いています。


【写真 上(左)】 無量門
【写真 下(右)】 鐘楼門
参道とは別に庫裡に向かう通用道があり、そちらには楼閣造りの鐘楼門があります。
無量門をくぐると門脇にお幸(身代り)地蔵尊。
右手には楼閣造りの摩尼輪堂で、一層の摩尼車には四天王と地蔵菩薩が御座。
二層には「磨墨観音」の扁額があるので名馬・磨墨ゆかりの観音様(馬頭観世音?)が奉安されているのかもしれません。


【写真 上(左)】 摩尼輪堂
【写真 下(右)】 磨墨観音の扁額
さらに進むと右手に子安観音と「当山開基 源頼朝随将 梶原平三景時公菩提寺」の石標。


【写真 上(左)】 山内案内図
【写真 下(右)】 「菩提寺」の石標
その先には鬼子母神。
当寺には重病の日蓮聖人が一夜参籠されたという伝承があり、参籠明けに聖人が奉納された持佛の鬼子母神というもので、当山相伝の守護神とのこと。
お像(御前立?)よこには「日蓮聖人参籠祈願之霊跡」の石碑が建っています。
鬼子母神縁起と日蓮聖人参籠のいきさつについては、公式Webに掲載されています。
馬込における曹洞宗と日蓮宗の関係が記された貴重な内容です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝-1


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂は入母屋造本瓦葺。正面手前に大がかりな千鳥破風の向拝を起こして風格があります。
水引虹梁両端に獅子二連の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に龍の彫刻。
格天井。正面硝子格子扉のうえに扁額が掲げられていますが、すみません、達筆すぎて筆者には読めません ^^;)
「慈眼 萬福」か?
御本尊の阿弥陀三尊は一光三尊の善光寺式で天文三年(1534年)以前の作とみられ、区の文化財に指定されています。(いまは光背は逸失とのこと)


【写真 上(左)】 「丸に並び矢」の天水鉢
【写真 下(右)】 レリーフ
本堂前の天水鉢には梶原氏の「丸に並び矢」の紋。本堂脇には景時ゆかりのレリーフと、梶原カラー満載です。
景時の墓所は本堂向かって左手の歴代住職の墓のよこにあります。
墓所は撮影しておりませんので、→こちら(公式Web)をご覧くださいませ。
当寺の隣地は室井犀星の旧宅で、「春の寺」で描かれた”うつくしきみ寺”は当寺のこと。
山内には犀星旧宅の銘石を譲り受け犀星の句を刻んだ句碑が安置されています。
御朱印は、雰囲気ある庫裡にて拝受しました。
こちらは3回参拝していますが、すべて異なる揮毫でしたので3体ともご紹介します。
うちひとつは、閻魔霊場へのご縁日(16日)の参拝です。
閻魔様の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印を拝受しています。
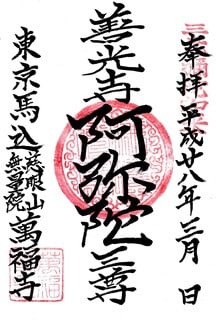
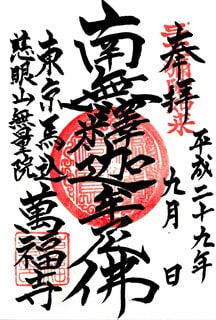
【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 宗派本尊・釈迦牟尼佛の御朱印
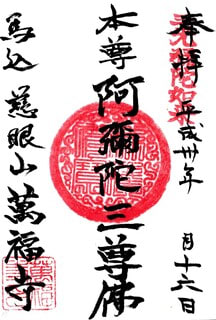
■ 江戸・東京四十四閻魔参り第19番の申告でいただいた御朱印
29.永劫山 華林院 慶元寺
〔江戸太郎重長〕
東京都世田谷区喜多見4-17-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:多摩川三十四観音霊場第4番、小田急武相三十三観音霊場第6番、玉川六阿弥陀霊場第2番、玉川北百番霊場第10番
江戸氏は桓武平氏良文流、秩父氏族の一流で豊島郡江戸郷(現在の千代田区~文京区)に拠って勢力を伸ばしました。
常陸國那珂郡(現・茨城県)には別流の江戸氏があるので、通常「武蔵江戸氏」として区別されます。
鎌倉幕府草創時の当主は第2代の江戸太郎重長で、当初は平家方に属していました。
治承四年(1180年)8月の衣笠城合戦では、同族の畠山重忠、河越重頼とともに三浦・衣笠城の三浦氏を攻め、三浦氏当主の三浦義明を討ち取っています。
この合戦の原因については所説ありますが、平家への義理や外聞からの挙兵を採る説はすくないようです。
こちらの系図(さくらいようへいブログ様掲載)をみると、城を攻めた畠山、河越、江戸氏はすべて秩父姓で、攻められた三浦氏は千葉姓です。
おなじ桓武平氏良文流とはいえ、支流同士で確執があったのかもしれません。
ちなみに桓武平氏良文流は秩父姓に畠山氏、小山田・稲毛氏、河越氏、江戸氏、渋谷氏、豊島氏、葛西氏。千葉姓に上総氏、千葉氏、村山氏、三浦氏、和田氏、岡崎氏と、多くの有力御家人を生み出した血統です。
『吾妻鏡』9月28日条には、頼朝公はこの強大な秩父一族の切り崩しを狙って重長に使いを送り、「大庭景親の催促を受け、石橋山で合戦に及んだのはやむを得ないが、以仁王の令旨の通り(頼朝公に)従うべきである。畠山重能・小山田有重が在京の今、武蔵国では汝(重長)が棟梁である。もっとも頼りにしているので近辺の武士達を率いて参上すべし」と伝えたとあります。
頼朝公が江戸重長の家柄と実力を「武蔵国の統領」ということばを使って認めていることがわかります。
その一方で、重長が景親に味方してなかなか自陣に参じないので、はやくから麾下となった秩父姓の葛西清重に、大井の要害に重長を誘い出し討ち取るよう命じています。(『吾妻鏡』9月29日条)
10月2日、頼朝軍が武蔵に入ると、4日、重長は畠山重忠、河越重頼とともに頼朝に帰順し、重長は頼朝公から武蔵の在庁官人や諸郡司を統率して国の諸雑事を沙汰する権限を与えられたといわれます。
(この権限は「武蔵国留守所総検校職」によるものとも思われますが、この職は河越氏の世襲という見方もあり、江戸氏がこれに任ぜられたかどうかは諸説ある模様。)
しかし、頼朝公の遅参への怒りは収まらず、重長の所領を没収して葛西清重に与えようとしました。
この話を受けた清重は「(秩父)一族の重長の所領を賜うのは私の意志にあらず。」と拒絶。
清重にも激怒した頼朝公は従わないなら清重の所領も没収すると脅しましたが、清重は「受けるべきものでないものを受けるのは義にあらず。」と峻拒。
清重の気骨に感じ入った頼朝公は、ついに重長を許したといいます。(『沙石集』)
以降、頼朝公の御家人となり文治五年(1189年)の奥州合戦には兄弟の親重とともに従軍、建久元年(1190年)秋の頼朝公上洛参院では後陣随兵をつとめています。
同族の河越重頼、畠山重忠は政権内部の勢力争いで滅ぼされましたが、江戸氏は巧みに命脈を保ち幕政に参画しています。
鎌倉幕府では無難に処世を図ったとみられる江戸氏ですが、それ以降は幾多の波乱に見舞われます。
「鎌倉殿の13人」を離れますが、江戸氏の菩提寺・慶元寺が世田谷にあることも含めて関係しますので、しばらく辿ってみます。
なお、江戸氏はすでに鎌倉期から宗家の武蔵江戸氏と庶流の浅草江戸氏の系譜が錯綜したともいわれますが、これにかかわると煩雑になるので割愛します。
ともかくも、江戸氏は江戸郷の所領を保って室町時代に入りました。
南北朝では家内で南北に分かれてこれをしのぎましたが、応安元年(1368年)、運命の武蔵平一揆を迎えます。
これは、秩父氏一族、相模の中村氏一族などの平氏を中心とした国人がおこした一揆で、関東管領・上杉憲顕が上洛した隙を狙い、河越直重以下、高坂氏、豊島氏、江戸氏、高山氏、古屋谷氏、仙波氏、山口氏、金子氏など武蔵の武士が河越館に拠り、下野の宇都宮氏、越後の新田氏などと連携したもの。
上杉憲顕は京で室町幕府を味方にし、足利基氏の後を継いだ鎌倉公方・足利氏満を擁して関東入りし河越に出兵。一揆は鎮圧されました。
戦に敗れた河越直重一党は南朝の北畠顕能を頼り伊勢国へ敗走し、領地はすべて没収され、関係した武将も領地を削られ没落しました。
その例にもれず、武蔵(江戸)宗家の江戸氏も没落しています。
以降、江戸の地には太田道灌が進出し、宗家江戸氏はこれに対抗できずに江戸郷を退去して世田谷木田見(喜多見)へと移住。
長禄元年(1457年)春には、太田道灌が江戸城を築いたと伝わります。
江戸氏は、鎌倉時代からすでに新恩として喜多見を領していたという説があります。
家勢が衰えた江戸氏が喜多見の地にやすやすと新領地を得たというのは無理があり、やはりなんらかの拠点があって、そこに退去したとみるのが自然です。
(「城郭図鑑」様Webに典拠は不明ですが「鎌倉時代には江戸武重が木田見次郎と名乗って木田見郷を領有しており、このとき既に江戸氏と喜多見の地には関係ができていたことが窺える。」という記事がありました。)
喜多見に移った宗家江戸氏は御北条氏の将、世田谷城主・吉良氏の家臣として仕え、徳川家康公の江戸入府後はその家臣(旗本)となり、喜多見領を安堵され姓を江戸から喜多見に改めました。
綱吉公治世の当主・喜多見重政は綱吉の寵臣として出世、約千石の旗本から加増を重ね、天和三年(1683年)ついに1万石の譜代大名となり喜多見藩を立藩しました。
のちに1万石の加増を受けて2万石。貞享二年(1685年)には側用人となるなど異例の出世を遂げたものの、元禄二年(1689年)2月に突如改易され大名の座を失いました。
改易の理由については諸説あり、定説はないようです。
江戸氏累代の菩提寺である慶元寺は、文治二年(1186年)江戸太郎重長が、江戸氏始祖江戸重継(重長の父)の菩提のため、のちの江戸城紅葉山のあたりに創建とされます。
創建当時は天台宗で、岩戸山 大沢院 東福寺と号しました。
以降、現地案内板、新編武蔵風土記稿、『多摩川三十四ヶ所観音霊場札所案内』などから寺歴を追ってみます。
上記のとおり、江戸氏の江戸退去を受けて康正二年(1451年)元喜多見(現・成城)に移転、次いで応仁二年(1468年)には喜多見の現在地に移転。
天文九年(1540年)、真蓮社空誉上人により中興開山、浄土宗に改宗して京・知恩院の末寺となり永劫山 華林院 慶元寺と号を改めました。
文禄二年(1593年)喜多見氏初代の若狭守勝忠が再建、寛永十三年(1635年)には三代将軍家光公より寺領十石の御朱印地を賜りました。
名刹だけに寺宝も多く、江戸・喜多見両氏の系図も蔵しています。
十夜法要(11月24日)と仏名会(12月31日)で奏される「(喜多見)双盤念仏」は相互に鉦を打ち鳴らし、節のついた念仏を唱えるもので、江戸時代に奥沢の九品仏浄真寺から伝えられたといいます。世田谷区指定無形民俗文化財(民俗芸能)です。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
所在は喜多見一丁目。交通の便はいまひとつですが、喜多見氷川神社や区立喜多見農業公園などがあり緑の多いところです。
参道脇には慶元寺幼稚園があり、園児の声でにぎやかです。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 銅像
山内入口は築地塀で本瓦葺の屋根を乗せています。その手前に寺号標。
ここから本堂にかけて木立の下の長い参道がつづき、その途中に狩衣姿の江戸太郎重長の銅像があります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
その先の山門は切妻屋根桟瓦葺の重厚な四脚門で、山号扁額を置いています。
江戸中期の宝暦五年(1755年)築で、かつては喜多見陣屋の門であったとも伝わります。
鐘楼堂も江戸中期の築とされています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は享保元年(1716年)築で、現存する世田谷区内の寺院本堂では最古の建物といわれています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。桟瓦葺ながら屋根の勾配や照りに勢いがあり、名刹ならではの風格を感じます。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に大ぶりな本蟇股。
向拝正面桟唐戸の上欄は菱狭間で、そのうえに寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂妻部
【写真 下(右)】 庫裡と本堂
妻側にまわると破風部は三連の斗栱のうえに虹梁、その上には笈形なしの大瓶束で、それを覆うように猪の目懸魚。
鬼板部は整った経の巻獅子口です。


【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 三重塔
墓地エリアには、江戸氏・喜多見氏累代の墓所があり、江戸重長追善供養のためといわれる五輪塔があります。
この喜多見家(江戸家)墓所は、世田谷区指定史跡となっています。
また、山内には喜多見古墳群のうち、慶元寺三号墳から六号墳までの4基の古墳が現存しています。
名族・江戸氏、そして短期間ではありますが大名・喜多見氏の菩提寺だけあって、随所に風格を感じる山内です。
御朱印は庫裡にて多摩川三十四観音霊場のものを拝受しました。
御本尊・阿弥陀如来の御朱印は不授与とのことです。
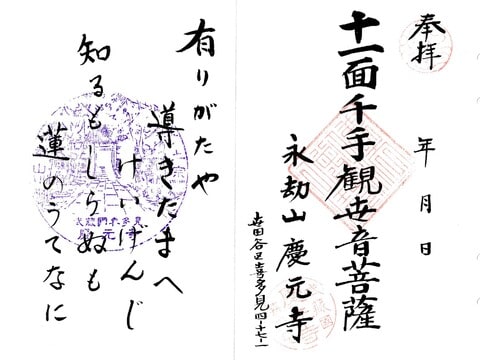
■ 多摩川三十四観音霊場の御朱印
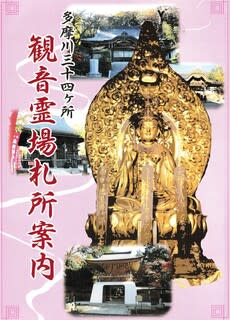

【写真 上(左)】 観音霊場の札所案内
【写真 下(右)】 観音霊場の専用納経帳
多摩川三十四観音霊場は、調布常演寺観音講が中心となり昭和8年に制定された多摩川中流域を巡る観音霊場です。
風情のある名刹が多く廻り応えがあり、原則として札所御朱印は常時授与されているようですが、当寺のように御朱印は観音霊場のもの(専用納経帳用用紙)のみで、御本尊御朱印は不授与のケースが目立ちます。
なお、近くに御鎮座の(喜多見)氷川神社も喜多見氏にゆかりをもちますが、別の機会にご紹介します。(御朱印授与されています。)
30.龍智山 毘廬遮那寺 常光院
〔中条藤次家長〕
公式Web
埼玉県熊谷市上中条1160
天台宗
御本尊:釈迦如来(三尊佛)
札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番
中条藤次家長は、八田知家の猶子となり、幾度か失脚の危機に見舞われながらもその地位を巧みに保ち、晩年まで幕府中枢の座を保ったという有力御家人です。
中条(ちゅうじょう)氏の出自は諸説ありますが、武蔵七党の横山党の流れとみる説が有力です。
横山党は、小野篁の子孫の小野孝泰が武蔵守として武蔵国に下向し、その子義孝が南多摩郡横山に拠り横山を称したのが始まりとされます。
義孝の末裔、成田太郎成綱は保元の乱では源義朝公に従い、頼朝の旗揚げには一族とともに馳せ参じました。
成綱の弟成尋は北埼玉郡中条保に拠って中条義勝房法橋(中条兼綱)を称し、石橋山の合戦にも加わったといいます。
成尋の子・家長も源平合戦、奥州合戦などに参戦して戦功をあげ、御家人としての地位を固めていきます。(源平合戦に「藤次家長」の名がみられます。)
家長の叔母(近衛局)は宇都宮宗綱に嫁いで八田知家を生んだといわれ、頼朝公の乳母もつとめたとされます。
八田知家はその縁から家長を養子とし、中条藤次家長を名乗らせました。
その際に本姓藤原氏(藤原北家道兼流)を称したといいます。
家長は有力者八田知家の後ろ盾もあって、一時は不遜な挙動も目立ったといいます。
建久元年(1190年)、頼朝公の許諾を得ずに右馬允に補任され、頼朝公の怒りを買って辞官しています。
建久六年(1195年)には毛呂季光と私闘を起こして公的行事を延期させ、頼朝公は養父知家を通じて家長に出仕停止を命じています。
ここまではかなりの暴れん坊だった可能性がありますが、これ以降はみずからの行いを悔い改めたとされ、建久六年(1195年)頼朝公上洛の随兵に召されています。
『吾妻鏡』では、中條藤次のほか中條平六という名もみられ、こちらは文治元年(1185年)十月廿四日の勝長壽院供養で「六御馬」の重責を担っていますが、家長との関係は不明です。
建仁三年(1203年)頼朝公を祀る法華堂の奉行。法華堂は頼朝公の公的な墓所とされていますから、こちらの奉行職はかなりの重職とみられます。
その後も政権内の権力闘争を巧みにかわし、嘉禄元年(1225年)評定衆設置の際にはその一員に任ぜられ、以降も幕政の中枢を占めて御成敗式目の策定にもかかわっています。
坂東武者にはめずらしく御成敗式目の策定に係わったということは、文官の才も当代一流のものがあったとみられます。
尾張国守護職にも任ぜられ、以降中条氏が数代世襲し、とくに高橋庄(猿投・挙母など)を中心に強く勢力を張りました。
室町時代には幕府内で地位を確保して評定衆をつとめ、家伝の剣法中条流を足利将軍に師範したと伝わります。
戦国期に入るとその勢力は漸減し、永禄年間(1558年-)、徳川家康、織田信長に相次いで攻められいかんともしがたく、ついに本拠の挙母城は落ちたとされます。
龍智山 常光院は中条家長が鎌倉に住んだため、かつての中条氏居館・中條館を寺とし、中条(條)氏の祖で祖父である中条常光などの菩提のため開基した寺院と伝わります。
公式Webおよび現地掲示に中条家長の出自・業績と併せ、由緒の記載があるので要点を抜粋引用します。
・長承元年(1132年)藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光が武蔵国司として下向、当地に公文所を建て、土地の豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。同年に中条館を築館。
・常光の孫の中條出羽守藤次家長は、若干16歳で石橋山の合戦時にはすでに頼朝公に扈従していて信任が厚かった。
・家長は評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺とし、祖父常光などの菩提を弔うため、比叡山から名僧金海法印を迎えて建久三年(1192年)に開基。
・開基以来延暦寺の直末で天台宗に属し、とくに梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章「梶竪一葉紋」を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至って寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇を与えられ、東比叡山の伴頭寺。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内まわり
熊谷市街の北東の利根川寄り、山内まわりに堀、石垣、土塀を構えて中世豪族の居館の趣きがあります。
参道庫裡入口に「県指定 中條氏舘跡 常光院」の石標。山内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。


【写真 上(左)】 史跡標
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 参道
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、門柱には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。見上げには山号扁額。
深い木立のなかつづく参道を辿ると本堂が見えてきます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺のどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。
正面が御本尊向拝、向かって左が「熊谷厄除大師」の二連向拝で、さらにそのよこが授与所です。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 「熊谷厄除大師」向拝
御本尊向拝は、軒下に向拝柱を構え、手前に寺紋「梶竪一葉紋」の向拝幕。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備の板蟇股にはめずらしく山号が刻まれていますが、現・山号とは異なるようです。
「熊谷厄除大師」の向拝にも「梶竪一葉紋」の向拝幕が懸けられていました。
山内は広く、いろいろと見どころがありますが長くなったので省略です。
こちらは「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度参拝がベターかもしれません。
なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)
本堂に御座します。

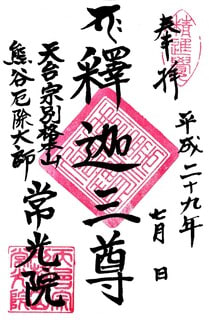
2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)
本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

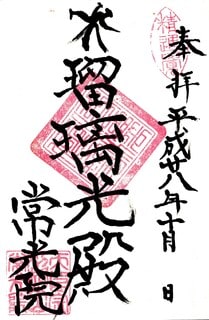
3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)
本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

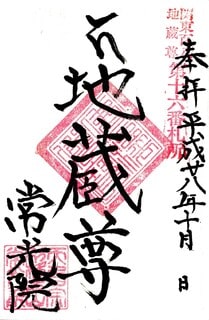
4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)
境内に露仏として奉安されています。

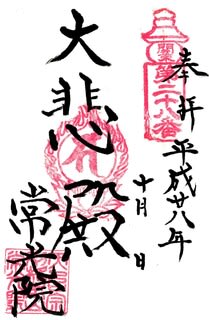
5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)
境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

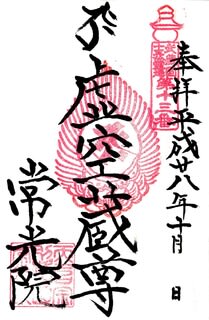
→ ■ 熊谷温泉 「熊谷温泉 湯楽の里」のレポ
31.礒明山 松岸寺
〔佐々木三郎盛綱〕
安中市Web資料
群馬県安中市磯部4-4-27
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:
佐々木氏は宇多源氏の名流で、近江国佐々木庄を地盤として勢力を蓄えました。
平安末期の当主、秀義は八幡太郎義家公の孫で、頼朝公の祖父為義公の息女を娶ったとされ、清和(河内)源氏とふかいつながりがありました。
保元の乱では秀義は義朝公に属して勝利、平治元年(1159年)の平治の乱でも義朝公に属したものの敗れ、縁を頼って奥州へと落ちのびる途中、相模国の渋谷重国に引き止められ、重国の息女を娶って此所に落ち着きました。
秀義には長男:定綱、次男:経高、三男:盛綱、四男:高綱、五男:義清などの優れた息子がおりました。
治承四年(1180年)頼朝公の旗揚げにあたり、平家方の大庭景親から頼朝公討伐の計画を聞き、急遽定綱を頼朝公に使わして危急を知らせ、定綱、経高、盛綱、高綱を頼朝公挙兵の援軍として向かわせて頼朝公の信任を得ました。
秀義の三男、盛綱は源為義の息女を母にもつという源家としては抜群の血筋で、一説には頼朝公の伊豆配流時代から仕えていたともされます。
Wikipediaには典拠不明ながら「治承4年(1180年)8月6日、平氏打倒を決意した頼朝の私室に一人呼ばれ、挙兵の計画を告げられる。この時に頼朝は『未だ口外せざるといえも、偏に汝を恃むに依って話す』と述べた。」とあり、旗揚げ前から頼朝公の信任厚かったことがうかがえます。
治承四年(1180年)8月の伊豆目代・山木兼隆館襲撃にも加わったとされています。
石橋山敗戦後はいったん渋谷館に逃れたもののふたたび鎌倉で頼朝公の許に参じ、富士川の戦いや佐竹氏討伐にも参加しています。
源平合戦では藤戸合戦(児島合戦)で範頼公麾下として奮戦、対岸の平行盛勢を前にわずか6騎で乗馬のまま海路を押し渡り、行盛軍を追い落としたと伝わります。
この戦いの戦後のいきさつは「藤戸」として能の演目のひとつとなりました。
弟の高綱も宇治川の戦いで梶原景季と先陣を争い、名馬「いけづき」とともに名を残しており、佐々木兄弟は華やかな戦歴に彩られています。
頼朝公館での双六の最中、盛綱の息子・信実が工藤祐経の額を石で打ち割るといういさかいが勃発。盛綱は頼朝公より信実追補の命を受けるも「信実はすでに出家し親子の縁を切った」としてこの上意を拒むという、なかなか骨のある対応をとっています。
それでも盛綱に特段のお咎めはなかったようですから、それだけ頼朝公の信任が厚かったのでしょう。
『吾妻鏡』によると、文治元年(1185年)十月廿四日の勝長壽院供養では「十御馬」という重責、建久元年(1190年)十一月七日の頼朝公上洛参院御供では「先陣随兵」、同月十一日の石淸水八幡宮御參にも供奉し、以降もしばしば『吾妻鏡』に記名されていることから一貫して主力御家人の地位にあったことがわかります。
建久六年(1195年)4月10日、東大寺供養参内供奉の折に兵衛尉に任官。
頼朝公逝去後の建久十年(1199年)3月、出家して西念と称しました。
備前国児島荘、越後国加地荘、上野国磯部などを領し、出家後は主に磯部郷に在ったようです。
出家後も武将としての働きを期待され、越後国鳥坂城の城資盛を激戦の末に破っています。
越後国加地荘では子孫が加地氏を称し、戦国時代までかなりの勢力を張りました。
また、備前国児島荘五流尊瀧院は修験道でも高い格式を誇る「児島修験」の本拠でしたが、五流尊瀧院とゆかりのある南北朝時代の南朝の忠臣・児島高徳は、盛綱の子・盛則の次男・重範の流れとする説もあるようです。
盛綱の領地であった上野国磯部の松岸寺には、佐々木盛綱夫妻の墓と伝わる五輪塔があり、県指定の重要文化財となっています。
非札所で情報があまりとれないのですが、「群馬県:歴史・観光・見所様」によると「平安時代の天暦六年(952年)に開かれたと伝わる古刹」のようです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山門鬼板
【写真 下(右)】 本堂-1
磯部温泉にもほど近い、中磯部の碓井川沿いにあります。
参道入口に寺号標。その先には塀つきの切妻屋根桟瓦葺の四脚門。
妻側に経の巻獅子口とその下に「松岸寺」の瓦板を掲げ、さらに下には渦巻き様の変わった形状の懸魚。
境内向かって右手が本堂。その右手の奥にかの五輪塔があります。本堂右手には庫裡。


【写真 上(左)】 本堂-2
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺。向拝柱のない禅刹らしいすっきりとした意匠。
向拝正面サッシュ扉のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 五輪塔
二基ある五輪塔は立派な覆屋のなかに安置され、横に建つ石碑には「佐々木盛綱古墳」とあります。
覆屋前の説明板には正応六年(1293年)造建とあります。
盛綱の没年は不明ですが、生年は仁平元年(1151年)と年代差があるので、墓所というより供養塔のようなものかもしれません。
こちらは、以前に一度参拝してご不在。
今回「ウクライナ難民支援御朱印」(令和4年4月8日~6月30日)で参拝して御朱印を拝受しました。。
札所ではないので、ご住職ご不在時には拝受できない可能性があります。

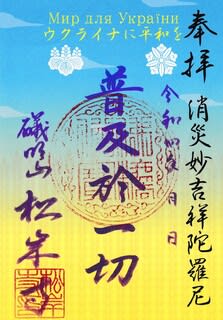
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 ウクライナ難民支援御朱印(限定)
→ 〔 温泉地巡り 〕 磯部温泉
32.勅使山 大光寺
〔勅使河原三郎有直〕
埼玉県上里町勅使河原1864
臨済宗円覚寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:円覚寺百観音霊場第49番
勅使河原氏は武蔵国七党のひとつ丹党の流れで、宣化天皇の子孫である多治比氏の後裔を称します。
丹党は神流川流域の児玉地方を本拠地とし、勅使河原氏も神流川右岸の現・上里町付近に拠りました。
秩父(丹)基房の長男直時を始祖とし、直時の孫三郎有直は御家人として『吾妻鏡』にその名がみえます。
上里町のWeb資料「上里町の中世」では、有直が範頼公・義経公麾下として六条河原合戦で木曽方の那波広純らと戦ったこと(平家物語九)、元暦元年(1184年)範頼公・義経公に追われて京都を脱出する木曽義仲を勅使河原有直・有則兄弟が追撃したこと(源平盛衰記)が紹介されています。
『吾妻鏡』によると、有直は文治元年(1185年)十月廿四日の南御堂(勝長壽院)供養供奉では「次随兵西方」、建久元年(1190年)十一月七日の頼朝公上洛参院では「先陣随兵」をつとめ、文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵にもその名がみえます。
埼玉県上里町の大光寺は勅使河原(権)三郎有直の創建と伝わる古刹です。
現地由緒書および「円覚寺百観音霊場納経帳」によると、建保三年(1215年)に勅使河原(権)三郎有直が創建、勧請開山は日本における臨済宗の開祖・栄西禅師です。
栄西禅師の入滅は京の建仁寺で建保三年(1215年)の夏。
栄西禅師は建久九年(1198年)以降に鎌倉に下向、正治二年(1200年)頼朝公一周忌の導師を務め、寿福寺住職に招聘という記録があります。
鎌倉にゆかりのふかい栄西禅師を、その没年に勧請ということでしょうか。
南北朝に入ると勅使河原直重(- 建武三年(1336年))は南朝方として新田義貞に従い上京、九州から進軍した足利尊氏軍を迎撃しましたが大渡で敗れ、次いで三条河原で奮戦するも後醍醐帝の比叡山への脱出を知ると悲嘆して羅城門近くで自刃したと伝わります。
一時廃れた大光寺は応永十八年(1411年)に現・伊勢崎市の泉龍寺・白崖宝生禅師により再興されたものの、天正十年(1582年)の神流川合戦により総門のみを残して焼失しました。
神流川合戦は上野厩橋城主滝川一益と武蔵鉢形城主北条氏邦・小田原城主北条氏直との戦いです。
上里町資料によると、滝川一益は甲斐の武田家滅亡後、信濃・上野の領国支配を任され関東管領として箕輪城、後に厩橋城(前橋市)に入城しました。
天正十年(1582年)6月、本能寺の変が勃発。一報を聞いた一益はまずは本国伊勢に向かおうとしました。
北条氏直は信長殺害の報を得ると鉢形城の北条氏邦を先方として神流川に陣を張り、滝川一益軍と数日にわたる激しい戦いとなりました。
大光寺の総門には、神流川合戦の矢の跡が当時のまま残されています。
大光寺の境内は勅使河原氏の館跡とも伝わります。
みどころも多く、総門(勅使門)、神流川の渡しの安全を祈念した見透燈籠、親子地蔵、石幢は上里町の有形文化財に指定されています。
毎年4月23日には勅使河原氏の慰霊祭でもある”蚕影山”が催され、植木市なども立って賑わいを見せるそうです。


【写真 上(左)】 総門
【写真 下(右)】 総門扁額
国道17号線の群馬県との境「神流川橋南」の交差点から脇道へ入り、高崎線の高架下をくぐった、神流川河畔にもほど近いところです。
総門は切妻屋根本瓦葺の風格ある四脚門で、山号扁額を掲げています。
総門手前に寺号標と「勅使河原氏館跡」の石標。
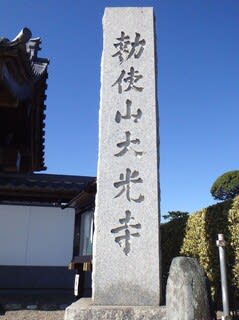

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内
広々とした山内、手前に立派な鐘楼とそのおくに本堂。
参道右手の百体観音は霊験あらたかにして篤い信仰があるとのこと。


【写真 上(左)】 円覚寺百観音霊場ののぼり
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造桟葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備には龍の彫刻を置いています。
向拝正面サッシュ扉のうえに寺号扁額を掲げます。
当山は栄西禅師直筆の扁額を蔵すとのことですが、こちらがその扁額かどうかは不明です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
こちらは円覚寺百観音霊場の札所なので手慣れたご対応です。
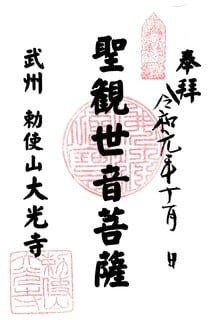
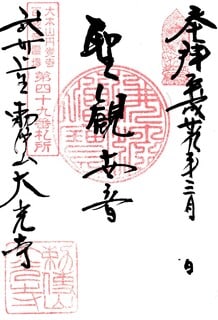
【写真 上(左)】 円覚寺百観音霊場 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 円覚寺百観音霊場 御朱印帳揮毫御朱印
→ ■ 神川温泉 「かんなの湯」のレポ
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5へつづく。
【 BGM 】
■ Whatcha' Gonna Do For Me - Average White Band (1980)
■ What Love Can Do - Island Band (1983)
■ Closer To You - Roby Duke (1984)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
文字数オーバーしたので、Vol.3をつくりました。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
21.冷水山 清浄土院 長徳寺
〔仙波氏〕
埼玉県川越市仙波町3-31-23
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第27番
武蔵七党、村山党の一族として知られる仙波氏。
武蔵山口氏の祖、山口家継の子・家信が川越市仙波町を本貫(名字の地)とし、仙波氏を名乗ったのが始祖とされます。
武蔵七党には多くの系図が残り、錯綜しているので系譜を辿りにくくなっていますが、これを精緻に整理された難波田城資料館の早坂廣人氏の『武蔵七党系図(村山党系図)と難波田氏』という文献がWeb上で公開されています。
この文献には、仙波(右馬允)安行、仙波盛直、仙波(入道)安家、仙波(太郎)康高、仙波邏曜、仙波(太(大)郎)信恒、仙波(二郎入道)時綱の名がリストされています。
一方、『「鶴ヶ島町史」通史編』(鶴ヶ島市立図書館/鶴ヶ島市デジタル郷土資料)の第六節には、「仙波氏については、山口六郎家俊の弟家信は仙波(川越市)に住んで仙波七郎といい仙波氏の祖となるが、この家信は保元の乱に義朝に従っている。そして、彼の長子仙波平太信平、次子の仙波二郎安家は『吾妻鏡』に、頼朝の随兵として名を見せる。また、承久(じょうきゅう)の乱の宇治川合戦で負傷者の中に、仙波太郎、仙波左衛門尉、そして戦死者の中に仙波弥次郎がいる。それぞれ信平の子信恒、信平の弟三郎左衛門尉家行、そして安家の次子弥二郎光時と推定される。ただし『武蔵七党系図』には、信恒、家行ともに宇治川合戦で溺死したと註記してある。どちらが正しいかは分らない。」とあります。
これに、川越について詳細な分析をされている『川越雑記帳』(川越原人氏)の「仙波氏」の頁の内容を併せると、
・仙波氏の祖・家信の長子・仙波平太信平 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵
・家信の次子・仙波二郎安家 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵
・家信の子・(三郎左衛門尉)ないし(二郎)家行 → 『吾妻鏡』 文治元年頼朝随兵
・信平の子・仙波太郎(信恒) → 『吾妻鏡』 建久六年将軍家随兵
また、承久三年(1221年)6月の承久の乱の宇治橋合戦で負傷・戦死したのは(『吾妻鏡』)、
・仙波太郎(信恒?)
・仙波左衛門尉(家行?)
・仙波弥次郎(安家の次子・弥二郎光時?)
と推測されます。
これだけの名が『吾妻鏡』に記載されている以上、御家人の家柄として相応のポジションを確保していたことは間違いないかと思われます。
また、宇治橋合戦で負傷・戦死者が多いのは、この戦さで仙波一族が前線で奮戦したことを物語っています。
仙波氏の居館として、仙波町堀ノ内の「仙波氏館」(市指定史跡)が知られています。
ここは長徳寺に近接し、長徳寺を館址とする資料もあります。
長徳寺山内の説明書『仙波氏舘跡』(川越市教育委員会)には「大仙波の長徳寺は天台宗の末寺で、『新編武蔵風土記稿』によると『永承甲戌(一五一四)天台沙門實海』の名が古い過去帳に記されていたという。境内に、もと若干の土塁と堀があったといわれ、小字に『堀の内』という地名も残っているところから、仙波氏の館跡だと推定されている。『保元物語』に仙波七郎高家、『吾妻鏡』に仙波平太・同太郎・次郎・弥三郎・左衛門尉などの名がみえ、これらは在名をもって氏としたことが考えられる。ただし郷庄の唱えではこの大仙波村は山田庄に属し、仙波庄を唱うる村はこれより南部の市内高階地区と上福岡・大井・富士見・三芳の各市町に拡がっているものが多く、仙波氏の支配した荘園と考えられる。」とあり、現・長徳寺山内を仙波氏舘跡に比定しています。
『平成 小江戸川越 古寺巡礼』(信州信濃浄土出版会)には、開山は慈覚大師円仁で山号は長徳元年(995年)朝廷からの下賜。中興開山は永正十一年(1514年)喜多院第十四世実海大僧正とあります。
山内の観音堂に御座す白衣観世音菩薩は、「川越観音」として信仰を集めています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額

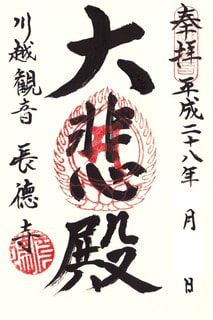
【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 長徳寺の御朱印
※Webでは御本尊阿弥陀如来の御朱印がみつかりますが、授与されていないそうです。
22.阿毘盧山 密乗院 大日寺
〔千葉介常胤〕
公式Web
千葉県千葉市稲毛区轟町2-1-27
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:千葉寺八十八所霊場第3番
頼朝公の挙兵・関東平定の功労者として外せない御家人に千葉介常胤がいます。
千葉氏は桓武平氏良文流、坂東八平氏(千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏)を代表する名族として知られています。
律令制のもとの親王任国(親王が国守に任じられた国。常陸国、上総国、上野国の3国ですべて「大国」)の国守(太守)は親王で、次官として「介」(すけ)がおかれ、実質的な国の長官は「介」ないし「権介」であったとされます。
常陸国の「介」には平家盛、頼盛、経盛、教盛など伊勢平氏(いわゆる「平家」)が任ぜられました。上総国の「介」は早くから坂東に下向した桓武平氏良文流の上総氏、下総国は親王任国ではありませんが、こちらも実質的な長官は「介」ないし「権介」で、良文流の千葉氏が占めて”千葉介”を称し、有力在庁官人としてともに勢力を張りました。
もうひとつの親王任国、上野国(現・群馬県)には、平良文公や千葉氏の嫡流・平(千葉)常将公にまつわる伝承が多く残ります。
(ご参考→『榛名山南東麓の千葉氏伝承』)
千葉氏の妙見信仰にもかかわる逸話が伝わるので、少しく寄り道してみます。
千葉氏の妙見信仰のはじまりについては諸説がありますが、千葉市史のなかに、上野国の妙見菩薩にちなむとする記載がありました。(『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』(千葉市地域情報デジタルアーカイブ))
これによると、桓武天皇四世、平高望公の子・平良文公は武蔵国大里郡を本拠とし、良文公と平将門公が結んで上野国に攻め入り、上野国府中花園の村の染谷川で平国香公の大軍と戦った際に示現された妙見菩薩(花園妙見・羊妙見)が、その信仰のはじまりだというのです。
「染谷川の戦い」は、伊勢平氏の祖・国香公と良文流の祖・良文公、そして関東の覇者・将門公という超大物が相戦うスケール感あふれる戦いですが、複数の伝承があるようで、国香公と将門公の対峙は明らかですが、良文公がどちらについたかが定かでありません。(そもそも史実かどうかも不明)
しかし、この戦いで花園妙見の加護を得た将門公と良文公が実質的な勝利を得、国香公は撤収したとされています。
これに類する逸話は『源平闘諍録』にも記されており、千葉市史はこれにもとづいて構成されたのかもしれません。
また、良文公の嫡流、平(千葉)常将公も、上野国の榛名山麓に多くの逸話を残しています。
上野国に大きな所領を得たわけでもない良文公や常将公の足跡が上野国にのこるのは、やはり房総平氏の妙見信仰が上野国所縁であることを示すものかもしれません。
※関連記事 → ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)の6.三鈷山 吉祥院 妙見寺
房総半島に依った桓武平氏は「房総平氏」とも呼ばれ、平忠常公がその始祖とされます。
「房総平氏」の代表格は上総介と千葉介で、鎌倉幕府草創期の当主は上総介広常と千葉介常胤でした。(→千葉氏系図)(千葉一族の歴史と史跡)
石橋山の戦いで敗れ房総で再挙を図った頼朝公ですが、大きな武力をもつ「房総平氏」の上総介と千葉介の協力なくして鎌倉入りは果たせなかったとみられています。
上総介広常は頼朝公に粛清されましたが、頼朝公のサポート役に徹した千葉介常胤はその地位を能く保ちました。
常胤は千葉氏の祖ともされる平常重の嫡男で、保元元年(1156年)の保元の乱では源義朝公の指揮下で戦いました。
治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れた頼朝公が安房に逃れると、頼朝公は安達盛長を使者として千葉庄(現在の千葉市付近)の常胤に送り、常胤は盛長を迎え入れ、頼朝公に源氏ゆかりの鎌倉に入ることを勧めたとされます。(『吾妻鑑』治承4年9月9日条)
『吾妻鏡』には、同年9月17日に常胤が下総国府に赴き頼朝公に参陣とあります。
この時期、頼朝公が千葉妙見宮を参詣、以降も尊崇篤かったと伝えられ、頼朝公は房総における妙見信仰の大切さを熟知していたのかもしれません。
これに関連して『千葉市における源頼朝の伝説と地域文化の創出に向けて』(丸井敬司氏)には興味ぶかい説が記されています。
頼朝公は鎌倉に入るやいなや鶴岡若宮(現・元八幡宮)を北に遷座(現・鶴岡八幡宮)していますが、同書では「(鶴岡若宮の北遷は)八幡神を道教における四神の玄武と見做したことを意味する。こうした既存の八幡社に妙見の神格を加えるような事例は房総半島には多く確認される。」とし、守谷の妙見八幡、竜(龍)ヶ崎の妙見八幡を例にひいています。
また、「尊光院(現・千葉神社)のように妙見の別当寺を町の北側に建立することで、事実上、八幡社を妙見社とする例もある(こうした八幡に妙見の神格を加えたものを「千葉型の八幡信仰」という)。こうした事例から考えると筆者は、鶴岡若宮は典型的な「千葉型の八幡信仰」の寺院であったと考えている。」とし、鶴岡八幡宮の御遷座に千葉氏の関与ないしは献策があったことを示唆しています。
源平合戦では範頼公に属して一ノ谷の戦いに参加、豊後国で軍功をあげ、奥州討伐では東海道方面の大将に任じられて活躍、鎌倉幕府でも重きをなしたとされています。
頼朝公も常胤を深く信頼し、「(常胤を)以て父となす」という言葉が伝わります。
千葉氏における常胤の存在の大きさは、常胤以降、嫡流は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが通例となったことからもうかがわれます。
また、千葉市Webや千葉市立郷土博物館Webでも、千葉氏が大きくとりあげられ、この地における千葉氏の存在の大きさが感じられます。
これは千葉氏が単なる豪族にとどまらず、房総に広がる妙見信仰と深くかかわっていることもあると思われ、実際、千葉市公式Webには「千葉氏と北辰(妙見)信仰」というコンテンツが掲載されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 薬師堂
千葉氏ゆかりの寺院として千葉市稲毛区の大日寺があります。
公式Webには「文献や資料などから、大日寺は1254年に千葉介頼胤によって松戸の馬橋に創建され、1284年に頼胤の子、胤宗によって千葉に移されたという説が有力なようです。」とあります。
山内には、千葉(平)常兼(1046-1126年)から胤将に至る千葉氏16代の墓碑である五輪塔が安置されており、昭和35年に千葉市の重要文化財として「史跡千葉家十六代廟所」の指定を受けています。
このなかに千葉介常胤の墓もあるという説もみられます。
常胤の6人の息子の子孫は分家を繰り返しながら全国に広がり、のちに「千葉六党(ちばりくとう)」(千葉氏、相馬氏、武石氏、大須賀氏、国分氏、東氏)と呼ばれる同族勢力を形成しました。


【写真 上(左)】 千葉氏五輪塔
【写真 下(右)】 御朱印
山内本堂まわりはさほど広くはないですが、高度感ある楼閣造の薬師堂や、手厚く供養されている大師堂など、多くのみどころがあります。
御朱印は、御本尊・大日如来のものを庫裡にて拝受できます。
23.和田(義盛)神社
〔和田太郎義盛〕
富士市Web資料
静岡県富士市今泉8-7
御祭神:和田義盛 (合祀)大山津見命、建速須佐之男命
今回は正真正銘の「十三人の合議制」のメンバーです。
和田氏は坂東八平氏に数えられる三浦氏の支族で、相模国三浦郡和田、ないし安房国和田御厨を所領としていたことから和田を名乗ったといいます。
鎌倉幕府草創期の当主は和田義盛で、三浦義明の子の杉本義宗の子として誕生し、母は大庭景継の息女と伝わります。
治承四年(1180年)三浦氏の一族として頼朝公の挙兵に呼応し、石橋山の合戦に向かうも丸子川(酒匂川)の増水で渡れず三浦へ兵を返しましたが、平家方だった畠山重忠の軍勢と遭遇し小坪合戦を展開。
次いで、畠山重忠軍は三浦氏の本拠・衣笠城を襲って城は落城し、祖父・三浦義明は討ち死にしました。(衣笠城合戦)。
衣笠城を落ちた義盛らは海上で北条勢と合流し、安房の地で頼朝公を迎えました。
『平家物語』によると、この際に義盛は、頼朝公が本懐を遂げ天下を取った暁には侍所別当に任じて欲しい旨を乞い、頼朝公は鎌倉入り後にこの義盛の願いを容れて初代侍所別当に任じました。
いかな本人の切実な願いとはいえ、重職の侍所別当にそうやすやすとは任ずることはできないので、相応の貢献と頼朝公からの信任があったと思われます。
このことは、上総介広常への使者という重責に義盛が任ぜられていることからも裏付けられます。
源平合戦では範頼公の軍奉行をつとめ、山陽道から九州に渡って豊後葦屋浦の戦いなどで奮戦。
壇ノ浦の戦いでは義盛は渚から盛んに遠矢を射かけて平家方を脅かしましたが、平家方の仁井親清が見事に矢を射返すと、これに憤激した義盛は船を漕ぎだし海上で獅子奮迅の戦いを繰り広げたといいます。(『平家物語』)
奥州合戦でも武功を重ねた義盛は、御家人筆頭格としての地位を確保し、大倉の頼朝公御所入御の儀式の折には御家人の筆頭の場を占めたと伝わります。
建久三年(1192年)、侍所別当職を梶原景時と交代していますが、『吾妻鏡』によると、景時が「一日だけ」と義盛に頼み込んで別当職となり、そのまま義盛へ返さずに別当職を奪われてしまったといいます。
それでも、義盛の宿老としての地位は揺るがず、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」に列しています。
頼朝公の死後、梶原景時の弾劾(梶原景時の変)では中心的な役割を果たしたとされ、景時滅亡後は侍所別当に復しています。
梶原景時の変は感情的なしがらみが背景にあったとみられ、そのなかで御家人の中心となって動いた義盛は、御家人衆からの人望が厚かったとみられます。
『源平盛衰記』には木曾義仲公滅亡後、義仲公の愛妾・巴御前が鎌倉へ下った際、義盛は巴御前のような剛の者に子を産ませたいと頼朝公に申し出て許され、巴を娶って朝比奈義秀が生まれたとあります。
しかし、時系列的に齟齬があるのと、他の史料や物語でこの逸話がみられないことからこの話は創作とみられます。
朝比奈義秀は無双の剛勇で知られたことから、巴御前を母とする逸話がつくられたとされます。
戦国時代、今川氏の重臣として活躍した朝比奈氏は藤原北家の出とされますが、義盛の子・朝比奈義秀から興ったという説もあります。
比企氏や畠山氏の乱では北条氏に与し、与党のポジションを保ちました。
しかし、執権・北条義時のたび重なる挑発により、建暦三年(1213年)5月ついに挙兵に追い込まれ、鎌倉で激しい市街戦を繰り広げたのちに討ち死にし、ここに和田一族は滅亡しました。(和田合戦)
義盛が戦死した由比ヶ浜には、いまも「和田塚」という地名が残ります。
和田一族の墓は江ノ電の和田塚駅のそばにあり、「和田一族戦没地」の碑も立てられています。
また、南伊豆町南伊豆町湊にも「和田塚」があり、和田義盛の墓と伝わります。こちらは和田合戦で義盛が南伊豆に落ちのび、当地の庄屋の娘と結婚して子をなしたという伝承にもとづくものとみられます。
三浦市南下浦町にある真宗大谷派寺院の和田山 来福寺は、義盛の開基、和田一族の菩提寺として知られ、本堂に奉安されている義盛像は三浦市の指定文化財となっています。
三浦市初声町和田の(神明)白旗神社は、弘長三年(1263年)、領主だった義盛を偲ぶため村民が義盛を祀って創祀と伝わります。
御祭神は、現在でも天照大神と和田義盛です。
今回ご紹介するのは、静岡県富士市今泉に御鎮座の和田(義盛)神社です。
和田義盛関係の資料にもあまり登場しない神社ですが、地元では「義盛さん」と呼んで尊崇を集めているようです。
境内由緒書には「治承四年(1180年)10月、富士南麓の加島平野に源平の大合戦が展開されようとした時、源氏の大軍は今泉・原田の高台を中心に依田橋・鈴川・鮫島あたり一帯に陣を布いた。勢子村(今泉村)付近の守りを頼朝から命じられた和田義盛は、東泉院付近に本陣をおき、南側を流れる川に逆茂木をしかけて厳重に警備した。そのため、のちにその川を和田川と呼び陣を布いた所を和田城、その付近の土地を『和田』と呼んだ。そして土地の人々は和田義盛をこの土地の守護神として神社を建てた。」とあります。
この戦いは「富士川の戦い」とみられますが、義盛が陣を布いただけで土地の守護神として創祀とは、やや動機にうすいような感じもします。
和田(義盛)神社は日吉浅間神社の兼務社で、日吉浅間神社は富士山 東泉院が別当をつとめていました。
(東泉院は真言宗寺院で下方五社(富知六所浅間神社・浅間本町、瀧川神社・原田字滝川、今宮浅間神社・今宮字西村、日吉浅間神社・今泉上和田、入山瀬浅間神社・入山瀬字久保上)の別当であったとされる。)
東泉院は富士山 興法寺を拠点とする村山修験と関係があったとされますから、東泉院・下方五社を差配していた六所家あるいは村山修験は、和田義盛ないしその子孫となんらかの関係があったのかもしれません。
(あくまでも筆者の想像です。)


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鳥居
日吉浅間神社から徒歩でほんの1~2分ですが、境内からは見えずわかりにくいのでGoogle マップの経路案内をつかうのがベター。
駐車場はないので、日吉浅間神社のPに停めての参拝となります。
住宅地の路地奥に朱の鳥居。その先に社殿。
目指していかなければまずわからないこぢんまりとしたお社です。

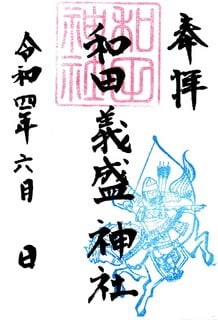
【写真 上(左)】 社殿
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は日吉浅間神社の社務所で拝受できますが、「鎌倉殿の13人」放映時のみの限定授与かもしれません。


【写真 上(左)】 日吉浅間神社
【写真 下(右)】 日吉浅間神社の御朱印
授与時間は火曜・水曜をのぞく9:00~15:00のようで、本務社の日吉浅間神社の御朱印も授与され、オリジナル御朱印帳も頒布されています。
→日吉浅間神社のfacebook
24.(羽根倉)浅間神社
〔金子小太郎高範〕
志木市Web資料
埼玉県志木市上宗岡4-27-20
御祭神:木花開耶姫大神
御利益:子授安産
旧社格:村社
元別当:観音寺
授与所:水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)※常時授与かは不明
『吾妻鑑』の文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)に金子小太郎高範の名がみえます。
金子氏は武蔵七党の一派、村山党に属し桓武平氏の流れとされます。
武蔵国多摩郡村山を領した平頼任が村山党の祖で、孫の家範が入間郡金子に拠って金子を名乗ったのが始まりとされます。
家範の子として金子十郎家忠、金子小太郎高範、金子親範の名が伝わり、いずれも御家人に名を連ねていたようです。
保元の乱では後白河天皇方に金子十郎家忠の名がみえ、源為朝公の配下で剛勇で知られた高間兄弟を討ちとるという武功をあげています。
(→西多摩新聞に詳しいです。)
『吾妻鏡』によると、金子一族は治承四年(1180年)、畠山重忠軍に合流し相模・衣笠城の三浦氏を攻めていますが、後に頼朝公の配下に入りました。
十郎家忠は源平合戦でも数々の武功をあげ、播磨国斑鳩荘などの地頭職に任ぜられています。
『東上沿線新聞』の記事によると、金子小太郎高範は十郎家忠の兄で、承久の乱の宇治川の合戦で討ち死にしています。
埼玉県富士見市周辺に依った難波田氏の祖とされますが、同記事には「おそらく討ち死にの恩賞として子孫に難波田が領地として与えられ、それで難波田氏を名乗るようになったのではないか」と記されています。
金子十郎家忠については、いまのところ御朱印授与の関連寺社がみつからないので、まずは金子小太郎高範ゆかりの寺社をご紹介します。
難波田氏は富士見市南畑を本拠とし、現在、館跡は「難波田城公園」として公開されています。
その富士見市南畑にもほど近いところに(羽根倉)浅間神社があります。
荒川にかかる羽根倉橋のたもとに鎮座し、「羽根倉橋の浅間様」として崇敬される浅間神社です。
境内説明板などによると、建久四年(1193年)、源頼朝公が富士の裾野で巻狩りを催した際、宗岡の住民は勢子役を課せられ、その代償として年貢が免ぜられたのでこれを記念して字大野の地に祠を建てて富士浅間社を祀ったとあります。
富士山から距離のあるこの地の住民が勢子役を課せられたのは不思議な感じがしますが、『しきふるさと史話/志木市教育委員会刊』によると、ここからほど近い難波田の地の武士、難波田高範は頼朝公が初めて京に上った折の随兵として選ばれ、奥州征伐にも加わるなど武蔵武士の中では重きをなしていたため、その支配下にあった宗岡の村民が使役されたのだろう、とのことです。
その後、長禄年間(1457-1460年)の荒川大洪水で字大野の祠が流され羽根倉(現在の羽根倉橋上流)に流れ着いたので、これを神意と考えこの地に社殿を建立。
明治維新後、荒川の改修工事にともない字蓮田に移転、字十人野の稲荷杜、字大野の浅間社、字蓮田の稲荷社、字東前の八幡社の無格社四社を合祀して村社に列格。
昭和48年(1973年)、県道浦和所沢線の建設のため当地へ御遷座しています。
この羽根倉は、南北朝時代の「観応の擾乱」の際、足利尊氏方の高麗常澄と直義方の難波田九郎三郎が激闘を繰り広げた「羽根倉の合戦」の地としても知られています。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
南に羽根倉通、西に浦所バイパスの築堤、北に荒川の堤防を控えた立地ですが、境内には富士塚が整然とそびえ、右手の社殿の日当たりもよく、高燥なイメージがあります。
境内には参拝者用の駐車場もありました。
境内には地元の丸藤(まるとう)講が築いた高さ約5m、直径約17mの富士塚があります。
平成24年に崩落防止のためコンクリート補修されているものの、黒ボク(富士山の溶岩)は残り、胎内穴も残る本格的な富士塚です。
(詳細は「■ 志木開運・招福七社参り-1」をご覧くださいませ。)

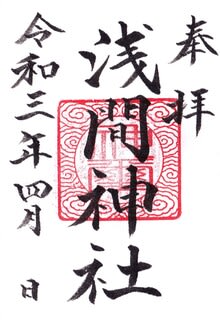
【写真 上(左)】 羽根倉富士塚
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は本務社の水宮神社(富士見市水子1762-3)で拝受しましたが、常時授与されているかは不明です。
25.瑠璃光山 薬師院 玉井寺
〔玉井四郎資重/玉井氏〕
公式Web
埼玉県熊谷市玉井1888
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
司別当:玉井大神社境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)
武蔵国の名族、成田氏は藤原道長(ないし基忠)の流れとも伝わりますが、横山党(小野篁の後裔)の代表氏族とされます。
鎌倉幕府草創期の当主は成田七郎助綱で、その二代前の成田太夫助隆(高)の長男・助広が成田氏を継ぎ、二男の行隆が別府氏、三郎の高長が奈良氏、四男の助実(資重・助重)が玉井氏とそれぞれ家を興しています。
『平家物語』には、元暦元年(1184年)の一ノ谷合戦で範頼軍の玉井四郎資(助)景(助重?)らが平通盛(教盛の子)を討ったとあります。
建久元年(1190年)の頼朝公入洛参院では、後陣隨兵 四十一番に玉井四郎資(助)重の名がみえます。
熊谷市玉井にある瑠璃光山 玉井寺の山内にある石積みは、昔から「玉井四郎の墓」といわれ、玉井寺の公式Webでも下記のとおり軍功が紹介されています。
「『保元物語』の白河夜討ちの条に源頼朝に従い、玉井四郎氏が軍功をたてたとあり、『平家物語』では玉井助景が源頼朝に仕えて一ノ谷の合戦で平通盛を討ち取ったとあります。」
また、『郡村誌』には「元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。
玉井寺、玉井神社周辺は玉井氏の館跡と伝わりますが、遺構らしきものは残っていない模様です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
玉井寺の由緒はふるく、桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧・賢璟は巡視の足を東国までのばしました。
賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。
この井戸「玉の井」は玉井寺の山内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。
中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。
別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。
本堂は入母屋造桟瓦葺の端正なつくり。
玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。
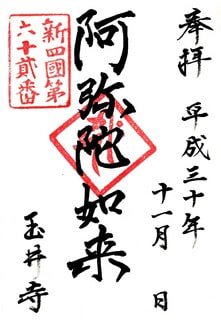

【写真 上(左)】 幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 熊谷七福神の御朱印
御朱印は庫裡にて拝受しました。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な霊場の御朱印を授与されています。
布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。
布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。
26.如意山 観音院 大輪寺
〔(小山七郎)結城朝光〕
結城市Web
関東八十八ヵ所霊場公式Web
茨城県結城市結城1139
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所:関東八十八箇所霊場第37番、結城七福神(大黒天)
前回の「鎌倉殿の13人」で北条政子の妹、阿波局に琵琶を教えていたイケメン武将、結城朝光は容姿だけでなく家柄も胆力も備えた実力者としてその名を残します。
『吾妻鏡』などからその足跡を辿ってみます。
結城朝光は小山氏初代とされる小山政光の子として生まれ、当初は下野の小山に住して小山氏を名乗りました。
小山氏は藤原北家秀郷流で、発祥当時から東国有数の名家として知られていました。
母は八田宗綱の息女で頼朝公の乳母をつとめた寒河尼。
治承四年(1180年)、頼朝公の旗揚げ時には小山政光は大番役で京にいたため、寒河尼は当時14歳の朝光を伴い隅田宿の頼朝公の宿所を訪れました。
寒河尼はわが子朝光を頼朝公側近として臣従させたい旨を申し出、これを容れた頼朝公はみずから烏帽子親となって元服させ、小山七郎宗朝と名乗ったとされます。(のちに朝光に改名)
頼朝公挙兵時、房総は上総介、千葉氏を味方につけたことで固まりましたが、下野国は動静がはっきりせず、その状況で下野国の有力者小山氏が麾下に入った功績は大きなものであったとみられています。
養和元年(1181年)4月、朝光は頼朝公寝所警護の11名に抜擢され、頼朝公側近としての地位を固めていきます。
寿永二年(1183年)2月の野木宮合戦(頼朝公と叔父の志田義広の戦い)では小山氏一族は主力として奮戦し、頼朝方を勝利に導きました。
この戦に先立って頼朝公が鶴岡八幡宮で戦勝祈願した際、御剣役をつとめた朝光は、義広が敗北する旨の「神託」を告げて頼朝公から称賛されました。
御剣役は御家人として栄えある役目で、『吾妻鏡』で確認できる朝光の10回は御家人最多とみられています。
野木宮合戦の論功行賞で朝光は結城郡の地頭職に任命されています。(朝光は下総結城氏初代当主)
元暦元年(1184年)木曾義仲追討に参加。源平合戦では諸戦に加わり奮戦。
東下りした義経公を頼朝公の使者として酒匂宿に訪ね、「鎌倉入りならず」の口上を伝えたのは朝光と伝わります。
文治三年(1187年)の沼田御厨代官狼藉事件では、畠山重忠の窮地を救って名声を高めました。
文治五年(1189年)の奥州合戦では、阿津賀志山の戦いで敵将・金剛別当秀綱を討ち取り、奥州白河三郡を与えられています。
建久六年(1195年)、頼朝公の東大寺再建供養参列の際の騒動では見事な調停をこなし、衆徒達から「容貌美好、口弁分明」と称賛されました。
『吾妻鏡』に「容貌美好」と記されているほどですから、やはり衆目の認めるイケメン武将であったのでしょう。
頼朝公逝去後の正治元年(1199年)秋、朝光は侍所詰所で頼朝公を偲びつつ、「『忠臣二君に仕えず』というが、自分も出家するべきだった。なにやら今の世は薄氷を踏むような思いがする。」と述べたといいます。(『吾妻鏡』10月25日条)
この翌々日、阿波局(北条政子の妹)が「梶原景時が先日のあなたの発言を謀反の証拠として将軍・頼家公に讒訴し、あなたは殺されることになっている」と朝光に告げました。
驚いた朝光はいそぎ三浦義村や和田義盛らの有力御家人にはかり、奉行人の中原仲業に景時の糾弾状をつくらせ、御家人66名の連判をもって大江広元に差し出しました。
大江広元はやむなくこれを頼家公に提出し、頼家公は景時に弁明の機会を与えたものの景時は抗弁もせず、一族を引き連れて所領(相模国一宮)に退去しました。
結局、頼家公は景時を救うことができず、景時は京へのぼる途中で襲撃を受けて討ち死にしました。(梶原景時の変)
これはナゾにつつまれた事件で、当時の公家の日記と『吾妻鏡』で内容の違いがみられ、動機や目的については様々な説が展開されています。
ただ、いずれにしても有力御家人66名の連判をまとめ上げたのは朝光であり、その人望と影響力のほどがうかがわれます。
承久三年(1221年)の承久の乱では東山道軍の将の一人として参戦。
寛喜元年(1229年)上野介に叙任、のちに幕府評定衆の一員となり幕政に重きをなしました。
しかし、「13人の合議制」に列してもいいほどの勲功と見識、そして人望をもちながら晩年は政治から距離をおいたといわれます。
若いころから念仏に傾倒していた朝光は、あいつぐ鎌倉府の政変のなかで世の無常を悟り、法然上人や親鸞上人に知己を得てふかく帰依し、晩年には出家して結城上野入道日阿と号して結城称名寺を建立するなど信仰に生きたと伝わります。
朝光の性格は誇り高く、あまたの御家人衆も一目置いていたこと、結城家当主は代々「朝」を通字としたことなどから頼朝公のご落胤説もありますが、史料による確たる裏付けはないとされています。
中世、結城家は下総の名家として存続し、奥州白河でも分家が興隆しました。
白河結城家当主の結城親光は建武の新政で活躍し、楠木正成、千種忠顕、名和長年と合わせて「三木一草」と称されました。
室町期には結城基光が下野守護を務め、第3代鎌倉公方・足利満兼公の代には宇都宮氏、小山氏、佐竹氏、小田氏、那須氏、千葉氏、長沼氏と並んで「関東八屋形」の一つに列し、屋形号を許されるなど名家の格式を保ちました。
永享十年(1438年)の永享の乱以降は動乱に巻き込まれ、古河公方を奉じて各地で戦を繰り広げ戦国大名としても勢力を張りました。
戦国期の当主・晴朝には子がなかったため、徳川家康公の次男で秀吉公の養子であった秀康公を養子に迎えました。(結城秀康)
これほどの武将を養子に迎えられたことは、結城氏の家格の高さを物語っています。
墓所である称名寺をはじめ、結城朝光ゆかりの寺院はいくつかありますが、ここでは朝光が(開基)改号して以来、結城家代々の祈願所となった大輪寺をご紹介します。
草創当初は常陸国河内郡で大輪坊と号しましたが、安貞元年(1227年)、朝光が坊舎を移築し田川原郷大輪坊の僧・元観を招いて開基とし、大輪寺と号したと伝わります。
朝光の帰依篤く、結城家代々の祈願所になっています。
元禄年間(1688-1703年)には僧・俊寿が中興、藩主水野家の祈願所となり、中本寺として末寺二十二ヶ寺を擁したといいます。
名刹だけに寺宝も多く、結城家第8代当主直光寄進で境外仏堂に御座された正観世音菩薩(人手観音)は県指定文化財、大黒天像、経典十三巻・根来塗経管などは市の指定文化財となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は三間一戸の八脚門で屋根は本瓦葺。脇間には仁王尊が御座します。

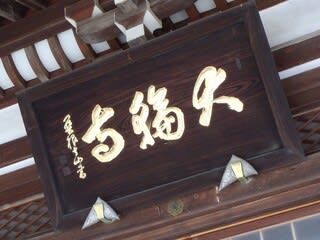
【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
入母屋造本瓦葺流れ向拝の本堂は、名刹にふさわしい風格を備えるもの。
水引虹梁両端に簡素な木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股、正面桟唐戸の上には寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 人手観音堂
【写真 下(右)】 布袋尊
人手観音堂は入母屋造銅板葺流れ向拝で観音堂らしい朱塗り。こちらは水引虹梁まわりに精緻な彫刻が施されています。

■ 関東八十八箇所霊場の御朱印
御朱印は庫裡にて拝受できます。
メジャー霊場・関東八十八箇所の札所なので、手慣れたご対応です。
結城七福神(大黒天)の札所ですが、七福神の御朱印の授与は不明です。
27.宝林山 称念寺
〔河津三郎祐泰〕
伊豆88遍路の紹介ページ
静岡県河津町浜334-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場別格旧第31番
河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。
藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。
称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。
現地由緒書および霊場ガイド記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。
その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。
文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。
しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈りつつ鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せたちまち空に舞い上がりました。
帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。
帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。
このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。
河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に供養したそうです。
現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。
『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。
永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。
河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。
国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。


【写真 上(左)】 道沿いの札所案内
【写真 下(右)】 六地蔵
アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。
その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。
彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 向拝扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
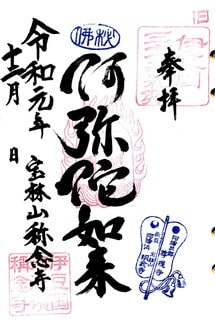

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
28.慈眼山 無量院 萬福寺
〔梶原平三景時〕
大田区南馬込1-49-1
曹洞宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:江戸・東京四十四閻魔参り第19番、閻魔三拾遺第29番
先日(7/24)の「鎌倉殿の13人」で、ついに「梶原景時の変」にさしかかりました。
梶原氏は桓武平氏良文流といわれる鎌倉氏の一族です。
鎌倉権五郎景正は相模国鎌倉に拠って鎌倉氏を称し、後三年の役での凄絶な戦ぶりは広く知られています。
鎌倉氏一族の系譜については諸説ありますが、景正の嫡子・景継が鎌倉氏を継ぎ、景正の父・(鎌倉)景成の兄弟・景通の子の景久が鎌倉郡梶原郷で梶原氏を称し、景成のもうひとりの兄弟・景村の孫の景宗が大庭御厨で大庭氏を称したとされます。
このほか、長江氏、板倉氏、安積氏、香川氏、古屋氏、長尾氏などが鎌倉党とされます。
同族の大庭氏(大庭景親)が平家方の有力者であったこともあり、石橋山の戦いでは平家方に属しましたが、景時は石橋山の山中で窮地に陥っていた頼朝公を見逃して救いました。
治承四年(1180年)秋の頼朝公鎌倉入りののち、景時は土肥実平を通じて頼朝公に降伏し、翌年正月に頼朝公と対面して御家人に列しました。
武術のみならず弁舌に秀で、教養もある景時は頼朝公に厚く信任されて数々の重責を果たし、「鎌倉ノ本体ノ武士」と称されて十三人の合議制にも列しました。
梶原景時にまつわる逸話は枚挙にいとまがないので、こちら(Wikipedia)をご覧ください。(と逃げる(笑))
その峻烈果断な性格は平家追討、幕府草創に必要なものでしたが、それだけに敵も多く、ついに結城朝光の悲嘆に端を発した政変(梶原景時の変)により、正治二年(1200年)正月、上洛の途中に駿河国で討ち死にしました。
有能な官吏で頼朝公の信任厚かったことは間違いないですが、とくに義経公への讒言が喧伝されたため、後世の評価が大きくわかれる人物とされています。
梶原景時の所領と館は相模国一宮(現在の寒川町)にあったとされ、比定地には「梶原景時館址」の石碑が建てられています。
また、多磨郡柚井領(現・八王子市)にも所領があったようです。
景時の墓所として伝わる場所はいくつかあります。
1.鎌倉・深沢小学校裏のやぐら五輪塔
2.梶原景時館址の墓石群(寒川町)
3.梶原山の墓石群(静岡市葵区長尾・梶原山公園)
4.慈眼山 萬福寺(大田区南馬込)
このうち御朱印をいただけるのは4の萬福寺なので、こちらをご紹介します。
なお、1.深沢小学校そばの御霊神社(鎌倉市梶原)(→ 神奈川県神社庁Web)は景時の創建と伝わり、御朱印も授与されているようですが筆者は未拝受です。
御霊神社の元別当で山号が景時ゆかりと伝わる休場山 等覚寺(鎌倉市梶原)の御朱印は拝受していますのでUPします。
■ 休場山 弥勒院 等覺寺
鎌倉市梶原1-9−2
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所:相模国準四国八十八ヶ所霊場21番


※ 字数制限にかかったので、以降はVol.4をご覧ください。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4へつづく。
【 BGM 】
■ If I Had My Wish Tonight - David Lasley
■ Morricone: Nella Fantasia
■ In My Dreams - REO Speedwagon
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2から
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
21.冷水山 清浄土院 長徳寺
〔仙波氏〕
埼玉県川越市仙波町3-31-23
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第27番
武蔵七党、村山党の一族として知られる仙波氏。
武蔵山口氏の祖、山口家継の子・家信が川越市仙波町を本貫(名字の地)とし、仙波氏を名乗ったのが始祖とされます。
武蔵七党には多くの系図が残り、錯綜しているので系譜を辿りにくくなっていますが、これを精緻に整理された難波田城資料館の早坂廣人氏の『武蔵七党系図(村山党系図)と難波田氏』という文献がWeb上で公開されています。
この文献には、仙波(右馬允)安行、仙波盛直、仙波(入道)安家、仙波(太郎)康高、仙波邏曜、仙波(太(大)郎)信恒、仙波(二郎入道)時綱の名がリストされています。
一方、『「鶴ヶ島町史」通史編』(鶴ヶ島市立図書館/鶴ヶ島市デジタル郷土資料)の第六節には、「仙波氏については、山口六郎家俊の弟家信は仙波(川越市)に住んで仙波七郎といい仙波氏の祖となるが、この家信は保元の乱に義朝に従っている。そして、彼の長子仙波平太信平、次子の仙波二郎安家は『吾妻鏡』に、頼朝の随兵として名を見せる。また、承久(じょうきゅう)の乱の宇治川合戦で負傷者の中に、仙波太郎、仙波左衛門尉、そして戦死者の中に仙波弥次郎がいる。それぞれ信平の子信恒、信平の弟三郎左衛門尉家行、そして安家の次子弥二郎光時と推定される。ただし『武蔵七党系図』には、信恒、家行ともに宇治川合戦で溺死したと註記してある。どちらが正しいかは分らない。」とあります。
これに、川越について詳細な分析をされている『川越雑記帳』(川越原人氏)の「仙波氏」の頁の内容を併せると、
・仙波氏の祖・家信の長子・仙波平太信平 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵
・家信の次子・仙波二郎安家 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵
・家信の子・(三郎左衛門尉)ないし(二郎)家行 → 『吾妻鏡』 文治元年頼朝随兵
・信平の子・仙波太郎(信恒) → 『吾妻鏡』 建久六年将軍家随兵
また、承久三年(1221年)6月の承久の乱の宇治橋合戦で負傷・戦死したのは(『吾妻鏡』)、
・仙波太郎(信恒?)
・仙波左衛門尉(家行?)
・仙波弥次郎(安家の次子・弥二郎光時?)
と推測されます。
これだけの名が『吾妻鏡』に記載されている以上、御家人の家柄として相応のポジションを確保していたことは間違いないかと思われます。
また、宇治橋合戦で負傷・戦死者が多いのは、この戦さで仙波一族が前線で奮戦したことを物語っています。
仙波氏の居館として、仙波町堀ノ内の「仙波氏館」(市指定史跡)が知られています。
ここは長徳寺に近接し、長徳寺を館址とする資料もあります。
長徳寺山内の説明書『仙波氏舘跡』(川越市教育委員会)には「大仙波の長徳寺は天台宗の末寺で、『新編武蔵風土記稿』によると『永承甲戌(一五一四)天台沙門實海』の名が古い過去帳に記されていたという。境内に、もと若干の土塁と堀があったといわれ、小字に『堀の内』という地名も残っているところから、仙波氏の館跡だと推定されている。『保元物語』に仙波七郎高家、『吾妻鏡』に仙波平太・同太郎・次郎・弥三郎・左衛門尉などの名がみえ、これらは在名をもって氏としたことが考えられる。ただし郷庄の唱えではこの大仙波村は山田庄に属し、仙波庄を唱うる村はこれより南部の市内高階地区と上福岡・大井・富士見・三芳の各市町に拡がっているものが多く、仙波氏の支配した荘園と考えられる。」とあり、現・長徳寺山内を仙波氏舘跡に比定しています。
『平成 小江戸川越 古寺巡礼』(信州信濃浄土出版会)には、開山は慈覚大師円仁で山号は長徳元年(995年)朝廷からの下賜。中興開山は永正十一年(1514年)喜多院第十四世実海大僧正とあります。
山内の観音堂に御座す白衣観世音菩薩は、「川越観音」として信仰を集めています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額

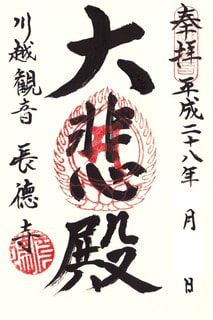
【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 長徳寺の御朱印
※Webでは御本尊阿弥陀如来の御朱印がみつかりますが、授与されていないそうです。
22.阿毘盧山 密乗院 大日寺
〔千葉介常胤〕
公式Web
千葉県千葉市稲毛区轟町2-1-27
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:千葉寺八十八所霊場第3番
頼朝公の挙兵・関東平定の功労者として外せない御家人に千葉介常胤がいます。
千葉氏は桓武平氏良文流、坂東八平氏(千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏)を代表する名族として知られています。
律令制のもとの親王任国(親王が国守に任じられた国。常陸国、上総国、上野国の3国ですべて「大国」)の国守(太守)は親王で、次官として「介」(すけ)がおかれ、実質的な国の長官は「介」ないし「権介」であったとされます。
常陸国の「介」には平家盛、頼盛、経盛、教盛など伊勢平氏(いわゆる「平家」)が任ぜられました。上総国の「介」は早くから坂東に下向した桓武平氏良文流の上総氏、下総国は親王任国ではありませんが、こちらも実質的な長官は「介」ないし「権介」で、良文流の千葉氏が占めて”千葉介”を称し、有力在庁官人としてともに勢力を張りました。
もうひとつの親王任国、上野国(現・群馬県)には、平良文公や千葉氏の嫡流・平(千葉)常将公にまつわる伝承が多く残ります。
(ご参考→『榛名山南東麓の千葉氏伝承』)
千葉氏の妙見信仰にもかかわる逸話が伝わるので、少しく寄り道してみます。
千葉氏の妙見信仰のはじまりについては諸説がありますが、千葉市史のなかに、上野国の妙見菩薩にちなむとする記載がありました。(『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』(千葉市地域情報デジタルアーカイブ))
これによると、桓武天皇四世、平高望公の子・平良文公は武蔵国大里郡を本拠とし、良文公と平将門公が結んで上野国に攻め入り、上野国府中花園の村の染谷川で平国香公の大軍と戦った際に示現された妙見菩薩(花園妙見・羊妙見)が、その信仰のはじまりだというのです。
「染谷川の戦い」は、伊勢平氏の祖・国香公と良文流の祖・良文公、そして関東の覇者・将門公という超大物が相戦うスケール感あふれる戦いですが、複数の伝承があるようで、国香公と将門公の対峙は明らかですが、良文公がどちらについたかが定かでありません。(そもそも史実かどうかも不明)
しかし、この戦いで花園妙見の加護を得た将門公と良文公が実質的な勝利を得、国香公は撤収したとされています。
これに類する逸話は『源平闘諍録』にも記されており、千葉市史はこれにもとづいて構成されたのかもしれません。
また、良文公の嫡流、平(千葉)常将公も、上野国の榛名山麓に多くの逸話を残しています。
上野国に大きな所領を得たわけでもない良文公や常将公の足跡が上野国にのこるのは、やはり房総平氏の妙見信仰が上野国所縁であることを示すものかもしれません。
※関連記事 → ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)の6.三鈷山 吉祥院 妙見寺
房総半島に依った桓武平氏は「房総平氏」とも呼ばれ、平忠常公がその始祖とされます。
「房総平氏」の代表格は上総介と千葉介で、鎌倉幕府草創期の当主は上総介広常と千葉介常胤でした。(→千葉氏系図)(千葉一族の歴史と史跡)
石橋山の戦いで敗れ房総で再挙を図った頼朝公ですが、大きな武力をもつ「房総平氏」の上総介と千葉介の協力なくして鎌倉入りは果たせなかったとみられています。
上総介広常は頼朝公に粛清されましたが、頼朝公のサポート役に徹した千葉介常胤はその地位を能く保ちました。
常胤は千葉氏の祖ともされる平常重の嫡男で、保元元年(1156年)の保元の乱では源義朝公の指揮下で戦いました。
治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れた頼朝公が安房に逃れると、頼朝公は安達盛長を使者として千葉庄(現在の千葉市付近)の常胤に送り、常胤は盛長を迎え入れ、頼朝公に源氏ゆかりの鎌倉に入ることを勧めたとされます。(『吾妻鑑』治承4年9月9日条)
『吾妻鏡』には、同年9月17日に常胤が下総国府に赴き頼朝公に参陣とあります。
この時期、頼朝公が千葉妙見宮を参詣、以降も尊崇篤かったと伝えられ、頼朝公は房総における妙見信仰の大切さを熟知していたのかもしれません。
これに関連して『千葉市における源頼朝の伝説と地域文化の創出に向けて』(丸井敬司氏)には興味ぶかい説が記されています。
頼朝公は鎌倉に入るやいなや鶴岡若宮(現・元八幡宮)を北に遷座(現・鶴岡八幡宮)していますが、同書では「(鶴岡若宮の北遷は)八幡神を道教における四神の玄武と見做したことを意味する。こうした既存の八幡社に妙見の神格を加えるような事例は房総半島には多く確認される。」とし、守谷の妙見八幡、竜(龍)ヶ崎の妙見八幡を例にひいています。
また、「尊光院(現・千葉神社)のように妙見の別当寺を町の北側に建立することで、事実上、八幡社を妙見社とする例もある(こうした八幡に妙見の神格を加えたものを「千葉型の八幡信仰」という)。こうした事例から考えると筆者は、鶴岡若宮は典型的な「千葉型の八幡信仰」の寺院であったと考えている。」とし、鶴岡八幡宮の御遷座に千葉氏の関与ないしは献策があったことを示唆しています。
源平合戦では範頼公に属して一ノ谷の戦いに参加、豊後国で軍功をあげ、奥州討伐では東海道方面の大将に任じられて活躍、鎌倉幕府でも重きをなしたとされています。
頼朝公も常胤を深く信頼し、「(常胤を)以て父となす」という言葉が伝わります。
千葉氏における常胤の存在の大きさは、常胤以降、嫡流は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが通例となったことからもうかがわれます。
また、千葉市Webや千葉市立郷土博物館Webでも、千葉氏が大きくとりあげられ、この地における千葉氏の存在の大きさが感じられます。
これは千葉氏が単なる豪族にとどまらず、房総に広がる妙見信仰と深くかかわっていることもあると思われ、実際、千葉市公式Webには「千葉氏と北辰(妙見)信仰」というコンテンツが掲載されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 薬師堂
千葉氏ゆかりの寺院として千葉市稲毛区の大日寺があります。
公式Webには「文献や資料などから、大日寺は1254年に千葉介頼胤によって松戸の馬橋に創建され、1284年に頼胤の子、胤宗によって千葉に移されたという説が有力なようです。」とあります。
山内には、千葉(平)常兼(1046-1126年)から胤将に至る千葉氏16代の墓碑である五輪塔が安置されており、昭和35年に千葉市の重要文化財として「史跡千葉家十六代廟所」の指定を受けています。
このなかに千葉介常胤の墓もあるという説もみられます。
常胤の6人の息子の子孫は分家を繰り返しながら全国に広がり、のちに「千葉六党(ちばりくとう)」(千葉氏、相馬氏、武石氏、大須賀氏、国分氏、東氏)と呼ばれる同族勢力を形成しました。


【写真 上(左)】 千葉氏五輪塔
【写真 下(右)】 御朱印
山内本堂まわりはさほど広くはないですが、高度感ある楼閣造の薬師堂や、手厚く供養されている大師堂など、多くのみどころがあります。
御朱印は、御本尊・大日如来のものを庫裡にて拝受できます。
23.和田(義盛)神社
〔和田太郎義盛〕
富士市Web資料
静岡県富士市今泉8-7
御祭神:和田義盛 (合祀)大山津見命、建速須佐之男命
今回は正真正銘の「十三人の合議制」のメンバーです。
和田氏は坂東八平氏に数えられる三浦氏の支族で、相模国三浦郡和田、ないし安房国和田御厨を所領としていたことから和田を名乗ったといいます。
鎌倉幕府草創期の当主は和田義盛で、三浦義明の子の杉本義宗の子として誕生し、母は大庭景継の息女と伝わります。
治承四年(1180年)三浦氏の一族として頼朝公の挙兵に呼応し、石橋山の合戦に向かうも丸子川(酒匂川)の増水で渡れず三浦へ兵を返しましたが、平家方だった畠山重忠の軍勢と遭遇し小坪合戦を展開。
次いで、畠山重忠軍は三浦氏の本拠・衣笠城を襲って城は落城し、祖父・三浦義明は討ち死にしました。(衣笠城合戦)。
衣笠城を落ちた義盛らは海上で北条勢と合流し、安房の地で頼朝公を迎えました。
『平家物語』によると、この際に義盛は、頼朝公が本懐を遂げ天下を取った暁には侍所別当に任じて欲しい旨を乞い、頼朝公は鎌倉入り後にこの義盛の願いを容れて初代侍所別当に任じました。
いかな本人の切実な願いとはいえ、重職の侍所別当にそうやすやすとは任ずることはできないので、相応の貢献と頼朝公からの信任があったと思われます。
このことは、上総介広常への使者という重責に義盛が任ぜられていることからも裏付けられます。
源平合戦では範頼公の軍奉行をつとめ、山陽道から九州に渡って豊後葦屋浦の戦いなどで奮戦。
壇ノ浦の戦いでは義盛は渚から盛んに遠矢を射かけて平家方を脅かしましたが、平家方の仁井親清が見事に矢を射返すと、これに憤激した義盛は船を漕ぎだし海上で獅子奮迅の戦いを繰り広げたといいます。(『平家物語』)
奥州合戦でも武功を重ねた義盛は、御家人筆頭格としての地位を確保し、大倉の頼朝公御所入御の儀式の折には御家人の筆頭の場を占めたと伝わります。
建久三年(1192年)、侍所別当職を梶原景時と交代していますが、『吾妻鏡』によると、景時が「一日だけ」と義盛に頼み込んで別当職となり、そのまま義盛へ返さずに別当職を奪われてしまったといいます。
それでも、義盛の宿老としての地位は揺るがず、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」に列しています。
頼朝公の死後、梶原景時の弾劾(梶原景時の変)では中心的な役割を果たしたとされ、景時滅亡後は侍所別当に復しています。
梶原景時の変は感情的なしがらみが背景にあったとみられ、そのなかで御家人の中心となって動いた義盛は、御家人衆からの人望が厚かったとみられます。
『源平盛衰記』には木曾義仲公滅亡後、義仲公の愛妾・巴御前が鎌倉へ下った際、義盛は巴御前のような剛の者に子を産ませたいと頼朝公に申し出て許され、巴を娶って朝比奈義秀が生まれたとあります。
しかし、時系列的に齟齬があるのと、他の史料や物語でこの逸話がみられないことからこの話は創作とみられます。
朝比奈義秀は無双の剛勇で知られたことから、巴御前を母とする逸話がつくられたとされます。
戦国時代、今川氏の重臣として活躍した朝比奈氏は藤原北家の出とされますが、義盛の子・朝比奈義秀から興ったという説もあります。
比企氏や畠山氏の乱では北条氏に与し、与党のポジションを保ちました。
しかし、執権・北条義時のたび重なる挑発により、建暦三年(1213年)5月ついに挙兵に追い込まれ、鎌倉で激しい市街戦を繰り広げたのちに討ち死にし、ここに和田一族は滅亡しました。(和田合戦)
義盛が戦死した由比ヶ浜には、いまも「和田塚」という地名が残ります。
和田一族の墓は江ノ電の和田塚駅のそばにあり、「和田一族戦没地」の碑も立てられています。
また、南伊豆町南伊豆町湊にも「和田塚」があり、和田義盛の墓と伝わります。こちらは和田合戦で義盛が南伊豆に落ちのび、当地の庄屋の娘と結婚して子をなしたという伝承にもとづくものとみられます。
三浦市南下浦町にある真宗大谷派寺院の和田山 来福寺は、義盛の開基、和田一族の菩提寺として知られ、本堂に奉安されている義盛像は三浦市の指定文化財となっています。
三浦市初声町和田の(神明)白旗神社は、弘長三年(1263年)、領主だった義盛を偲ぶため村民が義盛を祀って創祀と伝わります。
御祭神は、現在でも天照大神と和田義盛です。
今回ご紹介するのは、静岡県富士市今泉に御鎮座の和田(義盛)神社です。
和田義盛関係の資料にもあまり登場しない神社ですが、地元では「義盛さん」と呼んで尊崇を集めているようです。
境内由緒書には「治承四年(1180年)10月、富士南麓の加島平野に源平の大合戦が展開されようとした時、源氏の大軍は今泉・原田の高台を中心に依田橋・鈴川・鮫島あたり一帯に陣を布いた。勢子村(今泉村)付近の守りを頼朝から命じられた和田義盛は、東泉院付近に本陣をおき、南側を流れる川に逆茂木をしかけて厳重に警備した。そのため、のちにその川を和田川と呼び陣を布いた所を和田城、その付近の土地を『和田』と呼んだ。そして土地の人々は和田義盛をこの土地の守護神として神社を建てた。」とあります。
この戦いは「富士川の戦い」とみられますが、義盛が陣を布いただけで土地の守護神として創祀とは、やや動機にうすいような感じもします。
和田(義盛)神社は日吉浅間神社の兼務社で、日吉浅間神社は富士山 東泉院が別当をつとめていました。
(東泉院は真言宗寺院で下方五社(富知六所浅間神社・浅間本町、瀧川神社・原田字滝川、今宮浅間神社・今宮字西村、日吉浅間神社・今泉上和田、入山瀬浅間神社・入山瀬字久保上)の別当であったとされる。)
東泉院は富士山 興法寺を拠点とする村山修験と関係があったとされますから、東泉院・下方五社を差配していた六所家あるいは村山修験は、和田義盛ないしその子孫となんらかの関係があったのかもしれません。
(あくまでも筆者の想像です。)


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鳥居
日吉浅間神社から徒歩でほんの1~2分ですが、境内からは見えずわかりにくいのでGoogle マップの経路案内をつかうのがベター。
駐車場はないので、日吉浅間神社のPに停めての参拝となります。
住宅地の路地奥に朱の鳥居。その先に社殿。
目指していかなければまずわからないこぢんまりとしたお社です。

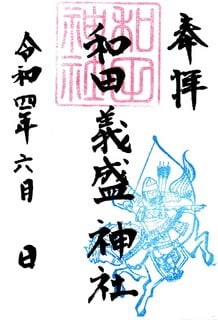
【写真 上(左)】 社殿
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は日吉浅間神社の社務所で拝受できますが、「鎌倉殿の13人」放映時のみの限定授与かもしれません。


【写真 上(左)】 日吉浅間神社
【写真 下(右)】 日吉浅間神社の御朱印
授与時間は火曜・水曜をのぞく9:00~15:00のようで、本務社の日吉浅間神社の御朱印も授与され、オリジナル御朱印帳も頒布されています。
→日吉浅間神社のfacebook
24.(羽根倉)浅間神社
〔金子小太郎高範〕
志木市Web資料
埼玉県志木市上宗岡4-27-20
御祭神:木花開耶姫大神
御利益:子授安産
旧社格:村社
元別当:観音寺
授与所:水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)※常時授与かは不明
『吾妻鑑』の文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)に金子小太郎高範の名がみえます。
金子氏は武蔵七党の一派、村山党に属し桓武平氏の流れとされます。
武蔵国多摩郡村山を領した平頼任が村山党の祖で、孫の家範が入間郡金子に拠って金子を名乗ったのが始まりとされます。
家範の子として金子十郎家忠、金子小太郎高範、金子親範の名が伝わり、いずれも御家人に名を連ねていたようです。
保元の乱では後白河天皇方に金子十郎家忠の名がみえ、源為朝公の配下で剛勇で知られた高間兄弟を討ちとるという武功をあげています。
(→西多摩新聞に詳しいです。)
『吾妻鏡』によると、金子一族は治承四年(1180年)、畠山重忠軍に合流し相模・衣笠城の三浦氏を攻めていますが、後に頼朝公の配下に入りました。
十郎家忠は源平合戦でも数々の武功をあげ、播磨国斑鳩荘などの地頭職に任ぜられています。
『東上沿線新聞』の記事によると、金子小太郎高範は十郎家忠の兄で、承久の乱の宇治川の合戦で討ち死にしています。
埼玉県富士見市周辺に依った難波田氏の祖とされますが、同記事には「おそらく討ち死にの恩賞として子孫に難波田が領地として与えられ、それで難波田氏を名乗るようになったのではないか」と記されています。
金子十郎家忠については、いまのところ御朱印授与の関連寺社がみつからないので、まずは金子小太郎高範ゆかりの寺社をご紹介します。
難波田氏は富士見市南畑を本拠とし、現在、館跡は「難波田城公園」として公開されています。
その富士見市南畑にもほど近いところに(羽根倉)浅間神社があります。
荒川にかかる羽根倉橋のたもとに鎮座し、「羽根倉橋の浅間様」として崇敬される浅間神社です。
境内説明板などによると、建久四年(1193年)、源頼朝公が富士の裾野で巻狩りを催した際、宗岡の住民は勢子役を課せられ、その代償として年貢が免ぜられたのでこれを記念して字大野の地に祠を建てて富士浅間社を祀ったとあります。
富士山から距離のあるこの地の住民が勢子役を課せられたのは不思議な感じがしますが、『しきふるさと史話/志木市教育委員会刊』によると、ここからほど近い難波田の地の武士、難波田高範は頼朝公が初めて京に上った折の随兵として選ばれ、奥州征伐にも加わるなど武蔵武士の中では重きをなしていたため、その支配下にあった宗岡の村民が使役されたのだろう、とのことです。
その後、長禄年間(1457-1460年)の荒川大洪水で字大野の祠が流され羽根倉(現在の羽根倉橋上流)に流れ着いたので、これを神意と考えこの地に社殿を建立。
明治維新後、荒川の改修工事にともない字蓮田に移転、字十人野の稲荷杜、字大野の浅間社、字蓮田の稲荷社、字東前の八幡社の無格社四社を合祀して村社に列格。
昭和48年(1973年)、県道浦和所沢線の建設のため当地へ御遷座しています。
この羽根倉は、南北朝時代の「観応の擾乱」の際、足利尊氏方の高麗常澄と直義方の難波田九郎三郎が激闘を繰り広げた「羽根倉の合戦」の地としても知られています。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
南に羽根倉通、西に浦所バイパスの築堤、北に荒川の堤防を控えた立地ですが、境内には富士塚が整然とそびえ、右手の社殿の日当たりもよく、高燥なイメージがあります。
境内には参拝者用の駐車場もありました。
境内には地元の丸藤(まるとう)講が築いた高さ約5m、直径約17mの富士塚があります。
平成24年に崩落防止のためコンクリート補修されているものの、黒ボク(富士山の溶岩)は残り、胎内穴も残る本格的な富士塚です。
(詳細は「■ 志木開運・招福七社参り-1」をご覧くださいませ。)

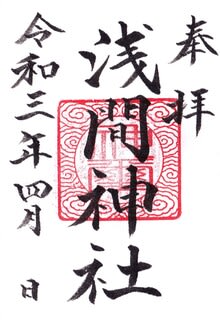
【写真 上(左)】 羽根倉富士塚
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は本務社の水宮神社(富士見市水子1762-3)で拝受しましたが、常時授与されているかは不明です。
25.瑠璃光山 薬師院 玉井寺
〔玉井四郎資重/玉井氏〕
公式Web
埼玉県熊谷市玉井1888
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
司別当:玉井大神社境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)
武蔵国の名族、成田氏は藤原道長(ないし基忠)の流れとも伝わりますが、横山党(小野篁の後裔)の代表氏族とされます。
鎌倉幕府草創期の当主は成田七郎助綱で、その二代前の成田太夫助隆(高)の長男・助広が成田氏を継ぎ、二男の行隆が別府氏、三郎の高長が奈良氏、四男の助実(資重・助重)が玉井氏とそれぞれ家を興しています。
『平家物語』には、元暦元年(1184年)の一ノ谷合戦で範頼軍の玉井四郎資(助)景(助重?)らが平通盛(教盛の子)を討ったとあります。
建久元年(1190年)の頼朝公入洛参院では、後陣隨兵 四十一番に玉井四郎資(助)重の名がみえます。
熊谷市玉井にある瑠璃光山 玉井寺の山内にある石積みは、昔から「玉井四郎の墓」といわれ、玉井寺の公式Webでも下記のとおり軍功が紹介されています。
「『保元物語』の白河夜討ちの条に源頼朝に従い、玉井四郎氏が軍功をたてたとあり、『平家物語』では玉井助景が源頼朝に仕えて一ノ谷の合戦で平通盛を討ち取ったとあります。」
また、『郡村誌』には「元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。
玉井寺、玉井神社周辺は玉井氏の館跡と伝わりますが、遺構らしきものは残っていない模様です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
玉井寺の由緒はふるく、桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧・賢璟は巡視の足を東国までのばしました。
賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。
この井戸「玉の井」は玉井寺の山内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。
中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。
別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。
本堂は入母屋造桟瓦葺の端正なつくり。
玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。
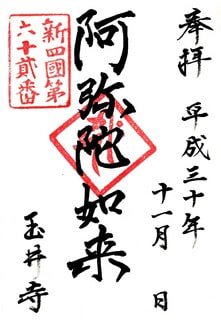

【写真 上(左)】 幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 熊谷七福神の御朱印
御朱印は庫裡にて拝受しました。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な霊場の御朱印を授与されています。
布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。
布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。
26.如意山 観音院 大輪寺
〔(小山七郎)結城朝光〕
結城市Web
関東八十八ヵ所霊場公式Web
茨城県結城市結城1139
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所:関東八十八箇所霊場第37番、結城七福神(大黒天)
前回の「鎌倉殿の13人」で北条政子の妹、阿波局に琵琶を教えていたイケメン武将、結城朝光は容姿だけでなく家柄も胆力も備えた実力者としてその名を残します。
『吾妻鏡』などからその足跡を辿ってみます。
結城朝光は小山氏初代とされる小山政光の子として生まれ、当初は下野の小山に住して小山氏を名乗りました。
小山氏は藤原北家秀郷流で、発祥当時から東国有数の名家として知られていました。
母は八田宗綱の息女で頼朝公の乳母をつとめた寒河尼。
治承四年(1180年)、頼朝公の旗揚げ時には小山政光は大番役で京にいたため、寒河尼は当時14歳の朝光を伴い隅田宿の頼朝公の宿所を訪れました。
寒河尼はわが子朝光を頼朝公側近として臣従させたい旨を申し出、これを容れた頼朝公はみずから烏帽子親となって元服させ、小山七郎宗朝と名乗ったとされます。(のちに朝光に改名)
頼朝公挙兵時、房総は上総介、千葉氏を味方につけたことで固まりましたが、下野国は動静がはっきりせず、その状況で下野国の有力者小山氏が麾下に入った功績は大きなものであったとみられています。
養和元年(1181年)4月、朝光は頼朝公寝所警護の11名に抜擢され、頼朝公側近としての地位を固めていきます。
寿永二年(1183年)2月の野木宮合戦(頼朝公と叔父の志田義広の戦い)では小山氏一族は主力として奮戦し、頼朝方を勝利に導きました。
この戦に先立って頼朝公が鶴岡八幡宮で戦勝祈願した際、御剣役をつとめた朝光は、義広が敗北する旨の「神託」を告げて頼朝公から称賛されました。
御剣役は御家人として栄えある役目で、『吾妻鏡』で確認できる朝光の10回は御家人最多とみられています。
野木宮合戦の論功行賞で朝光は結城郡の地頭職に任命されています。(朝光は下総結城氏初代当主)
元暦元年(1184年)木曾義仲追討に参加。源平合戦では諸戦に加わり奮戦。
東下りした義経公を頼朝公の使者として酒匂宿に訪ね、「鎌倉入りならず」の口上を伝えたのは朝光と伝わります。
文治三年(1187年)の沼田御厨代官狼藉事件では、畠山重忠の窮地を救って名声を高めました。
文治五年(1189年)の奥州合戦では、阿津賀志山の戦いで敵将・金剛別当秀綱を討ち取り、奥州白河三郡を与えられています。
建久六年(1195年)、頼朝公の東大寺再建供養参列の際の騒動では見事な調停をこなし、衆徒達から「容貌美好、口弁分明」と称賛されました。
『吾妻鏡』に「容貌美好」と記されているほどですから、やはり衆目の認めるイケメン武将であったのでしょう。
頼朝公逝去後の正治元年(1199年)秋、朝光は侍所詰所で頼朝公を偲びつつ、「『忠臣二君に仕えず』というが、自分も出家するべきだった。なにやら今の世は薄氷を踏むような思いがする。」と述べたといいます。(『吾妻鏡』10月25日条)
この翌々日、阿波局(北条政子の妹)が「梶原景時が先日のあなたの発言を謀反の証拠として将軍・頼家公に讒訴し、あなたは殺されることになっている」と朝光に告げました。
驚いた朝光はいそぎ三浦義村や和田義盛らの有力御家人にはかり、奉行人の中原仲業に景時の糾弾状をつくらせ、御家人66名の連判をもって大江広元に差し出しました。
大江広元はやむなくこれを頼家公に提出し、頼家公は景時に弁明の機会を与えたものの景時は抗弁もせず、一族を引き連れて所領(相模国一宮)に退去しました。
結局、頼家公は景時を救うことができず、景時は京へのぼる途中で襲撃を受けて討ち死にしました。(梶原景時の変)
これはナゾにつつまれた事件で、当時の公家の日記と『吾妻鏡』で内容の違いがみられ、動機や目的については様々な説が展開されています。
ただ、いずれにしても有力御家人66名の連判をまとめ上げたのは朝光であり、その人望と影響力のほどがうかがわれます。
承久三年(1221年)の承久の乱では東山道軍の将の一人として参戦。
寛喜元年(1229年)上野介に叙任、のちに幕府評定衆の一員となり幕政に重きをなしました。
しかし、「13人の合議制」に列してもいいほどの勲功と見識、そして人望をもちながら晩年は政治から距離をおいたといわれます。
若いころから念仏に傾倒していた朝光は、あいつぐ鎌倉府の政変のなかで世の無常を悟り、法然上人や親鸞上人に知己を得てふかく帰依し、晩年には出家して結城上野入道日阿と号して結城称名寺を建立するなど信仰に生きたと伝わります。
朝光の性格は誇り高く、あまたの御家人衆も一目置いていたこと、結城家当主は代々「朝」を通字としたことなどから頼朝公のご落胤説もありますが、史料による確たる裏付けはないとされています。
中世、結城家は下総の名家として存続し、奥州白河でも分家が興隆しました。
白河結城家当主の結城親光は建武の新政で活躍し、楠木正成、千種忠顕、名和長年と合わせて「三木一草」と称されました。
室町期には結城基光が下野守護を務め、第3代鎌倉公方・足利満兼公の代には宇都宮氏、小山氏、佐竹氏、小田氏、那須氏、千葉氏、長沼氏と並んで「関東八屋形」の一つに列し、屋形号を許されるなど名家の格式を保ちました。
永享十年(1438年)の永享の乱以降は動乱に巻き込まれ、古河公方を奉じて各地で戦を繰り広げ戦国大名としても勢力を張りました。
戦国期の当主・晴朝には子がなかったため、徳川家康公の次男で秀吉公の養子であった秀康公を養子に迎えました。(結城秀康)
これほどの武将を養子に迎えられたことは、結城氏の家格の高さを物語っています。
墓所である称名寺をはじめ、結城朝光ゆかりの寺院はいくつかありますが、ここでは朝光が(開基)改号して以来、結城家代々の祈願所となった大輪寺をご紹介します。
草創当初は常陸国河内郡で大輪坊と号しましたが、安貞元年(1227年)、朝光が坊舎を移築し田川原郷大輪坊の僧・元観を招いて開基とし、大輪寺と号したと伝わります。
朝光の帰依篤く、結城家代々の祈願所になっています。
元禄年間(1688-1703年)には僧・俊寿が中興、藩主水野家の祈願所となり、中本寺として末寺二十二ヶ寺を擁したといいます。
名刹だけに寺宝も多く、結城家第8代当主直光寄進で境外仏堂に御座された正観世音菩薩(人手観音)は県指定文化財、大黒天像、経典十三巻・根来塗経管などは市の指定文化財となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は三間一戸の八脚門で屋根は本瓦葺。脇間には仁王尊が御座します。

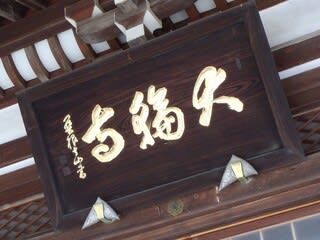
【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
入母屋造本瓦葺流れ向拝の本堂は、名刹にふさわしい風格を備えるもの。
水引虹梁両端に簡素な木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股、正面桟唐戸の上には寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 人手観音堂
【写真 下(右)】 布袋尊
人手観音堂は入母屋造銅板葺流れ向拝で観音堂らしい朱塗り。こちらは水引虹梁まわりに精緻な彫刻が施されています。

■ 関東八十八箇所霊場の御朱印
御朱印は庫裡にて拝受できます。
メジャー霊場・関東八十八箇所の札所なので、手慣れたご対応です。
結城七福神(大黒天)の札所ですが、七福神の御朱印の授与は不明です。
27.宝林山 称念寺
〔河津三郎祐泰〕
伊豆88遍路の紹介ページ
静岡県河津町浜334-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場別格旧第31番
河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。
藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。
称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。
現地由緒書および霊場ガイド記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。
その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。
文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。
しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈りつつ鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せたちまち空に舞い上がりました。
帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。
帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。
このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。
河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に供養したそうです。
現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。
『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。
永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。
河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。
国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。


【写真 上(左)】 道沿いの札所案内
【写真 下(右)】 六地蔵
アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。
その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。
彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 向拝扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
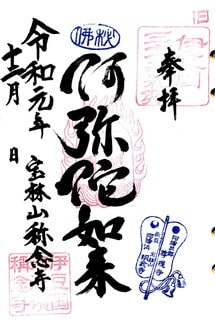

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
28.慈眼山 無量院 萬福寺
〔梶原平三景時〕
大田区南馬込1-49-1
曹洞宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:江戸・東京四十四閻魔参り第19番、閻魔三拾遺第29番
先日(7/24)の「鎌倉殿の13人」で、ついに「梶原景時の変」にさしかかりました。
梶原氏は桓武平氏良文流といわれる鎌倉氏の一族です。
鎌倉権五郎景正は相模国鎌倉に拠って鎌倉氏を称し、後三年の役での凄絶な戦ぶりは広く知られています。
鎌倉氏一族の系譜については諸説ありますが、景正の嫡子・景継が鎌倉氏を継ぎ、景正の父・(鎌倉)景成の兄弟・景通の子の景久が鎌倉郡梶原郷で梶原氏を称し、景成のもうひとりの兄弟・景村の孫の景宗が大庭御厨で大庭氏を称したとされます。
このほか、長江氏、板倉氏、安積氏、香川氏、古屋氏、長尾氏などが鎌倉党とされます。
同族の大庭氏(大庭景親)が平家方の有力者であったこともあり、石橋山の戦いでは平家方に属しましたが、景時は石橋山の山中で窮地に陥っていた頼朝公を見逃して救いました。
治承四年(1180年)秋の頼朝公鎌倉入りののち、景時は土肥実平を通じて頼朝公に降伏し、翌年正月に頼朝公と対面して御家人に列しました。
武術のみならず弁舌に秀で、教養もある景時は頼朝公に厚く信任されて数々の重責を果たし、「鎌倉ノ本体ノ武士」と称されて十三人の合議制にも列しました。
梶原景時にまつわる逸話は枚挙にいとまがないので、こちら(Wikipedia)をご覧ください。(と逃げる(笑))
その峻烈果断な性格は平家追討、幕府草創に必要なものでしたが、それだけに敵も多く、ついに結城朝光の悲嘆に端を発した政変(梶原景時の変)により、正治二年(1200年)正月、上洛の途中に駿河国で討ち死にしました。
有能な官吏で頼朝公の信任厚かったことは間違いないですが、とくに義経公への讒言が喧伝されたため、後世の評価が大きくわかれる人物とされています。
梶原景時の所領と館は相模国一宮(現在の寒川町)にあったとされ、比定地には「梶原景時館址」の石碑が建てられています。
また、多磨郡柚井領(現・八王子市)にも所領があったようです。
景時の墓所として伝わる場所はいくつかあります。
1.鎌倉・深沢小学校裏のやぐら五輪塔
2.梶原景時館址の墓石群(寒川町)
3.梶原山の墓石群(静岡市葵区長尾・梶原山公園)
4.慈眼山 萬福寺(大田区南馬込)
このうち御朱印をいただけるのは4の萬福寺なので、こちらをご紹介します。
なお、1.深沢小学校そばの御霊神社(鎌倉市梶原)(→ 神奈川県神社庁Web)は景時の創建と伝わり、御朱印も授与されているようですが筆者は未拝受です。
御霊神社の元別当で山号が景時ゆかりと伝わる休場山 等覚寺(鎌倉市梶原)の御朱印は拝受していますのでUPします。
■ 休場山 弥勒院 等覺寺
鎌倉市梶原1-9−2
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所:相模国準四国八十八ヶ所霊場21番


※ 字数制限にかかったので、以降はVol.4をご覧ください。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4へつづく。
【 BGM 】
■ If I Had My Wish Tonight - David Lasley
■ Morricone: Nella Fantasia
■ In My Dreams - REO Speedwagon
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




