関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ カラバトU-18黄金の世代の7人+4人
いろいろな歌番組を視るにつけ、どうしても彼女たちの歌のレベルの高さを再認識してしまう。
歌の巧い子はたくさんいるけど、一聴しただけでそれとわかるオリジナリティを備えた逸材はそうそういない。
内容が似ているふたつの記事をひとつにしてみました。
-------------------------
さきほどの記事を書きながら「歌のオリジナリティ」について考えていました。
カバー曲がカバー崩れする大きな原因は、歌い手のオリジナリティが確立していないから。
だからモノマネにさえならず、曲を追うだけで精一杯となり、結果は下位互換ないし崩壊。
このケースがほとんどだけど、一群の歌い手たちだけは別の展開をみせていた。
やっぱりU-18黄金の世代は ↓ 彼女たちだったのかもしれぬ。
(順不同です)
■ 佐久間彩加ちゃん
■ 三阪咲ちゃん
■ 原藤由衣ちゃん
■ 富金原佑菜ちゃん
■ 熊田このはちゃん
■ 鈴木杏奈ちゃん
■ 堀優衣ちゃん
それとその下の世代の4人。
彼女たちもオリジナリティあふれるすばらしいパフォーマンスをみせてくれる。
(順不同です)
■ 島津心美ちゃん
■ 岩口和暖ちゃん
■ 加藤礼愛ちゃん
■ 川嵜心蘭ちゃん
論より証拠、オリジナルと彼女たちのカバーを聴きくらべてみました。
オリジナルはいずれも名手といわれるシンガー。
さすがに「上位互換」しているとまではいわないが、それぞれが自身の確立したオリジナリティのうえで解釈して歌い上げているのがわかる。
だから、オリジナルでは気づかなかった楽曲の微妙なニュアンスが感じとれたりして、聴いていて面白い。
名曲やヒット曲は原曲(オリジナル曲)の歌手の声と強く結びついているので、そこから引き離し、さらに歌い手のオリジナリティを加えて別の魅力をつくりだすなど、並みの才能では到底できない。
やっぱり類い希な才能をもつ世代なんだと思う。
まぁ、とにかく聴きくらべてみてくださいまし。
※ 番号は便宜上、順不同です。
01.島津心美 / 誰より好きなのに
■ オリジナル(古内東子)
■ カバー(島津心美)
■ ナイステイク/ SEASONS - 浜崎あゆみ
2021/07/22 Kokomi 11th Birthday Live 溝ノ口劇場
強弱が効いてて歌いまわしがやたらにエモーショナル。そして歌にスケール感がある。
この子本当に小学生か?
溝ノ口劇場だ! そのうちにここ、歌姫の聖地になるかも・・・。
02.岩口和暖 / 月光
■ オリジナル(鬼束ちひろ)
■ カバー(岩口和暖)
■ ナイステイク/ アイノカタチ - MISIA
抜群の声量。それとニュアンスの込め方がますます巧くなってきている。
03.加藤礼愛 / Jupiter(Little Glee Monster Vers.)
■ オリジナル(Little Glee Monster)
■ カバー(加藤礼愛)
■ ナイステイク/ HALO - BEYONCE
11/25(木)21:00〜フジTV【千鳥クセスゴ】出演💄『HALO』加藤礼愛(カトレア.Kato Leia.12yrs) BEYONCE cover
この子の歌声聴いてると、
「最高の楽器は人の生の声」とか「優秀な男性ボーカルが10人束になってかかっても、1人の才能ある女性ボーカルには及ばない」
などという音楽格言が想い浮かんでくる。
なんというか、もって生まれたボーカリストとしての格の高さを感じる。
04.川嵜心蘭 / 点描の唄(井上苑子ソロVers.)
■ オリジナル(井上苑子)
■ カバー(川嵜心蘭)
■ ナイステイク/ しるし - Mr.Children
【カラオケバトル公式】川嵜心蘭:Mr.Children「しるし」(森アナイチオシ動画)
カラバトでこんな難しい曲ぶつけてくるとは・・・。
このあたりの感覚は、黄金の世代の7人に通じるところあり。
(優勝も狙うけど、なにより歌いたい曲を歌う。)
やっぱり、歌に複雑な感情が乗っている。
歌にこれだけ ”切なさ” を載っけられるとは、熊田このはちゃん以来の才能では?
05.佐久間彩加 / 駅
■ オリジナル(竹内まりや) ※似てるけど、オリジナルじゃありません。
■ カバー(佐久間彩加)
■ ナイステイク/ 君がいたから - Crystal Kay
2020/12/13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
この子は掛け値なしに天才だと思う。音の扱い方が普通じゃない。
荒れ声を瞬時に力感に昇華するって、この年代でできることじゃない。
それにこの情感の入り方って、いったい何事?
→ ■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦
06.三阪 咲 / Finally
■ オリジナル(安室奈美恵)
■ カバー(三阪 咲)
■ ナイステイク/ Rollercoaster (Acoustic Live Performance)
声に雰囲気があって、強弱のコントロール&声のまわし方が抜群で、とくにR&B系のこなしは絶品。
ユニットのアンサンブルを大切にする行き方は、時流を捉えているかも。
07.原藤由衣 / 出逢った頃のように
■ オリジナル(Every Little Thing/持田香織)
■ カバー(原藤由衣)
■ ナイステイク/ 初恋 - 三田寛子
2022/09/04 原藤由衣 Birthday ワンマンライブ⑨ 溝ノ口劇場
美声。だけど単なる「歌のお姉さん声」とは一線を画す粒立ち感あふれる声色。
いそうだけど、なかなかいない存在。
08.富金原佑菜 / Flavor Of Life
■ オリジナル(宇多田ヒカル)
■ カバー(富金原佑菜)
■ ナイステイク/ One Last Time - Ariana Grande
声の成分が複雑でなかなかいないタイプ。それと声量のキャパシティ。(ぜったいお腹で支えてる)
すでに自分の世界をもち作曲力もばっちりなので、曲がはまれば大化けするかも?
→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク
09.熊田このは / Can You Celebrate?
■ オリジナル(安室奈美恵)
■ カバー(熊田このは)
■ ナイステイク/ アイノカタチ - feat.HIDE(GReeeeN) MISIA
2020/02/23 LIVE
比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎ。
切なさを帯びているのに、聴き手を元気づける希有の歌声。
この子の声って絶対セラピー効果あると思う。
→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2
10.鈴木杏奈 / 炎
■ オリジナル(LiSA)
■ カバー(鈴木杏奈)
■ ナイステイク/ ラピスラズリ - 藍井エイル
2019.12.15 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
このところ、とくにエモーショナルな歌い回しが目立つのは歌の感性に優れていることの証明。
そして抜群の音程は、絶対音感ゆえのもの?
11.堀 優衣 / This Love
■ オリジナル(アンジェラ・アキ)
■ カバー(堀 優衣)
■ ナイステイク/ LOVE SONG - 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
2021/07/11 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。
しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。
大学生になって、さらにハイトーンの艶に磨きがかかってる。
一度でいいから、このメンツでコラボってほしかった。
できれば梶浦由記さんの楽曲・プロデュースで・・・。
-------------------
■ 砂塵の彼方へ....
FictionJunction + Kalafina + Sound Horizon + FBM(FRONT BAND MEMBERS)。
↑ のメンツならば、このなかに入っても引けをとらないのでは?
〔関連記事〕
■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
歌の巧い子はたくさんいるけど、一聴しただけでそれとわかるオリジナリティを備えた逸材はそうそういない。
内容が似ているふたつの記事をひとつにしてみました。
-------------------------
さきほどの記事を書きながら「歌のオリジナリティ」について考えていました。
カバー曲がカバー崩れする大きな原因は、歌い手のオリジナリティが確立していないから。
だからモノマネにさえならず、曲を追うだけで精一杯となり、結果は下位互換ないし崩壊。
このケースがほとんどだけど、一群の歌い手たちだけは別の展開をみせていた。
やっぱりU-18黄金の世代は ↓ 彼女たちだったのかもしれぬ。
(順不同です)
■ 佐久間彩加ちゃん
■ 三阪咲ちゃん
■ 原藤由衣ちゃん
■ 富金原佑菜ちゃん
■ 熊田このはちゃん
■ 鈴木杏奈ちゃん
■ 堀優衣ちゃん
それとその下の世代の4人。
彼女たちもオリジナリティあふれるすばらしいパフォーマンスをみせてくれる。
(順不同です)
■ 島津心美ちゃん
■ 岩口和暖ちゃん
■ 加藤礼愛ちゃん
■ 川嵜心蘭ちゃん
論より証拠、オリジナルと彼女たちのカバーを聴きくらべてみました。
オリジナルはいずれも名手といわれるシンガー。
さすがに「上位互換」しているとまではいわないが、それぞれが自身の確立したオリジナリティのうえで解釈して歌い上げているのがわかる。
だから、オリジナルでは気づかなかった楽曲の微妙なニュアンスが感じとれたりして、聴いていて面白い。
名曲やヒット曲は原曲(オリジナル曲)の歌手の声と強く結びついているので、そこから引き離し、さらに歌い手のオリジナリティを加えて別の魅力をつくりだすなど、並みの才能では到底できない。
やっぱり類い希な才能をもつ世代なんだと思う。
まぁ、とにかく聴きくらべてみてくださいまし。
※ 番号は便宜上、順不同です。
01.島津心美 / 誰より好きなのに
■ オリジナル(古内東子)
■ カバー(島津心美)
■ ナイステイク/ SEASONS - 浜崎あゆみ
2021/07/22 Kokomi 11th Birthday Live 溝ノ口劇場
強弱が効いてて歌いまわしがやたらにエモーショナル。そして歌にスケール感がある。
この子本当に小学生か?
溝ノ口劇場だ! そのうちにここ、歌姫の聖地になるかも・・・。
02.岩口和暖 / 月光
■ オリジナル(鬼束ちひろ)
■ カバー(岩口和暖)
■ ナイステイク/ アイノカタチ - MISIA
抜群の声量。それとニュアンスの込め方がますます巧くなってきている。
03.加藤礼愛 / Jupiter(Little Glee Monster Vers.)
■ オリジナル(Little Glee Monster)
■ カバー(加藤礼愛)
■ ナイステイク/ HALO - BEYONCE
11/25(木)21:00〜フジTV【千鳥クセスゴ】出演💄『HALO』加藤礼愛(カトレア.Kato Leia.12yrs) BEYONCE cover
この子の歌声聴いてると、
「最高の楽器は人の生の声」とか「優秀な男性ボーカルが10人束になってかかっても、1人の才能ある女性ボーカルには及ばない」
などという音楽格言が想い浮かんでくる。
なんというか、もって生まれたボーカリストとしての格の高さを感じる。
04.川嵜心蘭 / 点描の唄(井上苑子ソロVers.)
■ オリジナル(井上苑子)
■ カバー(川嵜心蘭)
@mabo3939 ♬ オリジナル楽曲 - mabo
■ ナイステイク/ しるし - Mr.Children
【カラオケバトル公式】川嵜心蘭:Mr.Children「しるし」(森アナイチオシ動画)
カラバトでこんな難しい曲ぶつけてくるとは・・・。
このあたりの感覚は、黄金の世代の7人に通じるところあり。
(優勝も狙うけど、なにより歌いたい曲を歌う。)
やっぱり、歌に複雑な感情が乗っている。
歌にこれだけ ”切なさ” を載っけられるとは、熊田このはちゃん以来の才能では?
05.佐久間彩加 / 駅
■ オリジナル(竹内まりや) ※似てるけど、オリジナルじゃありません。
■ カバー(佐久間彩加)
■ ナイステイク/ 君がいたから - Crystal Kay
2020/12/13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
この子は掛け値なしに天才だと思う。音の扱い方が普通じゃない。
荒れ声を瞬時に力感に昇華するって、この年代でできることじゃない。
それにこの情感の入り方って、いったい何事?
→ ■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦
06.三阪 咲 / Finally
■ オリジナル(安室奈美恵)
■ カバー(三阪 咲)
■ ナイステイク/ Rollercoaster (Acoustic Live Performance)
声に雰囲気があって、強弱のコントロール&声のまわし方が抜群で、とくにR&B系のこなしは絶品。
ユニットのアンサンブルを大切にする行き方は、時流を捉えているかも。
07.原藤由衣 / 出逢った頃のように
■ オリジナル(Every Little Thing/持田香織)
■ カバー(原藤由衣)
■ ナイステイク/ 初恋 - 三田寛子
2022/09/04 原藤由衣 Birthday ワンマンライブ⑨ 溝ノ口劇場
美声。だけど単なる「歌のお姉さん声」とは一線を画す粒立ち感あふれる声色。
いそうだけど、なかなかいない存在。
08.富金原佑菜 / Flavor Of Life
■ オリジナル(宇多田ヒカル)
■ カバー(富金原佑菜)
■ ナイステイク/ One Last Time - Ariana Grande
声の成分が複雑でなかなかいないタイプ。それと声量のキャパシティ。(ぜったいお腹で支えてる)
すでに自分の世界をもち作曲力もばっちりなので、曲がはまれば大化けするかも?
→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク
09.熊田このは / Can You Celebrate?
■ オリジナル(安室奈美恵)
■ カバー(熊田このは)
■ ナイステイク/ アイノカタチ - feat.HIDE(GReeeeN) MISIA
2020/02/23 LIVE
比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎ。
切なさを帯びているのに、聴き手を元気づける希有の歌声。
この子の声って絶対セラピー効果あると思う。
→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2
10.鈴木杏奈 / 炎
■ オリジナル(LiSA)
■ カバー(鈴木杏奈)
■ ナイステイク/ ラピスラズリ - 藍井エイル
2019.12.15 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
このところ、とくにエモーショナルな歌い回しが目立つのは歌の感性に優れていることの証明。
そして抜群の音程は、絶対音感ゆえのもの?
11.堀 優衣 / This Love
■ オリジナル(アンジェラ・アキ)
■ カバー(堀 優衣)
■ ナイステイク/ LOVE SONG - 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
2021/07/11 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。
しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。
大学生になって、さらにハイトーンの艶に磨きがかかってる。
一度でいいから、このメンツでコラボってほしかった。
できれば梶浦由記さんの楽曲・プロデュースで・・・。
-------------------
■ 砂塵の彼方へ....
FictionJunction + Kalafina + Sound Horizon + FBM(FRONT BAND MEMBERS)。
↑ のメンツならば、このなかに入っても引けをとらないのでは?
〔関連記事〕
■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 徳川家康公と御朱印
このところけっこうアクセスをいただいているので、御朱印を追加しました。
-------------------------
2023/01/09 UP
今年のNHK大河ドラマは『どうする家康』、徳川家康公が主役です。
昨年の「『鎌倉殿の13人』と御朱印」に引きつづき、今年は「徳川家康公と御朱印」を連載のかたちでまとめてみたいと思います。
今回も範囲を絞り、関東、山梨県、静岡県を対象とします。
なので家康公晩年にゆかりの寺社がメインとなります。
(大河ドラマも”桶狭間の戦い”から始まっていますね。)
まずは家康公の生涯を晩年中心にまとめてみます。
天文十一年(1543年)12月
・岡崎城主松平広忠(松平清康の子)の嫡男として岡崎城で生誕。
・生母は緒川城主水野忠政の娘・大子(伝通院)。幼名は竹千代。
天文十六年(1547年)8月
・数え6歳で今川氏への人質として駿府へ送られる。
天文二十四年(1555年)3月
・駿府の今川氏の下で元服。次郎三郎元信。
・今川義元の姪で関口親永の娘・瀬名(築山殿)を娶る。後に蔵人佐元康と改める。
永禄三年(1560年)5月
・桶狭間の戦いで先鋒。戦捷後、岡崎城に入城。
永禄四年(1561年)
・今川氏と断交して信長と同盟を結ぶ。(清洲同盟)
永禄六年(1563年)
・元康から家康と名を改める。
永禄九年(1566年)
・三河国を統一。朝廷から藤原氏とされ従五位下三河守に叙任し「徳川」に改姓。
・新田氏庶流の世良田三河守頼氏を松平氏の祖とした。
・改姓に伴い本姓を「藤原氏」から「源氏」に復している。
(略)
天正十八年(1590年)
・秀吉公の命により、北条氏の旧領、武蔵国・伊豆国・相模国・上野国・上総国・下総国・下野国の一部・常陸国の一部の関八州に移封。
慶長三年(1598年)
・五大老の一人に任命される。
慶長五年(1600年)9月
・関ヶ原の戦いで勝利。
慶長八年(1603年)2月
・征夷大将軍に任ぜられる。
慶長十年(1605年)4月
・征夷大将軍を辞し、嫡男・秀忠への将軍宣下。
慶長十二年(1607年)
・駿府城に移る。(大御所政治)
慶長十九年(1614年)大坂冬の陣。
慶長二十年(1615年)大坂夏の陣。
元和元年(1615年)
・禁中並公家諸法度、武家諸法度、一国一城令を制定。徳川氏による日本全域の支配を確定したとされる。
元和二年(1616年)4月
・駿府城において死去。
・『本光国師日記』によると、家康公の遺言として「臨終候はば御躰をば久能へ納。御葬禮をば增上寺にて申付。御位牌をば三川之大樹寺に立。一周忌も過候て以後。日光山に小き堂をたて。勧請し候へ。」
・葬儀は5月17日増上寺。戒名は「安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」。
・遺体は駿府の南東の久能山(現久能山東照宮)に葬られ、遺言通り一周忌を経て日光の東照社に分霊。
・「墓所」は一般に、久能山東照宮の廟所宝塔(神廟)と、日光東照宮の奥社宝塔の2つとされる。
・神号は側近の天海と崇伝、神龍院梵舜の間で権現号と明神号が議論され、山王一実神道に則って薬師如来を本地とする権現「東照大権現」とされる。
元和三年(1617年)2月
・東照大権現の神号、3月に神階正一位が贈られる。
寛永二十年(1643年)
将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立。
正保二年(1645年)11月
・宮号宣下、東照宮となる。
・東照宮に正一位の神階が贈られ、家康公は江戸幕府の始祖として東照神君、権現様とも呼ばれて江戸時代を通して崇拝される。
*****************
【家康公の信仰】
家康公の信仰仏として、以下の尊仏が知られています。(他にもまだまだあります)
・増上寺(東京・芝)の黒本尊(阿弥陀如来)

■ 増上寺・黒本尊の御朱印
・宝台院(静岡市・葵区)の白本尊(阿弥陀如来)
・隣松寺(愛知県豊田市)の冑三尊(阿弥陀三尊))
・大相模不動尊(大聖寺(埼玉県越谷市)Web)、鼠切り不動明王(不動院禅寺(三重県津市)Web)
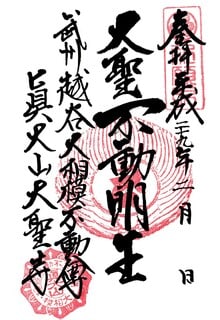
■ 大聖寺・大相模不動尊の御朱印
・摩利支天(摩利支尊 徳大寺(東京上野広小路)Web)
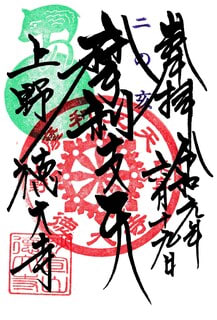
■ 徳大寺・摩利支天の御朱印
・北辰妙見大菩薩(覚成寺(群馬県みどり市)Web)
・三面大黒天(大蔵経寺(山梨県笛吹市)Web)

■ 大蔵経寺の御朱印
・善國寺の毘沙門天(善國寺(新宿区神楽坂)Web)
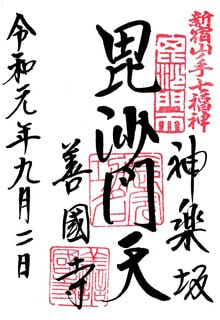
■ 善國寺・毘沙門天の御朱印
・寶珠院の開運出世大辨財天(寶珠院(港区芝公園)Web)
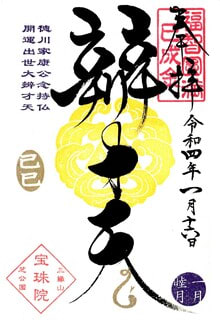
■ 寶珠院・開運出世大辨財天の御朱印
・寶田恵比寿神社の恵比寿神
「馬込勘解由と云う人は家康公が入府の時、三河の国から随行して、此の大業を成し遂げられた功に依り、徳川家繁栄御祈念の恵比寿様を授け賜ったので、平穏守護の御神体として宝田神社に御安置」(日本橋江戸屋Webより)とのこと。
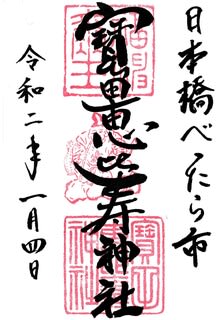
■ 寶田恵比寿神社の御朱印
【家康公と宗派】
家康公と各宗派とのゆかりについて、まずは代表例をざっくりと書き出してみます。主に関東周辺関連です。
〔浄土宗〕
家康公は「熱心な浄土宗信者」で(知恩院Web、浄土宗大辞典)増上寺住職・源誉存応上人に帰依し、葬儀も浄土宗の増上寺であげられています。
徳川家の菩提寺は増上寺で、徳川氏(松平氏)の菩提寺・大樹寺(愛知県岡崎市)も浄土宗です。
小石川の傳通院は、慶長七年(1602年)に家康公のご生母於大の方が逝去し、家康公が菩提寺とされて現号に改め、以来徳川家の菩提寺として重きをなしました。
行徳の徳願寺、蔵前の松平西福寺も家康公開基と伝わります。
また、鎌倉大長寺の住職暁誉源栄は、小田原征伐時に家康公の意を受け玉縄城主北条氏勝を説得して開城につなげ、以降家康公との交流を深めたといいます。
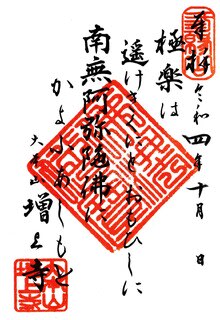
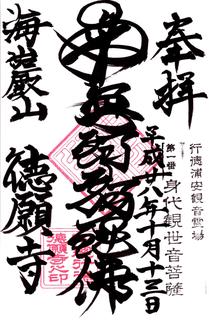
【写真 上(左)】 増上寺の御朱印(御詠歌)
【写真 下(右)】 徳願寺の御朱印
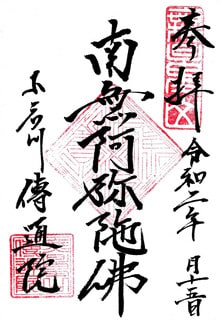

【写真 上(左)】 傳通院の御朱印
【写真 下(右)】 大長寺の御朱印
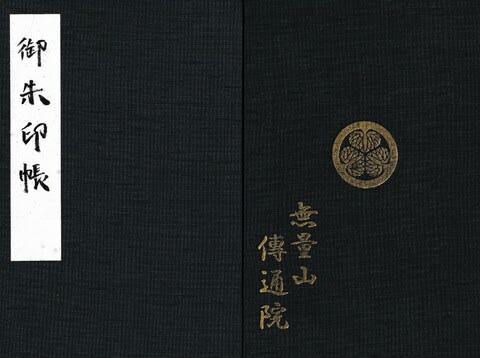
■ 葵の御紋が入った傳通院の御朱印帳
徳川軍の旗印「厭離穢土欣求浄土」(お(え)んりえどごんぐじょうど)は浄土宗(浄土教)の思想に基づくものとの説があります。
〔天台宗〕
家康公は天台宗の天海大僧正に帰依(喜多院Web、会津美里町観光協会Web)したことから、天台宗との関係もふかいとされます。
天海大僧正が創建された上野の寛永寺は、江戸城の鬼門の守護とされる門跡寺院です。
上野の輪王寺には天海(慈眼大師)と良源(慈恵大師、元三大師)の両大師が祀られています。
舞台造りで有名な上野の清水観音堂も天海大僧正の建立です。


【写真 上(左)】 喜多院の御朱印
【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印


【写真 上(左)】 上野輪王寺の御朱印
【写真 下(右)】 上野・清水観音堂の御朱印
〔臨済宗〕
駿府時代の家康公が師事したともいわれる太原雪斎(崇孚)は臨済禅であり、晩年のブレーンのひとり金地院(以心)崇伝も臨済禅でした。(清見寺(静岡市清水区)Web)
幼少時の家康公は、太原雪斎ゆかりの臨済寺(静岡市葵区)に居住し学んだと伝わります。
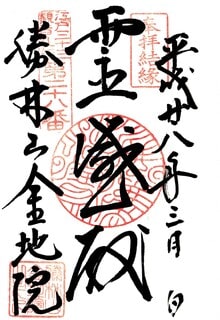
■ 金地院崇伝創建の芝・金地院の御朱印
〔曹洞宗〕
曹洞宗寺院の可睡斎(静岡県袋井市)の第11代住職仙隣等膳は竹千代の教育を受け持ったことがあり、後に浜松城主となった家康公が等膳和尚を城に招いた際、居眠りを始めてしまった和尚に親しみ、家康公が「可睡斎」と名付けたという逸話がのこります。山内には三方ヶ原の戦いで武田軍から逃れた家康公が隠れたとされる洞窟「出世六の字穴」がいまも残ります。
泉岳寺(東京・高輪)は、家康公の開基と伝わります。
来見寺(茨城県利根町)の住職は家康公の知己で、公が立ち寄った際「私が来て見たので、来見寺にせよ」との言で改号されたと伝わります。


【写真 上(左)】 泉岳寺の御朱印
【写真 下(右)】 来見寺の御朱印
〔真言宗〕
家康公は駿府在住時にしばしば真言宗の音羽山清水寺観音堂に詣で、念待仏の恵心僧都作の千手観音の像や寺領を寄進したといい、住職秀尊阿闍梨は陣僧として行動をともにしたともいいます。
また将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立しています。
また、筑波山の知足院中禅寺(現・大御堂)は家康公以来将軍家と幕府の祈祷を行っていたとされ、知足院の江戸別院・護持院はのちに音羽護国寺の境内に移されて幕府の祈願寺としての役割を担いました。
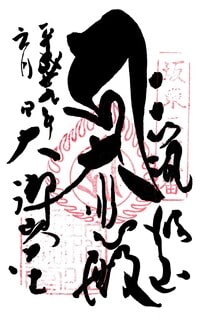
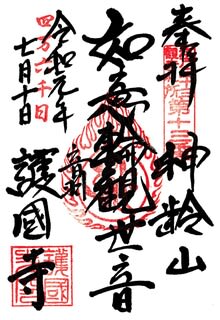
【写真 上(左)】 つくば大御堂の御朱印
【写真 下(右)】 護国寺の御朱印
〔時宗〕
・「松平八代」の初代とされる親氏公は時宗の僧で徳阿弥と称し、諸国遍歴後、三河の地にたどり着いたとされています。
称名寺(愛知県碧南市)は三河松平家(徳川家)との関わりがふかく、家康公の幼名竹千代は十五世一天和尚が命名と伝わり、山内には三州大浜東照宮が鎮座します。
〔日蓮宗〕
台東区根岸の要伝寺のWebには、家康公と日蓮宗とのゆかりが記され、これによると、谷中の瑞輪寺は家康公の開基檀越、世田谷区北烏山(もと神田湯島)の幸龍寺も家康公の開基で徳川将軍家の祈願寺として外護されたとされています。
神楽坂の善國寺も家康公開基と伝わります。
鎌倉・植木の日蓮宗寺院・久成寺は、小田原合戦の際に家康公が立ち寄り寺領を寄進、以降も外護されたと伝わります。
身延山には家康公の側室で熱心な日蓮宗信徒であった養珠院(お万の方)ゆかりの上の山東照宮が祀られています。
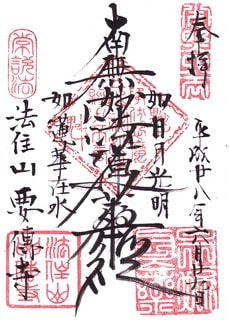
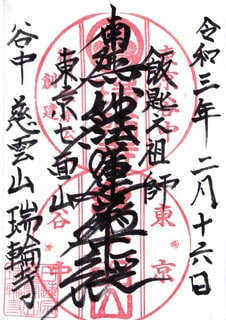
【写真 上(左)】 要伝寺の御首題
【写真 下(右)】 瑞輪寺の御首題
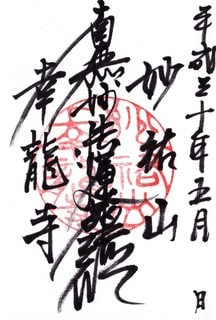
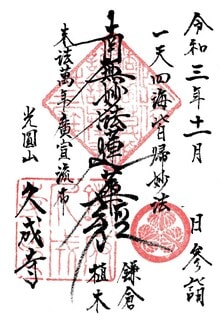
【写真 上(左)】 幸龍寺の御首題
【写真 下(右)】 久成寺の御首題
一般に家康公は浄土宗、天台宗とのゆかりがふかいとされますが、以上のように多くの宗派と関係をもっていました。
【家康公ゆかりの神社】
家康公ゆかりの神社としては、家康公(東照大権現)を祀る東照宮が代表格ですが、他にも家康公ゆかりの神社は数多くあります。
〔八幡社〕
浜松八幡宮は浜松城の鬼門の方角に位置していたことから家康公が鬼門鎮守として信仰し、度々参拝したといいます。
また家康公は、伊賀八幡宮(愛知県岡崎市)への尊崇篤かったといわれます。
〔浅間神社〕
静岡浅間神社は、天文二十四年(1555年)、駿府で人質となっていた14歳の竹千代が元服し松平元信となった神社とされます。
江戸時代には、徳川家康公の崇敬社として歴代将軍の祈願所にもなりました。
家康公は駿河国一之宮富士山本宮浅間神社にも神殿を寄進しており、浅間神社への崇敬が篤かったことがうかがえます。
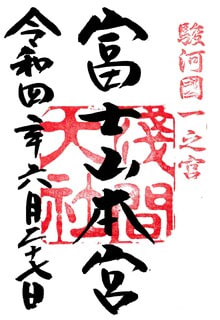
■ 富士山本宮浅間神社の御朱印
〔神田明神〕
家康公は関ヶ原の戦いの前に神田明神に戦勝祈願したとされ、成就ののちも江戸総鎮守として広く人々から崇敬を受けました。
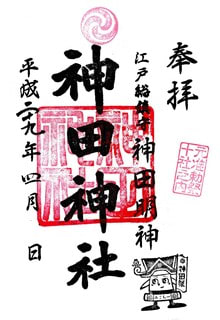
■ 神田神社(神田明神)の御朱印
〔稲荷神〕
江戸の街にこれだけ稲荷神社が広まったのは、家康公の稲荷神信仰の影響という説があります。
文京区本郷の三河稲荷神社はもともと三州碧海郡上野庄稲荷山に御鎮座で、家康公の崇敬篤く、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して造営奉遷とされています。
千代田区神田駿河台の太田姫稲荷神社(一口稲荷神社)は慶長十一年(1606年)の江戸城大改築の際、城内に御遷座の当社を西丸の鬼門にあたる神田駿河台に御遷座と伝わり、相伝には菅原道真公と徳川家康公が祀られています。
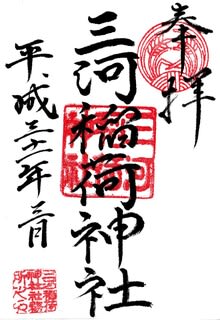

【写真 上(左)】 三河稲荷神社の御朱印
【写真 下(右)】 太田姫稲荷神社の御朱印
〔天満宮・天神社〕
霊光殿天満宮(京都市上京区)は家康公の崇敬篤く、家康公も祭祀されています。
湯島天神は家康公の崇敬を受け、桐生の総鎮守・桐生天満宮は天正九年(1581年)、徳川家の祈願所となり、関ヶ原合戦の際には戦勝祈願したと伝わります。
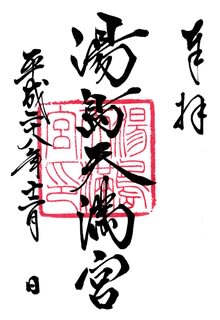
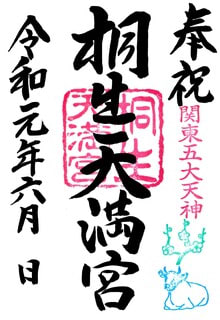
【写真 上(左)】 湯島天神(湯島天満宮)の御朱印
【写真 下(右)】 桐生天満宮の御朱印
〔氷川神社〕
江戸・武蔵一帯は氷川神社の多いところです。
家康公は文禄五年(1595年)伊奈備前守忠次を奉行として武蔵一之宮氷川神社の社頭を造営しています。
赤坂氷川神社も徳川将軍家代々の尊崇を受けたと伝わります。
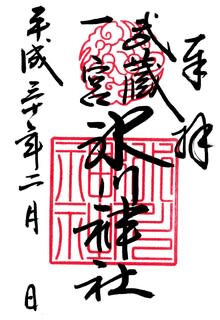
■ 武蔵一宮氷川神社の御朱印
〔愛宕神社〕
港区愛宕の愛宕神社は、慶長八年(1603年)、家康公の命により江戸の防火の神様として創祀され、以降も徳川家の尊崇篤い神社です。
愛宕権現の江戸期の別当、圓福寺は家康公が伊賀越えに際して護持された勝軍地蔵を本地佛として奉安し、この勝軍地蔵は明治に入って真福寺に遷られました。
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6の第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺を参照。

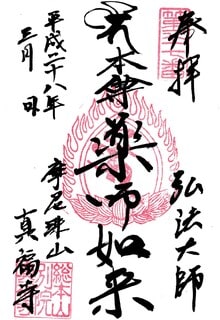
【写真 上(左)】 愛宕神社の御朱印
【写真 下(右)】 真福寺の御朱印
〔湯前神社〕
家康公はしばしば熱海に湯治に行かれたと伝わります。
この故事にならってか、熱海の大湯のお湯を江戸将軍家に献上する「湯くみ道中」の記録が伝わります。
湯前神社の御祭神は薬神、温泉の神ともされる少彦名命。
家康公は製薬調合の達人としても知られているので、少彦名命への崇敬も篤かったかもしれません。
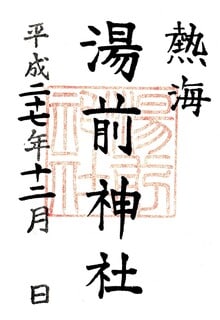
■ 湯前神社の御朱印
〔諏訪神社〕
諏訪大社上社本宮の四脚門は、慶長十三年(1608年)家康公が大久保長安に命じ、国家の安泰を祈願して造営寄進したもので、勅使門とも呼ばれます。
浜松市中区の諏訪神社は、秀忠公誕生に当り産土神として崇敬され、天正7年(1579年)家康公が社殿を造営したといいます。(昭和37年、五社神社と合祀され、五社神社諏訪神社となっています。)
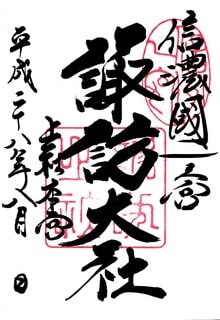
■ 諏訪大社上社本宮の御朱印
〔賀茂神社〕
徳川家の先祖・松平家は賀茂神を崇めていたといわれ、各地に徳川・松平家ゆかりの賀茂神社がみられます。
徳川宗家の家紋「三つ葉葵」は、賀茂神と関係があるという説があります。(賀茂神社の神紋は葵紋)
〔日枝神社〕
山王の日枝神社は、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して家康公が江戸城を居城とするにあたり、「徳川家の守り神」「江戸の産神」として崇敬したと伝わります。(太田道灌が川越から山王社を勧請)
日枝信仰は山王一実神道とふかいかかわりをもち、家康公祭祀を語るうえで重要なファクターです。


【写真 上(左)】 日枝神社の御朱印
【写真 下(右)】 日枝神社境内社 猿田彦神社の御朱印
〔山王一実神道〕
家康公祭祀を語るうえで外せないのが、山王一実神道(さんのういちじつしんとう)です。
もともと山王神道(さんのうしんとう)は、鎌倉時代にかけて天台宗総本山・比叡山延暦寺で生まれ、日枝山(比叡山)の山岳信仰、神道、天台宗が融合した流派で、本地垂迹説を容れた神仏習合の思想とされます。
僧・天海は山王神道説をベースに山王一実神道へと発展させ、家康公の歿後、山王一実神道に則り家康公の霊を東照大権現として祭祀しました。(当初は吉田神道の流儀で埋葬されたという説あり)
日光の家康公の墓所には東照宮が建立され、東照大権現は薬師如来の垂迹とされました。(『東照大権現縁起』)
天台宗と山王一実神道との関係はきわめて複雑で、日光の「二社一寺」(日光東照宮、二荒山神社、輪王寺)、上野東照宮と寛永寺(寒松院)、川越の仙波東照宮、喜多院、日枝神社の例をみるとその複雑さが実感できます。
鳴龍で有名な日光東照宮の本地堂は、日光東照宮の境内にありながら、家康公ゆかりで東照大権現の本地とされる薬師如来を奉安する輪王寺のお堂なのです。
もはやこうなると、神社やらお寺やら、手を叩いて参拝していいのやらそれすらもわからないカオス的な状況となってきます。
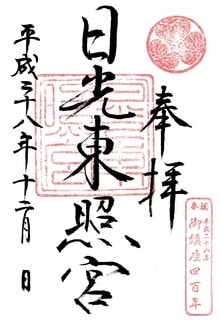
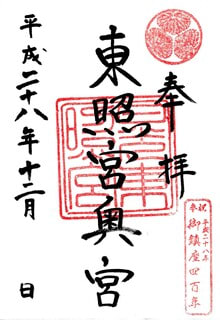
【写真 上(左)】 日光東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 日光東照宮奥宮の御朱印


【写真 上(左)】 日光二荒山神社本社の御朱印
【写真 下(右)】 日光二荒山神社中宮祠の御朱印


【写真 上(左)】 日光山 輪王寺 黒門の御朱印
【写真 下(右)】 日光山 輪王寺 本地堂の御朱印
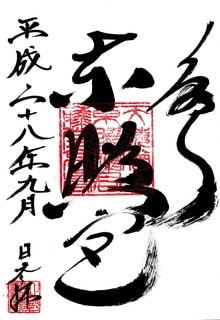

【写真 上(左)】 上野東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印
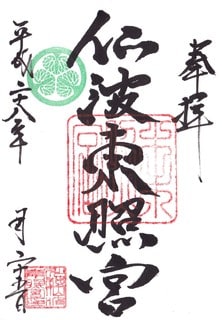
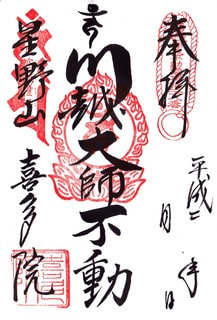
【写真 上(左)】 仙波東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 喜多院の御朱印

■ 日枝神社の御朱印
家康公の祭祀を辿ることは、江戸時代に隆盛を極めた神仏集合の歴史を辿ることかもしれません。
なお、群馬県太田市徳川町・世良田町周辺は「徳川氏発祥の地」とされ、家康公ないし徳川家ゆかりの寺社が少なくありません。家康公ゆかりの地としてこのエリアを訪ねてみるのも面白いかもしれません。
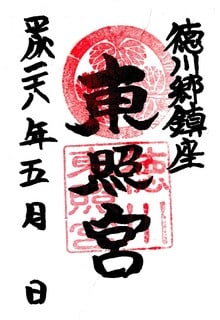
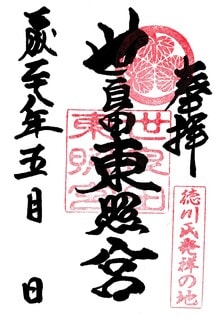
【写真 上(左)】 徳川東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 世良田東照宮の御朱印
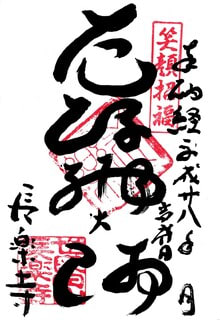
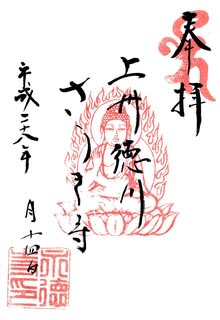
【写真 上(左)】 長楽寺(太田市世良田町)の御朱印
【写真 下(右)】 永徳寺(太田市徳川町)の御朱印
太田市の大光院は、慶長十八年(1613年)一族の繁栄と始祖新田義重公の追善供養のため、芝増上寺の観智国師の門弟で四哲の一人といわれた呑龍上人を開山に迎え、家康公が開基した寺院と伝わります。

■ 大光院の御朱印
足利市の鑁阿寺は、世良田氏(新田氏流・徳川氏の祖ともされる)の祖・世良田頼氏の正室が足利義氏の娘である関係から家康公が帰依したと伝わり、寺領60石を安堵されたといいます。

■ 鑁阿寺の御朱印
太田、足利あたりは、探せばまだ家康公ゆかりの寺社がみつかると思います。
-------------------------
家康公の室の開基ないしゆかりの寺院も少なくありません。
・正室・築山殿(瀬名姫) 嫡男信康、長女亀姫の生母
築山殿を祀る月窟廟は西来院(浜松市中区/曹洞宗)
・継室・南明院(朝日姫、駿河御前) 豊臣秀吉の異母妹
墓所は凌雲山 東福寺(南明禅院)(京都市東山区/臨済宗東福寺派)
・蓮葉院(西郡局、於葉の方) 二女督姫の生母
墓所は本禅寺塔頭・心城院(京都市上京区/法華宗)、芳荷山 長應寺(品川区小山/法華宗陣門流)
・長勝院(於古茶、於万の方、小督局) 次男結城秀康の生母
墓所は天女山 孝顕寺(茨城県結城市/曹洞宗)
・竜泉院(西郷局、於愛の方) 三男秀忠公、四男松平忠吉の生母
墓所は金米山 宝台院(静岡市葵区/浄土宗)
・良雲院(於竹の方) 三女振姫の生母
墓所は東光山 西福寺(松平良雲院)(台東区蔵前/浄土宗)
・下山殿(於都摩の方、於津摩の方、秋山夫人) 五男徳川信吉の生母
墓所は長谷山 本土寺(千葉県松戸市/日蓮宗)
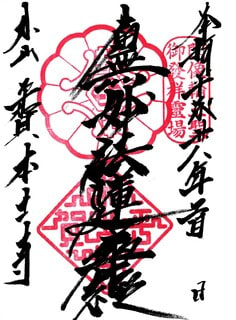
■ 本土寺の御首題
・茶阿局(於茶阿、お八) 六男松平忠輝、七男松平松千代の生母
墓所は吉水山 宗慶寺(文京区小石川/浄土宗)

■ 宗慶寺の御朱印
・普照院(於久の方) 四女松姫の生母
墓所は玉桂山 華陽院(静岡市葵区/浄土宗)
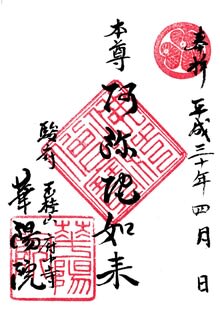
■ 華陽院の御朱印
・相応院(於亀の方) 八男松平仙千代、九男徳川義直(尾張家)の生母
菩提寺は宝亀山 相応寺(名古屋市千種区/浄土宗)
・養珠院(於万の方) 十男頼宣(紀伊家)、十一男頼房(水戸家)の生母
墓所は大野山 本遠寺(山梨県身延町/日蓮宗)
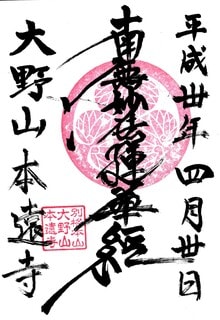
■ 本遠寺の御首題
・英勝院(於梶の方、於勝の方) 五女・市姫の生母
墓所は東光山 英勝寺(鎌倉市/浄土宗)、経王山 妙法華寺(静岡県三島市/日蓮宗)
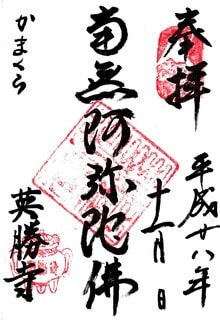
■ 英勝寺の御朱印
・蓮華院(於梅の方)
墓所は観音山 梅香寺(三重県伊勢市/浄土宗)
・雲光院(阿茶局)
墓所は開基の龍徳山 雲光院(江東区三好/浄土宗)

■ 雲光院の御朱印
・正栄院(於牟須の方)
肥前名護屋で逝去
・泰栄院(於仙の方)
駿府で死去。墓所は藤枝の浄念寺から信濃浄久寺に改葬。
・養儼院(於六の方)
墓所は日光山内?
・清雲院(於夏の方、於奈津の方)
墓所は無量山 傳通院(文京区小石川/浄土宗)、東照山 清雲院(三重県伊勢市/浄土宗)

■ 傳通院の御朱印
・信寿院((山田)富子)
墓所は長栄山 池上本門寺(大田区池上/日蓮宗)
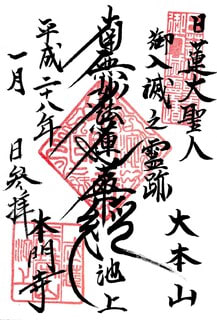
■ 池上本門寺の御首題
・法光院(於松の方?) 松平民部の生母?
・三条氏 小笠原権之丞の生母
宗派は浄土宗と日蓮宗が多く、家康公の室はこのふたつの宗に帰依しやすい環境だったのかもしれません。
東京には御府内八十八ヶ所霊場という弘法大師霊場があり、家康公ないし徳川家ゆかりの寺院もすくなくありません。
なので、併行してこちらの記事で御府内八十八ヶ所霊場も紹介していきたいと思います。
【 BGM 】
■ A Clue - Boz Scaggs
■ That's Why - Michael McDonald
■Oh Yeah! - Roxy Music
-------------------------
2023/01/09 UP
今年のNHK大河ドラマは『どうする家康』、徳川家康公が主役です。
昨年の「『鎌倉殿の13人』と御朱印」に引きつづき、今年は「徳川家康公と御朱印」を連載のかたちでまとめてみたいと思います。
今回も範囲を絞り、関東、山梨県、静岡県を対象とします。
なので家康公晩年にゆかりの寺社がメインとなります。
(大河ドラマも”桶狭間の戦い”から始まっていますね。)
まずは家康公の生涯を晩年中心にまとめてみます。
天文十一年(1543年)12月
・岡崎城主松平広忠(松平清康の子)の嫡男として岡崎城で生誕。
・生母は緒川城主水野忠政の娘・大子(伝通院)。幼名は竹千代。
天文十六年(1547年)8月
・数え6歳で今川氏への人質として駿府へ送られる。
天文二十四年(1555年)3月
・駿府の今川氏の下で元服。次郎三郎元信。
・今川義元の姪で関口親永の娘・瀬名(築山殿)を娶る。後に蔵人佐元康と改める。
永禄三年(1560年)5月
・桶狭間の戦いで先鋒。戦捷後、岡崎城に入城。
永禄四年(1561年)
・今川氏と断交して信長と同盟を結ぶ。(清洲同盟)
永禄六年(1563年)
・元康から家康と名を改める。
永禄九年(1566年)
・三河国を統一。朝廷から藤原氏とされ従五位下三河守に叙任し「徳川」に改姓。
・新田氏庶流の世良田三河守頼氏を松平氏の祖とした。
・改姓に伴い本姓を「藤原氏」から「源氏」に復している。
(略)
天正十八年(1590年)
・秀吉公の命により、北条氏の旧領、武蔵国・伊豆国・相模国・上野国・上総国・下総国・下野国の一部・常陸国の一部の関八州に移封。
慶長三年(1598年)
・五大老の一人に任命される。
慶長五年(1600年)9月
・関ヶ原の戦いで勝利。
慶長八年(1603年)2月
・征夷大将軍に任ぜられる。
慶長十年(1605年)4月
・征夷大将軍を辞し、嫡男・秀忠への将軍宣下。
慶長十二年(1607年)
・駿府城に移る。(大御所政治)
慶長十九年(1614年)大坂冬の陣。
慶長二十年(1615年)大坂夏の陣。
元和元年(1615年)
・禁中並公家諸法度、武家諸法度、一国一城令を制定。徳川氏による日本全域の支配を確定したとされる。
元和二年(1616年)4月
・駿府城において死去。
・『本光国師日記』によると、家康公の遺言として「臨終候はば御躰をば久能へ納。御葬禮をば增上寺にて申付。御位牌をば三川之大樹寺に立。一周忌も過候て以後。日光山に小き堂をたて。勧請し候へ。」
・葬儀は5月17日増上寺。戒名は「安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」。
・遺体は駿府の南東の久能山(現久能山東照宮)に葬られ、遺言通り一周忌を経て日光の東照社に分霊。
・「墓所」は一般に、久能山東照宮の廟所宝塔(神廟)と、日光東照宮の奥社宝塔の2つとされる。
・神号は側近の天海と崇伝、神龍院梵舜の間で権現号と明神号が議論され、山王一実神道に則って薬師如来を本地とする権現「東照大権現」とされる。
元和三年(1617年)2月
・東照大権現の神号、3月に神階正一位が贈られる。
寛永二十年(1643年)
将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立。
正保二年(1645年)11月
・宮号宣下、東照宮となる。
・東照宮に正一位の神階が贈られ、家康公は江戸幕府の始祖として東照神君、権現様とも呼ばれて江戸時代を通して崇拝される。
*****************
【家康公の信仰】
家康公の信仰仏として、以下の尊仏が知られています。(他にもまだまだあります)
・増上寺(東京・芝)の黒本尊(阿弥陀如来)

■ 増上寺・黒本尊の御朱印
・宝台院(静岡市・葵区)の白本尊(阿弥陀如来)
・隣松寺(愛知県豊田市)の冑三尊(阿弥陀三尊))
・大相模不動尊(大聖寺(埼玉県越谷市)Web)、鼠切り不動明王(不動院禅寺(三重県津市)Web)
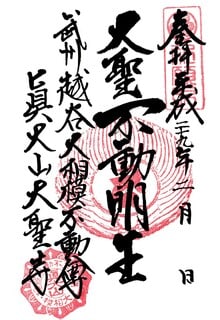
■ 大聖寺・大相模不動尊の御朱印
・摩利支天(摩利支尊 徳大寺(東京上野広小路)Web)
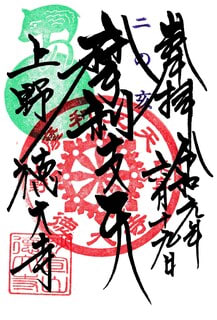
■ 徳大寺・摩利支天の御朱印
・北辰妙見大菩薩(覚成寺(群馬県みどり市)Web)
・三面大黒天(大蔵経寺(山梨県笛吹市)Web)

■ 大蔵経寺の御朱印
・善國寺の毘沙門天(善國寺(新宿区神楽坂)Web)
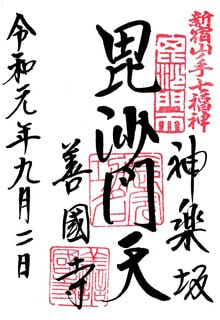
■ 善國寺・毘沙門天の御朱印
・寶珠院の開運出世大辨財天(寶珠院(港区芝公園)Web)
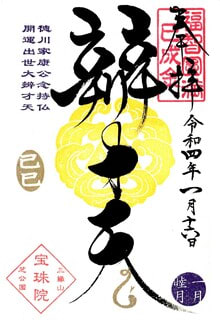
■ 寶珠院・開運出世大辨財天の御朱印
・寶田恵比寿神社の恵比寿神
「馬込勘解由と云う人は家康公が入府の時、三河の国から随行して、此の大業を成し遂げられた功に依り、徳川家繁栄御祈念の恵比寿様を授け賜ったので、平穏守護の御神体として宝田神社に御安置」(日本橋江戸屋Webより)とのこと。
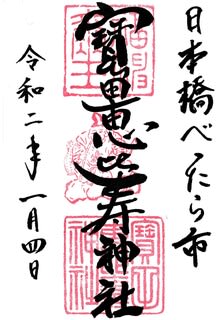
■ 寶田恵比寿神社の御朱印
【家康公と宗派】
家康公と各宗派とのゆかりについて、まずは代表例をざっくりと書き出してみます。主に関東周辺関連です。
〔浄土宗〕
家康公は「熱心な浄土宗信者」で(知恩院Web、浄土宗大辞典)増上寺住職・源誉存応上人に帰依し、葬儀も浄土宗の増上寺であげられています。
徳川家の菩提寺は増上寺で、徳川氏(松平氏)の菩提寺・大樹寺(愛知県岡崎市)も浄土宗です。
小石川の傳通院は、慶長七年(1602年)に家康公のご生母於大の方が逝去し、家康公が菩提寺とされて現号に改め、以来徳川家の菩提寺として重きをなしました。
行徳の徳願寺、蔵前の松平西福寺も家康公開基と伝わります。
また、鎌倉大長寺の住職暁誉源栄は、小田原征伐時に家康公の意を受け玉縄城主北条氏勝を説得して開城につなげ、以降家康公との交流を深めたといいます。
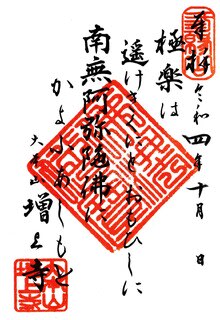
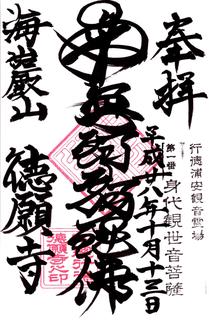
【写真 上(左)】 増上寺の御朱印(御詠歌)
【写真 下(右)】 徳願寺の御朱印
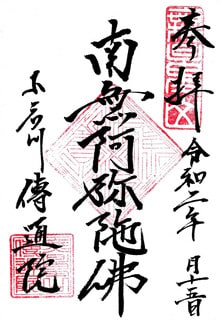

【写真 上(左)】 傳通院の御朱印
【写真 下(右)】 大長寺の御朱印
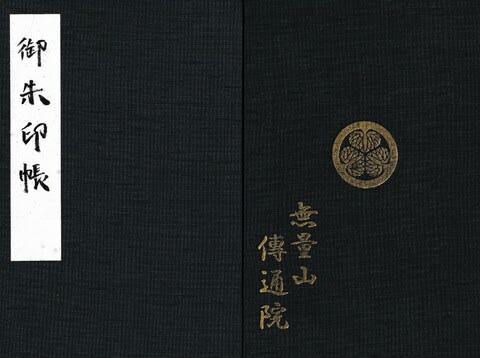
■ 葵の御紋が入った傳通院の御朱印帳
徳川軍の旗印「厭離穢土欣求浄土」(お(え)んりえどごんぐじょうど)は浄土宗(浄土教)の思想に基づくものとの説があります。
〔天台宗〕
家康公は天台宗の天海大僧正に帰依(喜多院Web、会津美里町観光協会Web)したことから、天台宗との関係もふかいとされます。
天海大僧正が創建された上野の寛永寺は、江戸城の鬼門の守護とされる門跡寺院です。
上野の輪王寺には天海(慈眼大師)と良源(慈恵大師、元三大師)の両大師が祀られています。
舞台造りで有名な上野の清水観音堂も天海大僧正の建立です。


【写真 上(左)】 喜多院の御朱印
【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印


【写真 上(左)】 上野輪王寺の御朱印
【写真 下(右)】 上野・清水観音堂の御朱印
〔臨済宗〕
駿府時代の家康公が師事したともいわれる太原雪斎(崇孚)は臨済禅であり、晩年のブレーンのひとり金地院(以心)崇伝も臨済禅でした。(清見寺(静岡市清水区)Web)
幼少時の家康公は、太原雪斎ゆかりの臨済寺(静岡市葵区)に居住し学んだと伝わります。
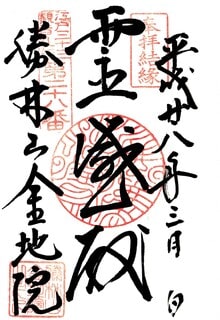
■ 金地院崇伝創建の芝・金地院の御朱印
〔曹洞宗〕
曹洞宗寺院の可睡斎(静岡県袋井市)の第11代住職仙隣等膳は竹千代の教育を受け持ったことがあり、後に浜松城主となった家康公が等膳和尚を城に招いた際、居眠りを始めてしまった和尚に親しみ、家康公が「可睡斎」と名付けたという逸話がのこります。山内には三方ヶ原の戦いで武田軍から逃れた家康公が隠れたとされる洞窟「出世六の字穴」がいまも残ります。
泉岳寺(東京・高輪)は、家康公の開基と伝わります。
来見寺(茨城県利根町)の住職は家康公の知己で、公が立ち寄った際「私が来て見たので、来見寺にせよ」との言で改号されたと伝わります。


【写真 上(左)】 泉岳寺の御朱印
【写真 下(右)】 来見寺の御朱印
〔真言宗〕
家康公は駿府在住時にしばしば真言宗の音羽山清水寺観音堂に詣で、念待仏の恵心僧都作の千手観音の像や寺領を寄進したといい、住職秀尊阿闍梨は陣僧として行動をともにしたともいいます。
また将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立しています。
また、筑波山の知足院中禅寺(現・大御堂)は家康公以来将軍家と幕府の祈祷を行っていたとされ、知足院の江戸別院・護持院はのちに音羽護国寺の境内に移されて幕府の祈願寺としての役割を担いました。
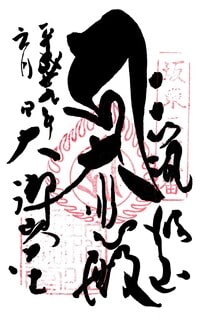
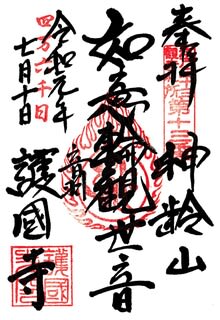
【写真 上(左)】 つくば大御堂の御朱印
【写真 下(右)】 護国寺の御朱印
〔時宗〕
・「松平八代」の初代とされる親氏公は時宗の僧で徳阿弥と称し、諸国遍歴後、三河の地にたどり着いたとされています。
称名寺(愛知県碧南市)は三河松平家(徳川家)との関わりがふかく、家康公の幼名竹千代は十五世一天和尚が命名と伝わり、山内には三州大浜東照宮が鎮座します。
〔日蓮宗〕
台東区根岸の要伝寺のWebには、家康公と日蓮宗とのゆかりが記され、これによると、谷中の瑞輪寺は家康公の開基檀越、世田谷区北烏山(もと神田湯島)の幸龍寺も家康公の開基で徳川将軍家の祈願寺として外護されたとされています。
神楽坂の善國寺も家康公開基と伝わります。
鎌倉・植木の日蓮宗寺院・久成寺は、小田原合戦の際に家康公が立ち寄り寺領を寄進、以降も外護されたと伝わります。
身延山には家康公の側室で熱心な日蓮宗信徒であった養珠院(お万の方)ゆかりの上の山東照宮が祀られています。
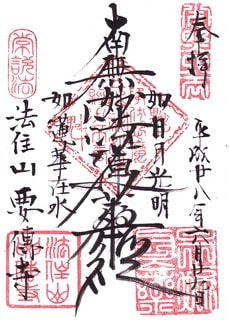
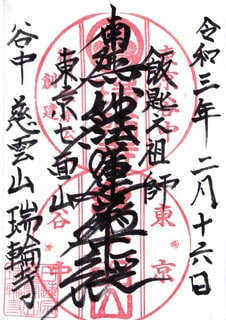
【写真 上(左)】 要伝寺の御首題
【写真 下(右)】 瑞輪寺の御首題
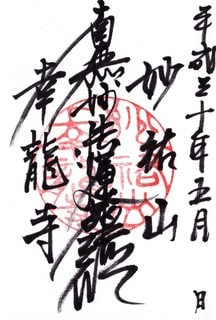
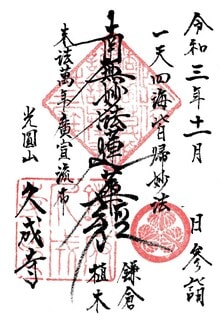
【写真 上(左)】 幸龍寺の御首題
【写真 下(右)】 久成寺の御首題
一般に家康公は浄土宗、天台宗とのゆかりがふかいとされますが、以上のように多くの宗派と関係をもっていました。
【家康公ゆかりの神社】
家康公ゆかりの神社としては、家康公(東照大権現)を祀る東照宮が代表格ですが、他にも家康公ゆかりの神社は数多くあります。
〔八幡社〕
浜松八幡宮は浜松城の鬼門の方角に位置していたことから家康公が鬼門鎮守として信仰し、度々参拝したといいます。
また家康公は、伊賀八幡宮(愛知県岡崎市)への尊崇篤かったといわれます。
〔浅間神社〕
静岡浅間神社は、天文二十四年(1555年)、駿府で人質となっていた14歳の竹千代が元服し松平元信となった神社とされます。
江戸時代には、徳川家康公の崇敬社として歴代将軍の祈願所にもなりました。
家康公は駿河国一之宮富士山本宮浅間神社にも神殿を寄進しており、浅間神社への崇敬が篤かったことがうかがえます。
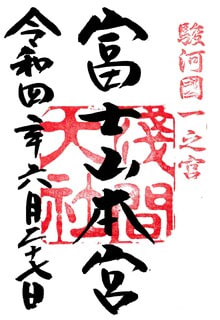
■ 富士山本宮浅間神社の御朱印
〔神田明神〕
家康公は関ヶ原の戦いの前に神田明神に戦勝祈願したとされ、成就ののちも江戸総鎮守として広く人々から崇敬を受けました。
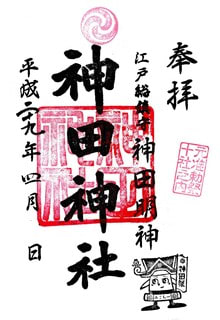
■ 神田神社(神田明神)の御朱印
〔稲荷神〕
江戸の街にこれだけ稲荷神社が広まったのは、家康公の稲荷神信仰の影響という説があります。
文京区本郷の三河稲荷神社はもともと三州碧海郡上野庄稲荷山に御鎮座で、家康公の崇敬篤く、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して造営奉遷とされています。
千代田区神田駿河台の太田姫稲荷神社(一口稲荷神社)は慶長十一年(1606年)の江戸城大改築の際、城内に御遷座の当社を西丸の鬼門にあたる神田駿河台に御遷座と伝わり、相伝には菅原道真公と徳川家康公が祀られています。
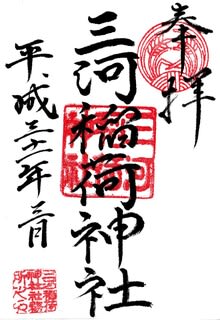

【写真 上(左)】 三河稲荷神社の御朱印
【写真 下(右)】 太田姫稲荷神社の御朱印
〔天満宮・天神社〕
霊光殿天満宮(京都市上京区)は家康公の崇敬篤く、家康公も祭祀されています。
湯島天神は家康公の崇敬を受け、桐生の総鎮守・桐生天満宮は天正九年(1581年)、徳川家の祈願所となり、関ヶ原合戦の際には戦勝祈願したと伝わります。
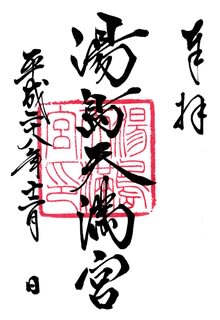
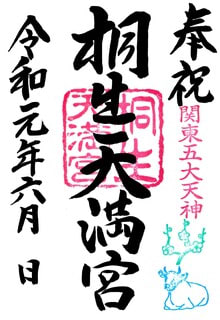
【写真 上(左)】 湯島天神(湯島天満宮)の御朱印
【写真 下(右)】 桐生天満宮の御朱印
〔氷川神社〕
江戸・武蔵一帯は氷川神社の多いところです。
家康公は文禄五年(1595年)伊奈備前守忠次を奉行として武蔵一之宮氷川神社の社頭を造営しています。
赤坂氷川神社も徳川将軍家代々の尊崇を受けたと伝わります。
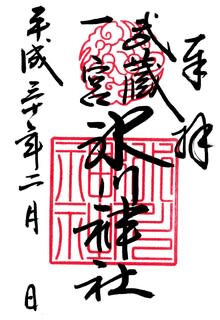
■ 武蔵一宮氷川神社の御朱印
〔愛宕神社〕
港区愛宕の愛宕神社は、慶長八年(1603年)、家康公の命により江戸の防火の神様として創祀され、以降も徳川家の尊崇篤い神社です。
愛宕権現の江戸期の別当、圓福寺は家康公が伊賀越えに際して護持された勝軍地蔵を本地佛として奉安し、この勝軍地蔵は明治に入って真福寺に遷られました。
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6の第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺を参照。

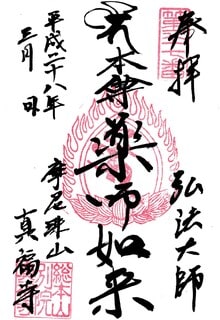
【写真 上(左)】 愛宕神社の御朱印
【写真 下(右)】 真福寺の御朱印
〔湯前神社〕
家康公はしばしば熱海に湯治に行かれたと伝わります。
この故事にならってか、熱海の大湯のお湯を江戸将軍家に献上する「湯くみ道中」の記録が伝わります。
湯前神社の御祭神は薬神、温泉の神ともされる少彦名命。
家康公は製薬調合の達人としても知られているので、少彦名命への崇敬も篤かったかもしれません。
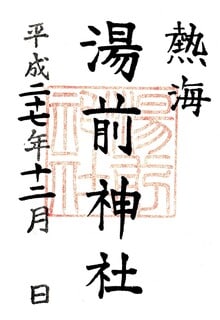
■ 湯前神社の御朱印
〔諏訪神社〕
諏訪大社上社本宮の四脚門は、慶長十三年(1608年)家康公が大久保長安に命じ、国家の安泰を祈願して造営寄進したもので、勅使門とも呼ばれます。
浜松市中区の諏訪神社は、秀忠公誕生に当り産土神として崇敬され、天正7年(1579年)家康公が社殿を造営したといいます。(昭和37年、五社神社と合祀され、五社神社諏訪神社となっています。)
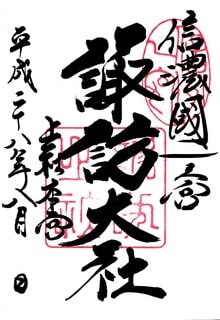
■ 諏訪大社上社本宮の御朱印
〔賀茂神社〕
徳川家の先祖・松平家は賀茂神を崇めていたといわれ、各地に徳川・松平家ゆかりの賀茂神社がみられます。
徳川宗家の家紋「三つ葉葵」は、賀茂神と関係があるという説があります。(賀茂神社の神紋は葵紋)
〔日枝神社〕
山王の日枝神社は、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して家康公が江戸城を居城とするにあたり、「徳川家の守り神」「江戸の産神」として崇敬したと伝わります。(太田道灌が川越から山王社を勧請)
日枝信仰は山王一実神道とふかいかかわりをもち、家康公祭祀を語るうえで重要なファクターです。


【写真 上(左)】 日枝神社の御朱印
【写真 下(右)】 日枝神社境内社 猿田彦神社の御朱印
〔山王一実神道〕
家康公祭祀を語るうえで外せないのが、山王一実神道(さんのういちじつしんとう)です。
もともと山王神道(さんのうしんとう)は、鎌倉時代にかけて天台宗総本山・比叡山延暦寺で生まれ、日枝山(比叡山)の山岳信仰、神道、天台宗が融合した流派で、本地垂迹説を容れた神仏習合の思想とされます。
僧・天海は山王神道説をベースに山王一実神道へと発展させ、家康公の歿後、山王一実神道に則り家康公の霊を東照大権現として祭祀しました。(当初は吉田神道の流儀で埋葬されたという説あり)
日光の家康公の墓所には東照宮が建立され、東照大権現は薬師如来の垂迹とされました。(『東照大権現縁起』)
天台宗と山王一実神道との関係はきわめて複雑で、日光の「二社一寺」(日光東照宮、二荒山神社、輪王寺)、上野東照宮と寛永寺(寒松院)、川越の仙波東照宮、喜多院、日枝神社の例をみるとその複雑さが実感できます。
鳴龍で有名な日光東照宮の本地堂は、日光東照宮の境内にありながら、家康公ゆかりで東照大権現の本地とされる薬師如来を奉安する輪王寺のお堂なのです。
もはやこうなると、神社やらお寺やら、手を叩いて参拝していいのやらそれすらもわからないカオス的な状況となってきます。
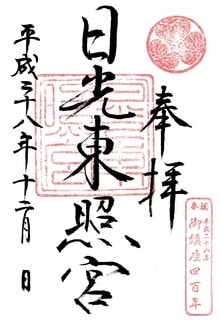
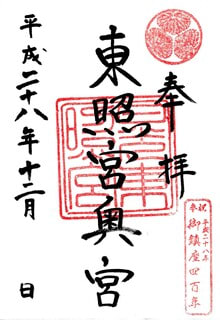
【写真 上(左)】 日光東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 日光東照宮奥宮の御朱印


【写真 上(左)】 日光二荒山神社本社の御朱印
【写真 下(右)】 日光二荒山神社中宮祠の御朱印


【写真 上(左)】 日光山 輪王寺 黒門の御朱印
【写真 下(右)】 日光山 輪王寺 本地堂の御朱印
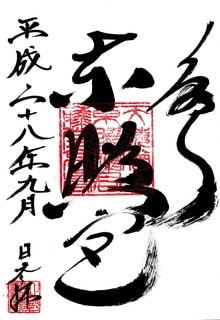

【写真 上(左)】 上野東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印
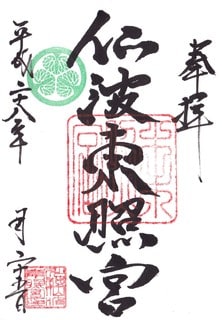
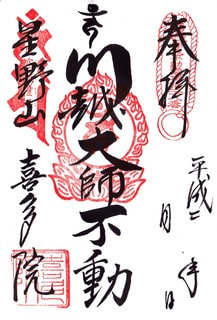
【写真 上(左)】 仙波東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 喜多院の御朱印

■ 日枝神社の御朱印
家康公の祭祀を辿ることは、江戸時代に隆盛を極めた神仏集合の歴史を辿ることかもしれません。
なお、群馬県太田市徳川町・世良田町周辺は「徳川氏発祥の地」とされ、家康公ないし徳川家ゆかりの寺社が少なくありません。家康公ゆかりの地としてこのエリアを訪ねてみるのも面白いかもしれません。
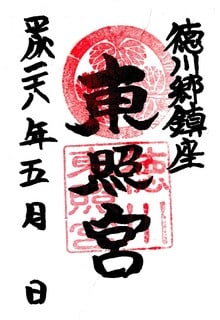
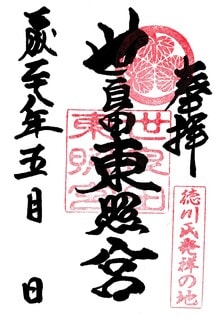
【写真 上(左)】 徳川東照宮の御朱印
【写真 下(右)】 世良田東照宮の御朱印
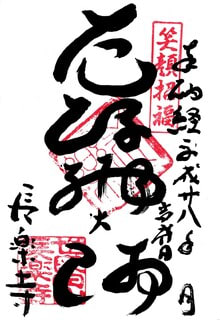
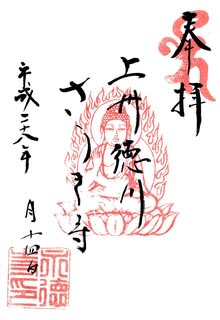
【写真 上(左)】 長楽寺(太田市世良田町)の御朱印
【写真 下(右)】 永徳寺(太田市徳川町)の御朱印
太田市の大光院は、慶長十八年(1613年)一族の繁栄と始祖新田義重公の追善供養のため、芝増上寺の観智国師の門弟で四哲の一人といわれた呑龍上人を開山に迎え、家康公が開基した寺院と伝わります。

■ 大光院の御朱印
足利市の鑁阿寺は、世良田氏(新田氏流・徳川氏の祖ともされる)の祖・世良田頼氏の正室が足利義氏の娘である関係から家康公が帰依したと伝わり、寺領60石を安堵されたといいます。

■ 鑁阿寺の御朱印
太田、足利あたりは、探せばまだ家康公ゆかりの寺社がみつかると思います。
-------------------------
家康公の室の開基ないしゆかりの寺院も少なくありません。
・正室・築山殿(瀬名姫) 嫡男信康、長女亀姫の生母
築山殿を祀る月窟廟は西来院(浜松市中区/曹洞宗)
・継室・南明院(朝日姫、駿河御前) 豊臣秀吉の異母妹
墓所は凌雲山 東福寺(南明禅院)(京都市東山区/臨済宗東福寺派)
・蓮葉院(西郡局、於葉の方) 二女督姫の生母
墓所は本禅寺塔頭・心城院(京都市上京区/法華宗)、芳荷山 長應寺(品川区小山/法華宗陣門流)
・長勝院(於古茶、於万の方、小督局) 次男結城秀康の生母
墓所は天女山 孝顕寺(茨城県結城市/曹洞宗)
・竜泉院(西郷局、於愛の方) 三男秀忠公、四男松平忠吉の生母
墓所は金米山 宝台院(静岡市葵区/浄土宗)
・良雲院(於竹の方) 三女振姫の生母
墓所は東光山 西福寺(松平良雲院)(台東区蔵前/浄土宗)
・下山殿(於都摩の方、於津摩の方、秋山夫人) 五男徳川信吉の生母
墓所は長谷山 本土寺(千葉県松戸市/日蓮宗)
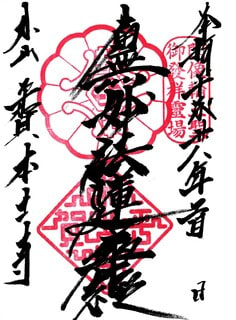
■ 本土寺の御首題
・茶阿局(於茶阿、お八) 六男松平忠輝、七男松平松千代の生母
墓所は吉水山 宗慶寺(文京区小石川/浄土宗)

■ 宗慶寺の御朱印
・普照院(於久の方) 四女松姫の生母
墓所は玉桂山 華陽院(静岡市葵区/浄土宗)
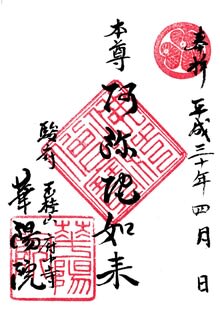
■ 華陽院の御朱印
・相応院(於亀の方) 八男松平仙千代、九男徳川義直(尾張家)の生母
菩提寺は宝亀山 相応寺(名古屋市千種区/浄土宗)
・養珠院(於万の方) 十男頼宣(紀伊家)、十一男頼房(水戸家)の生母
墓所は大野山 本遠寺(山梨県身延町/日蓮宗)
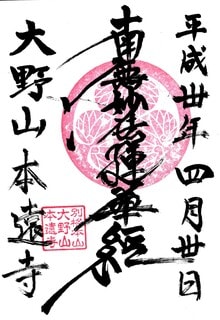
■ 本遠寺の御首題
・英勝院(於梶の方、於勝の方) 五女・市姫の生母
墓所は東光山 英勝寺(鎌倉市/浄土宗)、経王山 妙法華寺(静岡県三島市/日蓮宗)
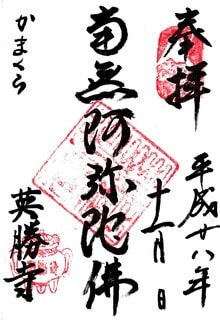
■ 英勝寺の御朱印
・蓮華院(於梅の方)
墓所は観音山 梅香寺(三重県伊勢市/浄土宗)
・雲光院(阿茶局)
墓所は開基の龍徳山 雲光院(江東区三好/浄土宗)

■ 雲光院の御朱印
・正栄院(於牟須の方)
肥前名護屋で逝去
・泰栄院(於仙の方)
駿府で死去。墓所は藤枝の浄念寺から信濃浄久寺に改葬。
・養儼院(於六の方)
墓所は日光山内?
・清雲院(於夏の方、於奈津の方)
墓所は無量山 傳通院(文京区小石川/浄土宗)、東照山 清雲院(三重県伊勢市/浄土宗)

■ 傳通院の御朱印
・信寿院((山田)富子)
墓所は長栄山 池上本門寺(大田区池上/日蓮宗)
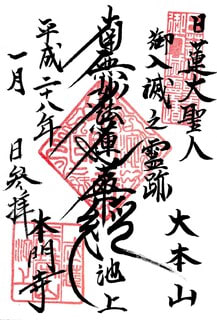
■ 池上本門寺の御首題
・法光院(於松の方?) 松平民部の生母?
・三条氏 小笠原権之丞の生母
宗派は浄土宗と日蓮宗が多く、家康公の室はこのふたつの宗に帰依しやすい環境だったのかもしれません。
東京には御府内八十八ヶ所霊場という弘法大師霊場があり、家康公ないし徳川家ゆかりの寺院もすくなくありません。
なので、併行してこちらの記事で御府内八十八ヶ所霊場も紹介していきたいと思います。
【 BGM 】
■ A Clue - Boz Scaggs
■ That's Why - Michael McDonald
■Oh Yeah! - Roxy Music
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6
Vol.-5からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第18番 獨鈷山 光明寺 愛染院
(あいぜんいん)
新宿区若葉2-8-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第18番
司元別当:
授与所:庫裡ないし本堂前
第18番はいきなり四ッ谷に飛びます。
開山について『ルートガイド』と史料類で異なるので、まずは『ルートガイド』から要旨を引用してみます。
天正年間(1573-1592年)、加藤清正の実弟・正濟上人が麹町貝坂のあたりに開いたといいます。
慶長十六年(1611年)麹町から四谷に、寛永十一年(1634年)に現在地に移転しています。
ところが 『寺社書上』『御府内寺社備考』および、それらを典拠とした「四谷区史」はさらに古い縁起を伝えています。
弘仁年中(810-824年)、弘法大師が関東巡錫の折に現在の麻布善福寺の地に創建、本尊五指量愛染尊を安置され「八祖相承之獨鈷」を納められたといいます。
その後慶長十六年(1611年)正斎上人(加藤清正の実弟?)が麹町貝塚の地に中興、寛永十一年(1634年)現在地に移転といいます。
たしかに麻布善福寺の公式Webには「麻布山善福寺は、平安時代の天長元年(824年)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。」と明記されています。
(のちの鎌倉時代に真言宗から浄土真宗に改宗)
『寺社書上』には「然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給」とあり、愛染院が善福寺の奥之院であったことを伝えています。


【写真 上(左)】 麻布善福寺
【写真 下(右)】 麻布善福寺の参拝記念印
↑ 参拝記念印に「弘法大師開山」とあります。
加藤清正の実弟という正濟(斎)上人についてもほとんど情報がとれません。
清正公は熱心な日蓮宗の信徒として知られています。
兄弟が同じ信仰とは限りませんが、日蓮宗の重要人物の実弟が密寺を中興とは、すんなり頷けないものはあります。
『寺社書上』をみると、弘法大師創建を物語る数々の寺宝が列挙されています。(下記)
弘法大師の御作、御筆の寺宝だけでも実に5点以上を数え、しかも「開祖 弘法大師」と明記されています。
故なきところにこれだけの縁起や寺宝が残るのは不自然ですから、やはり愛染院は真言宗時代の麻布善福寺となんらかの関係があったのでは。
現時点ではこれ以上の史料がみつからないので、ここまでにしておきます。
現地の案内書には沿革として『四谷区史』(文政寺社書上の引用部)が掲載され、同書には中興開山の正斎は寛永十五年(1638年)の寂とありました。
御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされ、愛染院の現在地への移転はそれ以前の寛永十一年(1634年)。
江戸八十八ヶ所霊場でも同番の第18番ですから、御府内霊場開創時からの札所とみられます。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.63』
大塚護持院末 四ッ谷南寺町 獨鈷山 光明寺 新義真言宗 愛染院
当寺開闢之儀は、人王五拾弐代嵯峨天皇御宇 弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、當國一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五●量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候
開祖 弘法大師 中興 正済(?)上人 中興二世 實盛 寛永十二年(1638年入寂)
本尊 両部大日如来
両脇士 不動尊 愛染尊 智證大師作
増長天 廣目天 持國天 多聞天
弘法大師木座像弐尺弐寸● 厨子入 興教大師 厨子入
辨財天 附十五童子 弘法大師作
阿弥陀如来 恵心僧都作
八祖相承獨鈷 但弘法大師●持ト●
四處明神 寛平法皇(宇多天皇)
弘法大師 右御同筆
愛染明王 弘法大師筆
五大明王 興教大師筆
愛染明王 嵯峨天皇御筆
般若心経 弘法大師筆
愛染堂
本尊 愛染明王 弘法大師作 丈二寸余
脇立 不動明王 愛染明王
大聖天三躰
本地十一面観音 弘法大師作 丈一尺八寸厨子入
鎮守社 稲荷 金毘羅 愛宕
寺中弐ヶ院
光明院 本尊 大威徳明王 開山不知
蓮花院 本尊 弥陀如来 開山不知
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
獨鈷山光明寺愛染院は、大塚護持院末の新義真言宗で、四谷南寺町今の寺町にある。境内は千五百廿坪余の拝領地で、起立は慶長十六年辛亥(1611年)、麹町貝塚邊が元地であつた。寛永十一年甲戌(1634年)十二月に此地に替地を賜うて移転したのである。
文政寺社書上に拠れば、「当寺開闢之儀は、人王五十二代嵯峨天皇御宇、弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、当國に一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候」と伝へて、その来由することの頗る古きを語つて、慶長(1596-1615年)当時の開山正斎はその中興と称して居る。此地に移つて以来、住持を替ふること八代、寶暦十年庚辰(1760年)梵鐘を鑄たが、鐘銘中に(略)「惟愛染堂假而毎免、可謂幸矣」といふことが見えて、愛染尊の功徳厳然たるを称へている。
-------------------------


【写真 上(左)】 愛染院前から東福寺坂
【写真 下(右)】 山内入口
四谷周辺、若葉、須賀町から鮫河橋にかけては寺院が集中する寺町となっています。
これは、寛永年間(1624-1645年)家光公の治世に江戸城外堀工事のため、麹町の寺院が一斉に四谷に移転させられたためといいます。
愛染院の元地は麹町貝塚邊で、寛永十一年(1634年)に現在地に遷っているので、この江戸城外堀工事によるものとみられます。
このあたりはことに土地の起伏が激しいところで、凹凸地形マニアの聖地となっています。
(→ 四谷の坂道レポ)
新宿通りから円通寺坂を南に下って鮫河橋に至る道(名称不明)が谷筋で、そこから東西方向はすべて登り坂となります。
愛染院はこの谷道から東福院坂(天王坂)を登った坂の途中に、坂名の由来である東福院とほぼ向き合ってあります。
東福院は御府内霊場第21番札所、他にも御府内霊場札所がいくつかありますので、順打ち(逆打ち)でない場合は、まとめてまわることになります。


【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 案内書
門まわりは赤レンガで固められ、すぐ奥は駐車場。
さらにその奥にも黒い門扉を構えて、なんとなく近寄りがたい空気が漂っています。
こちらは直書き御朱印は納経者のみ授与なので、そんな先入観もあるのかもしれません。
山内入口に院号標と案内書(上記)。
内藤新宿の生みの親、高松喜六の墓と、江戸中期の国学者・塙保己一の墓の説明書もあります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
第二の門を抜けると俄然古刹の雰囲気が出てきます。
正面本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った寺院建築で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に三連の本蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
向拝と左右の身舎扉は格子状で小壁に菱格子を置き、きりりと引き締まった印象。
本堂右手の梵鐘には貴重な百字真言や銘叙が刻され、銘叙は湯島霊雲寺第四世法明が識(しる)されたものです。
(鐘楼は堂宇とともに戦火で焼失。)
当山は真言宗豊山派ですが、真言律宗となんらかの交流があったのかもしれません。


【写真 上(左)】 梵鐘
【写真 下(右)】 「倶會一處」の石碑
倶會一處(くえいっしょ)の石碑もあります。
倶會一處(倶会一処)とは、『阿弥陀経』の「舎利弗。衆生聞者。応当発願。願生彼国。所以者何。得与如是。諸上善人。倶会一処。舎利弗。不可以少善根。福徳因縁。得生彼国。」にある経文で、阿弥陀佛の極楽浄土への往生を願って一途に念仏の信仰に生きる心持ち、あるいは念仏信仰により、ご先祖や家族たちとともに極楽浄土の仏や菩薩と一処で出会うことができるという趣旨で、主に浄土教(浄土宗、浄土真宗)で説かれ、浄土宗寺院では御朱印に揮毫されることもあります。
ただし、密教寺院でこの言葉に触れることはめずらしいのでは。
こちらの御朱印は原則、本堂前に用意された印判の自捺しで、納経者にのみ「特別の朱印」(揮毫御朱印)が授与されます。
自捺し御朱印は金属箱のなかの印判と朱肉を使い、見本も置いてあるのでとくに問題なく拝受できます。
御朱印代として300円(2017年6月時点)をお納めしました。
印判自捺しの場合、御朱印帳への直捺しは一発勝負となりリスクがあります。
筆者は常々、御朱印帳とサイズを合わせた和紙を数枚持ち歩き、そちらに捺してその紙をのちほど御朱印帳に貼付けます。
これだと、失敗をおそれることなく自捺しができます。老婆心ながら・・・。
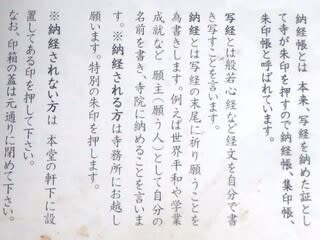

【写真 上(左)】 御朱印についての案内書
【写真 下(右)】 庫裡サイドから本堂
筆者は最初の参拝では自捺し御朱印を拝受、2度目以降の参拝では般若心経を納経して揮毫御朱印を拝受しました。
いささか敷居の高さを感じるお寺さまですが、ご対応はご親切でした。
なお、以上は平成元年11月時点の情報で、現在もこの授与方式かどうかはわかりません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
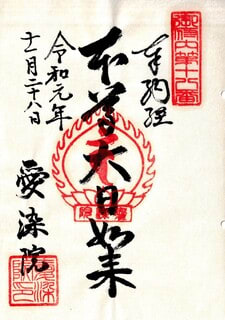
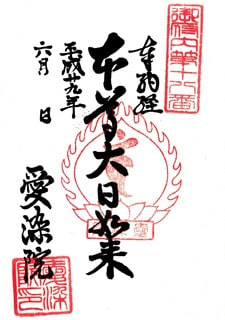
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第十八番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 自捺しの印判御朱印
■ 第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺
(しょうれんじ)
板橋区成増4-36-2
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第77番、荒川辺八十八ヶ所霊場第86番
司元別当:(成増村)山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))
授与所:庫裡
第19番にはふたつの札所がリストされています。
ひとつは板橋の青蓮寺、もうひとつは馬込の圓乗院です。
順にご紹介していきます。
青蓮寺の開基開山は不詳ですが、当初弁天塚付近(現高島平4-23付近)にあったとされ、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して3つの弘法大師霊場の兼務札所となりました。
-------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(成増村)
青蓮寺 新義真言宗 上石神井村三寶寺末 本尊薬師
(成増村)
山王社 青蓮寺持
『新編武蔵風土記稿』の記述は簡素なので詳細不明です。
孫引きで恐縮ですが、「猫の足あと」様が引かれている『いたばしの寺院』の記述を抜粋引用させていただきます。
「開基開山については明確な口碑さえなく、わずかに伝えるところによれば、寺は始め、弁天塚のほとり(現高島平4-23あたり)に建てられてあったが水害のためにいつの時代にか現在地に移転したという。本尊薬師如来が室町時代の作風を持つので、寺の創建も凡そその時代の頃を推定される。(略)文政末期から大正初期まで凡そ百年間は無住であった。(略)大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺し、昭和9年に13世正善大和尚入山以来、本寺は面目を一新したという。なお、本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」
以上から、青蓮寺は室町時代創建の古刹で、大正初期に再興、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して御府内霊場の札所となったことがわかります。
また、『新編武蔵風土記稿』によると、青蓮寺は江戸期には村内の山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))の別当でした。

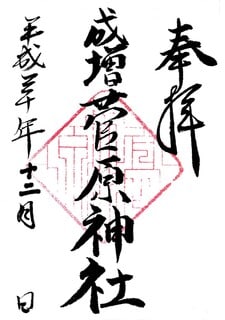
【写真 上(左)】 (成増)菅原神社 (成増天神)
【写真 下(右)】 (成増)菅原神社 (成増天神)の御朱印
弘法大師霊場から青蓮寺を語るとき、浅草の清光寺は外せず、御府内霊場に限っていえば愛宕の圓福寺も避けて通ることができません。
どうして圓福寺まで辿る必要があるかというと、江戸八十八ヶ所の第19番は「(愛宕)円福院」で、明治2年の廃仏毀釈を受けて圓福寺が廃絶するまでは圓福寺が御府内霊場第19番だった可能性が高いからです。
浅草清光寺、愛宕圓福寺ともに現在廃寺(ないし合寺)となっています。
しかし愛宕圓福寺は御府内霊場とのゆかりが深いので、できる限り史料を当たって縁起沿革を探ってみたいと思います。
□【愛宕圓福寺】
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕別當 圓福寺
武州豊島郡芝愛宕
新義真言宗触頭 別當 圓福寺
本寺 山城國宇陀郡醍醐山無量壽院
山号等 愛宕山寶珠院圓福寺
本尊 地蔵菩薩 厨子入 定朝作
不動明王 本尊左脇立
毘沙門天 同右脇立
本堂内安置 十一面観自在菩薩
同所 聖天
●祖弘法大師 興教大師
開山 俊賀
圓福寺地中幷末寺
(圓福寺地中脇坊)
金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院
(御府内三田寺町)寶生院
(御府内浅草寺町)威光院
(御府内浅草寺町)清光院
(御府内下谷坂本)大聖院
-------------------------
【史料】
-------------------------
■ 『江戸名所図会 7巻 [3]』(国立国会図書館)
(愛宕山権現社/抜粋引用)
本地佛を勝軍地蔵尊 行基大士の作なり 永く火災を退けるの守護神なり
別當圓福教寺ハ石階の下にあり 新議の真言宗江戸の触頭四箇寺の随一なり
開山を神證上人と号す 二世俊賀上人といふ
四箇寺とハ湯島根生院、本所彌勒寺、當所真福寺並に當寺(圓福寺)といふ
神證上人下野の人なりて 姓を塩谷氏母ハ皆川氏なり
元和五年(1619年)鈞命に依って金剛院に退居をゆるさ●天年を終ふ
春音(神證上人)の坊ハ遍照院と号す 今の圓福寺是なり
金剛院 普賢院 満蔵院 鏡照院 壽桂院等末●六院あり
俊賀上人 野州西方邑の人姓ハ越路氏にして宇都宮弥三郎頼綱の後裔
父ハ伊勢守近津神祠に祈りて産す 祖始下妻の圓福寺に住を然
其頃下総結城の元寿 上州松井田秀算等一世の豪俊●● 俊賀上人をあハせて新義の三傑と称せらる
元和五年(1619年)俊賀上人愛宕権現の別當に命せられ 共に圓福寺の号を●く一宇を開きしめ
-------------------------
江戸期の真言宗には「江戸四箇寺触頭」という制度があり、これにより本末関係が精緻に整えられていました。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)によると、発足当初の「江戸四箇寺触頭」はつぎの4箇寺です。
・知足院(江戸白銀町)
→ 関連資料
・真福寺(愛宕下)
・円(圓)福寺(愛宕下)
・弥勒寺(本所)
智積院公式Webには「貞享4年(1687)七月に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、代わりに根生院が任じられます。以後、明治までは変化はありません(円福寺は明治二年に廃仏毀釈により廃寺)。」とあるので、貞享四年(1687年)以降は真福寺(67)、圓福寺(19)、弥勒寺(46)、根生院(35)の四箇寺体制となっています。
( )内は御府内霊場の札番で、これをみても御府内霊場が真言宗の名刹をおおむねカバーしていたことがわかります。
また、『宝瞳寺文書解題』(国文学研究資料館/PDF)にも「江戸四箇寺触頭」の役割が詳細に記されています。
圓福寺は「江戸四箇寺触頭」を勤められ、御府内にいくつもの末寺をもつ御府内有数の名刹でした。
これほどの名刹がどうして明治の廃仏毀釈でいともあっさり(?)と廃絶してしまったのでしょうか。
(実際、触頭4箇寺のうち他の3箇寺は現存しています。)
どうにも気になったので、まずはここから調べてみました。
真福寺の勝軍地蔵尊の説明書には以下のとおりあります。
「この勝軍地蔵菩薩は、天平十年(738年)行基が近江信楽遊行の砌、造顕したもので、同地に安置され、霊験あらたかなり。天正十年(1582年)徳川家康、本能寺の変の難を逃れんがため伊賀越に際し、信楽の土豪多羅尾氏、当勝軍地蔵を献上、沙門神証これを護持し、三河に帰還するをえたり。爾来、家康の帰依厚し。慶長八年(1603年)家康、征夷大将軍に栄進するにより、江戸に愛宕神社を創建し、同社の本地仏として勧請、神証を別当の円福寺第一世とせり。明治の廃仏毀釈で円福寺は廃寺、尊像は真福寺に移されたが、大正十二年 (1923年)関東大震災で焼失、昭和九年(1934年)弘法大師一千百年御遠忌記念として、霊験を不朽にせんがため、銅製で造顕せり。」
一方、愛宕神社の公式Webには配祀として将軍地蔵尊が明記され、愛宕権現(神社)にとって将軍(勝軍)地蔵尊がいかに重要な尊格であるかがわかります。
以上から、圓福寺は愛宕権現の別当の色彩がすこぶる濃厚だったとみられます。
この点は、全国の愛宕神社の総本社とされる愛宕神社(京都市右京区嵯峨愛宕町)と、その別当・白雲寺との関係とよく似ています。
中世~江戸期の愛宕権現社の多くは、本殿に愛宕大権現の本地仏である勝軍地蔵、奥の院に愛宕山の天狗の太郎坊が祀られたといいます。
神仏習合のもと修験道の道場として栄えたこともあり、別当の勢力はたいへん強かったとみられます。
この強大な立場が明治の廃仏毀釈で裏目に出て、愛宕権現の別当・圓福寺は存続の危機に見舞われたのでは。
実際、京都の愛宕神社総本社の別当・白雲寺は廃仏毀釈で廃絶となっています。
総本社の別当・白雲寺が廃絶となった以上、東都の愛宕権現の別当・圓福寺も、たとえ「江戸四箇寺触頭」の格式があったとしても廃絶を遁れられなかったのでは?
ちなみに『寺社書上』の圓福寺の項には「従是愛宕山上之分」として以下のとおりあります。
□「(圓福寺)従是愛宕山上之分」(諸佛のみ抜粋引用)
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕大権現御神● 秘像
御前立 勝軍地蔵尊
脇立 不動明王 毘沙門天
本地堂 脇坊金剛院持
朝日愛染明王
太郎坊北之方
唐●地蔵尊 勝軍地蔵尊 地蔵尊 石地蔵尊
女坂
勝軍地蔵尊
男坂上り口
役行者堂
-------------------------
これをみると江戸期の愛宕権現が諸佛に満ち、神仏習合していたことがよくわかります。
本地堂の別当は金剛院(圓福寺地内末寺)とあるので、愛宕権現全体の別当が圓福寺、本地堂の別当が金剛院という二重構造だったのかもしれません。
なお、『江戸名所図会』の愛宕社總門の絵図をみると、男坂の右手に本地堂、左手に別当(おそらく圓福寺)がみえ、本地・別当系の諸堂は坂下にあったことがわかります。
ここから「出世の石段」を登って参拝する愛宕権現は海抜26mという都内随一の高みにあり、ここからの見晴らしと桜花のすばらしさは御府内有数と称えられ、ほおずき市や羽子板市も賑わいをみせて江戸の図絵類に描かれています。
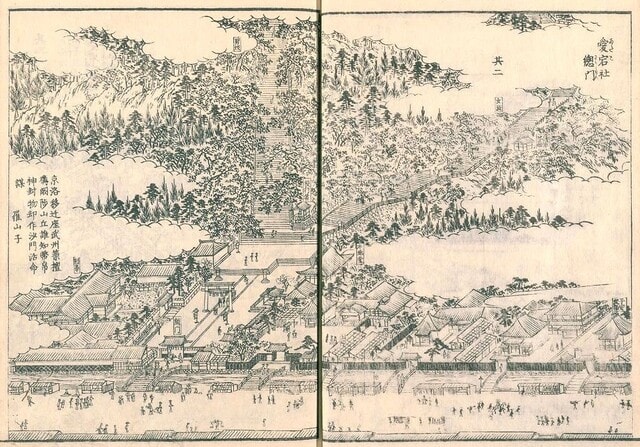
■『江戸名所図会』 7巻 (須原屋茂兵衛[ほか])/愛宕社總門
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
~ 伊勢へ七度 熊野へ三度 芝の愛宕へ月まいり ~ (愛宕神社御由緒書より)


【写真 上(左)】 愛宕神社社頭
【写真 下(右)】 出世の石段

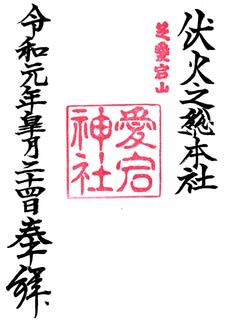
【写真 上(左)】 愛宕神社拝殿
【写真 下(右)】 愛宕神社の御朱印
真福寺勝軍地蔵尊の説明文のとおり、圓福寺が廃寺となったとき、御本尊の(勝軍)地蔵菩薩は愛宕の真福寺に遷られました。
このとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所だったので、重番を避けるため御府内霊場第19番は浅草の清光院に承継されたとみられます。


【写真 上(左)】 真福寺外構と勝軍地蔵尊
【写真 下(右)】 勝軍地蔵尊
圓福寺が廃されたとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所で、重番を避けるとしたら第19番は承継できません。
第20番金剛院は圓福寺の地内末寺で、本地堂の別当だったため同時に廃絶された可能性がありますが、こちらはおそらく同じ圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に承継されています。
で、圓福寺の第19番の行方です。
『寺社書上』に記載の圓福寺の御府内末寺(地内末寺のぞく)はつぎの4箇寺。
・(三田寺町)寶生院 / おそらく御府内霊場第69番(龍臥山 宝生院)
・(浅草寺町)威光院 / おそらく御府内霊場第62番(鶴亭山 威光院)
・(浅草寺町)清光院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第86番
・(下谷坂本)大聖院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第87番(宝橋山 大聖院)
末寺に御府内霊場札所を継がせるとなると、荒川辺八十八ヶ所霊場の2箇寺、すなわち清光院か大聖院とするのが自然な流れです。
下谷坂本(現・台東区北上野)の大聖院は御府内霊場札所集中エリアから若干離れているため、威光院(御府内霊場第62番)にほど近い清光院が承継したのでは。
以上はあくまでも筆者の憶測です。
□【清光院】
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [83] 浅草寺社書上 甲八止』(国立国会図書館)
※達筆すぎて読みとれないので、適宜『御府内寺社備考 P.108』にて補足しています。
浅草 不唱小名
新義真言宗 芝愛宕山圓福寺末
花園山神應寺清光院
諸書●号焼失 往古知不申●
開山 慈観法印 卒年不知
本尊 阿弥陀如来座像
弘法大師 興教大師
不動尊立像 長一尺五寸五分 土蔵ニ安置
扇稲荷社 神体白幣
護摩堂 不動尊立像
-------------------------
もうひとつナゾが残ります。
「猫の足あと」様には「清光院は、江戸時代の書物によると慶長11年(1606)頃の創建と言われていたようです。大正12年関東大震災で焼失し、青蓮寺に合寺されました。」とあります。
大正12年の関東大震災で焼失した清光院の名跡は下谷坂本の大聖院が継いでもよさそうですが、実際は成増村の青蓮寺が継いでいます。
震災後の混乱で大聖院による合寺は困難だったのかもしれず、あるいは郊外の青蓮寺に合寺したほうが安全という判断があったのかもしれません。
また、青蓮寺の本寺は練馬の名刹、三寶寺ですからその保護下に入ったほうが都合がよかったのかも。
いずれにしても決定的な史料がみつからない以上、憶測の域を出ることはできません。
とまれ、愛宕圓福寺から続く御府内霊場第19番の名跡は、大正13年の清光院合寺をもって青蓮寺に承継されました。
『いたばしの寺院』には「本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」とあるようです。
御府内霊場第19番と荒川辺霊場第86番はたしかに清光院由来とみられますが、豊島霊場は豊島郡メインの霊場なので、青蓮寺はもともと豊島霊場の札所だったのでは。
実際、『ルートガイド』には「本堂にある二体の弘法大師像は、震災の中持ち出した清光院八十八ヶ所十九番の尊像と青蓮寺に伝わってきた豊島八十八ヶ所七十七番の尊像だそうです。」とあります。
豊島霊場の開創は明治40年とされるので、豊島霊場第77番の青蓮寺が、関東大震災で焼失した浅草清光院(御府内霊場第19番、荒川辺霊場第86番)を大正13年に合寺し、3つの弘法大師霊場の兼務札所となったとみるのが妥当かと。
なお、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所一覧は→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。
天保九年(1838年)刊の『東都歳時記』に記されているため、文化年間(1804-1818年)以降にみられる八十八ヶ所巡りの流行を受けての開創ではないかとみられています。
初番・初願は根岸の世尊寺、日暮里、尾久、船堀、滝野川、豊島、江北、足立元木、西新井、梅田、千住、綾瀬、堀切、墨田、亀戸、元浅草とまわり、第88番結願は根岸の千手院です。
おもに下町をまわるので、御府内霊場との重複札所は亀戸・東覚寺、元浅草・延命院、元浅草・観蔵院、成増・青蓮寺の4箇寺と多くはありません。
-------------------------
最寄りは東武東上線「成増」駅・東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅ないし都営三田線「西高島平」駅ですが、いずれからもけっこうな距離があります。
周囲の道は入り組んで狭く、駐車スペース(?)も狭いので、交通アクセス的な難所といえそうです。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 札所碑


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
路地から階段の参道が伸び、門前に寺号標、札所碑、地蔵菩薩、如意輪観世音菩薩などが並びます。
山門はおそらく切妻屋根の薬医門で、門柱に札所板兼寺号板が掲げられています。
参道は途中で直角に曲がり、正面が本堂、その向かって右手前には修行大師像。
高台の住宅地にあり、山内は広くはないものの背後に竹林を配して瀟洒なたたずまい。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端木鼻に見返りの獅子、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、向拝柱には古色を帯びた札所板。
木鼻、中備の彫刻はボリューム感を備えた見事なもので、正面格子硝子扉のうえに山号扁額を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 見事な木鼻彫刻


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 札所板
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
郊外にあり、ご不在もあるようなので事前連絡がベターかと思います。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
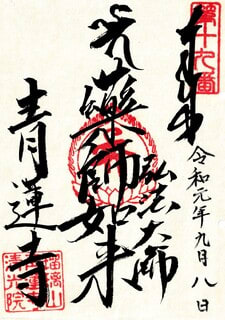
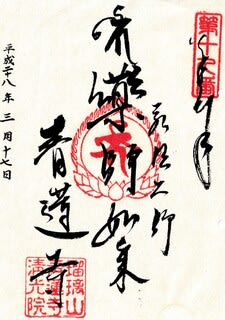
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「ベイ」の揮毫と「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第十九番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
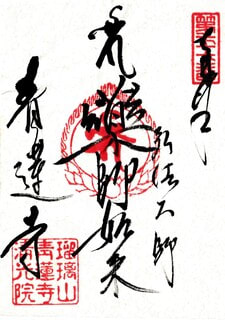
〔 荒川辺八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第19番-2 陽岳山 南晴寺 圓乗院
(えんじょういん)
公式Web
大田区南馬込5-15-5
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第71番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第76番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第36番
司元別当:
授与所:寺務所
ふたつめの第19番は馬込の圓乗院です。
御府内霊場第19番であることは公式Webに「ご本尊には大聖不動明王をお祀りし、御府内霊場88番中第19番札所、玉川霊場88番中第71番札所にも定められています。」と明記されています。
公式Webによると鎌倉時代末期、天永法印によって草創されたと伝えられています。
『新編武蔵風土記稿』には馬込長遠寺末、開山天永法印、中興開山は秀英僧都(大永二年(1522年)寂)とありますが、史料類が少なく御府内霊場第19番札所の経緯についてはよくわかりません。
御府内霊場旧19番とみられる愛宕圓福寺と圓乗院本寺の長遠寺の関係も当たってみましたが、長遠寺は山城國醍醐三寶院の直末で、愛宕圓福寺とのゆかりは見出せませんでした。
本寺の長遠寺は御府内霊場第8番の札所で、玉川八十八ヶ所霊場第72番の札所、圓乗院も玉川八十八ヶ所霊場第71番の札所ですから、その流れで御府内霊場第19番札所となったのかも。
ただし旧本山の長遠寺は新義真言宗(現・真言宗智山派)、圓乗院は現在高野山真言宗でしかも準別格本山ですから、江戸期の本末関係は承継されていないかもしれません。
なお、玉川八十八ヶ所霊場は、多摩川流域の真言宗寺院で構成される弘法大師霊場で、江戸時代からあった多摩川四郡八十八ヶ所霊場が「多摩川八十八ヶ所霊場」として再編という説があり、明治~大正にかけて「永楽講」が結成されて賑わったといいます。
その後衰退していたところ、昭和48年の弘法大師御生誕1200年を契機に川崎大師・平間寺が中心となって「玉川八十八ヶ所」として再興されました。
札所リストは→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。
御府内霊場との重複札所は、海賞山 来福寺、海岳山 長遠寺、陽岳山 圓乗院の3箇寺で、むしろ神奈川県の弘法大師霊場「新四国東国八十八ヶ所霊場」との重複が多くなっています。
御府内霊場、玉川霊場、新四国東国霊場は実質的にはほぼ現役霊場で、この3つの弘法大師霊場を巡ると、都内から鎌倉辺りまでのめぼしい真言宗寺院を巡拝できるかたちとなっています。
------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(馬込村)
圓乗院 新義真言宗 村内長遠寺末 陽岳山ト号ス 開山ハ天永法印トイヘト 年代ヲモ傳ヘス 中興開山秀英僧都大永二年(1522年)二月寂セリ 本尊不動明王ヲ客殿ニ安ス
-------------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像
都営浅草線「西馬込」駅から徒歩5分、広めの駐車場もありアクセスしやすいお寺です。
マンションメインの住宅地の一画に、切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門を構えています。
門前には端正な修行弘法大師像。


【写真 上(左)】 「準別格本山」の銘板
【写真 下(右)】 山門扁額
門柱には「準別格本山」の銘板が燦然と輝き、見上げには山号扁額。
門脇には御府内霊場の札所標で「弘法大師 御府内八十八所 第十九番霊場」と刻まれています。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 閻魔堂
【写真 下(右)】 水屋
山門をくぐると左手に大師堂、その先に閻魔堂、水屋と並びます。
閻魔堂は公式Webに説明があります。
「古くは『円乗院のおえんまさま』と親しまれ、正月十六日と盆の十六日には市が立つほど多くの参詣客を集めた、由緒ある閻魔大王」との由。
正面階段上に本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 見事な木鼻彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額
入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風を構え、すこぶる均整のとれた堂容です。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備下欄に龍の彫刻、上欄間に笈形付大瓶束。
兎毛通に朱雀?の彫刻、唐破風鬼には御本尊・不動明王のお種子「カン/カーン」とみられる梵字を掲げ、とくに彫刻類の意匠は見応えがあります。
向拝見上げには院号扁額が掲げられています。
御本尊・札所本尊の不動明王は本堂内に奉安。
御府内霊場御朱印には「十一面観世音」の揮毫もあるので、本堂内に十一面観世音菩薩も奉安されているかもしれません。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂向拝


【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板
【写真 下(右)】 大師堂の扁額
大師堂はおそらく宝形造で流れ向拝。
こぶりな堂宇ながら水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股をしっかり構え、左右の向拝柱には御府内霊場と玉川霊場の札所板が掲げられています。
圓乗院は御府内霊場、玉川霊場のふたつの弘法大師霊場の兼務札所で、しかも本堂とは別に大師堂を構えています。
御府内、玉川両霊場の札所板が掲げられた大師堂は唯一かも。
見上げには「弘法大師」の扁額が掲げられています。
堂横には聖観世音菩薩立像と厄除延命地蔵菩薩立像が安置されています。
御朱印は本堂向かって右手前の客殿にて拝受できます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
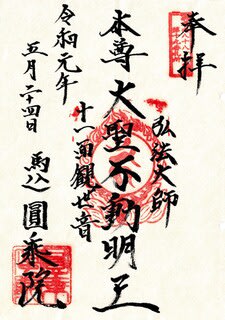
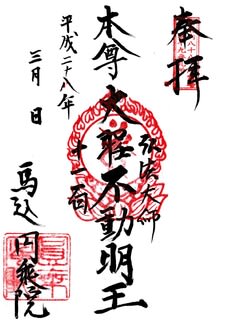
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」「十一面観世音」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八ヶ所第十九番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
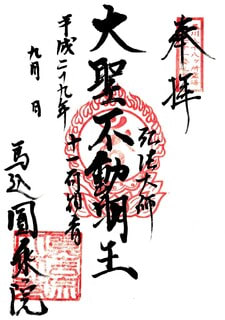
■ 第20番 身代山 玉泉寺 鏡照院
(きょうしょういん)
港区西新橋3-14-3
真言宗系単立
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
司元別当:
授与所:寺務所ないし郵送
『ルートガイド』によると、応永六年(1399年)、常陸国の海上に出現した「身代不動明王」を笠間の地で祀っていましたが慶長十九年(1603年)当時の住職宥俊阿闍梨が江戸に遷し、愛宕下に改めて開かれたといいます。
19番-1の青蓮寺の記事で触れたとおり、江戸八十八ヶ所霊場の第20番札所は愛宕金剛院で、これは圓福寺地内末寺の金剛院のことかと思われます。
また、江戸期の御府内霊場第20番も金剛院であったとみられます。
明治2年の廃仏毀釈による圓福寺の廃絶時、愛宕権現本地堂の別当の立場にあった金剛院もおそらく廃絶を免れなかったとみられ、実際、金剛院は現存していません。
諸史料から考えると、圓福寺御本尊の勝軍地蔵菩薩は真福寺に移され、本地堂(別当・金剛院)御本尊の勝軍地蔵菩薩と御府内霊場第20番の札所は、圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に遷されたのではないでしょうか。
『寺社書上』から引くと、鏡照院は愛宕山圓福の寺中末寺で、御本尊は應永年中(1394-1428年)に上総國海中から出現した身代不動明王(秘仏)。
往時は御前立の不動明王木立像と四大明王立像、両童子木立像を奉安していたようです。
弘法大師、興教大師の座像を安じ、聖天堂には聖天尊と、聖天尊の本地である十一面観音木立像を奉安していました。
また、両脇大神宮として春日明神木立像を祀っていたようです。
一方、金剛院は愛宕(権現)本地堂別当で本寺は圓福寺。
御本尊は、愛宕権現の本地佛である勝軍地蔵尊(秘仏)。
奉安する弘法大師像は「御府内八十八ヶ所之●第弐拾番」と明記されています。
一言石地蔵尊、一言地蔵尊も奉安するお地蔵様のお寺だったようです。
「猫の足あと」様に「明治廿二年、高尾山飯綱不動明王を境内に勧請せり(東京名所図会)」、「本尊は身代不動明王で、後小松天皇の御宇應永六年(1399年)の開基と傳へられる。徳川家康から傳はつたといはれる寸餘の秘佛、将軍地蔵尊像が當院内に安置(芝區誌)」とあります。
上記より、家康公由来の(本地堂・金剛院ご本尊の)将軍地蔵尊像が当院内に安置されていた(る)可能性がありますが、当山の御本尊はもともとの鏡照院由来の身代不動明王。
金剛院時代の御府内霊場の札所本尊は、将軍(勝軍)地蔵菩薩と弘法大師だった可能性がありますが、明治初期とみられる金剛院から鏡照院への札所異動により、札所本尊は身代不動明王と弘法大師に替わったのではないでしょうか。
近年、鏡照院は西新橋に移転したため愛宕権現とのつながりはわかりにくくなりましたが、やはり愛宕権現(圓福寺)系の札所とみることができます。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕別當 圓福寺
武州豊島郡芝愛宕
新義真言宗触頭 別當 圓福寺
圓福寺地中幷末寺
(圓福寺地中脇坊)
金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
(鏡照院)
愛宕山圓福寺中 新義真言宗
愛宕山鏡照院
開基 不●明
本尊 身代不動明王
應永年中(1394-1428年)上総國海上●●海中出現
御前立不動明王木立像
本尊●●安並四大明王木立像 両童子木立像
弘法大師 興教大師 木座像
聖天堂 安聖天尊増 聖天本地十一面観音木立像
両脇大神宮 春日明神木立像
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
(金剛院)
芝愛宕本地堂別当
新義真言宗 金剛院
愛宕圓福寺中之内
本寺 愛宕圓福寺
山号 愛宕山金剛院●●●
愛宕本地堂
本尊 本地佛勝軍地蔵尊 秘像
●●佛
弘法大師 御府内八十八ヶ所之●第弐拾番
一言石地蔵尊
一言地蔵尊
-------------------------
都営三田線「御成門」駅、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅、JR「新橋」駅から歩ける距離で交通至便ですが、駐車場はありません。
東京都心のオフィス街の、まっただなかにある御府内霊場札所です。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 扁額
ビルの1階にあり、向拝は鉄扉で閉ざされ、扁額がなければおそらく寺院とは気がつきません。
むしろ、境内社の末廣稲荷大明神の方が目立っています。
この稲荷社は、京都伏見稲荷大社より明治時代に勧請されたもので、商売繁盛のご利益あらたかとのことです。

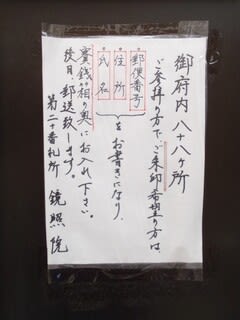
【写真 上(左)】 末廣稲荷大明神
【写真 下(右)】 御朱印案内
前の道はオフィスワーカーが行き交います。
このシチュエーションで、堂前で数珠をとり、勤行をあげるのはある意味勇気がいります。
御府内霊場の巡拝なので、よんどころなく勤行をあげました。
背中に感じる視線。
おそらく道行く人は、「この人なにしてるんだろう?」モードだったかと思います。
2度目の参拝はご縁日だったかと思いますが、ご開扉されて堂内(というか開扉するとすぐ前が護摩壇なので堂前)で勤行できました。
こうなれば落ち着いて参拝できます。
(このときの写真がなぜかみつからないので、みつかり次第UPします。)
御朱印は門扉に案内が貼ってあり、郵送で受けることができます。
ご開扉のときは専用納経帳に拝受できました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
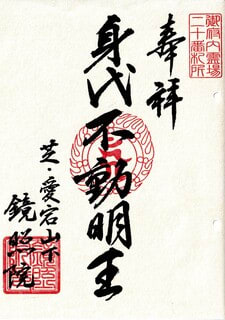
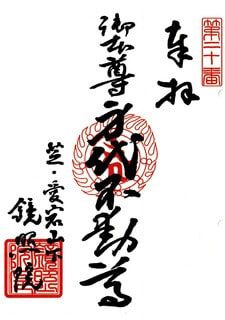
【写真 上(左)】 専用集印帳(直書)
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「身代不動明王」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。
右上に「御府内霊場二十番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ Vol.7)
【 BGM 】
■ far on the water - Kalafina
■ Erato - 志方あきこ
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第18番 獨鈷山 光明寺 愛染院
(あいぜんいん)
新宿区若葉2-8-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第18番
司元別当:
授与所:庫裡ないし本堂前
第18番はいきなり四ッ谷に飛びます。
開山について『ルートガイド』と史料類で異なるので、まずは『ルートガイド』から要旨を引用してみます。
天正年間(1573-1592年)、加藤清正の実弟・正濟上人が麹町貝坂のあたりに開いたといいます。
慶長十六年(1611年)麹町から四谷に、寛永十一年(1634年)に現在地に移転しています。
ところが 『寺社書上』『御府内寺社備考』および、それらを典拠とした「四谷区史」はさらに古い縁起を伝えています。
弘仁年中(810-824年)、弘法大師が関東巡錫の折に現在の麻布善福寺の地に創建、本尊五指量愛染尊を安置され「八祖相承之獨鈷」を納められたといいます。
その後慶長十六年(1611年)正斎上人(加藤清正の実弟?)が麹町貝塚の地に中興、寛永十一年(1634年)現在地に移転といいます。
たしかに麻布善福寺の公式Webには「麻布山善福寺は、平安時代の天長元年(824年)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。」と明記されています。
(のちの鎌倉時代に真言宗から浄土真宗に改宗)
『寺社書上』には「然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給」とあり、愛染院が善福寺の奥之院であったことを伝えています。


【写真 上(左)】 麻布善福寺
【写真 下(右)】 麻布善福寺の参拝記念印
↑ 参拝記念印に「弘法大師開山」とあります。
加藤清正の実弟という正濟(斎)上人についてもほとんど情報がとれません。
清正公は熱心な日蓮宗の信徒として知られています。
兄弟が同じ信仰とは限りませんが、日蓮宗の重要人物の実弟が密寺を中興とは、すんなり頷けないものはあります。
『寺社書上』をみると、弘法大師創建を物語る数々の寺宝が列挙されています。(下記)
弘法大師の御作、御筆の寺宝だけでも実に5点以上を数え、しかも「開祖 弘法大師」と明記されています。
故なきところにこれだけの縁起や寺宝が残るのは不自然ですから、やはり愛染院は真言宗時代の麻布善福寺となんらかの関係があったのでは。
現時点ではこれ以上の史料がみつからないので、ここまでにしておきます。
現地の案内書には沿革として『四谷区史』(文政寺社書上の引用部)が掲載され、同書には中興開山の正斎は寛永十五年(1638年)の寂とありました。
御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされ、愛染院の現在地への移転はそれ以前の寛永十一年(1634年)。
江戸八十八ヶ所霊場でも同番の第18番ですから、御府内霊場開創時からの札所とみられます。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.63』
大塚護持院末 四ッ谷南寺町 獨鈷山 光明寺 新義真言宗 愛染院
当寺開闢之儀は、人王五拾弐代嵯峨天皇御宇 弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、當國一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五●量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候
開祖 弘法大師 中興 正済(?)上人 中興二世 實盛 寛永十二年(1638年入寂)
本尊 両部大日如来
両脇士 不動尊 愛染尊 智證大師作
増長天 廣目天 持國天 多聞天
弘法大師木座像弐尺弐寸● 厨子入 興教大師 厨子入
辨財天 附十五童子 弘法大師作
阿弥陀如来 恵心僧都作
八祖相承獨鈷 但弘法大師●持ト●
四處明神 寛平法皇(宇多天皇)
弘法大師 右御同筆
愛染明王 弘法大師筆
五大明王 興教大師筆
愛染明王 嵯峨天皇御筆
般若心経 弘法大師筆
愛染堂
本尊 愛染明王 弘法大師作 丈二寸余
脇立 不動明王 愛染明王
大聖天三躰
本地十一面観音 弘法大師作 丈一尺八寸厨子入
鎮守社 稲荷 金毘羅 愛宕
寺中弐ヶ院
光明院 本尊 大威徳明王 開山不知
蓮花院 本尊 弥陀如来 開山不知
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
獨鈷山光明寺愛染院は、大塚護持院末の新義真言宗で、四谷南寺町今の寺町にある。境内は千五百廿坪余の拝領地で、起立は慶長十六年辛亥(1611年)、麹町貝塚邊が元地であつた。寛永十一年甲戌(1634年)十二月に此地に替地を賜うて移転したのである。
文政寺社書上に拠れば、「当寺開闢之儀は、人王五十二代嵯峨天皇御宇、弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、当國に一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候」と伝へて、その来由することの頗る古きを語つて、慶長(1596-1615年)当時の開山正斎はその中興と称して居る。此地に移つて以来、住持を替ふること八代、寶暦十年庚辰(1760年)梵鐘を鑄たが、鐘銘中に(略)「惟愛染堂假而毎免、可謂幸矣」といふことが見えて、愛染尊の功徳厳然たるを称へている。
-------------------------


【写真 上(左)】 愛染院前から東福寺坂
【写真 下(右)】 山内入口
四谷周辺、若葉、須賀町から鮫河橋にかけては寺院が集中する寺町となっています。
これは、寛永年間(1624-1645年)家光公の治世に江戸城外堀工事のため、麹町の寺院が一斉に四谷に移転させられたためといいます。
愛染院の元地は麹町貝塚邊で、寛永十一年(1634年)に現在地に遷っているので、この江戸城外堀工事によるものとみられます。
このあたりはことに土地の起伏が激しいところで、凹凸地形マニアの聖地となっています。
(→ 四谷の坂道レポ)
新宿通りから円通寺坂を南に下って鮫河橋に至る道(名称不明)が谷筋で、そこから東西方向はすべて登り坂となります。
愛染院はこの谷道から東福院坂(天王坂)を登った坂の途中に、坂名の由来である東福院とほぼ向き合ってあります。
東福院は御府内霊場第21番札所、他にも御府内霊場札所がいくつかありますので、順打ち(逆打ち)でない場合は、まとめてまわることになります。


【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 案内書
門まわりは赤レンガで固められ、すぐ奥は駐車場。
さらにその奥にも黒い門扉を構えて、なんとなく近寄りがたい空気が漂っています。
こちらは直書き御朱印は納経者のみ授与なので、そんな先入観もあるのかもしれません。
山内入口に院号標と案内書(上記)。
内藤新宿の生みの親、高松喜六の墓と、江戸中期の国学者・塙保己一の墓の説明書もあります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
第二の門を抜けると俄然古刹の雰囲気が出てきます。
正面本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った寺院建築で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に三連の本蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
向拝と左右の身舎扉は格子状で小壁に菱格子を置き、きりりと引き締まった印象。
本堂右手の梵鐘には貴重な百字真言や銘叙が刻され、銘叙は湯島霊雲寺第四世法明が識(しる)されたものです。
(鐘楼は堂宇とともに戦火で焼失。)
当山は真言宗豊山派ですが、真言律宗となんらかの交流があったのかもしれません。


【写真 上(左)】 梵鐘
【写真 下(右)】 「倶會一處」の石碑
倶會一處(くえいっしょ)の石碑もあります。
倶會一處(倶会一処)とは、『阿弥陀経』の「舎利弗。衆生聞者。応当発願。願生彼国。所以者何。得与如是。諸上善人。倶会一処。舎利弗。不可以少善根。福徳因縁。得生彼国。」にある経文で、阿弥陀佛の極楽浄土への往生を願って一途に念仏の信仰に生きる心持ち、あるいは念仏信仰により、ご先祖や家族たちとともに極楽浄土の仏や菩薩と一処で出会うことができるという趣旨で、主に浄土教(浄土宗、浄土真宗)で説かれ、浄土宗寺院では御朱印に揮毫されることもあります。
ただし、密教寺院でこの言葉に触れることはめずらしいのでは。
こちらの御朱印は原則、本堂前に用意された印判の自捺しで、納経者にのみ「特別の朱印」(揮毫御朱印)が授与されます。
自捺し御朱印は金属箱のなかの印判と朱肉を使い、見本も置いてあるのでとくに問題なく拝受できます。
御朱印代として300円(2017年6月時点)をお納めしました。
印判自捺しの場合、御朱印帳への直捺しは一発勝負となりリスクがあります。
筆者は常々、御朱印帳とサイズを合わせた和紙を数枚持ち歩き、そちらに捺してその紙をのちほど御朱印帳に貼付けます。
これだと、失敗をおそれることなく自捺しができます。老婆心ながら・・・。
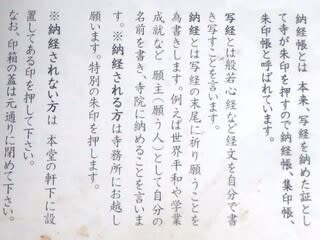

【写真 上(左)】 御朱印についての案内書
【写真 下(右)】 庫裡サイドから本堂
筆者は最初の参拝では自捺し御朱印を拝受、2度目以降の参拝では般若心経を納経して揮毫御朱印を拝受しました。
いささか敷居の高さを感じるお寺さまですが、ご対応はご親切でした。
なお、以上は平成元年11月時点の情報で、現在もこの授与方式かどうかはわかりません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
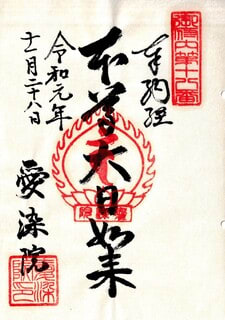
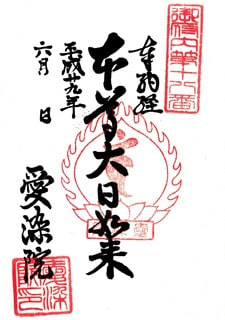
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第十八番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 自捺しの印判御朱印
■ 第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺
(しょうれんじ)
板橋区成増4-36-2
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第77番、荒川辺八十八ヶ所霊場第86番
司元別当:(成増村)山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))
授与所:庫裡
第19番にはふたつの札所がリストされています。
ひとつは板橋の青蓮寺、もうひとつは馬込の圓乗院です。
順にご紹介していきます。
青蓮寺の開基開山は不詳ですが、当初弁天塚付近(現高島平4-23付近)にあったとされ、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して3つの弘法大師霊場の兼務札所となりました。
-------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(成増村)
青蓮寺 新義真言宗 上石神井村三寶寺末 本尊薬師
(成増村)
山王社 青蓮寺持
『新編武蔵風土記稿』の記述は簡素なので詳細不明です。
孫引きで恐縮ですが、「猫の足あと」様が引かれている『いたばしの寺院』の記述を抜粋引用させていただきます。
「開基開山については明確な口碑さえなく、わずかに伝えるところによれば、寺は始め、弁天塚のほとり(現高島平4-23あたり)に建てられてあったが水害のためにいつの時代にか現在地に移転したという。本尊薬師如来が室町時代の作風を持つので、寺の創建も凡そその時代の頃を推定される。(略)文政末期から大正初期まで凡そ百年間は無住であった。(略)大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺し、昭和9年に13世正善大和尚入山以来、本寺は面目を一新したという。なお、本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」
以上から、青蓮寺は室町時代創建の古刹で、大正初期に再興、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して御府内霊場の札所となったことがわかります。
また、『新編武蔵風土記稿』によると、青蓮寺は江戸期には村内の山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))の別当でした。

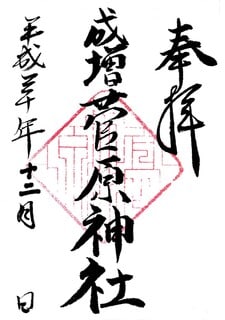
【写真 上(左)】 (成増)菅原神社 (成増天神)
【写真 下(右)】 (成増)菅原神社 (成増天神)の御朱印
弘法大師霊場から青蓮寺を語るとき、浅草の清光寺は外せず、御府内霊場に限っていえば愛宕の圓福寺も避けて通ることができません。
どうして圓福寺まで辿る必要があるかというと、江戸八十八ヶ所の第19番は「(愛宕)円福院」で、明治2年の廃仏毀釈を受けて圓福寺が廃絶するまでは圓福寺が御府内霊場第19番だった可能性が高いからです。
浅草清光寺、愛宕圓福寺ともに現在廃寺(ないし合寺)となっています。
しかし愛宕圓福寺は御府内霊場とのゆかりが深いので、できる限り史料を当たって縁起沿革を探ってみたいと思います。
□【愛宕圓福寺】
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕別當 圓福寺
武州豊島郡芝愛宕
新義真言宗触頭 別當 圓福寺
本寺 山城國宇陀郡醍醐山無量壽院
山号等 愛宕山寶珠院圓福寺
本尊 地蔵菩薩 厨子入 定朝作
不動明王 本尊左脇立
毘沙門天 同右脇立
本堂内安置 十一面観自在菩薩
同所 聖天
●祖弘法大師 興教大師
開山 俊賀
圓福寺地中幷末寺
(圓福寺地中脇坊)
金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院
(御府内三田寺町)寶生院
(御府内浅草寺町)威光院
(御府内浅草寺町)清光院
(御府内下谷坂本)大聖院
-------------------------
【史料】
-------------------------
■ 『江戸名所図会 7巻 [3]』(国立国会図書館)
(愛宕山権現社/抜粋引用)
本地佛を勝軍地蔵尊 行基大士の作なり 永く火災を退けるの守護神なり
別當圓福教寺ハ石階の下にあり 新議の真言宗江戸の触頭四箇寺の随一なり
開山を神證上人と号す 二世俊賀上人といふ
四箇寺とハ湯島根生院、本所彌勒寺、當所真福寺並に當寺(圓福寺)といふ
神證上人下野の人なりて 姓を塩谷氏母ハ皆川氏なり
元和五年(1619年)鈞命に依って金剛院に退居をゆるさ●天年を終ふ
春音(神證上人)の坊ハ遍照院と号す 今の圓福寺是なり
金剛院 普賢院 満蔵院 鏡照院 壽桂院等末●六院あり
俊賀上人 野州西方邑の人姓ハ越路氏にして宇都宮弥三郎頼綱の後裔
父ハ伊勢守近津神祠に祈りて産す 祖始下妻の圓福寺に住を然
其頃下総結城の元寿 上州松井田秀算等一世の豪俊●● 俊賀上人をあハせて新義の三傑と称せらる
元和五年(1619年)俊賀上人愛宕権現の別當に命せられ 共に圓福寺の号を●く一宇を開きしめ
-------------------------
江戸期の真言宗には「江戸四箇寺触頭」という制度があり、これにより本末関係が精緻に整えられていました。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)によると、発足当初の「江戸四箇寺触頭」はつぎの4箇寺です。
・知足院(江戸白銀町)
→ 関連資料
・真福寺(愛宕下)
・円(圓)福寺(愛宕下)
・弥勒寺(本所)
智積院公式Webには「貞享4年(1687)七月に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、代わりに根生院が任じられます。以後、明治までは変化はありません(円福寺は明治二年に廃仏毀釈により廃寺)。」とあるので、貞享四年(1687年)以降は真福寺(67)、圓福寺(19)、弥勒寺(46)、根生院(35)の四箇寺体制となっています。
( )内は御府内霊場の札番で、これをみても御府内霊場が真言宗の名刹をおおむねカバーしていたことがわかります。
また、『宝瞳寺文書解題』(国文学研究資料館/PDF)にも「江戸四箇寺触頭」の役割が詳細に記されています。
圓福寺は「江戸四箇寺触頭」を勤められ、御府内にいくつもの末寺をもつ御府内有数の名刹でした。
これほどの名刹がどうして明治の廃仏毀釈でいともあっさり(?)と廃絶してしまったのでしょうか。
(実際、触頭4箇寺のうち他の3箇寺は現存しています。)
どうにも気になったので、まずはここから調べてみました。
真福寺の勝軍地蔵尊の説明書には以下のとおりあります。
「この勝軍地蔵菩薩は、天平十年(738年)行基が近江信楽遊行の砌、造顕したもので、同地に安置され、霊験あらたかなり。天正十年(1582年)徳川家康、本能寺の変の難を逃れんがため伊賀越に際し、信楽の土豪多羅尾氏、当勝軍地蔵を献上、沙門神証これを護持し、三河に帰還するをえたり。爾来、家康の帰依厚し。慶長八年(1603年)家康、征夷大将軍に栄進するにより、江戸に愛宕神社を創建し、同社の本地仏として勧請、神証を別当の円福寺第一世とせり。明治の廃仏毀釈で円福寺は廃寺、尊像は真福寺に移されたが、大正十二年 (1923年)関東大震災で焼失、昭和九年(1934年)弘法大師一千百年御遠忌記念として、霊験を不朽にせんがため、銅製で造顕せり。」
一方、愛宕神社の公式Webには配祀として将軍地蔵尊が明記され、愛宕権現(神社)にとって将軍(勝軍)地蔵尊がいかに重要な尊格であるかがわかります。
以上から、圓福寺は愛宕権現の別当の色彩がすこぶる濃厚だったとみられます。
この点は、全国の愛宕神社の総本社とされる愛宕神社(京都市右京区嵯峨愛宕町)と、その別当・白雲寺との関係とよく似ています。
中世~江戸期の愛宕権現社の多くは、本殿に愛宕大権現の本地仏である勝軍地蔵、奥の院に愛宕山の天狗の太郎坊が祀られたといいます。
神仏習合のもと修験道の道場として栄えたこともあり、別当の勢力はたいへん強かったとみられます。
この強大な立場が明治の廃仏毀釈で裏目に出て、愛宕権現の別当・圓福寺は存続の危機に見舞われたのでは。
実際、京都の愛宕神社総本社の別当・白雲寺は廃仏毀釈で廃絶となっています。
総本社の別当・白雲寺が廃絶となった以上、東都の愛宕権現の別当・圓福寺も、たとえ「江戸四箇寺触頭」の格式があったとしても廃絶を遁れられなかったのでは?
ちなみに『寺社書上』の圓福寺の項には「従是愛宕山上之分」として以下のとおりあります。
□「(圓福寺)従是愛宕山上之分」(諸佛のみ抜粋引用)
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕大権現御神● 秘像
御前立 勝軍地蔵尊
脇立 不動明王 毘沙門天
本地堂 脇坊金剛院持
朝日愛染明王
太郎坊北之方
唐●地蔵尊 勝軍地蔵尊 地蔵尊 石地蔵尊
女坂
勝軍地蔵尊
男坂上り口
役行者堂
-------------------------
これをみると江戸期の愛宕権現が諸佛に満ち、神仏習合していたことがよくわかります。
本地堂の別当は金剛院(圓福寺地内末寺)とあるので、愛宕権現全体の別当が圓福寺、本地堂の別当が金剛院という二重構造だったのかもしれません。
なお、『江戸名所図会』の愛宕社總門の絵図をみると、男坂の右手に本地堂、左手に別当(おそらく圓福寺)がみえ、本地・別当系の諸堂は坂下にあったことがわかります。
ここから「出世の石段」を登って参拝する愛宕権現は海抜26mという都内随一の高みにあり、ここからの見晴らしと桜花のすばらしさは御府内有数と称えられ、ほおずき市や羽子板市も賑わいをみせて江戸の図絵類に描かれています。
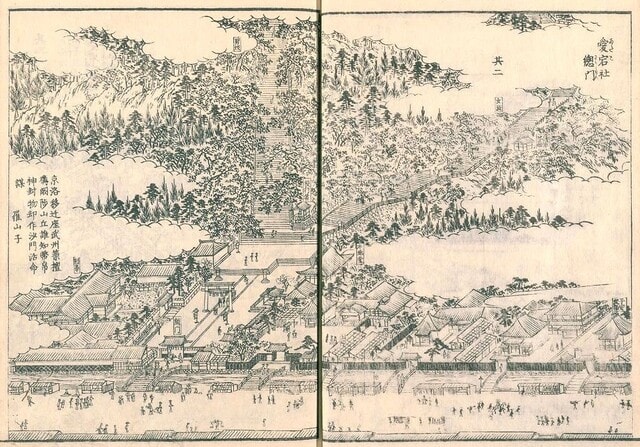
■『江戸名所図会』 7巻 (須原屋茂兵衛[ほか])/愛宕社總門
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
~ 伊勢へ七度 熊野へ三度 芝の愛宕へ月まいり ~ (愛宕神社御由緒書より)


【写真 上(左)】 愛宕神社社頭
【写真 下(右)】 出世の石段

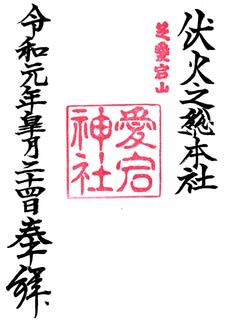
【写真 上(左)】 愛宕神社拝殿
【写真 下(右)】 愛宕神社の御朱印
真福寺勝軍地蔵尊の説明文のとおり、圓福寺が廃寺となったとき、御本尊の(勝軍)地蔵菩薩は愛宕の真福寺に遷られました。
このとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所だったので、重番を避けるため御府内霊場第19番は浅草の清光院に承継されたとみられます。


【写真 上(左)】 真福寺外構と勝軍地蔵尊
【写真 下(右)】 勝軍地蔵尊
圓福寺が廃されたとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所で、重番を避けるとしたら第19番は承継できません。
第20番金剛院は圓福寺の地内末寺で、本地堂の別当だったため同時に廃絶された可能性がありますが、こちらはおそらく同じ圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に承継されています。
で、圓福寺の第19番の行方です。
『寺社書上』に記載の圓福寺の御府内末寺(地内末寺のぞく)はつぎの4箇寺。
・(三田寺町)寶生院 / おそらく御府内霊場第69番(龍臥山 宝生院)
・(浅草寺町)威光院 / おそらく御府内霊場第62番(鶴亭山 威光院)
・(浅草寺町)清光院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第86番
・(下谷坂本)大聖院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第87番(宝橋山 大聖院)
末寺に御府内霊場札所を継がせるとなると、荒川辺八十八ヶ所霊場の2箇寺、すなわち清光院か大聖院とするのが自然な流れです。
下谷坂本(現・台東区北上野)の大聖院は御府内霊場札所集中エリアから若干離れているため、威光院(御府内霊場第62番)にほど近い清光院が承継したのでは。
以上はあくまでも筆者の憶測です。
□【清光院】
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [83] 浅草寺社書上 甲八止』(国立国会図書館)
※達筆すぎて読みとれないので、適宜『御府内寺社備考 P.108』にて補足しています。
浅草 不唱小名
新義真言宗 芝愛宕山圓福寺末
花園山神應寺清光院
諸書●号焼失 往古知不申●
開山 慈観法印 卒年不知
本尊 阿弥陀如来座像
弘法大師 興教大師
不動尊立像 長一尺五寸五分 土蔵ニ安置
扇稲荷社 神体白幣
護摩堂 不動尊立像
-------------------------
もうひとつナゾが残ります。
「猫の足あと」様には「清光院は、江戸時代の書物によると慶長11年(1606)頃の創建と言われていたようです。大正12年関東大震災で焼失し、青蓮寺に合寺されました。」とあります。
大正12年の関東大震災で焼失した清光院の名跡は下谷坂本の大聖院が継いでもよさそうですが、実際は成増村の青蓮寺が継いでいます。
震災後の混乱で大聖院による合寺は困難だったのかもしれず、あるいは郊外の青蓮寺に合寺したほうが安全という判断があったのかもしれません。
また、青蓮寺の本寺は練馬の名刹、三寶寺ですからその保護下に入ったほうが都合がよかったのかも。
いずれにしても決定的な史料がみつからない以上、憶測の域を出ることはできません。
とまれ、愛宕圓福寺から続く御府内霊場第19番の名跡は、大正13年の清光院合寺をもって青蓮寺に承継されました。
『いたばしの寺院』には「本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」とあるようです。
御府内霊場第19番と荒川辺霊場第86番はたしかに清光院由来とみられますが、豊島霊場は豊島郡メインの霊場なので、青蓮寺はもともと豊島霊場の札所だったのでは。
実際、『ルートガイド』には「本堂にある二体の弘法大師像は、震災の中持ち出した清光院八十八ヶ所十九番の尊像と青蓮寺に伝わってきた豊島八十八ヶ所七十七番の尊像だそうです。」とあります。
豊島霊場の開創は明治40年とされるので、豊島霊場第77番の青蓮寺が、関東大震災で焼失した浅草清光院(御府内霊場第19番、荒川辺霊場第86番)を大正13年に合寺し、3つの弘法大師霊場の兼務札所となったとみるのが妥当かと。
なお、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所一覧は→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。
天保九年(1838年)刊の『東都歳時記』に記されているため、文化年間(1804-1818年)以降にみられる八十八ヶ所巡りの流行を受けての開創ではないかとみられています。
初番・初願は根岸の世尊寺、日暮里、尾久、船堀、滝野川、豊島、江北、足立元木、西新井、梅田、千住、綾瀬、堀切、墨田、亀戸、元浅草とまわり、第88番結願は根岸の千手院です。
おもに下町をまわるので、御府内霊場との重複札所は亀戸・東覚寺、元浅草・延命院、元浅草・観蔵院、成増・青蓮寺の4箇寺と多くはありません。
-------------------------
最寄りは東武東上線「成増」駅・東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅ないし都営三田線「西高島平」駅ですが、いずれからもけっこうな距離があります。
周囲の道は入り組んで狭く、駐車スペース(?)も狭いので、交通アクセス的な難所といえそうです。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 札所碑


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
路地から階段の参道が伸び、門前に寺号標、札所碑、地蔵菩薩、如意輪観世音菩薩などが並びます。
山門はおそらく切妻屋根の薬医門で、門柱に札所板兼寺号板が掲げられています。
参道は途中で直角に曲がり、正面が本堂、その向かって右手前には修行大師像。
高台の住宅地にあり、山内は広くはないものの背後に竹林を配して瀟洒なたたずまい。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端木鼻に見返りの獅子、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、向拝柱には古色を帯びた札所板。
木鼻、中備の彫刻はボリューム感を備えた見事なもので、正面格子硝子扉のうえに山号扁額を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 見事な木鼻彫刻


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 札所板
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
郊外にあり、ご不在もあるようなので事前連絡がベターかと思います。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
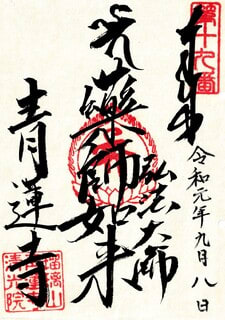
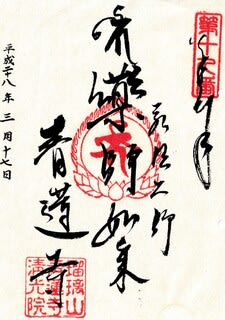
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「ベイ」の揮毫と「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第十九番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
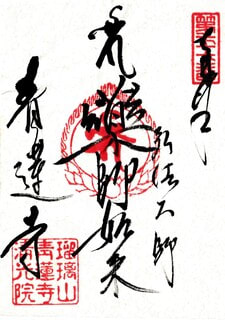
〔 荒川辺八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第19番-2 陽岳山 南晴寺 圓乗院
(えんじょういん)
公式Web
大田区南馬込5-15-5
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第71番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第76番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第36番
司元別当:
授与所:寺務所
ふたつめの第19番は馬込の圓乗院です。
御府内霊場第19番であることは公式Webに「ご本尊には大聖不動明王をお祀りし、御府内霊場88番中第19番札所、玉川霊場88番中第71番札所にも定められています。」と明記されています。
公式Webによると鎌倉時代末期、天永法印によって草創されたと伝えられています。
『新編武蔵風土記稿』には馬込長遠寺末、開山天永法印、中興開山は秀英僧都(大永二年(1522年)寂)とありますが、史料類が少なく御府内霊場第19番札所の経緯についてはよくわかりません。
御府内霊場旧19番とみられる愛宕圓福寺と圓乗院本寺の長遠寺の関係も当たってみましたが、長遠寺は山城國醍醐三寶院の直末で、愛宕圓福寺とのゆかりは見出せませんでした。
本寺の長遠寺は御府内霊場第8番の札所で、玉川八十八ヶ所霊場第72番の札所、圓乗院も玉川八十八ヶ所霊場第71番の札所ですから、その流れで御府内霊場第19番札所となったのかも。
ただし旧本山の長遠寺は新義真言宗(現・真言宗智山派)、圓乗院は現在高野山真言宗でしかも準別格本山ですから、江戸期の本末関係は承継されていないかもしれません。
なお、玉川八十八ヶ所霊場は、多摩川流域の真言宗寺院で構成される弘法大師霊場で、江戸時代からあった多摩川四郡八十八ヶ所霊場が「多摩川八十八ヶ所霊場」として再編という説があり、明治~大正にかけて「永楽講」が結成されて賑わったといいます。
その後衰退していたところ、昭和48年の弘法大師御生誕1200年を契機に川崎大師・平間寺が中心となって「玉川八十八ヶ所」として再興されました。
札所リストは→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。
御府内霊場との重複札所は、海賞山 来福寺、海岳山 長遠寺、陽岳山 圓乗院の3箇寺で、むしろ神奈川県の弘法大師霊場「新四国東国八十八ヶ所霊場」との重複が多くなっています。
御府内霊場、玉川霊場、新四国東国霊場は実質的にはほぼ現役霊場で、この3つの弘法大師霊場を巡ると、都内から鎌倉辺りまでのめぼしい真言宗寺院を巡拝できるかたちとなっています。
------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(馬込村)
圓乗院 新義真言宗 村内長遠寺末 陽岳山ト号ス 開山ハ天永法印トイヘト 年代ヲモ傳ヘス 中興開山秀英僧都大永二年(1522年)二月寂セリ 本尊不動明王ヲ客殿ニ安ス
-------------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像
都営浅草線「西馬込」駅から徒歩5分、広めの駐車場もありアクセスしやすいお寺です。
マンションメインの住宅地の一画に、切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門を構えています。
門前には端正な修行弘法大師像。


【写真 上(左)】 「準別格本山」の銘板
【写真 下(右)】 山門扁額
門柱には「準別格本山」の銘板が燦然と輝き、見上げには山号扁額。
門脇には御府内霊場の札所標で「弘法大師 御府内八十八所 第十九番霊場」と刻まれています。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 閻魔堂
【写真 下(右)】 水屋
山門をくぐると左手に大師堂、その先に閻魔堂、水屋と並びます。
閻魔堂は公式Webに説明があります。
「古くは『円乗院のおえんまさま』と親しまれ、正月十六日と盆の十六日には市が立つほど多くの参詣客を集めた、由緒ある閻魔大王」との由。
正面階段上に本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 見事な木鼻彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額
入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風を構え、すこぶる均整のとれた堂容です。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備下欄に龍の彫刻、上欄間に笈形付大瓶束。
兎毛通に朱雀?の彫刻、唐破風鬼には御本尊・不動明王のお種子「カン/カーン」とみられる梵字を掲げ、とくに彫刻類の意匠は見応えがあります。
向拝見上げには院号扁額が掲げられています。
御本尊・札所本尊の不動明王は本堂内に奉安。
御府内霊場御朱印には「十一面観世音」の揮毫もあるので、本堂内に十一面観世音菩薩も奉安されているかもしれません。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂向拝


【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板
【写真 下(右)】 大師堂の扁額
大師堂はおそらく宝形造で流れ向拝。
こぶりな堂宇ながら水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股をしっかり構え、左右の向拝柱には御府内霊場と玉川霊場の札所板が掲げられています。
圓乗院は御府内霊場、玉川霊場のふたつの弘法大師霊場の兼務札所で、しかも本堂とは別に大師堂を構えています。
御府内、玉川両霊場の札所板が掲げられた大師堂は唯一かも。
見上げには「弘法大師」の扁額が掲げられています。
堂横には聖観世音菩薩立像と厄除延命地蔵菩薩立像が安置されています。
御朱印は本堂向かって右手前の客殿にて拝受できます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
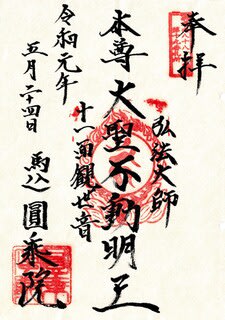
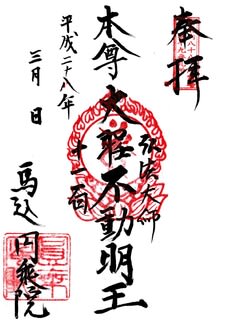
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」「十一面観世音」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八ヶ所第十九番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
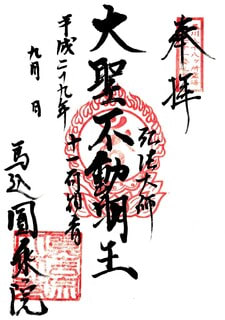
■ 第20番 身代山 玉泉寺 鏡照院
(きょうしょういん)
港区西新橋3-14-3
真言宗系単立
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
司元別当:
授与所:寺務所ないし郵送
『ルートガイド』によると、応永六年(1399年)、常陸国の海上に出現した「身代不動明王」を笠間の地で祀っていましたが慶長十九年(1603年)当時の住職宥俊阿闍梨が江戸に遷し、愛宕下に改めて開かれたといいます。
19番-1の青蓮寺の記事で触れたとおり、江戸八十八ヶ所霊場の第20番札所は愛宕金剛院で、これは圓福寺地内末寺の金剛院のことかと思われます。
また、江戸期の御府内霊場第20番も金剛院であったとみられます。
明治2年の廃仏毀釈による圓福寺の廃絶時、愛宕権現本地堂の別当の立場にあった金剛院もおそらく廃絶を免れなかったとみられ、実際、金剛院は現存していません。
諸史料から考えると、圓福寺御本尊の勝軍地蔵菩薩は真福寺に移され、本地堂(別当・金剛院)御本尊の勝軍地蔵菩薩と御府内霊場第20番の札所は、圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に遷されたのではないでしょうか。
『寺社書上』から引くと、鏡照院は愛宕山圓福の寺中末寺で、御本尊は應永年中(1394-1428年)に上総國海中から出現した身代不動明王(秘仏)。
往時は御前立の不動明王木立像と四大明王立像、両童子木立像を奉安していたようです。
弘法大師、興教大師の座像を安じ、聖天堂には聖天尊と、聖天尊の本地である十一面観音木立像を奉安していました。
また、両脇大神宮として春日明神木立像を祀っていたようです。
一方、金剛院は愛宕(権現)本地堂別当で本寺は圓福寺。
御本尊は、愛宕権現の本地佛である勝軍地蔵尊(秘仏)。
奉安する弘法大師像は「御府内八十八ヶ所之●第弐拾番」と明記されています。
一言石地蔵尊、一言地蔵尊も奉安するお地蔵様のお寺だったようです。
「猫の足あと」様に「明治廿二年、高尾山飯綱不動明王を境内に勧請せり(東京名所図会)」、「本尊は身代不動明王で、後小松天皇の御宇應永六年(1399年)の開基と傳へられる。徳川家康から傳はつたといはれる寸餘の秘佛、将軍地蔵尊像が當院内に安置(芝區誌)」とあります。
上記より、家康公由来の(本地堂・金剛院ご本尊の)将軍地蔵尊像が当院内に安置されていた(る)可能性がありますが、当山の御本尊はもともとの鏡照院由来の身代不動明王。
金剛院時代の御府内霊場の札所本尊は、将軍(勝軍)地蔵菩薩と弘法大師だった可能性がありますが、明治初期とみられる金剛院から鏡照院への札所異動により、札所本尊は身代不動明王と弘法大師に替わったのではないでしょうか。
近年、鏡照院は西新橋に移転したため愛宕権現とのつながりはわかりにくくなりましたが、やはり愛宕権現(圓福寺)系の札所とみることができます。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕別當 圓福寺
武州豊島郡芝愛宕
新義真言宗触頭 別當 圓福寺
圓福寺地中幷末寺
(圓福寺地中脇坊)
金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
(鏡照院)
愛宕山圓福寺中 新義真言宗
愛宕山鏡照院
開基 不●明
本尊 身代不動明王
應永年中(1394-1428年)上総國海上●●海中出現
御前立不動明王木立像
本尊●●安並四大明王木立像 両童子木立像
弘法大師 興教大師 木座像
聖天堂 安聖天尊増 聖天本地十一面観音木立像
両脇大神宮 春日明神木立像
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
(金剛院)
芝愛宕本地堂別当
新義真言宗 金剛院
愛宕圓福寺中之内
本寺 愛宕圓福寺
山号 愛宕山金剛院●●●
愛宕本地堂
本尊 本地佛勝軍地蔵尊 秘像
●●佛
弘法大師 御府内八十八ヶ所之●第弐拾番
一言石地蔵尊
一言地蔵尊
-------------------------
都営三田線「御成門」駅、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅、JR「新橋」駅から歩ける距離で交通至便ですが、駐車場はありません。
東京都心のオフィス街の、まっただなかにある御府内霊場札所です。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 扁額
ビルの1階にあり、向拝は鉄扉で閉ざされ、扁額がなければおそらく寺院とは気がつきません。
むしろ、境内社の末廣稲荷大明神の方が目立っています。
この稲荷社は、京都伏見稲荷大社より明治時代に勧請されたもので、商売繁盛のご利益あらたかとのことです。

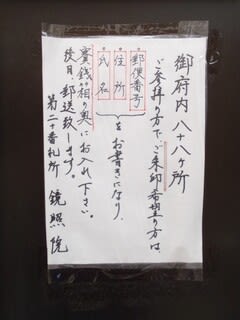
【写真 上(左)】 末廣稲荷大明神
【写真 下(右)】 御朱印案内
前の道はオフィスワーカーが行き交います。
このシチュエーションで、堂前で数珠をとり、勤行をあげるのはある意味勇気がいります。
御府内霊場の巡拝なので、よんどころなく勤行をあげました。
背中に感じる視線。
おそらく道行く人は、「この人なにしてるんだろう?」モードだったかと思います。
2度目の参拝はご縁日だったかと思いますが、ご開扉されて堂内(というか開扉するとすぐ前が護摩壇なので堂前)で勤行できました。
こうなれば落ち着いて参拝できます。
(このときの写真がなぜかみつからないので、みつかり次第UPします。)
御朱印は門扉に案内が貼ってあり、郵送で受けることができます。
ご開扉のときは専用納経帳に拝受できました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
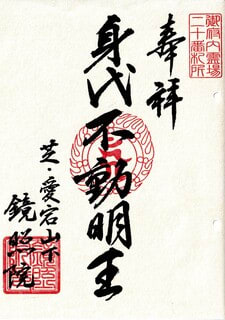
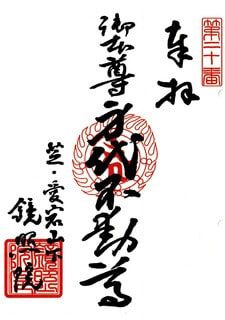
【写真 上(左)】 専用集印帳(直書)
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「身代不動明王」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。
右上に「御府内霊場二十番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ Vol.7)
【 BGM 】
■ far on the water - Kalafina
■ Erato - 志方あきこ
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-5
Vol.-4からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第16番 亀頂山 密乗院 三寶寺
(さんぽうじ)
練馬区石神井台1-15-6
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:豊島八十八ヶ所第16番、関東三十六不動尊霊場第11番、武蔵野三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第16番、大東京百観音霊場第77番
司元別当:(上石神井村)氷川社ないし石神井明神祠
授与所:寺務所
練馬屈指の名刹で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。
幾多の戦乱や火災で寺記の多くを失っていますが、一部は『新編武蔵風土記稿』などに残り、この名刹の華々しい歴史を伝えてくれます。
山内掲示、『新編武蔵風土記稿』などから由緒・来歴を追ってみます。
應永元年(1394年)、鎌倉胡桃ヶ谷(浄明寺)の大楽寺の大徳権大僧都幸尊法印が仏縁の地を求めて来錫され、石神井川の清流や三宝寺川の谷を控える景勝の当地を真言の道場として定めて開山・建立といいます。
大楽寺は律宗でしたから、当山も真言律宗の流れをくんでいるのかもしれません。
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)の「13.覚園寺」の記事で、大楽寺について触れているので転載します。
********
覚園寺入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。
胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。
これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。
********
『願行上人憲静の研究(下)』(伊藤宏見氏)」のP.43には「三宝寺誌」(小峰頼典、昭和35年)が引用され、三宝寺血脈として「憲静(願行上人)-公珍(鎌倉大楽寺開山)-栄珍-幸尊(三宝寺開山)」とあるので、法統(血脈)としては幸尊(三宝寺開山)は願行上人から数えて四世にあたることがわかります。
願行上人(1215-1295年)は鎌倉時代の高僧で、真言宗三宝院流と北京律(律宗)を兼修され、鎌倉幕府と密接な関係をもち多くの弟子を育成されたといいます。
詳細については■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)の「24.安養院」の記事をご覧ください。
『新編相模國風土記稿』によると、大楽寺は暦應四年(1341年)に足利「基氏の慈母」が佛事を執行しています。
足利基氏(1349-1367年)は足利尊氏の子で初代鎌倉公方。
基氏は文和二年(1353年)に武蔵国入間郡入間川(現・狭山市付近)に宿営地(入間川御陣)を設け北関東や越後の豪族に備え、9年間に渡りここに鎌倉府を置いたといいます。
鎌倉から入間川まで、多摩丘陵を避けるとすると石神井あたりはその道途に当たり、その交通の要衝ぶりは石神井城が築かれ、江古田原合戦の舞台となったことからもわかります。
願行上人は鎌倉幕府との関係が深く、その法流にある大楽寺もまた鎌倉府と関係が深かったとみられるので、石神井という要衝の地に大楽寺ゆかりの寺院が置かれたのは、何らかの政治的な意図もあったのかもしれません。
三寶寺は当初は石神井池南方の現・野球場付近にあったといいます。
文明九年(1477年)、太田道灌が豊島泰経をはじめとする豊島一族を亡ぼした江古田原合戦で豊島氏の居城・石神井城が落城した後、現在地に遷ったとされます。
天文十六年(1547年)、後奈良天皇から勅願所の綸旨を受け、戦国期には小田原北条氏が帰依して寺田の寄附を受け、天正十九年(1591年)には徳川幕府から十石の朱印地を受けています。
『Wikipedia』には「江戸時代には無本寺・独礼の寺格で遇され、塔頭6寺院(教学院、禅定院、観蔵院、最勝寺、正覚院、薬王院)、末寺は50以上の大寺院であった。」とあります。
また、新義真言宗の「関東七箇寺」「関東十一談林」に名を連ねています。
なお、「関東七箇寺」「関東十一談林」は下記のとおり。(諸説あり)
明星院:埼玉県桶川市 智山派 七箇寺
三学院:埼玉県蕨市 智山派 七箇寺
錫杖寺:埼玉県川口市 智山派 七箇寺
一乗院:埼玉県熊谷市 智山派 七箇寺
三寶寺:東京都練馬区 智山派 七箇寺
総持寺:東京都足立区 豊山派 七箇寺
寶仙寺:東京都中野区 豊山派 七箇寺
金剛寺:東京都日野市 高幡不動尊 智山派
長久寺:埼玉県行田市 智山派
法恩寺:埼玉県越生町 智山派
薬王院:東京都八王子市 智山派
龍花院:埼玉県加須市 智山派
宝生寺?:東京都八王子市 智山派
寛永二年(1625年)と正保元年(1644年)には大猷院(徳川三代将軍家光公)御放鷹の際の休憩所にもなっており、その寺格の高さがうかがわれます。
-------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(上石神井村)
三寶寺 新義真言宗 亀頂山密乗院ト号ス 無本寺ナリ 古ハ鎌倉大楽寺ノ末ナリシト云 本尊不動 傍ニ聖徳太子ノ作ノ正観音ヲ安ス 又勝軍地蔵ヲ置リ 是ハ村内愛宕社ノ本地ニシテ世ニ希ナル古佛ナリ 年ヲ追テ朽損セシカハ慶長十一年(1606年)檀越尾崎出羽守資忠住僧頼融ト謀リ修理ヲ加ヘシト云 其後賊ニアヒテ全体ハ失ヘリ 寺伝ヲ閲スルニ当寺ハ應永元年(1394年)権大僧都幸尊下石神井村ニ草創スル所ニシテ(略)後屢戦争ノ災ニ罹テ頗衰タリシニ。文明九年(1477年)太田道灌豊島氏ヲ滅セシ後 ソノ城跡ヘ当寺ヲ移セリト云 カヽル舊刹ナリシカハ 天文十六年(1547年)元ノ如ク勅願所タルヘキノ免状ヲ賜ヒ 永禄十年(1567年)現住尊海ヲ大僧正ニ任セラル 又北條氏ヨリモ寺田ヲ寄附シ制札等ヲ与ヘテ帰依浅カラサリシカハ 御当代ニ至リテモ先規ニ任セラレ天正十九年(1591年)領十石ノ御朱印ヲ賜ハレリ 寛永二年(1625年)正保元年(1645年)大猷院(徳川三代将軍家光公)御放鷹ノ序当寺ヘ御立寄アリ(略)
愛宕社
小名城山ニアリ 略縁起ニ文明中(1469-1487年)太田道灌豊嶋氏ヲ攻ルノ時 当社ヲ勧請シテ勝利を祈シト云
稲荷社ニ
一ハ火消稲荷ト称ス 当社ノ霊験ニヨリ三寶寺火難ヲ遁レシ事アリ故ニ名ツク同寺(三寶寺)持
■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)
亀頂山三寶寺 密乗院と号す。神石神井村にあり。真言宗の道場にして、頗る大刹なり。法印権大僧都幸尊、應永元年(1394年)の創建たり。往古は勅願の地なりし故、勅書数通を蔵すといふ。慶長十一年(1606年)、当寺十世頼融上人、檀主尾崎出羽守資忠といへる人と共に力をあはせ寺院修復の功を全うす。当寺は即ち尾崎氏第宅の舊址なりといへり。
本堂 本尊将軍地蔵菩薩 僧形にして馬に乗じたまふ御影なり。傳へ云ふ。往古此本尊盗賊の為に盗みとらる。其夜、本尊住持の夢中に告げて曰く、我願くは化を垂れ、六●の衆生を救はんとす、されど乗する所の馬は猶ここに止むと云々。住持暁に至り、堂中に入りて拝するに、はたして本尊いまさず、故に其後新に今の本尊を彫造し奉り、舊古の馬上に安じまいらすといへり。
稲荷祠 堂前左の岡にあり。里老相傳ふ、上代当寺の住持某灌頂修行の日、老狐鳴きて寺院を廻る事二三回、其過福をしらするに似たり。然るに其夜火起る事再三、その火遂に物ならずして即ち消えたり。故に火消稲荷と称するといへり。
千体地蔵堂 表門の左にあり。
八幡宮 同じ右にあり。
愛宕権現宮 同所西南の林岡にあり。三寶寺本尊の垂迹とす。其地(略)太田道灌の城跡なりと。土人は字して城山と唱ふ。前に関川を懐き、後に遅井を負ふ。
石神井明神祠 石神井村にあり。三寶院奉祀す。神體は一顆の霊石にして、往昔井を穿つとて、其土中に是を得たりとなり。よって石神井の地名こヽに起るといへり。

■『江戸名所図会』 第3 (有朋堂文庫)/三宝寺池~
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
-------------------------
『新編武蔵風土記稿』には「本尊不動 傍ニ聖徳太子ノ作ノ正観音ヲ安ス 又勝軍地蔵ヲ置リ 是ハ村内愛宕社ノ本地ニシテ世ニ希ナル古佛ナリ」という気になる記述があります。
『江戸名所図会』には三寶寺の御本尊が将軍地蔵であると記されています。
上記の愛宕社の由緒を考えあわせると、当山の勝軍地蔵はもともと太田道灌が豊島氏を攻める際に勧請、戦勝祈願した愛宕社の本地佛で、もともとは当山の御本尊ということになります。
これほどの来歴を秘めた勝軍地蔵ですが、御座所はよくわかりません。
また、「聖徳太子ノ作ノ正観音」についても調べはつきませんでした。
石神井公園~江古田周辺には江古田原合戦(太田道灌、豊島氏)とゆかりのある寺社が多く、道灌方、豊島氏方が複雑に絡み合っています。
少しく離れますが、新宿区西落合の西光山 自性院(豊島八十八ヶ所霊場第24番)は、江古田原合戦で道灌が一匹の猫に救われたことから猫地蔵を供養したとされ、「猫寺」の愛称で知られています。
『新編武蔵風土記稿』の(上石神井村)氷川社の項には「氷川社 上下石神井●田中谷原五ヶ村ノ鎮守ナリ(略)三寶寺ノ持 下三社同シ 末社 天神 辨天 天王 第六天 稲荷」とあります。
一方、『江戸名所図会』には(石神井)氷川神社祠の別当が三寶寺という記載はなく、石神井明神祠の別当(奉祀)が三寶寺とあり、三寶寺は(上石神井村)氷川社、あるいは石神井明神祠の別当を司っていたとみられます。

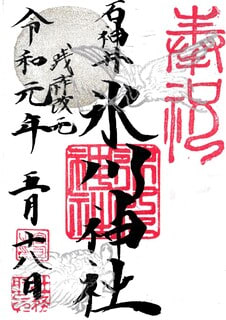
【写真 上(左)】 石神井氷川神社
【写真 下(右)】 石神井氷川神社の御朱印
-------------------------
練馬区の三宝寺池・石神井池(石神井公園)周辺は、区内でも殊に緑ゆたかなところです。
三寶寺は三方寺池(石神井城跡)を北に背負った南傾の地にあります。
南側正面に山門(御成門)、向かって右手に鐘楼堂、長屋門が木立ちのもと落ち着いたたたずまいをみせています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道入口の結界石
・結界石
山内入口にある「守護使不入」の結界石は、当山の寺格の高さをあらわすものとされています。


【写真 上(左)】 山門(御成門)
【写真 下(右)】 鐘楼
・山門(御成門)
文政十年(1827年)建立の山内最古の建築物で区の登録文化財。
家光公鷹狩りの際の御成りに因んで「御成門」とも称します。
切妻造銅板葺の四脚門で格天井。彫刻や細部絵様は江戸時代後期の特徴を示すとされます。
・鐘楼堂
梵鐘は延宝三年(1675年)の鋳造で、鋳物師の名工・椎名伊予守藤原吉寛の銘があり練馬区指定文化財に指定されています。
『新編武蔵風土記稿』は、江戸増上寺の大鐘を鋳た時、その余銅をもって造った梵鐘と伝えます。


【写真 上(左)】 長屋門
【写真 下(右)】 長屋門の扁額
・長屋門
もとは勝海舟邸の門で、旭町にあった兎月園から昭和35年に移築されたもの。
門脇には御府内霊場の札所標があります。


【写真 上(左)】 大黒堂
【写真 下(右)】 大黒堂の向拝
・大黒堂/千体地蔵堂
山門(御成門)をくぐった参道左手にある昭和4年創建の堂宇です。
入母屋造本瓦葺流れ向拝でがっしりとした水引虹梁を備える端正なつくり。
扁額はおそらく「福徳無量」かと思われます。
大黒堂奉安の大黒天神は当山第三十三世融憲和尚の念寺佛で、「開運出世大黒天」として
諸人の信仰篤く、札所ではないですが御朱印も授与されています。
地下の千体地蔵堂には江戸時代経堂に祀られていた子育千体地蔵尊と六道曼荼羅が奉安されています。
寺宝の来迎三尊来迎仏画像板碑(区登録文化財)や、永享八年(1436年)銘の国内最古の夜念仏板碑(区指定有形民俗文化財)も千体地蔵堂に安置されていますが公開の可否は不明です。

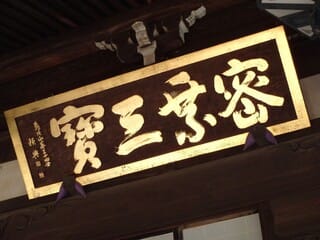
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の扁額
・本堂
参道正面、階段うえに本堂で、階段下右手には豪勢な手水舎。
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風とその奥に大がかりな千鳥破風を興し、複雑なフォルムを見せています。
水引虹梁両端に天女の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二段のボリューミーな彫刻、兎毛通に朱雀?の彫刻を構えて見応えがあります。
扁額は「密蔵三寶」。向拝まわりには御詠歌、御真言、札所板などが掛かり、霊場札所らしい華やいだ雰囲気。
御本尊の不動明王(石神井不動尊)を奉安し、御府内霊場、豊島霊場および関東三十六不動尊霊場の拝所はこちらになります。
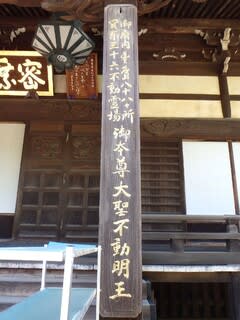

【写真 上(左)】 本堂向拝の札所板
【写真 下(右)】 根本大塔
・根本大塔
本堂向かって左手の高みに開創600年記念事業として発願され、平成8年落慶した佛塔。
高さ17mの木造多宝塔で法身大日如来を象徴しています。
・平和大観音像
根本大塔のさらに左奥に平和大観音像(高さ9mの十一面観世音菩薩像)。
こちらも開創600年記念事業として発願・建立されたものです。


【写真 上(左)】 平和大観音像
【写真 下(右)】 観音堂
・観音堂
武蔵野三十三観音霊場、大東京百観音霊場の拝所はこちらで、札所本尊はいずれも堂宇本尊の如意輪観世音菩薩です。
入母屋造銅板葺流れ向拝で水引虹梁を置き、堂前には回向柱が建てられています。
扁額には「補陀落迦」。補陀落とはふつう観世音菩薩の降臨する霊場を指します。
小壁には如意輪観世音菩薩の御真言と武蔵野観音霊場・大東京百観音霊場併記の札所板が掲げられています。
(大東京百観音霊場の札所標はレア。御朱印も授与されています。)


【写真 上(左)】 観音堂の扁額
【写真 下(右)】 観音堂の札所板
・大師堂(奥之院)
本堂左手奥の林のなかには八十八ヶ所お砂踏み霊場があり、さらにその奥に大師堂(奥之院)と向かって左に修行大師像。
本堂と大師堂は廊下でつながっていますが、一般参詣者はお砂踏み霊場側からの参詣となります。
もともとは経堂で現・根本大塔の場所にあり、千体地蔵尊と弘法大師が奉安されていたことから、従前から「大師堂」と呼ばれていたとのこと。
昭和42年の弘法大師ご誕生1200年を記念して現在の場所に改築されたものです。
ひときわ落ち着いた一画で、こころしずかにお参りができます。
大師堂はおそらく宝形造銅板葺で、向拝柱を構えた端正なつくりです。
扁額は大師堂。身舎には弘法大師の御詠歌と御府内霊場第16番の札所板が掲げられています。
弘法大師霊場(御府内・豊島)巡拝では、当然こちらも拝所となります。


【写真 上(左)】 奥之院入口
【写真 下(右)】 奥之院大師堂


【写真 上(左)】 大師堂向拝と修行大師像
【写真 下(右)】 大師堂扁額
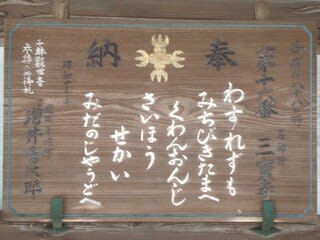

【写真 上(左)】 札所板(札所板)
【写真 下(右)】 札所碑(長屋門脇)
御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受できます。
なお、第70番の禅定院もすぐそばなので、順打ちでなければ併せての巡拝がベターです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
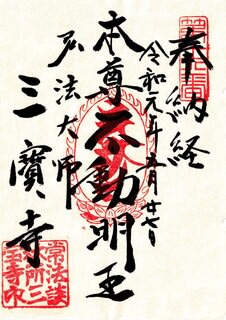
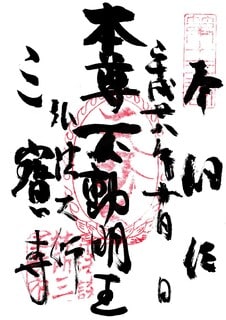
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」の揮毫とおそらく不動明王のお種子「カンマ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第十六番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
※「カンマ-ン」は梵字重字で、「カン」は不動心、「マ-ン」は柔軟心を表すともいわれます。
御朱印御寶印に使われる例は多くありませんが、三寶寺の塔頭寺院として創建された慈雲山 観蔵院(練馬区南田中/豊島八十八ヶ所霊場第81番)ではダイナミックな「カンマ-ン」の揮毫御朱印を授与されています。
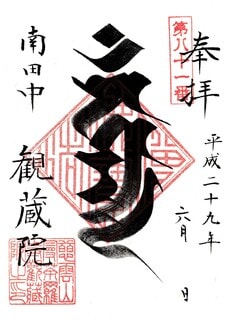
■ 慈雲山 観蔵院の御朱印
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
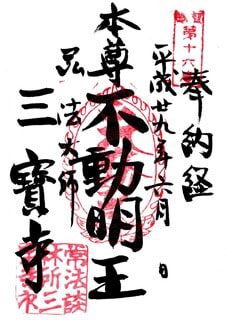
〔 関東三十六不動尊霊場の御朱印 〕
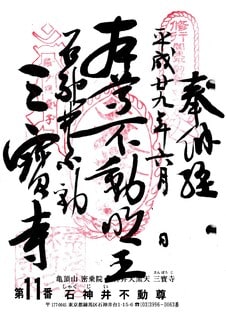
〔 武蔵野三十三観音霊場の御朱印 〕
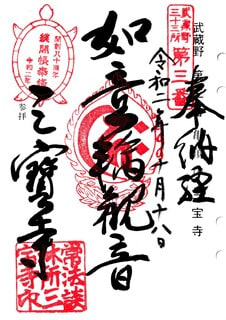
〔 大東京百観音霊場の御朱印 〕
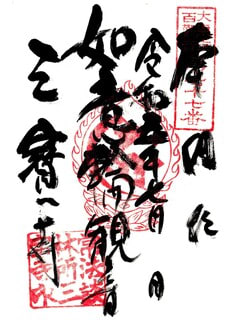
〔 大黒天神の御朱印 〕
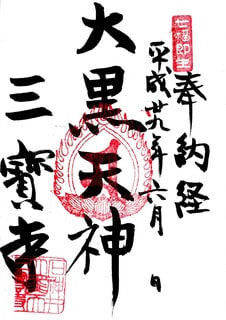
■ 第17番 東高野山 妙楽院 長命寺
(ちょうめいじ)
公式Web
練馬区高野台3-10-13
真言宗豊山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:豊島八十八ヶ所第17番、武蔵野三十三観音霊場第1番、江戸八十八ヶ所霊場第17番、江戸・東京四十四閻魔参り第31番、閻魔三拾遺第25番
司元別当:(谷原)氷川神社
授与所:寺務所
第16番三寶寺、第17番長命寺と、お大師さまとのゆかりがふかい札所がつづき、弘法大師霊場巡拝の醍醐味が味わえます。
長命寺は東高野山とも、新高野山とも称される練馬の名刹。
山内掲示、下記史料、『ルートガイド』などを参考に縁起・沿革を追ってみます。
慶長十八年(1613年)、後北条氏の一族・増島勘解由重明(慶算阿闍梨)が高野山に登り、修行中に弘法大師の御像を感得、谷原に弘法大師像を奉じて一庵(道中庵)を結んで草創といいます。
その子(甥とも)増島重俊が諸堂を建立、高野山奥の院の地勢を模して奥の院を整備。
寛永十七年(1640年)には大和長谷寺の小池坊秀算(正秀とも)が入られて谷原山長命寺と号しました。
弘法大師霊場としての名声高く、後世では東高野山の山号が使われることが多くなりました。
御本尊は金堂に奉安の十一面観世音菩薩で、行基菩薩の御作と伝わります。
金堂西の大師堂(奥之院)は高野山奥之院に倣った規模の大きなもので、東高野山と称されて参詣寺として信仰を集めています。
区のWeb史料には「江戸町奉行が支配した、品川大木戸・四谷大木戸・板橋・千住・本所・深川から多くの方が参拝したという練馬区屈指の古刹」とあります。
また、練馬区貫井5丁目にある「貫井の東高野山道道標」(練馬区登録文化財)は、旧清戸道(所沢秩父道)から長命寺へと向かう旧道の分岐点に建立された道標二基で、いずれも江戸時代後期における長命寺参詣や交通を考える上で貴重なものとされています。
『江戸名所図会』によると、本堂と観音堂、そして大師堂(奥之院)は橋廊で結ばれた一大伽藍であったようですが、幾度の火災に遭い往時の結構を失っています。
しかし数次の伽藍再建を経て、いまでも名刹の風格を保っています。
(谷原)氷川神社の境内掲示には「『新編武蔵風土記稿』には『村ノ鎮守ナリ、長命寺ノ持』とあります。長命寺はここから南西約百メートルにある真言宗の名刹で、江戸時代は当社の別当寺でした。祭神は須佐之男命です。(略)境内に皇大神宮(祭神天照大御神)、八幡神社(祭神応神天皇)、春日神社(祭神天児屋根命)の三社があります。この三社は『新編武蔵風土記稿』谷原村長命寺の項に『三社宮 大神宮・八幡・春日三神ヲ安ス』とある神社です。江戸時代は長命寺の境内にありましたが、神仏分離後に当地へ移されました。」とあり、長命寺が(谷原)氷川神社の別当であったこと、長命寺山内の三社宮(大神宮・八幡・春日三神)が神仏分離後、(谷原)氷川神社に御遷座されたことが明記されています。

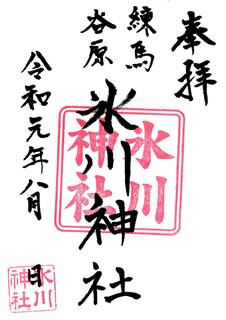
【写真 上(左)】(谷原)氷川神社
【写真 下(右)】(谷原)氷川神社の御朱印
豊島八十八ヶ所霊場、江戸八十八ヶ所霊場の札所で、武蔵野三十三観音霊場初番(発願寺)をつとめられ、観音巡礼でも重要な寺院です。
また、ふたつの閻魔霊場の札所でもあり、多彩な信仰の場となっていたことがわかります。
-------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(谷原村)
長命寺 新義真言宗 大和國初瀬小池坊末 谷原山妙楽院ト称ス 本尊不動 古ハ薬師ヲ安スト云 境内大師堂ノ縁起ニ 増島勘解由重明ナルモノ当村ニ住シ 仏心深ク兄重國カ第四子重俊ニ家ヲ譲リ 剃髪染衣シ慶算ト号シ 紀伊國高野山ニ登リ木食勤行スルコト年アリ 或日大師ノ夢想ニ因テ讃岐國彌谷寺ニ至リ 師自作ノ木像ヲ感得シ速ニ当村ニ帰リ高野山ニ擬シ一院ヲ営ムカノ像ヲ安置ス 今ノ大師堂是ナリ。
云慶算元和二年(1616年)六月寂シ 重俊其志ヲ継諸堂(略)建立(略)高野山ニ倣フ因テ東高野山ト呼 又新高野山トモ云
寛永十七年(1640年)小池坊住僧正秀推挙シテ長命寺ト名ツケ一寺トナセリ 是ヨリ佛燈彌興隆ス因テ正秀を請テ換算トス
金堂 十一面観音ヲ安ス 立像長三寸許行基ノ作ナリ 両脇に太神宮春日明神ヲ安ス
大師堂 奥ノ院ト称ス 弘法大師ハ木の坐像長二尺余
三社宮 大神宮八幡春日三神ヲ安ス
舊家者傳左右衛門 増島ト称ス 小田原北條ノ族士タリシカ天正十八年(1590年)没落ノ後 東照宮ニ謁シ奉リ 当村及田中ノ両邑ヲ賜ヒ後又加恩アリテ六百石ヲ領シ(略)
氷川社 (谷原)村の鎮守ナリ 長命寺の持 下同 稲荷社三 一ハ國廣稲荷 一ハ金山稲荷ト称ス
■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)
谷原山長命寺 妙楽院と号す。 真言宗にして、本尊に薬師如来の像を安置す。慈覚大師の作なり。慶安四年(1651年)慶算阿闍梨といへる木食の沙門、当寺を開基す。阿闍梨は伊豆國の産、北條早雲長氏の曽孫にして、増島氏なり、俗称は勘解由重明といふ。天正中(1573-1592年)北條氏規に属して、豆州韮山の城に籠居す。北條家滅亡の後、此地に退去して農民となる。(略)入道染衣の身となりて、慶算と改め、室を儲けて道中庵と号す。
観音堂 本堂の西にあり。本尊十一面観音の像は行基菩薩の作なり。和州初瀬寺にならびたりとて、天照、春日、八幡の三神をあがめまつりて、当寺の鎮護廟とす。寛永十七年(1640年)の九月、長谷の小池坊秀算僧正当寺を長命寺と号けらる。
大師堂 本堂の西にあり是を奥の院と称す。(略)すべて紀州高野山大師入定の地勢を模擬する故に、堂前に萬燈堂あり、又御廟の橋、蛇楊は、同じ前庭にありて(略)樹林鬱蒼として、閑寂玄蔭の地なり。
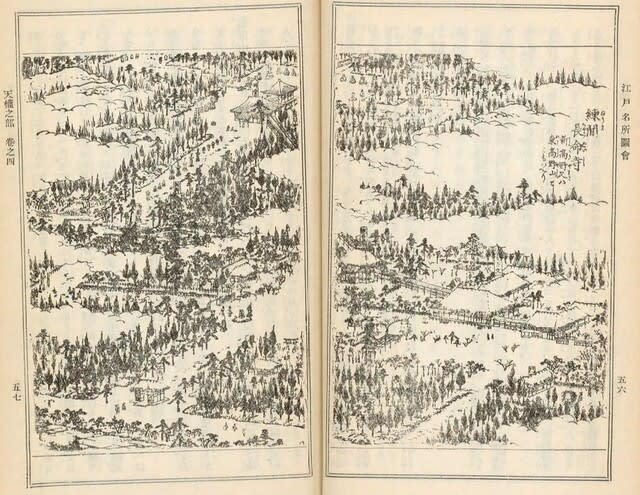
■『江戸名所図会』 第3 (有朋堂文庫)/練馬長命寺
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
-------------------------


【写真 上(左)】 南大門
【写真 下(右)】 南大門の扁額.
西武池袋線「練馬高野台」駅のそば、笹目通りにもほど近く交通は至便です。
南側正面に構える南大門は、切妻屋根銅板葺、三間一戸の八脚門で左右前後に四天王像、見上げに「南大門」の扁額。
スケール感ある結構で、名刹の風格をたたえています。
南大門の右手にある仁王門も小ぶりながら三間一戸の八脚門で、左右脇間に仁王尊像が御座し、ワラジが奉納されています。
寛文年間(1661-1672年)の築とされ、こちらは区の有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 東門


【写真 上(左)】 東門の扁額
【写真 下(右)】 鐘楼と十三佛
笹目通り側にも東門があります。
切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門で、寺号扁額を掲げています。
東参道脇には御府内八十八ヶ所が宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことを示す貴重な標石があります。
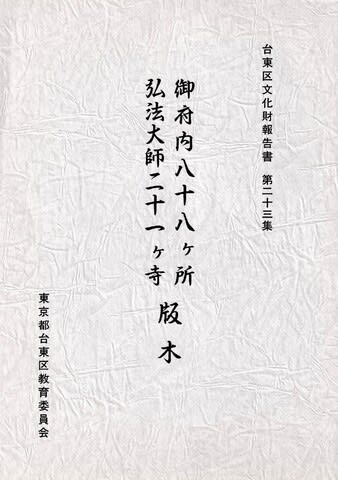
『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)には、「第十七番札所長命寺には「宝暦三癸酉三月廿一日」銘の御府内八十八ヶ所標石が現存する。(略)この銘文を信じる限り宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことになる。」
同書では第17番長命寺の標石と宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』を根拠とし、「ここでは、宝暦二年(1752年)頃『浅間山真楽寺住職』の開設とし、不明な点は後考に俟つこととしたい。」とあります。


【写真 上(左)】 第17番長命寺の御府内八十八ヶ所標石-1
【写真 下(右)】 同-2
南大門をくぐると参道右手に十三佛と鐘楼。
江戸時代初期の特徴を示すという梵鐘も区指定の有形文化財です。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 木遣塚
参道左手には子育て地蔵尊、弘法大師千百五十年御遠忌供養塔と修行大師像、木遣塚、阿弥陀如来立像(石像露仏)が並びます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道から本堂


【写真 上(左)】 香炉
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面が本堂(金堂)で、狛犬を乗せた青銅の香炉が存在感を放っています。
本堂前に高木はすくなく、明るく開けた感じの参道です。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
階段のうえの本堂の基盤はコンクリで入母屋造銅板葺流れ向拝、4本の向拝柱を備えるスケールの大きな建物です。
向拝は桟戸のうえに寺号扁額。
本堂の御本尊は不動明王です。
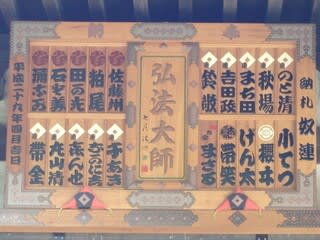

【写真 上(左)】 本堂の奴連の奉納額
【写真 下(右)】 観音堂


【写真 上(左)】 観音堂の扁額
【写真 下(右)】 木遣地蔵尊
本堂向かって左手には観音堂。
おそらく朱塗りの八角堂で、こちらには御本尊の十一面観世音菩薩が御座し、御府内霊場、豊島霊場、武蔵野観音霊場の拝所です。
鉄扉のうえに「観音堂」の扁額。
『新編武蔵風土記稿』には御本尊の十一面観世音菩薩は行基菩薩作とあり、小池坊秀算の作とも伝わる御像でしたが、現在の観音像は後の時代の再刻のようです。
観音堂の手前に木遣地蔵尊。風格のある六角の地蔵堂の中に御座されています。
掲出の由来書には「消防関係者の信仰極めて厚しその篤信凝って明治三十三年八月木遣地蔵堂の建立となる」とあります。
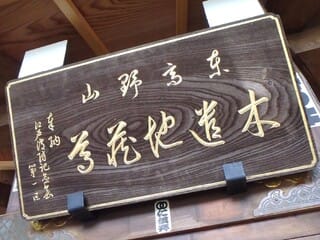

【写真 上(左)】 木遣地蔵尊の扁額
【写真 下(右)】 奥之院参道入口
木遣地蔵尊の右辺からも奥之院に行けますが、南大門をくぐって左手から奥之院専用の参道が伸びています。


【写真 上(左)】 奥之院参道-1
【写真 下(右)】 御廟橋


【写真 上(左)】 奥之院参道-2
【写真 下(右)】 大師堂
奥之院ゾーンは鬱蒼とした木々に囲まれてほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。
参道には反り石橋の御廟橋も掛けられ、豪壮な石燈籠が並びます。
参道途中の「姿見ノ井戸」は、井戸の水に顔が写ると長生きが出来ると伝わります。
こちらは本四国霊場第17番瑠璃山 井戸寺ゆかりの井戸とみられます。


【写真 上(左)】 大師堂向拝
【写真 下(右)】 大師堂扁額
大師堂(御影堂)はおそらく宝形造銅板葺で大がかりな流れ向拝を構えています。
向拝まわりは比較的シンプルですが、向拝正面の桟唐戸には精緻な彫刻が施されて風格があります。
見上げに「御影堂」の扁額。
向かって右手には牀座(しょうざ)に御座される真如親王様の弘法大師像が彫られた石碑があります。
お大師さまのお堂なので、御府内霊場、豊島霊場の拝所になります。


【写真 上(左)】 石碑の弘法大師御影
【写真 下(右)】 閻魔大王像
大師堂まわりも巡拝路となっていて七観音、六地蔵など多くの石仏が安置されています。
堂後には閻魔大王像と十王の石佛も御座します。
こちらの閻魔様は「身代わり閻魔」として著名だったらしく、江戸・東京四十四閻魔参り、閻魔三拾遺のふたつの閻魔霊場の札所となっています。(御朱印は不授与とのこと)
この奥之院一帯は「東高野山奥之院」として都の文化財(史跡)に指定されています。
公式Webによると、境内に紫陽花を見て楽しむお庭「紫陽花庭」ができ、5月末〜6月にかけて見頃を迎えるそうです。
また、山内には芭蕉、水原秋桜子などの句碑があり、俳句ファンにも知られたお寺さまのようです。
御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
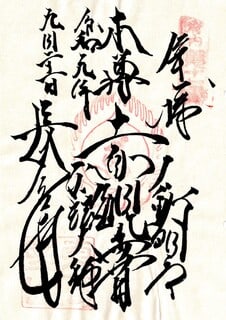
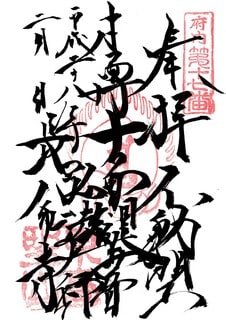
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 十一面観世音」「不動明王」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 武蔵野三十三観音霊場の御朱印 〕
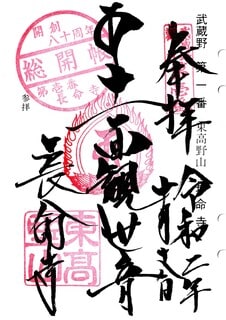
以下、つづきます。
(→ Vol.6)
【 BGM 】
■ ハナミズキ - 新垣結衣 [PV Version]
■ 夢の終わり愛の始まり - アンジェラ・アキ
■ 私たち - 西野カナ
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第16番 亀頂山 密乗院 三寶寺
(さんぽうじ)
練馬区石神井台1-15-6
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:豊島八十八ヶ所第16番、関東三十六不動尊霊場第11番、武蔵野三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第16番、大東京百観音霊場第77番
司元別当:(上石神井村)氷川社ないし石神井明神祠
授与所:寺務所
練馬屈指の名刹で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。
幾多の戦乱や火災で寺記の多くを失っていますが、一部は『新編武蔵風土記稿』などに残り、この名刹の華々しい歴史を伝えてくれます。
山内掲示、『新編武蔵風土記稿』などから由緒・来歴を追ってみます。
應永元年(1394年)、鎌倉胡桃ヶ谷(浄明寺)の大楽寺の大徳権大僧都幸尊法印が仏縁の地を求めて来錫され、石神井川の清流や三宝寺川の谷を控える景勝の当地を真言の道場として定めて開山・建立といいます。
大楽寺は律宗でしたから、当山も真言律宗の流れをくんでいるのかもしれません。
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)の「13.覚園寺」の記事で、大楽寺について触れているので転載します。
********
覚園寺入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。
胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。
これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。
********
『願行上人憲静の研究(下)』(伊藤宏見氏)」のP.43には「三宝寺誌」(小峰頼典、昭和35年)が引用され、三宝寺血脈として「憲静(願行上人)-公珍(鎌倉大楽寺開山)-栄珍-幸尊(三宝寺開山)」とあるので、法統(血脈)としては幸尊(三宝寺開山)は願行上人から数えて四世にあたることがわかります。
願行上人(1215-1295年)は鎌倉時代の高僧で、真言宗三宝院流と北京律(律宗)を兼修され、鎌倉幕府と密接な関係をもち多くの弟子を育成されたといいます。
詳細については■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)の「24.安養院」の記事をご覧ください。
『新編相模國風土記稿』によると、大楽寺は暦應四年(1341年)に足利「基氏の慈母」が佛事を執行しています。
足利基氏(1349-1367年)は足利尊氏の子で初代鎌倉公方。
基氏は文和二年(1353年)に武蔵国入間郡入間川(現・狭山市付近)に宿営地(入間川御陣)を設け北関東や越後の豪族に備え、9年間に渡りここに鎌倉府を置いたといいます。
鎌倉から入間川まで、多摩丘陵を避けるとすると石神井あたりはその道途に当たり、その交通の要衝ぶりは石神井城が築かれ、江古田原合戦の舞台となったことからもわかります。
願行上人は鎌倉幕府との関係が深く、その法流にある大楽寺もまた鎌倉府と関係が深かったとみられるので、石神井という要衝の地に大楽寺ゆかりの寺院が置かれたのは、何らかの政治的な意図もあったのかもしれません。
三寶寺は当初は石神井池南方の現・野球場付近にあったといいます。
文明九年(1477年)、太田道灌が豊島泰経をはじめとする豊島一族を亡ぼした江古田原合戦で豊島氏の居城・石神井城が落城した後、現在地に遷ったとされます。
天文十六年(1547年)、後奈良天皇から勅願所の綸旨を受け、戦国期には小田原北条氏が帰依して寺田の寄附を受け、天正十九年(1591年)には徳川幕府から十石の朱印地を受けています。
『Wikipedia』には「江戸時代には無本寺・独礼の寺格で遇され、塔頭6寺院(教学院、禅定院、観蔵院、最勝寺、正覚院、薬王院)、末寺は50以上の大寺院であった。」とあります。
また、新義真言宗の「関東七箇寺」「関東十一談林」に名を連ねています。
なお、「関東七箇寺」「関東十一談林」は下記のとおり。(諸説あり)
明星院:埼玉県桶川市 智山派 七箇寺
三学院:埼玉県蕨市 智山派 七箇寺
錫杖寺:埼玉県川口市 智山派 七箇寺
一乗院:埼玉県熊谷市 智山派 七箇寺
三寶寺:東京都練馬区 智山派 七箇寺
総持寺:東京都足立区 豊山派 七箇寺
寶仙寺:東京都中野区 豊山派 七箇寺
金剛寺:東京都日野市 高幡不動尊 智山派
長久寺:埼玉県行田市 智山派
法恩寺:埼玉県越生町 智山派
薬王院:東京都八王子市 智山派
龍花院:埼玉県加須市 智山派
宝生寺?:東京都八王子市 智山派
寛永二年(1625年)と正保元年(1644年)には大猷院(徳川三代将軍家光公)御放鷹の際の休憩所にもなっており、その寺格の高さがうかがわれます。
-------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(上石神井村)
三寶寺 新義真言宗 亀頂山密乗院ト号ス 無本寺ナリ 古ハ鎌倉大楽寺ノ末ナリシト云 本尊不動 傍ニ聖徳太子ノ作ノ正観音ヲ安ス 又勝軍地蔵ヲ置リ 是ハ村内愛宕社ノ本地ニシテ世ニ希ナル古佛ナリ 年ヲ追テ朽損セシカハ慶長十一年(1606年)檀越尾崎出羽守資忠住僧頼融ト謀リ修理ヲ加ヘシト云 其後賊ニアヒテ全体ハ失ヘリ 寺伝ヲ閲スルニ当寺ハ應永元年(1394年)権大僧都幸尊下石神井村ニ草創スル所ニシテ(略)後屢戦争ノ災ニ罹テ頗衰タリシニ。文明九年(1477年)太田道灌豊島氏ヲ滅セシ後 ソノ城跡ヘ当寺ヲ移セリト云 カヽル舊刹ナリシカハ 天文十六年(1547年)元ノ如ク勅願所タルヘキノ免状ヲ賜ヒ 永禄十年(1567年)現住尊海ヲ大僧正ニ任セラル 又北條氏ヨリモ寺田ヲ寄附シ制札等ヲ与ヘテ帰依浅カラサリシカハ 御当代ニ至リテモ先規ニ任セラレ天正十九年(1591年)領十石ノ御朱印ヲ賜ハレリ 寛永二年(1625年)正保元年(1645年)大猷院(徳川三代将軍家光公)御放鷹ノ序当寺ヘ御立寄アリ(略)
愛宕社
小名城山ニアリ 略縁起ニ文明中(1469-1487年)太田道灌豊嶋氏ヲ攻ルノ時 当社ヲ勧請シテ勝利を祈シト云
稲荷社ニ
一ハ火消稲荷ト称ス 当社ノ霊験ニヨリ三寶寺火難ヲ遁レシ事アリ故ニ名ツク同寺(三寶寺)持
■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)
亀頂山三寶寺 密乗院と号す。神石神井村にあり。真言宗の道場にして、頗る大刹なり。法印権大僧都幸尊、應永元年(1394年)の創建たり。往古は勅願の地なりし故、勅書数通を蔵すといふ。慶長十一年(1606年)、当寺十世頼融上人、檀主尾崎出羽守資忠といへる人と共に力をあはせ寺院修復の功を全うす。当寺は即ち尾崎氏第宅の舊址なりといへり。
本堂 本尊将軍地蔵菩薩 僧形にして馬に乗じたまふ御影なり。傳へ云ふ。往古此本尊盗賊の為に盗みとらる。其夜、本尊住持の夢中に告げて曰く、我願くは化を垂れ、六●の衆生を救はんとす、されど乗する所の馬は猶ここに止むと云々。住持暁に至り、堂中に入りて拝するに、はたして本尊いまさず、故に其後新に今の本尊を彫造し奉り、舊古の馬上に安じまいらすといへり。
稲荷祠 堂前左の岡にあり。里老相傳ふ、上代当寺の住持某灌頂修行の日、老狐鳴きて寺院を廻る事二三回、其過福をしらするに似たり。然るに其夜火起る事再三、その火遂に物ならずして即ち消えたり。故に火消稲荷と称するといへり。
千体地蔵堂 表門の左にあり。
八幡宮 同じ右にあり。
愛宕権現宮 同所西南の林岡にあり。三寶寺本尊の垂迹とす。其地(略)太田道灌の城跡なりと。土人は字して城山と唱ふ。前に関川を懐き、後に遅井を負ふ。
石神井明神祠 石神井村にあり。三寶院奉祀す。神體は一顆の霊石にして、往昔井を穿つとて、其土中に是を得たりとなり。よって石神井の地名こヽに起るといへり。

■『江戸名所図会』 第3 (有朋堂文庫)/三宝寺池~
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
-------------------------
『新編武蔵風土記稿』には「本尊不動 傍ニ聖徳太子ノ作ノ正観音ヲ安ス 又勝軍地蔵ヲ置リ 是ハ村内愛宕社ノ本地ニシテ世ニ希ナル古佛ナリ」という気になる記述があります。
『江戸名所図会』には三寶寺の御本尊が将軍地蔵であると記されています。
上記の愛宕社の由緒を考えあわせると、当山の勝軍地蔵はもともと太田道灌が豊島氏を攻める際に勧請、戦勝祈願した愛宕社の本地佛で、もともとは当山の御本尊ということになります。
これほどの来歴を秘めた勝軍地蔵ですが、御座所はよくわかりません。
また、「聖徳太子ノ作ノ正観音」についても調べはつきませんでした。
石神井公園~江古田周辺には江古田原合戦(太田道灌、豊島氏)とゆかりのある寺社が多く、道灌方、豊島氏方が複雑に絡み合っています。
少しく離れますが、新宿区西落合の西光山 自性院(豊島八十八ヶ所霊場第24番)は、江古田原合戦で道灌が一匹の猫に救われたことから猫地蔵を供養したとされ、「猫寺」の愛称で知られています。
『新編武蔵風土記稿』の(上石神井村)氷川社の項には「氷川社 上下石神井●田中谷原五ヶ村ノ鎮守ナリ(略)三寶寺ノ持 下三社同シ 末社 天神 辨天 天王 第六天 稲荷」とあります。
一方、『江戸名所図会』には(石神井)氷川神社祠の別当が三寶寺という記載はなく、石神井明神祠の別当(奉祀)が三寶寺とあり、三寶寺は(上石神井村)氷川社、あるいは石神井明神祠の別当を司っていたとみられます。

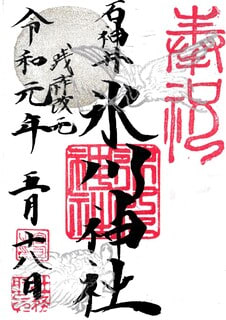
【写真 上(左)】 石神井氷川神社
【写真 下(右)】 石神井氷川神社の御朱印
-------------------------
練馬区の三宝寺池・石神井池(石神井公園)周辺は、区内でも殊に緑ゆたかなところです。
三寶寺は三方寺池(石神井城跡)を北に背負った南傾の地にあります。
南側正面に山門(御成門)、向かって右手に鐘楼堂、長屋門が木立ちのもと落ち着いたたたずまいをみせています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道入口の結界石
・結界石
山内入口にある「守護使不入」の結界石は、当山の寺格の高さをあらわすものとされています。


【写真 上(左)】 山門(御成門)
【写真 下(右)】 鐘楼
・山門(御成門)
文政十年(1827年)建立の山内最古の建築物で区の登録文化財。
家光公鷹狩りの際の御成りに因んで「御成門」とも称します。
切妻造銅板葺の四脚門で格天井。彫刻や細部絵様は江戸時代後期の特徴を示すとされます。
・鐘楼堂
梵鐘は延宝三年(1675年)の鋳造で、鋳物師の名工・椎名伊予守藤原吉寛の銘があり練馬区指定文化財に指定されています。
『新編武蔵風土記稿』は、江戸増上寺の大鐘を鋳た時、その余銅をもって造った梵鐘と伝えます。


【写真 上(左)】 長屋門
【写真 下(右)】 長屋門の扁額
・長屋門
もとは勝海舟邸の門で、旭町にあった兎月園から昭和35年に移築されたもの。
門脇には御府内霊場の札所標があります。


【写真 上(左)】 大黒堂
【写真 下(右)】 大黒堂の向拝
・大黒堂/千体地蔵堂
山門(御成門)をくぐった参道左手にある昭和4年創建の堂宇です。
入母屋造本瓦葺流れ向拝でがっしりとした水引虹梁を備える端正なつくり。
扁額はおそらく「福徳無量」かと思われます。
大黒堂奉安の大黒天神は当山第三十三世融憲和尚の念寺佛で、「開運出世大黒天」として
諸人の信仰篤く、札所ではないですが御朱印も授与されています。
地下の千体地蔵堂には江戸時代経堂に祀られていた子育千体地蔵尊と六道曼荼羅が奉安されています。
寺宝の来迎三尊来迎仏画像板碑(区登録文化財)や、永享八年(1436年)銘の国内最古の夜念仏板碑(区指定有形民俗文化財)も千体地蔵堂に安置されていますが公開の可否は不明です。

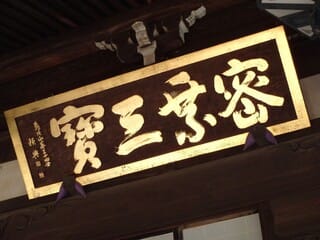
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の扁額
・本堂
参道正面、階段うえに本堂で、階段下右手には豪勢な手水舎。
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風とその奥に大がかりな千鳥破風を興し、複雑なフォルムを見せています。
水引虹梁両端に天女の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二段のボリューミーな彫刻、兎毛通に朱雀?の彫刻を構えて見応えがあります。
扁額は「密蔵三寶」。向拝まわりには御詠歌、御真言、札所板などが掛かり、霊場札所らしい華やいだ雰囲気。
御本尊の不動明王(石神井不動尊)を奉安し、御府内霊場、豊島霊場および関東三十六不動尊霊場の拝所はこちらになります。
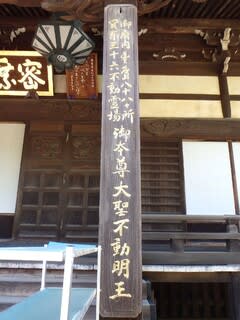

【写真 上(左)】 本堂向拝の札所板
【写真 下(右)】 根本大塔
・根本大塔
本堂向かって左手の高みに開創600年記念事業として発願され、平成8年落慶した佛塔。
高さ17mの木造多宝塔で法身大日如来を象徴しています。
・平和大観音像
根本大塔のさらに左奥に平和大観音像(高さ9mの十一面観世音菩薩像)。
こちらも開創600年記念事業として発願・建立されたものです。


【写真 上(左)】 平和大観音像
【写真 下(右)】 観音堂
・観音堂
武蔵野三十三観音霊場、大東京百観音霊場の拝所はこちらで、札所本尊はいずれも堂宇本尊の如意輪観世音菩薩です。
入母屋造銅板葺流れ向拝で水引虹梁を置き、堂前には回向柱が建てられています。
扁額には「補陀落迦」。補陀落とはふつう観世音菩薩の降臨する霊場を指します。
小壁には如意輪観世音菩薩の御真言と武蔵野観音霊場・大東京百観音霊場併記の札所板が掲げられています。
(大東京百観音霊場の札所標はレア。御朱印も授与されています。)


【写真 上(左)】 観音堂の扁額
【写真 下(右)】 観音堂の札所板
・大師堂(奥之院)
本堂左手奥の林のなかには八十八ヶ所お砂踏み霊場があり、さらにその奥に大師堂(奥之院)と向かって左に修行大師像。
本堂と大師堂は廊下でつながっていますが、一般参詣者はお砂踏み霊場側からの参詣となります。
もともとは経堂で現・根本大塔の場所にあり、千体地蔵尊と弘法大師が奉安されていたことから、従前から「大師堂」と呼ばれていたとのこと。
昭和42年の弘法大師ご誕生1200年を記念して現在の場所に改築されたものです。
ひときわ落ち着いた一画で、こころしずかにお参りができます。
大師堂はおそらく宝形造銅板葺で、向拝柱を構えた端正なつくりです。
扁額は大師堂。身舎には弘法大師の御詠歌と御府内霊場第16番の札所板が掲げられています。
弘法大師霊場(御府内・豊島)巡拝では、当然こちらも拝所となります。


【写真 上(左)】 奥之院入口
【写真 下(右)】 奥之院大師堂


【写真 上(左)】 大師堂向拝と修行大師像
【写真 下(右)】 大師堂扁額
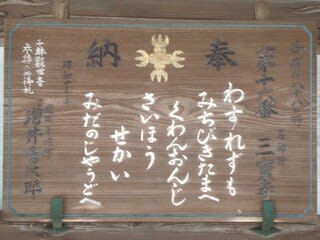

【写真 上(左)】 札所板(札所板)
【写真 下(右)】 札所碑(長屋門脇)
御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受できます。
なお、第70番の禅定院もすぐそばなので、順打ちでなければ併せての巡拝がベターです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
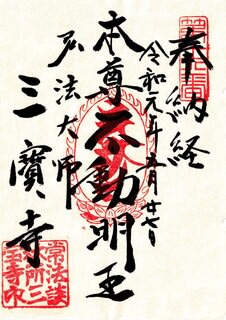
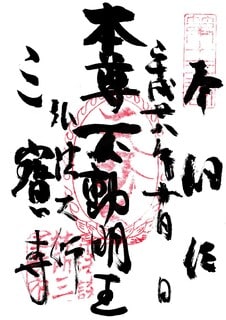
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」の揮毫とおそらく不動明王のお種子「カンマ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第十六番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
※「カンマ-ン」は梵字重字で、「カン」は不動心、「マ-ン」は柔軟心を表すともいわれます。
御朱印御寶印に使われる例は多くありませんが、三寶寺の塔頭寺院として創建された慈雲山 観蔵院(練馬区南田中/豊島八十八ヶ所霊場第81番)ではダイナミックな「カンマ-ン」の揮毫御朱印を授与されています。
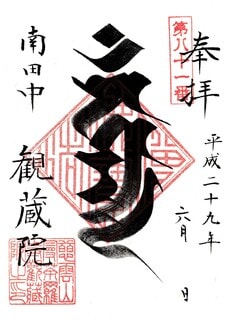
■ 慈雲山 観蔵院の御朱印
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
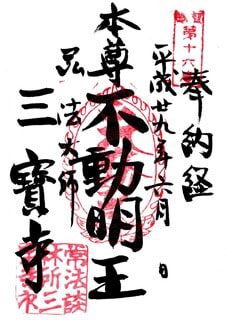
〔 関東三十六不動尊霊場の御朱印 〕
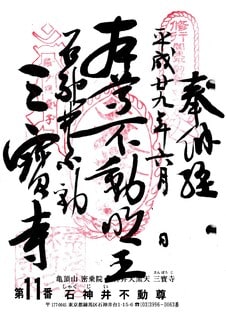
〔 武蔵野三十三観音霊場の御朱印 〕
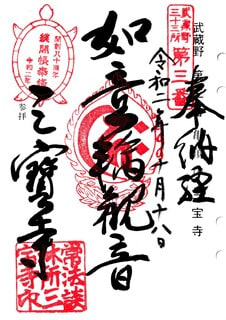
〔 大東京百観音霊場の御朱印 〕
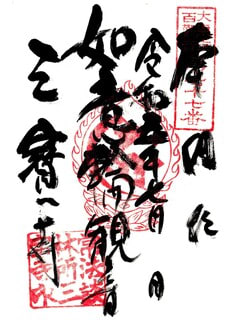
〔 大黒天神の御朱印 〕
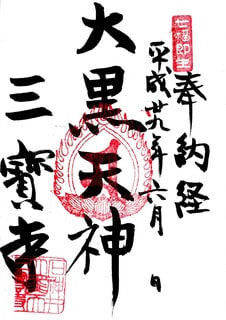
■ 第17番 東高野山 妙楽院 長命寺
(ちょうめいじ)
公式Web
練馬区高野台3-10-13
真言宗豊山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:豊島八十八ヶ所第17番、武蔵野三十三観音霊場第1番、江戸八十八ヶ所霊場第17番、江戸・東京四十四閻魔参り第31番、閻魔三拾遺第25番
司元別当:(谷原)氷川神社
授与所:寺務所
第16番三寶寺、第17番長命寺と、お大師さまとのゆかりがふかい札所がつづき、弘法大師霊場巡拝の醍醐味が味わえます。
長命寺は東高野山とも、新高野山とも称される練馬の名刹。
山内掲示、下記史料、『ルートガイド』などを参考に縁起・沿革を追ってみます。
慶長十八年(1613年)、後北条氏の一族・増島勘解由重明(慶算阿闍梨)が高野山に登り、修行中に弘法大師の御像を感得、谷原に弘法大師像を奉じて一庵(道中庵)を結んで草創といいます。
その子(甥とも)増島重俊が諸堂を建立、高野山奥の院の地勢を模して奥の院を整備。
寛永十七年(1640年)には大和長谷寺の小池坊秀算(正秀とも)が入られて谷原山長命寺と号しました。
弘法大師霊場としての名声高く、後世では東高野山の山号が使われることが多くなりました。
御本尊は金堂に奉安の十一面観世音菩薩で、行基菩薩の御作と伝わります。
金堂西の大師堂(奥之院)は高野山奥之院に倣った規模の大きなもので、東高野山と称されて参詣寺として信仰を集めています。
区のWeb史料には「江戸町奉行が支配した、品川大木戸・四谷大木戸・板橋・千住・本所・深川から多くの方が参拝したという練馬区屈指の古刹」とあります。
また、練馬区貫井5丁目にある「貫井の東高野山道道標」(練馬区登録文化財)は、旧清戸道(所沢秩父道)から長命寺へと向かう旧道の分岐点に建立された道標二基で、いずれも江戸時代後期における長命寺参詣や交通を考える上で貴重なものとされています。
『江戸名所図会』によると、本堂と観音堂、そして大師堂(奥之院)は橋廊で結ばれた一大伽藍であったようですが、幾度の火災に遭い往時の結構を失っています。
しかし数次の伽藍再建を経て、いまでも名刹の風格を保っています。
(谷原)氷川神社の境内掲示には「『新編武蔵風土記稿』には『村ノ鎮守ナリ、長命寺ノ持』とあります。長命寺はここから南西約百メートルにある真言宗の名刹で、江戸時代は当社の別当寺でした。祭神は須佐之男命です。(略)境内に皇大神宮(祭神天照大御神)、八幡神社(祭神応神天皇)、春日神社(祭神天児屋根命)の三社があります。この三社は『新編武蔵風土記稿』谷原村長命寺の項に『三社宮 大神宮・八幡・春日三神ヲ安ス』とある神社です。江戸時代は長命寺の境内にありましたが、神仏分離後に当地へ移されました。」とあり、長命寺が(谷原)氷川神社の別当であったこと、長命寺山内の三社宮(大神宮・八幡・春日三神)が神仏分離後、(谷原)氷川神社に御遷座されたことが明記されています。

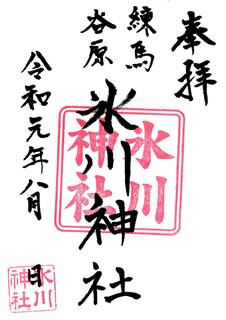
【写真 上(左)】(谷原)氷川神社
【写真 下(右)】(谷原)氷川神社の御朱印
豊島八十八ヶ所霊場、江戸八十八ヶ所霊場の札所で、武蔵野三十三観音霊場初番(発願寺)をつとめられ、観音巡礼でも重要な寺院です。
また、ふたつの閻魔霊場の札所でもあり、多彩な信仰の場となっていたことがわかります。
-------------------------
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(谷原村)
長命寺 新義真言宗 大和國初瀬小池坊末 谷原山妙楽院ト称ス 本尊不動 古ハ薬師ヲ安スト云 境内大師堂ノ縁起ニ 増島勘解由重明ナルモノ当村ニ住シ 仏心深ク兄重國カ第四子重俊ニ家ヲ譲リ 剃髪染衣シ慶算ト号シ 紀伊國高野山ニ登リ木食勤行スルコト年アリ 或日大師ノ夢想ニ因テ讃岐國彌谷寺ニ至リ 師自作ノ木像ヲ感得シ速ニ当村ニ帰リ高野山ニ擬シ一院ヲ営ムカノ像ヲ安置ス 今ノ大師堂是ナリ。
云慶算元和二年(1616年)六月寂シ 重俊其志ヲ継諸堂(略)建立(略)高野山ニ倣フ因テ東高野山ト呼 又新高野山トモ云
寛永十七年(1640年)小池坊住僧正秀推挙シテ長命寺ト名ツケ一寺トナセリ 是ヨリ佛燈彌興隆ス因テ正秀を請テ換算トス
金堂 十一面観音ヲ安ス 立像長三寸許行基ノ作ナリ 両脇に太神宮春日明神ヲ安ス
大師堂 奥ノ院ト称ス 弘法大師ハ木の坐像長二尺余
三社宮 大神宮八幡春日三神ヲ安ス
舊家者傳左右衛門 増島ト称ス 小田原北條ノ族士タリシカ天正十八年(1590年)没落ノ後 東照宮ニ謁シ奉リ 当村及田中ノ両邑ヲ賜ヒ後又加恩アリテ六百石ヲ領シ(略)
氷川社 (谷原)村の鎮守ナリ 長命寺の持 下同 稲荷社三 一ハ國廣稲荷 一ハ金山稲荷ト称ス
■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)
谷原山長命寺 妙楽院と号す。 真言宗にして、本尊に薬師如来の像を安置す。慈覚大師の作なり。慶安四年(1651年)慶算阿闍梨といへる木食の沙門、当寺を開基す。阿闍梨は伊豆國の産、北條早雲長氏の曽孫にして、増島氏なり、俗称は勘解由重明といふ。天正中(1573-1592年)北條氏規に属して、豆州韮山の城に籠居す。北條家滅亡の後、此地に退去して農民となる。(略)入道染衣の身となりて、慶算と改め、室を儲けて道中庵と号す。
観音堂 本堂の西にあり。本尊十一面観音の像は行基菩薩の作なり。和州初瀬寺にならびたりとて、天照、春日、八幡の三神をあがめまつりて、当寺の鎮護廟とす。寛永十七年(1640年)の九月、長谷の小池坊秀算僧正当寺を長命寺と号けらる。
大師堂 本堂の西にあり是を奥の院と称す。(略)すべて紀州高野山大師入定の地勢を模擬する故に、堂前に萬燈堂あり、又御廟の橋、蛇楊は、同じ前庭にありて(略)樹林鬱蒼として、閑寂玄蔭の地なり。
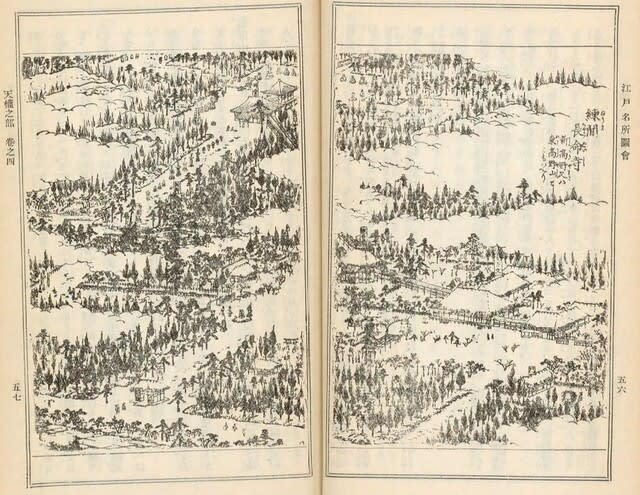
■『江戸名所図会』 第3 (有朋堂文庫)/練馬長命寺
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
-------------------------


【写真 上(左)】 南大門
【写真 下(右)】 南大門の扁額.
西武池袋線「練馬高野台」駅のそば、笹目通りにもほど近く交通は至便です。
南側正面に構える南大門は、切妻屋根銅板葺、三間一戸の八脚門で左右前後に四天王像、見上げに「南大門」の扁額。
スケール感ある結構で、名刹の風格をたたえています。
南大門の右手にある仁王門も小ぶりながら三間一戸の八脚門で、左右脇間に仁王尊像が御座し、ワラジが奉納されています。
寛文年間(1661-1672年)の築とされ、こちらは区の有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 東門


【写真 上(左)】 東門の扁額
【写真 下(右)】 鐘楼と十三佛
笹目通り側にも東門があります。
切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門で、寺号扁額を掲げています。
東参道脇には御府内八十八ヶ所が宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことを示す貴重な標石があります。
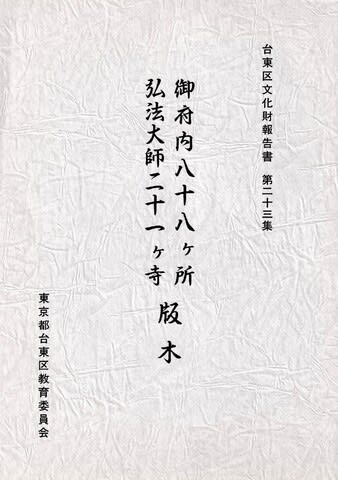
『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)には、「第十七番札所長命寺には「宝暦三癸酉三月廿一日」銘の御府内八十八ヶ所標石が現存する。(略)この銘文を信じる限り宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことになる。」
同書では第17番長命寺の標石と宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』を根拠とし、「ここでは、宝暦二年(1752年)頃『浅間山真楽寺住職』の開設とし、不明な点は後考に俟つこととしたい。」とあります。


【写真 上(左)】 第17番長命寺の御府内八十八ヶ所標石-1
【写真 下(右)】 同-2
南大門をくぐると参道右手に十三佛と鐘楼。
江戸時代初期の特徴を示すという梵鐘も区指定の有形文化財です。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 木遣塚
参道左手には子育て地蔵尊、弘法大師千百五十年御遠忌供養塔と修行大師像、木遣塚、阿弥陀如来立像(石像露仏)が並びます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道から本堂


【写真 上(左)】 香炉
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面が本堂(金堂)で、狛犬を乗せた青銅の香炉が存在感を放っています。
本堂前に高木はすくなく、明るく開けた感じの参道です。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
階段のうえの本堂の基盤はコンクリで入母屋造銅板葺流れ向拝、4本の向拝柱を備えるスケールの大きな建物です。
向拝は桟戸のうえに寺号扁額。
本堂の御本尊は不動明王です。
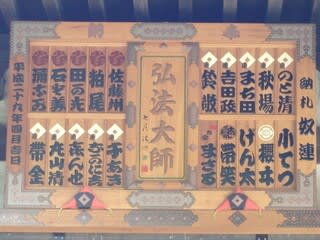

【写真 上(左)】 本堂の奴連の奉納額
【写真 下(右)】 観音堂


【写真 上(左)】 観音堂の扁額
【写真 下(右)】 木遣地蔵尊
本堂向かって左手には観音堂。
おそらく朱塗りの八角堂で、こちらには御本尊の十一面観世音菩薩が御座し、御府内霊場、豊島霊場、武蔵野観音霊場の拝所です。
鉄扉のうえに「観音堂」の扁額。
『新編武蔵風土記稿』には御本尊の十一面観世音菩薩は行基菩薩作とあり、小池坊秀算の作とも伝わる御像でしたが、現在の観音像は後の時代の再刻のようです。
観音堂の手前に木遣地蔵尊。風格のある六角の地蔵堂の中に御座されています。
掲出の由来書には「消防関係者の信仰極めて厚しその篤信凝って明治三十三年八月木遣地蔵堂の建立となる」とあります。
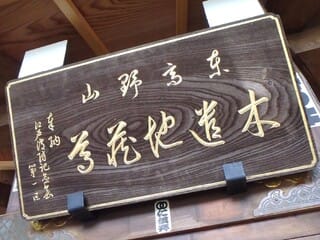

【写真 上(左)】 木遣地蔵尊の扁額
【写真 下(右)】 奥之院参道入口
木遣地蔵尊の右辺からも奥之院に行けますが、南大門をくぐって左手から奥之院専用の参道が伸びています。


【写真 上(左)】 奥之院参道-1
【写真 下(右)】 御廟橋


【写真 上(左)】 奥之院参道-2
【写真 下(右)】 大師堂
奥之院ゾーンは鬱蒼とした木々に囲まれてほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。
参道には反り石橋の御廟橋も掛けられ、豪壮な石燈籠が並びます。
参道途中の「姿見ノ井戸」は、井戸の水に顔が写ると長生きが出来ると伝わります。
こちらは本四国霊場第17番瑠璃山 井戸寺ゆかりの井戸とみられます。


【写真 上(左)】 大師堂向拝
【写真 下(右)】 大師堂扁額
大師堂(御影堂)はおそらく宝形造銅板葺で大がかりな流れ向拝を構えています。
向拝まわりは比較的シンプルですが、向拝正面の桟唐戸には精緻な彫刻が施されて風格があります。
見上げに「御影堂」の扁額。
向かって右手には牀座(しょうざ)に御座される真如親王様の弘法大師像が彫られた石碑があります。
お大師さまのお堂なので、御府内霊場、豊島霊場の拝所になります。


【写真 上(左)】 石碑の弘法大師御影
【写真 下(右)】 閻魔大王像
大師堂まわりも巡拝路となっていて七観音、六地蔵など多くの石仏が安置されています。
堂後には閻魔大王像と十王の石佛も御座します。
こちらの閻魔様は「身代わり閻魔」として著名だったらしく、江戸・東京四十四閻魔参り、閻魔三拾遺のふたつの閻魔霊場の札所となっています。(御朱印は不授与とのこと)
この奥之院一帯は「東高野山奥之院」として都の文化財(史跡)に指定されています。
公式Webによると、境内に紫陽花を見て楽しむお庭「紫陽花庭」ができ、5月末〜6月にかけて見頃を迎えるそうです。
また、山内には芭蕉、水原秋桜子などの句碑があり、俳句ファンにも知られたお寺さまのようです。
御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
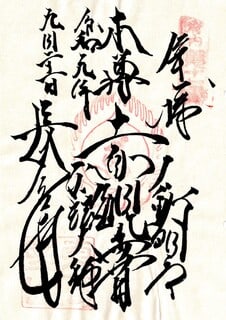
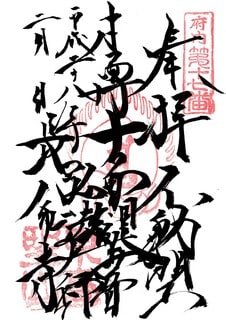
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 十一面観世音」「不動明王」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 武蔵野三十三観音霊場の御朱印 〕
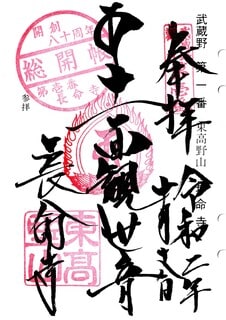
以下、つづきます。
(→ Vol.6)
【 BGM 】
■ ハナミズキ - 新垣結衣 [PV Version]
■ 夢の終わり愛の始まり - アンジェラ・アキ
■ 私たち - 西野カナ
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4
Vol.-3からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
第13番は通常、高野山 弘法寺 龍生院(港区三田)がリストされますが、和光山 興源院 大龍寺(北区田端)も第13番として札所対応をされています。
■ 第13番-1 三田高野山 弘法寺 龍生院 (大本山 弘法寺)
(りゅうしょういん/こうぼうじ)
公式Web
港区三田2-12-5
真言宗系単立?/旧高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
他札所:
司元別当:
授与所:寺務所
『ルートガイド』によると、元は高野山山内寺院のひとつで、弘仁七年(816年)弘法大師が高野山開創の際、声明(しょうみょう)の道場として建立された系譜を継ぐとされています。
明治24年(ないし23年)に三田の現在地に移転といいます。
江戸八十八ヶ所霊場第13番は「医王山 円覚寺(霊岸島白金町)」とあり、江戸期は円覚寺(圓覚寺)が御府内霊場第13番札所であったとみられます。
霊岸島の圓覚寺については『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに記載が見当たりませんが、『江戸名所図会 7巻 [2]』、『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [1]』に記載がみられます。
【史料】
■ 『江戸名所図会 7巻 [2]』(国立国会図書館)
薬師堂
霊巌島銀町にあり 別当ハ真言宗● 医王山圓覚寺と号す 本尊ハ三州鳳来寺峯の薬師と同木同作にして 理趣仙人●●をと称へ 大宝年間(701-704年)に造立ありしと●り 座像御丈三尺あり 鳳来寺薬師と称し又ハ橋本薬師とも称せり 此霊像ハ(もともと?)高野山橋本の里にありしを 慶長年間(1596-1615年)当寺の開基恵生阿闍梨此地にうつしたてまつり 後霊巌寺の境内に安す 深川霊巌寺のことなり 仮寺始此地にあり 萬治(1658-1661年)の後 霊巌寺深川にうつる其頃 此薬師堂と此地にあり 稲荷の社の● 此地に残し(以下略)
橋本稲荷社
同境内にあり 此所の鎮守と● 社記云神像ハ弘法大師の作にして 御丈一尺二寸あり 山城國伏見稲荷明神と同木同作なりといへり 往古高野山の麓橋本の里に宮居を造●安置ありし故ありて後 ここに勧請なしたてまつるとなり
■ 『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [1]』(同上)
橋本稲荷社 別当醫王山圓覚院 三州鳳来寺峯薬師同作の薬師あり よって医王山といふ
-------------------------
ふたつの史料によると、医王山圓覚寺は橋本稲荷社の別当で、御本尊は三河鳳来寺の薬師如来と同木同作の霊像とあり、鳳来寺薬師、橋本薬師とも称したといいます。
「Wikipedia」、「(一社)奥三河観光協議会」Webによると、三河の煙巌山鳳来寺は標高695mの鳳来寺山の中腹にあり、大宝二年(702年)利修仙人により開山といいます。
利修仙人は杉の霊木から御本尊・薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将、四天王を彫刻されこの地に奉安と伝わります。
時の文武帝がご病気になられた時、利修仙人に病気平癒祈願の勅使を使わされました。
仙人は鳳凰に乗って都にのぼり、七日間(十七日間とも)の加持祈祷によって帝は快癒されたといいます。
この御礼として伽藍を建立され、鳳凰に乗って参内ということで「鳳来寺」の名を賜ったのが寺号の由来とされています。
弘法大師による真言宗の開宗は弘仁十四年(823年)の嵯峨天皇からの教王護国寺勅賜とされるので、大宝二年(702年)の利修仙人による鳳来寺開山はこれより前です。
しかし、利修仙人の教義の系譜は真言宗五智教団として承継されました。
中世には源頼朝公により再興とも伝わり、江戸時代、とくに家光公の治世に栄えたといいます。
これは家康公の生母・於大の方が当山に参籠し、家康公を授けられたというゆかりによるものといい、実際、慶安四年(1651年)にはこの地に新たに東照宮が造営されています。
『東海道名所図会』には「煙厳山鳳来寺勝岳院(神祖宮 鎮守三社権現 六所護法神 開基利修仙人堂 常行堂三層塔 鏡堂 八幡宮 伊勢両太神宮 弁才天祠 天神祠 毘沙門堂 一王子 二王子 荒神祠 弘法大師堂 元三大師堂・・・」とあり、真言、天台両宗並び立つ神仏混淆の一大霊場であったことがわかります。
明治に入り鳳来寺と東照宮が分離されて鳳来寺は衰勢となり、明治38年、高野山金剛峯寺の特命を受け京都法輪寺から派遣された服部賢成住職に当山の再建が託されました。
宗派は真言宗に統一されて高野山の所属となり、寺院存続が図られたものの大正3年の伽藍焼失などで諸坊を失い、いまは松高院と医王院の二院の堂宇を残すのみといいます。(本堂は昭和49年に再建?)
以上ながながと鳳来寺について追ってみましたが、ここでわかったのは鳳来寺(真言宗五智教団)と高野山金剛峯寺(高野山真言宗)との関係のふかさです。
「中央区観光協会特派員ブログ」には、かつて霊岸島には ”七不思議” なるものがあって、その参は「円覚寺にある薬師は、宵薬師のため縁日の 8日・12日には参詣者がいない」とあります。
また、「(円覚寺は)明治になって火災に遭い廃寺になった」とも。
圓覚寺は明治に入って廃寺となったという情報は、複数のWeb記事で確認できるのでこれは事実だと思われます。
一方、『ルートガイド』には「元は高野山の山内子院の一つで、弘仁7年(816年)、弘法大師が高野山御開創の際、声明の道場として建立されたことが由来」とあります。
また、下記の『芝區誌』の記述を考えあわせると、高野山の声明の道場を草創とし、明治23年に中興開山とされる渡邊貞浄法尼が現在地に遷されるととともに、明治になって火災に遭い廃寺となっていた霊岸島の圓覚寺を承継し、御府内霊場第13番となったものとみられます。
【史料】
■ 『芝區誌_15』のP.70(デジタル版 港区のあゆみ)
龍生院 三田一丁目二十六番地 古義真言宗、往古の開山は不詳であるが、明治二十三年頃本寺中興の開山と謂はれる渡邊貞浄法尼が、今の地に一寺を建立して現在に至る。境内の西北隅に渡邊綱の産生湯の水を汲んだと傳へられる古井戸がある。元本堂の東南隅に、綱の社と云ふ稲荷神社があつたが、今は無い。
「声明とは、一般に僧侶がお経に旋律をつけて唱えるもので、密教儀礼の中で用いられる声楽の名称です。」「声明は高度に体系化された声楽である。声明には音階や表現技法、楽譜までもが存在し、それぞれ細かくルールが決められています。」(高野山真言宗総本山金剛峯寺Webより)
高野山金剛峯寺を中心とした声明(しょうみょう)は一般に「南山進流」(なんざんしんりゅう)と称され、儀礼の進行の際などに唱えられているそうです。
当山の前身?の高野山の声明道場(子院?)は、南山進流だった可能性があります。
■ 高野山南山進流聲明「心略梵語」 声明独唱 松島龍戒
-------------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 入口


【写真 上(左)】 以前の入口
【写真 下(右)】 札所標
三田の慶應義塾大学のすぐ北隣、桜田通りから参道に入りますが、奥まっているのであたりは住宅メインの落ち着いた雰囲気。
桜田通りからすでにモダンな白亜の本堂が見えています。
山内入口に「御府内八十八ヶ所 弘法大師 第拾三番」の札所標。
門柱には三田高野山 弘法寺の山号寺号。
ガイドなどでは「龍生院」と紹介されていますが、「弘法寺」が前面に出ているのでいささかわかりにくいかも。
先日、令和五年六月十五日の弘法大師御生誕一二五0年当日の記念法要時には五色の吹き流しが掲げられていました。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 エントランス
以前は木造建築でしたがモダンな伽藍に建て替えられて平成26年竣工。
改築後は主に「弘法寺」の寺号を使われているようです。
本堂入口上部に「弘法寺」の寺号扁額。
入って左手には「空海 消えずの火」が灯り、その上に立像の不動明王。
この火は、弘法大師が唐より帰朝後宮島に渡り弥山にて修行なされ、大同元年(806年)開基されたという宮島弥山の大聖院から採火されたもの。
本堂で護持され、毎日採火され1階に灯されるそうです。
大聖院は真言宗御室派の大本山。当山は現在真言宗系単立となっている模様で、宗派を越えて採火・護持されているのかも。
(公式Webには「大聖院と法縁関係にある弘法寺」とあります。)


【写真 上(左)】 エントランスの扁額
【写真 下(右)】 「消えずの火」と不動明王
入って正面はホテルのフロントのような瀟洒なかまえ。
声をお掛けすると3階の本堂にお参りするよう案内をいただくので、先にこちらで御朱印帳をお預けした方がいいかもしれません。
エレベーターで3階へ。
本堂は正面に金剛界大日如来と左右に両界曼荼羅。
向かって右手に弘法大師、左に坐像の不動明王が御座され、その前には護摩壇。
ビル内ながら真言密寺らしい荘厳な空間で、音響がよく、読経の声がよく響きます。
御朱印はフロント?にて拝受でき、ご対応はたいへんに丁寧です。
御府内霊場の御朱印の尊格は以前は弘法大師でしたが、Web情報によると現在は大日如来になっている模様。
弘法大師御生誕一二五0年のお参り時には、記念の限定切り絵御朱印が授与されていました。
筆者はふつう限定御朱印や切り絵御朱印は拝受しませんが、弘法大師御生誕一二五0年記念御朱印、しかも稚児大師と修行大師の御影入りの御朱印とあってはさすがに話は別で、ありがたく拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
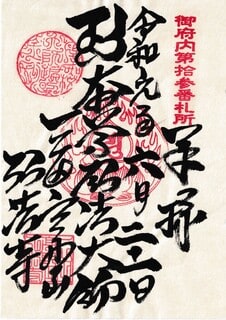

【写真 上(左)】 専用集印帳(令和元年)
【写真 下(右)】 専用集印帳(令和5年)

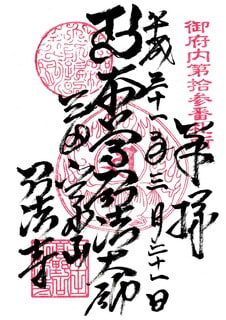
【写真 上(左)】 汎用御朱印帳(平成28年)
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(平成31年)
主印は弘法大師のお種子「ユ」(蓮華座+火焔宝珠)。右上に弘法大師の御印?。
揮毫は「本尊 弘法大師」で右上に「御府内霊場第拾三番札所」の札所印。左下には山号寺号揮毫と寺院印が捺されています。
※ 御府内霊場の御朱印尊格は以前は弘法大師でしたが、現在は大日如来となっている模様です。
令和5年8月拝受の御朱印の主印は弘法大師のお種子「ユ」(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。
揮毫は金剛界大日如来のお種子「バン」「大日如来」で右上に「御府内霊場第拾三番札所」の札所印。左下には山号寺号揮毫と寺院印が捺されています。
※平成28年6月拝受の御朱印はミニ御朱印的なサイズで、龍生院の揮毫と寺院印があります。
〔 弘法大師御生誕一二五0年記念御朱印 〕
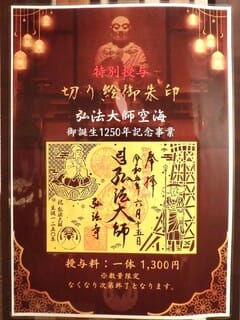

【写真 上(左)】 リーフレット
【写真 下(右)】 記念御朱印
当山内には渡邊綱の産湯の水を汲んだと伝えられる古井戸があります。
当山の北側を東西に走る坂は「綱の手引坂」と呼ばれ、渡辺綱(羅生門の鬼退治で有名な、平安時代の勇士源頼光の四天王の一人)がこの付近に生まれたという伝説によるとのこと。(「港区観光協会Web」)


【写真 上(左)】 産湯の井戸
【写真 下(右)】 井戸の碑
■ 第13番-2 和光山 興源院 大龍寺
(だいりゅうじ)
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第21番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第17番、滝野川寺院めぐり第6番
司元別当:(上田端)八幡神社
授与所:寺務所
真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺は、東京・豊島エリアの「豊島八十八ヶ所霊場」第21番の札所です。
こちらはWeb上で「弘法大師 十三番」の札所印の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
御府内八十八箇所は、番外・掛所などの札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院(弘法寺)がリストされています。
御府内霊場第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺とされ、明治初期に龍生院に引き継がれたとされていて大龍寺との関連は不詳です。
そこで「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」に注目してみました。
「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」は江戸期に開創とみられる弘法大師霊場で、『東都歳時記』に「弘法大師 二十一ヶ所」として記載があります。
同書に「未詳 湯嶋霊雲寺に弘法大師(読取不可)廿壱番とあり」とあり、謎の多い霊場ともされてきましたが、寛政二年(1790年)開版の『弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木』が発見され、実在が確定しています。
台東区のWeb史料には「この巡礼については、江戸時代の文献史料がほぼ皆無でしたので、発生年代、巡礼する寺院などはほとんど明らかでありませんでした。本版木は、寛政2年(1790)に碩峯という僧侶が開版したもので、巡礼寺院・所在地・御詠歌を紹介しています。寺院は谷中・下谷・浅草・本所・湯島に散在しますが、21ヶ寺のうち18ヶ寺が現在の台東区内です。」とあります。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
こちらをみると、ほとんどが新義真言宗系・真言宗霊雲寺派(天台宗1)で、古義真言宗寺院はありません。
ふたつの真言宗霊雲寺派は湯嶋霊雲寺(結願)と大龍寺で、湯嶋霊雲寺のみの御府内霊場より札所数が多くなっています。
ふつう、弘法大師二十一ヶ所は弘法大師八十八ヶ所の簡易版で、札所が重複するケースが多いですが、御府内二十一ヶ所霊場では21札所のうち7のみ(谷中観音寺、谷中加納院、谷中明王院、谷中長久院、谷中多宝院、谷中自性院、湯嶋霊雲寺)で重複はすくなく、御府内霊場とは別の観点から開創されたものかもしれません。
いずれにしても、すくなくとも大龍寺は豊島八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所霊場のふたつの弘法大師霊場札所なので、大師霊場とゆかりのふかい寺院であることは間違いないと思います。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国立国会図書館DC)。
「眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ、天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置 八幡社 村ノ鎮守トス 稲荷社」
創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興され、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。
『新編武蔵風土記稿』によると、江戸期は(上田端)八幡神社の別当を司っていたようです。

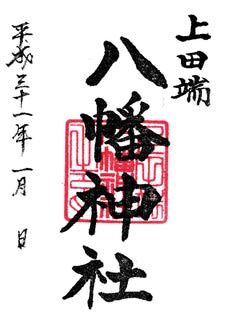
【写真 上(左)】 (上田端)八幡神社
【写真 下(右)】 (上田端)八幡神社の御朱印
-------------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れたご対応です。
拝受者が少ない滝野川寺院めぐりの御朱印申告についても、特段驚かれた風はありませんでした。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
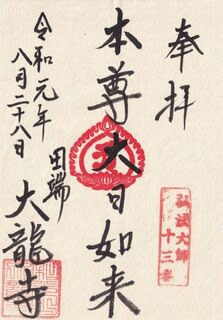
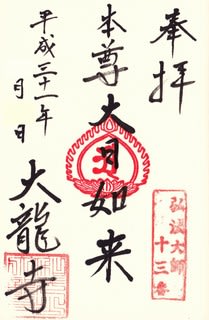
>
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右下に「弘法大師 十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 滝野川寺院めぐりの御朱印 〕

■ 第14番 白鷺山 正幡寺 福蔵院
(ふくぞういん)
中野区白鷺1-31-5
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第14番
司元別当:鷺宮八幡神社
授与所:庫裡
御府内霊場は第14番から第18番まで御府内を離れて郊外を回ります。
いずれも雰囲気のある名刹です。
文亀・永正年間(1501-1521年)、頼珍(大永元年(1521年)示寂)によって開山され、下鷺ノ宮村の鷺宮大明神(八幡社)の別当寺でした。
宝暦十二年(1762年)堂宇を焼失し寺伝詳細は伝わっておりません。
江戸八十八ヶ所霊場の札所でもあるので、当初からの札所とも思われますが、府外の当山が御府内霊場札所に指定された経緯はうかがい知れません。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(上鷺ノ宮村)
白鷺山正幡寺ト号ス 前ノ八幡(現・鷺宮八幡神社)ノ別当ナリ 則其御朱印地ノ内ニアリ 新義真言宗ニテ当郡中野村寶仙寺ノ末 開山ヲ頼珍ト云 大永元年(1521年)五月示寂 第九世ヲ鏡薫ト云 慶安二年(1649年)八月寂セリ 此僧ノトキ八幡ノ御朱印ヲ賜ヒシヨシ カヽル功アルニヨリ中興トス サレハ当寺ノ開基ハ文亀・永正ノ頃ナルヘシ 宝暦十二年(1762年)十二月丙丁ノ災ニカヽリテ 堂宇残ラス焼失セシカハ詳ナルコトヲ傳へス 今ノ客殿ハ其後造リシモノナリ(略) 本尊不動ノ坐像長二尺 二童子モ長二尺許 運慶ノ作ト云、又ハ智證大師ノ作トモ云傳フ
別当を司った八幡社(現・鷺宮八幡神社)は上下鷺ノ宮村の鎮守で、本地として十一面観世音菩薩を祀っていました。


【写真 上(左)】 鷺宮八幡神社
【写真 下(右)】 鷺宮八幡神社の御朱印
-------------------------
西武新宿線「鷺ノ宮」駅のすぐ南。妙正寺川の流れを北に押し上げる高みに鷺宮八幡神社と隣接してあります。
駅そばですが駐車場もあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 弘法大師碑と地蔵尊


【写真 上(左)】 意匠の効いた土塀
【写真 下(右)】 馬頭観世音菩薩
山内入口右手に弘法大師碑と2体の地蔵尊。
ここから山門に向かって意匠の効いた土塀が伸びています。
植木が綺麗に刈り込まれ、参道には木の葉ひとつ置ちておらず、手入れの行き届いたお寺さまであることがわかります。
参道途中に院号標と整った像容の馬頭観世音菩薩。


【写真 上(左)】 寺号標と参道
【写真 下(右)】 山門
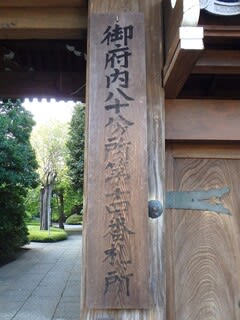

【写真 上(左)】 山門の札所板
【写真 下(右)】 山門扁額
山門は切妻屋根銅板葺の薬医門で左右に板塀を延べています。
見上げに山院号扁額、門柱には御府内霊場の札所板。


【写真 上(左)】 緑濃い山内
【写真 下(右)】 十三佛
山門をくぐると右手覆屋内に石佛の十三佛。案内板によると石佛で十三体そろったものは都内でもめずらしいそうです。
緑濃く手入れの行き届いた山内には、石佛、六地蔵、子育地蔵尊、そして修行大師像などが安置されています。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 修行大師と子育地蔵尊


【写真 上(左)】 手入れの行き届いた山内
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造金属板葺流れ向拝、屋根中央に置かれているのは太陽光パネルでしょうか。
昭和35年の落慶とのことですが、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備え、伝統的に整った寺院建築です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝開き戸の上に豪快な筆致の山号扁額が掲げられ、軒には不動明王の奉納額も掛けられています。


【写真 上(左)】 奉納額
【写真 下(右)】 庫裡
都内の駅そばとは思えない雰囲気のある山内で、落ち着いた参拝ができました。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。
手入れの行き届いた山内から予想されるとおり、たいへんご親切なご対応をいただきました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

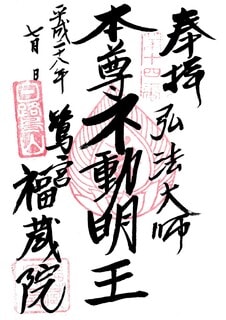
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は不動明王のお種子「カン/カーン」(蓮華座+火焔宝珠)。揮毫は「本尊 不動明王」「弘法大師」で右上に「御府内十四番」の札所印。左上に山号印、その下には院号揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第15番 瑠璃光山 医王寺 南蔵院
(なんぞういん)
練馬区中村1-15-1
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第15番、江戸八十八ヶ所霊場第15番
司元別当:(中村)八幡宮ほか
授与所:庫裡
御府内霊場には南蔵院と号する札所が練馬(第15番)、牛込(第22番)と高田(第29番)の3箇寺あり、それぞれ練馬南蔵院、牛込南蔵院、高田南蔵院と呼んで区別されます。
第15番の練馬南蔵院は、御府内からいささか離れるものの江戸八十八ヶ所霊場と同番で、御府内からの移転記録もないことから当初からの御府内霊場札所とみられます。
練馬辺りは豊島八十八ヶ所の巡拝エリアでもあり、当山も御府内霊場、豊島霊場というふたつの弘法大師霊場の兼務札所となっています。
現地掲示、『ルートガイド』および『新編武蔵風土記稿』によると、延文二年(1357年)(永正年中(1504-1521年)とも)、僧良辨の中興といいます。
良辨は諸国の霊場へ法華妙典を納めた後に当寺に錫をとどめ、妙経を埋めて「良辨塚」を建立してなおも修行をつづけると、ある日薬師の像を感得しました。
良辨は堂宇を建立してこの薬師像を奉安し、いまの御本尊になったといいます。
秘佛で33年に一度の御開扉。
当寺で出していた「白龍丸」という薬は良辨が夢中で感得した霊法の薬丸で万病に効くとされ、「南蔵院の投込み」と称して全国に広まりましたが、明治10年の法制定を受けて販売は中止となりました。
当山は元(中村)八幡宮の別当で、末寺の西光寺(廃寺)はこのそばにあったといいます。

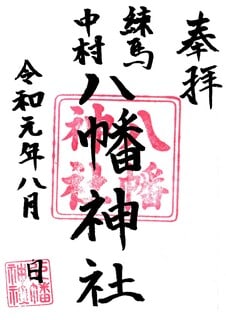
【写真 上(左)】 (中村)八幡神社
【写真 下(右)】 (中村)八幡神社の御朱印
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(中村)
南蔵院 新義真言宗 上練馬村愛染院末 瑠璃山醫王寺ト称ス(略)永正年中(1504-1521年)僧良辨(良弁僧正トハ異ナリ) 諸国ノ霊場ヘ法華妙典ヲ納メ志願畢リテ後 当寺ニ錫ヲトヽメ妙経ヲ理テ一箇ノ塚トス 今村ノ中程ニ良辨塚ト称スルモノ是ナリ 然シテヨリ此寺ニアリテ修法怠ラサリシカハ 其功空シカラサルニヤ 或日薬師ノ像ヲ感得セリ ヨリテ堂宇ヲ興隆シ其像ヲ安置スト云 今ノ本尊是ナリ 秘仏トシ三十三年ニ一度龕ヲ開テ拝セシム 又当寺ヨリ白龍丸ト云薬ヲ出セリ 曽テ良辨カ夢中感得セル霊法ノ薬丸ナリ
諸病ニ験アリト云 稲荷社 閻魔堂
西光寺 紫雲山阿彌陀院ト号ス 本尊阿彌陀 大日堂 南蔵院持
良辨塚 前(南蔵院の項)ニ云 経典ヲ埋メシ塚ナリ 古碑一基タテリ モトヨリ其頃立シモノトハ思ハレス 年月モ彫ラス
(中村)八幡宮 (中)村ノ鎮守ナリ 南蔵院持 下持同シ 稲荷社、大神社、辨天社、水神社、三峰社、金毘羅社
-------------------------
最寄りは都営大江戸線・西武池袋線「練馬」駅。
練馬の落ち着いた住宅地のなかに、かなりの広さを保ってあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道入口の対燈籠
東側の南蔵院通りに立派な門柱とその先に銅燈籠一対と右手に慈母観音立像。
その先に参道がながながとつづき、緑ゆたかな山内はとても練馬の住宅地とは思えません。


【写真 上(左)】 緑ゆたかな山内
【写真 下(右)】 手前から庫裡、本堂、薬師堂
しばらく進むと右手に本堂が見えてきます。
本堂向かって右手に庫裡、左手に薬師堂を配して堂々たる構え。


【写真 上(左)】 本堂参道
【写真 下(右)】 本堂と銅燈籠


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 本堂
本堂前に進むと左手に修行大師像。
本堂前の大ぶりで精緻な彫刻の銅燈籠が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は入母屋造桟瓦葺で間数が多く、濃茶色の格子扉、小壁下の菱格子が引き締まった印象。
向拝見上げには山号扁額。
柱のないすっきりとした向拝は、密寺というより禅刹的なイメージがあります。


【写真 上(左)】 薬師堂
【写真 下(右)】 斜めからの薬師堂
薬師堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻と見上げに「薬師堂」の扁額を掲げています。
当山の御本尊は秘佛の薬師如来。
本堂と薬師堂があるので、本堂と薬師堂にそれぞれ薬師如来が御座すか、本堂には宗派本尊の大日如来あるいは別尊が奉安され、薬師堂の薬師如来が御本尊とされているかのいずれかと思いますが、よくわかりません。
ちなみに、豊島霊場の御朱印尊格も薬師如来となっているお薬師さまのお寺です。


【写真 上(左)】 薬師堂の向拝
【写真 下(右)】 薬師堂の扁額


【写真 上(左)】 弘法大師碑
【写真 下(右)】 閻魔堂
山内西側には閻魔堂。
『新編武蔵風土記稿』に記載されている閻魔堂の流れと思われ、堂内には閻魔大王と十王像が御座されています。
その南側に赤門と鐘楼門。
薬師堂、閻魔堂、鐘楼門などは宝暦三年(1753年)建立とされ、とくに鐘楼門は「江戸時代中期の建築と考えられる区内唯一の鐘楼門」(区資料)とされ練馬区の指定文化財です。


【写真 上(左)】 鐘楼門
【写真 下(右)】 赤門
赤門と鐘楼門の向きが直角で、赤門は脇門用途ではなさそうです。
鐘楼門は入母屋屋根桟瓦葺朱塗りの三間一戸の八脚門で、脇間に迫力の仁王尊像、上層に鐘をおき、端正な垂木が目につきます。
赤門は切妻屋根瓦葺。朱塗りで本柱と控柱各二本を備えた様式は医薬門でしょうか。
山内南側に祠が二棟御鎮座で、一棟は弁財天尊のような気がします。
もうひとつは扁額がないのでよくわかりませんが、『新編武蔵風土記稿』にある稲荷神かもしれません。


【写真 上(左)】 首継地蔵尊
【写真 下(右)】 聖観世音菩薩像
その左手には首継(つぎ)地蔵尊。
もともとは末寺の西光院(廃寺・現中村八幡神社の社裏)に奉安とされますが、現在は南蔵院に遷られています。
かつて首のない地蔵尊と地蔵尊の首が別々に村人によって奉安されており、二人の村人の夢告が一致して首と胴体をあわせたところぴったりと収まったため、二体を継いで「首継(つぎ)地蔵尊」としたと伝わります。
昭和初期の不況期には「首切り」を遁れようと願う多くの参拝者で賑わったそうです。
首継地蔵尊の右脇に笠付角柱型のめずらしい聖観世音菩薩像がありますが、こちらも西光院から遷られたお像のようです。


【写真 上(左)】 長屋門
【写真 下(右)】 練馬消防団の施設
その左手には長屋門。山内南側にある唯一の門です。
その左にある分校のような雰囲気ある建物は、現在は練馬消防団の施設となっているようです。
山内には弘法大師碑(御府内霊場札所標かも)、弘法大師&興教大師碑などがあります。
弘法大師&興教大師碑は、横書きの山号碑の上に弘法大師碑と興教大師碑が置かれためずらしい形状で、新義真言宗寺院ならではのものです。

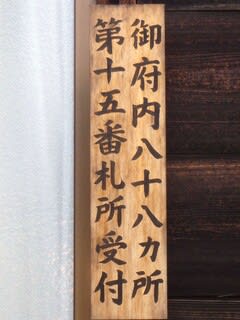
【写真 上(左)】 弘法大師&興教大師碑
【写真 下(右)】 札所受付板
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

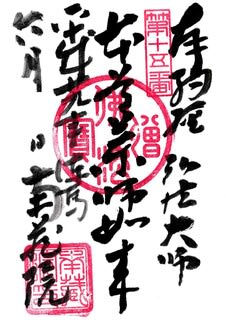
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 薬師如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右上に「第十五番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
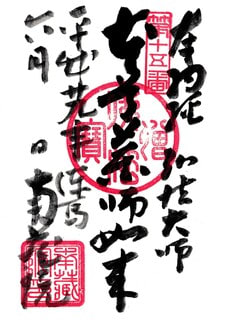
以下、つづきます。
(→ Vol.5)
【 BGM 】
■Far On The Water - Kalafina
■ I Will Be There with You ~日本語版~ - 杏里
■ 空に近い週末 - 今井美樹
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
第13番は通常、高野山 弘法寺 龍生院(港区三田)がリストされますが、和光山 興源院 大龍寺(北区田端)も第13番として札所対応をされています。
■ 第13番-1 三田高野山 弘法寺 龍生院 (大本山 弘法寺)
(りゅうしょういん/こうぼうじ)
公式Web
港区三田2-12-5
真言宗系単立?/旧高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
他札所:
司元別当:
授与所:寺務所
『ルートガイド』によると、元は高野山山内寺院のひとつで、弘仁七年(816年)弘法大師が高野山開創の際、声明(しょうみょう)の道場として建立された系譜を継ぐとされています。
明治24年(ないし23年)に三田の現在地に移転といいます。
江戸八十八ヶ所霊場第13番は「医王山 円覚寺(霊岸島白金町)」とあり、江戸期は円覚寺(圓覚寺)が御府内霊場第13番札所であったとみられます。
霊岸島の圓覚寺については『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに記載が見当たりませんが、『江戸名所図会 7巻 [2]』、『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [1]』に記載がみられます。
【史料】
■ 『江戸名所図会 7巻 [2]』(国立国会図書館)
薬師堂
霊巌島銀町にあり 別当ハ真言宗● 医王山圓覚寺と号す 本尊ハ三州鳳来寺峯の薬師と同木同作にして 理趣仙人●●をと称へ 大宝年間(701-704年)に造立ありしと●り 座像御丈三尺あり 鳳来寺薬師と称し又ハ橋本薬師とも称せり 此霊像ハ(もともと?)高野山橋本の里にありしを 慶長年間(1596-1615年)当寺の開基恵生阿闍梨此地にうつしたてまつり 後霊巌寺の境内に安す 深川霊巌寺のことなり 仮寺始此地にあり 萬治(1658-1661年)の後 霊巌寺深川にうつる其頃 此薬師堂と此地にあり 稲荷の社の● 此地に残し(以下略)
橋本稲荷社
同境内にあり 此所の鎮守と● 社記云神像ハ弘法大師の作にして 御丈一尺二寸あり 山城國伏見稲荷明神と同木同作なりといへり 往古高野山の麓橋本の里に宮居を造●安置ありし故ありて後 ここに勧請なしたてまつるとなり
■ 『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [1]』(同上)
橋本稲荷社 別当醫王山圓覚院 三州鳳来寺峯薬師同作の薬師あり よって医王山といふ
-------------------------
ふたつの史料によると、医王山圓覚寺は橋本稲荷社の別当で、御本尊は三河鳳来寺の薬師如来と同木同作の霊像とあり、鳳来寺薬師、橋本薬師とも称したといいます。
「Wikipedia」、「(一社)奥三河観光協議会」Webによると、三河の煙巌山鳳来寺は標高695mの鳳来寺山の中腹にあり、大宝二年(702年)利修仙人により開山といいます。
利修仙人は杉の霊木から御本尊・薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将、四天王を彫刻されこの地に奉安と伝わります。
時の文武帝がご病気になられた時、利修仙人に病気平癒祈願の勅使を使わされました。
仙人は鳳凰に乗って都にのぼり、七日間(十七日間とも)の加持祈祷によって帝は快癒されたといいます。
この御礼として伽藍を建立され、鳳凰に乗って参内ということで「鳳来寺」の名を賜ったのが寺号の由来とされています。
弘法大師による真言宗の開宗は弘仁十四年(823年)の嵯峨天皇からの教王護国寺勅賜とされるので、大宝二年(702年)の利修仙人による鳳来寺開山はこれより前です。
しかし、利修仙人の教義の系譜は真言宗五智教団として承継されました。
中世には源頼朝公により再興とも伝わり、江戸時代、とくに家光公の治世に栄えたといいます。
これは家康公の生母・於大の方が当山に参籠し、家康公を授けられたというゆかりによるものといい、実際、慶安四年(1651年)にはこの地に新たに東照宮が造営されています。
『東海道名所図会』には「煙厳山鳳来寺勝岳院(神祖宮 鎮守三社権現 六所護法神 開基利修仙人堂 常行堂三層塔 鏡堂 八幡宮 伊勢両太神宮 弁才天祠 天神祠 毘沙門堂 一王子 二王子 荒神祠 弘法大師堂 元三大師堂・・・」とあり、真言、天台両宗並び立つ神仏混淆の一大霊場であったことがわかります。
明治に入り鳳来寺と東照宮が分離されて鳳来寺は衰勢となり、明治38年、高野山金剛峯寺の特命を受け京都法輪寺から派遣された服部賢成住職に当山の再建が託されました。
宗派は真言宗に統一されて高野山の所属となり、寺院存続が図られたものの大正3年の伽藍焼失などで諸坊を失い、いまは松高院と医王院の二院の堂宇を残すのみといいます。(本堂は昭和49年に再建?)
以上ながながと鳳来寺について追ってみましたが、ここでわかったのは鳳来寺(真言宗五智教団)と高野山金剛峯寺(高野山真言宗)との関係のふかさです。
「中央区観光協会特派員ブログ」には、かつて霊岸島には ”七不思議” なるものがあって、その参は「円覚寺にある薬師は、宵薬師のため縁日の 8日・12日には参詣者がいない」とあります。
また、「(円覚寺は)明治になって火災に遭い廃寺になった」とも。
圓覚寺は明治に入って廃寺となったという情報は、複数のWeb記事で確認できるのでこれは事実だと思われます。
一方、『ルートガイド』には「元は高野山の山内子院の一つで、弘仁7年(816年)、弘法大師が高野山御開創の際、声明の道場として建立されたことが由来」とあります。
また、下記の『芝區誌』の記述を考えあわせると、高野山の声明の道場を草創とし、明治23年に中興開山とされる渡邊貞浄法尼が現在地に遷されるととともに、明治になって火災に遭い廃寺となっていた霊岸島の圓覚寺を承継し、御府内霊場第13番となったものとみられます。
【史料】
■ 『芝區誌_15』のP.70(デジタル版 港区のあゆみ)
龍生院 三田一丁目二十六番地 古義真言宗、往古の開山は不詳であるが、明治二十三年頃本寺中興の開山と謂はれる渡邊貞浄法尼が、今の地に一寺を建立して現在に至る。境内の西北隅に渡邊綱の産生湯の水を汲んだと傳へられる古井戸がある。元本堂の東南隅に、綱の社と云ふ稲荷神社があつたが、今は無い。
「声明とは、一般に僧侶がお経に旋律をつけて唱えるもので、密教儀礼の中で用いられる声楽の名称です。」「声明は高度に体系化された声楽である。声明には音階や表現技法、楽譜までもが存在し、それぞれ細かくルールが決められています。」(高野山真言宗総本山金剛峯寺Webより)
高野山金剛峯寺を中心とした声明(しょうみょう)は一般に「南山進流」(なんざんしんりゅう)と称され、儀礼の進行の際などに唱えられているそうです。
当山の前身?の高野山の声明道場(子院?)は、南山進流だった可能性があります。
■ 高野山南山進流聲明「心略梵語」 声明独唱 松島龍戒
-------------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 入口


【写真 上(左)】 以前の入口
【写真 下(右)】 札所標
三田の慶應義塾大学のすぐ北隣、桜田通りから参道に入りますが、奥まっているのであたりは住宅メインの落ち着いた雰囲気。
桜田通りからすでにモダンな白亜の本堂が見えています。
山内入口に「御府内八十八ヶ所 弘法大師 第拾三番」の札所標。
門柱には三田高野山 弘法寺の山号寺号。
ガイドなどでは「龍生院」と紹介されていますが、「弘法寺」が前面に出ているのでいささかわかりにくいかも。
先日、令和五年六月十五日の弘法大師御生誕一二五0年当日の記念法要時には五色の吹き流しが掲げられていました。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 エントランス
以前は木造建築でしたがモダンな伽藍に建て替えられて平成26年竣工。
改築後は主に「弘法寺」の寺号を使われているようです。
本堂入口上部に「弘法寺」の寺号扁額。
入って左手には「空海 消えずの火」が灯り、その上に立像の不動明王。
この火は、弘法大師が唐より帰朝後宮島に渡り弥山にて修行なされ、大同元年(806年)開基されたという宮島弥山の大聖院から採火されたもの。
本堂で護持され、毎日採火され1階に灯されるそうです。
大聖院は真言宗御室派の大本山。当山は現在真言宗系単立となっている模様で、宗派を越えて採火・護持されているのかも。
(公式Webには「大聖院と法縁関係にある弘法寺」とあります。)


【写真 上(左)】 エントランスの扁額
【写真 下(右)】 「消えずの火」と不動明王
入って正面はホテルのフロントのような瀟洒なかまえ。
声をお掛けすると3階の本堂にお参りするよう案内をいただくので、先にこちらで御朱印帳をお預けした方がいいかもしれません。
エレベーターで3階へ。
本堂は正面に金剛界大日如来と左右に両界曼荼羅。
向かって右手に弘法大師、左に坐像の不動明王が御座され、その前には護摩壇。
ビル内ながら真言密寺らしい荘厳な空間で、音響がよく、読経の声がよく響きます。
御朱印はフロント?にて拝受でき、ご対応はたいへんに丁寧です。
御府内霊場の御朱印の尊格は以前は弘法大師でしたが、Web情報によると現在は大日如来になっている模様。
弘法大師御生誕一二五0年のお参り時には、記念の限定切り絵御朱印が授与されていました。
筆者はふつう限定御朱印や切り絵御朱印は拝受しませんが、弘法大師御生誕一二五0年記念御朱印、しかも稚児大師と修行大師の御影入りの御朱印とあってはさすがに話は別で、ありがたく拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
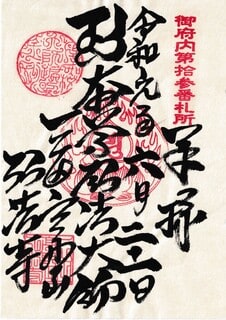

【写真 上(左)】 専用集印帳(令和元年)
【写真 下(右)】 専用集印帳(令和5年)

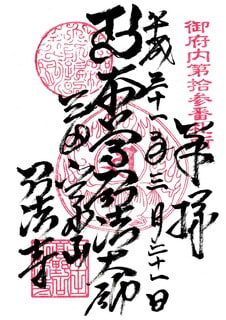
【写真 上(左)】 汎用御朱印帳(平成28年)
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(平成31年)
主印は弘法大師のお種子「ユ」(蓮華座+火焔宝珠)。右上に弘法大師の御印?。
揮毫は「本尊 弘法大師」で右上に「御府内霊場第拾三番札所」の札所印。左下には山号寺号揮毫と寺院印が捺されています。
※ 御府内霊場の御朱印尊格は以前は弘法大師でしたが、現在は大日如来となっている模様です。
令和5年8月拝受の御朱印の主印は弘法大師のお種子「ユ」(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。
揮毫は金剛界大日如来のお種子「バン」「大日如来」で右上に「御府内霊場第拾三番札所」の札所印。左下には山号寺号揮毫と寺院印が捺されています。
※平成28年6月拝受の御朱印はミニ御朱印的なサイズで、龍生院の揮毫と寺院印があります。
〔 弘法大師御生誕一二五0年記念御朱印 〕
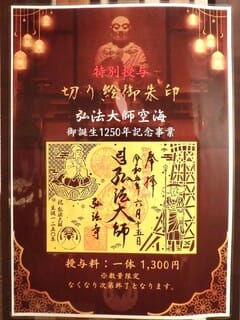

【写真 上(左)】 リーフレット
【写真 下(右)】 記念御朱印
当山内には渡邊綱の産湯の水を汲んだと伝えられる古井戸があります。
当山の北側を東西に走る坂は「綱の手引坂」と呼ばれ、渡辺綱(羅生門の鬼退治で有名な、平安時代の勇士源頼光の四天王の一人)がこの付近に生まれたという伝説によるとのこと。(「港区観光協会Web」)


【写真 上(左)】 産湯の井戸
【写真 下(右)】 井戸の碑
■ 第13番-2 和光山 興源院 大龍寺
(だいりゅうじ)
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第21番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第17番、滝野川寺院めぐり第6番
司元別当:(上田端)八幡神社
授与所:寺務所
真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺は、東京・豊島エリアの「豊島八十八ヶ所霊場」第21番の札所です。
こちらはWeb上で「弘法大師 十三番」の札所印の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
御府内八十八箇所は、番外・掛所などの札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院(弘法寺)がリストされています。
御府内霊場第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺とされ、明治初期に龍生院に引き継がれたとされていて大龍寺との関連は不詳です。
そこで「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」に注目してみました。
「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」は江戸期に開創とみられる弘法大師霊場で、『東都歳時記』に「弘法大師 二十一ヶ所」として記載があります。
同書に「未詳 湯嶋霊雲寺に弘法大師(読取不可)廿壱番とあり」とあり、謎の多い霊場ともされてきましたが、寛政二年(1790年)開版の『弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木』が発見され、実在が確定しています。
台東区のWeb史料には「この巡礼については、江戸時代の文献史料がほぼ皆無でしたので、発生年代、巡礼する寺院などはほとんど明らかでありませんでした。本版木は、寛政2年(1790)に碩峯という僧侶が開版したもので、巡礼寺院・所在地・御詠歌を紹介しています。寺院は谷中・下谷・浅草・本所・湯島に散在しますが、21ヶ寺のうち18ヶ寺が現在の台東区内です。」とあります。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
こちらをみると、ほとんどが新義真言宗系・真言宗霊雲寺派(天台宗1)で、古義真言宗寺院はありません。
ふたつの真言宗霊雲寺派は湯嶋霊雲寺(結願)と大龍寺で、湯嶋霊雲寺のみの御府内霊場より札所数が多くなっています。
ふつう、弘法大師二十一ヶ所は弘法大師八十八ヶ所の簡易版で、札所が重複するケースが多いですが、御府内二十一ヶ所霊場では21札所のうち7のみ(谷中観音寺、谷中加納院、谷中明王院、谷中長久院、谷中多宝院、谷中自性院、湯嶋霊雲寺)で重複はすくなく、御府内霊場とは別の観点から開創されたものかもしれません。
いずれにしても、すくなくとも大龍寺は豊島八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所霊場のふたつの弘法大師霊場札所なので、大師霊場とゆかりのふかい寺院であることは間違いないと思います。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国立国会図書館DC)。
「眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ、天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置 八幡社 村ノ鎮守トス 稲荷社」
創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興され、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。
『新編武蔵風土記稿』によると、江戸期は(上田端)八幡神社の別当を司っていたようです。

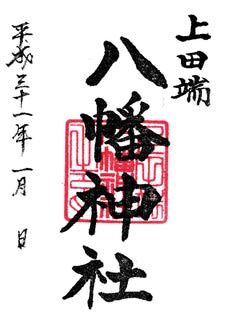
【写真 上(左)】 (上田端)八幡神社
【写真 下(右)】 (上田端)八幡神社の御朱印
-------------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れたご対応です。
拝受者が少ない滝野川寺院めぐりの御朱印申告についても、特段驚かれた風はありませんでした。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
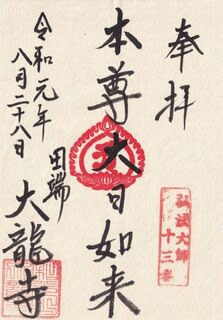
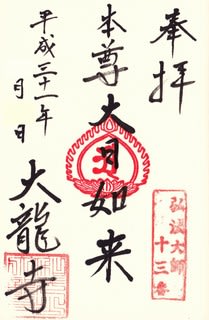
>
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右下に「弘法大師 十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 滝野川寺院めぐりの御朱印 〕

■ 第14番 白鷺山 正幡寺 福蔵院
(ふくぞういん)
中野区白鷺1-31-5
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第14番
司元別当:鷺宮八幡神社
授与所:庫裡
御府内霊場は第14番から第18番まで御府内を離れて郊外を回ります。
いずれも雰囲気のある名刹です。
文亀・永正年間(1501-1521年)、頼珍(大永元年(1521年)示寂)によって開山され、下鷺ノ宮村の鷺宮大明神(八幡社)の別当寺でした。
宝暦十二年(1762年)堂宇を焼失し寺伝詳細は伝わっておりません。
江戸八十八ヶ所霊場の札所でもあるので、当初からの札所とも思われますが、府外の当山が御府内霊場札所に指定された経緯はうかがい知れません。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(上鷺ノ宮村)
白鷺山正幡寺ト号ス 前ノ八幡(現・鷺宮八幡神社)ノ別当ナリ 則其御朱印地ノ内ニアリ 新義真言宗ニテ当郡中野村寶仙寺ノ末 開山ヲ頼珍ト云 大永元年(1521年)五月示寂 第九世ヲ鏡薫ト云 慶安二年(1649年)八月寂セリ 此僧ノトキ八幡ノ御朱印ヲ賜ヒシヨシ カヽル功アルニヨリ中興トス サレハ当寺ノ開基ハ文亀・永正ノ頃ナルヘシ 宝暦十二年(1762年)十二月丙丁ノ災ニカヽリテ 堂宇残ラス焼失セシカハ詳ナルコトヲ傳へス 今ノ客殿ハ其後造リシモノナリ(略) 本尊不動ノ坐像長二尺 二童子モ長二尺許 運慶ノ作ト云、又ハ智證大師ノ作トモ云傳フ
別当を司った八幡社(現・鷺宮八幡神社)は上下鷺ノ宮村の鎮守で、本地として十一面観世音菩薩を祀っていました。


【写真 上(左)】 鷺宮八幡神社
【写真 下(右)】 鷺宮八幡神社の御朱印
-------------------------
西武新宿線「鷺ノ宮」駅のすぐ南。妙正寺川の流れを北に押し上げる高みに鷺宮八幡神社と隣接してあります。
駅そばですが駐車場もあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 弘法大師碑と地蔵尊


【写真 上(左)】 意匠の効いた土塀
【写真 下(右)】 馬頭観世音菩薩
山内入口右手に弘法大師碑と2体の地蔵尊。
ここから山門に向かって意匠の効いた土塀が伸びています。
植木が綺麗に刈り込まれ、参道には木の葉ひとつ置ちておらず、手入れの行き届いたお寺さまであることがわかります。
参道途中に院号標と整った像容の馬頭観世音菩薩。


【写真 上(左)】 寺号標と参道
【写真 下(右)】 山門
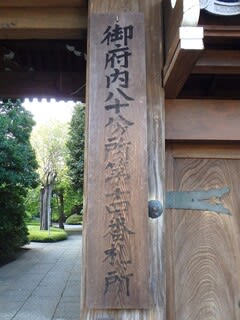

【写真 上(左)】 山門の札所板
【写真 下(右)】 山門扁額
山門は切妻屋根銅板葺の薬医門で左右に板塀を延べています。
見上げに山院号扁額、門柱には御府内霊場の札所板。


【写真 上(左)】 緑濃い山内
【写真 下(右)】 十三佛
山門をくぐると右手覆屋内に石佛の十三佛。案内板によると石佛で十三体そろったものは都内でもめずらしいそうです。
緑濃く手入れの行き届いた山内には、石佛、六地蔵、子育地蔵尊、そして修行大師像などが安置されています。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 修行大師と子育地蔵尊


【写真 上(左)】 手入れの行き届いた山内
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造金属板葺流れ向拝、屋根中央に置かれているのは太陽光パネルでしょうか。
昭和35年の落慶とのことですが、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備え、伝統的に整った寺院建築です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝開き戸の上に豪快な筆致の山号扁額が掲げられ、軒には不動明王の奉納額も掛けられています。


【写真 上(左)】 奉納額
【写真 下(右)】 庫裡
都内の駅そばとは思えない雰囲気のある山内で、落ち着いた参拝ができました。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。
手入れの行き届いた山内から予想されるとおり、たいへんご親切なご対応をいただきました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

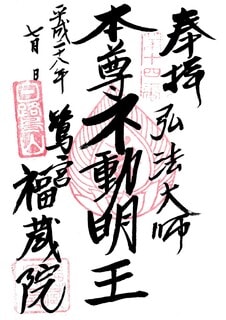
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は不動明王のお種子「カン/カーン」(蓮華座+火焔宝珠)。揮毫は「本尊 不動明王」「弘法大師」で右上に「御府内十四番」の札所印。左上に山号印、その下には院号揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第15番 瑠璃光山 医王寺 南蔵院
(なんぞういん)
練馬区中村1-15-1
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第15番、江戸八十八ヶ所霊場第15番
司元別当:(中村)八幡宮ほか
授与所:庫裡
御府内霊場には南蔵院と号する札所が練馬(第15番)、牛込(第22番)と高田(第29番)の3箇寺あり、それぞれ練馬南蔵院、牛込南蔵院、高田南蔵院と呼んで区別されます。
第15番の練馬南蔵院は、御府内からいささか離れるものの江戸八十八ヶ所霊場と同番で、御府内からの移転記録もないことから当初からの御府内霊場札所とみられます。
練馬辺りは豊島八十八ヶ所の巡拝エリアでもあり、当山も御府内霊場、豊島霊場というふたつの弘法大師霊場の兼務札所となっています。
現地掲示、『ルートガイド』および『新編武蔵風土記稿』によると、延文二年(1357年)(永正年中(1504-1521年)とも)、僧良辨の中興といいます。
良辨は諸国の霊場へ法華妙典を納めた後に当寺に錫をとどめ、妙経を埋めて「良辨塚」を建立してなおも修行をつづけると、ある日薬師の像を感得しました。
良辨は堂宇を建立してこの薬師像を奉安し、いまの御本尊になったといいます。
秘佛で33年に一度の御開扉。
当寺で出していた「白龍丸」という薬は良辨が夢中で感得した霊法の薬丸で万病に効くとされ、「南蔵院の投込み」と称して全国に広まりましたが、明治10年の法制定を受けて販売は中止となりました。
当山は元(中村)八幡宮の別当で、末寺の西光寺(廃寺)はこのそばにあったといいます。

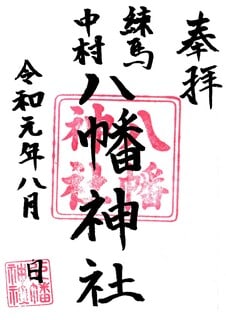
【写真 上(左)】 (中村)八幡神社
【写真 下(右)】 (中村)八幡神社の御朱印
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(中村)
南蔵院 新義真言宗 上練馬村愛染院末 瑠璃山醫王寺ト称ス(略)永正年中(1504-1521年)僧良辨(良弁僧正トハ異ナリ) 諸国ノ霊場ヘ法華妙典ヲ納メ志願畢リテ後 当寺ニ錫ヲトヽメ妙経ヲ理テ一箇ノ塚トス 今村ノ中程ニ良辨塚ト称スルモノ是ナリ 然シテヨリ此寺ニアリテ修法怠ラサリシカハ 其功空シカラサルニヤ 或日薬師ノ像ヲ感得セリ ヨリテ堂宇ヲ興隆シ其像ヲ安置スト云 今ノ本尊是ナリ 秘仏トシ三十三年ニ一度龕ヲ開テ拝セシム 又当寺ヨリ白龍丸ト云薬ヲ出セリ 曽テ良辨カ夢中感得セル霊法ノ薬丸ナリ
諸病ニ験アリト云 稲荷社 閻魔堂
西光寺 紫雲山阿彌陀院ト号ス 本尊阿彌陀 大日堂 南蔵院持
良辨塚 前(南蔵院の項)ニ云 経典ヲ埋メシ塚ナリ 古碑一基タテリ モトヨリ其頃立シモノトハ思ハレス 年月モ彫ラス
(中村)八幡宮 (中)村ノ鎮守ナリ 南蔵院持 下持同シ 稲荷社、大神社、辨天社、水神社、三峰社、金毘羅社
-------------------------
最寄りは都営大江戸線・西武池袋線「練馬」駅。
練馬の落ち着いた住宅地のなかに、かなりの広さを保ってあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道入口の対燈籠
東側の南蔵院通りに立派な門柱とその先に銅燈籠一対と右手に慈母観音立像。
その先に参道がながながとつづき、緑ゆたかな山内はとても練馬の住宅地とは思えません。


【写真 上(左)】 緑ゆたかな山内
【写真 下(右)】 手前から庫裡、本堂、薬師堂
しばらく進むと右手に本堂が見えてきます。
本堂向かって右手に庫裡、左手に薬師堂を配して堂々たる構え。


【写真 上(左)】 本堂参道
【写真 下(右)】 本堂と銅燈籠


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 本堂
本堂前に進むと左手に修行大師像。
本堂前の大ぶりで精緻な彫刻の銅燈籠が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は入母屋造桟瓦葺で間数が多く、濃茶色の格子扉、小壁下の菱格子が引き締まった印象。
向拝見上げには山号扁額。
柱のないすっきりとした向拝は、密寺というより禅刹的なイメージがあります。


【写真 上(左)】 薬師堂
【写真 下(右)】 斜めからの薬師堂
薬師堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻と見上げに「薬師堂」の扁額を掲げています。
当山の御本尊は秘佛の薬師如来。
本堂と薬師堂があるので、本堂と薬師堂にそれぞれ薬師如来が御座すか、本堂には宗派本尊の大日如来あるいは別尊が奉安され、薬師堂の薬師如来が御本尊とされているかのいずれかと思いますが、よくわかりません。
ちなみに、豊島霊場の御朱印尊格も薬師如来となっているお薬師さまのお寺です。


【写真 上(左)】 薬師堂の向拝
【写真 下(右)】 薬師堂の扁額


【写真 上(左)】 弘法大師碑
【写真 下(右)】 閻魔堂
山内西側には閻魔堂。
『新編武蔵風土記稿』に記載されている閻魔堂の流れと思われ、堂内には閻魔大王と十王像が御座されています。
その南側に赤門と鐘楼門。
薬師堂、閻魔堂、鐘楼門などは宝暦三年(1753年)建立とされ、とくに鐘楼門は「江戸時代中期の建築と考えられる区内唯一の鐘楼門」(区資料)とされ練馬区の指定文化財です。


【写真 上(左)】 鐘楼門
【写真 下(右)】 赤門
赤門と鐘楼門の向きが直角で、赤門は脇門用途ではなさそうです。
鐘楼門は入母屋屋根桟瓦葺朱塗りの三間一戸の八脚門で、脇間に迫力の仁王尊像、上層に鐘をおき、端正な垂木が目につきます。
赤門は切妻屋根瓦葺。朱塗りで本柱と控柱各二本を備えた様式は医薬門でしょうか。
山内南側に祠が二棟御鎮座で、一棟は弁財天尊のような気がします。
もうひとつは扁額がないのでよくわかりませんが、『新編武蔵風土記稿』にある稲荷神かもしれません。


【写真 上(左)】 首継地蔵尊
【写真 下(右)】 聖観世音菩薩像
その左手には首継(つぎ)地蔵尊。
もともとは末寺の西光院(廃寺・現中村八幡神社の社裏)に奉安とされますが、現在は南蔵院に遷られています。
かつて首のない地蔵尊と地蔵尊の首が別々に村人によって奉安されており、二人の村人の夢告が一致して首と胴体をあわせたところぴったりと収まったため、二体を継いで「首継(つぎ)地蔵尊」としたと伝わります。
昭和初期の不況期には「首切り」を遁れようと願う多くの参拝者で賑わったそうです。
首継地蔵尊の右脇に笠付角柱型のめずらしい聖観世音菩薩像がありますが、こちらも西光院から遷られたお像のようです。


【写真 上(左)】 長屋門
【写真 下(右)】 練馬消防団の施設
その左手には長屋門。山内南側にある唯一の門です。
その左にある分校のような雰囲気ある建物は、現在は練馬消防団の施設となっているようです。
山内には弘法大師碑(御府内霊場札所標かも)、弘法大師&興教大師碑などがあります。
弘法大師&興教大師碑は、横書きの山号碑の上に弘法大師碑と興教大師碑が置かれためずらしい形状で、新義真言宗寺院ならではのものです。

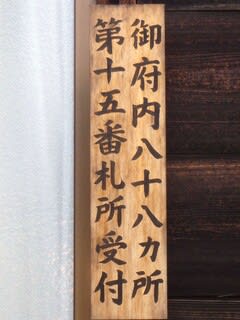
【写真 上(左)】 弘法大師&興教大師碑
【写真 下(右)】 札所受付板
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

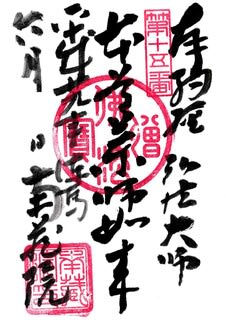
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 薬師如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右上に「第十五番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
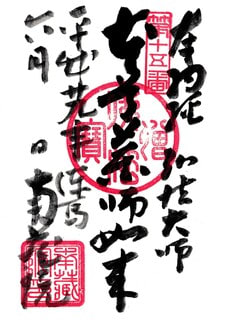
以下、つづきます。
(→ Vol.5)
【 BGM 】
■Far On The Water - Kalafina
■ I Will Be There with You ~日本語版~ - 杏里
■ 空に近い週末 - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-3
Vol.-2からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第9番 古碧山 龍厳寺
(りゅうげんじ)
渋谷区神宮前2-3-8
臨済宗南禅寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:
司元別当:(青山熊野権現/旧 浄性院)
授与所:庫裡
御府内霊場中、唯一の非真言宗寺院の禅刹(臨済宗南禅寺派)です。
『ルートガイド』には「弘法大師が関東を巡った際に開創され、かつては真言宗の寺院であったと伝わります。開創時の札所は青山熊野神社の別当・状(ママ)性院でしたが、明治七年の神仏分離で廃寺となり、弘法大師開創の伝承を有することから、龍厳寺が札所を引き継いだといわれています。」とあります。
たしかに江戸八十八ヶ所霊場第9番は「三光山 宝厳寺 浄性院(港区青山)」とあり、江戸期は浄性院が御府内霊場第9番札所であったとみられます。
旧9番浄性院は真言宗寺院で、新9番龍厳寺は臨済宗南禅寺派。
第9番が旧番のまま真言宗であれば御府内霊場の札所はすべて真言宗寺院で完結するのに、あえて新第9番を臨済宗南禅寺派とした理由があったのでしょうか。
まずは青山熊野権現元別当の浄性院から当たってみました。
『江戸名所図会』7巻 [8]の熊野権現社の項には「熊野権現社(略)南紀の熊野権現と同じく三社あり 青山の鎮守(略)別当ハ真言宗浄性院と号す」とあります。


【写真 上(左)】 (青山)熊野神社
【写真 下(右)】 (青山)熊野神社の御朱印
『寺社書上』(国立国会図書館)にも浄性院が収録されています。
熊野社と錯綜気味ですが、浄性院(寺院)に関連するとみられる記述を書き出します。
----------
本寺京知積院末 武州豊嶋郡原宿村 熊野権現別当 三光山 真(ママ)義真言宗 浄性院
開山法印清範明暦二年(1656年)寂 中興法印快圓宝暦十二年(1762年)寂
五百羅漢 十六善神 不動尊 愛染尊
本地堂 熊野三社本地 (中)十一面千手観音 (右)薬師如来 (左)彌陀如来
金胎大日如来 石洞稲荷社 聖天堂本尊歓喜天 同本地十一面観世音
(相殿)江州浅井郡竹生島 本尊弁才天(旅宿社?) 訶梨帝母立像
護摩堂 本尊不動尊立像 厨子入不動尊坐像 愛染明王坐像 如意輪観音坐像 弘法大師坐像 右勧請●立年月不知
延享二年(1745年)二月十二日社殿●不残焼失仕 安永八年(1779年)正月十●日自火●亦ハ焼失 不知●記縁●●焼失仕寺記並開基亦●由来相不知
----------
『寺社書上』によると浄性院は京知積院末の新義真言宗で開山は法印清範(明暦二年(1656年)寂)。
浄性院(相殿)の弁才天は、江州浅井郡竹生島ゆかりのようです。
琵琶湖の竹生島は弁才天の聖地で、竹生島弁才天は江島(与願寺)・ 厳島(大願寺)とならんで「日本三大弁天」のひとつに数えられます。
竹生島にある巌金山 宝厳寺は真言宗豊山派で御本尊は大弁才天。
観音堂は西国三十三所第30番札所となっています。
宝厳寺の公式Webには「弘法大師なども来島、修業されたと伝えられています。」とあり、弘法大師の「御請来目録」を所蔵されています。
「御請来目録」は「(弘法大師)空海が唐から請来した新旧訳経、梵字真言、論疏章、曼荼羅、道具などの目録」(国立情報学研究所)で、日本密教上きわめて重要な文献です。
「御請来目録」には3つの写本があるとされます。
施福寺(大阪府和泉市槙尾山町)の「施本」、東寺所蔵の「東寺本」、そして竹生島宝厳寺所蔵の「竹生島本」です。
(参考:「『御請来目録』の書誌学的研究(甲田宥吽氏/PDF)」
「施本」は「請来目録上表草稿」ともいわれる請来目録残巻で、ほぼ弘法大師の御眞蹟と断定されていますが、「東寺本」、「竹生島本」が御眞蹟であるかについては、従前から数々の議論がなされ未だ結論を得ていない模様です。
ただし、「弘法大師御請来目録の原本について」(眞保龍敞氏/PDF)によると、宝厳寺所蔵の「弘法大師御請来目録」(竹生島本)は「(弘法大師)空海によって上表された原本に相違ない、と考えられる」とされています。
また、筆者は「竹生島本」と他の弘法大師御眞蹟とで精緻な比較をされた結果、「竹生島本は、筆蹟の上からも空海自筆たる特徴を充分に具え、弘法大師の御眞蹟と認定し得るもの」とされています。
つまり竹生島宝厳寺は弘法大師御眞蹟の「御請来目録」を所蔵されている可能性があり、浄性院の弁才天はこの竹生島(宝厳寺)弁才天系なので、この流れから浄性院と弘法大師霊場(御府内霊場)のつながりが出てきたのかもしれません。
一方、護摩堂の不動尊は「目黄不動尊」として信仰を集めたといい、「江戸五色不動」の一尊に数えられることもあったようです。(ご参考→「江戸五色不動の御朱印」 )
護摩堂には弘法大師坐像が御座され、山内に祀られる聖天様、愛染明王、稲荷神はいずれも真言宗寺院で多く祀られる尊格で、浄性院が保守本流の真言宗寺院であったことを裏付け、弘法大師霊場(御府内霊場)としての資格を充分に備えていたことがうかがえます。
(『江戸名所図会』の絵図には、はっきりと「弘法大師 不動 あいせん」と載っています。)
龍厳寺の参拝時、本堂の御本尊と大師堂を礼拝した記憶があり、たしかこの「目黄不動尊」は大師堂内の御座だったかと思います。
となると、浄性院ゆかりの尊格は龍厳寺の大師堂に奉安されている可能性もあります。
御府内霊場の御朱印には「黄金目不動明王」の揮毫があるので、浄性院の「目黄不動尊」つながりで御府内霊場の札所となったのかもしれません。
また、たしか龍厳寺の大師堂前には宇賀神系の弁財天石仏が御座していました。
もともとの龍岩寺の地主ノ神である辨天様か、浄性院からの竹生島(宝厳寺)系弁才天かはわかりませんが、大師堂前御座から考えると後者かもしれません。
いずれにしても、青山熊野権現は『江戸名所図会』に載るほどの名所。
そしてその祭礼の華やかさは有名で、「青山に過ぎたるものが二つあり 鳶の薬缶に原宿の山車」という俗謡が伝わります。
浄性院はその著名な熊野権現の別当。その点からも弘法大師霊場の資格をもっていたかと思われます。
*********
つづいて龍岩寺(龍厳寺)です。
臨済宗で本寺は多磨郡由井領山田村(現八王子)の兜率山廣園寺。
当初は名主半右衛門の屋敷の鎮守に辨天社があり、そばに小庵を建て喚室という僧を招聘し、慶長七年(1602年)に喚室を開山として創建といいます。
「やさしいお坊さん」Web(LDT株式会社)によると、喚室(峻翁令山禅師)は、武蔵國秩父郡出身で寂後に勅号(天皇よりの法名命名)を賜り法光円明国師と呼ばれた名僧で、本山兜率山廣園寺、児玉郡威音山光厳寺、深谷常興山國済寺などを開山されたといいます。
原宿村の一名主がこれほどの高僧を自邸の一庵に招聘できたのは不可思議で、『寺社書上』には「鐘銘ニ拠ハ(家康公)御入國(天正十八年(1590年))以前ヨリノ寺ナリト載ス」ともありますが、2度にわたる火災で寺伝を焼失し詳細は不明のようです。
御本尊は釈迦如来。
境内に祀る弁天社は「地主ノ神」といい、もともとの半右衛門屋敷の鎮守神とみられます。
以上をみても龍岩寺に密寺色はうすく、むしろ純然たる禅刹のイメージがあります。
【史料】
■ 『寺社書上』(国立国会図書館)
武州八王山田廣園寺末 禅宗臨済派 古碧山龍岩寺
開闢 慶長(1596-1615年)トモ●傳 開山 喚室和尚元和八年(1622年)遷化 中興開山 青山和尚宝永八年(1711年)遷化 開基 相知不申候 中興開基 元禄五年(1692年)死去 俗名山崎半右エ門 当村名主作太郎先祖也
本尊 釈迦如来 脇立 文殊 菩薩
■ 『新編武蔵風土記稿』(同上)
龍岩寺 禅宗臨済派古碧山ト号ス 多磨郡由井領山田村廣園寺末 本尊釋迦 脇士文殊 普賢ヲ安ス 相傳フ 境内昔ハ名主半右衛門カ屋敷ニテ鎮守辨天社アリ 側ニ小庵ヲ建テ喚室ト云僧ヲシテ住セシメシカ 慶長七年(1602年)遂ニ宅ヲ捨テ寺トス 依テ喚室ヲ開山トスト寺傳ニイヘリ 鐘銘ニ拠ハ 御入國以前ヨリノ寺ナリト載ス 何レカ是ナルヤ喚室ハ元和八年(1622年)寂ス
辨天社 地主ノ神ナリ
天満宮 往古ハ木立像ナリシト(略)源義家此所ニテ出陣ノ連句ヲ催シ社前ニ納ム 依テ句寄ノ天神ト号スト 稲荷ヲ合祀セリ
日吉山王社 (略)往古ハ当村千駄谷村境榎樹ノ下ニ勧請アリシヲ 寛永中(1624-1644年)当寺第三世明叟ノ時ココニ移スト云
圓座松 砌下ニアリ囲モ四尺許 根上一尺許ヲ隔テ四方ヘ蟠延ス 大サ東西七間餘南北六間半 其状圓坐ヲ敷タル如クナレハ此名アリ
*********
とまぁ、いろいろ調べてみましたが、どうして廃寺後の浄性院の寺跡が、札所も含めて臨済宗の龍厳寺に引き継がれたかのはっきりとした答えは見いだせませんでした。
明治七年、神仏分離を受けた浄性院の廃寺の際にはかなりの混乱があった模様なので、なにか記録に残されていない複雑な経緯があったのかもしれません。
【 龍岩寺と熊野権現社(浄性院)の位置関係 】

※ 『江戸切絵図/青山渋谷絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
ただ、ひとつ気になる事柄があります。
多摩エリアの弘法大師霊場に「多摩新四国八十八ヶ所霊場」があります。
こちらはすべての札所が真言宗寺院です。
また、「多摩新四国八十八ヶ所霊場」をベースに開創といわれる「多摩百八ヶ所霊場」の札所もすべて真言宗寺院です。
ところが「多摩新四国八十八ヶ所霊場」には番外札所があって、それが八王子の廣園寺(こうおんじ)だというのです。
公式ガイドやWeb上の札所一覧情報には載っていませんが、一部のWebに記載があり、Wikipediaにも「多摩八十八箇所番外札所」と明記されています。


【写真 上(左)】 廣圓寺
【写真 下(右)】 廣圓寺の御朱印
兜卒山廣園寺は八王子市にある臨済宗南禅寺派の寺院で、龍厳寺の本寺です。
つまり、本寺・廣園寺は番外ながら唯一禅宗で「多摩新四国八十八ヶ所霊場」の札所、末寺・龍厳寺は「御府内霊場」唯一の禅宗の札所で、本末揃って禅宗で弘法大師霊場の一画を占めていることになり、なんとなく偶然の符合とは思えないものがあります。
ただし、Webから追えたのはここまでで真相は霧のなかです。
-------------------------
最寄りは都営大江戸線「国立競技場前」駅ですが、メトロ銀座線「外苑前」駅からも歩けます。
「外苑前」駅からだと青山熊野神社の前を通り、神社から龍厳寺に向かう坂道を「勢揃坂」といいます。
現地掲示板によると、永保三年(1083年)に八幡太郎義家公が奥州征伐(後三年の役)に出陣の際、ここで軍勢を揃えたといわれ、当地の豪族渋谷氏の祖・秩父十郎武綱も参陣と伝わります。
また、龍厳寺山内の天満宮は義家公が出陣の際に連句を催し、社前に句を納めたとされ「句寄の天神」ともいうそうです。


【写真 上(左)】 勢揃坂
【写真 下(右)】 参道
國學院高のちょうど西側で、敷地じたいは外苑西通りに面していますが、山門は1本奥まった枝道からさらに入ったところにあり、神宮前とは思えない静寂に包まれています。
路地から伸びるゆったりとした石敷きの参道。
あたりは都心としては奇跡的に?高い建物がなく、陽光が降りそそいで明るいです。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山門-1
山門前に寺号標。上部には「御府内第九番御札所 弘法大師霊場」と刻まれています。
正面の山門は切屋根桟瓦葺妻の薬医門で、両脇に桟瓦葺の板塀を延べています。
主門には木柵が置かれ、右手通用門横には「檀信徒以外の出入りをお断り申す 合掌」の掲示があって一瞬ひるみますが、「御府内霊場巡拝者はたぶん信徒だよな~」と気をとりなおして通用門をくぐり山内に進みます。
(たしか通用門を開けるといきなり鈴が鳴って、これまたびびった記憶が・・・(笑))


【写真 上(左)】 山門-2
【写真 下(右)】 門外からの山内
こちらは山内の撮影禁止なので撮影はしておりませんし、山内のご案内も控えます。
草木が茂ったほの暗い山内で、堂宇も趣きがあり、とても神宮前の一画とは思えません。
山内には石佛が点在していましたが、画像がないのでよくわかりません。
従前、山内にあった「圓座の松」は江戸の名木のひとつとして知られ文化十年著の『十万庵遊歴雑記』などで取り上げられています。
御朱印は庫裡にて拝受。敷居が高く謹厳なイメージがありますが、御朱印対応はご親切でした。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は釋迦如来のお種子「バク」ではなく、なぜか阿弥陀如来・如意輪観世音菩薩のお種子「キリーク」(蓮華座+火焔宝珠)。揮毫は「本尊 釋迦牟尼佛」「弘法大師」「黄金目不動明王」で右上に「第九番」の札番揮毫。左下には寺号揮毫と寺院印が捺されています。
「釋迦牟尼佛」の御朱印は禅刹では一般的ですが、御府内霊場では唯一と思われます。
■ 第10番 観谷山 福聚院 聖輪寺
(しょうりんじ)
渋谷区千駄ヶ谷1-13-11
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第10番、東京三十三所観世音霊場第13番、近世江戸三十三観音霊場第20番、大東京百観音霊場58番
司元別当:
授与所:庫裡
御府内霊場中、もっとも歴史が古いとされる古刹です。
『観谷山聖輪寺観音略縁起/寺社書上』によると、神亀二年(725年)5月の頃、行基菩薩が北越遊行された折に当地で休息されたとき、谷の中から光りが射して如意輪観世音菩薩が出現しました。
観音様は「我はこの地に因縁あり、汝(行基菩薩)が我の相を彫刻すれば末世の衆生に結縁せしめて広く利益をなさん」と告げられて、大きな朽木のもとでお姿を消されました。
行基菩薩は感じ入り、この枯木を加持して御長三尺五寸の尊像を刻み奉り石上に安置して持念されました。
観音様は御双眼より金色の光りを放たれたため観谷山、寺号を聖輪寺として本山を開創されたと伝わります。
神亀二年(725年)開創とすると、実に千三百年もの寺歴を有することになります。
明和九年(1772年)刊の『江戸砂子温故名蹟誌』には、江戸にて千年以上の霊場は浅草寺と当寺と記されています。
御本尊は行基菩薩の御作と伝わる如意輪観世音菩薩。
山内掲示によると、この地の豪族・渋谷氏一門はこの尊像を深く信仰し、そのご利益あってか一門は栄え、人々は「黄金長者」と呼んだといいます。
天正の頃(1573年)には、御本尊が疱瘡から里人を救われ、観音様の大悲護念を謝してこのときから御本尊を閉扉し秘仏として崇め奉ったとのことです。
慶長の頃には観音像の双眼が黄金であると聞いた賊が忍び込み、玉眼を鑿で取ろうとしたところ、冥罰に当り、自らの鑿で貫かれて死んでしまいました。
人々はこれも観音様の霊験と畏れ、信仰をいっそう篤くしたと伝わります。
このときより「千駄谷観音」「目玉の観音」とも呼ばれ、近世江戸三十三観音霊場第20番の札所ともなって人々の信仰を集めました。
慶安四年(1651年)には奈良・長谷寺の末寺となり、真言宗豊山派の名刹としていまに至っています。
【史料】
■ 『寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考』
新義真言宗 紀州初瀬小池坊末 千駄ヶ谷町
起立之儀古来●当地有之候得共、年数不分明
開山 法印宥光(明暦三年(1657年)遷化)
中興 法印宥仙(元禄七年(1694年)示寂)
本尊 如意輪観音 木座像丈三尺五寸 神亀二年(725年)行基菩薩作
前立 如意輪観音 両脇立 不動毘沙門 四天王 護摩壇本尊不動 両童子 聖天
鎮守社 諏訪明神 秋葉権現 稲荷明神
大師堂 弘法大師 厨子入座像 長二尺三寸
※鎮守の稲荷明神は「庄九郎稲荷」ともいわれ、往古は村の鎮守とも伝わります。
(観谷山聖輪寺観音略縁起)
抑当寺本尊聖如意輪観世音者 行基菩薩乃御作也 神亀二年(725年)五月の頃 行基北越遊行乃時 此所に暫く休息し(略)谷乃中より光りさし如意輪観音出現しぬ 告て宣く●此地ハ我に因縁あり汝よろしく●我相を彫刻し 末世の衆生に結縁せしめて廣く利益をなさんとて 大なる朽木の本ニ失給ふ 行基感涙肝に銘し(略)其枯木を採て御衣木とし加持して御長三尺五寸の尊像を刻み奉り 石上に安置し持念したまふ 御双眼より金色乃光りを放ち●故に 本山を観谷山といひ 寺を聖輪寺と号す
(以下、山内掲示の縁起書に概要記載あり)
■ 『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [5]』(国立国会図書館)
観音 千駄ヶ谷 観谷山 聖輪寺 真言 和州長谷末
開山行基菩薩 本尊如意輪 眼玉の観音と云●り 賊来りて本尊の玉眼黄金なりとて ぬき出し(略)おのれを害して死
江府にて千余歳の霊場ハ浅草寺と当寺
【 江戸期の聖輪寺周辺 】

※ 『江戸切絵図/内藤新宿千駄ヶ谷絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載

『江戸名所図会 7巻 [9] 千駄谷観音堂』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載)
-------------------------


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 札所標
国立競技場の西側にあり、「国立競技場」駅、「千駄ヶ谷」駅、「北参道」駅の3駅から徒歩でアクセスできます。
「観音坂」と呼ばれる坂の途中に位置しています。
入口は門柱。門前には御府内霊場の札所標、門扉には真言宗の宗紋門「五三の桐」。


【写真 上(左)】 五三の桐
【写真 下(右)】 入口


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 庚申塔
山内はさほど広くはありませんが、よく手入れされて落ち着いた参拝ができます。
鐘楼堂まわりには八十八カ所踏み石参拝所が設けられています。
塀ぎわには二童子を従えた身守不動尊と六地蔵。
渋谷区教育委員会の説明書がある庚申塔、桃?を持たれたかわいいお地蔵さまも御座。


【写真 上(左)】 身守不動尊
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 地蔵尊
【写真 下(右)】 本堂
本堂は近代建築で向拝上部に山号扁額、その上に真言宗豊山派の宗紋「輪違い紋」を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
墓域には真田氏の流れで『明良洪範』を著した、甲州流の兵学者増譽法印の墓があります。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は三寶印。揮毫は「本尊 如意輪観音」「不動明王」「弘法大師」で右上に「第十番」の札所印。左下には寺号揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第11番 光明山 真言院 荘厳寺
(しょうごんじ)
渋谷区本町2-44-3
真言宗室生寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来・不動明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第11番
司元別当:(幡ヶ谷)氷川神社(渋谷区本町)
授与所:不動堂札所(授与所)
「幡ヶ谷不動尊」としても知られる真言宗室生寺派の寺院。
『新編武蔵風土記稿』によると、開山は宥悦法印(天文二年(1533年)寂)。
寺院御本尊は薬師如来ですが、御府内霊場の御朱印には不動明王も揮毫されているので、札所本尊は薬師如来・不動明王両尊と思われます。
不動明王は智証大師(円珍)が三井寺開基の際に自ら彫刻し本尊とされた尊像と伝わり、天慶二年(939年)、承平天慶の乱で藤原秀郷が戦勝を祈願して御持佛とし、戦勝ののち下野国小山郷に安置と伝わります。
三井寺から遷られた経緯については『江戸名所図会』に「(天慶年間)平貞盛、及び藤原秀郷等、東国に発向す。其時三井寺より此本尊を奉持して、陣中に移し奉り、戦の勝利を祈誓」とあり、承平天慶の乱の際に東国に遷られた旨が記されています。
永禄年中(1558-1570年)、武田信玄が甲州七覺山(右左口の七覚山円楽寺?/真言宗)に遷して崇敬し、後に北条氏政がこれを奪って相州筑井縣地勝院(相州津久井城西麓?)に奉安、天正十八年(1590年)北条氏没落の後には徳川家康以下代々の武将が崇敬して多磨郡宅部村三光院(東大和市/真言宗)に遷られ、延享四年(1747年)9月、霊夢のお告げにより当山に安置と伝わります。
このお不動様を尊崇した武将は藤原秀郷、武田信玄、北条氏政、徳川家康という錚々たる面々で、相模原市の城山地域史研究会資料には「有名武将が競って崇敬した不動明王」と記されています。
以降「幡ヶ谷不動尊」として広く信仰を集め、「江戸近郷の三不動(成田山、光明山、高幡山)の一つとして広く尊崇を集めた。」というWeb記事もみつかりました。
立地は府外ですが、開創時から御府内霊場札所であったとみられ、これは『江戸名所図会』にも載せられた著名な「幡ヶ谷不動尊」の存在が大きかったのかもしれません。
江戸期には(幡ヶ谷)氷川神社(渋谷区本町)の別当も司っていました。


【写真 上(左)】 幡ヶ谷氷川神社
【写真 下(右)】 幡ヶ谷氷川神社の御朱印
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
新義真言宗 江戸大塚護國寺末 光明山真言院ト号ス 開山宥悦 天文二年(1533年)5月15日寂 本尊薬師
不動堂 木佛立像長三尺三寸 智證大師作 縁起ニ云 智證大師三井寺開基ノ時 自此不動ヲ彫刻シテ彼寺ノ本尊トセシカ 天慶二年(939年)平貞盛 藤原秀郷等平将門追討ノ時 秀郷此不動ニ祈誓ヲコメ 陣中マテ守リ行テ渇仰怠リ無ク 果シテ勝利ヲ得タリシカハ 凱陣ノ頃下野國小山ノ郷ニ安置セリ 其後遥星霜ヲ歴テ 永禄年中(1558-1570年)武田信玄甲州七覺山ニ移シ崇敬セシヲ 北條氏政奪テ相州筑井縣地勝院ニ納ム 然ルニ天正十八年(1590年)北條氏没落ノ後 東照宮代々ノ武将崇敬アリシ像ナル事ヲ聞シ召レテ 多磨郡宅部村三光院ニ移シ給ヒ 延享四年(1747年)9月霊夢ノ告アリテ当寺ニ安置スト云 稲荷社
(幡ヶ谷村)氷川社 村ノ鎮守ナリ荘厳寺持
-------------------------


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 不動堂


【写真 上(左)】 不動堂向拝
【写真 下(右)】 「幡ヶ谷不動尊」の尊号板
場所は初台の新国立劇場の北側で最寄りも「初台」駅、山手通りから1本なかに入った住宅地にあります。
南側の「ふどう通り」は、かつて幡ヶ谷不動尊の参道であったとも。
入口に「幡ヶ谷不動 荘厳寺」の寺号標。その先の門柱の右手奥が幡ヶ谷不動堂。
堂前は催しができる広めのアスファルト敷のスペースで、著名な仏堂によくあるかたち。
入母屋造本瓦葺流れ向拝の端正な不動堂で、向拝まわりの意匠は比較的シンプルです。
向拝柱に「幡ヶ谷不動尊」「厄除不動」の掛板。向拝見上げに「不動明王」の扁額。
向かって右手に札所(授与所)があり、御朱印はたしかこちらでいただいたかと思います。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 山門
不動堂の向かって左奥、狛犬一対の先に構える山門は、切妻屋根本瓦葺で手前左右の控柱に切妻屋根が掛かっているので高麗門かと思います。
山門柱に重厚な筆致の寺号板。


【写真 上(左)】 山門の寺号板
【写真 下(右)】 馬頭観音像
山門をくぐって左手に大師堂。堂前を直角に折れると正面が本堂。
緑が多く風情ある山内で、引き締まった像容の馬頭観世音菩薩像など見どころが多いです。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂扁額
大師堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で「遍照殿」の扁額を置いています。
同前に御府内霊場の札所碑もありました。


【写真 上(左)】 札所碑
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、その下に銅板葺の屋根を張りだしてやや変わった意匠です。
水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
向拝正面硝子格子扉のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
向拝身舎柱に「本尊 薬師如来」とあり、札所本尊のお薬師さまはこちらに御座。
本堂向かって右には修行大師像が御座。
なので、御府内霊場巡拝の拝所は、不動堂、大師堂、本堂、修行大師像の4ヶ所となります。
御朱印揮毫は薬師如来、不動明王、弘法大師の三尊。雄渾な筆致で見ごたえがあります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

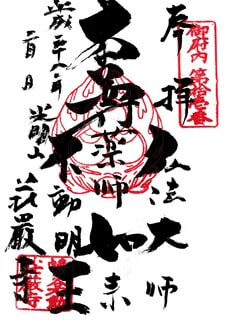
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は宝珠印。揮毫は「本尊 薬師如来」「不動明王」「弘法大師」で右上に「御府内 第拾壱番」の札所印。左下には山号寺号揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第12番 明王山 無動院 宝仙寺
(ほうせんじ)
公式Web
中野区中央2-33-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:弘法大師
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第12番、関東三十六不動尊霊場第15番、真言宗(関東)七箇寺
司元別当:和田村八幡(大宮八幡神社)、(中野村)氷川社
授与所:本堂向かって右手の大書院
公式Web、山内掲示、『新編武蔵風土記稿』によると、寛治年間(1087-1094年)、八幡太郎源義家公が奥州・後三年の役を平定して凱旋帰京の途中、陣中で護持されていた不動明王像を安置するため建立・創建。
旧地は、父・頼義公が祀った八幡社のある阿佐ヶ谷で、造寺竣成にあたり地主稲荷神が出現されて義家公に一顆の珠を与え「この珠は希世之珍 宝中之仙である 是を以って鎮となさば 則ち武運長久 法燈永く明かならん」と告げられたため、その地を寺地とされたと伝わります。
往時は和田村八幡(大宮八幡神社)の別当と伝わり、『新編武蔵風土記稿』には「((中野村)氷川社)村内寶仙寺ノ持」とあります。


【写真 上(左)】 大宮八幡宮
【写真 下(右)】 大宮八幡宮の御朱印

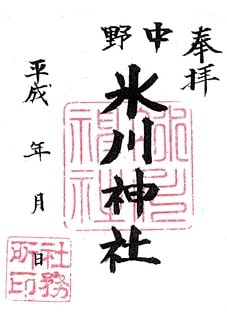
【写真 上(左)】 (中野)氷川神社
【写真 下(右)】 (中野)氷川神社の御朱印
鎌倉時代には相模國大山寺の願行上人が当寺を訪れ、御本尊の不動明王像をご覧になられて霊貌の凡常でないことに驚かれ、尊像を厨子の奥に秘蔵され、別に御前立の不動尊を刻して安置されました。
室町時代には、当寺中興第一世聖永(永享三年(1431年)寂)が現地に寺基を遷しました。
寛永十三年(1636年)には三重塔が建立されて庶民にも親しまれ、歴代将軍の尊崇篤く御鷹狩りの休憩所としても使われました。
徳川将軍家は清和源氏新田氏流を名乗り、その始祖は八幡太郎義家公です。
その義家公ゆかりの不動尊奉安の寺院となれば、歴代将軍の尊崇もなるほどうなづけるものがあります。
江戸期には「末寺三十二ヶ寺 門徒二十六ヶ寺ヲ統ヘ司トレリ」(『新編武蔵風土記稿』)という名刹です。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
往還ノ内小名中宿下宿ノ境ニアリ 明王山聖不動院ト号ス 新義真言宗 無本寺ニテ(略)
傳へ云 昔堀河院ノ御宇寛治年中(1087-1094年)鎮守府将軍源義家 奥州ノ夷賊ヲ征伐シ御利運アリシカハ 凱陣ノ後当寺ヲ建立シ給フト云 サレト往古ノ事ナレハ其詳ナル●ヲシラス 当寺昔シハ和田村八幡(大宮八幡神社)ノ別当ナリシカ 社地ヘノ路程ヘタゝリテ不便ナレハ 末寺ニソノ職ヲユツレリト云 サレハ八幡鎮座ノ時 当寺ヲ起立シテ別当ニ附ラレシニヤ 中興開山ヲ聖永トイフ 永享三年(1431年)2月24日示寂ス 末寺三十二ヶ寺 門徒二十六ヶ寺ヲ統ヘ司トレリ(略)
本堂 御成ノ時御膳所ナリ 本尊ハ不動ノ坐像ニテ長一尺七寸五5分 良弁ノ作 外ニ四大明王ノ四体ヲ安ス 木ノ立像ニテ長二尺三寸五分 願行ノ作ト云 古位牌一基アリ 碑面ニ云将軍頼義公信信海将軍義家公信了ト彫リテアリ(以下略)
(塔頭 玉泉寺)
境内東南ニアリ 本尊弘法大師木ノ坐像ニテ長二尺五寸 願行ト云ヘル作 什物 弘法大師畵像二軸 愛染明王ノ畵像一軸 右三軸トモ弘法大師ノ筆スル所ナリト云
(三重塔)
当寺ヨリ二町ホト東ノ方ニアリ三間半四面高サ五丈三尺五智如来ノ木像ヲ安ス
((中野村)氷川社)
村内寶仙寺ノ持

『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫) 中野寶仙寺』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載)
-------------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門-1


【写真 上(左)】 山門-2
【写真 下(右)】 寺号標
東京メトロ丸の内線「中野坂上」駅からほど近い職住学混在エリアに広大な山内を構えています。
青梅街道の「宝仙寺前」交差点から北に向けてまっすぐ伸びる道は、かつての参道だったのでは。
周囲を占める宝仙学園の創立者は宝仙寺第50世住職富田敦純大僧正で、昭和10年東京では初めての仏教系の保育者養成校・仏教保育協会保姆養成所(現・こども教育宝仙大学)が創始です。
公式Webには「弘法大師の『綜藝種智院』を模範に大師の思想を教育の根底におきました。」とあります。
山門は切妻屋根本瓦葺三間一戸の八脚門で、両脇間に迫力の仁王尊像を安置。
山門からしてすでに名刹の風格をただよわせています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 見返り地蔵&六地蔵
境内案内は公式Webにも掲載。
山門の先左手に寺号標、鐘楼、中野町役場跡碑、見返り地蔵&六地蔵、石臼塚、八十八大師塔、三重塔、御影堂とならびます。


【写真 上(左)】 石臼塚
【写真 下(右)】 三重塔
石臼塚は蕎麦挽きの石臼の供養塚。
そばを流れる神田川には江戸期水車が置かれて蕎麦粉が挽かれ、一大消費地・江戸に向け盛んに玄蕎麦が送られて、この地の蕎麦粉は「中野蕎麦」と呼ばれ名を馳せたとの由。
機械化で使われなくなった大量の石臼を見られた当山第50世住職富田敦純大僧正が「人の食のために貢献した石臼を大切に供養すべき」として建立されたものです。
当山の三重塔は、寛永十三年(1636年)に塔ノ山の飛び地境内(現・区立第十中学校(中野東中学校))に建立され、戦災で焼失した三重塔を平成4年に飛鳥様式で再建したもので、高さは約20メートル。
堂内には大日如来を中心とした胎蔵界五佛が奉安されています。
『新編武蔵風土記稿』には「(三重塔)当寺ヨリ二町ホト東ノ方ニアリ三間半四面高サ五丈三尺(約16m強)五智如来ノ木像ヲ安ス」とあり、区立第十中学校(中野東中学校)は当山からほぼ二町(約220m)ほどにあるので、この三重塔を再建とみられます。
ただし、風土記稿三重塔奉安の五智如来(=金剛界五佛/大日如来・阿閦如来・薬師如来・宝生如来・観自在王如来(ないし阿弥陀如来)、不空成就如来(ないし釈迦如来)に対し、こちらの三重塔は胎蔵界五佛(大日如来、宝幢如来、開敷華王如来、無量寿如来、天鼓雷音如来の奉安となっています。
なお、『江戸名所図会』によると、中野周辺は「中野七塔」と呼ばれ、塔が多いことで知られていたようです。
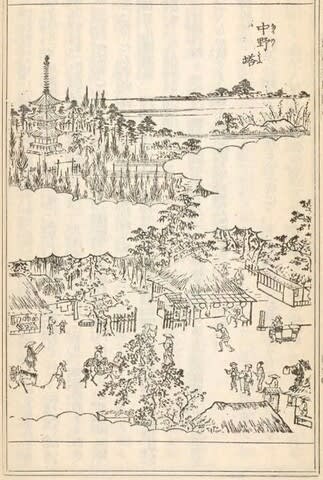
『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫) 中野塔』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載)


【写真 上(左)】 御影堂
【写真 下(右)】 日輪弘法大師
御影堂は三間四方の宝形造本瓦葺身舎柱朱塗りの整った堂宇で、堂宇御本尊の日輪弘法大師座像の高さは後背まで入れると約3メートル。
堂前説明書には「脱活乾漆という漆と麻布で作られておりこの技法でこのような大きな佛像は壱千年以上も絶えて作られておりませんでした。」とある稀少な尊像です。
御影堂は開扉されている時とされていないときがあり、21日は開扉されていたのでご縁日(月御影供)のみの御開扉かもしれません。
『新編武蔵風土記稿』には「(塔頭 玉泉寺)境内東南ニアリ 本尊弘法大師木ノ坐像ニテ長二尺五寸 願行ト云ヘル作 什物 弘法大師畵像二軸 愛染明王ノ畵像一軸 右三軸トモ弘法大師ノ筆スル所ナリト云」とあります。
宝仙寺塔頭玉泉寺の御本尊は伝・願行作の弘法大師坐像ですが、御影堂の日輪弘法大師坐像とは像高が異なるので、別個の尊像かと思います。
ただ「弘法大師畵像二軸 弘法大師ノ筆スル所ナリト云」というただならぬ記載があり、もともとお大師さまとゆかりのふかい寺院であったことがうかがえます。
立地は府外ながら弘法大師や八幡太郎源義家公ゆかりの名刹で、その流れから御府内霊場札所に迎えられたのでは。


【写真 上(左)】 弘法大師碑
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造本瓦葺で大棟に金色の鴟尾を置き、身舎の柱梁は朱塗りで華々しいイメージ。
向拝柱はなく、向拝見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
こちらには御本尊の不動明王を中心に五大明王が奉安され、関東三十六不動尊霊場第15番札所となっています。
本堂向かって右手は大書院で、御朱印はこちらで拝受できます。
大書院裏手の白玉稲荷は、寺号の由来となった宝珠を祀った祠とのことです。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 鐘楼
山門右手の近代建築は大師堂で、教化活動のお堂とのこと。
御朱印は御府内霊場、関東三十六不動尊霊場、そして日輪弘法大師の3種類が授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は弘法大師のお種子「ユ」(蓮華座)。揮毫は「日輪弘法大師」で右上に「府内八十八ヶ所 第十二番」の札所印。左下には寺号揮毫と寺院印が捺されています。
御府内霊場中5つしかない貴重なお大師さまの単独揮毫御朱印のひとつです。
〔 関東三十六不動尊霊場第15番の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
〔 日輪弘法大師の御朱印 〕

以下、つづきます。
(→ Vol.4)
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第9番 古碧山 龍厳寺
(りゅうげんじ)
渋谷区神宮前2-3-8
臨済宗南禅寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:
司元別当:(青山熊野権現/旧 浄性院)
授与所:庫裡
御府内霊場中、唯一の非真言宗寺院の禅刹(臨済宗南禅寺派)です。
『ルートガイド』には「弘法大師が関東を巡った際に開創され、かつては真言宗の寺院であったと伝わります。開創時の札所は青山熊野神社の別当・状(ママ)性院でしたが、明治七年の神仏分離で廃寺となり、弘法大師開創の伝承を有することから、龍厳寺が札所を引き継いだといわれています。」とあります。
たしかに江戸八十八ヶ所霊場第9番は「三光山 宝厳寺 浄性院(港区青山)」とあり、江戸期は浄性院が御府内霊場第9番札所であったとみられます。
旧9番浄性院は真言宗寺院で、新9番龍厳寺は臨済宗南禅寺派。
第9番が旧番のまま真言宗であれば御府内霊場の札所はすべて真言宗寺院で完結するのに、あえて新第9番を臨済宗南禅寺派とした理由があったのでしょうか。
まずは青山熊野権現元別当の浄性院から当たってみました。
『江戸名所図会』7巻 [8]の熊野権現社の項には「熊野権現社(略)南紀の熊野権現と同じく三社あり 青山の鎮守(略)別当ハ真言宗浄性院と号す」とあります。


【写真 上(左)】 (青山)熊野神社
【写真 下(右)】 (青山)熊野神社の御朱印
『寺社書上』(国立国会図書館)にも浄性院が収録されています。
熊野社と錯綜気味ですが、浄性院(寺院)に関連するとみられる記述を書き出します。
----------
本寺京知積院末 武州豊嶋郡原宿村 熊野権現別当 三光山 真(ママ)義真言宗 浄性院
開山法印清範明暦二年(1656年)寂 中興法印快圓宝暦十二年(1762年)寂
五百羅漢 十六善神 不動尊 愛染尊
本地堂 熊野三社本地 (中)十一面千手観音 (右)薬師如来 (左)彌陀如来
金胎大日如来 石洞稲荷社 聖天堂本尊歓喜天 同本地十一面観世音
(相殿)江州浅井郡竹生島 本尊弁才天(旅宿社?) 訶梨帝母立像
護摩堂 本尊不動尊立像 厨子入不動尊坐像 愛染明王坐像 如意輪観音坐像 弘法大師坐像 右勧請●立年月不知
延享二年(1745年)二月十二日社殿●不残焼失仕 安永八年(1779年)正月十●日自火●亦ハ焼失 不知●記縁●●焼失仕寺記並開基亦●由来相不知
----------
『寺社書上』によると浄性院は京知積院末の新義真言宗で開山は法印清範(明暦二年(1656年)寂)。
浄性院(相殿)の弁才天は、江州浅井郡竹生島ゆかりのようです。
琵琶湖の竹生島は弁才天の聖地で、竹生島弁才天は江島(与願寺)・ 厳島(大願寺)とならんで「日本三大弁天」のひとつに数えられます。
竹生島にある巌金山 宝厳寺は真言宗豊山派で御本尊は大弁才天。
観音堂は西国三十三所第30番札所となっています。
宝厳寺の公式Webには「弘法大師なども来島、修業されたと伝えられています。」とあり、弘法大師の「御請来目録」を所蔵されています。
「御請来目録」は「(弘法大師)空海が唐から請来した新旧訳経、梵字真言、論疏章、曼荼羅、道具などの目録」(国立情報学研究所)で、日本密教上きわめて重要な文献です。
「御請来目録」には3つの写本があるとされます。
施福寺(大阪府和泉市槙尾山町)の「施本」、東寺所蔵の「東寺本」、そして竹生島宝厳寺所蔵の「竹生島本」です。
(参考:「『御請来目録』の書誌学的研究(甲田宥吽氏/PDF)」
「施本」は「請来目録上表草稿」ともいわれる請来目録残巻で、ほぼ弘法大師の御眞蹟と断定されていますが、「東寺本」、「竹生島本」が御眞蹟であるかについては、従前から数々の議論がなされ未だ結論を得ていない模様です。
ただし、「弘法大師御請来目録の原本について」(眞保龍敞氏/PDF)によると、宝厳寺所蔵の「弘法大師御請来目録」(竹生島本)は「(弘法大師)空海によって上表された原本に相違ない、と考えられる」とされています。
また、筆者は「竹生島本」と他の弘法大師御眞蹟とで精緻な比較をされた結果、「竹生島本は、筆蹟の上からも空海自筆たる特徴を充分に具え、弘法大師の御眞蹟と認定し得るもの」とされています。
つまり竹生島宝厳寺は弘法大師御眞蹟の「御請来目録」を所蔵されている可能性があり、浄性院の弁才天はこの竹生島(宝厳寺)弁才天系なので、この流れから浄性院と弘法大師霊場(御府内霊場)のつながりが出てきたのかもしれません。
一方、護摩堂の不動尊は「目黄不動尊」として信仰を集めたといい、「江戸五色不動」の一尊に数えられることもあったようです。(ご参考→「江戸五色不動の御朱印」 )
護摩堂には弘法大師坐像が御座され、山内に祀られる聖天様、愛染明王、稲荷神はいずれも真言宗寺院で多く祀られる尊格で、浄性院が保守本流の真言宗寺院であったことを裏付け、弘法大師霊場(御府内霊場)としての資格を充分に備えていたことがうかがえます。
(『江戸名所図会』の絵図には、はっきりと「弘法大師 不動 あいせん」と載っています。)
龍厳寺の参拝時、本堂の御本尊と大師堂を礼拝した記憶があり、たしかこの「目黄不動尊」は大師堂内の御座だったかと思います。
となると、浄性院ゆかりの尊格は龍厳寺の大師堂に奉安されている可能性もあります。
御府内霊場の御朱印には「黄金目不動明王」の揮毫があるので、浄性院の「目黄不動尊」つながりで御府内霊場の札所となったのかもしれません。
また、たしか龍厳寺の大師堂前には宇賀神系の弁財天石仏が御座していました。
もともとの龍岩寺の地主ノ神である辨天様か、浄性院からの竹生島(宝厳寺)系弁才天かはわかりませんが、大師堂前御座から考えると後者かもしれません。
いずれにしても、青山熊野権現は『江戸名所図会』に載るほどの名所。
そしてその祭礼の華やかさは有名で、「青山に過ぎたるものが二つあり 鳶の薬缶に原宿の山車」という俗謡が伝わります。
浄性院はその著名な熊野権現の別当。その点からも弘法大師霊場の資格をもっていたかと思われます。
*********
つづいて龍岩寺(龍厳寺)です。
臨済宗で本寺は多磨郡由井領山田村(現八王子)の兜率山廣園寺。
当初は名主半右衛門の屋敷の鎮守に辨天社があり、そばに小庵を建て喚室という僧を招聘し、慶長七年(1602年)に喚室を開山として創建といいます。
「やさしいお坊さん」Web(LDT株式会社)によると、喚室(峻翁令山禅師)は、武蔵國秩父郡出身で寂後に勅号(天皇よりの法名命名)を賜り法光円明国師と呼ばれた名僧で、本山兜率山廣園寺、児玉郡威音山光厳寺、深谷常興山國済寺などを開山されたといいます。
原宿村の一名主がこれほどの高僧を自邸の一庵に招聘できたのは不可思議で、『寺社書上』には「鐘銘ニ拠ハ(家康公)御入國(天正十八年(1590年))以前ヨリノ寺ナリト載ス」ともありますが、2度にわたる火災で寺伝を焼失し詳細は不明のようです。
御本尊は釈迦如来。
境内に祀る弁天社は「地主ノ神」といい、もともとの半右衛門屋敷の鎮守神とみられます。
以上をみても龍岩寺に密寺色はうすく、むしろ純然たる禅刹のイメージがあります。
【史料】
■ 『寺社書上』(国立国会図書館)
武州八王山田廣園寺末 禅宗臨済派 古碧山龍岩寺
開闢 慶長(1596-1615年)トモ●傳 開山 喚室和尚元和八年(1622年)遷化 中興開山 青山和尚宝永八年(1711年)遷化 開基 相知不申候 中興開基 元禄五年(1692年)死去 俗名山崎半右エ門 当村名主作太郎先祖也
本尊 釈迦如来 脇立 文殊 菩薩
■ 『新編武蔵風土記稿』(同上)
龍岩寺 禅宗臨済派古碧山ト号ス 多磨郡由井領山田村廣園寺末 本尊釋迦 脇士文殊 普賢ヲ安ス 相傳フ 境内昔ハ名主半右衛門カ屋敷ニテ鎮守辨天社アリ 側ニ小庵ヲ建テ喚室ト云僧ヲシテ住セシメシカ 慶長七年(1602年)遂ニ宅ヲ捨テ寺トス 依テ喚室ヲ開山トスト寺傳ニイヘリ 鐘銘ニ拠ハ 御入國以前ヨリノ寺ナリト載ス 何レカ是ナルヤ喚室ハ元和八年(1622年)寂ス
辨天社 地主ノ神ナリ
天満宮 往古ハ木立像ナリシト(略)源義家此所ニテ出陣ノ連句ヲ催シ社前ニ納ム 依テ句寄ノ天神ト号スト 稲荷ヲ合祀セリ
日吉山王社 (略)往古ハ当村千駄谷村境榎樹ノ下ニ勧請アリシヲ 寛永中(1624-1644年)当寺第三世明叟ノ時ココニ移スト云
圓座松 砌下ニアリ囲モ四尺許 根上一尺許ヲ隔テ四方ヘ蟠延ス 大サ東西七間餘南北六間半 其状圓坐ヲ敷タル如クナレハ此名アリ
*********
とまぁ、いろいろ調べてみましたが、どうして廃寺後の浄性院の寺跡が、札所も含めて臨済宗の龍厳寺に引き継がれたかのはっきりとした答えは見いだせませんでした。
明治七年、神仏分離を受けた浄性院の廃寺の際にはかなりの混乱があった模様なので、なにか記録に残されていない複雑な経緯があったのかもしれません。
【 龍岩寺と熊野権現社(浄性院)の位置関係 】

※ 『江戸切絵図/青山渋谷絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
ただ、ひとつ気になる事柄があります。
多摩エリアの弘法大師霊場に「多摩新四国八十八ヶ所霊場」があります。
こちらはすべての札所が真言宗寺院です。
また、「多摩新四国八十八ヶ所霊場」をベースに開創といわれる「多摩百八ヶ所霊場」の札所もすべて真言宗寺院です。
ところが「多摩新四国八十八ヶ所霊場」には番外札所があって、それが八王子の廣園寺(こうおんじ)だというのです。
公式ガイドやWeb上の札所一覧情報には載っていませんが、一部のWebに記載があり、Wikipediaにも「多摩八十八箇所番外札所」と明記されています。


【写真 上(左)】 廣圓寺
【写真 下(右)】 廣圓寺の御朱印
兜卒山廣園寺は八王子市にある臨済宗南禅寺派の寺院で、龍厳寺の本寺です。
つまり、本寺・廣園寺は番外ながら唯一禅宗で「多摩新四国八十八ヶ所霊場」の札所、末寺・龍厳寺は「御府内霊場」唯一の禅宗の札所で、本末揃って禅宗で弘法大師霊場の一画を占めていることになり、なんとなく偶然の符合とは思えないものがあります。
ただし、Webから追えたのはここまでで真相は霧のなかです。
-------------------------
最寄りは都営大江戸線「国立競技場前」駅ですが、メトロ銀座線「外苑前」駅からも歩けます。
「外苑前」駅からだと青山熊野神社の前を通り、神社から龍厳寺に向かう坂道を「勢揃坂」といいます。
現地掲示板によると、永保三年(1083年)に八幡太郎義家公が奥州征伐(後三年の役)に出陣の際、ここで軍勢を揃えたといわれ、当地の豪族渋谷氏の祖・秩父十郎武綱も参陣と伝わります。
また、龍厳寺山内の天満宮は義家公が出陣の際に連句を催し、社前に句を納めたとされ「句寄の天神」ともいうそうです。


【写真 上(左)】 勢揃坂
【写真 下(右)】 参道
國學院高のちょうど西側で、敷地じたいは外苑西通りに面していますが、山門は1本奥まった枝道からさらに入ったところにあり、神宮前とは思えない静寂に包まれています。
路地から伸びるゆったりとした石敷きの参道。
あたりは都心としては奇跡的に?高い建物がなく、陽光が降りそそいで明るいです。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山門-1
山門前に寺号標。上部には「御府内第九番御札所 弘法大師霊場」と刻まれています。
正面の山門は切屋根桟瓦葺妻の薬医門で、両脇に桟瓦葺の板塀を延べています。
主門には木柵が置かれ、右手通用門横には「檀信徒以外の出入りをお断り申す 合掌」の掲示があって一瞬ひるみますが、「御府内霊場巡拝者はたぶん信徒だよな~」と気をとりなおして通用門をくぐり山内に進みます。
(たしか通用門を開けるといきなり鈴が鳴って、これまたびびった記憶が・・・(笑))


【写真 上(左)】 山門-2
【写真 下(右)】 門外からの山内
こちらは山内の撮影禁止なので撮影はしておりませんし、山内のご案内も控えます。
草木が茂ったほの暗い山内で、堂宇も趣きがあり、とても神宮前の一画とは思えません。
山内には石佛が点在していましたが、画像がないのでよくわかりません。
従前、山内にあった「圓座の松」は江戸の名木のひとつとして知られ文化十年著の『十万庵遊歴雑記』などで取り上げられています。
御朱印は庫裡にて拝受。敷居が高く謹厳なイメージがありますが、御朱印対応はご親切でした。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は釋迦如来のお種子「バク」ではなく、なぜか阿弥陀如来・如意輪観世音菩薩のお種子「キリーク」(蓮華座+火焔宝珠)。揮毫は「本尊 釋迦牟尼佛」「弘法大師」「黄金目不動明王」で右上に「第九番」の札番揮毫。左下には寺号揮毫と寺院印が捺されています。
「釋迦牟尼佛」の御朱印は禅刹では一般的ですが、御府内霊場では唯一と思われます。
■ 第10番 観谷山 福聚院 聖輪寺
(しょうりんじ)
渋谷区千駄ヶ谷1-13-11
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第10番、東京三十三所観世音霊場第13番、近世江戸三十三観音霊場第20番、大東京百観音霊場58番
司元別当:
授与所:庫裡
御府内霊場中、もっとも歴史が古いとされる古刹です。
『観谷山聖輪寺観音略縁起/寺社書上』によると、神亀二年(725年)5月の頃、行基菩薩が北越遊行された折に当地で休息されたとき、谷の中から光りが射して如意輪観世音菩薩が出現しました。
観音様は「我はこの地に因縁あり、汝(行基菩薩)が我の相を彫刻すれば末世の衆生に結縁せしめて広く利益をなさん」と告げられて、大きな朽木のもとでお姿を消されました。
行基菩薩は感じ入り、この枯木を加持して御長三尺五寸の尊像を刻み奉り石上に安置して持念されました。
観音様は御双眼より金色の光りを放たれたため観谷山、寺号を聖輪寺として本山を開創されたと伝わります。
神亀二年(725年)開創とすると、実に千三百年もの寺歴を有することになります。
明和九年(1772年)刊の『江戸砂子温故名蹟誌』には、江戸にて千年以上の霊場は浅草寺と当寺と記されています。
御本尊は行基菩薩の御作と伝わる如意輪観世音菩薩。
山内掲示によると、この地の豪族・渋谷氏一門はこの尊像を深く信仰し、そのご利益あってか一門は栄え、人々は「黄金長者」と呼んだといいます。
天正の頃(1573年)には、御本尊が疱瘡から里人を救われ、観音様の大悲護念を謝してこのときから御本尊を閉扉し秘仏として崇め奉ったとのことです。
慶長の頃には観音像の双眼が黄金であると聞いた賊が忍び込み、玉眼を鑿で取ろうとしたところ、冥罰に当り、自らの鑿で貫かれて死んでしまいました。
人々はこれも観音様の霊験と畏れ、信仰をいっそう篤くしたと伝わります。
このときより「千駄谷観音」「目玉の観音」とも呼ばれ、近世江戸三十三観音霊場第20番の札所ともなって人々の信仰を集めました。
慶安四年(1651年)には奈良・長谷寺の末寺となり、真言宗豊山派の名刹としていまに至っています。
【史料】
■ 『寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考』
新義真言宗 紀州初瀬小池坊末 千駄ヶ谷町
起立之儀古来●当地有之候得共、年数不分明
開山 法印宥光(明暦三年(1657年)遷化)
中興 法印宥仙(元禄七年(1694年)示寂)
本尊 如意輪観音 木座像丈三尺五寸 神亀二年(725年)行基菩薩作
前立 如意輪観音 両脇立 不動毘沙門 四天王 護摩壇本尊不動 両童子 聖天
鎮守社 諏訪明神 秋葉権現 稲荷明神
大師堂 弘法大師 厨子入座像 長二尺三寸
※鎮守の稲荷明神は「庄九郎稲荷」ともいわれ、往古は村の鎮守とも伝わります。
(観谷山聖輪寺観音略縁起)
抑当寺本尊聖如意輪観世音者 行基菩薩乃御作也 神亀二年(725年)五月の頃 行基北越遊行乃時 此所に暫く休息し(略)谷乃中より光りさし如意輪観音出現しぬ 告て宣く●此地ハ我に因縁あり汝よろしく●我相を彫刻し 末世の衆生に結縁せしめて廣く利益をなさんとて 大なる朽木の本ニ失給ふ 行基感涙肝に銘し(略)其枯木を採て御衣木とし加持して御長三尺五寸の尊像を刻み奉り 石上に安置し持念したまふ 御双眼より金色乃光りを放ち●故に 本山を観谷山といひ 寺を聖輪寺と号す
(以下、山内掲示の縁起書に概要記載あり)
■ 『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [5]』(国立国会図書館)
観音 千駄ヶ谷 観谷山 聖輪寺 真言 和州長谷末
開山行基菩薩 本尊如意輪 眼玉の観音と云●り 賊来りて本尊の玉眼黄金なりとて ぬき出し(略)おのれを害して死
江府にて千余歳の霊場ハ浅草寺と当寺
【 江戸期の聖輪寺周辺 】

※ 『江戸切絵図/内藤新宿千駄ヶ谷絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載

『江戸名所図会 7巻 [9] 千駄谷観音堂』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載)
-------------------------


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 札所標
国立競技場の西側にあり、「国立競技場」駅、「千駄ヶ谷」駅、「北参道」駅の3駅から徒歩でアクセスできます。
「観音坂」と呼ばれる坂の途中に位置しています。
入口は門柱。門前には御府内霊場の札所標、門扉には真言宗の宗紋門「五三の桐」。


【写真 上(左)】 五三の桐
【写真 下(右)】 入口


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 庚申塔
山内はさほど広くはありませんが、よく手入れされて落ち着いた参拝ができます。
鐘楼堂まわりには八十八カ所踏み石参拝所が設けられています。
塀ぎわには二童子を従えた身守不動尊と六地蔵。
渋谷区教育委員会の説明書がある庚申塔、桃?を持たれたかわいいお地蔵さまも御座。


【写真 上(左)】 身守不動尊
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 地蔵尊
【写真 下(右)】 本堂
本堂は近代建築で向拝上部に山号扁額、その上に真言宗豊山派の宗紋「輪違い紋」を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
墓域には真田氏の流れで『明良洪範』を著した、甲州流の兵学者増譽法印の墓があります。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は三寶印。揮毫は「本尊 如意輪観音」「不動明王」「弘法大師」で右上に「第十番」の札所印。左下には寺号揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第11番 光明山 真言院 荘厳寺
(しょうごんじ)
渋谷区本町2-44-3
真言宗室生寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来・不動明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第11番
司元別当:(幡ヶ谷)氷川神社(渋谷区本町)
授与所:不動堂札所(授与所)
「幡ヶ谷不動尊」としても知られる真言宗室生寺派の寺院。
『新編武蔵風土記稿』によると、開山は宥悦法印(天文二年(1533年)寂)。
寺院御本尊は薬師如来ですが、御府内霊場の御朱印には不動明王も揮毫されているので、札所本尊は薬師如来・不動明王両尊と思われます。
不動明王は智証大師(円珍)が三井寺開基の際に自ら彫刻し本尊とされた尊像と伝わり、天慶二年(939年)、承平天慶の乱で藤原秀郷が戦勝を祈願して御持佛とし、戦勝ののち下野国小山郷に安置と伝わります。
三井寺から遷られた経緯については『江戸名所図会』に「(天慶年間)平貞盛、及び藤原秀郷等、東国に発向す。其時三井寺より此本尊を奉持して、陣中に移し奉り、戦の勝利を祈誓」とあり、承平天慶の乱の際に東国に遷られた旨が記されています。
永禄年中(1558-1570年)、武田信玄が甲州七覺山(右左口の七覚山円楽寺?/真言宗)に遷して崇敬し、後に北条氏政がこれを奪って相州筑井縣地勝院(相州津久井城西麓?)に奉安、天正十八年(1590年)北条氏没落の後には徳川家康以下代々の武将が崇敬して多磨郡宅部村三光院(東大和市/真言宗)に遷られ、延享四年(1747年)9月、霊夢のお告げにより当山に安置と伝わります。
このお不動様を尊崇した武将は藤原秀郷、武田信玄、北条氏政、徳川家康という錚々たる面々で、相模原市の城山地域史研究会資料には「有名武将が競って崇敬した不動明王」と記されています。
以降「幡ヶ谷不動尊」として広く信仰を集め、「江戸近郷の三不動(成田山、光明山、高幡山)の一つとして広く尊崇を集めた。」というWeb記事もみつかりました。
立地は府外ですが、開創時から御府内霊場札所であったとみられ、これは『江戸名所図会』にも載せられた著名な「幡ヶ谷不動尊」の存在が大きかったのかもしれません。
江戸期には(幡ヶ谷)氷川神社(渋谷区本町)の別当も司っていました。


【写真 上(左)】 幡ヶ谷氷川神社
【写真 下(右)】 幡ヶ谷氷川神社の御朱印
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
新義真言宗 江戸大塚護國寺末 光明山真言院ト号ス 開山宥悦 天文二年(1533年)5月15日寂 本尊薬師
不動堂 木佛立像長三尺三寸 智證大師作 縁起ニ云 智證大師三井寺開基ノ時 自此不動ヲ彫刻シテ彼寺ノ本尊トセシカ 天慶二年(939年)平貞盛 藤原秀郷等平将門追討ノ時 秀郷此不動ニ祈誓ヲコメ 陣中マテ守リ行テ渇仰怠リ無ク 果シテ勝利ヲ得タリシカハ 凱陣ノ頃下野國小山ノ郷ニ安置セリ 其後遥星霜ヲ歴テ 永禄年中(1558-1570年)武田信玄甲州七覺山ニ移シ崇敬セシヲ 北條氏政奪テ相州筑井縣地勝院ニ納ム 然ルニ天正十八年(1590年)北條氏没落ノ後 東照宮代々ノ武将崇敬アリシ像ナル事ヲ聞シ召レテ 多磨郡宅部村三光院ニ移シ給ヒ 延享四年(1747年)9月霊夢ノ告アリテ当寺ニ安置スト云 稲荷社
(幡ヶ谷村)氷川社 村ノ鎮守ナリ荘厳寺持
-------------------------


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 不動堂


【写真 上(左)】 不動堂向拝
【写真 下(右)】 「幡ヶ谷不動尊」の尊号板
場所は初台の新国立劇場の北側で最寄りも「初台」駅、山手通りから1本なかに入った住宅地にあります。
南側の「ふどう通り」は、かつて幡ヶ谷不動尊の参道であったとも。
入口に「幡ヶ谷不動 荘厳寺」の寺号標。その先の門柱の右手奥が幡ヶ谷不動堂。
堂前は催しができる広めのアスファルト敷のスペースで、著名な仏堂によくあるかたち。
入母屋造本瓦葺流れ向拝の端正な不動堂で、向拝まわりの意匠は比較的シンプルです。
向拝柱に「幡ヶ谷不動尊」「厄除不動」の掛板。向拝見上げに「不動明王」の扁額。
向かって右手に札所(授与所)があり、御朱印はたしかこちらでいただいたかと思います。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 山門
不動堂の向かって左奥、狛犬一対の先に構える山門は、切妻屋根本瓦葺で手前左右の控柱に切妻屋根が掛かっているので高麗門かと思います。
山門柱に重厚な筆致の寺号板。


【写真 上(左)】 山門の寺号板
【写真 下(右)】 馬頭観音像
山門をくぐって左手に大師堂。堂前を直角に折れると正面が本堂。
緑が多く風情ある山内で、引き締まった像容の馬頭観世音菩薩像など見どころが多いです。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂扁額
大師堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で「遍照殿」の扁額を置いています。
同前に御府内霊場の札所碑もありました。


【写真 上(左)】 札所碑
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、その下に銅板葺の屋根を張りだしてやや変わった意匠です。
水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
向拝正面硝子格子扉のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
向拝身舎柱に「本尊 薬師如来」とあり、札所本尊のお薬師さまはこちらに御座。
本堂向かって右には修行大師像が御座。
なので、御府内霊場巡拝の拝所は、不動堂、大師堂、本堂、修行大師像の4ヶ所となります。
御朱印揮毫は薬師如来、不動明王、弘法大師の三尊。雄渾な筆致で見ごたえがあります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

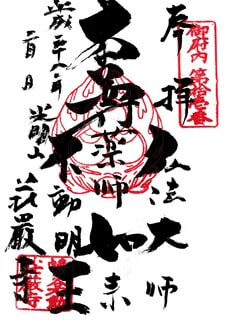
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は宝珠印。揮毫は「本尊 薬師如来」「不動明王」「弘法大師」で右上に「御府内 第拾壱番」の札所印。左下には山号寺号揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第12番 明王山 無動院 宝仙寺
(ほうせんじ)
公式Web
中野区中央2-33-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:弘法大師
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第12番、関東三十六不動尊霊場第15番、真言宗(関東)七箇寺
司元別当:和田村八幡(大宮八幡神社)、(中野村)氷川社
授与所:本堂向かって右手の大書院
公式Web、山内掲示、『新編武蔵風土記稿』によると、寛治年間(1087-1094年)、八幡太郎源義家公が奥州・後三年の役を平定して凱旋帰京の途中、陣中で護持されていた不動明王像を安置するため建立・創建。
旧地は、父・頼義公が祀った八幡社のある阿佐ヶ谷で、造寺竣成にあたり地主稲荷神が出現されて義家公に一顆の珠を与え「この珠は希世之珍 宝中之仙である 是を以って鎮となさば 則ち武運長久 法燈永く明かならん」と告げられたため、その地を寺地とされたと伝わります。
往時は和田村八幡(大宮八幡神社)の別当と伝わり、『新編武蔵風土記稿』には「((中野村)氷川社)村内寶仙寺ノ持」とあります。


【写真 上(左)】 大宮八幡宮
【写真 下(右)】 大宮八幡宮の御朱印

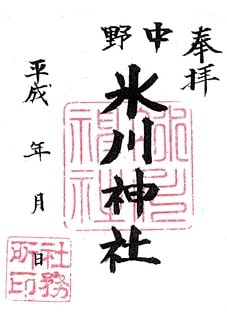
【写真 上(左)】 (中野)氷川神社
【写真 下(右)】 (中野)氷川神社の御朱印
鎌倉時代には相模國大山寺の願行上人が当寺を訪れ、御本尊の不動明王像をご覧になられて霊貌の凡常でないことに驚かれ、尊像を厨子の奥に秘蔵され、別に御前立の不動尊を刻して安置されました。
室町時代には、当寺中興第一世聖永(永享三年(1431年)寂)が現地に寺基を遷しました。
寛永十三年(1636年)には三重塔が建立されて庶民にも親しまれ、歴代将軍の尊崇篤く御鷹狩りの休憩所としても使われました。
徳川将軍家は清和源氏新田氏流を名乗り、その始祖は八幡太郎義家公です。
その義家公ゆかりの不動尊奉安の寺院となれば、歴代将軍の尊崇もなるほどうなづけるものがあります。
江戸期には「末寺三十二ヶ寺 門徒二十六ヶ寺ヲ統ヘ司トレリ」(『新編武蔵風土記稿』)という名刹です。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
往還ノ内小名中宿下宿ノ境ニアリ 明王山聖不動院ト号ス 新義真言宗 無本寺ニテ(略)
傳へ云 昔堀河院ノ御宇寛治年中(1087-1094年)鎮守府将軍源義家 奥州ノ夷賊ヲ征伐シ御利運アリシカハ 凱陣ノ後当寺ヲ建立シ給フト云 サレト往古ノ事ナレハ其詳ナル●ヲシラス 当寺昔シハ和田村八幡(大宮八幡神社)ノ別当ナリシカ 社地ヘノ路程ヘタゝリテ不便ナレハ 末寺ニソノ職ヲユツレリト云 サレハ八幡鎮座ノ時 当寺ヲ起立シテ別当ニ附ラレシニヤ 中興開山ヲ聖永トイフ 永享三年(1431年)2月24日示寂ス 末寺三十二ヶ寺 門徒二十六ヶ寺ヲ統ヘ司トレリ(略)
本堂 御成ノ時御膳所ナリ 本尊ハ不動ノ坐像ニテ長一尺七寸五5分 良弁ノ作 外ニ四大明王ノ四体ヲ安ス 木ノ立像ニテ長二尺三寸五分 願行ノ作ト云 古位牌一基アリ 碑面ニ云将軍頼義公信信海将軍義家公信了ト彫リテアリ(以下略)
(塔頭 玉泉寺)
境内東南ニアリ 本尊弘法大師木ノ坐像ニテ長二尺五寸 願行ト云ヘル作 什物 弘法大師畵像二軸 愛染明王ノ畵像一軸 右三軸トモ弘法大師ノ筆スル所ナリト云
(三重塔)
当寺ヨリ二町ホト東ノ方ニアリ三間半四面高サ五丈三尺五智如来ノ木像ヲ安ス
((中野村)氷川社)
村内寶仙寺ノ持

『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫) 中野寶仙寺』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載)
-------------------------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門-1


【写真 上(左)】 山門-2
【写真 下(右)】 寺号標
東京メトロ丸の内線「中野坂上」駅からほど近い職住学混在エリアに広大な山内を構えています。
青梅街道の「宝仙寺前」交差点から北に向けてまっすぐ伸びる道は、かつての参道だったのでは。
周囲を占める宝仙学園の創立者は宝仙寺第50世住職富田敦純大僧正で、昭和10年東京では初めての仏教系の保育者養成校・仏教保育協会保姆養成所(現・こども教育宝仙大学)が創始です。
公式Webには「弘法大師の『綜藝種智院』を模範に大師の思想を教育の根底におきました。」とあります。
山門は切妻屋根本瓦葺三間一戸の八脚門で、両脇間に迫力の仁王尊像を安置。
山門からしてすでに名刹の風格をただよわせています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 見返り地蔵&六地蔵
境内案内は公式Webにも掲載。
山門の先左手に寺号標、鐘楼、中野町役場跡碑、見返り地蔵&六地蔵、石臼塚、八十八大師塔、三重塔、御影堂とならびます。


【写真 上(左)】 石臼塚
【写真 下(右)】 三重塔
石臼塚は蕎麦挽きの石臼の供養塚。
そばを流れる神田川には江戸期水車が置かれて蕎麦粉が挽かれ、一大消費地・江戸に向け盛んに玄蕎麦が送られて、この地の蕎麦粉は「中野蕎麦」と呼ばれ名を馳せたとの由。
機械化で使われなくなった大量の石臼を見られた当山第50世住職富田敦純大僧正が「人の食のために貢献した石臼を大切に供養すべき」として建立されたものです。
当山の三重塔は、寛永十三年(1636年)に塔ノ山の飛び地境内(現・区立第十中学校(中野東中学校))に建立され、戦災で焼失した三重塔を平成4年に飛鳥様式で再建したもので、高さは約20メートル。
堂内には大日如来を中心とした胎蔵界五佛が奉安されています。
『新編武蔵風土記稿』には「(三重塔)当寺ヨリ二町ホト東ノ方ニアリ三間半四面高サ五丈三尺(約16m強)五智如来ノ木像ヲ安ス」とあり、区立第十中学校(中野東中学校)は当山からほぼ二町(約220m)ほどにあるので、この三重塔を再建とみられます。
ただし、風土記稿三重塔奉安の五智如来(=金剛界五佛/大日如来・阿閦如来・薬師如来・宝生如来・観自在王如来(ないし阿弥陀如来)、不空成就如来(ないし釈迦如来)に対し、こちらの三重塔は胎蔵界五佛(大日如来、宝幢如来、開敷華王如来、無量寿如来、天鼓雷音如来の奉安となっています。
なお、『江戸名所図会』によると、中野周辺は「中野七塔」と呼ばれ、塔が多いことで知られていたようです。
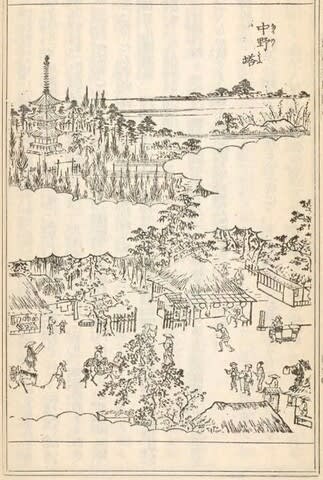
『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫) 中野塔』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載)


【写真 上(左)】 御影堂
【写真 下(右)】 日輪弘法大師
御影堂は三間四方の宝形造本瓦葺身舎柱朱塗りの整った堂宇で、堂宇御本尊の日輪弘法大師座像の高さは後背まで入れると約3メートル。
堂前説明書には「脱活乾漆という漆と麻布で作られておりこの技法でこのような大きな佛像は壱千年以上も絶えて作られておりませんでした。」とある稀少な尊像です。
御影堂は開扉されている時とされていないときがあり、21日は開扉されていたのでご縁日(月御影供)のみの御開扉かもしれません。
『新編武蔵風土記稿』には「(塔頭 玉泉寺)境内東南ニアリ 本尊弘法大師木ノ坐像ニテ長二尺五寸 願行ト云ヘル作 什物 弘法大師畵像二軸 愛染明王ノ畵像一軸 右三軸トモ弘法大師ノ筆スル所ナリト云」とあります。
宝仙寺塔頭玉泉寺の御本尊は伝・願行作の弘法大師坐像ですが、御影堂の日輪弘法大師坐像とは像高が異なるので、別個の尊像かと思います。
ただ「弘法大師畵像二軸 弘法大師ノ筆スル所ナリト云」というただならぬ記載があり、もともとお大師さまとゆかりのふかい寺院であったことがうかがえます。
立地は府外ながら弘法大師や八幡太郎源義家公ゆかりの名刹で、その流れから御府内霊場札所に迎えられたのでは。


【写真 上(左)】 弘法大師碑
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造本瓦葺で大棟に金色の鴟尾を置き、身舎の柱梁は朱塗りで華々しいイメージ。
向拝柱はなく、向拝見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
こちらには御本尊の不動明王を中心に五大明王が奉安され、関東三十六不動尊霊場第15番札所となっています。
本堂向かって右手は大書院で、御朱印はこちらで拝受できます。
大書院裏手の白玉稲荷は、寺号の由来となった宝珠を祀った祠とのことです。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 鐘楼
山門右手の近代建築は大師堂で、教化活動のお堂とのこと。
御朱印は御府内霊場、関東三十六不動尊霊場、そして日輪弘法大師の3種類が授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は弘法大師のお種子「ユ」(蓮華座)。揮毫は「日輪弘法大師」で右上に「府内八十八ヶ所 第十二番」の札所印。左下には寺号揮毫と寺院印が捺されています。
御府内霊場中5つしかない貴重なお大師さまの単独揮毫御朱印のひとつです。
〔 関東三十六不動尊霊場第15番の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
〔 日輪弘法大師の御朱印 〕

以下、つづきます。
(→ Vol.4)
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-2
Vol.-1Bからのつづきです。
■ 第4番 永峯山 瑠璃光寺 高福院(こうふくいん)
品川区上大崎2-13-36
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第4番
司元別当:誕生八幡神社(上大崎)
授与所:庫裡
当山の由緒沿革については、詳細な山内掲示(略縁起)があります。
高福院はもと高野山金剛峰寺の塔頭の一院とされます。
高野山開創の際、弘法大師は鎮守として山内各処に弁財天を祀られました。
高野山が疲弊して資糧が乏しくなったとき、弁天様が宝舟を引かれて来臨され山徒を救い給うたことから、その高福に因み高福院が建立されたといいます。
(高野山古図には、現在の金剛峰寺の右隣に高福院の名が見えるとのこと)
寛永年間(1624-1644年)、松平讃岐守侯は当地に下屋敷造営の際、讃岐の偉人である弘法大師の御寺建立の旨を高野山に要請しました。
これを受けて高野山高祖院の良尊和尚が、高福院の寺号と船引の弁天様さまを奉持され開創されたのが当院の縁起とされます。
開創当初は江戸に二箇所あった高野山在番所の控寺として、ゆかりの僧侶方の菩提所としても栄えたといいます。
しかし明和九年(1772年)、行人坂の大火ですべてが灰燼に帰してしまいました。
また、『寺社書上』には、大崎村長峰町、高野山門主無量寿院末、開山は阿遮●良尊(延宝三年(1675年)入滅)、中興開山は阿遮●實辨(宝暦十二年(1762年)入滅)、御本尊は大随求明王とあります。
大随求(だいずいく)明王は大随求菩薩とも呼ばれ、観世音菩薩の変化身とされます。
多くは関西の寺院で奉安され、江戸での奉安例は少ないかもしれません。
龍光山 正寶院(飛不動尊)公式Webには「苦厄を除き、悪を消す菩薩です。戦乱や嵐を治めることから子授けまで、幅広い功徳を持つ菩薩です。」とあります。
現在の本堂は、天保改革で知られる水野越前守忠邦侯が千駄ヶ谷穂田の屋敷内に建立、天保十五年(1844年)第十三世惠玉和尚が拝領して移築と伝わります。
明治の廃仏毀釈で一時疲弊したものの、歴代和尚の尽力により再興しています。
ことに目白僧園の雲照律師に提撕を受けられた第十五世浄識和尚は、お大師さまを背中に負うて托鉢しつつ布教され、多くの人々が檀家に加わったといいます。
雲照律師は、近衛文麿卿の父で第3代貴族院議長の近衞篤麿卿が東寺から招聘しているので、浄識和尚と近衛家もわかりがあったのかもしれません。
高田老松町に建立された目白僧園(雲照寺・吉祥院)は、のちに練馬・南田中に移転し、現在は雲照山 吉祥院 十善戒寺を号す真言宗東寺派寺院です。
目白僧園は、弘法大師の綜藝種智院の思想にならい、仏教精神に基づく庶民学校(十善徳教学校)とする予定でしたが諸般の事情により開設には至りませんでした。
しかし、弘法大師の綜藝種智院のお考え(身分貧富に関らず学べる総合的な教育施設の設立)は雲照律師から第十五世浄識和尚へと受け継がれ、この点からもお大師さまとのゆかりふかい寺院とみられます。
また、猫のあしあと様の『東京都寺社案内』記載の『東京都神社名鑑』によると、明治維新前、高福院はそばの誕生八幡神社の別当でした。
誕生八幡神社は太田道濯公による筑後・宇美八幡勧請が創祀とされているので、高福院は太田道濯公ともゆかりがあったことになります。
(なお、誕生八幡神社は下大崎の雉子神社の摂社ですが、現在御朱印は授与されていません。)
『寺社書上』には、「八幡宮別当 高福院」と明記され、『誕生八幡宮略縁起』が記されていることからも、誕生八幡神社の別当であったことが裏付けられます。
-------------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 誕生八幡神社
住所は上大崎ですが、目黒駅にもほど近い白金側にあります。
このあたりは江戸時代、永峯六軒茶屋町と呼ばれましたが、白金方面からつづく馬の背状の尾根上にあるため「永峯」、目黒不動尊への参詣道にあたり茶屋が六軒あったので、このように呼ばれたといいます。
『東京23区凹凸地図』(昭文社)をみると、高福院はみごとに目黒駅東の台地上にのっており、そこから目黒駅を越え行人坂を下ると目黒不動尊に至ります。
(ちなみに、この『東京23区凹凸地図』は都内の高低差がばっちりわかるので、御府内霊場巡拝時に持参すると面白いです。)


【写真 上(左)】 寺号標と門柱
【写真 下(右)】 山内
目黒通りに面し、誕生八幡神社と並ぶかたちで参道入口。
参道は広くはないものの、門柱の先はそれなりの広さがあります。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶏の彫刻。
向拝は障子扉で見上げに院号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「本尊 大日如来」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
■ 第5番 金剛山 (寶幢寺) 延命院
(えんめいいん)
港区南麻布3-10-15
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第5番、御府内二十八不動霊場第28番
司元別当:赤羽稲荷社?
授与所:庫裡
寛永年間(1624-1643年)に應圓阿闍梨によって開基(法印秀圓(慶安三年(1605年 )寂)の開山とも)。
当初は麻布本村町内新町にありましたが、寶永年間(1704-1711年)、五世住職のときに当初に移転したようです。
寶永年間(1751-1764年)、御府内霊場の札所になったといい、文化八年(1811年)、当時の御住職が四国第5番札所地蔵寺から弘法大師御作の子安地蔵尊を遷したとも伝わります。
以前は三田の?赤羽稲荷社の別当であったという史料があります。
【史料】
■ 『麻布區史』
智山派、智積院末。本尊金剛界大日如来。草創の年代不詳『續府内備考』には本村の内新町と云ふ處に有ったのを寶永年間(1704-1711年)に現在の地へ移建したと記してゐる。開山は法印秀圓(慶安三年(1650年)九月二十三日寂)である。舊幕地代は赤羽稲荷の別當であった。大師堂は府内八十八ヶ所札所の第五番霊場になってゐる。寺内に寶禄稲荷と呼ぶ小祠がある。柔術家戸塚彦右衛門英證の墓がある。
■ 『寺社書上』
「本寺 醍醐三寶院直末 麻布本村町 新義真言宗 開闢起立の儀の年代不知 麻布本村町内新町から●所(略) 当寺五世寶永年中(1704-1711年)当所●時移し(略) 本尊金剛界大日如来 両祖大師(弘法大師 興教大師) 阿弥陀如来 地蔵尊 境内弁天堂 弁財天 不動尊」等の記述が見えます。
【 江戸期の延命院周辺 】 ※「延明寺」とあります。
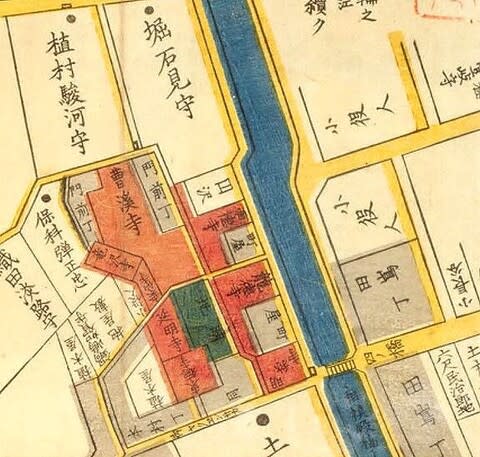
※ 『江戸切絵図/麻布絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
-------------------------


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 札所標-1
東京メトロ「白金高輪」駅から徒歩7分ほど。
「白金高輪」駅から寺下の明治通りにかけては低平地で、明治通りは東西に流れる渋谷川に沿って走っています。
「四の橋」あたりから北に絶江坂を登るとすぐ右手に見えてきます。
位置的には渋谷川から元麻布の高台への登り口にあたり、西側には「薬園坂の窪地」もあって複雑な地形です。
このあたりは寺町といってもいいほど寺院がたくさんありますが、札所は少なく御朱印授与寺も少なくなっています。


【写真 上(左)】 札所標-2
【写真 下(右)】 不動尊霊場の札所標
主門はフェンスで閉じられていますが、脇門から入れます。
門脇に建つ札所標には「第五番 子安●● 阿波國地蔵寺移 弘法大師之御作」とあります。
別に「御府内廿八ヶ所内 第廿八番 不動明王」の札所標がありますが、こちらは御府内二十八不動霊場第28番のものかと思われます。
寺号標にも「不動尊霊場第廿八番」とあるので間違いないかと思いますが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。
「ニッポンの霊場」様Webによると、御府内二十八不動霊場の開創は明治42年。
初番は深川不動堂、第28番結願は当山になります。
『寺社書上』によると当山に立像の不動尊が奉安されていたのは確かですが、由緒等は記載されていません。
御府内二十八不動霊場には橋場不動尊、浅草寿不動尊、赤坂不動尊などのお不動様が名を連ねているので、結願の不動尊と定められたからには、開創時には著名な不動尊であったのかもしれません。
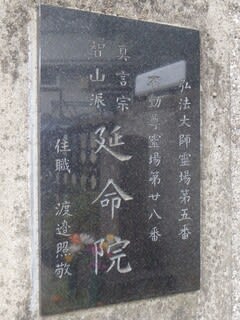

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺妻入で妻側に切妻屋根の向拝を設けています。
なので、千鳥破風をふたつ重ねたようなめずらしい意匠となっています。
シンプルな水引虹梁。妻の拝みに猪の目懸魚。向拝上部に院号扁額を掲げています。
向かって右手の花頭窓が意匠的に効いています。
御朱印は庫裡にて拝受しますが、ご不在時には書置を拝受できる模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫はお種子、「大日如来」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
■ 第6番 五大山 不動院
(ふどういん)
港区六本木3-15-4
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第6番
司元別当:
授与所:堂内、もしくは大安楽寺(日本橋小伝馬町)
六本木にある古義真言宗寺院です。
開山縁起は詳らかでないですが、山内掲示の縁起書、下記の史料などから由緒来歴を追ってみます。
伝承では家康公入府以前の開山とされ、当初は麹町平川町(現在の赤坂御門跡「虎屋」付近)にありましたが、万治元年(1658年)官命により寺地を収公され、当時の住職で中野寶仙寺の住職を兼ねていた玄海法印が現在地(麻布六軒町)を代地として賜り移したといいます。
本寺は大和國長谷小池坊。
小池坊は天正十三年(1585年)、焼き討ちにあった紀州の根来寺の能化坊を豊臣秀長の招きを受け長谷寺に入られた専譽僧正が再興されたと伝わります。
『寺社書上』に当山が「新義真言宗」と記されているのは、このような本寺の由来によると思われます。(現在は古義真言宗系の高野山真言宗)
また、『御府内寺社備考』によると孔子とのゆかりもあったようです。
当地に移転した当初の境内地は狭隘だったため、玄海法印は幕府に願い出て、近隣の沼地を埋め立て境内拡張の旨の許可を得ました。
しかし、その沼地の池には悪蛇が棲みついて近隣の住民を悩ませていました。
玄海法印は先祖と仰ぐ武田信玄公が自らの甲冑に奉持していた十一面観世音菩薩を本地佛として稲荷大明神を勧請され、祈りを捧げてこの悪蛇を調伏しました。
人々は玄海法印の験力に驚嘆し、こぞって帰依して沼地の埋め立てに協力したそうです。
また、近隣の女性が「麹町にあった不動院の鎮守神を当地の不動院にも祀り鎮守とせよ」との稲荷大明神のお告げを受け、兒稲荷大明神が祀られたという伝承もあります。
この伝承については、『兒稲荷大明神縁起』に詳細が記されています。
武田信玄公の信仰佛としては不動明王、毘沙門天、薬師如来などが知られていますが、十一面観世音菩薩は筆者の知る限りでは初出で、これは貴重な情報かもしれません。
(関連記事:【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】)
江戸時代には「麻布不動坂の一願不動さん」「六軒町の目黄不動」とも呼ばれ、広く庶民の信仰を集めたといいます。
「江戸五色不動」の目黄不動尊は、平井の最勝寺と三ノ輪の永久寺とされていますが、当山を目黄不動尊とする説もあるようです。
もともとの目青不動尊と伝わる麻布谷町にあった勧行寺(ないし正善寺)に近いため、こちらとの関連を示唆する説もみられます。
明治の初年、不動院の住職は日本橋小伝馬町の牢獄跡地の浄化を祈念し、寺院建立を発願。
大倉財閥、安田財閥などの支援を受け、大安楽寺を創建しました。
大安楽寺は高野山真言宗準別格本山の格式ですから、当山も相応の寺格を有していることがうかがえます。
【史料】
■ 『麻布區史』
五大山不動院 市兵衛町二ノ五七
古義眞言宗高野派 金剛峯寺末。本尊不動明王。創立も開山も明らかでないが、萬治元年(1658年)に麹町平川の邊から移って来たと云ふ。中興開山は玄海。境内にもと兒(チゴ)稲荷(本地佛十一面観音 銅像)と呼ぶ小祠があり、非常に栄えていゐたが明治二年神佛分離で廢棄された。
■ 『寺社書上』
大和國長谷小池坊末 麻布六軒町 新義真言宗 旧地●麹町平川町 開山開闢●●●旧記も無し 中興 玄海法印武州中野村宝仙寺の住職●麹町の不動院致兼(略) 旧地麹町平川に有し(略)万治元年(1658年)当地に引移す 本尊不動明王 脇立 矜羯羅童子 脇立 制吒迦童子 右不動尊は弘法大師の作と●伝(略) 四大明王 普賢菩薩 弘法大師 鎮守堂(兒稲荷大明神 本地佛十一面観世音菩薩 武田信玄公甲冑に納●を当院中興玄海法印は武田家由緒し者故 持念佛を鎮守し本地佛を勧請)(略) 弁財天」
(兒稲荷大明神縁起 不動院)
不動院之兒稲荷神社ハ者本地十一面観世音 其古当院ノ中祖玄海法印住職●武江中野ノ寶仙寺以兼セリ 麹町不動院然ルニ 玄海俗姓武田家ノ末葉ナルカ故ニ 信玄公公所ノ帯スル甲冑ニ十一面観世音ノ尊像 玄海傳得之如●為●神社本地佛ト而常ニ信仰シヌ
■ 『御府内寺社備考』
不動堂ハ往古麹町栖岸院にありし 寛永の頃当院へ移●俗人云往昔孔子堂といふ 孟子乃不動●●を本尊とし孔子堂といふ 近年孔子山五臺山といふ
【 江戸期の不動院周辺 】

※ 『江戸切絵図/赤坂絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
-------------------------
都内有数のエンタメエリア・六本木は実はさりげに寺院が多く、裏通りに入ると一種の寺町の様相を呈しています。
なかでもロアビル角の「六本木五丁目」交差点を北に下った窪地「共同墓地の窪地」には六本木墓苑があり、華やかな六本木の一画とは思えない異次元感を発しています。
六本木は土地の起伏の激しいところで、東の溜池方面から青山(六本木)通り沿いに走る低地は「共同墓地の窪地」に至り、南の麻布十番方面から入る旧吉野川の谷筋は「北日ヶ窪」と呼ばれ、芋洗坂を経て六本木駅に至ります。
(この「北日ヶ窪」には北日ヶ窪団地がありましたが、再開発で六本木ヒルズに生まれかわっています。)
六本木通りは市三坂をのぼって「六本木」駅の高台に至り、外苑東通りは一貫して尾根筋、六本木ヒルズ前の麻布十番通りは一貫して谷筋を走ります。
この起伏の激しさは麻布十番通りが六本木通りを麻布トンネルでアンダーパスしていることからもわかります。
なんだかタモリ氏のようになってきたので(笑)、本題に戻ります。


【写真 上(左)】 不動坂と不動院
【写真 下(右)】 外観
不動院は六本木墓苑の窪地から不動坂をのぼった途中右手にあります。
上の伝承にある沼地とは、この「共同墓地の窪地」を指しているのでは。
「六本木」駅から近いですが、アクセスは「六本木一丁目」駅からの方が楽かもしれません。
不動坂まわりは住宅街で、不動院はこの細い不動坂に面した平成11年(1999年)建立の3階建のビル内にあります。
外観は瀟洒なビルですが、3階に掲げられた金色の「真言宗輪宝」、1階エントランス(向拝)の山号扁額、そして「五大山 不動院」と刻まれた門柱が、歴とした寺院であることを示しています。


【写真 上(左)】 不動明王
【写真 下(右)】 稲荷神
館外向かって右には蓮の葉に囲まれた石造の不動明王立像(御前立?)
その横には赤い鳥居の稲荷神が祀られています。
鳥居扁額の文字が薄くて確信はもてないのですが、境内縁起書には「二月初午 児稲荷大明神初午祭(商売繁盛・火坊の祈願を致します)」とあるので、こちらは由緒ある兒稲荷大明神かもしれません。


【写真 上(左)】 エントランス(向拝)
【写真 下(右)】 扁額
エントランス(向拝)は格子ガラスの扉で、見上げに山号扁額。左右に不動明王の御真言と御府内霊場の札番&御詠歌が掲げられています。


【写真 上(左)】 御真言
【写真 下(右)】 札番&御詠歌
エントランスは通常は閉まっていますが28日の御縁日など、特定の日は開かれていることがあります。
通常は、御朱印は日本橋小伝馬町の大安楽寺でいただくことになりますが、開扉日はこちらで拝受できます。
開扉日は荘厳な堂内まで上げていただけ、お不動様に間近で参拝できるので、日を選んでの参拝がベターかと思います。
(ただしお不動様は、中央のお厨子のなかに御座のようです。)
現在は不明ですが、新型コロナ禍前には28日に月並祈願会が勤修され、年に何日かは「不動院寄席」が催されていたようです。
第5番までは比較的寺院らしいたたずまいでしたが、こちら第6番は近代的なビルで都会の寺院ならではのイメージ。
さすがに東京の霊場、御府内霊場の札所です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕 ※いずれも不動院で開扉時に拝受。
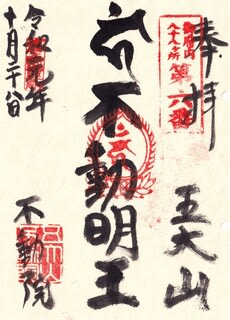

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は金剛界大日如来のお種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫はお種子、「不動明王」で札所印、「南無大師遍照金剛」の印と寺院印が捺されています。
■ 第7番 源秀山 永松院 室泉寺
(しつせんじ)
渋谷区東3-8-16
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第7番、弁財天百社参り第27番
司元別当:
授与所:庫裡
『札所めぐり』および『新編武蔵風土記稿』より、縁起由緒をまとめてみます。
当初は真宗西本願寺末の真宗寺院として芝金杉にありました。
元禄十三年(1700年)旗本松平外記忠益が当所にあった抱屋敷を和泉国神鳳寺中興の快圓(恵空)比丘(和上)に寄附してここに引移し、真言律宗に改宗して神鳳寺の宿寺としたといいます。中興開基は松平外記忠益、開山は快圓(恵空)比丘。
元禄十三年(1694年)快圓和上により開山、元禄十三年(1700年)五代将軍綱吉公の発願により開山という伝承もあるようです。
松平外記忠益は、五井松平家(現在の愛知県蒲郡市五井町を発祥とする松平氏庶流)9代の松平忠益と思われます。『Wikipedia』によると、父の松平伊耀は五千五百石の大身の旗本(寄合)で下総国海上郡飯沼に二千石の知行地をもち飯沼陣屋の主。
忠益はその家督を継いだとあるので、やはり大身の旗本であったと思われます。
縁起由緒からすると、松平忠益と和泉国神鳳寺の間には密接な関係があったと思われますが、Webからは追い切れませんでした。
また、五井松平家の菩提寺は銚子にある等覚寺で曹洞宗。
なので五井松平家と真言律宗に格別のゆかりがあったということも考えにくいです。
和泉国神鳳寺は、和泉国一宮の大鳥大社(大阪府堺市西区鳳北町)の別当であった大鳥山勧学院神鳳寺とみられます。
開山は和銅元年(708年)とも伝わる古刹で、快圓恵空が入り寺勢を拡大したといいます。
『江戸仏教の戒律思想(一)』(上田霊城氏、PDF)には、「真政円忍、快円恵空(1622-1712年)によって大鳥神鳳寺派が成立し、同派の玄忍慧海を証明として受具した覚彦浄厳が真言律宗を唱え、生駒宝山寺宝山湛海、円珠庵契沖も夫々真政・快円について受具している。」とあり、快圓恵空が真言律宗の成立において重要な役割を果たされていたことがわかります。
江戸における真言律宗は、浄厳律師覚彦が創建した湯島霊雲寺を総本山とする真言宗霊雲寺派への流れと、その他の真言宗派への流れがみられます。
室泉寺は真言律宗の寺院として再興されましたが、現在は古義の高野山真言宗に属しています。
しかし、『新編武蔵風土記稿』には「江戸湯嶋霊雲寺末」とあり、法統について複雑な経緯があったのかもしれません。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』
真言律宗 和泉國一ノ宮大島山神鳳寺宿寺ニテ 江戸湯嶋霊雲寺末ナリ 源秀山永松院ト号ス 当寺昔は芝金杉ニアリ 浄土真宗西本願寺末ニテ 同所壽林寺ヨリ兼帯セシヲ 元禄十三年(1700年)九月旗下ノ士松平外記忠益当所ノ抱屋敷ヲ 神鳳寺中興快圓比丘ニ寄附シ 彼寺名ヲ爰ニ引移シ 改宗シテ宿寺トナセリ 故ニ忠益ヲ開基トス(略)開山快圓ハ正徳二年(1712年)二月八日寂 本尊は彌陀 脇士ニ観音地蔵ヲ安ス
護摩堂 不動立像長二尺七寸 愛染坐像長二尺五寸ナルヲ安ス 共ニ南都招提寺開山鑑真和尚ノ弟子支卓律師ノ作ト云
鎮守社 金毘羅 大鳥明神、住吉
辨天堂
【 江戸期の室泉寺周辺 】

※ 『江戸切絵図/青山渋谷絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
-------------------------


【写真 上(左)】 山門下
【写真 下(右)】 山門
「恵比寿」駅から5分ほどの住宅街のなかにあります。
渋谷川沿いの低地から広尾・青山の台地にさしかかるこのあたりにはいくつかの寺院が点在しています。
やや奥まった立地で、山内は落ち着いた雰囲気です。
街路から数段のぼった山門は切妻屋根桟瓦葺のおそらく薬医門で左右に門塀をめぐらし、見上げに山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 源秀地蔵堂
山内には大聖歓喜天堂、源秀地蔵堂、そして地主神とみられる稲荷神のお社。
源秀地蔵尊は、身体健全に霊験あらたかと伝わります。


【写真 上(左)】 稲荷神
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑


【写真 上(左)】 修行大師像と山内
【写真 下(右)】 修行大師像
端正な修行弘法大師像が御座され、塔状の立派な札所碑もありました。
お砂踏み場よこの築山は高野山を模しているそうです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は宝形造ないし寄棟造銅板葺で身舎は朱色に彩られて華やかな印象。
向拝柱はなく比較的シンプルなつくりです。
真言律宗系の寺院の御本尊は大日如来が多いですが、こちらの御本尊は阿弥陀如来です。
御朱印は、庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫はお種子、「阿弥陀如来」で札所印と寺院印が捺されています。
■ 第8番 海岳山 大乗院 長遠寺
(ちょうおんじ)
大田区南馬込5-2-10
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第72番、大東京百観音霊場第43番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第78番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第11番
司元別当:馬込村八幡社ほか
授与所:寺務所
大田区馬込にある名刹で、複数の札所を兼務されています。
寺伝によると、馬込村字堂寺の地に天仁元年(1108年)宥尊上人が開山草創。
(『新編武蔵風土記稿』には、村の旧記として定海という僧(元弘二年(1332年)寂)が草創とあり。)
文亀二年(1502年)火災に遭い当地に移転、元禄年間(1688-1704年)に快慶法印が中興と伝わります。
御本尊の不動明王は、馬込不動尊として広く知られています。
行基菩薩の御作と伝わる木造十一面観音菩薩立像(通称「鎌作観世音」)は、大田区の文化財に指定されています。
山内掲出の観音様の説明書に「もと上大崎六軒茶屋の光雲寺にあった」とあること、府外の馬込にあることが気になり、江戸八十八ヶ所霊場第8番を当たってみると、第8番はまさに六軒茶屋の盤谷山光雲寺でした。
光雲寺は『寺社書上』に収録されており、場所は(白金)六軒茶屋町、宗派は新義真言宗、馬込村長遠寺末とあります。
光雲寺は明治8年(1875年)廃寺となっています。
江戸期の江戸八十八ヶ所第8番ないし御府内霊場第8番光雲寺の札所本尊はおそらく御本尊の千手観世音菩薩であったと考えられ、明治8年(1875年)光雲寺が廃寺となった際に、御本尊の千手観世音菩薩は本寺の馬込長遠寺に遷られ、同時に御府内霊場第8番札所も長遠寺に替わったのではないでしょうか。
御府内霊場の札所本尊は御本尊の例がほとんどですから、そのときに第8番の札所本尊は長遠寺の御本尊である不動明王に替わったのでは。
ただし、行基菩薩作とも伝わる光雲寺の御本尊・千手観世音菩薩は長遠寺でも「鎌作観世音」として手篤く奉安され、現在も人々の信仰を集めているのではないでしょうか。
『江戸名所図会』には、こちらの千手観世音菩薩は行基菩薩が巡錫先の信州更級郡で天人が鎌をもって彫刻し、行基菩薩に授けたものとあります。
また、行基菩薩が巡錫先の信州更級郡で一刀三礼してみずから鎌斧で彫り上げられた尊像という伝えもあり、「鎌作(かまつくり)観世音」と尊称されています。
『御府内寺社備考』には、光雲寺には行基菩薩が使われた鎌斧が寺宝として所蔵されているとあります。
「鎌作観世音」は大田区の文化財に指定。
山内説明板には平安時代十世紀頃の作と考えられ、もとは千手観世音菩薩と考えられるが千手を失い、文化財登録としては十一面観世音菩薩立像とされていること、もと上大崎六軒茶屋の光雲寺にあったが、明治初年に廃寺の際、長遠寺に移されたことなどが記されています。
品川区のWeb資料には「(目黒不動尊へ行く「目黒道」「白金通り」)の道筋の六軒茶屋町(現在の上大崎2・3丁目の目黒通り沿い)には、鎌作り観音・光雲寺(明治8年〔1875年〕に廃寺となる)がありました。鎌作り観音から同じ道沿いの永峯町には誕生八幡宮(現在の誕生八幡神社)と別当寺の高福院がありました。この3つの社寺は一緒に挿絵に描かれています。」とあり、江戸八十八ヶ所第8番の光雲寺は、同第4番高福院のそばにあったようです。
(「『江戸名所図会』を読む」様のWebにて詳しく解説されており、光雲寺は高福院のほぼ隣にあったことがわかります。)
【 光雲寺と高福院、行人坂(目黒不動尊方向)の位置関係 】

※ 『江戸切絵図/目黒白金辺図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
六軒茶屋町は御府内で『寺社書上』に記載され、馬込は府外で『新編武蔵風土記稿』に収録されています。
こうしてみると、御府内霊場の札所はやはり原則御府内で、現在、旧府外にある札所は移転統合など、なんらかの変遷を辿った例が多いのではないでしょうか。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』
除地六畝 (馬込村八幡社)社地ノ北ニ隣レリ 新義真言宗 山城國醍醐三寶院ノ末 海岳山大乗院トと号ス 村ノ舊記ニ定海ト云僧 当寺ヲ草創シテ後元弘二年(1332年)ニ寂セリト見ユ サレハ此人開山ナルヘシ 今寺ニテ開山トスルハ定尊法印ナリ 此法印其事歴寂年ヲ傳へサレハ 何ノ頃トモ云カタケレト 思フニ中興ノ僧ナルニヤ 後元禄(1688-1704年)ノ頃快慶法印ト云僧ノ住シ時 当寺ヲ興記(ママ)シテ檀林寺格トセシニヨリ 今ハ此法印ヲ中興開基トス(略) 本尊不動尊ノ座像ヲ安ス 門ハ客殿ノ正面ニアリ海岳山ノ三字ヲ扁ス
■ 『寺社書上』
(光雲寺)
馬込村長遠寺末 六軒茶屋町 盤谷山 光雲寺 新義真言宗
本尊 千手観世音菩薩 立像丈三尺 但行基菩薩作 延宝八年六月三日信州更級郡梵天平山盤谷山出現千手観音 元禄五年定光雲寺右●奉納石室内●縁起 開山光雲次第書(略)
■ 『御府内寺社備考』
起立ノ儀●元禄五年十一月中意運(略)草創 開山権大僧都智●意運 寺寶 鎌一挺 斧一挺 右ハ行基菩薩●●し●右を以本尊千手観音彫刻し●
■ 『江戸名所図会』
(鎌作観世音)
(妙見大菩薩)西の方一町半斗 向ふ側 六軒茶屋町の角 真言宗光雲寺にあり 相傳ふ 神亀年間(724-729年)行基菩薩諸国遊化の頃 信州更級に始て掛錫し●●ふに 平山と云ふところの池中より 此本尊出現あ● 又空中より化人あらはれ 鎌と御衣●を持ちて降臨し●ひ 彼観音の尊像を彫刻し行基に授け●ふ 此本尊是なり
-------------------------
最寄りは都営浅草線「西馬込」駅。
第二京浜に面した区画ですが、山門は第二京浜の反対側からまわりこむかたちで、周囲は落ち着いたたたずまいです。
向かって左手に馬込八幡神社が御鎮座。
旧馬込村総鎮守で旧村社。岩清水八幡宮の分霊を勧請して創祀され、江戸期は長遠寺が別当でした。
馬込村総鎮守だけあって神さびた境内。御朱印は授与されていないとの掲示がありました。


【写真 上(左)】 馬込八幡神社
【写真 下(右)】 馬込八幡神社の掲示


【写真 上(左)】 門柱から
【写真 下(右)】 山門
長遠寺は広い寺地をもち、名刹にふさわしいたたずまいをみせています。
街路からまずは門柱、左右駐車場の参道の先に、両脇に板塀を配した切妻屋根銅板葺の重厚な山門。
控柱が4本あるので四脚門にも見えますが、おそらく医薬門ないし高麗門かと思われます。
見上げに山号扁額、右門柱に文字が消えかかった札所板が掲げられていますが、かすかに「七十二番札所」と読めるので、これは玉川八十八ヶ所霊場の札所板と思われます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 玉川霊場札所板
こちらは御府内霊場、玉川霊場いずれの御朱印も授与されていますが、それぞれ系統の異なる弘法大師霊場なので、玉川霊場の巡拝は改めた方がベターかと思います。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑
山内は広々と明るく清掃が行き届き、気持ちのよい参拝ができます。
「新大田区百景」にも選ばれています。
参道脇には御府内霊場の立派な札所石碑がありました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面が本堂。
寄棟造銅板葺で瓦葺の向拝を附設した、やや変わった意匠です。
水引虹梁両端に見返り獅子の見事な木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に霊鳥の彫刻を配して整った意匠です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 見事な木鼻


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 玉川霊場の奉納額
本堂軒下には、多摩川(玉川)八十八ヶ所霊場の奉納額が掲げられています。
メジャー霊場2つの札所を兼ねられているため、ご対応は手慣れておられ、またとてもご親切です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳-1
主印は三寶印、揮毫は「本尊 不動明王」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
〔 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

内容は御府内霊場とほぼ同様です。
以下、つづきます。
(→ Vol.-3)
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
■ 第4番 永峯山 瑠璃光寺 高福院(こうふくいん)
品川区上大崎2-13-36
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第4番
司元別当:誕生八幡神社(上大崎)
授与所:庫裡
当山の由緒沿革については、詳細な山内掲示(略縁起)があります。
高福院はもと高野山金剛峰寺の塔頭の一院とされます。
高野山開創の際、弘法大師は鎮守として山内各処に弁財天を祀られました。
高野山が疲弊して資糧が乏しくなったとき、弁天様が宝舟を引かれて来臨され山徒を救い給うたことから、その高福に因み高福院が建立されたといいます。
(高野山古図には、現在の金剛峰寺の右隣に高福院の名が見えるとのこと)
寛永年間(1624-1644年)、松平讃岐守侯は当地に下屋敷造営の際、讃岐の偉人である弘法大師の御寺建立の旨を高野山に要請しました。
これを受けて高野山高祖院の良尊和尚が、高福院の寺号と船引の弁天様さまを奉持され開創されたのが当院の縁起とされます。
開創当初は江戸に二箇所あった高野山在番所の控寺として、ゆかりの僧侶方の菩提所としても栄えたといいます。
しかし明和九年(1772年)、行人坂の大火ですべてが灰燼に帰してしまいました。
また、『寺社書上』には、大崎村長峰町、高野山門主無量寿院末、開山は阿遮●良尊(延宝三年(1675年)入滅)、中興開山は阿遮●實辨(宝暦十二年(1762年)入滅)、御本尊は大随求明王とあります。
大随求(だいずいく)明王は大随求菩薩とも呼ばれ、観世音菩薩の変化身とされます。
多くは関西の寺院で奉安され、江戸での奉安例は少ないかもしれません。
龍光山 正寶院(飛不動尊)公式Webには「苦厄を除き、悪を消す菩薩です。戦乱や嵐を治めることから子授けまで、幅広い功徳を持つ菩薩です。」とあります。
現在の本堂は、天保改革で知られる水野越前守忠邦侯が千駄ヶ谷穂田の屋敷内に建立、天保十五年(1844年)第十三世惠玉和尚が拝領して移築と伝わります。
明治の廃仏毀釈で一時疲弊したものの、歴代和尚の尽力により再興しています。
ことに目白僧園の雲照律師に提撕を受けられた第十五世浄識和尚は、お大師さまを背中に負うて托鉢しつつ布教され、多くの人々が檀家に加わったといいます。
雲照律師は、近衛文麿卿の父で第3代貴族院議長の近衞篤麿卿が東寺から招聘しているので、浄識和尚と近衛家もわかりがあったのかもしれません。
高田老松町に建立された目白僧園(雲照寺・吉祥院)は、のちに練馬・南田中に移転し、現在は雲照山 吉祥院 十善戒寺を号す真言宗東寺派寺院です。
目白僧園は、弘法大師の綜藝種智院の思想にならい、仏教精神に基づく庶民学校(十善徳教学校)とする予定でしたが諸般の事情により開設には至りませんでした。
しかし、弘法大師の綜藝種智院のお考え(身分貧富に関らず学べる総合的な教育施設の設立)は雲照律師から第十五世浄識和尚へと受け継がれ、この点からもお大師さまとのゆかりふかい寺院とみられます。
また、猫のあしあと様の『東京都寺社案内』記載の『東京都神社名鑑』によると、明治維新前、高福院はそばの誕生八幡神社の別当でした。
誕生八幡神社は太田道濯公による筑後・宇美八幡勧請が創祀とされているので、高福院は太田道濯公ともゆかりがあったことになります。
(なお、誕生八幡神社は下大崎の雉子神社の摂社ですが、現在御朱印は授与されていません。)
『寺社書上』には、「八幡宮別当 高福院」と明記され、『誕生八幡宮略縁起』が記されていることからも、誕生八幡神社の別当であったことが裏付けられます。
-------------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 誕生八幡神社
住所は上大崎ですが、目黒駅にもほど近い白金側にあります。
このあたりは江戸時代、永峯六軒茶屋町と呼ばれましたが、白金方面からつづく馬の背状の尾根上にあるため「永峯」、目黒不動尊への参詣道にあたり茶屋が六軒あったので、このように呼ばれたといいます。
『東京23区凹凸地図』(昭文社)をみると、高福院はみごとに目黒駅東の台地上にのっており、そこから目黒駅を越え行人坂を下ると目黒不動尊に至ります。
(ちなみに、この『東京23区凹凸地図』は都内の高低差がばっちりわかるので、御府内霊場巡拝時に持参すると面白いです。)


【写真 上(左)】 寺号標と門柱
【写真 下(右)】 山内
目黒通りに面し、誕生八幡神社と並ぶかたちで参道入口。
参道は広くはないものの、門柱の先はそれなりの広さがあります。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶏の彫刻。
向拝は障子扉で見上げに院号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「本尊 大日如来」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
■ 第5番 金剛山 (寶幢寺) 延命院
(えんめいいん)
港区南麻布3-10-15
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第5番、御府内二十八不動霊場第28番
司元別当:赤羽稲荷社?
授与所:庫裡
寛永年間(1624-1643年)に應圓阿闍梨によって開基(法印秀圓(慶安三年(1605年 )寂)の開山とも)。
当初は麻布本村町内新町にありましたが、寶永年間(1704-1711年)、五世住職のときに当初に移転したようです。
寶永年間(1751-1764年)、御府内霊場の札所になったといい、文化八年(1811年)、当時の御住職が四国第5番札所地蔵寺から弘法大師御作の子安地蔵尊を遷したとも伝わります。
以前は三田の?赤羽稲荷社の別当であったという史料があります。
【史料】
■ 『麻布區史』
智山派、智積院末。本尊金剛界大日如来。草創の年代不詳『續府内備考』には本村の内新町と云ふ處に有ったのを寶永年間(1704-1711年)に現在の地へ移建したと記してゐる。開山は法印秀圓(慶安三年(1650年)九月二十三日寂)である。舊幕地代は赤羽稲荷の別當であった。大師堂は府内八十八ヶ所札所の第五番霊場になってゐる。寺内に寶禄稲荷と呼ぶ小祠がある。柔術家戸塚彦右衛門英證の墓がある。
■ 『寺社書上』
「本寺 醍醐三寶院直末 麻布本村町 新義真言宗 開闢起立の儀の年代不知 麻布本村町内新町から●所(略) 当寺五世寶永年中(1704-1711年)当所●時移し(略) 本尊金剛界大日如来 両祖大師(弘法大師 興教大師) 阿弥陀如来 地蔵尊 境内弁天堂 弁財天 不動尊」等の記述が見えます。
【 江戸期の延命院周辺 】 ※「延明寺」とあります。
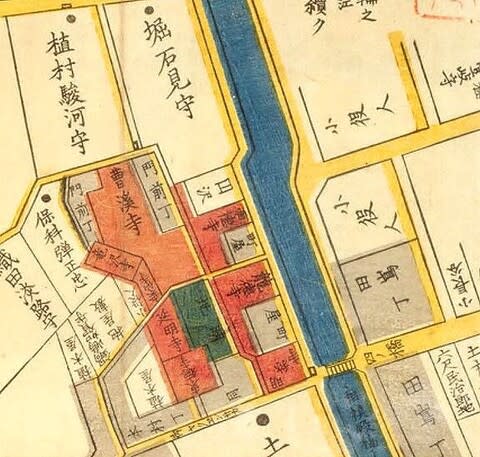
※ 『江戸切絵図/麻布絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
-------------------------


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 札所標-1
東京メトロ「白金高輪」駅から徒歩7分ほど。
「白金高輪」駅から寺下の明治通りにかけては低平地で、明治通りは東西に流れる渋谷川に沿って走っています。
「四の橋」あたりから北に絶江坂を登るとすぐ右手に見えてきます。
位置的には渋谷川から元麻布の高台への登り口にあたり、西側には「薬園坂の窪地」もあって複雑な地形です。
このあたりは寺町といってもいいほど寺院がたくさんありますが、札所は少なく御朱印授与寺も少なくなっています。


【写真 上(左)】 札所標-2
【写真 下(右)】 不動尊霊場の札所標
主門はフェンスで閉じられていますが、脇門から入れます。
門脇に建つ札所標には「第五番 子安●● 阿波國地蔵寺移 弘法大師之御作」とあります。
別に「御府内廿八ヶ所内 第廿八番 不動明王」の札所標がありますが、こちらは御府内二十八不動霊場第28番のものかと思われます。
寺号標にも「不動尊霊場第廿八番」とあるので間違いないかと思いますが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。
「ニッポンの霊場」様Webによると、御府内二十八不動霊場の開創は明治42年。
初番は深川不動堂、第28番結願は当山になります。
『寺社書上』によると当山に立像の不動尊が奉安されていたのは確かですが、由緒等は記載されていません。
御府内二十八不動霊場には橋場不動尊、浅草寿不動尊、赤坂不動尊などのお不動様が名を連ねているので、結願の不動尊と定められたからには、開創時には著名な不動尊であったのかもしれません。
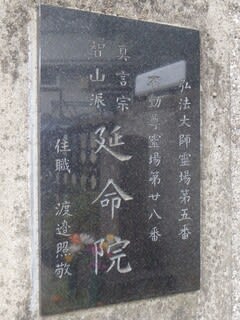

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺妻入で妻側に切妻屋根の向拝を設けています。
なので、千鳥破風をふたつ重ねたようなめずらしい意匠となっています。
シンプルな水引虹梁。妻の拝みに猪の目懸魚。向拝上部に院号扁額を掲げています。
向かって右手の花頭窓が意匠的に効いています。
御朱印は庫裡にて拝受しますが、ご不在時には書置を拝受できる模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫はお種子、「大日如来」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
■ 第6番 五大山 不動院
(ふどういん)
港区六本木3-15-4
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第6番
司元別当:
授与所:堂内、もしくは大安楽寺(日本橋小伝馬町)
六本木にある古義真言宗寺院です。
開山縁起は詳らかでないですが、山内掲示の縁起書、下記の史料などから由緒来歴を追ってみます。
伝承では家康公入府以前の開山とされ、当初は麹町平川町(現在の赤坂御門跡「虎屋」付近)にありましたが、万治元年(1658年)官命により寺地を収公され、当時の住職で中野寶仙寺の住職を兼ねていた玄海法印が現在地(麻布六軒町)を代地として賜り移したといいます。
本寺は大和國長谷小池坊。
小池坊は天正十三年(1585年)、焼き討ちにあった紀州の根来寺の能化坊を豊臣秀長の招きを受け長谷寺に入られた専譽僧正が再興されたと伝わります。
『寺社書上』に当山が「新義真言宗」と記されているのは、このような本寺の由来によると思われます。(現在は古義真言宗系の高野山真言宗)
また、『御府内寺社備考』によると孔子とのゆかりもあったようです。
当地に移転した当初の境内地は狭隘だったため、玄海法印は幕府に願い出て、近隣の沼地を埋め立て境内拡張の旨の許可を得ました。
しかし、その沼地の池には悪蛇が棲みついて近隣の住民を悩ませていました。
玄海法印は先祖と仰ぐ武田信玄公が自らの甲冑に奉持していた十一面観世音菩薩を本地佛として稲荷大明神を勧請され、祈りを捧げてこの悪蛇を調伏しました。
人々は玄海法印の験力に驚嘆し、こぞって帰依して沼地の埋め立てに協力したそうです。
また、近隣の女性が「麹町にあった不動院の鎮守神を当地の不動院にも祀り鎮守とせよ」との稲荷大明神のお告げを受け、兒稲荷大明神が祀られたという伝承もあります。
この伝承については、『兒稲荷大明神縁起』に詳細が記されています。
武田信玄公の信仰佛としては不動明王、毘沙門天、薬師如来などが知られていますが、十一面観世音菩薩は筆者の知る限りでは初出で、これは貴重な情報かもしれません。
(関連記事:【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】)
江戸時代には「麻布不動坂の一願不動さん」「六軒町の目黄不動」とも呼ばれ、広く庶民の信仰を集めたといいます。
「江戸五色不動」の目黄不動尊は、平井の最勝寺と三ノ輪の永久寺とされていますが、当山を目黄不動尊とする説もあるようです。
もともとの目青不動尊と伝わる麻布谷町にあった勧行寺(ないし正善寺)に近いため、こちらとの関連を示唆する説もみられます。
明治の初年、不動院の住職は日本橋小伝馬町の牢獄跡地の浄化を祈念し、寺院建立を発願。
大倉財閥、安田財閥などの支援を受け、大安楽寺を創建しました。
大安楽寺は高野山真言宗準別格本山の格式ですから、当山も相応の寺格を有していることがうかがえます。
【史料】
■ 『麻布區史』
五大山不動院 市兵衛町二ノ五七
古義眞言宗高野派 金剛峯寺末。本尊不動明王。創立も開山も明らかでないが、萬治元年(1658年)に麹町平川の邊から移って来たと云ふ。中興開山は玄海。境内にもと兒(チゴ)稲荷(本地佛十一面観音 銅像)と呼ぶ小祠があり、非常に栄えていゐたが明治二年神佛分離で廢棄された。
■ 『寺社書上』
大和國長谷小池坊末 麻布六軒町 新義真言宗 旧地●麹町平川町 開山開闢●●●旧記も無し 中興 玄海法印武州中野村宝仙寺の住職●麹町の不動院致兼(略) 旧地麹町平川に有し(略)万治元年(1658年)当地に引移す 本尊不動明王 脇立 矜羯羅童子 脇立 制吒迦童子 右不動尊は弘法大師の作と●伝(略) 四大明王 普賢菩薩 弘法大師 鎮守堂(兒稲荷大明神 本地佛十一面観世音菩薩 武田信玄公甲冑に納●を当院中興玄海法印は武田家由緒し者故 持念佛を鎮守し本地佛を勧請)(略) 弁財天」
(兒稲荷大明神縁起 不動院)
不動院之兒稲荷神社ハ者本地十一面観世音 其古当院ノ中祖玄海法印住職●武江中野ノ寶仙寺以兼セリ 麹町不動院然ルニ 玄海俗姓武田家ノ末葉ナルカ故ニ 信玄公公所ノ帯スル甲冑ニ十一面観世音ノ尊像 玄海傳得之如●為●神社本地佛ト而常ニ信仰シヌ
■ 『御府内寺社備考』
不動堂ハ往古麹町栖岸院にありし 寛永の頃当院へ移●俗人云往昔孔子堂といふ 孟子乃不動●●を本尊とし孔子堂といふ 近年孔子山五臺山といふ
【 江戸期の不動院周辺 】

※ 『江戸切絵図/赤坂絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
-------------------------
都内有数のエンタメエリア・六本木は実はさりげに寺院が多く、裏通りに入ると一種の寺町の様相を呈しています。
なかでもロアビル角の「六本木五丁目」交差点を北に下った窪地「共同墓地の窪地」には六本木墓苑があり、華やかな六本木の一画とは思えない異次元感を発しています。
六本木は土地の起伏の激しいところで、東の溜池方面から青山(六本木)通り沿いに走る低地は「共同墓地の窪地」に至り、南の麻布十番方面から入る旧吉野川の谷筋は「北日ヶ窪」と呼ばれ、芋洗坂を経て六本木駅に至ります。
(この「北日ヶ窪」には北日ヶ窪団地がありましたが、再開発で六本木ヒルズに生まれかわっています。)
六本木通りは市三坂をのぼって「六本木」駅の高台に至り、外苑東通りは一貫して尾根筋、六本木ヒルズ前の麻布十番通りは一貫して谷筋を走ります。
この起伏の激しさは麻布十番通りが六本木通りを麻布トンネルでアンダーパスしていることからもわかります。
なんだかタモリ氏のようになってきたので(笑)、本題に戻ります。


【写真 上(左)】 不動坂と不動院
【写真 下(右)】 外観
不動院は六本木墓苑の窪地から不動坂をのぼった途中右手にあります。
上の伝承にある沼地とは、この「共同墓地の窪地」を指しているのでは。
「六本木」駅から近いですが、アクセスは「六本木一丁目」駅からの方が楽かもしれません。
不動坂まわりは住宅街で、不動院はこの細い不動坂に面した平成11年(1999年)建立の3階建のビル内にあります。
外観は瀟洒なビルですが、3階に掲げられた金色の「真言宗輪宝」、1階エントランス(向拝)の山号扁額、そして「五大山 不動院」と刻まれた門柱が、歴とした寺院であることを示しています。


【写真 上(左)】 不動明王
【写真 下(右)】 稲荷神
館外向かって右には蓮の葉に囲まれた石造の不動明王立像(御前立?)
その横には赤い鳥居の稲荷神が祀られています。
鳥居扁額の文字が薄くて確信はもてないのですが、境内縁起書には「二月初午 児稲荷大明神初午祭(商売繁盛・火坊の祈願を致します)」とあるので、こちらは由緒ある兒稲荷大明神かもしれません。


【写真 上(左)】 エントランス(向拝)
【写真 下(右)】 扁額
エントランス(向拝)は格子ガラスの扉で、見上げに山号扁額。左右に不動明王の御真言と御府内霊場の札番&御詠歌が掲げられています。


【写真 上(左)】 御真言
【写真 下(右)】 札番&御詠歌
エントランスは通常は閉まっていますが28日の御縁日など、特定の日は開かれていることがあります。
通常は、御朱印は日本橋小伝馬町の大安楽寺でいただくことになりますが、開扉日はこちらで拝受できます。
開扉日は荘厳な堂内まで上げていただけ、お不動様に間近で参拝できるので、日を選んでの参拝がベターかと思います。
(ただしお不動様は、中央のお厨子のなかに御座のようです。)
現在は不明ですが、新型コロナ禍前には28日に月並祈願会が勤修され、年に何日かは「不動院寄席」が催されていたようです。
第5番までは比較的寺院らしいたたずまいでしたが、こちら第6番は近代的なビルで都会の寺院ならではのイメージ。
さすがに東京の霊場、御府内霊場の札所です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕 ※いずれも不動院で開扉時に拝受。
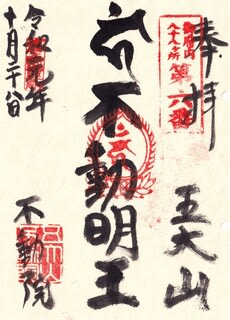

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は金剛界大日如来のお種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫はお種子、「不動明王」で札所印、「南無大師遍照金剛」の印と寺院印が捺されています。
■ 第7番 源秀山 永松院 室泉寺
(しつせんじ)
渋谷区東3-8-16
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第7番、弁財天百社参り第27番
司元別当:
授与所:庫裡
『札所めぐり』および『新編武蔵風土記稿』より、縁起由緒をまとめてみます。
当初は真宗西本願寺末の真宗寺院として芝金杉にありました。
元禄十三年(1700年)旗本松平外記忠益が当所にあった抱屋敷を和泉国神鳳寺中興の快圓(恵空)比丘(和上)に寄附してここに引移し、真言律宗に改宗して神鳳寺の宿寺としたといいます。中興開基は松平外記忠益、開山は快圓(恵空)比丘。
元禄十三年(1694年)快圓和上により開山、元禄十三年(1700年)五代将軍綱吉公の発願により開山という伝承もあるようです。
松平外記忠益は、五井松平家(現在の愛知県蒲郡市五井町を発祥とする松平氏庶流)9代の松平忠益と思われます。『Wikipedia』によると、父の松平伊耀は五千五百石の大身の旗本(寄合)で下総国海上郡飯沼に二千石の知行地をもち飯沼陣屋の主。
忠益はその家督を継いだとあるので、やはり大身の旗本であったと思われます。
縁起由緒からすると、松平忠益と和泉国神鳳寺の間には密接な関係があったと思われますが、Webからは追い切れませんでした。
また、五井松平家の菩提寺は銚子にある等覚寺で曹洞宗。
なので五井松平家と真言律宗に格別のゆかりがあったということも考えにくいです。
和泉国神鳳寺は、和泉国一宮の大鳥大社(大阪府堺市西区鳳北町)の別当であった大鳥山勧学院神鳳寺とみられます。
開山は和銅元年(708年)とも伝わる古刹で、快圓恵空が入り寺勢を拡大したといいます。
『江戸仏教の戒律思想(一)』(上田霊城氏、PDF)には、「真政円忍、快円恵空(1622-1712年)によって大鳥神鳳寺派が成立し、同派の玄忍慧海を証明として受具した覚彦浄厳が真言律宗を唱え、生駒宝山寺宝山湛海、円珠庵契沖も夫々真政・快円について受具している。」とあり、快圓恵空が真言律宗の成立において重要な役割を果たされていたことがわかります。
江戸における真言律宗は、浄厳律師覚彦が創建した湯島霊雲寺を総本山とする真言宗霊雲寺派への流れと、その他の真言宗派への流れがみられます。
室泉寺は真言律宗の寺院として再興されましたが、現在は古義の高野山真言宗に属しています。
しかし、『新編武蔵風土記稿』には「江戸湯嶋霊雲寺末」とあり、法統について複雑な経緯があったのかもしれません。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』
真言律宗 和泉國一ノ宮大島山神鳳寺宿寺ニテ 江戸湯嶋霊雲寺末ナリ 源秀山永松院ト号ス 当寺昔は芝金杉ニアリ 浄土真宗西本願寺末ニテ 同所壽林寺ヨリ兼帯セシヲ 元禄十三年(1700年)九月旗下ノ士松平外記忠益当所ノ抱屋敷ヲ 神鳳寺中興快圓比丘ニ寄附シ 彼寺名ヲ爰ニ引移シ 改宗シテ宿寺トナセリ 故ニ忠益ヲ開基トス(略)開山快圓ハ正徳二年(1712年)二月八日寂 本尊は彌陀 脇士ニ観音地蔵ヲ安ス
護摩堂 不動立像長二尺七寸 愛染坐像長二尺五寸ナルヲ安ス 共ニ南都招提寺開山鑑真和尚ノ弟子支卓律師ノ作ト云
鎮守社 金毘羅 大鳥明神、住吉
辨天堂
【 江戸期の室泉寺周辺 】

※ 『江戸切絵図/青山渋谷絵図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
-------------------------


【写真 上(左)】 山門下
【写真 下(右)】 山門
「恵比寿」駅から5分ほどの住宅街のなかにあります。
渋谷川沿いの低地から広尾・青山の台地にさしかかるこのあたりにはいくつかの寺院が点在しています。
やや奥まった立地で、山内は落ち着いた雰囲気です。
街路から数段のぼった山門は切妻屋根桟瓦葺のおそらく薬医門で左右に門塀をめぐらし、見上げに山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 源秀地蔵堂
山内には大聖歓喜天堂、源秀地蔵堂、そして地主神とみられる稲荷神のお社。
源秀地蔵尊は、身体健全に霊験あらたかと伝わります。


【写真 上(左)】 稲荷神
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑


【写真 上(左)】 修行大師像と山内
【写真 下(右)】 修行大師像
端正な修行弘法大師像が御座され、塔状の立派な札所碑もありました。
お砂踏み場よこの築山は高野山を模しているそうです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は宝形造ないし寄棟造銅板葺で身舎は朱色に彩られて華やかな印象。
向拝柱はなく比較的シンプルなつくりです。
真言律宗系の寺院の御本尊は大日如来が多いですが、こちらの御本尊は阿弥陀如来です。
御朱印は、庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫はお種子、「阿弥陀如来」で札所印と寺院印が捺されています。
■ 第8番 海岳山 大乗院 長遠寺
(ちょうおんじ)
大田区南馬込5-2-10
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第72番、大東京百観音霊場第43番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第78番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第11番
司元別当:馬込村八幡社ほか
授与所:寺務所
大田区馬込にある名刹で、複数の札所を兼務されています。
寺伝によると、馬込村字堂寺の地に天仁元年(1108年)宥尊上人が開山草創。
(『新編武蔵風土記稿』には、村の旧記として定海という僧(元弘二年(1332年)寂)が草創とあり。)
文亀二年(1502年)火災に遭い当地に移転、元禄年間(1688-1704年)に快慶法印が中興と伝わります。
御本尊の不動明王は、馬込不動尊として広く知られています。
行基菩薩の御作と伝わる木造十一面観音菩薩立像(通称「鎌作観世音」)は、大田区の文化財に指定されています。
山内掲出の観音様の説明書に「もと上大崎六軒茶屋の光雲寺にあった」とあること、府外の馬込にあることが気になり、江戸八十八ヶ所霊場第8番を当たってみると、第8番はまさに六軒茶屋の盤谷山光雲寺でした。
光雲寺は『寺社書上』に収録されており、場所は(白金)六軒茶屋町、宗派は新義真言宗、馬込村長遠寺末とあります。
光雲寺は明治8年(1875年)廃寺となっています。
江戸期の江戸八十八ヶ所第8番ないし御府内霊場第8番光雲寺の札所本尊はおそらく御本尊の千手観世音菩薩であったと考えられ、明治8年(1875年)光雲寺が廃寺となった際に、御本尊の千手観世音菩薩は本寺の馬込長遠寺に遷られ、同時に御府内霊場第8番札所も長遠寺に替わったのではないでしょうか。
御府内霊場の札所本尊は御本尊の例がほとんどですから、そのときに第8番の札所本尊は長遠寺の御本尊である不動明王に替わったのでは。
ただし、行基菩薩作とも伝わる光雲寺の御本尊・千手観世音菩薩は長遠寺でも「鎌作観世音」として手篤く奉安され、現在も人々の信仰を集めているのではないでしょうか。
『江戸名所図会』には、こちらの千手観世音菩薩は行基菩薩が巡錫先の信州更級郡で天人が鎌をもって彫刻し、行基菩薩に授けたものとあります。
また、行基菩薩が巡錫先の信州更級郡で一刀三礼してみずから鎌斧で彫り上げられた尊像という伝えもあり、「鎌作(かまつくり)観世音」と尊称されています。
『御府内寺社備考』には、光雲寺には行基菩薩が使われた鎌斧が寺宝として所蔵されているとあります。
「鎌作観世音」は大田区の文化財に指定。
山内説明板には平安時代十世紀頃の作と考えられ、もとは千手観世音菩薩と考えられるが千手を失い、文化財登録としては十一面観世音菩薩立像とされていること、もと上大崎六軒茶屋の光雲寺にあったが、明治初年に廃寺の際、長遠寺に移されたことなどが記されています。
品川区のWeb資料には「(目黒不動尊へ行く「目黒道」「白金通り」)の道筋の六軒茶屋町(現在の上大崎2・3丁目の目黒通り沿い)には、鎌作り観音・光雲寺(明治8年〔1875年〕に廃寺となる)がありました。鎌作り観音から同じ道沿いの永峯町には誕生八幡宮(現在の誕生八幡神社)と別当寺の高福院がありました。この3つの社寺は一緒に挿絵に描かれています。」とあり、江戸八十八ヶ所第8番の光雲寺は、同第4番高福院のそばにあったようです。
(「『江戸名所図会』を読む」様のWebにて詳しく解説されており、光雲寺は高福院のほぼ隣にあったことがわかります。)
【 光雲寺と高福院、行人坂(目黒不動尊方向)の位置関係 】

※ 『江戸切絵図/目黒白金辺図』(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了))から一部切り取り掲載
六軒茶屋町は御府内で『寺社書上』に記載され、馬込は府外で『新編武蔵風土記稿』に収録されています。
こうしてみると、御府内霊場の札所はやはり原則御府内で、現在、旧府外にある札所は移転統合など、なんらかの変遷を辿った例が多いのではないでしょうか。
【史料】
■ 『新編武蔵風土記稿』
除地六畝 (馬込村八幡社)社地ノ北ニ隣レリ 新義真言宗 山城國醍醐三寶院ノ末 海岳山大乗院トと号ス 村ノ舊記ニ定海ト云僧 当寺ヲ草創シテ後元弘二年(1332年)ニ寂セリト見ユ サレハ此人開山ナルヘシ 今寺ニテ開山トスルハ定尊法印ナリ 此法印其事歴寂年ヲ傳へサレハ 何ノ頃トモ云カタケレト 思フニ中興ノ僧ナルニヤ 後元禄(1688-1704年)ノ頃快慶法印ト云僧ノ住シ時 当寺ヲ興記(ママ)シテ檀林寺格トセシニヨリ 今ハ此法印ヲ中興開基トス(略) 本尊不動尊ノ座像ヲ安ス 門ハ客殿ノ正面ニアリ海岳山ノ三字ヲ扁ス
■ 『寺社書上』
(光雲寺)
馬込村長遠寺末 六軒茶屋町 盤谷山 光雲寺 新義真言宗
本尊 千手観世音菩薩 立像丈三尺 但行基菩薩作 延宝八年六月三日信州更級郡梵天平山盤谷山出現千手観音 元禄五年定光雲寺右●奉納石室内●縁起 開山光雲次第書(略)
■ 『御府内寺社備考』
起立ノ儀●元禄五年十一月中意運(略)草創 開山権大僧都智●意運 寺寶 鎌一挺 斧一挺 右ハ行基菩薩●●し●右を以本尊千手観音彫刻し●
■ 『江戸名所図会』
(鎌作観世音)
(妙見大菩薩)西の方一町半斗 向ふ側 六軒茶屋町の角 真言宗光雲寺にあり 相傳ふ 神亀年間(724-729年)行基菩薩諸国遊化の頃 信州更級に始て掛錫し●●ふに 平山と云ふところの池中より 此本尊出現あ● 又空中より化人あらはれ 鎌と御衣●を持ちて降臨し●ひ 彼観音の尊像を彫刻し行基に授け●ふ 此本尊是なり
-------------------------
最寄りは都営浅草線「西馬込」駅。
第二京浜に面した区画ですが、山門は第二京浜の反対側からまわりこむかたちで、周囲は落ち着いたたたずまいです。
向かって左手に馬込八幡神社が御鎮座。
旧馬込村総鎮守で旧村社。岩清水八幡宮の分霊を勧請して創祀され、江戸期は長遠寺が別当でした。
馬込村総鎮守だけあって神さびた境内。御朱印は授与されていないとの掲示がありました。


【写真 上(左)】 馬込八幡神社
【写真 下(右)】 馬込八幡神社の掲示


【写真 上(左)】 門柱から
【写真 下(右)】 山門
長遠寺は広い寺地をもち、名刹にふさわしいたたずまいをみせています。
街路からまずは門柱、左右駐車場の参道の先に、両脇に板塀を配した切妻屋根銅板葺の重厚な山門。
控柱が4本あるので四脚門にも見えますが、おそらく医薬門ないし高麗門かと思われます。
見上げに山号扁額、右門柱に文字が消えかかった札所板が掲げられていますが、かすかに「七十二番札所」と読めるので、これは玉川八十八ヶ所霊場の札所板と思われます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 玉川霊場札所板
こちらは御府内霊場、玉川霊場いずれの御朱印も授与されていますが、それぞれ系統の異なる弘法大師霊場なので、玉川霊場の巡拝は改めた方がベターかと思います。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑
山内は広々と明るく清掃が行き届き、気持ちのよい参拝ができます。
「新大田区百景」にも選ばれています。
参道脇には御府内霊場の立派な札所石碑がありました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面が本堂。
寄棟造銅板葺で瓦葺の向拝を附設した、やや変わった意匠です。
水引虹梁両端に見返り獅子の見事な木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に霊鳥の彫刻を配して整った意匠です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 見事な木鼻


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 玉川霊場の奉納額
本堂軒下には、多摩川(玉川)八十八ヶ所霊場の奉納額が掲げられています。
メジャー霊場2つの札所を兼ねられているため、ご対応は手慣れておられ、またとてもご親切です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳-1
主印は三寶印、揮毫は「本尊 不動明王」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
〔 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

内容は御府内霊場とほぼ同様です。
以下、つづきます。
(→ Vol.-3)
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 三浦三十八地蔵尊霊場の御開帳-1
いよいよ御開帳期間最後の週末となります。
こちらが終わると、関東周辺ではしばらくは大規模な御開帳はないかと思います。
興味のある方は、半日、数箇所でも御開帳の雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか。
-------------------------
2023/05/09
結願しました。
三浦半島は意外に広く、かなりまわり応えがありました。
札所のご対応も親切で、地蔵尊のすぐそばで拝める札所も多く、充実の巡拝となりました。
まだまだ時間はありますので、興味のある方はぜひぜひどうぞ。
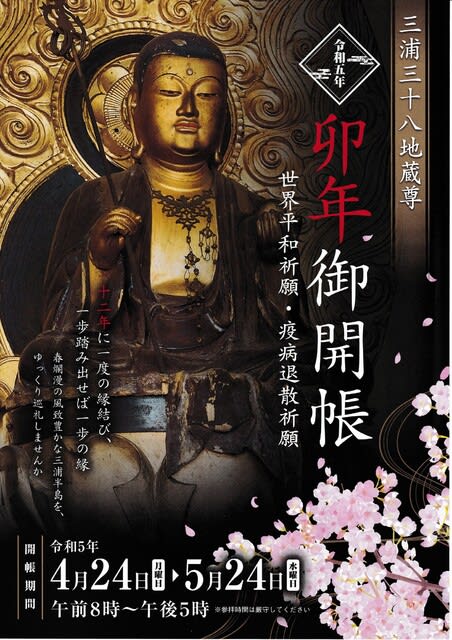
-------------------------
2023/05/04 UP
三浦三十八地蔵尊霊場が4/24から御開帳となっています。
→ タウンニュース
・御開帳期間:4/24(月)~5/24(水)
・札所数38、開帳数38、御朱印授与数38
・霊場概要・札所一覧はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:8:00~17:00 御朱印各300円
・専用納経帳あり(1,200円)
三浦半島(横須賀市・三浦市・葉山町・逗子市)の38の札所からなる地蔵尊霊場で、地蔵尊三浦札所とも呼ばれます。
12年に一度、卯歳に御開帳され、前回は平成23年春でした。
札所の宗派は多彩ですが、浄土宗と曹洞宗寺院が多くなっています。
札所寺院は近年入れ替えがあった模様です。
第9番
旧 荘厳寺(横須賀市津久井3-7-1)
旧 十却寺(三浦市南下浦町上宮田3527)
現 東光寺(横須賀市津久井5-8-3)
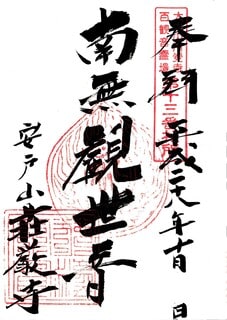
■ 荘厳寺の御本尊の御朱印
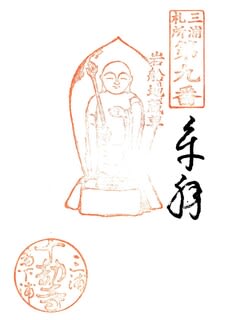
■ 十却寺の地蔵尊の御朱印
第16番
旧 西浜地蔵堂(三浦市三崎5-14-7)
現 妙音寺(三浦市初声町下宮田119)
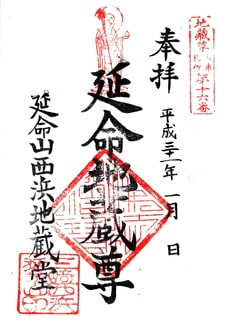
■ 西浜地蔵堂の御朱印
第21番
旧 圓乗院(横須賀市秋谷4387)
旧 西徳寺(横須賀市鴨居2-20)→ 現 第32番
現 長運寺(葉山町長柄615)
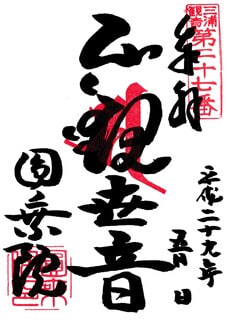
■ 圓乗院の観音霊場の御朱印
第32番
旧 常福寺(横須賀市西浦賀2-16-1)→ 現 第34番
現 西徳寺(横須賀市鴨居2-20)
三浦三十八地蔵尊霊場の開創・沿革については、現在筆者では調べがついておりません。
ただし三浦三十八地蔵尊霊場会Webには、「三浦半島には、古くから巡礼信仰が盛んにおこなわれ、三浦観音霊場、三浦不動尊、そして、三浦地蔵尊として、点在する各寺院が札所とされ、修行者や信者が各札所を巡り、お参りを重ねて、そのお参りの証に御宝印をいただくことからはじまりました。」とあります。
2017年4月~5月には三浦薬師如来霊場が33年ぶりの大開帳、三浦不動尊霊場が12年に1度の酉年大開帳の同時御開帳となりました。
三浦三十三観音霊場は2014年午歳の春に御開帳され、2021年丑歳春には中開帳が予定されていましたが、新型コロナ禍で翌年に延期となり、結局中止となりました。(次回予定は2026年春)
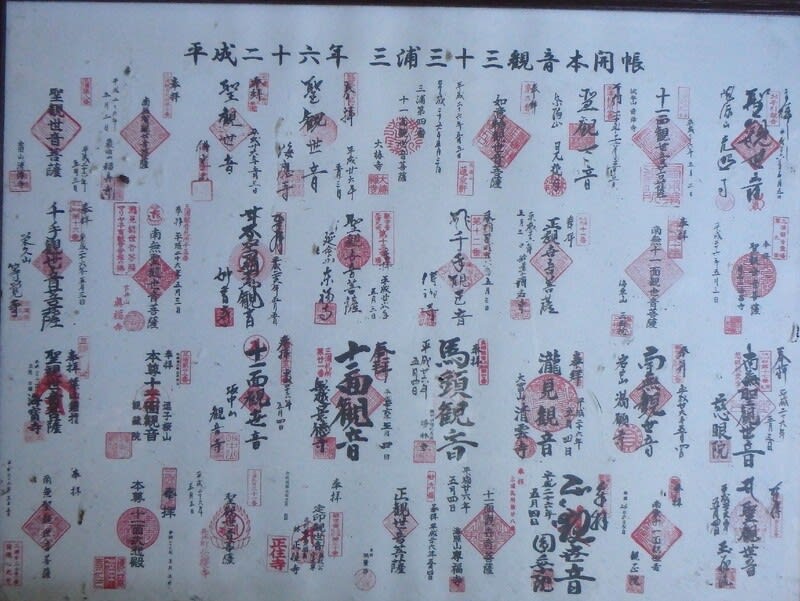
■ 三浦三十三観音霊場の前回御開帳時の御朱印揃
なお、三浦半島には上記のほかにも三浦半島四十八阿弥陀霊場、三浦半島七阿弥陀霊場、三浦半島観音三十三札所、三浦干支守り本尊八佛霊場、三浦半島秋の七草霊場、三浦半島毘沙門天七ヶ所霊場、三浦七福神、追浜七福神などがあり(活動停止霊場あり)、関東でも有数の霊場エリアとなっています。
専用納経帳付属のリーフレットに札所のアクセス地図は載っていますが、札所の分布がわかる全体地図は載っていません。
→ 「三浦三十八地蔵尊霊場会」Webの概略の地図、クリックすると詳細地図が載っています。(旧札所掲載あり要注意)
第32番西徳寺様で、前回平成23年の全体地図が掲示されていたので画像をUPします。(一部で札所変更あり要注意)
(今回、紙の全体地図が作成されていないので、巡拝ルートを計画しにくいとの声があるようです。)

また、今回新規に公式Webが開設され、札所紹介ページからGoogleマップにリンクが貼られています。
この新規公式Webは札所本尊の写真や、写真撮影の可否まで掲載され、とてもよくまとまっています。
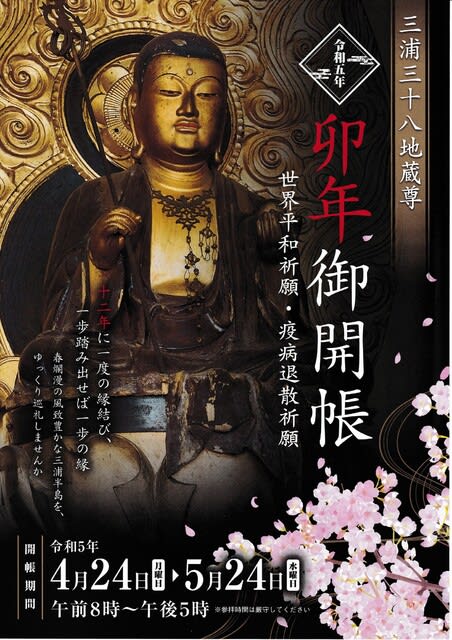
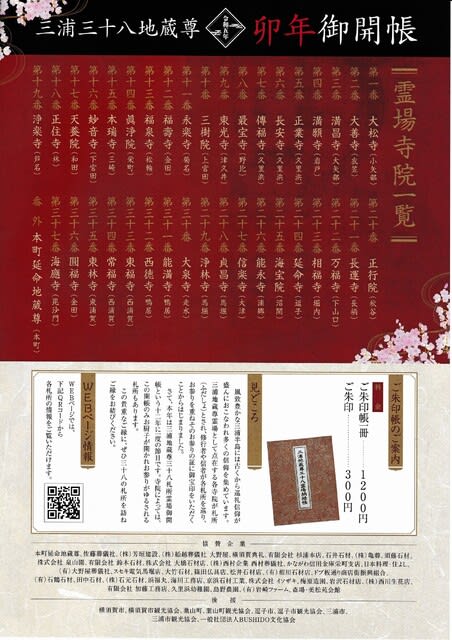
【写真 上(左)】 チラシ表面
【写真 下(右)】 同 裏面
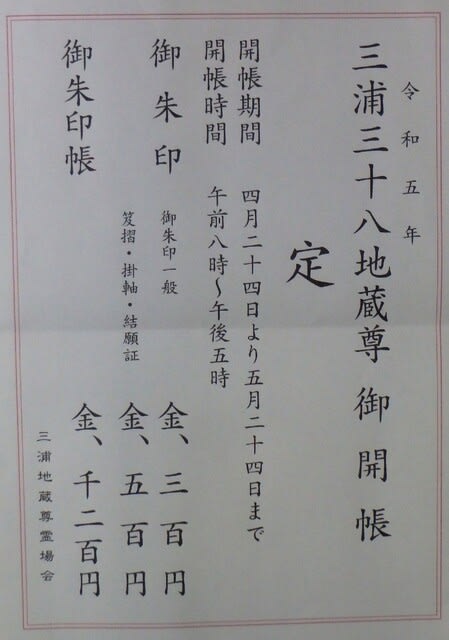
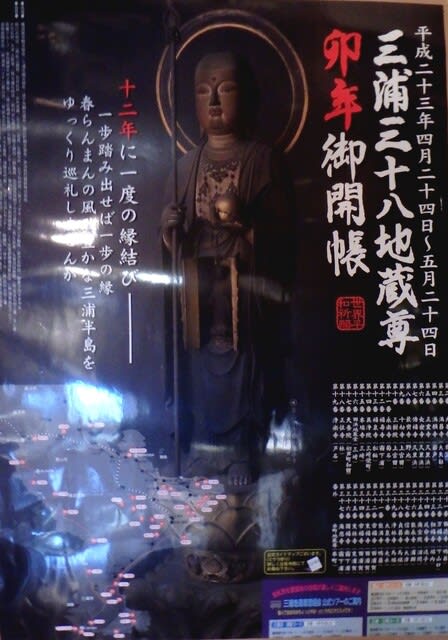
【写真 上(左)】 定書
【写真 下(右)】 前回のポスター
4/24に第1番の萬年山 大松寺から打ちはじめました。
専用納経帳は1,200円で頒布され、孔つきの専用御朱印をバインダーで綴じ込んでいきます。
予め綴じ込まれている専用用紙に揮毫いただくか、揮毫済みの書置用紙と交換します。
白紙の専用用紙で、サイズは大サイズ汎用御朱印帳とほぼ同じなので右端をカットすれば御朱印帳に貼り込めますが、原則専用納経帳綴じ込みの用紙使用なので、汎用御朱印帳でコンプリートできるかは不明です。
(札所によっては御朱印帳貼付用の綴じ孔のあいていない書置御朱印も用意されていますが、用意のない札所もあります。)
札所案内リーフレットや結願証用紙は専用納経帳に付属しているので、専用納経帳使用がベターかもしれません。
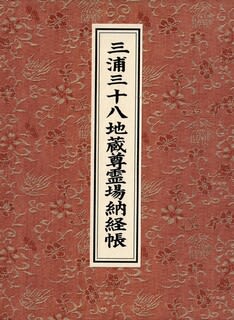
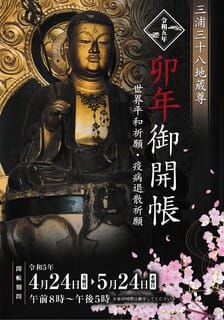
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 札所案内リーフレット
三浦半島の霊場札所(観音、不動尊、薬師如来、地蔵尊)の御朱印対応はまちまちで、常時揮毫いただける札所もあれば、御開帳時のみ授与の札所もあります。
地蔵尊霊場については中開帳がないので、札所によっては12年に一度の御朱印となる可能性があります。
-------------------------




順路はおおむね三浦半島の海沿いを時計回りに辿るかたちとなっていて、三崎マグロが人気の三崎漁港の近くやB級グルメのメッカ、横須賀市内の札所もあって観光的にも楽しめる行程です。
昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で活躍した三浦氏や和田氏ゆかりの札所寺院が多くあり、史跡めぐりとしても面白い巡拝となります。
公共交通機関の利用が推奨されているものの、多くの札所寺院は駐車場を備えられています。
ただし、三浦半島は概して道幅が狭く、急坂が多くて運転しにくいわりに交通量が多いので、車での巡拝は要注意です。
三浦半島の市街は常時渋滞気味で、予想以上に移動時間をとられます。
なので、朝8時~夕方17時までのご対応はありがたいことです。
回向柱は10箇寺ほど回った限りではほとんど建立され、縁の綱(善の綱)も曳かれています。
なお、撮影禁止箇所は札所によりまちまちで、札所本尊撮影可の札所もあります。
→ 公式Webの札所紹介ページに詳細が掲載されています。
初日の4/24の状況は、発願の大松寺では若干の混雑はありましたが、その他の札所はゆったりと巡拝できました。
巡拝者はおおむねミドル層以上で、ご夫婦や女性グループがメインのようでした。
(ただし、週末やGWは層が異なるかもしれません。)
現在、御開扉中の武相卯歳四十八観音霊場では、勤行式や般若心経を唱えられている方がそれなりにおられましたが、4/24の三浦三十八地蔵尊霊場ではほとんどみられませんでした。
ご住職もフレンドリーな方が多く、比較的敷居の低いまわりやすい霊場ではないでしょうか。
GWをはさんでの38札所なので、時間的にはかなり余裕があると思います。
12年に一度の貴重な機会、巡拝されてみてはいかがでしょうか。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
僧侶のみならず、在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
宗派は違っても、御開帳の回向柱にはおおむねこのような願いが揮毫されています。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
今回も武相卯歳四十八観音霊場方式で、リスト、写真、御朱印をご紹介していきます。
とりあえずできた分だけUPします。
-------------------------
第1番
萬年山 大松寺
横須賀市小矢部3-13-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所本尊:地蔵菩薩/子育延命地蔵尊
他札所:-
※御本尊御朱印の授与不明
・鎌倉御家人、秩父氏流の有力武将・稲毛三郎重成の開基と伝わる。
・天文二年(1533年)、代官古敷谷豊前種次が禅林寺八世無参圭徹を招聘して中興。
※御本尊(釈迦牟尼仏)の御朱印の授与不明
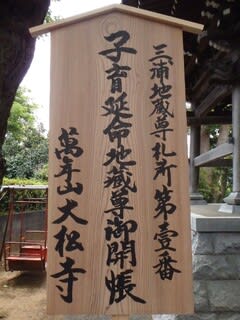

【写真 上(左)】 御開帳札
【写真 下(右)】 地蔵堂
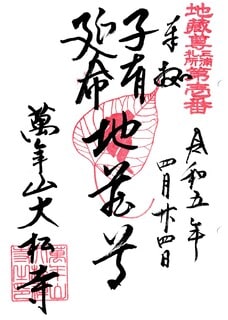
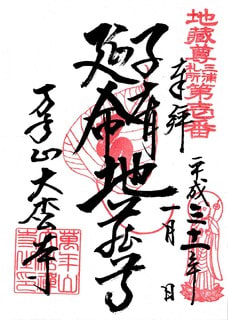
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(以前)
第2番
金笠山 大善寺
横須賀市衣笠町29-1
曹洞宗
御本尊:不動明王(阿弥陀如来)
札所本尊:地蔵菩薩/福壽地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場2番、三浦半島四十八阿弥陀霊場41番
※御本尊(不動明王/三浦二十八不動尊霊場)御朱印授与あり(繁忙時は不明)
・天平元年(729年)行基菩薩御作とされる不動明王を祀ったのが草創と伝わる。
・御本尊の不動明王像は、三浦為通が後三年の役に出陣したとき守本尊となり、敵が放つ矢を受け止めたため「箭執・矢取(やとり)不動尊」とも呼ばれる。
・札所本尊の地蔵尊は衣笠町にあった福壽院の御本尊で「福壽地蔵尊」とも呼ばれる。


【写真 上(左)】 回向柱と参道階段
【写真 下(右)】 堂内
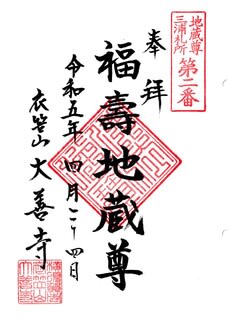
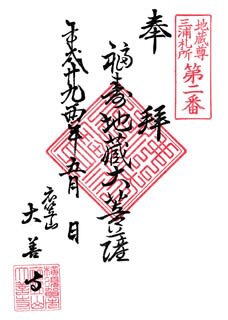
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(以前)
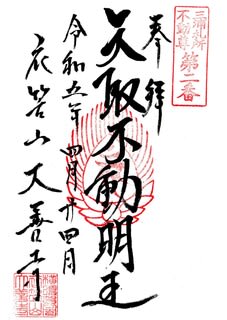
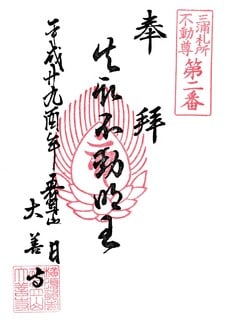
【写真 上(左)】 御本尊(不動明王)の御朱印(今回)
【写真 下(右)】 御本尊(不動明王)の御朱印(以前)
第3番
義明山 満昌寺
横須賀市大矢部1-5-10
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場4番
※御本尊(華厳釋迦佛)御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・建久五年(1194年)、三浦大介義明を開基とし源頼朝が建立と伝わる名刹。
・三浦義明坐像(国重文)、本尊華厳釈迦像(市重文)をはじめ多くの文化財を収蔵。

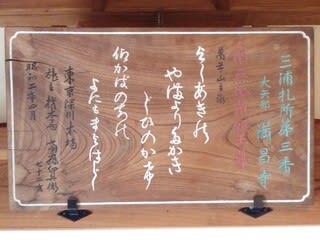
【写真 上(左)】 回向柱と地蔵堂
【写真 下(右)】 札所板
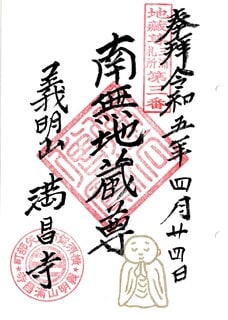
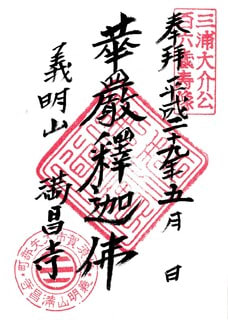
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(釈迦牟尼佛)の御朱印
第4番
岩戸山 満願寺
横須賀市岩戸1-4-9
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来(聖観世音菩薩)
札所本尊:地蔵菩薩/岩戸地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場18番、三浦二十八不動尊霊場3番、三浦半島秋の七草霊場2番、三浦半島毘沙門天七ヶ所霊場2番
※御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印授与
・建久五年(1194年)源頼朝公が三浦義明を追善の法要堂を矢部郷に建立したのが草創とされ、義明の末子・佐原城主の佐原十郎義連の創建とも伝わる名刹。
・札所本尊は多くの文化財とともに収蔵庫に安置され、御開帳もこちらの収蔵庫で催される。
・登記上の御本尊は釈迦如来だが、御本尊御朱印として聖観世音菩薩を授与とのこと。
(当御開帳中の授与不明)

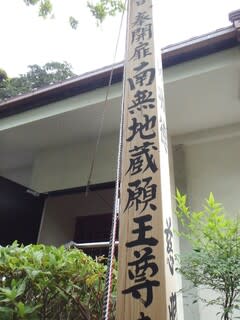
【写真 上(左)】 御開帳場の収蔵庫
【写真 下(右)】 回向柱
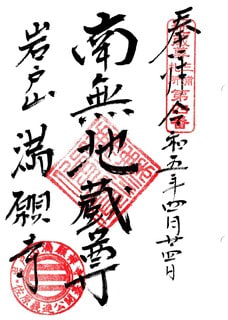
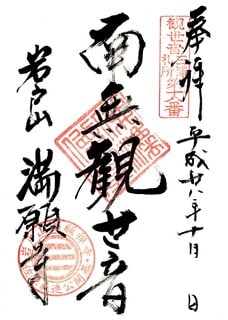
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印
第5番
御霊山 満蔵院 正業寺
横須賀市久里浜2-19-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/子育地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場10番、三浦半島観音三十三札所24番、三浦半島四十八阿弥陀霊場29番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・永禄九年(1566年)寂の僧・入誉元清の建立と伝わり、慶安元年(1648年)芝増上寺第21世還無上人が開山再興、元禄十一年(1698年)、内川新田開拓の砂村新左衛門の甥が現在地に移築とされる浄土宗寺院。
・江戸期の作とされる札所本尊は本堂内に奉安。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
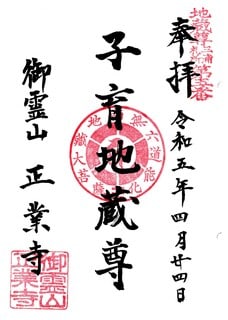
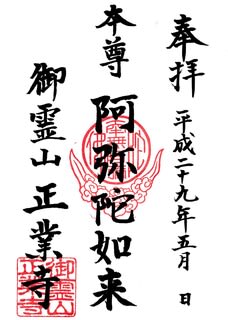
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第6番
亀養山 松樹院 長安寺
横須賀市久里浜2-8-9
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場9番、三浦二十一ヶ所薬師霊場10番、三浦干支守り本尊八佛霊場1番、三浦半島観音三十三札所23番、三浦半島四十八阿弥陀霊場28番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・天文二年(1533年)、鎌倉光明寺19世然誉上人により開山とされる浄土宗寺院。
・浄土宗寺院ながら著名なお不動様を奉安し、「丸山不動明王」「火伏せ不動」、また朝比奈三郎義家の守本尊と伝わる不動尊も御座される模様。
・札所本尊の地蔵尊は、三浦干支守り本尊八佛霊場の札所本尊・勢至菩薩と並んで庫裡横の仏殿に御座される。


【写真 上(左)】 回向柱と向拝
【写真 下(右)】 地蔵尊(右)と勢至菩薩(左)
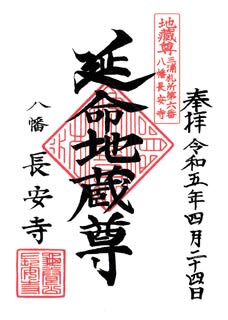
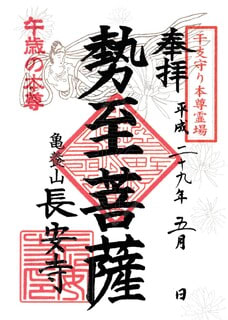
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 三浦干支守り本尊八佛霊場・勢至菩薩の御朱印
第7番
明星山 西生院 傳福寺
横須賀市久里浜8-23-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/多幸地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場12番、三浦二十一ヶ所薬師霊場9番、三浦干支守り本尊八佛霊場2番、三浦半島四十八阿弥陀霊場27番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・久里浜にある大永七年(1527年)開山の浄土宗寺院。
・札所本尊は本堂向かって左側の地蔵堂内に奉安。高さ124cmの迫力の半跏像。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 札所本尊
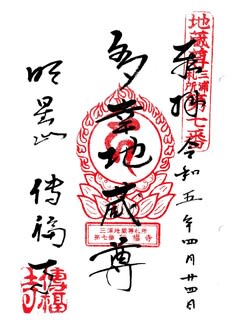
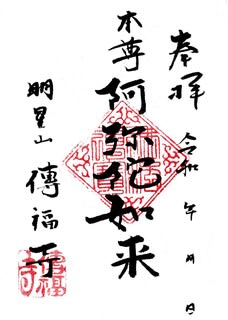
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第8番
高御蔵五明山 最寶寺
横須賀市野比1-51-1
浄土真宗本願寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊(たから地蔵尊)
他札所:三浦二十八不動尊霊場11番、三浦二十一ヶ所薬師霊場11番、三浦半島観音三十三札所22番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印不授与?
・源頼朝公が鎌倉扇ヶ谷に創建、建久六年(1195年)寺地を鎌倉弁ヶ谷に移した。
・開基は明光、当初は天台宗で薬師如来を本尊とし、後に浄土真宗に改宗。
・大永元年(1521年)火災を契機に現在地に移転。
・浄土真宗寺院ながら多くの霊場札所を務められ、御朱印も授与されている。(御開帳時のみ?)
・札所本尊は本堂向かって左手の仏間に奉安され、回向柱は本堂左手妻側に設けられている。


【写真 上(左)】 回向柱と向拝
【写真 下(右)】 堂内
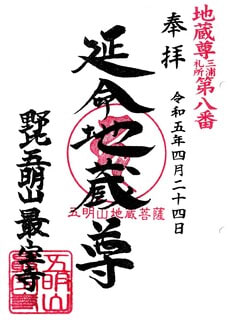
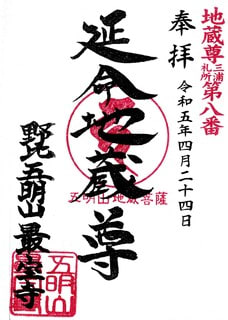
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(御朱印帳印判捺)
第9番
七寶山 東光寺
横須賀市津久井5-8-3
高野山真言宗
御本尊:大日如来・薬師如来・地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場11番、三浦二十一ヶ所薬師霊場11番、三浦半島観音三十三札所22番
※御本尊(大日如来・薬師如来)の御朱印はいずれも授与(繁忙時は不明)
・第9番札所は荘厳寺(横須賀市津久井3-7-1)から十却寺(三浦市南下浦町上宮田3527)と遷り、現在は東光寺となっている。
・行基菩薩が諸国行脚の際、当郷にて草庵を結び地蔵菩薩像を御作。
・当庵で三浦富士大権現の夢告を受け薬師三尊と十二神将の御作され、当寺を建立という。
・その後、三浦の庄司、平義継の二男・津久井次郎義行が当山を祈祷所と定めて中興。
・旧9番の荘厳寺(津久井)十劫寺(下浦町上宮田)に替わり新たに9番札所となる。
・札所本尊は本堂とは別棟で御開帳。堂棟内で地蔵尊のほか、弘法大師、大日如来、薬師如来、不動明王など多彩な尊格の御朱印を揮毫授与されている。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御開帳場の別棟
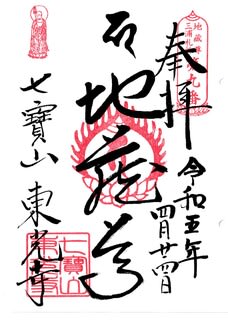
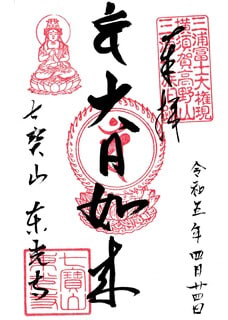
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(大日如来)の御朱印
第10番
海東山 三樹院
三浦市南下浦町上宮田601
浄土宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/子育延命地蔵菩薩
他札所:三浦三十三観音霊場10番
※御本尊(十一面観世音菩薩)、宗派本尊(阿弥陀如来)の御朱印はいずれも書置授与
・木曽義仲四天王の一人・今井四郎兼平が出陣の折この地に仮屋を設けたのが草創で、のちに鈴木某なる者が兼平の仮屋を移設し、伽藍を整えて旧上宮田岩井口の十劫寺の子院とした。
・宝永五年(1709年)、芝増上寺遍誉了海上人が應行上人作の十一面観世音菩薩(今井の観音さま)を笈来、当山の御本尊と改めたという。
・札所本尊は近在の地蔵堂に安置されていた子育延命地蔵菩薩で、本堂内に奉安されている。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
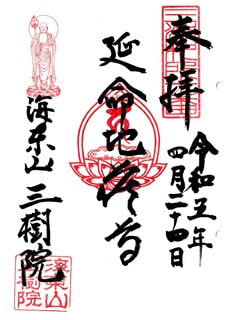
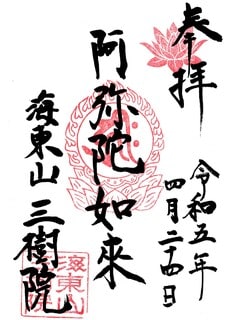
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第11番
牛込山 永楽寺
三浦市南下浦町菊名312
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/紫雲地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場14番
・札所本尊は「紫雲地蔵尊」、三浦二十八不動尊霊場の札所本尊は「牛込不動尊」と呼ばれてともに尊崇される。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印は現時点で不授与の模様

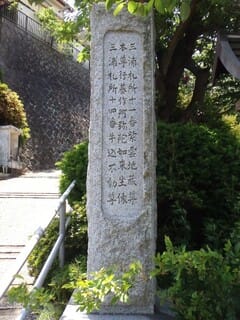
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 札所標
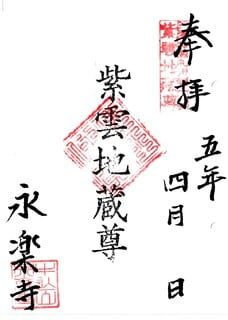
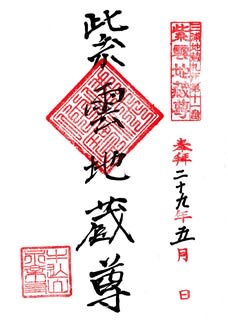
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(以前)
第12番
岩浦山 福壽寺
三浦市南下浦町金田2062
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
※御本尊(聖観世音菩薩/三浦三十三観音霊場)御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・正治二年(1200年)、三浦大介義明の孫三浦駿河守義村が開基と伝わる。
・御本尊は行基菩薩の御作とされ、寺宝として三浦義村使用の鞍・鎧・脇差などを収蔵。


【写真 上(左)】 回向柱と向拝
【写真 下(右)】 本堂内
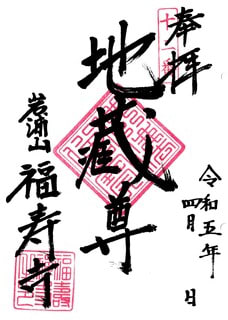
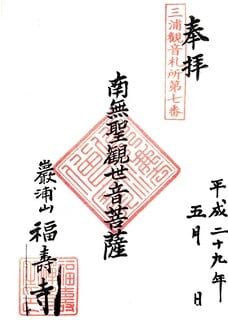
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印(三浦三十三観音霊場)
第13番
千光山 福泉寺
三浦市南下浦町松輪1421
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:-
※御本尊(聖観世音菩薩)御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・「松輪サバ」で知られる松輪にある浄土宗寺院。
・正中元年(1324年)創建、元禄十六年(1704年)の大津波により流失し現在地に移転再建と伝わる。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
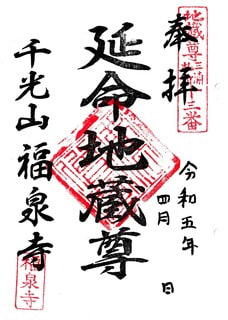
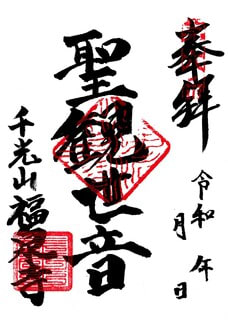
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印
第14番
海潮山 眞浄院
三浦市栄町3-16
臨済宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/身代り地蔵尊・延命地蔵尊
・以前は海汐寺と号した地蔵尊ゆかりの寺院。
・永正十五年(1516年)、北条早雲に攻められた新井城の三浦道寸義同は、最後の決戦を三崎城の出口茂忠に伝える伝令を家臣・川島身七に託した。
・身七は任を果たしたが新井城はすでに落城、身七は海汐寺の前身の地蔵堂に身を隠したものの追手は身七を発見しその首をはねた。しかし追手が切ったのは身七の首ではなく地蔵尊の首で、身七は地蔵尊の身代りにより難を遁れた。
・身七は地蔵尊への報恩と新井城の朋友の菩提を弔うため剃髪して地蔵坊と名乗り、一生をこの寺で過ごしたと伝わる。


【写真 上(左)】 回向柱
【写真 下(右)】 回向柱と向拝

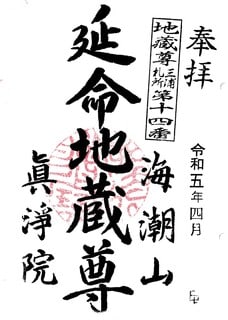
【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 御朱印(専用納経帳/今回)
第15番
海光山 本瑞寺
三浦市三崎1-19-1
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊(子育地蔵尊)
他札所:関東百八地蔵尊霊場88番、三浦半島観音三十三札所19番
・三崎の高台にある名刹。風光明媚な地にあり源頼朝公ゆかりの「桜の御所」とも呼ばれる。
・康平年間(1058-1065年)、三浦為継が鎌倉に創建、永正元年(1504年)この地に移転。
・御本尊の地蔵菩薩(延命地蔵尊)は弘法大師の御作で三浦道寸父子の御持佛とも伝わる。
・『(関東)百八地蔵尊めぐり』によると、三浦地蔵尊霊場の札所本尊は開山堂の「子育地蔵尊」とあり、関東百八地蔵尊霊場の御朱印は「延命地蔵尊」とあるが、三浦地蔵尊霊場の御開帳では「子育地蔵尊」「延命地蔵尊」の両尊御開帳されていた。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
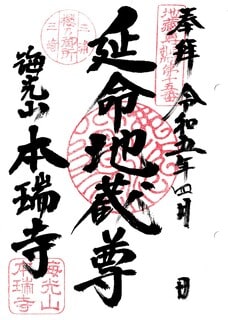
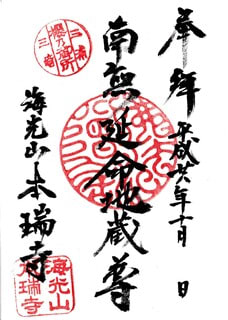
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(関東百八地蔵尊霊場)
第16番
飯盛山 明王院 妙音寺 (三浦大師)
三浦市初声町下宮田119
高野山真言宗
御本尊:不空羂索観世音菩薩・地蔵菩薩
※寺院公式Webでは不空羂索観世音菩薩、当霊場公式Webには地蔵菩薩とある。
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場14番、三浦二十八不動尊霊場15番、関東八十八箇所58番、七観音霊場4番、東国花の寺百ヶ寺霊場78番、三浦半島秋の七草霊場4番、三浦干支守り本尊八佛霊場3番、三浦七福神(鶴園福禄寿)、富士見楽寿(ぼけ封じ)観音霊場 1番
※御本尊(不空羂索観世音菩薩)御朱印拝受済(複数霊場)
・第16番札所は西浜地蔵堂(三浦市三崎5-14-7)から妙音寺に入れ替えとなっている。
・鎌倉時代初期に妙音寺原に草創、天正年間の1580年代に賢栄法印により現在地に移されて中興。小田原北条氏五代の雨乞い祈願所として庇護されたという。
・多くの霊場札所を兼務される高野山真言宗の寺院で、花の寺としても知られている。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 御開帳案内
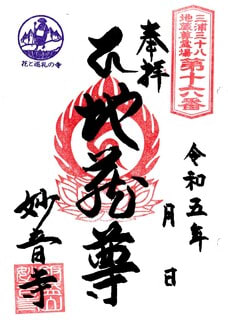
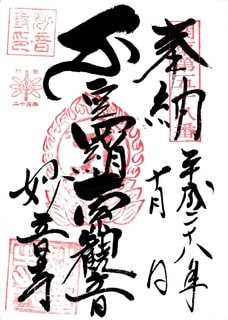
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(不空羂索観世音菩薩)の御朱印(関東八十八箇所)
第17番
五劫山 宝泉寺 天養院
三浦市初声町和田1669
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来(三尊)
札所本尊:地蔵菩薩/地蔵願王尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場14番、三浦半島四十八阿弥陀霊場19番
※御本尊(阿弥陀如来(三尊))の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・永禄二年(1559年)長澤和泉が開基、真蓮社性誉上人が開山と伝わる。
・別尊の薬師如来像は和田義盛の「身代わり薬師」とも呼ばれて県指定有形文化財。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
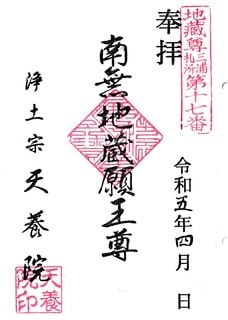
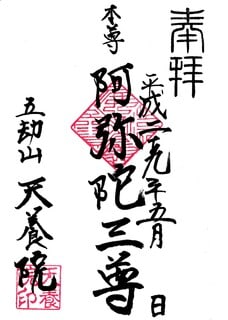
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来(三尊))の御朱印
第18番
宝林山 正住寺
横須賀市林5-1-5
浄土宗
御本尊:定印観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:三浦三十三観音霊場30番、三浦二十八不動尊霊場18番
・文明元年(1469年)、八代将軍足利義政公開基とされる名刹。
・御本尊の定印観世音菩薩は義政公の守本尊と伝わる。
※御本尊(阿弥陀如来(三尊))の御朱印拝受済(当御開帳中の授与は繁忙時は困難かも)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内
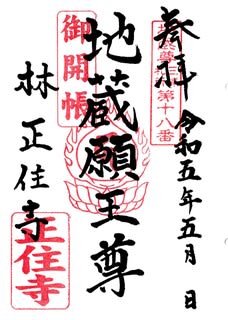
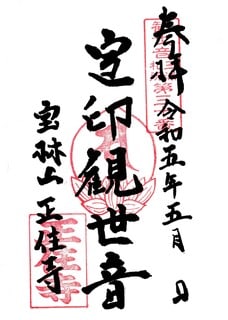
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(定印観世音菩薩)の御朱印
第19番
金剛山 勝長寿院 浄楽寺 (大御堂)
横須賀市芦名2-30-5
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場20番、三浦二十一ヶ所薬師霊場15番、三浦干支守り本尊八佛霊場6番、三浦半島観音三十三札所8番、三浦半島四十八阿弥陀霊場11番、三浦半島七阿弥陀霊場2番、三浦半島毘沙門天七ヶ所霊場6番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与されている模様)
・文治五年(1189年)に源頼朝公が父・義朝公の菩提のために創建した鎌倉・勝長寿院(大御堂)を、建永元年(1206年)の大風による堂宇破損で和田義盛と北条政子が現在地に移したと伝わる名刹。
・建治元年(1275年)に鎌倉光明寺2世・白幡流寂慧良暁上人が中興開山とされる
・運慶作とされる不動明王立像、毘沙門天立像のほか、御本尊・阿弥陀三尊も国の重要文化財に指定されている。
・札所本尊の延命地蔵尊は享保年間(1716-1735年)、悪疫流行の際に厄難消滅を祈願して造立。四十八夜の別時法要を営み、願成就された霊験あらたかな地蔵尊と伝わる。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 地蔵堂
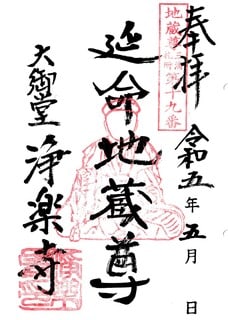
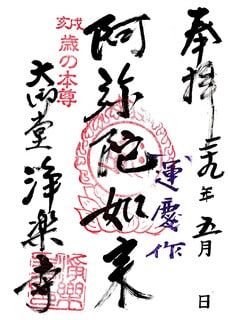
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第20番
紫雲山 秋谷寺 正行院
公式Web
横須賀市秋谷2-16-2
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場17番、三浦半島観音三十三札所7番、三浦半島四十八阿弥陀霊場10番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も書置授与されています)
・正治元年(1199年)侍所別当の和田義盛が妻の巴御前の菩提寺として、現在の横須賀市秋谷の乗越海岸に建立したのが草創とされる。
・明応七年(1499年)鎌倉光明寺9世・観誉祐崇上人が現在地に遷されて開山し、巴御前の遺髪が埋蔵されたという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内
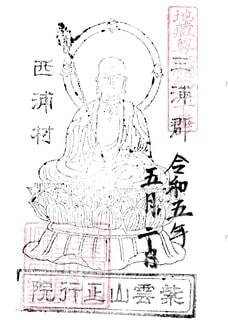
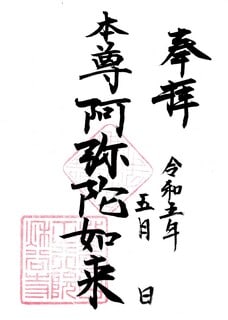
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
■ 三浦三十八地蔵尊霊場の御開帳-2へつづく。
【 BGM 】
■ Christopher Cross - Sailing (Official Audio)
■ Boz Scaggs - Isn't It Time
■ Boy Meets Girl - Waiting For A Star To Fall
こちらが終わると、関東周辺ではしばらくは大規模な御開帳はないかと思います。
興味のある方は、半日、数箇所でも御開帳の雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか。
-------------------------
2023/05/09
結願しました。
三浦半島は意外に広く、かなりまわり応えがありました。
札所のご対応も親切で、地蔵尊のすぐそばで拝める札所も多く、充実の巡拝となりました。
まだまだ時間はありますので、興味のある方はぜひぜひどうぞ。
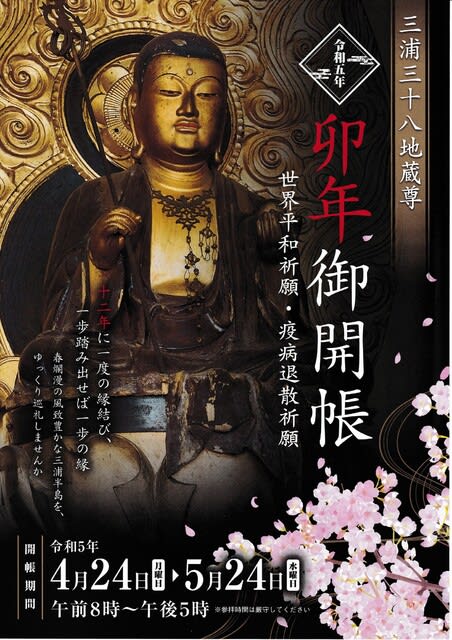
-------------------------
2023/05/04 UP
三浦三十八地蔵尊霊場が4/24から御開帳となっています。
→ タウンニュース
・御開帳期間:4/24(月)~5/24(水)
・札所数38、開帳数38、御朱印授与数38
・霊場概要・札所一覧はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:8:00~17:00 御朱印各300円
・専用納経帳あり(1,200円)
三浦半島(横須賀市・三浦市・葉山町・逗子市)の38の札所からなる地蔵尊霊場で、地蔵尊三浦札所とも呼ばれます。
12年に一度、卯歳に御開帳され、前回は平成23年春でした。
札所の宗派は多彩ですが、浄土宗と曹洞宗寺院が多くなっています。
札所寺院は近年入れ替えがあった模様です。
第9番
旧 荘厳寺(横須賀市津久井3-7-1)
旧 十却寺(三浦市南下浦町上宮田3527)
現 東光寺(横須賀市津久井5-8-3)
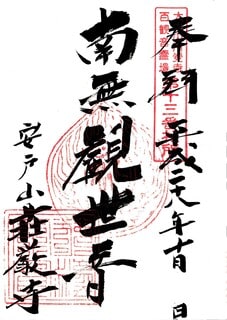
■ 荘厳寺の御本尊の御朱印
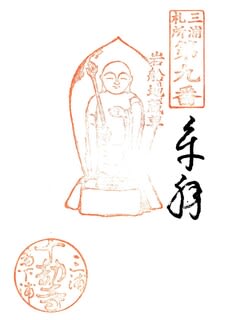
■ 十却寺の地蔵尊の御朱印
第16番
旧 西浜地蔵堂(三浦市三崎5-14-7)
現 妙音寺(三浦市初声町下宮田119)
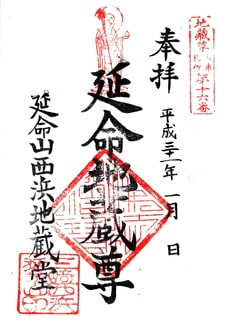
■ 西浜地蔵堂の御朱印
第21番
旧 圓乗院(横須賀市秋谷4387)
旧 西徳寺(横須賀市鴨居2-20)→ 現 第32番
現 長運寺(葉山町長柄615)
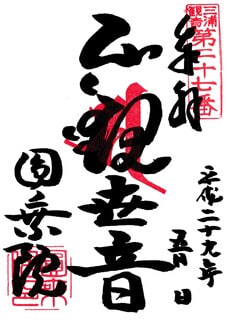
■ 圓乗院の観音霊場の御朱印
第32番
旧 常福寺(横須賀市西浦賀2-16-1)→ 現 第34番
現 西徳寺(横須賀市鴨居2-20)
三浦三十八地蔵尊霊場の開創・沿革については、現在筆者では調べがついておりません。
ただし三浦三十八地蔵尊霊場会Webには、「三浦半島には、古くから巡礼信仰が盛んにおこなわれ、三浦観音霊場、三浦不動尊、そして、三浦地蔵尊として、点在する各寺院が札所とされ、修行者や信者が各札所を巡り、お参りを重ねて、そのお参りの証に御宝印をいただくことからはじまりました。」とあります。
2017年4月~5月には三浦薬師如来霊場が33年ぶりの大開帳、三浦不動尊霊場が12年に1度の酉年大開帳の同時御開帳となりました。
三浦三十三観音霊場は2014年午歳の春に御開帳され、2021年丑歳春には中開帳が予定されていましたが、新型コロナ禍で翌年に延期となり、結局中止となりました。(次回予定は2026年春)
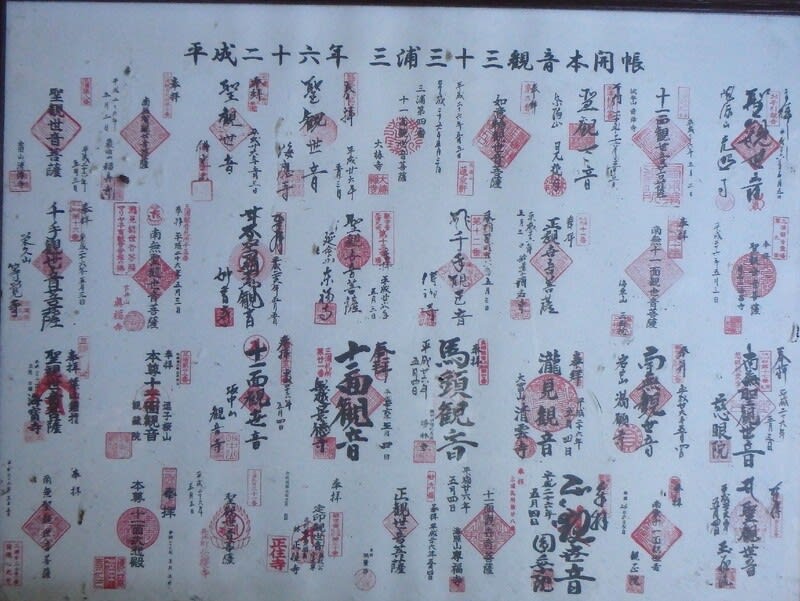
■ 三浦三十三観音霊場の前回御開帳時の御朱印揃
なお、三浦半島には上記のほかにも三浦半島四十八阿弥陀霊場、三浦半島七阿弥陀霊場、三浦半島観音三十三札所、三浦干支守り本尊八佛霊場、三浦半島秋の七草霊場、三浦半島毘沙門天七ヶ所霊場、三浦七福神、追浜七福神などがあり(活動停止霊場あり)、関東でも有数の霊場エリアとなっています。
専用納経帳付属のリーフレットに札所のアクセス地図は載っていますが、札所の分布がわかる全体地図は載っていません。
→ 「三浦三十八地蔵尊霊場会」Webの概略の地図、クリックすると詳細地図が載っています。(旧札所掲載あり要注意)
第32番西徳寺様で、前回平成23年の全体地図が掲示されていたので画像をUPします。(一部で札所変更あり要注意)
(今回、紙の全体地図が作成されていないので、巡拝ルートを計画しにくいとの声があるようです。)

また、今回新規に公式Webが開設され、札所紹介ページからGoogleマップにリンクが貼られています。
この新規公式Webは札所本尊の写真や、写真撮影の可否まで掲載され、とてもよくまとまっています。
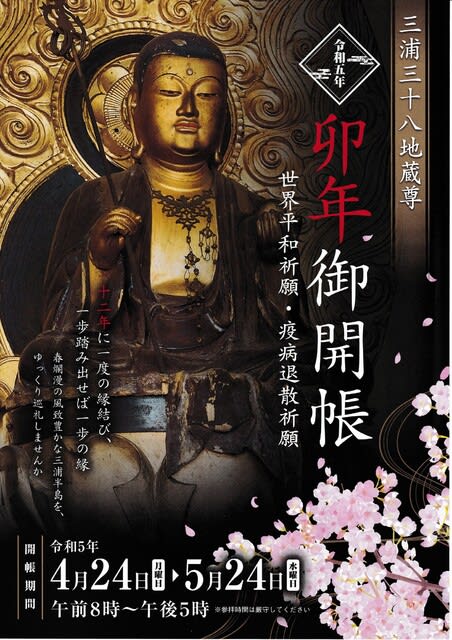
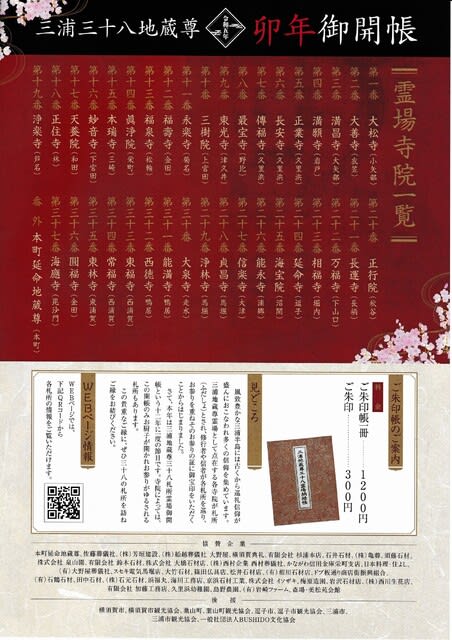
【写真 上(左)】 チラシ表面
【写真 下(右)】 同 裏面
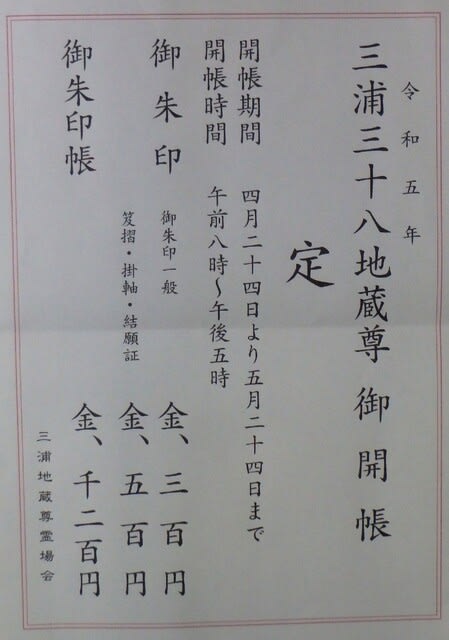
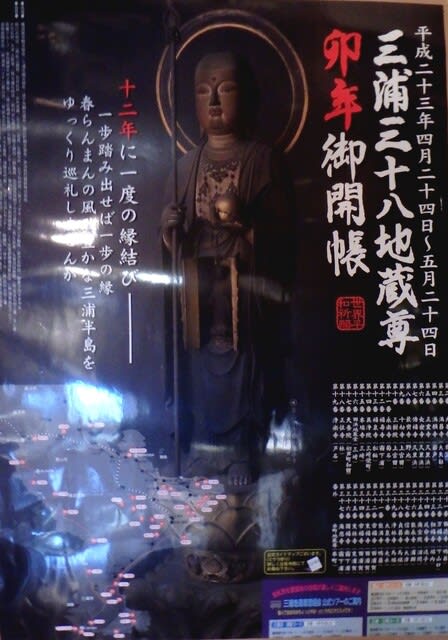
【写真 上(左)】 定書
【写真 下(右)】 前回のポスター
4/24に第1番の萬年山 大松寺から打ちはじめました。
専用納経帳は1,200円で頒布され、孔つきの専用御朱印をバインダーで綴じ込んでいきます。
予め綴じ込まれている専用用紙に揮毫いただくか、揮毫済みの書置用紙と交換します。
白紙の専用用紙で、サイズは大サイズ汎用御朱印帳とほぼ同じなので右端をカットすれば御朱印帳に貼り込めますが、原則専用納経帳綴じ込みの用紙使用なので、汎用御朱印帳でコンプリートできるかは不明です。
(札所によっては御朱印帳貼付用の綴じ孔のあいていない書置御朱印も用意されていますが、用意のない札所もあります。)
札所案内リーフレットや結願証用紙は専用納経帳に付属しているので、専用納経帳使用がベターかもしれません。
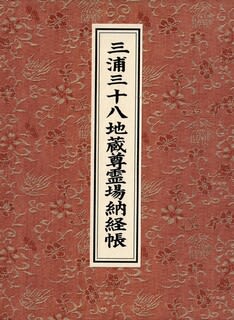
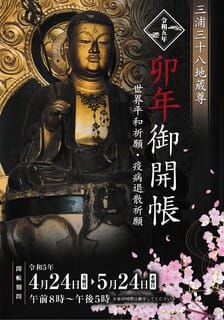
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 札所案内リーフレット
三浦半島の霊場札所(観音、不動尊、薬師如来、地蔵尊)の御朱印対応はまちまちで、常時揮毫いただける札所もあれば、御開帳時のみ授与の札所もあります。
地蔵尊霊場については中開帳がないので、札所によっては12年に一度の御朱印となる可能性があります。
-------------------------




順路はおおむね三浦半島の海沿いを時計回りに辿るかたちとなっていて、三崎マグロが人気の三崎漁港の近くやB級グルメのメッカ、横須賀市内の札所もあって観光的にも楽しめる行程です。
昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で活躍した三浦氏や和田氏ゆかりの札所寺院が多くあり、史跡めぐりとしても面白い巡拝となります。
公共交通機関の利用が推奨されているものの、多くの札所寺院は駐車場を備えられています。
ただし、三浦半島は概して道幅が狭く、急坂が多くて運転しにくいわりに交通量が多いので、車での巡拝は要注意です。
三浦半島の市街は常時渋滞気味で、予想以上に移動時間をとられます。
なので、朝8時~夕方17時までのご対応はありがたいことです。
回向柱は10箇寺ほど回った限りではほとんど建立され、縁の綱(善の綱)も曳かれています。
なお、撮影禁止箇所は札所によりまちまちで、札所本尊撮影可の札所もあります。
→ 公式Webの札所紹介ページに詳細が掲載されています。
初日の4/24の状況は、発願の大松寺では若干の混雑はありましたが、その他の札所はゆったりと巡拝できました。
巡拝者はおおむねミドル層以上で、ご夫婦や女性グループがメインのようでした。
(ただし、週末やGWは層が異なるかもしれません。)
現在、御開扉中の武相卯歳四十八観音霊場では、勤行式や般若心経を唱えられている方がそれなりにおられましたが、4/24の三浦三十八地蔵尊霊場ではほとんどみられませんでした。
ご住職もフレンドリーな方が多く、比較的敷居の低いまわりやすい霊場ではないでしょうか。
GWをはさんでの38札所なので、時間的にはかなり余裕があると思います。
12年に一度の貴重な機会、巡拝されてみてはいかがでしょうか。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
僧侶のみならず、在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
宗派は違っても、御開帳の回向柱にはおおむねこのような願いが揮毫されています。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
今回も武相卯歳四十八観音霊場方式で、リスト、写真、御朱印をご紹介していきます。
とりあえずできた分だけUPします。
-------------------------
第1番
萬年山 大松寺
横須賀市小矢部3-13-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所本尊:地蔵菩薩/子育延命地蔵尊
他札所:-
※御本尊御朱印の授与不明
・鎌倉御家人、秩父氏流の有力武将・稲毛三郎重成の開基と伝わる。
・天文二年(1533年)、代官古敷谷豊前種次が禅林寺八世無参圭徹を招聘して中興。
※御本尊(釈迦牟尼仏)の御朱印の授与不明
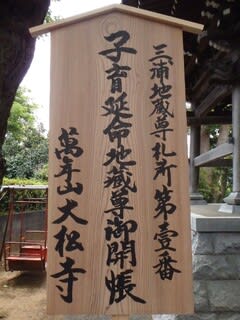

【写真 上(左)】 御開帳札
【写真 下(右)】 地蔵堂
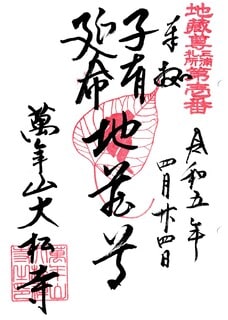
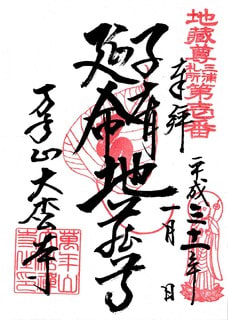
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(以前)
第2番
金笠山 大善寺
横須賀市衣笠町29-1
曹洞宗
御本尊:不動明王(阿弥陀如来)
札所本尊:地蔵菩薩/福壽地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場2番、三浦半島四十八阿弥陀霊場41番
※御本尊(不動明王/三浦二十八不動尊霊場)御朱印授与あり(繁忙時は不明)
・天平元年(729年)行基菩薩御作とされる不動明王を祀ったのが草創と伝わる。
・御本尊の不動明王像は、三浦為通が後三年の役に出陣したとき守本尊となり、敵が放つ矢を受け止めたため「箭執・矢取(やとり)不動尊」とも呼ばれる。
・札所本尊の地蔵尊は衣笠町にあった福壽院の御本尊で「福壽地蔵尊」とも呼ばれる。


【写真 上(左)】 回向柱と参道階段
【写真 下(右)】 堂内
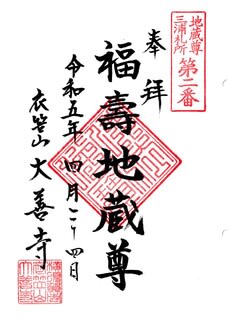
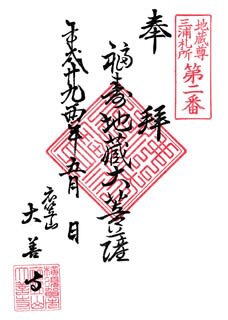
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(以前)
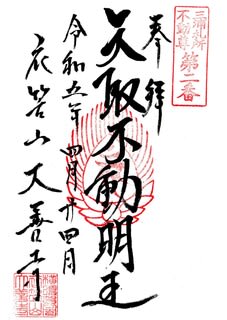
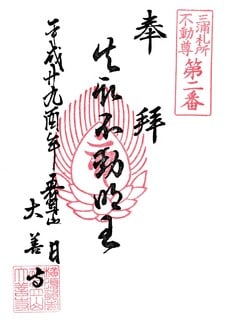
【写真 上(左)】 御本尊(不動明王)の御朱印(今回)
【写真 下(右)】 御本尊(不動明王)の御朱印(以前)
第3番
義明山 満昌寺
横須賀市大矢部1-5-10
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場4番
※御本尊(華厳釋迦佛)御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・建久五年(1194年)、三浦大介義明を開基とし源頼朝が建立と伝わる名刹。
・三浦義明坐像(国重文)、本尊華厳釈迦像(市重文)をはじめ多くの文化財を収蔵。

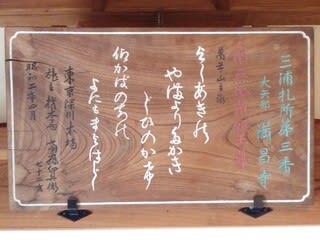
【写真 上(左)】 回向柱と地蔵堂
【写真 下(右)】 札所板
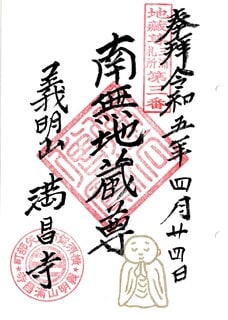
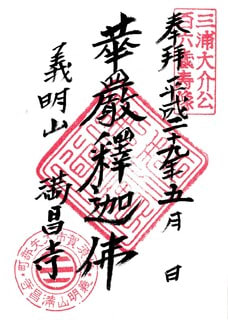
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(釈迦牟尼佛)の御朱印
第4番
岩戸山 満願寺
横須賀市岩戸1-4-9
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来(聖観世音菩薩)
札所本尊:地蔵菩薩/岩戸地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場18番、三浦二十八不動尊霊場3番、三浦半島秋の七草霊場2番、三浦半島毘沙門天七ヶ所霊場2番
※御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印授与
・建久五年(1194年)源頼朝公が三浦義明を追善の法要堂を矢部郷に建立したのが草創とされ、義明の末子・佐原城主の佐原十郎義連の創建とも伝わる名刹。
・札所本尊は多くの文化財とともに収蔵庫に安置され、御開帳もこちらの収蔵庫で催される。
・登記上の御本尊は釈迦如来だが、御本尊御朱印として聖観世音菩薩を授与とのこと。
(当御開帳中の授与不明)

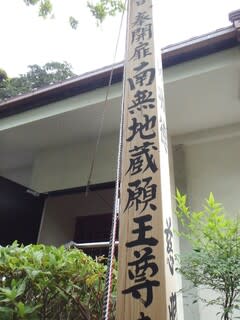
【写真 上(左)】 御開帳場の収蔵庫
【写真 下(右)】 回向柱
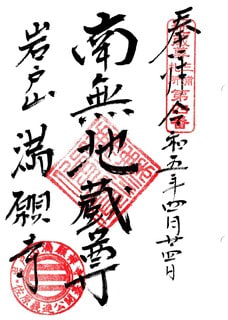
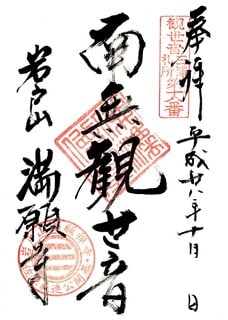
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印
第5番
御霊山 満蔵院 正業寺
横須賀市久里浜2-19-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/子育地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場10番、三浦半島観音三十三札所24番、三浦半島四十八阿弥陀霊場29番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・永禄九年(1566年)寂の僧・入誉元清の建立と伝わり、慶安元年(1648年)芝増上寺第21世還無上人が開山再興、元禄十一年(1698年)、内川新田開拓の砂村新左衛門の甥が現在地に移築とされる浄土宗寺院。
・江戸期の作とされる札所本尊は本堂内に奉安。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
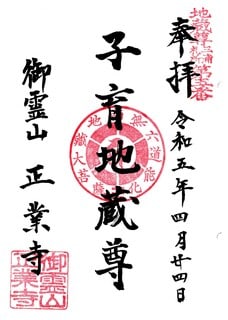
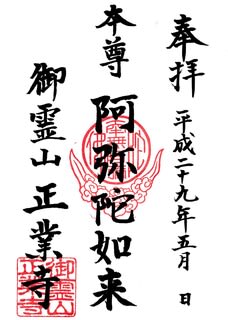
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第6番
亀養山 松樹院 長安寺
横須賀市久里浜2-8-9
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場9番、三浦二十一ヶ所薬師霊場10番、三浦干支守り本尊八佛霊場1番、三浦半島観音三十三札所23番、三浦半島四十八阿弥陀霊場28番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・天文二年(1533年)、鎌倉光明寺19世然誉上人により開山とされる浄土宗寺院。
・浄土宗寺院ながら著名なお不動様を奉安し、「丸山不動明王」「火伏せ不動」、また朝比奈三郎義家の守本尊と伝わる不動尊も御座される模様。
・札所本尊の地蔵尊は、三浦干支守り本尊八佛霊場の札所本尊・勢至菩薩と並んで庫裡横の仏殿に御座される。


【写真 上(左)】 回向柱と向拝
【写真 下(右)】 地蔵尊(右)と勢至菩薩(左)
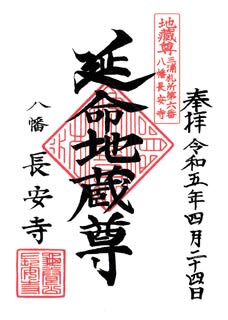
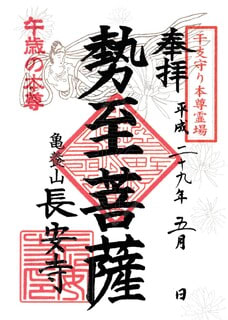
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 三浦干支守り本尊八佛霊場・勢至菩薩の御朱印
第7番
明星山 西生院 傳福寺
横須賀市久里浜8-23-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/多幸地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場12番、三浦二十一ヶ所薬師霊場9番、三浦干支守り本尊八佛霊場2番、三浦半島四十八阿弥陀霊場27番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・久里浜にある大永七年(1527年)開山の浄土宗寺院。
・札所本尊は本堂向かって左側の地蔵堂内に奉安。高さ124cmの迫力の半跏像。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 札所本尊
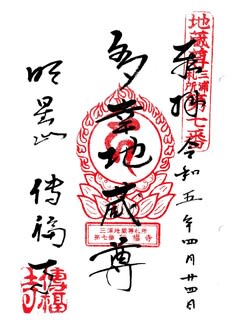
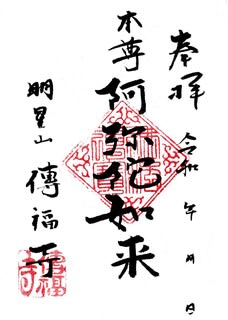
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第8番
高御蔵五明山 最寶寺
横須賀市野比1-51-1
浄土真宗本願寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊(たから地蔵尊)
他札所:三浦二十八不動尊霊場11番、三浦二十一ヶ所薬師霊場11番、三浦半島観音三十三札所22番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印不授与?
・源頼朝公が鎌倉扇ヶ谷に創建、建久六年(1195年)寺地を鎌倉弁ヶ谷に移した。
・開基は明光、当初は天台宗で薬師如来を本尊とし、後に浄土真宗に改宗。
・大永元年(1521年)火災を契機に現在地に移転。
・浄土真宗寺院ながら多くの霊場札所を務められ、御朱印も授与されている。(御開帳時のみ?)
・札所本尊は本堂向かって左手の仏間に奉安され、回向柱は本堂左手妻側に設けられている。


【写真 上(左)】 回向柱と向拝
【写真 下(右)】 堂内
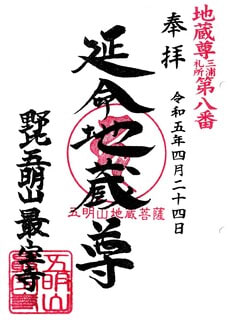
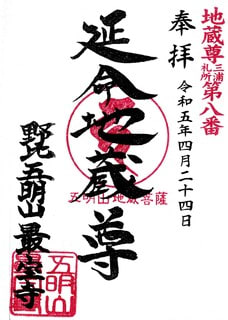
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(御朱印帳印判捺)
第9番
七寶山 東光寺
横須賀市津久井5-8-3
高野山真言宗
御本尊:大日如来・薬師如来・地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場11番、三浦二十一ヶ所薬師霊場11番、三浦半島観音三十三札所22番
※御本尊(大日如来・薬師如来)の御朱印はいずれも授与(繁忙時は不明)
・第9番札所は荘厳寺(横須賀市津久井3-7-1)から十却寺(三浦市南下浦町上宮田3527)と遷り、現在は東光寺となっている。
・行基菩薩が諸国行脚の際、当郷にて草庵を結び地蔵菩薩像を御作。
・当庵で三浦富士大権現の夢告を受け薬師三尊と十二神将の御作され、当寺を建立という。
・その後、三浦の庄司、平義継の二男・津久井次郎義行が当山を祈祷所と定めて中興。
・旧9番の荘厳寺(津久井)十劫寺(下浦町上宮田)に替わり新たに9番札所となる。
・札所本尊は本堂とは別棟で御開帳。堂棟内で地蔵尊のほか、弘法大師、大日如来、薬師如来、不動明王など多彩な尊格の御朱印を揮毫授与されている。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御開帳場の別棟
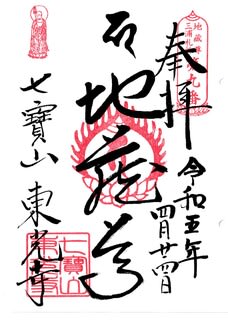
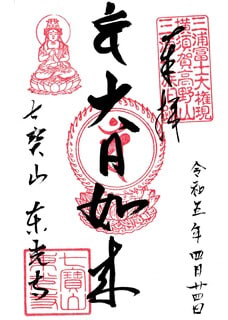
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(大日如来)の御朱印
第10番
海東山 三樹院
三浦市南下浦町上宮田601
浄土宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/子育延命地蔵菩薩
他札所:三浦三十三観音霊場10番
※御本尊(十一面観世音菩薩)、宗派本尊(阿弥陀如来)の御朱印はいずれも書置授与
・木曽義仲四天王の一人・今井四郎兼平が出陣の折この地に仮屋を設けたのが草創で、のちに鈴木某なる者が兼平の仮屋を移設し、伽藍を整えて旧上宮田岩井口の十劫寺の子院とした。
・宝永五年(1709年)、芝増上寺遍誉了海上人が應行上人作の十一面観世音菩薩(今井の観音さま)を笈来、当山の御本尊と改めたという。
・札所本尊は近在の地蔵堂に安置されていた子育延命地蔵菩薩で、本堂内に奉安されている。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
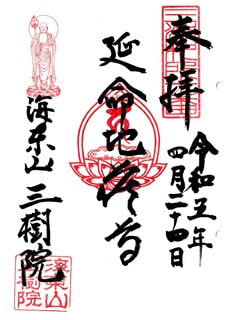
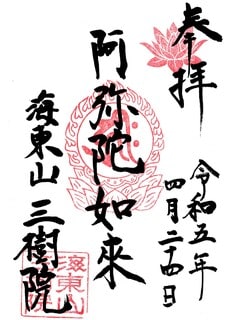
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第11番
牛込山 永楽寺
三浦市南下浦町菊名312
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/紫雲地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場14番
・札所本尊は「紫雲地蔵尊」、三浦二十八不動尊霊場の札所本尊は「牛込不動尊」と呼ばれてともに尊崇される。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印は現時点で不授与の模様

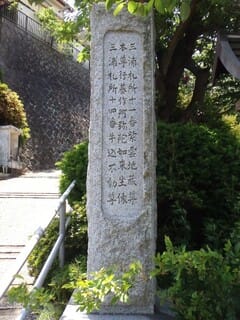
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 札所標
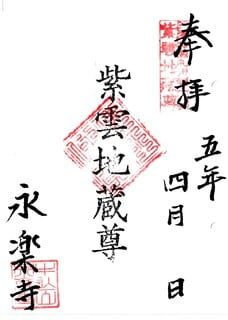
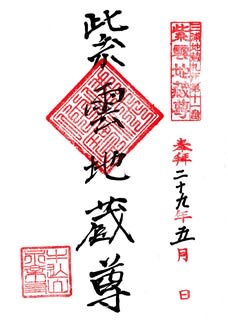
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(以前)
第12番
岩浦山 福壽寺
三浦市南下浦町金田2062
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
※御本尊(聖観世音菩薩/三浦三十三観音霊場)御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・正治二年(1200年)、三浦大介義明の孫三浦駿河守義村が開基と伝わる。
・御本尊は行基菩薩の御作とされ、寺宝として三浦義村使用の鞍・鎧・脇差などを収蔵。


【写真 上(左)】 回向柱と向拝
【写真 下(右)】 本堂内
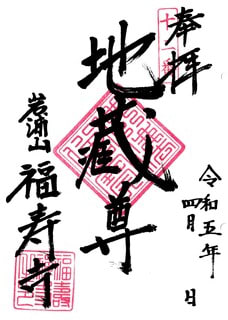
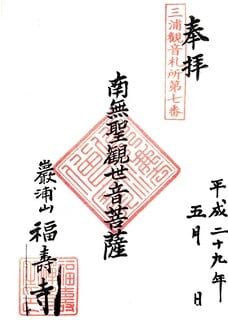
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印(三浦三十三観音霊場)
第13番
千光山 福泉寺
三浦市南下浦町松輪1421
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:-
※御本尊(聖観世音菩薩)御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・「松輪サバ」で知られる松輪にある浄土宗寺院。
・正中元年(1324年)創建、元禄十六年(1704年)の大津波により流失し現在地に移転再建と伝わる。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
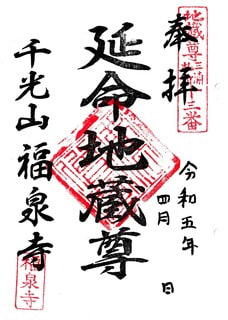
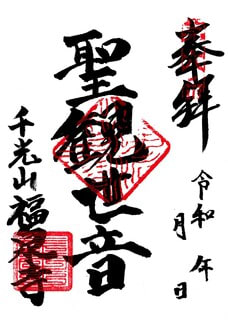
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(聖観世音菩薩)の御朱印
第14番
海潮山 眞浄院
三浦市栄町3-16
臨済宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/身代り地蔵尊・延命地蔵尊
・以前は海汐寺と号した地蔵尊ゆかりの寺院。
・永正十五年(1516年)、北条早雲に攻められた新井城の三浦道寸義同は、最後の決戦を三崎城の出口茂忠に伝える伝令を家臣・川島身七に託した。
・身七は任を果たしたが新井城はすでに落城、身七は海汐寺の前身の地蔵堂に身を隠したものの追手は身七を発見しその首をはねた。しかし追手が切ったのは身七の首ではなく地蔵尊の首で、身七は地蔵尊の身代りにより難を遁れた。
・身七は地蔵尊への報恩と新井城の朋友の菩提を弔うため剃髪して地蔵坊と名乗り、一生をこの寺で過ごしたと伝わる。


【写真 上(左)】 回向柱
【写真 下(右)】 回向柱と向拝

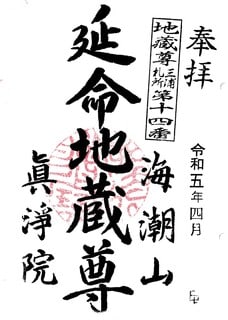
【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 御朱印(専用納経帳/今回)
第15番
海光山 本瑞寺
三浦市三崎1-19-1
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊(子育地蔵尊)
他札所:関東百八地蔵尊霊場88番、三浦半島観音三十三札所19番
・三崎の高台にある名刹。風光明媚な地にあり源頼朝公ゆかりの「桜の御所」とも呼ばれる。
・康平年間(1058-1065年)、三浦為継が鎌倉に創建、永正元年(1504年)この地に移転。
・御本尊の地蔵菩薩(延命地蔵尊)は弘法大師の御作で三浦道寸父子の御持佛とも伝わる。
・『(関東)百八地蔵尊めぐり』によると、三浦地蔵尊霊場の札所本尊は開山堂の「子育地蔵尊」とあり、関東百八地蔵尊霊場の御朱印は「延命地蔵尊」とあるが、三浦地蔵尊霊場の御開帳では「子育地蔵尊」「延命地蔵尊」の両尊御開帳されていた。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
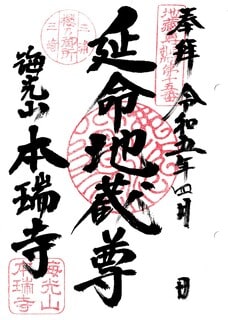
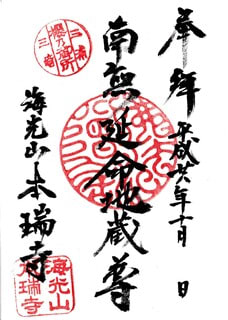
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印(関東百八地蔵尊霊場)
第16番
飯盛山 明王院 妙音寺 (三浦大師)
三浦市初声町下宮田119
高野山真言宗
御本尊:不空羂索観世音菩薩・地蔵菩薩
※寺院公式Webでは不空羂索観世音菩薩、当霊場公式Webには地蔵菩薩とある。
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場14番、三浦二十八不動尊霊場15番、関東八十八箇所58番、七観音霊場4番、東国花の寺百ヶ寺霊場78番、三浦半島秋の七草霊場4番、三浦干支守り本尊八佛霊場3番、三浦七福神(鶴園福禄寿)、富士見楽寿(ぼけ封じ)観音霊場 1番
※御本尊(不空羂索観世音菩薩)御朱印拝受済(複数霊場)
・第16番札所は西浜地蔵堂(三浦市三崎5-14-7)から妙音寺に入れ替えとなっている。
・鎌倉時代初期に妙音寺原に草創、天正年間の1580年代に賢栄法印により現在地に移されて中興。小田原北条氏五代の雨乞い祈願所として庇護されたという。
・多くの霊場札所を兼務される高野山真言宗の寺院で、花の寺としても知られている。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 御開帳案内
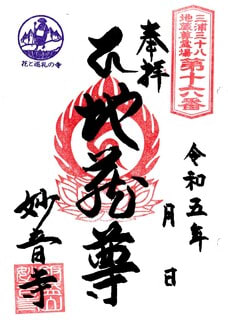
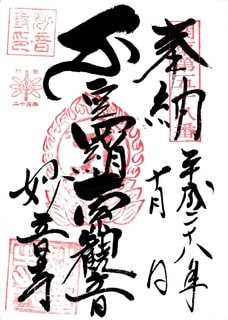
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(不空羂索観世音菩薩)の御朱印(関東八十八箇所)
第17番
五劫山 宝泉寺 天養院
三浦市初声町和田1669
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来(三尊)
札所本尊:地蔵菩薩/地蔵願王尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場14番、三浦半島四十八阿弥陀霊場19番
※御本尊(阿弥陀如来(三尊))の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・永禄二年(1559年)長澤和泉が開基、真蓮社性誉上人が開山と伝わる。
・別尊の薬師如来像は和田義盛の「身代わり薬師」とも呼ばれて県指定有形文化財。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
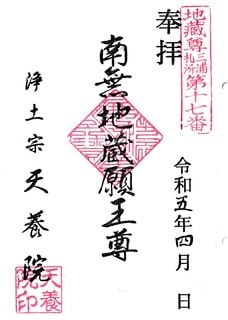
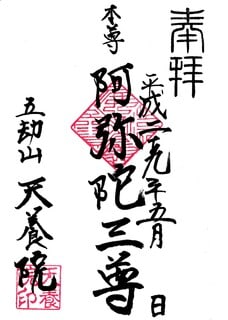
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来(三尊))の御朱印
第18番
宝林山 正住寺
横須賀市林5-1-5
浄土宗
御本尊:定印観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:三浦三十三観音霊場30番、三浦二十八不動尊霊場18番
・文明元年(1469年)、八代将軍足利義政公開基とされる名刹。
・御本尊の定印観世音菩薩は義政公の守本尊と伝わる。
※御本尊(阿弥陀如来(三尊))の御朱印拝受済(当御開帳中の授与は繁忙時は困難かも)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内
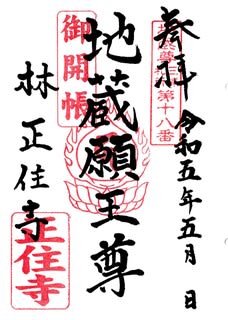
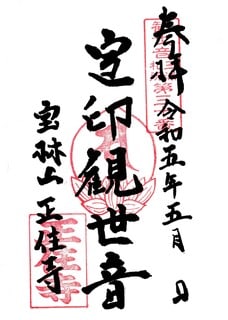
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(定印観世音菩薩)の御朱印
第19番
金剛山 勝長寿院 浄楽寺 (大御堂)
横須賀市芦名2-30-5
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十八不動尊霊場20番、三浦二十一ヶ所薬師霊場15番、三浦干支守り本尊八佛霊場6番、三浦半島観音三十三札所8番、三浦半島四十八阿弥陀霊場11番、三浦半島七阿弥陀霊場2番、三浦半島毘沙門天七ヶ所霊場6番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与されている模様)
・文治五年(1189年)に源頼朝公が父・義朝公の菩提のために創建した鎌倉・勝長寿院(大御堂)を、建永元年(1206年)の大風による堂宇破損で和田義盛と北条政子が現在地に移したと伝わる名刹。
・建治元年(1275年)に鎌倉光明寺2世・白幡流寂慧良暁上人が中興開山とされる
・運慶作とされる不動明王立像、毘沙門天立像のほか、御本尊・阿弥陀三尊も国の重要文化財に指定されている。
・札所本尊の延命地蔵尊は享保年間(1716-1735年)、悪疫流行の際に厄難消滅を祈願して造立。四十八夜の別時法要を営み、願成就された霊験あらたかな地蔵尊と伝わる。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 地蔵堂
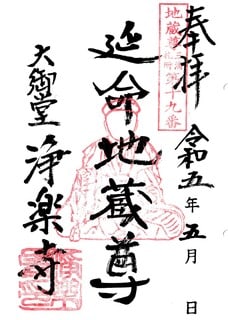
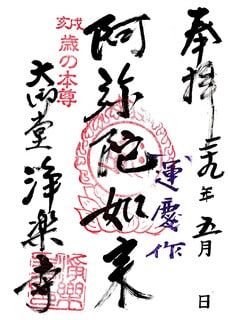
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第20番
紫雲山 秋谷寺 正行院
公式Web
横須賀市秋谷2-16-2
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場17番、三浦半島観音三十三札所7番、三浦半島四十八阿弥陀霊場10番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も書置授与されています)
・正治元年(1199年)侍所別当の和田義盛が妻の巴御前の菩提寺として、現在の横須賀市秋谷の乗越海岸に建立したのが草創とされる。
・明応七年(1499年)鎌倉光明寺9世・観誉祐崇上人が現在地に遷されて開山し、巴御前の遺髪が埋蔵されたという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内
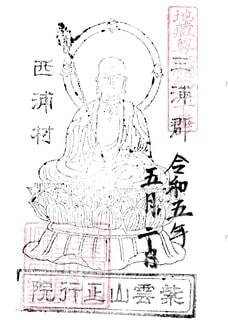
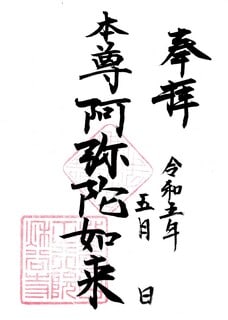
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
■ 三浦三十八地蔵尊霊場の御開帳-2へつづく。
【 BGM 】
■ Christopher Cross - Sailing (Official Audio)
■ Boz Scaggs - Isn't It Time
■ Boy Meets Girl - Waiting For A Star To Fall
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 三浦三十八地蔵尊霊場の御開帳-2
■ 三浦三十八地蔵尊霊場の御開帳-1からのつづきです。




第21番
景政山 長運寺 (葉山厄除不動尊)
公式Web
葉山町長柄615
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:地蔵菩薩/地蔵十王図
他札所:三浦二十八不動尊霊場25番、湘南七福神(布袋尊)
※御本尊(不動明王)の御朱印拝受済(三浦二十八不動尊霊場/当御開帳中も書置授与)
・第21番札所は円乗院(横須賀市秋谷4387)から西徳寺(横須賀市鴨居2-20)と遷り、現在は長運寺となっている。
・大永年間(1521-1527年)、長江義景が祖父・鎌倉権五郎景正の菩提のため宥海を開基に創建と伝わる。
・御本尊の木造不動明王と二童子像、および地蔵十王図は葉山町の有形文化財に指定。
・札所本尊は地蔵十王図の掛軸。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内

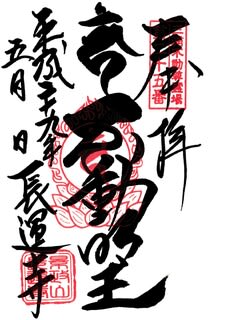
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(不動明王)の御朱印
第22番
沙白山 万福寺
葉山町下山口1515
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/鎌介身代わり地蔵
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場18番、三浦半島観音三十三札所5番、三浦半島四十八阿弥陀霊場9番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・前身は下山口平の里にあった満蔵院で、領主の鎌介という人が満蔵院御本尊の薬師如来の信仰篤く、明応四年(1495年)に寄進して現在地に寺を開基建立、鎌倉光明寺四代の法孫寂恵上人の法弟・源誓上人を招請して開山と仰ぎ「沙白山満蔵院万福寺」と号したという。
・藥師如来は行基の御作とも伝わる。
・札所本尊の地蔵菩薩は、鎌介が自身の姿を地蔵菩薩に写して造らせたと伝わり「鎌介身代わり地蔵」と呼ばれ、眼病平癒に御利益ありという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝

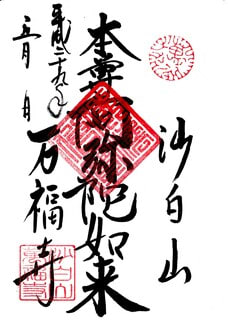
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第23番
長江山 無量寿院 相福寺
葉山町堀内568
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来(十夜仏)
札所本尊:地蔵菩薩/地蔵願王尊
他札所:三浦半島観音三十三札所3番、三浦半島四十八阿弥陀霊場5番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与あり。繁忙時不可かも)
・室町時代に鎌倉光明寺を本山として建立されたという浄土宗寺院。
・御本尊の阿弥陀如来坐像は葉山町の有形文化財で、葉山町Web資料には「天明八年(1788年)の鎌倉光明寺からの送り状によれば、本像は光明寺の秘仏であったのである。(中略)光明寺は仁治元年(1240年)佐助ヶ谷に開かれた蓮乗寺がその前身と伝えられる。(中略)この光明寺から移安された阿弥陀如来像は、光明寺の秘仏だったとあるから、或は蓮乗寺の本尊だったのかも知れない。」とある。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
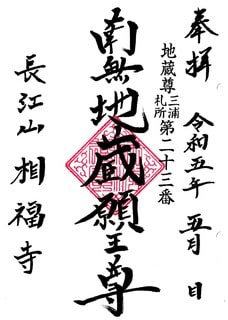

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第24番
黄雲山 地蔵密院 延命寺 (逗子大師)
公式Web
逗子市逗子3-1-17
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵菩薩(元本尊)
他札所:新四国東国八十八ヶ所霊場80番、三浦二十八不動尊霊場28番、三浦半島観音三十三札所1番、三浦干支守り本尊八佛霊場8番、湘南七福神(弁財天)
※御本尊(金剛界大日如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与あり)
・天平年間(724-749年)行基菩薩が開創され、御作の延命地蔵菩薩座像を御本尊として安置と伝わる。
・弘法大師巡錫のみぎり当山に立寄られ、延命地蔵菩薩を安置する御厨子を設けられたことから、当地を「厨子」と呼び「逗子」の地名の発祥となったとされる。
・鎌倉期には三浦一族の祈願寺となり、戦国期には後北条氏の帰依を得て天文年間に朝賢が中興、現在に至るまで「逗子大師」として人々の信仰を集める。
・貞享四年(1687年)伽藍竣工の際に、新たに大日如来尊像を造立して御本尊としたが、延命地蔵菩薩座像は「元本尊」(秘仏)として篤く奉安されている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 地蔵尊

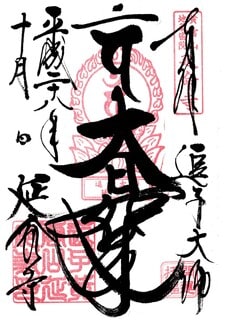
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(金剛界大日如来)の御朱印
第25番
長谷山 海宝院
逗子市沼間2-12-15
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/子育地蔵尊
他札所:-
※御本尊(十一面観世音菩薩)の御朱印拝受済(当御開帳中の書置授与あり)
・天正十八年(1590年)北条氏滅亡後、代官頭長谷川七左衛門長綱が徳川家康公から預かった十一面観世音菩薩を御本尊に、現在の良長院(横須賀市緑が丘)の地に駿河保壽寺の之源臨呼和尚を招聘して開山。当初は良長院と号した。
・慶長年間(1596-1615年)現在地に移転。
・家康公から拝領とされる陣鐘(梵鐘)は県指定重要文化財。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
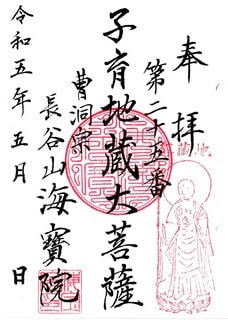

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(十一面観世音菩薩)の御朱印
第26番
楽浦山 能永寺
横須賀市浦郷町2-83
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:追浜七福神(弁財天)
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・応永元年(1394年)開山の時宗寺院。
・札所本尊の延命地蔵尊の腹部に、小さな木仏の地蔵尊が胎籠されている。
・地蔵十王図の掛軸は横須賀市文化財に指定。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)


【写真 上(左)】 回向柱と本堂
【写真 下(右)】 堂内
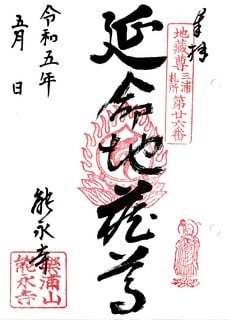

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第27番
宮谷山 至心院 信楽寺
横須賀市大津町3-29-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦半島観音三十三札所32番、三浦半島四十八阿弥陀霊場39番
・永正元年(1504年)、証誉上人の開山と伝わる浄土宗寺院で、御本尊の阿弥陀如来は運慶作とも伝わる。
・別尊の聖観世音菩薩は伝・行基作で、熊谷直実の守護仏とも伝わる。
・坂本龍馬の妻、楢崎龍(おりょうさん)の墓がある。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)

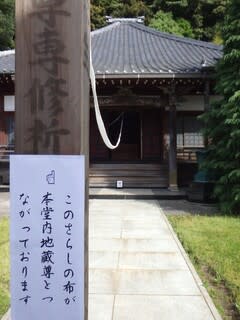
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
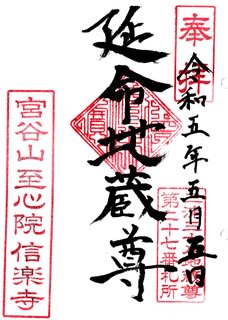
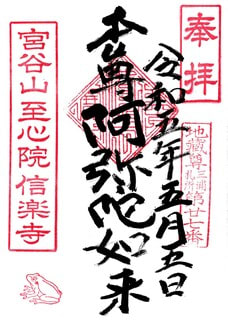
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第28番
竹林山 貞昌寺
横須賀市馬堀町 1-104
臨済宗円覚寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:-
・開創は建武二年(1335年)、南山士雲禅師が開山と伝わる。
・寛文三年(1663年)、船手奉行の向井将監正方が母・貞昌院の菩提を弔うため母の法号にちなんで谷戸奥の吸江庵を貞昌寺と改号したという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝

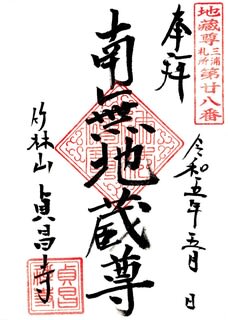
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 地蔵尊の揮毫御朱印
第29番
七重山 宝寿院 浄林寺
横須賀市馬堀町4-14-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来(阿弥陀三尊)
札所本尊:地蔵菩薩/厄除延命地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場20番、三浦二十一ヶ所薬師霊場5番、三浦半島観音三十三札所31番、三浦半島四十八阿弥陀霊場38番
※御本尊(阿弥陀如来(阿弥陀三尊))の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)
・永正二年(1505年)創建の浄土宗寺院。
・坂上の馬頭観音堂には「馬堀」の地名の由来である名馬・生唼(いきづき)の像や「蹄の井」(ひづめのい)があり、当山の馬頭観世音菩薩は三浦三十三観音霊場第20番の札所本尊。
・境内のムクロジは「かまくらと三浦半島の古木・名木50選」に指定されている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
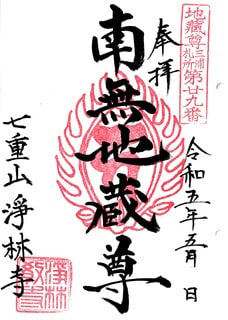
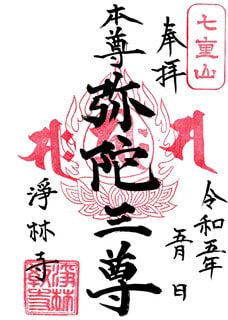
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀三尊)の御朱印
第30番
走水山 大泉寺
横須賀市走水2-11-13
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵菩薩
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場20番、三浦半島観音三十三札所29番
・天正十八年(1590年)、家康公の関東入国時に三浦郡代官頭となった長谷川七左衛門長綱が開基となり、逗子海宝院の伝英和尚を招いて開山と伝わる。
・幕末の黒船来航の折には、海防に従事した川越藩の定宿となった。
・札所本尊の延命地蔵尊は室町初期の作とされ、横須賀市有形文化財に指定されている。


【写真 上(左)】 参道&本堂
【写真 下(右)】 堂内

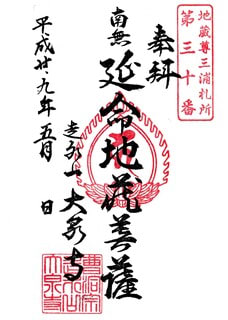
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 地蔵尊の御朱印(以前)
第31番
鴨居山 能満寺
横須賀市鴨居2-24-1
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場7番
※御本尊(虚空蔵菩薩)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・明応六年(1497年)の創建と伝わり、長谷川七左衛門長綱が代官頭として浦賀に赴任したときに曹洞宗に改宗という。
・御本尊の虚空蔵菩薩は行基の作とも伝わり、「福徳・知恵」を授かるために13歳の子供が3月13日(現在は4月13日)に詣でる「十三参」で知られる。
・薬師堂の多光薬師如来像は「蛸薬師」とも呼ばれ、眼病快癒や豊漁祈願に霊験あらたかとされる。
・木食観正ゆかりの寺としても知られる。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内
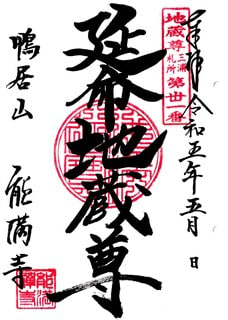

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(虚空蔵菩薩)の御朱印
第32番
東光山 無量寿院 西徳寺
横須賀市鴨居2-20-4
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/和田地蔵尊
他札所:三浦半島観音三十三札所28番、三浦半島四十八阿弥陀霊場36番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)
・第32番札所は常福寺(横須賀市西浦賀2-16-1)から西徳寺に入れ替えとなっている。
・鎌倉光明寺の末寺で、永祿元年(1558年)、光明寺法主の高弟、法誉順性上人が真言宗源徳寺、浄土真宗無量庵、浄土宗東光寺および寿経寺の四箇寺をまとめ、東光山無量寿院西徳寺と号したという。
・札所本尊の和田地蔵尊は、鎌倉御家人の和田義盛が当山の前の和田川に地蔵尊を沈め、戦で勝つことができるなら川上へ、敗れるなら川下へ流れるよう占ったところ、川上へ流れたため義盛は喜び、地蔵尊を引き上げてお堂を建て奉安したと伝わる。
・腫れ物や百日咳に霊験あらたかで、篤い信仰を集める。
・山内墓域には「和田義盛の髭剃塚」もある。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 和田地蔵尊


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第33番
延命山 東福寺
横須賀市西浦賀2-2-1
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵菩薩
他札所:三浦三十三観音霊場13番
・明応九年(1500年)、明海上人により真言宗寺院として開創。
・天正十八年(1590年)、三浦半島が徳川家の直轄領となり、代官長谷川七左衛門のときに沼間海寶院3世一機直宗が曹洞宗に改宗して開山という。
・奉安する聖観世音菩薩は海難除けとして浦賀港の出入船の航海の安全を祈願していることから、歴代の浦賀奉行も参拝に訪れたという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印帳受けの御朱印(印判)
第34番
放光山 延寿院 常福寺
横須賀市西浦賀2-16-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/子育地蔵尊、延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場8番、三浦二十八不動尊霊場7番、三浦半島四十八阿弥陀霊場32番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)
・文明年間(1469-1486年)鎌倉光明寺の圓蓮社教譽上人による開創で、浦賀の本陣(御用寺院)とされていた。
・「閻魔堂」の閻魔さまは、毎年1月16日と7月16日に開扉されたいへん賑わったと伝わる。開扉時に掛けられた「地獄極楽図」は狩野常信の作という。
・地蔵尊札所として第32番が子育地蔵尊、第34番が延命地蔵尊であったところ、第34番が子育地蔵尊、延命地蔵尊の二尊奉安の札所となり、第32番は現在、西徳寺(横須賀市鴨居2-20-4)となっている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内

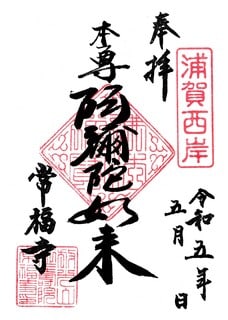
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第35番
浦賀山 立像院 東林寺
横須賀市東浦賀2-10-13
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦半島四十八阿弥陀霊場34番
・大永三年(1523年)立像院と東林寺を生蓮社専譽良道上人(唱阿上人とも)が合寺して開山と伝わる浄土宗寺院。
・奉安する善光寺式阿弥陀仏は室町時代初期の作風とみられ、横須賀市の文化財に指定されている。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
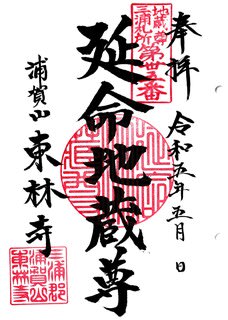
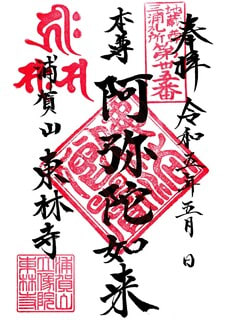
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第36番
金田山 圓福寺
三浦市南下浦町金田258
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦半島四十八阿弥陀霊場23番、三浦七福神(恵比寿尊)
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・天文十七年(1548年)、海岸にあった地蔵堂を現在地に遷し金田山圓福寺と号した。
・開山は鎌倉光明寺の伝設大和尚。
・札所本尊の地蔵菩薩は室町時代初期ないし南北朝時代の作と推定され、三浦市の重要文化財に指定されている。
・大漁の神として信仰篤い「金光恵比須尊」は、三浦七福神の一尊となっている。
※御本尊(阿弥陀如来・六字御名号)の御朱印は書置授与


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂内
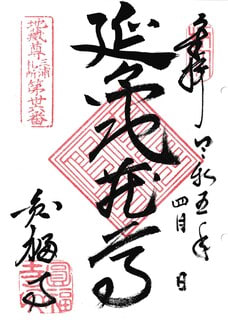

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(六字御名号)の御朱印
第37番
立光山 海應寺
三浦市南下浦町毘沙門1936
臨済宗円覚寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場5番、円覚寺百観音霊場14番
・鎌倉円覚寺36世無礙妙謙禅師を開山とし、六百年余の歴史をもつという古刹ながら寺伝を焼失し沿革等は定かでない。
・奉安する聖観世音菩薩は、かつて海上の安全を願って海辺のお堂に安置されていたが、当山に御遷座され三浦二十八不動尊霊場、円覚寺百観音霊場の札所本尊となっている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 同(以前)
番外(第38番)
(延命山 西往寺) 本町延命地蔵尊
横須賀市汐入町3-18
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/本町延命地蔵尊
他札所:-
・『新編相模国風土記稿』によると宝永年間(1704-1714年)、良長院の末寺として延命山西往寺と号し、御本尊を地蔵菩薩として旧浦賀街道筋の現・汐入小学校付近に建立。
・関東大震災の後に現在地に遷り交通安全祈願の地蔵尊として知られていたが、家内安全、商売繁盛、入学祈願、健康長寿などにも霊験あらたかとされ広く信仰を集める。


【写真 上(左)】 本町延命地蔵堂
【写真 下(右)】 堂内


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 結願証
【 BGM 】
■ Sneaker - More Than Just The Two Of Us
■ Bobby Caldwell - What You Won't Do for Love
■ Champagne - How 'Bout Us




第21番
景政山 長運寺 (葉山厄除不動尊)
公式Web
葉山町長柄615
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:地蔵菩薩/地蔵十王図
他札所:三浦二十八不動尊霊場25番、湘南七福神(布袋尊)
※御本尊(不動明王)の御朱印拝受済(三浦二十八不動尊霊場/当御開帳中も書置授与)
・第21番札所は円乗院(横須賀市秋谷4387)から西徳寺(横須賀市鴨居2-20)と遷り、現在は長運寺となっている。
・大永年間(1521-1527年)、長江義景が祖父・鎌倉権五郎景正の菩提のため宥海を開基に創建と伝わる。
・御本尊の木造不動明王と二童子像、および地蔵十王図は葉山町の有形文化財に指定。
・札所本尊は地蔵十王図の掛軸。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内

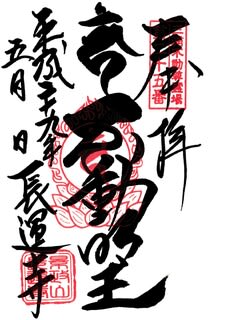
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(不動明王)の御朱印
第22番
沙白山 万福寺
葉山町下山口1515
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/鎌介身代わり地蔵
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場18番、三浦半島観音三十三札所5番、三浦半島四十八阿弥陀霊場9番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・前身は下山口平の里にあった満蔵院で、領主の鎌介という人が満蔵院御本尊の薬師如来の信仰篤く、明応四年(1495年)に寄進して現在地に寺を開基建立、鎌倉光明寺四代の法孫寂恵上人の法弟・源誓上人を招請して開山と仰ぎ「沙白山満蔵院万福寺」と号したという。
・藥師如来は行基の御作とも伝わる。
・札所本尊の地蔵菩薩は、鎌介が自身の姿を地蔵菩薩に写して造らせたと伝わり「鎌介身代わり地蔵」と呼ばれ、眼病平癒に御利益ありという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝

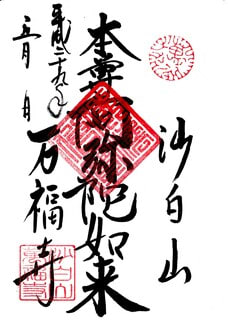
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第23番
長江山 無量寿院 相福寺
葉山町堀内568
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来(十夜仏)
札所本尊:地蔵菩薩/地蔵願王尊
他札所:三浦半島観音三十三札所3番、三浦半島四十八阿弥陀霊場5番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与あり。繁忙時不可かも)
・室町時代に鎌倉光明寺を本山として建立されたという浄土宗寺院。
・御本尊の阿弥陀如来坐像は葉山町の有形文化財で、葉山町Web資料には「天明八年(1788年)の鎌倉光明寺からの送り状によれば、本像は光明寺の秘仏であったのである。(中略)光明寺は仁治元年(1240年)佐助ヶ谷に開かれた蓮乗寺がその前身と伝えられる。(中略)この光明寺から移安された阿弥陀如来像は、光明寺の秘仏だったとあるから、或は蓮乗寺の本尊だったのかも知れない。」とある。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
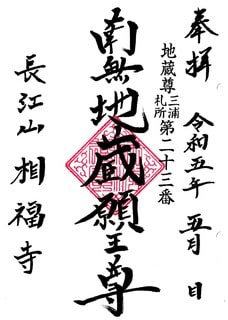

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第24番
黄雲山 地蔵密院 延命寺 (逗子大師)
公式Web
逗子市逗子3-1-17
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵菩薩(元本尊)
他札所:新四国東国八十八ヶ所霊場80番、三浦二十八不動尊霊場28番、三浦半島観音三十三札所1番、三浦干支守り本尊八佛霊場8番、湘南七福神(弁財天)
※御本尊(金剛界大日如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与あり)
・天平年間(724-749年)行基菩薩が開創され、御作の延命地蔵菩薩座像を御本尊として安置と伝わる。
・弘法大師巡錫のみぎり当山に立寄られ、延命地蔵菩薩を安置する御厨子を設けられたことから、当地を「厨子」と呼び「逗子」の地名の発祥となったとされる。
・鎌倉期には三浦一族の祈願寺となり、戦国期には後北条氏の帰依を得て天文年間に朝賢が中興、現在に至るまで「逗子大師」として人々の信仰を集める。
・貞享四年(1687年)伽藍竣工の際に、新たに大日如来尊像を造立して御本尊としたが、延命地蔵菩薩座像は「元本尊」(秘仏)として篤く奉安されている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 地蔵尊

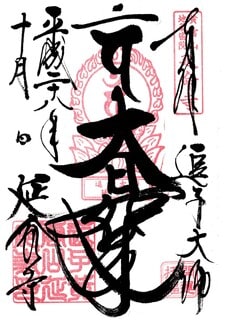
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(金剛界大日如来)の御朱印
第25番
長谷山 海宝院
逗子市沼間2-12-15
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/子育地蔵尊
他札所:-
※御本尊(十一面観世音菩薩)の御朱印拝受済(当御開帳中の書置授与あり)
・天正十八年(1590年)北条氏滅亡後、代官頭長谷川七左衛門長綱が徳川家康公から預かった十一面観世音菩薩を御本尊に、現在の良長院(横須賀市緑が丘)の地に駿河保壽寺の之源臨呼和尚を招聘して開山。当初は良長院と号した。
・慶長年間(1596-1615年)現在地に移転。
・家康公から拝領とされる陣鐘(梵鐘)は県指定重要文化財。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
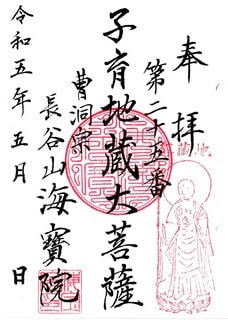

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(十一面観世音菩薩)の御朱印
第26番
楽浦山 能永寺
横須賀市浦郷町2-83
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:追浜七福神(弁財天)
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・応永元年(1394年)開山の時宗寺院。
・札所本尊の延命地蔵尊の腹部に、小さな木仏の地蔵尊が胎籠されている。
・地蔵十王図の掛軸は横須賀市文化財に指定。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)


【写真 上(左)】 回向柱と本堂
【写真 下(右)】 堂内
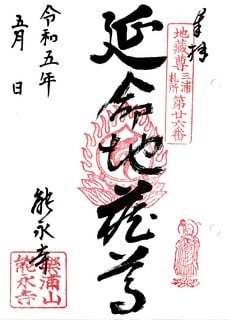

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第27番
宮谷山 至心院 信楽寺
横須賀市大津町3-29-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦半島観音三十三札所32番、三浦半島四十八阿弥陀霊場39番
・永正元年(1504年)、証誉上人の開山と伝わる浄土宗寺院で、御本尊の阿弥陀如来は運慶作とも伝わる。
・別尊の聖観世音菩薩は伝・行基作で、熊谷直実の守護仏とも伝わる。
・坂本龍馬の妻、楢崎龍(おりょうさん)の墓がある。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)

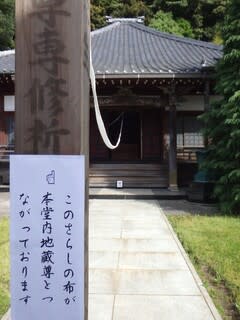
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
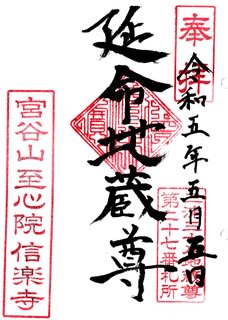
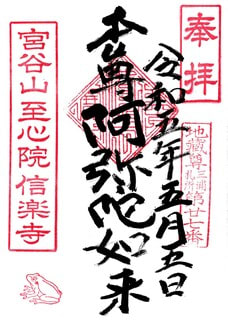
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第28番
竹林山 貞昌寺
横須賀市馬堀町 1-104
臨済宗円覚寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:-
・開創は建武二年(1335年)、南山士雲禅師が開山と伝わる。
・寛文三年(1663年)、船手奉行の向井将監正方が母・貞昌院の菩提を弔うため母の法号にちなんで谷戸奥の吸江庵を貞昌寺と改号したという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝

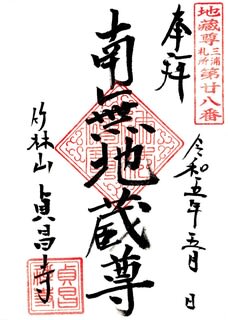
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 地蔵尊の揮毫御朱印
第29番
七重山 宝寿院 浄林寺
横須賀市馬堀町4-14-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来(阿弥陀三尊)
札所本尊:地蔵菩薩/厄除延命地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場20番、三浦二十一ヶ所薬師霊場5番、三浦半島観音三十三札所31番、三浦半島四十八阿弥陀霊場38番
※御本尊(阿弥陀如来(阿弥陀三尊))の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)
・永正二年(1505年)創建の浄土宗寺院。
・坂上の馬頭観音堂には「馬堀」の地名の由来である名馬・生唼(いきづき)の像や「蹄の井」(ひづめのい)があり、当山の馬頭観世音菩薩は三浦三十三観音霊場第20番の札所本尊。
・境内のムクロジは「かまくらと三浦半島の古木・名木50選」に指定されている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 回向柱と向拝
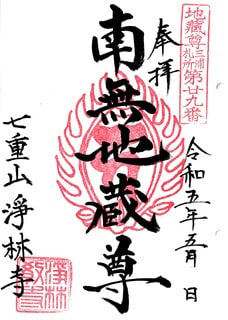
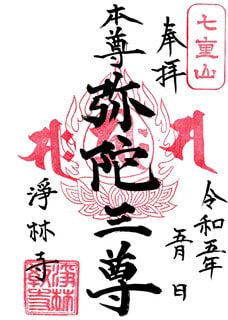
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀三尊)の御朱印
第30番
走水山 大泉寺
横須賀市走水2-11-13
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵菩薩
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場20番、三浦半島観音三十三札所29番
・天正十八年(1590年)、家康公の関東入国時に三浦郡代官頭となった長谷川七左衛門長綱が開基となり、逗子海宝院の伝英和尚を招いて開山と伝わる。
・幕末の黒船来航の折には、海防に従事した川越藩の定宿となった。
・札所本尊の延命地蔵尊は室町初期の作とされ、横須賀市有形文化財に指定されている。


【写真 上(左)】 参道&本堂
【写真 下(右)】 堂内

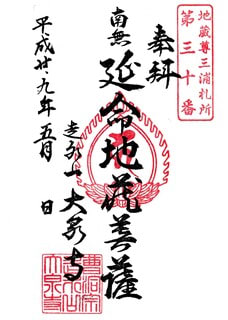
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 地蔵尊の御朱印(以前)
第31番
鴨居山 能満寺
横須賀市鴨居2-24-1
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場7番
※御本尊(虚空蔵菩薩)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・明応六年(1497年)の創建と伝わり、長谷川七左衛門長綱が代官頭として浦賀に赴任したときに曹洞宗に改宗という。
・御本尊の虚空蔵菩薩は行基の作とも伝わり、「福徳・知恵」を授かるために13歳の子供が3月13日(現在は4月13日)に詣でる「十三参」で知られる。
・薬師堂の多光薬師如来像は「蛸薬師」とも呼ばれ、眼病快癒や豊漁祈願に霊験あらたかとされる。
・木食観正ゆかりの寺としても知られる。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内
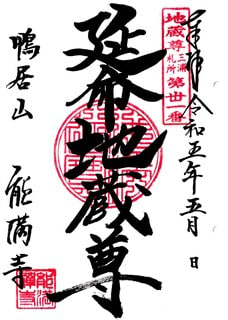

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(虚空蔵菩薩)の御朱印
第32番
東光山 無量寿院 西徳寺
横須賀市鴨居2-20-4
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/和田地蔵尊
他札所:三浦半島観音三十三札所28番、三浦半島四十八阿弥陀霊場36番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)
・第32番札所は常福寺(横須賀市西浦賀2-16-1)から西徳寺に入れ替えとなっている。
・鎌倉光明寺の末寺で、永祿元年(1558年)、光明寺法主の高弟、法誉順性上人が真言宗源徳寺、浄土真宗無量庵、浄土宗東光寺および寿経寺の四箇寺をまとめ、東光山無量寿院西徳寺と号したという。
・札所本尊の和田地蔵尊は、鎌倉御家人の和田義盛が当山の前の和田川に地蔵尊を沈め、戦で勝つことができるなら川上へ、敗れるなら川下へ流れるよう占ったところ、川上へ流れたため義盛は喜び、地蔵尊を引き上げてお堂を建て奉安したと伝わる。
・腫れ物や百日咳に霊験あらたかで、篤い信仰を集める。
・山内墓域には「和田義盛の髭剃塚」もある。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 和田地蔵尊


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第33番
延命山 東福寺
横須賀市西浦賀2-2-1
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵菩薩
他札所:三浦三十三観音霊場13番
・明応九年(1500年)、明海上人により真言宗寺院として開創。
・天正十八年(1590年)、三浦半島が徳川家の直轄領となり、代官長谷川七左衛門のときに沼間海寶院3世一機直宗が曹洞宗に改宗して開山という。
・奉安する聖観世音菩薩は海難除けとして浦賀港の出入船の航海の安全を祈願していることから、歴代の浦賀奉行も参拝に訪れたという。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御朱印帳受けの御朱印(印判)
第34番
放光山 延寿院 常福寺
横須賀市西浦賀2-16-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/子育地蔵尊、延命地蔵尊
他札所:三浦二十一ヶ所薬師霊場8番、三浦二十八不動尊霊場7番、三浦半島四十八阿弥陀霊場32番
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)
・文明年間(1469-1486年)鎌倉光明寺の圓蓮社教譽上人による開創で、浦賀の本陣(御用寺院)とされていた。
・「閻魔堂」の閻魔さまは、毎年1月16日と7月16日に開扉されたいへん賑わったと伝わる。開扉時に掛けられた「地獄極楽図」は狩野常信の作という。
・地蔵尊札所として第32番が子育地蔵尊、第34番が延命地蔵尊であったところ、第34番が子育地蔵尊、延命地蔵尊の二尊奉安の札所となり、第32番は現在、西徳寺(横須賀市鴨居2-20-4)となっている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 堂内

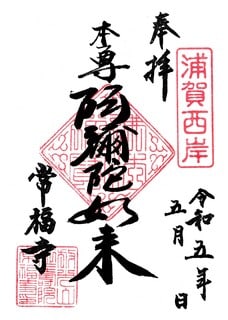
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第35番
浦賀山 立像院 東林寺
横須賀市東浦賀2-10-13
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦半島四十八阿弥陀霊場34番
・大永三年(1523年)立像院と東林寺を生蓮社専譽良道上人(唱阿上人とも)が合寺して開山と伝わる浄土宗寺院。
・奉安する善光寺式阿弥陀仏は室町時代初期の作風とみられ、横須賀市の文化財に指定されている。
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中も授与/繁忙時は不明)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
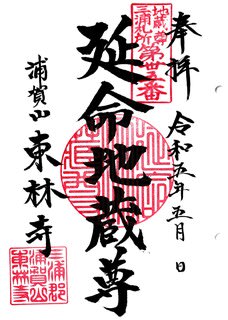
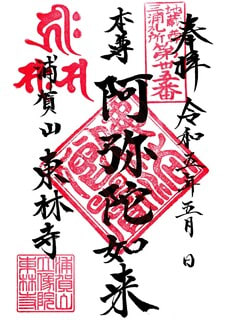
【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(阿弥陀如来)の御朱印
第36番
金田山 圓福寺
三浦市南下浦町金田258
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦半島四十八阿弥陀霊場23番、三浦七福神(恵比寿尊)
※御本尊(阿弥陀如来)の御朱印拝受済(当御開帳中の授与不明)
・天文十七年(1548年)、海岸にあった地蔵堂を現在地に遷し金田山圓福寺と号した。
・開山は鎌倉光明寺の伝設大和尚。
・札所本尊の地蔵菩薩は室町時代初期ないし南北朝時代の作と推定され、三浦市の重要文化財に指定されている。
・大漁の神として信仰篤い「金光恵比須尊」は、三浦七福神の一尊となっている。
※御本尊(阿弥陀如来・六字御名号)の御朱印は書置授与


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂内
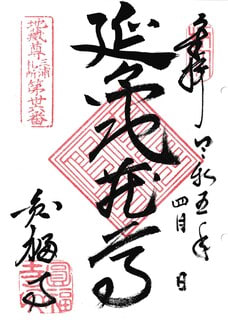

【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 御本尊(六字御名号)の御朱印
第37番
立光山 海應寺
三浦市南下浦町毘沙門1936
臨済宗円覚寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/延命地蔵尊
他札所:三浦三十三観音霊場5番、円覚寺百観音霊場14番
・鎌倉円覚寺36世無礙妙謙禅師を開山とし、六百年余の歴史をもつという古刹ながら寺伝を焼失し沿革等は定かでない。
・奉安する聖観世音菩薩は、かつて海上の安全を願って海辺のお堂に安置されていたが、当山に御遷座され三浦二十八不動尊霊場、円覚寺百観音霊場の札所本尊となっている。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 同(以前)
番外(第38番)
(延命山 西往寺) 本町延命地蔵尊
横須賀市汐入町3-18
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩/本町延命地蔵尊
他札所:-
・『新編相模国風土記稿』によると宝永年間(1704-1714年)、良長院の末寺として延命山西往寺と号し、御本尊を地蔵菩薩として旧浦賀街道筋の現・汐入小学校付近に建立。
・関東大震災の後に現在地に遷り交通安全祈願の地蔵尊として知られていたが、家内安全、商売繁盛、入学祈願、健康長寿などにも霊験あらたかとされ広く信仰を集める。


【写真 上(左)】 本町延命地蔵堂
【写真 下(右)】 堂内


【写真 上(左)】 御朱印(専用納経帳/今回)
【写真 下(右)】 結願証
【 BGM 】
■ Sneaker - More Than Just The Two Of Us
■ Bobby Caldwell - What You Won't Do for Love
■ Champagne - How 'Bout Us
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
※ 現在リニューアル中で、構成が錯綜しています。
【 真宗と信玄公 / 日蓮宗と信玄公 】
【 真宗と信玄公 】
■ 塩田山 超願寺



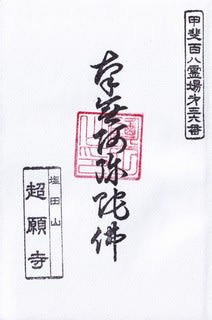
笛吹市一宮町塩田818
真宗大谷派 御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第36番
朱印尊格:南無阿弥陀佛 印判
札番:甲斐百八霊場第36番印判
・中央に山号印と「南無阿弥陀佛」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第三六番」の札所印。左に山号・寺号の印が捺されています。
真宗の御朱印(参拝記念)らしいシンプルな構成です。
文安四年(1447年)、布教のため甲斐を訪れた真宗8世・蓮如上人は、当時天台宗の寺院であった昌願寺を真宗に改め超願寺とされました。
織田信長と敵対した真宗本願寺派第十一世宗主顕如(光佐)の妻である如春尼は、信玄公の正室三条夫人の妹でした。
信玄公は加賀の一向一揆と結んで上杉謙信を牽制し、本願寺とも合力して信長包囲網を築いたとされ、真宗や本願寺との連携は政治的にも重要なものであったとみられています。
真宗本願寺勢力と織田信長公が刃を交えた石山合戦の際、超願寺の七世住職・喜西は石山の籠城に加わり、教如上人や下間頼龍とも親交があり、これを示す矢文が当寺に残っています。
甲斐の国は日蓮宗寺院も多く、甲斐百八霊場は、真宗や日蓮宗を含む多彩な宗派で構成されています。
■ 真宗大谷派東本願寺甲府別院 光澤寺
甲府市相生3-5-7
真宗大谷派 御本尊:阿弥陀如来
公式Web
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されていない模様です。
信玄公とふかいゆかりをもつ真宗の名刹です。
寺伝(公式Web)および資料Aから沿革等をまとめてみました。
天文十六年(1548年)、信玄公は当時鎌倉常葉町にあった一向宗蛇伏山長延寺(現在の真宗大谷派永勝寺:横浜市戸塚区)が相模北条氏と対立していた状況を憂慮され、住職実了師慶和尚を甲府へ招聘、広大な寺領を寄進し手厚い庇護を加えて長延寺として再興しました。
「超願寺」の記事でもふれましたが、信玄公は織田信長と敵対した真宗本願寺派第十一世宗主顕如(光佐)の妻である如春尼は、信玄公の正室三条夫人の妹でした。
信玄公は加賀の一向一揆と結んで上杉謙信を牽制し、本願寺とも合力して信長包囲網を築いたとされ、真宗や本願寺との連携は政治的にも重要なものであったとみられています。
実了和尚は僧として活躍するとともに、武田家御伽衆の有力メンバーであったとみられています。
御伽衆とは高級参謀兼外交特使といった役柄で、戦国時代に高僧が勤める例は少なくありません。
ちなみに「甲陽軍鑑」品第八(国会図書館DC、コマ番号26/265)には「長遠寺(実了師慶)といふ一向坊主をいつも江州浅井備前守そうじて上方へ計策に指上せらる 其年は一入様子能相調へ伊勢長島、大坂、和泉の堺下時 加賀越中迄も立寄 信玄公へ御味方の証文を取て参上いたす」とあり、実了師慶が上方から北陸までも足を伸ばして、各将の調略に奔走していたことがうかがわれます。
実了和尚の人徳に帰依した信玄公は、次男庄蔵(信親公・竜宝)の嫡男の信道公を実了和尚の養子とし、長延寺二世顕了として広大な寺領を寄進しました。
天正十年(1582年)天目山の戦いで武田家が滅亡すると、長延寺は信長によって焼かれ実了和尚は焚死されました。(顕了とともに信州犬飼村へ退去という説もあり。)
顕了は実母(信親公室)とともに信州犬飼村に迎えられ、徳川の代になると甲斐帰国が許されて、現寺地に長延寺を再興されました。
顕了は、慶長十八年(1613年)の大久保長安事件に連座し、元和元年(1615年)に伊豆大島に配流されのち同地で没したとされます。
顕了の子教了(武田信正公)も大島に配流され寛文三年(1663年)、徳川家光公十三回忌に赦免され江戸に入られました。(教了として長延寺三世を継がれたが長延寺は廃寺となったという説もあり。)
武田信正公は小山田信茂の養女・天光院殿(娘香具姫とも)を室としていた磐城平藩2代藩主内藤忠興の娘の婿として迎えられ、その子信興公は表高家に列せられて、子孫は代々表高家の家格を保って維新を迎えました。
現在に至るまで、表高家武田家の系統が甲斐武田氏の嫡流とされています。
つまり、長延寺は信玄公の帰依を受け、甲斐武田氏の嫡流が法灯を担われたという、二重の意味で武田家と深いゆかりをもつことになります。
慶長十八年(1614年)、本願寺12代目教如上人が、廃寺となった現寺地に本山掛所を設けられ化竜山光澤寺と号されました。
徳川幕府に請い、境内地および寺領の御朱印を受け、諸殿諸堂を整えて、以後、甲州における真宗大谷派の中心的存在となり今日に至ります。
真宗大谷派の寺院で、札所でもないので御朱印は授与されていない模様です。
■ 法流山 入明寺
※ 現在、整理中です。
【 日蓮宗と信玄公 】
日蓮宗と信玄公の関係については、さまざまな説がみられます。
日蓮宗総本山の身延山久遠寺は、文永十一年(1274年)5月、甲斐源氏の南部(波木井)実長が日蓮聖人を領地の身延山に招き、西谷に草庵を構えられたのが草創と伝わります。
日蓮聖人のご遺骨は身延山に奉ぜられ、この地に祀られました。
爾来、身延山は日蓮宗の聖地として崇められ今に至ります。
信玄公の治世は身延山草創から約250年ほど後であり、甲斐国内に聖地をもつ日蓮宗との関係については様々な説が唱えられています。
日蓮宗の『日蓮聖人降誕800年』Webの『日蓮宗と武田信玄』には、「(身延山久遠寺は)武田氏や徳川家の崇拝、外護(げご)を受けて栄え」とあります。
たしかに甲府市若松町の日蓮宗信立寺は、信玄公の父・信虎公の建立と伝わります。(→信立寺の公式Web)
同Webには「当山は、武田家の祈願所となりました。」とあり、「信玄もまた、父同様に当山を祈願所として保護していました。」ともあります。(→信立寺の公式Web)
一方、身延町資料の『権現さんの手洗石』には「信玄公は、駿河方面の敵に備えるため、日蓮宗の本山身延山に城を構えようとしたが、宗門は固く譲らないので、身延山征伐を決意して元亀三年(1572年)、自ら軍を率いて向かったのであるが、あいにく早川の出水で渡れなかったし、また戦いも意の如くならなかったので身延山征伐を断念して甲府に引き返す(以下略)」とあります。
上記の『日蓮宗と武田信玄』にも、「武田信玄は、日蓮宗の総本山である身延山を武田家の支配下に置くべく攻めようとした事がありました。」とあり、その攻防のさなかで数々の霊験を目の当たりにした信玄公は身延攻略をあきらめたとあります。
また、「信玄は(中略)久遠寺の霊験顕著なる信仰の証に感銘し、身延山久遠寺と和睦、山内に武田家の武の字を入れた武井坊と言う坊を建立し、武田家の祈願所としました。」とも記されています。
『(論文)武田・穴山両氏の対身延山政策』(町田是正氏)(PDF)には、信玄公はしばしば身延山に対して「禁制」や「書状」を発して牽制し、ときの久遠寺第15世法主日叙上人はこれに毅然とした応対をされた旨が記されています。
この論文には「全面的に武田氏が親密友好・融和の政策を保持していたのではなく、戦国領主・甲斐守護の立場を誇示しながら、身延山と適当な距離を置いて関係を維持していたと見るべき。」とあります。
決定的な対立を避けつつ融和を図って、「大人の関係」を保っていたのではないでしょうか。
とくに晩年の信玄公と身延山は融和的であったとみられ、このことは令和3年11月3日に催された「武田信玄公生誕五百年祭大法要」(PDF)に身延山 久遠寺が参画されたことからも伺われます。
『ご宝物で知る 身延山の歴史』という本には信玄公が身延山に寄進した経典(明版法華経)など、日蓮宗と信玄公の関係をあらわす宝物が載っているようです。詳細は→(こちら(「武田家の史跡探訪」様))
「明版法華経」はこちらにも載っています。
身延山の宿坊・武井坊の公式Webには「当坊は、信玄公の家紋(武田菱)をもって寺の紋としておりますが、これは武田家の祈願所としての性格を持っていたことに由来します。また『身延栞』という案内書には「武田信玄公、身延攻めに敗れ、感応のいちじるしきに驚き、日勢上人を請じて一寺を創る。故に坊は公の一字を用う」と紹介され、坊名の「武」一字は、武田信玄公の御名に由来します。」と明記されています。
甲府市武田の上行山 要法寺は、天文五年(1536年)、信玄公が盲目だった次男の信親(竜芳)公(御聖道様)の病気平療祈願のため建立したとされます。信親(竜芳)公(竜芳軒日香)を葬ったところとも伝えられています。
京から修徳院日祇上人を招かれ、開山・建立された日蓮宗寺院です。
(→要法寺公式Web)
北杜市武川町山高の大津山 実相寺の公式Webには「永禄四年(1561年)、川中島の合戦にあたって、武田信玄(1521-1573年)は蔦木越前守を当山第七世日忍上人の元に遣わし武運長久の祈願を命じ、永代祈願所として、一条次郎忠頼の城址を寄進され現在の地に移転しました。」とあり、日蓮宗と信玄公のゆかりを示しています。
日蓮宗寺院では夏場にしばしば炮烙(ほうろく)灸が催されますが、これは「炎天下で暑さ負けした信玄公が、兜の上から灸をすえたところたちどころに全快したのがはじまり」という説もあり、日蓮宗と信玄公の関係をうかがわせます。
信玄公の周辺にも日蓮宗の信仰をもったひとびとがいたようです。
甲府市武田の藤光山 法華寺は、天正五年(1577年)信玄公の弟、典厩信繁の夫人養周院により補修され、法華堂から法華寺として建立とされます。
富士川町小室の徳栄山 妙法寺の第10世日薬上人は信玄公の叔父(ないし伯父)にあたる人物とされ、当寺は武田家の祈願所として庇護され、天文年間には信玄公から寺領の寄進があったとも伝わります。
上総の真理谷城・庁南城に拠った庁南(真理谷)武田氏は甲斐武田氏の支流で、信玄公の三男を養子として継がせたともいわれ、庁南(真理谷)武田氏ゆかりの日蓮宗長久寺(千葉県長南町)には、信玄公寄進とされる仏舎利2粒が奉安されています。
-------------------------
信玄公の重臣・穴山信君は身延一帯(河内領)を領し、日蓮宗(身延山)と武田宗家との関係をとりもったとみられています。(→『武田・穴山両氏の対身延山政策』(町田是正氏)(PDF))
穴山信君は甲斐源氏で武田家臣の秋山越前守虎康の息女を養女とし、この養女は天正十年(1582年)、信君が織田・徳川氏に臣従した際に徳川家康公の側室となりました。(下山殿/お都摩の方)
下山殿は天正十一年(1583年)、家康公の五男・万千代君(武田信吉公)を出産。
信吉公は下総小金城3万石~下総佐倉城10万石と移り、佐竹氏に替わって水戸25万石の太守となり、旧武田遺臣を付けられて武田氏を再興するやにみえましたが、慶長八年(1603年)21歳で死去し武田氏再興はなりませんでした。
下山殿は天正十九年(1591年)下総国小金にて早逝。平賀の日蓮宗の名刹・長谷山 本土寺に葬られました。
また、下山殿の実父(武田信吉公の実祖父)・秋山虎康は松戸市大橋の地に止住し、慶長元年(1596年)に了修山 本源寺を開山しているのでおそらく日蓮宗信徒です。
下山殿の「下山」は身延町下山から称したといいます。
『穴山氏とその支配構造』/町田是正氏(PDF)には「(秋山氏の祖)秋山太郎光朝の末の下山氏の住する処で(中略)『日蓮聖人遺文』にも下山氏の存在が記される所」とあり、下山氏(秋山氏)と日蓮宗のゆかりのふかさがうかがえます。
下山殿の実家の秋山氏は、京よりはやくに讃岐に日蓮宗を伝えた(→ビジネス香川)ともいいますから、下山殿もまた熱心な日蓮宗信徒であったのかも。
想像をたくましくすれば、もし、下山殿も信吉公も早世しなければ武田家は水戸25万石の大名として再興存続し、その宗派は日蓮宗となっていたかもしれません。
〔関連寺院〕
■ 日蓮宗祖山・総本山 身延山 久遠寺
山梨県身延町身延3567
日蓮宗

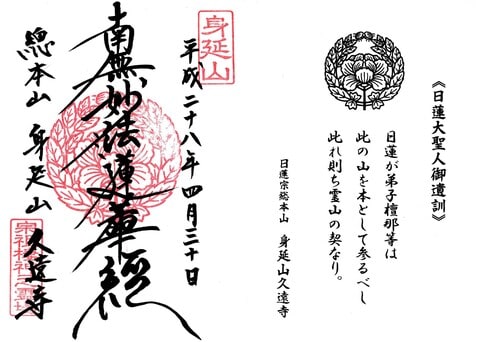
■ 広教山 信立寺
山梨県甲府市若松町6-5
日蓮宗
甲斐百八霊場第54番

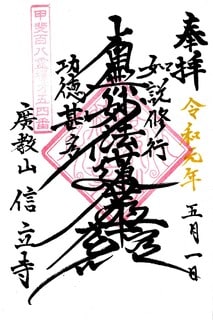
■ 西谷 武井坊
山梨県身延町身延3583
日蓮宗


■ 上行山 要法寺
山梨県甲府市武田4-1-43
日蓮宗
※「甲府城北史蹟めぐり」の御首題

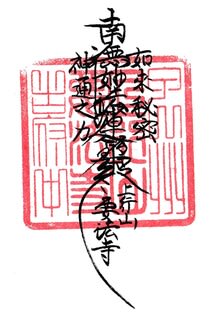
■ 大津山 実相寺
山梨県北杜市武川町山高2763
日蓮宗


■ 藤光山 法華寺
山梨県甲府市武田1-4-34
日蓮宗


■ 徳栄山 妙法寺
山梨県富士川町小室3063
日蓮宗
甲斐百八霊場第91番

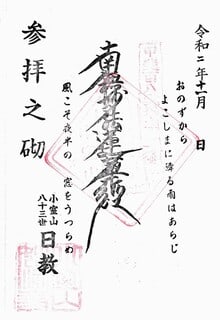
■ 長谷山 本土寺
千葉県松戸市平賀63
日蓮宗

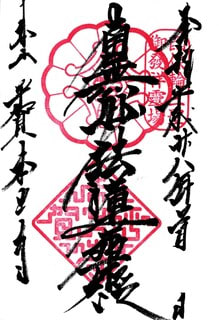
■ 了修山 本源寺
千葉県松戸市大橋766
日蓮宗

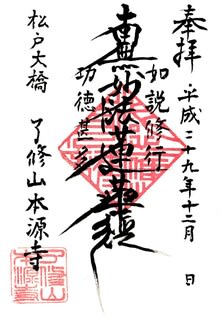
【 山梨県外のゆかりの寺社 】
【 長野県 】
・新海三社神社 (長野県佐久市田口宮代)
・新海山 上宮寺 (長野県佐久市田口)
・一行山 西念寺 (長野県佐久市岩村田)
・寶林山 安養寺 (長野県佐久市安原)
・平林山 千手院 (長野県佐久穂町平林)
・海尻山 醫王院 (長野県南牧村海尻)
・横湯山 温泉寺 (長野県山ノ内町平穏)
【 群馬県 】
・榛名神社 (群馬県高崎市榛名山町)
以上は、現在整理中です。
■ 生島足島神社
公式Web
長野県上田市下之郷中池西701-甲
御祭神:生島大神、足島大神
旧社格:式内社(名神大)、国幣中社、別表神社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
長野県上田に鎮座する古社です。
社伝には「生島神は生国魂大神、足島神は足国魂大神とも称され、共に日本全体の国の御霊として奉祀され、太古より国土の守り神と仰がれる極めて古い由緒を持つ大神であります。神代の昔、建御名方富命が諏訪の地に下降する途すがら、この地にお留まりになり、二柱の大神に奉仕し米粥を煮て献ぜられてたと伝えられ、その故事は今も御籠祭という神事として伝えられています。」とあります。(公式Webより)
建治年間(1275年~1278年)に北条国時(陸奥守入道)が社殿を営繕、戦国時代以降は真田昌幸・信之等の武将をはじめ、代々の上田城主の崇敬を集めています。
当社には戦国時代の多くの文書が伝わっており、「武田信玄願文」(永禄二年(1559年)、信玄公が上杉謙信との決戦を前に戦勝を祈念した願文)、「武田家臣団起請文」(永禄十年(1567年)、甲斐・信濃国内の家臣団に信玄への忠誠を誓わせた文書。)などが代表例で、いくつかは国の重要文化財に指定されています。
信玄公ゆかりの願文・起請文を語る上で、はずせない神社とされています。
■ 太田山 龍雲寺
長野県佐久市岩村田415
曹洞宗 御本尊:十一面観世音菩薩
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
鎌倉時代の正和元年(1312年)大井玄慶を開基、浄学天仲を開山として臨済宗寺院として建立。文明年間(1469年~1487年)曹洞宗の僧天英祥貞によって復興され、曹洞宗に改められました。
戦国期、佐久を掌握された信玄公は永禄年間(1558年~1570年)、自ら開基となり、越後から北高全祝を招聘して中興されました。
北高の招聘に際しては、甲斐の龍華院(甲府市上曽根)と永昌院(同山梨市矢坪)の住職がこれに当たったと伝わります。
永禄十年(1567年)には信玄公は寺領を寄進され、西上野侵攻の折には末寺を寄進されています。
当寺は分国内曹洞宗派の僧録所となり、僧録司となった北高は元亀元年(1570年)には宗派統制を目的に定められた曹洞宗新法度の制定にも携わったとされます。
元亀三年(1572年)4月、西上に際して僧録司北高の立場を示すため、小宮山昌友を奉行として千人法幢会を実施し、正親町天皇から扁額を下賜されたといいます。
信玄公は翌元亀四年、西上の途上で逝去されましたが、当寺は信玄公の火葬地として伝わっています。(実際に遺骨が出土し、分骨の可能性も考えられているようです。)
■ 富蔵山 岩殿寺
長野県東筑摩郡筑北村別所13505
天台宗 御本尊:馬頭観世音菩薩
札所:信濃三十三観音霊場第15番
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
舒明天皇の御代(629~641)役の行者の弟子学文行者が修験道場として開山し、嘉祥元年(848年)に比叡山座主慈覚大師円仁が仁明天皇の勅命を奉じ、寺領三百町を賜り開基されたと伝わります。
四院十二坊、境内に七十五社を配した名刹とされています。
信玄公の帰依篤く、川中島合戦では当寺観世音の霊験があったとして、寺紋に武田菱を賜り、信者は甲州、上州、越後に及んだといわれます。
信濃侵攻先での信玄公の寄進を伝える貴重な寺院です。
----------------------------------------------
古府中町の万年山 大泉寺も信玄公とのゆかりがふかいですが、こちらは信虎公開基なので、「信虎公編」でご紹介します。
【 古長禅寺 】
■ 瑞雲山 古長禅寺








南アルプス市鮎沢505
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
朱印尊格:本尊 釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第86番
・中央に三寶印と中央に「本尊 釈迦牟尼佛」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第八六番」の札所印と「武田信玄公御母堂 大井夫人墓所」の印判。
左は上から参拝記念印、「夢窓國師古道場」の印判と山号・寺号の印判が捺されています。
多彩な印判、華やかな印象の御朱印です。
古長禅寺は、Vol.3 でご紹介した甲府市愛宕町の長禅寺の前身となる名刹です。
もともとこの地には行基創建と伝わる真言宗の大寺西光寺があり、南北朝時代の正和五年(1316年)に夢窓疎石が西光寺の一角に長禅寺を創建し、臨済宗に改宗されたと伝わります。
西郡の有力国衆大井氏の菩提寺で、信玄公の母、大井夫人(瑞雲院殿)は大井氏の出です。
大井夫人は賢母で、悟渓宗頓(大徳寺五二世住持、妙心寺四派の一、東海派の開祖)の法統を嗣ぐ、尾張国瑞泉寺の岐秀元伯を長禅寺に招き、若き日の信玄公に「四書五経」「孫子」「呉子」などを学ばせたといわれます。
だとすると、信玄公は甲府の躑躅ヶ崎館から、西郡鮎沢の当寺まで遠路はるばる参禅されていたことになります。
大井夫人は天文十年(1541年)の信玄公による信虎公駿河追放ののちも甲斐に留まられ、躑躅ヶ崎館北曲輪に居住されました。
天文二一年(1552年)に逝去。法名は瑞雲院殿月珠泉大姉。
葬儀の大導師を務められたのは岐秀元伯と伝わります(『高白斎記』)。
大井夫人逝去の後、西郡の鮎沢では墓所が遠いため、亡き母を開基に、導師の岐秀元伯を開山に請じて新たに府中に長禅寺を開かれました。
これより、当寺は古長禅寺と称されます。
大井夫人ゆかりの事物は甲府の長禅寺に移っていますが、当寺には「木造夢窓疎石坐像」が所蔵されています。
山門からすこし離れた飛び地境内に、境内の樹齢約700年、「夢窓国師お手植えの四つビャクシン」があり、国の天然記念物に指定されています。
山門は一間一戸の切妻造桟瓦葺ながら鬼飾り付きの降棟を備え、大棟に手の込んだ意匠と花菱紋二つを置いて風格があります。
山内はさほど広くはないですが、夢窓国師構想と伝わる本堂前の庭園はさすがに趣きがあり、境内全体が県指定史跡に指定されています。
本堂は桁行六間の入母屋造桟瓦葺で、正面に唐破風向拝を付設、重心が低く安定したイメージのお堂です。
本堂裏手に開山堂跡と大井夫人の墓所があります。
墓所は花菱紋付きの玉垣に囲まれ、ひっそりと佇んでいます。
傍らには、甲斐国・安芸国守護武田信武公から始まる大井氏の家系図が示されています。
大井夫人 歌
- 春は花 秋はもみじの色いろも 日かずつもりて ちらばそのまヽ -
御朱印は本堂前に書置のものが用意されています。ご住職がいらっしゃるときは揮毫いただけるかもしれませんが、当日はご不在につき書置を拝受しました。
【 恵林寺 】
■ 乾徳山 恵林寺
公式Web






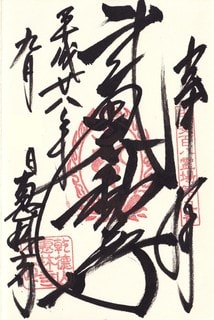
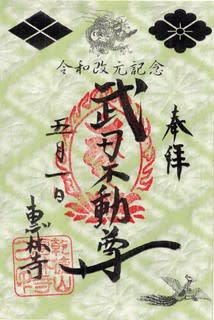
甲州市小屋敷2280
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第73番
※御朱印はVol.5でご紹介していますが、再掲します。
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第9番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第九番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
甲斐百八霊場の札所本尊は御本尊の例が多いですが、当寺では「武田不動尊」となっています。
〔令和改元記念の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 書置(筆書)
札番:なし
・中央に不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。左上に「武田菱」の紋、中央上におそらく青龍、右上に武田家の控え紋「花菱」の紋
右下におそらく朱雀。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
青龍と朱雀は四神の内ですが、改元にちなんでの配置と思われます。
この御朱印には「甲斐百八霊場第九番」の札所印は捺されておらず、「武田不動尊」単独の御朱印となっています。
武田家の菩提寺であり、信玄公の墓所でもある甲斐を代表する名刹。
元徳二年(1330年)、甲斐牧ノ庄の地頭職二階堂出羽守貞藤が夢窓国師を招き、自邸を禅院として創建したとされます。
武田信玄の尊敬を受けた快川和尚の入山で寺勢を高め、永禄七年(1564年)には信玄公自ら寺領を寄進して菩提寺と定めました。
甲斐を代表する名刹だけに、事跡や寺宝が多く遺されています。
四脚門は、徳川家康公建立の切妻造檜皮葺の四脚門。丹塗りが施され通称「赤門」と呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。扁額は「乾徳山」の揮毫。
三門は、一門一戸入母屋造檜皮葺の四脚の楼門。
照りの強い屋根と上部の高欄が意匠的に効いて、きりりと引き締まったイメージがあります。
大棟には武田菱がふたつ。門柱には有名な快川国師の遺偈が掲げられています。
開山堂は、入母屋造妻入り銅板葺で、夢窓国師、快川国師、末宗和尚の木像が安置されています。
拝観は妻入りの大建築である庫裡が受付です。
本堂、うぐいす廊下、明王殿、方丈庭園などが拝観できます。
本堂背後の方丈庭園は鎌倉時代、夢窓国師の作庭。京都の西芳寺、天竜寺の庭園とともに夢窓国師の代表作として知られ、国の史跡・名勝に指定されています。
「武田不動尊」は信玄公の御霊屋である「明王殿」(不動堂)の奥深く御座します。
当寺の資料には、「この不動明王は、信玄公が京から仏師康清を招聘し、信玄と対面して彫刻させ、信玄自らの頭髪を焼いて彩色させたもので、伝承によると、信玄は剃髪した毛髪を漆に混ぜ、自ら坐像の胸部に刷毛で塗りこめたといわれている。」とあります。
また、『甲陽軍鑑』『甲斐国志』には、信玄公の姿を写した像とする伝承が記されています。
元亀四年(1573年)4月12日、西上の途上、信玄公は信濃国駒場において病にて逝去されました。
辞世の句は、
- 大ていは 地に任せて 肌骨好し 紅粉を塗らず 自ら風流 -
と伝わります。
天正四年(1576年)春、勝頼公は快川国師の導師のもと、信玄公の葬儀を厳修しました。
戒名は法性院機山信玄。
武田氏滅亡後、恵林寺は織田信長軍の焼き討ちにあい、快川国師は
「安禅必ずしも山水を須(もち)いず、心頭滅却すれば火も自(おのずか)ら涼し」
との言葉を残して入定されました。
恵林寺の公式Webには、信玄公の人となりや教養について詳細に記されています。
いくつか抜粋引用してみます。
信玄公は母、大井夫人の実家の菩提寺である古長禅寺の名僧・岐秀元伯から「四書五経」「孫子」「呉子」等を学ばれました。
軍学のみならず、「京から公家を招いて詩歌会・連歌会を行い、自身も数多くの歌や漢詩を残されています。
とくに詩歌の道に優れ、その作品が「為和集」、「心珠詠藻」、「甲信紀行の歌」などに収載されています。また、漢詩も嗜まれ、京都大徳寺の宗佐首座によって「武田信玄詩藁」として編纂された」とのことです。
「信玄公が招き、交流を持った禅僧たちは、たとえば、策彦周良、惟高妙安、岐秀元伯、希庵玄密、月航玄津、天桂玄長、説三宗璨、東谷宗杲、鉄山宗鈍、そして快川紹喜。いずれも名の轟く同時代の高僧ばかりです。」(同Web)
「ご出陣の間には日々夜々の参禅学道他事なし(甲陽軍鑑より)」に記されているように、出陣のあいまであっても、昼も夜も、常にひたすら禅に参じていたといわれています。
信玄公は生涯かずかずの名言を残され、後世に語録が編まれたほどですが、なかでもつぎの言葉はよく知られています。
「凡そ軍勝五分を以て上となし、七分を以て中となし、十分を以て下と為す。その故は五分は励を生じ七分は怠を生じ十分は驕を生じるが故。たとへ戦に十分の勝ちを得るとも、驕を生じれば次には必ず敗るるものなり。すべて戦に限らず世の中の事この心掛け肝要なり」
(意訳)
戦というものは、五分と五分であれば、上々。七分三分で優勢であれば、中程度。十分で圧勝するならば、結果は下だと考えなさい。
なぜならば、五分五分の互角であれば、次こそはと励みが生まれる。
しかし、七分の勝ちであれば油断が生じて怠けが始まる。
そして、百パーセント勝ってしまえば、驕慢、傲りを招くからだ。
戦で完勝しようとも、驕慢を生じてしまえば、次には必ず負ける。戦に限らず、世の中のことは、すべてこうだという心がけが肝心である。
(恵林寺公式Webより)
いまの時代でも、いや、「勝者総取り」のいまの時代だからこそ、いっそう響く名言だと思います。
---------------------------------------
これで「信玄公編」は終わりです。
つぎは、「信虎公編」、「勝頼公編」を予定していますが、しばらく時間をおきます。
---------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
〔関連記事〕
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
【 BGM 】(遥海 特集)
■ 遥海 -『名もない花』(TVアニメ「アルスの巨獣」ED)
■ 遥海 -『Pride』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)
■ 遥海 -『answer』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)
【 真宗と信玄公 / 日蓮宗と信玄公 】
【 真宗と信玄公 】
■ 塩田山 超願寺



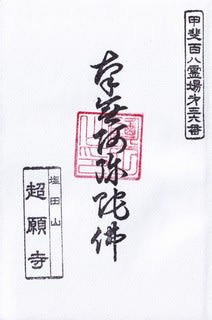
笛吹市一宮町塩田818
真宗大谷派 御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第36番
朱印尊格:南無阿弥陀佛 印判
札番:甲斐百八霊場第36番印判
・中央に山号印と「南無阿弥陀佛」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第三六番」の札所印。左に山号・寺号の印が捺されています。
真宗の御朱印(参拝記念)らしいシンプルな構成です。
文安四年(1447年)、布教のため甲斐を訪れた真宗8世・蓮如上人は、当時天台宗の寺院であった昌願寺を真宗に改め超願寺とされました。
織田信長と敵対した真宗本願寺派第十一世宗主顕如(光佐)の妻である如春尼は、信玄公の正室三条夫人の妹でした。
信玄公は加賀の一向一揆と結んで上杉謙信を牽制し、本願寺とも合力して信長包囲網を築いたとされ、真宗や本願寺との連携は政治的にも重要なものであったとみられています。
真宗本願寺勢力と織田信長公が刃を交えた石山合戦の際、超願寺の七世住職・喜西は石山の籠城に加わり、教如上人や下間頼龍とも親交があり、これを示す矢文が当寺に残っています。
甲斐の国は日蓮宗寺院も多く、甲斐百八霊場は、真宗や日蓮宗を含む多彩な宗派で構成されています。
■ 真宗大谷派東本願寺甲府別院 光澤寺
甲府市相生3-5-7
真宗大谷派 御本尊:阿弥陀如来
公式Web
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されていない模様です。
信玄公とふかいゆかりをもつ真宗の名刹です。
寺伝(公式Web)および資料Aから沿革等をまとめてみました。
天文十六年(1548年)、信玄公は当時鎌倉常葉町にあった一向宗蛇伏山長延寺(現在の真宗大谷派永勝寺:横浜市戸塚区)が相模北条氏と対立していた状況を憂慮され、住職実了師慶和尚を甲府へ招聘、広大な寺領を寄進し手厚い庇護を加えて長延寺として再興しました。
「超願寺」の記事でもふれましたが、信玄公は織田信長と敵対した真宗本願寺派第十一世宗主顕如(光佐)の妻である如春尼は、信玄公の正室三条夫人の妹でした。
信玄公は加賀の一向一揆と結んで上杉謙信を牽制し、本願寺とも合力して信長包囲網を築いたとされ、真宗や本願寺との連携は政治的にも重要なものであったとみられています。
実了和尚は僧として活躍するとともに、武田家御伽衆の有力メンバーであったとみられています。
御伽衆とは高級参謀兼外交特使といった役柄で、戦国時代に高僧が勤める例は少なくありません。
ちなみに「甲陽軍鑑」品第八(国会図書館DC、コマ番号26/265)には「長遠寺(実了師慶)といふ一向坊主をいつも江州浅井備前守そうじて上方へ計策に指上せらる 其年は一入様子能相調へ伊勢長島、大坂、和泉の堺下時 加賀越中迄も立寄 信玄公へ御味方の証文を取て参上いたす」とあり、実了師慶が上方から北陸までも足を伸ばして、各将の調略に奔走していたことがうかがわれます。
実了和尚の人徳に帰依した信玄公は、次男庄蔵(信親公・竜宝)の嫡男の信道公を実了和尚の養子とし、長延寺二世顕了として広大な寺領を寄進しました。
天正十年(1582年)天目山の戦いで武田家が滅亡すると、長延寺は信長によって焼かれ実了和尚は焚死されました。(顕了とともに信州犬飼村へ退去という説もあり。)
顕了は実母(信親公室)とともに信州犬飼村に迎えられ、徳川の代になると甲斐帰国が許されて、現寺地に長延寺を再興されました。
顕了は、慶長十八年(1613年)の大久保長安事件に連座し、元和元年(1615年)に伊豆大島に配流されのち同地で没したとされます。
顕了の子教了(武田信正公)も大島に配流され寛文三年(1663年)、徳川家光公十三回忌に赦免され江戸に入られました。(教了として長延寺三世を継がれたが長延寺は廃寺となったという説もあり。)
武田信正公は小山田信茂の養女・天光院殿(娘香具姫とも)を室としていた磐城平藩2代藩主内藤忠興の娘の婿として迎えられ、その子信興公は表高家に列せられて、子孫は代々表高家の家格を保って維新を迎えました。
現在に至るまで、表高家武田家の系統が甲斐武田氏の嫡流とされています。
つまり、長延寺は信玄公の帰依を受け、甲斐武田氏の嫡流が法灯を担われたという、二重の意味で武田家と深いゆかりをもつことになります。
慶長十八年(1614年)、本願寺12代目教如上人が、廃寺となった現寺地に本山掛所を設けられ化竜山光澤寺と号されました。
徳川幕府に請い、境内地および寺領の御朱印を受け、諸殿諸堂を整えて、以後、甲州における真宗大谷派の中心的存在となり今日に至ります。
真宗大谷派の寺院で、札所でもないので御朱印は授与されていない模様です。
■ 法流山 入明寺
※ 現在、整理中です。
【 日蓮宗と信玄公 】
日蓮宗と信玄公の関係については、さまざまな説がみられます。
日蓮宗総本山の身延山久遠寺は、文永十一年(1274年)5月、甲斐源氏の南部(波木井)実長が日蓮聖人を領地の身延山に招き、西谷に草庵を構えられたのが草創と伝わります。
日蓮聖人のご遺骨は身延山に奉ぜられ、この地に祀られました。
爾来、身延山は日蓮宗の聖地として崇められ今に至ります。
信玄公の治世は身延山草創から約250年ほど後であり、甲斐国内に聖地をもつ日蓮宗との関係については様々な説が唱えられています。
日蓮宗の『日蓮聖人降誕800年』Webの『日蓮宗と武田信玄』には、「(身延山久遠寺は)武田氏や徳川家の崇拝、外護(げご)を受けて栄え」とあります。
たしかに甲府市若松町の日蓮宗信立寺は、信玄公の父・信虎公の建立と伝わります。(→信立寺の公式Web)
同Webには「当山は、武田家の祈願所となりました。」とあり、「信玄もまた、父同様に当山を祈願所として保護していました。」ともあります。(→信立寺の公式Web)
一方、身延町資料の『権現さんの手洗石』には「信玄公は、駿河方面の敵に備えるため、日蓮宗の本山身延山に城を構えようとしたが、宗門は固く譲らないので、身延山征伐を決意して元亀三年(1572年)、自ら軍を率いて向かったのであるが、あいにく早川の出水で渡れなかったし、また戦いも意の如くならなかったので身延山征伐を断念して甲府に引き返す(以下略)」とあります。
上記の『日蓮宗と武田信玄』にも、「武田信玄は、日蓮宗の総本山である身延山を武田家の支配下に置くべく攻めようとした事がありました。」とあり、その攻防のさなかで数々の霊験を目の当たりにした信玄公は身延攻略をあきらめたとあります。
また、「信玄は(中略)久遠寺の霊験顕著なる信仰の証に感銘し、身延山久遠寺と和睦、山内に武田家の武の字を入れた武井坊と言う坊を建立し、武田家の祈願所としました。」とも記されています。
『(論文)武田・穴山両氏の対身延山政策』(町田是正氏)(PDF)には、信玄公はしばしば身延山に対して「禁制」や「書状」を発して牽制し、ときの久遠寺第15世法主日叙上人はこれに毅然とした応対をされた旨が記されています。
この論文には「全面的に武田氏が親密友好・融和の政策を保持していたのではなく、戦国領主・甲斐守護の立場を誇示しながら、身延山と適当な距離を置いて関係を維持していたと見るべき。」とあります。
決定的な対立を避けつつ融和を図って、「大人の関係」を保っていたのではないでしょうか。
とくに晩年の信玄公と身延山は融和的であったとみられ、このことは令和3年11月3日に催された「武田信玄公生誕五百年祭大法要」(PDF)に身延山 久遠寺が参画されたことからも伺われます。
『ご宝物で知る 身延山の歴史』という本には信玄公が身延山に寄進した経典(明版法華経)など、日蓮宗と信玄公の関係をあらわす宝物が載っているようです。詳細は→(こちら(「武田家の史跡探訪」様))
「明版法華経」はこちらにも載っています。
身延山の宿坊・武井坊の公式Webには「当坊は、信玄公の家紋(武田菱)をもって寺の紋としておりますが、これは武田家の祈願所としての性格を持っていたことに由来します。また『身延栞』という案内書には「武田信玄公、身延攻めに敗れ、感応のいちじるしきに驚き、日勢上人を請じて一寺を創る。故に坊は公の一字を用う」と紹介され、坊名の「武」一字は、武田信玄公の御名に由来します。」と明記されています。
甲府市武田の上行山 要法寺は、天文五年(1536年)、信玄公が盲目だった次男の信親(竜芳)公(御聖道様)の病気平療祈願のため建立したとされます。信親(竜芳)公(竜芳軒日香)を葬ったところとも伝えられています。
京から修徳院日祇上人を招かれ、開山・建立された日蓮宗寺院です。
(→要法寺公式Web)
北杜市武川町山高の大津山 実相寺の公式Webには「永禄四年(1561年)、川中島の合戦にあたって、武田信玄(1521-1573年)は蔦木越前守を当山第七世日忍上人の元に遣わし武運長久の祈願を命じ、永代祈願所として、一条次郎忠頼の城址を寄進され現在の地に移転しました。」とあり、日蓮宗と信玄公のゆかりを示しています。
日蓮宗寺院では夏場にしばしば炮烙(ほうろく)灸が催されますが、これは「炎天下で暑さ負けした信玄公が、兜の上から灸をすえたところたちどころに全快したのがはじまり」という説もあり、日蓮宗と信玄公の関係をうかがわせます。
信玄公の周辺にも日蓮宗の信仰をもったひとびとがいたようです。
甲府市武田の藤光山 法華寺は、天正五年(1577年)信玄公の弟、典厩信繁の夫人養周院により補修され、法華堂から法華寺として建立とされます。
富士川町小室の徳栄山 妙法寺の第10世日薬上人は信玄公の叔父(ないし伯父)にあたる人物とされ、当寺は武田家の祈願所として庇護され、天文年間には信玄公から寺領の寄進があったとも伝わります。
上総の真理谷城・庁南城に拠った庁南(真理谷)武田氏は甲斐武田氏の支流で、信玄公の三男を養子として継がせたともいわれ、庁南(真理谷)武田氏ゆかりの日蓮宗長久寺(千葉県長南町)には、信玄公寄進とされる仏舎利2粒が奉安されています。
-------------------------
信玄公の重臣・穴山信君は身延一帯(河内領)を領し、日蓮宗(身延山)と武田宗家との関係をとりもったとみられています。(→『武田・穴山両氏の対身延山政策』(町田是正氏)(PDF))
穴山信君は甲斐源氏で武田家臣の秋山越前守虎康の息女を養女とし、この養女は天正十年(1582年)、信君が織田・徳川氏に臣従した際に徳川家康公の側室となりました。(下山殿/お都摩の方)
下山殿は天正十一年(1583年)、家康公の五男・万千代君(武田信吉公)を出産。
信吉公は下総小金城3万石~下総佐倉城10万石と移り、佐竹氏に替わって水戸25万石の太守となり、旧武田遺臣を付けられて武田氏を再興するやにみえましたが、慶長八年(1603年)21歳で死去し武田氏再興はなりませんでした。
下山殿は天正十九年(1591年)下総国小金にて早逝。平賀の日蓮宗の名刹・長谷山 本土寺に葬られました。
また、下山殿の実父(武田信吉公の実祖父)・秋山虎康は松戸市大橋の地に止住し、慶長元年(1596年)に了修山 本源寺を開山しているのでおそらく日蓮宗信徒です。
下山殿の「下山」は身延町下山から称したといいます。
『穴山氏とその支配構造』/町田是正氏(PDF)には「(秋山氏の祖)秋山太郎光朝の末の下山氏の住する処で(中略)『日蓮聖人遺文』にも下山氏の存在が記される所」とあり、下山氏(秋山氏)と日蓮宗のゆかりのふかさがうかがえます。
下山殿の実家の秋山氏は、京よりはやくに讃岐に日蓮宗を伝えた(→ビジネス香川)ともいいますから、下山殿もまた熱心な日蓮宗信徒であったのかも。
想像をたくましくすれば、もし、下山殿も信吉公も早世しなければ武田家は水戸25万石の大名として再興存続し、その宗派は日蓮宗となっていたかもしれません。
〔関連寺院〕
■ 日蓮宗祖山・総本山 身延山 久遠寺
山梨県身延町身延3567
日蓮宗

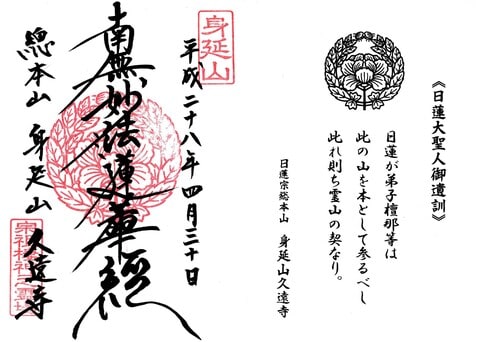
■ 広教山 信立寺
山梨県甲府市若松町6-5
日蓮宗
甲斐百八霊場第54番

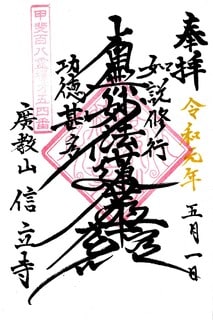
■ 西谷 武井坊
山梨県身延町身延3583
日蓮宗


■ 上行山 要法寺
山梨県甲府市武田4-1-43
日蓮宗
※「甲府城北史蹟めぐり」の御首題

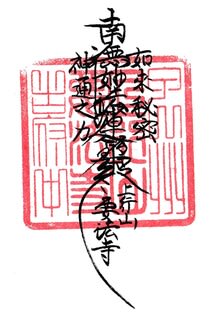
■ 大津山 実相寺
山梨県北杜市武川町山高2763
日蓮宗


■ 藤光山 法華寺
山梨県甲府市武田1-4-34
日蓮宗


■ 徳栄山 妙法寺
山梨県富士川町小室3063
日蓮宗
甲斐百八霊場第91番

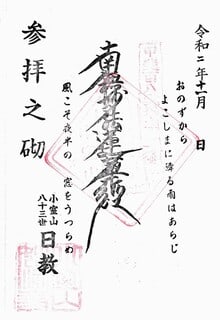
■ 長谷山 本土寺
千葉県松戸市平賀63
日蓮宗

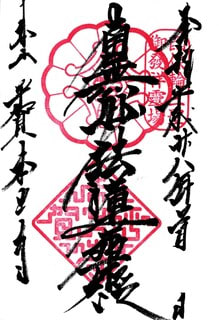
■ 了修山 本源寺
千葉県松戸市大橋766
日蓮宗

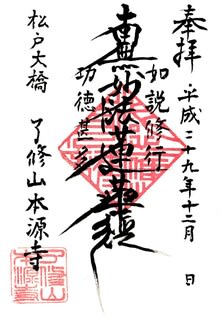
【 山梨県外のゆかりの寺社 】
【 長野県 】
・新海三社神社 (長野県佐久市田口宮代)
・新海山 上宮寺 (長野県佐久市田口)
・一行山 西念寺 (長野県佐久市岩村田)
・寶林山 安養寺 (長野県佐久市安原)
・平林山 千手院 (長野県佐久穂町平林)
・海尻山 醫王院 (長野県南牧村海尻)
・横湯山 温泉寺 (長野県山ノ内町平穏)
【 群馬県 】
・榛名神社 (群馬県高崎市榛名山町)
以上は、現在整理中です。
■ 生島足島神社
公式Web
長野県上田市下之郷中池西701-甲
御祭神:生島大神、足島大神
旧社格:式内社(名神大)、国幣中社、別表神社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
長野県上田に鎮座する古社です。
社伝には「生島神は生国魂大神、足島神は足国魂大神とも称され、共に日本全体の国の御霊として奉祀され、太古より国土の守り神と仰がれる極めて古い由緒を持つ大神であります。神代の昔、建御名方富命が諏訪の地に下降する途すがら、この地にお留まりになり、二柱の大神に奉仕し米粥を煮て献ぜられてたと伝えられ、その故事は今も御籠祭という神事として伝えられています。」とあります。(公式Webより)
建治年間(1275年~1278年)に北条国時(陸奥守入道)が社殿を営繕、戦国時代以降は真田昌幸・信之等の武将をはじめ、代々の上田城主の崇敬を集めています。
当社には戦国時代の多くの文書が伝わっており、「武田信玄願文」(永禄二年(1559年)、信玄公が上杉謙信との決戦を前に戦勝を祈念した願文)、「武田家臣団起請文」(永禄十年(1567年)、甲斐・信濃国内の家臣団に信玄への忠誠を誓わせた文書。)などが代表例で、いくつかは国の重要文化財に指定されています。
信玄公ゆかりの願文・起請文を語る上で、はずせない神社とされています。
■ 太田山 龍雲寺
長野県佐久市岩村田415
曹洞宗 御本尊:十一面観世音菩薩
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
鎌倉時代の正和元年(1312年)大井玄慶を開基、浄学天仲を開山として臨済宗寺院として建立。文明年間(1469年~1487年)曹洞宗の僧天英祥貞によって復興され、曹洞宗に改められました。
戦国期、佐久を掌握された信玄公は永禄年間(1558年~1570年)、自ら開基となり、越後から北高全祝を招聘して中興されました。
北高の招聘に際しては、甲斐の龍華院(甲府市上曽根)と永昌院(同山梨市矢坪)の住職がこれに当たったと伝わります。
永禄十年(1567年)には信玄公は寺領を寄進され、西上野侵攻の折には末寺を寄進されています。
当寺は分国内曹洞宗派の僧録所となり、僧録司となった北高は元亀元年(1570年)には宗派統制を目的に定められた曹洞宗新法度の制定にも携わったとされます。
元亀三年(1572年)4月、西上に際して僧録司北高の立場を示すため、小宮山昌友を奉行として千人法幢会を実施し、正親町天皇から扁額を下賜されたといいます。
信玄公は翌元亀四年、西上の途上で逝去されましたが、当寺は信玄公の火葬地として伝わっています。(実際に遺骨が出土し、分骨の可能性も考えられているようです。)
■ 富蔵山 岩殿寺
長野県東筑摩郡筑北村別所13505
天台宗 御本尊:馬頭観世音菩薩
札所:信濃三十三観音霊場第15番
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
舒明天皇の御代(629~641)役の行者の弟子学文行者が修験道場として開山し、嘉祥元年(848年)に比叡山座主慈覚大師円仁が仁明天皇の勅命を奉じ、寺領三百町を賜り開基されたと伝わります。
四院十二坊、境内に七十五社を配した名刹とされています。
信玄公の帰依篤く、川中島合戦では当寺観世音の霊験があったとして、寺紋に武田菱を賜り、信者は甲州、上州、越後に及んだといわれます。
信濃侵攻先での信玄公の寄進を伝える貴重な寺院です。
----------------------------------------------
古府中町の万年山 大泉寺も信玄公とのゆかりがふかいですが、こちらは信虎公開基なので、「信虎公編」でご紹介します。
【 古長禅寺 】
■ 瑞雲山 古長禅寺








南アルプス市鮎沢505
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
朱印尊格:本尊 釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第86番
・中央に三寶印と中央に「本尊 釈迦牟尼佛」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第八六番」の札所印と「武田信玄公御母堂 大井夫人墓所」の印判。
左は上から参拝記念印、「夢窓國師古道場」の印判と山号・寺号の印判が捺されています。
多彩な印判、華やかな印象の御朱印です。
古長禅寺は、Vol.3 でご紹介した甲府市愛宕町の長禅寺の前身となる名刹です。
もともとこの地には行基創建と伝わる真言宗の大寺西光寺があり、南北朝時代の正和五年(1316年)に夢窓疎石が西光寺の一角に長禅寺を創建し、臨済宗に改宗されたと伝わります。
西郡の有力国衆大井氏の菩提寺で、信玄公の母、大井夫人(瑞雲院殿)は大井氏の出です。
大井夫人は賢母で、悟渓宗頓(大徳寺五二世住持、妙心寺四派の一、東海派の開祖)の法統を嗣ぐ、尾張国瑞泉寺の岐秀元伯を長禅寺に招き、若き日の信玄公に「四書五経」「孫子」「呉子」などを学ばせたといわれます。
だとすると、信玄公は甲府の躑躅ヶ崎館から、西郡鮎沢の当寺まで遠路はるばる参禅されていたことになります。
大井夫人は天文十年(1541年)の信玄公による信虎公駿河追放ののちも甲斐に留まられ、躑躅ヶ崎館北曲輪に居住されました。
天文二一年(1552年)に逝去。法名は瑞雲院殿月珠泉大姉。
葬儀の大導師を務められたのは岐秀元伯と伝わります(『高白斎記』)。
大井夫人逝去の後、西郡の鮎沢では墓所が遠いため、亡き母を開基に、導師の岐秀元伯を開山に請じて新たに府中に長禅寺を開かれました。
これより、当寺は古長禅寺と称されます。
大井夫人ゆかりの事物は甲府の長禅寺に移っていますが、当寺には「木造夢窓疎石坐像」が所蔵されています。
山門からすこし離れた飛び地境内に、境内の樹齢約700年、「夢窓国師お手植えの四つビャクシン」があり、国の天然記念物に指定されています。
山門は一間一戸の切妻造桟瓦葺ながら鬼飾り付きの降棟を備え、大棟に手の込んだ意匠と花菱紋二つを置いて風格があります。
山内はさほど広くはないですが、夢窓国師構想と伝わる本堂前の庭園はさすがに趣きがあり、境内全体が県指定史跡に指定されています。
本堂は桁行六間の入母屋造桟瓦葺で、正面に唐破風向拝を付設、重心が低く安定したイメージのお堂です。
本堂裏手に開山堂跡と大井夫人の墓所があります。
墓所は花菱紋付きの玉垣に囲まれ、ひっそりと佇んでいます。
傍らには、甲斐国・安芸国守護武田信武公から始まる大井氏の家系図が示されています。
大井夫人 歌
- 春は花 秋はもみじの色いろも 日かずつもりて ちらばそのまヽ -
御朱印は本堂前に書置のものが用意されています。ご住職がいらっしゃるときは揮毫いただけるかもしれませんが、当日はご不在につき書置を拝受しました。
【 恵林寺 】
■ 乾徳山 恵林寺
公式Web






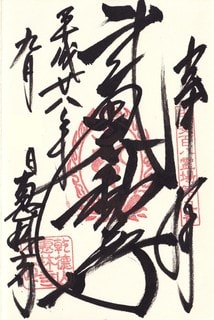
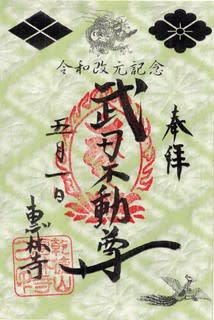
甲州市小屋敷2280
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第73番
※御朱印はVol.5でご紹介していますが、再掲します。
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第9番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第九番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
甲斐百八霊場の札所本尊は御本尊の例が多いですが、当寺では「武田不動尊」となっています。
〔令和改元記念の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 書置(筆書)
札番:なし
・中央に不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。左上に「武田菱」の紋、中央上におそらく青龍、右上に武田家の控え紋「花菱」の紋
右下におそらく朱雀。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
青龍と朱雀は四神の内ですが、改元にちなんでの配置と思われます。
この御朱印には「甲斐百八霊場第九番」の札所印は捺されておらず、「武田不動尊」単独の御朱印となっています。
武田家の菩提寺であり、信玄公の墓所でもある甲斐を代表する名刹。
元徳二年(1330年)、甲斐牧ノ庄の地頭職二階堂出羽守貞藤が夢窓国師を招き、自邸を禅院として創建したとされます。
武田信玄の尊敬を受けた快川和尚の入山で寺勢を高め、永禄七年(1564年)には信玄公自ら寺領を寄進して菩提寺と定めました。
甲斐を代表する名刹だけに、事跡や寺宝が多く遺されています。
四脚門は、徳川家康公建立の切妻造檜皮葺の四脚門。丹塗りが施され通称「赤門」と呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。扁額は「乾徳山」の揮毫。
三門は、一門一戸入母屋造檜皮葺の四脚の楼門。
照りの強い屋根と上部の高欄が意匠的に効いて、きりりと引き締まったイメージがあります。
大棟には武田菱がふたつ。門柱には有名な快川国師の遺偈が掲げられています。
開山堂は、入母屋造妻入り銅板葺で、夢窓国師、快川国師、末宗和尚の木像が安置されています。
拝観は妻入りの大建築である庫裡が受付です。
本堂、うぐいす廊下、明王殿、方丈庭園などが拝観できます。
本堂背後の方丈庭園は鎌倉時代、夢窓国師の作庭。京都の西芳寺、天竜寺の庭園とともに夢窓国師の代表作として知られ、国の史跡・名勝に指定されています。
「武田不動尊」は信玄公の御霊屋である「明王殿」(不動堂)の奥深く御座します。
当寺の資料には、「この不動明王は、信玄公が京から仏師康清を招聘し、信玄と対面して彫刻させ、信玄自らの頭髪を焼いて彩色させたもので、伝承によると、信玄は剃髪した毛髪を漆に混ぜ、自ら坐像の胸部に刷毛で塗りこめたといわれている。」とあります。
また、『甲陽軍鑑』『甲斐国志』には、信玄公の姿を写した像とする伝承が記されています。
元亀四年(1573年)4月12日、西上の途上、信玄公は信濃国駒場において病にて逝去されました。
辞世の句は、
- 大ていは 地に任せて 肌骨好し 紅粉を塗らず 自ら風流 -
と伝わります。
天正四年(1576年)春、勝頼公は快川国師の導師のもと、信玄公の葬儀を厳修しました。
戒名は法性院機山信玄。
武田氏滅亡後、恵林寺は織田信長軍の焼き討ちにあい、快川国師は
「安禅必ずしも山水を須(もち)いず、心頭滅却すれば火も自(おのずか)ら涼し」
との言葉を残して入定されました。
恵林寺の公式Webには、信玄公の人となりや教養について詳細に記されています。
いくつか抜粋引用してみます。
信玄公は母、大井夫人の実家の菩提寺である古長禅寺の名僧・岐秀元伯から「四書五経」「孫子」「呉子」等を学ばれました。
軍学のみならず、「京から公家を招いて詩歌会・連歌会を行い、自身も数多くの歌や漢詩を残されています。
とくに詩歌の道に優れ、その作品が「為和集」、「心珠詠藻」、「甲信紀行の歌」などに収載されています。また、漢詩も嗜まれ、京都大徳寺の宗佐首座によって「武田信玄詩藁」として編纂された」とのことです。
「信玄公が招き、交流を持った禅僧たちは、たとえば、策彦周良、惟高妙安、岐秀元伯、希庵玄密、月航玄津、天桂玄長、説三宗璨、東谷宗杲、鉄山宗鈍、そして快川紹喜。いずれも名の轟く同時代の高僧ばかりです。」(同Web)
「ご出陣の間には日々夜々の参禅学道他事なし(甲陽軍鑑より)」に記されているように、出陣のあいまであっても、昼も夜も、常にひたすら禅に参じていたといわれています。
信玄公は生涯かずかずの名言を残され、後世に語録が編まれたほどですが、なかでもつぎの言葉はよく知られています。
「凡そ軍勝五分を以て上となし、七分を以て中となし、十分を以て下と為す。その故は五分は励を生じ七分は怠を生じ十分は驕を生じるが故。たとへ戦に十分の勝ちを得るとも、驕を生じれば次には必ず敗るるものなり。すべて戦に限らず世の中の事この心掛け肝要なり」
(意訳)
戦というものは、五分と五分であれば、上々。七分三分で優勢であれば、中程度。十分で圧勝するならば、結果は下だと考えなさい。
なぜならば、五分五分の互角であれば、次こそはと励みが生まれる。
しかし、七分の勝ちであれば油断が生じて怠けが始まる。
そして、百パーセント勝ってしまえば、驕慢、傲りを招くからだ。
戦で完勝しようとも、驕慢を生じてしまえば、次には必ず負ける。戦に限らず、世の中のことは、すべてこうだという心がけが肝心である。
(恵林寺公式Webより)
いまの時代でも、いや、「勝者総取り」のいまの時代だからこそ、いっそう響く名言だと思います。
---------------------------------------
これで「信玄公編」は終わりです。
つぎは、「信虎公編」、「勝頼公編」を予定していますが、しばらく時間をおきます。
---------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
〔関連記事〕
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
【 BGM 】(遥海 特集)
■ 遥海 -『名もない花』(TVアニメ「アルスの巨獣」ED)
■ 遥海 -『Pride』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)
■ 遥海 -『answer』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 武相卯歳四十八観音霊場の御開扉
結願しました。
各札所の概要、写真と御朱印を掲載します。
-------------------------
第1番
鶴間山 東照院 観音寺 〔真言院 金亀坊〕
神奈川県大和市下鶴間2240
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:武相寅歳薬師如来霊場21番(R4.4/9-5/8御開帳)、小田急武相三十三観音霊場28番、高座郡三十三ヶ所観音霊場29番


・青山往還沿いにあり、「青山往還の赤門寺」と呼ばれて参詣者を集めたとされる発願寺。
・御本尊の十一面観世音菩薩は慈覚大師の御作と伝わる。
第2番
陽向山 随流院 (火ぶせ観音) 〔長蔦寺〕
神奈川県横浜市緑区長津田5-4-30
曹洞宗
御本尊:釈迦無尼佛(聖観世音菩薩)
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・江戸幕府の旗本・岡野家の菩提寺で「長津田」の地名の元とも。
・聖観世音菩薩は、ふるくから「火防の観音」として信仰を集めている。
第3番
大峰山 松岳院 (奈良村観音堂) 〔正覚院〕
神奈川県横浜市青葉区奈良2-4-6
曹洞宗
御本尊:釈迦無尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与あり(書置)

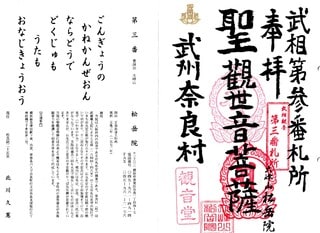
・開基は旧奈良村知行の石丸有貞とされる。
・聖観世音菩薩は、旧奈良村にあった観音堂から水害を受けて遷されたと伝わる。
第4番
三枝山 観性寺
東京都町田市西成瀬2-11-8
曹洞宗
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
※通常無住(成瀬4-14-1東雲寺管理)

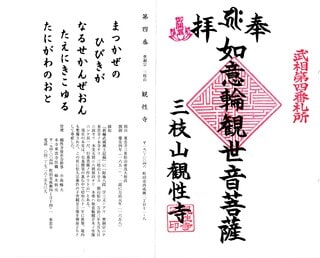
・御本尊の如意輪観世音菩薩は、行基菩薩の御作と伝わる。
・別尊として松久宗琳作の子育て観音を奉安。
第5番
鶏足山 智光院 養運寺
東京都町田市本町田3654
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印拝受済(御開扉期間中の授与不明)


・鎌倉時代からつづくとされる浄土宗の古刹で、札所は山内観音堂。
・もとは大谷村との境に御座の観音さまを、安永五年(1776年)に合祀と伝わる。
第6番
岩子山 普門寺 千手院
東京都町田市小野路町2057
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:関東八十八箇所64番、多摩新四国八十八ヶ所霊場12番、多摩川三十四観音霊場34番、小田急武相三十三観音霊場10番


・奈良時代、行基菩薩の開基と伝わる真言宗豊山派の名刹。
・本堂裏手高台の奥の院も観音堂で、現在は十一面観世音菩薩を奉安。この観音堂は小山田次郎重義が観音像を感得して建立と伝わる。
第7番
慈眼山 唐仏院 観音寺 (せきど観音)
東京都多摩市関戸5-31-11
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩十三仏霊場5番(地蔵菩薩)、多摩川三十四観音霊場12番


・「関戸観音堂」と呼ばれ古くから信仰を集めた。
・元弘三年(1333年)、新田義貞と鎌倉幕府の「関戸の戦」の地で関連の史跡が残る。
第8番
清谷山 蓮華院 真照寺 (子安観音)
東京都日野市落川1113
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場17番、多摩川三十四観音霊場11番、日野七福神(恵比須天)


・長和年間(1012-1017年)開山と伝わる真言宗の古刹。
・子安観音として知られる千手観世音菩薩を山内観音堂に奉安。
第9番
桝井山 松連寺 観音堂 (百草観音堂)
東京都下日野市百草849-1
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
※通常無住(八王子清鏡寺管理?)

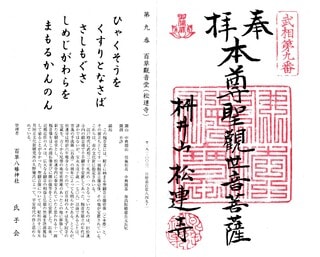
・もとは京王百草園にあったとされ、景勝の地として知られていた。
・旧松連寺所蔵の多くの仏像を奉安し、「百草観音堂仏教彫刻群」として市の文化財に指定されている。
第10番
塩釜山 清鏡寺 (大塚観音堂・御手の観音)
東京都八王子市大塚378
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊(阿弥陀如来)
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:多摩川三十四観音霊場10番、京王三十三観音霊場24番
※御本尊御朱印は御開扉期間中授与なし


・清鏡寺は、もとは北条氏再興祈願の観音堂の別当。
・山内高台の観音堂に奉安の千手観世音菩薩は足腰健康の霊験あらたかで「大塚観音堂・御手の観音」としてふるくから信仰を集めている。
第11番
補陀山 水月院 大泉寺
東京都町田市下小山田町332
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・『新編武蔵風土記稿』には「町田の大寺」と掲載され、いまも大寺の風格を湛える。
・鎌倉武士・小山田有重の城跡に建立し、札所本尊は「見合い観音」とも呼ばれ若い女性の参詣を集めたという。
第12番
龍澤山 保井寺
東京都八王子市堀之内547
曹洞宗
御本尊:虚空藏菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
※御本尊御朱印拝受済(御開扉期間中の授与不明)


・読みは「ほうせいじ」。町田市下小山町の観音寺から遷られた如意輪観世音菩薩が札所本尊で、山内観音堂に奉安されている。「椿の寺」としても有名。
第13番
吹王山 (不動院) 玉泉寺(もかけの観音)
東京都八王子市越野726
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩百八ヶ所霊場105番
※御本尊御朱印拝受済(多摩百八ヶ所)


・裳が蓮台までかかる宗風の像容から「もかけの観音」と呼ばれる札所本尊は、旧導義寺観音堂から玉泉寺観音堂に遷られ、現在は越野自治会集会所に奉安されている。
・札所本尊造立の願主は、底部墨書から北条氏照の家臣・小田野周重とみられている。
第14番
高雲山 永泉寺
東京都八王子市鑓水80
御本尊:釈迦無尼仏
札所本尊:正観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・甲州武田家臣・永野和泉開基の古刹で、鑓水の絹商人・八木下要右衛門の旧邸の地とされる。
・俳句の寺として知られ、山内には芭蕉堂が建つ。
第15番
安榮山 明王院 福傳寺 (子安観音)
東京都八王子市明神町4-10-6
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場77番、八王子三十三観音霊場30番、武玉八十八ヶ所霊場65番
※御本尊御朱印拝受済(多摩新四国)


・八王子の街なかにある真言宗寺院で、子安神社の元別当。
・安産の観音さまとして信仰篤く「村内に難産の者なし」と伝わる。
第16番
慈高山 金剛院
東京都八王子市上野町39-2
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩
関東八十八箇所63番、多摩新四国八十八ヶ所霊場73番、八王子三十三観音霊場31番、京王三十三観音霊場30番、八王子七福神(福禄寿)、武玉八十八ヶ所霊場63番
※御本尊御朱印拝受(関東八十八箇所、多摩新四国)


・草創は天正四年(1576年)僧真清開基の明王院。のちに当地の大師堂とあわせ金剛院と号す。
・札所本尊の十一面観世音菩薩は、本堂参道向かって左手の福聚堂に奉安されている。
第17番
中和山 泉龍寺
神奈川県相模原市南区上鶴間本町8-54-21
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印は御開扉中不授与


・大規模な三重塔を擁する曹洞宗の大寺。三重塔よこに観音堂があるが、御開扉時は本堂に奉安されていた。
・札所本尊は公所の井上助右衛門の霊夢を受けての造立と伝わる。
第18番
竜雲山 高乗寺
東京都八王子市初沢町1425
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:十一面観世音菩薩・三十三体観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場19番
※御本尊御朱印拝受済(御開扉中書置)


・片倉城主・永井大膳太夫高乗(広秀)が開基の「多摩八大寺」に数えられる曹洞宗の名刹。
・札所本尊は、本堂向かって左の大慈閣に奉安されている。
第19番
天龍山 福昌寺
横浜市青葉区恩田町1021-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:武相寅歳薬師如来霊場14番(R4.4/9-5/8御開帳)
※御本尊御朱印拝受済(御開扉中書置)


・横浜市青葉区の住宅地にある曹洞宗寺院。
・以前は二間四方の観音堂があったとされるが、現在、札所本尊は本堂に奉安されている。
第20番
北岸山 喜福寺
東京都八王子市中野山王2-11-11
真言宗系単立
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場11番、武玉八十八ヶ所霊場82番


・応永元年(1394年)開基、徳川幕府から篤く保護されたと伝わる古刹。
・近代建築の本堂は斬新で、この霊場のなかでも異彩を放っている。
第21番
祥雲山 長安寺
東京都八王子市並木町7-1
曹洞宗
御本尊:准胝観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
※御本尊御朱印授与不明


・八王子千人同心の円山長安居士(島村豊後)の開基と伝わる。
・札所本尊の正観世音菩薩は、もとは明治初年に廃寺となった黄檗宗の宗明寺の御本尊。
・御本尊の准胝観世音菩薩は、もともと秩父三十四ヶ所の観音像の一尊ともいわれる。
第22番
常光山 観音院 真覚寺
東京都八王子市散田町5-36-10
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場71番、京王三十三観音霊場32番
※御本尊御朱印拝受済(多摩新四国)

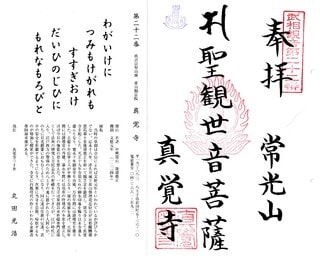
・応永十八年(1411年)、津久井城主・長山修理が観音堂を建立。真覚寺は観音堂の別当であったという。
・心字池を配し、緑豊かでなごめる山内は八王子市の指定旧跡。
第23番
聚林山 千光院 興福寺
東京都八王子市東浅川町754
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場23番


・関東十八代官のひとり雨宮勘兵衛の祖、雨宮秀徳の開基と伝わる。
・もとは観音堂があったと伝わるが、現在は本堂が札所となっている。
第24番
祐照庵 (大戸観音堂)
東京都町田市相原町4643
臨済宗南禅寺派
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場20番
※通常無住、寺役管理


・八王子市山田の雲律院の末寺として慶長元年(1596年)に開創。
・観音堂は明治初期に焼失し、現堂宇は第21番長安寺の太子堂を移築したもの。八王子八景のひとつ鐘楼門が見事。
第25番
金剛山 普門寺
神奈川県相模原市緑区中沢200
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・天平年間(729-748年)、行基菩薩開基と伝わる古刹で、山内の飯縄大権現は武田信玄公の尊崇篤かったと伝わる。
・観音堂に奉安の聖観世音菩薩は行基菩薩の御作とも伝わる古仏。
第26番
大瀧山 長徳寺
神奈川県相模原市緑区大島756
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:高座郡三十三ヶ所観音霊場26番
※御本尊御朱印授与なし


・甲州武田家臣の鳳山良長が、北条との戦いの戦死者を弔うために津久井の巧雲寺から宗山洞益和尚を招聘して創建と伝わる。
・以前は観音堂があったが焼失し、札所本尊は本堂内向かって左手壇内に奉安されている。
第27番
瑞石山 清水寺 (坂下観音、相原観音)
東京都町田市相原町701
臨済宗妙心寺派
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩


・坂下観音、相原観音とも呼ばれて信仰を集めた観音様のお寺。
・高台に建つ観音堂は華麗な彫刻が施され見事。市の文化財に指定されている。
第28番
施弥山 慈眼院 福生寺 〔田端観音寺・荒ヶ谷戸の観音〕
東京都町田市小山町2524
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:多摩百八ヶ所霊場97番
※御本尊御朱印拝受済(多摩百八ヶ所)


・天福元年(1233年)、天野孫兵衛が建立し、北条泰時から一字を賜り「福生寺」と号す。
・第28番札所本尊は、田端観音寺の「荒ヶ谷戸の観音」を観音堂に合祀。
第29番
施弥山 慈眼院 福生寺
東京都町田市小山町2524
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:多摩百八ヶ所霊場97番
※御本尊御朱印拝受済(多摩百八ヶ所)


・第29番札所本尊は、平安時代の作とされる檜一本造の正観世音菩薩像で、都有形文化財。 第28番札所本尊とともに観音堂に奉安されている。
第30番
白瀧山 高厳寺 (元町観音堂)
神奈川県相模原市中央区上溝6-18-4 元町自治会館
真言宗
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:高座郡三十三ヶ所観音霊場24番
※通常無住、自治会管理。


・もとは堂ヶ谷戸にあった高厳寺が、明治末に現地に移されたという。
・現在は自治会管理で、御開扉時のみの開堂と思われる。
第31番
聲音山 観心寺
神奈川県相模原市南区当麻774 原当麻自治会集会所
時宗
御本尊:正観世音大菩薩
札所本尊:正観世音大菩薩
※無量光寺(当麻)の管理。現在無量光寺は御朱印不授与。


・家内安全、ことに安産の観音さまとしてふるくから信仰を集める。
・現在は無量光寺の兼務だが、御開扉時以外は御朱印拝受は困難とみられる。
第32番
補陀洛山 清水寺
神奈川県相模原市南区下溝1457
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:高座郡三十三ヶ所観音霊場第22番


・読みは「せいすいじ」。征夷大将軍坂上田村麻呂ゆかりの地に慶長元年(1596年)開山と伝わる。浅草・東岳寺とゆかりをもち、双盤念仏で知られる。
・現在の御本尊は開山時に井戸から出現の十一面観世音菩薩で、坂上田村麻呂ゆかりの尊像とされる。
第33番
吉祥山 覺圓坊 (木曽の観音様)
東京都町田市木曽町4-7-33
天台寺門宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩


・当霊場では唯一の天台宗系寺院。康平六年(1063年)、園城寺第31代長吏覺圓僧正が開基という格式をもち、木曾義仲とゆかりをもつ。
・無住の堂宇だが広い境内をもち、端正な堂内に聖観世音菩薩が安置されている。
第34番
柳澤山 泉蔵寺
東京都町田市下小山田町1391
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛(十一面観世音菩薩)
札所本尊:十一面観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・正徳五年(1715年)下小山田村領主・柳澤備後守信尹が牛込・宗参寺の末寺として開基。
第35番
上柚木観音堂
東京都八王子市上柚木402-2 神明町会集会所
御本尊:準提観世音菩薩
札所本尊:準提観世音菩薩
※通常無住、14番永泉寺にて授与?

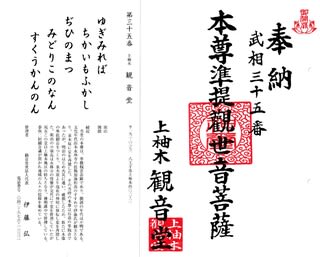
・文化年間(1804-1818年)、由木・永林寺住職の勧めにより並木原に伊藤氏が再興。
・明治はじめに当地に移転。当初は石仏が本尊で、いまは新造の木像とともに本堂厨子内に奉安されている。
第36番
富亀山 養樹院 圓通庵
東京都町田市上小山田町2536
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:准提観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・慶長十九年(1614年)下小山田の大泉寺住職が再興した趣きある寺院。
・札所本尊の准提観世音菩薩は女性の守護仏として信仰篤く、観音堂(圓通庵)に奉安されている。
第37番
瀧澤山 祥雲寺 (身代わり観音)
東京都町田市高ヶ坂7-15-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:身代聖観世音菩薩
他札所:武相寅歳薬師如来霊場19番(R4.4/9-5/8御開帳)
※御本尊御朱印授与なし


・大永六年(1526年)、伊勢原の石雲寺第三世・蓼堂秀郭大和尚を招聘して開山、北条氏の祈願所として創建されたという名刹。
・「身代わり観音」として知られる札所本尊は山内観音堂に奉安されている。
第38番
大悲山 慈眼寺 (都井沢の観音さま)
神奈川県相模原市緑区城山4-367
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩


・安産に霊験あらたかな「都井沢の観音さま」として地域の信仰を集めた観音さま。
・底を閉じない「底なし袋」を観音堂の扉に吊して安産祈願する風習が残る。
第39番
金森山 宗保院
東京都町田市原町田1-8-13
曹洞宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:原町田七福神(布袋尊)


・天文十一年(1542年)、この地の郷士・大河伊与が開基。町田駅に近い街なかの寺院ながら広大な境内をもつ。
・札所本尊の千手観世音菩薩は、大河氏の守り本尊と伝わる。
第40番
飯成山 永昌院
東京都八王子市中山452-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:十一面観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・天正十年(1582年)下柚木の栄林寺住職により創建、開基は葛沢豊前守と伝わる。
・札所本尊は山内観音堂に奉安。「ネコの寺」として有名?
第41番
金峰山 永林寺
東京都八王子市下柚木4
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:京王三十三観音霊場25番
※御本尊御朱印あり(書置)


・八王子だも有数の名刹。天文元年(1532年)、由木城主、武蔵國守護代・大石定久がこの地を叔父の一種長澄大和尚に譲り、永鱗寺として創建。徳川家康公も参拝し、赤門の建立を許される。
・札所本尊は山内高台の三重塔内に塔本尊として奉安され、御開扉時にはめずらしい三重塔と回向柱のとりあわせが見られる。
第42番
白華山 慈眼寺
東京都八王子市片倉町944
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・曹洞宗寺院ながら、御本尊は聖観世音菩薩。
・札所本尊の十一面観世音菩薩は、讃岐の七宝山観音寺の写しと伝わる。
第43番
金龍山 信松院
東京都八王子市台町3-18-28
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:八王子七福神(布袋尊)
※御本尊、信松尼の御朱印あり


・武田信玄公の息女・松姫を開基とする歴史の香り高い名刹。
・松姫は織田信長公の長男・信忠と婚約するも破談となり、天正十年(1582年)武田氏滅亡ののち八王子に逃れ、心源院にて出家(信松尼)、御所水(台町)の当地に庵を結んだという。
・以降、当庵で武田氏ゆかりの人々の菩提を弔い、八王子千人同心をはじめとする旧武田家臣の尊敬を集めたという。
第44番
大澤山 宗印寺
東京都日野市平山6-15-11
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:日野七福神(布袋尊)


・鎌倉御家人の重鎮・平山季重公ゆかりの名刹。
・「人々の願いには必ず応える」という聖観世音菩薩が御本尊として奉安されている。
第45番
金光山 観泉寺
東京都町田市真光寺町1210
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩


・元和元年(1615年)、大坂夏の陣で戦死したこの地の領主・飯田右馬之助昌有の菩提のために子の飯田次郎右衛門昌重が、小山田の大泉寺の住職を迎えて開創。
・御本尊・聖観世音菩薩のほか、脇本尊に二尊の観音像を奉安する観音さまのお寺。
第46番
一乗山 久松寺 吉祥院
東京都八王子市長房町58-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場67番、八王子七福神(吉祥天)
※御本尊御朱印拝受済(多摩新四国)

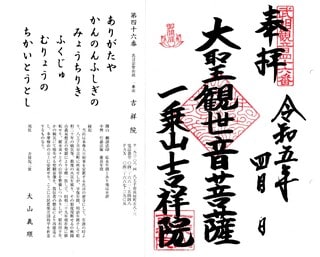
・八王子北部の高台に建つ真言宗寺院で、山内には多彩な尊格が奉安されている。
・八王子七福神の吉祥天霊場で、古来からの当寺の縁起にちなむという。
第47番
境國山 定方寺
神奈川県大和市下鶴間145
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:正観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・当初は境川沿い(現・定方寺公園)にあったが水害により当地に移転。
・札所本尊の正観世音菩薩は、庫裡寄りの一画で御開扉されていた。
第48番
淵源山 龍像寺
神奈川県相模原市中央区東淵野辺3-25-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


【写真 上(左)】 第48番 龍像寺
【写真 下(右)】 同 御朱印(専用納経帳用)
・暦応年間(1338-1341年)、この地の地頭・淵辺伊賀守義博による開基で、江戸時代のこの地の領主・岡野氏一族の菩提寺。
・札所本尊は、本堂向かって左手の高台に建つ六角堂(観音堂)内に奉安されている。
〔 結願証 〕

第48番龍像寺様にていただきました。
48箇寺はさすがにまわり応えがありましたが、札所のご対応も親切で充実した札所巡りとなりました。
まだ半月あります。
12年にいちどの貴重な機会、ぜひぜひどうぞ。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
僧侶のみならず、在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
宗派は違っても、御開帳の回向柱にはおおむねこのような願いが揮毫されています。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
-------------------------
2023/04/12 UP
半分以上回り終えました。
次第に知られてきているようで、先の土日はかなりの賑わいだった模様です。
東大和と寺院散策様の情報によると、非御開扉時でもだいたい御朱印はいただけそうです。
ただし、第31番観心寺の御朱印は「相模原市南区の無量光寺」でとなっていますが、無量光寺では現在御朱印を授与しておられませんので、こちらは「12年に一度の御朱印」となる可能性があります。


【写真 上(左)】 第31番観心寺
【写真 下(右)】 第31番観心寺の御朱印


【写真 上(左)】 無量光寺
【写真 下(右)】 無量光寺の掲示
無住のお堂で寺役さんに連絡して御朱印をいただくのはたいへんですし、なにより御開扉時の観音堂は華やいで、常とはちがう巡拝が味わえます。
まだまだ時間はありますので、貴重な卯年の御開扉を味わってみてはいかがでしょうか。


【写真 上(左)】 第27番清水寺
【写真 下(右)】 第27番清水寺の御朱印
なお、御本尊の御朱印については、関東八十八ヶ所や多摩新四国霊場の兼務札所では拝受できますが、武州卯歳の単独札所では不授与のところが多そうです。
入手困難と思っていたガイドブック(1999年11月刊)が第43番信松院様で頒布されていたので購入しました。

↓ こちらのガイドにも詳細に載っています。(メイツ出版 1,630円税別)

-------------------------
武相卯歳四十八観音霊場が4/1から御開扉となっています。
・御開扉(開帳)期間:4/1~4/30
・札所数48、開扉(開帳)数48、御朱印授与数48
・霊場概要・札所一覧はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~17:00 御朱印各300円
・専用納経帳あり(300円) 各札所にて頒布されています。
・武蔵国(八王子市・日野市・多摩市・町田市)と相模国(横浜市・相模原市・大和市)の48の札所からなる観音菩薩霊場です。
・12年に一度、卯歳に御開扉(開帳)され、前回は平成23年春でした。
・開創は宝暦九年(1759年)と伝わり、今回の御開扉(開帳)は第23回目。第1回御開扉から264年目に当たります。
・札所数は変動し、江戸時代の開創当時は33、第二十回開扉(1987年)では50、第二十一回開扉(1999年)では48となり、以降48で固定している模様です。(『武相観音めぐり』より)
・札所の宗派は多彩ですが、曹洞宗と真言宗寺院が多くなっています。


【写真 上(左)】 パンフレット
【写真 下(右)】 御開扉の幟
〔 パンフレット掲載の札所位置図 〕

4/1に第1番の鶴間山 観音寺様から打ちはじめました。
いまのところ6札所回っただけですが、最新情報をお伝えします。
専用納経帳は300円で頒布され、これに綴じ孔つきの専用御朱印を綴じ込んでいくかたちです。
前回、平成23年の専用納経帳よりひとまわり小さな体裁となっています。

【写真 上(左)】 今回の専用納経帳
【写真 下(右)】 前回(平成23年)の専用納経帳


【写真 上(左)】 第1番 観音寺の専用納経帳用御朱印(今回)
【写真 下(右)】 同(前回)
※「御開扉」印は、ご対応ある札所とない札所があるようです。


【写真 上(左)】 第1番 観音寺の御朱印帳貼付用御朱印(今回)
【写真 下(右)】 同 回向柱と向拝
別に御朱印帳貼付用の綴じ孔のあいていない書置御朱印も授与されていますが、すべての札所で授与されているかは不明。
御朱印帳直書についてのご対応は不明ですが、むずかしいかもしれません。


【写真 上(左)】 第1番 観音寺の札所標
【写真 下(右)】 第1番 観音寺の参道
通常無人の観音堂から、複数の霊場札所を兼務される大寺までさまざまで、変化に富んだ巡拝を味わえます。
とくに多摩丘陵の山ふところに点在する禅刹は、いずれも趣きのあるたたずまいです。


【写真 上(左)】 第17番 泉龍寺
【写真 下(右)】 同 御朱印(専用納経帳用)
無人の札所についてはおそらく通常は不授与で、中開帳もない模様なので12年に一度の御朱印となります。
公共交通機関の利用が推奨されているものの、多くの札所寺院は駐車場を備えられています。
(第2番 随流院様には駐車場はありませんが、すぐそばにコインパーキングがあります。)
ただし鶴間周辺、町田市中心部、八王子市中心部などは渋滞気味で予想以上に移動時間をとられます。
なので、17時までのご対応はありがたいことです。
回向柱は建立されている札所とない札所があります。
札所本尊の観音様はおおむね堂内奥に御座されて御開扉。回向柱はなくとも縁の綱は向拝まで引かれているようです。
なお、堂内はすべての札所で撮影禁止です。
早いタイミングであれば、桜のもとでの巡拝もできます。
札所数は多いですが、この貴重な機会に巡拝されてみてはいかがでしょうか。
詳細については、第1番 観音寺様の公式Web(→こちら)をご覧ください。
札所地図はこちらの「第23回 御開扉 パンフレット」からjpeg形式でダウンロードできます。
(各札所で配布されているパンフにも掲載されています。)
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子(Covered)
■ ひらひら ひらら - ClariS
■ 名もない花 - 遥海
各札所の概要、写真と御朱印を掲載します。
-------------------------
第1番
鶴間山 東照院 観音寺 〔真言院 金亀坊〕
神奈川県大和市下鶴間2240
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:武相寅歳薬師如来霊場21番(R4.4/9-5/8御開帳)、小田急武相三十三観音霊場28番、高座郡三十三ヶ所観音霊場29番


・青山往還沿いにあり、「青山往還の赤門寺」と呼ばれて参詣者を集めたとされる発願寺。
・御本尊の十一面観世音菩薩は慈覚大師の御作と伝わる。
第2番
陽向山 随流院 (火ぶせ観音) 〔長蔦寺〕
神奈川県横浜市緑区長津田5-4-30
曹洞宗
御本尊:釈迦無尼佛(聖観世音菩薩)
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・江戸幕府の旗本・岡野家の菩提寺で「長津田」の地名の元とも。
・聖観世音菩薩は、ふるくから「火防の観音」として信仰を集めている。
第3番
大峰山 松岳院 (奈良村観音堂) 〔正覚院〕
神奈川県横浜市青葉区奈良2-4-6
曹洞宗
御本尊:釈迦無尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与あり(書置)

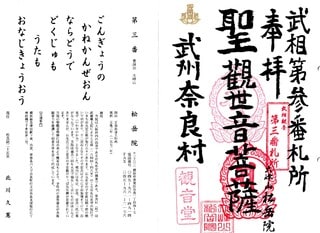
・開基は旧奈良村知行の石丸有貞とされる。
・聖観世音菩薩は、旧奈良村にあった観音堂から水害を受けて遷されたと伝わる。
第4番
三枝山 観性寺
東京都町田市西成瀬2-11-8
曹洞宗
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
※通常無住(成瀬4-14-1東雲寺管理)

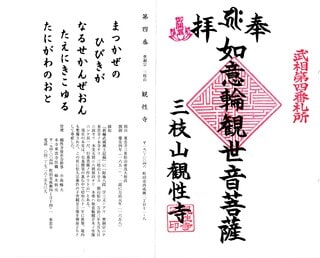
・御本尊の如意輪観世音菩薩は、行基菩薩の御作と伝わる。
・別尊として松久宗琳作の子育て観音を奉安。
第5番
鶏足山 智光院 養運寺
東京都町田市本町田3654
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印拝受済(御開扉期間中の授与不明)


・鎌倉時代からつづくとされる浄土宗の古刹で、札所は山内観音堂。
・もとは大谷村との境に御座の観音さまを、安永五年(1776年)に合祀と伝わる。
第6番
岩子山 普門寺 千手院
東京都町田市小野路町2057
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:関東八十八箇所64番、多摩新四国八十八ヶ所霊場12番、多摩川三十四観音霊場34番、小田急武相三十三観音霊場10番


・奈良時代、行基菩薩の開基と伝わる真言宗豊山派の名刹。
・本堂裏手高台の奥の院も観音堂で、現在は十一面観世音菩薩を奉安。この観音堂は小山田次郎重義が観音像を感得して建立と伝わる。
第7番
慈眼山 唐仏院 観音寺 (せきど観音)
東京都多摩市関戸5-31-11
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩十三仏霊場5番(地蔵菩薩)、多摩川三十四観音霊場12番


・「関戸観音堂」と呼ばれ古くから信仰を集めた。
・元弘三年(1333年)、新田義貞と鎌倉幕府の「関戸の戦」の地で関連の史跡が残る。
第8番
清谷山 蓮華院 真照寺 (子安観音)
東京都日野市落川1113
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場17番、多摩川三十四観音霊場11番、日野七福神(恵比須天)


・長和年間(1012-1017年)開山と伝わる真言宗の古刹。
・子安観音として知られる千手観世音菩薩を山内観音堂に奉安。
第9番
桝井山 松連寺 観音堂 (百草観音堂)
東京都下日野市百草849-1
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
※通常無住(八王子清鏡寺管理?)

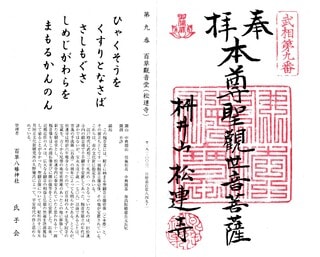
・もとは京王百草園にあったとされ、景勝の地として知られていた。
・旧松連寺所蔵の多くの仏像を奉安し、「百草観音堂仏教彫刻群」として市の文化財に指定されている。
第10番
塩釜山 清鏡寺 (大塚観音堂・御手の観音)
東京都八王子市大塚378
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊(阿弥陀如来)
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:多摩川三十四観音霊場10番、京王三十三観音霊場24番
※御本尊御朱印は御開扉期間中授与なし


・清鏡寺は、もとは北条氏再興祈願の観音堂の別当。
・山内高台の観音堂に奉安の千手観世音菩薩は足腰健康の霊験あらたかで「大塚観音堂・御手の観音」としてふるくから信仰を集めている。
第11番
補陀山 水月院 大泉寺
東京都町田市下小山田町332
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・『新編武蔵風土記稿』には「町田の大寺」と掲載され、いまも大寺の風格を湛える。
・鎌倉武士・小山田有重の城跡に建立し、札所本尊は「見合い観音」とも呼ばれ若い女性の参詣を集めたという。
第12番
龍澤山 保井寺
東京都八王子市堀之内547
曹洞宗
御本尊:虚空藏菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
※御本尊御朱印拝受済(御開扉期間中の授与不明)


・読みは「ほうせいじ」。町田市下小山町の観音寺から遷られた如意輪観世音菩薩が札所本尊で、山内観音堂に奉安されている。「椿の寺」としても有名。
第13番
吹王山 (不動院) 玉泉寺(もかけの観音)
東京都八王子市越野726
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩百八ヶ所霊場105番
※御本尊御朱印拝受済(多摩百八ヶ所)


・裳が蓮台までかかる宗風の像容から「もかけの観音」と呼ばれる札所本尊は、旧導義寺観音堂から玉泉寺観音堂に遷られ、現在は越野自治会集会所に奉安されている。
・札所本尊造立の願主は、底部墨書から北条氏照の家臣・小田野周重とみられている。
第14番
高雲山 永泉寺
東京都八王子市鑓水80
御本尊:釈迦無尼仏
札所本尊:正観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・甲州武田家臣・永野和泉開基の古刹で、鑓水の絹商人・八木下要右衛門の旧邸の地とされる。
・俳句の寺として知られ、山内には芭蕉堂が建つ。
第15番
安榮山 明王院 福傳寺 (子安観音)
東京都八王子市明神町4-10-6
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場77番、八王子三十三観音霊場30番、武玉八十八ヶ所霊場65番
※御本尊御朱印拝受済(多摩新四国)


・八王子の街なかにある真言宗寺院で、子安神社の元別当。
・安産の観音さまとして信仰篤く「村内に難産の者なし」と伝わる。
第16番
慈高山 金剛院
東京都八王子市上野町39-2
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩
関東八十八箇所63番、多摩新四国八十八ヶ所霊場73番、八王子三十三観音霊場31番、京王三十三観音霊場30番、八王子七福神(福禄寿)、武玉八十八ヶ所霊場63番
※御本尊御朱印拝受(関東八十八箇所、多摩新四国)


・草創は天正四年(1576年)僧真清開基の明王院。のちに当地の大師堂とあわせ金剛院と号す。
・札所本尊の十一面観世音菩薩は、本堂参道向かって左手の福聚堂に奉安されている。
第17番
中和山 泉龍寺
神奈川県相模原市南区上鶴間本町8-54-21
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印は御開扉中不授与


・大規模な三重塔を擁する曹洞宗の大寺。三重塔よこに観音堂があるが、御開扉時は本堂に奉安されていた。
・札所本尊は公所の井上助右衛門の霊夢を受けての造立と伝わる。
第18番
竜雲山 高乗寺
東京都八王子市初沢町1425
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:十一面観世音菩薩・三十三体観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場19番
※御本尊御朱印拝受済(御開扉中書置)


・片倉城主・永井大膳太夫高乗(広秀)が開基の「多摩八大寺」に数えられる曹洞宗の名刹。
・札所本尊は、本堂向かって左の大慈閣に奉安されている。
第19番
天龍山 福昌寺
横浜市青葉区恩田町1021-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:武相寅歳薬師如来霊場14番(R4.4/9-5/8御開帳)
※御本尊御朱印拝受済(御開扉中書置)


・横浜市青葉区の住宅地にある曹洞宗寺院。
・以前は二間四方の観音堂があったとされるが、現在、札所本尊は本堂に奉安されている。
第20番
北岸山 喜福寺
東京都八王子市中野山王2-11-11
真言宗系単立
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場11番、武玉八十八ヶ所霊場82番


・応永元年(1394年)開基、徳川幕府から篤く保護されたと伝わる古刹。
・近代建築の本堂は斬新で、この霊場のなかでも異彩を放っている。
第21番
祥雲山 長安寺
東京都八王子市並木町7-1
曹洞宗
御本尊:准胝観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
※御本尊御朱印授与不明


・八王子千人同心の円山長安居士(島村豊後)の開基と伝わる。
・札所本尊の正観世音菩薩は、もとは明治初年に廃寺となった黄檗宗の宗明寺の御本尊。
・御本尊の准胝観世音菩薩は、もともと秩父三十四ヶ所の観音像の一尊ともいわれる。
第22番
常光山 観音院 真覚寺
東京都八王子市散田町5-36-10
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場71番、京王三十三観音霊場32番
※御本尊御朱印拝受済(多摩新四国)

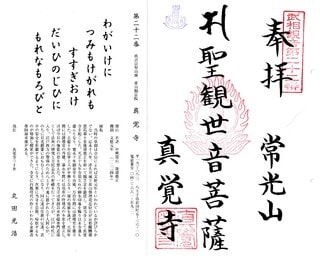
・応永十八年(1411年)、津久井城主・長山修理が観音堂を建立。真覚寺は観音堂の別当であったという。
・心字池を配し、緑豊かでなごめる山内は八王子市の指定旧跡。
第23番
聚林山 千光院 興福寺
東京都八王子市東浅川町754
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場23番


・関東十八代官のひとり雨宮勘兵衛の祖、雨宮秀徳の開基と伝わる。
・もとは観音堂があったと伝わるが、現在は本堂が札所となっている。
第24番
祐照庵 (大戸観音堂)
東京都町田市相原町4643
臨済宗南禅寺派
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:八王子三十三観音霊場20番
※通常無住、寺役管理


・八王子市山田の雲律院の末寺として慶長元年(1596年)に開創。
・観音堂は明治初期に焼失し、現堂宇は第21番長安寺の太子堂を移築したもの。八王子八景のひとつ鐘楼門が見事。
第25番
金剛山 普門寺
神奈川県相模原市緑区中沢200
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・天平年間(729-748年)、行基菩薩開基と伝わる古刹で、山内の飯縄大権現は武田信玄公の尊崇篤かったと伝わる。
・観音堂に奉安の聖観世音菩薩は行基菩薩の御作とも伝わる古仏。
第26番
大瀧山 長徳寺
神奈川県相模原市緑区大島756
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:高座郡三十三ヶ所観音霊場26番
※御本尊御朱印授与なし


・甲州武田家臣の鳳山良長が、北条との戦いの戦死者を弔うために津久井の巧雲寺から宗山洞益和尚を招聘して創建と伝わる。
・以前は観音堂があったが焼失し、札所本尊は本堂内向かって左手壇内に奉安されている。
第27番
瑞石山 清水寺 (坂下観音、相原観音)
東京都町田市相原町701
臨済宗妙心寺派
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩


・坂下観音、相原観音とも呼ばれて信仰を集めた観音様のお寺。
・高台に建つ観音堂は華麗な彫刻が施され見事。市の文化財に指定されている。
第28番
施弥山 慈眼院 福生寺 〔田端観音寺・荒ヶ谷戸の観音〕
東京都町田市小山町2524
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:多摩百八ヶ所霊場97番
※御本尊御朱印拝受済(多摩百八ヶ所)


・天福元年(1233年)、天野孫兵衛が建立し、北条泰時から一字を賜り「福生寺」と号す。
・第28番札所本尊は、田端観音寺の「荒ヶ谷戸の観音」を観音堂に合祀。
第29番
施弥山 慈眼院 福生寺
東京都町田市小山町2524
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:多摩百八ヶ所霊場97番
※御本尊御朱印拝受済(多摩百八ヶ所)


・第29番札所本尊は、平安時代の作とされる檜一本造の正観世音菩薩像で、都有形文化財。 第28番札所本尊とともに観音堂に奉安されている。
第30番
白瀧山 高厳寺 (元町観音堂)
神奈川県相模原市中央区上溝6-18-4 元町自治会館
真言宗
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:正観世音菩薩
他札所:高座郡三十三ヶ所観音霊場24番
※通常無住、自治会管理。


・もとは堂ヶ谷戸にあった高厳寺が、明治末に現地に移されたという。
・現在は自治会管理で、御開扉時のみの開堂と思われる。
第31番
聲音山 観心寺
神奈川県相模原市南区当麻774 原当麻自治会集会所
時宗
御本尊:正観世音大菩薩
札所本尊:正観世音大菩薩
※無量光寺(当麻)の管理。現在無量光寺は御朱印不授与。


・家内安全、ことに安産の観音さまとしてふるくから信仰を集める。
・現在は無量光寺の兼務だが、御開扉時以外は御朱印拝受は困難とみられる。
第32番
補陀洛山 清水寺
神奈川県相模原市南区下溝1457
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:高座郡三十三ヶ所観音霊場第22番


・読みは「せいすいじ」。征夷大将軍坂上田村麻呂ゆかりの地に慶長元年(1596年)開山と伝わる。浅草・東岳寺とゆかりをもち、双盤念仏で知られる。
・現在の御本尊は開山時に井戸から出現の十一面観世音菩薩で、坂上田村麻呂ゆかりの尊像とされる。
第33番
吉祥山 覺圓坊 (木曽の観音様)
東京都町田市木曽町4-7-33
天台寺門宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩


・当霊場では唯一の天台宗系寺院。康平六年(1063年)、園城寺第31代長吏覺圓僧正が開基という格式をもち、木曾義仲とゆかりをもつ。
・無住の堂宇だが広い境内をもち、端正な堂内に聖観世音菩薩が安置されている。
第34番
柳澤山 泉蔵寺
東京都町田市下小山田町1391
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛(十一面観世音菩薩)
札所本尊:十一面観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・正徳五年(1715年)下小山田村領主・柳澤備後守信尹が牛込・宗参寺の末寺として開基。
第35番
上柚木観音堂
東京都八王子市上柚木402-2 神明町会集会所
御本尊:準提観世音菩薩
札所本尊:準提観世音菩薩
※通常無住、14番永泉寺にて授与?

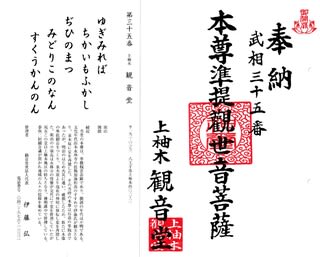
・文化年間(1804-1818年)、由木・永林寺住職の勧めにより並木原に伊藤氏が再興。
・明治はじめに当地に移転。当初は石仏が本尊で、いまは新造の木像とともに本堂厨子内に奉安されている。
第36番
富亀山 養樹院 圓通庵
東京都町田市上小山田町2536
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:准提観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・慶長十九年(1614年)下小山田の大泉寺住職が再興した趣きある寺院。
・札所本尊の准提観世音菩薩は女性の守護仏として信仰篤く、観音堂(圓通庵)に奉安されている。
第37番
瀧澤山 祥雲寺 (身代わり観音)
東京都町田市高ヶ坂7-15-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:身代聖観世音菩薩
他札所:武相寅歳薬師如来霊場19番(R4.4/9-5/8御開帳)
※御本尊御朱印授与なし


・大永六年(1526年)、伊勢原の石雲寺第三世・蓼堂秀郭大和尚を招聘して開山、北条氏の祈願所として創建されたという名刹。
・「身代わり観音」として知られる札所本尊は山内観音堂に奉安されている。
第38番
大悲山 慈眼寺 (都井沢の観音さま)
神奈川県相模原市緑区城山4-367
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩


・安産に霊験あらたかな「都井沢の観音さま」として地域の信仰を集めた観音さま。
・底を閉じない「底なし袋」を観音堂の扉に吊して安産祈願する風習が残る。
第39番
金森山 宗保院
東京都町田市原町田1-8-13
曹洞宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:原町田七福神(布袋尊)


・天文十一年(1542年)、この地の郷士・大河伊与が開基。町田駅に近い街なかの寺院ながら広大な境内をもつ。
・札所本尊の千手観世音菩薩は、大河氏の守り本尊と伝わる。
第40番
飯成山 永昌院
東京都八王子市中山452-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:十一面観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・天正十年(1582年)下柚木の栄林寺住職により創建、開基は葛沢豊前守と伝わる。
・札所本尊は山内観音堂に奉安。「ネコの寺」として有名?
第41番
金峰山 永林寺
東京都八王子市下柚木4
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:京王三十三観音霊場25番
※御本尊御朱印あり(書置)


・八王子だも有数の名刹。天文元年(1532年)、由木城主、武蔵國守護代・大石定久がこの地を叔父の一種長澄大和尚に譲り、永鱗寺として創建。徳川家康公も参拝し、赤門の建立を許される。
・札所本尊は山内高台の三重塔内に塔本尊として奉安され、御開扉時にはめずらしい三重塔と回向柱のとりあわせが見られる。
第42番
白華山 慈眼寺
東京都八王子市片倉町944
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・曹洞宗寺院ながら、御本尊は聖観世音菩薩。
・札所本尊の十一面観世音菩薩は、讃岐の七宝山観音寺の写しと伝わる。
第43番
金龍山 信松院
東京都八王子市台町3-18-28
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:八王子七福神(布袋尊)
※御本尊、信松尼の御朱印あり


・武田信玄公の息女・松姫を開基とする歴史の香り高い名刹。
・松姫は織田信長公の長男・信忠と婚約するも破談となり、天正十年(1582年)武田氏滅亡ののち八王子に逃れ、心源院にて出家(信松尼)、御所水(台町)の当地に庵を結んだという。
・以降、当庵で武田氏ゆかりの人々の菩提を弔い、八王子千人同心をはじめとする旧武田家臣の尊敬を集めたという。
第44番
大澤山 宗印寺
東京都日野市平山6-15-11
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:日野七福神(布袋尊)


・鎌倉御家人の重鎮・平山季重公ゆかりの名刹。
・「人々の願いには必ず応える」という聖観世音菩薩が御本尊として奉安されている。
第45番
金光山 観泉寺
東京都町田市真光寺町1210
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩


・元和元年(1615年)、大坂夏の陣で戦死したこの地の領主・飯田右馬之助昌有の菩提のために子の飯田次郎右衛門昌重が、小山田の大泉寺の住職を迎えて開創。
・御本尊・聖観世音菩薩のほか、脇本尊に二尊の観音像を奉安する観音さまのお寺。
第46番
一乗山 久松寺 吉祥院
東京都八王子市長房町58-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場67番、八王子七福神(吉祥天)
※御本尊御朱印拝受済(多摩新四国)

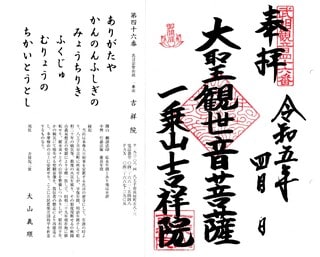
・八王子北部の高台に建つ真言宗寺院で、山内には多彩な尊格が奉安されている。
・八王子七福神の吉祥天霊場で、古来からの当寺の縁起にちなむという。
第47番
境國山 定方寺
神奈川県大和市下鶴間145
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:正観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


・当初は境川沿い(現・定方寺公園)にあったが水害により当地に移転。
・札所本尊の正観世音菩薩は、庫裡寄りの一画で御開扉されていた。
第48番
淵源山 龍像寺
神奈川県相模原市中央区東淵野辺3-25-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:聖観世音菩薩
※御本尊御朱印授与なし


【写真 上(左)】 第48番 龍像寺
【写真 下(右)】 同 御朱印(専用納経帳用)
・暦応年間(1338-1341年)、この地の地頭・淵辺伊賀守義博による開基で、江戸時代のこの地の領主・岡野氏一族の菩提寺。
・札所本尊は、本堂向かって左手の高台に建つ六角堂(観音堂)内に奉安されている。
〔 結願証 〕

第48番龍像寺様にていただきました。
48箇寺はさすがにまわり応えがありましたが、札所のご対応も親切で充実した札所巡りとなりました。
まだ半月あります。
12年にいちどの貴重な機会、ぜひぜひどうぞ。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
僧侶のみならず、在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
宗派は違っても、御開帳の回向柱にはおおむねこのような願いが揮毫されています。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
-------------------------
2023/04/12 UP
半分以上回り終えました。
次第に知られてきているようで、先の土日はかなりの賑わいだった模様です。
東大和と寺院散策様の情報によると、非御開扉時でもだいたい御朱印はいただけそうです。
ただし、第31番観心寺の御朱印は「相模原市南区の無量光寺」でとなっていますが、無量光寺では現在御朱印を授与しておられませんので、こちらは「12年に一度の御朱印」となる可能性があります。


【写真 上(左)】 第31番観心寺
【写真 下(右)】 第31番観心寺の御朱印


【写真 上(左)】 無量光寺
【写真 下(右)】 無量光寺の掲示
無住のお堂で寺役さんに連絡して御朱印をいただくのはたいへんですし、なにより御開扉時の観音堂は華やいで、常とはちがう巡拝が味わえます。
まだまだ時間はありますので、貴重な卯年の御開扉を味わってみてはいかがでしょうか。


【写真 上(左)】 第27番清水寺
【写真 下(右)】 第27番清水寺の御朱印
なお、御本尊の御朱印については、関東八十八ヶ所や多摩新四国霊場の兼務札所では拝受できますが、武州卯歳の単独札所では不授与のところが多そうです。
入手困難と思っていたガイドブック(1999年11月刊)が第43番信松院様で頒布されていたので購入しました。

↓ こちらのガイドにも詳細に載っています。(メイツ出版 1,630円税別)

-------------------------
武相卯歳四十八観音霊場が4/1から御開扉となっています。
・御開扉(開帳)期間:4/1~4/30
・札所数48、開扉(開帳)数48、御朱印授与数48
・霊場概要・札所一覧はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~17:00 御朱印各300円
・専用納経帳あり(300円) 各札所にて頒布されています。
・武蔵国(八王子市・日野市・多摩市・町田市)と相模国(横浜市・相模原市・大和市)の48の札所からなる観音菩薩霊場です。
・12年に一度、卯歳に御開扉(開帳)され、前回は平成23年春でした。
・開創は宝暦九年(1759年)と伝わり、今回の御開扉(開帳)は第23回目。第1回御開扉から264年目に当たります。
・札所数は変動し、江戸時代の開創当時は33、第二十回開扉(1987年)では50、第二十一回開扉(1999年)では48となり、以降48で固定している模様です。(『武相観音めぐり』より)
・札所の宗派は多彩ですが、曹洞宗と真言宗寺院が多くなっています。


【写真 上(左)】 パンフレット
【写真 下(右)】 御開扉の幟
〔 パンフレット掲載の札所位置図 〕

4/1に第1番の鶴間山 観音寺様から打ちはじめました。
いまのところ6札所回っただけですが、最新情報をお伝えします。
専用納経帳は300円で頒布され、これに綴じ孔つきの専用御朱印を綴じ込んでいくかたちです。
前回、平成23年の専用納経帳よりひとまわり小さな体裁となっています。

【写真 上(左)】 今回の専用納経帳
【写真 下(右)】 前回(平成23年)の専用納経帳


【写真 上(左)】 第1番 観音寺の専用納経帳用御朱印(今回)
【写真 下(右)】 同(前回)
※「御開扉」印は、ご対応ある札所とない札所があるようです。


【写真 上(左)】 第1番 観音寺の御朱印帳貼付用御朱印(今回)
【写真 下(右)】 同 回向柱と向拝
別に御朱印帳貼付用の綴じ孔のあいていない書置御朱印も授与されていますが、すべての札所で授与されているかは不明。
御朱印帳直書についてのご対応は不明ですが、むずかしいかもしれません。


【写真 上(左)】 第1番 観音寺の札所標
【写真 下(右)】 第1番 観音寺の参道
通常無人の観音堂から、複数の霊場札所を兼務される大寺までさまざまで、変化に富んだ巡拝を味わえます。
とくに多摩丘陵の山ふところに点在する禅刹は、いずれも趣きのあるたたずまいです。


【写真 上(左)】 第17番 泉龍寺
【写真 下(右)】 同 御朱印(専用納経帳用)
無人の札所についてはおそらく通常は不授与で、中開帳もない模様なので12年に一度の御朱印となります。
公共交通機関の利用が推奨されているものの、多くの札所寺院は駐車場を備えられています。
(第2番 随流院様には駐車場はありませんが、すぐそばにコインパーキングがあります。)
ただし鶴間周辺、町田市中心部、八王子市中心部などは渋滞気味で予想以上に移動時間をとられます。
なので、17時までのご対応はありがたいことです。
回向柱は建立されている札所とない札所があります。
札所本尊の観音様はおおむね堂内奥に御座されて御開扉。回向柱はなくとも縁の綱は向拝まで引かれているようです。
なお、堂内はすべての札所で撮影禁止です。
早いタイミングであれば、桜のもとでの巡拝もできます。
札所数は多いですが、この貴重な機会に巡拝されてみてはいかがでしょうか。
詳細については、第1番 観音寺様の公式Web(→こちら)をご覧ください。
札所地図はこちらの「第23回 御開扉 パンフレット」からjpeg形式でダウンロードできます。
(各札所で配布されているパンフにも掲載されています。)
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子(Covered)
■ ひらひら ひらら - ClariS
■ 名もない花 - 遥海
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 1980年代の母性曲
■ 翳りゆく部屋(松任谷由実~私と荒井由実の50年~)から分離して、曲を追加してみました。
-------------------
1980年代前後はいささか迷いがあったようなコメント。「もがき」と表現していた。
でも、そんなことないと思うけどね。楽曲のできからすると。
-------------------
■ユーミンの母性曲
その迷い?を打開したのが1981年の「守ってあげたい」だと思う。
これはユーミンの「母性」を感じさせる曲だった。
ここからの数年間でリリースした「ずっとそばに」「ノーサイド」を合わせて、個人的にはユーミンの3大母性曲だと思っている。
□ 守ってあげたい(1981年)
これもカノン進行だよね。でもベタつかない。
□ ずっとそばに 『REINCARNATION』(1983年)
バックのインストのフレーズどりが神すぎる。個人的にはユーミン屈指の名曲。
□ ノーサイド 『NO SIDE』(1984年)
この時代ならではのフェンダー・ローズの響きがたまらん。
たしかにこの時代(1980年代前半~中盤)、男性が同世代の女性に無意識的にでも「母性」を求める流れがあったのかもしれぬ。
それだけ女性サイドにも余裕があったのでは・・・。
□ YOU ARE NOT ALONE - ANRI 杏里 『Timely!!』(1983年)
□ Cloudyな午後 - 中原めいこ 『ロートスの果実』(1984年)
□ Anytime Anyplace - 当山ひとみ 『Hello Me』(1986年)
□ ホノルル・シティ・ライツ - 二名敦子(1984年)
□ やわらかなあした - 今井優子(1988年)
□ 瞳がほほえむから - 今井美樹(1986年)
こういう路線を敷いたのはやっぱりユーミンでは・・・。
↓ これも母性曲だと思う。
□ シャ・ラ・ラ - サザンオールスターズ(1982年)
-------------------
1980年代前後はいささか迷いがあったようなコメント。「もがき」と表現していた。
でも、そんなことないと思うけどね。楽曲のできからすると。
-------------------
■ユーミンの母性曲
その迷い?を打開したのが1981年の「守ってあげたい」だと思う。
これはユーミンの「母性」を感じさせる曲だった。
ここからの数年間でリリースした「ずっとそばに」「ノーサイド」を合わせて、個人的にはユーミンの3大母性曲だと思っている。
□ 守ってあげたい(1981年)
これもカノン進行だよね。でもベタつかない。
□ ずっとそばに 『REINCARNATION』(1983年)
バックのインストのフレーズどりが神すぎる。個人的にはユーミン屈指の名曲。
□ ノーサイド 『NO SIDE』(1984年)
この時代ならではのフェンダー・ローズの響きがたまらん。
たしかにこの時代(1980年代前半~中盤)、男性が同世代の女性に無意識的にでも「母性」を求める流れがあったのかもしれぬ。
それだけ女性サイドにも余裕があったのでは・・・。
□ YOU ARE NOT ALONE - ANRI 杏里 『Timely!!』(1983年)
□ Cloudyな午後 - 中原めいこ 『ロートスの果実』(1984年)
□ Anytime Anyplace - 当山ひとみ 『Hello Me』(1986年)
□ ホノルル・シティ・ライツ - 二名敦子(1984年)
□ やわらかなあした - 今井優子(1988年)
□ 瞳がほほえむから - 今井美樹(1986年)
こういう路線を敷いたのはやっぱりユーミンでは・・・。
↓ これも母性曲だと思う。
□ シャ・ラ・ラ - サザンオールスターズ(1982年)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 静岡県河津町の御朱印
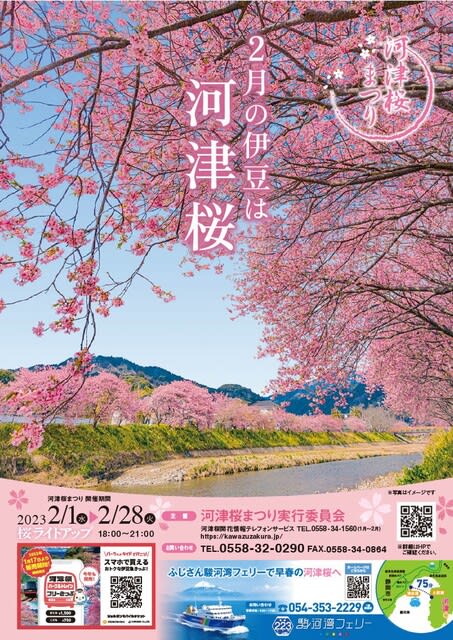
河津町の河津桜がそろそろ見頃のようです。
「河津桜まつり」(2/1~3/5)が開催されています。
(当初~2/28までが~3/5に変更か?)
18時~21時はライトアップもされる模様。
河津町の御朱印を網羅的にまとめたWebが見当たらないのでつくってみました。
河津町は伊豆八十八ヶ所霊場と伊豆横道三十三観音霊場の札所が複数あり、拝受可能御朱印数は多いエリアです。
ただし、伊豆横道三十三観音霊場の札所は無住のお堂がメインで、他所でいただくことになるので拝受難易度は高くなっています。


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場のガイドブック
【写真 下(右)】 伊豆横道三十三観音霊場のガイドブック
御朱印帳は神社なら川津来宮神社、寺院ならば栖足寺で頒布されています。
仏像ファンならば谷津の「河津平安の仏像展示館」も見どころとなります。
(南禅寺の御朱印はこちらでいただけます。)
それでは天城峠から河津浜に向かって順にご紹介していきます。
※現在、拝受できない御朱印があるかもしれません。
〔ご参考〕
→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
■ 天城山 慈眼院(じげんいん)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
賀茂郡河津町梨本28-1
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
札所:伊豆八十八ヶ所霊場(新?)第35番
授与所:温泉施設「禅の湯」内
・国道414号天城街道が天城峠から七滝ループ橋を経て下ってきたところ、温泉地としても知られる梨本エリアにあり、お寺というより温泉施設「禅の湯」が前面に出ています。
・伊豆山中に真言宗の庵として草創、慶安(1648-1652年)年間に現在地に遷り普門院雲國和尚を開山祖として庵を院に改めています。
・伊豆八十八ヶ所霊場第35番は栖足寺から慈眼院に変更された模様です。



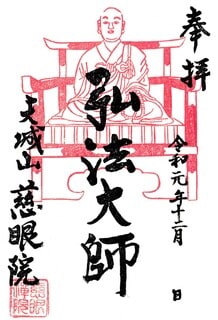
【写真 上(左)】 御本尊・聖観世音菩薩の御朱印
【写真 下(右)】 弘法大師の御朱印

■ ほうそうばあさんの御朱印
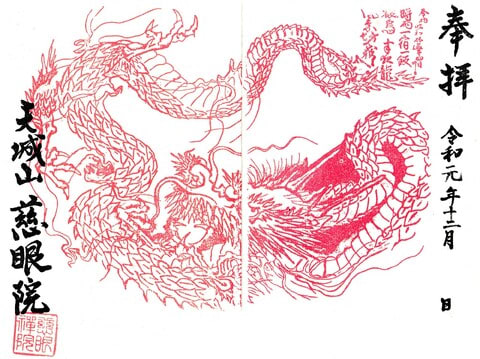
■ 龍の御朱印
龍の御朱印は、本堂の豪快な天井絵にちなむもの。
「ほうそうばあさん」は、疱瘡神(疱瘡を患うことがないよう祈念する神様)です。
詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
■ 千手山 三養院(さんよういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町川津筏場807-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第34番
授与所:庫裡
・現地由緒書等の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。
・開山当初は千手院(庵)と号しました。
・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。
・この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。
・なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。


〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
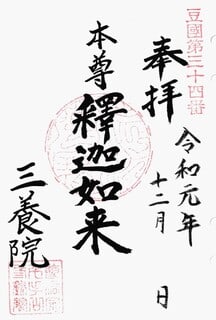
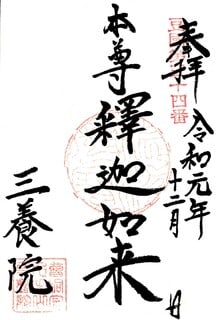
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ
■ 澤田涅槃堂(さわだねはんどう)
紹介Web(河津町)
河津町沢田108
曹洞宗?
御本尊:釈迦如来涅槃像
札所本尊:-
札所:-
授与所:期間限定・現地
・創立は江戸時代初期で三養院の控寺として建てられたものと推定されています。
澤田涅槃堂の御朱印は、河津さくらまつり(2/1~3/5)中の限定授与となる模様です。(筆者未拝受)
■ 萬松山 普門院(ふもんいん)
河津町逆川500
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
札所:伊豆横道三十三観音霊場第13番
授与所:入口左手の個人宅
・応永七年(1400年)、鈴木采女正が一寺を建立し、模菴宗範和尚(足利持氏の甥)を迎えて開山と伝わります。
・模菴宗範和尚はのちに小田原最乗寺の住職となり、足利持氏とのゆかりもあって寺勢は隆盛したといいます。


■ 金鳥山 東大寺(とうだいじ)
河津町峰382
曹洞宗
御本尊:
札所本尊:十一面観世音菩薩
札所:伊豆横道三十三観音霊場第15番
授与所:寺役管理で現地に授与先の電話番号
・草創は東大庵と号する小庵で、慶長元年(1596年)菩提寺と合併して東大寺に改めました。
・御本尊は行基菩薩の御作と伝わる十一面観世音菩薩。


■ 稲荷山 善光庵(ぜんこうあん)
河津町峰382
宗派不明
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
札所:伊豆横道三十三観音霊場第16番
授与所:観音堂区長管理
・峰温泉のそばにあり、南禅寺より十一面観世音菩薩を移遷して改築・再興と伝わります。
・下峰観音堂とも呼ばれ、伊豆横道三十三観音霊場第16番札所です。
・檜材一本造等身大の御本尊は、平安中期の作とみられ県の指定文化財です。


■ 東泉山 南禅寺(なぜんじ)
河津町谷津129
真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
札所:伊豆横道三十三観音霊場第17番
授与所:河津平安の仏像展示館受付
※絵御朱印がある模様。
・行基菩薩開創と伝わる古刹で、御本尊の薬師如来も行基の自刻と伝わります。
・当初は那蘭陀(ならんだ)寺と号し、伽藍建立は康和元年(1099年)といいます。
・多くの仏像を擁し、一部はすぐよこの河津平安の仏像展示館で公開されています。


■ 小峰堂(こみねどう)
河津町田中268
宗派不明
御本尊:
札所本尊:千手観世音菩薩
札所:伊豆横道三十三観音霊場第14番
授与所:近くの谷水屋商店にて(営業日のみ、原則火曜休)
・縁起類が遺っておらず詳細不明ですが、伊豆横道三十三観音霊場第14番の札所で、御本尊は千手観世音菩薩です。


■ 杉桙別命神社 (川津来宮神社)(すぎほこわけのみことじんじゃ)
公式Web
河津町田中宮ノ脇153
御祭神:杉桙別命
旧社格:延喜式内社(小)、郷社、川津17箇村総鎮守
授与所:境内社務所にて
・社格が高く、このあたりでは貴重なご神職常駐の神社。樹齢千年以上といわれる「来宮様の大クス」で有名。

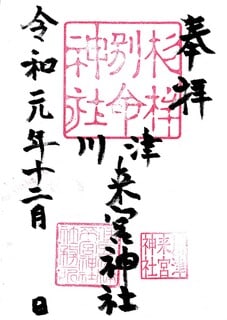
■ 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)
公式Web
河津町谷津256
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
札所:(旧)伊豆八十八ヶ所霊場第35番
授与所:授与所 or 本堂内
・河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。
・公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。
・徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。
応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。
・カラフルで多彩な御朱印で有名です。


〔 (旧)伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
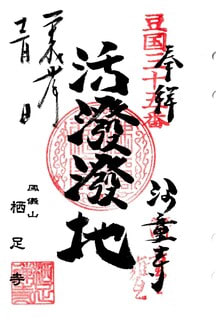

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっている模様です。
公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印
詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
■ 佛光山 専光寺(せんこうじ)
河津町谷津256
浄土真宗本願寺派
御本尊:
札所本尊:-
札所:-
授与所:本堂内
・開放的なお寺さまで、浄土真宗本願寺派ですが御朱印(参拝記念)を授与されています。


■ 長運山 乗安寺(じょうあんじ)
河津町観光協会
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町谷津413
日蓮宗
御本尊:十界曼荼羅
札所本尊:
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第36番
授与所:庫裡
・伊豆八十八ヶ所霊場唯一の貴重な日蓮宗の札所です。
・『こころの旅』『霊場めぐり』によると、慶長年間(1596-1615年)縄地金山採掘の際、縄地に身延山久遠寺廿二世日遠上人を開山に創立、のちに現在地に移されたといいます。
・開山日遠上人が法輪のため駿府城に赴いた際、家康公の怒りにふれ安倍川の河原で斬罪に処せられるところ、側室お万の方が上人を自らの女駕籠に乗せてこの地へ逃したという伝承があります。当山には、そのときの女乗物駕籠が保存されています。


〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 御首題

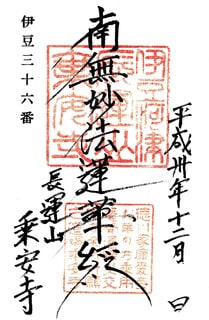
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御首題帳
詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
■ 金剛山 真乗寺(しんじょうじ)
公式Web
河津町見高540
臨済宗建長寺派
御本尊:大日如来
札所本尊:
札所:-
授与所:庫裡
・臨済宗建長寺派の寺院で、札所ではないですが山内の樹齢41年の河津桜が知られています。
・豪快な筆致の大日如来の御朱印を拝受できます。


■ 玉田山 地福院(じふくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町縄地430
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第37番
授与所:第38番禅福寺(下田市白浜)庫裡
・平安時代の創立ともいわれ、かつては玉田山金生院という真言宗寺院でしたが、慶長五年(1600年)に曹洞宗に改め再興。
・縄地金山が栄えた際に、近隣に創立された9つの寺院のうちの一ヶ寺で、金山衰退後に他の8つの寺院は移転ないし廃寺となりましたが、地福院だけはこの地に残ったとの由。


〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
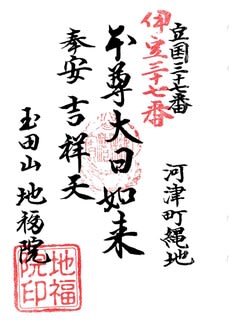

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
■ 宝林山 称念寺(しょうねんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町浜334-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場別格旧第31番
授与所:庫裡
・伊豆八十八ヶ所霊場に設定されている別格札所。
・称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。


・歴史の香り高い寺院なので、すこしく長めにご紹介します。
河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。
藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。
「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。
非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。
「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。
■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
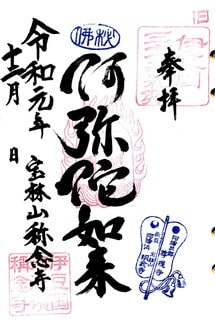

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ
おとなりの稲取も伊豆有数の御朱印スポットです。
1/20~3/31の雛のつるし飾りまつり期間中は、普段いただけない素盞嗚神社の御朱印も拝受できます。
【 BGM 】
■ サクラ色 - アンジェラ・アキ
もう歌わない?。日本は貴重なシンガーソングライターを失ったのか・・・?
感情過多にならず、たおやかに聴き手のこころをゆさぶる歌声。
■ 春風 - Rihwa(リファ)
■ 桜 - 中村舞子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県所沢市の札所と御朱印
2023/02/12 追加UP
所沢市内の御朱印はほぼ拝受した気がするので、画像を交えてUPします。
まずはリストと御朱印画像をUPし、寺社の写真は追って追加します。
【エリア概要】
所沢市は埼玉県南西部の主要都市で、古くから鎌倉街道上道筋に位置した交通の要衝。
中世には新田氏と北条氏、足利氏の戦場となり、戦国時代は関東管領扇谷上杉氏、ついで後北条氏の支配下にあり、これらの武将ゆかりの寺院も多い。
江戸時代も交通の要衝の地の利を生かして物資の集積地として発展し、巡拝霊場の札所もかなりの数がおかれている。
川越のように観光寺院が多い訳ではないが、複数の現役の観音霊場があるため御朱印がいただきやすいエリアとなっている。
宗派は真言宗豊山派と曹洞宗が多い。
令和二年正月、あらたに所沢七福神が開創され、書置ながら通年御朱印対応されているので、さらに拝受可能な御朱印数が増えている。
-----------------------
所沢市域はかなり広く、札所も全域に広がっているので、車がないとアクセスがやっかいなエリアといえる。
ただし、所沢は西武鉄道の牙城で、メインとなっている武蔵野三十三観音霊場、狭山三十三観音霊場ともに西武鉄道がバックアップし、巡拝コースも設定されているので、このふたつの霊場については鉄道・バス利用でも比較的回りやすくなっている。
市東部は都心から車で川越に向かうルート上に位置するので、川越の御朱印巡りとの合わせワザも可能。
【所沢市と札所】
県内では秩父三十四ヶ所観音霊場と並んでメジャーな武蔵野三十三観音霊場の札所は7を数え、現役霊場として機能している狭山三十三観音霊場の札所も12を数える。
とくに狭山三十三観音霊場は発願、結願の両寺ともに所沢市内に位置し、発願寺の金乗院放光寺は県内有数の名刹として知られている。
弘法大師霊場では、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所が複数ある。専用納経帳を持参すれば御朱印を授与いただける札所が多い。
活動を停止している武玉八十八ヶ所霊場の札所が数箇寺あるが、いずれも他の現役霊場の札所となっているので現役霊場の御朱印は拝受できる。
狭山三十七薬師霊場の札所も数箇寺あるが、現役霊場ではなく御朱印は不授与の模様。
ただし、こちらも他の現役霊場の札所となっているケースが多く、最近、御朱印通年授与の所沢七福神が設定されたこともあって市内の札所寺院の御朱印授与率は高くなっている。
他に武蔵野七福神の札所が一箇所(金乗院放光寺)あるが、広域の霊場札所は少ないエリアである。
御朱印をいただいた非札所系寺院についても名刹がメインのため、今回はあわせてご紹介します。
【拝受データ】 (おおむね東部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
■ (坂之下)天神社
所沢市坂之下64
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社、旧坂下村鎮守
元別当:梅林山 大學院(現・富士見市南畑)
授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)
御朱印揮毫:天神社 /筆書(直書)

・もともとは当地の治水開発の守護神として水神様が祀られ、その後天神様が合祀されたと伝わる。旧坂下村の鎮守で、現在は「柳瀬総鎮守」ともいわれる。
■ 城山神社
所沢市城537
御祭神:宇迦之魂神
旧社格:村社、旧城村鎮守
元別当:城村龍蔵院、本郷村東福寺、氏照院
授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)
御朱印揮毫:城山神社 /直書(筆書)
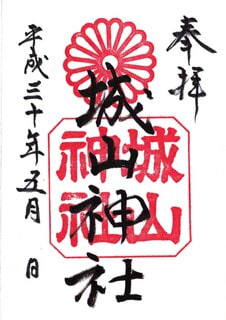
・後北条氏の麾下、大石氏の軍事拠点であった「滝の城」(本郷城)の鎮守社といわれ、城跡に祀られる神社。明治に入り村内各社を合祀し村社に列格した。
■ 医王山 東光寺
公式Web
所沢市坂之下383
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所:-

・滝の城城主・北条氏照により城の東北に鬼門の鎮めとして建てられた寺院。。
・御本尊の薬師如来は「平の時頼公」ゆかりで、北条氏照の守り仏と伝わる。
・山内には金毘羅大王尊が祀られ、毎月十日のご縁日は賑わいをみせる。
■ 大光山 妙乗寺
所沢市南永井688−2
日蓮宗
御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。
■ 武蔵野坐令和神社
公式Web
所沢市東所沢和田3-31-3
御祭神:天照大御神、素戔嗚命
授与所:境内授与所 ※オリジナル御朱印帳あり
御朱印揮毫:武蔵野坐令和神社 /直書(筆書)

・「KADOKAWAによる日本初のコンテンツモール、ところざわサクラタウン」内に祀られ、「所沢から新たな物語を創造・発信する起点となることを目的として」創建。
・正式名称は「武蔵野坐令和神社(むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ)」、通称「武蔵野令和神社(むさしのれいわじんじゃ)」。
・社務所は常駐で、オリジナル御朱印帳も頒布されています。
■ 成田山 観音院 東福寺
所沢市本郷764
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・天平勝寶元年(聖武天皇の御代)に行基菩薩が創建、聖寶尊師(延喜九年(909年)入寂)の開祖と伝わる真言宗の古刹。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番の札所本尊は、羽村の加藤家から羽村市の道路拡張工事にともない平成29年(2017年)5月に東福寺に御遷座、札所も移転し東福寺となる。
(旧札所は羽村山 禅林寺)
・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。
■ 龍王山 霊源寺
所沢市上安松1353
日蓮宗
御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。
・新座市野火止の清立山 番星寺も護持されており、こちらの御首題も授与いただけました。
■ 宝塔山 吉祥寺 多聞院
所沢市中冨1501
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
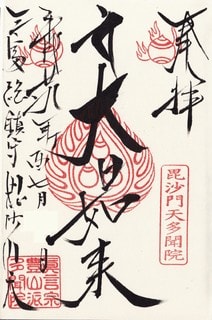

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印

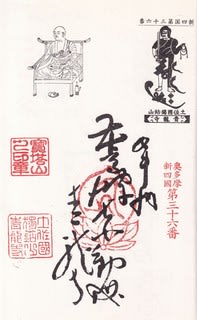
【写真 上(左)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・元禄九年(1696年)、川越藩主柳沢吉保が三富新田として上富・中富・下富村を開村した際、祈願所・鎮守の宮として毘沙門社を創建。明治の神仏分離令によって多門院として独立した。
・毘沙門堂本尊の毘沙門天は、武田信玄公の守り本尊であったと伝わる。
・よく整備された境内。300株にも及ぶ牡丹で有名で紅葉も綺麗。
・御朱印は霊場申告なしだと毘沙門天の御朱印になる模様。奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。
■ (三富・富岡総鎮守)神明社
公式Web
所沢市中富1507
御祭神:天照太御神 ほか
旧社格:村社、三富・富岡総鎮守
元別当:多門院?
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:神明社 /直書(書置)

・元禄九年(1696年)、川越城主柳沢出羽守が上富村、中富村、下富村の三ヶ村を開かれた折、鎮守宮として毘沙門社と多聞院を創立し、宝暦十一年(1761年)境内に神明社を勧請したのが創祀と伝わる。
・三富・富岡総鎮守で「富の神明様」として崇敬篤く、境内には天神宮、いも神様などを祀る。
・境内社務所に書置御朱印を用意されているようなので、どなたかおられれば拝受できる。
■ 北田山 長寿院 寳泉寺
公式Web
所沢市北岩岡130
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第50番


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・公式Webには天和三年(1683年)の開山、所沢市資料には寛延年間(1748-1751年)多摩郡澤井村から移転とあり。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所本尊は、立派な大師堂内に御座されています。
・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。
■ (下新井)熊野神社
所沢市西新井町17-33
御祭神:伊邪那岐命、伊邪那美命、須佐之男命、大己貴命、少毘古那命
旧社格:村社、旧下新井村鎮守
授与所:ご神職宅
御朱印揮毫:熊野神社 /直書(筆書)
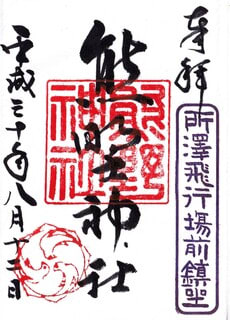
・新井郷(旧上新井・下新井)の惣社として創建、鎌倉時代から続く社家の三上山城守清定が長禄三年(1457年)再興と伝わる。明治期に村内各社を合祀。
■ 東光山 自性院 薬王寺
所沢市有楽町8-18
曹洞宗
御本尊:薬師如来

御本尊の御朱印
・南北朝時代の武将、新田義貞の三男新田武蔵守義宗が観応の擾乱、武蔵野合戦を経て当地に隠棲し、草庵をかまえたことがはじまりとされる。
・義宗は当寺で一族の菩提を弔い、この地で亡くなったと伝わり、境内には義宗の子孫が建てた「新田義宗終焉之地」の碑がある。
・札所ではありませんが、歴史的な伝承をもち、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
■ 乾坤山 長青寺
所沢市弥生町2868
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛

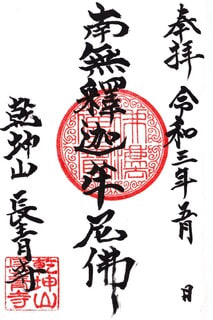
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 御本尊の御朱印
・昭和40年所沢市林の長清山 松林寺の別院として堂宇が建立された比較的新しい曹洞宗寺院。
・札所ではありませんが、快く御朱印を授与いただけたのでご紹介します。
■ 所澤神明社
公式Web
所沢市宮本町1-2-4
御祭神:天照大御神、倉稲魂大神、大物主大神
旧社格:村社、旧所沢村鎮守
元別当:花向院
授与所:境内社務所 ※オリジナル御朱印帳あり
御朱印揮毫:神明社 /直書(筆書)



オリジナル御朱印帳
・日本武尊の東夷征伐の際、当地で天照大御神に祈られたことが創祀とされる旧所沢村(野老澤)の鎮守社。
・所沢は日本の航空の発祥の地として知られ、明治四十四年(1911年)、日本初の飛行場が造られ、徳川好敏大尉は所沢での初飛行に際して当社に参詣祈願し、無事初飛行を果たしたとされる。
・御朱印に積極的で、航空機をデザインしたオリジナル御朱印帳も頒布されています。
■ 鳥船神社
所沢市宮本町1-2-4
授与所:所澤神明社社務所
御朱印揮毫:鳥船神社 /直書(筆書)

・所澤神明社の境内社。所沢航空場で徳川好敏大尉が初飛行を成し遂げたことを記念し、初飛行から100年後の平成23年に創建、所澤航空神社とも称する。
・御朱印のデザインは、1月、4月、7月、10月に替わります。
■ 遊石山 観音院 新光寺
所沢市宮本町1-7-3
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:武蔵野三十三観音霊場第10番、狭山三十三観音霊場第8番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第24番


【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(専用納経帳規定用紙)

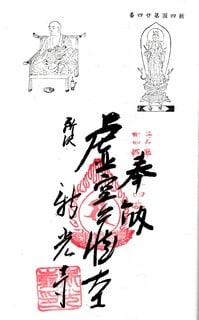
【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・御本尊の聖観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わることから、天平年間(729-749年)開基の説がある。
・建久四年(1193年)源頼朝が那須野へ鷹狩に赴く途中、当地で昼食をとった折に幕舎の地を当寺に寄進したといわれる。
・元弘三年(1333年)新田義貞が鎌倉攻めの途上、必勝を祈願し、北条氏を平げての帰途に再び立ち寄り土地を寄進したと伝わる。
・3つの霊場の札所を兼務され、御朱印はすべて授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)
■ 野老山 実蔵院
所沢市元町20-15
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:武蔵野三十三観音霊場第9番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第68番


【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)
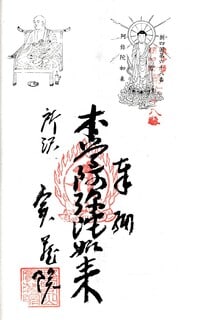
奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・宥圓(元和二年(1616年)七月二十四日示寂)の開山と伝わる真言宗豊山派の寺院で、もとは正福寺と号し、宝暦年間(1751-1764年)に慧海阿闍梨により中興開山。
・以前所蔵していた半鐘には「新田義興開基」の銘があったという。
・ふたつの霊場の御朱印は、いずれも授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)
■ 愛宕権現社
所沢市緑町3-13-1
御祭神:愛宕大権現
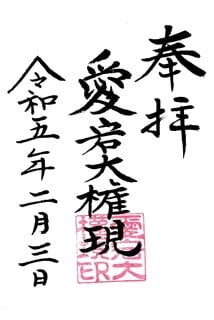
・山口の中氷川神社の奉仕社で、区画整理により上新井字中丁道から御遷座。
・正月、節分、祭典日等の限定授与。→授与情報
■ 三ツ井戸大師
所沢市Web資料
所沢市西所沢1-26
御本尊:弘法大師、十一面観世音菩薩
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・所沢の市街地にある奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所。
・「所沢の火事は土で消す」といわれたほど水利の悪かったこの地に、ある日ひとりの僧が訪れ三つの場所を杖で指し示し、井戸を掘るようにと言い残された。村人達がその場所を掘ると、清らかな水がこんこんと湧き出し涸れることがなく、しかも諸病を除き寿命無量の益があったという。村人達はこの有り難い井戸を「三ツ井戸」と呼び、いつしかかの僧は弘法大師であったという話が広まった。
・「三ツ井戸」の地にはかつて普門院が建ち、寛文年間(1661-1663年)に普門院が移転してからもお大師様ゆかりの地として崇められ、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所として参拝者を集めている。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は普門院にて授与いただけますが、専用納経帳が必要かもしれません。
■ 六所神社
所沢市上新井2-6-8
御祭神:小野大神、小河大神、氷川大神、秩父大神、金佐奈大神、杉山大神
元別当:上洗山 普門院(上新井/真言宗豊山派)

・府中大国魂神社(旧称:六所宮)を勧請して創建。
・明治43年、字荒神脇の稲荷社と字前の稲荷社を合祀。
・原則として毎月1日・15日の午前8時〜11時ごろに限定授与。
■ 上洗山 無量寺 普門院
所沢市まちづくり観光協会Web資料
所沢市上新井189
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:武蔵野三十三観音霊場第11番、狭山三十三観音霊場第7番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第72番
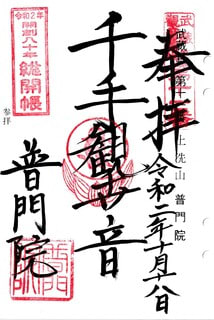

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)


【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・もとは「三ツ井戸」付近にあり、お大師さまゆかりの「三ツ井戸」に寿命無量の益があったことから無量寺と号したとされる。
・天平年間(1573-1592年)に重誉が中興、寛文年間(1661-1663年)に現在地に移転。
・木造毘沙門天は市指定文化財。
・車でのアプローチは狭い路地経由ですが、駐車場はそれなりに広いです。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番(三ツ井戸大師)の御朱印もこちらで授与されています。
・ご丁寧な対応をいただけますが、御本尊の御朱印は授与されていないとのこと。
■ 祥雲山 瑞岩寺
所沢市まちづくり観光協会Web資料
所沢市山口400
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第6番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・山口城の城主、山口氏の菩提寺として室町時代初期ごろに創建と伝わる曹洞宗の寺院。
・山口氏は平安時代の末期に武蔵七党のひとつ村山党から分かれたとされる当地の名族。
■ 大龍山 永源寺
所沢市久米1342
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:所沢七福神(弁財天)、狭山三十七薬師霊場第25番

所沢七福神(弁財天)の御朱印
・南北朝時代に大石信重が創建したと伝わる古刹。大石氏は木曾義仲の末裔を名乗り、関東管領山内上杉氏に仕え多摩・入間両郡の内十三郷の領主となり、武蔵・伊豆両国の守護代を歴任したとされる。
・開山は八王子の由木城主大石定久の叔父で由木永林寺を開山した一種長純大和尚(永禄八年(1565年)寂)と伝わる。
・所沢七福神(弁財天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。
■ 花向山 常行院 長久寺
公式Web
所沢市久米411
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:所沢七福神(大黒天)、狭山三十七薬師霊場第27番

所沢七福神(大黒天)の御朱印
・所沢で唯一の時宗寺院で、元弘元年(1331年)玖阿弥陀佛(二祖真教上人の徒弟)による開山。
・御本尊の金銅造阿弥陀三尊立像は秘仏で所沢市指定有形文化財。
・豊川稲荷は愛知県の豊川稲荷よりの分社で熊野大権現とともに寺の鎮守として大切にお祀りされている。
・所沢七福神(大黒天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。
■ 淵上山 持明院
所沢市立所沢図書館Web資料
所沢市北秋津85
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:所沢七福神(恵比寿尊)
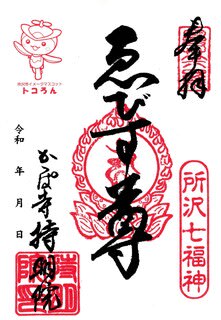
所沢七福神(恵比寿尊)の御朱印
・元慶二年(878年)権大僧都寂寛によって創建と伝わる古刹。
以前は秋津村の中央に位置し松根寺と号していたとされ、享保六年(1721年)当地に移転し改号したとされています。
・曼荼羅堂(阿弥陀堂)の本尊阿弥陀如来は弘法大師のお作といわれていたが明治17年の火災で焼失。
・柳瀬川の曼荼羅淵で悪さをしていた河童が書いたとされる「河童のわび証文」ゆかりの寺院としても知られている。
・竹林に囲まれた風情あるお寺さんです。所沢七福神(恵比寿天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。
■ 王禅山 釋迦院 佛眼寺
所沢市Web資料
所沢市久米2445
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:所沢七福神(福禄寿)、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第53番、狭山三十七薬師霊場第26番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
※所沢七福神(福禄寿)の御朱印も授与されています。
・延暦二十一年(802年)の建立とも伝えられ、当村出身の圓宥が元亀年間(1570-1573年)に中興したとされる真言宗豊山派の寺院で、3つの霊場の札所。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は、専用納経帳が必要かもしれません。
■ 鳩峯八幡神社
所沢市久米2428
御祭神:誉田別命、比売神、気長足姫尊
旧社格:郷社、久米地域の総鎮守
元別当:王禅山仏眼寺(所沢市久米)
御朱印揮毫:鳩峯八幡神社 /直書(筆書)

・延喜二十一年(921年)、石清水八幡宮より分祀して創建。
・元弘三年(1333年)、新田義貞の鎌倉攻めの際、当社で社前の松に兜を掛け、境内に鎧を置いて戦勝祈願し、戦勝ののち兜を掛けた松を「兜掛の松」と呼び、鎧を置いたところに稲荷社を祀って「鎧稲荷」と称したと伝わる。
・本殿は一間社流造見世棚形式の木造建築で、県内に残る稀少な室町時代以前の建造物で、埼玉県指定有形文化財に指定。
・御朱印は境内脇のご神職宅にて授与されています。
■ 久米水天宮
所沢市Web情報
所沢市久米鳩峯2432
御祭神:安徳天皇
御朱印揮毫:久米水天宮 /直書(筆書)

・久留米水天宮の分祀で鳩峯八幡神社の境内社だが、八幡神社の社殿からは若干離れている。
・安産や水難除けの神様として崇敬を集め、1月5日のだるま市は賑わいを見せる。
・御朱印は鳩峯八幡神社のご神職宅にて授与されています。
■ 荒幡山 無量院 光蔵寺
所沢市荒幡499
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:所沢七福神(寿老人)


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 所沢七福神(寿老人)の御朱印
・創建年代は不詳、もとは奥富にあり寛和年間(985ー987年)記銘の古碑があったと伝わる。寛永年間(1624-1645年)に法印賢宥が中興開山。
・御本尊阿弥陀如来像は、弘法大師の御作と伝わる。
・庫裡にて御本尊の御朱印を授与いただけましたが、ご多忙の折はむずかしいかもしれません。七福神(寿老人)の御朱印は本堂前で書置授与されています。
■ 月桂山 本覚院 喜福寺
所沢市荒幡653
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:所沢七福神(布袋尊)、狭山三十七薬師霊場第24番

所沢七福神(布袋尊)の御朱印
・庚暦二年(1380年)、阿闍梨法印法円により創建、弘治元年(1555年)大僧都法印恵静によって中興と伝わる古刹。
・明るく開けた感じの境内に立派な伽藍。七福神(布袋尊)は書置授与ですが、御本尊の御朱印は授与されておりません。
■ 荒幡浅間神社
所沢市まちづくり観光協会Web情報
所沢市荒幡748
御祭神:木花咲耶姫命、大山咋命 ほか
旧社格:村社、旧荒幡村総鎮守
元別当:月桂山 本覚院(所沢市荒幡)
授与所:中氷川神社社務所(所沢市山口1850)
御朱印印判:浅間神社 印判
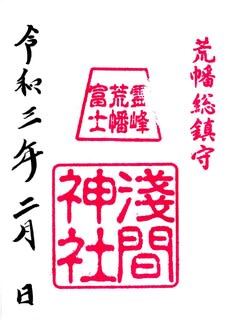
・創立年代は不詳。明治5年(1872年)、荒幡村内の神社を合祀し村社に列し、明治17年(1884年)には字浅間久保からの遷座を機に村民総出で富士山(荒幡富士)を築き上げ明治32年(1899年)に完成。
・高さ約10mと富士塚としてはかなりの規模で、頂上からは360°の眺望が開ける。
・御朱印は本務社の中氷川神社(所沢市山口1850)にて授与されています。
■ 辰爾山 勝楽寺 佛蔵院
所沢市山口1119
真言宗豊山派
御本尊:釈迦如来
札所:狭山三十三観音霊場第2番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第73番、武玉八十八ヶ所霊場第35番、狭山三十七薬師霊場第21番


【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・百済より帰化した儒生王仁の五代孫、王辰爾の子が父の菩提の為に旧勝楽寺村に創建、権大僧都尊海が延久三年(1071年)に中興とされ、往時は寺中十二坊を数えたという古刹。
・山口貯水池の造成(昭和9年(1934年)完成)にともない、旧勝楽寺の地より当地へ移転。(「勝楽寺」の地名はいまも狭山湖南岸に残る。)
・古刹の歴史を物語るように、じつに4つの霊場札所を兼務され、うち2つの霊場の御朱印を授与されています。
■ 瑞幡山 勝光寺
所沢市山口1410
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦如来
札所:狭山三十三観音霊場第5番、狭山三十七薬師霊場第19番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・弘安四年(1281年)、建長寺第一世石門和尚が開山、北条時宗を開基として創建されたという名刹。
・元禄七年から九年(1694-1696年)にかけて建立された唐様桜門造の山門は、野火止の平林寺、上富の多福寺の山門とならび称されるもの。
・本堂に御座す若狭法眼賀竹作の不動明王像も名作として評価されている。
・御朱印は、狭山三十三観音霊場のものを授与いただけます。
■ 川嶋山 釋迦院 海藏寺
所沢市山口2725
真言宗豊山派
御本尊:釈迦如来
札所:所沢七福神(毘沙門天)


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 所沢七福神(毘沙門天)の御朱印
・創建年代等は不詳で従前霊場札所でもなかったため情報が少ない寺院ですが、『新編武蔵風土記稿』には記載されています。
・御朱印は御本尊釈迦如来と所沢七福神(毘沙門天)のものを拝受できましたが(いずれも書置)、御本尊御朱印が常時拝受できるかは不明です。
■ 中氷川神社
公式Web
所沢市山口1850
御祭神:素戔嗚命、稲田姫命、大己貴命、七社大神
旧社格:延喜式式内社(小)論社、県社
元別当:普賢寺(旧打越村)
御朱印揮毫:中氷川神社 /直書(筆書)

・崇神天皇の朝に創始せられ、延喜式式内社の中氷川社に比定される歴史ある神社。
・大宮の武蔵國一之宮氷川神社と奥多摩氷川の奥氷川神社の中間に鎮座するため、中氷川神社と号されたという説がある。
・武蔵國造、山口城主の崇敬篤く、入間・多摩二郡内九十二ヶ村の総鎮守として尊崇されたという。
・終戦直後の昭和20年(1945年)11月、GHQ民間情報教育局初代局長のケン・R・ダイク准将が当社の例大祭を視察しました。このタイミングはGHQが日本政府に対して発した「神道指令」(同年12月15日発出)の直前で、村人総出で和気藹々と催されるこの祭礼の様子は、GHQがそれまで抱いていた全体主義的な神道感を改めさせ、後の神社政策に大きな影響を与えたとされています。
・境内社務所にて境内社、兼務社を含め4社の御朱印を授与され、御朱印界?では有名。
■ 金刀比羅神社
公式Web
所沢市山口1850
御祭神:
御朱印印判:金刀比羅神社 /印判

・中氷川神社の境内社で、御朱印は社務所にて授与されています。
■ (堀口)天満天神社
公式Web
所沢市上山口字長久保436
御祭神:菅原道真朝臣、天穂日命、花園姫
元別当:星見山 清照寺(所沢市上山口)
御朱印印判:天満天神社 /印判

・天正年間(1573-1593年)、徳川家家臣久松氏の崇敬あり耕地を奉納された旧堀口村の鎮守。
・明治元年(1872年)、元別当の清照寺境内に鎮座の八坂神社、稲荷神社を合祀し現・堀口総鎮守。旧堀口村字天神山に鎮座していたが、昭和9年狭山湖の造成に伴い現社地に御遷座。
・社叢に囲まれ神さびた境内。境内社の稲荷神社は「火消し稲荷」と称され火防の信仰を受けている。
・御朱印は本務社の中氷川神社社務所にて授与されています。
■ 星見山 無量壽院 清照寺
所沢市上山口439
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第42番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・村山党の末裔といわれる里見小太郎が星見堂と号して室町期に創建。僧賢譽(明暦二年(1656年)入寂)の代に、当地の領主、旗本久松忠次が東谷にあった安楽寺を引寺して清照寺と改号、以後久松氏の菩提寺になったとされる。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 証智庵(正智庵)
所沢市上山口13
臨済宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第4番
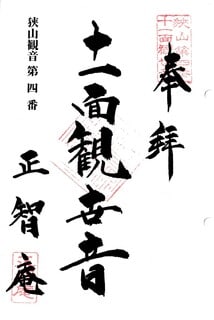
狭山三十三観音霊場の御朱印
・僧白瑛(宝暦七年(1757年)入寂)の創建と伝わる、十一面観世音菩薩を祀る庵。
・御朱印は、第5番勝光寺にて拝受できます。
■ 六斎堂
所沢市上山口1642
真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第3番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・創立年代は不詳。往時は六観音が祀られ、六斎(毎月八・十四・十五・二十三・二十九・三十日は「斎戒謹慎」し、善心を起こすべき日とする民衆教化の宗教行事)の守り本像として六観音が祀られていたと推測されている。
・昭和17年(1942年)金乗院の所属となり、御朱印も金乗院にて授与されています。
■ 菩提山 仏國寺 密厳院
所沢市山口2045
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第23番、武玉八十八ヶ所霊場第40番、狭山三十七薬師霊場第23番
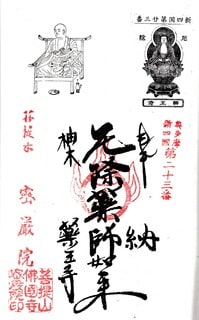
奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・弘法大師が東国修行の折りに当地で三尊阿弥陀如来を刻まれ、そのしるしに現在の翁樹神社に菩提樹の木を植えられた事により、当地を菩提樹村と呼び当寺を菩提山 密厳院 佛國寺と号したという伝承がある。
・また、圓清(元和八年(1622年)入寂)による開山とも伝わる。
・奥多摩新四国霊場の札所は開創当時青梅市柚木地区にあったが廃寺となり密厳院に移管。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 狭山山 不動寺(狭山不動尊)
公式Web
所沢市上山口2214
天台宗
御本尊:不動明王
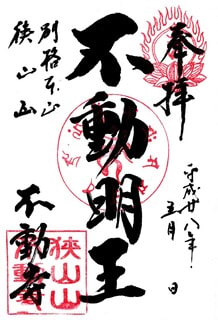
御本尊の御朱印
・昭和50年(1975年)、 当時の西武グループのオーナー堤義明氏が寛永寺の助力を受けて天台宗別格本山として建立した寺院で、西武ライオンズが必勝祈願を行う寺として知られる。
・芝増上寺をはじめとする各地の文化財を移築し、「文化財の寺」としても知られている。
・御朱印の授与は10:00~15:00(年末年始を除く)、駐車場利用可能時間は10:00~14:45なので要注意です。
■ 吾庵山 金乗院 放光寺
所沢市上山口2203
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第52番、第65番、第67番、第77番、第79番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番

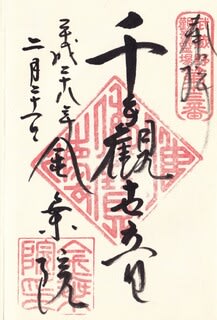
【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

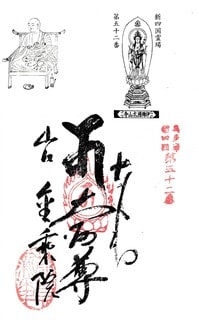
〔 狭山三十三観音霊場の御朱印 〕
〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕


〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕
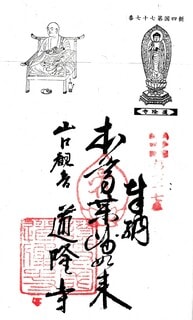

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕
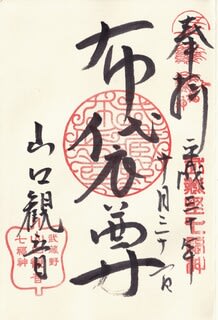
〔 武蔵野七福神(布袋尊)の御朱印 〕
・所沢市内屈指の名刹で山口観音とも称される。
・寺伝によれば弘仁年間(810-824年)、行基菩薩の東国巡錫の際、光り輝く木に千手観世音菩薩を感得され、そのお姿を霊木に刻まれて安置し開創。
・弘法大師が湯殿山に向かわれる途中、当地に立ち寄られ白髪の老婆から行基作の観音様について告げられ堂宇を建立されて開基。弘法大師は観音像供養のため閼伽水を求められたところ神龍が応じて浄水を湧かせ、これが加持水として今も湧き出ている。
・また、新田義貞の鎌倉攻めの際に当寺に祈願し、後にみずからの乗馬を寄進したとも伝わる。
・御本尊千手観音は「木造千手観音立像」として市の指定文化財に指定され33年に一度の御開帳。脇仏として不動明王と毘沙門天が祀られている。
・多くの霊場札所を兼ねられているため、御朱印拝受にあたっては霊場の申告が必要と思われます。
■ 物部天神社・国渭地祗神社・天満天神社(北野天神社)
公式Web
所沢市小手指元町3-28-44
御祭神:櫛玉饒速日命、八千矛命(大国主命)、菅原道真公
旧社格:県社、延喜式式内社
御朱印揮毫:物部天神社国渭地祗神社天満天神社 /直書(筆書)
御朱印揮毫:北野天神社 /直書(筆書)

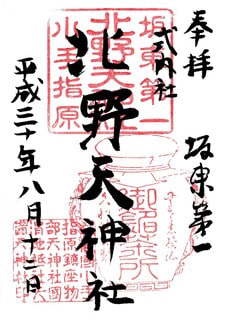

令和改元奉祝御朱印
・正式な社名は物部天神社・國渭地祇神社・天満天神社で、総称として北野天神社が使われる。
・社伝によると物部天神社・國渭地祇神社は、景行天皇の御代に日本武尊が天神の櫛玉饒速日命と地祇の八千矛神をお祀りした延喜式内社。
・天満天神社は、長徳元年(995年)に菅公五世の孫、武蔵国司菅原修成が勅命を奉じて京都の北野天満宮より御分霊を関東地方以東で最初に勧請したため、「坂東第一北野天満宮」と定められたとされる。
・源頼義・義家公が奥州追討の宿願成就のため境内に総社を建立。建久六年(1195年)源頼朝公が正八幡宮を勧請、社殿を全て修造し、新たに延喜式内の諸神を祀った諸神堂を建立。
・延文元年(1356年)には足利尊氏も境内諸社を再建したとされ、以降も前田利家、徳川家康、大久保石見守などの尊崇篤く、度々社殿が造営されている。
・御朱印は境内授与所にて2種類を拝受。限定御朱印も適宜授与されている模様です。
■ 梅林山 北野院 全徳寺
所沢市北野2-13-5
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:武蔵野三十三観音霊場第12番、狭山三十七薬師霊場第20番
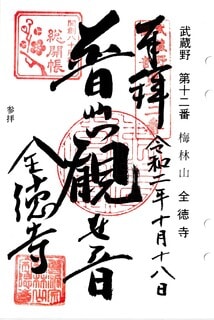

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)
・西多摩郡平井の寶光寺二世願山明鑑大和尚(永禄十一年(1568年)入寂)が地区内の数寺を統合して開山・創建したという曹洞宗寺院。
・ロウバイの寺として有名で、武蔵野三十三観音霊場の札所でもあります。
・御本尊の御朱印は授与されていない模様。
■ 糀谷八幡神社
公式Web
所沢市糀谷78
御祭神:誉田別尊
旧社格:村社、旧糀谷村鎮守、神饌幣帛料供進神社
御朱印揮毫:糀谷八幡宮 /直書(筆書)


【写真 上(左)】 御朱印
【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳
・江戸時代初期に鶴岡八幡宮を勧請して創建。明治41年(1908年)に字富士塚の山神社)、大字三ヶ島字新水の愛宕神社、同境内社金刀比羅神社を合祀したと伝わる。
・御朱印に力を入れられており、多彩な限定御朱印が授与され、御朱印帳も頒布されています。
■ 愛宕神社
公式Web
所沢市糀谷78
御朱印印判:愛宕(愛太子)大権現のお姿の印判

・糀谷八幡神社に合祀された愛宕神社で、白鳳十三年(673年)役行者の勧請と伝わり本山派修験玉蔵坊(後に竜蔵院)にお祀りされていた愛宕様とみられる。
・御朱印は、糀谷八幡神社社務所にて授与されています。
■ 聴松軒(長昌軒)
所沢市堀ノ内
真言宗
御本尊:馬頭観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第31番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・金仙寺の住僧覚秀が宝永年間(1704-1710年)に創建したとされる馬頭観世音菩薩を安置するお堂。
・御本尊の馬頭観世音菩薩は弘法大師の御作といわれ、金仙寺の本寺である青梅の金剛寺から移られたと伝わる。
・御朱印は近くの「別所人形店」で拝受できます。
■ 別所山 西光院 金仙寺
所沢市堀之内343
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第66番、武玉八十八ヶ所霊場第34番


【写真 上(左)】御本尊の御朱印
【写真 下(右)】奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・平安時代に傳燈阿闇梨覚堂という僧が、弘法大師御作の阿弥陀如来を本尊として、現在地の西方「堂入り」に開山と伝わる。
・その後、鎌倉北条氏からの寄進を得て、天正十八年(1590年)堯戒律師により現在地に移転・再建される。
・所沢市指定の「しだれ桜」は樹齢百二十年余の名木といわれる。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 慈眼庵
所沢市三ヶ島5-821
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第32番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・狭山三十三観音霊場の第32番札所で開創等詳細は不明。
・御朱印は第33番の妙善院で拝受できます。
■ 稲荷山 寳玉院
所沢市三ヶ島3-1167
真言宗豊山派
御本尊:
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第47番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・寛永年間(1624-1645年)に権大僧都長賢法印が創建したと伝わる寺院。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 光輪山 三ヶ島寺(原の寺) 妙善院
所沢市三ヶ島3-1410
曹洞宗
御本尊:白衣観世音菩薩
札所:武蔵野三十三観音霊場第14番、狭山三十三観音霊場第33番、狭山三十七薬師霊場第18番


【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印
・天正年間(1573-1592年)、後北条氏の家臣澤(佐和)次郎右衛門吉縄(光輪院殿)が、東久留米市大門の浄牧院11世呑碩和尚を開山に迎えて開創したという曹洞宗寺院。
・天明八年(1788年)、金乗院の住職亮盛和尚と妙善院の住職卍杲禅師は狭山三十三観音霊場を開創、当寺は結願寺となっている。
・御本尊の白衣観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わる。
■ 吟龍山 松林寺
所沢市林2-147
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:武蔵野三十三観音霊場第15番、狭山三十三観音霊場第30番、狭山三十七薬師霊場第15番


【写真 上(左)】武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印
・承応二年(1653年)、吟國寒龍大和尚により開山・創建という曹洞宗寺院で、ふたつの現役霊場の札所を兼務される。
・御本尊の御朱印は不授与の模様。
----------------------------------------------
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県富士見市・ふじみの市・三芳町の御朱印
■ 御朱印情報の関連記事
所沢市内の御朱印はほぼ拝受した気がするので、画像を交えてUPします。
まずはリストと御朱印画像をUPし、寺社の写真は追って追加します。
【エリア概要】
所沢市は埼玉県南西部の主要都市で、古くから鎌倉街道上道筋に位置した交通の要衝。
中世には新田氏と北条氏、足利氏の戦場となり、戦国時代は関東管領扇谷上杉氏、ついで後北条氏の支配下にあり、これらの武将ゆかりの寺院も多い。
江戸時代も交通の要衝の地の利を生かして物資の集積地として発展し、巡拝霊場の札所もかなりの数がおかれている。
川越のように観光寺院が多い訳ではないが、複数の現役の観音霊場があるため御朱印がいただきやすいエリアとなっている。
宗派は真言宗豊山派と曹洞宗が多い。
令和二年正月、あらたに所沢七福神が開創され、書置ながら通年御朱印対応されているので、さらに拝受可能な御朱印数が増えている。
-----------------------
所沢市域はかなり広く、札所も全域に広がっているので、車がないとアクセスがやっかいなエリアといえる。
ただし、所沢は西武鉄道の牙城で、メインとなっている武蔵野三十三観音霊場、狭山三十三観音霊場ともに西武鉄道がバックアップし、巡拝コースも設定されているので、このふたつの霊場については鉄道・バス利用でも比較的回りやすくなっている。
市東部は都心から車で川越に向かうルート上に位置するので、川越の御朱印巡りとの合わせワザも可能。
【所沢市と札所】
県内では秩父三十四ヶ所観音霊場と並んでメジャーな武蔵野三十三観音霊場の札所は7を数え、現役霊場として機能している狭山三十三観音霊場の札所も12を数える。
とくに狭山三十三観音霊場は発願、結願の両寺ともに所沢市内に位置し、発願寺の金乗院放光寺は県内有数の名刹として知られている。
弘法大師霊場では、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所が複数ある。専用納経帳を持参すれば御朱印を授与いただける札所が多い。
活動を停止している武玉八十八ヶ所霊場の札所が数箇寺あるが、いずれも他の現役霊場の札所となっているので現役霊場の御朱印は拝受できる。
狭山三十七薬師霊場の札所も数箇寺あるが、現役霊場ではなく御朱印は不授与の模様。
ただし、こちらも他の現役霊場の札所となっているケースが多く、最近、御朱印通年授与の所沢七福神が設定されたこともあって市内の札所寺院の御朱印授与率は高くなっている。
他に武蔵野七福神の札所が一箇所(金乗院放光寺)あるが、広域の霊場札所は少ないエリアである。
御朱印をいただいた非札所系寺院についても名刹がメインのため、今回はあわせてご紹介します。
【拝受データ】 (おおむね東部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
■ (坂之下)天神社
所沢市坂之下64
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社、旧坂下村鎮守
元別当:梅林山 大學院(現・富士見市南畑)
授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)
御朱印揮毫:天神社 /筆書(直書)

・もともとは当地の治水開発の守護神として水神様が祀られ、その後天神様が合祀されたと伝わる。旧坂下村の鎮守で、現在は「柳瀬総鎮守」ともいわれる。
■ 城山神社
所沢市城537
御祭神:宇迦之魂神
旧社格:村社、旧城村鎮守
元別当:城村龍蔵院、本郷村東福寺、氏照院
授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)
御朱印揮毫:城山神社 /直書(筆書)
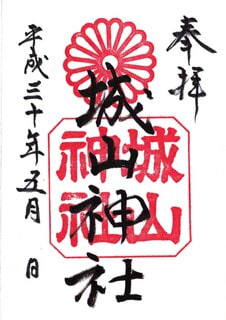
・後北条氏の麾下、大石氏の軍事拠点であった「滝の城」(本郷城)の鎮守社といわれ、城跡に祀られる神社。明治に入り村内各社を合祀し村社に列格した。
■ 医王山 東光寺
公式Web
所沢市坂之下383
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所:-

・滝の城城主・北条氏照により城の東北に鬼門の鎮めとして建てられた寺院。。
・御本尊の薬師如来は「平の時頼公」ゆかりで、北条氏照の守り仏と伝わる。
・山内には金毘羅大王尊が祀られ、毎月十日のご縁日は賑わいをみせる。
■ 大光山 妙乗寺
所沢市南永井688−2
日蓮宗
御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。
■ 武蔵野坐令和神社
公式Web
所沢市東所沢和田3-31-3
御祭神:天照大御神、素戔嗚命
授与所:境内授与所 ※オリジナル御朱印帳あり
御朱印揮毫:武蔵野坐令和神社 /直書(筆書)

・「KADOKAWAによる日本初のコンテンツモール、ところざわサクラタウン」内に祀られ、「所沢から新たな物語を創造・発信する起点となることを目的として」創建。
・正式名称は「武蔵野坐令和神社(むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ)」、通称「武蔵野令和神社(むさしのれいわじんじゃ)」。
・社務所は常駐で、オリジナル御朱印帳も頒布されています。
■ 成田山 観音院 東福寺
所沢市本郷764
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・天平勝寶元年(聖武天皇の御代)に行基菩薩が創建、聖寶尊師(延喜九年(909年)入寂)の開祖と伝わる真言宗の古刹。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番の札所本尊は、羽村の加藤家から羽村市の道路拡張工事にともない平成29年(2017年)5月に東福寺に御遷座、札所も移転し東福寺となる。
(旧札所は羽村山 禅林寺)
・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。
■ 龍王山 霊源寺
所沢市上安松1353
日蓮宗
御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。
・新座市野火止の清立山 番星寺も護持されており、こちらの御首題も授与いただけました。
■ 宝塔山 吉祥寺 多聞院
所沢市中冨1501
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
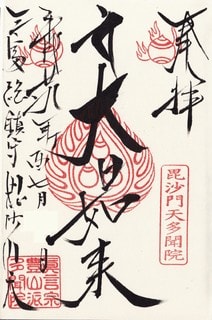

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印

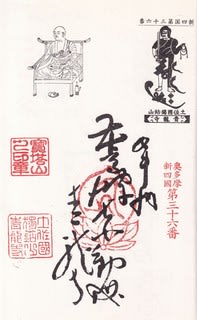
【写真 上(左)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・元禄九年(1696年)、川越藩主柳沢吉保が三富新田として上富・中富・下富村を開村した際、祈願所・鎮守の宮として毘沙門社を創建。明治の神仏分離令によって多門院として独立した。
・毘沙門堂本尊の毘沙門天は、武田信玄公の守り本尊であったと伝わる。
・よく整備された境内。300株にも及ぶ牡丹で有名で紅葉も綺麗。
・御朱印は霊場申告なしだと毘沙門天の御朱印になる模様。奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。
■ (三富・富岡総鎮守)神明社
公式Web
所沢市中富1507
御祭神:天照太御神 ほか
旧社格:村社、三富・富岡総鎮守
元別当:多門院?
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:神明社 /直書(書置)

・元禄九年(1696年)、川越城主柳沢出羽守が上富村、中富村、下富村の三ヶ村を開かれた折、鎮守宮として毘沙門社と多聞院を創立し、宝暦十一年(1761年)境内に神明社を勧請したのが創祀と伝わる。
・三富・富岡総鎮守で「富の神明様」として崇敬篤く、境内には天神宮、いも神様などを祀る。
・境内社務所に書置御朱印を用意されているようなので、どなたかおられれば拝受できる。
■ 北田山 長寿院 寳泉寺
公式Web
所沢市北岩岡130
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第50番


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・公式Webには天和三年(1683年)の開山、所沢市資料には寛延年間(1748-1751年)多摩郡澤井村から移転とあり。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所本尊は、立派な大師堂内に御座されています。
・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。
■ (下新井)熊野神社
所沢市西新井町17-33
御祭神:伊邪那岐命、伊邪那美命、須佐之男命、大己貴命、少毘古那命
旧社格:村社、旧下新井村鎮守
授与所:ご神職宅
御朱印揮毫:熊野神社 /直書(筆書)
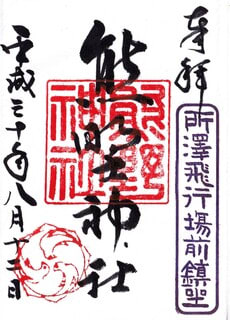
・新井郷(旧上新井・下新井)の惣社として創建、鎌倉時代から続く社家の三上山城守清定が長禄三年(1457年)再興と伝わる。明治期に村内各社を合祀。
■ 東光山 自性院 薬王寺
所沢市有楽町8-18
曹洞宗
御本尊:薬師如来

御本尊の御朱印
・南北朝時代の武将、新田義貞の三男新田武蔵守義宗が観応の擾乱、武蔵野合戦を経て当地に隠棲し、草庵をかまえたことがはじまりとされる。
・義宗は当寺で一族の菩提を弔い、この地で亡くなったと伝わり、境内には義宗の子孫が建てた「新田義宗終焉之地」の碑がある。
・札所ではありませんが、歴史的な伝承をもち、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
■ 乾坤山 長青寺
所沢市弥生町2868
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛

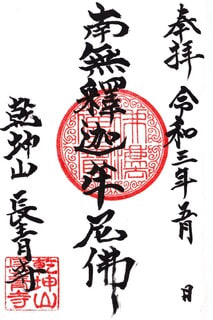
【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 御本尊の御朱印
・昭和40年所沢市林の長清山 松林寺の別院として堂宇が建立された比較的新しい曹洞宗寺院。
・札所ではありませんが、快く御朱印を授与いただけたのでご紹介します。
■ 所澤神明社
公式Web
所沢市宮本町1-2-4
御祭神:天照大御神、倉稲魂大神、大物主大神
旧社格:村社、旧所沢村鎮守
元別当:花向院
授与所:境内社務所 ※オリジナル御朱印帳あり
御朱印揮毫:神明社 /直書(筆書)



オリジナル御朱印帳
・日本武尊の東夷征伐の際、当地で天照大御神に祈られたことが創祀とされる旧所沢村(野老澤)の鎮守社。
・所沢は日本の航空の発祥の地として知られ、明治四十四年(1911年)、日本初の飛行場が造られ、徳川好敏大尉は所沢での初飛行に際して当社に参詣祈願し、無事初飛行を果たしたとされる。
・御朱印に積極的で、航空機をデザインしたオリジナル御朱印帳も頒布されています。
■ 鳥船神社
所沢市宮本町1-2-4
授与所:所澤神明社社務所
御朱印揮毫:鳥船神社 /直書(筆書)

・所澤神明社の境内社。所沢航空場で徳川好敏大尉が初飛行を成し遂げたことを記念し、初飛行から100年後の平成23年に創建、所澤航空神社とも称する。
・御朱印のデザインは、1月、4月、7月、10月に替わります。
■ 遊石山 観音院 新光寺
所沢市宮本町1-7-3
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:武蔵野三十三観音霊場第10番、狭山三十三観音霊場第8番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第24番


【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(専用納経帳規定用紙)

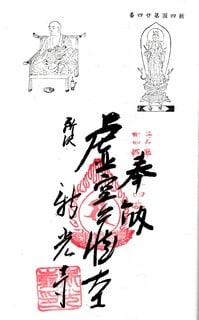
【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・御本尊の聖観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わることから、天平年間(729-749年)開基の説がある。
・建久四年(1193年)源頼朝が那須野へ鷹狩に赴く途中、当地で昼食をとった折に幕舎の地を当寺に寄進したといわれる。
・元弘三年(1333年)新田義貞が鎌倉攻めの途上、必勝を祈願し、北条氏を平げての帰途に再び立ち寄り土地を寄進したと伝わる。
・3つの霊場の札所を兼務され、御朱印はすべて授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)
■ 野老山 実蔵院
所沢市元町20-15
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:武蔵野三十三観音霊場第9番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第68番


【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)
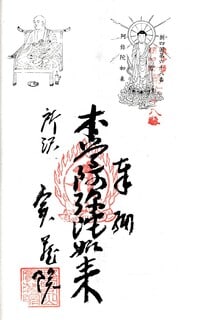
奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・宥圓(元和二年(1616年)七月二十四日示寂)の開山と伝わる真言宗豊山派の寺院で、もとは正福寺と号し、宝暦年間(1751-1764年)に慧海阿闍梨により中興開山。
・以前所蔵していた半鐘には「新田義興開基」の銘があったという。
・ふたつの霊場の御朱印は、いずれも授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)
■ 愛宕権現社
所沢市緑町3-13-1
御祭神:愛宕大権現
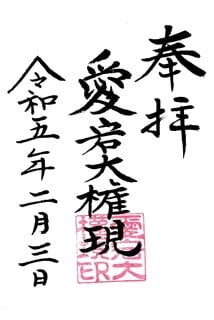
・山口の中氷川神社の奉仕社で、区画整理により上新井字中丁道から御遷座。
・正月、節分、祭典日等の限定授与。→授与情報
■ 三ツ井戸大師
所沢市Web資料
所沢市西所沢1-26
御本尊:弘法大師、十一面観世音菩薩
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・所沢の市街地にある奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所。
・「所沢の火事は土で消す」といわれたほど水利の悪かったこの地に、ある日ひとりの僧が訪れ三つの場所を杖で指し示し、井戸を掘るようにと言い残された。村人達がその場所を掘ると、清らかな水がこんこんと湧き出し涸れることがなく、しかも諸病を除き寿命無量の益があったという。村人達はこの有り難い井戸を「三ツ井戸」と呼び、いつしかかの僧は弘法大師であったという話が広まった。
・「三ツ井戸」の地にはかつて普門院が建ち、寛文年間(1661-1663年)に普門院が移転してからもお大師様ゆかりの地として崇められ、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所として参拝者を集めている。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は普門院にて授与いただけますが、専用納経帳が必要かもしれません。
■ 六所神社
所沢市上新井2-6-8
御祭神:小野大神、小河大神、氷川大神、秩父大神、金佐奈大神、杉山大神
元別当:上洗山 普門院(上新井/真言宗豊山派)

・府中大国魂神社(旧称:六所宮)を勧請して創建。
・明治43年、字荒神脇の稲荷社と字前の稲荷社を合祀。
・原則として毎月1日・15日の午前8時〜11時ごろに限定授与。
■ 上洗山 無量寺 普門院
所沢市まちづくり観光協会Web資料
所沢市上新井189
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:武蔵野三十三観音霊場第11番、狭山三十三観音霊場第7番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第72番
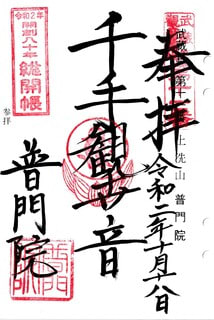

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)


【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・もとは「三ツ井戸」付近にあり、お大師さまゆかりの「三ツ井戸」に寿命無量の益があったことから無量寺と号したとされる。
・天平年間(1573-1592年)に重誉が中興、寛文年間(1661-1663年)に現在地に移転。
・木造毘沙門天は市指定文化財。
・車でのアプローチは狭い路地経由ですが、駐車場はそれなりに広いです。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番(三ツ井戸大師)の御朱印もこちらで授与されています。
・ご丁寧な対応をいただけますが、御本尊の御朱印は授与されていないとのこと。
■ 祥雲山 瑞岩寺
所沢市まちづくり観光協会Web資料
所沢市山口400
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第6番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・山口城の城主、山口氏の菩提寺として室町時代初期ごろに創建と伝わる曹洞宗の寺院。
・山口氏は平安時代の末期に武蔵七党のひとつ村山党から分かれたとされる当地の名族。
■ 大龍山 永源寺
所沢市久米1342
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:所沢七福神(弁財天)、狭山三十七薬師霊場第25番

所沢七福神(弁財天)の御朱印
・南北朝時代に大石信重が創建したと伝わる古刹。大石氏は木曾義仲の末裔を名乗り、関東管領山内上杉氏に仕え多摩・入間両郡の内十三郷の領主となり、武蔵・伊豆両国の守護代を歴任したとされる。
・開山は八王子の由木城主大石定久の叔父で由木永林寺を開山した一種長純大和尚(永禄八年(1565年)寂)と伝わる。
・所沢七福神(弁財天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。
■ 花向山 常行院 長久寺
公式Web
所沢市久米411
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:所沢七福神(大黒天)、狭山三十七薬師霊場第27番

所沢七福神(大黒天)の御朱印
・所沢で唯一の時宗寺院で、元弘元年(1331年)玖阿弥陀佛(二祖真教上人の徒弟)による開山。
・御本尊の金銅造阿弥陀三尊立像は秘仏で所沢市指定有形文化財。
・豊川稲荷は愛知県の豊川稲荷よりの分社で熊野大権現とともに寺の鎮守として大切にお祀りされている。
・所沢七福神(大黒天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。
■ 淵上山 持明院
所沢市立所沢図書館Web資料
所沢市北秋津85
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:所沢七福神(恵比寿尊)
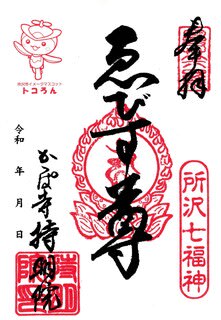
所沢七福神(恵比寿尊)の御朱印
・元慶二年(878年)権大僧都寂寛によって創建と伝わる古刹。
以前は秋津村の中央に位置し松根寺と号していたとされ、享保六年(1721年)当地に移転し改号したとされています。
・曼荼羅堂(阿弥陀堂)の本尊阿弥陀如来は弘法大師のお作といわれていたが明治17年の火災で焼失。
・柳瀬川の曼荼羅淵で悪さをしていた河童が書いたとされる「河童のわび証文」ゆかりの寺院としても知られている。
・竹林に囲まれた風情あるお寺さんです。所沢七福神(恵比寿天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。
■ 王禅山 釋迦院 佛眼寺
所沢市Web資料
所沢市久米2445
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:所沢七福神(福禄寿)、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第53番、狭山三十七薬師霊場第26番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
※所沢七福神(福禄寿)の御朱印も授与されています。
・延暦二十一年(802年)の建立とも伝えられ、当村出身の圓宥が元亀年間(1570-1573年)に中興したとされる真言宗豊山派の寺院で、3つの霊場の札所。
・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は、専用納経帳が必要かもしれません。
■ 鳩峯八幡神社
所沢市久米2428
御祭神:誉田別命、比売神、気長足姫尊
旧社格:郷社、久米地域の総鎮守
元別当:王禅山仏眼寺(所沢市久米)
御朱印揮毫:鳩峯八幡神社 /直書(筆書)

・延喜二十一年(921年)、石清水八幡宮より分祀して創建。
・元弘三年(1333年)、新田義貞の鎌倉攻めの際、当社で社前の松に兜を掛け、境内に鎧を置いて戦勝祈願し、戦勝ののち兜を掛けた松を「兜掛の松」と呼び、鎧を置いたところに稲荷社を祀って「鎧稲荷」と称したと伝わる。
・本殿は一間社流造見世棚形式の木造建築で、県内に残る稀少な室町時代以前の建造物で、埼玉県指定有形文化財に指定。
・御朱印は境内脇のご神職宅にて授与されています。
■ 久米水天宮
所沢市Web情報
所沢市久米鳩峯2432
御祭神:安徳天皇
御朱印揮毫:久米水天宮 /直書(筆書)

・久留米水天宮の分祀で鳩峯八幡神社の境内社だが、八幡神社の社殿からは若干離れている。
・安産や水難除けの神様として崇敬を集め、1月5日のだるま市は賑わいを見せる。
・御朱印は鳩峯八幡神社のご神職宅にて授与されています。
■ 荒幡山 無量院 光蔵寺
所沢市荒幡499
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:所沢七福神(寿老人)


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 所沢七福神(寿老人)の御朱印
・創建年代は不詳、もとは奥富にあり寛和年間(985ー987年)記銘の古碑があったと伝わる。寛永年間(1624-1645年)に法印賢宥が中興開山。
・御本尊阿弥陀如来像は、弘法大師の御作と伝わる。
・庫裡にて御本尊の御朱印を授与いただけましたが、ご多忙の折はむずかしいかもしれません。七福神(寿老人)の御朱印は本堂前で書置授与されています。
■ 月桂山 本覚院 喜福寺
所沢市荒幡653
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:所沢七福神(布袋尊)、狭山三十七薬師霊場第24番

所沢七福神(布袋尊)の御朱印
・庚暦二年(1380年)、阿闍梨法印法円により創建、弘治元年(1555年)大僧都法印恵静によって中興と伝わる古刹。
・明るく開けた感じの境内に立派な伽藍。七福神(布袋尊)は書置授与ですが、御本尊の御朱印は授与されておりません。
■ 荒幡浅間神社
所沢市まちづくり観光協会Web情報
所沢市荒幡748
御祭神:木花咲耶姫命、大山咋命 ほか
旧社格:村社、旧荒幡村総鎮守
元別当:月桂山 本覚院(所沢市荒幡)
授与所:中氷川神社社務所(所沢市山口1850)
御朱印印判:浅間神社 印判
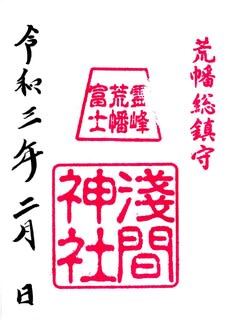
・創立年代は不詳。明治5年(1872年)、荒幡村内の神社を合祀し村社に列し、明治17年(1884年)には字浅間久保からの遷座を機に村民総出で富士山(荒幡富士)を築き上げ明治32年(1899年)に完成。
・高さ約10mと富士塚としてはかなりの規模で、頂上からは360°の眺望が開ける。
・御朱印は本務社の中氷川神社(所沢市山口1850)にて授与されています。
■ 辰爾山 勝楽寺 佛蔵院
所沢市山口1119
真言宗豊山派
御本尊:釈迦如来
札所:狭山三十三観音霊場第2番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第73番、武玉八十八ヶ所霊場第35番、狭山三十七薬師霊場第21番


【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・百済より帰化した儒生王仁の五代孫、王辰爾の子が父の菩提の為に旧勝楽寺村に創建、権大僧都尊海が延久三年(1071年)に中興とされ、往時は寺中十二坊を数えたという古刹。
・山口貯水池の造成(昭和9年(1934年)完成)にともない、旧勝楽寺の地より当地へ移転。(「勝楽寺」の地名はいまも狭山湖南岸に残る。)
・古刹の歴史を物語るように、じつに4つの霊場札所を兼務され、うち2つの霊場の御朱印を授与されています。
■ 瑞幡山 勝光寺
所沢市山口1410
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦如来
札所:狭山三十三観音霊場第5番、狭山三十七薬師霊場第19番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・弘安四年(1281年)、建長寺第一世石門和尚が開山、北条時宗を開基として創建されたという名刹。
・元禄七年から九年(1694-1696年)にかけて建立された唐様桜門造の山門は、野火止の平林寺、上富の多福寺の山門とならび称されるもの。
・本堂に御座す若狭法眼賀竹作の不動明王像も名作として評価されている。
・御朱印は、狭山三十三観音霊場のものを授与いただけます。
■ 川嶋山 釋迦院 海藏寺
所沢市山口2725
真言宗豊山派
御本尊:釈迦如来
札所:所沢七福神(毘沙門天)


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 所沢七福神(毘沙門天)の御朱印
・創建年代等は不詳で従前霊場札所でもなかったため情報が少ない寺院ですが、『新編武蔵風土記稿』には記載されています。
・御朱印は御本尊釈迦如来と所沢七福神(毘沙門天)のものを拝受できましたが(いずれも書置)、御本尊御朱印が常時拝受できるかは不明です。
■ 中氷川神社
公式Web
所沢市山口1850
御祭神:素戔嗚命、稲田姫命、大己貴命、七社大神
旧社格:延喜式式内社(小)論社、県社
元別当:普賢寺(旧打越村)
御朱印揮毫:中氷川神社 /直書(筆書)

・崇神天皇の朝に創始せられ、延喜式式内社の中氷川社に比定される歴史ある神社。
・大宮の武蔵國一之宮氷川神社と奥多摩氷川の奥氷川神社の中間に鎮座するため、中氷川神社と号されたという説がある。
・武蔵國造、山口城主の崇敬篤く、入間・多摩二郡内九十二ヶ村の総鎮守として尊崇されたという。
・終戦直後の昭和20年(1945年)11月、GHQ民間情報教育局初代局長のケン・R・ダイク准将が当社の例大祭を視察しました。このタイミングはGHQが日本政府に対して発した「神道指令」(同年12月15日発出)の直前で、村人総出で和気藹々と催されるこの祭礼の様子は、GHQがそれまで抱いていた全体主義的な神道感を改めさせ、後の神社政策に大きな影響を与えたとされています。
・境内社務所にて境内社、兼務社を含め4社の御朱印を授与され、御朱印界?では有名。
■ 金刀比羅神社
公式Web
所沢市山口1850
御祭神:
御朱印印判:金刀比羅神社 /印判

・中氷川神社の境内社で、御朱印は社務所にて授与されています。
■ (堀口)天満天神社
公式Web
所沢市上山口字長久保436
御祭神:菅原道真朝臣、天穂日命、花園姫
元別当:星見山 清照寺(所沢市上山口)
御朱印印判:天満天神社 /印判

・天正年間(1573-1593年)、徳川家家臣久松氏の崇敬あり耕地を奉納された旧堀口村の鎮守。
・明治元年(1872年)、元別当の清照寺境内に鎮座の八坂神社、稲荷神社を合祀し現・堀口総鎮守。旧堀口村字天神山に鎮座していたが、昭和9年狭山湖の造成に伴い現社地に御遷座。
・社叢に囲まれ神さびた境内。境内社の稲荷神社は「火消し稲荷」と称され火防の信仰を受けている。
・御朱印は本務社の中氷川神社社務所にて授与されています。
■ 星見山 無量壽院 清照寺
所沢市上山口439
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第42番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・村山党の末裔といわれる里見小太郎が星見堂と号して室町期に創建。僧賢譽(明暦二年(1656年)入寂)の代に、当地の領主、旗本久松忠次が東谷にあった安楽寺を引寺して清照寺と改号、以後久松氏の菩提寺になったとされる。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 証智庵(正智庵)
所沢市上山口13
臨済宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第4番
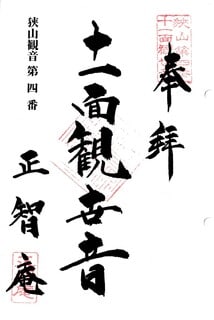
狭山三十三観音霊場の御朱印
・僧白瑛(宝暦七年(1757年)入寂)の創建と伝わる、十一面観世音菩薩を祀る庵。
・御朱印は、第5番勝光寺にて拝受できます。
■ 六斎堂
所沢市上山口1642
真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第3番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・創立年代は不詳。往時は六観音が祀られ、六斎(毎月八・十四・十五・二十三・二十九・三十日は「斎戒謹慎」し、善心を起こすべき日とする民衆教化の宗教行事)の守り本像として六観音が祀られていたと推測されている。
・昭和17年(1942年)金乗院の所属となり、御朱印も金乗院にて授与されています。
■ 菩提山 仏國寺 密厳院
所沢市山口2045
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第23番、武玉八十八ヶ所霊場第40番、狭山三十七薬師霊場第23番
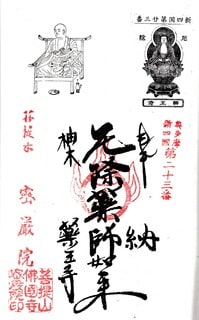
奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・弘法大師が東国修行の折りに当地で三尊阿弥陀如来を刻まれ、そのしるしに現在の翁樹神社に菩提樹の木を植えられた事により、当地を菩提樹村と呼び当寺を菩提山 密厳院 佛國寺と号したという伝承がある。
・また、圓清(元和八年(1622年)入寂)による開山とも伝わる。
・奥多摩新四国霊場の札所は開創当時青梅市柚木地区にあったが廃寺となり密厳院に移管。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 狭山山 不動寺(狭山不動尊)
公式Web
所沢市上山口2214
天台宗
御本尊:不動明王
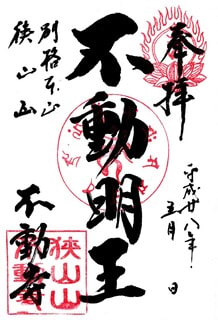
御本尊の御朱印
・昭和50年(1975年)、 当時の西武グループのオーナー堤義明氏が寛永寺の助力を受けて天台宗別格本山として建立した寺院で、西武ライオンズが必勝祈願を行う寺として知られる。
・芝増上寺をはじめとする各地の文化財を移築し、「文化財の寺」としても知られている。
・御朱印の授与は10:00~15:00(年末年始を除く)、駐車場利用可能時間は10:00~14:45なので要注意です。
■ 吾庵山 金乗院 放光寺
所沢市上山口2203
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第52番、第65番、第67番、第77番、第79番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番

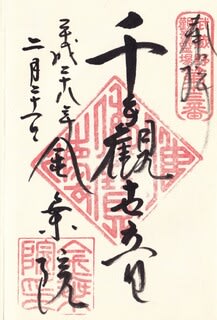
【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

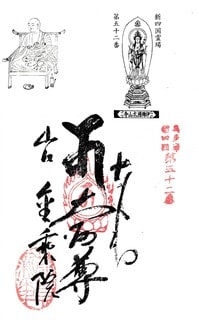
〔 狭山三十三観音霊場の御朱印 〕
〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕


〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕
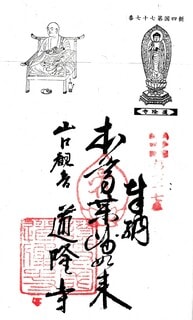

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕
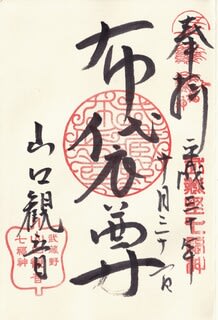
〔 武蔵野七福神(布袋尊)の御朱印 〕
・所沢市内屈指の名刹で山口観音とも称される。
・寺伝によれば弘仁年間(810-824年)、行基菩薩の東国巡錫の際、光り輝く木に千手観世音菩薩を感得され、そのお姿を霊木に刻まれて安置し開創。
・弘法大師が湯殿山に向かわれる途中、当地に立ち寄られ白髪の老婆から行基作の観音様について告げられ堂宇を建立されて開基。弘法大師は観音像供養のため閼伽水を求められたところ神龍が応じて浄水を湧かせ、これが加持水として今も湧き出ている。
・また、新田義貞の鎌倉攻めの際に当寺に祈願し、後にみずからの乗馬を寄進したとも伝わる。
・御本尊千手観音は「木造千手観音立像」として市の指定文化財に指定され33年に一度の御開帳。脇仏として不動明王と毘沙門天が祀られている。
・多くの霊場札所を兼ねられているため、御朱印拝受にあたっては霊場の申告が必要と思われます。
■ 物部天神社・国渭地祗神社・天満天神社(北野天神社)
公式Web
所沢市小手指元町3-28-44
御祭神:櫛玉饒速日命、八千矛命(大国主命)、菅原道真公
旧社格:県社、延喜式式内社
御朱印揮毫:物部天神社国渭地祗神社天満天神社 /直書(筆書)
御朱印揮毫:北野天神社 /直書(筆書)

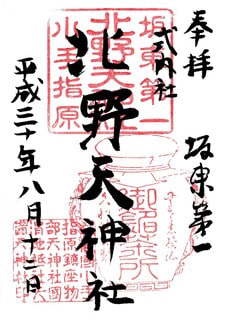

令和改元奉祝御朱印
・正式な社名は物部天神社・國渭地祇神社・天満天神社で、総称として北野天神社が使われる。
・社伝によると物部天神社・國渭地祇神社は、景行天皇の御代に日本武尊が天神の櫛玉饒速日命と地祇の八千矛神をお祀りした延喜式内社。
・天満天神社は、長徳元年(995年)に菅公五世の孫、武蔵国司菅原修成が勅命を奉じて京都の北野天満宮より御分霊を関東地方以東で最初に勧請したため、「坂東第一北野天満宮」と定められたとされる。
・源頼義・義家公が奥州追討の宿願成就のため境内に総社を建立。建久六年(1195年)源頼朝公が正八幡宮を勧請、社殿を全て修造し、新たに延喜式内の諸神を祀った諸神堂を建立。
・延文元年(1356年)には足利尊氏も境内諸社を再建したとされ、以降も前田利家、徳川家康、大久保石見守などの尊崇篤く、度々社殿が造営されている。
・御朱印は境内授与所にて2種類を拝受。限定御朱印も適宜授与されている模様です。
■ 梅林山 北野院 全徳寺
所沢市北野2-13-5
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:武蔵野三十三観音霊場第12番、狭山三十七薬師霊場第20番
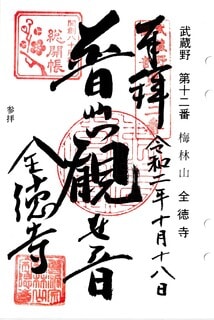

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)
・西多摩郡平井の寶光寺二世願山明鑑大和尚(永禄十一年(1568年)入寂)が地区内の数寺を統合して開山・創建したという曹洞宗寺院。
・ロウバイの寺として有名で、武蔵野三十三観音霊場の札所でもあります。
・御本尊の御朱印は授与されていない模様。
■ 糀谷八幡神社
公式Web
所沢市糀谷78
御祭神:誉田別尊
旧社格:村社、旧糀谷村鎮守、神饌幣帛料供進神社
御朱印揮毫:糀谷八幡宮 /直書(筆書)


【写真 上(左)】 御朱印
【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳
・江戸時代初期に鶴岡八幡宮を勧請して創建。明治41年(1908年)に字富士塚の山神社)、大字三ヶ島字新水の愛宕神社、同境内社金刀比羅神社を合祀したと伝わる。
・御朱印に力を入れられており、多彩な限定御朱印が授与され、御朱印帳も頒布されています。
■ 愛宕神社
公式Web
所沢市糀谷78
御朱印印判:愛宕(愛太子)大権現のお姿の印判

・糀谷八幡神社に合祀された愛宕神社で、白鳳十三年(673年)役行者の勧請と伝わり本山派修験玉蔵坊(後に竜蔵院)にお祀りされていた愛宕様とみられる。
・御朱印は、糀谷八幡神社社務所にて授与されています。
■ 聴松軒(長昌軒)
所沢市堀ノ内
真言宗
御本尊:馬頭観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第31番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・金仙寺の住僧覚秀が宝永年間(1704-1710年)に創建したとされる馬頭観世音菩薩を安置するお堂。
・御本尊の馬頭観世音菩薩は弘法大師の御作といわれ、金仙寺の本寺である青梅の金剛寺から移られたと伝わる。
・御朱印は近くの「別所人形店」で拝受できます。
■ 別所山 西光院 金仙寺
所沢市堀之内343
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第66番、武玉八十八ヶ所霊場第34番


【写真 上(左)】御本尊の御朱印
【写真 下(右)】奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・平安時代に傳燈阿闇梨覚堂という僧が、弘法大師御作の阿弥陀如来を本尊として、現在地の西方「堂入り」に開山と伝わる。
・その後、鎌倉北条氏からの寄進を得て、天正十八年(1590年)堯戒律師により現在地に移転・再建される。
・所沢市指定の「しだれ桜」は樹齢百二十年余の名木といわれる。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 慈眼庵
所沢市三ヶ島5-821
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:狭山三十三観音霊場第32番

狭山三十三観音霊場の御朱印
・狭山三十三観音霊場の第32番札所で開創等詳細は不明。
・御朱印は第33番の妙善院で拝受できます。
■ 稲荷山 寳玉院
所沢市三ヶ島3-1167
真言宗豊山派
御本尊:
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第47番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印
・寛永年間(1624-1645年)に権大僧都長賢法印が創建したと伝わる寺院。
・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。
■ 光輪山 三ヶ島寺(原の寺) 妙善院
所沢市三ヶ島3-1410
曹洞宗
御本尊:白衣観世音菩薩
札所:武蔵野三十三観音霊場第14番、狭山三十三観音霊場第33番、狭山三十七薬師霊場第18番


【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印
・天正年間(1573-1592年)、後北条氏の家臣澤(佐和)次郎右衛門吉縄(光輪院殿)が、東久留米市大門の浄牧院11世呑碩和尚を開山に迎えて開創したという曹洞宗寺院。
・天明八年(1788年)、金乗院の住職亮盛和尚と妙善院の住職卍杲禅師は狭山三十三観音霊場を開創、当寺は結願寺となっている。
・御本尊の白衣観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わる。
■ 吟龍山 松林寺
所沢市林2-147
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:武蔵野三十三観音霊場第15番、狭山三十三観音霊場第30番、狭山三十七薬師霊場第15番


【写真 上(左)】武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印
・承応二年(1653年)、吟國寒龍大和尚により開山・創建という曹洞宗寺院で、ふたつの現役霊場の札所を兼務される。
・御本尊の御朱印は不授与の模様。
----------------------------------------------
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県富士見市・ふじみの市・三芳町の御朱印
■ 御朱印情報の関連記事
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPします。
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)から。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
4.旧 妻沼町エリア
■ 瑠璃光山 浄光院 福生寺
熊谷市日向1154(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第34番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番
・こちらも御由緒詳細がとれませんが、山内石碑には「四九四年前に開創せられし名刹」とあり、『新編武蔵風土記稿』の日向村の項には「邑楽郡赤岩村光恩寺末 開山専祐寛永十八年(1641年)寂 本尊大日ヲ安セリ 薬師堂」とあります。
・重厚な山門、本堂、観音堂を擁して山内はよく整っています。
・こちらは忍秩父三十四観音霊場第34番の結願所で、札所本尊は馬頭観世音菩薩。御本尊の大日如来は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所本尊でもあり、こちらの御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第34番 馬頭観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番 大日如来

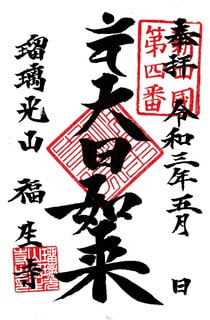
■ 寶積山 白道院 大龍寺
公式Web
熊谷市葛和田898(旧・大里郡妻沼町)
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第15番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第21番
・名刹のようですが、現地、Webともに詳しい情報がとれませんでした。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に記載がありますので抜粋引用します。「館林町善導寺末 開山ハ幡随意上人元和元年正月示寂 開基ハ成田氏ノ臣嶋田采女正ナリ コノ子孫今村民六兵衛ナリト云 本尊阿弥陀ヲ安セリ 荒神社 愛宕社 不動堂 観音堂」。
・幡随意(ばんずいい)上人は、 慶長二十年(1615年)寂と伝わる浄土宗の名僧で、鎌倉光明寺で教学を修められ、後に京都百万遍知恩寺の三十三世住持。徳川家康公の信任厚く、駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創、熊谷の名刹、熊谷寺(ゆうこくじ)の中興など全国で寺院を創立・再興されました。
・当寺所蔵の「幡随意上人の書」、本堂に御座す「三十三体観音像」(元禄期、寄木造金泥)は市の文化財に指定されています。
・名刹らしい風趣のある山内。御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。御本尊および幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第15番 三十三体観世音菩薩


■ 浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺
公式Web
熊谷市西城93-1(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来・薬師如来?
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番
司元別当:西城神社(西城村、旧西城村(本郷)鎮守)
・こちらは詳細な公式Webをお持ちなので、そちらから引用させていただきます。
・南北朝の永和二年(1376年)、慶弘という僧が伝・行基作の薬師如来像を祀り開創。赤岩光恩寺の末寺で、歴代の住職が隠居されていました。
・薬師如来像は12年に一度、寅年の御開帳で信仰を集めているようです。
・本堂と薬師堂、薬師堂厨子は、2020年9月に市の有形文化財に指定されています。
・ともに、上州花輪村の名工・石原吟八郎のグループと、「歓喜天聖天堂」の棟梁の林兵庫正清を中心に建立。江戸期のこの地の彫物師集団の技巧を示す作品として評価されています。
・本堂には阿弥陀如来、薬師堂には薬師如来が御座します。
公式Webに「本堂の阿弥陀如像は、宝永年間(1704-1711年)に祀られた。平成26年遷座300年目に修復。本尊とご縁を結び、人生を輝いて全うできるように御手綱を握ってお参りができる」とあるので、当寺のいまの御本尊は阿弥陀如来とみられますが、宝永年間までの御本尊は薬師如来とみられ、現在でも御本尊のポジションなのかもしれません。
・仏教寺院、とくに密寺の御本尊のポジションは複雑で、観音堂、薬師堂、不動堂などで草創し、のちに本堂が建てられた場合などは、複数の御本尊がおられる場合もあるようです。(例えば、本堂御本尊は大日如来、薬師堂御本尊は薬師如来で、寺院としての御本尊は両尊併記となる。)
・弘法大師霊場の札所本尊は草創時の御本尊が札所本尊になられる場合も多く、こちらもその例ではないでしょうか。
・御朱印はご住職がご不在で書置もなかったので、ご親切な寺庭様にお願いして郵送をいただきました。なお、こちらは忍秩父三十四観音霊場第10番光明山 観音寺(上中条)の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番 薬師如来




■ 福聚山 慈眼寺
熊谷市田島238(旧・大里郡妻沼町)
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第14番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番
司元別当:(田島村)稲荷社(旧田島村鎮守)
・こちらも無住の寺院で情報が少ないです。
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
・『新編武蔵風土記稿』の田島村の項に「弥藤五村観清寺末(略)古ハ観音ノ堂ナリシガ寛永年中(1624--1645年)●月堂開山シテ一寺トナセリ コノ人ハ慶安四年(1651年)寂セリト云 本尊十一面観音ヲ安ス」とあり、もとは観音堂として草創、寛永年中(1624--1645年)に寺院になったようです。
・入り組んだ路地のなか、集落に囲まれるようにあります。寄棟造桟瓦葺で右手に庫裡らしき建物を連接しています。
・向拝柱はなく中央サッシュ扉、上部に「慈眼寺」の寺号扁額を掲げています。
・参拝時ご不在でしたので郵送をお願いしお送りいただきました。郵送なので欲張らず忍観音霊場の御朱印のみお願いしましたが、御朱印には幡羅郡新四国霊場の札番揮毫もいただいておりました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第14番 十一面観世音菩薩
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番 十一面観世音菩薩
※1通に2札所併記。


■ 福源山 長昌寺
熊谷市八ツ口869(旧・大里郡妻沼町)
臨済宗円覚寺派
御本尊:
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第88番
・山内由来書によると、長井庄司斎藤別当実盛公が堀之内に館を構えたとき、この地にあった薬師堂を鬼門除けの祈願所に定めたといいます。
・山内の椎の巨木は、鬼門除けの祈願所に選んだ証に植えた3本のうち、唯一残った1本と言われているそうです。(熊谷市Web)
・同由来書によると、慶安年中に寺領二十石余の朱印を賜る名刹とのこと。
・忍城主成田氏の臣、山田伊半が武川の合戦で討死し、息子の弥治郎が追福のため開基となり建立。その折には成田氏より寄進等があったといいます。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の第88番(結願所)の重要なポジションは、斎藤別当実盛公や忍城主成田氏とのゆかりに由来するものかもしれません。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第17番 釈迦如来

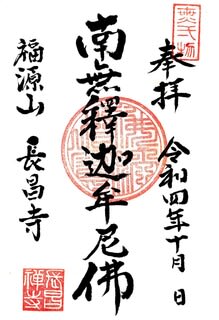
〔村の鎮守十社めぐり〕
当初は「以下10社について御朱印を拝受していますが、長井神社と大杉神社以外は常時授与かどうか不明なのでとりあえずリストのみです。」としましたが、令和2年秋に案内パンフが作成され、実際に御朱印も拝受していますので、ご参考までにUPします。
なお、現時点では御朱印は原則不授与かもしれません。詳細は長井神社宮司様にご確認ください。


情報が少ないですが、現地掲示のほか、案内パンフ、『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、『新編武蔵風土記稿』などを参考にまとめてみます。
1.(日向)長井神社 熊谷市日向
2.(俵瀬)伊奈利神社 熊谷市俵瀬
3.神明社・大杉神社 熊谷市葛和田
4.(大野)伊奈利神社 熊谷市大野
5.(弁財)嚴島神社 熊谷市弁財
6.善ヶ島神社 熊谷市善ヶ島
7.(八ツ口)日枝神社 熊谷市八ツ口
8.江波神社 熊谷市江波
9.西城神社 熊谷市西城
10.八幡大神社 熊谷市上須戸
■ (日向)長井神社
熊谷市日向1090(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:品陀別命、息長帯姫命
旧社格:村社、旧日向村鎮守
元別当:三学院(日向村、当山修験)
授与所:境内脇社務所
・江戸時代には八幡社と称された旧日向村の鎮守社。(明治9年現社号に改号)
・天喜五年(1057年)、源頼義公が安陪貞任討伐の折にこの地に滞留されたとき、竜海という池に棲み村人を悩ましていた大蛇の退治を島田大五郎道竿に命じた。頼義公より弓矢と太刀を下賜された道竿は、竜海から利根川まで堀(道竿堀/どうかんぼり)を掘り、池の水を利根川に落としてこの四丈もの大蛇を退治した。頼義公は東北地方平定の吉事として、大蛇を倒したところに当社を、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったといいます。
・暦応元年(1338年)、足利尊氏が再興、戦国時代には忍城主成田長泰が信仰した記録が残ります。
・『新編武蔵風土記稿』の日向村の項に八幡社があり、上記の「竜海伝説」が詳細に記載されています。
・本地堂の御本尊は阿弥陀如来で、これは八幡神の本地が阿弥陀如来とされたことと符合します。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:長井神社 筆書


■ (俵瀬)伊奈利神社
熊谷市俵瀬489(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧俵瀬村鎮守
元別当:寶林山 妙音寺 成就院(俵瀬村/新義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・俵瀬は利根川と福川に挟まれた島状のエリアで、『新編武蔵風土記稿』には俵瀬村の項に稲荷社が記載されているものの「成就院持」としかありません。
・これにはさすがの『埼玉の神社』も困り果てたらしく、成就院の記載を引き「成就院は慶安四年(1651年)の草創と伝えている。当地が一村としての体裁を整え始めるのが寛永(1624-1645年)の末ごろと思われ、当社の創建も、別当成就院と前後して行われたものであろう。」と記されています。
・江戸時代には「稲荷社」と称し、明治初期に「伊奈利社」と改め、明治41年合祀政策により同大字の神明社、厳島神社を合祀し、大正2年には堤防工事に伴い利根川縁にあった当社を厳島神社の旧社地に御遷座と伝わります。
・厳つい石垣の上に入母屋造桟瓦葺でどっしりと鎮座するお社は、ながらく水害と闘ってきた俵瀬の地の鎮守社ならではのお姿に思えます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市俵瀬 伊奈利神社 筆書


■ (葛和田)神明社・大杉神社
熊谷市葛和田591(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:天照皇大神、大杉大神
※大杉神社は(葛和田)神明社の境内社
旧社格:旧葛和田村鎮守
元別当:瑠璃光山 東光院 醫王寺(葛和田村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・伊勢の御師が当地に逗留した折に奉齋した社であると伝わります。
・旧社地は現在利根川の川中にあり、数回の移転を経て高台の現社地(氷川神社の社地)に御遷座とのこと。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に神明社があり「氷川ヲ合殿トス 村ノ鎮守ナリ 別当醫王寺」とあります。
・境内社の大杉神社(あんば様)の祭礼は利根川の流れに大御輿・大杉御輿を乗り入れるもので、「葛和田の勇み御輿」「関東一のあばれ御輿」として広く知られています。
・江戸時代の葛和田の地は利根川の河岸場として賑わいました。あるとき、与助という腕のいい船頭が霞ヶ浦の西浦で暴風雨に襲われ窮まったとき、日頃から信仰している大杉明神に祈りをささげると神佑を得て難を逃れました。このご神徳への御礼と今後の船路安全祈念のため、茨城県稲敷の大杉神社から勧請し、御輿を造営したと伝わります。
・当初は利根川に注ぐ道竿堀の南に御鎮座でしたが、大正3年堤防工事に伴い現社地に御遷座・合祀されました。
・御朱印は(日向)長井神社社務所にて拝受しました。
・Web上では神明社の御朱印がみつかりますが、現在は大杉神社の御朱印のみ授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大杉大神 筆書




■ (大野)伊奈利神社
熊谷市大野751(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:豊宇気比咩命
旧社格:旧村社、旧大野村鎮守
元別当:大野山 利劔寺 文殊院(葛和田(大野)村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・〔村の鎮守十社めぐり〕のなかではもっとも利根川に近く、利根川の堤防下に鎮座します。
・江戸期には大野村は葛和田村の一部とされ、『新編武蔵風土記稿』には葛和田村の項に「稲荷社二宇 一ハ文殊院 一ハ正泉寺持」とあり、『埼玉の神社』には文殊院が別当とあるので、こちらが該当とみられます。
・ただし、『埼玉の神社』には「宝暦六年(1756年)の伏見稲荷からの分霊証書に『武州 大野村鎮守』とあることから、当時既に『大野村』という名称が使われており、葛和田村から実質は独立していたことがわかる」とあります。
・上記のとおり、宝暦六年(1756年)には伏見稲荷からの分霊証書を受けて創祀しています。
・地形からしても、なにより水害防除が求められる地とみられ、『埼玉の神社』には「伊奈利社を(利根)川の側に勧請することによって水害から村を守ろうとした開発者の心情が推察される。」とあります。
・小山状の高台に鎮座し、参道右手が旧文殊院跡。その手前に大国主尊、参道階段右手に三峰社、拝殿左手には馬頭観世音菩薩、庚申様、青面金剛が祀られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市大野 伊奈利神社 筆書


■ (弁財)嚴島神社
熊谷市弁財174(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:弁財地区鎮守
元別当:辨財山 醫王院 薬王寺(辨財村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「当地(弁財)は大昔利根川の流れの中にあったが、やがて流路が変わり、自然堤防を形作った所である。」とあり、河川とのかかわりから弁財天が祀られたとする一方、口碑に「当地の草分けであり、屋号を庄屋と呼ぶ大島清和家の先祖が祀った。」とあり、「同家は平家の落人であり、そのゆかりから嚴島神社を祀った。」という説にも触れています。
・『新編武蔵風土記稿』の辨財村の項に辨財天社があり「村名ナリシテ見レハ古社ナルヘケレト傳ヘテ失フ」とあります。
・(日向)長井神社縁起の竜海伝説では、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったとされ、この弁財天を当社とする説と(日向)長井神社境内の宇賀神(弁天様)とする説があるようです。
・『埼玉の神社』では、享保十六年(1731年)の利根川大洪水の折、当地に沼ができて、その後沼の主と呼ばれる大蛇が棲み、それが竜海伝説に重なったと指摘しています。
・こちらも社叢のなかに御鎮座。拝殿は石垣のうえに入母屋造桟瓦葺で、主屋根の軒に瓦屋根の向拝を重ねるようにせり出し変化のある意匠。
・弁財天や厳島社はもともと蛇とのゆかりがありますが、向拝の屋根飾りにも蛇の姿がみられます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:嚴島比賣 筆書


■ 善ヶ島神社
熊谷市善ヶ島197(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧善ヶ島村鎮守
元別当:光明山 福壽院 龍泉寺(善ヶ島村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』『パンフ』には、当地は当初葦が生えた島で葦ヶ島と呼ばれたが、後に利根川の流れが変わり、近村と地続きになり善ヶ島と改めた。また、1500年頃の蔵王権現社の勧請が当社の起源とされ、当初は蔵王権現社、明治初期に御嶽神社と称し、明治42年に善ヶ島神社に改称といいます。
・明治41年には大字裏久保の愛宕神社と、上元割の阿夫利神社を合祀。地元では合祀社の阿夫利神社に因み「阿夫利様」と呼ばれることが多いそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の善ヶ島村の項に蔵王権現社があり「永正(1504-1521年)年中の勧請ト云 龍泉寺持 末社 天神 疱瘡神 摩陀羅神」とあります。
・金剛蔵王権現は修験系の尊格で、ことにの吉野の金峯山寺本堂(蔵王堂)の御本尊として知られています。
・当社の現在の主祭神は不明ですが、金剛蔵王権現は大己貴命、少彦名命、国常立尊、日本武尊、金山毘古命との習合例が多く、明治の神仏分離時、金剛蔵王権現を祀る堂祠は上記の神々を祭神とする神社となった例がみられます。
・末社に摩陀羅神の名がみられます。すこぶる複雑な性格をもたれる尊格として知られ、東日本で祀られる例は多くありません。
・別当龍泉寺は古義真言宗で赤岩光恩寺の末。赤岩光恩寺の寺伝には「推古天皇11年(603年)には秦河勝を勅使として仏舎利三粒が納められた」とあります。(秦河勝と摩陀羅神は強い関係があるとされる。)
・当社に摩陀羅神が祀られていた背景には、このような所縁が関連しているのかもしれません。
・現在も、複雑な由緒を想起させる境内社が複数ご鎮座されます。
・社叢のなか、入母屋造桟瓦葺向拝付設の社殿と境内社が御鎮座。
・鳥居、灯籠ともに大きく嵩が上げられ、拝殿も数段高く、水害防除が大切な地であることを物語っています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:善島神社 筆書


■ (八ツ口)日枝神社
熊谷市八ツ口922(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧村社、旧八ツ口村鎮守
元別当:●源山 長昌寺(八ツ口村/禅宗臨済派)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「(別当の)長昌寺は、天文元年(1532年)に成田氏に従い武川の合戦で討死した山田弥次郎の菩提追福のために、その父山田伊平が、弥次郎の領地であったこの地に草創した寺院である。当社の成立背景には、長昌寺の僧とのかかわりが考えられるが、明らかにできない。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の八ツ口村の項に山王社があり「村ノ鎮守ニテ稲荷ヲ合殿トス 長昌寺持」とあります。
・元別当の長昌寺は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第88番の結願寺で、相応の寺格をお持ちかと思いますが、現在のところ御朱印は拝受しておりません。
・社頭に朱塗りの2つの鳥居。向かって左手が日枝神社、右手が八坂神社と伊奈利社です。
八坂神社の夏祭りの御輿渡御は、以前は「暴れ御輿」として広く知られていたようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市八ツ口 日枝神社 筆書

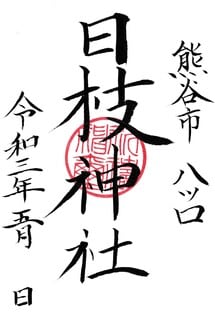
■ 江波神社
熊谷市江波315(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:菅原道真公
旧社格:旧村社、旧江波村鎮守
元別当:福原山 寶蔵院(江波村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「明治四十一年の改正まで天神社であったことから、氏子にはいまだに天神様と呼ばれている。(中略)明治四十一年、字西嬉愛の宇知多神社(妙見社)と字道上の稲荷神社の無格社二社を合祀した。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の江波村の項に天神社があり「村ノ鎮守トス 寶蔵院持」とあります。
・一面の麦畑のなかに浮かぶように、切妻造瓦葺妻入りの社殿が御鎮座。向拝も切妻の屋根がかかり、めずらしい様式の社殿です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:江波神社 筆書


■ 西城神社
熊谷市西城2(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧村社、旧西城村(本郷)鎮守
元別当:浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺(西城村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「西城の地名は、かつてこの地に左近衛少将藤原義孝の居舘があったことにちなむものといわれ、古来、西城の村は郭(くるわ)と呼ばれる幾つかの小さい集落に分かれ、神社の祭祀もまた郭ごとに鎮守として各々神社を祀っていた。明治維新の際、社格を定めるに当たり、(大天貘社は)村内の諸社の中で最も規模が大きく、村の中で最も早く開かれた本郷の鎮守であったことから、当社が西城村の村社になった。恐らく、明治9年に村社となった時に村名を採って西城神社と社名を改めたものであろう。明治42年には、字東田鎮座の稲荷神社と字鴉森鎮座の厳島神社を合祀し現在に至っている。」とあります。
・また同書には「境内にある勝根神社は、古くから当社の末社として祀られており、その祭神は大物主命である。当社(大天貘社)が元は本郷だけで祀る神社であったのに対し、勝根神社は初めから(西城)村全体で祀る神社」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の西城村の項に大天貘社があり「村ノ鎮守トス 長慶寺持」とあります。
・西城神社は入母屋造桟瓦葺、「西城神社」と彫り込まれた棟飾りは精緻で一見の価値があります。
・向かって左手に御鎮座の勝根神社は、切妻造桟瓦葺の整った社殿で「村全体で祀ってきた神社」としての重みを放たれています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:西城神社 筆書

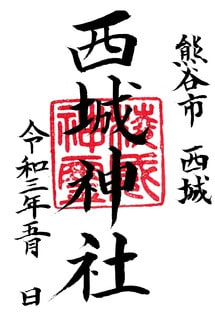
■ 八幡大神社
熊谷市上須戸838(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:大字上須戸鎮守、(旧長井村総鎮守)
元別当:福原山 開城院 正法寺(上須戸村/天台宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「伝説によると、天喜五年(1057年)、源頼義が安倍貞任を討つために奥州へ下る途中、当地に逗留した。この折竜海という沼に棲む大蛇が村人を悩ますことを聞いたため、土地の島田大五郎道竿に命じて退治させた。頼義はこの大蛇退治を安倍氏征討の門出に吉事であると喜び、大蛇の棲んでいたところから、東・西・北に三本の矢を放ち、その落ちた所にそれぞれ八幡社を、沼の中央に大蛇慰霊のための弁天社を祀った。当社は、西に放たれた矢が落ちた所に祀られたという。」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の上須戸村の項に八幡社があり「八幡社 辨天社 何レモ社領ヲ附ラル年代下●出セリ 別当正法寺」とあります。
・『埼玉の神社』の内容は、(日向)長井神社の「竜海伝説」とほぼ同様で、このエリアに広く伝わっていたことが伺われます。
・うっそうと茂る社叢。木造朱塗りの両部鳥居、石造の明神鳥居の正面おくに入母屋造桟瓦葺平入り流れ向拝の八幡神社、向かって右手には切妻造桟瓦葺妻入りの八坂大神が御鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市上須戸 八幡大神社 筆書


■ 王子山 観清寺
熊谷市弥藤吾574-1(旧・大里郡妻沼町)
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第3番
・こちらは幡羅郡新四国霊場のみの札所なので、とくに情報が少ないです。
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 下奈良村集福寺末王子山ト號ス(中略)開山ハ本寺(集福寺)二世要岩春津弘治三年(1557年)示寂 本尊ハ釋迦文殊普賢ヲ安ス」とあります。
・予想以上の大寺で境内もよく整っています。御朱印は庫裡にて授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛


■ 禅源山 長井寺
熊谷市弥藤吾1979(旧・大里郡妻沼町)
臨済宗円覚寺派
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第17番
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 上野國那波郡矢場村泉福寺末 禅源山ト號ス 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・その他の由来などは不明です。
・現況は無住と思われ、御朱印は別途お願いし郵送いただきましたが、これはイレギュラー対応で原則不授与かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第17番 釈迦如来


■ 大悲山 薬師院 観音寺
公式Web
熊谷市八木田198(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第18番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第44番、第67番(薬師堂)
・公式Webに、慶長年間(1596-1615年)のはじめ、澄海上人による開基とされ、徳川幕府よりご朱印を賜り、とあります。
・『新編武蔵風土記稿』には「大田村能護寺末大悲山薬師院ト号ス 慶安(1648-1652年)中寺領六石五斗ノ御朱印ヲ賜フ 開山澄海寂年知レス 本尊千手観音ヲ安ス」とあります。
村内の薬師堂と阿弥陀堂一宇も護持していたようです。
・忍秩父三十四観音霊場の観音堂は本堂とは別で、札所本尊は十一面観世音菩薩です。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていない模様です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第18番 十一面観世音菩薩


■ 聖天山 長楽寺 歓喜院(妻沼聖天山)
公式Web
熊谷市妻沼1627(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:大聖歓喜天
札所:関東八十八箇所第88番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番、武州路十二支霊場 午(勢至菩薩)、東国花の寺百ヶ寺霊場第26番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番、第76番(旧宝蔵院)
・「日本三大聖天」のひとつ、「妻沼の聖天様」と呼ばれる関東を代表する名刹で、複数の霊場札所を務められます。
・名刹だけに記事ネタが多いですが、こちらでは簡単なご縁起と御朱印関連に絞ってご案内します。
・平安時代末期の武将斎藤別当実盛公(長井別当)が治承三年(1179年)、守り本尊の大聖歓喜天を祀る聖天宮を建立し、長井庄の総鎮守としたのが始まりとされます。
・実盛公は、源平争乱期に源義朝公、木曾義仲公、平維盛公と複雑な関係をもち、寿永二年(1183年)、平維盛公らと木曾義仲公追討のため出陣した加賀国篠原の戦いで奮戦し、ついに討ち取られました。この篠原の戦いの顛末は『平家物語』巻第七「実盛最期」として一章を成し、東国武士の機微を語るものとして広く知られています。
・建久八年(1197年)、良応僧都(実盛公の次男である実長(宗光))が聖天宮の別当(本坊)として歓喜院長楽寺を建立し、十一面観世音菩薩を本尊としたといいます。
・国宝の本殿は絢爛たる廟型式権現造で、「埼玉日光」ともいわれます。
・御朱印は境内授与所にていただけます。5つの札所を確認しており、うち4つを拝受しています。残りの幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番については不明です。
なお、札所御朱印ではない御本尊・大聖歓喜天の御朱印も授与されている模様です。
〔拝受御朱印〕
1.東国花の寺百ヶ寺霊場第26番 大聖歓喜天
札所本尊は御本尊。本殿が札所とみられます。


2.関東八十八箇所第88番 大聖歓喜天
本殿向かって左の大師堂が札所(第88番結願所)となっています。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所もこちらになります。


3.武州路十二支霊場 午 勢至菩薩
本殿向かって左の大師堂のお大師さまの右手(礼拝者からは左手)に御座す立像の勢至菩薩が札所本尊と思われます。大師堂内に単尊で勢至菩薩が安置される例は少ないと思われます。
当地は二十三夜月待講がさかんで、当山山内にも二十三夜塔が建立されています。そちらとの関連もあるのかもしれません。


4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番 聖観世音菩薩
中門そばの護摩堂の手前に御座す露仏の観音様が札所本尊です。


■ 寶珠山 光明禅寺 玉洞院
熊谷市妻沼2404(旧・大里郡妻沼町)
臨済宗円覚寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第16番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第86番
・開基は月峯常圓居士、開山を養嚴宗胡(文明九年(1477年)寂)とする曹洞宗寺院。
・『新編武蔵風土記稿』には鐘樓の銘文に「淀城主石川主殿頭憲之妻女、及び次男義孝、武運長久の誓の為に元禄三年(1690年)寄附する由を鐫す」とあります。
・石川憲之(1634-1707年)は、石川数正の叔父、石川家成の家を継いだ大久保忠隣の次男、石川忠総の孫にあたり、近江膳所藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家四代、山城淀藩初代藩主を務めました。憲之の妻女(正室)は羽林家の公家、梅園実清(1609-1662年)の息女で、その子石川義孝は山城淀藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家五代。
・妻女梅園氏、石川義孝ともに妻沼とのゆかりは確認できず、どうして当寺にこのような鐘銘が残っているのかも不明です。
御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受しました。幡羅郡新四国霊場については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第16番 聖観世音菩薩


■ 祥興山 真徳院 瑞林寺
熊谷市妻沼2485(旧・大里郡妻沼町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番
・『新編武蔵風土記稿』および境内記念碑によると、建久年間(1190-1199年)に天台宗寺院として創建。慶長六年(1598年)矢場村惠林寺第五世大庵文恕により曹洞宗に改められて開山、開基は大河内孫十郎政信と伝わります。
・大河内氏は摂津源氏源頼政流とされ、三河の吉良氏の家老の家柄でしたが、天正十五年(1587年)大河内秀綱の二男正綱が家康の命で長沢松平家庶流の松平正次の養子となり、子孫は大河内松平家と称します。武蔵野の名刹、平林寺は大河内大名家の墓所として知られています。
・こちらのWeb(大河内松平氏の研究)に「吉良家を去った大河内秀綱後は伊奈氏の配下で代官として活動している。『伊奈忠次文書集成』の中に、大河内秀綱に宛てた慶長年間の文書がある。文禄三年(1594年)、徳川家康が江戸から上州新田に向かうため、通り道にあたる妻沼の名主に人馬継立を命じる文書が大河内孫十郎(久綱)の名で発給されている。このころ既に久綱が代官だったことが知られる。」とあり、孫十郎(久綱)と孫十郎政信が同一人物であるかはわかりませんが、江戸時代初期に大河内氏が妻沼の地を代官差配していたことがうかがわれます。
・本堂向かって右手前の日限地蔵堂には赤い幟がならび、信仰を集めている感じがします。
・墓所には江戸時代の俳匠・有磯庵五渡(ありそあんごと)三代の墓があります。江戸時代の妻沼は芭蕉ゆかりの俳句のメッカで、各地の俳人たちは妻沼聖天の参詣と併せて妻沼の俳人と交流し、これを「妻沼詣」と称したと伝わります。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番の札所で、門前に御朱印のサンプルが掲示されています。庫裡にて「新四国第七十三番」の札所印入りの御朱印を拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番 釈迦牟尼佛


■ 能満山 定禅院 能護寺(あじさい寺)
熊谷市Web
熊谷市永井太田1141(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第25番
・天平十五年(743年)に国家安穏・万民豊楽と五穀豊穣祈願のため行基上人が開山し、後に弘法大師空海が再建され真言密教の道場として整えられたと伝わります。
・「妻沼のあじさい寺」として知られ、毎年6月には多くの参詣者を迎えます。
・現本堂は文化十一年(1814年)の再建で、内陣に大日如来、外陣に阿弥陀如来を安置した堂内の格天井(十六羅漢図)には、金井烏洲・岩崎榮益・樋口春翠などの彩色の花鳥獣が描かれています。
・虚空蔵堂には虚空蔵菩薩が祀られ、男女13歳厄除け祈願(十三参り)の寺として信仰を集めています。
・鐘楼の鐘は、元禄十四年(1701年)、諸八郎兵衛藤原正綱による鋳造で、乳の間に百字真言の梵字が鋳込まれているもの。市の文化財に指定されています。
・メジャー霊場「東国花の寺百ヶ寺霊場」の札所で、御朱印は庫裡にて拝受。御朱印尊格は「十三参り」の虚空蔵尊となっています。
〔拝受御朱印〕
1.虚空蔵堂御本尊 虚空蔵菩薩


2.東国花の寺百ヶ寺霊場第25番 虚空蔵菩薩


【 BGM 】
■ glow Piano&Strings Acoustic .Ver うたってみた 鹿子
■ 夢の途中 - KOKIA
■ far on the water - Kalafina
深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。
併せてまわってみてはいかがでしょうか。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)から。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
■ 関連記事
「血洗島 諏訪神社の御朱印」
↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。
なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
4.旧 妻沼町エリア
■ 瑠璃光山 浄光院 福生寺
熊谷市日向1154(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第34番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番
・こちらも御由緒詳細がとれませんが、山内石碑には「四九四年前に開創せられし名刹」とあり、『新編武蔵風土記稿』の日向村の項には「邑楽郡赤岩村光恩寺末 開山専祐寛永十八年(1641年)寂 本尊大日ヲ安セリ 薬師堂」とあります。
・重厚な山門、本堂、観音堂を擁して山内はよく整っています。
・こちらは忍秩父三十四観音霊場第34番の結願所で、札所本尊は馬頭観世音菩薩。御本尊の大日如来は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所本尊でもあり、こちらの御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第34番 馬頭観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番 大日如来

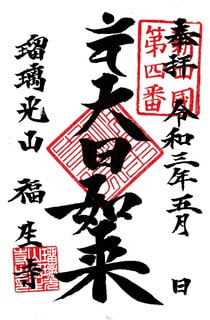
■ 寶積山 白道院 大龍寺
公式Web
熊谷市葛和田898(旧・大里郡妻沼町)
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第15番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第21番
・名刹のようですが、現地、Webともに詳しい情報がとれませんでした。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に記載がありますので抜粋引用します。「館林町善導寺末 開山ハ幡随意上人元和元年正月示寂 開基ハ成田氏ノ臣嶋田采女正ナリ コノ子孫今村民六兵衛ナリト云 本尊阿弥陀ヲ安セリ 荒神社 愛宕社 不動堂 観音堂」。
・幡随意(ばんずいい)上人は、 慶長二十年(1615年)寂と伝わる浄土宗の名僧で、鎌倉光明寺で教学を修められ、後に京都百万遍知恩寺の三十三世住持。徳川家康公の信任厚く、駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創、熊谷の名刹、熊谷寺(ゆうこくじ)の中興など全国で寺院を創立・再興されました。
・当寺所蔵の「幡随意上人の書」、本堂に御座す「三十三体観音像」(元禄期、寄木造金泥)は市の文化財に指定されています。
・名刹らしい風趣のある山内。御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。御本尊および幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第15番 三十三体観世音菩薩


■ 浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺
公式Web
熊谷市西城93-1(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来・薬師如来?
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番
司元別当:西城神社(西城村、旧西城村(本郷)鎮守)
・こちらは詳細な公式Webをお持ちなので、そちらから引用させていただきます。
・南北朝の永和二年(1376年)、慶弘という僧が伝・行基作の薬師如来像を祀り開創。赤岩光恩寺の末寺で、歴代の住職が隠居されていました。
・薬師如来像は12年に一度、寅年の御開帳で信仰を集めているようです。
・本堂と薬師堂、薬師堂厨子は、2020年9月に市の有形文化財に指定されています。
・ともに、上州花輪村の名工・石原吟八郎のグループと、「歓喜天聖天堂」の棟梁の林兵庫正清を中心に建立。江戸期のこの地の彫物師集団の技巧を示す作品として評価されています。
・本堂には阿弥陀如来、薬師堂には薬師如来が御座します。
公式Webに「本堂の阿弥陀如像は、宝永年間(1704-1711年)に祀られた。平成26年遷座300年目に修復。本尊とご縁を結び、人生を輝いて全うできるように御手綱を握ってお参りができる」とあるので、当寺のいまの御本尊は阿弥陀如来とみられますが、宝永年間までの御本尊は薬師如来とみられ、現在でも御本尊のポジションなのかもしれません。
・仏教寺院、とくに密寺の御本尊のポジションは複雑で、観音堂、薬師堂、不動堂などで草創し、のちに本堂が建てられた場合などは、複数の御本尊がおられる場合もあるようです。(例えば、本堂御本尊は大日如来、薬師堂御本尊は薬師如来で、寺院としての御本尊は両尊併記となる。)
・弘法大師霊場の札所本尊は草創時の御本尊が札所本尊になられる場合も多く、こちらもその例ではないでしょうか。
・御朱印はご住職がご不在で書置もなかったので、ご親切な寺庭様にお願いして郵送をいただきました。なお、こちらは忍秩父三十四観音霊場第10番光明山 観音寺(上中条)の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番 薬師如来




■ 福聚山 慈眼寺
熊谷市田島238(旧・大里郡妻沼町)
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第14番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番
司元別当:(田島村)稲荷社(旧田島村鎮守)
・こちらも無住の寺院で情報が少ないです。
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
・『新編武蔵風土記稿』の田島村の項に「弥藤五村観清寺末(略)古ハ観音ノ堂ナリシガ寛永年中(1624--1645年)●月堂開山シテ一寺トナセリ コノ人ハ慶安四年(1651年)寂セリト云 本尊十一面観音ヲ安ス」とあり、もとは観音堂として草創、寛永年中(1624--1645年)に寺院になったようです。
・入り組んだ路地のなか、集落に囲まれるようにあります。寄棟造桟瓦葺で右手に庫裡らしき建物を連接しています。
・向拝柱はなく中央サッシュ扉、上部に「慈眼寺」の寺号扁額を掲げています。
・参拝時ご不在でしたので郵送をお願いしお送りいただきました。郵送なので欲張らず忍観音霊場の御朱印のみお願いしましたが、御朱印には幡羅郡新四国霊場の札番揮毫もいただいておりました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第14番 十一面観世音菩薩
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番 十一面観世音菩薩
※1通に2札所併記。


■ 福源山 長昌寺
熊谷市八ツ口869(旧・大里郡妻沼町)
臨済宗円覚寺派
御本尊:
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第88番
・山内由来書によると、長井庄司斎藤別当実盛公が堀之内に館を構えたとき、この地にあった薬師堂を鬼門除けの祈願所に定めたといいます。
・山内の椎の巨木は、鬼門除けの祈願所に選んだ証に植えた3本のうち、唯一残った1本と言われているそうです。(熊谷市Web)
・同由来書によると、慶安年中に寺領二十石余の朱印を賜る名刹とのこと。
・忍城主成田氏の臣、山田伊半が武川の合戦で討死し、息子の弥治郎が追福のため開基となり建立。その折には成田氏より寄進等があったといいます。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の第88番(結願所)の重要なポジションは、斎藤別当実盛公や忍城主成田氏とのゆかりに由来するものかもしれません。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第17番 釈迦如来

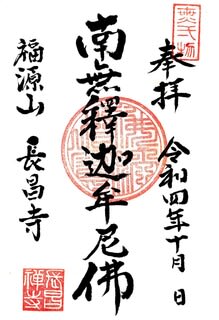
〔村の鎮守十社めぐり〕
当初は「以下10社について御朱印を拝受していますが、長井神社と大杉神社以外は常時授与かどうか不明なのでとりあえずリストのみです。」としましたが、令和2年秋に案内パンフが作成され、実際に御朱印も拝受していますので、ご参考までにUPします。
なお、現時点では御朱印は原則不授与かもしれません。詳細は長井神社宮司様にご確認ください。


情報が少ないですが、現地掲示のほか、案内パンフ、『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、『新編武蔵風土記稿』などを参考にまとめてみます。
1.(日向)長井神社 熊谷市日向
2.(俵瀬)伊奈利神社 熊谷市俵瀬
3.神明社・大杉神社 熊谷市葛和田
4.(大野)伊奈利神社 熊谷市大野
5.(弁財)嚴島神社 熊谷市弁財
6.善ヶ島神社 熊谷市善ヶ島
7.(八ツ口)日枝神社 熊谷市八ツ口
8.江波神社 熊谷市江波
9.西城神社 熊谷市西城
10.八幡大神社 熊谷市上須戸
■ (日向)長井神社
熊谷市日向1090(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:品陀別命、息長帯姫命
旧社格:村社、旧日向村鎮守
元別当:三学院(日向村、当山修験)
授与所:境内脇社務所
・江戸時代には八幡社と称された旧日向村の鎮守社。(明治9年現社号に改号)
・天喜五年(1057年)、源頼義公が安陪貞任討伐の折にこの地に滞留されたとき、竜海という池に棲み村人を悩ましていた大蛇の退治を島田大五郎道竿に命じた。頼義公より弓矢と太刀を下賜された道竿は、竜海から利根川まで堀(道竿堀/どうかんぼり)を掘り、池の水を利根川に落としてこの四丈もの大蛇を退治した。頼義公は東北地方平定の吉事として、大蛇を倒したところに当社を、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったといいます。
・暦応元年(1338年)、足利尊氏が再興、戦国時代には忍城主成田長泰が信仰した記録が残ります。
・『新編武蔵風土記稿』の日向村の項に八幡社があり、上記の「竜海伝説」が詳細に記載されています。
・本地堂の御本尊は阿弥陀如来で、これは八幡神の本地が阿弥陀如来とされたことと符合します。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:長井神社 筆書


■ (俵瀬)伊奈利神社
熊谷市俵瀬489(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧俵瀬村鎮守
元別当:寶林山 妙音寺 成就院(俵瀬村/新義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・俵瀬は利根川と福川に挟まれた島状のエリアで、『新編武蔵風土記稿』には俵瀬村の項に稲荷社が記載されているものの「成就院持」としかありません。
・これにはさすがの『埼玉の神社』も困り果てたらしく、成就院の記載を引き「成就院は慶安四年(1651年)の草創と伝えている。当地が一村としての体裁を整え始めるのが寛永(1624-1645年)の末ごろと思われ、当社の創建も、別当成就院と前後して行われたものであろう。」と記されています。
・江戸時代には「稲荷社」と称し、明治初期に「伊奈利社」と改め、明治41年合祀政策により同大字の神明社、厳島神社を合祀し、大正2年には堤防工事に伴い利根川縁にあった当社を厳島神社の旧社地に御遷座と伝わります。
・厳つい石垣の上に入母屋造桟瓦葺でどっしりと鎮座するお社は、ながらく水害と闘ってきた俵瀬の地の鎮守社ならではのお姿に思えます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市俵瀬 伊奈利神社 筆書


■ (葛和田)神明社・大杉神社
熊谷市葛和田591(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:天照皇大神、大杉大神
※大杉神社は(葛和田)神明社の境内社
旧社格:旧葛和田村鎮守
元別当:瑠璃光山 東光院 醫王寺(葛和田村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・伊勢の御師が当地に逗留した折に奉齋した社であると伝わります。
・旧社地は現在利根川の川中にあり、数回の移転を経て高台の現社地(氷川神社の社地)に御遷座とのこと。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に神明社があり「氷川ヲ合殿トス 村ノ鎮守ナリ 別当醫王寺」とあります。
・境内社の大杉神社(あんば様)の祭礼は利根川の流れに大御輿・大杉御輿を乗り入れるもので、「葛和田の勇み御輿」「関東一のあばれ御輿」として広く知られています。
・江戸時代の葛和田の地は利根川の河岸場として賑わいました。あるとき、与助という腕のいい船頭が霞ヶ浦の西浦で暴風雨に襲われ窮まったとき、日頃から信仰している大杉明神に祈りをささげると神佑を得て難を逃れました。このご神徳への御礼と今後の船路安全祈念のため、茨城県稲敷の大杉神社から勧請し、御輿を造営したと伝わります。
・当初は利根川に注ぐ道竿堀の南に御鎮座でしたが、大正3年堤防工事に伴い現社地に御遷座・合祀されました。
・御朱印は(日向)長井神社社務所にて拝受しました。
・Web上では神明社の御朱印がみつかりますが、現在は大杉神社の御朱印のみ授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大杉大神 筆書




■ (大野)伊奈利神社
熊谷市大野751(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:豊宇気比咩命
旧社格:旧村社、旧大野村鎮守
元別当:大野山 利劔寺 文殊院(葛和田(大野)村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・〔村の鎮守十社めぐり〕のなかではもっとも利根川に近く、利根川の堤防下に鎮座します。
・江戸期には大野村は葛和田村の一部とされ、『新編武蔵風土記稿』には葛和田村の項に「稲荷社二宇 一ハ文殊院 一ハ正泉寺持」とあり、『埼玉の神社』には文殊院が別当とあるので、こちらが該当とみられます。
・ただし、『埼玉の神社』には「宝暦六年(1756年)の伏見稲荷からの分霊証書に『武州 大野村鎮守』とあることから、当時既に『大野村』という名称が使われており、葛和田村から実質は独立していたことがわかる」とあります。
・上記のとおり、宝暦六年(1756年)には伏見稲荷からの分霊証書を受けて創祀しています。
・地形からしても、なにより水害防除が求められる地とみられ、『埼玉の神社』には「伊奈利社を(利根)川の側に勧請することによって水害から村を守ろうとした開発者の心情が推察される。」とあります。
・小山状の高台に鎮座し、参道右手が旧文殊院跡。その手前に大国主尊、参道階段右手に三峰社、拝殿左手には馬頭観世音菩薩、庚申様、青面金剛が祀られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市大野 伊奈利神社 筆書


■ (弁財)嚴島神社
熊谷市弁財174(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:弁財地区鎮守
元別当:辨財山 醫王院 薬王寺(辨財村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「当地(弁財)は大昔利根川の流れの中にあったが、やがて流路が変わり、自然堤防を形作った所である。」とあり、河川とのかかわりから弁財天が祀られたとする一方、口碑に「当地の草分けであり、屋号を庄屋と呼ぶ大島清和家の先祖が祀った。」とあり、「同家は平家の落人であり、そのゆかりから嚴島神社を祀った。」という説にも触れています。
・『新編武蔵風土記稿』の辨財村の項に辨財天社があり「村名ナリシテ見レハ古社ナルヘケレト傳ヘテ失フ」とあります。
・(日向)長井神社縁起の竜海伝説では、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったとされ、この弁財天を当社とする説と(日向)長井神社境内の宇賀神(弁天様)とする説があるようです。
・『埼玉の神社』では、享保十六年(1731年)の利根川大洪水の折、当地に沼ができて、その後沼の主と呼ばれる大蛇が棲み、それが竜海伝説に重なったと指摘しています。
・こちらも社叢のなかに御鎮座。拝殿は石垣のうえに入母屋造桟瓦葺で、主屋根の軒に瓦屋根の向拝を重ねるようにせり出し変化のある意匠。
・弁財天や厳島社はもともと蛇とのゆかりがありますが、向拝の屋根飾りにも蛇の姿がみられます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:嚴島比賣 筆書


■ 善ヶ島神社
熊谷市善ヶ島197(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧善ヶ島村鎮守
元別当:光明山 福壽院 龍泉寺(善ヶ島村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』『パンフ』には、当地は当初葦が生えた島で葦ヶ島と呼ばれたが、後に利根川の流れが変わり、近村と地続きになり善ヶ島と改めた。また、1500年頃の蔵王権現社の勧請が当社の起源とされ、当初は蔵王権現社、明治初期に御嶽神社と称し、明治42年に善ヶ島神社に改称といいます。
・明治41年には大字裏久保の愛宕神社と、上元割の阿夫利神社を合祀。地元では合祀社の阿夫利神社に因み「阿夫利様」と呼ばれることが多いそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の善ヶ島村の項に蔵王権現社があり「永正(1504-1521年)年中の勧請ト云 龍泉寺持 末社 天神 疱瘡神 摩陀羅神」とあります。
・金剛蔵王権現は修験系の尊格で、ことにの吉野の金峯山寺本堂(蔵王堂)の御本尊として知られています。
・当社の現在の主祭神は不明ですが、金剛蔵王権現は大己貴命、少彦名命、国常立尊、日本武尊、金山毘古命との習合例が多く、明治の神仏分離時、金剛蔵王権現を祀る堂祠は上記の神々を祭神とする神社となった例がみられます。
・末社に摩陀羅神の名がみられます。すこぶる複雑な性格をもたれる尊格として知られ、東日本で祀られる例は多くありません。
・別当龍泉寺は古義真言宗で赤岩光恩寺の末。赤岩光恩寺の寺伝には「推古天皇11年(603年)には秦河勝を勅使として仏舎利三粒が納められた」とあります。(秦河勝と摩陀羅神は強い関係があるとされる。)
・当社に摩陀羅神が祀られていた背景には、このような所縁が関連しているのかもしれません。
・現在も、複雑な由緒を想起させる境内社が複数ご鎮座されます。
・社叢のなか、入母屋造桟瓦葺向拝付設の社殿と境内社が御鎮座。
・鳥居、灯籠ともに大きく嵩が上げられ、拝殿も数段高く、水害防除が大切な地であることを物語っています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:善島神社 筆書


■ (八ツ口)日枝神社
熊谷市八ツ口922(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧村社、旧八ツ口村鎮守
元別当:●源山 長昌寺(八ツ口村/禅宗臨済派)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「(別当の)長昌寺は、天文元年(1532年)に成田氏に従い武川の合戦で討死した山田弥次郎の菩提追福のために、その父山田伊平が、弥次郎の領地であったこの地に草創した寺院である。当社の成立背景には、長昌寺の僧とのかかわりが考えられるが、明らかにできない。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の八ツ口村の項に山王社があり「村ノ鎮守ニテ稲荷ヲ合殿トス 長昌寺持」とあります。
・元別当の長昌寺は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第88番の結願寺で、相応の寺格をお持ちかと思いますが、現在のところ御朱印は拝受しておりません。
・社頭に朱塗りの2つの鳥居。向かって左手が日枝神社、右手が八坂神社と伊奈利社です。
八坂神社の夏祭りの御輿渡御は、以前は「暴れ御輿」として広く知られていたようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市八ツ口 日枝神社 筆書

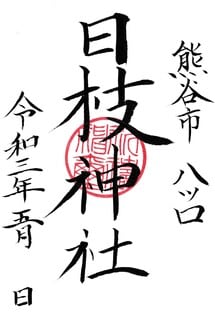
■ 江波神社
熊谷市江波315(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:菅原道真公
旧社格:旧村社、旧江波村鎮守
元別当:福原山 寶蔵院(江波村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「明治四十一年の改正まで天神社であったことから、氏子にはいまだに天神様と呼ばれている。(中略)明治四十一年、字西嬉愛の宇知多神社(妙見社)と字道上の稲荷神社の無格社二社を合祀した。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の江波村の項に天神社があり「村ノ鎮守トス 寶蔵院持」とあります。
・一面の麦畑のなかに浮かぶように、切妻造瓦葺妻入りの社殿が御鎮座。向拝も切妻の屋根がかかり、めずらしい様式の社殿です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:江波神社 筆書


■ 西城神社
熊谷市西城2(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:旧村社、旧西城村(本郷)鎮守
元別当:浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺(西城村/古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「西城の地名は、かつてこの地に左近衛少将藤原義孝の居舘があったことにちなむものといわれ、古来、西城の村は郭(くるわ)と呼ばれる幾つかの小さい集落に分かれ、神社の祭祀もまた郭ごとに鎮守として各々神社を祀っていた。明治維新の際、社格を定めるに当たり、(大天貘社は)村内の諸社の中で最も規模が大きく、村の中で最も早く開かれた本郷の鎮守であったことから、当社が西城村の村社になった。恐らく、明治9年に村社となった時に村名を採って西城神社と社名を改めたものであろう。明治42年には、字東田鎮座の稲荷神社と字鴉森鎮座の厳島神社を合祀し現在に至っている。」とあります。
・また同書には「境内にある勝根神社は、古くから当社の末社として祀られており、その祭神は大物主命である。当社(大天貘社)が元は本郷だけで祀る神社であったのに対し、勝根神社は初めから(西城)村全体で祀る神社」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の西城村の項に大天貘社があり「村ノ鎮守トス 長慶寺持」とあります。
・西城神社は入母屋造桟瓦葺、「西城神社」と彫り込まれた棟飾りは精緻で一見の価値があります。
・向かって左手に御鎮座の勝根神社は、切妻造桟瓦葺の整った社殿で「村全体で祀ってきた神社」としての重みを放たれています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:西城神社 筆書

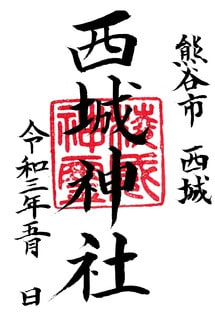
■ 八幡大神社
熊谷市上須戸838(旧・大里郡妻沼町)
御祭神:
旧社格:大字上須戸鎮守、(旧長井村総鎮守)
元別当:福原山 開城院 正法寺(上須戸村/天台宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「伝説によると、天喜五年(1057年)、源頼義が安倍貞任を討つために奥州へ下る途中、当地に逗留した。この折竜海という沼に棲む大蛇が村人を悩ますことを聞いたため、土地の島田大五郎道竿に命じて退治させた。頼義はこの大蛇退治を安倍氏征討の門出に吉事であると喜び、大蛇の棲んでいたところから、東・西・北に三本の矢を放ち、その落ちた所にそれぞれ八幡社を、沼の中央に大蛇慰霊のための弁天社を祀った。当社は、西に放たれた矢が落ちた所に祀られたという。」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の上須戸村の項に八幡社があり「八幡社 辨天社 何レモ社領ヲ附ラル年代下●出セリ 別当正法寺」とあります。
・『埼玉の神社』の内容は、(日向)長井神社の「竜海伝説」とほぼ同様で、このエリアに広く伝わっていたことが伺われます。
・うっそうと茂る社叢。木造朱塗りの両部鳥居、石造の明神鳥居の正面おくに入母屋造桟瓦葺平入り流れ向拝の八幡神社、向かって右手には切妻造桟瓦葺妻入りの八坂大神が御鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市上須戸 八幡大神社 筆書


■ 王子山 観清寺
熊谷市弥藤吾574-1(旧・大里郡妻沼町)
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第3番
・こちらは幡羅郡新四国霊場のみの札所なので、とくに情報が少ないです。
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 下奈良村集福寺末王子山ト號ス(中略)開山ハ本寺(集福寺)二世要岩春津弘治三年(1557年)示寂 本尊ハ釋迦文殊普賢ヲ安ス」とあります。
・予想以上の大寺で境内もよく整っています。御朱印は庫裡にて授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛


■ 禅源山 長井寺
熊谷市弥藤吾1979(旧・大里郡妻沼町)
臨済宗円覚寺派
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第17番
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 上野國那波郡矢場村泉福寺末 禅源山ト號ス 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・その他の由来などは不明です。
・現況は無住と思われ、御朱印は別途お願いし郵送いただきましたが、これはイレギュラー対応で原則不授与かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第17番 釈迦如来


■ 大悲山 薬師院 観音寺
公式Web
熊谷市八木田198(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第18番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第44番、第67番(薬師堂)
・公式Webに、慶長年間(1596-1615年)のはじめ、澄海上人による開基とされ、徳川幕府よりご朱印を賜り、とあります。
・『新編武蔵風土記稿』には「大田村能護寺末大悲山薬師院ト号ス 慶安(1648-1652年)中寺領六石五斗ノ御朱印ヲ賜フ 開山澄海寂年知レス 本尊千手観音ヲ安ス」とあります。
村内の薬師堂と阿弥陀堂一宇も護持していたようです。
・忍秩父三十四観音霊場の観音堂は本堂とは別で、札所本尊は十一面観世音菩薩です。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていない模様です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第18番 十一面観世音菩薩


■ 聖天山 長楽寺 歓喜院(妻沼聖天山)
公式Web
熊谷市妻沼1627(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:大聖歓喜天
札所:関東八十八箇所第88番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番、武州路十二支霊場 午(勢至菩薩)、東国花の寺百ヶ寺霊場第26番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番、第76番(旧宝蔵院)
・「日本三大聖天」のひとつ、「妻沼の聖天様」と呼ばれる関東を代表する名刹で、複数の霊場札所を務められます。
・名刹だけに記事ネタが多いですが、こちらでは簡単なご縁起と御朱印関連に絞ってご案内します。
・平安時代末期の武将斎藤別当実盛公(長井別当)が治承三年(1179年)、守り本尊の大聖歓喜天を祀る聖天宮を建立し、長井庄の総鎮守としたのが始まりとされます。
・実盛公は、源平争乱期に源義朝公、木曾義仲公、平維盛公と複雑な関係をもち、寿永二年(1183年)、平維盛公らと木曾義仲公追討のため出陣した加賀国篠原の戦いで奮戦し、ついに討ち取られました。この篠原の戦いの顛末は『平家物語』巻第七「実盛最期」として一章を成し、東国武士の機微を語るものとして広く知られています。
・建久八年(1197年)、良応僧都(実盛公の次男である実長(宗光))が聖天宮の別当(本坊)として歓喜院長楽寺を建立し、十一面観世音菩薩を本尊としたといいます。
・国宝の本殿は絢爛たる廟型式権現造で、「埼玉日光」ともいわれます。
・御朱印は境内授与所にていただけます。5つの札所を確認しており、うち4つを拝受しています。残りの幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番については不明です。
なお、札所御朱印ではない御本尊・大聖歓喜天の御朱印も授与されている模様です。
〔拝受御朱印〕
1.東国花の寺百ヶ寺霊場第26番 大聖歓喜天
札所本尊は御本尊。本殿が札所とみられます。


2.関東八十八箇所第88番 大聖歓喜天
本殿向かって左の大師堂が札所(第88番結願所)となっています。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所もこちらになります。


3.武州路十二支霊場 午 勢至菩薩
本殿向かって左の大師堂のお大師さまの右手(礼拝者からは左手)に御座す立像の勢至菩薩が札所本尊と思われます。大師堂内に単尊で勢至菩薩が安置される例は少ないと思われます。
当地は二十三夜月待講がさかんで、当山山内にも二十三夜塔が建立されています。そちらとの関連もあるのかもしれません。


4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番 聖観世音菩薩
中門そばの護摩堂の手前に御座す露仏の観音様が札所本尊です。


■ 寶珠山 光明禅寺 玉洞院
熊谷市妻沼2404(旧・大里郡妻沼町)
臨済宗円覚寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第16番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第86番
・開基は月峯常圓居士、開山を養嚴宗胡(文明九年(1477年)寂)とする曹洞宗寺院。
・『新編武蔵風土記稿』には鐘樓の銘文に「淀城主石川主殿頭憲之妻女、及び次男義孝、武運長久の誓の為に元禄三年(1690年)寄附する由を鐫す」とあります。
・石川憲之(1634-1707年)は、石川数正の叔父、石川家成の家を継いだ大久保忠隣の次男、石川忠総の孫にあたり、近江膳所藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家四代、山城淀藩初代藩主を務めました。憲之の妻女(正室)は羽林家の公家、梅園実清(1609-1662年)の息女で、その子石川義孝は山城淀藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家五代。
・妻女梅園氏、石川義孝ともに妻沼とのゆかりは確認できず、どうして当寺にこのような鐘銘が残っているのかも不明です。
御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受しました。幡羅郡新四国霊場については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第16番 聖観世音菩薩


■ 祥興山 真徳院 瑞林寺
熊谷市妻沼2485(旧・大里郡妻沼町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番
・『新編武蔵風土記稿』および境内記念碑によると、建久年間(1190-1199年)に天台宗寺院として創建。慶長六年(1598年)矢場村惠林寺第五世大庵文恕により曹洞宗に改められて開山、開基は大河内孫十郎政信と伝わります。
・大河内氏は摂津源氏源頼政流とされ、三河の吉良氏の家老の家柄でしたが、天正十五年(1587年)大河内秀綱の二男正綱が家康の命で長沢松平家庶流の松平正次の養子となり、子孫は大河内松平家と称します。武蔵野の名刹、平林寺は大河内大名家の墓所として知られています。
・こちらのWeb(大河内松平氏の研究)に「吉良家を去った大河内秀綱後は伊奈氏の配下で代官として活動している。『伊奈忠次文書集成』の中に、大河内秀綱に宛てた慶長年間の文書がある。文禄三年(1594年)、徳川家康が江戸から上州新田に向かうため、通り道にあたる妻沼の名主に人馬継立を命じる文書が大河内孫十郎(久綱)の名で発給されている。このころ既に久綱が代官だったことが知られる。」とあり、孫十郎(久綱)と孫十郎政信が同一人物であるかはわかりませんが、江戸時代初期に大河内氏が妻沼の地を代官差配していたことがうかがわれます。
・本堂向かって右手前の日限地蔵堂には赤い幟がならび、信仰を集めている感じがします。
・墓所には江戸時代の俳匠・有磯庵五渡(ありそあんごと)三代の墓があります。江戸時代の妻沼は芭蕉ゆかりの俳句のメッカで、各地の俳人たちは妻沼聖天の参詣と併せて妻沼の俳人と交流し、これを「妻沼詣」と称したと伝わります。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番の札所で、門前に御朱印のサンプルが掲示されています。庫裡にて「新四国第七十三番」の札所印入りの御朱印を拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番 釈迦牟尼佛


■ 能満山 定禅院 能護寺(あじさい寺)
熊谷市Web
熊谷市永井太田1141(旧・大里郡妻沼町)
高野山真言宗
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第25番
・天平十五年(743年)に国家安穏・万民豊楽と五穀豊穣祈願のため行基上人が開山し、後に弘法大師空海が再建され真言密教の道場として整えられたと伝わります。
・「妻沼のあじさい寺」として知られ、毎年6月には多くの参詣者を迎えます。
・現本堂は文化十一年(1814年)の再建で、内陣に大日如来、外陣に阿弥陀如来を安置した堂内の格天井(十六羅漢図)には、金井烏洲・岩崎榮益・樋口春翠などの彩色の花鳥獣が描かれています。
・虚空蔵堂には虚空蔵菩薩が祀られ、男女13歳厄除け祈願(十三参り)の寺として信仰を集めています。
・鐘楼の鐘は、元禄十四年(1701年)、諸八郎兵衛藤原正綱による鋳造で、乳の間に百字真言の梵字が鋳込まれているもの。市の文化財に指定されています。
・メジャー霊場「東国花の寺百ヶ寺霊場」の札所で、御朱印は庫裡にて拝受。御朱印尊格は「十三参り」の虚空蔵尊となっています。
〔拝受御朱印〕
1.虚空蔵堂御本尊 虚空蔵菩薩


2.東国花の寺百ヶ寺霊場第25番 虚空蔵菩薩


【 BGM 】
■ glow Piano&Strings Acoustic .Ver うたってみた 鹿子
■ 夢の途中 - KOKIA
■ far on the water - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




