定年退職後にギターを習い始めて、10年目にして初めて発表会なるものに出たのが4年前。そして今年の発表会は4回目。易しい2重奏、ヘンデルの「サラバンド」を先生とやって、独奏がタレガの「エンディーチャとオレムス」とマニュエル・ポンセの「スケルティーノ・メヒカーノ」。前者はまー「僕の表現、『音楽』」をよく出すことができて上手く行ったが、後者がちょっと雑な感じになったのはどうもやはり僕の腕には余る曲ということだろう。ただ、4回目にして初めて指が一度も震えなかったのには驚いたし、そもそもとても嬉しかった。長年の癖である右手薬指と左手小指の悪癖を直したことが自信になったのかも知れない。
左小指はバネのように大きく動く癖、右薬指は弾き方の微妙な不安定さなのだが、一人習い時代に身についてしまったこんな根深い悪癖を我ながらよく直せたものだと思う。年寄りはただでさえ不測のミスが増えるものだから、規則的なミスを生む悪癖だけはどうしても直したかったのである。悪癖を直すということは、それに関わる全ての部分が弾きやすくなるということ。その成果はなかなか絶大だったと、今日々よーく分かるのである。長年の悪癖を直すということは大変な苦労だが、一つの質的変化、前進と痛感している。こんな心境からなのだろうが、練習が楽しくなって、1日3時間ほど弾いている。それでも身体をどこも痛めないのは、有酸素運動に強いランナーの役得というものだろう。
先週土曜日のこの発表会以降は、セゴビア編集「ソルのプレリュード20曲集」の第16番をやっている。これはさほど難しくないから今度上がる見込みだが、次の18番は難しそうだ(だいだい大好きな17番は前からずっと弾き込んできて、少しスピードを落とせば人前でも、旋律をしっかり響かせつつ弾けるようになっている)。ただ、この18番は結構よい曲で熱を入れる価値が高いと感じている。13、14番あたりと同じほど好きになりそうだ。










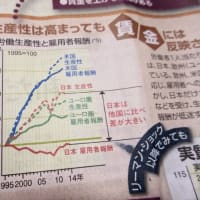
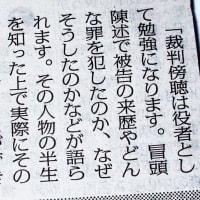





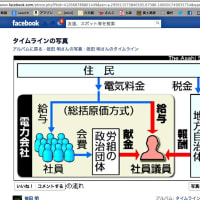
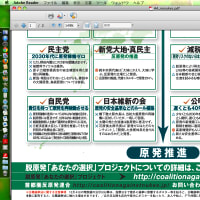




連続重和音の曲というと1,12,13番などもそうなのだが、これらはまだ、すぐに曲に乗れたから覚えやすかった。と、今分かる。ただ、1番はちょっと乗りにくく、結構難しいのだが。アレグロという速さにちっともならないで苦労した12番は取り分け苦労したが、あの苦労とは全く違う。
でも、2か月ほどかけてどんどん弾き込んでいきたい曲にもなってきた。♭三つというギターとしては珍しい調子にも慣れてみたいし、相対音階で曲を覚える僕特有の難しさにも、挑戦してみたいということ。
18番は相変わらず苦闘している。習い始めて1か月経って、暗譜はほぼ出来たのだが、一向にスラスラとならない。特に、ここら辺り3カ所が。セゴビア編「ソニーミュージック」版で、述べてみよう。1頁目の下から三段目最後から2段目中にかけて。次いで、2頁目下から4段目以下に難所が2カ所。
ここまでのところ、以上の3カ所が12番全体と同じように速くできないのである。
でもまー、ものは思いよう。「自分に苦手な曲こそ、練習価値があるというもの」。そう思って励むことにしよう。老人発心者は、重和音連続曲というのが一番難しいはずなのだから。ピアノで苦闘している5歳の孫ハーちゃんが、僕にこんなことを言ってくれるようになったことだし。
「ジーのように、楽器練習をする年寄りは居ないよ!」
おそらく、パパママの受け売りなのだろう。