落石さん
大切な話題提供を、有り難うございました。
今、自然が日本で久しぶりにブームになっていますね。自然崇拝宗教も含めてこんなことは歴史的に当たり前であった日本人が、戦後これを軽視しすぎてきた。高度経済成長社会などの中で「文化的生活」ということが「人工的生活」と同義語であるように。そして、何かただ「新しければ良い」というように。そんなふうにして戦後の日本人は、「新しい商品に何か幸せがある」というように暮らしてきたのではなかったでしょうか。もうこういう感じ方が、一つの「哲学」になっていた。商売に都合の良い、物を買わせ、金が儲かる哲学ですね。
山登りが凄い人気です。「百峰登る」とか、「体力維持」とかもありますが、移り変わる自然がなければ面白さ半減以下のはず。
家庭菜園はとても高級な趣味だと思いますね。「自分で作って、自分で鑑賞(賞味)する」。鑑賞だけではない、芸術の創造と同じ価値があると考えています。そういうことの大衆化だ。ある種の芸術創造をプロのものと考えるような悪い習慣すら存在した。
そして、エコロジーね。あれは、自然好きを一つの宗教にまで高めるようなものにもなりうる。
山が大好きな人で、「オレが死んだら、あの山の山頂近く、大きな石の下にでも散骨しておいて」と遺言された方も何人か知っています。海に散骨を言い残した歴史的文化人も非常に多いでしょう。
僕はこんな気さえしてるんですよ。自然を疎外してきたことが人間の死を「何か得体の知れぬ、恐ろしいものにしてきたという側面はなかったか」と。3月16日からこのブログに転載、3連載させていただいた作品「歳々年々人同じからず」はそういう問題提起のつもりだったんですが。
(落石さんの「お返事」)
親は自己の死をもって、子供に死を教えているんですね。
でも今の社会は老いに価値を見ようとしないで
この大切な部分を医療とか福祉という専門家に
ゆだねてしまっているんじゃないでしょうか?
親の背中を見て育つということは親がなくなるまで
一生続くものではないでしょうか?
更に言えば、死んでからも教えてもらっていますが。
(僕の「返事」)
ばかに明るい社会で (文科系)
落石さん
死に関わって言えば、ばかに明るい社会、馬鹿なほど明る過ぎる社会と思います。「明るい人が好き」と結婚の第1条件を若者皆が語り、いっぱい、どんどん離婚していく。
その若者たちが最も恐れるのが「ネクラ」と思われること。シリアスな問題はなかなか話題にもできない雰囲気があると言っても良いでしょうか。
昔はテレビの端っこに座っていたお笑い芸人が、テレビの主流で、人生観までを説き、タレント人気投票で男女ともトップの方に位置している。
どこか虚飾の、上っ面な人間関係社会と言えるのではないかと考え込むばかりです。
こんな社会では死なんて、最も疎外されるべきものなのでしょうね。誰にでも訪れる人生の最大問題であって、人間、これを考えるから生き方を問うと言っても良いほどのことなのに。
それかあらぬか、「健康老人」、「生き生き老後」、「リタイアー後の生き甲斐ブーム」の風潮には、「死の陰」消すようなものが多いようです。
この馬鹿に明るい社会、「バラ色老後ブーム」の裏側にはこんなことが放置されている。老人病棟、老人保健施設では本当に惨めに人が死んでいました。戦後日本の繁栄を築き上げてきた人々が。きっと誰かが悪いということではなく、死というものを、死を迎えようとしている人々の心への想像力が根本的に欠けているのだろうなと、僕は考え込んでいたものです。
大切な話題提供を、有り難うございました。
今、自然が日本で久しぶりにブームになっていますね。自然崇拝宗教も含めてこんなことは歴史的に当たり前であった日本人が、戦後これを軽視しすぎてきた。高度経済成長社会などの中で「文化的生活」ということが「人工的生活」と同義語であるように。そして、何かただ「新しければ良い」というように。そんなふうにして戦後の日本人は、「新しい商品に何か幸せがある」というように暮らしてきたのではなかったでしょうか。もうこういう感じ方が、一つの「哲学」になっていた。商売に都合の良い、物を買わせ、金が儲かる哲学ですね。
山登りが凄い人気です。「百峰登る」とか、「体力維持」とかもありますが、移り変わる自然がなければ面白さ半減以下のはず。
家庭菜園はとても高級な趣味だと思いますね。「自分で作って、自分で鑑賞(賞味)する」。鑑賞だけではない、芸術の創造と同じ価値があると考えています。そういうことの大衆化だ。ある種の芸術創造をプロのものと考えるような悪い習慣すら存在した。
そして、エコロジーね。あれは、自然好きを一つの宗教にまで高めるようなものにもなりうる。
山が大好きな人で、「オレが死んだら、あの山の山頂近く、大きな石の下にでも散骨しておいて」と遺言された方も何人か知っています。海に散骨を言い残した歴史的文化人も非常に多いでしょう。
僕はこんな気さえしてるんですよ。自然を疎外してきたことが人間の死を「何か得体の知れぬ、恐ろしいものにしてきたという側面はなかったか」と。3月16日からこのブログに転載、3連載させていただいた作品「歳々年々人同じからず」はそういう問題提起のつもりだったんですが。
(落石さんの「お返事」)
親は自己の死をもって、子供に死を教えているんですね。
でも今の社会は老いに価値を見ようとしないで
この大切な部分を医療とか福祉という専門家に
ゆだねてしまっているんじゃないでしょうか?
親の背中を見て育つということは親がなくなるまで
一生続くものではないでしょうか?
更に言えば、死んでからも教えてもらっていますが。
(僕の「返事」)
ばかに明るい社会で (文科系)
落石さん
死に関わって言えば、ばかに明るい社会、馬鹿なほど明る過ぎる社会と思います。「明るい人が好き」と結婚の第1条件を若者皆が語り、いっぱい、どんどん離婚していく。
その若者たちが最も恐れるのが「ネクラ」と思われること。シリアスな問題はなかなか話題にもできない雰囲気があると言っても良いでしょうか。
昔はテレビの端っこに座っていたお笑い芸人が、テレビの主流で、人生観までを説き、タレント人気投票で男女ともトップの方に位置している。
どこか虚飾の、上っ面な人間関係社会と言えるのではないかと考え込むばかりです。
こんな社会では死なんて、最も疎外されるべきものなのでしょうね。誰にでも訪れる人生の最大問題であって、人間、これを考えるから生き方を問うと言っても良いほどのことなのに。
それかあらぬか、「健康老人」、「生き生き老後」、「リタイアー後の生き甲斐ブーム」の風潮には、「死の陰」消すようなものが多いようです。
この馬鹿に明るい社会、「バラ色老後ブーム」の裏側にはこんなことが放置されている。老人病棟、老人保健施設では本当に惨めに人が死んでいました。戦後日本の繁栄を築き上げてきた人々が。きっと誰かが悪いということではなく、死というものを、死を迎えようとしている人々の心への想像力が根本的に欠けているのだろうなと、僕は考え込んでいたものです。










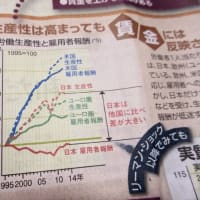
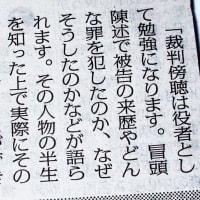






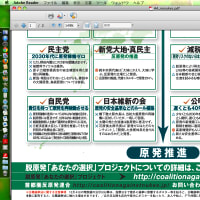





この問題とも案外、深いところで関わっていそうです。
武士の本領は、どんな逆境にあっても生き延びることです。
死を武士の本分という葉隠れは似非武士です。
というか、平和な時代の武士像です。
若者を死に追いやって生き延びた軍部の上層部のうち
何人が責任を感じたんでしょうか?
死の美化は、奇妙に明るい世の中の新しいトレンドとして
受け入れられていく危険がありそうですが・・・?
1.死の問題の多様性と死別の文化
2.死因で見る死の多様化
3.死の概念の変化
4.死の判定―心臓死と脳死
5.デス・ケアという視点
1.死の問題の多様性と死別の文化
今日「死の問題」は多様である。
高齢者にとっては第2次世界大戦という戦争による大量死の記憶がいまだに鮮明であろう。原爆や空襲による被災だけではない。多くの日本の青年が好むと好まざるをえなく、殺される側にも、人を殺す側にも立った。そして今なおアフガン、パレスチナ、イラク…と戦争は止むことなく、殺す者と殺される者を生み出し続けている。怨嗟の声が渦巻いている。
戦後日本は、貧しい生活を体験した後、朝鮮戦争以降は高度経済成長を謳歌し、太平の中にあった。だが、その日常が死と隣り合わせになっていることを民族体験として知らされたのは、6千人を超える死者を出した1995年の阪神・淡路大震災であったろう。2004年から2005年にかけて大水害、新潟県中越地震、30万人を超える死者・行方不明者を出したスマトラ島沖地震・インド洋大津波…自然の猛威の前にいのち、暮らしがいかに脆くあるかを思い知らされた。アフリカではいまだに餓死で死ぬ子どもが少なくない。
また、国内では1995年3月20日の宗教的狂信による暴発であるオウムの地下鉄サリン事件があり、国際的には政治的宗教的民族的対立を背景とする2001年の9・11米国同時多発テロ…無差別大量殺戮というテロ、そして無数の小規模テロが勃発し、無関係な民衆が死に巻き込まれるという解決の見えない事態もある。人間の生死が個々の価値を無視され、道具として扱われている。
その一方で1980年代から「尊厳死」についての話題も賑わすようになった。日本だけではない。アメリカ、オランダ等近代国家でかつ高度医療がもたらす死の問題である。がん等の末期患者への延命治療の是非の問題から、ターミナルケアの見直し、在宅ホスピスの普及へと話は展開している。
救命医療の進歩は著しく、その結果、かつては死を免れた人が生き延びる一方、脳死状態の患者、植物状態の患者が生み出され、死の境界線が見えにくい状況を引き起こしている。臓器移植はそれ以外の治療法のない患者にとっては福音であるが、他方で先端医療は人間としての倫理の限界線を踏み越そうとしている。医療の高度化と専門性の前で普通の人間のいのちが翻弄されている。
アフリカやアジアでは乳幼児の死亡率が依然として高い状況にある。
日本では第2次大戦後急速に保健・医療環境が改善し、乳幼児死亡率の激減と長寿化を達成、北欧を追い越し、未曾有の高齢社会を実現した。それは他方で要介護の高齢者の大量出現であり、病院や施設での死の増加となって現れている。
他方で「自死」は2000年以降、年間3万人という高水準で推移している。縊首、飛び降り、薬物等の手段により、1日に平均して80人以上が死んでいる計算になる。この数字は「日常」という名の戦場で、終わることのない戦死者が日々誕生しているようなものである。経済不況を背景とした中高年男性の自死、鬱病等の心の病の結果としての自死、そして最近ではネットで仲間を募っての集団死がある。
こうした特別な死だけがあるのではない。多くの名も知れぬ普通の死が日常化している。31秒に1人、1日平均2805人、年間102万4千人(2004年人口動態年間推計)が死んでいる。死者一人につき家族や親しくしていた人が10人いたとしたら年間1千万の人が、おそらくもっと多くの人が身近な者の死を体験していることになる。
亡くなる者、死者だけに死はあるのではない。それを看取る者も死を体験する。死にゆく者、それを看取る者、その双方に無数の死の物語がある。そこにはリアルな死がある。
日本人の死亡率は年間では対千人比で8・1である。だが一人の生涯でいえば、間違いなく100%である。その過程や事情はさまざまであるが、死を免れる者はいない。誰のいのちも有限であり終期がある。その意味では平等であるが、その死に方は突然の災害死をもちだすまでもなく、さまざまであり不平等である。
このさまざまな死を受けとめる文化装置として、人類は、民族や宗教によりさまざまに形態を異にするが、有史以来葬送文化を形成してきた。日本人もまた死別の文化として葬送文化を形成してきたのである。
死別の文化を形成してきたのは、死者に対する愛惜はもちろんのこと、かけがえのない家族の一員を喪失したことによる悲嘆であり、家族を喪失したことによる将来への不安等が死によってもたらされるからである。また、死者を埋葬するという物理的な処理、死者なき後の家族が生きる社会との新しい関係づけを必要としたからである。
だが、この死別の文化としての葬送文化がいま大きな揺らぎの中にある。機能不全になりつつあるのではないだろうかという危惧がある。それは死というものが大きく様相を異にしてきているからである。そしてその背景にあるのは家族の変化、医療の進歩である。
「多様化」「自由化」「個人化」の名の下に、日本人の死を受け止める文化装置である葬式は、いま社会的コンセンサスを急速に失いつつある。葬式は地域文化と密接に絡んで展開してきたものだから、北海道から沖縄までの長い日本では地域特性が強く残っている。その変化も一様ではない。
現在葬儀に関してはかなりの変化と多様化が見られる。その変化の一つに「お別れ会」の流行がある。これは歴史的にとらえるならば告別式の独立形態といえる。大正期に「告別式」が登場してきたとき、当時の僧侶はそれを「耶蘇っぽい言葉だ」と言ったそうである。今は「告別式」という言葉自体が古くなって「お別れ会」と言い換えられる時代になった。
元来、日本(とは必ずしも限定できないが)の葬儀は、コミュニティ(地域共同体)が中心となって行うところに特徴があった。しかし、今日では急速に葬儀の担い手が個人化してきている。それに伴い葬儀にもかなりその人らしさ、個性が現れるように変わってきている。
昔「葬儀のことはわからなかったら年寄りに聞け」と言われたものである。しかし、都市部(何も東京や大阪近辺の話ではない)においては、高齢者さえも葬儀のことがわからなくなってきている。
最近よく公民館や消費生活センターから葬儀や墓についての講演を依頼されるのだが、ここには高齢者が多く集まる。60代・70代の方が中心で、その人たちは自分の葬儀について聞きたくて来ている。その人たちに葬儀について聞くと、ほとんど知らない。昔と違って、今の高齢者は、特に80歳未満の人は「戦後派」なのである。戦後、都市化で多くの人が地方から都会に来たが、若い時に都会に出たものだから地方の習俗についてもよく知らない。都会に出てくれば近所のお葬式を手伝うでもない。手伝うといっても受付くらい。ほとんどは焼香に参加するだけだから、ある意味、わからなくて当然なのである。
1960年代から70年代にかけて、ちょうど「核家族化」が進行した頃、日本の葬儀は大きく変化した。葬儀の運営の中心はコミュニティから葬祭業者に替わり、共同体の中で伝承されてきたさまざまな習俗がそこでぷっつり切れてしまった。担い手が葬祭業者となり、葬儀の習俗は、葬祭業者から教えられて、遺族は消費者として行動する形になった。90年代の中期以降、「家族の分散化」が進む中で、葬儀の個人化が加速度的に進み、従来片隅で営まれていた密葬が「家族葬」という名で市民権を得るなどしてさらなる変化をしようとしている。いまもう一つ特筆すべきは地方の葬儀習俗の急激な衰退であろう。葬儀の場所が斎場(葬儀会館)に移動することにより地域コミュニティの葬儀から葬祭業者の手になる葬儀への移行が急激に進んでいることである。
2.死因で見る死の多様化
死亡原因は、03年の人口動態月報年計で見ると、表1のようになっている。
(表1)死因
(1)悪性新生物 309,465人
(2)心疾患 159,406人
(3)脳血管疾患 132,044人
(4)肺炎 94,900人
(5)不慮の事故 38,688人
(6)自殺 32,082人
(7)老衰 23,446人
悪性新生物(がん)が約30%で依然トップである。3人に1人近くががんで亡くなっている勘定となる。一時は不治の病と恐れられたが、早期発見による治癒率も向上している。まだまだ問題はあるが、一時に比べれば、医師と患者の関係ではインフォームド・コンセント(説明と同意)も改善されているし、末期ケアのあり方についても患者・家族の選択肢が拡がっている。
自己決定の伴う「尊厳死」が問われるようになったきっかけは、末期がん患者の延命治療の是非の問題であった。患者の生命の質を問わない、むしろ犠牲とした延命優先主義の見直しであった。医療関係者の努力や世論の高まりを背景にして、患者自身の生活の質とバランスのとれた治療やケアがなされるようになってきたのは評価できる。だが、他方では患者の治療選択権という名の医師の専門家としての治療放棄もまた生まれている。もう一つは、この「尊厳死」が一人歩きしてしまう危険性である。知的障害者、脳障害者の人格や生存権の否定にまでいきかねないとすると、どこかで歯止めが必要であるように考えられる。
がんによる死亡者が多いが、末期の場合それは「予告された死」という特徴をもっている。告知された本人が、その告知による予告をどのように受け取るかという問題がある。
キューブラー・ロスがその過程を「否認と孤立」―「怒り」―「取り引き」―「抑鬱」―「受容」ととらえた。ターミナルケアのあり方も、身体的苦痛、精神的苦痛に対処するだけではなく、もっと根源的ないのちのありようという宗教的要素も加えた「スピリチュアル・ケア」の必要性が提唱されるまでになってきている。
また、残る限定された時間、日をどのように過ごし、後に残る家族にどういう想いを託そうとするのかという問題がある。
それだけではない。家族も死の予告に立ち向かわなければならない。ホスピス・ケアが、死にゆく患者本人へのケアに留まらず、それを看護し、患者本人の死後も遺される家族に対するケアも課題としてきている。
後期高齢者の場合、加齢もあり、そのターミナルはがんの手術による治療・延命というよりは、がんとの共生による穏やかな死という選択が多く、本人も家族もそれを希望することが多い。だがそうでない場合の末期がん患者本人とその家族の葛藤は深い。
死因の2番目と3番目にある心疾患や脳血管疾患は、他の病気で療養していたが末期に疾患が訪れるということもあるが、しばしば突然に発症する。脳血管疾患による死の6割は脳梗塞であり、心疾患による死の3割は急性心筋梗塞である。本人にとっては突然のことであり、家族も動揺の中、数日間看護するだけで死を迎えるということがある。
こうした突然の「予期されない死」の場合、家族はショックのため現実感覚を失うことが多い。事故等の被害者になった場合には加害者に対する怒りとなって現象する。「予期されない死」を受け入れるためには原因・理由がなければならない。それが持病や加齢のためであれば納得もしやすいが、理由が不明な場合には、周囲の健康管理方法であるとか「犯人捜し」が始まる。それが他の家族に向けられたり、家族自身の自責となって現れることも少なくない。
6番目の自殺は、年間死者が3万人を突破して以来新聞でも大きく取り扱われてきた。10代での死因のトップは不慮の事故で2位が自殺、20代・30代ではトップが自殺となっている。40代でもトップは悪性新生物であるが2位に自殺がきている。老年期の自殺も少なくない。特に目を惹くのは、中高年男性の自殺が増えたことである。バブル景気崩壊後の不況、それに伴う社会心理的混乱等に起因して精神的疾病が発症したためと推定されている。現代は大変なストレス社会なため鬱病が多くなっている。自殺者の8割以上は鬱病と関係していると推定されている。
自殺というのは一見極めて意思的な行為に見られがちである。自分の生死の自己決定の最たるものと考えられがちである。しかし、自殺のほとんどが、その人が意思的に選んだ結果ではないと思われる。社会的要因、人間関係要因、精神的要因で追い込められ心的に病を発症した結果、自殺に至るというのがそのほとんどではないだろうか。欝病に至るにはさまざまな要因があるだろう。だが欝病になると視野狭窄をもたらし、死以外の生の選択肢を本人から奪いがちである。
これまで統計だから「自殺」という表現を用いたが、私は自殺でなく「自死」という言葉を用いる。「自殺」という言葉は「自分を殺害する」という意味であるから、倫理的に悪であることを無意識に前提とした言葉である。だから「自殺はいいか、悪いか」という倫理の問題として論じられることがしばしばあるが、そう見ると問題は逸れてしまうように思う。自死という不自然な手段を採るが、その実態は心的疾患に起因する病死に等しい。
だが他方、自死が遺族に与える傷は深い。家族から言い訳を奪う。病気による死の場合は病気に原因を、事故の場合には石や車に原因を求めることができる。それぞれ死の受容は容易ではないものの、原因を死者以外に向けることができる。自死はそれが困難である。そのため家族が自らを苛み傷つく可能性が極めて高い。自死遺族の一人は「急に足元の地面が消えた感じ」とその衝撃を語る。
死因のあれこれを考えると私は思う。人間の身体、心は脆い存在であると。死と隣り合わせなのだと思わざるをえない。
65歳以上の人口が全体に占める割合を高齢化率という。2005年1月現在の概算値は19・6%となっている。地方によっては過疎化が進み、都市部に比べて高齢化率が高くなる。よく「高齢化社会」というが、この「化」が取れて、すでに日本は「高齢社会」となっている。
65歳以上の死が全体に占める割合は80・7%(03年)である。死亡者の5人中4人が高齢者である。特に80歳以上が46・2%で、今この80歳以上の死亡者の比率が高齢化に合わせてどんどん高まっているのが特徴である。
このことはあたりまえのように思うかもしれない。「年寄りが死ぬのが最も多くて何が不思議なの」と思うだろうが、これは日本の長い歴史を見れば最近のことなのである。昭和の初期の頃は80歳以上で亡くなる人は全体の3~5%というところであり10%を超えることはなかった。
今は子供が成長し、少年期、青年期、成年期、壮年期、老年期があって、そしてその先に死がある―と理解されている。いまは老年期も65歳から75歳未満の「元気な」前期高齢者と75歳以上の「介護を必要とする」後期高齢者に区分されるようになった。しかし昔の場合は、必ずしも人生計画の最後である老年期に達した後に死があると理解されていたわけではない。もし老年期までを人間の生全体として考えるならば、過去の日本人の多くは最終期まで到達しない「途中での死」が多かったのである。
中世来の無常観というのは、簡易にかつ卑属に解釈するならば「死はいつ誰に起こるかわからない」ということであったろう。日本人の伝統的な死の観念というのは老年期の先にあるものではなく、いつ、誰に訪れるかわからないものとして理解されてきた。現実に日本人の死の状況というのは半世紀前まではまさにそういうものであった。
それゆえ65歳以上の死が8割を超し、かつてはレアケースでしかなかった80歳以上の死が半数近くなることによって、「納得しやすい死」が増えていると言えるだろう。人生の活躍期を終え、「もう歳だから」と本人も家族もどこかで言い訳でき、納得しやすいからである。もちろん高齢者の死も家族に喪失感をもたらす。特に遺された配偶者には喪失感が強い。
また次のようなこともしばしば見られる。後期高齢者の死の場合、多くの場合、その看護、介護の期間に家族はいずれ来る死を予期していることが多い。この長い予期の期間に気持ちも準備してソフト・ランディングとなるケースが少なくない。現在の高齢者、特に80歳を超えての死に際して行われる葬儀で、重苦しくなく、どこか平穏な雰囲気を感じられることがしばしばあるのは、こうした事情によるだろう。
逆にいくら高齢者の死が全体の8割を超したとしても、2割近くの死はそうではない。不慮の事故による死者も約4万人。がんによる死が多いことからわかるように、死は高齢者以外にも、突然にも訪れる。しかし、突然の死、あるいは若くての死は、今は例外のケースになるので、そういうものに対する対応力がなくなってきている。これは各個人の覚悟の問題ではなく。死者が出たときに、その遺族をいかに手厚くフォローし、ケアする社会の態勢のことである。そうした葬儀では遺族・関係者の悲痛が露呈される。あるいはその悲哀が遺族の胸に抑え込まれる。
人生に充実感をもち、充分な長さを生き抜き、健康で病院や施設の世話を受けず、家族にあまり負担をかけることなく、できるだけ自然に死ねたら本人は満足だろう。家族もそれなりに介護や看護ができて静かに看取ることができたら納得しやすいだろう。でもそんなに都合のいい死ばかりではない。
そもそも人生に充実感をもてるということ自体が難しいし、いい人間関係、いい家族関係を作るのも難しい。どこかに欠けがあるほうが普通だろう。また、長生きしたからいいわけでもないだろう。単に死が、本人の生活の質を無視され、引き延ばされることもある。看護や介護で家族が体力的にも精神的にも疲労困憊に陥ることだってある。あるいは看護や介護する人がいなく尊厳を無視されて施設で飼われるようにして終末期を生きなければいけないこともある。看護も介護もなく「孤独死」するケースもある。
いい死に方というのは結果としてあっても目的とはできないものだろう。なるがままに人は死ななければならない。それは生き方が自由にならないのと同じことである。
葬儀の習俗には死穢観念が色濃く反映しているが、それは死をリアリティのあるものとして、どの世代においてもとらえられてきたからということに起因すると私は考えている。確かに、同い年の人が死ぬと死に巻き込まれないように豆を食べて「年違え」するなど、徒に死を怖がっているように思える。だが、そうした俗信、死穢観念の背後には、死がいつくるかわからないという緊張感があったと思われる。かつてと現在の死の状況には大きな違いがあり、現在の死の態様にも大きな問題がある。
いまは死ぬのは高齢者、死ぬ場所は病院、葬儀の場所も自宅以外の斎場等で行われることが多い。死が生活の中から離れ、別処理化されていっている。葬儀の担い手もかつては地域共同体であったが、これも葬祭業者に替わってきている。管理される死、そして消費される葬儀、これが現代日本の死と葬送の一つの局面である。
北米では「葬祭業」のことを近年では「デス・ケア産業」と呼ぶことが多い。人間の死後に関係するサービスの総体を指して言う。
ホスピスでケアの対象が患者つまり本人だけではなく家族のケアが大きな問題であり、患者本人の死後は遺族となった家族のケアも視野に入れられてきている。同様に、葬祭業においても「死後」だけではなく、本人と家族の生前の関係を引き継いでケアするものでなければならないだろう。とするならば日本においてもデス・ケアという視点で葬祭業のあり方を考えることは重要なものと言えよう。
北米ではデス・ケアを主として死者本人に対するケアである遺体のケア、つまりエンバーミングと、遺族に対するケアであるグリーフケア、という2つの視点から考える。これは極めて示唆的である。
葬儀のケアの対象は死者本人とその家族である遺族だからである。この2つのどちらかが欠けても、あるいはどちらかに偏っても葬儀というのは不完全であるように思う。そしてこの2つの主人公は重なり合っているのである。
葬儀が死者本人のためか、遺族のためか、というのは実は不毛な議論なのである。死者本人のために行われない葬儀は遺族にとっても意味のない葬儀であるからだ。近年の葬儀を巡る混乱の一つの要因は、葬儀を何のために行うか、という自明なことが、必ずしも自明でなくなっていることにあるように思う。
日本の古来の葬儀にしても、このことは自明かつ明確であった。
死後の通夜は、遺族関係者は死者に食事を供したり、寝ずに守ったりして、死者にひたすら仕えた。そしてそれは同時に、遺族が死を受け入れるための準備作業であった。
遺体を浄めるための湯灌は、死者の罪障を浄め、葬りの準備をすることであり、遺族はこのために自ら作業に加わったのである。
死者の往生、成仏を願う葬儀式は同時に遺族の安心のためでもあった。
葬儀後、四十九日までは中陰壇で、それ以降は仏壇で、遺族は死者をひたすら供養する。それは同時にそれは遺族のグリーフワークとして営まれた。
日本の葬儀を見直してみれば、それがひたすら死者のために営まれ、それが同時に家族を喪失して深い悲嘆の中にある遺族のためにも意味深い営みとしてあったことが明確である。
森岡恭彦(東大医学部名誉教授『死にゆく人のための医療』NHK出版)は、死に至るプロセスを「生物学的死」といい、葬儀を「社会的死」と分類している。だが、それは正確ではない。そもそも医学的死は個体としての死の判定であり、生物細胞としての死は個体の死以前からも発生するし、個体としての死以降も生物細胞はしばらく生きる。さらに医学的死に至るプロセスにおいては本人とその家族の葛藤、看取りがあるのであり、生物学的に留まらない人間的なプロセスとしてある。
また葬儀という医学的死の後のプロセスを「社会的死」と規定するのも大雑把すぎるように思う。確かに死者の供養・埋葬、死亡届の提出、遺産相続等は法律的には「死後の事務処理」という概念に包摂されるものである。社会的に生きた人間であるから当然にも社会的事務処理が伴う。だが葬儀とそのプロセスは精神的・宗教的・文化的な営みとしてもある。
医学的な個体の死の判定が点であるのに対して、葬儀は、遺族が死者を弔い、死を受けとめるために時間をかけて営む心的プロセスを内包している。
だが、死者と遺族にのみ焦点を合わせると、これも従来の日本の葬儀ではない。主要な要素であるがそれだけではない。死者と遺族に限定すれば、それは喪家の個人的な営みであるが、日本の葬儀は、それを運営する者として地域共同体が不可欠の要素としてあったことも記憶しておかなければならない。
死者・遺族・地域社会…という関係は並列的なものではない。死者を供養する者として遺族がいて、その遺族をケアする存在として地域社会が存在するという構図である。
それゆえに葬儀には死を社会的に告知するという社会的機能はあるが、地域社会の関わりの最も大きな精神的要素は「共感」なのである。
そして90年代後半以降特に顕著な日本の葬儀の変化は、地域社会の関係の衰退という点である。勢い社会性を失い、個人化の方向に進まざるをえないのである。
そして今、死者と遺族を有機的に結びつけていた家族という紐帯、宗教的関係もまたあやふやなものになりつつある。
葬祭業がデス・ケアのプロフェッショナルであろうとするならば、葬儀の原点を再構築し、葬儀を意味あるものにしていく必要があるだろう。
※四章の「死の判定」については専門的な内容なので割愛させてもらいました。(ネット虫)
この方の見解はハッキリしませんが、僕とは違うようです。
僕は儀式やデスケアはいらない。広く「葬儀の文化」はあると思うが、僕が若い頃から考えてきて、同居して看取った父母から学んだ積もりのその「文化」はこういうことでしょうか。
死ぬ時までに大なり小なり子どもに迷惑をかけるのは仕方ないとして、葬儀などではできるだけ負担はかけたくない。ただ焼いて、どこか希望する「自然」の中へ返してもらえば、それでよい。むしろ葬儀の金などは彼らに残しておきたいと思う。
そして何よりも僕が帰っていくこの「自然」、これをもっともっと身近で、好きなものにしていきたいと考えている。だから、そのすばらしさをいっぱい味わいたい。
遺された人たちの問題のようです。
もちろん母のように、死後の供養をのぞんでいる人も
多いでしょうが、
それも遺された人たちにゆだねるわけですから、
思いとおりになるかどうかはワカリマセンね。
一番の悪弟子は仏陀の弟子たちでしょうか?
法然の弟子たちも遺言にそむいています。
他人の死と自分の死は、まったく別物ですから、
知識だけでは心が落ち着かないようです。
受け入れるには何が必要なのか?
少なくとも、私は文科系さんのようには考えられないようです。
このことはもう、連れ合いともかなり話し合い、考え尽くしてきたことです。
あなたの言うようなことがあるので、遺言をしたためます。遺る者には「世間」があるし、世間体からも自由ではあり得ない。次男ですが両親と同居して看取ったので、そのことは遺った我が身としてつくづく感じたもの。父はともかく、母の葬儀は母が不本意なものにしかならなかったと、思っているぐらい。ただ父の葬儀でも、率直な性格であった父に相応しく、色々考えました。祭壇は真っ白な花だけ、その中心は写真以外は(模型の社とかなんだとかは)無しなどなど。それでも父母とも、知らぬ間に葬儀屋が余分なものをいっぱい付け加えているんです。あんなのはもーまっぴらです。
さて、いやしくも「文化としての葬儀」というならば、たった一度の大切な生を終える自分に相応しい「葬儀」でこそあるべきでしょう。違いますか?僕はそれこそ必死にそう希望しますよ。
遺った者との折り合いを付けるためには、遺言で指示を出し、身近な人誰にでも見せられるようにしておく。年賀状のように「さようなら」を書いておき、「葬儀なしの葬儀」の直後に、遺族が必要な所には「弁解できる」ように自分で準備万端整えておく。
ぼくの「葬儀」には、以上のようなことも加わります。
僕は何故か、小学5年生ぐらいから死を強く意識していた。怖かったです。「自分が、永遠に無になる」としか捉えられませんでしたから。くっきりと「死の抽象画」のような怖い夢も、成年に至るまで何度見たことでしょう。それでも、そういう解釈以外の道は、不自然な「アガキ」にしか見えませんでした。それでとにかく、納得する人生を送りたかった。
まーそれはできたと思います。それでも怖さはなくならなかったけど、人とは逆に歳も取り色々考え、振る舞ううちにだんだん減ってきて、最近はほとんどありません。
以上の変化は一体何なのかなと考えています。
まず「認識」としてはこうです。永遠の無って、意識もないということだから、それ自身では全く悲しくも、辛くもない。何も感じずに、ただ無という状態だけである。これを恐れるというのは、今が生きていて、意識を持っているという状態があるからというだけのことだ。
こういう「認識」よりも僕に大きかったと思われるものがあります。自分の生をどう振り返ることができるかということ、生きてきた姿勢のようなことです。言うならば「死生にまつわって他人には何も期待せず、自分一人がぽつんと立っていても、それで満足できるか」というようなことです。「そういう心境、状態で人生を十分に楽しむことができただろうか」と言い換えても良い。こうして僕の場合、どうも答えは「人間関係の(自己内)処理」にあったようです。「他人が関わってくる形でしか幸せ観を持てない人は死に関して自立できない」とでも言いましょうか。
本日ここに書いたことの上で、今まで僕が上に書いてきたことが存在するというわけです。