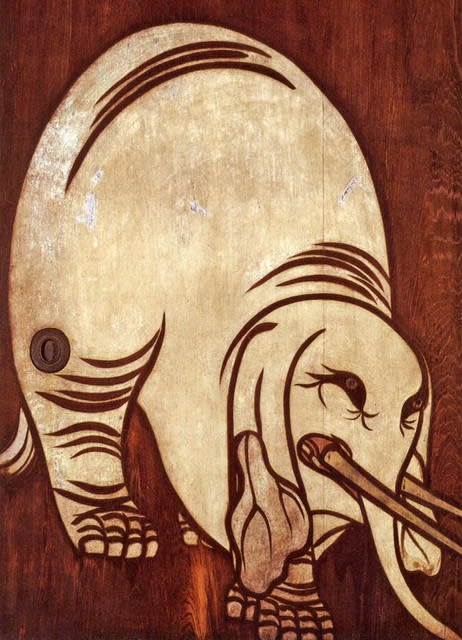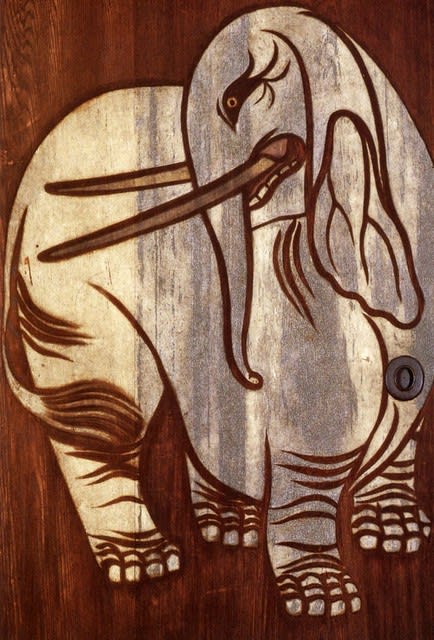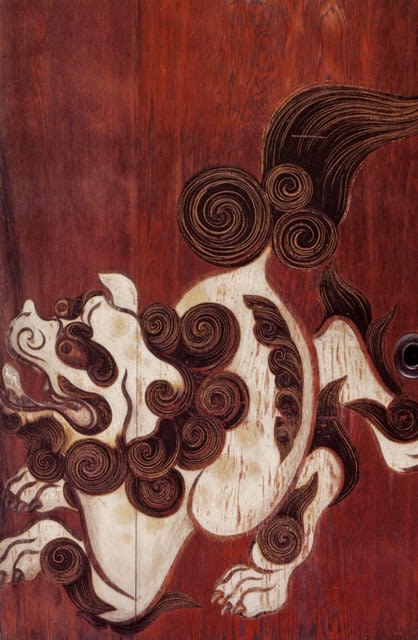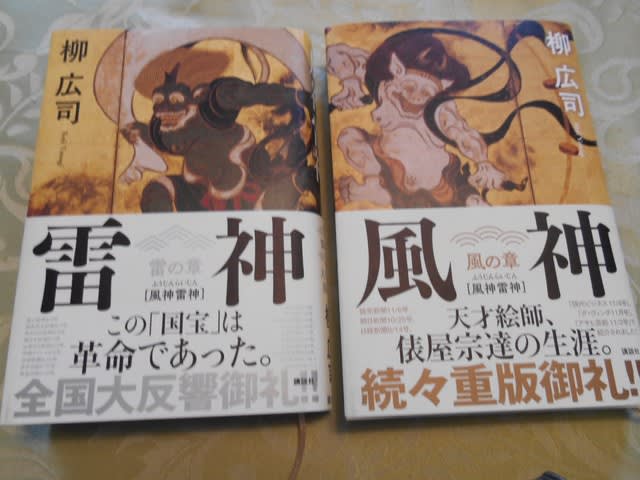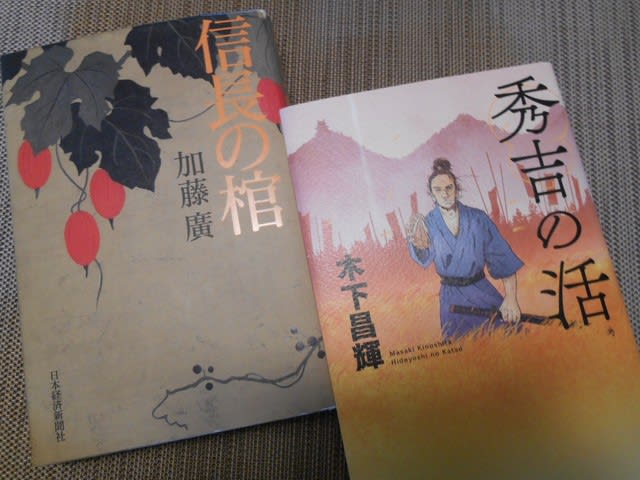雨の今朝です。
断続的に~ 「強く」、「柔らかく」
叩きつけるように降ったかと思うと…音もなく?静かだったり
梅雨の雨にしては、表現力がありすぎる。
ガラス越しから眺めから、思い切って全開にして外の景色を愉しむ。
天気のいい日とは、違った趣の景色になります。
それぞれの「樹」の葉が、いきいきとしているんです。
遠くから飛んできた、埃、細かな砂…こびりつているのを
雨が落としてくれる。
普段よりも格段に、綺麗に見えるんです。
これが雨の朝の 正面から眺められる庭の樹々~
「緑色」の競演です。
同じ「緑」でも、樹によって、個性の違いを表現しているのです。
その競演を眺める「こちら側」では、見事な緑のグラデーションなのです。

今は 雨の中ですから、太陽の光線を受けていません…
太陽光線は、その力で 対象物の「色」を変えていきます。
まさに、「七色変化」の演出者なんですから。
この画像からでも、緑と言っても、唯の緑ではなく、「白」が目の中に飛び込んでくるでしょう…
時間により、角度により 変化していくのです。
この変化が また 楽しいのです。
この画像の中に いったい 何種類の「樹」があるのだろうと~ と。
ちょっと数えてみました。
「ニセアカシア」「欅」「シマトネリコ」「ハナミズキ」「つばき」「サンシュウ」
「更紗ウツギ」「蘇鉄」「羊歯」「ヒメウツギ」「レンギョウ」「柴」「コデマリ」
「紅花トキワマンサク」「ユーカリ」「ネズミモチ」・・の樹
その傍に、「ルリマツリ」「蛍袋」「クリスマスローズ」「アイリス」
「ミズヒキ草」 こんなにもの種類で この庭も 賑わっています。
特に、雨の中で 際立って 目に飛び込んでくる のが
白い粉を吹いたような 「ユーカリ」の葉
綺麗ですね~… 細くて白い茎の線 これが効いています。

次に 右側の「ハナミズキ」の花が散った後、葉が変色していきます。 緑から暖色系に。
「緑」の中に ひとつだけ これって存在感ありです。

造形的に いいのが~ これ。 「レンギョウ」
整列した「葉」の見事さ! 茎の赤との対比も素敵です。

そして 何より これから夏に向かって 伸びて 伸びて いく 「ニセアカシア」の葉
夏になるまでには、この周辺を 覆ってしまいます・・・・
グリーンカーテンなのです。
去年までは 木の枝が多すぎ 日差しをまったく感じさせないほどの葉の茂り方だったので
思い切って、ばっさりと枝を落としました…
その結果、周囲の樹や、花たちが 大きく成長し、花を咲かせる結果にも。
「葉」の太陽光線を遮る力って 凄いものですね。
そんな アカシアの葉です。

アカシアの雨に 打たれて~ そのまま 死んでしまいたい ~
昔懐かしい 西田佐知子さんの あの 詩が 聴こえてきませんか?
「雨」って、 どしゃぶりや、洪水まで 成長するのは 勘弁ですが…
しっとりと、静かに 緑色を いろいろと変化してくれる こんな雨なら
「雨」も素敵ですね。
山の端から 雲が上りはじめました…もうすぐ 雨も止みそう。