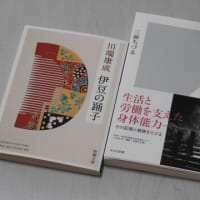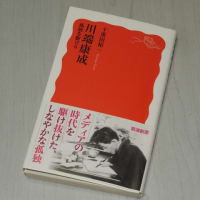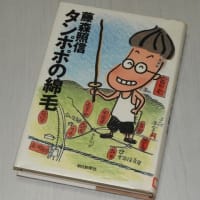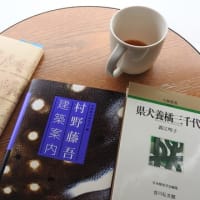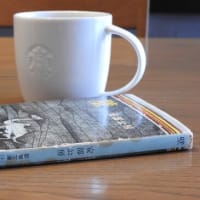■ 「消えゆく火の見櫓」とは何とも切ないタイトルだが、実態なのだから仕方がない。
(再)松本市高宮北 4脚8〇444型 撮影日2021.07.04
松本市高山北、国道19号沿いに立っているこの火の見櫓は昭和5年に建設され、松本では最も古い部類の1基だが、近々撤去されると聞いていた。撤去されてしまう前にもう一度見ておこうと思い、今朝(4日)出かけてきた。
櫓が下方に直線的に広がっていて、末広がりになっていない。柱材に等辺山形鋼が使われている。丸鋼や平鋼を曲げることは容易だろうが、山形鋼を滑らかにカーブさせる技術が建設当時にはまだ無かったのかも知れない。このようなことは文献を探し、じっくり調べれば分かるだろう。
梯子段の間隔の寸法と段数によって見張り台の床面のおよその高さが分かる。この方法で13メートルくらいだと分かった。

屋根と見張り台を見上げる。見張り台の床に方杖を突いている火の見櫓は珍しくもないが、屋根に方杖を突いているのは珍しい。現存する火の見櫓は昭和30年代に建設されたものが大半だが、それらにはこの火の見櫓のように方杖を突いているものはまず無いだろう。平鋼を交叉させて設置した例も他に見た記憶がない。手すり子の飾りは必要なものではないが、丁寧なつくりだ。仕事と割り切って出来るものではない。職人気質ということばがピッタリの仕事だ。手すり端部の処理も然り。

踊り場には半鐘があるが、見張り台の半鐘は既に無い。見張り台に吊り下げてあった半鐘はもともとお寺のものだったようだと、偶々居合わせた分団長(*1)から伺った。『あ、火の見櫓!』で、半鐘について、**よく響いて音が遠くまで伝わる小さな梵鐘、小鐘を火の見櫓でも使おうということになったのではないかと思います。半鐘は梵鐘と似ているというより元々同じものでしょう。**(59頁)と書いたが、全てがこの推測通りかどうか分からないが、梵鐘の転用が実際にあった、ということだろう。この火の見櫓の撤去された半鐘について、取材する機会があるかも知れない。


構造材は全てリベット接合されている。ただし柱脚は例外的にボルト接合。なぜ? 分団長に、この火の見櫓はもともと詰所の左隣に立っていたが、水路改修工事に際し、現在の場所に移設されたと伺った。なるほど、そういうことだったのか。
残念だが90年の長きにわたり地域を見守り続けて来たこの火の見櫓は今月(7月)撤去される・・・。
*1 名刺156