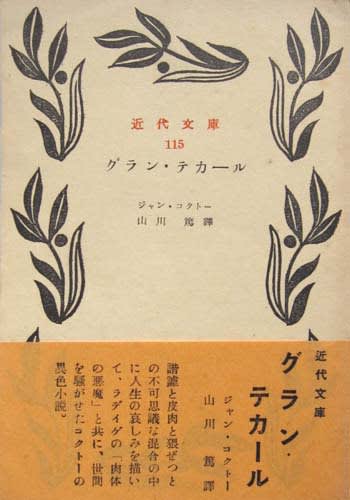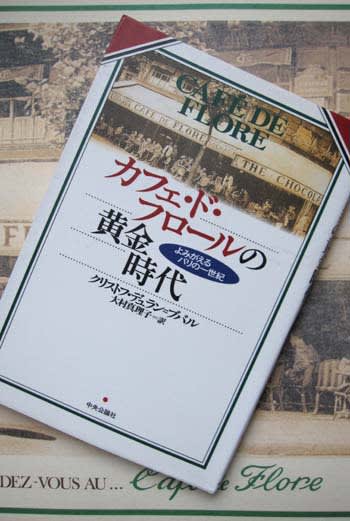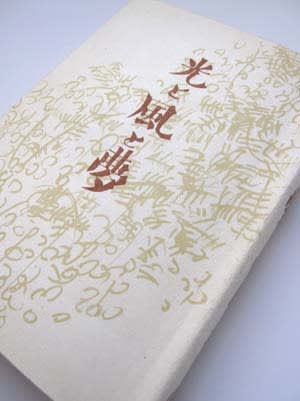物語のすべてが「内的独白」ですすめられるこの本は、1887年、パリで発行された当時はさして注目されず、
「埋もれた文学」の憂き目に二度もあったが 『ユリシーズ』 の著者ジェームス・ジョイスはこの本にいたく感動し、
初めて目にした1903年から十数年後の1917年にはデュジャルダンへ熱いメッセージを送っている。
内容は、学生のダニエル・プランスが女優レアに恋をし、恋の夢を思い描く。
彼女のためにお金を与え、馬車でデートをするがレアはダニエスほどの気持ちはなく、
次のデートの約束をしながら彼はレアに二度と会わない気持ちになって物語は終わる。
現在でもどこかにあるような出来事だけのことだけである。
しかしこの本の魅力は、内容よりもむしろデュジャルダンの「書き方」である。
読点「、」の多用が不思議な魅力を放ち、読者にことばを訴えかけてくる。
「かなたの空気の美しさ、影、うれい、風情、夜の美しさ、暗い灰色の空にあちこち宵が入り混じり、そこに点々とみえる星、水玉みたいに、ちいさく揺れて、しずくのような星、‥‥‥」 (本文より)
「内的独白」なので書かれているのはダニエスの「現在の意識」である。読みはじめれば四月のパリの夜をダニエスと一緒に歩き始め、パリのかぐわしい春、宵の魅惑などを体感することにもなる。
刊行されたものの埋もれてしまい、ジョイスの『ユリシーズ』により浮上し、その後また忘れ去られて
1960年代にフランスのヌーヴォー・ロマンの台頭期という文学状況で再浮上した経緯をもつ『もう森へなんか行かない』は青春のほろにがさ、
やるせなさを記した小ロマンといえるだろう。
原題は 『Les lauriers sont coupes』 で 『月桂樹は切られて』 だが、
英訳のこのタイトルに変えたのは詩的感応が濃いとの出版社の意向により英訳版にしたという。
どちらも青春の切ないはかなさを思わせるタイトルである。
1971年 都市出版社 鈴木幸夫・柳瀬尚紀(訳)