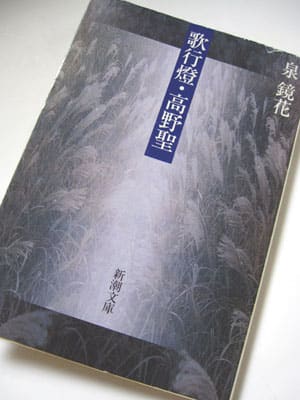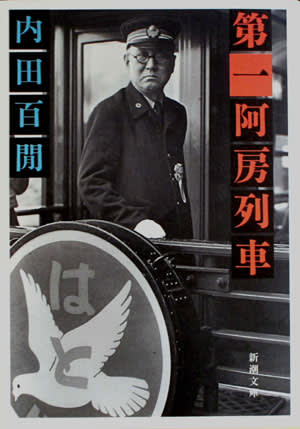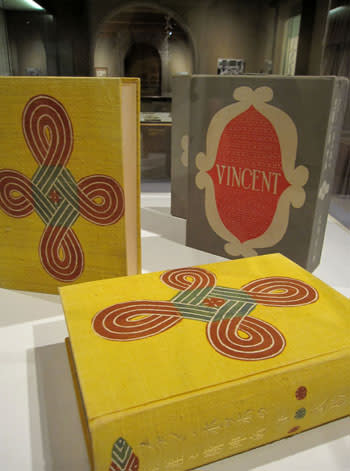短い生を駆け抜け、つかの間の青春のうちに逝ってしまった久坂葉子。
作品から垣間見えるのは久坂葉子が自分を偽らないそのありのままをぶつけてくるひたむきさである。

ここに収められているのは『ドミノのお告げ』『華々しき瞬間』『久坂葉子の誕生と死』
『幾度目かの最期』の4篇。
『ドミノのお告げ』は「落ちてゆく世界」を改題した作品で芥川賞候補になり、
没落した名家の日常を描いている。
栄華を誇った家は「私」が生まれた時はすでに斜陽の影がさしていた。
昔気質の父、宗教に没頭する名門の出の母、病身で入院している兄、
家族を突き放したように音楽に没頭する弟。
生活を支えていかなければならない「私」は家の骨董を売ったりアルバイトをしてしのいでゆくが
名門ゆえの世間体が家族に重くのしかかっている。
不安を孕んだ家族は先が見えない今を生きていく。
『華々しき瞬間』 南原杉子がもう一人の自分として別名「阿難」と称し
喫茶店カレワラでめぐり会う男と女の交錯する恋の心理を描く。
装う自分がピアノの音色の中で得られた一瞬の幸福。
『久坂葉子の誕生と死』は 作家・久坂葉子の足どりを綴った記録。
作家・久坂葉子の足どりを綴った記録。
そして『幾度目かの最期』は遺稿となった作品で
彼女が生きる望みを絶つ原因ともなった家のこと、恋愛のすべて、作家としての苦悩などが
ほとばしるように書かれている。
この作品は1952年12月31日、午前2時頃に書き終えている。
そしてその夜に彼女は阪急電車の六甲駅で自らの生に終止符を打った。
21歳。この作品を「全部本当のこと」と告白し、自分を罪深い女と結んで。
久坂葉子。名門の出で、芥川賞候補にものぼったその容貌はエキゾチックで、
ターバンのような帽子にたばこを手にした彼女は、
当時でも新しいタイプの女性であっただろうことを感じさせる。
そして大晦日の自殺。
傷つきながらも自分に忠実であり続けた彼女は鮮やかな光芒を残して逝ってしまった。
しかし作家・久坂葉子として作品を深め、
人間・川崎澄子(本名)として生きることをして欲しかったとも思わずにはいられない。
黒いリボンがかかった額の中に入るにはあまりにも早い年齢なのだから。