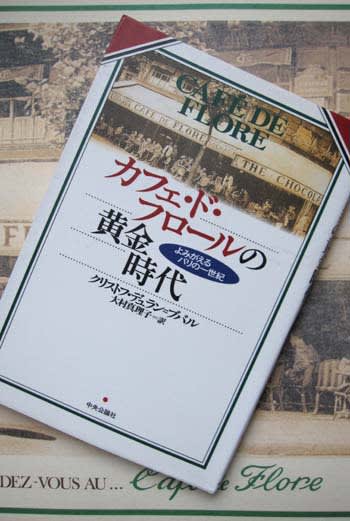著者クリストフ・デュラン=ブバルは、フランス「カフェ・ド・フロールの」最盛期を築き、名経営者であったポール・ブバル氏の孫である。
店に訪れた人々のエピソード、祖父の経営でひときわ輝いたカフェ・ド・フロールを語り、
そこに様々な人生があった黄金期の時代へ導いてくれる。1998年 中央公論社
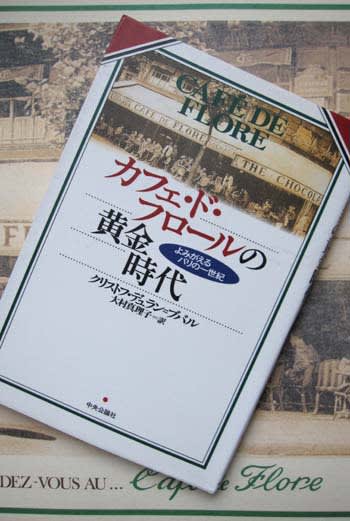
1884年。カフェの建物に記されている年号である。
作者の祖父ブバル氏は1938年にフロールのオーナーになった。
青年の頃はカフェレストラン「 屋根の上の牡牛」で働いていたという。
ここに訪れたアポリネールは毎日のように訪れては友と議論を交わし、前衛機関誌「ソワル・ド・パリ」を発行していた。
そして詩人のフィリップ・スーポー、また後にはアンドレ・ブルトンもフロールを訪れている。
時代は戦争をはさみフランスは激しく変化している。
若者たちは夢を語り、新しい芸術を創っていくエネルギーに満ちていた。
文化の華は開きサンジェルマン・デ・プレはその中心地となってゆく。
ピカソも古くからフロールに来ていた一人であり、サルトルとボーボワールが2階を
自分達の応接室のようにしていたという有名なエピソードをはじめとして
画家、詩人、音楽家、舞踊家、映画関係者、評論家、編集者、政治家、
そして他国の王女…と名が知られる人々がここでくつろぎ潤う時間のながれに身を置いていた。
そしてブバル氏の経営を支えたギャルソン(ボーイ)、パスカルは有能な従業員で
教養と節度ある人物であり全顧客から絶賛され、周囲の信頼を得ていた。
時を経て、のちに彼からの感動的な手紙でブバル氏はパスカルとの永遠の別れを知る。
マスコミは、時代を作る地としてサンジェルマン・デ・プレを取り上げ、フロールの店先では映画の撮影も多くなっていく。
ジャン・コクトーの映画「オルフェ」の詩人のカフェはこのフロールをモデルとし、ルイ・マル監督の「鬼火」もここで撮影された。
時代と人は動き続ける。
フロールは1968年の5月革命の喧騒を聞き、有名・無名にかかわらず多くの人々が去来し、
思いがけない事件や忘れらない出会い、ドラマがここに舞い込んだ。
ブバル氏は、自分の時代に心地よいテーブルを求めてやってきた客への愛着を胸に1985年、次のオーナーへこのメゾンを任せた。
伝統の慎みと栄光の輝きを多くの人々にもたらした「カフェ・ド・フロール」は、精霊(人間をさす)が
そこに入れば誰もが王子であり、友人であると著者は最後に結んでいる。