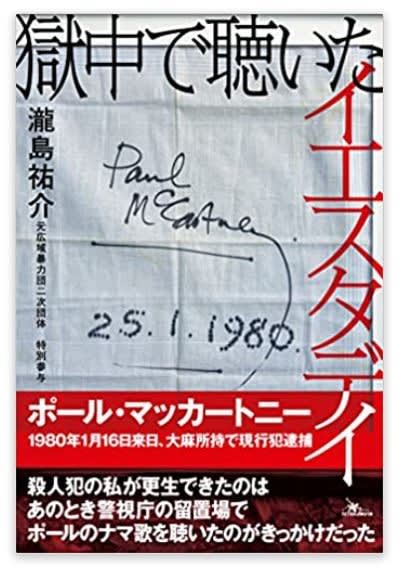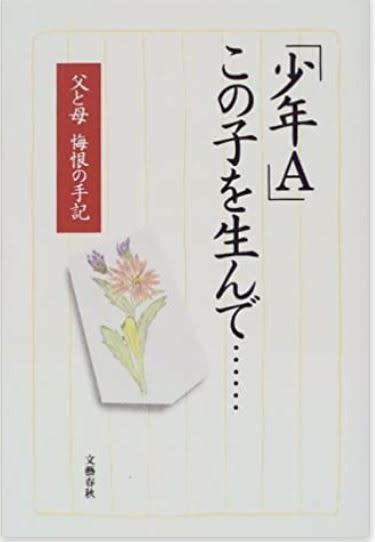この頃、年を取ったせいか、昔のことを思い出す。
最近は、たまたま図書館で「巴里に死す」を見つけて読み始めたのだが、もしかしたらそれがきっかけかもしれない。
東京に越してきてから住んでいた家のそばに、天理教のお寺があった。(あれはお寺というのかな?)
芹沢光治良の「人間の運命」では、天理教のことが書いてあるという記憶があったので、なんとなく意識してその前を通っていたが、今思うと、一度もそこに出入りする人々を見たことはなく、そして、私の人生の中で天理教の人には会ったことも話したこともない。
全く存在感がない宗教だった。ただ、そこに建物があり、門に「天理教」と書いてあったことだけを覚えている。
あれは、私が20代の頃で、高校を卒業してからはまだ数年しか経っていなかったのだ。だから記憶も新しかったのだろうけど、それ以来、天理教に関する物事に遭遇したことは一度もない。
天理教はともかく、「巴里に死す」を読んでいると、主人公の伸子が結核でスイスのサナトリウムで療養している。あの時代は、結核をそうやって治すしかなかった。特に治療法もなく、寒いところでなぜか窓を開けっぱなしにしている。冷たいきれいな空気を吸っていると良いということだったのか。そして、治る人もいたし治らない人もいた。が、治らない人も多く、不治の病と言えた。
結核は人に感染するが、感染した人が急に亡くなるわけではないし、感染しない人もいたようだ。感染しても慢性的に病状が進んで行き、重症にならなければ快復するが、数年のうちに次第に悪化していくとほぼ助からない。恐ろしい病気ではあるが、今の新型コロナほど厳重に隔離などはしていなかったようである。
結核患者が妊娠したら、堕胎したほうが良いと考えられたのは、患者の体力が消耗してしまうからで、子どもが感染するからということではないようである。生まれたあとも、母親が育てることはできず、人に育ててもらうのは、子供への感染を避ける意味もあるものの、母親が自分の結核を治すことに専念しないといけないからだろう。
それで、「巴里に死す」を読んでいたら、スイスのサナトリウムの場面で、私はトーマス・マンの「魔の山」を思い出していた。あの本は文庫本でものすごく厚い本だった。それを夏休みかなんかにかなり読み進んだものの、結局最後までは読まなかったと記憶している。
しかし、あの「魔の山」は何で読み始めたんだろうか?と思う。
それで、今回「巴里に死す」の後ろについている大江健三郎の芹沢光治良についての文を読んでいたら「魔の山」のことが書いてあった。やっぱり連想するのが当たり前なのだろう。
それから、「巴里に死す」の中で伸子が、ジイドの「狭き門」のことを書いているが、その前から、私は「伸子」の精神が、ジイドの「狭き門」の主人公女性と共通していると強く感じていた。
私はジイドの「狭き門」も読んだことがあるが、なぜそれを読んだのかも不明である。これは実家に世界文学全集があったのだが、読まなかったものも多々あるなかでどうしてもこれを選んだのだろう。
当時私は芋蔓式読書法をしていて、読んだものの中に出て来た小説を読み、またそれに関連した小説を読むと言うのをしていたのだった。
私は「巴里に死す」を読んだ記憶は全くないが、ここから芋蔓に「魔の山」や「狭き門」が出てくるのだ。まさか「巴里に死す」を読んでいたわけではないとはおもうのだが・・・。
あ、そうだ。今回はそのことを書くつもりではなかったのだ。
私は当時、2階の自室の窓際の屋根の上にクロッカスの球根を1つ育てていた。そのクロッカスには「シルビエ」と言う名前を付けていた。クロッカスは紫で白い線のある花を咲かせた。ふっくらとした花びらを開き、中には黄色いめしべとおしべがあった。その姿は神秘的だった。
私は当時、ハンサムな同級生にあこがれていた。その人は色白で彫りが深く小柄で、西洋人の少年のような容姿だった。私は心の中で彼を「美」と呼んでいた。
そして、なぜかそのクロッカスをその少年として見ていた。そのクロッカスになぜ「シルビエ」と言う名前を付けたのか記憶がないのだが、なぜかクロッカスの記憶とともに「魔の山」を連想するのである。
しかし、魔の山の主人公は「ハンス」というらしいし、その人に私があこがれるわけでもない。シルビエというのは一般に女性の名前らしいが、私はなぜか少年の名前として、それを花につけたのであった。テレビにでも出て来た少年から名前を取ったのかな?
「シルビエ」でウェブ検索すると、人の名では「シルヴィ」というのが出てくるが「シルビエ」はあまりない。「シルビア」というのは女性のなまえでよく聴くが、私は「シルビエ」と記憶している。
クロッカスが咲くのは春休みなので「魔の山」を読んだのは冬休みか春休みだったのかもしれない。
これらのことは、実家の天袋にある昔の日記を見ればわかりそうだが、もはや太った老婆には、天袋に登ることは不可能かもしれない。