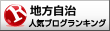自民党が農家所得を倍にするとブチ上げた。意欲のある農家・攻めの農業には支援をするということである。意欲があるとは規模を拡大することである。TPP参入を前提にした、農業政策の方向を示そうとしているのである。
規模拡大は、どんな農業にあっても農業の本質、生命を司るエネルギーの生産には無関係のことである。規模拡大をしても、単位農地面積当たりの生産が増えることはない。むしろ減少する。
ただ単位労働あたりの生産量が増えるだけである。それは一定の規模までは有効ではある。ある規模を超えると、生産コストがかかりリスクが高くなるからである。その規模は、農業の種類や地域の風土や個人の能力や考え方によって異なる。規模拡大は資金の投入と、化石エネルギーの投入の増加が前提になるが、それが上記のネックになる。
攻めの農業とは、日本の農産物は品質が良く、特に東南アジアでは評価が高いので、輸出をしようというのである。とても高価なイチゴやナシなどを、富裕層をターゲットにして輸出しようというのである。
僅かに成功したかに見えても、中国との関係が石原慎太郎が一方的に尖閣を買うぞと言い出して以降、どれもゼロに近い。上手く売れていた台湾にしても、嗜好や評判などでどうにでもなる、極めて不安定な需給関係にある。更に、原発事故で一昨年は全く、日本の農産物の市場は閉ざされてしまった。攻めの農業とは、僅かな評判や事故などで、皆無に近い状態になってしまう、極めて不安定なものである。
いずれにしても、政府が言う攻める農業・輸出できる農業が、金額や生産量で日本農業の主軸になることなどあり得ない。極めて限られた農家が生産する、珍品に近い製品である上に、ちょっとしたことでほとんど売れなくなってしまう。
十勝の長芋は、味も品質も高く台湾に結構な数量が輸出されている。ところが、長芋は連作ができない。豆やジャガイモやキャベツなどを毎年作り変えて、5年目ほどでまた同じところで作付することになる。つまり、豆やジャガイモやキャベツなどが売れなければ、長芋は生産できないのである。
政府は農業の基本すら理解せずに、攻めの農業や規模拡大を進めようとしているのである。農家所得を倍にするという政策は、農家にお金をばら撒くことである。農家にばらまくのではなく、農産物の価格支持などに使用されるべきである。
日本の農業政策は、農家に金は出すが農産物には金を出さない。サボタージュをする農家も、様々な工夫をする農家にも、兼業農家にも均等にばら撒くのである。そのことが、農家の生産意欲を削ぐことにつながっている。
規模拡大や意欲のある農家の論議の中には、食糧の自給率を高める論議や食の安全論議が抜けているのである。