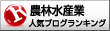太平洋戦争の終戦直前に、北海道に空襲があった。かすかな記憶を、根室空襲研究会の方がまとめてくれた。北海道の空襲は、終戦の年の昭和20年(1945年)7月14、15日のわずか2日だけ であった。
であった。
80ほどの市町村が、太平洋に浮かぶ空母からの艦載機の空襲を受けている。死者は2,000人程であった。室蘭は艦砲射撃を受けたが、釧路、根室が多くの犠牲者をだしている。函館は連絡船の犠牲者もあって、もっとも多くの犠牲者(死者520人ほど)を出している。
それ以外のところは、小さな軍事工場を抱えていたりしたところであるが、ほとんどが空襲警報すらなく、日常の中で不意の攻撃であった。そのため、多くの地域に犠牲者が北海道に散らばっている。
空襲は、日中戦争で国民政府のいる重慶を日本軍が爆撃したり、ドイツとイタリア軍がスペインのゲルニカを攻撃したのが始まりと言われてい る。空襲は、それまでの戦争が兵士間の戦いであった戦争を一変させた。戦闘要員でない一般人を攻撃するのである。空襲は、無差別攻撃の始まりなのである。
る。空襲は、それまでの戦争が兵士間の戦いであった戦争を一変させた。戦闘要員でない一般人を攻撃するのである。空襲は、無差別攻撃の始まりなのである。
一般に、空襲と言うと東京や大阪などの大都市だけが受けた被害のように思われてる。空襲は非人道的な無差別攻撃である。北海道の田舎には、防御の手段も何もない攻撃であった。それも僅か2日の出来事である。
日本のこんな田舎でも、大きな空襲を受けていた。根室では、死者400名近く負傷者はその数倍と思われる。市街地のほとんどを焼失している。別海、中標津、標津でも空襲を受けている。そんな中にあっても、軍部は被害実態を隠してるために、軍関係者の被害の詳細は不明のままである。
その後の調査でも、民間人と区別して軍人は扱われている。軍人は靖国に奉られ恩給を受けている。同時に空襲で亡くなったった民間人には何もない。戦争は非情である。
いつの時代でも犠牲になるのは一般人である。戦争を語り検証する、地味な活動が平和を語る資格があると思われる。自衛権を集団なら行使してもかまわないとする連中に、こうした戦争の実態を聞かせたいものである。