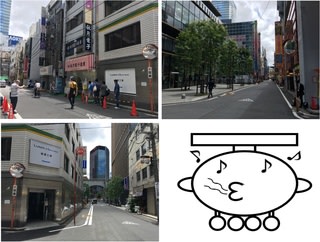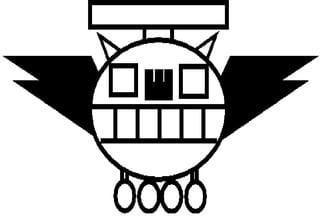「強い憎悪は、もはや感情ではなく、意思」というのは、
TVアニメのセリフだけど…。
フィクションであるTVアニメなどでは、
物語の“落としどころ”として悪役の存在も必要になる。
フィクションの世界とは異なる現実の生活においても…。
“不都合な事実”に対して、
身勝手な物語や悪者を必要とする人間は少なくない。
だから、本当のことを、ちゃんと伝えられているのかは分からない。
それでも、一言…。
「お前は、人の善意というものが、どのようなものか分かっているのか?」
そう問いただしたい相手がいる。
一般的な社会人であれば、「自分の仕事」が、
会社や組織を支えているという想いは、自負であり、やりがいとなる。
それに、職場内での業務経験も長く、
問題も起こしていなければ、社内で期待もされてくる。
まあ、煩わしくても、昇進などを考えていくことになる。
そんな雰囲気を感じてきたとき、部署移動の話があった。
仕事は、グループ会社が所有する商業ビルでの管理業務だった。
どうにも妙な感じはあったけど、
時期的に都合がよかったようにも思えた。
あれこれと手間取っていたら、正式な辞令が届き、
バタバタと、新しい部署へと移動することとなった。
そんな移動先は、ゴミ箱がひっくり返ったような事業所だった。
まず気付いたのは、
ディスプレイ前に雑然と積み上げられた書類やファイル。
せまい卓上には、クリップボードにはさまれた書類がいくつもあり。
クリップボードを取ってみると、ホコリまみれ。
ちゃんとしたマニュアルどころか資料や備品もなく。
これまでとは、書式や案件も違う。
ゴミ箱もあふれて、床もホコリまみれ。
このように自分たちの職場も片づけられてないのだから、
関係者からの印象がよいハズもなく。
すべて手探りでの仕事となっていった。

さて…。
通常、企業社会には、平社員より1つ上の役職は、“主任”になり。
その上に、係長代理、係長、課長という感じになっている。
この事業所において、主任に相当する責務を負っていたものが2名。
その上にあたるものが1名。
係長に相当する役職者が2名。
現場(事業所)のトップは、課長にあたる“現場長”(1名)となっていた。
しかし、職務経験が長いだけで、現場の責任者になったものも少なくなく。
ほとんど決まりきったようなルーチンワーク以外は、
何もしていないのが実情だった。
“明確な取り決め”や“線引き”がなされていないことで、
次々と起こるトラブルやクレームに対し、
改善案や打開策も思いつかないのか。
不都合なことは、「お前(部下)が悪い」となるか、
「仕方がない」となっていた。
それは、現場長の実力不足や知識不足が原因でしかなく。
本社にも人員を評価できるだけの基準もなかったからだった。
だから、カンのいい社員などは、
こんな事業所への移動を、やんわりとかわしていたのが実情だった。
…とは言え、紙ベースのマニュアルは存在しないが、
一部の役職者やベテラン社員の指導力は、決して低くなかった。
とにかく四苦八苦していくこととなった。
(2021年7月加筆訂正:続く⇒)