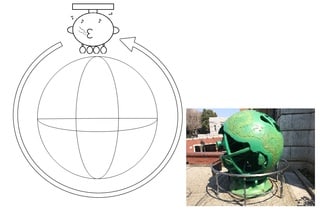現在では常識となっている“地動説”は…、
(この場合、地球が太陽の周囲を回っているというものです。)
ある日、ガリレオという偉い“学者さん”によって、
「これまでの考え方は間違っている!」
「私の唱える“地動説”が正しいのです!」と、
自説を強引に押し通したようなものではなかった。
それまでにも“地動説”を唱えていたコペルニクスは、
天体の観測から、説明のつかない事実に気付き、
地球は恒星である太陽を回る惑星であり、
地球の周囲を回っている天体は、月のみになると考えていた。
※もっともコペルニクスには、宗教的な背景もあり、
科学的な始点だけで、地動説への発想に導かれたのではないらしい。

ガリレオは…。
当時、子供の玩具程度にしか扱われていなかった望遠鏡を改良して、
天体の観測に用いていくことで、
地球と同じような惑星である木星にも、
3つの衛星があることを観測し、天体の軌道を導いていった。
その軌道から、“地動説”を裏付けていく。
この発見が、聖書の教えに反するからと、
ローマの異端審問所において、撤回させられたという話の方が、
あまりにも印象的なことから?
“どうして地動説”が正しいのか?を、
ちゃんと覚えていなくて、説明に困ったことがあった。
(関連する過去の記事「ガリレオの衛星を探そう!?」)
「宗教は個人を幸せにするもので、世界を平和にするものではない」
…と言われたことがある。
キリスト教が支配する中世という時代は、哲学は神学に準ずるもの。
17世紀のイタリアで…。
ガリレオに対するキリスト教会の反応は、
科学的な思考が、一般にも浸透している時代ではなく。
宗教が、文化や知識、芸術であり、
そして、権威であった時代。
しかも、古代、アリストテレスらによって提唱された“天動説”は、
日蝕や月蝕を、数値的に予測できるもので、
現代の教養人でさえ、理解するのが困難なもの。
必ずしも、非合理的なものでなく。
おそらく、当時はハイレベルな科学的な教養だった。
アリストテレスは、ギリシアの哲学者プラトンの弟子と言われ、
あらゆる方面への研究を行った“万学の祖”とも言われる人物。
ありきたりな言い方になってしまうけど、天才だったのだろう。
歴史的な大天才の学説に対して、ガリレオが提示した科学的な実証は…。
当時の教養人たちを動揺させたのかも知れない。
「自分には不都合だ!」というだけで、
権威が根拠のある発言を黙らせたという歴史的な事実は、
今後もあり得ることだけに考えさせられるときがある。
ガリレオの科学的な功績としては、「落体の法則」も有名で、
その理論を実験で証明するという手法は、現在の科学にも踏襲されている。(2020年8月16日加筆訂正)

(過去の画像より:イタリアつながりで、イタリアンビール)