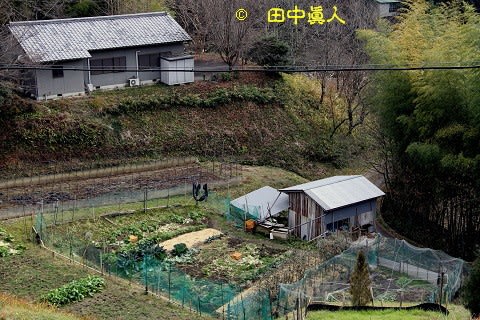30日の晦日。
民俗取材の行先は、奈良市山陵町(みささぎちょう)の山上八幡神社の砂モチ。
写真家のKさんが事前に聞いた話によれば、「これが最後か」の詞に、釣られてカンジョウ縄かけ取材計画していた京都・加茂町の銭司行は諦めた。
山上八幡神社の砂モチは以前も拝見しているのだが、どのような作業をされて、砂モチ形成をしているのか、見るのは初めてだった。
山上八幡神社は、幾度も訪れて年中行事を拝見していただけに「よう来てくれた、久しぶりやのう・・」、のご挨拶。

朝8時から正月飾りの作業をしていた神社役の六人衆。
割り拝殿内に左右2基の門松をつくっていた。
寒い朝だけに防寒服を着ていた。
しめ縄は業者発注にしたが、門松つくりは手作業。
松・竹・梅の三役も揃えている。
これらの枝を飾る順位は、背の高い木枝お後方に据える、と話していた。
中央に据えた3本の孟宗竹。
高さそれぞれ違えて、正面に向ける面は綺麗に切った斜め切り。
杉皮付きの杉板で囲った門松の土台。
崩れないよう黒紐できっちり締めた土台に砂を盛っている。
かつては、竹を組んでつくった土台であったが、杉板に切り替えた。
竹組の時代は、毎年新しくつくっていたから青竹だった。
毎年の作業に、竹の伐採作業もある。
そんなこんなで、当面は作り直しが無要の杉板に換えられた。
作業労力の負担軽減を考慮された六人衆の決断である。
できあがった門松は、運搬車に積んで所定の位置に運ぶ。

鳥居の前、参道両側に据えた、次の作業が砂モチ。
砂モチをする場は、拝殿前の境内一面。
等間隔に砂モチを置く箇所を決める。
そのために必要な道具はメジャー。
置く間隔は50cm。
いやいや、そうやなくて30cmや、疑義の声があがった。
六人衆がもつ規定資料に書いてあるはずや、という。
図面を確認してみれば、30cm。
測り直して、あらためて筋をつけていく。
さて、砂モチに置く砂は、2種類の真砂土。
赤土に白い土。
どちらの色土から置いていくのだろうか。
これも規定があり、図面に示している赤土の●、白土の〇印に置く順を確認する。

その開始の基点は、拝殿側から見て、右位置の角に赤土。
その次に白土。
開始地点が決まれば、交互にこの配置を繰り返す。

その紋様はまるでオセロのように見えるが、どうも違う。
和柄紋様の鹿の子紋に近い格子状に黒、白、黒、白が交互に配置される。

手分けして砂モチ作業を進める六人衆。
およそ砂モチ作業を終えたら、次はしめ縄飾り。
 数年前までは板しめ縄の名で呼ぶ簾型のしめ縄をかけていた
数年前までは板しめ縄の名で呼ぶ簾型のしめ縄をかけていたが、手つくりはやめ、京都の業者に手配するよう切り替えた。
先行きが不透明な座だけに、
苦しい選択をされたのである。
これまで引退した先輩方がつくってくれた材は神社に遺る。
1人、2人は交替しながら役に就く六人衆。
いつまでもこの体制を続けるには無理がある。
若い人が神社役に加わってくれるのが尤もな体制になるのだが・・。
数年、いや数年後は、さてどうなることやら。
現状維持を続けられるのも4~5年までか、と沈痛な思いで
作業してきた正月飾り。
これまでの板しめ縄から、太くなったしめ縄に移ったが、中央に飾り付ける葉付きのダイダイにユズリハ。

紅白の水引で括った奉書包みはカタスミに”ニコニコ仲睦まじく”といわれている縁起物の串柿も飾る。
拝殿のしめ縄以外に、細縄のしめ飾りはあ、うんお表現する狛犬とか、境内のご神木にかける。
また、社殿左手に大きく育った太い幹のご神木は、中太のしめ縄を飾る。
作業が終るころに見つかった一輪の花。
雨が降っていたこの日に咲いた四季桜。
毎年に咲いているようだ。
ほぼ終わりころに合流できた写真家のKさん。
そして、一昨年、昨年から県内の砂モチを調査している橿考研所属の発掘調査専門のYさんも合流した。
Yさんからの砂モチ情報は、田原本町西代の八坂神社。
また、Kさんからは、かつて度々調査していた天理市長滝町にカラスのモチを見つけたと、連絡が入った。
また、天理市の上仁興の四社神社の灯籠に正月の餅を想定する白餅が数個、供えていた。
情報としてであるが、奈良市中山町の八幡神社に砂モチがあった、という。
県外を離れ、京都南部・木津川市の市坂にもあったそうだ。
なお、2件の民俗事例は、貴重な情報。
西代は1月3日に、長滝は1月2日に現地入り調査した。
(R2.12.30 SB805SH撮影)
(R2.12.30 EOS7D撮影)