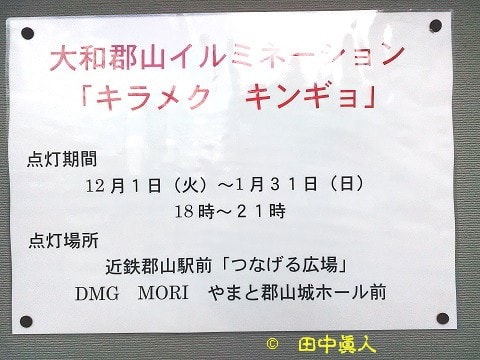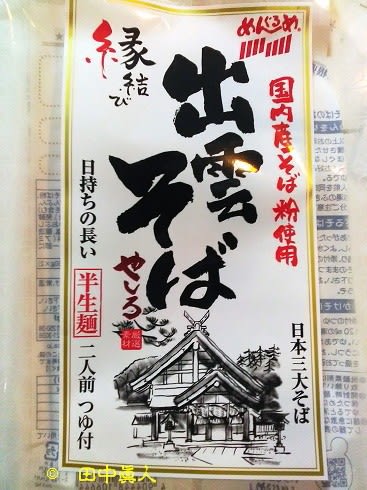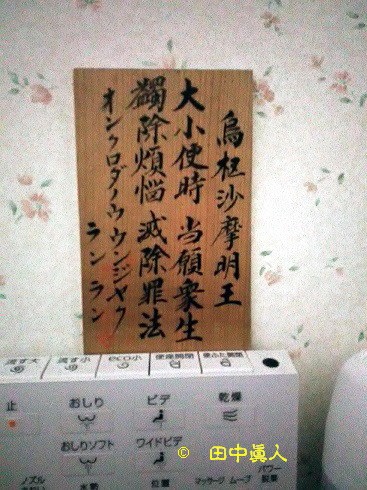元日は、前日の大晦日に教えてもらった天理市檜垣町訪問。
大日堂に正月御供を供えると聞いていた。
時間は特に決まってないが、来られるなら午前10時ころ、ということで自宅を出た。
出発直後にかかってきた今年初の電話が鳴った。
かけてきた人は大和郡山市小林町住民のSさん。
コトが起これば、直ちに電話してくださる。正月早々にかかった電話は、元日の挨拶は、そこそこに伝えてくれた村の件。
なんでも、修復していた神輿が氏神社の杵築神社に戻ってきた。
小林町の元日の朝。村の人たちが寄り合う元日参拝がある。
今年は、綺麗になって戻ってきた修復直後の神輿布団太鼓台披露。
氏子たちへのお披露目に、笑顔で集まってきた。
修理を担った市教育委員会文化財保護・史跡発掘調査員の山川均さんが来られて、解説しているから、という急なお誘いに、檜垣町行きに途中下車。

大日堂の正月御供取材があるので、1分間の顔出しなら、と思って村行きを決行した。
久々にお会いする年始の挨拶に、美しい姿になった神輿を拝見する。
五層からなる布団太鼓。

太鼓を打つ四人が座る位置。
その下に装置の太鼓が見える。
実は、と教えてくださった神輿太鼓台の記録。
神輿の屋根裏から発掘された「明治弐拾八年(1895)十月再新ス」の棟札。
再建の偉業を示す棟札に、当時、再建に関わっていた住民の名がつらつら記されていたそうだ。
再建の記録はわかったが、いつ頃、どこに発注し、製造してもらったのか、その記録はなかったようだ。
そこに「若連中」の名がいっぱいある。
神輿の手すりに「若」、「中」刻印入りの銅板。
同じく「若中」の文字がある神輿提灯に首を捻る山川さん。
民俗担当でなく遺跡・史跡発掘調査が主な仕事だから、さっぱりわからない、といわれたので伝えた若中。
地方では若組とか若衆などで呼ばれてきた今の青年団のようなものです、と・・・
その話を聞いていたビデオ撮り記録班が、もう一度、お願いしますって・・。
修復の記録映像撮りに巻き込まれたようだ。
布団太鼓台は、奈良県のみならず、大阪・東大阪、堺、貝塚など泉南に多くみられ、遠くは瀬戸内海沿岸から九州・佐賀や長崎にも・・・。
特に、後述する布団締めの布団太鼓は、豪華絢爛な金糸の立体刺繍で飾られており、愛媛県の東予地方から香川県、兵庫県に見られるそうだ。
江戸時代に上方で発生した太鼓台は、19世紀前半に、現在のような布団を積み重ねた形になり、西日本の各地に伝播したのである。
ちなみに、後年になるが修復事業の広報用ビデオが公開されている。
あるブロガーさんが、あげた記事。
「2013年に文化庁が、山車などの修理・復元に補助金を出す事業(※当初は「文化遺産を活かした地域活性化事業」)に、助成金を活用し、だんじり(山車)や太鼓台を修理する町があった。また、2019年からは「地域文化財総合活用推進事業」名に移り、現在に至るらしい。この文化庁助成金を利用する場合は、映像等の記録が条件になっている。(若干補正した)
記録映像は、DVD化され、図書館などに収められるほか、一部はユーチューブ動画で公開されている。
神輿を担ぐなど、神賑わい(かみにぎわい)の様子やだんじり(出車)、神輿太鼓台の解体、組み立て作業、彫り物洗浄、修繕作業、お披露目の様子などを、1時間余りの動画に収めている。」とあった。
つまり、小林町の神輿太鼓台も、文化庁の助成金活用を依頼、修理され、その一部をユーチューブ動画で公開していた。
後世に継承しておきたい動画テロップ・キャプション。
文字化し、下記に記しておく。(執筆者により文中補正した)
「老朽化により、神輿は斜めに傾斜していた。このままでは著しく危険と判断され、祭りの使用を断念、本格的な補修理、ごく一部を新調、他すべては再使用に道をとられた。
基本的に、組木であることから楔(くさび)を抜けば、簡単に外れる。狭間、雲板(うんぱん)、虹梁(※こうりょう)、木鼻(※きばな)の解体作業。その解体中に、見つかった棟札の文字に、世話人など当時の人たちの連名墨書があった」

今回のお披露目に別途拝見した棟札。世話人は7人。大工人は、筒井(の)大吉。また、若連中は23人。127年前の小林の地に、いずれも苗字名は見られない。
「解体したら、薬剤が入っている強勢水をホースで飛ばし灰汁(※あくじる)洗い。再使用する部品を綺麗にする。また、洗剤でも洗う専門異業者(宮大工)の人たち。」
「木鼻彫刻の8個のうち、損傷の激しい一つは新調する。ノミとか彫刻刀を用いて彫る。微妙な部分は、金槌で叩かず、手の力で彫る。
目の部分は透き通るようなガラス玉。獅子頭の両眼にあてがうガラス製の眼。はめ込み調整してから、裏側より”目”を塗る。白い綿を入れた、そこに綺麗に描く二重丸。命を吹き込む眼ができる。」
「一方、飾り金物は洗浄してから、再加工する。
金属を柔らかくするため、銅にバーナーの火をあてる。胴が燃えると、炎色が反応し、緑色の炎が発生する。硫酸液にジュっと浸けて、さらに水浸け。ブラシでこすり、金具は一旦、平らにし、圧延機で調える。平らになれば、金属床にあてて金槌で叩きながら丸めていく」
こうした工程は、機械工業高校を卒業(※私は昭和44年卒)した人は、実習体験済だから、みな理解されよう。
「丸めた銅は、型合わせをして、最終的には溶接で締め、グラインダーをかけ、表面を研磨する」
「布団締めは、たいへん細かい刺繍作業をともなうため、中国の国に運び、委託発注し、元の刺繍から復元、すべてを新調した。なお、五層の布団台は、主要とする部分はヒノキ材。竹で編んでいたが、今回はベニヤ板を加工し、新調した。
重ねた布団部を安定させる雲板台も含め、ほぼ全体が再使用。美しくなった彫り物もそろったら、元の状態に戻す組立作業に取りかかる」
令和2年の5月から12月末までが修理作業。
完成した神輿布団太鼓台は、12月29日に納入された。
最後の組み立てに、職人だけでなく、氏子らも参加し、仕上げた。
顔見知りの親しき氏子たちの表情は、みな笑顔。
幕や提灯も取り付けた。
和針が使われていることから、江戸時代に製作された、と考えられる小林の神輿布団太鼓台。
綺麗になった長いオーコも、随所に亘って、ロープで締め付け。すべてが調った。
我も我も、と集まってきた氏子たち。オーコを肩にあてて、身体ごと持ちあげた。
10人がかりで持ち上げた、そのときに喚声があがった。
太鼓台は車付き。現在の移動に使用する補助輪。
かつては頑強な若中らが担いで巡行していた。
平成24年10月7日の宵宮に撮った地域巡行から戻ってきた神輿布団太鼓台が美しい。
コロナ禍が去り、神賑わいの祭りが待ち遠しい。
かつての若蓮中たちが、気合入るのもわかるような気がする。
(R3. 1. 1 EOS7D撮影)
大日堂に正月御供を供えると聞いていた。
時間は特に決まってないが、来られるなら午前10時ころ、ということで自宅を出た。
出発直後にかかってきた今年初の電話が鳴った。
かけてきた人は大和郡山市小林町住民のSさん。
コトが起これば、直ちに電話してくださる。正月早々にかかった電話は、元日の挨拶は、そこそこに伝えてくれた村の件。
なんでも、修復していた神輿が氏神社の杵築神社に戻ってきた。
小林町の元日の朝。村の人たちが寄り合う元日参拝がある。
今年は、綺麗になって戻ってきた修復直後の神輿布団太鼓台披露。
氏子たちへのお披露目に、笑顔で集まってきた。
修理を担った市教育委員会文化財保護・史跡発掘調査員の山川均さんが来られて、解説しているから、という急なお誘いに、檜垣町行きに途中下車。

大日堂の正月御供取材があるので、1分間の顔出しなら、と思って村行きを決行した。
久々にお会いする年始の挨拶に、美しい姿になった神輿を拝見する。
五層からなる布団太鼓。

太鼓を打つ四人が座る位置。
その下に装置の太鼓が見える。
実は、と教えてくださった神輿太鼓台の記録。
神輿の屋根裏から発掘された「明治弐拾八年(1895)十月再新ス」の棟札。
再建の偉業を示す棟札に、当時、再建に関わっていた住民の名がつらつら記されていたそうだ。
再建の記録はわかったが、いつ頃、どこに発注し、製造してもらったのか、その記録はなかったようだ。
そこに「若連中」の名がいっぱいある。
神輿の手すりに「若」、「中」刻印入りの銅板。
同じく「若中」の文字がある神輿提灯に首を捻る山川さん。
民俗担当でなく遺跡・史跡発掘調査が主な仕事だから、さっぱりわからない、といわれたので伝えた若中。
地方では若組とか若衆などで呼ばれてきた今の青年団のようなものです、と・・・
その話を聞いていたビデオ撮り記録班が、もう一度、お願いしますって・・。
修復の記録映像撮りに巻き込まれたようだ。
布団太鼓台は、奈良県のみならず、大阪・東大阪、堺、貝塚など泉南に多くみられ、遠くは瀬戸内海沿岸から九州・佐賀や長崎にも・・・。
特に、後述する布団締めの布団太鼓は、豪華絢爛な金糸の立体刺繍で飾られており、愛媛県の東予地方から香川県、兵庫県に見られるそうだ。
江戸時代に上方で発生した太鼓台は、19世紀前半に、現在のような布団を積み重ねた形になり、西日本の各地に伝播したのである。
ちなみに、後年になるが修復事業の広報用ビデオが公開されている。
あるブロガーさんが、あげた記事。
「2013年に文化庁が、山車などの修理・復元に補助金を出す事業(※当初は「文化遺産を活かした地域活性化事業」)に、助成金を活用し、だんじり(山車)や太鼓台を修理する町があった。また、2019年からは「地域文化財総合活用推進事業」名に移り、現在に至るらしい。この文化庁助成金を利用する場合は、映像等の記録が条件になっている。(若干補正した)
記録映像は、DVD化され、図書館などに収められるほか、一部はユーチューブ動画で公開されている。
神輿を担ぐなど、神賑わい(かみにぎわい)の様子やだんじり(出車)、神輿太鼓台の解体、組み立て作業、彫り物洗浄、修繕作業、お披露目の様子などを、1時間余りの動画に収めている。」とあった。
つまり、小林町の神輿太鼓台も、文化庁の助成金活用を依頼、修理され、その一部をユーチューブ動画で公開していた。
後世に継承しておきたい動画テロップ・キャプション。
文字化し、下記に記しておく。(執筆者により文中補正した)
「老朽化により、神輿は斜めに傾斜していた。このままでは著しく危険と判断され、祭りの使用を断念、本格的な補修理、ごく一部を新調、他すべては再使用に道をとられた。
基本的に、組木であることから楔(くさび)を抜けば、簡単に外れる。狭間、雲板(うんぱん)、虹梁(※こうりょう)、木鼻(※きばな)の解体作業。その解体中に、見つかった棟札の文字に、世話人など当時の人たちの連名墨書があった」

今回のお披露目に別途拝見した棟札。世話人は7人。大工人は、筒井(の)大吉。また、若連中は23人。127年前の小林の地に、いずれも苗字名は見られない。
「解体したら、薬剤が入っている強勢水をホースで飛ばし灰汁(※あくじる)洗い。再使用する部品を綺麗にする。また、洗剤でも洗う専門異業者(宮大工)の人たち。」
「木鼻彫刻の8個のうち、損傷の激しい一つは新調する。ノミとか彫刻刀を用いて彫る。微妙な部分は、金槌で叩かず、手の力で彫る。
目の部分は透き通るようなガラス玉。獅子頭の両眼にあてがうガラス製の眼。はめ込み調整してから、裏側より”目”を塗る。白い綿を入れた、そこに綺麗に描く二重丸。命を吹き込む眼ができる。」
「一方、飾り金物は洗浄してから、再加工する。
金属を柔らかくするため、銅にバーナーの火をあてる。胴が燃えると、炎色が反応し、緑色の炎が発生する。硫酸液にジュっと浸けて、さらに水浸け。ブラシでこすり、金具は一旦、平らにし、圧延機で調える。平らになれば、金属床にあてて金槌で叩きながら丸めていく」
こうした工程は、機械工業高校を卒業(※私は昭和44年卒)した人は、実習体験済だから、みな理解されよう。
「丸めた銅は、型合わせをして、最終的には溶接で締め、グラインダーをかけ、表面を研磨する」
「布団締めは、たいへん細かい刺繍作業をともなうため、中国の国に運び、委託発注し、元の刺繍から復元、すべてを新調した。なお、五層の布団台は、主要とする部分はヒノキ材。竹で編んでいたが、今回はベニヤ板を加工し、新調した。
重ねた布団部を安定させる雲板台も含め、ほぼ全体が再使用。美しくなった彫り物もそろったら、元の状態に戻す組立作業に取りかかる」
令和2年の5月から12月末までが修理作業。
完成した神輿布団太鼓台は、12月29日に納入された。
最後の組み立てに、職人だけでなく、氏子らも参加し、仕上げた。
顔見知りの親しき氏子たちの表情は、みな笑顔。
幕や提灯も取り付けた。
和針が使われていることから、江戸時代に製作された、と考えられる小林の神輿布団太鼓台。
綺麗になった長いオーコも、随所に亘って、ロープで締め付け。すべてが調った。
我も我も、と集まってきた氏子たち。オーコを肩にあてて、身体ごと持ちあげた。
10人がかりで持ち上げた、そのときに喚声があがった。
太鼓台は車付き。現在の移動に使用する補助輪。
かつては頑強な若中らが担いで巡行していた。
平成24年10月7日の宵宮に撮った地域巡行から戻ってきた神輿布団太鼓台が美しい。
コロナ禍が去り、神賑わいの祭りが待ち遠しい。
かつての若蓮中たちが、気合入るのもわかるような気がする。
(R3. 1. 1 EOS7D撮影)